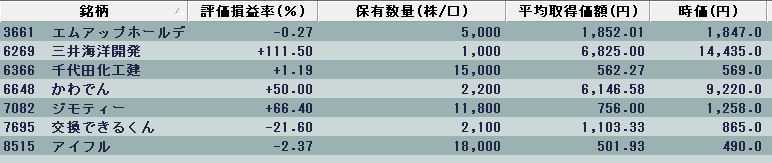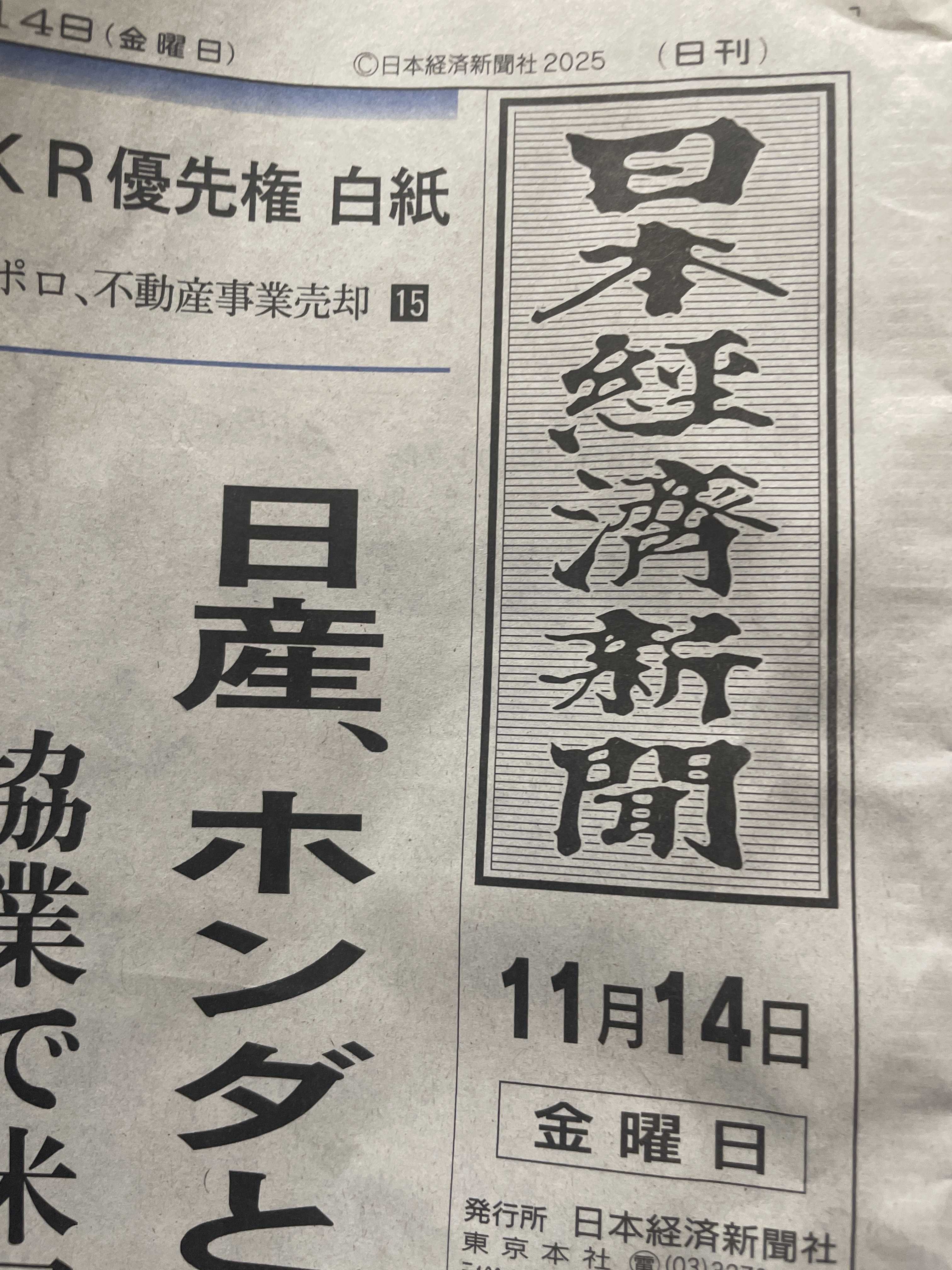2009年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
医学部
30年前には,私立医学部入学時に,現在価値に換算で平均6000万円が必要であり,また何年も浪人して私立医学部に入学する人たちが珍しくなかった.それを払う経済学的合理性があるということであり,また医師一人を育てるのには,6年間で約1億円の費用を要するという話だった.つまり国立医学部に入るだけで,約1億円を得ることに等しいという高校生でも経済学的にわかりやすいモデルだった.それだけの費用を国が負担してくれるというのは医学生の私はありがたいと思ったものだった.(それを払う経済学的合理性があるということは,資本再投資の観点からすれば,普通に暮らせばいずれはそれだけのものが手元に残るということなのだしね,,,,,)もし将来的に,このモデルが崩壊しても医師一人の育成費用はいつの時代でも,おおむね同じなのだから経済的に割に合わない私立医学部入学希望者が激減することになり,まず私立が成り立たなくなる.国立医学部に入っておけば,医師過剰の時期が来ても需給を長い目で考えれば,いずれ需給は改善する.国の言っていることだって当てにならない.10年少し前の小渕さんの時代は「医師過剰問題」を討議していたのにいまでは医学部の定員増を討議している.(人口当たりの医師数は以前より増大したが,高齢化による有病率はもっと増大している.先進国で下から3番目くらいの医師数だしね)結局は一人の医師を育成するのに,どれだけ国民が支払えば先進国として満足できるレベルに到達できるかということに関与している.国民が満足できなければ,費用がかさむのが道理だろう.足るを知らない時代だしねいまの半分の知識量の医師でも,国民がその医療レベルに満足できるようならいずれ医学部は4年で卒業できるようになるだろう.ところが事態は逆で30年前とは異なり,現在は獣医師も薬剤師も卒業までに6年を要するようになっている.医学部卒後2年間の臨床研修義務化は,さらに育てる費用を増大させたし,移行時期には供給をたたれた現役の病院医師の疲弊を招き,かさにかかったマスコミの医療不信攻撃により,病院医師はメスを捨てて逃げ出した.あまりにひどい状況なので,ずいぶん私もメスを捨てようか迷ったが,病院に残る道をえらんだ(しばらく我慢することで得られるはずの残存者利得を選んだ).残存者利得の典型例は,たたかれすぎていなくなった病院産婦人科医だ.2年前くらいは三重県あたりで年収5200万ほどで産婦人科医を募集していた.となりの奈良県は病院医師の給与が全国で最も低い(北海道の半分くらいだ).ところがM日新聞が徹底的に同県の産婦人科をたたいて崩壊(県の半分くらいの地域に産婦人科医は皆無に近い状況になったようだ)させたので,いずれ年収は改善されるだろう.全国で最も低い給料でも働いていた奈良県には,きっと良い医師がたくさんいたはずなのだ.だからこそ,たたかれていても,いずれわかってくれると思ってしまい,マスコミへの反論が大きくならなかったのかもしれない.われわれ同様に規制産業の典型例,,,,,新聞おしがみの山で広告料をもらっているようだが,それでも補えないほどの部数減少.医療バッシングしたとろで,彼らの運命は変りそうにないと思う.私たちの年収が落ちるのは,君たちの年収が落ちた後なのだから医療と訴訟,,,,,この問題を別の視点で考えると結局は2つの最強の資格をもった人間たちの仕事を増やし,そのコストを増大させて,,,普通の生活を送っているひとたちから,お金を少しずつ奪っていくことになるのだがそれに気がついている人は少ないのではないだろうか?理系は手に職なら,文系なれば世の中を知る視点をいくつ身につけているかということになるのだろうか?ーーーーーー文系では,企業は修士を望まず学士卒でよいという.学士卒を企業内教育で育成したほうがよいと考えているようだが,企業が求める理想像と大学での文系修士の教育内容が合致していないという問題があるのだろう.医学部の場合には,学生を指導する大学教官はいつも現場で手術に明け暮れている現役バリバリなのであり,そのなかで選ばれた人間たちなのだ.つまり教育内容が現実に即しているので無駄がないということだ.また臨床と研究に9割くらいの労力をつぎ込まないとレベルが保てないので学生の教育コストはたかくならざる得ないのだ.文系修士の教育内容も,そのように変っていくのかもしれない.それがいまできている職業大学院なのかもしれないが,いまの職業大学院の教育内容がうまくいっているかわからないが将来的にはうまくいくようになるんだろうと思う.そうなれば,,,,,30年後は学部卒ではなく修士卒が重宝されるようになっているかもしれないし,そうなれないところは少子化の波にもまれて淘汰されてなくなっているだろう.ーーーーーーーーーーarts and scienceこのように文系のscience化(職業化=目先のかねになる,役に立つ)が進めば,ほんとに必要なartsだけが文系には残るだろうけど,,,それはきっと目新しいものではなくいつの時代にも人々が「こころのよりどころ」としてきたartsが残っていると思う.逆説的だけど,世の中がこぞって職業化をめざしたあとには,いずれ,ほんとのartsが見直される時がくるだろうというのが本音だ.
Jul 10, 2009
コメント(0)
-
学費
http://www.igakubu.com/archives/53_gakuhi/index.html医学部の学費私が受験したのは30年以上まえになるが,そのときの私立は入学時だけでも,平均3000万円くらいだったと思う.今のほうが安いように見えるけど.あのころは医学部フィーバーの時代だったのだろう.国立は半年で授業料が4.8万だったと思う.現在の平均給与は平均年齢42歳(勤続年数13.3年)の男性で33.67万円1977年=32年前は16.6万円であり,約2倍になっている.現在価値に換算すると,入学時に平均6000万円というのはいかに高額だったかがわかる.国立医学部に入った途端に,いろんな銀行の支店長が家に挨拶に来た時代だった.いまでは考えられないことだが,,,
Jul 10, 2009
コメント(0)
-
ポスドク 博士のあと
特別研究員(PD) 日本学術振興会 1,891人 給与37万9千円/月、研究費150万円以内 34歳未満(医歯獣医系36歳未満) 3年間 (平成14年)どうなんだろう?民間企業というのはもっとよいのでしょうか?私にはわかりません。私は卒後しばらくは公的病院にいくつか勤めましたが、当時は一般サラリーマンのボーナスが、私の月給くらいでした。その後、平成バブルがきて、民間がかなりよくなり私のほうは大学で医員という身分になり、月給は8万くらいになってしまいました。後輩たちのポスドクの高給がうらやましかったです。大学で外来や手術ができるわれわれよりも、大卒すぐの新人医師のほうが給料が高い逆転現象を生じていました。大学院生もアルバイトしており、年収はわれわれよりも上でした。すでに家庭を持ち、子供もおり、土日のアルバイトでしのいでいました。その後、博士になり、アカデミックポストを得て、大学には49歳までいました。その後、民間に就職、、、、最近の話です。そういう点では医学部なんてのは昔から矛盾だらけです。偉いほうがお金がない。それでも学生紛争前よりはずっとよくなったのです。博士になったら仕事がないなんて騒いでいる「学歴ロンダリング」の本、、、、、読まなければよかったかもしれない。人生はそんなものではない、、、とやはり私は思っている。それは著者の君たちがもう20年してみれば、気がつくのかもしれない。私の親戚縁者には、医者が多いのだけど、ほかには大蔵その他のキャリア官僚や東一早慶教授や日銀とかいろんなヒトがいるけどたぶん、おおむね同じ意見だと思うよ。私も助教授で医師だったので、年収としてはよかったけど、50を目前にして夜中に心マッサーッジしながら、その時給が高校生の牛丼屋バイトよりも安いという矛盾には驚いたけどもね。当時、、、医療崩壊というのは、おきるべくしておきたと思っている。マスコミの「押し紙」、発行部数の偽り、それに基づく広告料収入、、、こっちのほうが巨悪ではないか?ドラッカー氏は日本の銀行には、本当は50万人位いれば十分なところに250万人もの人が雇用されていると指摘している。割のよい仕事を求めるのは当然である。そして割のよい投資(すぐに儲かる)を求めるのも当然である。しかし、その多くが実現されないことは「ものの道理」書くまでもないことだが、風向きが変わったときに、みんな逃げ遅れるからだ。割に合わない仕事、割のよくない投資(すぐには儲からない投資)これが最終的には成り立つのは、それを知り、それを待てるヒトが、いつの時代でもあまりにも少ないからなのだろう。ウオーレンバフェットはバリュー投資が成り立つ理由としてほぼ同じことを言っている。
Jul 4, 2009
コメント(0)
-
学歴
「学歴ロンダリングー楽して東大卒の学歴を手にいれる方法教えます」という本を通読した。最終学歴を東大院とすれば、それまでの学歴が問われることはなく、内部生院卒と同格で就職活動ができる。とくに修士卒が不利にならない理系では、この方法が有利であり、「少しばかりの戦略と努力で新しい人生を切り開く裏ワザ」といううたい文句だ。あくまでも有効なのは修士までであり、博士過程への進学には強い警告を述べている。(目的を果たせば、深追いするなということなのだろうか?)また東大学卒が北関東の大学院に入ったがまもなく消息知れずとなり、医学部再受験をしているといううわさを聞いたという「逆学歴ロンダリング」の失敗例を、、、、ーーーーーーーーーーーーーーーー少子化を生き残ろうとして大学院枠を増やした大学、、、、、その大学院重点化のひずみをうまく利用して、この困難な時代に、強力な就活ツールを入手する手段であると筆者は言いたいのかもしれない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大学院過去問を入手は言うに及ばず、研究室訪問、そこで人脈をつくり講義ノートのコピーを入手する。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの本で参考になったのは、公共政策大学院 他大学卒57% 競争率3.1倍総合文化研究科 60% 2.6倍情報学環 79% 1.9倍新領域創世科学 70% 1.7倍情報学環や新領域創世科学は他大学卒が7,8割を占め、なおかつ競争率は2倍以下であり、入りやすい部門だというさらに文系と理系が混合した学問であり、文系修士は就職が不利であるため、彼らが理系就職するのに向いているというーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー東大院に進む場合には、院生の半分は他大学出身であり、なんだか別の大学のようだ。でも、それも必要なことかもしれない。またこの本によれば、東大院卒であれば、採用企業側としては、どの大学出身であれ差をつけないようである。ライバルたちが、どのような戦略で大学院に望んでいるかについて知るには有用だったのかもしれない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー卒業後は留学するのが、よいように思えている。修士というのは、1年目の4-7月に研究テーマを決め8月からは就職活動も開始、、、、、2年目の春に内定をもらい、それからは本格的に研究一本に打ち込むようだ。まじめに研究に打ち込めば、就職はおぼつかず博士への困難な道が待っている、、、なんだかなあ、、医学部以外の博士がいかにつぶしが利かないか、ということらしい読んでためになったかといえば、ためになったが、読まないほうが、知らないほうがよかったとも感じている。米国では私も2年かけて基礎研究の論文を1つ書いたがそこに価値を見出すかどうかということなのだが博士であったし、日本政府と米国の両方から給料もらえて恵まれていた立場だったともいえるし、
Jul 4, 2009
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1