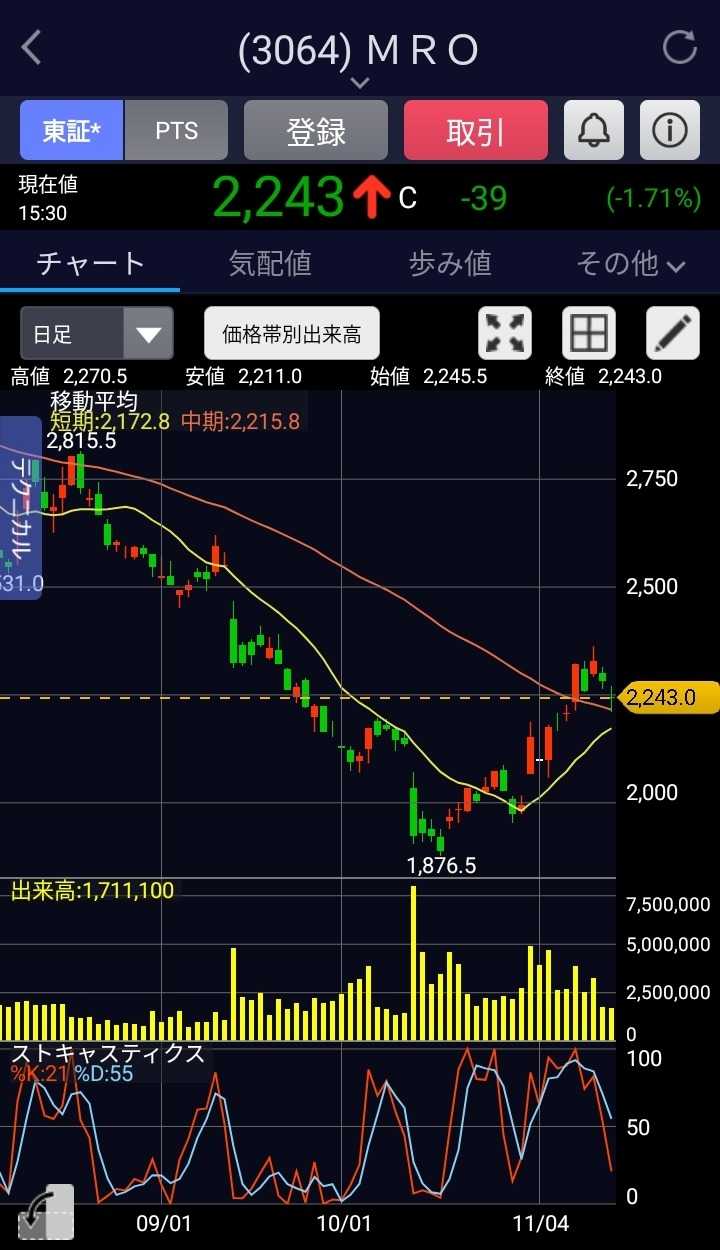2009年04月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
エマニュエル トッド
彼がソ連崩壊を予言する「最後の転落」を発表したのはオックスフォードの大学院を卒業してすぐだった.彼はソ連の乳児死亡率が悪くなっていることを,予言の根拠とした.いま,米国では,乳児死亡率が上昇しているかもしれない.以下は引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーハワイ大学医学部産婦人科 矢澤珪二郎 (産科と婦人科 2007年 8号 p990-991) 米国南部は,北部の工業に対して,農業を中心とした地域で,その人口は白人と貧困層をなす大多数の黒人に二分される.南部の人種差別は激しい.東洋系人種は白人と黒人のはさまで,あまりにも少数(mainority)で,どちらに入るのかわからないが.まあ白人の仲間として遇されている.米国南部の乳児死亡率は,いままで下降の一途をたどっていたが、最近になり上昇がみられた. 南部でももっとも貧困なミシシッピ州では、乳児死亡率(生後1年までの乳児1,000名につきの死亡数)は2004年には9.7であったが,2005年には11.4に増加した.全米平均は6.9である.この増加はアラバマ,ノースカロライナ,テネシー,ルイジアナ、サウスカロライナ,の南部州においても,ミシシッピ州よりは程度が低いが,増加がみられた.南部諸州の乳児死亡率の原因は,未熟児,低体重児,乳児突然死,などが多く、妊婦に肥満が多く,それに伴って,糖尿病や高血圧も多い.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーさてミシシッピ州では,2001年に保険の掛け金が4倍増しになったことで、医師不足が生じ、人口14,550人のYazoo Cityには産科医がいなくなったという。この医療クライシスは全米20州くらいで生じた.4倍どころか,いくら払っても保険に加入を認めないという州が20州ほどあったということだ.このため外科医が州外に逃げ出すか,廃業救急室からコールがあっても応じない,あるいは今後は手術をしないという約束で医師賠償保険に加入したまた、ネバダ州では保険金が高いという理由で、大学を卒業したら他の州に移ると決めている人がほとんどで、深刻な医師不足になっています。このようななかでの乳児死亡率の悪化は,,なんとなくソ連の末期を連想させる.解体したのは,トッドの指摘から15年ほどあとのことだった.http://www.cbsnews.com/stories/2007/06/02/eveningnews/main2878184.shtmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもっとも日本も住民辺り医師数の基準が、いまだ昭和23年策定時のままである.しかも、医師数の最低基準を定めたはずなのに、それが標準値となり,さらには「医師数抑制」を推し進めるための上限値になってしまった。小渕内閣では医師過剰問題を討議してたんですからねえ,過剰労働でみんな大変でしたのに,,,,厚労省は医師数は過剰と表明.しかし各国と比較して著しく低いことがわかると、これまで65歳まででカウントしていた医師数を、いつのまにか年齢上限なしでカウントしている,,,,そして「医師不足でない」と昭和23年にはこんな高齢化になるとは誰も思わなかったはずです.高齢者の有病率はすごく高いんですが,,当時の優生保護法が団塊世代以降の出生急減これも当時の食糧難をかんがえれば仕方なかったのかもしれませんけど
Apr 23, 2009
コメント(0)
-
読書:貝と羊の中国人、武士の家計簿
「貝と羊の中国人」加藤徹「武士の家計簿」磯田道史帰りの新幹線で読むものを3冊もとめたうちの2冊。1:「貝と羊の中国人」加藤徹病院の前には葬儀屋があるのが便利で当たり前という認識の中国人、、、、「中国人の頭の中はいったいどうなっているのか?」について述べている。その広く、深い知識はまるで中国の民俗学者であるかのようで驚かされた。作者は京劇を専門とする学者なのだが、芸術を理解するということはやはり通り一遍のレベルではないのだなあ、、、、これは掘り出し物の一冊でした。時間をおいて、再読すべき本。2:「武士の家計簿」磯田道史著者はケンブリッジの家族人口学を日本で研究した速水氏のお弟子さんなのだろうか?前田藩の会計係り一族の家計簿。ちょうど東大赤門を建築時期に藩主の書記兼会計係として、奮闘した猪山家のやりくりを中心に描かれている。武士階級の崩壊にあたって前田藩でのリストラ、金融不安、教育問題これはしばらくまえにテレビでも紹介されていたが、庶民の生活がわかって大変面白い。階級や組織が崩壊するような激動の時代であってもヒトの役に立つ仕事をしていたヒトは、生き残れるという言葉で作者は文を結んでいる以上の2冊を読んで、階級というものに考えが及んだ。中国では士太夫階級(続くためには代々と科挙合格の者が必要となる?)が孔子以前の時代から孫文の時代まで脈々と政治の中枢にいた。漢字だけで文章を書くためには、最低2000は覚えなくてはならないが彼らは文字を制し、これを簡略化しないことで、自らの地位を保った。この本を読んでよかった。ずっと疑問だったことが解けた。日本には「ひらがな」つまり発音記号がはやくからできたため、歴史上初めてのエッセイも小説も日本の女性の手による。朝鮮通信使が日本を訪問し、ここでは身分の隔たりなくだれもが字を読めると驚き自国でも「ひらがな」に相当する訓民正音を作らせた。中国では発音記号を作ることを阻害することで地位を保った階級が何千年も政治の中枢にいたということだ、、科挙の廃止まではいまでは中国語の半分は日本で用いられる単語をそのまま逆輸入しているらしい。日本でも武士は崩壊したが、かれらのなかには海軍や官僚になり家族を支えた。軍人は先の戦争で滅んだが、官僚階級は残っている。ALSOKの創業家なんかは、こういった階級の典型例かも親戚はこういった階層論?を専門としていた有名な学者だったらしいがちゃんと著作を読んだことがない。今度、読んでみようと思う。
Apr 19, 2009
コメント(0)
-
ハイパーインフレの勉強
http://www7b.biglobe.ne.jp/~bokujin/こちらの方からのコピー 政府借入金総額 国債総額 一般会計歳出総額昭和 9年 \9,780 \9,090 \2,163昭和10年 \10,525 \9,854 \2,206昭和11年 \11,302 \10,575 \2,282昭和12年 \13,355 \12,817 \2,709昭和13年 \17,921 \17,345 \3,288昭和14年 \23,566 \22,886 \4,494昭和15年 \31,003 \29,848 \5,860昭和16年 \41,786 \40,470 \8,134昭和17年 \57,152 \55,444 \8,276昭和18年 \85,115 \77,556 \12,552昭和19年 \151,952 \107,633 \19,872昭和20年 \199,454 \140,812 \21,496昭和21年 \265,342 \173,125 \115,207昭和22年 \360,628 \209,423 \205,841昭和23年 \524,409 \280,433 \461,974昭和24年 \637,286 \391,415 \699,448昭和25年 \554,008 \341,423 \633,295昭和26年 \645,463 \362,867 \749,838昭和27年 \826,679 \437,454 \873,942昭和28年 \851,135 \543,563 \1,017,16ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー現在は政府,地方の債券は1000兆でGDPの2倍これは,おおむね昭和19-20年と同じレベルです.昭和19年を現在レベルになおすと,1000兆の債券があり,一般会計は198兆円となる.いまは特別会計を含めて220兆円の年間予算とも似ているなあ.やはり,これくらい借金があるとこのくらいの予算を使わないといけないのかも戦時国債のような雰囲気がhttp://www.yuichiro-itakura.com/essay/itakuras_eye/itakuras_eye_35.htmlhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~bokujin/このかたのデータはすばらしい.GLDがいかに価値を保ったか一目瞭然です.砂糖とか塩も保存しておけば長持ちしますね,,,,ただ,このときは戦時により産業が徹底的に破壊されたときで供給力不足の時代いまの日本は供給力過剰の時代もしひどい円高で産業が徹底的に廃業に追い込まれない限りはならないのかもそれにしてもハイパーインフレによる政府債務の急速な減少には驚かされる.http://royallibrary.sakura.ne.jp/ww2/gimon/gimon8.htmlこちらはドイツハイパーインフレを鎮めたレンテンマルクの奇跡,,,,,土地など不動産を担保にした紙幣によっておさまった超インフレhttp://hiroshima.cool.ne.jp/h_sinobu/inflation1.HTMインフレ時の老人と年金生活者の悲惨さが述べられています.こうなると早期リタイヤにはやはり否定的にならざるを得ません,,,
Apr 13, 2009
コメント(0)
-
完結編?:年金と世代間会計
http://www.nli-research.co.jp/report/pension_strategy/2009/Vol154/str0904c.pdfこれは本当に待ちのぞんでいたレポートだった.多くの人がこの国の行く末に不安を感じている.このレポートをみるとがっかりする人もいるかもしれないが,わたしは非常に大きな安堵感を得た.試算根拠が人口中位推計であろうし,成長率推定と運用利益見込みも矛盾している.いわゆる「うそも方便な2004年改革」だったのは十分承知なのだが世代間会計で約300兆の削減を行ったことに賛同したい.ずっと子供の海外移住を視野に入れていたが,考え直すことにした.明治以来,先の大戦までは,国は借金を膨らましながら他国の領土を占領する政策で国民生活の向上を図った.そして敗戦,預金封鎖,債券やお金は紙切れ同然今回は老人たちの年金,飲み食いのつけを,孫の代に背負わせる非道徳的な状況がこの国を崩壊させることを懸念していた.対外資産は600兆円,対外負債は350兆円くらいで250兆円の純資産はまだある,,おそらく貿易赤字が続き,ついで経常黒字も消えかかれば年金はふたたび大きく見直されるだろう..当初見込みでは2020年ごろ経常赤字のはずだったが,もっと早いだろう,そのときは遠くないもう待ったなしで,年金はふたたび大きく見直されるだろう,でも「国民はわかってくれる」とおもう.今後待っている大きな減額の年金であってもこの国の紙幣や資産が紙くずになってしまうよりははるかにましだ.いまの日本よりもずっと減額になるが悪くとも英国並みの年金くらいでおさまるのではないだろうか?これで勉強を始めて5年.ブログ開設よりちょうど4年.そして1000回目.私にとって非常に勉強になった5年間でした.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー仕事を趣味としてとらえて,無理なく,なるべく長く働く,年金に生活費の3分の1を期待する.ステップ1:時々:若林さんのブログをみる.本を読んでおく(2年に1回出版)ステップ2:月1回:Dr SchillerのHPを訪問し,10年PERが10以下を待つ.ステップ3:10年PERが10以下となり,新聞に暴落の見出しが出たとき:AlexのPRまたはTobin's qをみる.ステップ4:Tobin's qが0.4以下のとき:MarcFaberのコメントをみて,天底を確かめる.ステップ5:どの企業と付き合えばよいかをバフェットのポートフォリオを見てきめる.生活費の3分の1ほどは,配当をあてにする.ステップ6:配当は景気で上下するので不足するなら,株式投資に投じたのと同額のインフレ連動国債のほうから引き出す.ステップ7:生活費の残り3分の1は不動産から得る.のこりは不測に備えた資産とする.
Apr 7, 2009
コメント(2)
-
総集編2
20世紀は市場全体のトービンのq(98%PBRと相関)をみて安いときに買えば良かった。もっとも100年前の世界上位100の大企業のうち、現在は50企業しか残っていない。それでもいまの日本のように10年で93.8%の新規会社が消滅するよりはマシであるが今後、各国の年金基金が証券、債券を長期にわたり、売却することになるけどだれが買えるの?債券は金利が上がり、証券はそれに応じて配当利回りの分だけ価値が下落する紙を信じる時代はゆっくり終わりを告げ、ヒトとモノが大事になる。当たり前の時代、、、子どもを育てるのは親の仕事、親の面倒は子どもがみる時代へとそれとなく移行するのではないだろうか?労働はいつの時代でも有効である.そして人のために必要な基本的職業はなくならない.バフェットが投資したのも、そんな企業だったのかもしれない各国の年金基金が証券、債券を長期にわたり、損切り、売却することになるけどだれが買えるの?たぶん利回りが上がれば、年金に頼らず働いている若者たちがすこしづつ、自分とその家族の将来のために労働の対価をそれに交換していくことになるんだろうと思う1930年生まれのバフェットが、2007年にほぼ全ての財を寄付したようにたぶんいまごろは、どこかの国で第2のバフェットが生まれているのかもしれない。
Apr 5, 2009
コメント(0)
-
総集編1 早期リタイアへのアンチテーゼ
投資期間というのは引退して、資産を取り崩す期間を示します。60歳の男性が引退した場合、その8割のヒトが亡くなるまでに必要な年数は27年間です。米国のデータですので、日本の場合には+3年、ちょうど30年必要です。余生30年間送ろうとして、毎年4%取り崩した場合に、生きているあいだにお金が尽きない確率を示しています。引退期間が20年なら、100%債券でなければ大丈夫、、、1972年に引退して毎年7%引き出した場合,1982年には資金が尽きる.これは株式の暴落による.世界の富を独占した覇権国、米国のデータでさえ、この状況。まして、先進国は高齢化のため、資産を売ろうとしても買ってくれる相手がいなくなります。誰に売るの?買い手を後進国に期待する意見もありますが、その確率は高いでしょうか?日本の文化を海外がお金を出して欲しがるとしてもいくらの収入が期待できるかということなのですが日本人の中で、その恩恵を直接的に被る立場にあるひとには良いかもしれないですが、、全ての老人を潤してくれるとは思えません。働けるうちは出来るだけ長くヒトのために働くのが安全。知足安分:分際をわきまえ、足るを知ることなのかも。このデータは、以下のようにも読めます。20年の引退期間に預金を5%づつ引き出せば、お金が尽きない生存率は100%です。ところが、100%株式では20年で88%の生存率、20年で100%債券(10年確定利回り)での生存率は47%。証券会社と国家に貢ぐ、骨折り損のくたびれもうけ。助かろうとして、かえって早期に資金が尽きる。これは悲しい話です。高齢化する先進国のGDPが上昇するとは思えないし、先進国ETFは長期的には骨折り損のくたびれもうけになるかも
Apr 5, 2009
コメント(0)
-
安く見えるよなあ,,,,
http://1.bp.blogspot.com/_d4aL5xTH0xg/SdLAnN5E9WI/AAAAAAAADhU/WsVTL9c8E-I/s1600-h/VL+Div+Model.PNGこの配当が続くのなら,,,
Apr 3, 2009
コメント(0)
-
TobinのqとPBR
TobinのqとPBRは98%の相関関係がある。長期的に100年程度を見渡すにはTobinのqのほうが計算しやすく数年程度を正確に見るにはPBRが適しているのだろう2000年のSP500はPBRが5.4倍、Tobinのqが1.8なのでおおむね3倍くらいとなるようだちなみに1982年の大底はPBR1.2倍くらい、Tobinのqは0.4より少し下だろうこれを当てはめてよいか判らないが日経はPBRが0.9倍くらいまで下落した時はTobinのqは0.3倍くらいなんだろうね資産のバリューとしては合格なんだが人口構成からのボーナスがどこの先進国でももう期待できないそれを先行しているのが、日本なのかもしれない、、、青山の土地は去年の3分の1で取引されているくらいだからPBRの分母があてにならない
Apr 2, 2009
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1