2022年02月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
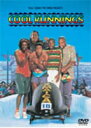
2月のおしゃれ手紙:冬季五輪あれこれ
1988年冬季オリンピックにボブスレー競技で挑んだ南国ジャマイカ・チームの実話を映画化した傑作コメディドラマ「クール・ランニング」。1988年、カルガリーのオリンピックで世界中に注目されたチームがあった。それは、冬期五輪史上初の南国ジャマイカのボブスレー選手団。かれらの予想外の大健闘という実話を基に、とびきり愉快で心暖まるこの映画がつくられた。ジャマイカ選手の陽気で勇気ある挑戦に、心から声援を送りたくなる!ジャマイカの陸上競技100mの有力選手デリース(リオン)は、最初で最後の挑戦となるオリンピック出場を目指して練習に励んでいた。しかし、運悪く最終予選で転倒、夢を絶たれてしまう。が、どうしてもあきらめきれない彼は、とんでもないことを考えつく。それは、常夏の南国ジャマイカ始まって以来の”冬”のオリンピック出場だ!? 北京オリンピックの期間中に「クール・ランニング」というコメディを見た。面白くて、ほのぼのとしていて、何度見ても笑って泣いた。まだ、ドイツは東西に分かれている時代。ついこの間のことのようで、いろいろなことが変わったことに驚く。日本は、過去最高のメダル数というけれど、競技の数が多くなったのでメダルの数が多くなるのは当たり前。■この大会でフィギュアスケート■において日本の伊藤みどりが、当時の女子で最高難易度レベルのジャンプを連発し地元メディアに「flying woman(空飛ぶ女性)」と紹介され一躍人気を集めた。伊藤は、決勝では5位に終わったが、多くのファンからの要望でエキシビションに登場した。メダリストを差し置いてトリを飾ったという逸話がある。メダルを取ったから強いのではないと思うんだけど、今なお、ドーピングする国、(選手、チーム)がいるなんて、おかしい・・・。●コロナワクチン、3回目終わる。■2022年2月見た映画■*ちょっと思い出しただけ*フレンチ・ディスパッチ*ウエスト・サイド・ストーリー■暮らしのvlog/気分を上げる模様替え/変化し続けるキッチン/シェーカーボックス/休日パンケーキ■最初の所で絵を飾るシーンと0.22にもう一回。これは「COFFEE」という映画のチラシ。私もこのチラシを壁に飾りたいと思って大事にとってある。■ヒゲとわたし【ルームツアー】デザイナーふたり暮らし | 1LDK賃貸 | 植物のある暮らし | 古道具インテリア■■辻ちゃんのモーニングルーティーンを真似したらなぜか夕飯が出来上がった。■■書き残したネタ■*レッドオーシャン、ブルーオーシャン*SDGs(エスディージーズ)のバッジ*食器の柄*丁寧語*高師浜*背という言葉*大阪弁*読書ネタ*丁寧すぎる言葉*プラスティックごみ*白樺のかご*会話力*妄想古民家カフェ「くるり」*漆の木・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.28
コメント(0)
-

昔語り:綿入れ
ここ数年、時代小説をよく読んでいる。その中に、「綿入れの着物」が出てくる。寒くなる前に、着物に綿を入れるのだ。読んでいて、綿入れの着物なんてあるはずがない!と思っていた。しかし、よく考えたら、私の子どもの時代には、綿を入れた衣服があった。今から65年ほど前の岡山の山間部の村で私は子供時代を送っていた。 ★当時、大人も子どもも、男も女も、冬になると「ちゃんちゃんこ」を着ていた。それは、綿の入った袖なしの袢纏のようなもので、今の時代のダウンジャケットのようなものだった。★綿入れ袢纏もよく着ていた。綿入れ袢纏は、高校に通うようになっても家の中で着ていた。あれは、秋の深まった頃だろうか、夜、小学生の私に母が一緒に付いて行ってと言って、小学校に行ったことがある。母親たちの音楽同好会があって、歌が好きな母も入っていたのだった。その時も、「はんちゃ」を着て、片手に読みかけの本を持って、母のお供をしたことがあった。綿入れ袢纏のことを「はんちゃ」と言っていた。語源を調べたが分からなかった。しかし、九州の糸島や東北でも使われる言葉だそうだ。★■ねんねこ半纏(ばんてん)■というのもあった。赤ん坊を背負った時、赤ん坊が寒くないようにと綿の入ったおんぶ用の袢纏があった。春や秋には綿の入っていな袷(あわせ)のを使っていた。★亀の子袢纏ねんねこ袢纏は、仕事がしにくいということで、ねんねこ袢纏の袖をなくしたものが、よく使われていた。背負われた子供に、「ええなあ、温(ぬく)うて」と大人たちは声を掛けた。また、背負っている母親にも、「子どもを負うとったら、温(ぬ)くかろう」と声を掛けた。★丹前冬、仕事から帰ると父は、風呂に入り、下着を変えてから、その上に、丹前を着た。丹前は、綿の入った着物。そして、夕食と晩酌。母が作る料理を「美味しい、美味しい・・・」と何度も言いながら酒を飲んだ。 いつも、夏の暑さより寒い方がましと思う私だが、今年の冬の寒さは辛い。家に入ってもダウンジャケットを脱ぐことが出来ない私に、「外みたいな恰好をするな」と夫が叱責する。昔は、外でも内でも綿入れを着ていたのだがと私は言葉に出さずつぶやき、春の訪れを待っている。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.26
コメント(0)
-

ウエスト・サイド・ストーリー★群舞
■ウエスト・サイド・ストーリー■ひとつになりたかった。ひとつになれない世界で・・・。1950年代のニューヨーク、差別や偏見により社会への不満を募らせる若者たちは仲間と団結し激しく敵対し合っていた。そんななか「ジェッツ」と呼ばれるポーランド系移民によるチームの元リーダー、トニーは、対立するプエルトリコ系チーム「シャークス」のリーダーの妹マリアと出会い一瞬で恋に落ちる。しかしこのふたりの恋は、やがて多くの人の運命を変える悲劇となっていく。 スティーブン・スピルバーグ監督のキャリア初となるミュージカル作品。1957年にブロードウェイ・ミュージカルとして生まれ、1961年に映画化されアカデミー賞10部門を受賞した『ウエスト・サイド物語』を現代に蘇らせた。主演は『ベイビー・ドライバー』のアンセル・エルゴート、ヒロイン役をオーディションで選ばれたレイチェル・ゼグラーが務める。また、1961年版でアニタ役を演じアカデミー賞を受賞したリタ・モレノが出演し、製作総指揮も兼任している。 ご存じ、大ヒットミュージカルの映画化のリメイク。作品の内容は、みんな知っているし、監督がスティーブン・スピルバーグということ、見に行ったのが、水曜日、レディスデイで、1200円で見ることが出来る、その上に、祝日ということが重なったので、ほぼ満席だった。 最初、ジェット団の男たちが行くシーン、ダンスシーン、「アメリカ」を歌いながら踊るシーン・・・。どれも群舞がすばらしかった。「ウエスト・サイド・ストーリー」が映画化されたのが、1961年。1964年、「マイ・フェア・レディ」 1965年、「サウンド・オブ・ミュージック」と60年代前半に豪華なミュージカルが映画になった。 その後、1975年初演の「コーラスライン」がヒットしたが、これは、ものすごく地味なものだった。なんせ、オーデション風景が延々と続くのだから、華やかな衣装もない。キラキラなのは、最後だけだった・・・。最近のミュージカルは、「美女と野獣」、「ライオンキング」などディズニーとのコラボで多くの観客を集めている。「ウエスト・サイド・ストーリー」、「マイ・フェア・レディ」、「サウンド・オブ・ミュージック」は、あまりにも初回の映画が完璧で、伝説的な作品。だから、今回のは、どうだろうと心配しながら見に行ったが、ものすごくよかった!!■撮影の裏側■がを見たが、すごい規模の裏方さんがいるんだなと感動!本年度アカデミー賞では主要部門の作品賞・監督賞・助演女優賞含む7部門でノミネートされる快挙を達成。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.24
コメント(0)
-

マンガ 皇妃エリザベート:ハプスブルクの美神
■マンガ 皇妃エリザベート■今なお、全世界の人々を魅了!!美と個性の皇妃の数奇な運命!!没後百年たってもますます人気を集める悲劇の女(ひと)エリザベート。その魅力の秘密は何だったのか?!19世紀末ヨーロッパの歴史と共に描く「女」の貫き方!!19世紀半ば、隆盛を誇る名門ハプスブルク家の若き当主、オーストリア帝国皇帝フランツ・ヨーゼフは、バイエルンの公女エリザベート姫に出合い、電撃的な恋に落ちる。身分的には何の問題もなく見えたこの結婚は、自由を愛するエリザベートの個性によってけっして幸福とはならなかった。しかし全ヨーロッパを魅了したこの美貌の皇妃と、彼女の苦しみを深く理解し愛した皇帝との物語は、時代を超えて人々の心を打ち続けている。華麗なタッチで綴る歴史絵巻!! 「バイエルンの薔薇」と呼ばれ、ハプスブルク家六百有余年の歴史上最も美しいといわれた皇妃エリザベート。激動の時代、彼女は嫉妬と羨望のなか、皇室の因習に抗い自由奔放に生きた。没後百年を経てもオーストリアの人々の心を捉えてはなさない"シシィ"エリザベートの波瀾万丈の人生をいきいきと描いた決定版!■若さと美貌を永遠に保持するため、■二十代からベジタリアンとなったエリザベートは日に三回体重計に乗り、痩身に専心。一七二センチという長身だったが、体重は四十五―七キロを保ち、ウェストは五十一センチにも絞り込まれた。断食を始めとする過度なダイエットのほか、北欧で生まれたばかりの体操を即座に取り込むなどして体形維持に努めた。背中がまっすぐになるよう枕は使わずに寝ていたという。★皇妃エリザベート(愛称 シシイ)と周りの人々。60歳で殺害される。★夫・オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフエリーザベトのいとこ。母親同士が姉妹。夫、肩書は47にのぼる。●子ども(4人)★ゾフィー(1855年 - 1857年)幼くして死亡。★ギーゼラ(1856年 - 1932年)★ルドルフ(1858年 - 1889年) オーストリア皇太子(謎の死をとげる。他殺された。自殺の説もある。)★マリー・ヴァレリー(1868年 - 1924年)エリーザベトの愛人との間の子という噂もある。■エリザベートの圧倒的な美しさ■エーデルワイスの花と、星の形のダイヤモンドをちりばめた腰まで届く長い栗色の髪、同じような星型の刺繍のある白い豪華なドレスに身を包んだエリザベートの美しさは、典雅、気品、端麗、威厳、孤高、静寂、ロマンティシズム、あらゆる美しさの要素が混ざり合っていて、いかなる言葉を並べても表現できないほどの存在感と迫力を持っていて、見るものを金縛りにした。それはこの世のものとも思われぬ、幻想的な妖精の魅力をたたえている絵であった。 エリザベートの、皇太子のルドルフは、31歳のときに男爵令嬢マリー・フォン・ヴェッツェラと情死する。それが、「マイヤーリンク事件」として有名。「うたかたの恋」というタイトルでも知られている。 ドイツ・ベイエルこの最後の国王ルドウイヒ二世が1869年から17年の歳月と巨額をかけて完成した城の城主、国王ルドウイヒ二世は、父方の親戚で、エリザベートのいとこになる。この王も謎の死をとげた。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.23
コメント(0)
-

処分の前に記念撮影:バナナの葉模様の大皿
70歳もとっくに過ぎているので、終活をしなければと見の周りを観察する。処分できるものは、今のうちに必要な人のところにと思っている。写真の大皿は、そんなものの一つ。直径25センチぐらい。いつの時代のものか、分からないが、近所の蔵を潰すときにもらった。それからすでに40年ほど経っている。4~5人家族なら、この皿に盛りつけて、各自の取り皿にという風に使えるが、老人夫婦二人では、大きすぎる。とりあえず、皿の写真を撮っておこう。写真が下手・・・。_| ̄|○大皿のサイズを現すために、アボカドを入れた皿を横に置いた。この皿の絵には、バショウが描いてある。なぜ、バショウの絵が描いてあるのかも調べた。バショウは中国原産であり、観賞用として庭園などに植えられます。中国磁器は明代にバショウを描いたり、その葉の連続文を盛んに描きました。そのため有田磁器も早くからバショウを文様として描きますが、17世紀後半にバショウを描き込んだ中国の風景文様の例が多くなります。バショウ模様の食器沢山ある・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.21
コメント(0)
-

フレンチ・ディスパッチ★ウエス・アンダーソン監督
■フレンチ・ディスパッチ■物語の舞台は、20世紀フランスの架空の街にある「フレンチ・ディスパッチ」誌の編集部。米国新聞社の支社が発行する雑誌で、アメリカ生まれの名物編集長が集めた一癖も二癖もある才能豊かな記者たちが活躍。国際問題からアート、ファッションから美食に至るまで深く斬り込んだ唯一無二の記事で人気を獲得している。ところが、編集長が仕事中に心臓まひで急死、彼の遺言によって廃刊が決まる。果たして、何が飛び出すか分からない編集長の追悼号にして最終号の、思いがけないほどおかしく、思いがけないほど泣ける、その全貌とは──?『グランド・ブダペスト・ホテル』のウェス・アンダーソン監督の長編10作目。雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の編集部を取り巻く物語を描く。 「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」というのがこの映画のタイトルだけど長すぎるから省略。★■ダージリン急行■(2007年)★■ファンタスティック Mr.FOX■(2009年)★■ムーンライズ・キングダム■(2012年)★■グランド・ブダペスト・ホテル■(2014年)ウエス・アンダーソン監督の映画、大好き!! 映画の内容は、■「自転車レポーター」記者のサゼラックが編集長の愛した街アンニュイ・シュール・ブラゼを自転車で一巡しながら紹介。■「確固たる名作」記者ベレンセンが超個性的な画家で囚人のモーゼスと、彼のミューズで看守のシモーヌとの驚くべき関係を記事にしたためる。■「宣言書の改定」記者ルシンダが、“若き理想主義者運動”を立ち上げたリーダーのゼフィレッリと会計士ジュリエットが関わる学生運動、その青春の激しさと甘さを間近で捉える。■「警察所長の食事室」記者ローバックが警察署長お抱えの天才シェフ・ネスカフィエのお手製絶品料理を優雅に堪能する。■ポップかつシニカル、そして大胆な脚本。■キャッチーな色彩とディテールで構築されたセットや小道具の数々。精巧な構図とカメラ移動で生み出されるマジカルな空間演出。そしてひとクセもふたクセもありながら誰もが愛さずにはいられない登場人物たち……。 今回も、魅力的な画面だった。舞台のカキワリかと思うようなセットだったり、どこの国もいつの時代の町なんだろうと思ったり・・・。小道具も、かわいい♪パソコンではなくて、タイプライター!ラジオやジュークボックスなどなどかわいいものがいっぱい♪アンダーソン作品に登場するキャラクターたちは、みんなどこかこじれていて風変りだが、魅力的。■アメリ■■ミックマック■■天才スピヴェット■の監督、ジャン=ピエール・ジュネと同類のにおいがするのだが・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村
2022.02.19
コメント(0)
-

ちょっと思い出しただけ★ふたりの6年間
■ちょっと思い出しただけ■「ある1日」だけで遡る、ふたりの6年間・・・。怪我でダンサーの道を諦めた照生(池松壮亮)と、その彼女でタクシードライバーの葉(伊藤沙莉)。めまぐるしく変わっていく東京の中心で、何気ないある一日が流れていく。特別な日も、そうでない日もあるが、決して同じ日は来ない。二度と戻れない愛しい日々を、ちょっと思い出す……。「くれなずめ」の松居大悟が監督・脚本を手掛けたラブストーリー。怪我でダンサーの道を諦めた照生と、その彼女でタクシードライバーの葉。二人を中心に関わる登場人物たちとの会話を通じて、都会の夜に無数に輝く人生たちの機微を繊細かつユーモラスに描く。 出演は、■「アジアの天使」■の池松壮亮、「ボクたちはみんな大人になれなかった」の伊藤沙莉。第34回東京国際映画祭コンペティション部門選出。ふたりは、なぜ別れたのだろうか?別れから始まるドラマなので、いつ決定的な別れがあるのだろうと注意して見ていたけれど、分からなかった。お互いに、「明日から別れよう」というシーンがなかった。それだけに、会わなくなっても、二人とも引き摺っている。けれども、時は過ぎていく・・・。輝生の誕生日だけでつづる時の過ぎゆく様・・・。映画の最後のシーンを見て、「葉ちゃん、幸せになってね・・・」と心の中で祈った。 映画のチラシは、私が手に入れたものだけで、9種類あった。それぞれに、ふたりの住むアパートでの暮らしや、葉がタクシーに乗っているシーン、家の近くの階段を駆け下りて行くシーン・・・。6年間の暮らしを垣間見せるチラシになっている。 輝生がよく行く店のスタッフとして、成田凌が出演!!ほんのちょい役、イケメンの無駄遣いや~~!!■尾崎世界観が役者として出ていて、主題歌も歌っていた。■主役を演じる池松壮亮は、「松居(監督)さんとクリープハイプの尾崎世界観さん(主題曲&出演)とは、僕が20代前半の頃によく3人で遊んでいました。映画を作ったり、観たり、お酒を飲んだり、旅行をしたり…。一緒に青春を過ごした人たちと再会をして、青春に決着をつけるような気持ちでした」とオファーを受けた瞬間を述懐。縁を感じる。お笑いコンビ、ニューヨークの屋敷も出ていてビックリ! 一年に一度会うというストーリーで忘れられないのが、■ワン・デイ 23年のラブストーリー■23年。23回の7月15日。どの1日も、あなただけを見ていた―――。この映画も切なかった・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.17
コメント(0)
-

動画で懐かしい「煮ぐい」という言葉を発見した!
■昔語り:2019.1.26■で「煮ぐい」という食べ物の思い出を書いた。65年程前の岡山での冬の食卓には、時々「煮ぐい」というご馳走があった。「煮ぐい」は、サバなどの魚と冬野菜のなべだ。肉の代わりに安いサバを、そしてその中に、白菜など野菜を入れて醤油で味をつけて炊く。これって、私たちだけが使っていた言葉だったのだろうと思っていたら、思いがけず、「煮食い」という言葉を聞いた。■2020.3.7 花月にてサバのすき焼き。■21分11秒。高知の90歳の方の言葉で、孫は、はじめて聞いたようだ。調べてみると、以下のことが分かった。■煮食い・煮ぐい(にぐい)■鍋で煮炊きして食べること。鍋料理。煮物。魚の切り身を用いるすき焼き風鍋の、島根県や高知県などにおける呼称。魚すき。鶏肉と根菜類などを煮付けた、大分県や福岡県の一部地域にみられる郷土料理。相撲業界で、すき焼きおよびすき焼き風のちゃんこを意味する符牒。 それにても、高知のユーチューバーさん、90代のお爺さん、お婆さんと3人暮らしらしいが、ご両親はどうしたのだろうかと気になった仕方がない。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.16
コメント(0)
-

DVD「エマ:恋するキューピッド」★BBC、二度目
■エマ:恋するキューピッド■エマは幼くして母を亡くしたため、心配性な父に大切に育てられる。 そのおかげで生まれ育った土地を一度も離れたことのない箱入り娘であった。 それでも視野が広く、社交的で芸術の才能にも恵まれた美しい女性へと成長したエマは、姉と家庭教師のミス・テイラーの結婚は、自分のおかげと思いこみ、他人の縁結びに夢中になる。 長年の友人ナイトリーはそんなエマをたしなめるのだが、エマは縁結びに躍起になる…。 しかし、自分の恋愛のこととなると、恋愛の百戦錬磨の牧師のエルトンや、派手で無責任な冒険家のフランク・チャーチル、無骨で率直で皮肉屋のどこにでもいるタイプのジョージ・ナイトレイに言い寄られても、自分自身の本当の気持ちにはいつも気づかない。今回、■2度目の、『エマ』(Emma)■は、ジェーン・オースティンの長編小説の4回にわたるBBC制作の作品。1814年1月21日に起稿し、翌年3月29日に完成、12月に刊行された。 オースティンが40歳の頃の作品だ。 ジェーン・オースティンの代表作といわれる、「高慢と偏見」が1813年に刊行。(1796年10月から1797年8月(ジェーン20-21歳)に執筆。)「高慢と偏見」のヒットで執筆の依頼があったのだろうか? 当時のイギリスの上流階級は大きく貴族院に議席を持ち爵位を持つ貴族とそれ以外の大地主階級(ジェントリ)に分けられるが、ジェントリ階級の中でも歴史的血統、親族の質、財産などにより格の上下が意識されていた。通常の社交上の儀礼では同等とされていたが、結婚など現実問題においては、そのような格差が重要となってくる。エマの家は、大地主階級。エマの友人、ジョージ・ナイトリーは、ハイベリーの隣の教区の大地主である。自由な風潮のエマの中にも、階級の差別はあるのは当たり前。★ハリエット・スミスが結婚するかも知れないと思ったエマは、相手が農夫であることを理由に断る方向に持っていった。ハリエットは、エマの年下の友人。初心でエマを崇拝している。しかし、私生児なので、これは良縁だったとナイトリー氏が怒る。■「エマ」主な登場人物■★今回「?」と思ったのは、服装。部屋の中で、エマは半そでの薄物のワンピース。(多分、下着は一枚だろう。)部屋の中では暖炉に火が入っている。そんな中で、ナイトリー氏は、ジャケットを着て、きっちりタイをしている。見るからの暑そう。★あと、ダンスパーティに馬で乗って行ってはいけないという作法があるのを今回、はじめて気が付いた。馬車があるということは、それをひく馬がいるし、御者もいる。馬車があるかどうかが、金持ちかどうかの分け目ということだろうか。ちなみに、牧師のエルトンは、馬車をもっていない。★また、真夏にピクニックに行くシーン。イギリスと言えども、夏は暑い。なぜ、北のスコットランドや湖水地方に保養に行かないのだろうか?そんな中、友人として付き合っている、ナイトリー氏の、貧しい人や、立場の弱い人に対する思いやりは、胸を打つ。主人公・エマも「高慢と偏見」のエリザベスも元気はつらつとした知性をもつ、当時珍しいタイプの女性。▲エマが歩いていそうな村。■コッツウォルズ■▼・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.14
コメント(0)
-

まだ「パンまつり」の白い皿いりますか?
買い物の帰りにふとみると「〇〇春のパンまつり」をやっていた。まだやっているんだ、パン祭。春になってパンを買うと、白い皿がもらえるっていうの、もう春の恒例、常識になっている?「パンまつり」って俳句の季語じゃね??■いつからやっているのかと調べてみたた、1981年だった。■もう40年以上前からじゃないか!!! 40年前といえば、白い皿が新鮮に見えた。「クロワッサン」の店などが、しきりに白い皿をすすめていて、シンプルが一番という時代。80年代は昭和だったから、どの家にも。けっこうゴテゴテした模様の皿が家にあった時代だ。私もその頃は、気に入ったのを雑誌などでみると、籠、キッチン秤、グラスなど東京の店に注文して送ってもらっていた。その後、「クロワッサンの店」、「無印良品」、「IKEA」・・・などなどおしゃれな生活雑貨の店が出来て、簡単におしゃれな雑貨が手に入るようになった。 (▲■我が家の正月の食器■)ちなみに私の、好きな食器は、骨董。骨董市や親せきなどでもらったり、捨ててあるのをレスキューしたり・・・。結構持っている。しかし、少しづつ少しづつ人にあげたりしている。 今はやりの断捨離。断捨離とは、捨てることばかり考えるけど、もらわないことが大事だと思う。百均にいけば、大きさも形も色々ある白い食器。40年以上前と、時代ががらりと変わったのに、みんな今も白い皿を求めているのだろうか?・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.12
コメント(0)
-

ほかほか蕗ご飯:居酒屋ぜんや:江戸の飯屋
■ほかほか蕗ご飯:居酒屋ぜんや■家禄を継げない武家の次男坊・林只次郎は、鶯が美声を放つよう飼育するのが得意で、それを生業とし家計を大きく支えている。ある日、上客の鶯がいなくなり途方に暮れていたときに暖簾をくぐった居酒屋で、美人女将・お妙の笑顔と素朴な絶品料理に一目惚れ。青菜のおひたし、里芋の煮ころばし、鯖の一夜干し……只次郎はお妙と料理に癒されながらも、一方で鶯を失くした罪責の念に悶々とするばかり。もはや、明日をも知れぬ身と嘆く只次郎が瀕した大厄災の意外な真相とは。美味しい料理と癒しに満ちた連作時代小説、新シリーズ開幕。歴史ものが好きな私は、江戸時代の食事や暮らしがわかるこの本に目がいった。そこでメモしておく。●メモ ◎は私のコメント●鳥の糞買い。●鶯の糞は肌を白くすると、聞いたことがあるのを覚えていた。●先に湯屋へ行って・・・◎朝風呂に入ってから仕事をする。みんなそうしていたのだろうか?■与力の朝風呂(よりきのあさぶろ)■江戸時代の銭湯は、明け六つ(夜明け)から営業を開始する。朝早くから、博打場や遊廓に行っていた者が湯に入りにきて、混み始める。次第に、隠居の立場にある者や医者、坊主、下級武士らが入りにくる。想像以上に、午前中の客が多かったのである。一方、女湯の場合、女たちには食事の支度や掃除、洗濯などの家事があるので、朝入りにくる客はほとんどいない。 ■くらしの今と昔:風呂屋■ ●初物好きの江戸っ子のために大坂と西宮の樽廻船問屋が新酒を積み込んだ船の先着を競う、新酒番船という行事が催される。(略)普通なら十日以上かかる道のりを、三日四日で運んでしまう・・・(略)●(略)矢場女と亭主がいい仲ではないかと疑っていた。(略)矢場女は矢を拾うだけではなく客も取る。◎(矢場とは)元来は矢を射る所の意。元禄期に社寺の境内,盛り場などに出現し,10矢で4文などの料金を取り,的や糸でつった景品を射させた。楊弓場(ようきゅうば)とも。のち矢場女とか矢取女という接客婦がおかれて売春も行われ,次第に私娼窟(ししょうくつ)化した。幕末〜明治中期に浅草,芝,両国等で盛行したが,明治末年にはすたれた。●本来鶯がなきはじめるのは立春を過ぎてから。(略)だが商家では「春告げ鳥」と呼ばれるめでたい鶯の声を、元日の訪問客に聞かせたい訳である。ゆえに多少強引ではあるが、鶯に日が長くなったと思わせて早めに鳴くように仕向けてやる。実際になにをするかというと、あぶるのである。日没前から灯火をつけ、それを鶯に見せて体内の時計を狂わせる。これを俗に、あぶりという。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.11
コメント(0)
-

ファジーな大阪弁一覧表:「わ」
■ファジーな大阪弁一覧表:「わ」■■わや(関西方言の「わやく」から)駄目、失敗、無謀、無茶苦茶。わう惑の約訛という。わうわく→わわく→わやく→わや■ファジーな大阪弁:「あ」~「お」■■ファジーな大阪弁:「か」~「こ」■■ファジーな大阪弁:「さ」~「そ」■■ファジーな大阪弁:「た」~「と」■■ファジーな大阪弁:「な」~「の」■■ファジーな大阪弁:「は」~「ほ」■■ファジーな大阪弁:「ま」~「も」■■ファジーな大阪弁:「や」~「よ」■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.09
コメント(0)
-

雪降れば佃は古き江戸の島
雪降れば佃は古き江戸の島 北條秀司 ■2020年、東京・佃島に行った。■その時、佃島にあったのが、「雪降れば・・・」の俳句の碑だった。俳句の作者の北条秀司は、1902年(明治35年)11月7日 - 1996年(平成8年)5月19日)は、劇作家、演出家。大阪生まれで1926年に上京。1926年といえば、大正15年、昭和元年。その頃は、まだ佃島は、昔の景色が残っていただろう。 佃島の光景を愛していた劇作家の北條秀司が、1957年に佃の渡しを舞台に新派俳優花柳章太郎のために書き下ろした芝居に『佃の渡し』がある。初演以来高い評価を受け、滅びゆく日本の古き良き情景を舞台で再生させた名作として、昭和39年には花柳十種のひとつに選ばれているなど、北條、花柳、そして新派にとって欠くことの出来ない代表作のひとつとなっている。 ■「随筆 明治の東京」■という明治、大正、昭和を生きた画家・鏑木清方には、佃島のことを書いた文章があった。(下の文章)■築地界隈■昭和8年3月発表(略)明石町と入り江を挟んでいるのは佃島である。今では相生橋で深川につながり、月島と境もわからないようになってしまったが、まだ月島埋め立ての行われなかった時分は、橋もなければ、全くの離れ小島、 大きいものは住吉神社の大鳥居だけ、島人というのは漁師ばかりで、名物佃煮をこしらえる家には、年中洗ったことのないという大釜が据えてある。(略) この島に生まれた男の子は、十歳になるかならないうちに天秤棒を担がされて、冬は蜆(しじみ)、夏は鰯(いわし)を売りに出される。京橋いまわりで育った子供は、悪戯をすると佃へやってしまう、と脅かされて思い出をもたぬものはすくなかろう。■2020年東京・佃■立春は過ぎたので、もう雪は降らないだろうか・・・。しかし、寒さは、まだまだ厳しい。武陽佃島とは隅田川の河口にあった小島であり、図の右側の家が密集している場所が佃島で左側の木立で覆われた部分は石川島です。現在の東京都中央区佃島は、江戸時代大坂の佃村の漁夫が江戸へ移り、砂州を埋め立てた場所で、彼らの故郷にちなんで佃島と名付けられたそうです。佃島周辺で採れる海産物を使って作った煮物が「佃煮」は今でも有名です。図には7艘の船が描かれゆったりとした雰囲気を醸し出しており、佃島からくっきりと綺麗に見える富士山が描かれています。・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.07
コメント(0)
-

随筆集 明治の東京:鏑木清方・日本画家の見た明治の東京
■随筆集 明治の東京:鏑木清方■代表作「築地明石町」などにみられるように,鏑木清方の画は,明治の東京の庶民生活を描いて他に類がないといわれるが,折々に書かれた彼のエッセイもまた,江戸や明治への郷愁を誘う美しい小品として忘れられない。「白足袋」「草双紙」「兎と万年青」「銀座回想」「芝居昔ばなし」「明治の東京語」「甘いものの話」等40篇を精選。 鏑木 清方(かぶらき きよかた、1878年(明治11年)8月31日 - 1972年(昭和47年)3月2日)は、明治期から昭和期にかけての浮世絵師、日本画家、随筆家。私の祖父が明治9年生まれだったから、祖父の時代の人だ。鏑木清方は、日本画の名手と言われている。しかし、それ以上に、随筆でも評価されている。私が、そのことを知ったのは、今から25年以上前のこと。■みどり学講座■という講座を受けて、その中鏑木清方のことを知った。清方は、■都市には緑が必要■と言っている。建物4に対して緑6の割合がいいとまでいってる。土と草と、木と水と、そういう総合美から成り立たせた住宅街、高層建築もそこだけには除いて・・・。緑や自然は、金銭的な計量化をこえたアメニティの価値に深くかかわっているといっているのだ。以来、私は、清方のファンになったが、随筆を読むのはこれがはじめて。 文章が上手いな・・・と思うながら読んだが、子どもの頃から、大人になったら、小説家になろうかと考えていたらしい。清方が求めた美というのは、江戸の町が育んだ美、そして,清方の絵にも随筆にも江戸へのノスタルジーが溢れている。幼い頃、家が貧しくなって、住む家もなく親戚に母親、祖母と一緒に世話になっていたというのに、美意識も人間性も汚れていない。至る所に、清方の美学が書かれている随筆集だ。 ■鏑木清方■近代日本の美人画家として上村松園、伊東深水と並び称せられる。作品は風景画などはまれで、ほとんどが人物画であり、単なる美人画というよりは明治時代の東京の風俗を写した風俗画というべき作品が多い。関東大震災と第二次大戦による空襲という2つの災害によって、清方がこよなく愛した明治時代の古き良き東京の風景は消え去ってしまったが、彼は自分がこよなく愛した東京の下町風俗や当世風の美人を終生描き続けた。■没後50年 鏑木清方展■◆東京展◆会期:2022年3月18日〜5月8日◆会場:東京国立近代美術館◆京都展◆会期:2022年5月27日〜7月10日◆会場:京都国立近代美術館・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.05
コメント(0)
-

北海道歳時記:節分・鬼やらいと厄払い
節分とは、季節の変わり目のことで、立春、立夏、立秋、立冬の前日をさし、1年に4回あります。2月初めは、陰暦の正月にあたり、暦日上重複または連続する日が多かったことから一部地域で、大晦日から正月にかけての行事の一部が節分の日に行こうして行われたことが全国に伝わり、現在では、大寒の末日で春に季節が変わる立春の前日をさすようになりました。各地で行われている節分には、大晦日に行われる新しい年の年占い、厄よけや邪気を払う行事が伝承されています。●鬼やらいと厄払い●社寺でその年の年男が「福は内、小野は外」と唱えて炒った豆を鬼に打つ。また、家庭では、家長(主人)または年男が炒った大豆を入れた升を神棚に供えて家族の幸せを祈った後、戸口や窓を開けて「鬼は外、福は内」と唱えて豆をまく。まかれた豆は家人が各々年の数より一つ多く拾って食べる。これは年をまたいで健康に過ごせるようにといった願いがこめられている。 *旧浦河公会堂(元浦河協会)を設立した日本基督教会団体、赤心社(兵庫県出身団体)の創始者鈴木清は、三田藩主九鬼家の家臣であったが、その九鬼家では「鬼は内、福は外、富は内」と唱えた。主人は恵方(新しい年神、歳徳神を迎える方位)に座り、年男が先の言葉を唱え主人に打ちつけた。これは、鬼の字が姓についているための工夫である。■北海道・札幌;野外博物館:北海道開拓の村■■18日間北海道ドライブ旅行■■北海道歳時記:秋の彼岸■■北海道歳時記:秋じまい・庭じまい■■北海道歳時記:餅つき■■北海道歳時記:節分、豆占い■■北海道歳時記:ひなまつり■■北海道歳時記:半夏生(はんげしょう)■■北海道歳時記:北海道の七夕■■北海道歳時記:竹細工■■北海道歳時記:盆踊り■■北海道歳時記:節分ヤイカガシ■■北海道歳時記:雛祭■■北海道歳時記:雛おくり■■北海道歳時記:八十八夜■■北海道歳時記:ローソクもらい■■北海道歳時記:お九日(くにち)■■北海道歳時記:ふいご祭■■北海道歳時記:漁村の正月、農村の正月■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.03
コメント(0)
-

とら年ですから:「山月記」の虎が表すものと国語の教科書問題
とら年ですから虎の話書こう。主人公の李徴が虎になる、中島敦の『山月記』は、高校の授業で読んでから、今も何年かに一度は読み返すほどのお気に入りの小説だ。■山月記■李徴は非常に優秀な人物で、本人にもその自負と自信がありました。その実力は若くして役人になるほどで、自他ともに認めるエリート中のエリートです。そんな李徴は仕事を辞めて詩人として生きていくことを決意します。詩作に励むこと数年、思うような結果が得られなかった李徴は再び元の職場に戻ってきました。そこでは以前の同期が上司となっていて、李徴は彼らに使われる側になっていました。それから1年後、李徴は発狂して虎となり行方不明になります。■自尊心自分の思想や言動などに自信をもち、他からの干渉を排除する気持ちや態度。■羞恥心恥ずかしく感じる気持ち。「臆病な自尊心」、「尊大な羞恥心」=「強すぎる自意識」李徴が虎になったのは、強すぎる自意識に飲み込まれたから。『山月記』が高校の国語で使われるもう一つの理由は、多感な高校生が自意識をこじらせやすいからだと考えられます。 なるほど・・・。■「山月記」は■教科書で好きだった小説ランキングの2位になっている。私たちには、身近だった国語の中の小説だが、国語の教科書から小説が消えて、全て実用文になるという大幅な改定がなされるという。簡単に説明すると、「大学入試および高等学校指導要領の『国語』改革」において、高校で文学の勉強をせずに、もっぱら実用文に重きを置いた教育をすることになったのである。小説を排除する代わりに「求人票」や「説明書」の文章を入れた高校の国語の教科書で、実用的な国語力を育てる――。教科書も当然、小説を排除したものが求められる。そんな文部省の誤った考え方で現場は大混乱だという。そんな中で一石を投じたのが、広島にある「第一学習社」の「現代国語」。ここには、あってはならない、小説が五つ収録されている。「第一学習社」は、なぜお上の意向に反して「現代の国語」の教科書に小説を収録したのか。 同社に取材を申し込むと文書で回答が寄せられた。〈教育現場の先生方からご意見を伺うなかで、「現代の国語」の授業の中で小説を扱いたいとの要望が多く聞かれたことを踏まえました〉〈文部科学省による事前の説明会などを踏まえ、小説を扱うことは難しいとの認識はございましたが、上記現場ニーズを踏まえ、不合格を覚悟でチャレンジするだけの価値があると判断しました〉 教育現場の声を汲み取り、あえて“狙って”小説を入れたというのだ。そして、その狙いは見事に的中したといえそうだ。 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授の阿部公彦氏は、「文学における言葉には、さまざまな働きや効果、面白さなど、我々には計り知れないエネルギーのようなものがある。そうしたことを体験したり、体験を通して知ったり、知ったことを実践するのが非常に重要。こうした言葉の不思議な働き方を体験する入り口に連れて行ってくれるのが国語教育の大事な要素のはずです。」「週刊新潮」2021年10月7日号 掲載もし学校で「山月記」を読まなかったら、今も知らなかったと思う。 「赤毛のアン」を知ったのも中学校の国語の教科書。そして、それは今も私を形成するひとつになっている。国語の教科書から小説をなくしていいのか?!■昔語り:読書の思い出■■動画:ロザンの楽屋:国語の教科書検定問題■■とら年ですから:陽気に虎拳:とらとら■・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022.02.01
コメント(4)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 内勤です。⛅️(5度)寒い秋模様🍁
- (2025-11-15 14:51:05)
-
-
-
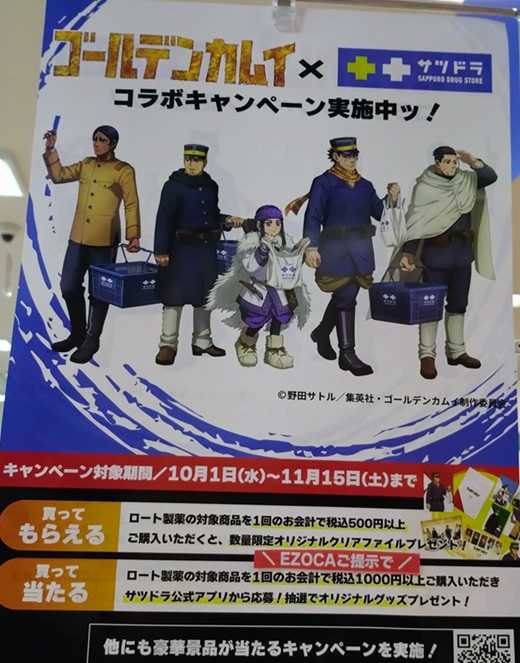
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-
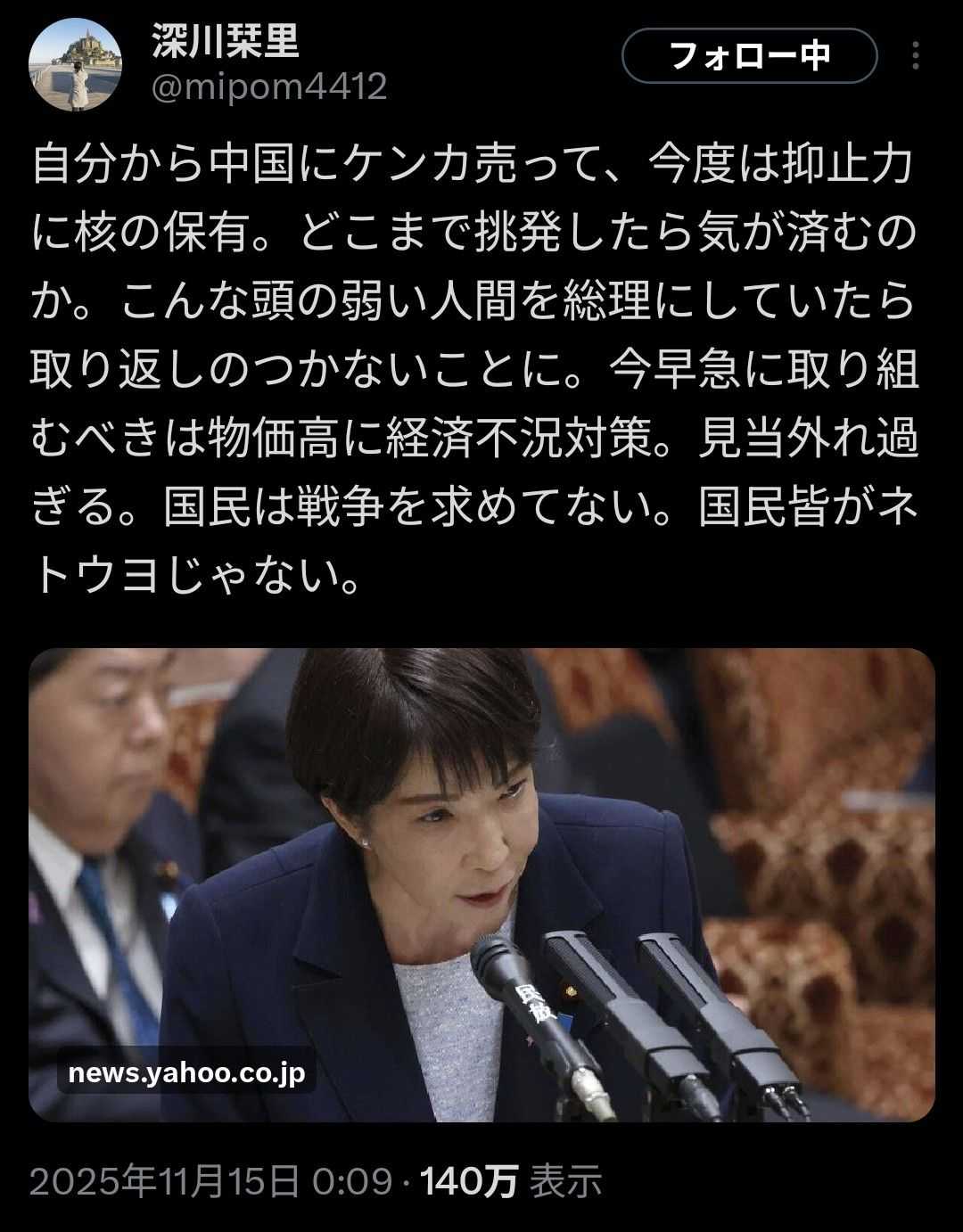
- 政治について
- 国民皆がネトウヨではない。
- (2025-11-15 19:35:21)
-






