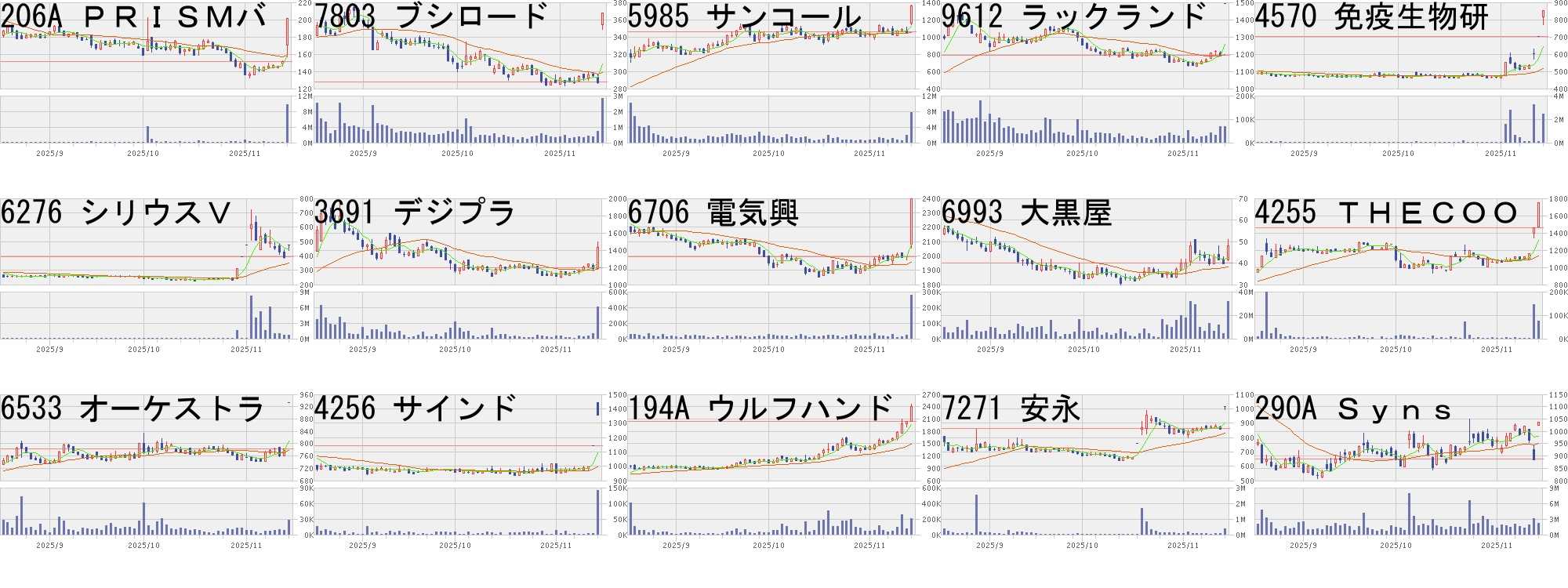2014年02月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

2月の読み聞かせ
月に1度の読み聞かせ。年度内は今日で最後です。 【1000円以上送料無料】これはのみのぴこ/谷川俊太郎/和田誠延々と続く繰り返しのリズムに子供達も大ウケ。【送料無料】ふゆめがっしょうだん [ 富成忠夫 ]こちらも長新太さんの繰り返しのリズムにはまったようです。冬芽の表情豊かな写真もしっかり見ていましたよ。
2014年02月23日
コメント(0)
-

壁抜け男
羽生結弦くん、オリンピック金メダルおめでとう!!マルセル・エイメ 長島良三・訳私が読んだのは角川文庫。表紙が四季初演時のサントラ等と同じで無駄にテンション上がる。今回はお話の感想というより舞台との違いなどを。(舞台のネタバレあります)文庫にしてわずか16ページの短編。これを2時間に膨らませた脚本がまず凄い。原作が発表されたのは1943年。第2次大戦下で空襲はすごいしナチスの占領はあるしでパリは大変な時代。でも原作にはそんなことはこれっぽっちも出てきません。なので舞台でのパンを盗むシーンや告発シーンは原作になく共産党員や八百屋兼娼婦や新聞売りもM嬢も全部脚本オリジナルです。これは脚本家がどうしても書きたかったのだろうと想像するほかありません。舞台が発表された1997年でも当時から50年以上経っているし、70年も経った現在、そんな時代もあったよねと忘れられることも多い。そういったことに危機感を持って当時の様子を織り交ぜたのかな、と。当時の共産党員はレジスタンス運動の中でナチス将校をどんどん殺害していたから国民の支持もあったし、その中での裁判シーンでの共産党員の発言は重みがあるということなんでしょうね。怪盗ガルーガルー(原作では狼男)になる前は旧式の鼻眼鏡をかけ、真っ黒な短いヤギひげを生やしている主人公のデュティユルだけど、逮捕-脱獄後はヤギひげを剃り落とし、べっこう縁の眼鏡に変え、鳥打帽をかぶり、大柄なチェックの上着にゴルフ用の半ズボンといういでたち。で、この姿がイザベルの空想をかきたてるのです。映画関係者みたいな感じで、カクテル・パーティーやハリウッドの夜を連想させるんですって。舞台を鑑賞される皆さん!あのリアルテディベアみたいになってる洋輔さんの姿はイケメン設定なのですよ!で、イザベルはその見た目だけでデュティユルと朝の3時まで愛し合うという…これが中学校の発表会で演じられる国民的舞台というのだからフランスのお国柄ってやっぱりかなりオープン。アムールでジュテームの国だわ。原作では分厚い壁の中にすっかり体を入れたところで身動きできなくなってしまいます。これはどこに行ったかわからないということなのかなぁ?でも最後に画家がデュティユルをなぐさめようとギターを弾いてくれるし。画家という職業柄、物事の本質が見えるという設定とか?最初に壁を抜けるところからして何の不思議でもないように書かれてる時点でこの程度のことを疑問に思ってはいけないのでしょう。原作を読んだ限りでは決して「人生は素敵、人生は最高!」という展開ではないけどデュティユルのことは憎めない。泥棒だし脱獄犯(国外逃亡しようともする)だし不倫男だけど。壁に挟まってしまっても何だか同情してしまう。それにしても気になるのはイザベルのその後。二晩の夢と納得できるのかな。
2014年02月14日
コメント(0)
-

狼生きろ豚は死ね
いろいろあってくさくさしていた私に結婚記念日にと贈ってくれた息子からの花。10日以上たってもがんばって咲いてくれています。ありがとね。さて、ソング&ダンス60のキャストからの挨拶では開催地初演の作品の説明がありました。通ってしまった大阪での初演は1960年の「狼生きろ豚は死ね」今の劇団四季では考えられないようなハードなタイトル。どんなものかと検索したらアマゾンでは12750円だって!でも図書館にあったので早速取り寄せて読んでみました。『狼生きろ豚は死ね・幻影の城』 石原慎太郎 昭和38年何と著者はあの石原慎太郎。本の発行は昭和38年だけど、初演は昭和35年だから石原慎太郎がまだ青年と言ってよい20代の時の作品ということになりますね。並行して『芝居を愛した作家たち 文士劇の百二十年』を読んでいるのでこの頃の文壇の様子もうかがうことができておもしろい。時々、政治家が集ってコーラスしたりするニュースがあるけど、あれの作家バージョンだと思えばいいのかな。文壇なんて縁がないからわからない。東宝宝塚劇場を2日間借り切っての興業というから作家さんが思いっきり遊んでる感じがしますね。文春文士劇の発案が菊池寛というからさもありなん。さて『狼生きろ豚は死ね』タイトルだけ読んだら現代劇かと思ってましたが、明治維新の話でした。坂元龍馬の護衛をする久の宮清二郎が龍馬自身と幕府老中の松平帯刀、商人の山井九兵衛、土佐藩士後藤象二郎らの権謀術数の中で理想と政治と権力に振り回されるお話。帯刀と九兵衛の妻との間は、別れても好きな人状態。もちろん九兵衛はお約束通り嫉妬してまたしても謀をしたり。今の四季で上演することはないだろうなぁという内容でした。ちょっと新国劇の香りがするような作品に思えました。この『狼』と『豚』という言葉から連想するのものがどうも私と一部の若い人達とは、ずれているということを発見。私の中での『豚』は、弱い者をこき使い自分達はのうのうと肥え太っていく悪い政治家とか大地主などのイメージで『狼』はそこに反発していく改革者もしくは革命者という感じなんだけど、ネットで徘徊してると『狼』はいわゆる経済的勝ち組で『豚』は情報弱者のためにいろいろなことを手に入れられない人達。勝ち組の下で働く人達って感じですかね。はー、そうかー。そうなるとまるっきり意味が違ってきますね。とりあえず石原慎太郎の作品では『豚』は権力者です。でも歴史的にはこの人達は『狼』であったりもするんだよねぇ。再読したらまた複雑なスパイラルが見えてくるような気もします。浅利慶太と石原慎太郎の接点は「若い日本の会」という組織らしい。これが安保反対のための会だったらしいというから驚き。石原慎太郎に何があって180度違う思想を持つようになったのか。
2014年02月10日
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1