2025年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

伊藤屋晩酌で珍しいものをいろいろいただいた
1月31日(金)最近は、ほぼ毎週金曜日の夜には「旬の味 伊藤屋」で晩酌というのが定番になっています。「コース」なので、内容はおまかせなのですが、メニューにはないような珍しいものが出てきたりするので、とても楽しみにしています。今日は、はじめていただくようなものがいくつも盛り込まれていて、特に興味深くたのしい晩酌となりました。by SHARP AQUOS Sense7 SH-53C初っ端から、ほかではなかなかお目にかからない「しめいわし」。しめさば、はポピュラーな居酒屋メニューですが、さばではなくいわしというところが極めてめずらしい。「しめ」具合がマイルドなのか、新鮮ないわし自体がマイルドなのか・・・しめさばに比べて生のみずみずしさが残っている印象です。続いては、「鶏の天ぷら」。こちらのお店では天ぷらメニューは種類も多くておいしい、ということは承知の上、また「とり天」自体もめずらしいものではありません。しかし!場合によっては天ぷらにすることによって鶏のエキスが逃げてしまってパサパサになることもあったりすると思いますが、この鶏の天ぷらは鶏肉のジューシーさを衣に閉じ込めてあるというような、そこらのとり天とはひと味ふた味違うおいしさです。写真では主役の鶏がうしろに隠れてしまっていますが、手前にある「かぼちゃ」と「せり根」の天ぷらも揚げたてでたいへんおいしいのです。晩酌コース、最後は「ひらきも」「あんきも」というのはよくある珍味ですが、「あんこう」ではなく「ひらめ」のキモです。あんきもと比べて小ぶり(とはいってもひらめと考えればかなり大きいのでは)、お味もあっさりめです。晩酌コースには「松」と「竹」があり、「松」はお料理五品、「竹」は三品と飲み物がセットになっています。「松」にしてすべておまかせ、終了・・・といくよりは、「竹」で三品おまかせ、あとひとつふたつ「通常メニューでは出さない今日の一品」を選んで、というスタイルが良いです。今日は「能登産天然寒ぶりの刺身」というのがあったので、そちらをいただきました。先月にもいちどいただきましたが、「能登産」がいいのか「天然」がいいのか・・・いずれにしてもふつうの養殖物のぶり刺(こちらもおいしいのですが)とは違う次元のおいしさでした。そして、親方からのミニサービス、「サヨリの炙り」「サヨリ」自体もあまりお目にかかることのない魚ですが、それを炙っている(おそらく生の魚ではなくみりん干しだったのか?)という、二重の珍しさです。やはり、通い続けて「馴染み」になると、ちょっとしたいいことがありますね。
2025.01.31
コメント(0)
-
はじめてのJR楽パック赤い風船利用を終えて
1月30日(木)昨日、今日の一泊二日京都出張ではじめて、楽天トラベルの「JR楽パック赤い風船」を利用して新幹線で行ってきました。「赤い風船」からわかるとおり、楽天トラベルのパックというわけではなく、日本旅行のパックなので、予約成立後は日本旅行で対応するという方式のようです。いままで、新幹線を使った出張では「えきねっと」でJRの切符を手配し、宿だけ楽天トラベルで、というパターンでした。パックにすればトータルとして代金が安くすむ(すみそう)なので、今回思い切って利用してみたわけです。予約の内容(新幹線の乗車時刻や宿の情報)を確認するのに、楽天とは別に日本旅行のサイトへ入る必要があって、少々面倒に感じました。切符の受け取りは、えきねっとを利用した場合と大差ないので不便は感じませんでしたが。一晩寝て朝ごはんをいただいて出るだけ、というあっさりした滞在ではありましたが、今回利用させていただいた「京都プラザホテル京都駅南」がなかなか良かったので、クチコミ投稿しようと思ったら・・・JR楽パック赤い風船で利用した場合には、クチコミ投稿できないことになっている・・・と、あとで知りました。なんということか。いちおう、今日の日記の最後にクチコミ的なコメントを少しいれておきました。
2025.01.30
コメント(1)
-

仙台へ戻る前に・・・京都の小さなお寺
1月30日(木)はじめて楽天トラベルの「JR楽パック赤い風船」を利用した今回の出張。(利用してみた感想は別記事にあります)昨日から一泊、利用したのは京都駅の南側、九条通に面した「京都プラザホテル京都駅南」でした。朝食(なかなか良い内容のバイキング形式)後準備をして出発。ホテルのすぐ東隣、やはり九条通に面して小さなお寺の門がありました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2「西山浄土宗 月輪山 長福寺」さんだそうです。その門自体も、小さいながらなかなかの風格があるのですが(といいつつ、門をメインにした写真は撮っていなかった)、その脇の、塀の向こう側から顔を出していた白い八重の花がみごとでした。この花、名前は何だろう?おそらく八重咲きのサザンカではないかと予想したのですが・・・あとでネットで調べてみたら、たぶん間違いないだろうと思います。東北、仙台ではなかなか白花、しかも八重咲きというサザンカは見かけないので、珍しがって何枚も写真を撮ってしまいました。そんな中に、たまたま写った屋根瓦の紋。最近、新寺のお寺(善導寺)で知った「宗紋」ではないか?(宗紋の話題は2024年12月8日の日記をご参照ください)切り抜いてアップで見てみます。けっこう複雑なデザインです。このお寺が「西山浄土宗」であることはわかっているので、ちょっと調べてみました。たしか、新寺で見たのも浄土宗。しかしまったく異なるデザインですね。「西山浄土宗」「宗紋」で調べると、いろいろと情報が出てきました。「光明寺」というお寺の住職さんによれば・・・西山浄土宗にはふたつの宗紋があるそうです。そのひとつが今回の紋で、「竜胆車(りんどうぐるま)」あるいは「久我竜胆(こがりんどう、「くが」と書いて「こが」と読むのですね)」。リンドウの花がぐるっと放射状に並んでいるわけですね。新寺で見た宗紋は「杏葉(ぎょうよう、杏の葉)紋」。浄土宗開祖、法然上人の実家である漆間家由来の紋です。~~~※今回お世話になった「京都プラザホテル京都駅南」についてメモ新幹線とセットのパックだったので、実際の宿泊料金がどれくらいなのかはっきりとはわかりませんが、おそらく京都駅から徒歩圏内ではかなりリーズナブルな金額なのではないかと思います。エレベーターはひとつしかなく、階段での上り下りもできないつくりで、しかも最上階(9階)の部屋。エレベーターでの移動に待たされるのではないかと心配でしたが、想像以上に「呼べばすぐ来る」エレベーターで好印象。フロントスタッフの方々も親切で好印象。お部屋はふつうのビジネスホテルという感じで標準的ですが、一通りの設備は整っています。シャワーも問題なく、トイレ洗面も十分。フリーのコーヒーサービスが夜0時まで1階に用意されているのも好印象。コーヒーのお味自体も(個人的な嗜好で申し訳ないですが)じつにおいしい。夜と朝、2回いただきました。今回はリュックひとつだけの軽装だったので困りませんでしたが、大きなキャリーバッグがあったら、ベッドの上か床で広げなければならないのでちょっと困るかもしれないと思いました。パッと広げて使える荷物置きがあると良いなと思います。朝食は朝6時半から用意されていて、なかなか充実した内容のバイキング形式でした。by SHARP AQUOS Sense7 SH-53C食事スペースは全体的に小さいものの、平日だったからか混雑することもなく、ゆったり快適に朝食をとることができました。京都駅から近いとはいえ適度に離れており、また市内観光スポットからすこし距離を置いた立地だからなのか、観光客がドッと押し寄せるような宿ではないごようす、観光以外のビジネス出張目的で利用するには絶好のお宿なのではないでしょうか。
2025.01.30
コメント(0)
-

京都へ出張/東京駅の「新橋鶏繁 どんぶり子」は2020年に閉店していたそうです
1月29日(水)今日から一泊二日(用務は今日の午後のみですが)の京都出張です。朝の新幹線で仙台を出発、東北新幹線、東海道新幹線と乗り継いで京都へ。東北新幹線はわりと席が空いていましたが、東京で乗り換えたら様相は一変。やはり外国人が多い。京都駅で新幹線を降り、在来線に乗り換え。駅構内も混雑してました。東海道本線で一駅だけ乗り、西大路駅で下車。歩いて用務先の堀場テクノサービス(堀場製作所本社内にあるグループ会社)へ。会議と講演会、そして夕方の懇親会(技術交流会)。最近取り組んでいる比較的エネルギーの高いPd(パラジウム)K吸収端での蛍光XAFSで困っていたCompton散乱の問題・・・対策法はないもんでしょうかねえ、と訊いてみたのですが「そういうもんだ」「どうしようもない」という悲しい反応。さてどうしたものか。用務は終わってもギリギリ今日中には仙台に戻れないので、京都駅の南側すこし歩いたところにある「京都プラザホテル京都駅南」に宿泊、明日仙台へ帰ります。今回、はじめて楽天トラベルの「JR楽パック」で新幹線の切符と宿泊をセットで予約しました。飛行機とセットの「ANA楽」「JAL楽」はありましたが、JRでもパックできるということを知らなかったのでちょっとびっくりです。ただし、予約は楽天からしましたが、実際には日本旅行(赤い風船)の扱いになるようで、新幹線の切符を受け取るためのQRコード取得などはそちらからアクセスするシステムでした。東京出張でもJR楽パックが利用できるのかと期待したのですが、いつも利用するような安宿はリストに上がってきません。残念。また、行き帰りの出発駅、到着駅が同じでなければならないとか、いろいろと制約はあるようです。これからは、新幹線を利用した出張でも楽天トラベルを使っていこうと思います。~~~ここからはちょっと古い話になります。かつて、東京へ出張した際によく利用していた、「東京駅キッチンストリート」の「新橋鶏繁 どんぶり子」がいつの間にかなくなっていたのですが、ちょうど10年前の2015年1月29日に千葉出張のついでに立ち寄っていました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2(2015.01.29撮影)そのころのお気に入りだった「鶏レバー入り親子丼」をいただいていたようです。写真をよく見ると、手前すこし食べちゃってますね。この日の日記には、千葉への出張のことしか書いていなかったのですが、この「どんぶり子」の話題はFacebookに写真付きで投稿していました(2月3日になってからですが)。とても気に入っていたお店だったのに、いつの間にか閉店していたので残念に思っていましたが、あらためて調べてみると、「2020年12月31日に閉店」していたようです。「新橋鶏繁(とりしげ)」というのは焼き鳥屋さんで、名前の通り新橋にあるようですが、そのお店のメニューには親子丼などはありません。丼もの専門のお店として東京駅構内に出していたのかもしれません。「どんぶり子」としては、現在もお店を出しているようで、常磐自動車道 守谷SA(下り)内にあります。「どんぶり子」ではないですが、やきとりの「鶏繁」は、新橋周辺に何店舗か、麻布十番にもお店がありますが、東京出張のついでにというわけにはなかなか・・・と思ったら、「大丸東京店」というのがあるみたいです。東京駅の脇にある「大丸」の12階。まあ、なかなか出向くことはないとは思いますが・・・※余談ですが、もうひとつ10年前の今日のトピック。午前中新幹線で仙台から東京へ向かっているとき・・・その日は天気が良く、またいつもは通路側の席に座ることが多いのがたまたまこのときは進行方向向かって右(西向き)窓側の席だったこともあり、窓からの景色を眺めていました。すると、たしか大宮前後のあたりだったと思いますが、ちょうどいい角度に富士山が見えました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2(2015.01.29撮影)新幹線の窓から富士山、といえば静岡県というイメージだったのですが、こんなところからもきれいに見ることができるとは!・・・と、当時も驚いたのですが、その「驚いたこと」自体をすっかり忘れていました。
2025.01.29
コメント(0)
-

いい具合の枯れサザンカが増えてきた
1月22日(水)仙台市青葉区、馬上蛎崎(うばがみかきざき)神社のサザンカの木は、いつも散歩の途中で立ち止まってじっくり眺める立ち寄りスポットです。とくに、花の少ないこの季節には真っ赤なサザンカの花は目を楽しませてくれます。by OLYMPUS STYLUS XZ-2今でも次々とつぼみがふくらみ、開いてきれいに咲きますが、しおれて枯れていく花もまた次々と生まれています。まだ開ききっていないこれくらいの花が、咲いている花の中ではベストのタイミングと思います。このような、きれいに咲いた花もいいですが、咲き終わったあとの枯れ花もなかなかです。枯れ花とひとくちに言ってもさまざまな段階があり、それぞれに趣があります。すっかり最終形態になった枯れ花。これももいいですが、こちらの枯れ花、花びらはすっかりおちていますが、おしべがちょうど良い具合にしおれて垂れ下がっています。まだ赤い色の残った、しおれた花びらが一枚・・・これくらいの枯れ花が個人的にはいちばんのお気に入りです。これからも次々と咲いてはしおれていくことでしょう。さまざまなタイミングの枯れ花を楽しむことができそうです。
2025.01.22
コメント(0)
-

緑水庵庭園の石灯籠が気になる
1月21日(火)いま、インフルエンザが流行っているようです。用心に越したことはないですが、いまのところ朝の出勤時のバスor地下鉄車内でだけマスクしています。いよいよ危なくなってきたら、外出時オールタイムでマスク着用モードになるかもしれません。さて、年末に五橋の鈴木耳鼻咽喉科から毎年恒例の花粉症対策はがきが届きました。今年は花粉の飛散量も多く時期も早めという予想だそうです。いつも2月に入ってから薬をもらいに行く、というパターンが続いているので、今年は早めに行っておこうと、今朝の出勤前に。これで対策は万全です。ランチのあとに、緑水庵の庭園へ。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO門の前に植えられているサザンカ。まだつぼみでした。入って正面には茶室があります・・・が、中へは入らず脇から庭園の方へ。茶室の横を通り過ぎて振り返ります。ちょっと前まで地面を覆っていた落ち葉はほとんど姿を消しています。(管理人さんがしっかり掃除されたのだと思いますが)E-M1 Mark IIIとM.ZUIKO 12-40mm F2.8のコンビで、なにかいい絵になる被写体はないかと見回します。茶室の横に、大変立派な石灯籠が立っています。庭園内にはほかにもたくさん石灯籠がありますが、庭園の広さに比べるととても大きいです。これは、かつてここが「良覺院」という大寺院だった名残だそうです。となりの良覺院丁公園もかつての良覺院の敷地内。いまは1月、きれいに咲いているような花もなく、寂しい雰囲気ではありますが、それがかえって大きな石灯籠への興味を引くことになります。三日月状にくりぬいてあるその下のポコポコは何を表しているのだろう?下に波が彫ってあるので、島か?いくら考えてもわかるわけがない。裏側はどうなっているだろうと、うしろへ回ります。これは鹿ですね。うーん。これはどういう意味合いがあるのでしょう。二匹の鹿がモチーフとなっているレリーフはなかなかの趣ではあるのですが。ナゾのまま今日の寄り道は終了です。
2025.01.21
コメント(0)
-

2012年の日記ブログ投稿にコメントがきた
1月16日(木)この日記ブログに、2012年10月27日付で投稿した「一昔前の評定河原橋」という記事があります。なんと12年以上前の古い記事。そのコメント欄に、先週(1月7日)ひとつコメントが入っていたことを今日になってたまたま知りました。まさか自分の個人的な日記ブログの記事に外からコメントがくるなんて思ってもいなかったものですから、気づくのもずいぶん遅くなりました。さてそのコメント、書き込んでいただいた方はというと、宮城の橋に興味がおありの方のようで、現在の橋になる前の評定河原橋について知りたいことがあると、いくつか質問をいただいています。しかし、今の橋に架け替えられる前の評定河原橋については、たった一枚の写真と当時の淡い淡い記憶が残るのみ。ここであらためてその一枚の写真を披露いたします。なんとかこの写真から引き出せる情報はないかと、ネットで調べてみたり写真を穴が開くかというほど見回してみたりしました。・・・でも、やはり古い写真一枚だけでは限界があります。調べたりこの写真について考えたことをまとめて、ブログ「仙台市青葉区片平界隈情報」に記事をとうこうしましたので、興味のある方はそちらをご参照ください。もしかしたら、現場へ出向いて橋の周辺に、先代の評定河原橋のことがわかる痕跡が何か残っているかもしれない・・・ということで、今日は昼休みに、もう一度あらためて現場へ出向きました。それは、現在の橋と以前の橋がまったく同じ位置に架けられているわけではなく、わずかに下流側にずらした場所にあるからです。まずは片平丁通り、片平丁小学校の向かい側から広瀬川のたもとに降りて行く階段へ。by OLYMPUS STYLUS XZ-2「片平丁小学校前」バス停の横から階段を降ります。けっこうな高低差があります。「崖」といっても良いほどです。上から見下ろすと、広瀬川の横の道までは「ストーン!」と降りて行く階段が手前にあり、橋のたもとに通じる道は、昔から変わっていないようです。古いフィルムカメラで撮った写真、撮影した立ち位置がどこだったのか、という疑問がずっとあたまにあります。とはいっても、撮影機材が何だったのか、もうすっかり忘れ去っていますので、使用したレンズがどれなのかすらわかりません。でも、今日あらためて撮ったこの写真を見ると、この崖の上から撮影した可能性も考えられます。しかし、いちばん手前に写っている藪がけっこう近いので、階段の途中、または下まで降りてから撮った可能性も考えられます。階段を下まで降りていくことにしましょう。降り口には「→ 評定河原橋 瑞鳳殿(近道)」と案内されています。片平丁通りをもう少し下って行って、霊屋橋を渡って行くルートもあるのですが、歩けばこちらのほうが近道、ということです。階段を降り始めると、右には崖の垂直な壁、左には木が枝を広げて視界を遮ります。階段を少し降りた程度では、広瀬川や評定河原橋を見渡すことはできません。ほぼ階段を降りきったところで振り返って仰ぎ見ると、この片平の崖が相当高いことを実感します。堤防のところまで出て評定河原橋のほうを見てみると・・・これでは視点が低すぎますね。ということは、あの写真を撮ったのは階段の中間地点あたりの可能性が高くなります。左手に広瀬川、右側にはテニスコートと評定河原球場を見ながら橋に向かって歩いて行きます。この道、広瀬川の堤防(護岸?)は、評定河原橋が架け替えられる前からのものです。そして、橋に近づいたところで白い手すりに囲まれ上り坂になっている数十メートルの区間がありますが、これは新しい橋ができたとき、同時につくられたものと思われます。橋の高さまで数メートルの高低差があります。ここを登り切って、ちょっと見回してみます。評定河原橋は、片側(片平側)だけ、りっぱな歩道があります。橋の向こうには経ヶ峯の森。反対側を眺めると、これも新たに盛り上げてつくられたように見える坂道。ちょっとこの坂を降りてみます。脇へ入って行く道があります。奥にある花壇自動車学校へ入って行く道、路上教習の車が出入りしますが、評定河原橋を渡ってきてここを入って行くのはたいへんでしょう。ちょっと入って坂の下のほうを見てみます。なんだか不自然、こちらの道のほうがメインで、まっすぐ降りていくようになっていたのをむりやり断ち切って、右側につくった新しい道につなげた、という感じです。実際、縁石も古く、こちらの道は前からあったもので、新しい橋がかかったときそれにあわせて新しくつくった坂道はかつては存在しなかったものです。橋のほうを見てみると、新しい橋はかなり高い位置に架けられていることがわかります。かつての古い道路はほぼ水平で、広瀬川に突き当たったところで右に折れ、川に沿って花壇の奥のほうへ通じています。折れ曲がるカーブのあたりまで先へ進んでみます。左には現在の評定河原橋。やはりちょっと高いところに架けられています。向こう岸を見ると、橋の右側に不自然な出っ張りがあることがわかります。それと対になるような感じで、こちら側にも出っ張りがあります。古い橋はあちら側の出っ張りとこちら側のこの出っ張りのあいだにかかっていたのでしょうか?それにしては、手前側の古い道路のレベルと数十センチのギャップがあります。コンクリートも新しいものではないので、古くからこうしてここにあったものと思われます。ということは、古い橋のこちら側はこの出っ張りの右側だった可能性が高いです。古い写真で、このあたりのようすを確認すると、片平の崖を降りて広瀬川沿いに進んだあと、橋へ出るために10段前後の階段が付いていて、そこを上ったところに平らなスペースがあることがわかります。これがこの出っ張りだったのではないでしょうか。現在の橋の上に行って見下ろしてみます。さて、どうでしょうか。手前の四角い出っ張りは、階段を上がって出たテラス状のスペース部分の土台?そして古い橋はその先にあった?すこし橋を渡って別の角度から見てみます。四角い出っ張りと、左手の古い護岸、そのあいだに白っぽい護岸があります。このあたりがクサイですね。下を見ると、橋脚の土台の石ともとれる四角い石があります。手前側の中州にも四角い石。このラインで古い橋が渡っていたのでしょう。霊屋下側まで橋を渡りきりました。ここが古い橋の名残なのか?もしかしたら、現在の評定河原橋はまだ完成していなくて、反対側の歩道を設けるために幅を広げる予定なのかもしれません。そうすると、花壇側の出っ張りも、この新しい橋を作ったときに「とりあえず車道と片側の歩道だけつくって、あとでもう片方の歩道を付けられるように準備だけしておこう」と、あとからつくられた出っ張りなのかもしれません。しかし、霊屋下方面からやってくる道路の不自然な折れ曲がりかた、キワまで迫った住宅を見ると、やはりこの出っ張り部分が古い橋のかかっていた場所と考えるのが妥当のような気がします。まだまだ考察、検証が必要ですね。
2025.01.16
コメント(0)
-

ちょうど10年前の今日のFacebook投稿
1月7日(火)Facebookでは、過去の自分の投稿が「○○年前の思い出」として表示されたりします。ちょうど10年前、2015年1月7日に投稿した記事が出てきました。内容はその2日前の1月5日、仕事始めの月曜日の話題について。「2015年はじめてのランチ」で食べた「ぶり刺身定食」がとてもおいしかった、と言っていますがいったいどこでいただいたのか・・・それが気になってしまいました。 そこで、2015年1月5日に撮影した写真のもとをたどってみました。このFacebook記事に載せた写真の画像ファイルを収めたフォルダ名は「20150105-2_Lunch-HIKARI」。ああ、そうだ!これは仙台市青葉区北目町にある「食事 光」でした。このお店でお刺身定食をいただくことはめったにないのですが、年明け早々のランチ、お正月気分だったのか?ちなみにこのお店、「ひかり」ではなく「ひかる」なのですが、学生時代からずっと通っていて店の名前を間違って呼んでいたことに気づかずにいました。数年前に「ひかる」だということを知っても、やはりいまだに「ひかり」と呼んでいます。かつては週に何度も、ランチや夕食で利用させていただいていました。今はそれほど頻繁に行くことがなくなり、たまに夜出向く程度になっています。このころ(2015年当時)は食事の記録に当時の高級コンデジ、OLYMPUS STYLUS XZ-2を使っていました。このカメラは2012年暮れの入手以来、今でも現役で活躍していますが、食事記録用としてはスマホのカメラを使うようになっています。このときの撮影データを見ると、11.3mm(35mmライカ判で53mm相当)という中途半端な焦点距離、F4で、当時マイルールの最高感度ISO1600で撮影しており、シャッター速度は1/60秒、少し遅め。このカメラのズームは6.0mm(28mm相当)から24mm(112mm相当)までをカバーしていますが、ちょうど真ん中あたりの標準レンズに相当する画角ということになります。10年前に撮影したぶり刺身写真の画像を、画像処理ソフトのDxO PureRAW 3.17でノイズ除去とレンズ光学系を考慮した収差補正を施してみました。最近(2024年12月20日)にも、土樋の「旬の味 伊藤屋」で能登産天然寒ぶりのお刺身をいただいていました。この季節、ぶりのお刺身はおいしいですね。
2025.01.07
コメント(0)
-

仙台での初詣、柳町と田町の大日堂へ
1月4日(土)今日は、仙台での初詣に出かけました。私の干支、申年の守り本尊は大日如来。仙台市内には3つの大日堂があります。そのうちのふたつ、柳町の教楽院大日堂、そして田町の文殊院大日堂へ。by SHARP AQUOS Sense7 SH-53Cまずは柳町教楽院大日堂へ。正月三が日が終わって、ほとんどお参りする人もいないですね。お守り お札 授与所・・・すでに閉まっています。お札を受けることはできないのか・・・柳町通りをはさんだ斜め向かいにある「タゼン」で取り扱っているとのこと。そちらへ向かいます。お店は開いていて、中でお守りやお札を受けることができるようになっていました。お札を受けて、田町の大日堂へ向かいます。田町通りは北目町から南へ降りて、東へ折れ荒町のほうへ抜けて行きますが、そのまままっすぐ南へ行くと「猿曳丁通り」に入り、まもなく文殊院大日堂に到着。入って行くと、手前は駐車場になっており、その奥に小さなお堂があります。左右に「申」「未」の絵馬がおいてあります。お参りを済ませて、仙台市内の二つの大日堂参拝を終了。あとひとつ、大崎八幡宮にある大日如来堂にも詣でればコンプリート。はたして今年は達成できるでしょうか。
2025.01.04
コメント(0)
-

天橋立観光から無事帰仙
1月3日(金)昨日、天橋立(ビューランド、文殊堂)を観光して一泊。宿は「ザ グランリゾート 天の橋立」。窓からは、天の橋立の向こうの山からのぼる日の出を拝みました。by OLYMPUS STYLUS XZ-XZ-2こちらは仙台と比べて日の出の時刻が遅いですね。宿での朝食は7時開始。昨日の夕食に続き、一番乗りでした。内容も、多すぎずちょうど良い量でおいしくいただくことができました。by SHARP AQUOS Sense7, SH-53C朝食も、お正月ムード満点。すまし仕立ての雑煮までついていて、正月気分を十分に味わえました。荷物をまとめ、9時過ぎにチェックアウト。出発してまもなく、ガソリンスタンドが開いていて、無事に給油することもできて安心しました。高速道をひたすら走り、途中雨や雪に見舞われ・・・こんなことになってしまいました。吸気口は確保されているので問題ないと思いますが、前面がすっかり雪で覆われてしまったときは大丈夫なのでしょうか?全体としては、雨や雪もそれほど大きな影響はなく、渋滞にはまることもなく仙台へ戻ってくることができました。西友でちょっと買い物をして帰宅したのは22時ちょっと前。ほぼ12時間のドライブでした。なんとか今日中に到着できてよかったです。
2025.01.03
コメント(0)
-

まっすぐ仙台へ帰らず天橋立へ寄り道
1月2日(木)いつもの正月帰省であればまっすぐに仙台へ戻るのですが、今年は途中で一泊寄り道して帰ることを計画。思い立ったのが暮れも押し迫った頃だったので、選択肢は限られていましたが、便所が共同ではないという条件で、価格的にはほぼ一択だったホテルを予約していました。予想はしていましたが、大阪からの出発は予定より大幅に遅れて9時前。初めての京都縦貫自動車道を走って天橋立へ向かいます。一日500円という(おそらく一般家庭の庭先の)2台分だけある駐車場に車を置いて、ケーブルカーで山の上の「天橋立ビューランド」へ。by SHARP AQUOS Sense7, SH-53C無事に股覗きもして、レストハウスでカレーライス、ハヤシライスの昼食。「三人寄れば文殊の知恵」でおなじみ、文殊堂へ行ってお参り。天気が悪くなってきたので早々に車に乗り込み、今晩一泊お世話になる宿、天橋立の反対側の岸辺にある「ザ グランリゾート 天の橋立」へ。途中で給油できればよかったのですが、どこも営業していませんでした。明日の出発時に、なんとか給油できればよいですが。さて宿に到着、チェックインして部屋へ。畳敷きの和室ですがツインのベッドが置かれた和洋折衷スタイル。窓からは天橋立が見えます・・・とはいってもすでにシルエットになっていましたが。夕食はちょうど良いボリュームでかなり凝ったお正月仕様のチョッピリ豪華な内容。出されるお料理の品数は多いですが、どれもちょうどよいボリュームで、最後までおいしくいただくことができました。大変満足して部屋に戻り、落ち着いてから大浴場へ。それほど広くはないですが、天然温泉ということでじっくりゆっくりと湯に浸かって・・・と思ったらけっこう温度が高めだったのでほどほどに。奥さんは「肌がつるつるになった」と喜んでいました。さて、明日は仙台までの長旅です。天気が心配ですが、大雪の予報は明日の夜遅くからということなので、なんとか大丈夫そうです。
2025.01.02
コメント(0)
-

実家で迎えた正月、午前中は墓参り、午後には蹉跎(さだ)神社へ初詣
1月1日(水)今年も実家で迎えた正月。冬にしては穏やかな天気。車で我が家のお墓がある霊園へ。仙台から持っていった仏花、家にあった花を合わせて豪華に供えます。ろうそく、線香に火をつけてから母へ電話。かつてのように、現地まで出向くのが難しくなった母にはLINEのテレビ電話で中継しながら般若心経を読んでもらおうと思ったのですが、上手く繋がらず・・・しかたなく音声のみで中継読経ということになりました。なんとか墓参りも終わり、一旦家に戻ってくつろいだあと、午後3時前に近くにある蹉跎(さだ)神社への初詣へ。蹉跎神社とは・・・2年前の元旦に投稿した日記にも書きましたが、意外と?由緒のある神社です。※枚方市の観光雑誌「ひらいろ」で2020年に紹介された記事※Wikipediaの記事実家から歩いて行くと、いちばんの近道をたどれば神社の裏参道へ出ます。いったんうら参道から境内に入ってようすを見ます。表参道に通じる石段の下のほうからお参りの行列ができていたので、その列の横を降りていき、まずは列の最後尾を通り越し、いちばん下まで行って京阪電車の線路前まで出てから正式に?「蹉跎参道」からお参りすることにします。まず、参道入口には「蹉跎神社」と書いた石柱?があります。by SHARP AQUOS Sense7, SH-53C「蹉跎神社」の上に書いてあるのは「何社」なのでしょう。「御社」か?蹉跎参道は緩やかな上り坂。参道の先に石造りの鳥居が見えます。進んで行くとけっこう立派です。この鳥居を潜ってさらに進むと、それまでも狭かった道幅がさらに狭まります。それでも車が通るのだから・・・数十メートル歩いたところで、石段の下へ出ます。下の鳥居よりは一回り小さい石の鳥居、山門のような二階建ての「絵馬堂」、そして石段が続きます。じわりじわりと行列は進み、3,40分ほど進んでようやく参拝。ご朱印と母への健康お守りをいただいて帰りました。あらためて参拝の行列を眺めてみます。立派な石灯籠の並ぶ石畳を本殿へ進んで行きます。すべてが終了し、また裏参道から外へ出ます。出てから裏参道を振り返ります。かつてはけもの道のようだった裏参道は、車も上がっていけるほどの広い幅の坂道に。そして神社の山を少し削って、京阪電車に沿って走る府道21号線(八尾枚方線)に通じる新しい道路ができていました。この道路、Googleマップを見てみると「中振交野線」となっていますが、どこをどう通って交野へ通じるのか、ちょっと想像できません。しかし、蹉跎神社の蹉跎山をこんなに削ってしまって罰が当たらないか心配になります。枚方市のHPに、詳しく載っていました。枚方市道路河川整備課、中振交野線整備事業母親が「この道が公孫樹通りにつながる」と言っていたのを「そんなはずない」と否定したのですが、はなしは本当でした。完成はずいぶん先のことになりそうですが。
2025.01.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-
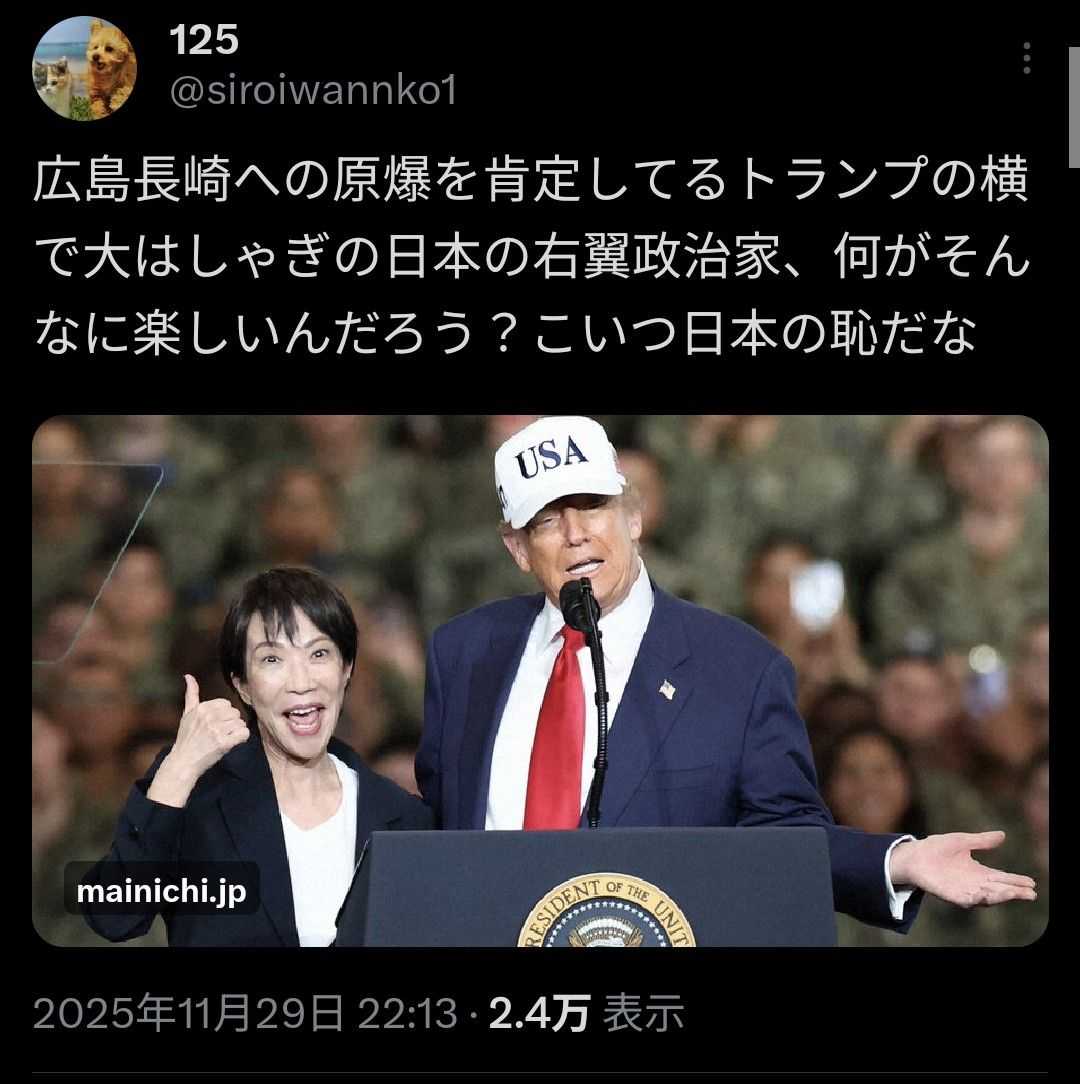
- 政治について
- 同感ですね。高市は日本の恥。支持し…
- (2025-11-30 13:56:17)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 今月のNISA利用(2025.11月)
- (2025-11-30 09:50:04)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 離婚はいけないことなのか?
- (2025-11-30 08:43:17)
-







