2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年04月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-

はちみつ蔵
車山高原にあるはちみつ蔵というお店に行ってきた。ここでは、ちょっとした展示物を見て蜂蜜について学んだり、様々な はちみつをティスティング(有料:100円)した上で選んで買うこともできる。はちみつ蔵の入口は、懐かしいフレンチブルーミーティングの会場近く、和風のお宿の裏手にあった。玄関の引戸を開け、誰もいない展示室に上がると、ピカピカに手入れされた木の床が心地良い。足元のおぼつかない我が家の3歳児は 床の上でつるつる滑り、転倒→復活を繰り返しながらケラケラ笑っていた。展示室からティスティング・販売の部屋に入ると、奥から作務衣を着たおじいちゃんが現れた。仙人のような白いお髭のおじいちゃんに頼んで、蜂蜜ティスティングにトライしてみた。おじいちゃんによると、一般的な蜂蜜は一ヶ所に置かれた巣箱から時期を選ばずに採取されるため、複数の花の蜜がブレンドされた形になっているらしい。アメリカやカナダでは、そのような方法が一般的だが、花前線を追って巣箱を移したり、蜜を回収する時期を調整するなどすれば、特定の花の純度が70%となった蜂蜜を作ることができる。この場合、花の名前を蜂蜜に表示することができる。はちみつ蔵では、花の名前を呈した蜂蜜がたくさん用意されていて、これを試すことができる仕組みだ。たくさんの蜂蜜を舌で比べるのは、まったく初めてのこと。どれもいい味わいなので、夢中になってしまう。甘いもの好きのゆうちゃんも「ちょーだい!ちょーだい!」と何度もせがみ、珍しい蜂蜜をいくつも味わっていた。「アカシア」「れんげ」あたりの蜂蜜は、小さい頃から 慣れ親しんだオーソドックスな味に近く、身近に売られているブレンド蜜は、これらを多く含んでいるもののようだ。逆に「そば」や「菩提樹」などはかなりクセのある味で、蜜の甘さよりも クセの方が目立つ。せっかくなので、あまり流通量が多くない蜜を選ぼうと「さくら」「りんご」「かき」などを繰り返し味わってみた。子供の頃から桜の花の蜜を吸っていた私は「さくら」の蜂蜜が一番気に入ったが、残念ながら売り切れだったので、フルーティな甘さの「りんご」を購入した。---ゆうちゃんと一緒に行く信州は、今回で8回目。一人で出かけた回数も含めると、この3年で11回ということになる。いつも同じ宿に泊まっているので、近隣の有名スポットは、ほぼ回りつくした感がある。そうなってみると、ちょっと遠出する余裕ができたり、近隣でも これまで気付かなかった おもしろいスポットに出会うチャンスを得たり、ますます楽しみ方が広がってきた気がする。
Apr 30, 2008
コメント(6)
-
鉄道博物館(埼玉・大宮)
ゆうちゃんと一緒に埼玉の鉄道博物館に行ってみた。平日を狙ったが、人気スポットのようで、朝一番から軽い入場制限。20分ほど並んでエントランスに入るころには、ゆうちゃんは退屈ぎみだった。三歳児の時間感覚は早い。この二年で、碓氷峠鉄道文化村(群馬)、梅小路蒸気機関車館(京都)、交通科学博物館(大阪)、長浜鉄道スクエア(滋賀)とあちこち行ってみたが、展示物の歴史的価値は埼玉がダントツ。しかし運転席に入れる車両は無く、車内すら外から見るだけものが多い。運転シミュレーター、体験ミニ運転列車なども超満員で、夫婦で交代して延べ二時間並んだ。鉄道博物館は、確かに素晴らしいのだが、ガラ空きで自由に見て遊べる大阪・弁天町の交通科学博物館や運転席入り放題の碓氷峠鉄道文化村の方が、ちびっこや親にはやさしいかも。どこへ連れて行っても楽しく過ごせるゆうちゃんは、展望デッキから見た憧れの東北新幹線・秋田新幹線・山形新幹線のホンモノに大興奮したり、まる一日を自分なりにエンジョイし、良い思い出になったようだ。長野を拠点とした往復400kmで、パパママは疲れてしまったが...
Apr 29, 2008
コメント(4)
-
ワインの丘
以前にTwinkleTwinkleさんの日記で拝見して、一度行ってみたいと思っていた勝沼ぶどうの丘へ行った。百何十種類かのワインを試飲し放題(有料1100円)なので、好みにぴったりあったハズレのないワインを購入できる。いつも嗜んでいるのは数種類だけだが、普段から飲みつけているせいか、何十種類と飲んだ中で、それなりに熟成や風味、ブドウ種の違いが分かるようになった。しかも簡単には酔わないので、じっくり味わえる。丘の下にはのんびりしたぶどう畑がひろがり、ぶどうの実がなる頃には、もっと素敵な風景になっていることだろう。ワイン好きにはほんとに良い場所で、ぶどうの丘というよりワインの丘と呼びたい。
Apr 26, 2008
コメント(2)
-
オープンカーと 革シート
これまで乗ってきたオープンカーのほとんどが、革シートを装備したクルマだった。革シートは、ちょっとしたことで傷が付くし、水蒸気を逃がさないので、蒸し暑いこともある。また、同型車のファブリック仕様と比べると、座り心地が ちょっと落ちることが少なくない。私は、革シートの見た目はあまり好きではないし、普通のクルマなら、迷わずファブリックを選ぶ。それでもオープンカーで 革シートを選ぶのは、オープン走行を前提とした扱い易さがあるから。特に、オープン走行時にクルマに降り積もる埃が、ひと拭きするだけでキレイになるのは とてもラクだ。207CCでは、ファブリックのカジュアルさに惹かれたが、オープン後のメンテ性を重視して、革装備のプレミアムを選んだ。オープンカーを楽しむためには、開閉の気軽さのほか、走った後のメンテナンスの手軽さも、大切な要素である。---オープンカー歴も、数えてみれば かれこれ10年になる。いつの間にか、バイクに乗っていた期間(9年)を超えている。ある休日、長時間のオープン走行から帰ってきて、シートを濡れタオルで拭きながら、そんなことを思った。
Apr 24, 2008
コメント(14)
-
欧州車への逆風
為替相場は、対ドルでは 大きく円高に振れているが、対ユーロでは、一時に比べると 円安傾向のままである。欧州車は、もともと 原価が日本車に比べて安くはない上に、ユーロ高が続いているせいで、売りにくくなってきてはいないか。特に、利幅が少ない小型車・非高級車を中心とするブランド、例えば、プジョーやルノーなどは、苦しいのではないだろうか。小型車の輸入を止めて、高級側にシフトしていこうとしても、はたして、これまでのユーザー層が付いて来てくれるか...仮に、新しいゾーンで ユーザーを獲得できたとしても、彼らを満足させられる品質を提供し続けられるかどうか...そして、忘れてはならないのは 環境対応。フランス車も、使用素材の有害物質対応は満たしているだろうが、ドイツ車・日本車に比べ、燃費・排出ガス面でのビハインドはある。これから数年、何をウリにして セールスを展開するのか、これらのブランドは、目先の施策だけでは 苦しいのではないか。
Apr 23, 2008
コメント(6)
-

こんな風に見える(見せられる)のか...
All Aboutに、春を探して - 207CC という特集記事が掲載されていた。菜の花畑をバックにした佇まいや、老舗旅館の玄関でのショットが、「こんな写真撮りたいなぁ」と思ってしまうくらい いい感じ。実は、ここに登場している207CCは、ウチと同仕様・同色のクルマ。こんな風に見える(見せられる)のかと、あらためて感じた記事だった。
Apr 21, 2008
コメント(4)
-
新車状態復活
クルマで速く走れたり 気持ちよく走れるということの前提に、そのクルマの絶対的な動力性能に加えて、体感的なフィーリングが良いということが挙げられる。例えば、エンジンを回した時に ざらついた感じがするようなクルマでは、アクセルを踏み込もうという気持ちを得にくい。あるいは、振動によってギシギシと不快な異音がするクルマでは、スピードを出そうとは思えない。我が家のメガーヌツーリングワゴンは、1万kmを超えたあたりから、アクセルを踏み込んだ時にざらついた回り方をするようになってきた。ちょうど、3000回転前後くらい、高速道路では 常用とも言える領域だ。心地よくないフィーリングで、古いクルマを運転しているような錯覚すらあった。メカニックの方に相談して、アクセルペダルの振動があるので、まずエンジンマウントを交換してみることに。その結果、確かに振動は減ったが、ボディが振動するとコツコツと何かに当たるような異音が聞こえるようになった。また、エンジンのざらつきは、停止時の空吹かしでも見分けられるようになった。そこで さらに調べてもらった結果、前者の異音については、エアコン配管のボディへの接触が見つかった。また後者のざらつきについては、触媒の遮熱か何かのカバーが スタビライザーに当たっていたことが分かった。ボディが振動する度に配管が車体にぶつかり、エンジン回転をあげると、カバーがスタビライザーに振動を伝えて、ざらついた音を起てていた訳である。3つの対策を行った結果、メガーヌTWのフィーリングは 新車状態に戻った。帰り道、これほど気持ちよく走れたのは 数ヶ月ぶりのことだと思った。実際 巡行スピードも20kmくらいアップしていた。クルマのフィーリングとは 主観的なものかもしれないが、これを制するか否かで クルマの価値を変えられる。
Apr 20, 2008
コメント(4)
-

歴代クラウン
ドラマを見ていたら、1970年代のシーンに、このクルマがでてきた。子供のころ 父が乗っていたクルマ、1971年に登場した四代目クラウン。社長車か専属ハイヤー落ちのLPガス車で、カラーはシルバーだった。この先代の1967年・三代目クラウンにも乗っていたと思うが、幼稚園より前のことで 私自身の記憶がない。8トラックのカセットが いい音で鳴っていたことと、前席からのカーエアコンの風の涼しさを まず思い出す。90年代後半まで、私の家にはエアコンが無かった。今、このクルマの室内写真を見ても ピンとはこない。私自身が、まだ運転そのものに興味がない年齢だったのだろう。---その後、中学に上がる前後くらいに、このクルマになった。1979年・六代目クラウン。教習所で知りあった農協の子が、配達の途中でウチに寄ってくれた時に、ちょっと古くなったこのクルマを見て、「アメ車か?」と驚いていた。そのくらい、ダークブラウンのボディには迫力があった。仮免許練習中の札を貼り付けて、父と一緒に練習してみたが、ゴツ過ぎるボディの割には、ステアリングは軽かった。---学部を上がり、クルマで通学していた頃の父のクルマはこれ。1987年登場の八代目クラウン。ダークブルーのボディは、友人の研究室の教授のクルマと同色で、スーパーチャージャー・ロイヤルサルーンのエンブレムまで同じだった。普段は母のお下がりの車に乗っていた私だったが、ごくたまに父のクルマを借りて通学すると、とても紛らわしかった。ホントは、父のクルマは エンブレムを取り付けただけのナンチャッテ仕様。LPガス車で スーパーチャージャーが機能するのか、私は知らない。その後、バイト代と奨学金をためて自分でクルマを買った頃から、父のクルマを借りることは無くなった。---どのクルマも似たような履歴で我が家に落ちついたLPガス車。「いつかは クラウン」などと言われていたが、ハイヤー落ちのクルマは、リーズナブルだったのかもしれない。それでも、維持の手間があったのか、フツーの人は 手を出さなかった。自家用車をLPガス車で選ぶ人を、父以外に 見たことがない。クラウンのトランクは広いが、LPガスの高圧タンクが居座ると狭い。家が広くなった後も、父は 洗車用具やらトランクに積んだままで、トランクはいつも満杯で ちょっと所帯じみていた。クルマに乗るようになってから、17~8年。自分名義のクルマを持つようになってから、14年。今、私のクルマのトランクに 常置されているものは無い。ある中古屋さんに クルマの下取り査定をしてもらった時、「クルマのトランクを見れば、すべて分かります。大切にしてますね。」と言われたことがあるが、真実は 父のマネをしたくなかっただけである。---ちなみに、その後の父のクルマ選びは、LPガス仕様のセドリックから ガソリン仕様のセドリックへ。LPガスを諦めたことで クルマ選びの制約がなくなったせいか、現在は 先代のフェアレディZに乗っている。 ※今回 参考にさせて頂いた 歴代クラウンの特集
Apr 20, 2008
コメント(2)
-
カンベンして欲しい 楽天のスパム広告
うちの日記で 個別の日の日記を選択すると、広告が出るようになった。自分で設定したつもりはないが、消すことができない。楽天ブログの仕様がそのようになったのだろう。無料のブログなので、文句を言う筋合いはないのだろうが、この広告の内容が気に入らない。「包茎手術」「美容整形」「ローン」「素行調査」など、ほとんどスパム広告に近いと言える。せめて、「自動車」「子育て」「仕事」に関わる内容にならないものか...
Apr 18, 2008
コメント(6)
-
かたちで おぼえる(その3)
図書館で、ゆうちゃんと電車の本を見ていたら、なんだか、読める字が増えていることに気付いた。今昔の特急のヘッドマークの写真を見ながら、「あ、とき」「こだま!」「あさかぜ」などと言う。また、「ふつう」「しんかいそく」「うめだ」のほかに、「かいそう ってかいてゆ。しゃこにはいる?」とも。最近、京都市内を走ると、市バスとすれ違うたびに、「どこゆき、ってかいてゆ?」と質問される。そこで「京都駅」「四条大宮」などと教えてあげた中で、「回送って書いてあるから 車庫に行くよ。」と答えた記憶が。たった一回か二回のことで、しっかり憶えているようだ。恐るべし、3歳0ヶ月。。。
Apr 18, 2008
コメント(4)
-
3歳児との休日
このところ、意識して、ゆうちゃんと出かける機会を持つようにしている。図書館や公園、ショッピングセンターに行くことが多いが、先日は 二人だけでランチに出かけた。---そのイタリアンレストランには、これまでも何度か訪れている。ビュッフェスタイルなので、ゆうちゃんが食べられるものを選べるのがうれしい。まずは、ゆうちゃんが好きそうなものを二人で取りに行き、子供用のプレートに入れて持ち帰る。先にテーブルに座らせて、前掛けをして幼児用のスプーンで食べ始めてもらう。当然、大好きなジュースも用意済みだ。ゆうちゃんが落ち着いたところで、「パパのご飯取って来るね?」と一言 断ってから、自分の料理を取りに行く。黙って席を外すと不安になって迷子になったりしそうな気がして、声掛けは大切にしている。私が席に座って料理を味わい始めると、私のお皿を見たゆうちゃんが「ちょうだい!」とリクエストをかけてくるので、好みの料理を小分けにして与えると、自分の食べる分がなくなって、あらためて取り行くことになる。再び席に戻ると、ゆうちゃんが「じゅーす こぼれた」と不安そうに言う。見ると、テーブルの上にオレンジの水溜りができていて、ズボンも湿っている。本人が「だいじょうぶ?」と気にしているので、「大丈夫だよ。後で 着替えようね。」と答えて、とりあえず拭き取っておく。ジュースだけでなく、ピザを手で食べたり、こぼれたパスタを指でつまんだりするので、そのままにさせておいて、時々 汚れをふき取る。ある程度食べたところで「ごちそうさまする」と言い始めた。私はまだ終わっていなかったが、デザートに入ることにする。「けーきもいらない」と言っていたのに、一緒にデザートを見に行くと「ぜりーたべる!」と、俄然やる気を出し始めた。ゼリーの中のブルーベリーは食べず、一々 取り出しては「たべてー」と渡してくる。結局、ゼリーの小鉢を 4つ平らげてしまった。この頃には、食事に飽きてしまったようで、店員さんのマネをして「いらっしゃいませー」「ありがとうございましたー」と大声で叫んでいた。平日の昼下がり、ママ友+子供数人か、女性二人連れと言った客層が厚い。ただでさえ マイナーな父子二人なので、ゆうちゃんの店員ぶりは、かわいい反面 ちょっと恥ずかしい。遊びながら ゼリーを食べ終わると、トレーナーをめくって、お腹の上からロンパスをさすっている。「どうしたの?」と聞くと、「おなかいたいの」と答える。これはまずいと思って、あわてて会計を済ませて外のベンチで休ませたが、大したことがなかったようで、すぐにいたずらを始めた。たぶん食べすぎで便意を感じたが、結局そこまで至らなかったのだろう。お手洗いのオムツスペースに連れて行き、濡れたズボンを予備の服に着替えさせた。---その後、併設のゲームコーナーで、電車の紙模型を取るクレーンゲームを一緒にやって、600円で6つの電車をゲットした。ゆうちゃんは、このクレーンゲームが大好きだ。こういうものは 持って歩きたがるので、持ちやすいように袋に入れて渡した。途中、ディーラーなどにも寄ったが、結局 家に帰るまで 袋を 手放すことがなかった。クルマの中では大事そうに握ったまま、すやすや眠っていた。家に帰る頃には起きだして、どこからか洗濯ばさみを持ち出し、ゲットした電車を挟んで持ち上げて、クレーンゲームごっこをしていた。
Apr 16, 2008
コメント(4)
-
307SWとメガーヌTW(その3)
以前、ここや ここで ちょこっと書いたことがあったが、今回は、オートマチックトランスミッション(以下AT)の比較、そして、最後に総合的に見た印象など...---307SWとメガーヌTWに搭載されているAL4/DPOは、ベースはプジョー/ルノーの共同開発で、同じ設計のATだ。ソフトウェアまで含めて、どこまでが同仕様なのか、専門家ではない私には、いまいち良く分からない。ただ、同年代に開発された206/ルーテシア2の印象を比較すると、取りあえず、当初の基本制御ロジックは同じだと推測する。そして、その後に開発された307/メガーヌなどを比べると、ハード・ソフトとも、改善・進化は別々に行われているようだ。---307SWのATは、207シリーズと同じようなクセを持っていて、206シリーズにあった、停止→急発進時のモタツキが減っている。また、変速時のショックは、かなり減っているようで、フツーに走っている限り、スームーズだという印象に表れる。どうやら、206→307の間で 大きく改善されているようで、307/207のように、シフトゲート周りの形状が同じなら、同世代のATが搭載されていると思って良いのではないか。世代間で変化がないところで良い所は、ブレーキング時に、積極的にシフトダウンし、エンジンブレーキをかけるところ。逆に、良くない所は、登り坂などでのシフトショックで、まだまだ、日本製のATには及ばないところも残っている。---メガーヌTWのATは、残念ながら、307SWには及ばず、当初設計からのブラッシュアップ不足が感じられる。最も顕著なのが、バックに入れた時のタイムラグで、シフトチェンジ後、日本車と同じ感覚でブレーキを緩めると、タイムラグの間に、坂道などでは クルマが動いてしまう。そのほか、慣れてしまえば 全く気にならなくなるが、全般に、307SWの方がスムーズに走るように感じるのは、シフトショックが、307SWの方が小さいからだと思う。この点については、エンジンの違いもあるかもしれない。メガーヌは可変バルブタイミングのエンジンだが、なんとなく ちょっとだけ、もっさり回るような感じがする。---クルマの総合評価としては、どちらも甲乙つけがたいが、項目別に比べると、次のようになると思う。 操縦の楽しさ 307SW > メガーヌTW 操縦の安定性 307SW ≦ メガーヌTW 取り回し 307SW < メガーヌTW 乗り心地 307SW < メガーヌTW ATの仕上がり 307SW > メガーヌTW エンジン 307SW ≧ メガーヌTW シート 307SW = メガーヌTWデザインについては、人それぞれだし、コメントしない。また、見てすぐ分かる機能面での話も、ここでは割愛する。求める特性に応じて、自分に合ったものを選べれば幸いだと思う。
Apr 15, 2008
コメント(6)
-
なまいき 3歳児
3歳になったばかりの ゆうちゃんとの会話。---立ったまま 足で顔をタッチできるほど、ゆうちゃんは、体が柔らかい。 私「ゆうちゃん、体 柔らかいねぇ」 ゆ「そう」 私「すごいねぇ。 パパは 柔らかくないから、できないよ」 ゆ「ぱぱも、おおきくなったら、 できるようになるかもしれないよ」 私「・・・」---クルマ沿いの線路に、見たことがない電車が走っていた。 私「おっ、見たことない電車が走ってるよ」 ゆ「あ、えーでるとっとり」 私「・・・」家に帰ってから調べると、確かに「エーデル鳥取」という列車だった。私も妻も、その名前を教えた記憶を失っている...---食事の時間に、読みかけの本を読み続けていた。 ゆ「ごはんのときは、ほん よまないでください」 私「・・・」 ゆ「ほん よまないでって、いってるでしょ!」 ごはん たべてって、いってるでしょ!」 私「・・・」---プラレールアナウンス絵本のマイクを握って、プラレールを動かしながら... ゆ「いちばんのりばに とうちゃくした でんしゃは、 おおさかかんじょうせん です でんしゃは、ろくりょうでまいります と おもったら、さんりょうでした おきゃくさんが、がくってなりますので、 けいたいでんわをおきりください つぎは、あしや・あしやにとまります あしやをでますと、あまがさきにとまります」電車なんて、10回乗ったかどうかぐらいなのに、なんで、ここまで詳しくマネできるのだろう...---3歳になった今でも、言葉に半宇宙語が混じっている。「新橋!」と訴えてきて、意味が分からなかったが、何度も聞き返すと「すばらしい」と言っていた。「鉄道御殿」と呟きながら、プラレールで遊んでいたが、2週間経ってから「てつどうもけい」のことだと分かった。本人は、正しく発音しているつもりらしいが、早口で舌足らずなので、半宇宙語に聞こえるらしい。宇宙語混じりだからこそ、余計に生意気に聞こえる。
Apr 14, 2008
コメント(4)
-
役員会資料・役員会報告
ビジネスの場で、プレゼンテーションにパワーポイントが使われるようになって、かなりの年数が経つ。普及し始めの頃は、個々人の表現スタイルがストレートに反映され、小うるさい資料も少なくなかったが、最近では それなりに平均レベルが整ってきて、分かりやすいものが多い。そして、プレゼンテーションをする側のスキルも一般化されてきて、どこの会社・どこの業界に行っても、上手な人のプレゼンは 汎用的に通用する。パワーポイントで作るプレゼンテーション資料の対極にあるのが、役員会資料である。数千人・数万人の組織を抱える会社では、事業・技術・機能領域の数だけ役員がいるが、それぞれ専門分野の外までは詳しく知っている訳ではない。経営トップであるCEO・COOなども、大局的・経営直感的な判断は下せても、いちいち細かなことまでは憶えていない。そこで、役員会で審議するための資料は、各事業部門やスタッフ部門から、役員に決裁して欲しいことを理解してもらうために、こってり手間をかけられて作られる。当然のことだが、役員会資料は、社外に出ることがほとんどない。従って、自社の役員会資料が他社のそれとどのように違うのか、多くの人は知らない。例外があるとすれば、他社の社外取締役を兼務する役員自身と、各社の役員会資料の元となる戦略立案段階で関与するコンサルぐらいである。役員会資料は、パワーポイントが普及する何十年も前から存在していた。そのため、会社によっては、作成ツールとしてそれが使われても、あまりスタイルが変わっていないことがある。あるいは、パワーポイント導入によって、表現がすっかり様変わりした会社もある。ある大手自動車メーカーの役員会資料は、A3版にびっちり細かく書いた資料が基本スタイルだと聞く。同様のスタイルを採る会社は少なくないが、このメーカーの資料の特徴は、書いてあることがとても多いのに、良く整理されていて分かりやすいことである。パパッと資料を眺めるだけで、背景・やりたいこと・現在値と目標値・乗り越えるべき課題・解決手段・必要リソースなどが、手に取るように分かる。金太郎飴のように、どこを切っても○○ウェイが見えてくる同社だからこそ、いつも中身が整理・共有されている状態で仕事が進められており、そのことが資料にも表れている。A3版資料を使ってプレゼンテーションを行う場合、パワーポイントを使った場合と比べて、話し方が大きく変わる。パワーポイントでは、一枚一枚の画面送りがペースメーカーになるが、A3版資料では配られた瞬間に全てが見えてしまう。そのような資料を使って話す人は、その時点その時点で 細かな資料のどこを役員に見て欲しいのか、話しながらナビゲートする役割が求められる。ナビゲートでは、論点のストーリーに沿って落とし込まねばならず、途中で疑問点を抱かせてしまったり、飽きさせてしまったりするとすると、ストーリの最後まで付き合ってもらえなくなる。即ち、納得ある決裁が得られない。こんなテクニックは、技術やビジネスに関わる上で、本質的ではないような気がする。だから「資料が分かりやすい」「説明がうまい」と誉められても、ちょっと虚しい気持ちになる。きっと、悟りが足りないのだろう。
Apr 13, 2008
コメント(2)
-
307SWとメガーヌTW(その2)
クルマを比較する際には、人の感度やヒステリシスの問題があって、たった一度 試乗するだけでは分からないことが多い。私達のクルマ特性に対する感度は自分が思っているよりも低く、大きな変化でなければ気付けなかったり、普段乗っているクルマの特性や、新しいクルマの見た目の特性に惑わされやすい。プロのような訓練の機会がなければ、評論家と同レベルの感度を得ることは難しい。感度の問題を乗り越えるためには、比較したいクルマに試乗する距離と回数を、増やすしかないし、ヒステリシスの問題を回避するためには、比較したい両車種を、毎日のように繰り返し乗り換えてみるしかない。307SWに乗った翌日、メガーヌTWに乗って遠出をして、あらためてそう思った。---我が家のメガーヌTWは、エンジンマウントを交換してから間がないので、乗り心地は極めてソフトでマイルドだ。307SWの乗り心地も決して悪くはないし、フランス車らしい しなやかさを持っている。しかし妻曰く「307はカタイから、遠くに行くならメガーヌにして」とのことである。私としては、307SWのサスペンション設定は運転が楽しくなる設定なので気にならないが、違う感性で見ると そのように感じるらしい。確かに、交互に乗り換えてみたら違いは明らかで、307SWが「コトンコトン」と乗り越える段差が、メガーヌTWでは「コロンコロン」くらいにしか感じられない。高速道路に乗ると、メガーヌTWのステアリング特性は とてもラクだ。路面に沿って勝手にクルマが方向を変えてくれるような錯覚を持つほど。ただし、走っていて楽しいという感じではなく、あくまでソフト・マイルド・ラクという印象が強い。古く狭い街中を通りながら感じたのは、メガーヌTWの取り回しの良さ。307CC・307HBでも感じたことだが、307SWでは、なんだかクルマが一回り大きくなった感じがする。ホントにそうなのか、諸元を調べてみた。▼メガーヌTW ・全長=4515mm(HB:4240) ・全幅=1775mm ・ホイールベース=2685mm(HB:2625) ・回転半径=5.2m▼307SW ・全長=4425mm(HB:4210) ・全幅=1760mm ・ホイールベース=2720mm(HB:2610) ・回転半径=5.5m(HB:5.4)数字を見ると、実はメガーヌTWの方がサイズは大きい。HBからホイールベースを延長する手法も同じ。ただし回転半径が圧倒的に小さくて、これが取り回しの良さの一因だと思われる。他の要因としては、デザインによる前方・後方の見切りの良さも 関係しているように思う。---プジョーではあまりないことだが、メガーヌTWで遠出をすると、帰りに眠くなることが多い。信号待ちのアイドリング音や、走行時のボディ各部の小さな音は、307SWの方が静かだと思う。しかし、クルマを運転している人だけが感じる刺激や楽しさは、プジョーのクルマの方が よりダイレクトに伝わってくる。遠出の帰り道にも、運転者に飽きさせない何かを持っていることが、「運転して楽しいクルマ」なのか「乗って・乗せて楽しいクルマ」の違いになるのだろう。 ※この日記は、前回の続きです...
Apr 12, 2008
コメント(6)
-

桜のこの時期に
「桜の名所・百選」みたいな記事を、この時期ちょくちょく見かける。それはそれで魅力的なスポットも多く、実際 いくつかには、今年も行ってみるつもりだ。でも、記憶の中に残り続ける桜は、それを見るために訪れた観桜スポットではなく、人生の中の何かのイベントに結び付けられた桜の情景ではないかと思う。桜の時期の代表イベントと言えば、入学・卒業、そして就職であろう。大学の入学式を覚えていない私だが、大学生になって最初に見た桜のことは今でも覚えている。四月の良き日、私は私鉄の駅を降りて、古い商店街を抜け、踏み切りを渡った。そのまま しばらく歩くと、学生向けの飯屋や喫茶店が見えてくる。そこから、看護学校の古い塀を見ながら、池のほとりの坂道を登る頃には、眩しいような桜並木の下を歩いていた。谷を隔てた向かい側には学生寮が建っていて、その斜面にも桜のパラソルが開いていた。クラブのボックスからは、トランペットの響きや混声合唱の歌声が、学生生活を予感させるように楽しげに聴こえていた。就職で移り住んだ京都は、いっそう桜が美しかった。桜は、古ければ古いほど美しくなる。街自体が古い京都では、新しい桜の方が少ないので、桜が美しいことにも無理はない。特に、阪急線よりも北側や京阪線よりも東側の地域では、古い京都の町並みが当たり前のように残っていて、部屋に戻るために ただ歩くだけでも、目が醒めるような夜桜を見つけることがあった。---ゆうちゃんが生まれる前の日、ほぼ予定日頃だったこともあり、妻は軽い運動を兼ねて散歩をしていた。神戸市内のそのエリアでは、1995年以前には古い街並みが残っていたが、今やその風貌は一変している。ただ、密集地を抜けた川沿いの公園には、昔ながらの古い桜がそのままで、その日も満開の桜が、眩しいほどだったと言う。「散歩をしたら、お腹が痛くなったので、帰って来ました。」と言う暢気なメールが届いた翌朝、いきなり破水して、みんなが慌てた。腹痛が陣痛だったことに、本人も気付いていなかった。いったん出社していた私は、連絡を受けて職場の駐車場に向かった。駐車場の区画は、植えられて25年くらいの立派な桜に縁取られていて、こちらも満開になっていた。その後も、毎日この駐車場を利用しているが、この時期だけは、駐車されているクルマよりも、周囲の景色の方に関心が寄る。結構な咲きぶりなので、鼻が利く私は、満開の時期には甘い蜜の香りさえ感じられる。行き帰りのおり、軽い罪悪感を覚えながら桜の花を摘み取り、その根元から蜜を吸ってみる。ほのかに伝わる甘い味は、子供の頃と何も変わっていない。桜は、人生のあちこちを定点観測するために、毎年やって来るのだ。オープンにした207CCの運転席から見上げた桜。助手席のゆうちゃんも「きれいだねぇ」と言っていた。
Apr 11, 2008
コメント(2)
-

307SWとメガーヌTW(その1)
307SWに乗る機会を得た。307SWは、プジョーのCセグメントのワゴンで、ルノー・メガーヌTWとは、真っ向対決のライバルとなる。ちなみに、同セグメントの他のブランドとしては、シトロエン・C4、VW・ゴルフ、フォード・フォーカスなど。---走り出して感じたのは、まずステアリングの素直さ。メガーヌの電動パワステに慣れてしまう前は、メガーヌのステアリングの欠点に気付けなかった。だが、慣れてしまった後で 改めてトライしてみると、ニュートラル設定の油圧ステアリングは運転しやすい。207CCと比較しても、こちらの方が気持ちはいいが、反面、街乗りでは、軽めのメガーヌの方がラクかも。足回りだが、新車当時のメガーヌTWと比べると、307SWの足腰は 少し固めの印象だが、走りはいい。ただ、メガーヌの方も、ロールは大きめに感じるが、峠を走らせると、そこそこ速く走るポテンシャルを持つ。乗り心地は、おそらくメガーヌTWの方が上だったと思う。ただ、うちでも同じだが、メガーヌはブッシュ類の劣化が早い。数年乗れば、乗り心地は逆転している可能性が高い。---ルノーとプジョーの両ブランドについては、これまで、5つのライバル対決を体験している。ルーテシア2/206、メガーヌ/307、メガーヌGC/307CC、ルーテシア3/207、そして 今回のメガーヌTW/307SW。ドイツ車っぽくなってきたフランス車のトレンド、さらに、日本車のような便利さも身につけ始めている。そのような中で、フランスの両ブランドの違いは、なんとなく、縮まってきたような気はしている。今回の307SWにもメガーヌTWにも、装備の違いは少なく、流行りのグラスルーフも、両者で 用意されている。ただ、私の中のルノー/プジョーの印象は、ここ何年か、以下のように、あまり変わっていない。どのレンジに乗っても、外回りのデザインが変わっても、尖がった一部のモデルを除いて、当てはまることだと思う。ルノーは、家族でドライブを楽しめるクルマ。プジョーは、走りが楽しめるプライベートっぽいクルマ。
Apr 10, 2008
コメント(4)
-

プラレールコレクション(新幹線)
ゆうちゃんのプラレールコレクション。新幹線だけでも、ご覧のように6種類ある。紹介すると...奥から ・700系のぞみ ・E2系やまびこ(東北新幹線) ・400系つばさ(山形新幹線) ・E4系MAX(東北新幹線) ・イーストアイ(JR東日本) ・E3系こまち(秋田新幹線)という布陣。なぜか、ほとんどが JR東日本の車両で、700系を除いて、私も見たことがない列車ばかり。これは、本人が新幹線に乗ったことがないので、絵本で見る車両のほうに、馴染みがあるためか。確かに、JR東日本の新幹線の方がバリエーションも豊富で、絵本でも、多くのページを割いて紹介されている。---この中で「こまち」「やまびこ」「つばさ」は、連結器が出し入れできて、連結して走れる。最初、祖父母に 連結器付き「つばさ」をもらったのだが、連結器のスイッチ操作が大のお気に入りになった。ただ、1編成だけでは 連結して遊べないし、本人も「れんけつして あそびたい」と欲しがっていた。ただ、欲しいモノをすぐ買うのもどうかと思って、数ヶ月ほど、買い与えるタイミングを計っていた。そして、今回ついに、お誕生日のプレゼントに、こまち・やまびこの連結セットをあげた。案の定、大喜びして、ベッドの中でも抱えたままだ。最近のプラレールは、私が子供だった頃と比べ、ずいぶん、いろいろな機能が付加されている。このような連結機能のほかに、走行音を発したり、ドア開閉や、駅・踏切・橋などの情景部品なども。だんだん、模型のような方向に近づいてきている。---ゆうちゃんは、本当は大人の鉄道模型が欲しいらしい。NHKの趣味悠々の鉄道模型第2シリーズを見て、また、模型の世界が気になりだしたようだ。以前に放送していたときも、かなり楽しんでいて、そのことを日記に書いたら、三波豊和氏からコメントを頂戴した。でも、3歳になったばかりの幼児には まだ模型は早すぎるので、今はプラレールを模型だと思って、遊んでもらっている。
Apr 8, 2008
コメント(4)
-

花まつり
休日出勤の道すがら、久しぶりに、クルマのルーフを開けて走った。お寺の脇道を、土塀に沿って走ってみる。境内に植えられた桜は、もう八部ほど花を咲かせながら、白いパラソルのように道路を覆っていた。春の陽射しの柔らかさのせいか、不思議と路面には花の影が見えない。門前まで進むと、目の前に「こども花まつり」と書かれた看板を見つけた。潅仏会のその日、ゆうちゃんは 3歳の誕生日を迎える。彼が生まれた日も、今日と良く似たうららかな春の日だった。病院まで走った高速道路でも、当時乗っていた206CCのルーフを開けた。沿線の山や丘のあちこちに、白いパラソルが開いていた。空気は、薫るように暖かかった。ゆうちゃんの性格を季節で表すなら、生まれた季節そのままに、まさしく春だろうと思う。人あたりが良く、いじわるをしない。知らない子が躓いてこけると「だいじょうぶ?」と駆け寄る2歳児。---この時期、桜だけでなく、あちこちに花が咲いている。菜種油を取るのだろうか、菜の花が広がる畑もある。広がると言っても、日本では せいぜい一町くらいのことだが、中国で見た菜の花畑は、すごかった。3月の半ば、西安から成都へ向かう直快に乗った。寝台列車はいったん西に向かい、それから南に下る。夜中には、薄暗いランプが灯った駅に何度も停まったが、陽が昇ると列車は順調に走り始めた。四川省に入ってから、景色が黄色くなった。手前の畑から彼方の山の麓まで、見渡す限りが菜の花畑だった。中国では、何を見ても、壮大だった。万里の長城は、登っても登っても 次の峰が現れる。街中では、自転車と人の洪水。人民元紙幣についた手垢は、1ミリは積もっているように思えた。その当時から「HITAOHI」などと紛らわしく明示された家電製品や、ニセモノの青いファミコンなどが売られていた。経済優先に舵を切り出す直前の中国には、共産主義下で蓄積された欲望が、うねるように横たわっていた。反面、人々はまだまだ素朴なところもあって、糧票(配給票)を持たずに肉マンを買えなかった私を見て、列に並んでいたおばちゃんが券を分けてくれた。日本語を話すタカリの輩も、金がないと分かると、若者同士 他愛無いことを語り合って楽しんだ。---私が中国を旅したのは、二十歳の頃のことだ。ゆうちゃんが二十歳になる2025年前には、中国のGDPは、アメリカのそれを超えて世界一になると言う。経済発展に伴って、大きく変わりつつある中国のことだ。その頃には、あんな菜の花畑を見ることは、できなくなっているかもしれない。CCから見上げた桜は、Cieloとは また別の味わいだった。
Apr 7, 2008
コメント(4)
-

207Cieloと207CC(その4)
CieloからCCに戻ってみて、気付いたこと。同じようなパーツを使いながらも、CCは、うまくプライベートカーを演出している。着座位置が低く設定され、包まれ感があったり、同じエンジンなのに、ちょっとだけ静かに走る。206CCの時に、styleにもしばらく乗ったことがあるが、その時に感じたCC/styleの違いに、良く似ていた。207CCのコンセプトは、206の時と変わっておらず、やはり、正常な進化と言えるのではないか。---ところで、Cieloのマルチファンクションディスプレイが、私が乗っている時に、突然リセットされた。207では良くある不具合だと聞いていたが、私のCCでは、未だに遭遇していない。リセットされた時計は、なぜか2003年になっていた。ちょうど、モデルの開発スタートのタイミングあたりか。パワーウィンドウを左右同時に動作させた時に、不具合が発生したので、電源系統の問題かもしれない。---パワーウィンドウで思い出したが、207CCでは、窓を閉める時のワンタッチ機能が付いていない。今時、どんなクルマにも付いている機能だし、Cieloにもあったので、CCだけのレス設定のようだ。おかしなことに、開ける時のワンタッチはある。206CCでは、開・閉とも、キチンと機能していた。また、スイッチの閉方向にはクリックがあり、ハード的には、用意されているように見える。CCでは、ワンタッチ閉機能が、ルーフ開閉の動作仕様と、どこかでバッティングしているのかもしれない。いつか、ソフト改善がなされて、この機能が使えるようになって欲しい...---Cieloのグラスルーフから見た京都市内の桜。市内の中部・南部あたりでは、ちょうど、この土日くらいが、満開になるのだろう。Cieloのグラスルーフは、なかなか良い。
Apr 6, 2008
コメント(0)
-
フランス車の思い出(その2)
学部4年生になると、学生は研究室に入る。研究室では、学部生・修士・博士課程までが学生で、合わせて6~9名。これに教授1名、助教授1名、講師・助手・技官が数名という体制が、一般的だった。この他に、研究室によっては、「秘書」という名前で、女性のアシスタントがいることもあった。秘書は、研究室の予算で採用されるアルバイトのようなもので、正規の職員ではない。ただ、大学教授の秘書という名前にステータスがあったのか、優秀な女性が多かった。そして、いわゆる「お嬢様」が多かった。関西だと、神戸女学院みたいな大学の英文科を卒業した女性が、就職活動をすることなく秘書になる。そんなパターンが目立った。英語に堪能な人も多くて、研究室の庶務の他、論文執筆の手伝いをする人もいた。私は、学内のある研究所に配属された。予算面で恵まれていたのだろうか、学部よりも秘書の数は多かった。駐車場には、秘書達のクルマも停められていたが、メルセデスやBMWの他に、時にはフランス車に乗っている人もいた。そんな秘書の一人とドクターコースの大先輩が親しく、たまに一緒にご飯に連れて行ってもらうことがあった。彼女のクルマが、シトロエンBXだった。---トヨタのコンパクトハッチに乗っていたフツーの学生にとって、彼女のBXは、別世界のものだった。シングルスポークのステアリングや、エンジンをかけると「ムクッムクッ」とクルマが起き上がってくるサスにも驚いた。普段は自分で運転しているのに 男性を乗せる時はキーを預ける、という彼女のスタイルも、新鮮だった。私が2番目に関わることになったフランス車も、やはりシトロエンだった。あれから15年が過ぎて、ハイドロニューマティックの乗り心地も、後部座席で聴いた二人の会話の大人っぽさも、もう忘れてしまった。でも、シトロエンに どこか一目置いている自分がいて、ルノーやプジョーに乗っても、未だにシトロエンには手を出していない。
Apr 5, 2008
コメント(6)
-
フランス車の思い出
大学1年の頃、学部にあがる前の教養課程では、フランス語を第二外国語として履修していた。文法と会話の2本の講義が必修になっていて、会話クラスでは、妙齢のフランス人女性が講師だった。かれこれ、17~8年前のことである。---およそ、1クラス10人くらいだっただろうか。大きな字でフランス語と絵が書かれたテキスト。どうやら、フランスの幼稚園か小学校低学年の、国語の教科書を、流用したものだったらしい。ある時は、先生の娘さんの名前がサインされたフランス人学校のプリントが流用されたこともあった。先生に似たアリちゃんという娘さんを見た同級生は、「宮沢りえのように可憐だった」と報告した。---先生は、私達のクラスが好きではなかった。昼寝をしている学生が必ず一人二人はいたし、カンニングをするような輩も、後を絶たなかった。「フランスでは、昼寝は、先生への抗議の意味です。 つまらない授業では、わざと寝たりします。 初めて日本で昼寝を見た時、私はとても傷つきました。 でも、後で、そうではないということが分かりました。 日本人の学生は、本当に眠いのです。。」なんだか、そんなような口調で、説教された。---先生のマイカーは、シトロエンのCXか何かだった。日本車に乗りたくないので、わざわざ、フランスから持ってきたという噂だった。先生は、私達を含め、日本が好きでないように見えた。教養部の脇にとまっていた先生のシトロエンが、私が初めて意識したフランス車だった。その後、縁あってフランス車に乗るようになったが、先生に習ったフランス語は、ほとんど使いものにならない。ふと、フランス語で数字を数え始めてみても、いつも、11か12でカウントが止まってしまう。
Apr 4, 2008
コメント(4)
-
ディーラーオリジナルキャンペーン
プジョー京都南・京都北で、ディーラーオリジナルのキャンペーンを始めたようだ。第一弾は特別限定車。ナビなどのオプションプレゼントで、実質18~25万円相当の値引き。第二弾はお友達紹介キャンペーンということで、紹介者にプジョーサイクルがプレゼントされる。以前は、プジョージャポンのキャンペーンを忠実に実行するだけだったような気がするが、こうしたオリジナルキャンペーンは、ディーラのやる気や思いが伝わってくるもので、なんだか見た目以上に効果がありそうな気がする。特に、同じプジョーディーラーの中でも、サービスや接客レベルに差がある現在では...ルノーのディーラーでも、今は発注できない6MTのメガーヌ2.0の限定車が発売されているようだ。こちらも、他ではないモノを提供しようという心意気を感じて、なんだか頼もしい。※もし、プジョーのクルマを買おうとされている方がおられたら、ご一報下さい。 京都南店・北店を気にいられたら、私からの紹介と言うことにしておいて、 紹介者用の自転車プレゼント品は 差し上げます。
Apr 3, 2008
コメント(2)
-

207Cieloと207CC(その3)
前回に引き続き...---207Cieloに乗り込んで すぐに、室内の仄かな香りに 気が付いた。プジョーの新車は、ルノーのように、もともとメーカー独特の匂いは強くない。今回のCieloの香りは、新車の香りでもないし、車用の芳香剤のようにキツイものでもない。3日後、何気なくグローブボックスを開けると、仄かな香りが、ふわっと強くなるのを感じた。中には、こんなものが入っていた。パフューム・ディフューザーだった。---これは プジョー純正のカー・フレグランスで、オプションで、7種類の香りが用意されている。通風口の上にカートリッジ差込口があって、切替スイッチを花のマークにすると機能する。密封されたフレグランスを開封しなくても、外箱を開けるだけで、心地よい香りがあふれてきた。---このパフューム・ディフューザーは、Cieloには純正装着だが、207CCには装備されない。ひょっとしたら、部品を取ると207CCにも装着できる?...と、つい考えてしまうくらい魅力ある装備だった。
Apr 2, 2008
コメント(6)
-
207Cieloと207CC(その2)
前回に引き続き、Cieloについて...---Cieloのシートは、207CCとは違い、ハーフレザーシートとなっている。ちょうど背中に当たる部分はファブリックで、レザーよりもふんわりしていて、心地良い。着座位置が207CCよりも高いこともあって、シートの落ち着き感は、なかなかのものだ。シートの座りごこちだけを考えるなら、レザーよりハーフ、さらに素の方が良さそう。ただし、オープンカーの場合、メンテ性や、対候性を考えると、レザーは欠かせない。一見、レザーはメンテが面倒に見えるが、埃を吸わないし、普段は軽い水拭きだけで済む。---タイヤサイズの違いも関係ありそうだが、ハンドリングの差も、だんだん見えてきた。60km/h以下の街乗りをしている限りは、Cieloの軽快さは、乗りやすくてちょうど良い。轍も軽く乗り越えるし、直進性も素直。旋回操作も、リニアに決まってくれる。207CCでは、ロードホールディングの粘りの分、轍に影響を受けたり、相対的に少し操作が重い。反対に、高速域では、207CCの方が安心だ。Cieloは、直進性はCCと変わらないレベルだが、路面のうねりには、ポンポン跳ねてしまう感じだ。これは、単純に 車重の違いなのかもしれない。---206CCの進化版だと思うかどうかは別にして、最近のクルマらしく、207CCは良くできている。そして、今回の207HBも また、ずいぶん良くなっていると思う。数字上は、サイズアップや車重アップしているが、運転すると、ほとんど気にならない取りまわしだ。気軽さや ハンドリングの良さを見る限り、206ユーザーも共感できる仕上がりだと思う。
Apr 1, 2008
コメント(4)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-
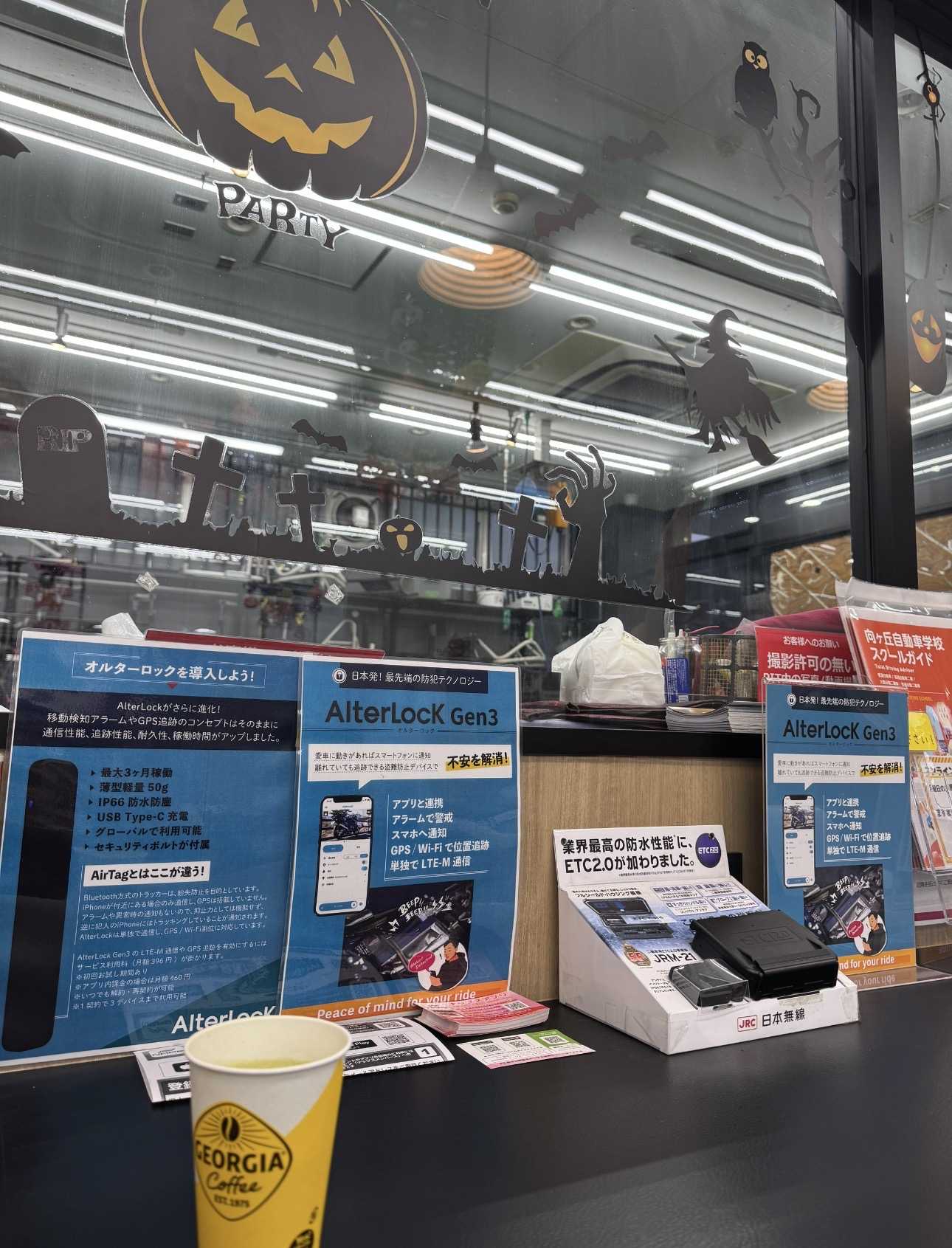
- バイクのメンテ&カスタム
- VTR250 ドライブチェーン清掃、給油
- (2025-11-04 05:16:12)
-
-
-
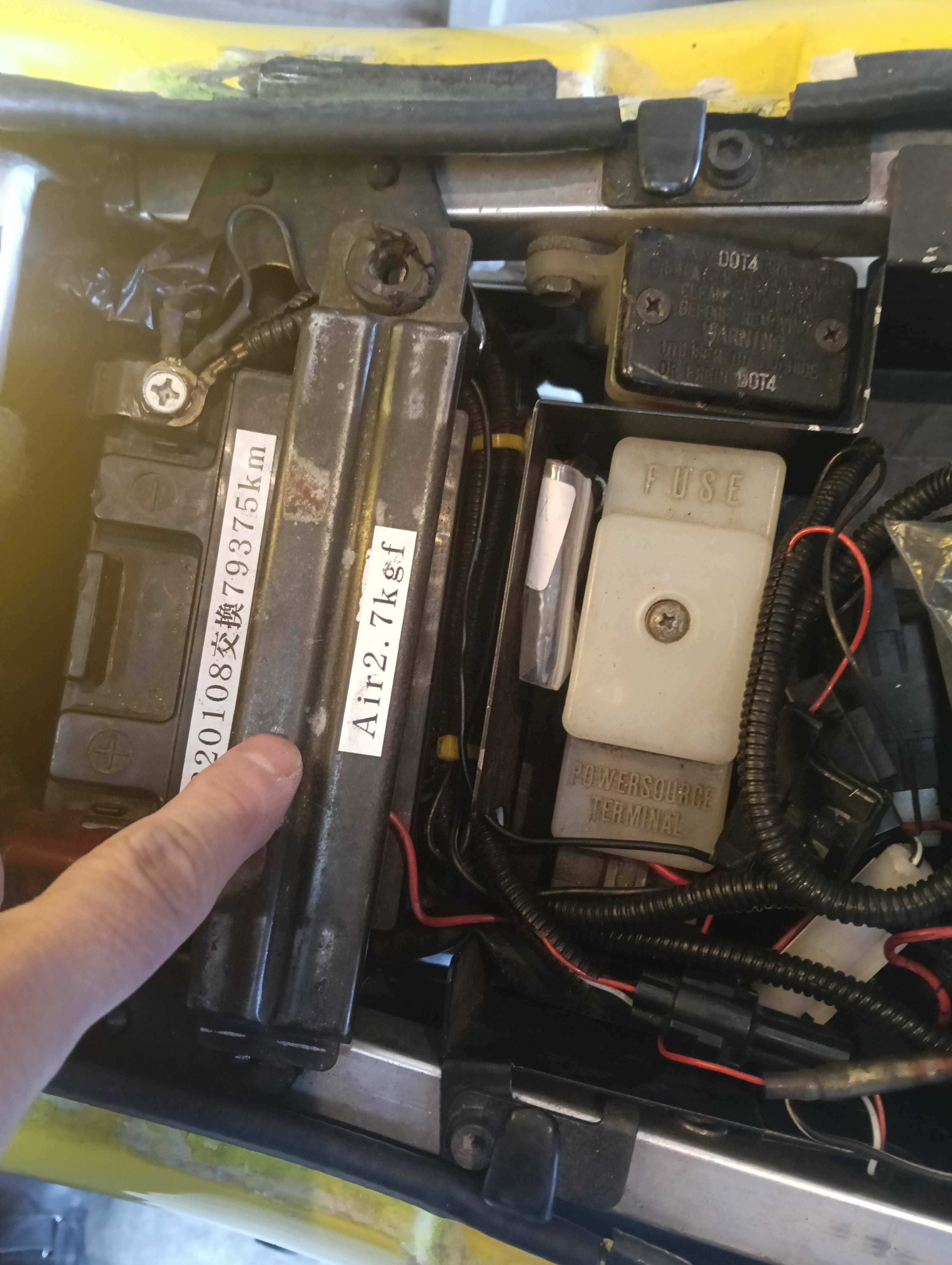
- 自動車・バイクのメンテナンス
- 251110:GSX-R1100:電装系トラブルメ…
- (2025-11-10 00:00:12)
-
-
-

- カーナビあれこれ
- 3シリーズのバックカメラ修理
- (2025-11-12 16:36:25)
-







