全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
ブログ引越しのお知らせ
このたび、楽天ブログの仕様変更に伴い、このブログを引っ越すことになりました。新たなURLは次のとおりです。http://yosizumi2009.cocolog-nifty.com/blog/過去記事は移行されますが、コメントが引き継げません。コメントを寄せていただいた皆さん、申し訳ありません。本ブログはしばらくの間、残しておきます。つたない日記ですが、引き続きよろしくお願いいたします!
2011.12.23
コメント(2)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その11 ~ダーウィンからアリススプリングスへ~
朝6時過ぎにダーウィン市街のホテルを出発、ダーウィン空港へと向かう。忌々しいJetstarのカウンターではなく、今日はQantasのカウンターでチェックイン。ダーウィン空港は雲間から昇る朝日に照らされ、その中に小さなQANTASLINK(オーストラリアでコミューター路線を運航するカンタス航空の子会社の総称およびそのブランド名)の飛行機が佇んでいる。 乗客は、3列座席に1人、2列座席に1人、というぐらいに少ない。7:20に離陸。いろいろあったダーウィンの街、ノーザンテリトリーの主都だが、空から見るとやはり小さな街だ。下の写真、左手に見えるのがダーウィン中心部、右手に突き出た岬がイースト・ポイントで、その下の白い地域が空港周辺。飛行機は、ノーザンテリトリー第2の街、アリススプリングスへと向かっている。 眼下には大陸縦断鉄道とスチュアート・ハイウェイが沿って走る。いずれもオーストラリア南岸の南オーストラリア州・アデレードまでオーストラリア大陸を南北に貫く路だ。ダーウィンからアデレードまで、大陸縦断特急「The Ghan」号で2泊3日、距離にして2979km。スチュアート・ハイウェイでは、同じルートで毎年「ワールド・ソーラー・チャレンジ」と呼ばれるソーラーカーレースが開催されており、2011年は日本の東海大学が2連覇を達成、総走行時間は32時間45分、平均時速は91.54kmだったという。 それだけ太陽が照りつける大地、ということだ。 しばらくして上空の雲がなくなり、窓の下に大地が見え始める。赤茶けた大地とユーカリと砂と、たまに道路と、たまのたまに家。オーストラリア内陸部の乾燥地帯、いわゆる「outback」(アウトバック)と呼ばれる地域に入った。 一直線に平行に、層のようになって続く山。地殻変動で地層が斜めになり、長年の風化で上部が削られて地層が露出したもので、ケスタ地形という。世界でも古い地層を持つオーストラリアらしい風景だな、と思う。日本ではこういう年月の経過した地形はあまり見られない。 ケスタの山頂部をずーっと眺めていると、徐々に高度は下がり始め、9:20にアリススプリングス空港に到着した。タラップを降りて空港に立つときに感じた陽射しの強さ。これがoutbackの陽射しか!待合所で待つ間、しばしテラスへ出て、飛行機の中で冷めきった身体を温める。 初めてユーカリの葉を触ってみる。表面に油分はないが、葉をくしゃくしゃにすると、水分は出ないのだが良い香りがした。まさしく、ユーカリオイルの香りだ。 アリススプリングスは、オーストラリアの観光地、ウルル(エアーズロック)へのゲートウェイ。今回は空港だけのわずか50分の滞在だが、いつかはウルルにも行ってみたいものだ。タラップを上り、再び同じ飛行機に乗り込むのだが、今度の行先は、西オーストラリア州・パース行きだ。 <つづく>
2011.11.01
コメント(0)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その10 ~再びダーウィン~
さて、ミリタリー・ミュージアムから再び3km歩いてFunnie Bayバス停に戻り、市内経由で空港へ戻る。イースト・ポイントを気ままに楽しんだせいで、到着は15:30。昨日から何度も訪れたJetstarのカウンターには、あの英語の聞き取りにくい女性が、仕事をしていた。 自分が声を掛けようとすると、機先を制してその女性が口を動かす。「荷物は届いているわ。一緒に事務室へ来てくれる?」 よっしゃー! 盗難とか、所在不明とか、想定していたいくつかの最悪事態が消え、今後の旅に明るい光が差してきた。 バックパックには「急送荷物 至急」と書かれた札。渡された書類を見ると、この荷物の発送地がシドニーとなっている! そうか、成田からケアンズ空港に到着したとき、日本人が大挙して搭乗ゲートに移動していた、あのシドニー行きの便に荷物を入れてしまった、ということなのか。自分が行ったこともないシドニーに、バックパックだけが一人旅をしてきたわけだな。この10年来のバックパックが急に愛おしく感じてきた。 こうなったら、この先の旅程を組み直し、新たにチケットを取らなければならない。そのスタッフの女性に「今後のスケジュールをインターネットで探したいんだけれども」と言うと、「インターネットはそこにあるから探してみて」と言って、空港に設置された有料のインターネット接続用PCを指差した。自分としては、そちらの会社がこれだけ迷惑かけているのだし、その先の旅程作成やチケット入手ぐらい手伝ってくれるのだろう、という期待も込めて話したのだが、「自分で金を払って探してね。」というその態度に、怒るというより呆れた。 空港の有料PCは、マウスがなくて非常に使いづらく、使用料もどんどんかさむので、市内に出てインターネットカフェを探すことにし、まずは安宿にチェックイン。荷物を置き、ようやく手許に届いた充電機でバッテリーの切れた携帯電話を復活させながら、街に出た。 昼に歩いたとき見つけた旅行会社に寄ると、既に営業時間終了。望みを捨てず、インターネットカフェへ。安く使いやすいPCでQantas航空のサイトからフライトを調べると・・・明日中に西オーストラリア州・ピルバラ地域のポート・ヘッドランドに到着するフライトがあった。若干ルート変更が必要だが、なんとか予定のコースに復帰することができる! そのサイトから即予約し、クレジットカードで支払いを済ませ、Eチケットによる発券まですることができた。つくづく今の時代は便利だと思う。言葉の壁に苦労しながら旅行会社でチケットを取るという手間も省け、インターネットカフェで発券できてしまうのだから。これでようやく、オーストラリアの旅が、始まった。 その夜は、他民族が集まるダーウィンらしく、インド料理屋でカレー。やはりオーストラリア、ラム肉が美味しい! 旅のエンジンが、掛かってきた。明朝は、因縁のダーウィン空港を後に、オーストラリア大陸の真ん中、アリススプリングスへ向けて出発だ。<つづく>
2011.10.30
コメント(2)
-

御礼
つたない旅日記を始めて丸2年が経ちました。訪れていただいた皆様、心より御礼申し上げます。 今年は半年ぐらい「ボランティア日記」となりました。少しでも被災地のためにお役に立てればと思い、被災地の現状やボランティア活動に触れましたが、GWのときには普段の3倍近いアクセスがあり、こんな素人ブログが何らかの役に立っていたとしたら、それは本望です。 今後も微力ながら情報発信していければと思います。引き続きよろしくお願いします!気仙沼市 岩井崎にて 2011.7.17
2011.10.24
コメント(2)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その9 ~ダーウィン・イーストポイント4~
「襲われた」鳥たちに別れを告げると、すぐにイースト・ポイントの中心に到着した。 「イースト・ポイント」と題された看板には、「our military heritage」、オーストラリア軍遺跡とでもいうようなサブタイトルがある。 ここイースト・ポイント、そしてダーウィンは、オーストラリア建国後、オーストラリア本土で初めて他国に攻撃されたという、オーストラリアにとっては国家的にメモリアルな場所。その攻撃した国とは、他ならぬ日本である。 オランダ領東インド(現在のインドネシア)を占領していた日本は、対抗しようとする連合国軍の基地があった北部オーストラリアに対し攻撃を加えようとした。1942年2月19日午前9時58分、ダーウィンに対し188機の日本の戦闘機により最初の空襲が開始され、戦艦、市街地及び飛行場に甚大な被害が発生した。公式には243名の死亡が確認されているが、実際にはさらに多数の方が亡くなっているとの説もある。その後も日本軍は空襲を繰り返し、ダーウィン及びその周辺に対し64回もの攻撃を行ったほか、その他のノーザンテリトリー、クィーンズランド州、西オーストラリア州北部の町に対して攻撃を行った。 しかしながら、オーストラリアの北東に位置するソロモン諸島方面でアメリカ軍が勝利を収めた1943年頃に戦局は転換、1943年11月12日の空襲が最後となった。 オーストラリア政府は、厳しい検閲を行い、空襲やこの地域で発生したことに関する情報を伏せようとした。オーストラリア国民は何も知らない方がよいだろうと判断したのである。しかし、その代わりとして、オーストラリア国民は、食糧や弾薬が不足し、危険や不便と隣り合わせで、日本軍が退却するまで何か月も何年もの間過ごしてきたダーウィンの人々のことをほとんど知ることがなかったという。 イースト・ポイントの一角には、「ミリタリー・ミュージアム」があって、中には当時使われていた旭日旗(日本の軍旗)や寄せ書きされた日本国旗、兵器、戦車などが展示されているほか、9.2インチ砲の砲台が開放されている。 自分は、外国に来た時、なるべくその国と日本との間の歴史をその国で学びたい、と思っている。日本では見えにくい「歴史」がその国だとはっきり見えることがあるからだ。オーストラリアと日本、現在の良好な関係の過去には、このような歴史の積み重ねがある。そして、その事実は、被害を蒙った場所で語り継がれている。<つづく>参考資料:"When War Came To Australia"(ダーウィン・ミリタリー・ミュージアム内で配布されていたパンフレット)
2011.10.23
コメント(0)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その8 ~ダーウィン・イーストポイント3~
モンスーン・フォレストを抜けて芝生の広場に出ると、20m先ぐらいの地面に2,3羽の鳥がいた。全体が白っぽく、くちばしの先が黄色い。鳥の色もやっぱり目立つ原色が混じっているんだなあ、と思っているとすると、そのうち1羽が飛び立ち、なんと自分に向かって低空飛行してきた。 いつまでたっても曲がらず前方3m。鳥に襲われた経験はないのでさすがに恐怖を感じ、とっさに身を翻してしゃがみ込む。再び襲われるのか?と思い、鳥の位置を探そうと後方を見るも鳥はいない。周りを見回してもいない。再襲来がないのだとわかり少しほっとしていると、別の1羽が再び前方から突進してくる。何だ?狙われているのか?再び身をかがめる。鳥の行方を捜すと、自分の右方にいた。ということは・・・?直前で向きを変えたということか? しばらく20m先の定位置に戻っていた鳥が、3度目の突進。今度は怖がらずギリギリまで粘って立ってみる。すると、鳥は直前1mぐらいのところでさっと右へ避けてゆく。そうか、自分を狙っているんじゃないし、避けた後すぐにまた襲ってくるわけでもないので、威嚇しているわけでもない。ということは、からかっているのかな・・・? 4度目の突進をカメラでパチリ。鳥にからかわれているんだと思うと、なんだか楽しくなってきた。<つづく>
2011.10.19
コメント(0)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その7 ~ダーウィン・イーストポイント2~
もうかれこれ30分は歩いたか、目の前に「モンスーン・フォレスト・ウォーク」という大きな看板があって、航空写真の地図がある。岬まで少しショートカットできそうだから、その小道に入ってみた。 整備された小道の両脇は、予想外に樹齢の若い、細い木ばかり。手つかずの原生林、という感じはあまりしない。樹高が低いせいか、空の光もよく届いている。 小道のそばに、倒れた大木の根がまるでオブジェのように広く横たわっている。直径は1.5mぐらいか。根こそぎ倒れる樹木は日本でも見ることがあるが、もっと根が深い。 熱帯地域は、激しい雨がよく降るため、表土が流されてしまい、日本のような温帯に比べると表土が薄いという。水も光もあって温度も高く、樹木はよく育つのだが、薄い表土の中で根を張るので、自然と浅く広くなるのだ。そこにこの地域特有のサイクロンがやってきて突風に煽られると、根の浅い大木は倒れてしまう。 でも、倒れた樹木から、また新たに幹が上へと伸びる。きっと、これまで葉に覆われ光の届かなかった地面からも、小さな若木が上へ上へと光を求めて競争する。これこそ森の輪廻、生命力。日本の静かな「森」とは違う、「モンスーン・フォレスト」だな、と風景を感じながら、小道を先へ進んでいった。<つづく>
2011.10.18
コメント(0)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その6 ~ダーウィン・イーストポイント~
さて、マクドナルドを見つけてテラス席で朝食。つかの間ではあるが煩わしさから解放され、街をゆく人々を目にすると新鮮で、自分が外国にいることをふと感じる。『地球の歩き方』から探して、ダーウィン市街から7km北に離れて突き出した岬、イーストポイント保護区へ行くことに決め、市内バスターミナルへ向かった。 12:25、4番バスに乗車、バスは中心部を抜け海沿いを走り、リゾートやショッピングセンターを掠めながら20分程度、路線マップから見て最もイーストポイントに近いFunnie Bayバス停に到着。 一番近いバス停とはいっても、イーストポイントまで約3kmはある。最初のうちは車道を、その後海沿いの道に出てからは、車道横のサイクリングロードを歩いていく。ロードに沿ってベンチや運動施設、そして無料のバーベキュー施設が設置されていて、オーストラリア人がワイワイパーティーをしている。日本だったら、バーベキュー台を借りるときは有料だし、そもそもバーベキューが禁止されている公園も多く、日本にはない独特の施設と文化が羨ましい。その近くでは、地元の方が網を持って投網漁をしようとしていた。 なにより、きれいな海や大きな雲、ユーカリの白い幹や珍しい花々、原色のカラフルな鳥など、日本ではあまり見ない風景を目にしながら歩くと時間が経つのを忘れ、保護区内に入ってかなり進んでいた。<つづく>
2011.10.15
コメント(2)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その5 ~ダーウィン~
翌朝(12/29)、決して安くないホテル代を払って空港近くのホテルをチェックアウト。9:50、とりあえず空港のカウンターに行ってみるも、相変わらずJetstarのカウンターに人はいない。Qantasのスタッフに聞くと、15:00頃までスタッフは来ない、とのこと。もう、これでは荷物の状況が全く分からないし、予定していた10:50発のBroome行きフライトはキャンセルせざるを得ない(直前なので返金ゼロ・・・)。 しょうがない、どうあがいても15:00まで状況が変わらないのであれば、それまでダーウィン市内に出てぶらぶらしよう、と決意し、タクシーに乗った。 ダーウィンはオーストラリアのTop Endとも呼ばれるオーストラリア北部最大の都市、とはいっても人口は約13万人、街の名前の起源は「進化論」のチャールズ・ダーウィンから来たものだが、ダーウィンの入江を「発見した」イギリス人船長がダーウィンの名をつけただけで、本人は来ていないらしい。 市中心部にあるショッピングモールの中には、水道会社の窓口があったので覗いてみる。パンフレットがあるので、水道料金や水道事業の概要が書いてあるのかと思いきや、「水に賢明な庭の作り方」と書いてある。水道会社がガーデニングの仕方まで指導しているのか?? 中を開くと、ダーウィンの水道使用量の6割が屋外使用、そのほとんどが庭への散水であって、使用量はオーストラリアの他の主要都市の2倍にも上るのだそうだ。現在水不足に陥っているわけではないけれど、効率的な使用、まずは庭への散水を抑制することで、水の保全を図っていこうと呼び掛ける。 たしかに、熱帯気候に属するダーウィンだが、雨が降るのは10月から4月にかけてで、5月から9月はほとんど雨が降らないのに、平均最高気温は30度を超えるのだ。そんな気候と広い庭があれば大量に水を使うだろう。 そのため、蒸発を防ぐために夜散水しようとか、水分を保持しやすい土壌に変えようとか、雨季の水やりは控えようとか、乾季は節水型機器で水やりをしようとか、土の根覆いは15cmしておこうとか、いろいろな提案がなされている。日本の水道の窓口ではまず見られないパンフレットだし、水の貴重さを呼び掛けるという点で、日本とオーストラリアの水に対する価値観の違いを感じさせる。<つづく>
2011.10.13
コメント(0)
-
西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その4 ~ダーウィン空港2~
ダーウィン空港のJetstarのカウンターでスタッフからLost Baggageの事情を聞く。とりあえず、空港内に残っていないかどうか調べる、ということでしばらく待たされるのだが、このアジア系のスタッフの英語がとにかく聞きとれない! 英語生活の始まりはもう少しやさしい状況から始めたかったのに・・・一番面倒な状況から始まってしまい、しかもよく聞きとれないので急速に自信をなくす。 20分程待った後、ダーウィン空港内には荷物がないと判明し、次に搭乗地のケアンズ空港での存在確認に移った。とにかくトイレに駆け込んでいる間が空白なので、荷物がダーウィンに届いて盗まれたのか、そもそも届いていないのかがはっきりしない。ケアンズ-ダーウィン間のJetstarは1日1便なのだが、ケアンズ空港にあったとすれば、今晩中に系列のQantas航空で届けることも可能だという。 予定通りいかないのも旅、自分の思うようにならないのも旅。もし盗まれていたら・・・それもそれで考えよう。自分の力でどうにもならないことを悔いても何も進まないのだ。その状況の中でどう過ごすかが大事、というのが過去のLost Baggageで得た教訓。 いろいろな可能性を考え、空港の隣にあるホテルに急きょチェックインすることにした。 実は、この旅に出る前に風邪を引き、完全には復調しない中で日本を発っていたので、まずは仮眠し、夕食のビールもそこそこにして、体力回復を優先した。Jetstarのスタッフには、荷物が来たら携帯に電話してくれ、と話してあるし、できればそのまま朝まで寝てしまいたいのだが、念のためケアンズからのカンタス便が到着する21時頃、再びチェックインカウンターへ向かう。しかし、ジェットスターのカウンターにはもう誰もいなくなっていた。Qantas航空のスタッフに尋ねたが、何も聞いていないらしい。いよいよ落胆して、ホテルへと暗い夜道へ戻った。 さて、この先どうするか。いつ荷物が届くかで、あるいは届かないかで、この先5つの選択肢を書きだした。明日(12/29)の10:00頃までに荷物が来ないと、この先のスケジュールは大幅に変更しなければならないし、最悪、ピルバラには寄れずにオーストラリアを後にしなければならない。とりあえず、いろいろな可能性を考えておいて、床に着くことにした。<つづく>
2011.10.12
コメント(2)
-
西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その3 ~ダーウィン空港~
ダーウィン空港到着後、手荷物受取所へ行って、預けた自分のバックパックがベルトコンベアで流れてくるのを待っていた。ところが、機内で冷えたのか急に腹が痛くなりトイレへ駆け込む。荷物が盗まれることのないよう、ピックアップするまではコンベア前を離れたくないのだが・・・、まあ先進国オーストラリアだからその点は取り越し苦労だろう、とスッキリしてからトイレを出ると、もうかなりの荷物がピックアップされ、残っている荷物は少なくなっていた。 ・・・ん? 自分のバックパックが、ない。流れている荷物が1周し、もう一度回ってくるのに自分の荷物は、ない! あ、これは・・・トラブルを直感した。過去のLost baggageの記憶が甦ってくる。まず、近くにいた係員に荷物が見つからない旨を伝えた。係員からは、チェックインカウンターに行くよう指示があったので、もう誰も客のいなくなった税関を通ろうとすると、ごつい男性税関職員が携行していたデイザックをX線でチェックする。 「メントスのような物ないか?」 ん? メントスはないが、そういえば成田で買ったアーモンドチョコレートがある。その丸い形が気になったのだろうか、とそのチョコを取り出すと、厳しい口調で職員は言う。 「これは食品だよな。でも申告書に食品は持ち込んでいません、とチェックしているじゃないか。」 べ、弁解の余地がありません。。ごつい男性税関職員は続けざまに、「ここにあるのは何だ?」とポケットを指差す。中にはじんましん用の薬があった。薬はドラッグに間違われることもあるので、その用途を伝えようと思い、「これはアレルギー用の薬です。」と答えた。すると、そのごつい職員は間髪入れず追及する。「医薬品も持ち込んでいない、と君は申告しているじゃないか。」。 用途は関係なかった・・。これまた弁解の余地がありません。食品といっても大量じゃないし、薬は持参しているのを忘れて申告しなかったのだが、さあ、どう答えよう・・・。 「ごめんなさい、私のミスです!」と謝った。やばい、どこか連れて行かれるだろうか・・・ただでさえ荷物届かないのに! ごつい職員は「次回からきちんと書くように!」と厳しい口調で言って、自分を釈放してくれた。こんなに厳しい税関は初めてだ。オーストラリアは周辺国から隔絶された大陸で、独自に発展した生態系も多い。外国からの物品に関する検疫体制が特に厳しい国だと、身を持って経験した。 税関を抜けた。でも、Lost Baggageは何ら解決していない・・・。<つづく>【参考までに】オーストラリアに持ち込めないものは? (オーストラリア大使館HP)
2011.10.11
コメント(2)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その2 ~東京からダーウィンへ~
2010年12月27日、午後から休みを取って、夕方、成田空港へと出発する。この年7月に開業した「成田スカイアクセス線」のおかげで、山手線の日暮里から空港まで約40分、今までに比べて画期的に早い。のではあるが、この年10月の羽田空港国際化で、その利便性は霞んでしまっている。 今年になって成田空港のリムジンバスに乗る機会があったが、「羽田空港にどんどん客が取られて、客足は減る一方だよ」と嘆くバス関係者の声を聞いた。今後、成田空港という巨大インフラの行きつく先はどこにあるのか。 今のところ、オーストラリア路線は成田からのみ出発しており、ケアンズ、ゴールドコースト、シドニー、パースへと夜行便が飛び立つ。今回の旅では、年末年始の高い航空運賃を考慮し、これまで使ったことのないLCC(格安航空会社)を使ってみることにした。行きはオーストラリア・カンタス航空系の「Jetstar」だ。 LCCの特徴は、安い航空運賃を生み出すためのコスト削減と機内サービスの有料化だ。Jetstarでも、機内食やブランケットは有料だし、モニターもなくシートピッチも狭い。自分は機内食を頼まず、ペットボトルとパンを買って搭乗した。ただ、アルコールは、機内持込みはOKだが持ち込んだら飲んではダメ。ただ、機内でお金を払って頼んだアルコールは飲んでもOK、という、ずいぶんと会社に都合のよいルールがある。男性乗務員がイヤホンの配布などキャビンアテンダントの仕事をこなし、またその乗務員もオーストラリア系、中国系、東南アジア系と多国籍だ。 20:15、Jetstar・ケアンズ行きが成田空港を出発。一路南へ飛行を続ける。窓越しに見える翼にはずっと月の光が反射する。これも南行路線の特徴か。座席は狭いが耐えられない程ではない。旅の準備の疲れもあって、早々に寝入る。 翌12月28日早朝4:45、オーストラリア・クィーンズランド州のケアンズ空港へ到着。ケアンズの時差は東京+1時間、つまり日本時間で3:45なので、当然眠い。次のフライトの搭乗口がある国際線ターミナルへと向かう。同じ方向に進む人はそれなりにいたのだが、ほぼすべての人がシドニー行きの搭乗口へ向かい、6:00頃には飛行機へと消えていった。次のフライトまで約7時間、まずはすっかり人のいなくなった待合ロビーのベンチで横になり仮眠する。 朝食を取り、免税店を冷やかしながら時間をつぶし、ようやく12:45、Jetstarのダーウィン経由シンガポール行きに搭乗。約2時間半のフライトの後、14:40、ノーザンテリトリー(北部準州)の州都、ダーウィンの空港に到着。今日は、これから車を借りて、近くのリッチフィールド国立公園へ向かう予定だ。<つづく>
2011.10.10
コメント(2)
-

西オーストラリア・ピルバラ 灼熱の大地 その1
震災以降のことをまとめようと思っていたのですが、まだまだ時間がかかる感があります。一方、先日「はまセン」のメンバーで飲んだ時、オーストラリアを縦断する「スチュアート・ハイウェイ」を車で旅した方の話を聞いて、オーストラリアの話を書いてみようと思い立ちました。 しばらくお付き合い下さい。 自分にとって未踏の大陸、オーストラリア。日本人にとって人気の外国の一つであり、英語が公用語である上、コアラやカンガルー、グレートバリアリーフやウルル(エアーズロック)など、大自然を満喫できる観光地の知名度も高く、心理的距離感も近い国だ。 とはいえ、ケアンズ、ブリスベン、シドニー、メルボルンといった主要都市は東海岸に集中し、西海岸で名の知られた都市はパースぐらいだ。ましてや、オーストラリア西北部といったら何があるのかも想像しづらいし、「Pilbara」という地域名など耳にすることはほとんどない。「Pilbaraに行ったんですか?! オーストラリア人でも行ったことのある人は珍しいんですよ。」と連邦政府関係の方から言われた。「え?仕事じゃなくて個人的にPilbaraに行ったんですか? おたくの職場には面白い人がいるなあ!」と資源関係で働いている方にも言われた。「その旅行は仕事なの?プライベートなの? 自分も一度は行ってみたいと思うけれど、プライベートで行くのなら何をしにPilbaraに行くの?」と南オーストラリア州出身の英会話の先生にも言われた。http://iguide.travel/Pilbara/Getting_There#/Gallery 「今しかできない旅」を自分は大事にしている。そして、いわゆる「観光地」よりも、一般旅行者があまり行かないような地域を旅する方が好きだ。たしかに、きっかけは仕事かもしれないが、そんなきっかけでもなければまず旅しないであろうエリア。そして、相当広大なエリアにもかかわらず、分厚い『地球の歩き方 オーストラリア』でも1ページしか紹介されないのがPilbara。自分にとってプライベートの旅をする条件は十分整っている。 そんなPilbaraと西オーストラリアに、2010年の年末、行ってみることにした。日本は真冬だが南半球では真夏、しかも年間降水量300mmという砂漠地帯へと向かう。<つづく>
2011.10.09
コメント(6)
-

気仙沼物産展@銀座
今日は東京も良い天気。東急不動産が企画している、銀座の気仙沼物産展に行ってきました。会場は銀座TSビル。数寄屋橋の阪急が入っているビル、という方がわかりやすいかもしれません。三陸特産の「ホヤ」をモチーフにした気仙沼市の観光キャラクター「ホヤぼーや」が銀座にやってきました。ちなみに、ベルトはホタテ、剣はサンマ、と気仙沼色満載。 2階ではさんまのつみれ汁が振る舞われていました。明日9日はふかひれスープ、明後日10日はマグロ丼とか。 同じ2階では、三陸新報社の写真展も。震災後何度も訪れて見慣れて来た気仙沼の街。その街が津波に飲み込まれている写真を見ると、やはり涙が溢れてきます。 1階では物産展。海産物やお菓子など気仙沼産品が並び、なかなか盛況です。 自分もいくつか買いました。 「ミートよねくら」の気仙沼ホルモン。気仙沼ホルモンは地元の方に人気で、バーベキューでは欠かせず、一人1kg計算で買うとか。気仙沼のいかの塩辛は、気仙沼独特のレシピがあるらしく、気仙沼に行ったときはいつも買いたいと思っていたのですが、冷やして持ち帰れないのでいつも断念していました。ここで手に入るとは。 大島のゆずを使ったポン酢しょうゆ。大島のゆず畑が目に浮かんできました。復興はまだこれからです。このような企画を通じて、東京の中心部で震災の風化を防ごうと情報発信することは大きな意義があると思います。近くをお通りの際は、お立ち寄り下さい。
2011.10.08
コメント(2)
-

十三
大阪・梅田から阪急電車で1駅の十三。駅西口には、昔ながらの横丁がある。以前、ここにあった串カツ料理屋さんの「珍寿」に何度かお世話になったのだが、残念ながら店をたたまれてしまった。代わりに立ち寄った焼き肉店「珍牛」ホルモンが美味かったのだが、メニューには10種類くらいある和牛ホルモンが現在手に入るものは4種類しかないという。手に入り次第入れてくれと卸には言っているのだが、全然届かない、とのこと。ホルモンはそもそも絶対量が少ないところ、昨今のホルモンブームで品不足になっている、ともいう。
2011.08.21
コメント(4)
-

気仙沼市大島 ボランティア その10
昨日大島を離れ、帰京しました。大島、浦の浜港。夕方の満潮時、土嚢袋で浸水を食い止めていますが、溢れだすように陸が海水に洗われる場所もあります。到着した気仙沼港、海水は、どこかの排水溝を通じて逆流しているのでしょう、港の陸側に海水がたまり、タクシーは水深10cm程度の「潮だまり」の中で待機していました。何m嵩上げするのか、そして何m高さがあったら住居を建ててよいのか、まだ何も決まっていない、と大島の方はおっしゃっていました。 生活する術を失ったまま、「あと10歳若ければなあ、でもこの年じゃ、新しく何か始めるなんてできないよ、、」と語り続ける方。 毎年学校に贈っている柚子に想いを馳せ、「柚子の数だけ人に支えてもらっているような気がして・・・」とせきを切ったように話し始める方。 津波で仕事を失い、親族も失い、畑が潮をかぶっても、「この島は自衛隊とボランティアに救われたんだ」と語って、表土が残った部分で夏野菜を植えて育てる方。 「津波で床下が洗われただけで「半壊」扱いなのに、地震の揺れで屋根瓦に大きな被害が出ても「一部損壊」だなんてこんな不公平ある?」と家の修理を続けながら憤る方。復興どころか、生活の回復も瓦礫の撤去も間々ならない、これも東日本大震災の現状です。だからこそ言いたい、「震災は、まだまだ終わっていません。」
2011.08.15
コメント(1)
-

気仙沼市大島 ボランティア その9
今日のボランティア活動は、暑さとの闘いでした。活動は、沢の瓦礫撤去。沢に瓦礫が散乱していると、大雨のとき水がはけず、洪水被害の原因になります。表面上、瓦礫は撤去されたように見えますが…実は沢の左岸、津波で瓦礫が押し寄せた後に斜面が崩れたのか、草の下に漁具やサッシなどが埋もれているのです。沢には深みもあり、足場が悪く作業は難航、トラックを使って引き上げた瓦礫の一部、それは洗濯機でした。大島・浦の浜で津波により陸上に打ち上げられたフェリー、5ヵ月を経て、海へ戻ろうとしています。一歩一歩、復興に向けた歩みは進んでいきます。でも、まだ震災は終わっていないのです。
2011.08.14
コメント(2)
-

気仙沼市大島 ボランティア その8
今日は朝から快晴、暑くなりました。昨日に引き続き、同じ現場で瓦礫を処分場へ運搬する作業を続けつつ、地震で流れが淀んでしまい池ができたところに沈んでいる瓦礫の撤去作業です。大島も地盤沈下の被害はひどく、海岸線を砂利や土嚢袋、瓦礫の瓦まで使って海水の浸水を防いでいます。それ程に、海面と地面の差がなくなっているのです。震災は、まだまだ終わっていません。
2011.08.13
コメント(0)
-

気仙沼市大島 ボランティア その7
今日は3名加わって8名の活動。谷筋の林に散乱した瓦礫の撤去作業です。日陰のおかげで体力を消耗せずにすみました。途中からハチが出没、一同肝を冷やしました。幸い、刺されることもなく、午後には、重機で出来ない瓦礫処理はやはりあります。でも、もっと大事なのは、活動を通じて、被災された方々に「気持ち」を届けることなのだろう、とと思います。震災はまだまだ終わっていません。
2011.08.12
コメント(2)
-

気仙沼市大島 ボランティア その6
今日からは、はまセン時代の有志が集まり、団体として大島で活動します。今日の活動場所は、津波で根元から傾いてしまい畑が使えなくなってしまったお宅で、その木の撤去です。ボランティアとして参加している植木職人の方が手際よく木を刻んでいきます。今日は震災5か月目、14:46、黙祷のサイレンが島に響きます。海に向かって黙祷。サイレンは1分で終わりました。でも、親族の方を津波で失われ、畑も被害を受けた依頼主の方は、終わっても暫くの間、じっと海を見続けていました。あの穏やかな海が、今いる場所のはるか頭上まで襲ってきたのです。まだまだ震災は終わっていません。
2011.08.11
コメント(0)
-

気仙沼市大島 ボランティア その5
今夜から再び気仙沼市大島へボランティア活動に向かいます。携行荷物。バックバックの重さ約20キロ。今日は友人の車に同乗させてもらうので助かります。
2011.08.10
コメント(2)
-

気仙沼市大島 ボランティア その4
昨日の現場がヘビーだったせいか、昨日から継続して大島へ向かうメンバーはわずか3名。自分も疲れが残っている。足の指が筋肉痛なのには驚いた。ぬかるんだ田んぼでバランスを取っていたせいだろう。班が2つに分かれ、自分は軽トラでの瓦礫運搬を頼まれたので、昨日の現場は2日間大島で行動を共にしたボランティア仲間にお願いした。2日がかり、のべ36名で主に瓦屋根があった田んぼ1枚がようやくキレイになったようだ。ただ、潮をかぶった田んぼはすぐには使えない。菜種を植えるのも一つの方法らしいが、なんらかの方法で塩抜きをしなければならない。まだまだ手間と時間とお金がかかるだろう。ところで、気仙沼はカツオの街でもあります。港も一部復活し、カツオは旬を迎えています。東京で食べるのとは本当に味が違ってとても美味しい!漁業の街、気仙沼に魚を食べに行くのも一つの復興支援の形ではないかと思います。
2011.08.01
コメント(0)
-

気仙沼市大島 ボランティア その3
今日は現場のリーダーをさせてもらったので、現場の写真はありませんが、帰りのフェリーで1枚ちょうどカモメの向こう側、自分たち以外のグループですが、活動させてもらった家の方々が、フェリーに向かって手を振って見送ってくれる。ボランティアの方も精一杯手を振って返す。温かい島です。
2011.07.31
コメント(2)
-

気仙沼市大島 ボランティア その2
瓦礫の整理、まだまだ進行中です。
2011.07.30
コメント(0)
-

気仙沼市大島 ボランティア
まだまだ震災は終わっていません。
2011.07.17
コメント(2)
-

気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター その7
気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター 通称「はまセン」は、6月12日(日)まで活動を続けています。→南三陸町(旧歌津町)名足地区での活動を行うため、6月26日(日)まで活動が延長されました。詳しくはサイトを御覧下さい。気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター はまセン 自分は、昨日で「はまセン」における活動に終止符を打ちました。数えればいつの間にか計7回、16日間。今までこれ程長い間ボランティア活動をしたことは、ありませんでした。それだけ、小泉浜の地域、小泉浜の皆さんに対する思い入れが強くなっていったわけで、もちろん、今週末の「交流会」で小泉浜のみなさんといろいろお話したい、そういう気持ちはことのほか強いものがあります。 ただ、どこかで「自分の生活との両立」に折り合いをつけなければいけないのも事実で、残念ながら今週末の「はま行き」は断念せざるをえませんでした。 帰ってきてから1日経って、東京で普通に通勤電車に乗っていても、小泉浜のみなさんの顔や、ボランティア活動での様々な場面が思い浮かんできます。昨日の別れよりも大きく、寂しさを感じているのかもしれません。 被災地では、まだまだ震災は過去のものではありません。今でも震災と闘っていらっしゃる方々が大勢いらっしゃいます。世間では放射能や停電が話題の中心になっている感がありますが、震災・津波被害は今も続いており、日本全体で息の長い支援が必要なのだ、ということを微力ながらも発信していければ、と思っています。その意味で、少しボランティア活動を振り返ってみようと思います。
2011.06.06
コメント(0)
-

気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター その6
気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター、通称「はまセン」では、ボランティアの力で瓦礫を整理していきますが、瓦礫を仕分けしているとき、被災者の方々の写真やアルバム、通帳、位牌など大切なものが出てきたら、「思い出の品」として避難所のテントで保管しています。 先日の日曜日、地域の方々のお力を借りて集落別に分類し、ホールに並べて、地域の方々に見ていただきました。 ある被災者の方からは、「見つかってよかったぁ。本当にありがとうございました!」と弾むような声が上がりました。 ボランティアに来た方々の「被災者のために役に立ちたい!」という気持ちを大事にして、1日でも半日でさえも、活動していただいています。活動期間の長短に関係なく、そのような被災者への気持ちの結晶の一つが、この「思い出の品」です。 その「思い出の品」が持ち主に戻り、感謝の気持ちを表していただける。拾われた方はこの被災者の方と挨拶することはなかったでしょうが、直接でなくても時間を超えて、相手を思いやる気持ちと気持ちが出逢えたのです。 思わず涙がこぼれそうになりました。 ただ、ホールで探した後、こう言って去っていく方もいらっしゃいました。 「俺の探してるものは、やっぱり太平洋の海の底に行っちまったんだよな。」 残念ですが、これも現実です。 気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター、通称「はまセン」は、6月12日までボランティアを募集しています(活動期間延長)。どこに行こうかと迷っていらっしゃる方は、是非お越しください!◆ 気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター
2011.05.18
コメント(1)
-

気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター その5
浜区避難所には水道が復旧しました(^O^)とはいえ、水圧は十分でないようですが。。電気の復旧作業も急ピッチで進んでいます!とはいえ、まだボランティアのみなさんまだ活動する場所はあります。5月29日までボランティアを募集しています!
2011.05.14
コメント(2)
-

気仙沼市 小泉浜 災害ボランティアセンター その4
気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンターで活動してきました。 ボランティアのみなさんの熱い気持ち、受け容れてくださる地域のみなさんの温かい気持ち、その気持ちが一つになったとき、一人一人の力は小さくても、大きな力が生まれて、一緒に小泉浜地区を支えていきます。 GWには600人近い方が集まり、作業は一気に進展しました。けれども、まだ手が届いていないお宅は多くあります。被災地が広範にわたることが、今回の震災の特徴なのです。 小泉浜災害ボランティアセンターは、5月29日まで活動を続けています。GWを過ぎて活動人数は少なくなっています。平日休日問わず、ボランティアを募集していますので、是非お越しください!。そして、浜地区の再生を地域の皆さんと一緒に目指していきましょう!◆ 気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター
2011.05.10
コメント(3)
-

気仙沼市 小泉浜災害ボランティアセンター その3
ボランティアのみなさんがたくさん集まっていただいたおかげで、小泉浜がどんどんキレイになっていきます。まだまだ人手が必要です。気仙沼市 小泉浜災害ボランティアセンターへ御連絡ください、お越しください!
2011.05.01
コメント(0)
-

気仙沼 小泉浜 災害ボランティアセンター その2
4月23日に気仙沼市の小泉浜災害ボランティアセンターに入ったのだが、そのときの行き方は公共交通機関だった。 新幹線の運行は福島まで。その先、一関まで普通列車で到着は22時40分頃。もうその先の列車はないので、一ノ関駅の東口付近でテント泊。翌朝、通常運転の大船渡線に乗り、気仙沼へ。 気仙沼駅前の道を500m程下りT字路にぶつかった近くの三日市バス停から、宮城交通の本吉体育館行きのバスに乗る。1日3本。最初はそれほどの被害を感じなかったのだが、10分もすれば凄惨な景色へと変わる。 道路だけは整備されたが、後は瓦礫。窓から横を見れば、1か月経っても瓦礫の山で、トラックや船が散乱する。気仙沼線の線路はめくれあがって、線路の下にあるはずの枕木が線路の上にくっついている、つまり線路が180度ねじ曲がっている。修復の痕跡はどこにもない。 そう、震災は、未だに終わっていない。 これだけ広い被災地、支援の手は、まだまだ長期間にわたり継続的に必要だと感じる。 このバス、運賃箱で釣銭が出ませんでした。きっちり払いたい方は小銭を十分に用意してください。お釣りは寄附、でも結構だと思います。 本吉体育館からは、気仙沼市小泉浜地区の被災者の方が迎えに来てくれてボランティアセンターにたどり着くことができました。本当にありがとうございます。 ただ、このルートで来られる方、4月23日現在、本吉発気仙沼行きのバスは13時台が最終なので、帰り方は十分検討してください。 小泉浜災害ボランティアセンターでは、ボランティアが不足しています。GWに東北へボランティアへ行こうと思われている方は、是非次のサイトをご覧になってください。気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター(はまセン)
2011.04.27
コメント(3)
-

気仙沼 小泉浜 災害ボランティアセンター
被災者のために何かできることはないかという思いが募り、先週末、気仙沼市にあるボランティアセンター、「気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター」、通称「はまセン」で活動してきた。 小泉浜地域は、気仙沼市(旧本吉町)の南端、南三陸町との境にある集落で、被災者が300名程、そのうち避難所生活をされている方が70名程の小さな農漁村集落だ。 「津波が軽く15mはいきましたよ」と言う。たしかに「なんでこんな標高のビニールハウスがめちゃめちゃになっているの?」という高さにまで津波が到達している。 何より驚くのは、道路は復旧しているものの、それ以外はほとんど瓦礫が手つかずなのである。この光景は、気仙沼市から5kmも離れない所から延々と10km以上にわたって続いている。 小泉浜地区は、気仙沼中心部からも離れ、いまだに公共交通機関ではたどり着けず、電気・水も復旧していない。学校などの基幹施設もないため、仮設住宅の建設は一番遅くなるのではないか、とも予想される。 そこでボランティアセンターを立ち上げたのが川上さんだ。しかし、交通が不便なことや、ボランティア情報の発信が最近のせいか、ボランティアが集まらない。先の日曜日、活動者は合計で10名弱。それでも、若い女性から年配の方まで力と知恵を合わせて、1軒の被災者宅の瓦礫を、なんとか仕分けて山積みするところまで活動した。 写真は、3mぐらい上段の平地から撮影。手前から奥に向けて斜面となっているが、活動前はこの斜面の地肌が全く見えない程に木材、雨で水を吸った畳、ふとん、仏壇、ノート、ガラス、家族の記念のもの、瓦、丸太、漁船の網、ブイなど多種多様のものが積み重なっていた。当初は、重機がなければ整理は無理ではないかと思っていたが、10人の力が合わさると、なかなか威力を発揮する。 そんな小泉浜ボランティアセンターだが、大きな被害を受けた方々がたくさんいらっしゃり、被災者のニーズが多いのに対しボランティアが不足している。現地でお会いしたボランティアの方から聞くところによると、石巻や南三陸など大きなボランティアセンターでは、ボランティアの方が多く集まってしまい、なかなか十分な活動ができないという実態もあるようだ。 GWに東北へボランティアへ行こうと思われている方は、是非次のサイトをご覧になってください。気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター(はまセン)
2011.04.26
コメント(0)
-
がんばろう日本! 応援しています、大船渡!
大船渡市は、リアス式海岸の一部である大船渡湾に面した漁業が盛んな街。セメント産業も賑わう。その湾内の最奥部にあるのが、盛(さかり)という街。 盛は、自分が初めて一人で寿司屋に入った街。陸前高田、気仙沼と旅した途中、盛駅前で、どこか夕飯を食べるところを探していたところ見つけたのが一軒の寿司屋。といっても、当時は高校生、値段の書いてない寿司屋で寿司を食べる勇気もお金もない。それでもそこに入ろうと決めたのは、1,000円以下の釜めしがある、と書いてあったからだ。 店に入ると客は自分のみ。3,4名が座れるカウンターに座ると、店主が出て来た。「何にしましょう!」 「釜めしをお願いします。。」 がっかりした顔をして調理場に入っていった顔が忘れられない。。 今度こそは、海の幸と岩手の酒を楽しみにして、復興した盛を訪ねたいと思います。大船渡の復興を、心より祈念しています。 大船渡のみなさん、遠くからですが応援しています!◆ 大船渡市への義援金情報はこちらへ
2011.04.17
コメント(0)
-

がんばろう日本! 応援しています、陸前高田!
唐桑のユースホステルに泊まった次の日は、岬を巡った後、大島へ渡り、鳴き砂で有名な十八鳴浜で遊び、気仙沼から陸前高田へ向かった。宿は陸前高田の高田松原の中にある、陸前高田ユースホステルにしたが、遅い時間だったので、ペアレントさん(各ユースホステルの運営者のこと。)が陸前高田駅に出迎えてくれて、駅から夕闇迫る市内をユースホステルまで車に乗せてくれた。 暗くなり始めた海辺に一際輝いて建つ大きなホテル、「あれが千昌夫が建てたホテルだよ」とペアレントさんが教えてくれた。そう、陸前高田市は千昌夫の出身地。ホテルの名は「キャピタルホテル1000」で、「千」にひっかけたネーミング。時はバブルがはじけるかどうかの時代、千昌夫は「不動産王」の名を欲しいままにしていた頃だ。 ユースホステルに着き、夕食を食べた後、お茶を飲みながら同宿者と話していて、自分が東京に住んでいるのだというと、たしか東北のどこかから来たという自分よりも年輩の彼が、そのことをとても羨ましがった。 自分は、「東京は空気も悪いしうるさいし、物価も高いし住むのにはよくないところだ、こういう自然の中で暮らせる方が羨ましい。」と率直な感想を述べ、「東京のどんなところがよいのか」、と逆に尋ねた。 その彼は、「東京では様々な、そして最新のコンサートやライブや美術展を見ることができる。東北ではせいぜい仙台で少し遅れて見られるかどうかだ。わざわざ東京に出かけていかなくても、ちょっと散歩する程度の距離でそれらを楽しむことができるのだから。」、と諭してくれた。 その当時、自分は「コンサートやライブや美術展」のいずれにも縁遠かった旅青年だったので、そういう見方を知ることで視野を広げる機会となったが、その価値までは当時共有できなかった。 その後自分も歳を重ね、さまざまな経験を積み、彼の価値観は十分に共有できるようにはなった。東京で見られるライブ、芝居、美術展、それが東北で同様に見られるか、といえば、現在でも難しい。 ただ、海や山の豊かな自然の中で暮らせることが羨ましいという価値観、それは自分の中で当時も今でも変わっていない。そして、こういう今だからこそ、その価値観の大切さを日本の中で大事にしていかなければならないのだと思う。◆ 「1本残った「希望の松」 陸前高田市の高田松原」(2011.3.30 産経ニュース) 豊かな自然、美しい海岸と共に生活する街、陸前高田の復興を心から祈念いたします。 陸前高田のみなさん、遠くからですが応援しています!◆ 陸前高田市への義援金情報はこちらへ
2011.04.16
コメント(0)
-
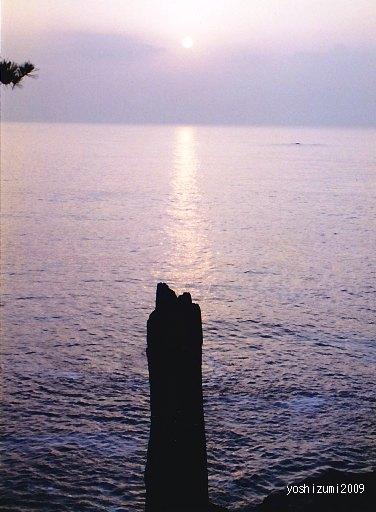
がんばろう日本! 応援しています、気仙沼!
気仙沼を初めて訪れたのは、高校生のとき。初めて一人旅というものに触れてから間もない頃で、「青春18きっぷ」と「ユースホステル」を使って、日本の中の未知の自然や社会や人に触れることがたまらなく面白く感じていた、そういう時期だった。 金はないが体力と時間はあり余っていて、東京から気仙沼まで普通列車の旅。途中、一ノ関駅では、以前新幹線で来たときにみすぼらしく見えた立ち売りの駅弁屋が、普通列車で来るととても頼もしく見えたりして、今思うと、そうやって社会の視野を少しずつ拡げていく過程だったのかもしれない。 気仙沼は漁業の街。マグロやカツオの水揚げも多く、唐桑半島には「唐桑御殿」(まぐろ御殿)とも呼ばれる、漁師たちの立派な家が建っているほか、気仙沼湾内では牡蠣の養殖も盛んだ。 その気仙沼についたのはもう夕暮れどき。港から船に乗って暗闇の気仙沼湾を渡り、唐桑半島の小鯖に着いて唐桑YH(ユースホステル)で宿泊。翌早朝、同宿者と一緒に近くの太平洋岸の景勝地、「巨釜(おおがま)・半造」へ日の出を見に行った。 柱のようにそびえるこの高さ16mの石、「折石」と呼ばれる。その名の由来は、明治29年、三陸大津波が沿岸を襲った際、この柱のような石の先端2m程が折れてしまったからだという。 当時、こんな高いところに波が来る、ということにまったくリアリティを感じなかったのだが、三陸大津波以上という今回の津波であれば、あの「折石」も無事では済まないだろう、と思っていた。ところが、、、◇ 「折石」津波に耐え勇ましく (2011.4.9 河北新報) 今回の大地震を乗り越え、度重なる津波にも耐えて、海に向かって以前のように雄々しく立ち続けている、というのだ! これから復興へ向けて、大小さまざまな「波」が被災者の方々の前に姿を現すことになるかもしれませんが、どんな「波」が来ようとも、折れずに立ち向かっていけば、やがて「波」は必ず穏やかになってくるはずです。そんな自然のシンボルと共に、室根の森に育まれた豊かな海が気仙沼に再び戻ってきますよう、1日も早い復興を心から祈念しております。 気仙沼のみなさん、遠くからですが応援しています!◆ 気仙沼市への義援金情報はこちらへ
2011.04.10
コメント(0)
-
がんばろう日本! 応援しています、石巻!
かれこれ10数年前、免許を取得し初めてレンタカーを借りて両親を乗せたドライブに出ようと向かった先が石巻。仙台から仙石線に乗り、元日の陽光煌めく松島湾の光に照らされながら石巻駅に到着し、レンタカーを借りた。 免許取得後、何度か友人と一緒に運転したことはあったが、親を乗せるのは初めてで、土地勘もない不慣れな道を海沿いに北上、女川付近で右折して牡鹿半島に入った。 道は入江を巡りながら曲がりくねって進む。ある入江の港近くには、大量の牡蠣殻が山積みされていた。そう、この牡鹿半島は牡蠣の養殖が盛んな地域だ。 やがて、半島の背骨にあたる峰を貫く「牡鹿コバルトライン」を進み、役場のある牡鹿町(現石巻市)の中心、もうすぐ半島の先端、という街、鮎川に着いて車を下りた。 ここ鮎川には、金華山(島)への船が発着する港がある。元日の参拝客で人出があり、元日でも活魚料理の店が開いていて、その1軒に入った。ここ鮎川は捕鯨の町でもある。その店では鯨や牡蠣、季節は外れるがウニやホヤが食べられた(いずれも自分の大好物)。この豊富な海の幸は魅力的で、数年後、衝動的に再訪したこともある。 船で金華山に渡り、黄金山神社、そして親父と山頂まで登った。黄金山神社、そして金華山は、古くから修験者が訪れる信仰の山である。港の売店で、当時自分の属していたグループがちょうど寄付金集めをやっていたので、金色のまねき猫を買って帰った。読んで名の如く、この神社は金運開運で名高いのだ! 近いうちに、また穏やかな海が石巻に戻ってくるでしょう! そして海からの恵みが、被災されたみなさんの支えになる日も遠からずやってきます! 金運、開運をひらいてくれるという黄金山神社が、最も震源に近かったけれど今も健在だというのも一つの復興のシンボルですね。一日も早く石巻が復興されることを、心から祈念しております。 石巻のみなさん、遠くからですが応援しています!* 1口1万円で石巻も含めた三陸の牡蠣のオーナーになることにより、三陸の牡蠣業者の復興を支援していこうという「三陸牡蠣復興支援プロジェクト」が立ち上げられました!▲ 三陸牡蠣復興支援プロジェクトはこちらへ ◆ 石巻市への義援金情報はこちらへ◆ 石巻市災害ボランティアセンターの情報はこちらへ
2011.04.09
コメント(0)
-

がんばろう日本! 応援しています、新地!
数年前、他愛もないことからやけっぱち気分になり、その嫌な気分を晴らすため冒険したくなった。とはいいながら南米に旅するわけにもいかず、ふと上野駅から路線バスで北を目指そう、そう思い立ったことがあった。 週末を何回か使って、福島駅までたどり着いたのだが、そこから北へ向かうバスがなく、やむを得ず阿武隈高地を横断して海岸線へ出た。そこが相馬であり、松川浦だった。 そこから先、バスはないので、とりあえず歩けるところまで歩こうと、北へ向かい歩き始めた。松川浦から少し行くと「新地町」という看板が立つ。右手に相馬港、左手に新地火力発電所という、工場地域の真ん中を道は延びていく。港から発電所へのコンベヤーをくぐり川を渡ると一変、春の香り漂う自然と人の生活が織りなす豊かな風景に変わった。[2007.4] 道は波打ち際をかすめるように北へ続いていく。なぜこんな所を北へ向けて歩いているのだろう、と、ふと旅の始まりを思い返す。[2007.4] 心の負担になっていたことも、春の自然を前にすれば、他愛もないこと。足は疲れはじめていたが、心は清々しく、新たなエネルギーが沸いてくるようだった。 釣師浜の集落を経て、ようやく辿り着いた常磐線・新地駅。駅前の桜の蕾が、ほころび始めたところだった。[2007.4] 春は自然が息吹く季節です。新地でも必ず、草が生え、花咲く季節がやってきます。自分も力をいただいた、新地の草木の生きる力、その力とともに、一日も早く新地が復興することを、心から祈念しております。 新地のみなさん、遠くからですが応援しています!◆ 新地町への義援金情報はこちらへ(新地町HP)
2011.04.03
コメント(0)
-

がんばろう日本! 応援しています、相馬!
首都圏では、春の陽気が訪れ、計画停電も見送られることが多くなり、徐々に生活が戻りつつある。 一方、東日本大震災の被災地では、復興に向けて被災者のみなさんが一歩一歩頑張っていらっしゃることと思う。 美しく元気な地域に戻ってほしい、という復興への願いを込めて、被災者のみなさまへのささやかな応援メッセージを綴りたいと思う。 福島県相馬市、 福島県浜通り北部の中心都市。「相馬野馬追」と呼ばれる騎馬による神事でも有名な街。 相馬駅からバスで20分程海へ向かったところにあるのが松川浦。季節の魚、特に冬は松葉ガニで有名ですね。[2007.4] このように穏やかで、海の豊かな相馬へと復興されることを心から祈念しております。 相馬のみなさん、遠くからですが応援しています!◆ 相馬市への義援金情報はこちらへ(相馬市役所)◆ 相馬市は県外ボランティアも受け付けています。(4月2日現在)
2011.04.02
コメント(0)
-
哀悼の意と復興祈念
東北・関東大震災で命を落とされた方の御冥福をお祈りいたします。 また、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 相馬、新地、女川、気仙沼、陸前高田、大船渡、釜石、宮古と、旅でエネルギーをいただいた場所ばかり。一刻も早い孤立者の救助、怪我をされた方の御回復と街の復興を、深く祈念いたします。
2011.03.13
コメント(0)
-

岡山・北木島の旅 その6
~北木島と畑~大浦から金風呂へ。コンクリート舗装された道は、時に藪の下をくぐるように進み、ときに瀬戸内海の穏やかな海景色が開けながら、それほどのアップダウンもなく、山の中腹を進んでいく。この未開の自然のまま金風呂へ着くのかと思ったら、急に山側の斜面にコンクリート擁壁が現れた。その擁壁の上にあったのは、急斜面に開かれた畑である。畑は雑草に覆われてはおらず、誰かが今でも管理しているようであった。風景に人が加わったとき、そこにはリアリティが増す。少し道を進み、尾根を回り抜けると前方に視界が開けた。谷の向こうにある急斜面の山肌の、この道よりも高く結構山頂に近いところに、わずかな面積ではあるが畑が開かれていた。しかも、その畑の真ん中で、おばあさんらしき人が鍬を振り下ろして耕しているではないか!この島は花崗岩の島だから、保水力のある表土は少ない。だから、たとえ山の急斜面で不便なところであったとしても、畑に向いている土壌があれば、食糧を自給するために開墾したということなのではないのか・・・やがて前方から、カートのようなものに畑道具を入れて転がしながら、おばあちゃんが坂道を登ってきた。この島では、道行く人が自分のような外者でも挨拶してくれる。こちらも人と会えば自然に挨拶するようになっていた。おばあちゃんも坂の上で一息つきたかったのか、自分の話に付き合ってくれた。おばあちゃんは齢80前後か、これから畑に行って芋(さつまいも)を取ってくるという。きっと、これまで通ってきた道の側にあった急斜面の畑のどこかへ行くのだろう。それにしても、立ち話しているこの場所と、おばあちゃんの住んでいる金風呂地区の標高差は70~80m程度。畑道具も運びながら金風呂からの急坂を登って来るのは体力的にも大変だ。「おばあちゃんも、金風呂から坂を登って畑仕事できるんですから、ほんとお元気ですよね。」「いやいや、身体はもうしんどいよ。でもさあ、先祖伝来の畑だから、身体が続く限りは守っていこうかな、とね。」先祖伝来の畑・・・おばあちゃんが口にする「先祖伝来の畑」。急斜面を開墾し、雨で表土が流されたとしても維持し続けてきた先祖の苦労の結晶なのだから、そうやすやすと「捨てる」ことなどできないんだ、そんな心の声が聞こえてくるような言葉だった。おばあちゃんとお別れしたあと、道の山側の斜面にある畑を見た。急斜面の奥の奥、一畝に野菜2,3株をようやく植えられるような場所しかない斜面の上まで、畑が開かれていた。そこまでして食糧を自給しようとしたその島の方の想いが伝わってくるような風景で、強く心を打たれた。そして、この風景は、ペルーの空中都市マチュピチュで、食糧を確保しようと断崖絶壁にまで段々畑を作っていた風景に相通ずるものを感じた。北木島の畑、これは北木島が水に食糧に不自由していた時代の生活の証なのだと思う、きっと。そして、その「歴史の遺跡」を、人々が今もって生活の一部として支え続けていることの素晴らしさを感じて、港をあとにした。北木島、久々に強く印象に残る日本の旅になった。島のみなさん、グルメ北木島のマスター、奥さまに心より感謝申し上げます。良い旅との出逢いに、多謝<北木島の旅日記 おわり>
2009.11.08
コメント(0)
-

岡山・北木島の旅 その5
~北木島の水~翌朝、同宿者が宿の車で大浦港まで送ってもらうと聞いたので、便乗させていただくことにした。島にはタクシーがなく、バスも平日のみと、休日には公共交通機関が全くないので、大変助かる。車のすれ違いもしづらい海岸道をくねくねと右回りに進み、楠集落を経てしばらくすると、湾を取り囲む緩斜面に家並みが続く集落、大浦に入った。大浦港は、笠岡からの船が1日8便(うち5便は高速船)が入港する、北木島の東の玄関口であり、豊浦と同じく郵便局や商店がある集落である。宿のマスターと同宿者に別れの挨拶をして、集落をぶらぶらした。表通りから中へ入ると、山へ向かって軽自動車が通れそうな道が何本かあるほかは、自転車やバイクがすれ違える程度の「路地」が縦横に巡っている。その狭い路地の両側に家がびっしりと並んでいる。しかもその路地は、正確な碁盤目状に作られているわけではなく、くねくね曲がっていたり、次の路地と交差したところで途切れてしまったり、と自然発生的に作られた印象を受ける。大浦というあまり広くはない島の住宅適地に、なるべく多くの人が住めるよう個々の住民が最低限の交通路を残して家を建ててきた結果のようにも思える。では多くの人が住めるよう小さな家屋ばかりかというとそうでもない。敷地は狭いが立派な建物が建っていたり、瓦を載せた木塀で敷地を囲んだ家もあったりで、北木島の過去の財力がこのような家並みを生んだのかと想像する。時間があったらもっと路地を散策して楽しむのだが、帰りの船の時間もあるため、山に向かって歩き始めた。今日は金風呂まで島の西側を歩いていく予定でコースを組んだのだが、宿の奥さんからは「その道は藪をこいでいくような道ですよ」と言われていたし、離島巡りが好きな同宿者からは「人しか歩けないような離島の道って、道が悪かったり蜘蛛の巣が張っていたりで、思いのほか歩くのに時間がかかったりしますよ。」と言われていたので、距離は3km程度なのだが、かかる時間が読めなかったのである。道端にいた島の方々に道を尋ねながら、島の脊梁を越え、水道の配水池を横目に道を下り、丸岩方面への道と分かれて右へ降り、さらに下浦方面への道を左に分けて歩いていく。道幅は自転車やバイクが通れる程度。蜘蛛の巣対策に枯れ木を前方で上下させながら歩いていたが、路面はコンクリート舗装で歩きやすい。こんな良い道はいずれ終わり、歩きにくい山道が始まるのだろうと覚悟していたが、周囲の藪が道に覆いかぶさろうとしていても、路面はコンクリート舗装のまま続いていた。蜘蛛の巣も結構あり、到底多くの人が通行しているようには思えない。それでもなぜコンクリート舗装なのか? 昔の主要街道だったのか、などと答えをあれこれ思案していたところ、路面に直径20cm程度の鉄蓋を見つけ、謎が解けた。「そうか、この道の下には水道管が埋まっているのか!」昨夜、離島巡りをする同宿者が「この島は水に不安がないんですか?」とマスターに聞いた。離島では水を自由に使えるほどの水源がないため、水圧が低かったり水が十分使えないところもあるという。ところが、マスターの答えは意外だった。「この島は本土から海底送水管で水が配られているんだよ」。後で白石島との瀬戸に行ったとき、海岸に次のような三角の標識と看板が掲げてあった。瀬戸の向かい側の白石島の海岸にも、同じ三角の標識が立っている。きっと、このそれぞれの標識を結ぶように海底送水管が布設されているのだろう。あとで笠岡市のHPで知ったが、この海底送水管は昭和57年度に完成したもので、本土から高島、白石島と布設されてきた管が北木島に渡ったところで分岐し、隣の真鍋島や小飛島、さらにその先の島までつながっている。水源は遠く倉敷市の近くの高梁川から取水してきているようだ。金風呂地区の配水池でフェンスに絡んだ蔦を取り払っている地元の人からこんな話を聞いた。「本土から水が来る前は地下水だったけれど、石の工場でもよく水を使うから、水を巡ってしょっちゅう喧嘩してたよね。」本土から水が来たときの、島のみなさんの笑顔が目に浮かぶようだった。そして、都会では蛇口から出るのが当たり前の水、その水が存在することのありがたさを、この島で感じた。<つづく>
2009.11.07
コメント(0)
-

岡山・北木島の旅 その4
~グルメ北木島~ そもそも、北木島に来たのは、宿泊先「グルメ北木島」をネットで見つけたのがきっかけであった。 都会育ちの自分にとっては「離島へ行きたい」という冒険心溢れた「旅欲」とも言える欲求があったのに加え、「瀬戸内の美味しい魚が食べたい」という「食欲」も溢れており、ちゃっかり両欲を満たしてくれるような場所を探していた。 笠岡諸島は旅欲を十分満たしてくれる場所だが、瀬戸内海の真ん中にあるにもかかわらず、食事を売りにした店や宿をネットで探しても、意外に少ない。「新鮮な魚で日本酒を一杯・・・」という食欲が暴走し始めた頃、食事を売りにしている宿、「グルメ北木島」を掲示板やクチコミで見つけたのであった。 豊浦港から北へ10分程度、立ち並ぶ石材作業所を横目に見ながら歩くと、白い建物のグルメ北木島が見えてくる。マスターの奥さんに迎えられ、2階の海側の和室に案内された。前方と右方の窓から穏やかな海と白石島と本土が見える。海に近いけれども穏やかなせいか、波の音はほとんど聞こえない。水がきれいなせいか、磯の香りもしない。車の往来もほとんどなく、たまに鳥の鳴き声が聴こえる程度で静かだ。 風呂は別棟にあり、島にあった石で作ったという石風呂である。風呂も大きく、石の感触が心地よく気持ちいい。 夕暮れの時間になった。宿から2,3分岸壁を歩いた。夕陽が間もなく白石島に落ちようとするところであった。 刻々と太陽が沈み、雲が動き、空の色調が変わっていく。低層の雲が燃えるようなオレンジ色に染まる一方、高層の筋雲はいまだ白く凛としている。天空は徐々に夜の蒼さが増していく。1分として同じ景色はない、素晴らしい地球の贈り物だ。 さて、宿に帰れば夕食である。クチコミでは、夕食の量が多いとあったので、風呂あがりのビールを我慢してテーブルについたのだが、大正解だった。 お刺身、焼き魚、煮魚、酢の物、陶板焼き、土瓶蒸し、唐揚げ等々・・・どれも素材が良く、調理も和食の趣向あり、フランス料理の趣向あり、マスターのこれまでの経験がにじみ出たものだと思われ、いずれもとても美味しかった。 途中でマスターがやってきて、他の同宿者と一緒にいろいろお話した。メニューの準備は2週間前から始めるのだという。天然ものにこだわっているそうで、必要な材料を確保するのが大変だそうだ。そのためにいけすも用意しているのだとか。 マスターは自然体で生活しているとおっしゃっていたが、島にたくさんの人に来てもらいたい、という強い気持ちを内に秘めているような、そんな気持ちが伝わってきた。 それに・・・宿のマスターと同宿者と一緒になっていろんな話をする、そんな雰囲気がとても温かく、楽しい時間だった。ここのところ旅の宿はビジネスホテルや旅館ばかりで、こういう楽しさを忘れかけていた そうやって喋りながらかれこれ2時間、完食しかけたところでマスターが「ご飯は食べる?」と聞いてくる。今から白いご飯は食べられないと遠慮していたところ、隣の同宿者が「昨日は○○めしでしたよ。」と伝えてくれた。「あ、それならいただきます!」「もしかして白いご飯でも出すと思ってたの? そんな芸のないことしないよ~」と気さくに言いながら、調理場へ向かっていく。マスターの心意気を見た気がした。 そして出てきた蛸めしと蟹の味噌汁、満腹でも別腹? 美味しかった! 部屋に戻ると、窓には穏やかな海と白石島にわずかに灯る夜景、空には星。部屋の電気は消したまま、暗闇に目が慣れるのを待ちながら、レミオロメンの「花火」を聞いていた。海岸をイメージしたスローテンポの曲が、このゆったりとした穏やかな景色のBGMとしてハマっていた。至福の時間だ。 朝、明るくなって目が覚め、窓の水滴を拭き取ると、大きな朝焼けが迎えてくれた。【グルメ北木島HP】http://www.kcv.ne.jp/~gurume00/【チームグルメHP】(北木島とグルメ北木島が大好きになった人たちで作るファンクラブのようなものだと思ってください)http://www1.megaegg.ne.jp/~nyanko/index.htm<つづく>
2009.10.27
コメント(2)
-

岡山・北木島の旅 その3
~北木島の秋祭り~ 北木島・豊浦に着いた日、港の近くの広場には大きなノボリがはためいていた。豊浦地区にある豊浦八幡宮で秋祭りが開かれる日だったのである。 でも、祭りの開始時刻13時30分まで少し時間があったので、金風呂方面に歩いていった。岬を回って千ノ浜地区に入ると、今度は「春日神社」と書かれたノボリが立っている。どこだ、春日神社は? と探しながら歩いてもう一つ岬を回って金風呂地区に入ると、山の上の方に春日神社を見つけた。いろいろ飾り付けられているようで、春日神社も今日が秋祭りらしい。 遠くから声が聞こえる。声のする方へ歩いていくと、1基のお神輿と出遭った。 家々の門の前に立ち、オレンジ色のはっぴを着たおばさん達が、扇子を持ちながら何か節をつけて詠んでいる。あるタイミングで男性陣がお神輿を持ち上げ、2度3度と上下に揺らす。これが一つの儀式なのだろう。「全部の家に回っているんですか?」「いやいや、希望する家だけだよ。でも担ぐのに若いモンがいなくてねえ。」といって、「おぅ、あと2軒か~」と疲れた声を出しながら、また別の家へと向かっていった。 豊浦の八幡宮に戻ると、くじを引かせてくれた。午後7時に発表だという。境内にははっぴを着た若者達が集まり、準備万端のようであった。実はフェリー到着後に歩いていると、とある建物の中から「一気コール」が聞こえてきていたので、テンションも準備万端だろう。普段は本土に住んでいる島の出身者が、秋祭りに参加するため戻ってきている様子である。 お神輿には青、赤、黄色の布が巻かれてグループ分けされている。神主さんがお神輿の準備を行う。見物客にはお神酒が振舞われ、用意が整うと、音頭を取る3人が前に出てきて、扇子を片手に唄を始める。唄が終わると、3つのお神輿をそれぞれ担ぎ上げ、円状にぐるぐると回り始める。そのうち、1基のお神輿がダッシュし始めた! みんなが円状になって前のお神輿を追うようにグルグル回る。狭いところでやっているので、遠心力に負けて脱落したり転んだりしている。大の大人がやっているのだから、なかなかの迫力で勇壮だ。15秒くらい続けると、一旦終了する。が、境内でこれを6回繰り返す。最後はグルグル回った勢いで鳥居をくぐり、豊浦の街の中へその勢いで飛び出していった。 豊浦と金風呂は、船で5分。歩いても15分程度と、島の中では「近接している」といっても過言ではない。そして、どちらの地区もそれほど多くの人が住んでいるわけではない。にもかかわらず、そんな近いところに2つの神社があって、それぞれのお祭りが続けられているというのは、昔この両地区にそれなりの財力があったということの証であろうか。 さて、豊浦八幡宮で引いたくじの結末を見に行くつもりでいたのだが、発表の時間、自分はすっかり「グルメ北木島」の夕食に夢中になっていた。。<つづく>
2009.10.26
コメント(0)
-

岡山・北木島の旅 その2
~石が根付く島・北木島~ 街には様々なところに北木の石が使われていた。特に、この千ノ浜の舟溜まりは、切り出した石の切れ端だろうか、赤みを帯びた小さな薄い北木の石が何重にも積み重ねられて作られていた。石垣が創り出す曲線美も、海や木の色とのコントラストも印象的であった。 このような石垣は、豊浦港の一部にも残っている。また、そう遠くない時代に作られたと思われる岸壁や堤防の下部にも、北木の石が使われていた。 一般的に、石は切り出しや運搬のために費用がかかり、それなりのお金を出さなければ建築資材として使えないものと思われる。しかし、この島の場合、近くから簡単に手に入るのだから、容易には腐らず堅固な素材を使わない手はないだろう。家と道路の境にも何気なく石が積まれていたり、盛り土で作られた宅地の擁壁代わりに使われていたりもする。 金風呂地区にある春日神社には、石像や石が奉納されていた。この石の意味まではわからなかったが、石を奉るということこそ、この島の方々の石に対する思いが現れているのではないか、そんな風にも感じた。 何かと石が絵になる島である。<つづく>
2009.10.25
コメント(3)
-

岡山・北木島の旅 その1
~北木島は石の島~ 友人の結婚式で岡山へ行くことになったので、せっかくの機会だから瀬戸内の島を旅してみたくなった。 離島の雰囲気を味わいたくて、美味しいものが食べたくて、ネットを探して決めたのが、岡山県の西端、笠岡諸島にある北木島である。 北木島は「石の島」とされ、島から切り出された「北木みかげ石」は、古くは大阪城の石垣から、東京の靖国神社の鳥居や日銀本店までにも使われたという。そんな程度の予備知識で、笠岡・伏越港からフェリーに乗り、海のきらめきを楽しみながら北木島・豊浦港に到着し、ぶらぶら散歩した。 豊浦地区から岬を一つ西に回ると千ノ浜地区である。海沿いの県道からそれて集落に入ると、高くて垂直な石の崖が見え始めた。これが石切場(丁場)のようだ。 辺りには機械の音もモーターの音もない。遠く鳥の鳴き声が聴こえるほかは、風の音ぐらいである。崖の下には深緑色の水をたたえた池がある。水面にさざ波が立っているほか、景色に動きはない。赤みを帯びた崖の中段には緑色の大きな松が生えている。山から石を切り出さなくなって長い年月が経過しているようだった。 これだけの高さの山を切り崩していった人の力。今も操業していれば、周囲は活気に溢れ、この崖も人工的な尖った景色に見えただろう。でも、静寂に囲まれ、人工物が自然に同化しつつある風景に心が魅かれ、しばらくその場を立ち去ることができなかった。 集落には、石を切り出すための機械を扱う商店があった。こちらも店をたたんで長い年月が経っているようだった。現在、島で石を切り出しているのは1箇所のみ、しかも山ではなく地下200~300m近く掘り進んでいるという。あの静寂に囲まれた池も、地下へ掘り進んだ穴に雨が溜まって出来たものだと後から聞いた。近くの空き地には、切り出した岩が無造作に置かれ、蔦が絡まっていた。 白石島との瀬戸の近くに、こんな句碑があった。「切り出す 石は生きもの 山眠る」 今詠んだら、「切り出す 石は眠りて 山静か」であろうか。 北木の石材業は、中国産石材に押されて切り出しを行わなくなり、それでも石材加工に転換して続けていたが、ここ数年は加工業も厳しくなっているという。 でも、赤みを帯びたこの北木の石には、石の持つ冷たさよりも、何か温かみを感じるのである。そんな石が、街のあちこちに根付いていた・・・<つづく>
2009.10.24
コメント(2)
全45件 (45件中 1-45件目)
1










