-
1

「歴史の回想・宝亀の乱」多賀城。 川村一彦
多賀城(創建当初は「多賀柵」。現在の宮城県多賀城市に所在)は神亀元年(724年)、大野東人によって創建された。重ねて述べるとおり多賀城造営の背景には養老4年の蝦夷の大反乱があり、朝廷の東北政策再構築の一環として構築されたものである。したがって当初より石背・石城両国の再併合後の新たな陸奥国府かつ鎮守府としての役割が期待された。多賀城では郡山遺跡Ⅱ期で確立された都に倣う官衙要素を発展的に継承し、かつ軍事的な拠点性を高め、以降の城柵に大きな影響を与えた。 周囲との比高差がほとんどない郡山遺跡に対し、多賀城は低丘陵上に位置し、仙台平野を見渡せる位置にあった。また、地形上の制約のため外周は歪んだ方形となっており、おおむね敷地中央に、整った方形の内郭が築かれて政庁が置かれた。 塀で囲まれた政庁の周囲に実務官衙や兵舎を置き、更に外周を塀で囲う二重構造城柵は、まさしく多賀城で確立したものであり、以降の城柵の基本様式となる。この多賀城をモデルとして造営されたとみられるのが天平5年(733年)出羽国に築かれた秋田城(第Ⅱ次出羽柵)であり、内郭施設内の建物配置および正殿・脇殿の面積はおおむね多賀城I期と共通する。 ただし、多賀城正殿では四面に廂をめぐらす一方、秋田城正殿では正面の南側にだけ廂を配置し簡素化するなどの差異もみられる。 三重構造城柵の出現 第Ⅲ段階の城柵は、8世紀後半に造営されたもので、新規に築かれたものとしては雄勝城、桃生城、伊治城が挙げられ、同時期に秋田城も改修を受け、出羽柵から改称して秋田城(阿支太城)と称されるようになった。 また、同じく多賀城も大改修を受け、その荘重な装飾性においてピークに達した時期にあたる。先述の通り、雄勝城、桃生城の造営は一度廃止された鎮兵制の復活と軌を一にするものであり、朝廷による征服事業の再始動を示すものであった。 これはまさしく中央において藤原仲麻呂が専権を握り、聖武天皇後期の領土不拡大の方針を放棄して、再度積極的な征服を目指す方針に転換したことによるものである。 この藤原仲麻呂政権の確立に先立つことおよそ20年前、天平5年(733年)の出羽柵の移転北進(=秋田城の造営)の後、天平9年(735年)に陸奥国から出羽柵を最短距離で結ぶ奥羽連絡路の建設が計画されたことがあった。 当時は藤原四子政権の時代であり、藤原四兄弟の一人藤原麻呂が持節大使として多賀城に派遣され、奥羽連絡路建設のためにルート上の「賊地」である雄勝村(男勝村)の制圧が企てられたのである。なお、この時は東国から騎兵1,000人が集められたが、これらの大半は天皇の代理人である持節大使とともに多賀城ほかの城柵の留守番の役割に充てられ、実際の軍事行動は陸奥按察使と鎮守将軍を兼ねた大野東人が、これらの城柵に元々配置されていた常備の軍勢(鎮兵・兵士)を率いて行った。 先述の騎兵1,000人のうち196人が大野東人に預けられ、大野東人は騎兵196人、鎮兵499人、陸奥国の兵5,000人、帰順した蝦夷249人という陣容のもと、奥羽連絡路を開削しながら雄勝村の制圧に向かったのである。 この時の軍事行動は、強硬な侵攻策の非と損失を訴えて寛大な処置を主張する出羽守田辺難波の建言を容れた大野東人が、雄勝村の征服を中止して途中の比羅保許山までの道路開通を成果として撤退し、藤原麻呂もこれを了承したために、一度の戦闘もともなわずに終結することとなった。 この時はあくまで暫定的な侵攻の中止であったが、同年の内に帰京した藤原麻呂が都で猖獗を振るっていた天然痘に倒れて病没し、藤原四子政権が崩壊。聖武天皇が仏教への傾斜を深め大仏と国分寺の建立に国力を傾注する中で、それまで行ってきた征服と版図拡大の方針はその後20年余りにわたって凍結されることとなったのである。 天平勝宝8歳(756年)の聖武天皇崩御の翌天平宝字元年(757年)、自身と結びつきの強い大炊王を立太子(翌年天皇に即位、後に淳仁天皇と諡号される)させ、比類なき権力を確立した藤原仲麻呂は、聖武期後半において凍結されていた本州北東部への征服事業を再始動させることとなる。 この時期に造営されたのが前代に未着手となっていた雄勝城と桃生城であり、陸奥国の浮浪人や坂東諸国から徴発した労働力により造営が進められた。これらの事業を現地にて指揮したのが仲麻呂の四男(三男とも)藤原朝狩である。朝狩は大炊王立太子後の天平宝字元年に起きた橘奈良麻呂の乱の後、奈良麻呂の同調者と目されて変により自害に追い込まれた佐伯全成の跡を襲い陸奥守及び按察使に就任、その後上記は雄勝・桃生の2上使がらみの造営のほか、で羽国に雄勝・平鹿の2郡を設置、陸奥国から秋田城まで7つの宿駅を置き連絡路を開通させた。天平宝字4年(760年)、朝廷では朝狩が雄勝城を一戦も交えずに完成させたこと、それまで蝦夷の領域とみられていた北上川の対岸に桃生城を築き蝦夷たちを驚嘆させたことを称揚して、朝狩に従四位下を授けた[89]。同年に朝狩は多賀城の改修にも着手し、天平宝字6年(762年)に多賀城碑を設置して自らの功績を称揚させている。 この多賀城碑は、それまで多賀柵と呼ばれていた城柵が多賀城と記されるようになった初見である。これは中国風の名称を好んだ仲麻呂政権の性格を反映したものと考えられており、同時期に改修を受けた第Ⅱ次出羽柵も「阿支太城」(秋田城)と記されている。 このように仲麻呂政権では藤原朝狩の指示のもと積極的な政策を展開し、天平9年(735年)に一時中断された征服事業を継承しながら、より発展させていくこととなった。特に桃生城の造営はそれまで約1世紀に渡って暗黙の裡に守られてきた朝廷と蝦夷の境界を踏み越えるものであり、以後急速に高まっていく蝦夷との緊張関係は、最終的に海道蝦夷の蜂起をきっかけとした「三十八年戦争」(虎尾俊哉による命名。後述)を惹起していくこととなる。 このような背景のもと造営されたこの時期の城柵は軍事的な緊張関係を窺わせる構成となっており、桃生城(現在の宮城県石巻市に所在)は比高差80mほどの急峻な丘陵上に立地し、中枢部は政庁を中心とした中央郭に、西郭と住民の住居域を取り込んだ東郭とが取り付く構造となっている。 仲麻呂政権を打倒した称徳・道鏡政権においても強硬な征服政策が引き継がれたことで朝廷と蝦夷との対立は更に深刻化し、東国から送り込まれた柵戸や鎮兵が逃亡する事態を招くこととなった。このような時勢のもと、神護景雲元年(年)に造営された伊治城(現在の宮城県栗原市に所在)では、三重構造城柵という新たな形態がみられることとなる。 三重構造城柵とは、通常の城郭にみられる材木塀ないし築地塀で区画された政庁及び外郭の更に外側にさらに区画施設を巡らし、居住域をも城柵の中に取り込んだものである。伊治城の最外郭は南辺が築地塀である以外は土塁に空堀であり、さらに北辺には土塁を二条巡らしていて、北方の蝦夷からの防御を意識していることが明白である。 この最外郭の内側に居住域が存在し、多数の竪穴式住居が検出されている。この時期には東山遺跡(宮城県加美町)、城生柵跡(同)など、8世紀前半に造営された近隣の城柵も、城外の集落を取り込むように防御施設を巡らして三重構造化していたことが判明しており、先述の桃生城で住居域を城柵内部に取り込む端緒がみられることを考え合わせると、「三十八年戦争」以前に既に城柵周辺の不穏な情勢を窺うことが出来る。 三十八年戦争及び徳政相論以後の城柵 蝦夷と朝廷との緊張関係は、宝亀5年(774年)7月、海道蝦夷が蜂起し桃生城を攻撃するに至り、ついに均衡が破れることとになる。この後2,3年程で急速に情勢が悪化し、蝦夷社会と朝廷との汀であった辺郡ばかりでなく、胆沢・志和・秋田周辺なども巻き込んで陸奥・出羽両国が全面的な戦争の時代に至ったのである。以降朝廷により執拗な征夷が繰り返され、大規模な戦争の最終局面となる阿弖流爲(アテルイ)と坂上田村麻呂の対決を経て、延暦24年(805年)の徳政相論の後、 弘仁2年(811年)の文屋綿麻呂による最後の大規模な征夷まで戦乱の時代が続く。前後の時代とは明らかに様相を異にするこの時代の戦乱を、虎尾俊哉は「三十八年戦争」と命名している。 昭和50年(1975年)に著された虎尾の論は、この戦争を律令国家と「アイヌ国家」との戦争と捉え、蝦夷とアイヌをそのまま同一視するものであり、アイヌ、蝦夷双方の研究が進展した後代においてそのまま認める事は出来ないものだが、宝亀5年(774年)から弘仁2年(811年)までの38年間を戦乱の時代と捉える歴史認識は平安時代初の当時において既に存在しており、「三十八年戦争」の語は今日の学会でもほぼ定着している。 「三十八年戦争」と命名されるこの時代は、征夷の方法によって更に三期に区分される。第I期は、宝亀5年(774年)桃生城襲撃から宝亀11年(780年)覚鱉城(かくべつじょう)造営計画が持ち上がるまでの6年間で、陸奥国・出羽国の現地官人と現地兵力を中心とした征夷が行われていた時期である。 しかし、覚鱉城造営の計画が持ち上がった宝亀11年(780年)、伊治呰麻呂の乱により事態は新たな局面を迎える。第Ⅱ期はその呰麻呂の乱から、桓武天皇の治世末期の延暦24年(805年)に行われた徳政相論による征夷中止の決定までの25年間で、朝廷主導のもと征夷軍が編成され、大規模な軍事行動が繰り返された時期である。延暦20年の征夷で大将軍坂上田村麻呂が胆沢の地を平定。翌年胆沢城の造営に着手し、蝦夷の族長であった阿弖流爲と母礼(モレ)が降伏するに至って、大規模な征夷の時代は終わりを迎えた。 第Ⅲ期は徳政相論から弘仁2年(811年)までの6年間である。先年蝦夷への軍事侵攻に勝利したとはいえ既に国力の限界に達しており、蝦夷政策の転換を迫られていた朝廷側は、疲弊した東国を征夷に関する負担から解放することに主眼を置いた。 弘仁2年(811年)には「征夷終結のための征夷」と位置付けられる文屋綿麻呂による最後の征夷が行われたが、兵力は全て陸奥国・出羽国から徴募されたものであり、その中に朝廷側に帰服した蝦夷で構成される俘軍を含む。その後も不安な情勢はなおも続くが、弘仁2年閏12月に文屋綿麻呂は征夷の時代の終結を宣言し、征夷と呼ばれた軍事活動は史上から絶えることになるのである。
2024年11月26日
閲覧総数 62
-
2

「歴史の回想・宝亀の乱」目次・はじめに・川村一彦
「宝亀の乱」1, 「宝亀の乱の概略」・・・・・・・・・・・・・・・22、 「宝亀の乱の起因」・・・・・・・・・・・・・・・43、 「背景と原因」・・・・・・・・・・・・・・・・・554、 「乱の発生」・・・・・・・・・・・・・・・・・・645、 「征夷使派遣とそれを巡る混乱」・・・・・・・・・676、 「光仁天皇と桓武天皇への戦乱時代」・・・・・・・927、 「出羽国そして渡嶋蝦夷への影響」・・・・・・・・1408、 「秋田城の停廃問題」・・・・・・・・・・・・・・1559、 「天応改元と桓武天皇」・・・・・・・・・・・・・16510、「著者紹介」・・・・・・・・・・・・・・・・・・176 1「宝亀の乱の概略」宝亀11年(780年)3月、突如として呰麻呂は反乱を引き起こすこととなる。当時、政府による東北地方経営を現地で取り仕切っていたのは陸奥按察使兼鎮守副将軍の紀広純であった。按察使とは複数の令制国を管轄して国司を監察する律令国家の地方行政の最高官である。その紀広純が山道蝦夷の本拠であった胆沢攻略のための前進基地として覚鱉城(かくべつじょう)造営を計画し、工事に着手するため呰麻呂と陸奥介大伴真綱、そして牡鹿郡大領の道嶋大楯を率いて伊治城に入った折、呰麻呂は自ら内応して俘軍を率い、まず道嶋大楯を殺害、次いで紀広純も殺害するに至ったものである。大伴真綱のみ多賀城まで護送したが、これは多賀城の明け渡しを求めてのこととみられる。多賀城には城下の人民が保護を求めて押し寄せたが、真綱は陸奥掾石川浄足とともに逃亡してしまった。このため人民も散り散りとなり、数日後には反乱軍が到達して府庫の物資を略奪した上、城に火を放って焼き払ったという。この時伊治城・多賀城ともに大規模な火災により焼失したことは、発掘調査によっても裏付けられている。この反乱の理由として『続日本紀』では、呰麻呂の個人的な怨恨を理由に挙げている。夷俘の出身である呰麻呂は、もともと事由があって紀広純を嫌っていたが、恨みを隠して媚び仕えていたために、紀広純の方では意に介さずに大いに信頼を置いていた。これに対し道嶋大楯は常日頃より呰麻呂を夷俘として侮辱していたために、呰麻呂がこれを深く恨んでいたとするものである。道嶋大楯は呰麻呂と同じく郡の大領であるが、道嶋氏はもともと坂東からの移民系の豪族であり蝦夷ではない。また、同じく道嶋氏からは中央貴族となった近衛中将道嶋嶋足も輩出しており、陸奥国内での勢力は他を圧するものであった。道嶋大楯がつとに呰麻呂を侮辱してきたのもその威を借りたものと考えられ、政府に協力し功績を認められて地位を上昇させてきた呰麻呂にとって耐えがたい屈辱であったと考えられる。一方で呰麻呂の蜂起に同調して多数の蝦夷が蜂起しており、その中には宝亀9年、呰麻呂と同時に外従五位下を賜った吉弥侯部伊佐西古も含まれる。このことはすなわち、事件の原因が呰麻呂の個人的な理由に留まるものでなく、政府の政策に多数の蝦夷が怨恨を抱いていたことを示すものである。また、故地に城柵を設けられて土地を奪われ、自らの一族は労役や俘軍への徴発など負担を強いられてきたこと、更には伊治城造営を主導したのも道嶋の一族である道嶋三山であったことなども、呰麻呂が恨みを募らせた理由として推測されている。呰麻呂の反乱とそれにともなう混乱は、多賀城を文字通り灰燼に帰せしめ、これまでの政府による支配の成果を烏有に帰せしめるものであった。このため政府は「伊治公呰麻呂反」と記して八虐のうち謀反にあたると断じ、国家転覆の罪に当たるとした。しかし、呰麻呂の名はその後の記紀に現れることはなく、その行方は杳として知れない。反乱の翌年に即位した桓武天皇が賊中の首魁として名指ししたのも、上記の伊佐西古を含む、「諸絞・八十嶋・乙代」らであり、その中に呰麻呂の名は見えない。しかしながら呰麻呂の反乱を契機として陸奥国の動乱はより深まっていき、政府から征夷軍が繰り返し派遣される時代が到来することとなる。この桓武天皇時代の征夷には、俘軍の参加は確認できない。呰麻呂自身がかつてそうであったような、政府に帰属した蝦夷が俘軍を率いて協力した時代は、呰麻呂の乱によって転換点を迎え、律令国家と蝦夷が全面対決する局面へと移行していくのである。
2024年11月26日
閲覧総数 52
-
3

「歴史の回想・宝亀の乱」城柵。 川村一彦
〇「城柵」(じょうさく)は、7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷(ヤマト王権、中央政権)が、本州北東部を征服する事業の拠点として築いた施設である。城柵は朝廷が蝦夷の居住地域に支配を及ぼすための拠点となる官衙であると同時に、柵戸と呼ばれる住民を付随する施設でもあり、兵を駐屯させる軍事的拠点でもあるという複合的な性格を有していた。 現代の歴史学では特に東北地方及び新潟県(陸奥国、出羽国、越後国)に置かれた政治行政機能を併せ持つものに限って言うことが多い。城柵は軍事拠点としての性格を有する一方で、中国地方や九州地方に築かれた古代山城と比べると防備が弱く、官衙としての性格が強いのが特徴である。 なお、前九年の役、後三年の役で安倍氏や清原氏が軍事拠点として設置した柵(沼柵、金沢柵、贄柵など)は成り立ちや性格が異なるので、一般的にはここで言う「城柵」に含めない。 城柵は朝廷が本州北東部に支配域を拡げていく中で、その拠点として造営した施設である。20世紀半ばまでは蝦夷との戦争に備えた軍事施設として、城柵を最前線の砦と見る説が強かったが、1960年代以降の発掘調査で城柵に官衙が置かれていたことがはっきりすると、軍事・防衛機能を専一とする旧来のイメージは次第に改められていった。 特に発掘調査の進展は、城柵の重要な構成要素が政庁を中心とした官衙であることを示している。しかし、城柵には軍団兵や鎮兵などの軍事力が常駐していたのも事実であり、官衙のみを重視する一面的な理解もまた適切でない。城柵の性格について政治的拠点と軍事的拠点のどちらを重視すべきかについての議論はあるにせよ、城柵とは律令国家の北方経営において軍政・民政の両面を執行した行政機関であり、西国の古代山城とはその性質を異にする。 一方、発掘調査の進展により、多賀城に代表されるような方形の外郭を持つ官衙的な城柵だけがその全てではないことも明らかになりつつあり、従来の官衙対軍事施設とは異なる別の視座からの対立軸を見出すこともできる。 すなわち、形成史上は多賀城、胆沢城、城輪柵跡などに代表される王権の出先機関として築かれた官衙的な城柵及びその発展形の城柵と、桃生城や伊治城といった移民が集住する拠点であった囲郭集落に起源を持つとみられる城柵という2つの流れを見ることもできるのである。 城柵をめぐる人びと 城柵と公民(柵戸) 律令国家では基本的に郡(大宝律令以前は評を用いた)を基本単位とする国郡制によって地域を支配した。しかし、現在の東北地方北部にあたる蝦夷の居住地域では国郡制が及んでおらず、城柵はこれらの地域に朝廷による支配を及ぼしていくために造営された。 城柵の多くが国郡制未施行、すなわち朝廷の支配がまだ及んでいない地域に造営されたということは、当初城柵の周囲にそれを維持するための経済的な背景が乏しかったことを意味する。したがって通常は城柵の設置と前後してその地域に郡を置き、他地域から柵戸と呼ばれる移民を集住させて、城柵を維持するための人的・物的な基盤とした。 柵戸の移住は城柵の中でも初期に設置された渟足柵、磐舟柵において既に行われており、以降も踏襲され城柵設置時の基本政策となった。郡の設置は朝廷の支配域を城柵という「点」から、「面」に拡げるものであり、柵戸の存在は城柵の維持にとって政策上一体不可分の関係であったと言える。 移民である柵戸は城柵の周辺に出身地域ごとに居住地を定められ、周辺を開墾したとみられている。それを示すように、古代東北の郷名には坂東と共通するものがみられる。同様に越後においても、渟足柵・磐舟柵の周辺で越前国・越中国と共通する郷名がみられた。しかし、柵戸の生活は厳しく、逃亡するものも多かった。移住後定着のために1~3年間調庸などの租税を免除されたが、その後は公民として租庸調、兵士役、雑徭、公出挙などの諸負担を負った。 一方で、城柵が必要とする物資は膨大であり、柵戸の生産力だけで負担できるものでなかった。陸奥国、出羽国が他の令制国と異なる長大な領域を持つのも、北方に支配域を拡げる上で、人的・物的資源を供給するための基盤が必要だったからであり、城柵を拠点とした朝廷による征服事業は、陸奥・出羽のみならず関東地方を中心とする東山道及び北陸道諸国にも多大な負担を強いたのである。 城柵と蝦夷(俘囚) 城柵とは柵戸の拠点であるのみならず、蝦夷の支配という役割も担っていた。これもまた、他の国衙にはみられない城柵固有の役割である。朝廷と蝦夷の関係は端的に言えば朝貢関係をとるものであり、城柵を通じた蝦夷との関係は「饗給(撫慰)」、「征討」、「斥候」の3つの様態に集約された。これは、蝦夷支配のために辺遠国(辺要国とも)である陸奥・出羽・越後の3か国の国司にのみ付与された権限である。城柵をめぐる政策にとって、柵戸の移住と郡設置による「面」的な支配は一体的に遂行されたものだが、同時に城柵を拠点として個別の蝦夷集団と朝貢関係を結ぶ「点」的な支配政策もまた、継続して行われていたのである。 朝廷が本州北東部への征服事業を進める中で、蝦夷とは時に激しい対立をもたらし、最終的に「三十八年戦争」を惹起していくことになるが、その間常に対立関係にあった訳でなく、また軍事的な緊張期にあっても全ての蝦夷と対立した訳ではなかった。 したがって朝廷側に帰属を求める蝦夷の集団も少なくなかったのである。彼らは産物を貢納する見返りとして饗宴を受け、鉄器や布などの産物、あるいは食糧を得たり、朝廷の政策に協力して位階や姓を授かるなどの対価を得た。このような朝貢によるゆるやかな支配は、政治的な上下関係が規定されるものの、両者を一種の経済的な交易関係に結び付けるものであると言えた。 しかし、このような関係は流動的で、いったん利害が対立すると容易に敵対状態にも転じうる不安定なものでもあった。また、経済的な「交易」と表現したものの、両者の関係が対等でない以上、時に略奪に近いものでもあったようである。しかしながら饗給の実施は、朝廷による硬軟織り交ぜた蝦夷支配政策の「軟」の性格をあらわしたものであると言える。 なお、「俘囚」とは朝廷に帰服した蝦夷全般を指す場合もあるが、より狭義には個別に朝廷と服属する関係を結んだ蝦夷のことであり、部姓を与えられて多くは城柵の周囲に居住した。集団で朝廷に服属したものは「蝦夷」という身分として、本拠地の地名+「君」(あるいは「公」)の姓を得(例:伊治公呰麻呂、大墓公阿弖利爲(アテルイ)と盤具公母禮(モレ))、多くは従来からの居住地に留まった。 城柵の設置は、本州北東部における在地社会の再編ももたらしたのである。また、服属した蝦夷の軍は「俘軍」として、しばしば朝廷側の武力として活動したが、前述の通り朝廷と蝦夷の利害関係は流動的であったため、時に敵対する諸刃の刃ともなった。 一方、饗給の実施は、その物資を供給しなければならない諸地域にとって莫大な負担を強いるものであった。 養老6年(722年 )、朝廷は饗給に用いる布を調達するため、陸奥按察使管内(石背国・石城国再併合後の陸奥国と出羽国)を対象に、調・庸を停止して、代わりに一人あたり長さ一丈三尺、幅一尺八寸の布(それまで調庸として貢納していた布の4分の1の面積)を納めさせることとした。これは両国の住民にとって調庸の負担を大幅に軽減させる民力休養策であると同時に、徴発した布は蝦夷に支給する「夷禄」として用いられた。この政策変更の背景には、養老4年(720年)に起きた蝦夷の大反乱(海道の蝦夷が反乱し、按察使の上毛野広人が殺害された。 同年には九州で隼人の反乱も起きている)が挙げられる。史上初めて蝦夷の大反乱として記録されたこの出来事は、朝廷に大きな衝撃を与え、これまで進めてきた征服事業に抜本的な見直しを迫ることとなった。すなわち、それまで中央政府が収奪してきた調庸を放棄し、新たに管内で納めさせた布を全て蝦夷への饗給に充ててまでも、支配の安定を目指したのである。 城柵に駐屯した軍事力 冒頭で記したように、城柵に対する考古学調査の進展は、その基本的な構成要素が官衙にあるとする知見をもたらした。一方で城柵が朝廷による本州北東部征服事業の拠点であり、蝦夷を支配する場としての機能も担った以上、その軍事的な性格も決して軽視できないものである。 律令国家の地方軍制は、軍団を基本とし、それは辺遠国である陸奥国(及び石城国・石背国)においても例外でなかった。軍団に務める兵士は、当該令制国内の公民の中から徴募され、同じく国内の営に配された。養老4年(720年)当時、陸奥国には名取団・丹取団の2団が、石城国には行方団が、石背国には安積団があったと推測され、4個軍団を合わせると4,000人の常備兵がいたことになる。しかしながら、軍団制は交代で勤務(番上)するものであるため、実質的な兵力はその6分の1の670人程度に過ぎなかった。 前掲の養老4年の蝦夷の大反乱は、このような従前の軍団では兵力が全く不足していたことを露呈させ、さらに按察使を介して陸奥・石城・石背の3か国を連携させるプランにも問題があることを明らかにした。したがって、軍団の兵力をより弾力的に運用できるようにするとともに、令外の全く新しい兵制として鎮兵制を導入し、それを統括する機関として、鎮守府を置くことになったのである。 鎮兵制の成立は、神亀元年(724年)頃とみられている。養老4年の蝦夷の大反乱を受けた一連の支配体制の立て直しは、神亀元年体制とも称され、その要旨は前掲の税制の見直しや、石城・石背国の陸奥国への再併合、鎮兵制と鎮守府の創設、黒川以北十郡の設置、玉造柵や牡鹿柵等五柵の設置と、国府と鎮守府を兼ねた陸奥国の新たな拠点としての多賀城造営等からなる。 多賀城は政庁による内郭と、それを取り囲む外郭という以降の城柵の基本構造(二重構造城柵)を決定づけたものであり、政庁の規格化や屋根瓦の統一など、その後各地に展開される城郭のモデルとなった。なお、設置当初の多賀城は多賀柵と称しており、城の文字が使われるのは多賀城碑が初出である。他の城柵においても、8世紀末には「城」の表記が一般化する。 鎮兵制の創設に先立つ養老6年(722年)の政策見直しでは、陸奥国の「鎮所」に穀物の献上を募っており、これは兵力の駐屯に先立って軍糧を備蓄する目的で行われたものとみられている。国内から徴兵される軍団と異なり、鎮兵は主として坂東を中心とした東国の兵士が派遣され、専門の兵士として城柵に常勤(長上)した。 東国の兵を陸奥国に常駐させる制度である鎮兵の性格は、征夷軍の常設化と言えるものであった。また、その人的な基盤を東国の兵士に求める鎮兵の性格は、九州北部に置かれた防人と類似するものである。これはまさに、朝廷が東国の軍事力を九州北部と東北で必要に応じて配置転換していたことを意味していた。 九州で防人が停止された天平2年(730年)は、陸奥で鎮兵が実施された時期にあたっている。鎮兵は天平18年(746年)、軍団を6,000人規模に拡充した際に一度全廃されたが、天平宝字元年(757年)桃生城・雄勝城の造営にあたって復活した。 天平宝字元年もまた、九州で復活させた東国防人の制度が再び停止され、九州北部の防衛を西海道出身の兵士に切り替える決定がなされている。九州ではその後東国出身者による防人は復活せず、逆に陸奥の鎮兵は「三十八年戦争」が終結する9世紀初頭まで廃止されることはなかった。鎮兵が全廃されるのは弘仁6年(815年)のことである。 石城国・石背国の2国は、養老2年(718年)に陸奥国の一部を分割して設置したものだが、その存続期間は短く、養老5年(721年)の8月から10月までの約2カ月の時期に、陸奥国に再併合されたものとみられている。 これも、養老4年の蝦夷の大反乱を受けた朝廷の政策見直しの一環として、石城・石背両国の軍団を陸奥国の有事に動員しやすくする目的で行われたと考えられており、これにより陸奥国司は自らの権限で動員できる兵力が増大した。 また、両国の再併合は多賀城造営の費用負担を求める理由もあったと思われ、多賀城創建期の瓦には磐城郡進と記されたものが見つかっている。 なお、鎮兵制の創設と軍団制度の再編により、城柵に駐屯する軍事力は、軍団と鎮兵の二本立てとなったが、前者が基幹的、後者が補完的な制度である。 このように城柵に駐屯する軍事力は朝廷の征服事業の遂行過程で次第に増強されていったが、それは在地の蝦夷社会にとって大きな脅威となっていった。
2024年11月26日
閲覧総数 52
-
4

「歴史の回想・宝亀の乱」宝亀の乱の起因。 川村一彦
2「宝亀の乱の起因」(ほうきのらん)は、奈良時代の宝亀11年(780年)に、現在の東北地方で起きた反乱。現在の宮城県にあたる陸奥国にて、古代日本の律令国家(朝廷、中央政権)に対し、上治郡の蝦夷の族長であった伊治呰麻呂が起こしたもので、首謀者の名を採って伊治公呰麻呂の乱または伊治呰麻呂の乱とも呼ばれる。 〇伊治 呰麻呂(これはり/これはる の あざまろ、生没年不詳)は、奈良時代の人物。姓は公。官位は外従五位下・上治郡大領。 8世紀後半に陸奥国(現在の東北地方)で活動した蝦夷の族長で、朝廷から官位も授けられていたが、宝亀11年(780年)に宝亀の乱(伊治呰麻呂の乱/伊治公呰麻呂の乱)と呼ばれる反乱を引き起こした。 伊治呰麻呂は、現在の宮城県内陸北部の栗原市付近に勢力を持っていた蝦夷の族長である。 8世紀中葉以降の律令国家は、本州北東部への版図拡大を基本政策として、現地において時に強硬な軍事活動を行い、時に蝦夷を懐柔しながら、城柵を置き柵戸と呼ばれる移民を移住させて支配の拡充を図りつつあった。 蝦夷に対しては征討と撫慰(懐柔)の硬軟を使い分けたが、あくまで基本は撫慰であり、政府に帰順した蝦夷を使って未服の蝦夷を懐柔させることも行われた。したがって政府と蝦夷とは間断なく対立関係にあった訳でなく、武力衝突があった時でさえも全ての蝦夷と対立関係に陥った訳でない。 蝦夷の中には彼ら自身の思惑で政府の威光を恃み、また政府の政策に協力することで自らの地位上昇を目論む者もあったのである。このように政府に帰服した蝦夷は、身分上更に狭義の「蝦夷」と、「俘囚」とに分けられる。狭義の「蝦夷」とは、彼ら本来の集団を保持したまま政府に帰服したもので、君または公の姓を与えられて、多くは従来の居留地に留まった。対して俘囚とは個別に政府に帰服したもので、部姓を与えられて城柵の周辺に居住した。 伊治呰麻呂が、「公」の姓を附して伊治公呰麻呂とも称されるのは、まさしく彼が政府側に帰属して活動していたことを示す。 さらにこの証左となるのが彼に与えられた位階で、もともと夷爵第二等を有していたが、これは狭義の「蝦夷」に対して与えられるものであり、さらに宝亀9年には、前年行われた海道・山道蝦夷の征討に功があったことを嘉して、外従五位下という地方在住者としては最高の位階を授けられるのである。 また、当時「呰麻呂」という名前は和人において珍しいものでなく、忌部呰麻呂や大伴呰麻呂など、史料上散見される。このことから、神護景雲元年(767年)伊治城造営の頃に伊治公一族が政府に帰順した折に、呰麻呂という和人の名前に改めたのではないかとの推測がある(今泉隆雄)。また「呰」の字は「痣」に通じ、身体的な特徴に由来すると考えられ、古代においては計帳に記述する身体的特徴として注記する情報でもあった。 一方で、「伊治」については、長く読み方を確定できず、「イヂ」と音読されるのが通例であった。しかし昭和53年(1978年)に解読された多賀城出土漆紙文書に「此治城」とあり、「此」と「伊」の訓読の一致から此治城を伊治城と同定できるため、「コレハリ」(または「コレハル」)と読むことが明らかになっている(「此治」と「上治」を同定できるかについては後述)。 来歴 俘軍を率いる族長として 伊治(公)呰麻呂の名が六国史に現れるのは、宝亀9年(778年)6月に前年行われた海道・山道蝦夷の征討に際しての戦功を賞し、外従五位下の位階が授けられたことを記す記事においてである。これは地方在住者として最高の位であり、これによって彼は官人たりえる身分を得たと考えられる。 この時期の東北地方は、宝亀5年(774年)、海道蝦夷が蜂起して桃生城を奪取したことを契機として、後世「三十八年戦争」とも称される戦乱の時代に突入していくが、当初から政府が大規模な征討軍を派遣していた訳でなく、当初は現地官人と現地兵力が、敵対する蝦夷と武力衝突していた。 天平9年(737年)の征討将軍大野東人以来中央からの派遣軍は絶えており、それが復活するのは皮肉にも後に呰麻呂本人が引き起こす反乱が原因である。 ともあれ、この時期は政府によって各国に置かれた軍団兵と、政府側に帰属した蝦夷・俘囚によって構成される俘軍という二本立ての現地兵力によって、敵対する蝦夷と武力衝突が起きていた時期であるが、その中で呰麻呂は俘軍を率い政府側で戦功を重ねていた。 上治郡大領 宝亀9年(778年)に外従五位下の位階を得た呰麻呂は、宝亀11年(780年)3月までに「上治郡」の大領の地位に就いていた。この「上治郡」について、上記多賀城出土漆紙文書から、「此治」の表記が検出されたことから、「上治」を「此治」の誤記とする見解が示され、有力な説となった。 しかしその後熊谷公男の研究により陸奥国の郡制について検討が行われ、政府によって扶植された移民系の郡である栗原郡と、服属した狭義の蝦夷を編成した蝦夷郡である上治郡とは別の郡であるとする見解が示された。 栗原郡と上治郡を別であるとする説は今泉隆雄、鈴木拓也]、永田英明らによって支持されている。また、呰麻呂が後に乱を引き起こす発端となった、彼が夷俘として差別を受けていた事実および、俘軍との強い結びつきは、彼が移民を編成した郡の長でなく、服属蝦夷によって構成された郡の長であったことを示唆する。加えて、上治郡の設置が、呰麻呂が官人身分を得た宝亀9年(778年)から、郡名が記録上初見する宝亀11年(780年)までの間と考えられる一方で、栗原郡は神護景雲3年には設置されている。 宝亀の乱 宝亀11年(780年)3月、突如として呰麻呂は反乱を引き起こすこととなる。 当時、政府による東北地方経営を現地で取り仕切っていたのは陸奥按察使兼鎮守副将軍の紀広純であった。按察使とは複数の令制国を管轄して国司を監察する律令国家の地方行政の最高官である。 その紀広純が山道蝦夷の本拠であった胆沢攻略のための前進基地として覚鱉城(かくべつじょう)造営を計画し、工事に着手するため呰麻呂と陸奥介大伴真綱、そして牡鹿郡大領の道嶋大楯を率いて伊治城に入った折、呰麻呂は自ら内応して俘軍を率い、まず道嶋大楯を殺害、次いで紀広純も殺害するに至ったものである。 大伴真綱のみ多賀城まで護送したが、これは多賀城の明け渡しを求めてのこととみられる。多賀城には城下の人民が保護を求めて押し寄せたが、真綱は陸奥掾石川浄足とともに逃亡してしまった。 このため人民も散り散りとなり、数日後には反乱軍が到達して府庫の物資を略奪した上、城に火を放って焼き払ったという。この時伊治城・多賀城ともに大規模な火災により焼失したことは、発掘調査によっても裏付けられている。 この反乱の理由として『続日本紀』では、呰麻呂の個人的な怨恨を理由に挙げている。夷俘[注 1]の出身である呰麻呂は、もともと事由があって紀広純を嫌っていたが、恨みを隠して媚び仕えていたために、紀広純の方では意に介さずに大いに信頼を置いていた。これに対し道嶋大楯は常日頃より呰麻呂を夷俘として侮辱していたために、呰麻呂がこれを深く恨んでいたとするものである。 道嶋大楯は呰麻呂と同じく郡の大領であるが、道嶋氏はもともと坂東からの移民系の豪族であり蝦夷ではない。また、同じく道嶋氏からは中央貴族となった近衛中将道嶋嶋足も輩出しており、陸奥国内での勢力は他を圧するものであった。 道嶋大楯がつとに呰麻呂を侮辱してきたのもその威を借りたものと考えられ、政府に協力し功績を認められて地位を上昇させてきた呰麻呂にとって耐えがたい屈辱であったと考えられる。 一方で呰麻呂の蜂起に同調して多数の蝦夷が蜂起しており、その中には宝亀9年、呰麻呂と同時に外従五位下を賜った吉弥侯部伊佐西古も含まれる。このことはすなわち、事件の原因が呰麻呂の個人的な理由に留まるものでなく、政府の政策に多数の蝦夷が怨恨を抱いていたことを示すものである。 また、故地に城柵を設けられて土地を奪われ、自らの一族は労役や俘軍への徴発など負担を強いられてきたこと、更には伊治城造営を主導したのも道嶋の一族である道嶋三山であったことなども、呰麻呂が恨みを募らせた理由として推測されている。 呰麻呂の反乱とそれにともなう混乱は、多賀城を文字通り灰燼に帰せしめ、これまでの政府による支配の成果を烏有に帰せしめるものであった。このため政府は「伊治公呰麻呂反」と記して八虐のうち謀反にあたると断じ、国家転覆の罪に当たるとした。 しかし、呰麻呂の名はその後の記紀に現れることはなく、その行方は杳として知れない。反乱の翌年に即位した桓武天皇が賊中の首魁として名指ししたのも、上記の伊佐西古を含む、「諸絞・八十嶋・乙代」らであり、その中に呰麻呂の名は見えない。 しかしながら呰麻呂の反乱を契機として陸奥国の動乱はより深まっていき、政府から征夷軍が繰り返し派遣される時代が到来することとなる。この桓武天皇時代の征夷には、俘軍の参加は確認できない。呰麻呂自身がかつてそうであったような、政府に帰属した蝦夷が俘軍を率いて協力した時代は、呰麻呂の乱によって転換点を迎え、律令国家と蝦夷が全面対決する局面へと移行していくのである。 宝亀11年(780年)、政府側に帰服して上治郡の大領に任じられていた「蝦夷」である伊治公呰麻呂が、覚鱉城(かくべつじょう)造営に着手するために伊治城(現在の宮城県栗原市にあった城柵)に駐留することとなった陸奥按察使紀広純およびそれに付き従っていた陸奥介大伴真綱、牡鹿郡大領であった道嶋大楯らを襲撃。
2024年11月26日
閲覧総数 48
-
5

「歴史の回想・宝亀の乱」藤原仲麻呂の乱。 川村一彦
藤原仲麻呂の乱 孝謙上皇・道鏡と淳仁天皇・仲麻呂との対立は深まり危機感を抱いた仲麻呂は、天平宝字8年(764年)自らを都督四畿内三関近江丹波播磨等国兵事使に任じ、さらなる軍事力の掌握を企てる。しかし謀反の密告があり、上皇方に先手を打たれて天皇のもとにあるべき御璽や駅鈴を奪われると、仲麻呂は平城京を脱出する。子の辛加知が国司を務めていた越前国に入り再起を図るが、官軍に阻まれて失敗。仲麻呂は近江国高島郡の三尾で最後の抵抗をするが官軍に攻められて敗北する。 敗れた仲麻呂は妻子と琵琶湖に舟をだしてなおも逃れようとするが、官兵石村石楯に捕らえられて斬首された。享年59。僅か1週間前には完全に軍権を把握して意気揚々たる状態だったが、将棋倒しのように不運な敗戦と誤算が相次ぎ急転直下の滅亡となった。 死後 仲麻呂の一族はことごとく殺されたが、六男の刷雄は死刑を免れて隠岐国への流罪となり、のちに赦されて桓武天皇の時代に大学頭や陰陽頭を歴任している。また十一男と伝わる徳一も処刑されず東大寺に預けられて出家し、のちに筑波山知足院中禅寺の開山となり、やがて最澄や空海の論敵としてその名を馳せることになる。 仲麻呂の滅亡によって彼が推進してきた政策は、官名の唐風改称こそは廃されて旧制に戻されたものの、養老律令はじめとする先進的な政策の多くは一部修正を加えられながらもその後の政権によって継続されていくことになる。東北地方への進出を強め、現地住民との軋轢を増してきた政府の政策に対する、蝦夷側の反作用というべき性格も持っている。ただし反乱の舞台となった地域は完全に政府側の勢力が及んでいなかった地域でなく、首謀者の呰麻呂が受爵していたことからもわかる通り、ある程度政府の政治的・文化的な影響下にある地域であった。反乱は、それを踏まえた政府によるさらなる現地支配の強化に対しての抵抗と捉えられるものである。 4「乱の発生」乱の発生は宝亀11年3月22日(780年5月1日)である。陸奥按察使であった紀広純は、覚鱉城造営のため、俘軍を率い、陸奥介大伴宿禰真綱、牡鹿郡大領道嶋大楯、そして反乱の首謀者となる上治郡大領伊治呰麻呂を従えて、伊治城に入った。これを機会に呰麻呂は自ら内応して俘軍を誘い、反乱に至ったものである。呰麻呂はまず道嶋大楯を殺すと、ついで衆を率いて紀広純を囲み、攻めてこれも弑した。大伴真綱に対しては囲みを開いて多賀城まで護送した。これは真綱に多賀城の明け渡しを求めてのこととみられる。城下の住民が多賀城の中に競うようにして入り保護を求めたが、真綱は陸奥掾の石川浄足(いしかわのきよたり) 〇「掾」(じょう)とは、日本の律令制下の四等官制において、国司の第三等官(中央政府における「判官」に相当する)を指す。 中世以後、職人・芸人に宮中・宮家から名誉称号として授けられるようになり、江戸時代中期以後はとくに浄瑠璃太夫の称号となった。 国司の官名 国司の四等官は、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)という文字を用いた。本来「掾」という漢字の音読みは「エン」であるが、三等官は文字にかかわらず「じょう」と訓ぜられる。これは唐の一部官庁で三等官の呼称とされていた「丞」の借音とされる。 大宝令・養老令に定められた規則では、国の規模(国力)によって国司の制度が異なっており、四等官すべてが置かれないことがある。最も低い位置付けの下国には掾が置かれなかった。逆に、最も高い位置づけの大国には大掾・少掾が設置された。このため掾が設けられたのは上国・中国となる。 ただし実際の運用上は人員の増減があり、上国である下野国に大掾と少掾が配置されたり、下国である飛騨国に掾が置かれたりした(国司#国等級区分参照)。 職人・芸人の名誉称号 律令国司における掾(または大掾・少掾)が転じて、中世以後は職人・芸人に宮中・宮家から与えられる名誉称号になった(これは、目など他の国司の官名についても同様である)。近世には刀工など多様な職人・商人や芸人に対して、宮中・宮家からその技芸を顕彰する意味で下賜された。掾号を授けられることを「受領する」という。 浄瑠璃 職人・芸人の名誉称号としての掾号のうち、もっとも後代まで残存していたのは浄瑠璃太夫に授けられるものである。例えば、竹本義太夫は筑後掾を受領した。 江戸時代中期以後、掾号はもっぱら浄瑠璃太夫の称号とされた[1]。掾号を授けられることは浄瑠璃太夫にとって最高の名誉とされた。称号としての掾は、大掾・掾・少掾の3等級に分かれる。 江戸時代は嵯峨御所(大覚寺門跡)、明治以後は宮家から与えられた。戦後では、1947年(昭和22年)に2代目豊竹古靱太夫が秩父宮家から山城少掾を、1956年(昭和31年)には4代目吉田文五郎が東久邇家から難波掾[注釈 4]を受領している。 とともに後門から隠れて逃げたため、住民も散り散りになって逃れた。数日後には反乱軍が多賀城まで来襲し、府庫の物資を略奪した上、城に火を放って焼き払ったという。この時伊治城・多賀城ともに大規模な火災により焼失したことは、発掘調査によっても裏付けられている。 5「征東使の派遣と、それを巡る混乱」概要で述べたとおり、この事件は政府では大きな衝撃として受け止められた。天皇の現地代理人である按察使が殺害され、陸奥国府の多賀城を失陥したことは国家や天皇の権威を著しく損なうものだったからである。このため事件から6日後の3月28日には征東使の人事が行われ、中納言の藤原継縄を征東大使に任じ、次いで大伴益立、紀古佐美を征東副使とし、さらに出羽国に動揺が波及しないようにするための出羽鎮狄将軍として安倍家麻呂を任じた。 〇「藤原 継縄」(ふじわら の つぐただ)は、奈良時代後期から平安時代初期にかけての公卿。藤原南家の祖である左大臣・藤原武智麻呂の孫。右大臣・藤原豊成の次男。官位は正二位・右大臣、贈従一位。桃園右大臣あるいは中山を号す。 出生から藤原仲麻呂の乱まで 天平宝字7年(763年)37歳で従五位下に叙爵する。末弟(四男)の縄麻呂は既に天平勝宝元年(749年)に20歳で従五位下に叙されているが、これは縄麻呂の母(参議・藤原房前の娘)の身分が高く、縄麻呂が嫡子として扱われた可能性があるのと、その後の藤原仲麻呂政権下で父と共に権力から排除されていたためと想定される。翌天平宝字8年(764年)正月に信濃守に任官するが、9月に藤原仲麻呂の乱が発生した際に、越前守であった藤原辛加知(仲麻呂の子)が佐伯伊多智に斬殺されると、継縄はその後任として越前守に転任した。藤原仲麻呂は北陸道への逃亡を企てており、越前は軍事的に重要な場所であった点から、軍事目的の任命と考えられる。また、この反乱を通じて大宰員外帥に左遷されていた父・豊成も右大臣に復帰している。 道鏡政権・光仁朝 道鏡政権に入ると急速に昇進し、天平神護元年(765年)正月に従五位上に進むと、同年11月の父・豊成の薨去に伴って三階昇進して従四位下に叙せられる。さらに翌天平神護2年(766年)には参議に任ぜられ公卿に列す傍ら、右大弁・外衛大将と文武の要職も兼帯した。 宝亀元年(770年)光仁天皇の即位に伴って従四位上に叙せられると、翌宝亀2年(771年)従三位と光仁朝初頭は引き続き順調に昇進する。また、光仁朝では外衛大将・左兵衛督・兵部卿など武官を歴任した。 宝亀10年(779年)に弟の中納言・藤原縄麻呂が薨去すると、継縄は藤原南家の氏上格となり、翌宝亀11年(780年)2月に中納言に昇進する。3月になると陸奥国で蝦夷の族長であった伊治呰麻呂が反乱を起こし、按察使・紀広純を殺害したため(宝亀の乱)、これを鎮圧すべく継縄は征東大使に任ぜられた。しかし継縄は準備不足などを理由にして平城京から出発しようとせず、遂に大使を罷免されてしまった(後任大使は藤原小黒麻呂)。ただし特に叱責を受けたり左遷されるなどの処分は受けていない。 桓武朝 天応元年(781年)桓武天皇が即位すると、同じ藤原南家の従兄弟・藤原是公が重用されるようになる。同年9月に2人は正三位・中納言となって肩を並べ、翌天応2年(782年)是公が先に大納言に昇進して官位面で後塵を拝することになった。 延暦2年(783年)には是公は右大臣に就任するが、後任の大納言には継縄が任ぜられ、藤原南家の公卿で太政官の首班・次席を占めた。延暦4年(785年)の藤原種継暗殺事件や、桓武天皇の皇后藤原乙牟漏・夫人旅子の相次ぐ死により藤原式家の勢力が衰えたためか昇進も順調で、大宰帥・皇太子傅・中衛大将を経て、延暦8年(789年)藤原是公の薨去により太政官の筆頭の地位に就き、延暦9年(790年)右大臣に至った。 継縄が太政官筆頭の時期の重要事項として、延暦11年(792年)全国の兵士を廃止して健児を置いたことがあげられる。延暦13年(794年)の平安京遷都に深く関わったとする説もある。『続日本紀』の編纂者としても名が挙げられているが、生前には一部分しか完成しておらず、実際に関与した部分は少なかったと見られている。 延暦15年(796年)7月16日薨去。享年70。最終官位は右大臣正二位兼行皇太子傅中衛大将。没後に従一位が贈られた。 夫人が百済系渡来氏族出身(百済王氏)であったためか、同じく百済系渡来氏族出身とされる高野新笠を母に持つ、桓武天皇からの個人的信頼が厚かった政治家の一人であり、天皇が継縄の邸に訪れることもしばしばであった。その際に百済王氏一族を率いて百済楽を演奏させたことがある。『日本後紀』の薨伝によれば凡庸な人物であるものの人柄はよかったというが、その点も桓武の信任を得た理由だという説がある。
2024年11月26日
閲覧総数 45
-
6

「歴史の回想・宝亀の乱」城柵を支配した官人。 川村一彦
城柵を支配した官人 城柵を統括したのが城司である。朝廷から官人が派遣されて城司の任に就き、国家権力の代理人としての権能をふるった。 これを示すのが、国府でない城柵に対しても政庁が用意され、都の朝堂あるいは各国の国衙に倣う様式となっていた事実である。朝廷にとって蝦夷の服属を受け入れて朝貢関係を結ぶことは、国内に中国に倣う華夷秩序を現出する意味を持った。 したがって城柵がその拠点として機能するためには、都と同じ様式の儀礼的な空間を必要としたのである。また、このような政治的な意味からも、蝦夷の服属を受け入れる城司は中央政府の代理人である必要があった。 城司として派遣された官人は国司や鎮官であり、8世紀には鎮官を兼任する国司が、9世紀から両官が別々に任命されて城司となった。『類聚三代格』所収の承和十一年(844年)九月八日官符によると、陸奥国司と鎮官をあわせて「辺城之吏」と称しており、国司が城柵に駐在する存在であったことを示すものである。また天平五年(733年)十一月十四日勅符は、陸奥国に派遣される国司以下官人に護衛の兵士をつける内容であり、奥地にある「塞」に派遣される場合は更に護衛を増員する規定が記されていることから、国司が城柵に派遣されていたことを裏付けるものとなっている。 出羽国においては、『続日本紀』宝亀十一年八月二十三日条に記された秋田城停廃問題において、新たに専任の国司(秋田城介)を置いて秋田城を存続させる決定がなされていることから、秋田城に国司が派遣されたことが明らかである。 また『類聚三代格』所収、天長七年閏十二月二十六日格からは、出羽国では秋田城・雄勝城と国府に国司を配していて人員が足りないことから、目(さかん)以下の官員を増員したことが記されており、雄勝城にも国司が駐在していたことを確認できる。 このように各種史料によって城柵に国司が派遣されていたことを確認できる一方で、律令制下では国司以下官人の定員が規定されていることから、全ての城柵に城司が駐在したのか検討する必要がある。 これについては、陸奥国・出羽国に置かれた城柵の数と両国の国司(四等官)及び史生の総定員の比較から、定員内で全ての城柵に国司を派遣することが可能であり、全ての城柵に城司を置いたのが原則であると考えられている。 ただし、一つの城柵に複数の城司を置く場合もあったことから、この場合国司・史生の定員内で城司をまかなうのが苦しくなる。この対応策として、出羽国では国司の増員がなされ、陸奥国では胆沢城設置を契機として鎮官を独立の官とした。より最前線に近い志波城・徳丹城にも鎮守府から鎮官が派遣され、城司を務めたものと考えられている。 城司の役割は、辺遠国である陸奥・出羽・越後の三か国の守のみに規定された特別の職掌である「饗給(撫慰)」、「征討」、「斥候」を、現地の拠点である城柵において分担して遂行することにあったと言える。したがって駐在にあたっては軍団の兵士を率い、有事の際は鎮兵や俘囚により編成された俘軍の指揮権を持った。 城柵の史的展開 城柵は大化3年(647年)に造営された渟足柵から、「三十八年戦争」終結後の9世紀前半に造営された徳丹城に至るまで、設置された年代が長期に渡ることから、その様態は一様でない。岡田茂弘の分類によると、時期によって4つの段階に区分される。 初期の城柵 城柵は、大化3年(647年)の渟足柵(現在の新潟県新潟市沼垂付近と比定される)設置が記録上の初出である。翌大化4年(648年)には同じく越後国に磐舟柵(現在の新潟県村上市岩船付近と比定される)が設置された。これに先立つ斉明天皇元年(642年)に当地の蝦夷数千人が服属を申し出ており、この2つの柵は政治的・軍事的な役割のほかに蝦夷との交易・交流の拠点という役割も担ったものと考えられる。また、『日本書紀』の記述からは渟足柵・磐舟柵の設置にあたって柵戸が置かれたことが記されており、城柵の設置と移民の扶植は、当初からの一体的な政策であったことがわかる。 この2つの城柵はともに海岸沿いの砂丘と河川の交点付近に築かれたと推測され、海上交通の便益が図られたとみられることも共通する。しかしながら両柵とも正確な場所が不明で、文献上の存在となっている。皇極天皇4年(658年)には都岐沙羅柵という名も『日本書紀』に見えるが、これもいつどこに設置されたのか不明である。 考古学的な調査から様相が明らかとなっている初期の城柵としては、宮城県仙台市太白区で発見された郡山遺跡が挙げられる。現在の長町駅( 東北本線・仙台市地下鉄南北線)東方にあり、広瀬川と名取川に挟まれた自然堤防と後背湿地上に位置する。この城柵は日本海側の渟足柵、磐舟柵に対応する、太平洋側の拠点であった。 郡山遺跡ではI期・Ⅱ期の二つの時期にわたる官衙の遺構が発見され、I期の遺構は東西約300㎡、南北約600mの広がりを持つ。建築方向は真北から西に約60度傾いており、材木塀や板塀で囲まれた政庁・工房・倉庫などの区画が連なっていた(ブロック連結構造城柵)。この施設構成は同時期の評家(郡家)遺跡と共通するものであるが、一方で武器工房を有し、櫓を設けるなど、一定の軍事的緊張を窺わせるものでもあった。 7世紀末頃、郡山遺跡はI期の官衙を廃棄し、その跡地に第Ⅱ期の官衙が造営された。Ⅱ期の遺構は東西約428m、南北約423mのほぼ正方形(一辺が約4町にあたることから、方四町官衙と呼ばれる)で、建築方位はほぼ真北を向く。敷地のほぼ中央に政庁たる正殿を置き、左右対照に脇殿や楼が配された。また、外周の塀から約9㎡離れて大溝が、さらに48mほど離れて外溝が開削されており、大溝と外溝の間は空き地である。 外溝を含めた全体の規模は一辺約535mの方形となり、これは初めて条坊制を採用した藤原京の一坊の長さに相当した。政庁の施設配置及び正殿が南面する様式や、正殿北側に石敷きの広場が設けられたこと、大溝と外溝の間を空閑地とするなどの構成は、飛鳥宮や藤原京の強い影響を受けたものと考えられている。 一方で、敷地の広大さに比して施設は全体的に希薄で、倉庫や官人の邸宅などの実務的な施設は郭外に置かれた。官衙内に倉庫を置かない構成は、秋田城を除いて後の城柵でも通例となっている。その他特筆すべき事項として、南西側に寺院が創建(郡山廃寺)されたことが挙げられ、城柵の周囲に寺院を置く構成は後代の多賀城や秋田城でも引き継がれた。 郡山遺跡Ⅱ期官衙ではI期のブロック連結構造城柵を脱却し、都の朝堂を直接的に模倣した儀礼的な空間が志向され、後の城柵もこれに倣うこととなった。その一方郡山遺跡では外周の材木塀は一重(単郭式)で、主な実務施設を郭外に置くことになるなど、防御性に乏しい。 郡山遺跡には陸奥国府が置かれていたと考えられており、多賀城の直接の前身と言える存在であった。7世紀中葉から8世紀初頭にかけての時期の城柵は、主に河川に隣接した平地や段丘上に築かれ、郡山遺跡Ⅱ期官衙で脱却するまで、郡家に倣うブロック連結構造を取っていたのが特徴である。 多賀城の設置と、城柵の規格化第Ⅱ段階の城柵は、8世紀前半に造営されたものであり、多賀城や秋田城に代表される、丘陵地上に不整ながら方形を意識した外郭を構える、二重の囲繞施設を持つ城柵である
2024年11月26日
閲覧総数 41
-
7

「歴史の回想・宝亀の乱」巣伏の戦い。 川村一彦
巣伏の戦い 延暦八年の征夷がおこると、朝廷軍は延暦8年3月9日(789年4月8日)に多賀城から進軍を始め、延暦8年3月28日(789年4月22日)に「陸道」を進軍する2、3万人ほどの軍勢が衣川に軍営を置いた。 征東将軍・紀古佐美は4月6日(5月5日)付の奏状で衣川に軍営を置いたことを長岡京へと報告するが、その後30日余りが経過しても戦況報告がないことを怪しんだ桓武天皇は延暦8年5月12日(789年6月9日)に衣川営に長期間逗留している理由と、蝦夷側の消息を報告せよと勅を発した。 衣川営での逗留を責める桓武天皇からの勅が陸奥へと届けられたと思われる延暦8年5月19日(789年6月16日)頃、古佐美は進軍するよう命じた。5月下旬から末頃、中・後軍より各2000人ずつ選抜された計4000人の軍兵が、衣川営を出発後、北上川本流を渡河して東岸に沿って北進、阿弖流爲の居宅やや手前の地点で蝦夷軍300人程と交戦した。 蝦夷軍は北へと退却したため、朝廷軍はこれを追いつつ途上の村々を焼き払いながら北上し、前軍との合流地点であったらしい巣伏村を目指した。しかし前方から800人ほどの蝦夷軍が現れて朝廷軍を押し戻すと、東の山上に潜んでいた400人ほどの蝦夷軍が朝廷軍の後ろへとまわって退路を絶ち、川と山に挟まれた狭い場所に追い込まれた朝廷軍は蝦夷軍に翻弄されて総崩れとなった。 朝廷軍の損害は戦闘による死者25人、矢疵を負った負傷者245人、溺死者1036人、裸で泳ぎ生還した者1257人と、胆沢の蝦夷軍は朝廷に対して驚異的な惨敗を与えた。 『続日本紀』には「賊帥夷阿弖流爲が居(おるところ)に至る比(ころあい)」とのみあり、胆沢の蝦夷軍は阿弖流爲の居宅やや手前で朝廷軍と交戦しているが、阿弖流爲が蝦夷軍を指揮していのかまでは不明。高橋崇は蝦夷側の抵抗戦線の中心人物であったといってよいだろうとしている。 降伏 延暦20年10月28日(801年12月7日)、延暦二十年の征夷から平安京へと凱旋して桓武天皇に節刀を返上した征夷大将軍・坂上田村麻呂が、延暦21年1月9日(802年2月14日)には陸奥国胆沢城を造営するために再び胆沢の地へと派遣されてきた。 同年1月11日(同年2月16日)には駿河・甲斐・相模・武蔵・上総・下総・常陸・信濃・上野・下野等の10国は、国中の浪人4000人を陸奥国胆沢城の柵戸とするようにとの勅が下っている。胆沢城造営についての史料は僅少で、造営開始の時期や完成した時期などは不明である。 延暦21年4月15日(802年5月19日)に陸奥国にいる田村麻呂から、大墓公阿弖利爲と盤具公母禮が種類500余人を率いて降伏した報告が平安京に届けられた。大墓公阿弖利爲らの根拠地である胆沢はすでに征服されており、北方の蝦夷の首長にはすでに服属していた者もいたため、大墓公阿弖利爲らは進退きわまっていたものと思われる。 田村麻呂に付き添われて盤具公とともに平安京へと向かった大墓公は、延暦21年7月10日(802年8月11日)に平安京付近へと着いた。これを受けて同年7月25日(同年8月26日)に百官が桓武天皇に上表を奉って、蝦夷平定の成功を祝賀している。 『日本紀略』には「田村麿来」とだけあり、大墓公と盤具公が「入京」したとまでは記されていない。また「夷大墓公二人並びに従ふ」とあることから、この時点では大墓公と盤具公は捕虜の扱いではなかったと考えられている。 延暦21年8月13日(802年9月13日)、大墓公阿弖利爲と盤具公母禮の2虜は奥地の賊首であることを理由として斬られた。公卿会議で田村麻呂が「この度は願いに任せて返入せしめ、其の賊類を招かん」と大墓公阿弖利爲と盤具公母禮を故郷に返して彼らに現地を治めさせるのが得策であると主張したが、公卿たちは執論して「野生獣心にして、反復定まりなし。たまたま朝威に縁りてこの梟帥を獲たり。もし申請に依り、奥地に放還すれば、いわゆる虎を養いて患いを残すなり」と田村麻呂の意見が受け容れられることはなかった。 そのため大墓公阿弖利爲と盤具公母禮は奥地の賊首として捉えられ、河内国□山(現在の枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、大阪市の一部[注 2]、堺市の一部のどこか)で斬られた。 死後 阿弖利爲の死後、胆沢や周辺地域で阿弖利爲と母禮が殺されたことに報復する弔い合戦などの反乱が発生した形跡は一切ない[17]。 弘仁5年12月1日(815年1月14日)、嵯峨天皇は「既に皇化に馴れて、深く以て恥となす。宜しく早く告知して、夷俘と号すること莫かるべし。今より以後、官位に随ひて称せ。若し官位無ければ、即ち姓名を称せ」と蝦夷に対して夷俘と蔑称することを禁止する勅を発し、ここに征夷の時代が終焉した。 年表 アイヌ説の否定 古代の蝦夷(えみし)について、近年でも「蝦夷=アイヌ説」に立脚した論著が散見されるものの、現在では学会の共有財産となる標準的な見解が成立している。 蝦夷の中には渡嶋(北海道)の蝦夷などきわめて僻遠の地の集団も含まれているが、本州内にいた蝦夷については、概ね現代日本人の祖先のうちの一群であったことが明らかである。また奈良時代から平安時代初期には、奥羽両国の蝦夷が関東から九州までのほぼ全国に移住させられたことがあり、彼らはその後各地に血統を伝えたこともうかがい知れる。 及川洵は、アテルイを研究し、遺跡を調査研究している者の疑問として、アテルイがアイヌ人の祖先であるとされていることについて、古代蝦夷がアイヌ民族であるかどうか「思いつきやムードではなく、純粋に学問的に考えて頂きたい」と論じている 河内国と終焉の地 アテルイ終焉の地について『日本紀略』延暦21年8月13日条は「即捉両虜斬於河内國□山」とだけ記録している。そのためアテルイが斬られた地は河内国内(現在の枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、大阪市の一部[注 6]、堺市の一部)のどこかであるということ以外は不詳である。 一方で「□山」については、テキストとして広く利用されてきた新訂増補国史大系『日本紀略』では「杜山」、旧輯国史大系『日本紀略』および増補六国史『日本後紀』(逸文)では「植山」、鴨祐之『日本逸史』では「椙山」とあり、異同があることがかねてから知られていた。 「河内國」の後に続く地名は、神英雄が写本を調査した結果、主に以下のように分けられた。 「(木へんに欠)+山」 蓬左文庫本(江戸時代初期)、国立公文書館林家本(江戸時代中期?) 「(欠)+山」 宮内庁書陵部松岡本・日本紀類(江戸時代中期) 「椙山」 宮内庁書陵部編年紀略(江戸時代末期)・日本逸史(宝永7年(1710年))、神宮文庫天明四年奉納本(江戸時代中期)・三冊本(江戸時代末?)、無窮会神習文庫大覚寺本(江戸時代後期?)、国立公文書館内務省地理局本(江戸時代後期?)、東洋文庫東洋文庫本(文政7年) 「榲山」 無窮会神習文庫会田家蔵書本(江戸時代後期?) 「植山」 宮内庁書陵部久邇宮文庫本(江戸時代末期)、無窮会神習文庫菊屋幸三郎校本(江戸時代後期?) 「木山」 神宮文庫明治写 神英雄は、『日本紀略』の写本を調査した結果、新訂増補国史大系が「杜山」としているのは、宮内庁書陵部所蔵久邇宮文庫本の「植」のくずし字を読み誤ったもので、「杜山」と記す写本が存在しないことを明らかにした。調査した30本程度ある『日本紀略』の写本のうち、判読不能なものもあるが24本を閲覧調査して、おおむね「植山」と「椙山」に分けるとこができた。 また神は、「植山」を「椙山」へと訂正した写本が複数あること、「植山」と記された4例の写本はすべて興福寺門跡一条院の伝本に関連した同一系統であることに対して、「椙山」と記された10例の写本は原本を一つの系統に求めることが困難であるため、『日本紀略』の原本に掲載されていた本来の文字は「椙山」であると結論した。 今泉隆雄は、神の述べる通り「杜山」は誤りだが、植山説と椙山説のどちらが正しいかはわからないとしている。 宇山説・杉山説ともに有力な批判もあり、現在、アテルイが斬られた地は河内国のどこかであること以外は不詳である。 椙山説と比定地 河内国椙山説は、枚方市東部の「杉」(旧交野郡杉村)を比定地とみなす説がある。 植山説と比定地 河内国植山説は、枚方市北部の「宇山町」(旧交野郡宇山村)が江戸時代初期に「上山村」から改称したため比定地とみなす説がある。 宇山……延暦二十一年坂上田村麿蝦夷二酋を河内植山に斬ると云ふは此なるべし……乃斬於河内植山。〇宇山の東一里菅原村大字藤坂に鬼墓あり夷酋の墳歟。……津田……於爾墓オニツカ〇河内志云、王仁墓、在河内國交野郡藤坂村東北墓谷、今稱於爾墓。按ずるに此は百濟博士王仁にや、又蝦夷酋を植山に斬りたれば、是其墓にあらずや。— 吉田東伍は、処刑地は旧宇山村で埋葬場所は旧菅原村藤坂と記載しているが、藤坂の該当地は今は並河誠所が企画し、並河を中心として編纂された『五畿内志』を根拠に「伝王仁博士墓」とされている。また発掘調査の結果、宇山の丘は古墳だったことが判明している。 舊名の上山は植山ならんとの説あり、植山は大日本史坂上田村麻呂の傳に「延暦二十一年……乃斬於河内植山」と見ゆる植山是れなり。— 大阪府全志(1922)、[28] 大字宇山 旧交野郡宇山村で牧ノ郷に属して古くは上山村と称したが、元和元年宇山村と称する様になった。延暦二十一年征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷の二酋長を率いて京師に帰り、次いで之を斬った河内植山とは当地の事と考えられる— 枚方市史(1951)、 ……宇山=植山説が成立するためには、(a)河内国杜山や、(b)河内国椙山よりも、(c)河内国植山の方が正しいことを論証する必要がある— 枚方市史第二巻(1972)、 その後に出版された地名辞書類でも、河内国植山は宇山説は書かれ続けている。 うやま 宇山<枚方市>……延喜年間坂上田村麻呂が蝦夷の首長2人を斬った土地とする伝説がある(地名辞書・全志4)— 角川書店、角川地名大辞典 27 大阪府Ⅱ(1983) 宇山村……延暦二一年(八〇二)坂上田村麻呂が蝦夷の二首長を率いて帰京、二人は八月一三日に斬られたが、その場所を当地に比定する説がある(大日本地名辞書・大阪府全志)— 平凡社、日本歴史地名大系第二八巻 大阪府の地名Ⅱ(1986) 2006年の「伝 阿弖流為 母禮 之塚」の建立当時、枚方市で勤務していた馬部隆弘は『大日本地名辞書』(1900年)からはじまる「アテルイ宇山で斬られ藤阪で埋葬される」という記載は一般には広がらなかったと述べている。 『日本紀略』無窮会神習文庫本では「河内国植山」でアテルイを斬ったと表記される。現在河内国には「植山」なる地名は残されていない。ただし、近世の宇山村は元「上山村」と称し、元和元年(一六一五)に宇山村と改称している。……この説の初見は、明治三三年(一九〇〇)に出版の始まる吉田東伍『大日本地名辞書』である。この書の「宇山」の項には「牧野村大字宇山は大字坂の北に接す。延暦二一年坂上田村麻呂、蝦夷二酋河内植山に斬ると云ふは此なるべし。」と記されている。『大阪府全志』や旧『枚方市史』にもこの記述は踏襲されるが、この説が一般に広まることはなかったようで、昭和末期に至るまで管見の限りガイドブックなどの一般書への掲載は確認できない。— 馬部隆弘、 2020年、枚方市宇山で蝦夷が殺害されたという「伝承」を話す人達は確かに何人も存在したが、それらは『大日本地名辞書』の記載が発端となったものにすぎず、伝承とは先祖代々伝わってきたものがそう呼ばれるべきであるのだから伝承には該当しないと判断、この程度の事は説明する必要がないと考え記載しなかったと述べている。 アテルイが当地近くで殺害されたという言説は、明治33年(1900)に刊行された吉田東伍氏の著書に始まり、昭和47年(1972)に刊行された『枚方市史』などにも引用されている。これらは、『日本紀略』の解釈から提示された仮説・学説で、当然ながら伝承ではない。 一方で、枚方市には蝦夷が殺害されたという「伝承」があると熱心に主張する方々もたしかに何人もいた。しかし、蝦夷が殺害されたという「伝承」は、どう聞いても先祖代々伝わってきた類のものではなく、明らかに上記の学説が発端となったものばかりであった。このようなものは到底伝承として扱えなかった。また、この程度のことを説明する必要もないというのが当時の筆者の判断である。— 馬部隆弘 河内国と禁野 杉村・宇山村がある枚方市周辺は桓武天皇がたびたび遊猟をおこなった交野の地で、桓武天皇の外戚で陸奥鎮守将軍等を務めた百済王氏の本拠地付近となる。 旧杉村・旧宇山村がある枚方市には明確にいつからかは不明であるがかつて天皇が所領する「禁野」があり、一般人の鷹狩は禁じられていた。 朝廷が自ら禁野を穢すとは考えられないため杉・宇山を比定地とすることに対して批判もある。 宮内庁書陵部「満基公記 合綴 河内国禁野交野供御所定文 道平公記抄出」にて記された禁野の大まかな地理的記述からその範囲を推定した馬部隆弘も旧宇山村説を否定しているが、室町時代の禁野の範囲とアテルイが処刑された平安時代初期・西暦802年の禁野の範囲や禁野の定義、穢れについての概念が合致していたかどうかは定かではなく、また旧宇山村他は京都府と大阪府の国境線上の山地に飛び地があり墓地等ももうけられていた。 アテルイが斬られた802年の後の大同3年(808年)河内国交野雄徳山(男山)での埋葬が禁じられているが、宇山村東山飛地は男山の裾野にあたる。 一定の鎮定がみられたとして行われた天応元年の論功行賞であるが、これは形式的な終結にすぎず、根本的な解決には至っていなかったのである。
2024年11月26日
閲覧総数 45
-
8

「歴史の回想・宝亀の乱」桓武天皇即位。 川村一彦
「志良須宇奈古」(しらす の うなこ、生没年不詳)は、8世紀に日本の出羽国秋田城下にいた蝦夷(俘囚)の指導者である。780年に秋田城の廃止をおそれて請願した。史料の読み方により志良須と宇奈古の2人とする説もある。秋田城停廃をめぐる『続日本紀』宝亀11年(780年)8月23日条にのみ見える。この頃、陸奥国では蝦夷との戦争(宝亀の乱)が激化し、3月には東北経営の中心拠点たる多賀城が一時陥落する事態にまで至っていた。その時、「狄志良須俘囚宇奈古等」が、「己らは官威に拠って久しく城下にある。今、この秋田城はついに永く棄てるところとなるか。また元のように交代制で保つことになるのか」と訴えでた。出羽国鎮狄将軍の安倍家麻呂は、これを都に報じて対応を問うた。朝廷は秋田城に多少の軍士[1]を派遣して守らせ、国司のうち一人を専門にあたらせよと命じ、また由理柵の守備についてもあわせて指示した。そして、狄俘と百姓によく尋ねて彼らとこちらの利害をつぶさに言え、という答えを下した。この後のやりとりは伝わらないが、秋田城は国司の一人、「介」を常駐させて保たれた。一人説と二人説「狄志良須俘囚宇奈古等」の解釈には、「狄志良須の俘囚宇奈古」の一人説と、「狄の志良須」と「俘囚の宇奈古」という二人説があり、いずれとも決めがたい。一人説の難点は、「狄の志良須の俘囚の宇奈古」のような冗長な人名表記が他に例をみないこと。「俘囚」を姓のように使った例が他に見られないこと。狄と俘囚という同列的な用語を重ねて用いる意味がわからないことにある。 二人説は文の読み方として自然だが、部姓がなく名だけの俘囚が他に例をみないのが難点となる。夷俘と俘囚を区別する学説に基づけば、朝廷がより強く把握していた俘囚で、長く城下にあり、城について意見を上げることができた有力者に姓がないはずがない。志良須・志良守と地名志良須については、持統天皇10年(696年)3月に見える粛慎の志良守頴草との類似が指摘できる[6]。蝦夷の氏姓は地名からとられることが多いので、志良須もその可能性がある。他に、史実とはしがたいが、秋田県南秋田郡五城目町の白州館(しらすだて、五城目城)の住民だったという俚伝がある。 〇「志良須宇奈古」(しらす の うなこ、生没年不詳)は、8世紀に日本の出羽国秋田城下にいた蝦夷(俘囚)の指導者である。780年に秋田城の廃止をおそれて請願した。史料の読み方により志良須と宇奈古の2人とする説もある。秋田城停廃をめぐる『続日本紀』宝亀11年(780年)8月23日条にのみ見える。この頃、陸奥国では蝦夷との戦争(宝亀の乱)が激化し、3月には東北経営の中心拠点たる多賀城が一時陥落する事態にまで至っていた。その時、「狄志良須俘囚宇奈古等」が、「己らは官威に拠って久しく城下にある。今、この秋田城はついに永く棄てるところとなるか。また元のように交代制で保つことになるのか」と訴えでた。出羽国鎮狄将軍の安倍家麻呂は、これを都に報じて対応を問うた。朝廷は秋田城に多少の軍士[1]を派遣して守らせ、国司のうち一人を専門にあたらせよと命じ、また由理柵の守備についてもあわせて指示した。そして、狄俘と百姓によく尋ねて彼らとこちらの利害をつぶさに言え、という答えを下した。この後のやりとりは伝わらないが、秋田城は国司の一人、「介」を常駐させて保たれた。一人説と二人説「狄志良須俘囚宇奈古等」の解釈には、「狄志良須の俘囚宇奈古」の一人説[2]と、「狄の志良須」と「俘囚の宇奈古」という二人説[3]があり、いずれとも決めがたい。一人説の難点は、「狄の志良須の俘囚の宇奈古」のような冗長な人名表記が他に例をみないこと。「俘囚」を姓のように使った例が他に見られないこと。狄と俘囚という同列的な用語を重ねて用いる意味がわからないことにある。 二人説は文の読み方として自然だが、部姓がなく名だけの俘囚が他に例をみないのが難点となる。夷俘と俘囚を区別する学説に基づけば、朝廷がより強く把握していた俘囚で、長く城下にあり、城について意見を上げることができた有力者に姓がないはずがない。志良須・志良守と地名志良須については、持統天皇10年(696年)3月に見える粛慎の志良守頴草との類似が指摘できる[6]。蝦夷の氏姓は地名からとられることが多いので、志良須もその可能性がある。他に、史実とはしがたいが、秋田県南秋田郡五城目町の白州館(しらすだて、五城目城)の住民だったという俚伝がある。 安倍家麻呂に対し秋田城廃止による不安を訴え、このまま城が永久に放棄されてしまうのか、元のように保つことはできないのかと言上している。彼らのように政府側に帰属する蝦夷系住民にとって、城の廃止は敵対する集団から攻撃される危険を招き、まさしく死活問題だったのである。家麻呂はこの訴えを政府に伝えて対応を求めた。政府からの回答は、秋田城は久しく敵を防ぎ民を守ってきたものであるから、放棄するのは得策でないとし、これを廃止せずに暫定的な措置として鎮狄将軍の率いる兵を駐屯させて鎮守させ、また鎮狄使か出羽国司の一人を駐在させて専当官とするべしという内容であった。加えて、由理柵(現在の秋田県由利本荘市にあったと推定される城柵)にも兵士を駐屯させ、秋田城と相互に救援するよう命じている。秋田城の暫定的な維持が決定した一方で、由理柵の防備が命じられているのは、既に秋田城以南の情勢も不穏になっていたことを示すものである。同様のことは更に南側の大室塞(現在の山形県尾花沢市付近にあったと推定される城柵)でも起きており、宝亀11年12月には光仁天皇からその防御を命じられることとなる。由理や大室といった、出羽国中部の地域も「賊の要害」(敵の攻撃を防ぐための場所)と呼ばれる最前線へと変貌したことになる。しかしながら記録上鎮狄使の活動が見られるのはこの時までで、翌年5月に安倍家麻呂が上野守に任じられている]ことから、それまでには出羽国に派遣された鎮狄使は任務を終了していたと考えられる。 9「天応改元と桓武天皇即位」呰麻呂によって引き起こされた戦乱を鎮定できないまま、混乱の宝亀11年は暮れた。翌年元日に日本史上唯一の元日改元である宝亀から天応への改元が行われる。改元にあたり伊勢斎宮の上空に美雲が顕れたことを瑞祥としたと詔が出されているが、 〇「斎宮」(さいぐう/さいくう[1]/いつきのみや/いわいのみや)は、古代から南北朝時代にかけて、伊勢神宮に奉仕した斎王の御所(現在の斎宮跡)であるが、平安時代以降は賀茂神社の斎王(斎院)と区別するため、斎王のことも指した。後者は伊勢斎王や伊勢斎宮とも称する。 斎宮の起こり 『日本書紀』崇神天皇紀によれば、崇神天皇が皇女豊鍬入姫命に命じて宮中に祭られていた天照大神を大和国の笠縫邑に祭らせたとあり、これが斎王(斎宮)の始まりとされる。そして次の垂仁天皇の時代、豊鍬入姫の姪にあたる皇女倭姫命が各地を巡行し伊勢国に辿りつき、そこに天照大神を祭った。この時のことを『日本書紀』垂仁天皇紀は「斎宮()を五十鈴の川上に興()つ。是を磯宮()と謂ふ」と記し、これが斎王の忌み籠る宮、即ち後の斎宮御所の原型であったと推測される。 また垂仁天皇紀は「天皇、倭姫命を以って御杖()として、天照大神に貢奉()りたまふ」とも述べ、以後斎王は天皇の代替わり毎に置かれて天照大神の「御杖代()」として伊勢神宮に奉仕したといい(ただし史料上は必ず置かれたかどうかは不明で、任期などもそれほど明確ではない)、用明天皇朝を契機に一時途絶えたが、天武天皇の時代に正式に制度として確立し(『扶桑略記』は天武天皇が壬申の乱の戦勝祈願の礼として伊勢神宮に自らの皇女大来皇女を捧げたのが初代とする)、以後は天皇の代替わり毎に必ず新しい斎王が選ばれ、南北朝時代まで続く制度となった。 なお、『扶桑略記』に初めて大来皇女が定められたとあること、同皇女の前任と伝える酢香手姫皇女(用明天皇皇女)との間に約50年の空白期間があること、その以前の稚足姫皇女(雄略天皇皇女)、荳角皇女(継体天皇皇女)、磐隈皇女(欽明天皇皇女)、菟道皇女(敏達天皇皇女)、酢香手姫皇女が伊勢に来ていないと考えられることの3点から、酢香手姫以前の斎宮は後世の虚構とする説がある(筑紫申真説)。 また福岡県糟屋郡久山町猪野にあるには、仲哀9年(200年)熊襲征伐の途中、「われを祭れば、戦をせずとも財宝の国を得ることができる」という神の託宣があったが、仲哀天皇が疑ったために、その祟りをうけ香椎宮で崩御し、そのことを知った神功皇后が、小山田の村に斎宮を建て、自ら神主となり、天照大神を祀ったという縁起がある。 斎宮の卜定から退下まで 卜定 先代の斎宮が退下すると、未婚の内親王または女王から候補者を選び出し、亀卜(亀の甲を火で焙って出来たひびで判断する卜占)により新たな斎宮を定める)。新斎宮が決定すると、邸に勅使が訪れて斎宮卜定を告げ、伊勢神宮にも奉幣使が遣わされて、斎宮はただちに潔斎に入る。 初斎院 宮城内の便所(便宜の場所)が卜定で定められて大内裏の殿舎(時々により異なる)が斎宮の潔斎所となる。これを初斎院()と呼ぶが、その場所は雅楽寮、宮内省、主殿寮、左右近衛府などが記録に残る。斎宮は初斎院で1年間斎戒生活を送るとされているが、もっと短期になる場合も多い。 野宮 初斎院での潔斎の後、翌年8月上旬に入るのが野宮()である。野宮は京外の清浄な地(平安時代以降は主に嵯峨野)を卜定し、斎宮のために一時的に造営される殿舎で、斎宮一代で取り壊されるならわしだった(野宮神社などがその跡地と言われるが、現在では嵯峨野のどこに野宮が存在したか正確には判っていない)。斎宮は初斎院に引き続き、この野宮で斎戒生活を送りながら翌年9月まで伊勢下向に備えた。なお、野宮は黒木(皮のついたままの木材)で造られ、このため黒木の鳥居が野宮の象徴とされた。『源氏物語』では前東宮と六条御息所の間に生まれた姫宮(後の秋好中宮)が「葵」帖で斎宮となったため、六条御息所がそれに同道することになり、『賢木巻』でこの野宮が光源氏との別れの舞台となり、後に能『野宮』の題材にもなった。 群行 詳細は「群行」を参照 初斎院・野宮を経て3年目の9月、野宮を出て禊の後、宮中で群行の儀に臨み、伊勢へ発向する。但し後述「退下」のように歴代の斎宮すべてが群行を行ったわけではない。 斎宮寮と祭祀 伊勢での斎宮の生活の地は、伊勢神宮から約20キロ離れた斎宮寮(現在の三重県多気郡明和町)であった。普段はここで寮内の斎殿を遥拝しながら潔斎の日々を送り、年に3度、「三時祭」(6月・12月の月次祭と9月の神嘗祭。三節祭とも)に限って神宮へ赴き神事に奉仕した。 斎宮寮には寮頭以下総勢500人あまりの人々が仕え、137ヘクタール余りの敷地に碁盤の目状の区画が並ぶ大規模なものだったことが、遺跡の発掘から判明している。特筆すべきは緑(青?)釉陶器の出土であり、色に何か意味があった可能性も考えられる。なお、斎宮跡は昭和45年(1970年)の発掘調査でその存在が確認され同54年に国の史跡に指定されたが、その後も発掘中である。 三時祭は外宮では各月の15・16日の、内宮は16・17日の両日に行われるが、斎宮はその2日目に参加し、太玉串を宮司から受取り、瑞垣御門の前の西側に立てる。また、2月祈年祭、11月新嘗祭で多気、度会の両神郡内の115座の神々に幣帛を分配する。 退下 斎宮が任を終えることを、奈良時代から平安時代中期まで(8〜10世紀頃)は退出と称したが、その後は退下または下座と言った。 斎宮の退下は通常、天皇の崩御或いは譲位の際とされるが、それ以外にも斎宮の父母や近親の死去による忌喪、潔斎中の密通などの不祥事、また斎宮の薨去による退下もあり、初斎院や野宮での潔斎中に退下した斎宮も多い。 なお、伊勢での在任中に薨去した場合は現地に葬られたらしい(伊勢で薨去した斎宮として確実なのは平安時代の隆子女王と惇子内親王の2人で、いずれも斎宮跡近くに墓所と伝わる御陵が残る)。退下の後、前斎宮は数ヶ月の間、伊勢で待機し準備が整った後に、奉迎使に伴われて帰京した。 帰京の道程は二通りあり、天皇譲位の時は群行の往路と同じ鈴鹿峠・近江路を辿るが、その他の凶事(天皇崩御、近親者の喪など)の場合には伊賀・大和路(一志、川口、阿保、相楽)を経て帰還するのが通例であった。どちらの行程も最後は船で淀川を下り、難波津で禊の後に河陽宮を経て入京した。 また、酢香手姫皇女以前の斎宮は酢香手姫皇女が任を終えて葛城に移ったと記されるのみで、稚足姫皇女を除くと他の斎宮のその後は不明。単なる記載漏れか、当然帰るべき所(例えば宮廷の周囲)があったので省略されたか、それとも、酢香手姫皇女の移転先である「葛城」の記載が他の斎宮の移転先をも代表しているとみるか、様々に推測できる。 退下後の斎宮 退下後の前斎宮のその後はごく数人を除いてあまり知られていない。律令制では本来内親王の婚姻相手は皇族に限られるため、奈良時代までは退下後の前斎宮が嫁いだのは天皇もしくは皇族のみであり、平安時代以降も内親王で臣下に降嫁したのは雅子内親王(藤原師輔室)ただ1人であった(ただし女王ではもう一人、藤原教通室となった嫥子女王がいる)。また藤原道雅と密通した当子内親王は父三条天皇の怒りに触れて仲を裂かれており、結婚は禁忌ではなかったらしいが、多くの前斎宮は生涯独身だったとも思われる。 ちなみに退下後に入内を果たした前斎宮に井上内親王(光仁天皇皇后、後廃位)、酒人内親王(桓武天皇妃)、朝原内親王(平城天皇妃)、徽子女王(村上天皇女御)の4人がいるが、井上・酒人・朝原の3内親王は母娘3代にわたり、斎宮となりかつ入内した(南北朝時代の懽子内親王も光厳上皇妃であるが、天皇退位後の入内である)。 その後院政期には、未婚のままで天皇の准母として非妻后の皇后(尊称皇后)、さらに女院となる内親王が現れる。この初例は白河天皇の愛娘媞子内親王(郁芳門院)であり、彼女は斎宮経験者であった。以後これに倣い、斎宮または斎院から准母立后し女院となる例が斎宮及び斎院制度の途絶まで見られた。 斎宮の終焉 平安時代末期になると、治承・寿永の乱(源平合戦)の混乱で斎宮は一時途絶する。その後復活したが(もう一つの斎王であった賀茂斎院は承久の乱を境に廃絶)、鎌倉時代後半には卜定さえ途絶えがちとなり、持明院統の歴代天皇においては置かれる事もなく、南北朝時代の幕開けとなる延元の乱により、時の斎宮祥子内親王(後醍醐天皇皇女)が群行せずに野宮から退下したのを最後に途絶した。この年は辛酉の年にあたり、かつ元日が辛酉の日[注 10]であった。辛酉とは中国の易姓革命思想において革命が起こる年と考えられており、 〇「易姓革命」(えきせいかくめい)とは、古代中国において起こった孟子らの儒教に基づく、五行思想などから王朝の交代を正当化する理論。 周の武王が殷の紂王を滅ぼした頃から唱えられ、天は己に成り代わって王朝に地上を治めさせるが、徳を失った現在の王朝に天が見切りをつけたとき、「革命(天命を革める)」が起きるとされた。 それを悟って、君主(天子、即ち天の子)が自ら位を譲るのを「禅譲」、武力によって追放されることを「放伐」といった。無論、堯舜などの神話の時代を除けば禅譲の事例は実力を背景とした形式的なものに過ぎない。 後漢から禅譲を受けた魏の曹丕は「堯舜の行ったことがわかった(堯舜の禅譲もまたこの様なものであったのであろう)」と言っている。後漢(劉氏)から魏(曹氏)のように、前王朝(とその王族)が徳を失い、新たな徳を備えた一族が新王朝を立てた(姓が易わる)というのが基本的な考え方であり、血統の断絶ではなく、徳の断絶が易姓革命の根拠としている。儒家孟子は易姓革命において禅譲と武力による王位簒奪の放伐も認めた。 ほとんどの新王朝の場合は史書編纂などで歴代王朝の正統な後継であることを強調する一方で、新王朝の正当性を強調するために前王朝と末代皇帝の不徳と悪逆が強調されるが(有名な桀・紂以外にも、煬帝のように悪い諡号を送られたり、そもそも諡号や廟号を送られない場合もある)、形式上は明に対する反逆者である李自成を討って天下を継承した清のような場合は、明の末代皇帝崇禎帝を一応は顕彰し、諡号や廟号も与えられている。 このように、易姓革命論は実体としては王朝交代を正当化する理論と言える[1]。またこのような理論があったからこそ劉邦や朱元璋のような平民からの成り上がり者の支配を正当化することが出来たとも言える。これは西洋において長年に渡る君主の血統が最も重視され、ある国の君主の直系が断絶した際、国内に君主たるに相応しい血統の者が存在しない場合には、他国の君主の血族から新しい王を迎えて新王朝を興す場合すらあるのとは対照的である。 また、日本では、山鹿素行など江戸時代の学者が「易姓革命は結局臣が君を倒すことで、そのようなことがしょっちゅう起こっている中国は中華の名に値しない。建国以来万世一系の日本こそ中華である」と唱えた。素行の著「中朝事実」はそのような思想によって記された日本史の本である。 五行思想面からの説明では、万物には木火土金水の徳があり、王朝もこの中のどれかの徳を持っているとされた。たとえば、漢の末期を揺るがした184年の黄巾の乱は、「蒼天已死 黄天當立 歳在甲子 天下大吉(蒼天已に死す、黄天当に立つべし、歳は甲子に在りて、天下大いに吉とならん、『後漢書』71巻 皇甫嵩朱鑈列傳 第61 皇甫嵩伝[2])」のスローガンが掲げられた。漢朝は火の徳を持っているとされ、漢朝に代わる王朝は土の徳を持っているはずだとの意味である。 王朝交代が起きなかった日本においても、「辛酉」は政治の刷新が期待される年であるとする思想は共有されていた。したがってこの時光仁天皇は山部親王すなわち後の桓武天皇に譲位する内意を固めていたとする。この改元の詔において、光仁天皇は異例の呼びかけを行っている。呰麻呂らのために道を誤って離反した百姓が「賊」を棄てて戻ってくるなら、三年間の課役免除を与えるとするものである。乱のために逃亡を余儀なくされた住民が多かったことを物語る内容であるが、果たして天応元年(781年)4月、光仁天皇は退位し桓武天皇が即位するのである。問題の解決は桓武天皇に託されることになり、征夷は都の造営と並んで彼の生涯の事業となる。了
2024年11月26日
閲覧総数 45
-
9

「歴史の回想・宝亀の乱」三十八年戦争。 川村一彦
「三十八年戦争」を経て、この時期(9世紀初)に現れた城柵が胆沢城、志波城、第Ⅱ次雄勝城説が有力視される払田柵跡、城輪柵、そして徳丹城である。この時代の城柵はそれまでの丘陵地ではなく(かつ、地形上の制約を受ける不整形の外郭でなく)、平地上に方形で作られている。 阿弖流爲と母礼の降伏及び処刑を挟んで、胆沢城は延暦21年(802年)、志波城は延暦22年(803年)に造営が開始された(それぞれ現在の岩手県奥州市及び盛岡市)。 それまで陸奥国の国府機構と鎮守府とで兼任となっていた官制を分離し、多賀城から胆沢城に鎮守府が移された。この官制の分離は、胆沢地方の征服により拡大した朝廷の支配域に対し、陸奥国司が鎮守府官人を兼ねる従来の官制では対応できなくなったためと考えられ、鎮守府は胆沢城を拠点として陸奥国北部を支配する統治機関へと変質していくこととなる。 多賀城に代わる新たな鎮守府となった胆沢城は、一辺約670m四方の築地塀による外郭と、一辺約90mの政庁を持ち、外郭南門は多賀城の規模を上回る、正面5間の重層門となっていた。 胆沢城の翌々年に造営が開始された志波城はそれをさらに凌駕する一辺840m四方、推定高さ4.5mの築地塀による外郭を持ち、当初は胆沢城より重要な城柵だったものと推定されている。 時期をほぼ同じくして出羽国でも、払田柵跡が東西1370m、南北780mという規模で造営されている(現在の秋田県大仙市、美郷町)。 これらの城柵が史上最大規模で造営されたのは、当時の朝廷がまだ北に向かって支配を拡大する意思を持っていたことのあらわれであると考えられる。 事実、志波城が完成したとみられる延暦23年正月には、坂上田村麻呂が再度征夷大将軍に任命され、桓武期での第四次征討計画が検討されている。しかし、この征夷計画は副将軍、軍監、軍曹などの人事が行われたもののその後進展せずに、翌年の徳政相論により都の造作と征夷の中止が国家の方針として決定されるに至って、計画が破棄されることとなった。 これは、桓武天皇の治世で行われた都の造作(長岡京、平安京)と征夷により、民衆の疲弊と国家財政の窮乏が進んだことで方針転換に至らざるを得なかったためであり、治世末期に行われたこの徳政相論のおよそ3か月後に、桓武天皇は崩御している。 桓武天皇の崩御を受けて即位した平城天皇及び、平城天皇から譲位された嵯峨天皇の治世でも、徳政相論で示された方針が踏襲されることとなった。平城天皇の治世はおよそ3年と短いが、中央の官司を整理したり、参議を廃して観察使を設置するなど財政と民生の回復に意を注ぐものであり、軍事政策についても版図不拡大の方針が確立する時期である。嵯峨天皇についても、平城天皇が行った政策の是正がしばしば行われたものの、弘仁2年(811年)の文屋綿麻呂の征夷は長年の征夷政策を終結させるために行った事業であり、徳政相論の方針と矛盾する性質のものではない。この時期の政策は、長年征夷政策を遂行するための人的・物的資源の供給源とされ、疲弊の著しかった東国の諸負担を開放することに主眼が置かれており、柵戸については延暦21年正月に胆沢城周辺に東国の浮浪人4,000人が送り込まれたのを最後に実施されず、鎮兵についても大同年間(806年-810年)に東国からの派遣が停止されて、陸奥・出羽両国からの徴発に改められた。 最後の征夷が行われた弘仁2年(811年)の閏12月、征夷将軍であった文屋綿麻呂は陸奥国の鎮兵3,800人を段階的に1,000人まで削減し、陸奥国に置かれていた4個軍団4,000人の兵力も2個2,000人まで縮小することを奏請した。この縮減の動きと関連して城柵の再編が行われ、史上最大規模の城柵であった志波城に代わって築かれたのが、最後の城柵である徳丹城である(現在の岩手県紫波郡矢巾町)。 志波城が雫石川に近く、しばしば氾濫による水害を被ることを理由とした理由とした移転だが、徳丹城は志波城より南に10㎞ほど後退し、外郭の規模も志波城の一辺約840mから一辺約355mへと大幅に縮小された。これは徳政相論以後の律令国家が、従前の版図拡大政策を放棄して現状維持に転換したことを示す考古学的な証左であるとみられる。また、以前から残る城柵に収められていた武器や食糧も他所に移され、この時に伊治城や中山柵が廃止されたものと推測されている。弘仁6年(815年)には鎮兵の制度が完全に廃止され、城柵の守備は軍団の兵士と、勲位を有する者を兵士に指定した健士によって担われることとなった。なお、発掘調査により、徳丹城の機能も9世紀半ばまでには廃絶したものと推測されている。 城柵の時代の終焉 鎮守府を胆沢城(ついで志波城)に移して軍事的な性格が後退した多賀城は、他国の国府と共通する官衙としての性格を強めていくこととなる。史料上に多賀城が「城」として表記されるのは「忽至城下」(たちまち城下に至る)と記録された貞観11年(869年)が最後で、その復旧は貞観12年(870年)「修理府」(府を修理す)とあり、以後はすべて多賀国府と記されるようになり、城柵としての位置づけは希薄となっていく。 承和年間(834年-847年)とみられる徳丹城と玉造塞の停止をもって、9世紀中葉に残存する城柵は、多賀城、秋田城、胆沢城、第Ⅱ次雄勝城とみられる払田柵跡、出羽国府とみられる城輪柵跡の5つとなった。これらの5城柵は10世紀中葉までは機能していたものと考えられ、最後まで残った多賀国府(多賀城)、秋田城は10世紀中葉あるいは11世紀前半ごろまで機能したものと考えられる。また胆沢城も、10世紀中葉以降の姿は考古学的には瞭らかでないものの、文献資料の上では胆沢鎮守府として後代まで現れており、鎮守府将軍の職名は後々まで残ることとなる。 終末期まで残った城柵は、鎮守府の在庁官人として現地の機構を掌握していたとみられる安倍氏や、同じく中央の貴族が下向して雄勝城の在庁官人として土着したとみられる清原氏など、その後の東北地方の歴史に関わる存在にとっての揺籃の役割を果たした。 特に終末期まで残り東北地方北部の「第二国府」的な役割を果たした胆沢城(鎮守府)、秋田城を通じた支配体制は「鎮守府・秋田城体制」とも呼ばれるが、一方で「鎮守府・秋田城体制」はあくまで中世史研究上の要請に基づいて理論化されたものであるという面を指摘し、鎮守府・秋田城とも陸奥・出羽両国府の被官以上の存在でなく、これに見直しを迫る見解も存在する。 国家事業としての征夷が終息を迎え、軍事的な緊張が緩和された中でも、ただちに蝦夷の支配が安定した訳でなかった。9世紀中葉には陸奥国の奥郡で蝦夷系住民と移民系住民の対立による騒乱が連年のように発生しており、出羽国では元慶2年(878年)、同国で史上空前の反乱である元慶の乱が発生している。また、9世紀から10世紀にかけての日本、なかんずく東北地方は貞観11年(869年)の貞観津波あるいは十和田火山の噴火など巨大な自然災害が頻発した時期でもある。このような情勢のもと、東北地方の社会全体の不安定な状況は9世紀後半から10世紀にかけて続くことになった。 また、あるいは10世紀中葉以降は、考古学的に検出される城柵遺構が消滅していく時期にあたり、これは全国的に他の国府遺構でも軌を一にする現象でもある。これは律令国家から王朝国家へと変容していく中で、地方支配が受領を通じた徴税請負に特化していき、律令体制下のような壮大な官衙ではなく国司館のような「館」支配へと転換していったとみられることによる。 実際の城柵が消滅していくにもかかわらず文献上に国守や鎮守府将軍、秋田城介といった官職が現れるのは、地方支配の拠点が城柵内の政庁ではなくこれら官人の公邸である館へと転換していたことを窺わせるものである。 〇「陸奥按察使」(むつあぜち、みちのくのあぜち)は、日本の奈良時代から平安時代に日本の東北地方に置かれた官職である。しばしば陸奥出羽按察使(むつでわのあぜち、みちのくいではのあぜち)とも言われた。720年頃に設置され、陸奥国と出羽国を管轄し、東北地方の行政を統一的に監督した。他の地方の按察使が任命されなくなってからも継続したが、817年以降は中央の顕官の兼職となり、形骸化した。令外官で、属官に記事があった。官位相当は721年に正五位上、812年から従四位下と定められたが、実際の位階は従五位上から正二位までの幅があった。 陸奥按察使の成立 按察使は養老3年(719年)7月に、全国ではなく一部地域を対象に設置された。陸奥・出羽両国は含まれなかったが、間もなく任命されたことが『続日本紀』が伝える翌年の事件で知れる。 すなわち養老4年(720年)9月28日に、按察使の上毛野広人が蝦夷に殺されたと陸奥国が報告した。この時期の陸奥国は一時的に石城国、石背国、陸奥国に三分されていた。広人が「陸奥按察使」だったとは明記されないが、状況的に陸奥守の兼任で石城国と石背国を下におき、出羽国は含めなかったものとみられる。 養老5年(721年)6月10日に按察使の位は正五位上相当と定められた。陸奥按察使が出羽国を隷下におさめたのは同年8月19日であった 当時、按察使は一般に職田6町と仕丁5人を給された。
2024年11月26日
閲覧総数 39
-
10

「歴史の回想・宝亀の乱」 秋田城非国府説の視点と論者。
秋田城非国府説の視点と論者 一方、秋田城非国府説を取る今泉隆雄の学説では、出羽国国府は一貫して出羽郡内にあったものと推測し、多賀柵から出羽柵までの直通道路についても、「陸奥国より出羽柵に達するに」との記述に着目して、両者の字句の違いは出羽柵が国府でなかったことを指し示すものとする。その上で国府の移転に関する記事と秋田城の停廃に関する記事との峻別の必要性を指摘し、河辺府とは後の河辺郡付近に置かれた郡衙であるとした。また今泉説では、宝亀初年に出羽国の要請で秋田城が停廃されており、『続日本紀』に記録される秋田城停廃を巡るやり取りがあった780年(宝亀11年)時点では、秋田城から一切の軍備が引き上げられていたと推測している。 熊谷公男も今泉説を継承する立場にあり、機能を停止していた時期の秋田城に国府が置かれていたことを否定する。このように秋田城非国府説を取る論者は、文献史学の立場から、『続日本紀』などの解釈をその主要な根拠とすることが多い。 また今泉隆雄は、秋田城から国司署名の文書が出土するならば、それはむしろ国府から発給された文書の宛先が秋田城であることを示すのであり、秋田城が国府でなかったことの傍証であるともしている。ただし、これについて古代の公文書の廃棄課程をまとめた森田悌の研究により、発給元に返還される例があるとする反論がなされている。 そもそも、秋田城の立地とは前述のように朝廷の支配域から北に突出したものであった。すなわち、最前線の城柵として危険に晒されるリスクを負っており、このような場所に国府を置くのだろうかという疑問が、秋田城非国府説の基本的な出発点と言える。国府の業務の内重要なものの一つである部内巡行についても、761年(天平宝字3年)の雄勝城(第I期)完成まで駅路さえ通じていなかった秋田城ではきわめて困難と考えられており、この点からも秋田城国府説に疑問が呈されている。 秋田城の構造と遺構 基本構造 秋田城は、秋田平野の西部、雄物川(秋田運河)右岸河口近くにある、標高40mほどの丘陵地上に造営された城である。城柵の基本構造は、築地塀などで囲われた外郭と、政庁を囲う内郭との二重構造からなり、外郭の東西南北に城門が配置されていた。政庁の配置は、正殿の南面に広場を設け左右に脇殿を配する「コ」の字型の施設配置となっており、これは都城にみられるような、大極殿正面に朝庭を設け、左右に朝堂を配する様式と共通する。 政庁施設は奈良時代から平安時代にかけてI – VI期の6期に渡る変遷が認められるが、政庁を囲う内郭の位置について大きな変化はなく、また「コ」の字型の建物配置も全期を通じて維持されている。 外郭の範囲と構造、城の外郭の範囲は、右上図赤線で示した通り北西部を切り欠いたような不整方形である。外郭の範囲は、東西・南北ともおよそ550m、約30haの広さを持つ[38]。外郭の位置も全期を通じて大きな変化は見られないが、塀の構造にはI – Ⅴ期までの5期に渡る変遷が見られた。このような構造の変更は出羽側の城柵にみられる特徴で、それに対し陸奥側では多賀城が拡張した際も築地塀の基本構造を維持している。秋田城では9世紀初頭に築地塀から材木塀に変更され、官衙としての荘重さが後退したことから、この時期に秋田城の性質が大きく変化したことが示唆されている。 外郭の構造は奈良時代のI期では瓦葺きの築地塀、同じく奈良時代のⅡ期では非瓦葺きの築地塀、平安時代に入ってからのⅢ期は柱列による材木塀、IⅤ期は材木列による材木塀、Ⅴ期は明確でなく、堀による区画がなされたと考えられている。Ⅴ期の堀は深さ1m、幅3mを超すものであるが、城の東辺、西辺での発見であり外周全体を囲うものであったかは定かでない。 Ⅲ期以降は外郭に附設して櫓が設けられており、検出された遺構からの推定では、およそ80 – 90㎡間隔で外郭に櫓が並んでいたと考えられている。外郭の城門はこれまで東門が確認されていたが、2008年(平成20年)の第92次調査で西門が、2012年(平成22年)の第101次調査で南門がそれぞれ発見されている。なお、2013年時点では北門は未だ発見されていない。外郭東門および附設の築地塀(延長45m)、幅12mの東大路が1998年(平成10年)に復元されており[44]、創建期の姿を現在に伝えている。 内郭と政庁の配置 内郭にあたる政庁跡は城域の中心からやや南西寄りに位置しており、その規模は創建期のもので東西約94m、南北約77mと、東西方向の差渡しの方がやや長い、横長の長方形となっている点が特徴である。八木光則によると東北地方の城柵における政庁の規模は以下の3つの類型に分けられ、秋田城は多賀城等より一回り小さい規模の地域中核拠点であるとされる。 秋田城の創建時期は多賀城の9年後であるため、当初の正殿・脇殿の建物構造は多賀城I期を踏襲し、共通点が多く見られた。多賀城正殿の四面廂と秋田城の南相廂という差異は見られるが、これは太平洋側と日本海側の降雪量の差を反映したものと考えられており、建物面積はほぼ同等である。一方で内郭そのものの面積は大きく異なることから、この点で陸奥国府を併置した多賀城と国府を置かなかった秋田城の差異が現れたと考えられている。 政庁跡ではI期からVI期までの変遷(うちVI期はさらにA期とB期の2小期に分けられる)が見られたが、「コ」の字型の施設配置は全期を通じて維持された。多賀城では8世紀の後半に正殿・脇殿が礎石化され、城域を拡大するなど、官衙が拡大充実していくのに対し、秋田城ではこの時期も当初の構造が変化せず、多賀城とは異なる路線を歩むこととなった。この点も、陸奥側では王権の支配域の拡大にともない、多賀城が桃生城、伊治城等を後方から支援する面的支配の拠点に変質していったのに対し、出羽国の北端に突出する秋田城では在地の蝦夷の饗応や渤海使受け入れなど、設置当初からの秋田城固有の役割が変化しなかったためであると考えられている。なお、秋田城の政庁がI期からVI期までの掘立式から礎石式に移行するのは最終期であるVI期においてであるが、なぜ最終期に礎石式に移行したのかは不明である。 政庁の様式は都の朝堂、あるいは各国の国衙に倣うものであり、秋田城は地域一帯の行政の拠点でもあったことから、政庁では一般の政務のほか、在地の蝦夷の饗応、さらには渤海使をはじめとする外交使節に対する送迎の儀式も行われていたものと考えられている。 なお、政庁跡を道路(国道7号旧々道)が跨いでいるために南西側が約3分の1に渡って削平・破壊されており、西脇殿・政庁南門の様相は不明である。 城内東部の大畑地区において掘立柱建物群、竪穴住居群、鍛冶工房群などの遺構が検出されており、この地区で発掘された考古資料には、非鉄製小札甲や漆紙文書、胞衣壺埋納機構など、貴重なものが含まれる。 この地区は竪穴住居が営まれて居住域として利用される時期もあったが、全体としては平安時代以降秋田城を支える生産施設として利用されたと考えられており、9世紀の前半から中頃にかけて盛期を迎えた。鉄生産施設も置かれており、大畑地区のように郭内の一定の区域に工房がまとまって置かれ、継続的に営まれた事例は珍しいものとされる。 したがってこの頃秋田城は守衛が停止され、機能を停止していたとみられる。そのためこれまで秋田城を通じて朝貢し、饗給を受けていたとみられる渡嶋(北海道)の蝦夷に対しては、宝亀11年5月、鎮狄将軍(家麻呂)と出羽国司に、渡嶋蝦夷が離反しないよう特に懇ろに饗応すべしと命じる勅が出されている。 8「秋田城の停廃問題」呰麻呂の反乱の以前から現在の東北地方の情勢はかなり不穏であり、呰麻呂の乱に先立つ宝亀5年(774年)には、海道蝦夷が反乱して桃生城を襲撃した。後世、「三十八年戦争」とも称される苛烈な戦乱の時代はこの時既に始まりを迎えていたのであり、そもそも呰麻呂や伊佐西古が政府から叙位を受けていたのも、そのような情勢下で政府側に立って活動した功績を嘉されてのことである。出羽国においても、宝亀2年(771年)の渤海国使来着を伝える記事の中で「出羽国賊地野代」 〇「渤海使」(ぼっかいし)は、渤海より日本を訪問した使節である。727年秋から919年までの間に34回(または922年までの間に35回。このほか929年、後継の東丹国(契丹(後の遼)の封国)による派遣が1回)の使節が記録に残っている。 渤海は698年に大祚栄により建国されたが、大武芸の時代になると唐や新羅と外交的に対立するようになり、国際的孤立に陥りそうになった渤海が、これらの勢力を牽制する目的で日本への遣使が計画された。使節団が日本に向かった出発地点は、ロシア沿海地方ポシェト湾近くにあるクラスキノ土城(塩州城)遺跡が有力とされる[1]。 渤海側は軍事同盟を結ぼうとして使節を送っていたが、日本側は突然、貢物を持って来朝してきたところから、これを日本の国威を慕って、日本に従属を願い出て、従国の礼をとってきた朝貢であると捉え、使節を非常に厚遇している。 しかし大欽茂の時代になり、唐との融和が図られる時代になると軍事的な意味合いは薄れ、もっぱら文化交流と経済活動を中心とした使節へとその性格を変化させていった。 特に問題となったのは朝貢貿易の形態を取ったことで、これにより渤海からの貢物に対して日本側では数倍の回賜でもって応える義務が生じ、渤海に多大な利益をもたらした。日本側は、朝廷の徴税能力が衰え、使節供応と回賜のための経費が重荷となった後は、使節来朝を12年に1度にするなどの制限を加えたが、その交流は渤海滅亡まで継続した。 唐渤関係の安定化に伴い、日唐間の交通の仲介として機能した。遭難して帰国できなかった遣唐使の平群広成が渤海使と共に帰国に成功したこと、日本で最も長く使われた暦である唐の宣明暦が渤海使により伝来したことはその例である。また『新唐書』渤海伝は唐の大暦年間(766年~779年)に渤海国が日本の舞女11人を唐に献上したことを伝えており、彼女らはそれ以前に日本から渤海に渡ったと見られる。 貿易品目 8世紀後半以降は渤海からはもっぱら北方産の獣皮(貂、虎、羆などの毛)また人参、蜜、日本からは繊維製品がほとんどで、他に金・水銀、金漆(山地に自生するコシアブラの木の実から搾り取った樹液で、強化剤や硬化接着剤として古代では用途の広い重宝な樹液)海石榴油一缶(髪油などの化粧用、皮革、金属の保存、さび止めなどに使用)水精念珠(真珠)、檳榔樹扇(今でも沖縄や台湾などで土産物として使われる檳榔樹の葉で作った扇)が貿易品目として扱われた[3]。 渤海使と漢詩 共に唐の漢字文化圏に属している渤海と日本の宮廷社会を構成する上級階層にとって、漢籍、漢文学の学習が基礎教養とされていた。互いに話す言葉は通じなくても、筆談すれば意志は通じ、文書の類は翻訳せずともそのまま通用する状況であった。 特に漢籍・漢文学が発達したのは、軍事的提携を結ぼうとして行われた初期の外交期ではなく、交易目的の経済外交として変化した時期以降である。渤海使も初期のころは全員武官の肩書を持っていたが、 762年(天平宝字6年)に来日した第6回渤海使王新福からは、文官の使節となり、ほとんどが漢詩文に長じた文人が選ばれて来日している。Ø 漢詩の応酬が行われた最初(記録上の初めという意)は、758年(天平宝字2年)に来日した第4回渤海使揚承慶の時であった。揚承慶らは、朝廷での正式な宴の他に藤原仲麻呂の私邸「田村第」に招かれ歓待を受けた。その際、当代の文士が集められ、漢詩を賦して使節を送別した。これに対し渤海使の方では文人であったと見える副使「楊泰師」(揚泰師)が漢詩を2首作ってこれに和した。その2首である七言の「夜聴擣衣」と五言の「奉和紀朝臣公詠雪詩」は『経国集』に残っている。Ø 文化人的性格の嵯峨天皇の権力が確立された後の第17回渤海使は、大使、副使以下、判官、録事に至るまで、文人をそろえた使節団を編成し派遣された。814年(弘仁5年)9月、出雲に到着したこの渤海使に対して、日本側は屈指の文人滋野貞主と坂上今継が存問兼領渤海客使として派遣された。(これは、平安朝の漢詩集『文華秀麗集』に残る巨勢識人や、渤海大使・王孝廉の詩題によって知ることが出来る。)やがて、年内に入京した使節団は元旦からの儀式、宴会に参列し、特に正月7日の使節団饗応のために開かれた宴では漢詩の交歓が行われた。この宴席での作と思われる渤海側3首、日本側5首の漢詩は『文華秀麗集』に撰集されている。1月22日に京を出て帰国の途についた後も漢詩を交歓しており、王孝廉の作品3首が同じく『文華秀麗集』に撰集されている。Ø この他にも、渤海からは王文矩、周元伯、楊成規、裴頲、裴璆などの一級文人が来日し、日本からは菅原清公、菅原道真、嶋田忠臣、都良香、紀長谷雄、大江朝綱、藤原雅量などの文人が応対している。交歓された漢詩は『経国集』、『文華秀麗集』の他に、『凌雲集』や『菅家文草』、『田氏家集』『扶桑集』などに残されている。これらの漢詩は、漢詩としての価値だけではなく、当時の状況を把握できる貴重なものとなっている。 (現在の秋田県能代市にあたる)と記されており、従前は秋田城の支配下にあった野代がこの時期政府の支配から離脱して「賊地」となっていた。この野代の蝦夷からの圧迫により、秋田の百姓が攻撃される恐れがあったので、秋田城を停廃して、民衆を河辺郡に移そうとする考えが宝亀初期より存在した。百姓が移住を嫌がったので宝亀11年まで移住を実現できず問題が先送りとなっていたが、当事国である出羽国としては、秋田城の維持にかかる負担は過重だったのである。この秋田城の停廃問題であるが、この宝亀初期から宝亀11年(780年)まで継続して停止状態にあったとみる見解と、宝亀7年(776年)頃までに一度復活しその後宝亀9年(778年)以後に再度停止したとみる見解があるが、今泉隆雄は後者の見解を採用している。このように秋田城の存廃と、その周辺住民の先行きが揺れ動く中で、秋田城の支配下にあった蝦狄の志良須、俘囚の宇奈古らは、
2024年11月26日
閲覧総数 40
-
11

「歴史の回想・宝亀の乱」延暦十三年征夷。 川村一彦
延暦十三年の征夷 延暦10年1月18日(791年2月25日)に桓武朝第二次蝦夷征討が具体化すると、田村麻呂は百済王俊哲と共に東海道諸国へと派遣され、兵士の簡閲を兼ねて戒具の検査を実施、征討軍の兵力は10万人ほどであった。 7月13日(791年8月17日)に大伴弟麻呂が征東大使に任命されると、田村麻呂は百済王俊哲・多治比浜成・巨勢野足とともに征東副使となった[23]。軍監16人、軍曹58人と伝わるが、軍曹の多さが異例であることから、実戦部隊の指揮官級を多くする配慮ともみれる。 なお実戦経験がないはずの田村麻呂が副使として登用された理由は不明だが、朝廷からみても田村麻呂の戦略家・戦術家としての能力は未知数であったと思われる。 延暦11年の東北地方では、1月11日(792年2月7日)に斯波村の夷・胆沢公阿奴志己等が陸奥国府に使者を送り、日頃から王化に帰したいと考えているものの、伊治村の俘等が妨害して王化を叶えられないと申し出たため、物をあたえて放還したと陸奥国司が政府に報告している。 政府から陸奥国司に対して夷秋は虚言もいい、常に帰服と称して利を求めるので、今後は夷の使者がきてもむやみに賜らないことを命じている。 これは伊治呰麻呂や伊佐西古のように服従した蝦夷が寝返ることもあり、報告では伊治村の俘とあるため不審から政府の言い分としてはもっともであった。同年7月25日(792年8月17日)の勅では夷・爾散南公阿波蘇が王化を慕って入朝を望んでいることを嘉し、入朝を許して路次の国では軍士300騎をもって送迎、国家の威勢を示したとある[原 9]。 同年11月3日(792年11月21日)に阿波蘇、宇漢米公隠賀、俘囚・吉弥候部荒嶋が長岡京へと入京して朝堂院で饗応され、阿波蘇と隠賀は爵位第一等を、荒嶋は外従五位下を賜り、今後も忠誠を尽くすようにと天皇が宣命を述べている。1月時点と7月以降では政府の立場が一転しているため、この頃には蝦夷に対する懐柔策も推進していたのではないかと推測できる。 延暦12年2月17日(793年4月2日)、征東使が征夷使へと改称され、2月21日(793年4月6日)には征夷副使の田村麻呂が天皇に辞見をおこなった。 延暦13年2月1日(794年3月6日)、弟麻呂は征討へ出発。3月16日(794年3月21日)には征夷のことが光仁天皇陵と天智天皇陵に報告され、3月17日(794年4月21日)には参議・大中臣諸魚に伊勢神宮に奉幣せしめ征夷を報告している。 同年6月13日(794年7月14日)、『日本紀略』には「副将軍坂上大宿禰田村麿已下蝦夷を征す」と短い記事のみあり、『日本後紀』に存在したはずの延暦13年の蝦夷征討の関係記事は散逸しているため、この戦いの具体的な経過や情況はほとんど不明である。9月28日(794年10月26日)には諸国の神社に奉幣して新京に遷ること、および蝦夷を征すことを祈願しているため、蝦夷征討は継続中であったと考えられる。 10月22日(794年11月18日)に長岡京から新京に遷都されると、10月28日(794年11月24日)に新京に到着した報告によると、戦闘終了時に近いとみられる10月下旬時点での官軍側の戦果が「斬首457級、捕虜150人、獲馬85疋、焼落75処」であった。11月8日(794年12月4日)、新京は「平安京」と名付けられる。 延暦14年1月29日(795年2月23日)、弟麻呂は初めて見る平安京に凱旋して天皇に節刀を返上した。同年2月7日(795年3月2日)には征夷の功による叙位が行われたが詳細は伝わらず従四位下に進んだとみられる。2月19日(795年3月14日)に木工頭に任命された。 征夷大将軍 延暦二十年の征夷 延暦15年1月25日(796年3月9日)、田村麻呂は陸奥出羽按察使兼陸奥守に任命されると、同年10月27日(796年11月30日)には鎮守将軍も兼ねることになった。延暦16年11月5日(797年11月27日)、桓武天皇より征夷大将軍に任ぜられたことで、東北地方全般の行政を指揮する官職を全て合わせ持った。桓武朝第三次蝦夷征討が実行されたのは3年後の延暦20年(801年)だが、田村麻呂がどのような準備をしていたかなどの記録は『日本後紀』に記載されていたと思われるものの、記載されている部分が欠落している。 延暦17年閏5月24日(798年7月12日)に従四位上、延暦18年(799年)5月に近衛権中将になると、延暦19年11月6日(800年11月25日)に諸国に配した夷俘を検校するために派遣されている。この頃には肩書きが「征夷大将軍近衛権中将陸奥出羽按察使従四位上兼行陸奥守鎮守将軍」となっていた。 延暦20年2月14日(801年3月31日)、田村麻呂が44歳のときに征夷大将軍として節刀を賜って平安京より出征する。軍勢は4万、軍監5人、軍曹32人であった。この征討は記録に乏しいが、9月27日(801年11月6日)に「征夷大将軍坂上宿禰田村麿等言ふ。臣聞く、云々、夷賊を討伏す」とのみあり[原 、征討が終了していたことがうかがえる。また「討伏」という表現を用いて蝦夷征討の成功を報じている。 同年10月28日(801年12月7日)に凱旋帰京して節刀を返上すると、11月7日(801年12月15日)に「詔して曰はく。云々。陸奥の国の蝦夷等、代を歴時を渉りて辺境を侵実だし、百姓を殺略す。是を以て従四位坂上田村麿大宿禰等を使はして、伐ち平げ掃き治めしむるに云々」と従三位を叙位された。12月には近衛中将に任命された。 胆沢城造営 延暦21年1月7日(802年2月12日)、田村麻呂が霊験があったことを奏上した陸奥国の3神に位階が加えられた。 同年1月9日(802年2月14日)、田村麻呂は造陸奥国胆沢城使として胆沢城を造営するために陸奥国へと派遣された。 同年1月11日(802年2月16日)には、諸国等10ヵ国の浪人4000人を陸奥国胆沢城の周辺に移住させることが勅によって命じられている。かつては胆沢城の造営について、大墓公阿弖利爲らを降伏に追い込む契機となった出来事ではないかと指摘されてきた。 近年では和平交渉の結果、阿弖利爲らの正式降伏に向けてシナリオが定まり、それにともなって戦闘が全面的に終結したため、本格的な造営工事の着手が可能になったとの見方もされている。 同年1月20日(802年2月25日)に田村麻呂が度者(僧侶)を1人賜っている。理由は不明であるが、『類聚国史』によると田村麻呂を含めた8人が度者1人を一括して賜ったとある。戦乱による彼我の戦没者の冥福を祈るため、蝦夷の教化のためなどの説が推定されている。 大墓公阿弖利爲の降伏 延暦21年4月15日(802年5月19日)、胆沢城造営中に大墓公阿弖利爲と盤具公母禮等が種類500余人を率いて降伏してきたことが田村麻呂から平安京へと報告された。阿弖利爲らの根拠地はすでに征服されており、北方の蝦夷の族長もすでに服属していたため、大墓公阿弖利爲らは進退きわまっていたものと考えられる。 また、降伏のさいに古代中国の礼法である「面縛待命」がおこなわれた可能性を説く学者もいるが、史料にはそこまでは書かれておらず、和平交渉が重ねられた末の降伏と見ることも不当ではないため、厳しい礼法が実施されたとはやや考えがたい。 同年7月10日(802年8月11日)には田村麻呂が付き添い、夷大墓公阿弖利爲と盤具公母禮等が平安京に向かった。『日本紀略』には「田村麿来」とのみあり、阿弖利爲と母禮が「入京」したとは記されていない。また「夷大墓公二人並びに従ふ」とあることから、この時点では捕虜の扱いではなかったとも説かれる。 上記に関連して同年25日(802年8月26日)には平安京で百官が上表を奉って、蝦夷の平定を祝賀している。 同年8月13日(802年9月13日)、陸奥の奥地の賊の首領であることを理由に夷大墓公阿弖利爲と盤具公母禮等の2人が斬られた。『日本紀略』には公卿会議でのやり取りが記されており、2人を斬るときに田村麻呂らが「この度は大墓公阿弖利爲と盤具公母禮の願を聞き入れて胆沢へと帰し、2人の賊類を招いて取り込もうと思います」と申し入れた。 しかし公卿は執論して「野蛮で獣の心をもち、約束しても覆してしまう。朝廷の威厳によってようやく捕えた梟帥を、田村麻呂らの主張通り陸奥国の奥地に放ち帰すというのは、いわゆる虎を養って患いを後に残すようなものである」と反対した。公卿の意見が受け容れられたことで、阿弖利爲と母禮が捉えられて河内国椙山で斬られた。 田村麻呂は公卿に対して阿弖利爲と母禮を故郷に返して、彼らに現地を治めさせるのが得策であると主張したが、田村麻呂の意見が受け容れられることはなかった。史料がごくわずかで推測の域をでないが、朝威を重んじて軍事(蝦夷征討)の正当化にこだわった桓武天皇の意思によって阿弖利爲らを斬る決定がされたとの論がある。平安京で公卿会議に参加していることから、田村麻呂は河内国椙山に居なかったものと考えられる。 延暦22年3月6日(803年4月1日)、田村麻呂は造志波城使として彩帛50疋、綿300屯を賜って志波城造営のために陸奥国へと派遣された。 参議就任 陸奥国に胆沢城と志波城を築いたこともあり、延暦23年1月19日(804年3月4日)、桓武朝第四次蝦夷征討が計画されると、7ヵ国が糒1万4315斛・米9685斛を陸奥国小田郡中山柵に搬入するよう命じられている。これを受けて田村麻呂が1月28日(804年3月13日)に征夷大将軍に任命され、副将軍には百済教雲・佐伯社屋・道嶋御楯の3名が、そして、軍監8人・軍曹24人が任命されている。 同年5月15日(804年6月25日)、危急に備えて志波城と胆沢郡の間に1駅を、11月7日(804年12月12日)には栗原郡に3駅を置くことなどが決まり、朝廷も蝦夷征討に向けて準備を整えていく。 この頃は平安京にいた田村麻呂は、延暦23年5月に造西寺長官に任命されると、8月7日(804年9月14日)には桓武天皇の巡幸の際の仮宮殿・行宮設定のため和泉国・摂津国に派遣され、10月8日(804年11月13日)には和泉国藺生野(現在の大阪府岸和田市)にて行われた狩猟に随行して桓武天皇に物を献上し、綿200斤を賜っている。この頃の肩書きは「征夷大将軍従三位行近衛中将兼造西寺長官陸奥出羽按察使陸奥守勲二等」であった[44]。 延暦24年6月23日(805年7月22日)、48歳の時に坂上氏出身者として初めてとなる参議に就任した。 同年10月19日(805年11月13日)、清水寺に寺印1面を賜ると、永く坂上氏の私寺とすることを認める太政官符が発符された。11月23日(805年12月17日)には坂本親王の加冠に列席して衣を賜った。 徳政相論 延暦24年12月7日(805年12月31日)、桓武天皇の勅命が中納言・藤原内麻呂に下り、殿中で天下の徳政について相論された。32歳の参議・藤原緒嗣が「方今天下の苦しむ所は、軍事と造作なり。 此の両事を停むれば百姓安んぜん」と桓武朝を象徴する軍事と造作、つまり蝦夷征討と造都事業の中止を論じた。反論の内容は伝わっていないものの65歳の参議・菅野真道は「異議を確執して、肯て聴かず」であった。桓武天皇は若い緒嗣の意見を善しとして認めたため、桓武朝による4度目の蝦夷征夷はここに中止となった。 参議となって半年後に起こった徳政相論の席に田村麻呂も参列していたものと考えられるが、桓武天皇が蝦夷征討の中止を決めたことから、田村麻呂は征夷大将軍として桓武朝第四次蝦夷征討での活躍の機会を失い、これより先は陸奥国へと赴くことはなかった。しかし本来は臨時職である征夷大将軍の称号を生涯に渡って身に帯び続けた。
2024年11月26日
閲覧総数 43
-
12

「歴史の回想・宝亀の乱」光仁天皇から桓武天皇への戦乱時代。
6「光仁天皇から桓武天皇へ戦乱の時代」しかし、結局のところこれらの軍事活動はみるべき成果をもたらさなかった。また、当初反乱の首謀者であったはずの呰麻呂も追捕できなかったばかりか、彼の名はその後の記紀にも現れない。征東使が翌年に帰京するまでの間に、宝亀から天応への改元が行われ、光仁天皇から山部親王すなわち桓武天皇への譲位がなされたが、新天皇である桓武は、呰麻呂ではなく、「賊中の首にして、一を以て千に当たる」として「伊佐西古・諸絞・八十嶋・乙代」の名を敵の首魁として挙げている。 〇「桓武天皇」(かんむてんのう、737年〈天平9年〉- 806年4月9日〈延暦25年3月17日〉)は、日本の第50代天皇(在位:781年4月30日〈天応元年4月3日〉 – 806年4月9日〈延暦25年3月17日〉)。諱は山部(やまのべ / やまべ)。 平城京から長岡京および平安京への遷都を行った。また、践祚と日を隔てて即位した初めての天皇である。桓武平氏の祖にも当たる。 白壁王(後の光仁天皇)の長男(第一王子)として天平9年(737年)に産まれた。生母は百済系渡来人氏族の和氏の出身である高野新笠。当初は皇族としてではなく官僚としての出世が望まれて、大学頭や侍従に任じられた(光仁天皇即位以前は山部王と称された)。 父王の即位後は親王宣下と共に四品が授けられ、後に中務卿に任じられたものの、生母の出自が低かったため立太子は予想されていなかった。しかし、藤原氏などを巻き込んだ政争により、異母弟の皇太子・他戸親王の母である皇后・井上内親王が宝亀3年3月2日(772年4月9日)に、他戸親王が同年5月27日(7月2日)に相次いで突如廃されたために、翌4年1月2日(773年1月29日)に皇太子とされた。 その影には式家の藤原百川による擁立があったとされる[1]。なお井上内親王と他戸親王は同日に同じ幽閉先で逝去したが、他戸親王の実姉(桓武天皇の異母妹にあたる)酒人内親王を妃として、朝原内親王を儲けた。 天応元年4月3日(781年4月30日)には父から譲位されて天皇に即き、翌日の4日(5月1日)には早くも同母弟の早良親王を皇太子と定め、11日後の15日(5月12日)に即位の詔を宣した。 延暦2年4月18日(783年5月23日)に百川の兄・藤原良継の娘・藤原乙牟漏を皇后とし、彼女との間に安殿親王(後の平城天皇)と神野親王(後の嵯峨天皇)を儲けた。また、百川の娘で良継の外孫でもあった夫人・藤原旅子との間には大伴親王(後の淳和天皇)がいる。 延暦4年(785年) 9月頃には、早良親王を藤原種継暗殺の廉により廃太子の上で流罪に処し、親王が抗議のための絶食で配流中に薨去するという事件が起こった。これを受け、同年11月25日(785年12月31日)に安殿親王を皇太子とした。また、同年11月10日、交野柏原(現在の大阪府枚方市)において、日本で初めて、天を祀る郊祀を行った。 延暦6年(787年)11月5日に、交野柏原において、2度目の郊祀を行った。 延暦10年(791年)、藤原乙牟漏の亡きあとに神野親王(嵯峨天皇)の乳母を務めた大秦公忌寸浜刀自女に賀美能宿禰の姓を贈る。(続日本紀) 在位中の延暦25年3月17日(806年4月9日)に崩御。宝算70。安殿親王が平城天皇として即位した。 治世 平城京における肥大化した奈良仏教各寺の影響力を厭い、天武天皇流が自壊して天智天皇流に皇統が戻ったこともあって、当時秦氏が開拓していたものの、ほとんど未開の山城国への遷都を行う。初め延暦3年(784年)に長岡京を造営するが、天災や後述する近親者の不幸・祟りが起こり、その原因を天皇の徳がなく天子の資格がないことにあると民衆に判断されるのを恐れて、わずか10年後の延暦13年(794年)、側近の和気清麻呂・藤原小黒麻呂(北家)らの提言もあり、気学における四神相応の土地相より長岡京から艮方位(東北)に当たる場所の平安京へ改めて遷都した。 また、蝦夷を服属させ東北地方を平定するため、3度にわたる蝦夷征討を敢行、延暦8年(789年)に紀古佐美を征東大使とする最初の軍は惨敗したが、延暦13年の2度目の遠征で征夷大将軍・大伴弟麻呂の補佐役として活躍した坂上田村麻呂を抜擢して、延暦20年(801年)の3度目の遠征で彼を征夷大将軍とする軍を送り、田村麻呂がアテルイら500人の蝦夷を京都へ護送した延暦21年(802年)に蝦夷の脅威は減退、翌22年(803年)に田村麻呂が志波城を築いた時点でほぼ平定された。 しかし晩年の延暦24年(805年)には、平安京の造作と東北への軍事遠征がともに百姓を苦しめているとの藤原緒嗣(百川の長子)の建言を容れて、いずれも中断している(緒嗣と菅野真道とのいわゆる徳政相論)。 また、軍隊に対する差別意識と農民救済の意識から、健児制を導入したことで百姓らの兵役の負担は解消されたが、この制度も間もなく機能しなくなり、9世紀を通じて朝廷は軍事力がない状態になった。その結果として、9世紀の日本列島は無政府状態となり、有力な農民が自衛のために武装して、武士へと成長することとなった。 文化面では『続日本紀』の編纂を発案したとされる。また最澄を還学生(短期留学生)として唐で天台宗を学ばせ、日本の仏教に新たな動きをもたらしたのも桓武天皇治下で、いわゆる「南都六宗」と呼ばれた既存仏教に対しては封戸の没収など圧迫を加えている。また後宮の紊乱ぶりも言われており、それが後の薬子の変へとつながる温床となったともされる。 その他、即位前の宝亀3年には井上内親王と他戸親王の、在位中の延暦4年には早良親王の不自然な薨去といった暗い事件が多々あった。 井上内親王や早良親王の怨霊を恐れて同19年7月23日(800年8月16日)に後者に「崇道天皇」と追号し、前者は皇后位を復すと共にその墓を山陵と追称したりしている。 治世中は2度の遷都や東北への軍事遠征を主導し、地方行政を監査する勘解由使の設置など、歴代天皇の中でもまれに見る積極的な親政を実施したが、青年期に官僚としての教育を受けていたことや壮年期に達してからの即位がこれらの大規模な政策の実行を可能にしたと思われる。しかしながら征東使の軍勢は、これら敵の指導者の一人として討ち果たせなかったばかりか、「賊」4,000人に対して、70人余りの首を持ち帰るに留まった。このため、首を持ち帰ったことを戦果として報告したいと入京を申請した藤原小黒麻呂に対し、桓武天皇は十分な戦果を挙げえないまま軍を解散させたとして叱責し、その入京を認めなかった。そして、副使である内蔵全成または多犬養を先に入京させて、軍中の委細を報告させるよう命じたのである。 〇「内蔵 全成」(くら の またなり)は、奈良時代の貴族。姓は忌寸のち宿禰。官位は正五位上・讃岐守。 内蔵氏(内蔵直・内蔵忌寸)は、坂上氏と同族にあたる漢系渡来氏族で[1]、阿知使主の孫にあたる爾波木直の後裔とする。また、氏の名称は皇室の財物を扱う内蔵を管掌していたことに由来する。 在唐中の遣唐大使・藤原清河を帰国させるための迎入唐使判官に任ぜられて、天平宝字3年(759年)2月に渤海に渡る。 しかし、唐は安史の乱が平定されておらず治安が悪化していたため、迎入唐使総勢99名のうち大使・高元度など11人だけが唐へ赴くこととなり、同年10月に全成らは渤海使・高南申を伴って日本への帰国の途につく。全成の乗った船は暴風に遭って対馬国に漂着し、12月に難波江に帰着した。 宝亀2年(771年)外従五位下に叙せられ、翌宝亀3年(772年)大外記に任ぜられる。同年9月には政情調査のために覆損使として山陰道に派遣された。宝亀8年(777年)内位の従五位下、宝亀10年(779年)二階昇進して正五位下に叙せられるなど、光仁朝末に続けて昇叙される一方、越後介・勅旨少輔なども務めた。 またこの間、宝亀5年(774年)に新羅使・金三玄以下235名が、宝亀10年(779年)に新羅使・金蘭孫が渡来した際には[8]、来朝の目的を問うために大宰府に派遣されている。 天応元年(781年)には宝亀の乱を平定するために征東副使として陸奥国へ派遣される。6月に平城京に帰京して、9月には陸奥守に任ぜられると共に、蝦夷征討の功労によって正五位上の昇叙と勲五等の叙勲を受けた。また、12月には鎮守副将軍も兼ねている。 その後、桓武朝では世職であった大蔵大輔・内蔵頭を務めた後、延暦6年(787年)讃岐守に任ぜられ地方官に転じている。またこの間の延暦4年(785年)には坂上苅田麻呂の上奏により、同族の坂上氏らと共に忌寸姓から宿禰姓へ改姓している。 〇「多 犬養」(おお の いぬかい)は、奈良時代の貴族。氏は太とも記される。姓は朝臣。官位は従五位上・刑部大輔。勲等は勲五等。 称徳朝の天平神護元年(765年)従六位下から四階昇進して従五位下に叙爵し、天平神護2年(766年)近江介次いで信濃守に任ぜられる。神護景雲3年(769年)右少弁として京官に遷る。 宝亀元年(770年)光仁天皇の即位後まもなく式部少輔に任ぜられるが、翌宝亀2年(771年)但馬員外介として地方官に転じる。宝亀7年(776年)式部少輔次いで右少弁に再任され京官に復す。 宝亀11年(780年)伊治呰麻呂の乱(宝亀の乱)が起こると征討副使に任ぜられ、持節征東大使・藤原小黒麻呂に従って蝦夷征討に参加する。しかし、優勢な蝦夷の軍勢の前に征討軍は大規模な軍事作戦を展開できないまま、翌天応元年(781年)5月に部隊の解散と帰京を願う上奏が行われる。 ここで、桓武天皇はすぐの帰京を認めず、副使の犬養もしくは内蔵全成のいずれかを先に入京させ、征討活動の詳細を報告するように命じた。9月になって従軍者に対する叙位・叙勲が行われ、犬養は従五位上・勲五等に叙せられている。その後、延暦4年(785年)刑部大輔に任ぜられた。 それから2か月余りを経た8月から9月にかけて論功行賞が行われ、征東大使の藤原小黒麻呂が正四位下から正三位に昇進し、紀古佐美、百済王俊哲、内蔵全成、多犬養、多治比宇美、百済王英孫、安倍猨嶋墨縄、入間広成ら10人も征夷の労によって叙位されたが、
2024年11月26日
閲覧総数 37
-
13

「歴史の回想・宝亀の乱」対蝦夷戦争期。 川村一彦
対蝦夷戦争期 次に名が上がるのは天平9年(737年)1月の大野東人である。彼は最初の鎮守将軍とも目される人物で、後世まで範とされる支配体制を陸奥・出羽に作り出した。大伴古麻呂は赴任前に橘奈良麻呂の乱に遭った。次の藤原朝狩は陸奥に桃生城、出羽に雄勝城を築いて東北地方の軍事・民政を推進した。いわゆる38年戦争の時代には、大伴駿河麻呂、藤原小黒麻呂、大伴家持、坂上田村麻呂が活躍した。 按察使が任地に赴かず遙任する傾向は他国ではままみられたが、8世紀の陸奥按察使で赴任の用意がなかったのは藤原田麻呂だけである。陸奥按察使は陸奥守か鎮守将軍と兼任することが多かった。参議のような高官が特に下向することもしばしばであった。陸奥・出羽両国を軍事面で束ねる鎮守将軍とも兼任することが多かったが、別人が立つときには按察使のほうが上位であった。 弘仁年間の整備 対蝦夷戦争が終結してから、東北地方では諸制度の整頓が進められた。その中で陸奥出羽按察使に関する規定は待遇改善の方向で改正された。 すなわち、弘仁3年(812年)1月26日に陸奥出羽両国按察使の位階が従四位下に引き上げられた。同年4月7日の太政官符で、陸奥出羽按察使を護衛する傔仗を1人増やして4人にすることになった。 対蝦夷戦争が収束してからもしばらくは、藤原緒嗣、文屋綿麻呂のような能力実績を買われての任命が続いた。両国の行政への積極的関与が見える最後の按察使は巨勢野足である。 遥任による形骸化 弘仁8年(817年)の藤原冬嗣以降、陸奥・出羽両国経営に関わりがない高位の公卿が陸奥出羽按察使を兼任することが多くなった。官位は三位、二位、官職は中納言、大納言である。それとともに遙任が普通になった。陸奥国・出羽国は按察使を介さずそれぞれ中央に直接結びつき、両国の統一行政は行われなくなった。 この現実にあわせ、寛平7年(895年)11月7日には遙授の陸奥出羽按察使の傔杖が廃止された。延喜式にも遙任の按察使に傔杖を与えないことが定められ、さらに与える場合にも太政官への申告を要することになっていた。 『延喜式』にはまた、按察使の公廨(公廨稲)が国守に准じ六分を給することが規定されている。季禄と衣服は陸奥国の正税を交易してあてることになっていた。 〇「紀 広純」(き の ひろずみ)は、奈良時代の公卿。大納言・紀麻呂の孫。左衛士督・紀宇美の子。官位は従四位下・参議。勲等は勲四等。 天平宝字2年(758年)北陸道問民苦使に任ぜられ(この時の位階は正六位上)、天平宝字7年(763年)従五位下・大宰員外少弐に叙任される。天平宝字8年(764年)9月に発生した藤原仲麻呂の乱では大宰府赴任中のためか活動の記録が残っていないが、翌天平神護元年(765年)正月になって薩摩守に左遷される。神護景雲2年(768年)筑後守に復帰する。 光仁朝に入ると、宝亀 2年(771年)閏3月左少弁に任ぜられて京官に復し、宝亀4年(773年)従五位上に叙せられる。宝亀5年(774年)新羅使・金三玄が大宰府に渡来すると河内守に任ぜられた上で、大外記・内蔵全成と共に大宰府に遣わされて、来朝の理由を問う役割を務めている。 宝亀5年(774年)7月鎮守副将軍を兼任して、陸奥守兼鎮守将軍・大伴駿河麻呂の下で蝦夷征討にあたる。翌宝亀6年(775年)9月本官も河内守から陸奥介に変更となり、同年11月には反乱を起こして桃生城へ攻め寄せた蝦夷を鎮圧した功労により、正五位下・勲五等に叙せられた。 その後も蝦夷征討に従事して、陸奥守・陸奥国按察使・鎮守将軍を歴任する。宝亀8年(777年)12月に出羽国志波村の蝦夷を鎮圧しようとして敗れて退却したことを言上。これを受けて鎮守権副将軍に任ぜられた佐伯久良麻呂の加勢によって蝦夷の鎮圧に成功したらしく、翌宝亀9年(778年)6月には従四位下・勲四等に叙せられている。 宝亀11年(780年)2月に参議に任ぜられ公卿に列す。広純は覚鼈柵という砦を建造し、遠くに衛兵や斥候を配置した上で、3月22日に伊治郡大領・伊治呰麻呂ら蝦夷軍を率いて伊治城に入るが、密かに敵側に通じて反乱を起こした呰麻呂に殺害された(宝亀の乱)。呰麻呂はわけあって広純を嫌っていたが、表面上は広純に媚びて仕える振りをしていた。一方で、広純は呰麻呂を非常に信用して気を許していたという[3]。最終官位は按察使参議従四位下。 〇「大伴 真綱」(おおとも の まつな)は、奈良時代の貴族。官位は従五位下・陸奥介。 宝亀8年(777年)従五位下・陸奥介に叙任される。 宝亀11年(780年)陸奥国上治郡(伊治郡)大領・伊治呰麻呂が伊治城で反乱を起こし、按察使・紀広純を殺害する。 この時、ただ一人真綱だけが蝦夷の兵士が包囲する一角を破って脱出し、多賀城に逃れた。多賀城には兵器や兵糧が潤沢にあり、城下の百姓らは競って城中に入り保護を求めた。しかし、真綱と陸奥掾・石川浄足は城の後門から逃走してしまったため、拠り所を失った百姓らは間もなく散り散りに去って行った。数日して蝦夷の兵士が多賀城に襲来し、城の物資を略奪した上で城を焼き放った(宝亀の乱)。 朝廷では即座に中納言・藤原継縄を征東大使とする征討軍の任官が行われ、真綱は陸奥鎮守副将軍に任ぜられている。 紀広純、道嶋大楯の殺害に至ったのち、呰麻呂に呼応して反乱した軍勢が陸奥国府であった多賀城を襲撃し、物資を略奪して城を焼き尽くしたものである。 〇「道嶋 大盾」(みちしま の おおたて・おおだて、生年不詳 - 宝亀11年3月22日(780年5月1日))は、奈良時代の官人。名は大楯とも記される。近衛中将・道嶋嶋足の一族とみられる。官職は陸奥国牡鹿郡大領。 伊治呰麻呂を卑しい夷俘の出と侮っており、恨みを持った呰麻呂により、宝亀11年(780年)に殺害された。また、直後には紀広純も殺されている(宝亀の乱)。 陸奥国、出羽国両国統治の最高責任者であった陸奥按察使が殺害され、多賀城が失陥したことにより、政府による東北地方の経営は大打撃を被った。 〇「多賀城」(たがじょう/たかのき、多賀柵)は、現在の宮城県多賀城市にあった日本の古代城柵。国の特別史跡に指定されている(指定名称は「多賀城跡 附 寺跡」)。 奈良時代から平安時代に陸奥国府や鎮守府が置かれ、11世紀中頃までの東北地方の政治・軍事・文化の中心地であった。なお、周辺はかつて「潟の世界」[3][4]が想定されていたが、にはすでに潟湖的環境は存在せず、かつて「潟」が存在した証拠の一つと例示された砂押川最下流部の「塩入」「塩留」「塩窪」などの地名についても再検討されている。 奈良平城京の律令政府が蝦夷を支配するため、軍事拠点として松島丘陵の南東部分である塩釜丘陵上に設置した。平時は陸奥国を治める国府(役所)として機能した。創建は神亀元年(724)、按察使大野東人が築城したとされる。8世紀初めから11世紀半ばまで存続し、その間大きく4回の造営が行われた。 第1期は724年 – 762年、第2期は762年 – 780年で天平宝字6年(762)藤原恵美朝狩が改修してから宝亀11年(780)伊治公砦麻呂の反乱で焼失するまで、第3期は780年 – 869年で焼失の復興から貞観11年(869年)の大地震(貞観地震)による倒壊および溺死者千人ばかりを出した城下に及ぶ津波被災まで、第4期は869年 – 11世紀半ばで地震及び津波被災からの復興から廃絶までに分けられる。なお、多賀城の「城」としての記載は『日本三代実録』中の貞観津波が「忽至城下」が最後であり、翌貞観12年の日本三代実録では「修理府」、藤原佐世『古今集註孝経』の寛平6年(894)朱書「在陸奥多賀国府」ほか、「府」あるいは「多賀国府」と記載されている。 多賀城創建以前は、仙台郡山遺跡(現在の仙台市太白区)が陸奥国府であったと推定されている。 陸奥国府のほか、鎮守府が置かれ、政庁や食料を貯蔵するための倉などが置かれ、附属寺院が設けられていた。霊亀2年(716)には、移民によって黒川以北十郡(黒川・賀美・色麻・富田・玉造・志太・長岡・新田・小田・牡鹿)が成立し、神亀元年(724)には陸奥国府は仙台郡山遺跡から多賀城に移された。 北方の備えとして石巻平野から大崎平野にかけては天平五柵(牡鹿柵・新田柵・玉造柵・色麻柵・不明の1柵/中山柵かが設置され、これらは石背国・石城国・陸奥国に三分された陸奥国を養老4年(720)ふたたび統合し、新国府として多賀城を建設し、弱体化した陸奥国の支配強化を図った。 これにより、奈良時代の日本では、平城京を中心に、南に大宰府、北に鎮守府兼陸奥国府の多賀城を建てて一大拠点とした。 多賀城跡とその周辺の調査が1961年から開始され、外郭は東辺約1000m、西辺約700m、南辺約880m、北辺約860mの築地塀や柵木列がめぐる政庁域が確認された。 その中心からやや南寄りに東西約106m、南北約170mの築地塀で囲まれた区域があり、主要な建物の跡と見られる礎石や柱穴が多数確認され、正殿と考えられた。政庁の南東方向に「多賀城廃寺」 (旧称「高崎廃寺」、城下の山王遺跡の発掘調査では「観音寺」の墨書土器が出土している)、政庁正殿の北側には延喜式内社の多賀神社(六月坂)がある。 多賀城政庁東門跡に隣接して陸奥国百社を祀る陸奥総社宮がある。陸奥国一宮鹽竈神社(塩竃神社)を精神的支柱として、松島湾・千賀ノ浦(塩竃湊)を国府津とする。都人憧憬の地となり、歌枕が数多く存在する[17]。政庁がある丘陵の麓には条坊制による都市が築かれ、砂押川の水上交通と東山道の陸上交通が交差する土地として繁栄した。 1966年4月11日、遺跡は国の特別史跡に指定された]。その後も発掘調査が進展した結果、多賀城跡一帯とともに多賀城廃寺跡、館前遺跡、柏木遺跡位置)、山王遺跡などを含む範囲の追加指定がなされている。 神亀元年(724)- 大野東人によって創建される(多賀城碑)。 天平9年(737)- 『続日本紀』に北方を固める「天平五柵」とともに「多賀柵」として初出。天平五柵とは、石巻平野から大崎平野にかけて造営された牡鹿柵・新田柵・玉造柵・色麻柵の四柵と不明の一柵である。伊東信雄は「古代史」『宮城県史』第1巻(1957)で不明の一柵に小田郡中山柵を充てた。 天平宝字6年 (762)- 藤原朝狩によって大規模に修造される(多賀城碑)。 宝亀11年(780)- 伊治呰麻呂の乱で焼失した後に、再建された事が書かれている。 延暦21年(802) - 坂上田村麻呂が蝦夷への討伐を行い、戦線の移動に伴って鎮守府も胆沢城(岩手県奥州市)へ移されて、兵站的機能に移ったと考えられる。 貞観11年 (869)- 陸奥国で巨大地震(貞観地震)が起こり、地震被害とともに城下は津波によって被災し、溺死者を千人ばかり出している(『日本三代実録』)。この後、「多賀国府」として復興した。 11世紀前半頃までかろうじて維持された国府政庁は、11世紀後半には政庁隣接地に平場を設け、政庁に代わる宴会儀礼の場が整備され、国府中枢としての機能は大きく変質した。 11世紀後半の前九年の役や後三年の役においても軍事的拠点として機能し、承徳元年(1097)にも陸奥国府が焼失している。 養和元年(1181)には陸奥国府および「高用名」(国府用に由来。南宮荘・岩切村・村岡村ほか)を拠点とする勢力は平泉の藤原秀郷を陸奥守として迎え入れ、八幡館(末の松山)および開発低湿地(八幡荘・中野郷・萩薗郷・蒲生郷を私領化。多くは津波被災地)に拠点を置く陸奥介らの勢力とに袂別した。多賀国府の勢力は文治5年(1189)奥州合戦および大河兼任の乱で没落していったが、八幡館を拠点とする陸奥介は鎌倉幕府から地頭職を得て、鎌倉に屋地を得るまでになっている。八幡荘は鎌倉将軍家を本所とする関東御領として存続した可能性が強い。 永仁7年(1299)2月朔日に大檀那介平景綱が奥州末松山八幡宮に鐘を奉納している。 南北朝時代には、後醍醐天皇率いる建武政府において陸奥守に任じられた北畠顕家、父の北畠親房らが義良親王(後村上天皇)を奉じて多賀城へ赴き、多賀城に東北地方、および北関東を支配する東北地方の新政府、陸奥将軍府が誕生した。 昭和36年(1961)、多賀城跡とその周辺の調査が始まった。 昭和41年(1966)4月11日、遺跡は国の特別史跡に指定された。この事件に大きな衝撃を受けた政府は、呰麻呂の行動を「伊治公呰麻呂反」と記して、八虐のうち謀反にあたると断じ、国家転覆の罪に当たるとした。のみならずただちに征東大使、出羽鎮狄将軍を派遣して軍事的な鎮圧に当たらしめたが、
2024年11月26日
閲覧総数 34
-
14

「歴史の回想・宝亀の乱」阿弖流為。 川村一彦
平城天皇の即位 延暦25年3月17日(806年4月9日)、桓武天皇が崩御すると同日に皇太子・安殿親王(平城天皇)の践祚が執り行われ、田村麻呂は春宮大夫・藤原葛野麻呂と共に身を伏したまま哀慟して自ら立つこともままならない安殿親王を抱きかかえて殿を下り、直ちに玉璽(御璽)と宝剣(天叢雲剣)を奉っている。 4月1日(806年4月22日)に中納言・藤原雄友に従って桓武天皇への誄辞を奉ると、4月18日(806年5月9日)に中納言、4月21日(806年5月12日)に中衛大将と立て続けて要職を兼ねた。 5月18日(806年6月8日)に即位の儀が行われて元号が延暦から大同に改元されると、平城天皇の側近として重んじられていく。10月12日(806年11月25日)付けで発布された太政官符に申請者として「中納言征夷大将軍従三位兼行中衛大将陸奥出羽按察使陸奥守勲二等」の肩書きで名前を連ねている。これは擬任郡司などを任命して辺境の防備体制を固めたいというものであった。 大同2年4月12日(807年5月22日)に中衛府が右近衛府へと改称されたのに併せて中衛大将から右近衛大将となり、8月14日(807年9月19日)には侍従も兼任するが、その直後となる10月に伊予親王の変が起こっている。この政変では11月12日(807年12月14日)に藤原吉子・伊予親王母子がそろって毒を飲んで心中しているが、11月16日(807年12月18日)に兵部卿を兼任していることから、田村麻呂は政変に関わっていないとみられ、平城天皇からも変わらず信頼を置かれていたものと思われる。大同4年3月30日(809年5月17日)に父・苅田麻呂を超える正三位となる。 大納言として 平城太上天皇の変(薬子の変) 大同4年4月1日(809年5月18日)、平城天皇は健康上の理由で皇位を皇太弟・神野親王へと譲位した。皇太子には平城天皇の第三皇子・高岳親王が立てられた。平城天皇の寵愛を受けていた藤原薬子と兄・藤原仲成は譲位に反対するものの、4月13日(809年5月30日)に神野親王が嵯峨天皇として即位する。 譲位後に健康を回復させた平城上皇は、大同4年11月、仲成に命じて平城京を修理させると、12月4日(810年1月12日)には平城京へと移り住んだ。 嵯峨天皇は大同5年(810年)3月に蔵人所を設置し、6月には平城天皇の治世で設置された観察使の制度を廃止する。これに怒った平城上皇を薬子と仲成が助長して「二所朝廷」といわれる両統迭立が起こる。 大同5年9月6日(810年10月7日)、平城上皇により平安京を廃して平城京へ遷都する詔勅を発せられたことで平城太上天皇の変(薬子の変)が始まる。平城京遷都の詔勅にひとまず従った嵯峨天皇は、坂上田村麻呂・藤原冬嗣・紀田上らを平城京造宮使に任命する。 しかし9月10日(810年10月11日)、嵯峨天皇は平城京遷都の拒否を決断して、固関使を伊勢国・近江国・美濃国の国府と関に派遣、同時に仲成を捕らえて右兵衛府に禁固し、佐渡権守に左遷、薬子は尚侍正三位を剥奪して宮中から追放という詔を発した。 『公卿補任』によるとこの日に田村麻呂は大納言に昇進しており、子の坂上広野も近江国の関を封鎖するために派遣されている。 嵯峨天皇側の動きを知った平城上皇は激怒して9月11日(810年10月12日)早朝、挙兵することを決断し、薬子と共に輿に乗って平城京を発し、東国へと向かった。嵯峨天皇は田村麻呂を派遣。 美濃道より上皇を迎え撃つにあたり、上皇側と疑われ左衛士府に禁固されていた文室綿麻呂の同行を願い出て、嵯峨天皇は綿麻呂を正四位上参議に任命した上で許可している。平城京から出発した平城上皇は東国に出て兵を募る予定だったが、田村麻呂が宇治・山崎両橋と淀市の津に兵を配したこの夜、右兵衛府で仲成が射殺された。 嵯峨天皇側の迅速な対応により上皇が9月12日(810年10月13日)に大和国添上郡越田村にさしかかったとき、田村麻呂が指揮する兵が上皇の行く手を遮った。進路を遮られたことを知り、平城上皇は平城京へと戻って剃髪して出家し、薬子は毒を仰いで自殺したことにより対立は天皇の勝利に終わった。この事件の時に空海が鎮護国家と田村麻呂の勝利を祈祷している。 晩年 弘仁2年1月17日(811年2月13日)、嵯峨天皇が豊楽院で射礼を観覧した際、行事の終了後に諸親王や群臣に対して弓を射させたが、12歳の葛井親王(平城上皇と嵯峨天皇の異母弟で桓武天皇と田村麻呂の娘・春子所生の皇子)にも戯れに射させたところ、百発百中であった。行事に居合わせた外祖父の田村麻呂は、驚き騒ぎ喜び勇んで葛井親王を抱いて立ち上がって舞った。 田村麻呂は天皇の前に進み出て、かつて自分は10万の兵を率いて東夷を征討した際、朝廷の威光を頼りに向かうところ敵なしであったものの、今思うに計略や兵術について究めていない点が多数あったが、葛井親王は幼いながら武芸がすばらしく私の及ぶところではないと言った。嵯峨天皇は大いに笑って、それは褒め過ぎであると返したという。 豊楽院での射礼から3日後の1月20日(811年2月16日)には、中納言・藤原葛野麻呂や参議・菅野真道らと共に、前年の暮より入京していた渤海国の使者を朝集院に招いて饗応する任に当たっている。田村麻呂生前の公的記録としてこれが現存する最後の資料のものとされる。 同年5月23日(811年6月17日)、平安京郊外粟田(現在の京都市左京区)の別宅で病の身を臥せていたが、54歳で生涯を閉じた。 嵯峨天皇は田村麻呂の死を悼み「事を視ざること一日」と喪に服し、この日は政務をとらず田村麻呂の業績をたたえる一篇の漢詩を作った。 田村麻呂が薨去したその日のうちに遺族に対して嵯峨天皇より、娘・春子が葛井親王の生母であることも考慮された上で絁69疋・調布101段・商布490段・米76斛・役夫200人(左右京各50人、山城国愛宕郡100人)と、御賜品を通例より加増されて賜っている。 死後と神格化 弘仁2年5月27日(811年6月21日)に大舎人頭・藤原縵麻呂と治部少輔・秋篠全継が田村麻呂宅に派遣され、天皇の宣命を代読して大納言・田村麻呂に従二位が贈られた。 葬儀が同日に営まれ、山城国宇治郡来栖村水陸田三町を墓地として賜わって、遺体は甲冑・兵仗・釼・鉾・弓箭・糒・塩を調へ備へて、合葬せしめ、城の東に向け窆を立つように埋葬された。 もし国家に非常時があれば田村麻呂の塚墓はあたかも鼓を打ち、あるいは雷電が鳴る。以後、将軍の職に就いて出征する時はまず田村麻呂の墓に詣でて誓い、加護を祈るとされた。現在、京都市山科区の西野山古墓が田村麻呂の墓所として推定されている。 弘仁3年(812年)正月、嵯峨天皇の勅令によって、鈴鹿峠の二子の峰に田村麻呂を祀る祭壇が設けられた。弘仁13年4月8日(822年5月2日)には土山の倭姫命を祀る高座大明神の傍らにも田村麻呂を祀る一社を建て、併せて高座田村大明神(現在の田村神社)と称した。 『公卿補任』に「毘沙門天の化身、来りてわが国を護ると云々」と記され、生前から毘沙門天の化身として評価されたことから伝説上の人物・坂上田村麻呂として語り継がれてい。 〇「阿弖流爲」(あてるい)、または大墓公阿弖利爲(たも の きみ あてりい、? - 延暦21年8月13日〈ユリウス暦802年9月13日、先発グレゴリオ暦802年9月17日〉)は、日本の奈良時代末期から平安時代初期の古代東北の人物。 8世紀末から9世紀初頭に陸奥国胆沢(現在の岩手県奥州市)で活動した蝦夷(えみし)の族長とされる。古代日本の律令国家(朝廷)による延暦八年の征夷のうち巣伏の戦いにおいて紀古佐美率いる官軍(朝廷軍)の記録中にはじめて名前がみえ、延暦二十年の征夷の後に胆沢城造営中の坂上田村麻呂に自ら降伏した。 その後は田村麻呂とともに平安京付近へと向かったものの、公卿会議で田村麻呂が陸奥へと返すよう申し出るが、公卿達の反対により盤具公母禮とともに河内国椙山で斬られた。 名前について 大墓公阿弖利爲は、古代日本の律令国家から「水陸万頃にして、蝦虜、生を存す」、「賊奴の奥区なり」と呼ばれた衣川以北の北上川流域平野部となる磐井郡・江刺郡・胆沢郡一帯(現在の岩手県南部)に勢力を持っていたと考えられている胆沢の蝦夷(えみし)の族長である[1]。 名前は古代日本の律令国家が編纂した六国史のなかに4度見える。内訳は「阿弖流爲」で1回、「大墓公阿弖利爲」で2回、「大墓公」で1回となる。 『日本紀略』には「夷大墓公阿弖利爲」と、朝廷から与えられた姓である「公」がつけられている。 このことについて田村麻呂のもとに帰降した直後の記事のため、大墓公の姓は降服後に国家から賜与されたものとの見解もある。 一方では、結果として河内国椙山で斬られたことからみても、国家が帰服したアテルイにわざわざ姓を与えたとは考えがたく、国家に従った蝦夷族長が離反した際に姓を剥奪された例もいくつかみられることから、大墓公の姓はアテルイらの一族が朝廷軍と戦うより以前に国家から賜与されていたものとの見解もある。 いずれにせよ、大墓公一族がかつては律令国家との間にかなり良好な政治的関係を築いていたことを示すひとつの重要な手がかりである。 「大墓公」を文字通り大きな墓の意味であると解釈し、胆沢地方に所在する角塚古墳の被葬者一族の系譜を引くものと国家に認定されたため、この姓が与えられたとみて「おおつかのきみ」「おおはかのきみ」などと読む見解がある。しかし「大墓」の字で表されるものは蝦夷居住地域の地名であるため、和語として意味を持つ訓読は避けるべきである。 また、奥州市水沢羽田町に田茂山の字名が遺っており、延暦8年(789年)の胆沢合戦でアテルイ率いる胆沢蝦夷軍が朝廷軍に奇襲作戦を仕掛けた地点でもあり、田茂山を「大墓」の遺称地として「たも」と読む見解がある。現在は後者の田茂山説を採用する研究者が最も多い。しかしながら「大墓公」の解釈はいずれも推測の域を出ない。 岩手県奥州市江刺に大萬館・小萬館とよばれる館跡があることから関連付けられ、大墓公阿弖利爲は大萬公阿弖利爲の誤記ではないかとする説や、跡呂井という地名と関連付けられることもあるが、これらの説について高橋崇は安易に類似の地名を求め、正史の転写次第での誤記とする考え方は危険であると述べている。 現在のところ、朝廷の記録に阿弖流爲]、大墓公阿弖利爲、大墓公と記録されていること以外は不詳である。※ 日付は和暦による旧暦。西暦表記の部分はユリウス暦とする。
2024年11月26日
閲覧総数 36
-
15

「歴史の回想・宝亀の乱」払田柵と雄勝常。 川村一彦
〇「大伴 益立」(おおとも の ますたて)は、奈良時代の貴族。大和守・大伴古慈悲の子。官位は正五位上・兵部大輔、贈従四位下。 淳仁朝にて蝦夷征討事業に従事し、天平宝字4年(760年)陸奥国の雄勝城と桃生柵の築城が賞され際、鎮守軍監として艱苦を顧みず再征したとして特に褒賞され従六位上から三階の昇叙を受け従五位下に叙爵される。天平宝字5年(761年)陸奥鎮守副将軍兼鎮国驍騎将軍(中衛少将)に任ぜられ、天平宝字6年(762年)陸奥介を兼ねた。 神護景雲元年(767年)正月に2階昇進して正五位下に、10月には伊治城築城の功労により正五位上に叙せられる。 のち、称徳朝後半は兵部大輔・式部大輔など一時京官を歴任する。称徳朝末の神護景雲4年(770年)5月に肥後守と再び地方官に転じると、宝亀2年(771年)大宰少弐に任ぜられるなど、光仁朝初頭は九州地方の地方官を務める。 宝亀6年(775年)遣唐副使に任ぜられるが、翌宝亀7年(776年)11月に遣唐大使・佐伯今毛人が唐への出発時機を逸し帰京して節刀を返上した際に、益立は遣唐判官・海上三狩と共に大宰府に留まって出発の時機を待つこととした。 この対応は世間の人々に称賛されたというが、結局同年12月には遣唐副使を解任され、小野石根・大神末足に取って代わられた。 益立は遣唐副使を解任されて間もない、宝亀8年(777年)正月に権左中弁、宝亀9年(778年)右兵衛督と京官に復帰した一方、小野石根は益立に代わって宝亀 8年(777年)に唐に渡るが、唐からの帰途で遭難し没している。 宝亀11年(780年)伊治呰麻呂の乱が発生すると、従四位下・征東副使兼陸奥守に叙任され、乱の平定のため遠征するが、駐留したまま進軍せず戦機を逸してしまう。 さらに新たに征東大使に任ぜられた藤原小黒麻呂が、陸奥国に到着後速やかに進軍して奪われた諸城塞を回復したことから、益立は進軍しなかったことを譴責され、天応元年(781年)に従四位下の位階を剥奪され正五位上に落とされた。延暦2年(783年)再び兵部大輔に任ぜられるが、その後の消息は不明。 承和4年(837年)になって、益立が讒訴を受けて位階を剥奪されたとして、子の野継が冤罪を訴えたところ認められ、益立は50年以上ぶりに本位である従四位下の贈位を受けた。 〇「紀 古佐美」(き の こさみ)は、奈良時代後期から平安時代初期にかけての公卿。大納言・紀麻呂の孫。正六位上・紀宿奈麻呂の子。官位は正三位・大納言、贈従二位。勲等は勲四等。 天平宝字8年(764年)藤原仲麻呂の乱終結後に従五位下に叙爵し、天平神護3年(767年)丹後守に任ぜられる。 光仁朝では、兵部少輔・式部少輔・伊勢介・右少弁を歴任する。宝亀11年(780年)正月に従五位上に叙せられるが、同年3月に陸奥国で伊治呰麻呂が宝亀の乱を起こすと征東副使に任ぜられ、同じく副使の大伴益立と共に東国へ赴いた。翌天応元年(781年)5月陸奥守に任じられ、同年9月には乱鎮圧の功労により、三階昇進して従四位下に叙せられ、勲四等の叙勲を受けた。 桓武朝に入ると、左兵衛督・中衛中将と武官を務めると共に、左中弁・式部大輔を兼ね、延暦4年(785年)には従四位上・参議に叙任されて公卿に列した。同年11月安殿親王(のち平城天皇)の立太子に伴いその春宮大夫に、翌延暦5年(786年)右大弁次いで左大弁と、これまでの中衛中将と合わせて議政官として文武の要職を兼帯している。延暦6年(787年)正四位下。 延暦7年(788年)7月に征東大将軍に任じられ、12月に節刀を受けて蝦夷の征討に赴く。翌延暦8年(789年)3月末に衣川(現在の岩手県西磐井郡平泉町付近)に陣を敷くが、1ヶ月以上に亘り軍を動かさなかったことから、5月中旬に桓武天皇の叱責を受ける。 これを受けて古佐美は5月末に大規模な渡河を伴う軍事行動を起こすが、蝦夷の族長であるアテルイの反撃に遭い、別将の丈部善理ら戦死25人、溺死1036人もの損害を出して大敗した(巣伏の戦い)。 6月に入ると古佐美は進軍に当たっての兵站の困難さと、軍を維持するために大量の兵糧が必要であることを理由に朝廷の許可を得ずに征東軍を解散し、桓武天皇から再度の叱責を受けた。 9月に帰京して節刀を進上、大納言・藤原継縄、中納言・藤原小黒麻呂らから進軍せずに大敗した状況の取り調べを受けて征東事業失敗の責任を承服する。副将軍の池田真枚と安倍猨嶋墨縄が官職や位階を剥奪された一方で、古佐美は敗戦の責任により処断されるべきところ、これまで朝廷に仕えてきた功績を勘案され罪を免じられている。 以後も、延暦9年(790年)正四位上、延暦12年(793年)従三位、延暦13年(794年)には正三位・中納言と順調に昇進する。延暦15年(796年)には右大臣・藤原継縄の薨去に伴い、大納言に任ぜられて太政官の首班を占めた。 またこの間の延暦12年(793年)には平安京遷都のために、大納言・藤原小黒麻呂と共に山背国葛野郡宇太村の土地を視察している。 延暦16年(797年)4月4日薨去。享年65。最終官位は大納言正三位兼行東宮傅。没後に従二位の位階を贈られた。 しかし、藤原継縄は当初より現地に下向しようとしなかった。代わって軍を率いることになったのが、征東副使であった大伴益立である。 〇「安倍 家麻呂」(あべ の やかまろ)は、奈良時代後期の貴族。大納言・阿倍宿奈麻呂の孫。式部少輔・阿倍子島の子。官位は正五位上・石見守。 光仁朝の宝亀3年(772年)従五位下・兵部少輔に叙任。宝亀10年(779年)従五位上に叙せられる。翌宝亀11年(780年)3月に陸奥国で宝亀の乱が起こると、中納言・藤原継縄が征東大使に任ぜられるなどの乱追討関連の任官に伴い、家麻呂は出羽鎮狄将軍に任じられ出羽国に赴く。 同年8月には二階の昇進により正五位上に叙せられると共に、蝦夷の攻撃にさらされて維持が難しくなっていた秋田城の存廃に関連して、帰属して城下に居住していた俘囚が動揺している旨を上奏。これを受けて朝廷では秋田城の防衛強化が図られ、専使あるいは専当の国司による鎮守方式を採ることになり[1]、これが後の秋田城介の起源になったとされている[2]。 天応元年(781年)桓武天皇の即位後まもなく上野守に任ぜられる。その後、延暦4年(785年)左兵衛督、翌延暦5年(786年)左大舎人頭と京官を務めるが、延暦8年(789年)石見守として再び地方官に転じた。 それ以降六国史に叙位任官記載がなく、動静は不明。一説では大同元年(806年)10月24日に享年71で卒去したともされる[3]。 益立は天平宝字年間に雄勝城・桃生城を造営した際に鎮守軍監を務めており、現地経験も豊富であった。 雄勝城(おかちじょう/おかちのき)は、出羽国雄勝郡(現在の秋田県雄物川流域地方)にあった日本の古代城柵。藤原朝狩が天平宝字3年(759年)に築造したとされる。 現在の雄勝郡域内に、雄勝城と同時代の遺構は見つかっておらず、その造営地は現在も不明である。記紀から推定されている雄勝城の造営地は、「雄物川流域沿岸地で、出羽柵と多賀城の経路上にあり、かつ出羽柵より2驛手前の距離の土地」である。現時点で発見されている城柵遺跡でこの条件に一致するものは払田柵跡のみである。 現在、横手市雄物川町での発掘調査が進められており、払田柵から出土したものと同等のものが出土している。今後、これらの雄勝村周辺遺跡の発掘調査が進むにつれ、古代雄勝城造営地が徐々に明らかにされていくものと期待されている。 払田柵と雄勝城 記紀から推定される造営地は、雄勝城と同じ奈良時代の城柵遺跡である払田柵跡付近が妥当であるため、払田柵が雄勝城であろうとの説が提唱された時期もあったが、年輪年代法による分析結果では払田柵の造営時期は9世紀初頭と推定されたため、払田柵を天平宝字年間に造営された雄勝城とする説には無理が生じた。しかしながら、払田柵の遺構はその規模において陸奥国府が置かれたとされる多賀城を遥かに凌ぐものであることから、払田柵が記紀にある出羽国に設置された1府2城のうちの1城である雄勝城であろうとの見方は尚且つ妥当と認められており、また記紀にも時折郡里が賊に襲われて郡府の再建が行われた記録も見られることから、現在では雄勝城は当初の造営地から9世紀初頭に払田柵跡の地に移設されたとの推定に至っている。 〇「桃生城」(ものうじょう)は、古代の朝廷が陸奥国桃生郡(現・宮城県石巻市)に築いた城柵。 『続日本紀』によれば、桃生城は天平宝字2年(758年)に造営が始まり、翌3年(759年)に完成した。翌年正月にはその功績によって按察使の藤原朝狩に従四位下が授与され、以下の者にも叙位叙勲が行われた。その後、桃生城は宝亀5年(774年)7月には海道蝦夷によってその西郭が敗(やぶ)られた(桃生城襲撃事件)。翌宝亀6年(775年)11月には、陸奥国按察使兼鎮守府将軍の大伴駿河麻呂以下1,790余人が、桃生城を侵した叛賊を討治、懐柔帰服した功績によって叙位叙勲を受けた。 しかし、桃生城に関する記述はそれ以降史料上に見えず、奪還後の様相については不明である。石巻市太田地区には、かつて「上郡山」という地名が存在しており[1]、少なくとも桃生郡家はこの地で存続した可能性が高い。また、叛乱を起こした海道蝦夷の拠点となった遠山村は、「登米(とよま)郡」として建郡されている。 調査・研究 桃生城の所在地については、明治28年(1895年)に桃生郡中津山村の熊谷眞弓が同郡北端にある「茶臼山」(標高159m)説を唱え、これが最有力視されて昭和30年代まではほぼ定説とされていた。ただし、茶臼山からは古瓦などの考古学的な確証を得ることができず、再検討の余地を残していた。 一方で、喜田貞吉は大正12年(1923年)に延喜式内社の「飯野山神社の向う側の山の上に平地があって、字長者森と云ひ、布目瓦を出すといふ」ことから、「古い寺でもあったものらしい」と後の桃生城長者森説の原形となる説を提唱していた[6]。喜田の論考と同年に発行された『桃生郡誌』(桃生郡教育会)では、『続日本紀』中の「跨大河」の記述と茶臼山付近の北上川の河道変遷に齟齬があり、「史筆の虚飾にて小流を大河と記したるものか」「疑存して後考を待つ」とされた。 昭和38年(1963年)、高橋富雄は、「丘陵台地の突端、大谷地飯野新田の台上」から「奈良時代末期と推定されるところの各種の瓦」「土師器・須恵器をともない、大きな施設があったことが確認できる」とし、「桃生町太田地区と河北町大谷地地区の接壌地帯」を最も有力な桃生城擬定地とした。 昭和44年(1969年)、地元の宮城県河南高等学校教諭(当時)の小野寺正人は、長者森には土塁等が存在すること、奈良時代末期と推定される布目瓦や土師器・須恵器が出土することから、桃生城跡として有力な推定地であることを述べている。 桃生城の範囲は、東は桃生町太田越路から飯野本地に至る線、西は桃生町袖沢から小池を通り河北町新田にいたる線、北は桃生町九郎沢から南は河北町飯野新田に至るとしており、宗全山(愛宕山)を頂点とする丘陵全域を桃生城とし、長者森の方形土郭を桃生城の中心施設と位置づけている。 小野寺の示した桃生城の範囲は、地形的にもまとまりのある一帯地を指しており、太田・飯野地区には、延喜式内社の日高見神社・飯野山神社が所在し、日高見神社からは古瓦も出土することから、桃生城擬定地のひとつとされたこともある。また、太田地区の九郎沢・入沢・拾貫には、年代不詳ながら「金を採掘した跡が無数」(みよし掘り跡)に残され、太田金山跡とされている。 昭和49年(1974年)から平成13年(2001年)までの、宮城県多賀城跡調査研究所による通算10次に及ぶ発掘調査の結果、桃生城域は東西二郭構造から構成されるとの見解が出された。 平成13年(2001年)から始まった三陸自動車道建設に伴う発掘調査では、角山遺跡の丘陵尾根に沿って柵列跡が検出され、この柵列は調査範囲を超えて延びており、桃生城の一番外側の外郭線の一部であったと考えられている。また、細谷B遺跡第2号住居の暗渠には桃生城の瓦が用いられており、同城との直接的な関連が窺われた。これらは小野寺が提唱した太田・飯野全域に及ぶ「広域桃生城説」を裏付ける証左のひとつと考えられる。 桃生城の隣接地の調査では、桃生城とされた範囲の東側から土塁(SⅩ03)や大溝(SD02・04・05)が確認され、同城の規模と構造・変遷については今後の課題とされた。桃生城の東に接する新田東遺跡からは、掘立柱建物跡や竪穴住居跡が発見され、これらの中には焼失遺構が含まれていることや、天平宝字8年(v年)に反乱を起こして戦死した藤原仲麻呂(恵美押勝)・藤原朝狩らの菩提を弔うために称徳天皇が発願した百万塔を模して作った「三重小塔」が出土していること、遺跡の東縁辺には二重の土塁状の高まりが認められることから、桃生城の東郭ないしは一部を構成すると考える説が有力となっている。このため副将軍にして異例の節刀を授けられて赴任することになったのである。
2024年11月26日
閲覧総数 35
-
16

「歴史の回想・宝亀の乱」坂上田村麻呂。 川村一彦
〇「多治比 宇美」(たじひ の うみ/うさみ)は、奈良時代から平安時代初期にかけての貴族。名は海、宇佐美とも記される。右大弁・多治比国人の子。官位は従四位上・右中弁。 宝亀11年(780年)4月に従五位下に叙爵し、6月には陸奥介に任ぜられて、同時に陸奥鎮守副将軍になった百済王俊哲らと共に宝亀の乱の鎮圧に当たる。 翌天応元年(781年)9月に乱鎮圧の功労者に対する叙位が行われ従五位上に叙せられている。延暦2年(783年)民部少輔ついで同大輔と一時京官に復す。 延暦4年(785年)正五位下・陸奥守に叙任されると、陸奥按察使と鎮守副将軍を兼ねて、再び蝦夷征討の任にあたる。延暦7年(788年)鎮守将軍。なお、この間の延暦8年(789年)には征東将軍・紀古佐美による大規模な遠征が行われるも、巣伏の戦いで蝦夷に大敗しているが、宇美の動静は明らかでない。 延暦9年(790年)右中弁に任ぜられて京官に復し、延暦10年(791年)には武蔵守に任ぜられている。延暦16年(797年)従四位上に至る。 〇「百済王 英孫」(くだらのこにきし えいそん)は、奈良時代後期から平安時代初期にかけての貴族・武人。宮内大輔・百済王慈敬の子。官位は従四位下・右衛士督。 宝亀11年(780年)に発生した宝亀の乱の鎮圧のための遠征軍に従軍したらしく、天応元年(781年)に乱鎮圧の功労に対する叙位・叙勲が行われた際、同族の百済王俊哲が正五位上・勲四等に、英孫も従五位下に叙爵する。その後も、延暦4年(785年)5月に鎮守府権副将軍、次いで10月には出羽守に任ぜられるなど、引き続き蝦夷征討に従事した。 延暦10年(791年)従五位上に叙せられる。その後、時期は不明ながら従四位下まで進むなど桓武朝中盤は順調に昇進しており、延暦12年(793年)から延暦13年(794年)にかけて行われ、征夷副使・坂上田村麻呂らが戦果を挙げた蝦夷遠征に従軍したか。 桓武朝後半は、延暦16年(797年)右兵衛督、延暦18年(799年)右衛士督と京官の武官を歴任した。 〇「安倍猨嶋 墨縄」(あべのさしま の すみなわ/すみただ、生没年不詳)は、奈良時代の貴族。姓は臣。官位は外従五位下・鎮守府副将軍。勲等は勲五等。 下総国猿島郡出身。桓武朝初頭の天応元年(781年)征夷事業の功績により、外従五位下に叙せられるとともに勲五等の叙勲を受ける。 陸奥按察使・大伴家持の下で、延暦元年(782年)鎮守権副将軍、延暦3年(784年)征東軍監に任ぜられ、蝦夷征討にあたる。延暦7年(788年)には蝦夷の地への赴任経験と戦場経験の豊富さを買われ、鎮守副将軍に任ぜられる。 延暦8年(789年)6月に征東大使・紀古佐美の下で、征東副使・入間広成と鎮守府副将軍・池田真枚とともに陸奥国胆沢(現在の岩手県奥州市)へ侵攻するために、北上川の渡河を伴う大規模な軍事作戦を実行したが、蝦夷のアテルイらの軍勢の挟み撃ちに逢って大敗する(巣伏の戦い)。墨縄は自らは陣営の中に留まって部下の補佐官のみを出撃させ大敗を招いたとして、朝廷から広成とともに批判され、9月には大納言・藤原継縄らからの取り調べを受ける。 その結果、愚かで頑固かつ臆病で拙劣であり、兵士を進退させる際に平静を失って軍機を逸したことから斬刑に該当するところ、長く辺境の守備を務めた功労により減刑され、官位剥奪に処された。 〇「入間 広成」(いるま の ひろなり)は、奈良時代から平安時代初期にかけての貴族。官位は従五位下・造東大寺次官 物部氏(物部直)は出雲氏族に属する天孫系氏族。 武蔵国入間郡の人。天平宝字8年(764年)に発生した藤原仲麻呂の乱において、藤原仲麻呂軍が越前国へ逃れるために愛発関に入ろうとしたところを拒みこれを退却させる(このときの官職は授刀舎人)など、乱での功労により勲五等の叙勲を受ける。 神護景雲2年(768年)広成以下一族6人が物部直から入間宿禰に改姓する(このときの位階は正六位上)。 桓武朝初頭の天応元年(781年)征夷の功労により外従五位下に叙せられ、翌延暦元年(782年)陸奥介に任ぜられる。征東軍監を経て、延暦7年(788年)には蝦夷の地への赴任経験と戦場経験の豊富さを買われ、多治比浜成・紀真人・佐伯葛城と共に征東副使(副将軍)に任ぜられ蝦夷征討にあたる。 延暦8年(789年)6月に鎮守府副将軍の池田真枚・安倍猨嶋墨縄と共に陸奥国胆沢(現在の岩手県奥州市)へ侵攻するために、北上川の渡河を伴う大規模な軍事作戦を実行したが、蝦夷の軍勢の挟み撃ちに逢って大敗する。 広成は自らは陣営の中に留まって部下の補佐官のみを出撃させ大敗を招いたとして朝廷から批判を受け、9月には大納言・藤原継縄らから取り調べを受けて敗戦の責任を承服している。しかし、具体的な処罰は受けなかったらしく、翌延暦9年(790年)には従五位下・常陸介に叙任されている。 延暦18年(799年)造東大寺次官に任ぜられた。 ひとり大伴益立が従四位下の剥奪処分に至ったのは前述のとおりである。征夷が遅れた原因を大伴益立一人の罪に帰したものと考えられる。一方、先に挙げられた「伊佐西古・諸絞・八十嶋・乙代」はいずれも有力な蝦夷の族長であり、中でも伊佐西古は宝亀9年(778年)、呰麻呂とともに外従五位下を授かった吉弥侯部伊佐西古その人である。このことはすなわち、呰麻呂が乱を起こすとともに従来政府側に協力してきた蝦夷たちまでもが離反したことを示す。これまで政府側に帰属してきた蝦夷は、「俘軍」として政府側の武力として活動することもあったが、桓武天皇の治世の下行われた3回に渡る征夷では、俘軍の政府軍への参加はみられない。ここに至り征夷は律令国家と蝦夷の全面対決の局面に突入し、坂上田村麻呂がアテルイらの軍勢に勝利して胆沢地方を平定するまで、大規模な戦乱の時代が続くこととなる。 〇「坂上 田村麻呂」(さかのうえ の たむらまろ)は、平安時代の公卿、武官。名は田村麿とも書く。 姓は忌寸のち大忌寸、大宿禰。父は左京大夫・坂上苅田麻呂。 官位は大納言正三位兼右近衛大将兵部卿。勲二等。贈従二位。 4代の天皇に仕えて忠臣として名高く、桓武天皇の軍事と造作を支えた一人であり、二度にわたり征夷大将軍を勤めて蝦夷征討に功績を残した。 薬子の変では大納言へと昇進して政変を鎮圧するなど活躍。死後は嵯峨天皇の勅命により平安京の東に向かい、立ったまま柩に納めて埋葬され、「王城鎮護」「平安京の守護神」「将軍家の祖神」と称えられて武神や軍神として信仰の対象となる。現在は武芸の神や厄除の大神として親しまれ、後世に多くの田村語り並びに坂上田村麻呂伝説が創出された。※ 日付は和暦による旧暦。西暦表記の部分はユリウス暦とする。 出生から征夷大将軍まで 天平宝字2年(758年)、坂上苅田麻呂の次男、または三男として誕生。生年は田村麻呂の薨伝に記録された没年からの逆算。母のことは一切不明。父の苅田麻呂は31歳、生まれた場所についてもあきらかにされていない(出生節も参照)。 田村麻呂の生まれた「坂上忌寸」は、後漢霊帝の曽孫阿智王を祖とする漢系渡来系氏族の東漢氏と同族を称し、代々弓馬や鷹の道を世職として馳射(走る馬からの弓を射ること)などの武芸を得意とする家系として、数朝に渡り宮廷に宿衛して守護したことから武門の誉れ高く天皇の信頼も厚い家柄であった。 曽祖父の坂上大国は右衛士大尉として武官にあり、祖父の坂上犬養は少年期から武人の才能を讃えられて聖武天皇から寵愛されると左衛士督に昇り、父の苅田麻呂は武芸によって公卿待遇を与えられた。 しかしながら、この頃の坂上氏は地方的豪族な存在にすぎなかった。そのため大国から苅田麻呂までの3代は氏族の没落を防ぐ試みに全力を尽くし、武人の供給源という特性を坂上氏の特徴にまで育てあげると「将種坂上氏」として武芸絶倫という家風を確立し、田村麻呂とその兄弟は幼少期から武芸を好むよう教育された。 幼少期の田村麻呂については史料こそないものの、宝亀元年(770年)に称徳天皇が崩御して光仁天皇が即位すると、父・苅田麻呂が道鏡の姦計を告げて排斥した功績により同年9月16日(770年10月9日)に陸奥鎮守将軍に叙任されている(宇佐八幡宮神託事件)。 宝亀2年閏3月1日(771年4月20日)に佐伯美濃が陸奥守兼鎮守将軍となり、苅田麻呂が安芸守となるまで半年ほどの在職期間ではあったが、その間は鎮守府のある多賀城に赴任していたものと思われる。律令では21歳未満であれば同道出来ることから、13歳前後であった田村麻呂は父とともに、道嶋氏が凋落して桃生城襲撃事件が起こる三十八年騒乱直前の比較的平和な時代の陸奥国で幼少期を過ごしていた可能性もある。 宝亀3年(772年)、大和国高市郡の郡司職に関して、代々郡司職にあった檜前忌寸ではなく、ここ数代は蔵垣忌寸・蚊帳忌寸・文山口忌寸が郡司職に任ぜられていることを父・苅田麻呂が上奏し、今後は譜第である檜前氏を郡司職に任じる旨の勅を得ている。 出仕 田村麻呂が蔭位の制を適用される21歳に達した宝亀9年(778年)に父の苅田麻呂は正四位下であったため、田村麻呂が庶子の場合は従七位上が叙位されるが、次男もしくは三男でも正室の長男であれば嫡子のため正七位下が叙位される。 しかし田村麻呂が嫡子もしくは庶子のどちらであったかを判断する決め手になる史料はない。いずれにせよ宝亀9年に出仕している場合は七位の官人として出発した。 宝亀11年(780年)、田村麻呂は23歳で近衛府の将監として将種を輩出する坂上氏らしく武官からの出仕であった。 天応元年4月3日(781年1月30日)、光仁天皇は山部親王に譲位して桓武天皇が即位した。桓武の生母である高野新笠は武寧王を祖とする百済系渡来系氏族の和氏出身で、帰化人の血を引く桓武の登場によって渡来系氏族は優遇措置がなされることもあった。 延暦元年(782年)閏1月に起きた氷上川継の乱では父・苅田麻呂が事件に連座したとして解官されているが、わずか4ヶ月後には再び右衛士督に復職している。また苅田麻呂は延暦4年(785年)6月に後漢の霊帝の子孫である坂上氏が忌寸の卑姓を帯びていることを理由に宿禰姓を賜りたいと上表し許され、同族11姓16名が忌寸姓から宿禰姓へ改姓、嫡流の坂上氏は大忌寸であったため大宿禰と称した。 延暦4年 (785年12月31日)、安殿親王(後の平城天皇)が立太子すると、田村麻呂は28歳で正六位上から従五位下へと昇進した。 外位の五位を通らずに従五位下へと昇進しているため、この頃には坂上氏が地方的豪族から中央貴族へと転身していた証左となる。延暦5年1月7日(786年2月10日)に父・苅田麻呂が薨去すると田村麻呂は一年間喪に服した。 延暦6年(787年)早々に喪があけると近衛将監へと復帰した。3月22日(787年4月14日)に内匠助を兼任、9月17日(787年11月1日)には近衛少将へと進んだ。 延暦7年6月26日(788年8月2日)に近衛少将と内匠助のまま越後介を兼任、延暦9年(790年)には越後守へと昇格した。
2024年11月26日
閲覧総数 35
-
17

「歴史の回想・宝亀の乱」出羽国、そして渡島蝦夷への影響。
7「出羽国、そして渡嶋蝦夷への影響」呰麻呂の乱の影響は、伊治城、多賀城周辺のみならず、陸奥国そして出羽国の広汎な範囲に影響を及ぼした。出羽国でも宝亀11年(780年)に、乱に連動して蜂起した蝦夷が雄勝郡・平鹿郡を襲撃・略奪したことが記録されている。このような情勢のもと、陸奥国に派遣する征東大使とあわせて、出羽鎮狄将軍に安倍家麻呂を任じる人事が発令されたのは前述のとおりである。この時家麻呂は軍事以外にも出羽国の政治問題にも関与している。もともと出羽国は陸奥国に比べ常備兵力が少なく、かつ乱の波及によって雄勝城の防衛に多くの兵力を割く必要が生じたため、秋田城の守備を維持することが困難になった。 〇「秋田城」(あきたじょう/あきたのき)は、出羽国秋田(現在の秋田県秋田市)にあった日本の古代城柵。国の史跡に指定されており、かつての城域の一部は現在高清水公園となっている。また、秋田県護国神社も秋田城の城址に遷座したものである。 秋田城の創建は、733年(天平5年)に出羽柵が庄内地方から秋田村高清水岡に移転したことにさかのぼり、その後天平宝字年間に秋田城に改称されたものと考えられている。秋田城は奈良時代の創建から10世紀中頃までの平安時代にかけて城柵としての機能を維持したと考えられており、その間幾度か改廃が取り沙汰されたことがあったものの、出羽国北部の行政・軍事・外交・文化の中心地としての役割を担った。 また、秋田城の発掘調査結果からは渤海との交流を伺わせる複数の事実が指摘されており、文献史料による確たる証拠はないものの、奈良時代を通じてたびたび出羽国に来着した渤海使の受け入れが秋田城においてなされた可能性が高いと考えられている。 秋田城は朝廷によって設置された城柵の中でも最北に位置するものであり、律令国家による統治の拠点として、また津軽・渡島の蝦夷との交流や渤海との外交の拠点として、重要な位置にあった。 2017年(平成29年)、続日本100名城(107番)に選定された。 秋田城の史料上の初出は、『続日本紀』において733年(天平5年)に出羽柵(いではのき)を秋田村高清水岡に遷置したと記述されたことにさかのぼる。7世紀の中葉から9世紀の初頭にかけて、当時の朝廷は東北地方の蝦夷を軍事的に制圧し服属させ、柵戸移民を扶植して積極的な支配域の拡大を図っており、日本海側では708年(和銅元年)に現在の山形県庄内地方を越後国出羽郡として建郡、712年(和銅5年)には越後国から分離して出羽国に昇格させ、陸奥国から移管された置賜郡・最上郡とあわせて初期の出羽国を形成した。前後して出羽郡内に出羽柵を設置したものと考えられている。 秋田城は朝廷の支配域の北上にともない出羽柵を移転したものと捉えられるのであるが、8世紀当時の秋田地方では大規模な集落の跡が確認されておらず、後城遺跡のような城柵の進出にともなって形成された集落が城柵の近傍に存在する程度であった。 すなわち当時の秋田地方は人口が希薄で、移転当初の出羽柵は朝廷の支配域の北辺に突出しており、出羽柵(秋田城)の設置にともなって城柵周辺に蝦夷や柵戸移民が混在する集落が形成されたものと推測されている[6]。 秋田に移った出羽柵は、760年(天平宝字4年)3月19日付の『丸部足人解』において「阿支太城」と表記されており、この頃秋田城に改称したものと考えられている。 『続日本紀』、780年(宝亀11年)8月23日の条では、秋田城へ派遣された鎮狄将軍安倍家麻呂の具申に対して朝廷から「秋田城は、前将軍や宰相が建てたものであり、長い年月を経てきた」と回答したことが見え、760年頃に秋田城へ機構改編したことを裏付ける。 このときの安倍家麻呂と朝廷の応答において秋田城の停廃が検討されたが、朝廷は秋田城の放棄を認めず、かえって軍兵を遣わして鎮守とし、鎮狄使または国司1名を専当として秋田城の防護にあたらせるものとした。これにより、国司次官である出羽介が秋田城介(あきたじょうのすけ)として城に常置され、出羽国北部の統治にあたることとなった。 8世紀には、沿海州付近にあった渤海国からの使節がたびたび出羽国へ来着した。そもそも出羽柵の秋田移転には、なぜ庄内地方から一挙100㎞も北進して人口希薄な秋田地方へ突出したのかという疑問が生じるのであるが、そこで秋田城の海上交流の拠点としての性格が着目され、秋田城が渤海使や北方民族との外交施設としての役割を担ったとする説が示されている。 8世紀の渤海使は、日本の使節船に同乗している場合を除いてほとんどが出羽に来着しており、新野直吉、古畑徹らの研究は、渤海使が沿海州・サハリン・北海道の沿岸部伝いに航行して本州日本海側に達する北回り航路を取っていたことを唱え、さらに新野は出羽柵移転の背景に、渤海使の来航があった出羽国北部に中央政府と直結した出先機関を置いて、外国使節への対応を担わせたとする見方を示した。 ただし、そのことは大和朝廷が積極的に外交に取り組んだということを意味せず、せいぜい新年朝賀への外交使節参列の便宜を図ろうという程度の意図であり、しかも、渤海国側の技術的な事情により、想定されたルートと頻度では使節が来訪しなかったので現実の有用性は限定的であった、との指摘もある。 発掘調査結果からは、城外南東側の鵜ノ木地区において規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の遺構と、水洗トイレの遺構などが検出されており、これらは国営調査では城に附属した寺院の四天王寺跡とする見解が示されているが、8世紀から9世紀初までの遺構については、建物が礎石式を取らず瓦葺きでないなど、寺院建築とするには疑問も示されており、これら施設群は外交使節を饗応する迎賓館だったのではないかとの推測も示されている。 なお、9世紀以降渤海使の出羽来航は途絶えており、鵜ノ木地区の遺構も、9世紀以降のものは木柵に囲われた寺院風の構成となっていく。 804年(延暦23年)、秋田城が停廃されて秋田郡が設置され、秋田城が担っていた機能は河辺府へ移されたとされる。先の802年(延暦21年)に朝廷はアテルイとの軍事的抗争に勝利し、これを受けて陸奥に胆沢城・紫波城を造営、出羽でも同時期に払田柵(第Ⅱ期雄勝城)が造営されたとみられるなど、9世紀初は朝廷と蝦夷との関係が大転換した時期にあたる。停廃という文言と裏腹にこの時期秋田城は大改修を受けており、秋田城の停廃とは陸奥方面での朝廷の軍事的勝利を受けて、秋田城を取り巻く環境が孤立した状態から解消されたことにともなう、支配体制再編の一環として行われたものと考えられる。 733年の出羽柵移転以降、秋田郡が設置されるまでの約70年間、秋田地方では郡を置かず城が領域支配をも担う特殊な体制が取られていたが、秋田城の改修は郡制への移行と軌を一にするものであり、むしろ支配体制を強化する形で秋田城は出羽北部の軍事・行政拠点として存続することとなった。 830年(天長7年)には出羽大地震により城廓および官舎のことごとくが損傷する被害を受けた事が記されている。この時の被害報告から城に附属して四天王寺・四王堂といった宗教施設が存在した事実が示されている。 878年(元慶2年)に勃発した俘囚の大規模反乱(元慶の乱)では、俘囚側が秋田城を一時占拠するに至り、発掘調査からも乱によって城が焼かれたことを裏付ける焼土炭化物層が検出されている。 この乱の背景に、長く軍事的緊張から遠ざかっていた秋田城では制度上常備すべきとされていた軍が実際には配備されておらず、少数の健児が守るのみで警備が手薄になっていたことが挙げられる[18]。 また、出羽国統治が安定していた反面、それに乗じて国司による苛烈な収奪が横行しており、元慶の乱の時期を記した『日本三代実録』元慶三年三月二日壬辰の条では、国内の公民の3分の1が「奥地」に逃亡するという異常事態に陥っていたことが記されている。 元慶の乱は、出羽権守として派遣された右中弁藤原保則が、主に上野国・下野国の兵で編成された軍を率いて乱の鎮圧にあたり、また鎮守将軍として派遣された小野春風による懐柔策も受けて、硬軟織り交ぜた対応により終結に向かい、秋田城は回復されて復興整備に向かっている。 その後939年(天慶2年)の天慶の乱の際にも、秋田城は攻撃を受けている。10世紀後半には秋田城の基本構造と機能が失われたと考えられており、鵜ノ木地区においては11世紀前半までの遺構が確認されているものの、城内では11世紀以降に該当する主要な遺構が確認されていないことから、この頃には衰退していたと考えられている。 平安時代後期から中世にかけて、史料上はなおも秋田城の文字が継続して確認されており、鎌倉時代には秋田城介の官職は武門にとって名誉あるものであったとされるが、中世の秋田城として比定される有力な遺構は確認されておらず、古代の秋田城跡周辺が有力な擬定地として推測されるにとどまっている。 秋田城国府説と非国府説について 8世紀の秋田城に出羽国の国府が置かれていたかどうかは、学説上の争点となっている。これは『日本後紀』および『日本三代実録』において、延暦年間に出羽国国府を移転した旨が記されていることに端を発する。 『日本後記』では804年(延暦23年)11月癸巳の条において、秋田城を停廃し郡制を布いて機能を河辺府に移転したことが、『日本三代実録』では887年(仁和3年)5月20日の条に、出羽郡井口にある国府は延暦年間に造営されたことが、それぞれ記されており、この二条の解釈によって、秋田城に国府が置かれたとする学説が現れることとなった。 なお、国府説、非国府説の両者ともに、712年(和銅3年)の出羽国設置時の国府は出羽柵であること、延暦年間以降は国府が出羽郡井口(=城輪柵)にあったということで見解が一致しており、争点となっているのは出羽柵が秋田に移転する733年(天平5年)から、「延暦年間」までの出羽国府の所在地ということになる。 秋田城国府説の視点と論者 秋田城国府説を取る平川南の学説では、733年の出羽柵秋田移転から804年の秋田城停廃までの期間秋田城に国府があったと推定し、737年(天平9年)に陸奥国の多賀柵から出羽柵までの直通道路が計画されたことを、陸奥按察使が陸奥・出羽の両国府間で連絡を密にするためであったとして、秋田城国府説の根拠に挙げている。 また、新野直吉は、733年の出羽柵秋田移転にともない国府も秋田城に移転し、その後804年(延暦23年)に河辺府に国府機能を移転(河辺府を払田柵跡と推定)、その後815年 – 819年(弘仁6年~10年)に再移転して、出羽郡井口に移ったとの見解を示した。 秋田城の発掘資料からは、出羽国の守と介の署名がある天平宝字年間の漆紙文書が出土しており、秋田城国府説の立場では、これを国府で最終保管されるべき性質の資料であるとみる。伊藤武士もこの立場に立っており、秋田城国府説では、発掘された考古資料を主要な根拠とすることが多い。しかし、秋田城国府説を裏付ける決定的な文字資料の出土には未だ至っていない。
2024年11月26日
閲覧総数 38
-
18

「歴史の回想・宝亀の乱」鎮狄将軍。 川村一彦
鎮狄将軍(ちんてきしょうぐん)は、日本の奈良時代におかれた令外官の官職の将軍である。 鎮狄将軍(征狄将軍)は、蝦夷征討に際し任命された将軍の一つで、日本海側を北に進む軍を率いる。なお、太平洋側を進む軍を率いる将軍を征夷将軍(征東将軍)、九州へ向かう軍を率いる将軍を征西将軍(鎮西将軍)という。これは、「東夷・西戎・南蛮・北狄」と呼ぶ中華思想の「四夷」を当て嵌めた為とされている。 蝦夷征討に際し、日本海側を進む軍を率いる最初の将軍は、和銅2年(709年)に陸奥・越後の蝦夷が良民を害するためとして、陸奥鎮東将軍の巨勢麻呂と同時に任じられた佐伯石湯であり、任命時は「征越後蝦夷将軍」とされ、征討を終え凱旋入京の際には「征蝦夷将軍」、褒賞では「征狄将軍」とされており、統一されてはいないがいずれにしろ鎮狄将軍の最初である。なお、これに先立つ和銅元年(708年)9月28日越後国に出羽郡がおかれ、その後の和銅5年(714年)9月23日に出羽国となった。 養老4年(720年)陸奥国の蝦夷の叛乱により、9月28日に陸奥按察使の上毛野廣人が殺害され、蝦夷鎮圧のため多治比縣守が持節征夷将軍に任じられ、同時に阿倍駿河が持節鎮狄将軍に任じられた[4]。 その後も、陸奥国での事件による征夷将軍の任命に併せ日本海側の鎮圧のため鎮狄将軍が任命された。神亀元年(724年)には、3月25日に陸奥大掾佐伯児屋麻呂が殺害され同年4月7日に藤原宇合を持節大将軍に任じ、その際5月24日小野牛養が鎮狄将軍に任じられた。 また、宝亀11年(780年)に陸奥国伊治郡で勃発した伊治呰麻呂の乱で陸奥按察使の紀広純が殺害され、3月28日藤原継縄が征東大使に任じられた際には、翌29日に安倍家麻呂が出羽鎮狄将軍に任じられた。 しかしこの後、秋田城に出羽介を長とする鎮守部隊がおかれ、陸奥国の蝦夷征討のため大規模な軍を率いる征夷大将軍が任じられるようになり、鎮狄将軍は任じられなくなった。 陸奥国の動乱はより深まっていき、政府と蝦夷が軍事的に全面対決する時代が到来する。にもかかわらず首謀者であった呰麻呂は捕らえられることなく、その後の記紀にも現れずに歴史の中に消えてしまっている。 3「背景と原因」乱の原因として『続日本紀』では、呰麻呂の個人的な怨恨を理由に挙げている。夷俘の出身である呰麻呂は、もともと事由があって紀広純を嫌っていたが、恨みを隠して媚び仕えていたために、紀広純の方では意に介さずに大いに信頼を置いていた。これに対し道嶋大楯は常日頃より呰麻呂を夷俘として侮辱していたために、呰麻呂がこれを深く恨んでいたとするものである。もともと呰麻呂には政府に協力した功績を賞して、伊治公の姓と、第二等の蝦夷爵の地位が与えられていたが、宝亀9年(778年)6月には、伊治城造営や俘軍を率いて戦った功績を賞して外従五位下という地方在住者としては最高の位が授けられている。このように政府に協力し、かつそれまでの功績を認められて地位を昇進させてきた呰麻呂にとって、つとに道嶋大楯から辱めを受けていたことは、耐えがたい屈辱であったと考えられる。一方でこの乱は、呰麻呂個人の怨恨に帰結するものでなく、藤原仲麻呂政権以降、 〇「藤原 仲麻呂」(ふじわら の なかまろ)は、奈良時代の公卿。名は仲麿または仲丸とも記される。淳仁朝以降は改姓・改名し藤原恵美押勝(ふじわらえみ の おしかつ)。左大臣・藤原武智麻呂の次男。官位は正一位・太師。恵美大臣とも呼ばれた。 文武天皇末年の慶雲3年(706年)に藤原南家の始祖である藤原武智麻呂の次男として生まれる。生まれつき聡明鋭敏であり、大抵の書物は読破していた。また、大納言・阿倍宿奈麻呂に算術を学び、優れた学才を示した。内舎人から大学少允を経て、天平6年(734年)従五位下に叙爵。 藤原四兄弟の死と橘諸兄の台頭 天平9年(737年)天然痘の流行により、光明皇后の後ろ盾として政権を担っていた父の武智麻呂と叔父の藤原房前・藤原宇合・藤原麻呂のいわゆる藤原四兄弟が相次いで病死し、藤原氏の勢力は大きく後退する。替わって光明皇后の異父兄で疫病禍をかわした橘諸兄が参議から一挙に大納言次いで右大臣に昇進して国政を担うようになった。 兄たちを次々と失った光明皇后は、その不安から聖武天皇へ大仏建立を強く勧めたとされる。また、天平12年(740年)に聖武天皇が河内国大県郡の智識寺を訪ね、その寺の盧舎那仏から大いに影響を受けたという。この智識寺は、名が表すとおり智識(同信集団)の勧進銭によって建立された寺で、それは東大寺成立の過程にも反映された。 橘諸兄との対立 天平11年(739年)従五位上、天平12年(740年)正五位上と橘諸兄政権下で仲麻呂は順調に昇進し、天平13年(741年)従四位下・民部卿に叙任される。また同年4月に河内国と摂津国が帰属を争っている川の堤の調査を、同年9月には恭仁京に派遣されて人民への宅地の分配を行っている。 天平15年(743年)従四位上参議に叙任され公卿に列する。天平18年(746年)式部卿に転じる。式部卿は官吏の選叙と考課を握る官職であり、仲麻呂は大幅な人事異動を行って諸兄の勢力を削ぎ、自らの派閥を形成した。仲麻呂は叔母にあたる光明皇后の信任が厚く、従兄妹で皇太子だった阿倍内親王(後の孝謙天皇)とも良好な関係にあった。 天平16年(744年)閏1月11日、当時17歳の聖武天皇の第二皇子安積親王が難波宮に行啓の途上、桜井頓宮で脚気になり恭仁京に引き返すが、わずか2日後に薨去した]。その死があまりにも急で不自然なところもあったことから、藤原仲麻呂に毒殺されたという説も根強い。 こののち仲麻呂は天平18年(746年)従三位、天平20年(748年)には正三位と急速な昇叙を続け、光明皇后の後ろ盾のもとでその権勢は左大臣・橘諸兄と拮抗するようになった。 孝謙天皇即位と大納言就任 天平勝宝元年(749年)7月に聖武天皇が譲位して阿倍内親王が即位(孝謙天皇)すると、仲麻呂は参議から中納言を経ずに直接大納言に昇進。次いで、光明皇后のために設けられた紫微中台の令(長官)と、中衛大将を兼ねた。光明皇后と孝謙天皇の信任を背景に仲麻呂は政権と軍権の両方を掌握して左大臣橘諸兄の権力を圧倒し、事実上の「光明=仲麻呂体制」が確立された。 同年10月に東大寺の盧舎那仏像 の鋳造が完了する。藤原仲麻呂自身も仏教に高い関心を示していたといわれ、仏教信仰に篤い光明皇太后を支援した。天平勝宝4年(752年)大仏開眼供養会が盛大に催され、その夜女帝は内裏に帰らず仲麻呂の私邸である田村第におもむき、しばらくここを在所とした。孝謙天皇は後年も平城京の修理を理由として田村第に長逗留したことから、この邸宅は「田村宮」とも呼ばれた。 この頃の太政官では仲麻呂の上位に外伯父の橘諸兄と実兄の藤原豊成が左右の大臣として並んでいた。仲麻呂は豊成を中傷しようと機会を窺っていたが、仲麻呂をよく知る豊成は乗じる隙を与えなかった。その一方で天平勝宝7歳(755年)には諸兄が朝廷を誹謗したとの密告があり、聖武上皇はこれを許したものの諸兄は恥じて翌天平勝宝8歳(756年)に左大臣を辞官した。 同年聖武上皇が崩御。遺詔により道祖王が皇太子に立てられた。しかし、翌天平勝宝9歳(757年)3月に道祖王は喪中の不徳な行動が問題視されて皇太子を廃され、仲麻呂の意中であった大炊王(後の淳仁天皇)が立太子される。この王は、仲麻呂の早世した長男・真従の未亡人(粟田諸姉)を妃としており、かねてより仲麻呂の私邸である田村第に身を寄せる身の上であった。5月には祖父の不比等が着手した養老律令を施行するとともに、仲麻呂は紫微内相に任ぜられ大臣に准じる地位に就いた。 橘奈良麻呂の乱Ø こうした仲麻呂の台頭に不満を持ったのが橘諸兄の子の奈良麻呂だった。皇太子廃立をうけて奈良麻呂は大伴古麻呂らとともに、仲麻呂を殺害して天武天皇の孫にあたる皇族を擁立する反乱を企てるが、はやくも同年6月に上道斐太都らの密告により計画が露見。奈良麻呂の一味は捕らえられ、443人が処罰される大事件となった。Ø 奈良麻呂と古麻呂をはじめ、新帝擁立の候補者に名が挙がっていた道祖王や黄文王も捕縛され拷問を受けて獄死、反乱に関与したとして右大臣藤原豊成も左遷された(橘奈良麻呂の乱)。これによって仲麻呂は太政官の首座に就き、名実ともに最高権力者となった。 淳仁天皇の時代 天平宝字2年(758年)8月に孝謙天皇が譲位して大炊王が即位(淳仁天皇)する。淳仁天皇を擁立した仲麻呂は独自な政治を行うようになり、中男と正丁の年齢繰上げや雑徭の半減、問民苦使や平準署の創設など徳治政策を進めるとともに、官名を唐風に改称させる唐風政策を推進した。 そして仲麻呂自身は太保(右大臣)に任じられる。さらに、仲麻呂の一家は姓に恵美の二字を付け加えられるとともに、仲麻呂は押勝の名を賜与された。また鋳銭と出挙の権利も与えられ、藤原恵美家には私印を用いることが許された。 新羅征討計画 この年唐で安史の乱が起きたとの報が日本にもたらされると、仲麻呂は大宰府をはじめ諸国の防備を厳にすることを命じる。天平宝字3年(759年)には新羅が日本の使節に無礼をはたらいたとして、仲麻呂は新羅征伐の準備をはじめさせた。軍船394隻、兵士4万700人を動員する本格的な遠征計画が立てられるが、この遠征は後の孝謙上皇と仲麻呂との不和により実行されずに終わる。 光明皇太后の崩御 天平宝字4年(760年)仲麻呂は皇族以外で初めて太師(太政大臣)に任じられるが、同年光明皇太后が崩御。皇太后の信任厚かった仲麻呂にとってこれが大きな打撃となる(ただし、皇太后の健康悪化を知っていた仲麻呂が自らの地位安定のために皇太后崩御に先んじて太師任命を受けたとする解釈もある。実際に太師任命は孝謙上皇が淳仁天皇臨席の場で宣命の形で発表し、後から淳仁天皇から正式な手続で任命されるという二重の手続が取られて、上皇・天皇から信を受けた形を取っている)。 さらにこの年には弟の乙麻呂も失っている。 天平宝字5年(761年)淳仁天皇と孝謙上皇を近江国の保良宮に行幸させ、唐の制度にならって保良宮を「北宮」とした。 天平宝字6年(762年)1月、仲麻呂は子の真先を氷上塩焼とともに参議に任じてたが、6月には尚蔵・尚侍を務めて仲麻呂と上皇の間のパイプ役になっていた正室の藤原袁比良を失い、続く7月と9月には仲麻呂の腹心から議政官になった参議紀飯麻呂と中納言石川年足も失って、仲麻呂の政治的基盤は弱体化した。そこで仲麻呂は12月には2子訓儒麻呂・朝狩と女婿の藤原弟貞を石川年足の弟の石川豊成とともに参議に任じ、同時に白壁王(後の光仁天皇)を参議を経ずに中納言に抜擢、中臣清麻呂も参議に任じて政権の補強を図った。しかし1年のうちに近親者4名を参議に任じた仲麻呂の人事はくすぶる反対派に油を注ぐ結果となっていく。 道鏡 一方、この頃病になった孝謙上皇は自分を看病した道鏡を側に置いて寵愛するようになった。仲麻呂は淳仁天皇を通じて、孝謙上皇に道鏡との関係を諌めさせた。これが孝謙上皇を激怒させ、上皇は出家して尼になるとともに天皇から大事・賞罰の大権を奪うことを宣言するが、これが実現したかどうかについては研究者のあいだでも見解が分かれる。孝謙上皇の道鏡への寵愛は更に深まり、天平宝字7年(763年)には道鏡を少僧都とした。
2024年11月26日
閲覧総数 33
-
19

「歴史の回想・宝亀の乱」節刀。 川村一彦
〇「節刀」(せっとう、せちとう)は、日本の歴史において、天皇が出征する将軍または遣唐使の大使に持たせた、任命の印としての刀。標の太刀(しるしのたち)、標剣(しるしのつるぎ)とも。「節」は符節(割り符)のことで、使臣が印として持つ物の意。任務を終了すると、天皇に返還された。 節刀を持たされた将軍を持節将軍(じせつしょうぐん)、節刀を持たされた大使を持節大使(じせつたいし)という。持節将軍は、辺境の反乱を鎮定するために派遣される軍団の総指揮官で、鎮定する対象により、征隼人将軍、征夷大将軍、征東将軍などと呼ばれた。「朝家の御守り」として遠征将軍に授ける場合は、鎮圧の対象は朝敵とされた。 『日本書紀』によれば、継体天皇21年(527年)に起きた磐井の乱に際して、筑紫君磐井の征討を命じられた物部麁鹿火に、継体天皇が刀を授けたことが、節刀の初めとされる。その後も、大宝元年(701年)に民部尚書と遣唐執節使に任じられた粟田真人に文武天皇が授けた例や、延暦20年(801年)に蝦夷討伐を命じられた征夷大将軍の坂上田村麻呂に桓武天皇が授けた例などがよく知られる。将軍や大使に節刀を授ける習わしは、遣唐使が廃止され、辺境の反乱が減少した平安時代末期には廃れた。 それから数百年が経過した江戸時代末期、政治的な意味を持つ儀式として、節刀下賜が注目されるようになる。文久3年(1863年)、上洛した徳川家茂に対して攘夷の実行を促すため、孝明天皇から節刀を授けることが図られた。 結局、この計画は流れたが、徳川将軍の権威の低下と天皇・朝廷の権威の復活は明らかとなった。さらに、慶応4年/明治元年(1867年)には、東征大総督に任じられた有栖川宮熾仁親王が東征に際して明治天皇から錦の御旗と節刀を授けられた。 明治時代には、天皇が国の元首として統帥権(大日本帝国憲法11条)を含む統治権を総攬し憲法に依拠してこれを行使する立憲君主制(帝国憲法4条)が整い、富国強兵の国策の下、天皇の軍事的権威も高められた。制度の近代化・西欧化が進められる中で、節刀の慣習は元帥への刀剣下賜という形で残される。1904年(明治37年)の日露戦争のときには、皇太子(後の大正天皇)が連合艦隊司令長官の東郷平八郎に名刀・一文字吉房[3]を下賜して激励した。これも節刀の一種と考えられている。 斧鉞 中国で、斧鉞を出征する将軍に兵を律し罰する処刑具として持たせていた。日本武尊や神功皇后の持つ鉞によって権力の移譲された記述をみられ、古代日本にも風習が伝来していたようである。また日本書紀の継体天皇の項で、先の物部麁鹿火に斧鉞を与え、筑紫から西の統治権を与えた記述がある。 益立の赴任に際し、3月29日に陸奥守を兼任させ、ついで4月4日に正五位上から従四位下に昇進させた。さらに5月14日には坂東諸国及び能登国、越中国、越後国に対し軍糧の供出も命じられ、5月16日には進士(志願兵)を募る勅までも発せられている。しかし、征東使として派遣されながら益立らの現地での軍事行動は遅々として進展しなかった。5月8日に最初の報告があり、「まずは兵糧を蓄え、5月下旬に国府に入った後敵の機を伺い、然るべき時期に征討を行う」とする方針を伝えてからその後2ヶ月近くに渡り、連絡さえも途絶えてしまったのである。これに対し光仁天皇は、6月28日に書状または軍監以下の者を遣わして実情を報告するよう強く命じるに至った。 〇「光仁天皇」(こうにんてんのう、709年11月18日〈和銅2年10月13日〉- 782年1月11日〈天応元年12月23日〉)は、日本の第49代天皇(在位:770年10月23日〈宝亀元年10月1日〉- 781年4月30日〈天応元年4月3日〉)。諱は白壁(しらかべ)。和風諡号は天宗高紹天皇(あまつむねたかつぎのすめらみこと)。天智天皇の第7皇子・施基親王(志貴皇子)の第6皇子。母は紀橡姫(贈太政大臣紀諸人の娘)。 8歳で父が死亡して後ろ盾を失くしたためか、初叙(天平9年(737年)従四位下)が29歳と当時の皇族としては非常に遅かった。 天平勝宝元年(749年)、聖武天皇が譲位し皇太子・阿倍内親王が受禅、孝謙天皇として即位した。これにより、同じく聖武天皇の皇女で孝謙天皇の異母姉妹である井上内親王・不破内親王の腹から、女性皇太子の地位を脅かしかねない男子後継者が生まれる可能性を警戒されることは無くなった。 そして井上内親王・不破内親王姉妹も伴侶を求める機会が与えられることになり、天平勝宝4年(752年)頃までに、すでに斎宮を退任していた井上内親王は権力争いに巻き込まれる恐れのない白壁王と結婚した。天平勝宝6年(754年)の白壁王45歳、井上内親王38歳の時に酒人女王が誕生。それから俄然として昇進を速め、天平宝字3年(759年)には50歳にして従三位に叙せられる。天平宝字5年(761年)井上内親王45歳の時、他戸王(第四皇子)が誕生。天平宝字6年(762年)に中納言に任ぜられる。 天平宝字8年(764年)には藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)鎮圧に功績を挙げ、称徳天皇(孝謙天皇が重祚)の信任を得て、天平神護2年(766年)には大納言に昇進した。だが度重なる政変で多くの親王・王が粛清されていく中、白壁王は専ら酒を飲んで日々を過ごす事により、凡庸・暗愚を装って難を逃れたと言われている。 神護景雲4年(770年)、称徳天皇が崩御する。生涯独身の称徳天皇に後継者はなく、また度重なる政変による粛清によって天武天皇の嫡流にあたる男系皇族が少なくなっていた。 しかし妃の井上内親王は聖武天皇の皇女であり、白壁王との間に生まれた他戸王(他戸親王)は女系ではあるものの天武天皇系嫡流の血を引く男性皇族の一人であった。このことから天皇の遺宣(遺言)に基づいて立太子が行われ、同年10月1日、62歳の白壁王は大極殿で即位することとなった[1]。 元号は宝亀と改められた。 称徳天皇崩御の際に左大臣・藤原永手、右大臣・吉備真備、参議の藤原宿奈麻呂、藤原縄麻呂、石上宅嗣、近衛大将・藤原蔵下麻呂らによる協議が行われたと『続日本紀』は伝えている。 「百川伝」を引用する『日本紀略』などの記述は、この協議で天武天皇系の長親王の子である文室浄三、次いでその弟・大市を推した真備と、白壁王を推す藤原永手・宿奈麻呂らで対立があり、藤原百川の暗躍によって白壁王の立太子が実現したと伝えている[2]。 即位後、井上内親王を皇后に、他戸親王を皇太子に立てるが、宝亀3年(772年)3月2日、皇后の井上内親王が呪詛による大逆を図ったという密告のために皇后を廃され、5月27日、皇太子の他戸親王も皇太子を廃された。 翌 宝亀4年(773年)高野新笠所生の山部親王が皇太子に立てられた(のちの桓武天皇)。この背景には、藤原百川ら藤原式家の兄弟と彼らが擁立する山部親王の陰謀があったとされる。 さらに、翌宝亀4年(773年)10月14日、天皇の同母姉・難波内親王が薨去すると、10月19日、難波内親王を呪詛し殺害した巫蠱・厭魅の罪で、井上内親王と連座した他戸親王は庶人に落とされ、大和国宇智郡の没官の邸に幽閉された。宝亀6年4月27日(775年5月30日)、井上内親王・他戸親王母子が幽閉先で急死した。この同じ日に二人が亡くなるという不自然な死には暗殺説も根強い。これによって天武天皇の皇統は完全に絶えた。 この事件後、光仁天皇の即位について藤原百川とともに便宜を謀った藤原蔵下麻呂が急死すると、宝亀7年(776年)、祟りを恐れた光仁天皇より秋篠寺建立の勅願が発せられる。開基は善珠僧正。 その後も、天変地異が続き、宝亀8年(777年)11月1日には光仁天皇が不豫(病)となり、12月、山部親王も死の淵をさまよう大病を得た。この年の冬、雨が降らず井戸や河川が涸れ果てたと『水鏡』は記している。 これらの事が井上内親王の怨霊によるものと考えられ、皇太子不例(病)の3日後の同年12月28日、井上内親王の遺骨を改葬し墓を御墓と追称、墓守一戸を置くことが決定した。 宝亀12年(781年)1月1日、伊勢斎宮に現れた美雲の瑞祥により天応に改元する。元日の改元は現在のところ日本史上唯一の事例である。 天皇は70歳を超えても政務に精励したが、天応元年(781年)2月に第一皇女・能登内親王に先立たれてから心身ともに俄かに衰え、同年4月3日、病を理由に皇太子に譲位し、太上天皇となる。同年12月23日、光仁天皇は崩御した。宝算73。 直後の天応2年(782年)閏正月頃、天武天皇の曾孫・氷上川継によるクーデタ未遂事件が起きた(氷上川継の乱)。川継の父は藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)で戦死した塩焼王、母は井上内親王の同母妹不破内親王であった。 同年6月14日、人臣の最頂点である左大臣・藤原魚名が氷上川継の乱に加担していたとして罷免され、その子の鷹取、末茂、真鷲もそれぞれ左遷された。藤原魚名は翌延暦2年(783年)7月25日頓死。光仁天皇の崩御後も政情が落ち着くことは決して無かった。 その結果7月下旬以降にあらためて武具や軍糧を多賀城方面に進発させるよう、東海道・東山道諸国に命が出されている。これにより9月以降に征夷がなされる見通しが立ったものの、最初の反乱から半年近くの時間を空費することになったのである。しかし、政府側の混乱はさらに続く。乱からおよそ半年後の9月23日、参議であった藤原小黒麻呂が正四位下の位を授けられ、持節征東大使に任命された。 〇「藤原 小黒麻呂」(ふじわら の おぐろまろ)は、奈良時代の公卿。藤原北家、従五位下・藤原鳥養の次男。官位は正三位・大納言、贈従二位。勲等は勲二等。 天平5年(733年)藤原鳥養の次男として誕生。天平宝字8年(764年)藤原仲麻呂の乱の論功によって従五位下・伊勢守に叙任される。称徳朝では式部少輔・安芸守・中衛少将を歴任する。 宝亀元年(770年)光仁天皇の即位に伴い従五位上に昇叙されると、宝亀2年(771年)正五位下、宝亀4年(773年)従四位下、宝亀9年(778年)従四位上と光仁朝にて順調に昇進し、翌宝亀10年(779年)には参議に任ぜられ公卿に列した。またこの間、左京大夫・右衛士督や上野国・常陸国等の国司を歴任している。 宝亀11年(780年)伊治呰麻呂の乱(宝亀の乱)が起こると、藤原南家・藤原継縄の後任として正四位下・持節征東大使に叙任され、2,000の兵を率いて出兵して敵の要害を遮断したという。 しかしながら、優勢な蝦夷の軍勢の前に大規模な軍事作戦を展開できないまま、翌天応元年(781年)6月征夷部隊を解散、8月に帰京するが、三階昇進して正三位に叙せられている。 延暦3年(784年)に中納言に昇進。延暦8年(789年)には、巣伏の戦いで蝦夷の酋長阿弖流為に惨敗した征東大使紀古佐美に対して、藤原継縄と共に敗軍状況に対する追及を行った。 延暦9年(790年)に大納言となる。同3年に長岡京、同12年に平安京のそれぞれ造営の相地役を務め、また光仁天皇・高野新笠・藤原旅子・藤原乙牟漏といった桓武天皇近親者の葬儀や喪事にも大きな役割を果たす等、桓武天皇の政権運営に当たって貢献するところ大であった。 延暦13年(794年)に病を得て、特に正倉院の雑薬を贈られたが、7月1日薨去。享年62。最終官位は大納言正三位中務卿兼皇后宮大夫。没後従二位が追贈された。 節刀を授けられるのは天皇の代理人であることの証であるため、一つの征討使の中に二人以上ということはあり得ず、この時に赴任しなかった前征東大使藤原継縄だけでなく、副使大伴益立の節刀も褫奪されたとみられる。結局のところ大伴益立が具体的な軍事行動に着手できなかったのも、人員、軍糧、武具のいずれもが不足していたからであると考えられている。更に副使でありながら異例の節刀を授けられたものの、節刀を持たないながらも同格である副将軍紀古佐美を従えねばならず、益立の指揮官としての権威は不十分であった。益立を更迭し高位高官の藤原小黒麻呂をあらためて征東大使に任じた背景には、このことを考慮した可能性が考えられる。結局益立は征東副使から更迭されたばかりか、翌年の天応元年(781年)5月27日には陸奥守も紀古佐美に交代させられ、9月26日には従四位下も剥奪される処分が下されてしまった。彼の死後、名誉が回復され従四位下に復されるのは実に56年後の承和4年(837年)、益立の子である大伴野継の熱心な訴えによってである。しかし、代わった藤原小黒麻呂による軍事行動も難航することになる。小黒麻呂の着任後とみられる10月22日には「今年は征討すべからず」と奏上しているが、光仁天皇はこれを厳しく譴責し、10月29日にあらためて征夷の実施を厳命している。これにより小黒麻呂も具体的な行動に着手せざるを得なくなり、12月10日には2,000の兵を動員して、「鷲座・楯座・石沢・大菅屋・柳沢等の五道」を塞ぎ、「賊」の要害を遮断したと報告している。
2024年11月26日
閲覧総数 31
-
20

「北条時行の群像」時行の誕生の背景。 川村一彦
3「誕生背景」鎌倉時代末期、鎌倉幕府の事実上の支配者北条氏の嫡流である得宗家の当主北条高時の次男として誕生。母は、軍記物語『太平記』の流布本第10巻「亀寿殿令落信濃左近太夫偽落奥州事」では、高時の妾(側室)である二位殿と伝承されている。このように流布本系統の表記では「二位殿」だが、『太平記』の古い写本の中には「新殿」とするものもあり、『太平記』研究者の長谷川端によれば、「新殿」が本来の表記であって「二位殿」は当て字であろうという[5]。時行の生年に関しては不明であるが、兄の北条邦時が正中2年11月22日(1325年12月27日)生まれなので[6]、それ以降ということになる。 ◯北条 邦時(ほうじょう くにとき)は、鎌倉時代末期の北条氏得宗家の嫡子。鎌倉幕府第14代執権・北条高時の長男。母は御内人・五大院宗繁の妹(娘とする系図もある)。乳母父は長崎思元。邦時の死後、中先代の乱を起こした北条時行は異母弟である。 元徳3年/元弘元年(1331年)12月15日に元服した]時は7歳であり、逆算すると生年は正中2年(1325年)となるが、同年11月22日付の金沢貞顕の書状によれば、「太守御愛物」(高時の愛妾)である常葉前が同日暁、寅の刻に男子を生んだことが書かれており、貞顕が「若御前」と呼ぶこの男子がのちの邦時であったことが分かる。同書状では高時の母(大方殿・覚海円成)や正室の実家にあたる安達氏一門が御産所へ姿を現さなかったことも伝えており、嫡出子ではない(庶長子であった)邦時の誕生に不快を示したようである。 翌3年(1326年、4月嘉暦に改元)3月13日に高時が出家。その後継者として安達氏は高時の弟・泰家を推したが、泰家の執権就任を阻みたい長崎氏(円喜・高資など)によって邦時が後継者に推される。しかし、当時の邦時は生後三カ月(数え年でも2歳)の幼児であり得宗の家督を継いだとしても幕府の役職に就くことはできず、邦時成長までの中継ぎとして同月16日に長崎氏は連署であった貞顕を執権に就けるが、安達氏による貞顕暗殺の風聞が流れたこともあって貞顕は僅か10日で辞任(嘉暦の騒動)、代わって中継ぎの執権には赤橋守時が就任した。 この後元徳元年(1329年)の貞顕(法名崇顕)の書状には「太守禅閣嫡子若御前」とあって最終的に高時の後継者となったようであり、慣例に倣って7歳になった同3年(1331年)12月に元服が行われた。儀式は幕府御所にて執り行われ、将軍・守邦親王の偏諱を受けて邦時と名乗った。 元弘3年/正慶2年(1333年)5月、 元弘の乱で新田義貞が鎌倉を攻めた際、邦時は父が自刃する前に伯父である五大院宗繁に託され、鎌倉市内に潜伏した。だが、北条の残党狩りが進められる中で、宗繁が褒賞目当てに邦時を裏切ろうと考えた。 邦時は宗繁に言いくるめられて別行動をとり、27日の夜半に鎌倉から伊豆山へと向かった。一方、宗繁がこれを新田軍の船田義昌に密告したため、28日の明け方に邦時は伊豆山へ向かう途上の相模川にて捕らえられてしまった。邦時はきつく縄で縛られて馬に乗せられ、白昼鎌倉へ連行されたのち、翌29日の明け方に処刑された。 享年9。『太平記』では、連行される邦時の姿を見た人やそれを伝え聞いた人も、涙を流さなかった人はいなかった、と記している。 なお、宗繁は主君であり自身の肉親でもある邦時を売り飛ばし、死に追いやった前述の行為が「不忠」であるとして糾弾され、義貞が処刑を決めた後に辛くも逃亡したものの、誰一人として彼を助けようとはせず、時期は不明だが餓死したという。幼名は文献によって違い、『保暦間記』では勝長寿丸、『梅松論』では勝寿丸、『太平記』では亀寿、『北条系図』では全嘉丸あるいは亀寿丸とされている。通称は相模次郎である。
2023年12月05日
閲覧総数 347
-
21

「大谷吉継の群像」賎ケ岳の戦いに従軍。 川村一彦
4「賤が岳の戦いに従軍」 秀吉時代の活躍 秀吉と織田家重臣である柴田勝家の対立は決定的となり、吉継はこの時期の秀吉の美濃国侵攻にも馬廻衆として従軍した。そして天正11年(1583年)に賤ヶ岳の戦いが起こった。この時、吉継は長浜城主・柴田勝豊を調略して内応させた。。 賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい)は、天正11年(1583年)4月、近江国伊香郡(現:滋賀県長浜市)の賤ヶ岳付近で起きた羽柴秀吉と柴田勝家の戦いである。 この戦いは織田勢力を二分する激しいものとなり、これに勝利した秀吉は亡き織田信長が築き上げた権力と体制を継承し天下人への第一歩がひらかれた。 詳細は「清洲会議」を参照 天正10年6月2日(1582年6月21日)、織田信長とその嫡男で当主の織田信忠が重臣明智光秀の謀反によって横死する本能寺の変が起こり、その後まもない山崎の戦いで光秀を討った羽柴秀吉が信長旧臣中で大きな力を持つにいたった。 6月27日(7月16日)、当主を失った織田氏の後継者を決定する会議が清洲城で開かれ、信長の三男・織田信孝を推す柴田勝家と嫡男信忠の子である三法師(のちの織田秀信)を推す羽柴秀吉との間で激しい対立が生じた。結果的には同席した丹羽長秀・池田恒興らが三法師擁立に賛成したため勝家も譲らざるをえず、この後継者問題は形の上ではひとまず決着をみた。 両陣営の動き この後双方とも周囲の勢力を自らの協力体制に持ち込もうと盛んに調略を行うが、北陸の柴田側の後方にある上杉景勝や、信孝の地盤である美濃の有力部将・稲葉一鉄が、羽柴側になびくなど秀吉に有利な状況が出来つつあった。 一方で勝家の側も土佐の長宗我部元親や紀伊の雑賀衆を取り込み、特に雑賀衆は秀吉の出陣中に和泉岸和田城などに攻撃を仕掛けるなど、後方を脅かしている。 勝家による和平交渉 10月16日、勝家は堀秀政に覚書を送り、秀吉の清洲会議の誓約違反、及び不当な領地再分配、宝寺城の築城を非難している(『南行雑録』)。 11月、勝家は前田利家・金森長近・不破勝光を使者として秀吉のもとに派遣し、秀吉との和睦を交渉させた。 これは勝家が北陸に領地を持ち、冬には雪で行動が制限されることを理由とした見せかけの交渉であった。秀吉はこのことを見抜き、逆にこの際に三将を調略しており、さらには高山右近、中川清秀、筒井順慶、三好康長らに人質を入れさせ、畿内の城を固めている。 秀吉による長浜城、岐阜城攻め[編集] 12月2日(12月26日)、秀吉は毛利氏対策として山陰は宮部継潤、山陽は蜂須賀正勝を置いた上で、和睦を反故にして大軍を率いて近江に出兵、長浜城を攻撃した。北陸は既に雪深かったために勝家は援軍が出せず、勝家の養子でもある城将柴田勝豊は、わずかな日数で秀吉に降伏した。 さらに秀吉の軍は美濃に進駐、稲葉一鉄などから人質を収めるとともに、12月20日(1583年1月13日)には岐阜城にあった織田信孝を降伏させた。 滝川一益の挙兵 翌天正11年(1583年)正月、伊勢の滝川一益が勝家への旗幟を明確にして挙兵し、関盛信・一政父子が不在の隙に亀山城、峯城、関城、国府城、鹿伏兎城を調略、亀山城に滝川益氏、峯城に滝川益重、関城に滝川忠征を置き、自身は長島城で秀吉を迎え撃った。 秀吉は諸勢力の調略や牽制もあり、一時京都に兵を退いていたが、翌月には大軍を率いこれらへの攻撃を再開、国府城を2月20日(4月11日)に落とし、2月中旬には一益の本拠である長島城を攻撃したが、滝川勢の抵抗は頑強であり、亀山城は3月3日(4月24日)、峯城は4月12日(6月4日)まで持ち堪え、城兵は長島城に合流している。 この時、亀山城、峯城の守将・益氏、益重は武勇を評され、益重は後に秀吉に仕えた。
2024年02月23日
閲覧総数 34
-
22

『歴史の回想・平治の乱」日宋貿易
日宋貿易(にっそうぼうえき)は、日本と中国の宋朝の間で行われた貿易である。⚽ 10世紀から13世紀にかけて行われ、日本の時代区分では平安時代の中期から鎌倉時代の中期にあたる。⚽ 中国の唐朝に対して日本が派遣した遣唐使が停止(894年)されて以来の日中交渉である。⚽ 貿易は朝鮮半島の高麗を含めた三国間で行われ、日本では越前国敦賀や、鎌倉時代には多くの宋人が住み国際都市となった博多が拠点となった。⚽ 歴史⚽ 平安時代⚽ 960年(日本の天徳4年)に成立した北宋は、貿易を振興する目的で各地に市舶司を設置し、日本、高麗との貿易や南海貿易を行った。日本では遣唐使停止(894年)の後大宰府の統制下で日唐貿易、鴻臚館貿易が行われた。1019年(寛仁3年)の刀伊の入寇の頃から太宰府権能の衰微が始まる。⚽ 日宋間の正式の外交貿易は行われず、一般人の渡航は表向き禁止され、宋の商人は主に博多や越前敦賀へ来航し、私貿易が行われていた。⚽ 1126年(日本の大治元年)に発生した靖康の変、それに伴う南宋の成立は、日宋貿易にも影響を与えることになった。⚽ 華中・華南の経済的発展に加えて、金の支配下に入った華北・中原から逃れてきた人々の流入に伴う南宋支配地域の急激な人口増加によって、山林の伐採に伴う森林資源の枯渇や疫病の多発などの現象が発生した。⚽ 前者は南宋における寺院造営や造船、棺桶製作のための木材を周防国などの日本産木材の大量輸入でまかなうことになり、阿育王寺舎利殿の造営には東大寺再建で知られる重源が、天童寺千仏閣再建には臨済宗を日本に伝えた栄西が日本産木材を提供している。⚽ 後者は南宋における漢方医学の発展を促して最新の医学知識や薬品が日本へと伝えられることになり、鎌倉時代後期のことになるが梶原性全が宋の医学書を元に『頓医抄』を編纂し、吉田兼好が『徒然草』(120段)の中で「唐の物は、薬の外に、なくとも事欠くまじ」と述べているのは、裏を返せば日宋貿易なくして日本の医療が成り立たなかったことを示している[1]。⚽ 越前守でもあった平忠盛は日宋貿易に着目し、後院領である肥前国神崎荘を知行して独自に交易を行い、舶来品を院に進呈して近臣として認められるようになった。平氏政権が成立すると、平氏は勢力基盤であった伊勢の産出する水銀などを輸出品に貿易を行った。⚽ 平治の乱の直前の1158年(保元3年)に大宰大弐となった平清盛は、日本で最初の人工港を博多に築き貿易を本格化させ、寺社勢力を排除して瀬戸内海航路を掌握した。⚽ また、航路の整備や入港管理を行い、宋船による厳島参詣を行う。1173年(承安3年)には摂津国福原の外港にあたる大輪田泊(現在の神戸港の一部)を拡張し、3月に正式に国交を開いて貿易振興策を行う。⚽ こうした流れの中で渡海制・年紀制などの律令制以来の国家による貿易統制も形骸化していった。一方で、宋銭の大量流入で貨幣経済が発達し物価が乱高下するようになったり、唐朝滅亡以来の異国に対する社会不安なども起こっている。⚽ 1199年(日本の建久10年)7月、高麗と日本の商人に銅銭の交易は禁止された。
2023年08月25日
閲覧総数 83
-
23

『歴史の回想・土佐勤王党」岡田以蔵が関わったとされる暗殺事件。
人物像 以蔵については同時代資料も本人の書簡なども乏しいが、その性格・事跡については土佐勤王党関係の史料によって断片的に窺うことが出来る。 以蔵の容姿に関して、土佐の牢番から「歯の反った奴(出っ歯)」と述べられている。 現存する血盟書の写しからは、以蔵を含め吉村虎太郎や池内蔵太らの名前が削られている。これは瑞山が容堂に血盟書を提出する際、脱藩者や見せるのに差し障りのある人物の名前を省いたものだと考えられる。 着牢時、以蔵が長州藩や吉村の事について牢番に大声で自慢話をしている様子が聞かれている。 投獄後の以蔵は、拷問により暗殺に関与した仲間等を次々に自白し、これが土佐勤王党崩壊の端緒となる。 以蔵の自白が引き金となり、まだ捕らえられていなかった同志が次々と捕らえられて入牢した事、吉田東洋暗殺の背後には山内家保守派層の関与が公然の秘密であった事から、お家騒動への発展を恐れて以蔵毒殺計画が仲間内で相談される。 しかし強引な毒殺は瑞山や島村寿之助らが止め、以蔵の弟で勤王党血盟者である啓吉に、以蔵の父から毒殺の許可、ないしは自害を求める手紙を寄越すよう獄外の同志に連絡を取らせる。これらの遣り取りの間に、瑞山の弟・田内衛吉は拷問に耐え切れず、兄に毒薬の手配を頼み自害、島村衛吉は拷問死した。獄中書簡に依ると、結局以蔵に毒は送られることなく結審を迎えたと考えられている。 慶応元年3月25日岡本次郎書簡武市瑞山宛では以蔵に関して「是迄の不義、血を出して改心」と伝えており、自白を反省していた様子が伺える。 『土佐偉人伝』によれば、同囚中の志士・檜垣直枝が自白した以蔵を励まし「拷問の惨烈なるは同志皆はじめから期するところなり、子その痛苦に忍ぶあたわざれば、速やかにその罪を自白して、早く死地につけ、必ず同志の累をなすなかれ」と説得に当たっており、以蔵はこれにより慚憤したとなっている。 以蔵は死刑言い渡しの際、瑞山によろしく伝えて欲しいと牢番に伝言を頼んだ。 しかし、瑞山の手紙ではその厚顔無恥ぶりを呆れられている。なお勤王党の獄で以蔵の自白により真っ先に犠牲になった者は、武市の身内であった。 『土佐偉人伝』には、「天資剛勇にして武技を好み、躯幹魁偉にして偉丈夫たり。宜振、はじめ勇にしてあと怯なり。人みなこれを惜しむ。 武市瑞山もまたその粗暴にして真勇なきをもって大事を謀らず、しかも少壮殺人を嗜みて人を斬る草の如く。 その挙、おうおう常軌を逸す(中略)末路、投獄同志みな鉄石漢にして拷問の惨苦なるも忍んで一言を発せず、しかるに宜振、独りその苦痛に忍びず罪案を白状し累を同志におよぼし遂に勤王の大獄を羅織せしは遺憾というべし」と書かれている。 『維新土佐勤王史』には「血気の勇はついに頼むに足らず、全く酒色のために堕落して、当初剣客なりし本分を忘れ、その乱行至らざる所なく、果ては無宿者鉄蔵の名を以て、京都所司代に脆くも捕縛せられぬ」とある。 以蔵が所有していたと見られるピストルが、以蔵の弟・啓吉の子孫の家に伝わっている。 高知県立坂本龍馬記念館の説明によれば、これはフランス製で、勝海舟より贈られた物だという。ちなみに「ピストル」とは公開の折に称されたものだが、厳密にはリボルバーである。なお、当該短銃は個人所有の物を借用し公開された。 以蔵の写真として出回っているものがあるが、その多くは岡田井蔵(おかだ せいぞう)のものである。実際の以蔵をモデルとした写真や肖像は伝存しない。 高知県護国神社にある、殉難した志士の為の顕彰碑・『南海忠烈碑銘』(1885年(明治18年)建立)には顕彰を拒まれ、以蔵の名前は無かったが、2019年1月20日に岡田以蔵顕彰会の尽力により刻印された。 靖国神社にも合祀されず、贈位も行われなかった。死後118年となる1983年(昭和58年)になって、高知県護国神社に合祀された。 岡田以蔵が関わったとされる暗殺事件 井上佐市郎暗殺(文久2年8月2日) 井上佐市郎は土佐藩の下横目(下級警官)で、同年4月8日の吉田東洋暗殺事件を捜査していた。 これを危険と見た勤王党では、まず井上を料亭「大与(だいよ、大與とも)」に呼び出して泥酔させ、心斎橋上にて、以蔵・久松喜代馬・岡本八之助・森田金三郎の4人で、身柄拘束のうえ手拭いで絞殺、遺体は橋上から道頓堀川へと投げ棄てた。 岩崎弥太郎は、この事件の際に井上と同行していたが難を逃れている。 以蔵らが最終的に捕縛された際、この事件についての取調べもあったといい、実行犯の1人である森田だけが黙秘を貫いたため生き残って戊辰戦争に参戦している。 森田は後にこれを五十嵐敬之に話し、五十嵐によって『井上佐市郎暗殺一件』なる記録が残された。Ø 本間精一郎暗殺(文久2年閏8月20日) 本間精一郎は越後国出身の勤皇の志士の1人であったが、特定の藩に属しない論客であったため、その態度を浮薄と見た各藩の志士から疎まれ始めていた。 そこへ青蓮院宮と山内容堂との間で、攘夷督促勅使を巡る争いが持ち上がり、前者を推進する本間と後者を推す勤王党の間で対立が起きたとも、本間が幕府と通じているのではないかと疑われたとも言われる。 『伊藤家文書』によると当日、本間は料亭から酔って退出したところを数人の男に取り囲まれて両腕を押さえつけられ、刀と脇差を取り上げられながらも激しく抵抗して格闘し数名を怯ませたものの、わずかな隙にわき腹を刺され、瀕死のところに止めをさされて斬首された(但し異説もあり、屋内にいた人物が本間と刺客が刀で打ち合う「炭をぶつけ合うような」音を聞いたという証言もある)。 本間も殺害されたあと、高瀬川へと投げ込まれた。このときの実行犯は以蔵をはじめ、平井収二郎・島村衛吉・松山深蔵・小畑孫三郎・弘瀬健太・田辺豪次郎、そして薩摩の人斬りこと田中新兵衛であった。
2023年09月12日
閲覧総数 173
-
24

「ゴローニン事件と高田屋嘉兵衛」其の後の高田屋嘉兵衛。 川村一彦
晩年文化11年(1814年)、兵庫の本店に戻る。9月に大坂町奉行所から呼び出され、宗門関係の調べを受けたほか、町奉行から日露交渉について尋ねられる。11月には大坂城代・大久保忠真に召し出されて、ゴローニン事件について質問される。文政元年(1818年)秋、養生のため淡路島に帰る。文政5年(1822年)には妻・ふさの養生の場として、大坂・野田に別荘を建てて、しばらく逗留する。文政7年(1824年)に隠居。淡路島に帰った後も、灌漑用水工事を行ったり、都志港・塩尾港の整備に寄付をするなど地元のために財を投じている。文政9年(1826年)、徳島藩主・蜂須賀治昭は嘉兵衛の功績を賞し、小高取格(300石取りの藩士並)待遇とした。翌文政10年(1827年)早春、御礼のため徳島に行き、藩主に拝謁している。同年、背中にできた腫物が悪化、4月に59歳で死去。戒名は「高譽院至徳功阿唐貫居士」。なお、大正6年(1917年)、高田屋一族の菩提寺である函館・称名寺の住職から戒名を追贈され、「高譽院殿至徳功阿唐貫大居士」となる。明治に入り北方開拓の功績を讃えられ、明治44年(1911年)に正五位を追贈、昭和13年(1938年)には開拓神社の祭神となった。その後の高田屋高田屋は弟・金兵衛が跡を継ぎ、文政4年(1821年)に蝦夷地が松前藩に返された後、松前藩の御用商人となり、文政7年には箱館に本店を移した。しかし、嘉兵衛の死から6年後の天保4年(1833年)に、幕府からロシアとの密貿易の疑いをかけられる。評定所での審問の結果、密貿易の嫌疑は晴れたものの、ゴローニン事件のときに嘉兵衛がロシア側と取り決めた「旗合わせ」(高田屋の船がロシア船と遭遇した際、高田屋の船を襲撃することを避けるため、高田屋が店印の小旗を出し、それに対しロシア船が赤旗を出し、相手を確認するもの)を隠していたことを咎められ、闕所および所払いの処分となり、高田屋は没落した。 4「事件までの経緯」東方へ領土を拡張していたロシア帝国は、18世紀に入るとオホーツクやペトロパブロフスクを拠点に、千島アイヌへのキリスト教布教や毛皮税(ヤサーク)の徴収を行い、得撫島に移民団を送るなど千島列島へ進出するようになった。ロシア帝国(ロシアていこく、 ラスィーイスカヤ・インピェーリヤ)は、1721年から1917年までに存在した帝国である。ロシアを始め、フィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、カフカーズ、中央アジア、シベリア、外満州などのユーラシア大陸の北部を広く支配していた。帝政ロシア(ていせいロシア)とも呼ばれる。通常は1721年のピョートル1世即位からロシア帝国の名称を用いることが多い。統治王家のロマノフ家にちなんでロマノフ朝とも呼ばれるがこちらはミハイル・ロマノフがロシア・ツァーリ国のツァーリに即位した1613年を成立年とする。君主がツァーリを名乗ったそれ以前のロシア・ツァーリ国においても「ロシア帝国」と翻訳されることがあるが、ロシア語では「ツァーリ」(本来は東ローマ皇帝を指したが、やがて一部の国の王、ハーンなどを指す語となった)と「インペラートル」(西欧に倣った皇帝を指す語)は異なる称号であるため、留意を要する[3]。帝政は1721年にツァーリ・ピョートル1世が皇帝(インペラートル)を宣言したことに始まり、第一次世界大戦中の1917年に起こった二月革命でのニコライ2世の退位によって終焉する。領土は、19世紀末の時点において、のちのソヴィエト連邦の領域にフィンランドとポーランドの一部を加えたものとほぼ一致する面積2000万km2超の広域に及び、1億を越える人口を支配した。首都は、1712年まで伝統的にモスクワ国家の首府であったモスクワからサンクトペテルブルクに移され、以降帝国の終末まで帝都となった。政治体制は皇帝による専制政治であったが、帝政末期には国家基本法(憲法)が公布され、国家評議会とドゥーマからなる二院制議会が設けられて立憲君主制に移行した。20世紀はじめの時点で陸軍の規模は平時110万人、戦時450万人でありヨーロッパ最大であった。海軍力は長い間、世界第3位であったが、日露戦争で大損失を出して以降は世界第6位となっている。宗教はキリスト教正教会(ロシア正教会)が国教ではあるが、領土の拡大に伴い大規模なムスリム社会を内包するようになった。そのほかフィンランドやバルト地方のルター派、旧ポーランド・リトアニアのカトリックそしてユダヤ人コミュニティも存在した。ロシア帝国の臣民は貴族、聖職者、名誉市民、商人・町人・職人、カザークそして農民といった身分に分けられていた。貴族領地の農民は人格的な隷属を強いられる農奴であり、ロシアの農奴制は1861年まで維持された。シベリアの先住民や中央アジアのムスリムそしてユダヤ人は異族人に区分されていた。ロシア帝国ではロシア暦(ユリウス暦)が使用されており、文中の日付はこれに従う。ロシア暦をグレゴリオ暦(新暦)に変換するには17世紀は10日、18世紀は11日、19世紀は12日そして20世紀では13日を加えるとよい。国土20世紀はじめ時点のロシア帝国の規模は世界の陸地の1/6にあたる約 22,800,000㎞2 (8,800,000 SQ mi)に及び、イギリス帝国の規模に匹敵した。しかしながら、この当時は人口の大半がヨーロッパロシアに居住していた。100以上の異なる民族がおり、ロシア人は人口の約43%を占めている。
2024年02月15日
閲覧総数 44
-
25
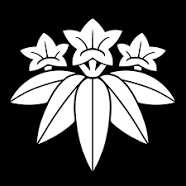
「北畠氏一族の群像」戦国・安土桃山時代の北畠氏。 川村一彦
儒学に通じた文化人である一方、仏教に深く帰依した信心厚い人物でもあったといわれている。 戦国・安土桃山時代戦国時代に入ると、英主・北畠晴具が現れ、北畠家は南伊勢、志摩国、伊賀国の南部、大和国の南部、紀伊国の東部にまでに及ぶ一大勢力となった。他方、北伊勢の雄たる長野工藤氏とは激しく争ったものの、決着をつけることができなかった。晴具の子・具教の代には、長野工藤氏を従わせて北伊勢に進出し、志摩への支配も強めるなど、戦国大名として最盛期を迎えた。また、永禄5年(1562)5月に長野稙藤と長野藤定が死去したため、長野氏の支配権を完全に握った。 11、「北畠 晴具」(きたばたけ はるとも)は、戦国時代の大名・公家。伊勢国国司北畠家の第7代当主。子に具教、木造具政、具親ら。文亀3年(1503)、第6代当主・北畠材親(具方)の嫡男として生まれる[1][2]。永正7年(1510)、叙爵、侍従となる。この頃は親平を名乗っていた。永正8年(1511)、父から家督を譲られて相続し、伊勢国司家第7代当主となる。永正13年(1517)、従五位上となる。この頃に具国に改名した。永正15年(1518)、左近衛中将となる。また、同年に第12代将軍・足利義晴から「晴」の字を拝領して晴具と名乗った。大永5年(1525)、正五位下となり、同8年には従四位下、参議となった。享禄2年(1529)、高国・足利義晴が三好元長・柳本賢治に敗北し、近江朽木谷へ逃亡した。高国は娘婿の晴具に援軍を要請するため伊勢へ下向した。その後、享禄4年(1531)に晴具の支援を受けた高国は再起を図り摂津まで侵攻し、細川晴元や三好元長と摂津天王寺で戦うも敗北し、大物浦で討死した(大物崩れ)。天文年間、晴具は志摩の鳥羽城を攻撃し、支配下に収める。そして小浜氏ら国人を掌握して志摩国をほぼ制圧した。その後、大和にも進出して吉野郡と宇陀郡を制圧し、支配下に収めている。しかしこの大和侵攻により、大和諸国人との対立が発生し、筒井氏・越智氏・十市氏・久世氏らと合戦に及んでいる。紀伊へも進出し、熊野地方から尾鷲・新宮方面までを領有化、十津川まで支配領域を広げた。晴具は伊勢国内でも北伊勢の雄たる長野氏と対立して争った。天文12年(1543)には長野藤定が北畠の領する南伊勢に侵攻すると、晴具は垂水鷺山に出陣、合戦となった(垂水鷺山の戦い)。北畠軍は家城之清、豊田五郎左衛門、垂水釈迦坊を、長野軍は細野氏・分部氏をそれぞれ主力にし、激しい戦闘の末、決着はつかずに双方退却することとなった。天文16年(1545)から天文18年(1547)にかけて、晴具は長野氏に反撃を仕掛け、葉野の戦いで長野方の分部与三衛門を討ち取るなど一志郡内で攻防を続けたが、長野氏を降すことはできなかった。長野氏が降伏するのは次の具教の代である。また、伊勢山田三方の神人層の対立にも介入し、天文3年(1534)1月に山田三方が自身の命令に従わないことを理由に出兵、宇治・山田の両門前町の軍勢を宮川の戦いで討ち、両門前町を支配下におさめている。天文5年(1536)、出家して「天祐」と号した。天文22年(1553)、隠居して家督を嫡男の具教に譲った。永禄6年(1563)、多気御所で死去、享年61歳。人物晴具は文武両道の名将で、弓馬の達人で和歌・連歌・茶道をよくし、能書家でもあった。特に和歌は、大永元年(1521)には細川高国らとともに歌合せを本拠地の多気御所で実施し、大永2年(1522)には連歌師の宗長を多気御所に招き、逗留させて連歌の興行も行っている。また、高国が多気御所に造った庭園は、現在北畠氏館跡庭園と呼ばれ、国指定の名勝となっている。 12、「北畠 具教」(きたばたけ とものり)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての大名・公家。伊勢国司北畠家の第8代当主。出生享禄元年(1528)、第7代当主で参議・北畠晴具の長男として生まれる。天文6年(1537)、従五位下侍従に叙任[。以後も天文21年(1552)従四位下参議に叙任されて公卿に列し、天文23年(1554)に従三位権中納言に叙任されているなど、朝廷から官位を授かって順風満帆な青年期を過ごした。この間の天文22年(1553)に父・晴具の隠居により家督を相続して第8代当主となる。弘治元年(1555)、父・晴具の命により伊勢国安濃郡を支配していた長野工藤氏と戦い、永禄元年(1558)に次男・具藤を長野工藤氏の養嗣子とする有利な和睦を結ぶことで北伊勢に勢力を拡大し、永禄5年(1562)5月5日に長野稙藤と長野藤定が同日に死去したため長野氏の支配権を完全に握った(具教による暗殺説もある)。
2024年04月26日
閲覧総数 78
-
26

「赤松政則の群像」長禄の変と赤松家の再興。 川村一彦
5「長禄の変と赤松家の再興」Ø 嘉吉の乱以後、旧赤松領は山名氏の領国となり赤松家の旧臣は排除され、または浪人となり討伐の対象とされる事もあった。このため、赤松家旧臣の多くは主家再興を悲願としていた。 赤松家の旧臣・上月満吉は康正2年(1456年)に吉野に入り、神璽に関する情報収集に務めた。これは後南朝に奪われた神璽奪還のためであり、これは「御屋形様(政則)」と「勅諚」「上意」との約束だったという。Ø 調査には1年の月日がかかり、長禄元年(1457年)12月に赤松家旧臣らは奥吉野に侵入し、南朝後胤とされる一の宮、二の宮を殺害した。二の宮を殺害したのが満吉である。Ø この時に神璽も奪還した(一時的に吉野の郷民に奪われたが、再度奪回している)。この結果、長禄2年(1458年)8月に神璽は京都に戻り、その功績により赤松家の再興が幕府から認められる事になった(長禄の変)。 長禄の変(ちょうろくのへん)は、室町時代の長禄元年12月2日(1457年12月18日)に赤松氏の遺臣らが後南朝の行宮を襲い、南朝の皇胤である自天王と忠義王(後南朝の征夷大将軍)の兄弟を討って、神璽を持ち去った事件。 嘉吉3年(1443年)9月の禁闕の変で、三種の神器の1つ「神璽」は後南朝に持ち去られたままだった。 嘉吉の乱で取り潰された守護大名赤松氏の再興を目指す赤松氏の遺臣達(上月満吉・石見太郎・丹生谷帯刀左衛門と四郎左衛門の兄弟など)はこの点に着目した。旧赤松領は山名領となり、赤松氏の旧臣らは追い出され、落ちぶれて浪人となっていた彼らにとって赤松氏再興は悲願であった。 また、朝廷や幕府とは神璽を後南朝から取り戻すことを条件として、成功の暁には赤松氏の再興を約していた。 赤松遺臣らは後南朝に接近するために策略を練った。彼らは「自分たちは(嘉吉の乱以降)どこにも仕える場所がなく、これ以上は耐えられないので吉野の朝廷に参上し、ともに京を奪還したい」、と後南朝に申し入れた。 そして、後南朝は赤松遺臣らを受け入れ、康正2年(1456年)12月20日に遺臣ら30人は吉野に向かった。 赤松遺臣らは吉野に入ってもすぐに行動には移さなかった。彼らは神璽のありかをさぐり、その調査にはおよそ1年の歳月を要した。 調査の結果、神璽は後南朝が行宮を置いていた奥吉野の北山(あるいは三之公)にあることが分かった。 長禄元年(1457年)12月2日の子の刻(午前0時頃)、赤松遺臣らは二手に分かれて、南朝の皇胤である自天王(北山宮、一の宮とも)と忠義王(河野宮、二の宮とも)の兄弟を襲撃した。 北山にいた自天王は丹生谷兄弟の兄によって討たれ、彼らはその神璽を強奪した。河野郷にいた忠義王も同じころ、上月満吉によって討たれている。 後南朝に仕えていた野長瀬盛高・盛実兄弟らは尊雅王(南天皇)を擁して奥吉野の山中を逃走したが、やがて十津川にて討たれた。 赤松遺臣らは神璽をいったん持ち去ることに成功するが、後南朝を支持する吉野の民にこの襲撃を察知されてしまう。 吉野の民の反撃によって、神璽を持っていた丹生谷兄弟は伯母谷で殺害され、神璽は自天王の首とともに奪還された。このため、赤松遺臣らは吉野から一旦引き上げた。 翌年の長禄2年(1458年)3月末、赤松遺臣らは大和の豪族小川弘光、さらに越智家栄の協力を得て、吉野の民によって戻されていた神璽がある自天王の母の屋敷を襲い、再度神璽を持ち去った。 この作戦もまた周到に計画されたものであった。その後、同年8月30日に神璽は京へと戻り、朝廷へ返還された。 室町幕府は後南朝によって約15年もの間京都から持ち去られていた神璽の奪還成功の功績を認め、赤松氏の再興を許し、赤松政則に家督相続をさせた。 また、その勲功として加賀北半国の守護職、備前新田荘、伊勢高宮保が与えられた。 赤松氏再興と所領の付与には細川勝元が積極的に関与している事も確認されており、赤松氏を取り立てる事で山名宗全に対抗する政治的意図があったとされている。 Ø 幕府が赤松家の再興を認めた背景には、長禄の変における功績の他に山名氏に対する政治背景があったとされる。嘉吉の乱で旧赤松領を分国とした山名氏の勢力は幕府を脅かすほど強大化していたため、赤松家を再興する事で山名氏の牽制に当てる狙いがあったとされている。Ø また赤松家再興と所領の付与には細川勝元が積極的に関与している事も確認されており、赤松家を取り立てる事で山名宗全に対抗する政治的意図があったとされている。 細川 勝元(ほそかわ かつもと)は、室町時代の武将・守護大名。第16、18、21代室町幕府管領。土佐・讃岐・丹波・摂津・伊予守護。第11代細川京兆家当主。父は第14代室町幕府管領、細川持之。政元の父。応仁の乱の東軍総大将として知られている。 家督・管領相続 永享2年(1430年)、細川持之の嫡男として生まれる。幼名は聡明丸。 嘉吉2年(1442年)8月、父が死去したため、13歳で家督を継承した。この時に7代将軍足利義勝から偏諱を受けて勝元と名乗り、叔父の細川持賢に後見されて摂津・丹波・讃岐・土佐の守護となった。 文安2年(1445年)、畠山持国(徳本)に代わって16歳で管領に就任すると、以後3度に渡って通算23年間も管領職を歴任し、幕政に影響力を及ぼし続けた。勝元が管領に就任していたのは、文安2年から宝徳元年(1449年)、享徳元年(1452年)から寛正5年(1464年)、応仁2年(1468年)7月から死去する文明5年(1473年)5月までである。 勢力争い 応仁の乱で敵対関係に至ったため、細川勝元と山名持豊(宗全)は不仲であったとされているが、はじめはそうではなかった。当時、細川京兆家は一族全てで9ヶ国の守護であったのに対し、山名氏は赤松氏を嘉吉の乱で滅ぼした功績から旧赤松領を併せて8ヶ国の守護になっていた。 このため、勝元は持豊と争うことは得策ではないと考え、文安4年(1447年)に持豊の養女を正室に迎えることで協調することにしていたのである。また、政敵畠山持国に対抗する意味からも持豊と手を組む必要があった。 持国が6代将軍足利義教に家督を追われた元当主の復帰を図ると勝元はそれに対抗して義教に取り立てられた大名・国人を支持、持国は信濃守護に小笠原持長を任命、元加賀守護富樫教家・成春父子を支持、大和では元興福寺別当経覚と越智家栄・古市胤仙・小泉重弘・豊田頼英を支援した。 勝元はこれに対して小笠原宗康・光康兄弟や富樫泰高を支持、大和で経覚派と敵対している成身院光宣・筒井順永を支援、信濃・加賀・大和で持国と勝元の代理戦争が頻発した。文安2年(1445年)に近江で反乱を起こした六角時綱を時綱の弟久頼と京極持清に鎮圧させた。 宝徳2年(1450年)に主君である和泉守護細川常有(細川元有の父)と対立して持国と古市胤仙を頼った守護代宇高有光が殺害される事件が起こったが、その件にも勝元の関与の可能性が指摘されている。 宝徳3年(1451年)、兵庫津に入港していた琉球商船のもとへ勝元が人を送り、商物を選って取得しながら代金の支払いをせず、琉球商人は幕府に訴え、足利義政は三人の奉行を送って究明させたが、勝元は押し取った物を返さないという事件を起こした(『康富記』)。享徳2年(1453年)に伊予守護職を河野教通から河野通春に改替するが、実は勝元が教通を支持する義政に内緒で御教書・奉書などを作成したもので、5月にその事実が発覚して義政に責められた勝元が引責辞任を表明しているが義政の説得で最終的に留任した(『康富記』)。2年後の享徳4年(1455年)に自分が伊予守護となった。 その後伊予守護職は通春に戻されたが、通春を傀儡として伊予支配を目指した勝元の策は通春に拒絶されるところとなり、分家の阿波守護細川成之と通春が戦ったため、勝元と通春も対立していった[6]。 享徳3年(1454年)、畠山氏で家督をめぐる内紛が起こった時には、持国を失脚させるため、舅にあたる持豊と共に持国の甥弥三郎を支援して持国の推す実子義就を追放に追い込んだ。 しかし8代将軍足利義政が嘉吉の乱で没落した赤松氏の再興を支援しようとすると、赤松氏の旧領を守護国に持つ持豊は赤松氏の再興に強硬に反対した。 このため、持豊は義政から追討を受けそうになるが、この時は勝元が弁護したため、持豊は追討を免れた(この前後に持豊は出家し、宗全と名乗った)。宗全が赤松則尚討伐のため但馬へ下向した直後に義就が上洛、弥三郎を追放し、翌年の持国の死で義政から当主に認められたため、両者に対抗して畠山氏の引き抜きを図った義政の謀略とされる。 義政の側近となった義就だったが、無断で大和へ軍事介入したことから義政の信頼を失い、一方の勝元も弥三郎と反義就派の大和国人への支援を続け、長禄3年(1459年)に弥三郎と成身院光宣・筒井順永・箸尾宗信の赦免を取り付けた。 弥三郎は同年に没したが、弟の政長を支援して翌4年(1460年)に義就から政長に家督が交替、義就が嶽山城の戦いを経て吉野へ没落した後の寛正5年(1464年)に管領職を政長に交替した。 しかし山名氏の勢力が勝元の想像以上に急速に拡大したため、勝元は宗全の勢力拡大を危険視するようになり、斯波氏の家督争い(武衛騒動)でも姻戚関係から斯波義廉を支持する宗全に対し、勝元は義廉と対立する斯波義敏を支持した。 また、宗全がかねてから反対していた赤松氏の再興問題に関しても勝元は積極的に支援し、ついには赤松政則(赤松満祐の弟義雅の孫)を加賀半国の守護と成し、赤松家を再興させたのである。 さらに勝元は勘合貿易の問題から大内教弘・政弘父子、河野通春らと敵対していたが、宗全はこれを支援するなどしたことから、細川と山名の対立構造が生じ始めた。このため、勝元は庶流の上野家出身の細川賢氏を伊予守護職に任じて通春を討伐させようとした。 また、はじめ継嗣がいなかった勝元は、宗全の末子豊久を養子にしていたが、文正元年(1466年)に実子政元の誕生後、豊久を廃嫡して仏門に入れるなど関係の悪化は明白となった(山名の血を引く政元を遠ざけ、分家の野州家から勝之を猶子に迎えたとも)。 寛正3年(1462年)に宗全の次男是豊を備後・安芸守護に任命、義就討伐に参戦させ、寛正5年に山城守護に任命したことも宗全への対抗とされる。 文正元年、義政と正室の日野富子に息子の義尚が誕生して足利将軍家でも将軍後継者をめぐって争いが始まる。 この時、義政の側近伊勢貞親と季瓊真蘂は義政が当初後継者に指名していた弟の足利義視の廃嫡と義尚の将軍後継を義政に提言した。 しかし義視を支持していた勝元はこれに反対、宗全も貞親が幕府内において権勢を強めていたことを苦々しく思っていたことから、この時は勝元に賛同し共に義政に対して貞親と真蘂の追放を訴え、これを強硬に実現させた(文正の政変)。斯波義敏・赤松政則も失脚したが、後に復権している。 これにより将軍家内部で実力者がいなくなると、宗全は12月、追放されていた畠山義就を上洛させ、義政に仲介して赦免の許しを出させた。 さらに宗全は応仁元年(1467年)1月、義政に強請して勝元が支援する畠山政長の管領職を取り上げて出仕停止処分に処し、代わりに宗全が支援する斯波義廉を管領に任命させたのである。ここに至って、勝元と宗全の武力衝突は避けられないものとなった。 応仁の乱 応仁の乱における最初の衝突は、畠山義就と畠山政長が争い、上御霊神社で衝突したことから始まった(御霊合戦)。 これに対して宗全は後花園上皇・後土御門天皇を確保して義就を支援したのに対し、勝元は義政の命令で畠山家の争いに関与することを禁じられていたため、御霊合戦では静観していた。このため、政長は敗れた。 しかし5月25日、天皇を擁した宗全に対して、勝元は幕府を占領して将軍を擁立し、5月26日には山名方に戦いを挑んだ(上京の戦い)。 勝元は東軍、宗全は西軍と区別され、勝元は将軍・義政から宗全追討令を受領したものの、戦況は互角であった。また、赤松政則を支援して山名領へ侵攻させたりした。そして一時は宗全に奪われていた上皇・天皇を確保するなど、次第に戦況は東軍有利に進むが、決定打は出せずにいた[10]。 応仁2年(1468年)閏10月、義政が伊勢貞親を復職させると、勝元は義尚を、宗全が義視を支持する立場に変わるなど戦況も変わり、段々京都の戦闘が行われなくなる一方で地方に戦乱が波及、両軍はそれぞれの有力武将の寝返り工作へと戦略を変化させ、義視が西軍の総大将に祭り上げられ幕府がもう1つ出来上がるまでになった。このような中で文明3年(1471年)に西軍の部将朝倉孝景を越前守護に任じて寝返らせ、翌文明4年(1472年)に宗全に和平交渉を試みるが、決裂する。 文明5年(1473年)3月に宿敵である宗全が死去して優位に立ったのも束の間、自身も後を追うように5月11日に死去した。享年44。死因は病死と言われているが、一説では山名派による暗殺説もある。死後、政元が細川政国の後見の下で家督を継承、文明6年(1474年)4月3日に宗全の孫・山名政豊と和睦を結んだ。 赤松政則には幕府から勲功として加賀北半国の守護職、備前新田荘、伊勢高宮保が与えられた。代わりに北半国の守護だった富樫成春は追放されている。
2024年11月08日
閲覧総数 45
-
27

『江戸泰平の群像』59・脇坂 安元
『江戸泰平の群像』59・脇坂 安元(わきざか やすもと)(1584~1654)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将・大名・歌人。伊予国大洲藩2代藩主、のち信濃国飯田藩初代藩主。播磨国龍野藩脇坂家2代。当時の将軍徳川家光の信任が厚い下総国佐倉藩主・堀田正盛の次男・安政を養子とすることを願い出て許されたことにより、外様の小藩であった脇坂家は譜代大名となることができた。なお、安元は2代・安政より以前に、実弟・安経、次いで堀田正盛の弟・安利を養子としていたが、いずれも早世した。天正12年(1584年)3月4日、脇坂安治の次男として山城国で生まれる。兄・安忠が若くして病没したために嫡子となり、慶長3年(1598年)に大坂にて徳川家康に謁見した。慶長5年(1600年)に豊臣姓を授けられ、従五位下、淡路守に叙任されている。家康による会津征伐が起こると、父・安治の命で家康の元に参陣しようとしたが、石田三成らに阻まれ断念した。三成らが挙兵すると、大坂に滞在していた脇坂親子は、止むを得ず西軍に加勢した。しかし、小早川秀秋の裏切りを機に東軍に寝返り、大谷吉継隊を壊滅させ、石田三成の居城佐和山城攻めに加わるなど東軍の勝利に貢献した。慶長11年(1606年)には、江戸城の普請を行っている。大坂の陣では先鋒として活躍する。大坂冬の陣が勃発すると、藤堂高虎指揮下で生玉辺りを攻め、大坂夏の陣においては土井利勝と共に天王寺辺りを攻めるなどして活躍した。同年、父の隠居に伴い大洲5万3,500石を襲封した。元和3年(1617年)、伊予大洲から信濃国飯田藩5万5000石(上総国一宮5000石を含む)に加増移封された。2代・安政と共に55年間にわたって飯田の城下町を整備し、飯田城の掘割を完成させ、飯田十八町を完成させた。街道の流通と伝馬を確立し、文化産業振興にも力を注ぐなど、飯田の発展に尽くした。元和9年(1623年)の秀忠の上洛や寛永3年(1626年)9月の秀忠、家光の上洛、寛永11年(1634年)7月11日の家光の上洛など将軍家の上洛に度々従っている。また、勅使馳走職として勅使の日光参詣に従ったり、朝鮮通信使を江戸接待役として江戸本誓寺にて接待するなど接待役としても活躍した。寛永9年(1632年)12月に改易された徳川忠長の居城・駿府城や正保元年(1644年)4月1日から一年間、当時天領であった下館城の守衛を務めている。下館城預かり時代の一年間の記録が「下館日記」として残されている。承応2年(1653年)12月3日、信濃飯田にて死去。享年70。当時安元は武家第一の歌人ともされ、八雲軒と号し、徳川秀忠の談伴衆でもあった教養人で、和漢書籍数千巻を蔵していた。「下館日記」「在昔抄」など著作も多い。林羅山には儒学を学び、逆に安元が羅山に歌道を教えるという師弟関係でもあった。また、狩野派の絵師狩野元俊とも親しく、安元が下館城在番中に江戸から元俊が訪ねてくるなど親密な仲だった。この下館城在番中に土佐派の絵師土佐一得に関する貴重な記録が残っている。この一得は容貌や所作が少々特殊であったがしかし安元は、絵は心で描き、一芸に秀でることは素晴らしいことだとして、一得を称賛している。一得は半月ほどの間に安元の求めに応じて絵を描き、安元は多額の謝礼を渡している。安元の教養を知らしめる逸話として、以下の話が有名である。 家光の治世「寛永諸家系図伝」が編纂されるにあたり、戦国時代に成り上がった大名諸家が源平藤橘などと名門の出であると取り繕った系図を競うように作る中で、安元は「祖先は藤原氏であるらしい」ということだけしかわからなかったため、祖父脇坂安明からの短い系図のみを作り、冒頭に「北南 それとも知らず この糸の ゆかりばかりの 末の藤原」(北家・南家ひいては京家、式家いずれかは判りませんが、父祖よりたまたま藤原氏の末裔を名乗っております=脇坂家は大した出自ではありません)という和歌をしたためて提出したと伝わる。
2023年07月16日
閲覧総数 129
-
28

『歴史の回想・保元の乱」保元の乱の罪人としての頼長。
保元の乱が終結してしばらくの間は、頼長は罪人として扱われた。頼長を罪人とする朝廷の認識は、頼長の子の師長が帰京を許され後白河院の側近になっても変わることはなかった。u しかし21年を経た安元3年(1177年)、延暦寺の強訴、安元の大火、鹿ケ谷の陰謀といった大事件が都で連発するに及んで、朝廷は保元の乱の怨霊による祟りと恐怖するようになる。u 同年8月3日、怨霊鎮魂のため、崇徳上皇の当初の追号「讃岐院」を「崇徳院」に改め、頼長には正一位・太政大臣が追贈された(『百錬抄』)。u 人物u 少年の頃は忠実の命に従わず馬にまたがって山野を駆け巡ったが、落馬して一命を失いかねないほどの目に遭い、心を入れ替えて学問に励むようになったという(『台記』康治元年12月30日条)。膨大な和漢の書を読んだ。甥にあたる慈円は『愚管抄』で「日本一の大学生(だいがくしょう)、和漢の才(ざえ)に富む」とその学識の高さを賞賛している。康治元年(1142年)10月の大嘗祭のときは、御禊の調査を徹夜で行い、終了後は10日間かけて膨大な式典の記録を書き残しており、事務的な能力にも優れていた。u 儒学を好み、誰しもが認める博識だったが、意外にも文学を不得手としており、「和歌の道に堪えず」と公言して漢詩も得意ではなかったという。u 頼長の苛烈で他人に厳しい性格は、「腹黒く、よろずにきわどき人」とも評され、「悪左府」の異名で有名だが、この「悪」も現代でいう「悪い」という意味ではなく、むしろ性質・能力・行動などが型破りであることを畏怖した表現である。u ただし私的報復の記録も多く、太政官の官人を殺害した犯人が恩赦で釈放されたことを怒り、秦公春に命じてこれを暗殺させ「天に代わって之を誅するなり」と自らの日記に明記することもあるほどだった(『台記』久安元年12月17日条)。u 私生活では男色を好んだことがその日記『台記』に記された数多くの出来事から窺える。u 東野治之や五味文彦の研究でその詳細が明らかにされ、男色相手としては随身の秦公春・秦兼任のほか、公家では藤原忠雅・藤原為通・藤原公能・藤原隆季・藤原家明・藤原成親・源成雅の名が特定されている。u 五味はこのうち4名までが院近臣として権勢を誇った藤原家成の親族であることを指摘している。u その『台記』に、少年の頃の飼い猫が病気になった際、千手像を描いて祈念して治してやったり、その猫が十歳まで長生きして死んだので、衣に包み櫃に入れて葬ってやった旨の記述がある。
2023年08月29日
閲覧総数 53
-
29

「歴史の回想・越後騒動」堀田正俊暗殺説。 川村一彦
堀田 正俊(ほった まさとし)は、江戸時代前期から中期の大名。江戸幕府の老中・大老。上野安中藩主。後に下総古河藩の初代藩主。正俊系堀田家初代。 寛永11年(1634年)11月12日、第3代将軍・徳川家光政権下の老中・堀田正盛の三男として生まれる。 寛永12年(1635年)に義理の曾祖母に当たる春日局の養子となり、その縁から寛永18年(1641年)、家光の嫡男・竹千代(徳川家綱)の小姓に任じられて頭角を現した。 寛永20年(1643年)、家光の上意で春日局の孫に当たる稲葉正則の娘と婚約、春日局の遺領3000石を与えられている。 慶安4年(1651年)、家光の死去に際して父・正盛が殉死すると、遺領のうち下野新田1万石を分与され、守谷城1万3000石の大名となる。同時に従五位下・備中守に叙位・任官する。 その後も4代将軍・家綱の時代に順調に昇進し、明暦2年(1656年)に稲葉正則の娘と結婚、正則の後見を受けて万治3年(1660年)には奏者番となり、上野安中藩2万石を与えられた。 同年に長兄の堀田正信が改易されたが、お咎めは無かった。寛文10年(1670年)に若年寄となり、延宝7年(1679年)に老中に就任し、2万石の加増を受けた。 延宝8年(1680年)、家綱の死去にあたり、家綱政権時代に権勢をもった大老・酒井忠清と対立して家綱の異母弟である綱吉を推したという。 綱吉が5代将軍に就任すると大手門前の忠清邸を与えられ、天和元年(1681年)12月11日、忠清に代わって大老に任ぜられる。就任後は牧野成貞と共に「天和の治」と呼ばれる政治を執り行ない、特に財政面において大きな成果を上げた。 しかし貞享元年(1684年)8月28日、従叔父で若年寄の美濃青野藩主・稲葉正休に江戸城内で刺殺された。享年51。 幕府の記録によれば発狂のためとされているが、事件は様々な憶測を呼び、大坂の淀川の治水事業に関する意見対立や、正休もその場で殺害されていることから、将軍綱吉の関与も囁かれた。 家督は長男の正仲への相続が許されるが、屋敷地や所領は移転されている。 暗殺陰謀説 正俊が暗殺される直前に綱吉は生類憐れみの令を布くことを表明しており、正俊はこれに反対していた。また、正俊には綱吉を将軍に就任させた功績があり、大きな発言力を持っていたと推測される。そのため両者の間に溝が生まれたことから、「綱吉による陰謀説」がある。 またこの事件以降、綱吉は奥御殿で政務を執るようになり、老中との距離が生じた。そのため、両者を連絡する柳沢吉保・牧野成貞ら側用人が力を持つこととなった。
2023年12月30日
閲覧総数 37
-
30

「畠山氏一族の群像」奥州畠山氏。 川村一彦
重忠旧領と畠山の名跡は、重忠未亡人の北条時政の娘と、足利義兼の庶長子足利義純が婚姻して継承された。なお、義純が婚姻したのは重忠と北条時政の娘との間に生まれた女性(つまり、重保の同母姉妹)との異説もある。子に時麿(小太郎重行)があったと伝え、目黒氏を称したという。ただし目黒氏の正確な出自は不詳で、重保の子孫ではないとする説もある(『目黒区史』)。 また父と同じ名の重忠と言う子がいたとも言われている(浄法寺氏の祖)重保の孫である重長は同族の武蔵江戸氏の養子となり、七代目当主となった。 4、「奥州畠山家」●奥州畠山家奥州二本松城によったかつての奥州四管領の一雄・畠山家の後裔であり、二本松畠山氏、二本松氏とも呼ばれる。源姓畠山氏の祖である足利義純の嫡流は、本来この二本松の奥州畠山家であったが、観応の擾乱において畠山高国・国氏は足利直義方の吉良貞家に敗れ自害し、国氏の子二本松国詮は二本松に移ったが、戦国時代には、一国人にまで衰退した。天正13年(1585)、当時の当主・二本松義継が伊達氏との抗争の中で討死し、まもなく国人領主としての二本松氏も滅亡する。彼の次男である二本松義孝は蘆名氏や佐竹氏などに仕えた後、徳川氏譜代大名である水野氏に仕えた。水野忠邦の転封運動に反対して諌死(かんし)した家老・二本松義廉はその子孫である。歴代当主(源姓畠山本宗家:奥州畠山家)*「二本松氏」(にほんまつし)は、陸奥国安達郡二本松城に拠った戦国大名。二本松畠山氏、奥州畠山氏とも。奥州管領畠山国氏の子、国詮を祖とする。本姓は清和源氏。足利氏の支流で室町幕府の三管領の一つである畠山金吾家の兄系にあたる。元々は畠山氏の嫡流筋だった貞和6年(1345)に畠山高国と吉良貞家が奥州管領に任ぜられて陸奥国に入ったが、 観応の擾乱が勃発すると、直義派の吉良貞家に尊氏派の高国・国氏父子が攻められて敗死し、 畠山一族の多くもこの時討死したが、安達郡二本松に逃げのびていた国氏の子・二本松国詮が奥州管領を自称して挽回(ばんかい)を図り、南朝方の北畠顕信と手を組んで一時国府を奪回したものの、貞家の反撃に遭って再び奪い返されてしまう。二本松氏が劣勢を挽回できない状況下で石塔氏も奥州管領を自称し、さらには中央から派遣された斯波家兼をも加えて四人の奥州管領が抗争することになった。四者の争いが斯波氏の勝利に終わると高国系畠山氏の勢力は完全に零落し、奥州においてこそ格式面での厚遇を受け、名字は畠山のままであったが、二本松城によった国詮の子・満泰は『満済准后日記』に「二本松。畠山修理と号す」と記されるなど、中央においては奥州在地の一国人として扱われるようになってしまった。寛正元年(1460)の足利義政御内書でも「二本松七郎」となっており、永正11年(1514)成立の『余目氏旧記』にも「二本松殿」と記されているのでこの頃に苗字を二本松としたようである。二本松氏は戦国時代に入っても勢力を盛り返すことができず、周囲の伊達氏や蘆名氏などの有力な国人に圧迫され、第10代当主・義国の頃には、古記録に「二本松畠山家、次第に衰微して、ようやく安達半郡、安積半郡を知行せられ、この節、会津の蘆名盛氏の武威輝かしかば、彼の風下にぞ属せられける」と記されるほどになっていた。そして天正13年(1585)10月、義国の子・義継は伊達輝宗拉致事件(粟之巣の変事)を起こして伊達政宗に殺され、天正14年(1586)7月、二本松城は無血開城する。この時、蘆名氏を頼った息子の義綱も同氏が政宗に滅ぼされた際には、蘆名義広に同行して佐竹氏の下に逃れたが、常陸国江戸崎で義広に殺害され、二本松氏は滅亡した。『続群書類従』所載の「二本松系図」によれば、義綱には遺児があった(満重)というが、その詳細は不明である。また、二本松氏は第4代満泰以来時宗に深く帰依しており、17世暉幽・20世一峰・25世仏天・28世遍円・20世体光と五人の遊行上人を輩出している。*「足利 義純・畠山 義純」(あしかが よしずみ/はたけやま よしずみ)は、鎌倉時代初期の足利一族の武将。源姓畠山氏・岩松氏の祖。義兼の庶長子であるが、遊女の子であったとも伝えられ、大伯父の新田義重に新田荘で養育されたという。畠山重忠が元久2年(1205)6月の畠山重忠の乱で北条氏の手により滅ぼされると、義純は重忠の未亡人(北条時政の娘)と婚姻し、重忠の旧領と畠山の名跡を継承した。異説として時政女を所生とする畠山重忠の娘と婚姻したとも考えられている。義純は元々従兄弟の新田義兼の娘来王姫と結婚しており、子時兼・時朝らを儲けていたが 、妻子と義絶しての継承であった。ただし、義純の生涯については不明な点も多く、来王姫も畠山重忠の乱以前に既に死去していた可能性もある。また、新田氏からも畠山氏(正確には重忠の未亡人。また、異説として時政女を所生とする畠山重忠の娘)からも義純に所領が継承された形跡はなく、岩松時兼・田中時朝・畠山泰国のいずれもが母方から直接所領を継承して各々の家の祖となったもので、義純を岩松氏や源姓畠山氏の祖とするのは正しくないとする指摘もある[2]。さらに岩松氏の所領の中に畠山重忠の旧領由来と思われる武蔵国大里郡の所領が含まれているとの指摘がある。
2024年04月15日
閲覧総数 124
-
31

「鍋島氏の群像」フェートン号事件の結末。 川村一彦
このため、世界各地にあったオランダの植民地はすべてフランス帝国の影響下に置かれることとなった。イギリスは、亡命して来たウィレム5世の依頼によりオランダの海外植民地の自国による接収を始めていたが、長崎出島のオランダ商館を管轄するオランダ東インド会社があったバタヴィア(ジャカルタ)は依然として旧オランダ(つまりフランス)支配下の植民地であった。しかし、アジアの制海権は既にイギリスが握っていたため、バタヴィアでは旧オランダ(つまりフランス)支配下の貿易商は中立国のアメリカ籍の船を雇用して長崎と貿易を続けていた。事件の経過文化5年8月15日(1808)、ベンガル総督ミントーの政策によりオランダ船拿捕を目的とするイギリス海軍のフリゲート艦フェートン(フリートウッド・ペリュー艦長)は、オランダ国旗を掲げて国籍を偽り、長崎へ入港した。これをオランダ船と誤認した出島のオランダ商館では商館員ホウゼンルマンとシキンムルの2名を小舟で派遣し、慣例に従って長崎奉行所のオランダ通詞らとともに出迎えのため船に乗り込もうとしたところ、武装ボートによって商館員2名が拉致され、船に連行された。それと同時に船はオランダ国旗を降ろしてイギリス国旗を掲げ、オランダ船を求めて武装ボートで長崎港内の捜索を行った。長崎奉行所ではフェートン号に対し、オランダ商館員を解放するよう書状で要求したが、フェートン号側からは水と食料を要求する返書があっただけだった。オランダ商館長(カピタン)ヘンドリック・ドゥーフは長崎奉行所内に避難し、商館員の生還を願い戦闘回避を勧めた。長崎奉行の松平康英は、商館員の生還を約束する一方で、湾内警備を担当する鍋島藩・福岡藩(藩主:黒田斉清)の両藩にイギリス側の襲撃に備える事、またフェートン号を抑留、又は焼き討ちする準備を命じた。ところが長崎警衛当番の鍋島藩が太平に慣れて経費削減のため守備兵を無断で減らしており、長崎には本来の駐在兵力の10分の1ほどのわずか100名程度しか在番していないことが判明する。松平康英は急遽、薩摩藩、熊本藩、久留米藩、大村藩など九州諸藩に応援の出兵を求めた。翌16日、ペリュー艦長は人質の1人ホウゼンルマン商館員を釈放して薪、水や食料(米・野菜・肉)の提供を要求し、供給がない場合は港内の和船を焼き払うと脅迫してきた。人質を取られ十分な兵力もない状況下にあって、松平康英はやむなく要求を受け入れることとしたが、要求された水は少量しか提供せず、明日以降に十分な量を提供すると偽って応援兵力が到着するまでの時間稼ぎを図ることとした。長崎奉行所では食料や飲料水を準備して舟に積み込み、オランダ商館から提供された豚と牛とともにフェートン号に送った。これを受けてペリュー艦長はシキンムル商館員も釈放し、出航の準備を始めた。17日未明、近隣の大村藩主大村純昌が藩兵を率いて長崎に到着した。松平康英は大村純昌と共にフェートン号を抑留もしくは焼き討ちするための作戦を進めていたが、その間にフェートン号は碇を上げ長崎港外に去った。結果結果だけを見れば日本側に人的・物的な被害はなく、人質にされたオランダ人も無事に解放されて事件は平穏に解決した。しかし、手持ちの兵力もなく、侵入船の要求にむざむざと応じざるを得なかった長崎奉行の松平康英は、国威を辱めたとして自ら切腹し、勝手に兵力を減らしていた鍋島藩家老等数人も責任を取って切腹した。さらに幕府は、鍋島藩が長崎警備の任を怠っていたとして、11月には藩主鍋島斉直に100日の閉門を命じた。フェートン号事件ののち、ドゥーフや長崎奉行曲淵景露らが臨検体制の改革を行い、秘密信号旗を用いるなど外国船の入国手続きが強化された。その後もイギリス船の出現が相次ぎ、幕府は1825年に異国船打払令を発令することになる。この屈辱を味わった鍋島藩は次代鍋島直正の下で近代化に尽力し、明治維新の際に大きな力を持つに至った。また、この事件以降、知識人の間で英国は侵略性を持つ危険な国「英夷」であると見なされ始め、組織的な研究対象となり、幕府は1809年に本木正栄ら6名の長崎通詞に英学修業を命じ、それに続いてオランダ語通詞全員に英語とロシア語の研修を命じた。本木らはオランダ人商人ヤン・コック・ブロンホフから英語を学び、1811年には日本初の英和辞書『諳厄利亜興学小筌』10巻が完成し、1814年には幕府の命による本格的な辞書『諳厄利亜語林大成』15巻が完成した。一方、イギリスは1811年になってインドからジャワ島に遠征軍を派遣し、バタヴィアを攻略、東インド全島を支配下に置いた。イギリス占領下のバタヴィアから長崎のオランダ商館には何の連絡もなく、商館長ドゥーフらはナポレオン帝国没落後まで長崎出島に放置された。ドゥーフたちは本国の支援もないまま、7年もの年月を日本で過ごしていくこととなる。
2024年08月13日
閲覧総数 82
-
32

「歴史の回想・紀州征伐」順慶の死後。 川村一彦
順慶の死後順慶の重臣だった島左近は順慶の死後、跡を継いだ定次と上手くいかず筒井家を離れたが、後に石田三成の家臣となり関ヶ原の戦いに参加した。天正13年(1585年)閏8月18日、筒井家は順慶亡き後秀吉に伊賀上野に20万石で転封された。徳川方の上杉討伐に動員されたが、上野城が攻められ留守番役の筒井玄播允が戦わず開城して逐電したとの報告で引き返した。そのため、城は取り返したが、関ヶ原の戦いには参戦できず、戦後の加増を受けることはなかった。その後も定次は豊臣秀頼に年賀の挨拶に参城し、家内が徳川派と豊臣派とで分裂し争い、慶長11年(1606年)12月23日、上野城が火災で罹災し、その復興問題から両派による抗争が再燃した。慶長13年(1608年)、筒井騒動で筒井家重臣の中坊秀祐が、家康に主君定次の悪政や鹿狩での倦怠などを訴え、それで改易、定次と嫡子の順定は、陸奥磐城平藩預かりでの幽閉後に慶長20年(1615年)3月5日切腹させられたことで筒井家は絶家した。畿内の要衝で豊臣家に対する抑えの伊賀上野に豊臣との間で曖昧な定次を置く危険性と、定次自体への不信があったとされる。人物順慶は茶湯、謡曲、歌道など文化面に秀でた教養人であり、自身が僧でもあった関係で、仏教への信仰も厚く大和の寺院を手厚く保護したとも言われている。ただし、天正8年には鉄砲鋳造のために釣鐘を没収したり、興福寺の寺僧の処罰を命じられたりと、信長政権下では必ずしも寺社の保護ばかりを行っているわけではない。しかしながら、当時なお多方面に敵を抱えていた織田氏がそれだけの兵力を高野山に投入することができたのかという疑問、また大軍に比してそれを指揮する武将の格が低すぎること、名を挙げられている人物には明らかに当時他方面で働いている者が含まれていることから、『高野春秋』の記す合戦規模については疑問符をつけざるを得ない。とはいえ、高野攻め自体については各種史料に残る断片的な情報から、虚構とも言いきれない。高野山側の記録よりもかなり小規模な形で戦いがあったとも考えられる。この項目では、基本的に戦いが実在したものとして扱う[33]。戦闘経過高野山側は伊都・那賀・有田郡の領内の武士を総動員し、軍師橋口隼人を中心に「高野七砦」をはじめとする多数の砦を築いた。そして西の麻生津口と北の学文路口を特に重視して、麻生津口に南蓮上院弁仙(遊佐信教の子)、学文路口に花王院快応(畠山昭高の子)を大将として配置した。また学侶方の老練の僧が交替で護摩を焚き、信長降伏の祈祷を行った。天正9年10月、織田勢は紀ノ川北岸一帯に布陣し、総大将織田信孝[35]は鉢伏山(背山)城(現かつらぎ町)に本陣を構えた。根来衆も織田方として動員された。織田勢と高野勢は紀ノ川を挟んで対峙する形になったが、なお交渉は継続しており、同年中は目立った戦いはなかった。天正10年(1582年)1月、信長は松山新介を多和(現・橋本市)に派遣する。松山は多和に築城し、2月初頭には盛んに九度山方面へ攻撃を仕掛けた。同月9日、信長は武田攻めに当たって筒井順慶以下大和衆に出陣を促した。同時に、大和衆の一部と河内衆は残留して高野山の抑えとなるよう命じた。14日、高野勢は多和城並びに筒井勢の守る大和口の砦を攻撃。同月末、織田方の岡田重孝らが学文路口の西尾山の砦を攻めたが部将2人を失って撃退される。3月3日、高野勢50余人が多和城を夜襲して損害を与えた。10日早朝、織田勢は夜襲の報復として寺尾壇の砦を攻撃、城将医王院が討死するも寄手の損害も大きく撃退された。4月初め、織田信孝は四国攻めの大将に任命されたため転任。同月、織田方の竹田藤内らが麻生津口の飯盛山城(現紀の川市)を攻撃した。高野勢は大将南蓮上院弁仙と副将橋口隼人らがこれを防ぎ、竹田ら四将を討ち取り甲首131を挙げる勝利を得た。6月2日夕刻に至って、高野山に本能寺の変の情報が届く。まもなく寄手は撤退を開始し、高野勢はこれを追撃し勝利した。高野山は危機を脱し、8月21日には恩賞が行われた。秀吉の紀州攻め根来寺は室町時代においては幕府の保護を背景に紀伊・和泉に八か所の荘園を領有し、経済力・武力の両面において強力であった。戦国時代に入ると紀北から河内・和泉南部に至る勢力圏を保持し、寺院城郭を構えてその実力は最盛期を迎えていた。天正3年(1575年)頃の寺内には少なくとも450以上の坊院があり、僧侶など5,000人以上が居住していたとみられる。また根来衆と通称される強力な僧兵武力を擁し、大量の鉄砲を装備していた。根来寺は信長に対しては一貫して協力しており友好を保っていたが、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄の戦いにおいて留守の岸和田城を襲うなどしたほか、大坂への侵攻の動きも見せていたため、秀吉に強く警戒されており、秀吉側は根来寺を攻略する機会を伺っていた。本能寺の変は雑賀衆内部の力関係も一変させた。天正10年6月3日朝に堺経由で情報がもたらされると、親織田派として幅を利かせていた鈴木孫一はその夜のうちに雑賀から逃亡し、4日早朝には反織田派が蜂起して孫一の館に放火し、さらに残る孫一の与党を攻撃した。以後雑賀は旧反織田派の土橋氏らによって主導されることとなった。土橋氏は根来寺に泉識坊を建立して一族を送り込んでいた縁もあり、根来寺との協力関係を強めた。また織田氏との戦いでは敵対した宮郷などとも関係を修復し、それまで領土の境界線などをめぐり関係の際どかった根来・雑賀の協力関係が生まれた。前哨戦天正11年(1583年)、秀吉は蜂屋頼隆を近江に転出させて中村一氏を岸和田城に入れ、紀伊に対する備えとした。一氏の直属兵力は3,000人ほどで、紀州勢と対峙するには十分でなかった。そのため和泉衆をその与力として付け、合わせて5,000人弱の兵力を編成した。これに対抗して根来・雑賀衆は中村・沢・田中・積善寺・千石堀(いずれも現貝塚市)に付城を築く。以後、岸和田勢と紀州勢との間で小競り合いが頻発するようになった。根来・雑賀衆は畠山貞政を名目上の盟主に立て、さらに紀南の湯河氏の支援も受けた。同年7月、顕如は鷺森から貝塚に移った。同年秋頃から紀州勢の動きが活発になる。10月、一氏は兵力で劣るために正面からの戦いを避け、夜襲で対抗するよう指示を出した。同12年(1584年)1月1日、年明け早々に紀州勢が朝駆けを行う。3日、今度は岸和田勢が紀州側の五か所の付城を攻め、これを守る泉南の地侍らと激戦となった。16日、紀州勢が来援し、五城の城兵と合わせて8,000人の兵力となり、岸和田を衝こうとした。岸和田勢は6,000人の軍勢で対抗し、近木川で迎撃して紀州勢を退けた。
2024年11月09日
閲覧総数 50
-
33

「戊辰戦争の群臣」 長州藩の攘夷決行
長州藩の攘夷決行 攘夷運動の中心となっていた長州藩は日本海と瀬戸内海を結ぶ海運の要衝である馬関海峡(下関海峡)に砲台を整備し、藩兵および浪士隊からなる兵1000程、帆走軍艦2隻(丙辰丸、庚申丸)、蒸気軍艦2隻(壬戌丸、癸亥丸:いずれも元イギリス製商船に砲を搭載)を配備して海峡封鎖の態勢を取った。 攘夷期日の文久3年5月10日(1863年6月25日)、長州藩の見張りが田ノ浦沖に停泊するアメリカ商船ペンブローク号(Pembroke)を発見。総奉行の毛利元周(長府藩主)は躊躇するが、久坂玄瑞ら強硬派が攻撃を主張し決行と決まった。翌日午前2時頃、海岸砲台と庚申丸、癸亥丸が砲撃を行い、攻撃を予期していなかったペンブローク号は周防灘へ逃走した。外国船を打ち払ったことで長州藩の意気は大いに上がり、朝廷からもさっそく褒勅の沙汰があった。 フランスの通報艦キャンシャン号の被害 文久3年5月23日、長府藩(長州藩の支藩)の物見が横浜から長崎へ向かうフランスの通報艦キャンシャン号(英語版)(Kien-Chang)が長府沖に停泊しているのを発見。長州藩はこれを待ち受け、キャンシャン号が海峡内に入ったところで各砲台から砲撃を加え、数発が命中して損傷を与えた。 キャンシャン号は備砲で応戦するが、事情が分からず(ペンブローク号は長崎に戻らず上海に向かったため、同船が攻撃を受けたことを、まだ知らなかった)、交渉のために書記官を乗せたボートを下ろして陸へ向かわせたが、藩兵は銃撃を加え、書記官は負傷し、水兵4人が死亡した。キャンシャン号は急ぎ海峡を通りぬけ、庚申丸、癸亥丸がこれを追うが深追いはせず、キャンシャン号は損傷しつつも翌日長崎に到着した。 文久3年5月26日、オランダ外交代表ポルスブルックを乗せたオランダ東洋艦隊所属のメデューサ号(Medusa)が長崎から横浜へ向かうべく海峡に入った。 キャンシャン号の事件は知らされていたが、オランダは他国と異なり鎖国時代から江戸幕府との長い友好関係があり、長崎奉行の許可証も受領しており、幕府の水先案内人も乗艦していたため攻撃はされまいと油断していたところ、長州藩の砲台は構わず攻撃を開始し、癸亥丸が接近して砲戦となった。 メデューサ号は1時間ほど交戦したが17発を被弾し死者4名、船体に大きな被害を受け周防灘へ逃走した。 長州藩のアメリカ、フランス艦船への砲撃は当時の国際法に違反するものである。 アメリカ・フランス軍艦による報復 アメリカ艦ワイオミング号の下関攻撃 Ø 長州奇兵隊の隊士 高杉晋作(中央)と伊藤博文(右)と三谷国松(左) ペンブローク号は長崎ではなく上海に向かったため、事件の知らせが横浜に届いたのは文久3年5月25日(1863年7月16日)であった。アメリカ公使ロバート・プルインは、横浜停泊中のワイオミング号の艦長デビッド・マクドゥーガルを列席させて幕府に抗議した。この時期のアメリカは南北戦争の最中でほとんどの軍艦は本国にあったが、南軍の通商破壊艦アラバマ号(英語版)を追跡していたワイオミング号が、居留民保護のために一時横浜に入港していたものであった。幕府は自身が処理するとしたが、マクドゥーガルは報復攻撃を促した。前任者のタウンゼント・ハリス同様に親幕府姿勢を取っていたプルインも最終的に同意し、ワイオミング号は横浜を出港した。 文久3年6月1日(1863年7月20日)、ワイオミング号は下関海峡に入った。不意を打たれた先の船と異なり、ワイオミング号は砲台の射程外を航行し、下関港内に停泊する長州藩の軍艦の庚申丸、壬戌丸、癸亥丸を発見し、壬戌丸に狙いを定めて砲撃を加えた。 壬戊丸は逃走するが遙かに性能に勝るワイオミング号はこれを追跡して撃沈する。庚申丸、癸亥丸が救援に向かうが、ワイオミング号はこれを返り討ちにし庚申丸を撃沈し、癸亥丸を大破させた。ワイオミング号は報復の戦果をあげたとして海峡を瀬戸内海へ出て横浜へ帰還した この戦闘でのアメリカ側の死者は6人、負傷者4人、長州藩は死者8人・負傷者7人であった。もともと貧弱だった長州海軍はこれで壊滅状態になり、陸上の砲台も艦砲射撃で甚大な被害を受けた。 フランス艦隊による報復攻撃 文久3年6月5日(1863年7月24日)、フランス東洋艦隊のバンジャマン・ジョレス准将率いるセミラミス号とタンクレード号(英語版)が報復攻撃のため海峡に入った。 セミラミス号は砲35門の大型艦で前田、壇ノ浦の砲台に猛砲撃を加えて沈黙させ、陸戦隊を降ろして砲台を占拠した。長州藩兵は抵抗するが敵わず、フランス兵は民家を焼き払い、砲を破壊した。長州藩は救援の部隊を送るが軍艦からの砲撃に阻まれ、その間に陸戦隊は撤収し、フランス艦隊も横浜へ帰還した。 アメリカ・フランス艦隊の攻撃によって長州藩は手痛い敗北を蒙り、欧米の軍事力の手強さを思い知らされた。 長州藩領内では一揆が発生し、一部の領民は自発的に外国軍隊に協力していた。長州藩は士分以外の農民、町人から広く募兵することを決める。これにより高杉晋作が下級武士と農民、町人からなる奇兵隊を結成した。また、膺懲隊、八幡隊、遊撃隊などの諸隊も結成された。長州藩は砲台を増強し、なおも強硬な姿勢を崩さなかった。 しかし、慶応3年(1867年)10月14日に江戸幕府代15代将軍・徳川慶喜は日本の統治権返上を明治天皇に奏上、翌15日に勅許された(大政奉還)。討幕の実行延期の沙汰書が10月21日になされ、討幕の密勅は事実上、取り消された。Ø 既に大政奉還がなされて幕府は政権を朝廷に返上したために倒幕の意味はなくなり、薩摩側も東国に於ける挙兵の中止命令を江戸の薩摩藩邸に伝えた。
2023年08月03日
閲覧総数 89
-
34

「幕藩一揆の攻防」39、皮産物の不吉と一揆打毀し多数処刑【長州藩天保一揆】
39、皮産物の不吉と一揆打毀し多数処刑【長州藩天保一揆】「長州藩天保一揆」1831年(天保2)長州藩領内のほぼ全域に起こった一揆。防長一揆ともいう。防長一揆ともいう。藩内農民の皮迷信(秋口に皮類を扱うと凶作になる)による皮騒動を発端とし、瀬戸内側や近接地域で一揆が拡大し第一期(7月下旬から8月上旬)と藩の一揆が鎮静工作の過程で、各地域での様々な矛盾に表面化し、一揆が同時多発化し第二期(8月下旬から11月上旬)と続く。第一期では藩の産物取り立て政策による。米価・諸物価格高騰で苦しく下層・貧困層の、産物会所、米穀商人、村役人への打毀しが先行し第二期も米穀不足の状況下で村役人の不正疑惑や村政運営への不満が爆発、各農民層を巻き込んだ広範囲で長期の抵抗が続いた。同藩では1830年と1837年の一揆があり、藩体制は動揺した。 ◎「長州天保大一揆」1831年(天保2)防長両国にわたり、藩府の専売制強化に反対して起こった大百姓一揆。参加者は15万~20万ともいわれる。一揆の原因は、藩府が安い値段で各地の特産物を買い上げる「御内用産物方」を設置したことによる。この制度は、藩の専売制の強化策であった。一揆の発端は、長門(ながと)国吉敷(よしき)郡小鯖(おさば)村(山口市)の皮番所で、産物方用達が禁忌を犯して犬皮を用いていることを見とがめられた事件に始まり、これを契機に、またたくまに藩内12地区に次々と広がった。一揆勢は各村の御内用方(庄屋(しょうや))宅を打毀(うちこわ)したが、その数は741軒に達した。藩府は同年末から主謀者の検挙を行い、死罪10名、遠島24名という処分をした。 ◎「長州一揆」1831年(天保2年)、小鯖[おさば]村(山口市)で中関の御用商人石見屋嘉右衛門[いわみやかえもん]が駕籠に犬の皮をしいていたのを農民が見つけたことから騒ぎとなり、一揆に発展しました。当時、稲の穂が出る頃に皮革類が田の回りを通ると風雨を招くと言われており、農民達は皮革類を持ちこませないように見はる小屋を立てて、通行人の荷物を調べていました。石見屋は、皮革類を持ち歩くことで天候をくずし、米の値段が上がるのを利用してもうけようとした、と思われたのです。一揆勢は各地で村役人や商人の家を打ちこわし、どんどんその人数を増やしていきました。この一揆は最終的には、三田尻宰判だけでなく長州藩全体を巻き込む一揆となり、十数万人が一揆に参加したと言われています。 ◎長州藩(ちょうしゅうはん)は、江戸時代に周防国と長門国を領国とした外様大名・毛利氏を藩主とする藩。家格は国主・大広間詰。藩庁は長く萩城(萩市)に置かれていたため、萩藩(はぎはん)とも呼ばれた。幕末には周防山口の山口城(山口政事堂)に移ったために、周防山口藩と呼ばれる事例もでてきた。一般には、萩藩・(周防)山口藩時代を総称して「長州藩」と呼ばれている。幕末には討幕運動の中心となり、続く明治維新では長州藩の中から政治家を多数輩出し、日本の政治を支配した藩閥政治の一方の政治勢力「長州閥」を形成した。長州藩の江戸中期・1831年(天保2),長州藩全藩を席巻した大百姓一揆。天保大一揆ともいう。長州藩は1829年(文政12)に産物会所を設けて特権的な豪農商を御用達に任命し,翌年には薬種と綿以外のいっさいの商品の他国からの仕入れを禁止して,農民の商品経済を藩の厳重な統制の下に置いた。1831年7月末,この産物政策にからんで,吉敷郡小鯖村の皮番所での御用達商人と農民の紛争が発端となり,百姓一揆が勃発した。7月に瀬戸内海沿岸地帯の三田尻,山口,小郡を中心に広がり,9月には瀬戸内海沿岸の他の地域,中部山間部,日本海沿岸地帯へと波及し,代官らの取締りも効果を示さず,一門寄組以下正規藩兵が城下入口の警固と鎮圧に出動した。江戸時代中期には、第7代藩主毛利重就が、宝暦改革と呼ばれる藩債処理や新田開発などの経済政策を行う。文政12年(1829年)には産物会所を設置し、村役人に対して特権を与えて流通統制を行う。天保3年(1831)には、大規模な長州藩天保一揆が発生。その後の天保8年(1836)4月27日には、後に「そうせい侯」と呼ばれた毛利敬親が藩主に就くと、村田清風を登用した天保の改革を行う。改革では相次ぐ外国船の来航や中国でのアヘン戦争などの情報で海防強化も行う一方、藩庁公認の密貿易で巨万の富を得た。 *毛利 重就は、長門長府藩第8代藩主、のち長州藩第7代藩主。諱ははじめ元房、のち匡敬(まさたか)、重就(しげなり)、さらに重就(しげたか)と改めた。享保10年(1725)、長州藩の支藩である長府藩主毛利匡広の十男として生まれる。幼名は岩之丞。匡広の跡を継いだ五男の師就が享保20年(1735)に死去した際、師就の実子・多賀之丞(毛利教逵)は出生が幕府に未届けで相続が認められず、匡広の七男の政苗、八男の広定はそれぞれ清末藩主、右田毛利家を継いでおり、仮養子として届けられていた岩之丞(重就)が家督を相続することになった。また、宝暦元年(1751)には本家にあたる長州藩第6藩主・毛利宗広が早逝し、世嗣がないことなどで、末期養子として家督を相続する。長州藩は、天災による米の不作、藩商品の販売不振などにより収入が減少し、財政赤字に陥っていた。重就は藩主就任と同時に坂時存、長沼正勝ら3家老を招集し、改革案の提出を要請する。宝暦3年(1753)「三老上書」が提出される。内容は、経費の削減などから新田開発、荒廃田の復旧、築港による流通整備などが掲げられていた。重就はまず検地を行い、8年後には新たに4万石分の収入を得ることに成功した。この収入を藩財政には組み込まず撫育方を設立させ、こちらの資金として充てる。撫育方はこの資金を元手に明和元年(1764)、鶴浜を開作、伊崎を埋め立て今浦港を築港、4年後には室積・中関(三田尻)の港整備を行う。港の改良により回船の寄港地として発展させると同時に、藩物品の販売、回船業者への資金貸し付け、倉庫貸出などを行い、利益を得る。撫育方がほぼ全てにあたった。また、塩田開発も進め、明和年間には21万石に上がる収益を得たと言われている。この他にも製紙、製蝋、製糖などにも力を入れた(防長三白)。一方で、過度な年貢取り立てなどの政策は一揆に悩まされることにもなった。天明元年(1781)、徳川家治の嗣子に一橋家の男子の豊千代が決定し、徳川家斉と改名すると、“しげなり”の“なり”が将軍嗣子の本名と同じだったため、読みを“しげなり”から“しげたか”に改める。天明2年(1782)に家督を四男・治親に譲って隠居し、自身は三田尻の三田尻御茶屋に住んだ。7年後の寛政元年(1789)に死去した。享年64。 ※長州藩天保一揆は「皮迷信」によりことから端を発し、その皮迷信は(秋口に皮製品を扱うと凶作になる)という言い伝えで一揆が始まった。藩は各地の特産物に「御内用産物方」が皮番所で禁止を犯して犬皮用いたことを見とがめられた事件に始まり、当時稲の穂が出るころに皮革類が田の周りを通ると暴風雨になるという。農民たちは皮革類を持ち込ませないように、見張り小屋を建てるほどだった。石見屋は皮を持ち歩くことで天候を崩し、米価が上がることを画策、これを知った農民は商人、御内用方(庄屋)を打毀し、その数741件に達した。一揆の数十数万人に達したという。その後幕府は首謀者の逮捕行い、死罪10名、遠島24名の刑に処した。
2023年08月15日
閲覧総数 275
-
35

「明応の政変」明応の政変の起因。 川村一彦
2「明応の政変の起因」(めいおうのせいへん)は、室町時代の明応2年(1493年)4月に細川政元が起こした室町幕府における将軍の擁廃立事件。この政変により、将軍は足利義材(義稙)から足利義遐(義澄)へと代えられ、以後将軍家は義稙流と義澄流に二分された。なお、近年の日本史学界においては戦国時代の始期をこの事件に求める説がある。細川 政元(ほそかわ まさもと)は、室町時代後期から戦国時代前期の武将、室町幕府守護大名であり、第24、26、27、28代管領。細川氏の第12代当主。摂津・丹波・土佐・讃岐守護。足利将軍家の在職将軍10代義材を追放して11代義澄を擁立し、政権を掌握。事実上の最高権力者となり、「半将軍」とも呼ばれた。室町幕府の三管領(足利一門の斯波、畠山、細川)である細川氏本家・京兆家の生まれ。父は応仁の乱時に東軍を率いた細川勝元。母は勝元の正室・山名熙貴の娘(養父は山名宗全)とされるが、根拠となる史料は無い。修験道に没頭して女性を近づけず独身を貫いたため実子はおらず、政元をもって細川家の嫡流は途絶え、養子に澄之、澄元、高国がいる。将軍を挿げ替え(明応の政変)、管領として幕政を牛耳り(京兆専制)、比叡山焼き討ちを行ったり畿内周辺にも出兵するなど、細川京兆家の全盛期を築き当時日本での最大勢力に広げたが、3人の養子を迎えたことで家督争いが生じ、自らもその争いに巻き込まれる形で家臣に暗殺された(永正の乱)。応仁の乱の混乱以来、実力者政元の登場によって小康状態にあった京・畿内周辺は、その死と澄元・高国両派の争いによって再び長期混迷していくこととなる。文正元年(1466年)、室町幕府管領として強い力を持っていた細川勝元の嫡男として生まれる。文明5年(1473年)5月、応仁の乱の最中に病死した勝元の後継として、わずか8歳で家督を相続。丹波・摂津・土佐守護に就任する。幼少のため、分家の典厩家当主細川政国の補佐を受けた。文明6年(1474年)4月3日、西軍方の山名政豊と和睦し、応仁の乱は終息する。文明10年(1478年)7月に13歳で元服し、8代将軍・足利義政の偏諱を受けて政元と名乗る。管領に任じられたものの、9代将軍・足利義尚の任大将拝賀の儀礼が終わると短期間(9日間)で辞職している。ところが、文明11年(1479年)12月に丹波国内における細川氏の家臣同士の争いが原因で一宮宮内大輔一族に拉致され、翌年3月まで丹波国に幽閉されている。文明14年(1482年)には摂津の国人が蜂起、畠山義就討伐に向かう管領・畠山政長と協力して連合を組んだが、摂津国人を討伐した後は義就が占領した摂津欠郡(東成郡・西成郡・住吉郡)の返還と引き換えに河内十七箇所を義就に渡し、単独で和睦して京都に撤退した。長享元年(1487年)、9代将軍・足利義尚は六角高頼(行高)討伐を決意するが、それを事前に知らされていたのは政元のみで、両者は極秘のうちに出陣の準備を進めていたと伝えられている。また、この年の長享改元の際に行われた幕府の吉書始の儀式のために1日だけ管領に就任している(2度目:長享元年8月9日)。だが、2年後の延徳元年(1489年)、将軍・義煕(義尚の改名後の名)は六角討伐(長享・延徳の乱)の最中、近江国で病死する。政元は次期将軍として義煕の従兄で堀越公方・足利政知の子で禅僧となっていた天竜寺香厳院の清晃(のちの足利義澄)を推挙するが、義煕の母・日野富子と畠山政長の後押しの結果、義煕の従弟で足利義視の息子・義材(後に義尹、更に義稙と改名)が10代将軍に就任する。この結果に不満であった政元は、延徳2年(1490年)7月5日に義材の就任儀式(判始)のために1日だけ管領を務めるが、やがて幕府に距離を置き始める。義材の将軍就任は、幕府内で足利義視と畠山政長の権勢が高まることとなり、延徳3年(1491年)1月に義視が死去した後は政長が幕府の権力を独占するようになる。直後の延徳3年2月13日に九条政基の末子(聡明丸と名乗る、のちの細川澄之)を猶子に迎えた。澄之を養子に迎えた意図として、妻帯していない(するつもりのない)政元には実子はもちろん弟もいないため後継者を得ておく必要性と、澄之は清晃の母方の従兄弟に当たるため足利政知との連携を深める狙いがあったとされる。更に直後の3月、政元は東国旅行へ出かけ、越後国を訪問、守護・上杉房定と会見した。奥州へ向かう予定だったが、将軍義材から六角高頼討伐の出陣命令が届いたため断念、4月に帰京した。この旅の背景は堀越公方足利政知と連携する意向で房定を取り込む意図があり、政知との会見も計画していたが、政知が亡くなったため帰京した。政元は、丹波で位田氏・荻野氏・大槻氏・須知氏らが起こしている国人一揆の鎮圧が上手くいっていないこともあり、この時の出兵には反対で、義材を諌めようとしたものの無視されている。この時から政変を計画していたとされる。
2024年02月06日
閲覧総数 73
-
36

「酒井氏一族の群像」姫路添付工作。 川村一彦
姫路転封工作寛延2年(1749年)、忠恭は前橋から姫路に転封する。酒井家は前橋にいた頃から既に財政が悪化していた。酒井家という格式を維持する費用、幕閣での勤めにかかる費用、放漫な財政運用、加えて前橋藩領内は利根川の氾濫が相次ぎ、あまり豊かでなかった、つまり財政基盤の脆弱さなどが大きかった。そのため家老の本多光彬や江戸の用人犬塚又内らは、同じ15万石ながら畿内の先進地に位置し、内実はより豊かと言われていた姫路に目をつけ、ここに移封する計画を企図し、忠恭もそれに乗った。ところが、本多と同じく家老の川合定恒は「前橋城は神君より『永代この城を守護すべし』との朱印状まで付された城地である」として姫路転封工作に強硬に反対したため、本多、犬塚らの国替え工作は以後、川合を頭越しに秘密裏に行われた(移封後の寛延4年(1751年)。川合は本多、犬塚の両名を殺害し、代々の藩主への謝罪状をしたためて自害している)。酒井家の期待とは裏腹にその頃姫路では、寛延元年(1748年)夏に大旱魃が起きたが姫路藩松平家は年貢徴収の手を緩めなかったため、領民の不満が嵩じている中で藩主・松平明矩が同年11月16日に死去する。そして不満が爆発した印南郡的形組の農民が12月21日に蜂起した。この一揆は「家財を売り払っても年貢完納ができない者は来季まで待つ」という触書によっておさまりを見せたが、1月15日に前橋の忠恭と姫路の松平喜八郎(朝矩)の領地替の命令が出されたことで借金の踏み倒しを恐れた領民は1月22日に再び蜂起し藩内各地を襲撃し、その被害は藩内全域に及んだ(寛延大一揆)一揆は2月には収拾したが、この混乱が尾を引き、酒井家の転封は5月22日にずれ込んだ。藩士の移住はさらに遅れ、しかも7月3日には姫路領内を台風が襲い、死者・行方不明者を400人以上も出した。8月にも再び台風が襲い、田畑だけではなく領民3000人余が死亡するなどの大被害を受け、酒井家はますます財政が悪化した。 「酒井 忠以」(さかい ただざね)は、江戸時代中期から後期の播磨姫路藩第2代藩主。雅楽頭系酒井家宗家10代。姫路藩世嗣・酒井忠仰の長男として江戸に生まれる。父が病弱だったため、祖父・忠恭の養嗣子となり、18歳で姫路藩の家督を継いだ。絵画、茶道、能に非凡な才能を示し、安永8年(1779年)、25歳の時、ともに日光東照宮修復を命じられた縁がきっかけで出雲松江藩主の松平治郷と親交を深め、江戸で、あるいは姫路藩と松江藩の参勤行列が行き交う際、治郷から石州流茶道の手ほどきを受け、のちには石州流茶道皆伝を受け将来は流派を担うとまでいわれた。大和郡山藩主の柳沢保光も茶道仲間であった。弟に江戸琳派の絵師となった忠因(酒井抱一)がいるが、忠以自身も絵に親しみ、伺候していた宋紫石・紫山親子から南蘋派を学び、『兎図』(掛軸 絹本著色、兵庫県立歴史博物館蔵)や『富士山図』(掛軸 絹本著色、姫路市立城郭研究室蔵)等、単なる殿様芸を超えた作品を残している。天明元年(1781年)、京都朝廷に忠以が使者として出かけることになった。出発の朝になると、愛犬の狆が玄関まで飛び出してきて駕籠を離れず、やむをえず品川まで連れて行き、そこでなだめたが効果がなく、結局京都まで連れて行ったところ、この噂が京都でひろまり、天皇の耳にまで届き、「畜類ながら主人の跡を追う心の哀れなり」ということで、この狆に六位の位が与えられた[1]。一方で藩政は、天明3年(1783年)から天明7年(1787年)までの4年間における天明の大飢饉で領内が大被害を受け、藩財政は逼迫した。このため、忠以は河合道臣を家老として登用し、財政改革に当たらせようとした。だが、忠以は寛政②年(1790年)に36歳の壮年で江戸の姫路藩邸上屋敷にて死去し、保守派からの猛反発もあって、道臣は失脚、改革は頓挫した。家督は長男の忠道が継いだ。筆まめで、趣味、日々の出来事・天候を『玄武日記』(22歳の正月から)『逾好日記』(33歳の正月から)に書き遺している。忠以の大成した茶懐石は『逾好日記』を基に平成12年9月に、和食研究家の道場六三郎が「逾好懐石」という形で再現している。年譜・1755年(宝暦5年) - 生まれ· (明和3年) - 名を忠以と改名· 1789年 (天明元年) - 愛犬の狆に六位の位が与えられる· 1785年(天明5年) - 溜間詰· 1790年(寛政2年) - 死去(7月17日)、享年36 「酒井 忠道」(さかい ただひろ / ただみち)は、江戸時代中期から後期の大名。播磨姫路藩第3代藩主。雅楽頭系酒井家宗家11代。若狭小浜藩十四代藩主酒井忠禄の子で明治維新後伯爵となった酒井忠道とは別人。第2代藩主酒井忠以の長男。寛政2年(1790年)、12歳の時に父の死により家督を継ぐ。この頃、姫路藩では財政窮乏のため、藩政改革の必要性に迫られており、文化5年(1808年)には藩の借金累積が73万両に及んでいた。父・忠以も河合道臣(寸翁)を登用して藩政改革に臨んだが、藩内の反対派によって改革は失敗し、道臣は失脚した。しかし忠道は再度、道臣を登用して藩政改革に臨んだ。 文化7年(1810年)には「在町被仰渡之覚」を発表して藩政改革の基本方針を定め、領民はもちろん、藩内の藩士全てに改革の重要性を知らしめた。まず、道臣は飢饉に備えて百姓に対し、社倉という食料保管制度を定めた。町民に対しては冥加銀講という貯蓄制度を定めた。さらに養蚕所や織物所を藩直轄とすることで専売制とし、サトウキビなど希少で高価な物産の栽培も奨励した。道臣は特に木綿の栽培を奨励していた。木綿は江戸時代、庶民にとって衣服として普及し、その存在は大変重要となっていた。幸いにして姫路は温暖な天候から木綿の特産地として最適だったが、当時は木綿の売買の大半が大坂商人に牛耳られていた。道臣ははじめ、木綿の売買権を商人から取り戻し藩直轄するのに苦慮したが、幸運にも忠道の八男・忠学の正室が第11代将軍・徳川家斉の娘・喜代姫であったため、道臣は家斉の後ろ盾を得て、売買権を藩直轄とすることができた。
2024年05月14日
閲覧総数 43
-
37

「西園寺公望の群像」国際連盟。 川村一彦
大国の首脳が集まるこの会議に、日本としてもそれなりの代表を送る必要があった。原首相と内田康哉外相が協議し、首席全権として西園寺を派遣する方針を決めた。西園寺は健康上の不安から辞退しようとしたが、12月18日に応諾した。この際、「無謀」であるが、老体を犠牲にするという覚悟を原に示している。しかし決定が遅れたことと、西園寺のために船室を改装する必要があったため、西園寺が出国したのは牧野伸顕や珍田捨巳といった他の全権が出発してから1ヶ月後の大正8年(1919年)1月14日のことであった。西園寺と同行したのは妾の奥村花子、娘の新子と八郎の夫妻、そして近衛文麿公爵らであった。また名門料亭なだ万の主人楠本萬助が板前二人を連れて乗船しており、船倉には日本食が5トンも積み込まれていた。これは現地で日本食パーティーを開くためのものであった。西園寺の一行は3月2日にパリに到着したが、フランス側からの出迎えはなかった。日本にとって重要な検討課題の討議は既に行われており、牧野や珍田が交渉の主役となっていた。さらに20年ぶりの訪仏であったこともあり、旧友クレマンソーの語るフランス語を聞くことはできても、話すことはできなくなっていた。また病気がちであったために精力的な活動もできず、会議には参加していたが、発言は一度も行っていない。このため外務省がまとめたパリ講和会議の概要文書で、西園寺が登場するのは4月27日のクレマンソーとの会談のみであった。吉野作造は「何を言ってよいか分からなかったためだ」と批判している。ただ、佐分利貞男は、山東半島問題が紛糾した際に、日本代表団の中から帰国しようという声が上がった際、西園寺が「国際連盟問題は山東問題よりも重要であるとし、自分一人でもパリに留まる」と発言したことを回想し、日本代表団内部に影響を与えたことを示唆している。 ◯国際連盟[こくさいれんめい、)、は、世界平和の確保と国際協力の促進を目的として設立された国際組織であった。第一次世界大戦を終結させたパリ講和会議の後、1920年1月10日に発足し、1946年4月20日に活動を終了した。 国際連盟規約に記載されている連盟の主な目的は、集団安全保障と軍縮によって戦争を防止し、交渉と仲裁によって国際紛争を解決することであった。また、労働条件、先住民の公正な扱い、人身売買、違法薬物の取引、武器取引、健康、戦争捕虜、ヨーロッパの少数民族の保護などが、この規約や関連条約に盛り込まれていた。国際連盟規約は、1919年6月28日にヴェルサイユ条約の第1編として調印され、1920年1月10日に他の条約とともに発効した。連盟理事会の第1回会合は1920年1月16日にフランス・パリで、連盟総会の第1回会合は1920年11月15日にスイス・ジュネーヴで開催された。1919年、アメリカ合衆国大統領ウッドロウ・ウィルソンは、連盟設立の立役者としてノーベル平和賞を受賞した。 連盟の外交理念は、それまでの100年間とは根本的に異なるものだった。連盟は独自の軍隊を持たず、第一次世界大戦で勝利した連合国(フランス、イギリス、イタリア、日本は常任理事国)が決議を執行し、経済制裁を守り、必要に応じて軍隊を提供することとしていた。しかし、大国はそれに消極的だった。制裁措置は連盟加盟国に損害を与える可能性があるので、大国は制裁措置を遵守することに消極的だった。第二次エチオピア戦争の際、イタリア軍の兵士が赤十字社の医療テントを攻撃していると連盟が非難したとき、ベニート・ムッソリーニは「連盟は雀が叫んでいるときには非常に良いが、鷲が喧嘩をしているときには全く良くない」と答えている。 また、人種的差別撤廃提案が否決されるなど、人種問題の解決を果たすこともできなかった。なお、2回目の提案の際、イギリス・アメリカ・ポーランド・ブラジル・ルーマニアの計5名の委員が反対した。 連盟の本部は1920年から1936年まではスイス・ジュネーヴのパレ・ウィルソン(英語版)に、1936年からは同じくジュネーヴのパレ・デ・ナシオンに設置されていた。パリ家モーリス・ド・ロチルド(英語版、フランス語版)の屋敷シャトー・ド・プレニー(英語版)も、1920年から1939年まで国際連盟の会場として使用された。 1934年9月28日から1935年2月23日までの間は、最多の58か国が加盟していた。連盟は、1920年代にいくつかの成功と初期の失敗を経験した後、最終的に1930年代の第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。アメリカ合衆国は連盟に加盟せず、ソビエト連邦は遅れて加盟した後、フィンランドへの侵攻後すぐに追放されたことで、連盟の信頼性は低下した。ドイツ、日本、イタリア、スペインなどは連盟を脱退した。第二次世界大戦の勃発により、連盟は「将来の世界大戦を防ぐ」という本来の目的を果たせなくなった。 第二次世界大戦終了後、国際連合(国連)が1945年10月24日に設立され、連盟が設立したいくつかの機関や組織は国連が引き継いだ。連盟は1946年4月20日をもって正式に解散した。連盟の存続期間は26年であった。 起源 背景 「国家間の平和のための共同体」という概念は、初期にはイマヌエル・カントが1795年の著書『永遠平和のために』[12]で、国家間の紛争を抑制し、平和を促進するための国家連合体の設立を主張した。カントは平和のための世界共同体の構築を主張したが、それは世界政府という意味ではなく、各国家が自国民を尊重し、外国からの訪問者を同じ理性的な存在として迎え入れる自由な国家であることを宣言することで、世界の平和な社会を促進することを願っていた。集団安全保障を推進するための国際協力は、19世紀のナポレオン戦争の後、ヨーロッパ諸国間の現状を維持し、戦争を回避するために展開されたヨーロッパ協調(英語版)に端を発している。また、この時代には国際法が整備され、ジュネーヴ条約では戦時中の人道的救済に関する法が制定され、1899年と1907年のハーグ条約では戦争のルールと国際紛争の平和的解決が規定された。歴史学者のウィリアム・H・ハーボーとロナルド・E・ポワスキー(英語版)が指摘するように、セオドア・ルーズベルトはアメリカ大統領として初めて国際的な連盟の設立を呼びかけた。ルーズベルトは、1906年にノーベル賞を受賞した際に、「誠実に平和を願う大国が平和連盟を結成してくれれば、それは素晴らしいことである」と述べている。
2024年08月01日
閲覧総数 47
-
38

「武市半平太の群像」出自と剣術家。 川村一彦
3「出自と剣術家」文政12年9月27日(1829年10月24日)、土佐国吹井村(現在の高知県高知市仁井田)に生まれる。武市家は元々土地の豪農であったが、半平太より5代前の半右衛門が享保11年(1726年)に郷士に取り立てられ、文政5年(1822年)には白札格に昇格。白札郷士とは上士として認められたことを意味する。天保12年(1841年)、一刀流・千頭伝四郎に入門して剣術を学ぶ。 ◯一刀流中西派(いっとうりゅうなかにしは)は、日本の剣術の流派。小野派一刀流の分派の一つ。 小野家第4代・小野忠一の直弟子であった中西子定が一刀流中西道場を開いたことから始まるが、子定自身は「一刀流中西派」という流名を称しておらず、正式名称は「一刀流」のままであり、小野家から学んだ一刀流という意味で対外的に「小野派一刀流」と名乗っていた。 また中西家に学んだ者は「小野派一刀流」と称していた。昭和期の高野佐三郎も小野派一刀流を名乗っている。「一刀流中西派」という名称は、いつ頃からか不明であるが、現在では高野弘正門下で使用されている。一般の小野派一刀流と中西子定の系統とを区別するための俗称であると思われる。なお、小野派一刀流との関係から中西派一刀流と誤って書かれる事も多いが、流派関係者は一刀流中西派と書く。また小野派一刀流中西派と書かれる事もある。 特徴 稽古は木刀による形稽古(組太刀)と竹刀稽古とに大別される。中西子定の子である中西子武が宝暦年間(1751年 – 1763年)に防具を改良し、竹刀稽古を導入したことが大きな特徴である。竹刀稽古の導入により一刀流中西派は急速に広まり、現代剣道の母体となった。嘉永2年(1849年)、父母を相次いで亡くし、された老祖母の扶養のために、半平太は同年12月に郷士・島村源次郎の長女・富子を妻としている。翌嘉永3年(1850年)3月に高知城下に転居し、小野派一刀流(中西派)の麻田直養(なおもと)の門で剣術を学び、間もなく初伝を授かり、嘉永5年(1852年)に中伝を受ける。嘉永6年(1853年)、ペリーが浦賀に来航して世情が騒然とする中、半平太は藩より西国筋形勢視察の任を受けるが、待遇に不満があったのかこれを辞退している。翌嘉永7年(1854年)に新町に道場を開き、同年(安政元年)に麻田より皆伝を伝授される。安政元年に土佐を襲った地震のために家屋を失ったが、翌・安政2年(1855年)に新築した自宅に妻の叔父にあたる槍術家・島村寿之助との協同経営の道場を開き、声望が高まっていた半平太の道場には120人の門弟が集まった。この道場の門下には中岡慎太郎や岡田以蔵等もおり、後に結成される土佐勤王党の母体となる。同年秋に剣術の技量を見込まれて、藩庁の命により安芸郡や香美郡での出張教授を行う。安政3年(1856年)8月、藩の臨時御用として江戸での剣術修行が許され、岡田以蔵や五十嵐文吉らを伴って江戸へ出て鏡心明智流の士学館(桃井春蔵の道場)に入門。半平太の人物を見込んだ桃井は皆伝を授け、塾頭とした。塾頭となった半平太は乱れていた道場の風儀を正し、その気風を粛然となさしめた。同時期に坂本龍馬も江戸の桶町千葉道場(北辰一刀流)で剣術修行を行っている。 ◯北辰一刀流(ほくしんいっとうりゅう)は、江戸時代後期に千葉周作成政(屠龍)が創始した剣術と薙刀術の流派。 千葉家家伝の北辰流、北辰夢想流と、一刀流を千葉周作が統合して北辰一刀流が創始された。よって剣術の組太刀(形)は一刀流のものとにている。千葉周作が加えた極意の大目録伝に伝わる口伝術と星王剣(星王とは北極星のこと)に千葉家の北辰信仰の影響がわずかに見られる程度である。竹刀と防具を用いた打ち込み稽古を中心に行い、現代剣道を築いた流派である。 北辰夢想流という剣術流派が、栗原郡荒谷村(現大崎市古川荒谷)の千葉家(周作の千葉家とは異なる)に家伝として伝わっていた。 6歳のとき気仙沼村(現気仙沼市)から父親とともに栗原郡荒谷村に住まいした於菟松(後の周作)は、千葉吉之丞からこれを学び、16歳のとき江戸に出て中西派一刀流の浅利義信に入門し、後に義信の師匠である中西子正(中西派一刀流第9代)からも学んだ。やがて義信の婿養子となるも、組太刀の改変を試みて妻(浅利の養女)を連れて義信から独立し、北辰一刀流を創始した。伝書には、北辰夢想流と一刀流を合法し、北辰一刀流にしたとある。また、初期の北辰一刀流免状には北辰夢想流免状に記された和歌が記されている。 その後、武蔵・上野、信濃の国などを周って他流試合を行い、門弟数も増え、伊香保神社に奉納額を掲げることを企画した。しかし、地元の馬庭念流に阻まれて騒動(伊香保神社掲額事件)にまで発展したため、掲額は断念した。この騒動で周作自身は名を挙げたが、北辰一刀流は上野から撤退した。周作は江戸に帰り、1822年(文政5年)秋、日本橋品川町に玄武館という道場を建てた(後に神田於玉ヶ池に移転)。 幕末期 浅草寺に掲額された門人名が6千人を超えるほどとなった玄武館は、練兵館(神道無念流)、士学館(鏡新明智流)を凌ぎ幕末江戸三大道場の筆頭に数えられた。また周作の弟・千葉定吉政道の道場も、桶町千葉として名があった。 これまでの剣術がしばしば仏理を併せて学ばせ、神秘性を強調して来たのに対して、玄武館は合理的な剣を解いた。儒者・東条一堂の塾「瑶地塾」の隣にあったので、周作は門弟に瑶地塾で朱子学を学んで合理精神を養うことを奨励したこともあり、北辰一刀流には漢詩に巧みな者が多かった。また、玄武館は天神真楊流柔術開祖・磯正足の道場の斜め向かいにあったので、天神真楊流柔術を併習する者も多かった。お玉が池には佐久間象山の象山塾もあり、負けず嫌いな佐久間象山は同郷の松代藩士塚田孔平のいた玄武館と門弟の数を競った、佐久間象山は塚田孔平の道場≪虎韜館≫の道場額も書いている。 入門からわずか5年で皆伝を得た海保帆平、玄武館四天王と呼ばれた稲垣定之助、庄司弁吉、森要蔵、塚田孔平などの高弟を輩出した。幕末の志士では坂本龍馬、毛利荒次郎、清河八郎、新選組では、藤堂平助、山南敬助、伊東甲子太郎、服部武雄、吉村貫一郎、日比谷健次郎らが北辰一刀流を学んだ。また、玄武館は、旗本や各藩からの剣術指導委託も積極的に行ったため、30余りの藩から藩士が集まった。周作及び子の奇蘇太郎、栄次郎、道三郎、多門四郎は水戸藩に仕え、水戸三流の一つとして北辰一刀流を指南した、玄武館四天王が水戸の天狗党を支援したため幕府よりとがめられ玄武館は一時閉館させられた。 周作の後は、長男・奇蘇太郎孝胤が肺病で早世していた為、次男・栄次郎成之が継承した。栄次郎は片手上段の構えを得意とし、「千葉の小天狗」と恐れられる天才であったが、彼もまた早世した。その後周作の三男・道三郎光胤が玄武館を継いだが、1872年(明治5年)に没する。四男・多門四郎政胤は小児のとき水戸藩主・徳川斉昭の前で演武し、将来を嘱目されたが、奇蘇太郎と同じく肺病で早世している。道三郎の長男・勝太郎勝胤(「剣法秘訣、北辰一刀流開祖千葉周作作述」を出版)も剣の英才教育を受け実力を発揮したが、眼病のため失明。玄武館は閉鎖され、宗家は廃絶され師範家のみが残った。 安政4年(1857年)8月、半平太と龍馬の親戚の山本琢磨が商人の時計を拾得売却する事件が起きた。事が藩に露見したため切腹沙汰になったが、半平太と龍馬が相談の上で山本を逃がしている。これから程ない9月に老祖母の病状が悪化したので土佐に帰国した。安政5年(1858年)に一生二人扶持の加増を受け、剣術諸事世話方を命じられる。安政6年(1859年)2月、一橋慶喜の将軍継嗣擁立を運動していた土佐藩主・山内豊信が大老・井伊直弼によって隠居させられ、同年10月には謹慎を命じられる。土佐藩士達はこの幕府の処置に憤慨したが、翌安政7年(1860年)3月3日に井伊が暗殺され(桜田門外の変)、土佐藩士達は変を赤穂義士になぞらえて喝采し、尊王攘夷の機運が高まった。
2024年11月01日
閲覧総数 42
-
39

「歴史の回想・永禄の変」岩城友通。 川村一彦
岩成 友通(いわなり ともみち)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。三好氏の家臣で、三好三人衆の1人。姓は石成とも書く。 元亀元年から「長信」の名乗りを使用している。 三好長慶の奉行人として頭角を現し、三好政権の中枢を占めるに至った。三好政権における出世頭ともいえる人物である。 友通の出自は不明とされる。室町時代の多くを通じて細川氏の支配下であった大和国石上神社の摂社に「石成神社」があることから、大和出身ではないかという見解がある他、備後国品治郡石成郷といった地名があることから、それらの土地の土豪との関係を推察されることが多い。 『史略名称訓義』には「岩成古〔原文ママ〕通」に註して「主税助と号、種成と名く、備後国岩成荘住人岩成蔵人正辰の男」と記される。 また、京都郊外の西九条の下司を務めていたが、やがて三好氏に臣従したともされる。 『東寺百合文書』所蔵の三好元長の家臣・塩田胤光が発給した文書に「岩成」の名字が見える他、同所蔵の文書には、下司の「岩成」が西九条の荘園を押領したという記述も見られる。 今谷明は「阿波出身でないのは確実」と断言しており、いずれにしても、松永久秀と同様に畿内で登用されたと思われる。 史料における初見は天文19年(1550年)であり、北野社の大工職の相論において、照会の役を務めていることが確認される。 翌天文20年(1551年)11月には、堺で開かれた天王寺屋の津田宗達(津田宗及の父)の茶会に出席している。 その後は三好長慶の下で奉行衆として仕えた。 永禄元年(1558年)の将軍山城占拠に参戦(北白川の戦い)しており、この従軍が軍事行動における友通の初見とされる。 永禄5年(1562年)に六角義賢が京に侵入した時は室町幕府13代将軍・足利義輝の警護を行った。 長慶の死後、三好三人衆の1人(他の2人は三好長逸、三好宗渭)として甥の三好義継の後見役を務めた。 永禄8年(1565年)の足利義輝暗殺(永禄の変)を初め他の三人衆と行動を共にし、松永久秀や畠山高政としばしば戦った。 また永禄9年(1566年)には、土豪の中沢満房、革嶋一宣らの立て籠もった山城国勝竜寺城を攻め落とすと、友通は敵対した土豪達を厳しく追及、革嶋一族を始め多くの土豪を追い出し、手に入れた土地の多くを新しい領主に与えた。同時に勝竜寺城を居城とし、山城西部の西岡を支配した。 これは、勝竜寺城を拠点に西岡地区に新たな支配を確立させようとする、斬新な手法であると評価される。 また、勝竜寺城も、戦の際に土豪が立て籠もる施設程度であったものが、友通が入城・整備して拠点とすることで、土豪をまとめ上げる政権の拠点として生まれ変わった[7]。友通はそうした点から、勝竜寺城の「最初の城主」とも評される。 永禄10年(1567年)に1万の軍勢を率いて池田勝正と共に大和東大寺で久秀と対陣したが、久秀の奇襲を受けて敗北(東大寺大仏殿の戦い)。 翌永禄11年(1568年)に織田信長が上洛してくると、三好長逸、三好宗渭、篠原長房らと連携し、それまで敵対していた六角義賢と手を組んで[8]強く抵抗したが、守城の勝竜寺城を攻撃され退去した(勝竜寺城の戦い)。 しかしこの際、他の畿内の城が抵抗らしい抵抗もせずに降伏してゆく中、友通の籠る勝竜寺城と池田勝正が籠る摂津国池田城だけは強硬に抵抗した。 これは、友通による支配が一定の奏功をし、土豪達が彼の下に結束していた証とされる。 敗退の推移について、『多聞院日記』『言継卿記』によれば、永禄11年9月27日に友通は信長に抵抗して勝竜寺城へ籠城したとあるが、9月29日には落城している。 言継卿記の翌永禄12年(1569年)の1月8日の記述によれば、勝竜寺城には細川藤孝が入城している。 友通が勝竜寺城主であったこの時期には、光源院から勝竜寺城主である友通に礼物が送られていたことが「光源院文書」から判明しているが、9月21日とあるだけで年月は未詳となっている。
2023年12月31日
閲覧総数 49
-
40
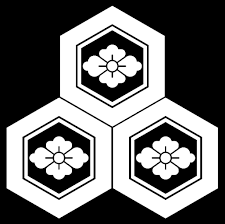
「堀氏一族の群像」松村藩8代堀藩主。 川村一彦
「堀 直央」(ほり なおひで/なおひさ、寛政9年7月7日(1797年7月30日) - 文久元年3月6日(1861年4月15日))は、越後村松藩の第9代藩主。直寄系支流堀家9代。第7代藩主・堀直方の三男。はじめ庸信と名乗った。正室は津軽寧親の娘、継室は土屋英直の娘。子は堀直休(次男)、堀直弘(三男)、福原資功(?男)、娘(吉田良義室)、清子(黒田直養正室)。官位は従五位下、丹波守。 文政2年(1819年)、兄・直庸の死により家督を相続した。直庸の時代から、家老・堀玄蕃を中心とした百姓収奪による財政改革という悪政が行なわれたため、文化11年(1814年)に藩内全土で百姓一揆が起こった。天保14年(1843年)、祖先の堀直寄所縁であるものの火災によって損傷していた上野大仏を、寄進により新鋳再建し、仏殿を修復した。嘉永3年(1850年)には城主格が与えられ、村松陣屋は城に改修された。こうした中、嘉永6年(1853年)に藩政の主導権を握って文武を奨励し、農村経済発達による専売制導入や流通整備による藩収増加など、財政再建にも力を注いだ。また、官営殖産興業の発展にも注力している。 安政2年(1855年)、安政の大地震によって上野大仏が破損したため修復した。安政4年(1857年)隠居し、家督を次男の直休に譲る。文久元年(1861年)死去した。「堀 直休」(ほり なおやす、天保7年11月3日(1836年12月10日) - 万延元年7月12日(1860年8月28日))は、越後村松藩の第10代藩主。直寄系支流堀家10代。第9代藩主・堀直央の次男。母は側室岩田氏。正室は加藤泰幹の娘。子は堀直儀(長男)、堀直張(次男)、娘(柳沢徳忠正室)、娘(岡本正鎮室)。官位は従五位下、丹波守。安政4年(1857年)、父の隠居により家督を相続した。藩政改革を引き続き推進したが、万延元年(壱八六〇年)に道半ばで死去した。跡を養子の直賀が継いだ。 堀 直賀」(ほり なおよし、天保壱四年閏9月24日(1843年11月15日) - 明治36年(1903)1月6日)は、越後村松藩の第11代藩主。直寄系支流堀家11代。第6代藩主・堀直教の長男・奥田教明の長男。子は奥田直紹(長男、旧椎谷藩主家を継ぐ、廃藩置県で奥田姓に復姓)、娘(高野金重室)。従五位下、左京亮。万延元年(1860年)11月Ⅰ日、先代藩主・直休の末期養子として家督を継ぐ。幕末期に入ると藩内に尊王論が起こり、尊王攘夷と軍制改革を主張する一派を形成した。慶応2年(1866年)には村松七士事件(尊王攘夷派7名を保守派が処刑した事件)が発生し、藩政が混乱した。慶応4年(1868年)の戊辰戦争では明治新政府を支持する正義党の近藤安五郎一派と対立し、佐幕保守派の直賀は奥羽越列藩同盟に参加した。明治元年(1868年)5月14日、長岡に出兵し、官軍と戦う。同年8月4日、官軍の攻撃で村松城を落とされて米沢藩に逃亡した。同年9月18日、新政府に謝罪を申し入れる。同年10月19日、新政府から謹慎を命じられる。一方、安五郎は先代藩主・直休の弟・直弘を新藩主に擁立して新政府軍に降伏し、村松藩は所領を安堵された。明治元年12月7日、直賀は隠居を命じられて、直弘に家督を譲った。明治10年(1877年)に奥田姓に復し、明治36年(1903年)に死去した。法名は安達院殿従三位清節直賀大居士。墓所は谷中霊園。
2024年05月04日
閲覧総数 103
-
41

『足利尊氏の群像」豊島河原合戦。 川村一彦
その報を受けた義貞は、箱根口の戦いでは大勝しながらも、退路を断たれるおそれが出たため軍を撤退させる。この情勢を見て手越河原の戦いで投降し義貞軍に加わっていた佐々木道誉も尊氏軍に寝返り、義貞軍も総崩れとなった。この時に尊良親王の近侍であった中将二条為冬が戦死した。13日には伊豆国府を尊氏軍が奪回し、義貞軍は東海道を総崩れで敗走した。天竜川に架かる浮き橋を義貞が遅れてくる味方のために残したと、どちらかというと足利寄りの『梅松論』には書かれているが、一方南朝寄りの『太平記』には浮き橋を斬って退却したと、全く逆に書かれている。 これを独自の武家政権を樹立する構えと解釈した天皇との関係が悪化、建武の乱が勃発した。箱根・竹下の戦いでは大勝するが、第一次京都合戦および打出・豊島河原の戦いで敗北した。 豊島河原合戦(てしまがわらがっせん)は、建武3年(1336年)に行われた新田義貞・北畠顕家を総大将とする後醍醐天皇軍と足利尊氏を総大将とする反乱軍の戦い。豊島河原の戦いとも言う。元弘3年/正慶2年(1333年)、鎌倉幕府が滅びた後、足利尊氏は後醍醐天皇に突如反旗を翻した。尊氏は建武2年(1335年)箱根・竹ノ下の戦いで新田義貞軍を破ると、京都へ進軍を始めた。尊氏は建武3年(1336年)1月11日に京都へ到着するが、京都へ駆け付けた北畠顕家軍に攻め入られ、同月27日の合戦と同晦日の糺河原の合戦における敗戦を経て丹波国に引き返す事となる。開戦丹波国に引き返した足利尊氏は勢力を盛り返し、再度京都に攻め入る為に、同年2月3日に摂津国猪名川付近へ到着する。これに対して後醍醐天皇側の新田義貞・北畠顕家勢は軍を率いて尊氏が陣を張る摂津へ向かう。梅松論の記述『梅松論』(30)によると、足利尊氏側に味方した山陽周防国(現:山口県東南)・長門国(現:山口県西)の守護大名が瀬戸内海を渡り、約500の軍艦を率いて摂津国神戸港に入港した。尊氏側は2月10日に周防・長門の援軍に合流して港を出て都に攻め上ろうとするが、西宮浜で待ち構えていた楠木正成と合戦になり終日戦って決着がつかなった。しかし同日夜に正成は陣を引いたため、尊氏は合流した援軍を従えて翌2月11日に攻め上り新田義貞・北畠顕家両軍と豊島河原(瀬川)で合戦を繰り広げた。その結果尊氏側は新田・北畠軍に敗れ去り、同月12日に兵庫へ退陣した。その後尊氏は周防・長門の援軍と共に九州へ落ち延びて行ったと書かれている。太平記の記述『太平記』(巻第十五)によると、丹波国に落ち延びた足利尊氏は、2月3日に足利直義に約16万の軍勢を与えて京都へ攻め上らせ、一方約10万騎の新田義貞・北畠顕家率いる後醍醐天皇軍が摂津国豊島河原(瀬川宿)で合戦を行った。結果は両軍共に勝敗が付かず、猪名川両岸で睨み合いが続いた後、後醍醐側として参戦した楠木正成が西宮へ赴き背後から直義・尊氏軍を襲い、西宮に合戦地が移ったとされる。その後、周防国・長門国の守護大名が神戸港に到着し、後醍醐天皇側軍も四国の伊予国から援軍が到着した。そこで両軍は湊川で合戦を行った。しかし、足利尊氏は自らの敗戦を見切って、周防・長門の援軍と共に九州へ落ち延びて行ったと書かれている。合戦場「豊島河原」とされている場所は不明であるが、『梅松論』には「新田義貞は摂津国瀬川の河原にて合戦を行った」と記述があり、「瀬川の河原」と伝わるのは、箕面川の下流で箕面市と池田市の境界を接する河原であると見られている。 一時は九州に都落ちしたものの、再び太宰府天満宮を拠点に上洛して京都を制圧、光明天皇を擁立して征夷大将軍に補任され新たな武家政権(室町幕府)を開いた。一度は京に降った後醍醐天皇は、すぐ後、吉野に脱出し南朝を創始することになった。
2024年07月07日
閲覧総数 102
-
42

『足利尊氏の群像」中先代の乱。 川村一彦
新政の瓦解後新政の瓦解後は、足利尊氏により室町幕府が開かれ、足利氏が15代に渡り政治の実権を握った。 7「中先代の乱」建武2年(1335年)信濃国で北条高時の遺児北条時行を擁立した北条氏残党の反乱である中先代の乱が起こり、時行の軍勢は鎌倉を一時占拠する。直義は鎌倉を脱出する際に独断で護良を殺害している。尊氏は後醍醐天皇に征夷大将軍の官職を望んだが許されず、8月2日、天皇の許可を得ないまま軍勢を率いて鎌倉に向かった。天皇はやむなく征東将軍の号を与えた。尊氏は直義の軍勢と合流し相模川の戦いで時行を駆逐して、8月19日には鎌倉を回復した。 中先代の乱(なかせんだいのらん)は、1335年(建武2年)7月、北条高時(鎌倉幕府第14代執権)の遺児時行が、御内人の諏訪頼重らに擁立され、鎌倉幕府再興のため挙兵した反乱。先代(北条氏)と後代(足利氏)との間にあって、一時的に鎌倉を支配したことから中先代の乱と呼ばれている。また、鎌倉支配が20日余りしか続かなかったことから、廿日先代(はつかせんだい)の異名もある。鎌倉幕府滅亡後、建武の新政により、鎌倉には、後醍醐天皇の皇子の成良親王を長とし尊氏の弟の足利直義が執権としてこれを補佐する形の鎌倉将軍府が設置された。しかし建武政権は武家の支持を得られず、北条一族の残党などは各地で蜂起を繰り返していた。北条氏が守護を務めていた信濃国もその1つで、千曲川(信濃川)周辺ではたびたび蜂起が繰り返され、足利方の守護小笠原貞宗らが鎮圧にあたっていた。1335年(建武2年)6月には、鎌倉時代に関東申次を務め、北条氏と繋がりがあった公家の西園寺公宗らが京都に潜伏していた北条高時の弟北条泰家(時興)を匿い、持明院統の後伏見法皇を擁立して政権転覆を企てた陰謀が発覚する。公宗らは後醍醐天皇の暗殺に失敗して誅殺されたが、泰家は逃れ、各地の北条残党に挙兵を呼びかけた。信濃に潜伏していた時行は、御内人であった諏訪頼重や滋野氏らに擁立されて挙兵した(『梅松論』)。時行の信濃挙兵に応じて北陸では北条一族の名越時兼が挙兵する。時行勢の保科弥三郎(保科氏)や四宮左衛門太郎らは青沼合戦において守護小笠原貞宗を襲撃し、この間に諏訪氏・滋野氏らは信濃国衙を焼き討ち襲撃して、建武政権が任命した公家の国司(清原真人某)を自害させる(『太平記』)。ところが、京都の建武政権は当初、反乱軍が時行を擁しているとの情報を掴んでいなかったらしく、京都では当初反乱軍は木曽路から尾張国に抜け、最終的には政権のある京都へと向かうと予想(『梅松論』)したために鎌倉将軍府への連絡が遅れ、それが後の鎌倉陥落につながったとみられている。勢いに乗った時行軍は武蔵国へ入り鎌倉に向けて進軍する。7月20日頃に女影原(埼玉県日高市)で渋川義季や岩松経家らが率いる鎌倉将軍府の軍を、小手指ヶ原(同県所沢市)で今川範満の軍を、武蔵府中で救援に駆けつけた下野国守護小山秀朝の軍を打ち破り、これらを自害あるいは討死させた。続いて、井手の沢(東京都町田市)にて鎌倉から出陣して時行軍を迎撃した足利直義をも破る。直義は尊氏の子の幼い足利義詮や、後醍醐天皇の皇子成良親王らを連れて鎌倉を逃れる。鎌倉には建武政権から失脚した後醍醐天皇の皇子護良親王(前征夷大将軍)が幽閉されていたが、直義は鎌倉を落ちる際に密かに家臣の淵辺義博に護良親王を殺害させている(7月23日)。鎌倉に護良を将軍・時行を執権とする鎌倉幕府が再興され建武政権に対抗する存在になることを恐れていたからと考えられている。24日は鶴見(神奈川県横浜市鶴見区)にて鎌倉将軍府側は最後の抵抗を試みるが佐竹義直(佐竹貞義の子)らが戦死、翌25日に時行は鎌倉に入り、一時的に支配する。更に時行勢は逃げる直義を駿河国手越河原で撃破した。直義は8月2日に三河国矢作に拠点を構え、乱の報告を京都に伝えると同時に成良親王を返還している。時行勢の侵攻を知らされた建武政権では、足利尊氏が後醍醐天皇に対して時行討伐の許可と同時に武家政権の設立に必要となる総追捕使と征夷大将軍の役職を要請するが、後醍醐天皇は要請を拒否する。8月2日尊氏は勅状を得ないまま出陣し、後醍醐天皇は尊氏に追って征東将軍の号を与える。尊氏は直義と合流し、9日遠江国橋本(静岡県湖西市)、12日に小夜の中山にて今川頼国の手により名越邦時戦死、14日に駿河国の清見関および国衙、17日に相模国箱根、18日に相模国相模川では尊氏方は義経来の北条方に遺恨を持つ中村経長が獅子奮迅の働きをするも今川頼国・頼周兄弟が戦死するなど各地が激戦に見舞われた。時行勢は次第に劣勢となり戦線は徐々に後退。19日には相模国辻堂で敗れた諏訪頼重が鎌倉勝長寿院で自害して、時行は鎌倉を保つこと20日余りで逃亡する。後醍醐天皇は尊氏へ出陣の許可は与えなかったものの、8月30日の小山朝氏への下野国司兼守護への補任は尊氏の奏請に応じたものと考えられ、また間に合わなかったとは言え九州の大友貞載に出陣を求める綸旨を出していることから、少なくてもこの段階では尊氏と天皇の方針に大きな違いはなかったと考えられている。
2024年07月07日
閲覧総数 77
-
43

「黒田清隆の群像」大久保利通の暗殺。 川村一彦
翌年に大久保利通が暗殺されると、薩摩閥の重鎮となった。 大久保 利通(おおくぼ としみち、文政13年8月10日(1830年9月26日) - 明治11年(1878年)5月14日)は、日本の武士(薩摩藩士)、政治家。位階勲等は贈従一位勲一等。明治維新の元勲であり、西郷隆盛、木戸孝允と並んで「維新の三傑」と称され、「維新の十傑」の1人でもある。初代内務卿で、内閣制度発足前の明治日本政府(太政官)の実質的・事実上の首相。幼名は正袈裟、通称は正助、一蔵、諱は利済、利通、雅号は甲東。 生い立ち 文政13年8月10日(1830年9月26日)、薩摩国鹿児島城下高麗町(現・鹿児島県鹿児島市高麗町)に、薩摩藩士・大久保利世と福の長男として生まれる。幼名正袈裟(しょうけさ)。家格は御小姓与と呼ばれる下級藩士。幼少期に加治屋町(下加治屋町方限)移住。下加治屋町の郷中や藩校造士館で西郷隆盛や税所篤、吉井友実、海江田信義らと共に学問を学び親友・同志となった。子供の頃は禁忌とされた桜島の火口に石を投げ落としたり温泉で滝水を使った温度調整をいじって温泉客を驚かせたりと、悪戯小僧であった。武術は胃が弱かったため得意ではなかったが、学問は郷中のなかでは抜きん出ていた。 天保15年(1844年)に元服し、正助(しょうすけ)と名乗る。 幕末 弘化3年(1846年)より藩の記録所書役助として出仕。嘉永3年(1850年)のお由羅騒動で父・利世に連座して罷免され謹慎処分となり、貧しい生活を強いられる。島津斉彬が藩主となると謹慎を解かれ、嘉永6年(1853年)5月に記録所に復職し、御蔵役となる。安政4年(1857年)10月1日、徒目付となる。同年11月、西郷に同伴し熊本に達し長岡監物、津田山三郎らと時事を談ずる。精忠組の領袖として活動し、安政5年(1858年)7月の斉彬の死後は、11月に失脚した西郷に代わり組を率いる。同年12月、西郷に書を送り脱藩義挙に就いて意見を問う。安政6年(1859年)11月、同志40余人と脱藩を企画する。しかし、新藩主・島津茂久から親書を降され思い留まる。同月、藩主の実父・島津久光に時事の建言を行い、税所篤の助力で接近する。篤の兄で吉祥院の住職・乗願が久光の囲碁相手であったことから、乗願経由で手紙を渡したりもしている。万延元年(1860年)3月11日、久光と初めて面会し、閏3月、勘定方小頭格となる。文久元年(1861年)9月、同志と謀り親族町田家が秘蔵していた楠木正成の木像を請い受けて伊集院石谷に社殿を造営する。同年10月23日、御小納戸役に抜擢され藩政に参与(去る10月7日には堀仲左衛門も御小納戸役に抜擢)し、家格も一代新番となる。 文久元年12月15日(1862年1月14日)から同2年(1862年)1月中旬までの間に久光から一蔵(いちぞう)の名を賜る。元年12月28日、久光の内命により京都に上る。 倒幕・王政復古 文久2年(1862年)、正月より久光を擁立して京都の政局に関わり、公家の岩倉具視らとともに公武合体路線を指向して、一橋慶喜の将軍後見職、福井藩主・松平慶永の政事総裁職就任などを進めた。同年正月14日、前左大臣近衛忠煕、忠房父子に謁して、久光上京、国事周旋を行うことを内々に上陳する。同年2月1日、近衛父子の書を携えて帰藩する。同月12日、大久保らの進言を受けて久光に召喚された西郷が奄美大島より戻る。翌13日、小松清廉邸において、西郷らと久光上京に関して打ち合わせる。3月に入り、西郷が先発して村田新八らとともに上京。同月16日、久光、千人を超える兵を率いて公武合体運動推進のため上京の途に就く。大久保はこれに従った。同月30日、兵に先駆けて、下関より西郷の後を追って大久保のみ急遽東上する。4月6日、西郷と会い、京都大阪の形勢を談ずる。同月8日、播州大蔵谷において久光を迎える。同月16日、久光入京する。大久保はこれに随行。翌17日、久光は浪士鎮撫の勅命を受ける。同月19日、大久保は大阪に赴き、志士を説得する。同月23日、伏見において寺田屋騒動勃発。奈良原繁らが有馬新七らの義挙を止めるも、これを受け容れず。新七ら8名が斬られる。5月6日、大久保は、正親町三条実愛、中山忠能、岩倉具視ら諸卿に謁して、勅使を関東に下向させることに関して建策する。同月9日、久光、勅使大原重徳卿の随行を命じられる。5月20日、御小納戸頭取に昇進となる。この昇進により、小松清廉、中山尚之介と並んで久光側近となる。同日、久光、関東に向けて進発する。大久保はこれに随行する。6月7日江戸着。同月26日、大久保は、大原勅使に謁したうえで、幕閣が勅命を奉じない場合、決心する所があることを告げた。8月21日、久光江戸を出発し西上する。大久保はこれに随行する。この日、生麦事件あり。翌閏8月7日京都に着く。同月9日に久光による参内、復命。大久保はこれに随う。同月23日、久光帰藩のため京都を出発する。大久保も随行。同月30日、大久保は御用取次見習となる[11]。文久3年(1863年)2月10日には、御側役(御小納戸頭取兼務)に昇進する。慶応元年(1865年)1月下旬から5月の間に利通と改諱する。 慶応2年(1866年)、第二次長州征討に反対し、薩摩藩の出兵拒否を行っている。慶応3年(1867年)、雄藩会議の開催を小松や西郷と計画し、四侯会議を開催させる。しかし四侯会議は慶喜によって頓挫させられたため、今までの公武合体路線を改めて武力倒幕路線を指向することとなる。 小松、西郷とともに公議政体派である土佐藩の後藤象二郎、寺村道成、真辺正心(栄三郎)、福岡孝弟、浪人の坂本龍馬、中岡慎太郎との間で将軍職の廃止、新政府の樹立等に関する薩土盟約を三本木の料亭にて結ぶも、思惑の違いから短期間で破棄。 武力による新政府樹立を目指す大久保・西郷・小松は8月14日に長州藩の柏村数馬に武力政変計画を打ち明け、それを機に9月8日に京都において薩摩藩の大久保・西郷と長州藩の広沢真臣・品川弥二郎、広島藩の辻維岳が会し出兵協定である三藩盟約を結んだ。なお、この三藩盟約書草案は大久保の自筆によって書かれたもので、現在も残っている。 10月14日、正親町三条実愛から倒幕の密勅の詔書を引き出した(ただしこの密勅には偽造説もある)大久保は、小松・西郷らと詔書の請書に署名し、倒幕実行の直前まで持ち込むことに成功した。しかし、翌日に土佐藩の建白を受けていた将軍・徳川慶喜が大政奉還を果たしたため、岩倉ら倒幕派公家とともに、王政復古の大号令を計画して実行する。王政復古の後、参与に任命され、小御所会議にて慶喜の辞官納地を主張した。 明治維新後 慶応4年(1868年)1月23日、太政官にて大阪への遷都を主張する。 明治2年7月22日(1869年8月29日)に参議に就任し、版籍奉還、廃藩置県などの明治政府の中央集権体制確立を行う。 明治4年(1871年)には大蔵卿に就任し、岩倉使節団の副使として外遊する。 明治6年(1873年)に帰国。外遊中に留守政府で問題になっていた朝鮮出兵を巡る征韓論論争では、西郷隆盛や板垣退助ら征韓派と対立し、明治六年政変にて西郷らを失脚させた。同年に内務省を設置し、自ら初代内務卿(参議兼任)として実権を握ると、学制や地租改正、徴兵令などを実施した。そして「富国強兵」をスローガンとして、殖産興業政策を推進した。 明治7年(1874年)2月、佐賀の乱が勃発すると、ただちに自ら鎮台兵を率いて遠征、鎮圧している。首謀者の江藤新平ら13人を、法によらない裁判で処刑した。さらに江藤を梟首しただけでなく、首を写真撮影して、全国の県庁で晒し者にした。しかし問題にはされなかった。また台湾出兵が行われると、戦後処理のために全権弁理大臣として9月14日に清に渡った。交渉の末に、10月31日、清が台湾出兵を義挙と認め、50万両の償金を支払うことを定めた日清両国間互換条款・互換憑単に調印する。また出兵の経験から、明治8年(1875年)5月、太政大臣の三条実美に海運政策樹立に関する意見書を提出した。 大久保が目標としていた国家はプロイセン(ドイツ)であるとも、イギリスであるともいわれる。当時、大久保への権力の集中は「有司専制」として批判された。また、現在に至るまでの日本の官僚機構の基礎は、内務省を設置した大久保によって築かれたともいわれている。
2024年09月06日
閲覧総数 40
-
44

「幕藩一揆の攻防」14、希れに見る三十万の一揆に藩は譲歩【元文一揆】
14、希れに見る三十万の一揆に藩は譲歩【元文一揆】「元文一揆」(げんぶんいっき)は、元文4年(1739)2月に鳥取藩で起きた大規模な百姓一揆。勘右衛門騒動ともいわれる。この一揆には藩領である因幡国と伯耆国の合わせ約5万人が参加したとされ、藩政史上最大の百姓一揆といわれる。(当時の因幡・伯耆の人口は約30万人程度であるから、実に総人口の6分の1が参加したことになる)当時、鳥取藩においては飢饉などによる藩政の混乱が続き、加えて藩主・池田吉泰に重用された米村広治・広当ら米村派とその改革に批判的な物頭派の対立は藩政の混乱に拍車をかけていた。 そのような中におきた元文3年(1738)の長雨は藩内全域に被害をもたらし、合計で約3万1000石余りの損害が生じた。年貢不足に苦しむ百姓の間には入牢者も相次ぐようになり、鳥取城下に食べ物を乞いに出て行く者も現れるようになっていたが、藩は救済策を講じず、郡代などを勤める米村広当の取り立ては厳しいままであった。藩民の不満が募っていく中、八東郡東村の松田勘右衛門らは、状況を打開しようと一揆を計画し、因幡・伯耆の各所に応援を求めた。鳥取藩側の史料である『御国日記』などによれば、一揆は元文4年(1739年)2月19日に因幡国岩井郡から始まり、一行は八東郡へ向かったという。その一方で当時岩井郡の大庄屋を務めていた中村半兵衛の日記・『御用日記』には「(半兵衛の下から派遣された)谷田利平らが一揆勢の中に岩井郡の者が一人もいないことを確認して帰ってきた」とする記述がある。一説に2月11日~12日にかけて岩井郡で不穏な動きが見られたことが原因とされる。しかし、この件に関しては一揆発生前に取調べが終了し、庄屋が閉門に処せられるなど沈静化した様子が見られることから、一揆との直接的な関係があったのかは不明である。2月20日、西御門村で勘右衛門らと合流した一揆勢は若桜の大庄屋・木島市郎右衛門の屋敷を打ち壊した。一報を聞いて駆けつけた在吟味役・小谷新右衛門、郡奉行・安田清左衛門ら藩の役人を追い返した一揆勢は各地で年貢の取立てに熱心な大庄屋などの住む屋敷の打毀しを行い、食事などの支給を受けながら城下の鳥取へと向かった。一方、伯耆においても因幡での動きに呼応して各地から参加者が集まり、城下へ向かった。途中、気多郡・高草郡を通過し、約2万人に膨れ上がった伯耆勢は打ち壊しなどの破壊行為は行わず、因幡勢より一足早く到着、城下近郊の千代川河川敷に集結した。2月23日、24日にかけては因幡勢が合流、最終的に約5万人あまりに膨れ上がったという。藩側は一揆勢を刺激しないように勤め、鳥取の町目付を派遣して対応、一揆勢からの願書を受理した。また、2月23日付けで郡代・米村広当らを罷免・閉門に処し、翌日には前の郡代・松井番右衛門を後任として対応させた。2月25日、松井番右衛門は12条から成る回答書を一揆勢に提示、一部の参加者は村へ帰るものも現れたが、大半の者は残っており、また新たに願書を提出した。これも受理されたようだが、内容については不明である。2月26日には一部の者が城下へ乱入を試みるも失敗、翌日には目付らの説得と長期化による疲労により、ほとんどの参加者が帰宅した。2月27日、大半の一揆参加者が帰宅したその日から藩は首謀者の捜索と逮捕を開始した。その日のうちに鳥取城下の長屋に潜伏していた松田勘右衛門兄弟らを逮捕、2月から3月にかけて数十名を逮捕した。しかし捜査が進むにつれ、武士の間にも一揆首謀者との接触が判明した者が現れ始めたために、処罰は大規模な一揆にもかかわらず最小限に止められた。武士の中では、一揆に同情的であった上野忠親、一揆勢から要職登用の願いがあった福住弥一兵衛、首謀者が隠れていた長屋の持ち主であった永原弥左衛門らが閉門や暇を出されている(これには一揆首謀者の松田勘右衛門が以前より出仕を希望して、役所などに出入りを繰り返し、役人などと接触していたからとされる)。取り調べ開始から1年以上経った元文5年(1740)11月21日、一揆の首謀者・松田勘右衛門らの処刑が執行された。それと同時に処罰された関係者40名あまりが追放刑に処せられた。 また、一揆のもたらした混乱と影響は大きく、完全な沈静化には時間がかかった。一揆が終結して1ヶ月ほど経った3月下旬には藩から出された通達が一揆勢の要求とは異なるとして伯耆国西部で打ち壊しが起こったほか、伯耆では新たな一揆を行うとする噂が立つなど不穏な情勢が続いた。これら一揆の余波は藩側が沈静化させようと努力した結果4月下旬になってようやく完全に静まった。一揆後、米村広当は国外へ退去し、藩の中枢における米村派の影響は著しく低下した。しかし、一揆勢が登用を求めていた武士の多くは閉門などに処せられ、あまり藩政の変化などは見られなかったが、大規模な一揆を目の当たりにした鳥取藩は新藩主・池田宗泰の進める改革の下で農民に対する一定の配慮を見せるようになった。
2023年08月14日
閲覧総数 92
-
45

「戦後日本の回想・S21] 吉田茂の出自。 川村一彦
生い立ち1878年(明治11年)9月22日、高知県宿毛出身の自由民権運動の闘士で板垣退助の腹心だった竹内綱の五男として東京神田駿河台(のち東京都千代田区)[注 1]に生まれる。父親が反政府陰謀に加わった科で長崎で逮捕されてからまもないことであった。実母の身元はいまでもはっきりしない。竹内の投獄後に東京へ出て竹内の親友、吉田健三の庇護のもとで茂を生んだ。吉田の実父と義父は若い武士として1868年(慶応4、明治元年)の明治維新をはさむ激動の数十年間に名を成した者たちであった。その養母は徳川期儒学の誇り高い所産であった。1881年(明治14年)8月に、旧福井藩士で横浜の貿易商(元ジャーディン・マセソン商会・横浜支店長)・吉田健三の養子となる。ジョン・ダワーによると、「竹内もその家族もこの余計者の五男と親しい接触を保っていたようにはみえない」という。養父・健三が40歳の若さで死去し、11歳の茂は莫大な遺産を相続した[2]。吉田はのちにふざけて「吉田財閥」などといっている。学生時代少年期は、大磯町西小磯で義母に厳しく育てられ、戸太町立太田学校(後の横浜市立太田小学校)を卒業後、1889年(明治22年)2月、耕余義塾に入学し、1894年(明治27年)4月に卒業すると、10年余りに渡って様々な学校を渡り歩いた。同年9月から、日本中学(日本学園の前身)へ約1年通った後、1895年(明治28年)9月、高等商業学校(一橋大学の前身)に籍をおくが商売人は性が合わないと悟り、同年11月に退校。1896年(明治29年)3月、正則尋常中学校(正則高等学校の前身)を卒業し、同年中に慶應義塾・東京物理学校(東京理科大学の前身)に入学しているがいずれも中退。1897年(明治30年)10月に学習院に入学、1901年(明治34年)8月に旧制学習院高等学科(のちの旧制学習院高等科、学習院大学の前身)を卒業した。同年9月、当時華族の子弟などを外交官に養成するために設けられていた学習院大学科に入学、このころにようやく外交官志望が固まったが、大学科閉鎖に伴い1904年(明治37年)同年9月に無試験で東京帝国大学法科大学に移り、1906年(明治39年)7月、政治科を卒業、同年9月、外交官および領事官試験に合格し、外務省に入省する。同期入省者には首席で合格した広田弘毅の他、武者小路公共、池邊龍一、林久治郎、藤井實らがいた。外交官時代当時外交官としての花形は欧米勤務だったが、吉田は入省後20年の多くを中国大陸で過ごしている。中国における吉田は積極論者であり、満州における日本の合法権益を巡っては、しばしば軍部よりも強硬であったとされる。吉田は合法満州権益は実力に訴えてでも守るべきだという強い意見の持ち主で、1927年(昭和2年)後半には、田中首相や陸軍から止められるほどであった。しかし、吉田は、満州権益はあくまで条約に基礎のある合法のもの以外に広げるべきではないという意見であり、満州事件以後もその点で一貫していた。中華民国の奉天総領事時代には東方会議へ参加。政友会の対中強硬論者である森恪と連携し、いわゆる「満蒙分離論」を支持。1928年(昭和3年)、田中義一内閣の下で、森は外務政務次官、吉田は外務次官に就任する。但し外交的には覇権国英米との関係を重視し、この頃第一次世界大戦の敗北から立ち直り、急速に軍事力を強化していたドイツとの接近には常に警戒していたため、岳父・牧野伸顕との関係とともに枢軸派からは「親英米派」とみなされた。統計をつかさどる中央統計委員会委員を兼ねた。1936年(昭和11年)は、二・二六事件から2か月後に駐イギリス大使となった。大命を拝辞した盟友の近衛文麿から広田への使者を任されて広田内閣で組閣参謀となり、外務大臣・内閣書記官長を予定したが、寺内寿一ら陸軍の反対で叶わなかった。駐英大使としては日英親善を目指すが、極東情勢の悪化の前に無力だった。また、日独防共協定および日独伊三国同盟にも強硬に反対した。1939年(昭和14年)待命大使となり外交の一線からは退いた。太平洋戦争(大東亜戦争)開戦前には、ジョセフ・グルー米大使や東郷茂徳外相らと頻繁に面会して開戦阻止を目指すが実現せず、開戦後は牧野伸顕、元首相近衛ら重臣グループの連絡役として和平工作に従事(ヨハンセングループ)し、ミッドウェー海戦敗北を和平の好機とみて近衛とともにスイスに赴いて和平へ導く計画を立てるが、その後の日本軍の勝利などにより成功しなかった。その後、日本の敗色が濃くなると、殖田俊吉を近衛文麿に引き合わせ後の近衛上奏文につながる終戦策を検討。しかし書生として吉田邸に潜入したスパイ(=東輝次)によって1945年(昭和20年)2月の近衛上奏に協力したことが露見し憲兵隊に拘束される。ただし、同時に拘束された他の者は雑居房だったのに対し、吉田は独房で差し入れ自由という待遇であった(親交のあった阿南惟幾陸相の配慮によるものではないかとされている)。40日あまり後に不起訴・釈放となったが、この戦時中の投獄が逆に戦後は幸いし「反軍部」の勲章としてGHQの信用を得ることになったといわれる。
2023年10月15日
閲覧総数 53
-
46

「蜂須賀氏一族の群像」蜂須賀重喜。
「蜂須賀 重喜」(はちすか しげよし)は、阿波徳島藩第10代藩主。号は公熙、南山、清風齋。元文3年(1738年)、出羽秋田新田藩2代藩主・佐竹義道の四男に生まれる。母は内藤政森の娘。幼名は岩五郎、初名は佐竹義居(さたけ よしすえ)。宝暦4年(1754)8月25日、阿波徳島藩第9代藩主・蜂須賀至央の末期養子として第10代藩主に就任する(至央は第8代藩主・蜂須賀宗鎮の実弟で、兄弟ともに讃岐高松藩松平家の一門松平大膳家からの養子である)。養子入りに際して諱を政胤(まさたね、「政」は藩祖・蜂須賀家政の1字を取ったもの)と改名する。この末期養子は、相次いで後継ぎが早世したために、家老の賀島出雲の提案により決定した。同年9月15日、第9代将軍・徳川家重に御目見する。同年11月25日に元服して家重より偏諱を受けて重喜と改名、従四位下阿波守に叙任する。後に侍従に任官する。宝暦5年(1755)4月15日、初めて領国に入部する許可を得る。留野留川の規制という法令を出し、家中の統制を図る。宝暦・明和期の藩政改革の萌芽と言える(中期藩政改革)。重喜が中心となって行なった改革の内容は、財政再建としての倹約令の施行と、藩体制の変革としての役席役高の制、若年寄の創設などであった。役席役高とは第8代将軍徳川吉宗(家重の父)の享保の改革で行なわれた足高の制を模範としているが、身分序列の崩壊を招いたことで、その性格は異なる。明和6年(1769)10月晦日、藩政宜しからずとして幕府より隠居を命じられ、長男・喜昭(のち治昭に改名)に家督を譲る。重喜32歳歳。隠居後は明和7年(1770)5月、江戸小名木屋敷に移り、大炊頭を称す。安永2年(1773)、療養のため国元へ帰り大谷別邸に住む。天明8年(1788)、かなりの贅沢三昧の生活を幕府に咎められ、江戸屋敷への蟄居を強要されそうになったので、同年8月、阿波の富田屋敷へ移り、江戸行きは免れた。享和元年(1801年)10月20日、富田屋敷で卒去した。享年64歳。蜂須賀家の膨大な蔵書は、重喜以降に増加したと推定される。数代に渡り蜂須賀家が収集した典籍は阿波国文庫と呼ばれる。公家との繋がり蜂須賀家では重喜以降、公家との婚姻が進む。これは、7代藩主蜂須賀宗英(寛保3年(1743)没)の墓が京都の清浄華院にあり、墓参と称した京都入りができた為と言われている。*「蜂須賀 治昭」(はちすか はるあき)は、阿波国徳島藩の第11代藩主。号は敬翁[1]。宝暦7年11月24日(1758)、10代藩主蜂須賀重喜の長男として生まれる。母は立花貞俶の娘・伝姫。幼名は千松丸。やがて父・重喜より偏諱を賜って喜昭(よしあき)を名乗る。明和4年(1767)7月28日、将軍徳川家治に初御目見する。明和6年(1769)10月晦日、父重喜の隠居により、家督を相続するが、父・重喜の失政により出仕をとどめられる。翌明和7年(1770)2月10日に赦される。同年11月7日従四位下阿波守に叙任する。なお、この日に元服し、将軍・家治から偏諱を賜り治昭(はるあき)に改名する。安永元年(1772)12月18日侍従に任官する。安永2年(1773)4月18日在国の許可を得る。文化3年(1806年)、藩祖・蜂須賀家政を祀る國瑞彦神社(徳島市)を建立。文化10年(1813)9月7日隠居し、次男・斉昌に家督を譲る。文化11年(1814)、58歳で死去。蔵書家としても知られていたらしく、足代弘訓は「書物ありきは聖堂なり、次は浅草・守村次郎兵衛(蔵前の札差で俳人)の十万巻、次は阿波の国・蜂須賀治昭の六万巻、次は塙氏(塙保己一)六万巻ばかりあり」と記した[2]。数代に渡り蜂須賀家が収集した典籍は阿波国文庫と呼ばれる。*「蜂須賀 斉昌」(はちすか なりまさ)は、阿波国徳島藩の第12代藩主。寛政7年7月10日(1795)、蜂須賀治昭の次男として生まれる。兄弟たち同様に父より偏諱を受け、諱を初め昭昌(あきまさ)と名乗る。文化6年(1809)、第11代将軍徳川家斉から松平の名字を授与されるとともに、その偏諱を授かり斉昌に改名する。文化10年(1813)9月、父・治昭の隠居にともない跡を継ぐ。この頃になると徳島藩でも財政が悪化していたため、藩政改革が必要となっていた。しかも幕府から甲斐国の河川の築堤などを命じられ、新たに4万5000両も拠出するなど、領民に多大な負担をかけた。子に恵まれなかったため、文政10年(1827)閏6月3日に家斉の二十二男・斉裕を養嗣子に迎えた。やがてこの斉裕が将軍の実子ということで天保6年(1835)12月に斉昌と同じ従四位上に叙せられると、養父としての立場がないと訴えて、天保10年(1839)12月には異例の正四位上叙任が認められるが、その際に老中水野忠邦に対して礼銭名目に4000両もの賄賂を贈ったという噂が庶民にまで広まった(『藤岡屋日記』)。このため、斉昌は財政再建のために徳島藩の特産品とも言えた煙草の専売に乗り出した。さらに、「煙草御口銀」という新たな税を課した。このため、領民は天保12年12月4日(1842)、600人近くが伊予国今治藩に逃散し、その翌年には一揆(山城谷一揆)も起こった。このとき、徳島藩は一揆の首謀者を処罰できなかったと言われており、領民の怒りが凄まじかったことがうかがえる。
2024年05月27日
閲覧総数 26
-
47

「歌川広重の群像」広重の出自と家業。 川村一彦
2「歌川 広重の出自と家業」(うたがわ ひろしげ、寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日)は、江戸時代の浮世絵師。本名は安藤重右衛門。かつては安藤広重(あんどう ひろしげ)とも呼ばれたが、安藤は本姓・広重は号であり、両者を組み合わせて呼ぶのは不適切で、広重自身もそう名乗ったことはない。 江戸の定火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、 火消、火消し(ひけし)とは、江戸時代の消防組織とその構成員である]。 消防組織としての火消は、江戸においては江戸幕府により、頻発する火事に対応する防火・消火制度として定められた。 武士によって組織された武家火消(ぶけびけし)と、町人によって組織された町火消(まちびけし)に大別される。武家火消は幕府直轄で旗本が担当した定火消(じょうびけし)と、大名に課役として命じられた大名火消(だいみょうびけし)に分けて制度化されたため、合わせて3系統の消防組織が存在していた。 江戸時代初期には火消の制度が定められておらず、度重なる大火を契機にまず武家火消が制度化され、発達していった。 江戸時代中期に入ると、享保の改革によって町火消が制度化される。そののち、江戸時代後期から幕末にかけては、町火消が武家火消に代わって江戸の消防活動の中核を担うようになっていった。 江戸以外の大都市や各藩の城下町などでも、それぞれ火消の制度が定められていた。これらの消防組織は、明治維新後に廃止・改編されるが、その系譜は現代の消防署・消防団へと繋がっている。 消防組織の構成員としての火消は、火消人足(ひけしにんそく)ともいう。定火消の配下であった臥煙(がえん)、町火消の中核をなした鳶人足(とびにんそく、鳶職)などがあげられる。 組織ごとの対抗心や気性の荒さから、「加賀鳶と定火消の喧嘩」や「め組の喧嘩」などの騒動を起こすこともあった。火消人足による消火の方法は、火事場周辺の建物を破壊し延焼を防ぐ破壊消防(除去消火法)が用いられ、明和年間ごろからは竜吐水(りゅうどすい、木製手押ポンプ)なども補助的に使用された。 江戸と火事 火消制度は、江戸において発展を遂げ、その構成員が1万人を上回る時期も長く存在した大規模なものであった。 これは、慶長6年(1601年)から慶応3年(1867年)の267年間に大火だけで49回、小火も含めると1798回もの火事が発生したという、江戸の特異な事情が大きく影響している。江戸の武家火消 江戸時代初期 江戸時代初期の江戸では、火消の制度が定められていなかった。江戸城が火事となった場合には老中・若年寄が大番組・書院番組・鉄砲組などの旗本に命じて消火を行った。 江戸市中においては、大名屋敷や旗本屋敷など武家地で火事となった場合は付近の大名・旗本が自身で、長屋・商家など町人地での火事は町人自身が消火を行なうという状態であり、組織的な消防制度は存在しなかった。 幕府が慶長18年(1613年)に出した禁令では、町人地の火事に武家奉公人が駆けつけることを禁じており、武家地と町人地を明確に区分する方針であったことも影響している。 奉書火消 奉書火消(ほうしょびけし)は、寛永6年(1629年)、第3代将軍徳川家光の時代にはじまる火消。 これは火事の際、老中の名で「奉書」を諸大名に送り、召集して消火に当たらせるというものである。 この方法は、火事が起きてから奉書を用意して大名に使者を出し、使者を受けて大名が家臣を引き連れ現場に向かうという、迅速さに欠けるものであった。また、駆けつける大名や家臣にしても、常時より消火の訓練を行なっているわけではなく、火事に対して有効な手段とはならなかった。 所々火消 所々火消(しょしょびけし)は、寛永16年(1639年)にはじまる火消。 同年に江戸城本丸が火事となったことを契機に、江戸城内の紅葉山霊廟に対する消防役を、譜代大名の森川重政に命じたことがはじまりである。 この所々火消は、後述の大名火消の中で担当場所が定められていたものであり、幕府にとっての重要地を火事から守るため設けられた、専門の火消役であった。 所々火消が定められた場所は元禄年間にかけて増加し、江戸城各所をはじめ、寛永寺・増上寺などの寺社、両国橋・永代橋などの橋梁、本所御米蔵などの蔵を、36大名が担当するようになった。のちに享保7年(1722年)、第8代将軍徳川吉宗により、重要地11箇所をそれぞれ1大名に担当させる方式に改編された。 担当場所は、江戸城内の5箇所(紅葉山霊廟・大手方・桜田方・二の丸・吹上)、城外の蔵3箇所(浅草御米蔵・本所御米蔵・本所猿江材木蔵)、寺社3箇所(上野寛永寺・芝増上寺・湯島聖堂)である。 江戸城内の最重要地に対する所々火消は譜代大名に命じられ、外様大名が命じられたのは本所御米蔵など江戸城外の施設であった。 大名火消 大名火消(だいみょうびけし)は、寛永20年(1643年)にはじまる火消。 寛永18年1月29日(1641年3月10日)正月、京橋桶町から発生した火事は、江戸の大半を焼くという大きな被害を出した。 この桶町火事に際しては、将軍家光自身が大手門で指揮を取り、奉書により召集した諸大名にも消火活動を行なわせたものの、火勢を食い止めることはできなかった。 消火の陣頭指揮を執っていた大目付加賀爪忠澄は煙に巻かれて殉職。消火活動を行っていた相馬藩主相馬義胤が事故で重傷を負った。 幕府は関係役人およびこれまでの奉書火消を担当した大名らを集めて検討した結果、桶町火事より2年後の寛永20年(1643年)、幕府は6万石以下の大名から16家を選び、4組に編成して新たな火消役を設けた。 従来の奉書火消を制度化したものであり、この火消役は選ばれた大名自らが指揮を取った。1万石につき30人ずつの定員420人を1組とし、1組は10日交代で消火活動を担当した。 火事が発生すると火元に近い大名が出動し、武家地・町人地の区別なく消火を行なうとされていた。 大火の場合には従来通り老中から奉書を送り、正式に召集して消火に当たらせた。これはそれまでの奉書火消と区別して増火消(ましびけし)と呼ばれる。 大名火消は火事が起こると、華麗な火事装束に身を包んだ家臣に隊列を組ませ、現場まで行進して消火活動に当たった。 大名自らが火事場に向かうこともあってその火事装束は次第に華美で派手なものとなり、たびたび幕府によって規制されている。 しかし傾向は変わらず、なかには消火活動中に装束の着替えを3度も行なう大名まであらわれ、そのため大勢の見物人が集まってきたという例もある。 明暦の大火以降 明暦3年(1657年)正月、本郷から発生した火事は、江戸の歴史上最悪の被害となった。明暦の大火(振袖火事)と呼ばれるこの火事のため、江戸城天守閣は焼失し、江戸市中で約68000人ともされる犠牲者を出した。 明暦の大火により、従来の方法では大火に対処できないことが明らかになったため、以後の江戸幕府は消防制度の確立に力を注いだ。 江戸市中の再建では、大名屋敷・旗本屋敷や寺社の一部を郊外に移転させ、延焼を防ぐための火除地を確保した。また、瓦葺屋根や土蔵造りなどの耐火建築を奨励し、火事に強い町づくりを目指した。そして、新たな消防組織である方角火消・定火消を編成している。 方角火消 方角火消(ほうがくびけし)は、明暦3年(1657年)、第4代将軍徳川家綱の時代にはじまる火消。 明暦の大火直後に大名12名を選び、桜田筋・山手筋・下谷筋の3組で編成した火消役がはじまりである。 大名火消の一種で、担当区域に火事が発生すると駆けつけて消火に当たることとなっていた。元禄年間にかけて東西南北の4組に改編され、方角火消と呼ばれるようになった。正徳2年(1712年)、5方角5組に改編。享保元年(1716年)以降は大手組・桜田組の2組(4名ずつ計8大名)に改編され、火事の際はそれぞれ大手門・桜田門に集結した。 大手組・桜田組への改編後は、主に江戸城の延焼防止を目的として活動し、江戸城内の火事以外では老中の指示を受けてから出動した。消火の主力ではなく、火元から離れた場所で火を防ぐため、防大名(ふせだいみょう)とも呼ばれた。 担当は参勤交代で江戸に滞在中の大名から選ばれ、屋敷では通常より高い火の見櫓の建築が許された。 方角火消や所々火消の定員は大名の石高によって異なっていた。1万石以上では騎馬3~4騎、足軽20人、中間・人足30人。10万石以上では騎馬10騎、足軽80人、中間・人足140-150人。20万石以上で騎馬15-20騎、足軽120-130人、中間・人足250-300人、などである。 定火消 定火消(じょうびけし、江戸中定火之番)は、万治元年(1658年)にはじまる幕府直轄の火消。 明暦の大火の翌年、4000石以上の旗本4名(秋山正房・近藤用将・内藤政吉・町野幸宣)を選び、それぞれに与力6名・同心30名を付属させて設けられた。幕府直轄の消防組織であり、若年寄の所管、菊間詰の役職であった。 4名の旗本には専用の火消屋敷と火消用具を与え、臥煙と呼ばれる専門の火消人足を雇う費用として300人扶持を加算した。4箇所の火消屋敷はそれぞれ御茶ノ水・麹町半蔵門外・飯田町・小石川伝通院前に設けられ、すべて江戸城の北西であった。 この屋敷の配置は、冬に多い北西の風による、江戸城延焼を防ぐためである。それぞれの担当地域で火事が発生すると、出動して武家地・町人地の区別なく消火活動に当たった。定火消は火事場の治安維持も担当し、鉄砲の所持と演習が許可されていた。 翌年正月の1月4日には、老中稲葉正則の率いる定火消4組が上野東照宮に集結して気勢をあげ、出初(でぞめ)を行なった。これが出初式のはじまりとなり、以降毎年1月4日には上野東照宮で出初が行なわれるようになった。 万治2年・3年にかけて代官町など4箇所、寛文2年(1662年)と元禄8年(1695年)にも日本橋浜町などが追加で設けられ、合わせて15組が江戸城を取りまくように配置された。 しかし、宝永元年(1704年)以降は10組(定員1280名)での編成となる。このため、総称して十人屋敷や十人火消などとも呼ばれた。10箇所の火消屋敷の場所は、赤坂溜池・赤坂門外・飯田町・市谷左内坂・小川町・御茶ノ水・麹町半蔵門外・駿河台・八重洲河岸・四谷門外であった。 定火消を命じられた旗本は、妻子とともに火消屋敷で居住した。火消屋敷は約3000坪の広い敷地を持ち、緊急出動用に馬も準備されていた。敷地内には3丈(約9.1m)の火の見櫓が設けられ、合図のため太鼓と半鐘がそなえられていた。この火消屋敷が、現在の消防署の原型である。 屋敷内には臥煙の寝起きする詰所があり、夜には長い1本の丸太を枕として並んで就寝した。夜に火事の連絡が入ると、不寝番がこの丸太の端を槌で叩き、臥煙を一斉に起こして出動した。
2024年10月14日
閲覧総数 50
-
48

「歴史の回想・御館の乱」御館の乱の起因。 川村一彦」
2「御館の乱の起因」(おたてのらん)は、天正6年(1578年)3月13日の上杉謙信急死後、上杉家の家督の後継をめぐって、ともに謙信の養子である上杉景勝(長尾政景の実子)と上杉景虎(北条氏康の実子)との間で起こった越後のお家騒動。景勝が勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となり、後に米沢藩の初代藩主となった。景虎と、景虎に加担した山内上杉家元当主・上杉憲政らは敗死した。御館とは、謙信が関東管領上杉憲政を越後に迎えた時に、その居館として春日山城下に建設された関東管領館のことで、後に謙信も政庁として使用した。現在の直江津駅近くに当時の御館の跡が御館公園として残っている。 3「謙信の死」上杉 謙信(うえすぎ けんしん) / 上杉 輝虎(うえすぎ てるとら)は、戦国時代の越後国の大名。関東管領(1561年 – 1578年)。山内上杉家16代当主。戦国時代でも屈指の戦上手とされ、その神懸った戦績から後世、軍神や、「越後の龍」などと称された。越後守護・上杉家に仕える越後守護代・長尾為景(三条長尾家)の四男として生まれ、初名は長尾 景虎(ながお かげとら)。1561年(景虎31歳)、関東管領・上杉憲政の養子となり山内上杉氏の家督を譲られ(「上杉」姓と憲政の「政」の1字を与えられ)上杉 政虎(うえすぎ まさとら)と改名し、上杉氏が世襲していた室町幕府の重職関東管領を引き継いだ。後に室町幕府の将軍・足利義輝より偏諱(「輝」の1字)を受けて、最終的には輝虎と名乗った。謙信は、さらに後に称した法号である。内乱続きであった越後国を統一し、戦や政だけではなく、産業を振興して国を繁栄させた。他国から救援を要請されると秩序回復のために幾度となく出兵し、武田信玄、北条氏康、織田信長、越中一向一揆、蘆名盛氏、能登畠山氏、佐野昌綱、小田氏治、神保長職、椎名康胤らと合戦を繰り広げた。特に宿敵武田信玄との5回にわたる川中島の戦いはよく知られている。さらに足利将軍家からの要請を受けて上洛を試み、越後国から北陸路を西進して越中国・能登国・加賀国へ勢力を拡大したが48歳で死去した。兜は、飯綱明神前立鉄錆地張兜。謙信には実子がおらず、謙信の死後、上杉家の家督の後継をめぐって御館の乱が勃発した。謙信は、他国から救援を要請されると出兵し、「依怙(えこ)によって弓矢は取らぬ。ただ筋目をもって何方(いずかた)へも合力す」(私利私欲で合戦はしない。ただ、道理をもって誰にでも力を貸す)『白河風土記』と述べている。また、謙信が敵将武田信玄に塩を送った逸話から、「敵に塩を送る」という故事も生まれた。出生から初陣まで享禄3年(1530年)1月21日、越後守護代・長尾為景(三条長尾家)の四男(または次男、三男とも)虎千代として春日山城に生まれる。母は同じく越後栖吉城主・長尾房景(古志長尾家)の娘・虎御前。幼名の虎千代は庚寅年生まれのために名づけられた。主君・上杉定実から見て「妻の甥」であり「娘婿の弟」にあたる。当時の越後国は内乱が激しく、下剋上の時代にあって父・為景は戦を繰り返していた。越後守護・上杉房能を自害に追い込み、次いで関東管領・上杉顕定を長森原の戦いで討ち取った。次の守護・上杉定実を傀儡化して勢威を振るったものの、越後国を平定するには至らなかった。虎千代誕生直後の享禄3年(1530年)10月には上条城主・上杉定憲が旧上杉家勢力を糾合し、為景に反旗を翻す。この兵乱に阿賀野川以北に割拠する揚北衆らだけでなく、同族の長尾一族である上田長尾家当主・長尾房長までもが呼応した。越後長尾家は、蒲原郡三条を所領し府内に居住した三条(府内)長尾家、古志郡を根拠地とする古志長尾家、魚沼郡上田庄を地盤とする上田長尾家の三家に分かれて守護代の地位を争っていた。しかしやがて三条長尾家が守護代職を独占するようになる。上田長尾房長はそれに不満を抱いて、定憲の兵乱に味方したのであった。為景は三分一原の戦いで勝利するも、上田長尾家との抗争は以後も続き、次代の上田長尾家当主・長尾政景の謀反や御館の乱へと発展する。天文5年(1536年)8月に為景は隠居し、虎千代の兄・晴景が家督を継いだ。虎千代は城下の林泉寺に入門し[6]、住職の天室光育の教えを受けたとされる。実父に疎んじられていたため、為景から避けられる形で寺に入れられたとされている。武勇の遊戯を嗜み、左右の人を驚嘆させた。また好んで、一間四方の城郭模型で遊んでいた。後年、景勝がこの模型を武田勝頼の嫡男信勝に贈っている。天文11年(1542年)12月、為景は病没したが、敵対勢力が春日山城に迫ったため、虎千代は甲冑を着け、剣を持って亡父の柩を護送した。兄・晴景に越後国をまとめる才覚はなく、守護・上杉定実が復権し、上田長尾家、上杉定憲、揚北衆らの守護派が主流派となって国政を牛耳る勢いであった。天文12年(1543年)8月15日、虎千代は元服して長尾景虎と名乗り、9月には晴景の命を受け、古志郡司として春日山城を出立して三条城、次いで栃尾城に入る。その目的は中郡(なかごおり)の反守護代勢力を討平した上で長尾家領を統治し、さらに下郡(しもごおり)の揚北衆を制圧することであった。当時、越後では守護・上杉定実が伊達稙宗の子・時宗丸(伊達実元)を婿養子に迎える件で内乱が起こっており、越後の国人衆も養子縁組に賛成派と反対派に二分されていたが、兄の晴景は病弱なこともあって内紛を治めることはできなかった。景虎が元服した翌年の天文13年(1544年)春、晴景を侮って越後の豪族が謀反を起こした。15歳の景虎を若輩と軽んじた近辺の豪族は栃尾城に攻めよせた。しかし景虎は少数の城兵を二手に分け、一隊に傘松に陣を張る敵本陣の背後を急襲させた。混乱する敵軍に対し、さらに城内から本隊を突撃させることで壊滅させることに成功。謀反を鎮圧することで初陣を飾った(栃尾城の戦い)。家督相続・越後統一天文14年(1545年)10月、守護上杉家の老臣で黒滝城主の黒田秀忠が長尾氏に対して謀反を起こした。秀忠は守護代・晴景の居城である春日山城にまで攻め込み、景虎の兄・長尾景康らを殺害、その後黒滝城に立て籠もった。景虎は、兄に代わって上杉定実から討伐を命じられ、総大将として軍の指揮を執り、秀忠を降伏させた(黒滝城の戦い)。だが、翌年の天文15年(1546年)2月、秀忠が再び兵を挙げるに及び再び攻め寄せて攻撃を加え、二度は許さず黒田氏を滅ぼした。するとかねてから晴景に不満をもっていた越後の国人の一部は景虎を擁立し晴景に退陣を迫るようになり、晴景と景虎との関係は険悪なものとなった。天文17年(1548年)になると、晴景に代わって景虎を守護代に擁立しようとの動きが盛んになる。その中心的役割を担ったのは揚北衆の鳥坂城主・中条藤資と、北信濃の豪族で景虎の叔父でもある中野城主・高梨政頼であった。さらに栃尾城にあって景虎を補佐する本庄実乃、景虎の母・虎御前の実家である栖吉城主・長尾景信(古志長尾家)、与板城主・直江実綱、三条城主・山吉行盛らが協調し、景虎派を形成した。これに対し、坂戸城主・長尾政景(上田長尾家)や蒲原郡奥山荘の黒川城主・黒川清実らは晴景についた。同年12月30日、守護・上杉定実の調停のもと、晴景は景虎を養子とした上で家督を譲って隠退し、景虎は春日山城に入り、19歳で家督を相続し、守護代となる。天文19年(1550年)2月、定実が後継者を遺さずに死去したため、景虎は室町幕府第13代将軍・足利義輝から越後守護を代行することを命じられ、越後国主としての地位を認められた。同年12月、一族の坂戸城主・長尾政景(上田長尾家)が景虎の家督相続に不満を持って反乱を起こした。不満の原因は景虎が越後国主となったことで、晴景を推していた政景の立場が苦しくなったこと、そして長年に亘り上田長尾家と対立関係にあった古志長尾家が、景虎を支持してきたために発言力が増してきたことであった。天文20年(1551年)1月、景虎は政景方の発智長芳(ほっち ながよし)の居城・板木城を攻撃し、これに勝利。さらに同年8月、坂戸城を包囲することで、これを鎮圧した(坂戸城の戦い)。降伏した政景は景虎の姉・仙桃院の夫であったこと等から助命され、以降は景虎の重臣として重きをなす。政景の反乱を鎮圧したことで越後国の内乱は一応収まり、景虎は22歳で越後統一を成し遂げたのである。一方で上田長尾家と古志長尾家の敵対関係は根深く残り、後の御館の乱において、上田長尾家は政景の実子である上杉景勝に、古志長尾家は上杉景虎に加担した。その結果、敗れた古志長尾家は滅亡するに至った。第一次〜第三次川中島の戦い天文21年(1552年)1月、関東管領・上杉憲政は相模国の北条氏康に領国の上野国を攻められ、居城の平井城を棄て、景虎を頼り越後国へ逃亡してきた。景虎は憲政を迎え、御館に住まわせる。これにより氏康と敵対関係となった。8月、景虎は平子孫三郎、本庄繁長等を関東に派兵し、上野沼田城を攻める北条軍を撃退、さらに平井城・平井金山城の奪還に成功する。北条軍を率いる北条幻庵長綱は上野国から撤退、武蔵松山城へ逃れた。なおこの年の4月23日、従五位下弾正少弼に叙任される。同年、武田晴信(後の武田信玄)の信濃侵攻によって、領国を追われた信濃守護・小笠原長時が景虎に救いを求めてくる。さらに翌・天文22年(1553年)4月、信濃国埴科郡葛尾城主の村上義清が晴信との抗争に敗れて葛尾城を脱出し、景虎に援軍を要請した。義清は景虎に援軍を与えられ村上領を武田軍から奪還するため出陣、同月に武田軍を八幡の戦いで破ると武田軍を村上領から駆逐し、葛尾城も奪還する。しかし一端兵を引いた晴信軍だったが、7月に再度晴信自ら大軍の指揮を執って村上領へ侵攻すると、義清は再び越後国へ逃亡。ここに及んで景虎は晴信討伐を決意し、ついに8月、自ら軍の指揮を執り信濃国に出陣。30日、布施の戦いで晴信軍の先鋒を圧倒、これを撃破する。9月1日には八幡でも武田軍を破り、さらに武田領内へ深く侵攻し荒砥城・青柳城・虚空蔵山城等、武田方の諸城を攻め落とした。これに対し晴信は本陣を塩田城に置き決戦を避けたため、上洛の予定があった景虎は深追いをせず、9月に越後へ引き上げた(第一次川中島の戦い)。天文22年(1553年)9月、初めての上洛を果たし、後奈良天皇および将軍・足利義輝に拝謁している。京で参内して後奈良天皇に拝謁した折、御剣と天盃を下賜され、敵を討伐せよとの勅命を受けた。この上洛時に堺を遊覧し、高野山を詣で、京へ戻って臨済宗大徳寺91世の徹岫宗九(てつしゅうそうく)のもとに参禅して受戒し「宗心」の戒名を授けられた。天文23年(1554年)、家臣の北条高広が武田と通じて謀反を起こしたが、天文24年(1555年)には自らが出陣して高広の居城・北条城を包囲し、これを鎮圧した(北条城の戦い)。高広は帰参を許される。この間、晴信は善光寺別当栗田鶴寿を味方につけ旭山城を支配下に置いた。これに対抗するため景虎は同年4月に再び信濃国へ出兵し、晴信と川中島の犀川を挟んで対峙した(第二次川中島の戦い)。また、裾花川を挟んで旭山城と相対する葛山城を築いて付城とし、旭山城の武田軍を牽制させた。景虎は、犀川の渡河を試みるなど攻勢をかけたものの、小競り合いに終始して決着はつかず。対陣5ヶ月に及び最終的に晴信が景虎に、駿河国の今川義元の仲介のもとで和睦を願い出る。武田方の旭山城を破却し武田が奪った川中島の所領をもとの領主に返すという、景虎側に有利な条件であったため、景虎は和睦を受け入れ軍を引き上げた。ところが弘治2年(1556年)3月、景虎は家臣同士の領土争いや国衆の紛争の調停で心身が疲れ果てたため、突然出家・隠居することを宣言し、同年6月には天室光育に遺書を託し(「歴代古案」)、春日山城をあとに高野山に向かう。しかしその間、晴信に内通した家臣・大熊朝秀が反旗を翻す。天室光育、長尾政景らの説得で出家を断念した景虎は越後国へ帰国。一端越中へ退き再び越後へ侵入しようとした朝秀を打ち破る(駒帰の戦い)。弘治3年(1557年)2月、晴信は盟約を反故にして長尾方の葛山城を攻略、さらに信越国境付近まで進軍し、景虎方の信濃豪族・高梨政頼の居城・飯山城を攻撃した。景虎は政頼から救援要請を受けるも、信越国境が積雪で閉ざされていたため出兵が遅れる。雪解けの4月、晴信の盟約違反に激怒した景虎は再び川中島に出陣する(第三次川中島の戦い)。高井郡山田城、福島城を攻め落とし、長沼城と善光寺を奪還。横山城に着陣して、さらに破却されていた旭山城を再興して本営とした。5月、景虎は武田領内へ深く侵攻、埴科郡・小県郡境・坂木の岩鼻まで進軍する。しかし景虎の強さを知る晴信は、深志城から先へは進まず決戦を避けた。7月、武田軍の別働隊が長尾方の安雲郡小谷城を攻略。一方の長尾軍は背後を脅かされたため、飯山城まで兵を引き、高井郡野沢城・尼巌城を攻撃する。その後8月、両軍は髻山城(近くの水内郡上野原で交戦するも、決定的な戦いではなかった。弘治4年(1558年)、将軍・義輝から上洛要請があり、翌年上洛することを伝える。また『宇都宮興廃記』によれば同年、上野国経由で下野国に侵攻し、小山氏の祇園城と壬生氏の壬生城を攻略、さらに宇都宮氏の宇都宮城を攻略するために多功城、上三川城を攻めるが、多功城主の多功長朝によって先陣の佐野豊綱が討ち取られると軍が混乱したために景虎は軍を引き上げた。多功長朝率いる宇都宮勢は上野国の白井城まで景虎を追撃してきたが、武蔵国岩槻城主の太田氏の仲介によって和睦をしている。その翌年の永禄2年(1559年)3月、高梨政頼の本城・中野城が武田方の高坂昌信の攻撃により落城。景虎が信濃国へ出兵できない時期を見計って、晴信は徐々に善光寺平を支配下に入れていった。小田原城の戦い永禄2年(1559年)5月、再度上洛して正親町天皇や将軍・足利義輝に拝謁する。このとき、義輝から管領並の待遇を与えられた(上杉の七免許)。室町幕府の記録の後鑑(江戸末期に江戸幕府が編纂したモノ)には、関東管領記、関東兵乱記(相州兵乱記)、春日山日記(上杉軍記)を出典として掲載されている。 また、内裏修理の資金を献上したともいうが、朝廷の記録である御湯殿上日記には、永禄3年6月18日に、越後の長尾(景虎)が内裡修理の任を請う、という記述があるだけで、年次や記述内容に違いがある。 言継卿記には、永禄2年5月24日、越後国名河(長尾)上洛云々、武家御相判御免、1,500人。という記述であり、上杉家譜などの兵5,000という記述と異なる。なお、天野忠幸はこの年に景虎だけではなく、織田信長や斎藤義龍も急遽上洛していることに注目している。この前年である永禄元年、足利義輝と三好長慶の戦いは長慶が正親町天皇の支持を取り付けて有利な形で和睦しており、曲りなりにも存続してきた室町将軍を頂点とする秩序が大きな打撃を受けた。このため、義輝との関係を維持することで権威を保ってきた諸大名が動揺し、状況を確かめるために上洛に踏み切ったのではないか、と推測している。景虎と義輝との関係は親密なものであったが、義輝が幕府の重臣である大舘晴光を派遣して長尾・武田・北条の三者の和睦を斡旋し三好長慶の勢力を駆逐するために協力するよう説得した際には、三者の考え方の違いが大きく実現しなかった。永禄3年(1560年)3月、越中の椎名康胤が神保長職に攻められ、景虎に支援を要請する。これを受け景虎は初めて越中へ出陣、長職の居城・富山城を落城させる。さらに長職が逃げのびた増山城も攻め落して逃亡させ、康胤を援けた。5月、桶狭間の戦いにより甲相駿三国同盟の一つ今川家が崩れた機会に乗じ、ついに景虎は北条氏康を討伐するため越後国から関東へ向けて出陣、三国峠を越える。上野国に入った景虎は、長野業正らの支援を受けながら小川城・名胡桃城・明間城・沼田城・岩下城・白井城・那波城・厩橋城など北条方の諸城を攻略。厩橋城を関東における拠点とし、この城で越年した。この間、関東諸将に対して北条討伐の号令を下し、檄を飛ばして参陣を求めた。景虎の攻勢を見た関東諸将は、景虎のもとへ結集、兵の数は増大した。景虎は、年が明けると自ら軍の指揮を執り上野国から武蔵国へ進撃。深谷城・忍城・羽生城等を支配下に治めつつ、さらに氏康の居城・小田原城を目指し相模国にまで侵攻、2月には鎌倉を落とした。氏康は、総大将が武略に優れる景虎であるため、野戦は不利と判断。相模の小田原城や玉縄城、武蔵の滝山城や河越城などへ退却し、篭城策をとる。永禄4年(1561年)3月、景虎は関東管領・上杉憲政を擁して、宇都宮広綱、佐竹義昭、小山秀綱、里見義弘、小田氏治、那須資胤、太田資正、三田綱秀、成田長泰ら旧上杉家家臣団を中心とする10万余の軍で、小田原城をはじめとする諸城を包囲、攻撃を開始した(小田原城の戦い)。小田原城の蓮池門へ突入するなど攻勢をかけ、籠城する氏康を追い込む。また小田原へ向かう途上には、関東公方の在所で当時は関東の中心と目されていた古河御所を制圧し、北条氏に擁された足利義氏を放逐のうえ足利藤氏を替りに古河御所内に迎え入れた。小田原城を包囲はしたものの、氏康と同盟を結ぶ武田信玄が川中島で軍事行動を起こす気配を見せ、景虎の背後を牽制。景虎が関東で氏康と戦っている間に、川中島に海津城を完成させてこれを前線基地とし、信濃善光寺平における勢力圏を拡大させた。こうした情勢の中、長期に亘る出兵を維持できない佐竹義昭らが撤兵を要求、無断で陣を引き払うなどした。このため景虎は、北条氏の本拠地・小田原城にまで攻め入りながら、これを落城させるには至らず。1ヶ月にも及ぶ包囲の後、鎌倉に兵を引いた。この後、越後へ帰還途上の4月、武蔵国の中原を押さえる要衝松山城を攻撃し、北条方の城主・上田朝直の抗戦を受けるも、これを落城させる(松山城の戦い)。松山城には城将として上杉憲勝を残し、厩橋城には城代に義弟・長尾謙忠をおいて帰国した。
2024年10月28日
閲覧総数 43
-
49
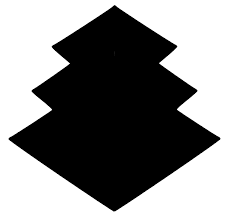
「小笠原氏一族の群像」小笠原庶流。 川村一彦
*「小笠原 長高」(おがさわら ながたか)は、戦国時代の武将。小笠原貞朝の長男。別名は豊松丸、彦五郎。官位は 右馬助、左京大夫。馬伏塚城主。信濃守護の小笠原氏の一族。高天神小笠原氏の祖とされる。父の貞朝は、先妻の武田氏との間に生まれた長男の長高を廃嫡し、後妻の海野氏との間に生まれた次男の長棟を偏愛し、後継者とした。廃嫡された長高は尾張知多郡に出奔して、後に三河幡豆郡に移り、吉良義堯、ついで今川氏親に仕官する。遠江国浅羽荘を領し、馬伏塚城に住する。享年57歳。法名は浄願。長男の小笠原春義が家督を継いだ。】 *「小笠原 信浄」(おがさわら のぶきよ、生年未詳 - 慶長4年4月19日(1599月11日))は、安土桃山時代の武将。津軽氏(大浦氏)の家臣。諱は「信清」とも。伊勢守。元々は信濃国深志郷の出身で、天文年間に陸奥国南部領の明野に移り、明野與四郎と名乗る。天文22年(1553年)頃より大浦為信に仕えた重臣で、さまざまな戦いで貢献したといわれる。森岡信元や兼平綱則らと並んで、大浦三老の一人に数えられている。文禄元年(1592)、木庭袋(きばくら)と改姓し、居土村に隠居した。】 *「小笠原 長国」(おがさわら ながくに、文化9年(1812) - 明治10年(1877)4月23日)は、肥前国唐津藩の第5代(最後)の藩主。忠知系小笠原家13代。信州松本藩主・松平光庸の長男。正室は土屋彦直の娘。子に娘(小笠原長行正室)、娘(藤井松平信庸正室)。官位は従五位下、佐渡守、中務大輔。文政7年(1824)7月9日生まれとも言われている。幼名は賢之進。天保11年(1840)10月に先代藩主小笠原長和が死去した後、翌年4月5にその養嗣子となって跡を継いだ。飢饉などで破綻寸前となった藩財政を再建するために、捕鯨業や炭鉱業の育成・奨励に努めている。初代藩主小笠原長昌(長昌の死後、短命の養子藩主が続き、長国は4人目の養子藩主にあたる)の遺児である長行が成長したため、安政2年(1855)頃からは長行に藩の実権を譲って、藩政改革を行なわせている。しかしこのため、長国を支持する大殿派と長行を支持する若殿派に藩内が分裂して、派閥対立が起こる。長国はこれを鎮めるために長行を養嗣子としている。長行は幕末期に老中を務めており、養父である長国も佐幕派であり、慶応4年(1868)の戊辰戦争でも新政府に容易に与しようとしなかった。このため、唐津藩は近隣の諸藩から討伐対象となり、さらに朝敵の汚名まで着せられそうになったことから、長国は佐賀藩の前藩主鍋島直正を通じて新政府に降伏を申し出た。このとき、最後まで幕府に忠義を尽くして箱館まで転戦していた長行との養子関係を義絶している。明治2年(1869)、版籍奉還により藩知事となったが、明治3年(1870)に藩内で一揆が起こっている。明治4年(1871)の廃藩置県で免官となった。明治6年(1873)9月に隠居し、長行の長男の長生に家督を譲る。明治10年(1877年)4月23日、66歳で死去した。墓所は東京都世田谷区北烏山の幸龍寺(以前は東京都台東区谷中の天王寺)。】 *「小笠原 信浄」(おがさわら のぶきよ、生年未詳 ~ 慶長4年4月19日(1599)6月11日))は、安土桃山時代の武将。津軽氏(大浦氏)の家臣。諱は「信清」とも。伊勢守。元々は信濃国深志郷の出身で、天文年間に陸奥国南部領の明野に移り、明野與四郎と名乗る。天文22年(1553年)頃より大浦為信に仕えた重臣で、さまざまな戦いで貢献したといわれる。森岡信元や兼平綱則らと並んで、大浦三老の一人に数えられている。文禄元年(1592)、木庭袋(きばくら)と改姓し、居土村に隠居した。】 *庶流水上氏・浅原氏・小見氏・跡部氏・打越氏・大井氏・大倉氏・長船氏・大日方氏・下条氏・仁賀保氏・二木氏・根田氏・羽場氏・林氏・伴野氏・船越氏・赤沢氏・井深氏・三好氏・三村氏・三間氏 – 越後長岡藩の抜擢家老を勤めた三間氏、小諸藩大参事を勤めた三間氏、徳川旗本の三間氏がある。了
2024年05月12日
閲覧総数 251
-
50

「小栗忠順の群像」大政奉還と王政復古の大号令。 川村一彦
参預会議解体後の元治元年(1864年)3月25日、慶喜は将軍後見職を辞任し、朝臣的な性格を持つ禁裏御守衛総督に就任した。以降、慶喜は京都にあって武田耕雲斎ら水戸藩執行部や鳥取藩主・池田慶徳、岡山藩主・池田茂政(いずれも徳川斉昭の子、慶喜の兄弟)らと提携し、幕府中央から半ば独立した勢力基盤を構築していく。江戸においては、盟友である政事総裁職・松平直克(川越藩主)と連携し、朝廷の意向に沿って横浜鎖港を引き続き推進するが、天狗党の乱への対処を巡って幕閣内の対立が激化し、6月に直克は失脚、慶喜が権力の拠り所としていた横浜鎖港路線は事実上頓挫する。 同年7月に起こった禁門の変において慶喜は御所守備軍を自ら指揮し、鷹司邸を占領している長州藩軍を攻撃する際は歴代の徳川将軍の中で唯一、戦渦の真っ只中で馬にも乗らず敵と切り結んだ。禁門の変を機に、慶喜はそれまでの尊王攘夷派に対する融和的態度を放棄し、会津藩・桑名藩らとの提携が本格化することとなる(一会桑体制)。また老中の本庄宗秀・阿部正外が兵を率いて上洛し、慶喜を江戸へ連行しようとしたが、失敗した。一方、長期化していた天狗党の乱の処理を巡っては、慶喜を支持していた武田耕雲斎ら水戸藩勢力を切り捨てる冷徹さを見せた。それに続く第一次長州征伐が終わると、欧米各国が強硬に要求し、幕府にとり長年の懸案事項であった安政五カ国条約の勅許を得るため奔走した。慶喜は自ら朝廷に対する交渉を行い、最後には自身の切腹とそれに続く家臣の暴発にさえ言及、一昼夜にわたる会議の末に遂に勅許を得ることに成功したが、京都に近い兵庫の開港については勅許を得ることができず、依然懸案事項として残された。 将軍職 慶応2年(1866年)の第二次長州征伐では、薩摩藩の妨害を抑えて慶喜が長州征伐の勅命を得る。しかし薩長同盟を結んだ薩摩藩の出兵拒否もあり、幕府軍は連敗を喫した。その第二次長州征伐最中の7月20日、将軍・家茂が大坂城で薨去する。当初は慶喜みずから長州征伐へ出陣するとして朝廷から節刀を下賜されたが、小倉城陥落の報に接して出陣を取りやめて今度は朝廷に運動して休戦の詔勅を引き出し、会津藩や朝廷上層部の反対を押し切る形で休戦協定の締結に成功する。 家茂の後継として、老中の板倉勝静、小笠原長行は江戸の異論を抑えて慶喜を次期将軍に推した。慶喜はこれを固辞し、8月20日に徳川宗家は相続したものの、将軍職就任は拒み続け、12月5日に二条城において将軍宣下を受けてようやく将軍に就任した。この頃の慶喜ははっきりと開国を指向するようになっており、将軍職就任の受諾は開国体制への本格的な移行を視野に入れたものであった。 慶喜政権は会津・桑名の支持のもと、朝廷との密接な連携を特徴としており、慶喜は将軍在職中一度も畿内を離れず、多くの幕臣を上洛させるなど、実質的に政権の畿内への移転が推進された。また、慶喜は将軍就任に前後して上級公家から側室を迎えようと画策しており、この間、彼に関白・摂政を兼任させる構想が繰り返し浮上した。一方、これまで政治的には長く対立関係にあった小栗忠順ら改革派幕閣とも連携し、慶応の改革を推進した。ただ寛文印知以来、将軍の代替わりの度に交付していた領知目録等は、最後まで一切交付できなかった。 慶喜はフランス公使・レオン・ロッシュを通じてフランスから240万ドルの援助を受け、横須賀製鉄所や造・修船所を設立し、ジュール・ブリュネを始めとする軍事顧問団を招いて軍制改革を行った。老中の月番制を廃止し、陸軍総裁・海軍総裁・会計総裁・国内事務総裁・外国事務総裁を設置した。また、実弟・徳川昭武(清水家当主とした)をパリ万国博覧会に派遣するなど幕臣子弟の欧州留学も奨励した。兵庫開港問題では朝廷を執拗に説いて勅許を得て、勅許を得ずに兵庫開港を声明した慶喜を糾弾するはずだった薩摩・越前・土佐・宇和島の四侯会議を解散に追い込んだ。 しかし兵庫開港問題を強引に推し進めたことで慶喜への反発は強まった。慶喜の強硬姿勢、上京四侯による内政改革の糸口をつかむことの不可能さ、京坂以西の反幕的政治情勢の深化は、薩摩藩を武力討幕路線へ傾斜させ、薩長芸に土佐藩内の討幕派(土佐は全体としては幕府を含めた雄藩連合を目指す力の方が強かった)が加わる薩藩主導の討幕勢力の形成が進んだ。 大政奉還と王政復古の大号令 土佐の後藤象二郎の大政返上策が薩長土芸の間で合意された。慶喜がこれを受け入れる可能性を信じていなかった西郷隆盛らはこれを武力討幕のシグナルと位置付けていた。そして土佐藩は「天下ノ大政ヲ議スル全権ハ朝廷ニアリ」「我皇国ノ制度法則一切万機必ズ京都ノ議政所ヨリ出ヅベシ」とする上書を慶喜に送った。 慶喜は8月から9月頃までには反徳川雄藩連合の形成が急速に進んでいる情勢に気づいて警戒を強めていた。もしこの土佐の献策を受けねば土佐は全体としても武力討幕派に転じることになり、越前と肥後、肥前、尾張もそれに同調する可能性が高いので受け入れるしかなかった。逆に受け入れれば武力討幕論は主張しにくくなると考えられた。 こうして慶応3年(1867年)10月14日に慶喜は大政返上上表を明治天皇に奏上し、翌日勅許された(大政奉還)。しかし大政奉還されたところで朝廷には何の実力もないため、朝廷は日常政務について「先是迄之通ニテ、追テ可及御沙汰候事」と返答せざるを得ず、結局実態としては慶喜政権が継続されたままとなった。朝廷内で慶喜に与えられる地位についても朝廷内の実権を関白二条斉敬と朝彦親王が握っている限り、また慶喜が800万石の卓絶した大名であり続ける限り、事実上の支配的地位が与えられると考えられた。やがて開催される諸侯会議でも慶喜は多数の支持を期待できたし、京都の軍事情勢を転換させるために江戸から続々と兵が上京中だった。
2024年08月19日
閲覧総数 40










