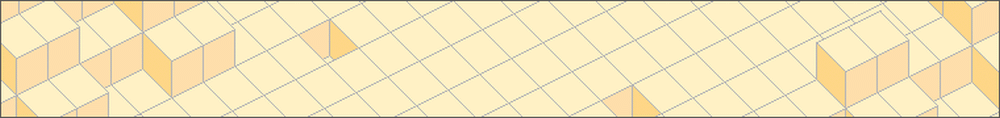2012年03月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

持ってた、斉藤佑樹が完投。そして横浜高OBの明暗~成瀬善久と涌井秀章
■プロ野球が開幕した。今日付の朝日新聞スポーツ面の大見出しは「持ってた 斎藤完投」。ほかのどんな言葉も必要なくて、この表現がすべてを言い表していると思った。9回、被安打4、奪三振7、与四死球4、自責点1。「頭が真っ白というか、興奮してます。ダルさんの穴を絶対埋めるという気持ちで開幕に臨みました。今は"持ってる"ではなくて、背負っています。ダルさんの穴をすき間だらけかもしれないけど、埋められるよう頑張ります」早稲田大時代の「持っている」発言以来、「持っている」ことを証明するために幾度も訪れる試練。それをひとつひとつクリアして、昨日の開幕戦も見事にクリアした。何よりボクは白星よりも完投したことに驚いた。へぇ~、斎藤って完投できるんだ!? と。大学時代はいつも途中降板して大石達也(現・西武)に救援を仰いでいたから。大事な場面での完投勝利、やっぱり斎藤佑樹は「持っている」?■ロッテの開幕投手は成瀬善久、西武は涌井秀章。この横浜高OBがそれぞれ「ハンカチ世代」の楽天・田中将大、日本ハム・斎藤佑樹と投げ合い明暗を分けた。成瀬は開幕投手3度目の挑戦で、初めて白星を挙げた。6回2/3、被安打7、奪三振7、与四死球1、自責点1。「純粋にうれしい。粘りの投球ができてよかった。今年のロッテは違うというところを見せたかった」一方の涌井、5季連続で迎えた開幕マウンドは制球に苦しみ、5回途中で降板した。4回、被安打6、奪三振2、与四死球5、自責点5。「試合を壊してしまって申し訳ない」■2003年、成瀬が横浜高3年、涌井が2年の時、2人は揃ってセンバツに出場し、主に成瀬-涌井のリレーでチームを準Vに導いた。その時のアーカイブを下記に。2回戦 ○横浜高 10-0 盛岡大付高3回戦 ○横浜高 8-4 明徳義塾高(延長12回)準々決勝 ○横浜高 3-0 平安準決勝 ○横浜高 5-3 徳島商高決勝 ●横浜高 3-15広陵高2回戦の盛岡大付高戦は成瀬-涌井のリレーで5安打完封。3回戦の明徳義塾高戦は9回から涌井が好リリーフを見せて勝利。準々決勝の平安高戦は成瀬が完封勝利した。準決勝の徳島商高戦は成瀬が先発、9回2死から涌井が救援して辛勝した。以下、『プロ野球選手の甲子園伝説』(宝島社)より引用。小倉清一郎部長の提案で新チームからメガネをやめ、「栃木の田舎者」から脱皮したエース・成瀬が好投。ストレートは130km前半がやっとだが、我慢の投球で、7回まで4安打1失点。4試合目の疲れもあり、8回、9回には5安打で2点を返されたが、横浜にはまだこの男がいた。涌井秀章だ。2年生で140kmをマークしていた本格派右腕は2点差に詰め寄られた9回二死二塁で登板。ライトフライで試合を終わらせた。「成瀬さんは最後球が行ってなかったので、出番があるかもと思ってました。最後は速い球で押しました」2人が協力して勝ち進んだ横浜高だったが、決勝の広陵高戦は大敗した。この試合先発の涌井が打ち込まれ、4回からリリーフした成瀬もつかまって20安打、15点を献上した。■優勝した広陵高のエースは現・読売の西村健太朗。徳島商高には平岡政樹(現・巨人球団職員、専修大在学中)がいた。またこのセンバツ大会には好投手が揃っていた。東洋大姫路高のグエン・トラン・フォク・アン(元・東芝)、遊学館高の小島達也(現・阪神)、浦和学院高の須永英輝(現・読売)など。ボクが最も記憶しているのは準々決勝の花咲徳栄高対東洋大姫路高戦。福本真史投手とアン投手の投げ合いは、まさに死闘だった。試合はスコア2-2のまま延長15回引き分け。そして翌日再試合も延長戦に。接戦の末延長10回に東洋大姫路が6-5でサヨナラ勝ちした。(※主審は両試合とも林清一さんが務めた)あ、そうそう、この大会にはダルビッシュ有(現・レンジャース)が東北高の2年生エースとして出場していた。 今日も1クリックお願いします
2012.03.31
コメント(0)
-

プロ野球開幕でボクが思い出す2つのこと~1994年西武vs近鉄、そして渡辺恒雄さんの「迷」言
今日(3月30日)プロ野球の開幕にあたり、ボクが思い出すことは2つある。■ひとつ目は1994年開幕戦、西武vs近鉄。近鉄ファンだったボクにとって、この試合は「江夏の21球」「10・19」に匹敵するほどの大事件。苦い思い出として記憶に残っている。4月9日、西武球場近鉄 000 000 003 =3西武 000 000 004X=4(近)野茂‐●赤堀、(西)○郭近鉄の開幕投手は、入団4年目の野茂英雄。この試合もトルネードは威力を発揮。球威とフォークの切れは抜群で、西武打線を8回まで0点に抑えていた。しかもノーヒット。近鉄は9回表に石井浩郎の3点本塁打で先制し、誰の目にも優位は揺るがなかった。しかしドラマはここから始まった。9回裏、先頭の清原和博が意地で右越えに二塁打を放ち、まずノーヒットノーランの夢が打ち砕かれる。その後、四球とエラーで一死満塁になり、近鉄ベンチはリリーフエース赤堀元之を投入した。迎えた打者は伊東勤。そして赤堀の8球目を伊東が弾き返し、打球は左翼スタンドに消えた。逆転満塁サヨナラ弾。試合後、興奮して声が震えた伊東と対照的に、野茂は無言を押し通した。ノーヒットノーランどころか、完封も勝利さえも失ったのだから当たり前かもしれない。それにしても、試合前「開幕戦は野茂と心中や!」と言っていた鈴木啓示監督の変心ぶりは何だったのか。投手心理は人一倍熟知しているだろうに・・・。この出来事が2人の確執の一因と言われ、後々まで尾を引く。結果、翌95年、野茂はドジャースの一員として開幕を迎えることになった。■二つ目は、昨年(2011年)開幕前の渡辺恒雄さんの「迷」言ぶり。3月11日、東日本大震災が各地に被害をもたらした。原発事故、電力不足が起こり、開幕の延期を選手会、世論が訴える中、渡辺さんが平然と言った。「開幕を延期しろとか、プロ野球をしばらくやめろとか俗説がありましたが、大戦争のあと、3ヶ月で選手から試合をやりたいと声があり、プロ野球を始めました。フェアプレー、緊張した試合をすれば見ている人は元気が出て、エネルギーが出て生産力が上がる」終戦後、たった3ヶ月後に始まったプロ野球とは、1945年11月23日、神宮球場で行われた「東西対抗戦」のことを指す。この発言を聞き、「東西対抗戦」と2011年の開幕を一緒に論じるのはいかがなものかと思ったものだった。終戦直後、たった3ヶ月で奇跡的に開催できたのは鈴木龍二さん、小西得郎さんや川村俊作さんのような「職業野球復活」に賭ける人たちがいたからこそ。道具類をかき集めることから始めた彼らの情熱的な行動が、選手たちの気持ちを動かし、ファンを球場に誘った。また戦争が「終結」したという事実が人びとに安堵感や解放感を与え、その空気が下支えした。昨年はまるで事情が違った。決定的に違うのは、まだ何も「終結」していなかったこと。東日本では余震が続き、いつ再び大地震が襲うかまるでわからない不安が覆っていた。また被害からの復旧、原発問題、そして電力不足、何ひとつ解決していなかったのだ。まるで空気を読めない傲慢さに、いつもながら辟易したことを憶えている。今日も1クリックお願いします
2012.03.30
コメント(2)
-

高橋ユニオンズのこと~佐々木信也さんの思い出
■LIVEDOORベースボールジャーナルでは、今、高橋ユニオンズが話題になっている。高橋ユニオンズとは、1954年から僅か3年間だけ日本プロ野球界に存在した球団のこと。今ではその球団名を知る人自体少なくなってしまったけど・・・。ボクも偉そうなことは言えない。せいぜい球団名と佐々木信也さんが入団した球団だったことくらいしか知らなかったし。火を点けたのはライター、の長谷川晶一さん。著書『最弱球団~高橋ユニオンズ青春記』についてベースボールジャーナルで語っている。野球書籍を書いているライターさんは数多いけれど、とっくに忘れ去られた野球史やあまり人々の記憶に残っていない選手にスポットを当て、強い意志をもって語り継いでいる人の作品を、ボクは特に好んで読んでいる。長谷川さんの作品はこのジャンルに属するのかな? このジャンルで一番好きなのは澤宮優さんの『巨人軍最強の捕手~伝説のファイター・吉原正喜の生涯を追う』(晶文社)。ボクにとっては『最弱球団』と『巨人軍最強の捕手』は双璧の存在になるかもしれない。まだインタビュー記事の内容しかわからないけど、ぜひ読んでみよう。■前述のとおり、ボクは高橋ユニオンズのことをあまり知らなかった。だけど佐々木信也さんの著書『「本番60秒前の快感』(ベースボールマガジン社新書)に少しだけ関連の記述を見つけた。それはこんな件だった。「プロ1年目、1956年、私は高橋ユニオンズで過ごしました。ある日、高橋ユニオンズの本拠地・川崎球場で行われた大映戦で、レフトに場外ホームランをかっ飛ばしました。 後から聞いた話ですが、相手投手は試合後に宿舎の監督の部屋呼ばれ、監督が飲んでいたウイスキーをいきなりぶっかけられ、『強打者に打たれるならわかるが、佐々木のような非力なバッターに場外に打たれるのは何事だ!』と、散々怒られたそうです」そして翌年、高橋ユニオンズの解散により、佐々木さんは大映ユニオンズの一員になると、ウイスキーを投手にぶっかけた敵将・松木謙治郎さんが大映ユニオンズ監督の座に就いた。怖い監督と思っていたが、佐々木さんの走力は認めており、アイコンタクトだけで盗塁のサイン交換する仲になったのだから縁は異なものだと、佐々木さんは述懐していた。今日も1クリックお願いします
2012.03.28
コメント(0)
-

法政大vs東京国際大のオープン戦~金光興二vs古葉竹識。思い出す1977年のドラフト、そして『江夏の21球』
■去る3月11日、法政大と東京国際大のオープン戦が行われた。一見、ただの大学生の練習試合に過ぎない。でも法政大の監督が金光興二さん、東京国際大の監督が古葉竹識さんということで、試合結果ではなく、過去2人にあった経緯から、ボクはこの対戦に興味が湧いた。金光さん「あのときは、なぜ・・・ですか?」古葉さん「いやぁ、すまん、すまん。実は・・・」ひょっとして、こんな会話があったかな?このことは、今から35年前、1977年のドラフトに遡って説明する必要がある。■高校時代からプロ球界から注目されていた金光さん、1973年夏の甲子園では、主将として広島商高を優勝に導くなど傑出した選手だった(同期に達川光男や佃正樹)。その後進学した法政大では東京六大学リーグで優勝5回、さらに明治神宮大会連覇に大いに貢献した(大学の同期生はスター揃い。江川卓、袴田英利、島本啓次郎らがおり、「花の(昭和)49年組」と呼ばれた)。そして迎えた1977年のドラフト。当然プロ球界は金光さんに熱い視線を送った。本人もプロ入りを希望、そして地元・広島への入団を熱望した。広島もその気で、両者は相思相愛だという報道もあった。だが結局、広島が金光さんを指名することはなかった。広島が1位指名したのは盈進高の田辺繁文という投手。そして4位に指名したのは、広島商高で金光さんのチームメイトだった東洋大の達川光男だった。広島の名スカウトだった木庭教さんが金光さんを推さなかったことが理由と聞いたこともあるが、その真偽はわからない。実はこの時、広島の監督は古葉さんだった。代わって金光さんを指名したのは近鉄だった。ドラフトで選手と球団のすれ違いがあることはよくあること。最近では菅野智之のケースもそう。菅野は浪人の道を選んだが、金光さんは近鉄の指名を受けることなく、それを拒否してノンプロに進んだ。以降、指導者の道を歩むことになった。プロ入りすることなく、アマチュア球界に身を置き続けるきっかけになったのが、このドラフトだった。もし古葉さんが金光指名を決断していたら? ボクはそう考えたことがある。金光さんなら、きっとプロの世界でも好成績を残して、今頃は広島の監督に就任していたかもしれない。そんな妄想をしてしまうのだ。あれから35年が過ぎた。2人はプロ野球とは違う、大学野球という世界で相対していることに不思議な縁を感じる。冒頭に書いた会話が実際にあったわけないけれど、江川卓さんと小林繁さんがTVCM(清酒・黄桜)で相対した時のような、緊張感をもって会話するシーンがあるのなら、ボクはこっそり覗いてみたいと思う。■妄想ついでに、もうひとつ。ドラフトがあった2年後の1979年、日本シリーズは広島と近鉄が戦った。両者3勝3敗で迎えた第7戦、後に『江夏の21球』で有名なった9回裏の攻防を、ボクは妄想することがある。第7戦、11月4日、大阪球場広島 101 002 000 =4近鉄 000 021 000 =3もし、ポジションがショートの金光さんが近鉄に入団していたら、この戦いはどう変わっていたろうか、と。当時、近鉄のショートは石渡茂だったが、プロ2年目の金光さんなら、ポジションを石渡から奪っていた可能性がある(石渡さん、申し訳ない!)。打順はもちろん、石渡と同じ1番だ。だとすれば、そもそも一死満塁の場面で、石渡のスクイズ失敗は球史に存在しなかった。金光さんが打席に入り、スクイズをばっちり決めていたかもしれない。はたまた逆転適時打をかっ飛ばしていたかもしれない。だとすれば、この時、近鉄にとって悲願の日本一が成就していたかもしれない。所詮、大の近鉄ファンだったボクの戯言であるけれど。いや待てよ、もし金光さんが広島に入団していたら、どうだったろうか。妄想が膨らむ。当時、広島のショートは難敵・高橋慶彦だったため、金光さんのポジション奪取は叶わない。では仮に、三塁を守っていたらどうだったか、ボクは想像してみる。9回裏、近鉄が無死満塁のチャンスで打席に立ったのは佐々木恭介。カウント1-1から江夏豊が投げた3球目を佐々木は強振した。打球は大きくバウンドして、ジャンプした三村敏之三塁手が差し出したグラブのわずかに上を通り過ぎて、三塁線左側にポトリと落ちた。一瞬、逆転サヨナラ適時打かと思ったが、判定はファール。三村は後に「あの時、自分の身長が低くて助かった(173cm)。もし衣笠(祥雄)が三塁を守っていたら、グラブの先に打球を当てて、フェアになっていたと思う」と語っていた。ちなみに衣笠の身長は175cm。もしこの場面で、身長179cmの金光さんが三塁を守っていたらどうだったろうか。きっとグラブの先に当てて、打球はフェアになっていたに違いない。だとすれば、三塁走者の藤瀬史朗、二塁走者の吹石徳一が相次いで生還し、近鉄は日本一を達成していたかもしれない。■もし金光さんが近鉄もしくは広島に入団していれば、球史は大きく変わっていたかもしれない。そして山際淳司さんが『江夏の21球』をテーマに作品を書くこともなかったかもしれないのだ。※金光さんの身長が179cmもあったら、打球はグラブに収まり、5-2-3の併殺が成立したのでは? といった指摘もあると思いますが、それはボクの妄想には存在しません。念のため今日も1クリックお願いします
2012.03.20
コメント(2)
-

斎藤佑樹、日本ハムの開幕投手に~5年前の、あの時と同じ3つのこと
■日本ハムの開幕投手は入団2年目の斎藤佑樹に決まったと、栗山英樹監督が昨日発表した。その報を受けネット上では「またのらりくらりと6回被安打10で3失点か」「野手の気持ちも考えて発言しろよ」(Sports Watch)などの批判が渦巻いているそうだ。いま野球界は「契約金超過問題」を巡り、朝日新聞と巨人軍の戦いが勃発。今後の推移次第ではNPBの存続が危ういかも?そんな状況下、斎藤が開幕投手に指名された。「斎藤佑樹、開幕投手」「(斎藤へ)周囲の批判」そして「裏金問題」、いま旬な話題を整理していて、たしか、あの時も同じだったことを思い出した。■2007年4月14日、東京六大学・春季リーグ戦が開幕した。開幕カードは早稲田大vs東京大。早稲田の先発はゴールデンルーキーの斎藤だった。東大 000 000 000 =0早大 203 030 00X =8(早)○斎藤-松下-須田斎藤は6回を投げ、被安打1、奪三振8の好成績を残してマウンドを降りた。試合後、 「2点以内に抑えることだけ考えていました。これで大学でもやっていける自信になりました」とコメントを残している。斎藤が勝利投手になって事なきを得たが、試合前、斎藤を先発に指名した應武篤良監督(当時)の心中は複雑だった。自著『早稲田野球の魂』(PHP刊)に「もしこれで失敗すれば、大変な批判を浴びることになる。選手には不満や嫉妬の感情を抱き、私への不信感を強める者も出るだろう。自分で下しておいて重い決断と思った。自らも緊張しながら、斎藤をマウンドに送った」と述懐していた。事実、先発は斎藤と聞いて、不満をもった選手たちが多くいた(以下も同書より引用)。「なぜだ、と思いました。須田の方が調子よかったですし」「マスコミ向けだと思いました。監督はふだん実力主義を掲げながら、言うこととやることが違うと思いました」など。須田とは、須田幸太(当時3年、現・横浜)のこと。この早稲田のエースナンバー「11」を背負う右腕こそ、開幕投手に相応しいとボクも思っていた。應武さんの判断はマスコミへの迎合そのものだと思ったし、多くのファンも同じ感想を持っていたと思う。そしてこの当時の野球界も、今と同じ「裏金問題」に揺れていた。西武が東京ガスにいた木村雄太や早稲田大の選手に栄養費を渡していたことを発表したことで事件が発覚。結果、木村は謹慎、東京ガスは対外試合禁止に。また早稲田の選手は退部になり、その選手の出身校(専大北上高)までが、野球部を一時解散する事態に発展した。■「斎藤佑樹、開幕投手」「(斎藤へ)周囲の批判」そして「裏金問題」。斎藤を指名した栗山監督の心中はいかに? あの時の應武監督と同じだろうか。また斎藤は開幕戦でどんなピッチングをするのか? 「持っている」発言以来、幾度となくやってくる試練、今回も「持っている男」ぶりを証明できるか。チームメイトたちの反応も気になる。そして「裏金問題」。当時もNPBは自浄能力がなかった。それどころか根来泰周コミッショナー代行(当時)は、急きょ改めたドラフト制度(=希望枠撤廃)を、「ただ俗論に従っただけ」(日刊ゲンダイ)と言って開き直っていたっけ。翻って今、あの時と同じく、NPBは「裏金問題」を主体的に解決する動きは見られない。加藤良三コミッショナーもダンマリを決め込んでいる模様。事態が動くも動かぬも朝日次第の様相だ。あれから5年経った。大学1年生だった斎藤はすでにプロのマウンドに立っているのに、NPBだけは相も変わらず、である。 今日も1クリックお願いします
2012.03.20
コメント(0)
-

清武英利さんの契約情報暴露で、スカウトマンたちの怒り噴出!~朝日vs巨人戦争の飛び火、そして思い出した「まじめなスカウト」木庭教さんのこと
■以下、読売新聞より要約。独断で記者会見を強行し、機密事項を暴露したなどとして、読売巨人軍から解任された元球団代表・清武英利氏の著書(今月16日発売)を巡り、野球界から批判が噴き出している。 巨人軍以外の球団が大学の有力選手と結んだ契約の詳細が明らかにされており、スカウトらからは「アマの選手たちとの信頼関係が崩れてしまい、今後の獲得活動にも大きな支障が出る」と怒りの声が上がった。清武氏が著書の中で暴露したのは、他球団の契約情報を記した文書。球団名も、選手名も匿名だが、「某球団の極秘文書が私の手元にある」とした上で、「契約金1億円 インセンティブ2億~2億5000万円(本人と調整中) 4~5年後メジャー挑戦の確約(本人と調整中)」などと記述していた。■これに対し、各球団のスカウトたちは怒り噴出だという。「冗談じゃない、という気持ち。あのような暴露が許されるのだろうか。人材発掘のためには、競争の中で最も激しい情報戦を行っている。球団トップが、スカウトが集めた重要な情報を外に出すことが許されるなら、我々はアマや関係者の信用を失ってしまう。契約の詳細は重要なトップシークレットのため、球団内での電話も控えるくらい情報漏れには注意を払っていた」「いい選手を獲得するために各球団は知恵を絞って企業努力をしている。そういうものが表ざたになると、まじめに活動しているスカウトまで色眼鏡で見られることになる」等々。■読売の記事だから、多少割り引いて読む必要はあるだろう。ただ「まじめに活動しているスカウト」という文を読んで、(冒頭の記事とは関係ないけれど)ボクは広島などでスカウトをされていた木庭教さんのことを思い出した。木庭さんこそ札束攻勢とは無縁な、まさに「まじめな名スカウト」だったんじゃなかろうかと。だいぶ以前、 『スカウト』(後藤正治著、講談社刊)を読んだ。この物語(ノンフィクション)の主人公が木庭さんだった。同書に紹介された木庭さんの風貌は、「まじめさ」を十分に醸している。以下、青文字の箇所は『スカウト』より引用した。「木庭は小柄な人である。白っぽい半そでのポロシャツに、白いソフト帽、肩から黒い大きなショルダーバッグを下げている。それが、この季節のいつもの出で立ちである。顔から首筋、それに半袖から出た腕は、擦り込んだように日焼けしている」また、いわゆる札束攻勢に手を染めたことは一度もない「まじめな」スカウトだった。「裏工作もまた、彼の好みではなかった。彼のスカウトとしての手腕は、(人間性を含めた)選手たちの力量を測る眼力が、相対的に高いということだった」札束攻勢に頼らず、己の眼力で選手を見る---これは広島という金銭力に乏しい球団事情が多少なりとも影響していたに違いない。でも、それでも、ボクが憧れるスカウト像は、木庭さんなのだ。■いまの時代、プロ球団のスカウトに求められる要素は「どうやって選手を見つけるか」ではなく「(裏金を含めて)優良選手をどうやって入団に結びつけるか」に変遷していることはボクも理解している。でも、そのような状態で、ファンから見た「面白い野球」が持続可能なんだろうか。スカウト自身の眼力で選手を発掘して、あっと驚くような(無名の)選手がいきなりグラウンドに姿を見せる・・・例えば、終戦直後の大下弘さんみたいな。う~ん、そんなことは無理だろうな。ただの懐古趣味なんだろう、きっと今日も1クリックお願いします
2012.03.19
コメント(0)
-

巨人軍、契約金超過問題~はてさて朝日新聞の意図は?そして巨人軍の過去にあった事件
■巨人軍の契約金超過問題が話題になっている。この事件の詳細は省略するけれど、ボクは2つのことを感じている。一つ目は「なぜ、今さら、こんなことをスクープと称して朝日新聞が報道するのか」ということ。朝日が用意している”落とし所”は何なのか、それがボクにはわからない。二つ目は、この事件は巨人軍の、これまでの歴史の延長線上にあるということ。■まず一つ目。誤解のないように言っておくと、もちろんボクは「ルール違反はいけない」という立場ではある。ただ契約金超過など球界では公然の秘密だったろうし、ボクのような一般のファンだって薄々感じていたことだ。なのに何故、今さら? と思う。だから余計に、朝日が用意する”落とし所”が気になる。結果として、仮りに巨人軍フロント(桃井某など)を引責辞任に追い込んだところで、あまりに瑣末過ぎて、朝日には面白くもおかしくもないはず。では純粋に球界の清浄化を願うものか。ただ、これまでの一場靖弘や那須野巧の事件以降、自由枠撤廃などの制度変更以外、さほど清浄化されない現実を見れば、「暖簾に腕押し」の感は拭えない。最近も長野正義、菅野智之等を一本釣りしようとした巨人の行動は、清浄化の対極にある。ここまで書いて、明治44年に起きた『野球害毒論』を思い出した。当時、過熱気味の野球人気に水を差すネガティブ・キャンペーンで、仕掛けたのは朝日だった。新渡戸稲造ら著名人の名を借りて、野球というスポーツの害悪、野球選手の品格堕落を説いたが、結局、「お騒がせ」に終始した過去をもつ。さらに大正4年、その舌の根が乾かぬ内、朝日が全国中等学校優勝野球大会(現・全国高等学校野球選手権大会)の主催を始めたのだから何をか言わん。ひょとして今回もあの時と同じ、ただの「お騒がせ」かしらん? 朝日が用意する”落とし所”がわからないため、ついつい余計なことを考えてしまう。■二つ目。そもそも「ルール破り」は、巨人の常套手段だったし、歴史そのものでもあった。「江川事件、空白の一日」(昭和52~53年)は言うに及ばず、古くは「別所引き抜き事件」(昭和23年)もある。これらの原因は昭和初期、日本に野球を根付かせたいと願った市岡忠雄、鈴木惣太郎ら有志たちが、あろうことか読売・正力松太郎社主に資金提供を懇願したことに始まる。米国と対等に戦えるチームを日本に作りたいという願いが、一新聞社の拡販材料にされ、次第に「そのチーム(=巨人)だけが強ければ、それでよい」という傲慢さに変遷した。その結果が今日の契約金超過問題である(もちろんその反面、読売が今日の野球発展に大いに寄与したことは理解しているが)。■結論(これから書くことが極論であることは重々承知しているが)もし朝日のスクープが「お騒がせ」でなく、落とし所が球界の清浄化であるならば、とことん問題を追及してほしい。そして読売に伝家の宝刀を抜かせることを期待したい。伝家の宝刀とは、読売のNPB脱退→新リーグ結成のこと。結果、NPBがどうなるか分からないリスクを伴うが、そういった事態に発展しなければ、結局何も変わらないはずだ。今日も1クリックお願いします
2012.03.17
コメント(0)
-

鈴木啓示さんの「西本幸雄と三原脩」評
前回の続き。■元・近鉄バファローズのエース・鈴木啓示さん(育英高)は、西本幸雄さんと三原脩さんを比較して「西本さんは選手を技術、体力、精神すべてにおいて育ててくれた監督、三原さんは選手をうまく使う監督」と評した。鈴木さんの詳しい比較評は『パ・リーグを生きた男 悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ刊)に詳しく書かれている。■まず西本さんについて。「初対面の時『20勝するのもいいけど、同じするなら負け数をひと桁にしろ』と、いきなり注文をつけられた。西本さんは不器用やけど、ひたすら熱心に情熱を傾ける人なんです。私も不器用な男です。お互い純粋で不器用やったから、、『わかった』と打ち解け合うまでに時間がかかる。でも、不器用なもん同士やったから、いったんできた絆が深いんやと思いますね」■そして、三原さんについて。「初めて見た印象では稲尾(和久)君より素晴らしいなぁ、と言われた。もし、心のレントゲンを撮る機械があったら、三原さんは最高機能のレントゲン機器をもってらっしゃったんでしょうね。選手の心を見透かし、やる気が高まるように持っていく。100の力がある選手が120の力が出るように持って行くのがうまかった」事実、鈴木さんは三原さんの言葉に乗せられるように、投げて投げて投げまくった。「ここはあんたしかおらん。あんたと心中や」と言われると意気に感じずにはいられなかった。三原さんが監督に就任した1968年、鈴木さんの登板イニングは359回。翌69年は330回。結果、69年は万年Bクラスだった近鉄を初優勝まであと一歩のところまで躍進させた。※昨年(2011年)、ダルビッシュ有が232回、田中将大が226回だったことからも、当時の鈴木さんの凄さが分かる。この三原評、西鉄ライオンズ時代の教え子、稲尾和久さんも同じことを言っていた。稲尾さんも西鉄の黄金時代は、三原さんに乗せられて投げまくった。ベンチで「ここの場面はエースに投げてほしいなぁ」と三原さんのつぶやきが聞こえると、例え先発完投した翌日であっても、リリーフ登板を厭わなかった、稲尾さんの述懐である。57年と58年は373回、59年は402回を投げ抜いた。これはもう驚異的な数字である。今日も1クリックお願いします
2012.03.16
コメント(0)
-

今日も佐々木信也さんと西本幸雄さんのこと。いや正確にいえば、+(プラス)三原脩さんの3人に起きた事件
■佐々木信也さん、西本幸雄さん、三原脩さん。その昔、この3人に起きた事件がある。それは1960年の日本シリーズ開幕2日前のこと。対戦カードは、当時新米監督だった西本さんが率いる大毎オリオンズと、知将・三原脩さんの大洋ホエールズ。テレビや新聞は日本シリーズを控え、競って両監督の対談を企画した。NETテレビ(現・テレビ朝日)もそのひとつ。司会者として佐々木さんがブッキングされていた。■生放送当日、西本さんは予定通りの時間にスタジオに現れたものの、三原さんが来ない。対談の一方が現れないまま放送が始まった。そして西本-三原の対談企画が、西本-佐々木の対談という、片落ちの状態のまま番組は終了した。西本さんの怒るまいことか。ギャラも受け取らず、顔を真っ赤にして、タクシーに乗って帰って行った。佐々木さんも怒り心頭、翌々日、三原さんに理由を尋ねた。以下『「本番60秒前」の快感』(佐々木信也著、ベースボールマガジン新書)より引用。佐々木「一昨日はどうなさったんですか?」三原「気が向かなかった、行きたくなかったんだよ」佐「それはないでしょう。スポーツマンとして、どうなんですか」三「じゃぁ、はっきり言おう。プロ野球の発展に貢献している会社が3つある。NHK、読売新聞、そしてベースボールマガジン。この3つから頼まれたらワシは出る。他はよろしい」後年、佐々木さんは、三原さんの欠席の理由が、別の意図的なものだったことに気づく。それは西本さんの感情を高ぶらせることで、日本シリーズを有利に進めようとした心理戦を企てたこと。戦いは球場内のみにあらず、場外も戦う。まさに知将・三原さんの真骨頂だった。結局日本シリーズは、三原さんの仕掛けた心理戦が効を奏し、大洋が4連勝して日本一を決めた。■西本さんの述懐。以下、『魔術師<下>三原脩と西鉄ライオンズ』(立石泰則著、小学館文庫)より。「忘れるなんてことはまさかないと思うんですけどね。まぁ何ちゅうかね、厳しさちゅうか、もっと厳しい言葉でいえば、えげつなさと言うか、そんなものを『ふ~ん』と思って感じました。三原さんにすれば、もう戦いは始まっているという感じだったんでしょうね。僕はそんな感じじゃなく、監督が試合をするわけじゃないと思っていました。三原さんのことは事前に聞かされていましたから『あ、これか』とも思いました。でも『もう、クソッ!』と思った。ま、そこらへんも三原さんの戦法だしね」■もし歴代の監督で好きな人を挙げよ、と言われたら、ボクは西本さんと三原さんの名前を答えると思う。(そんなボクから見れば)この2人の薫陶を受けたラッキーな投手がいる。元・近鉄の鈴木啓示さんがその人。三原さんは1968年~70年、西本さんは74年~81年、それぞれ近鉄バファローズの監督を務めた。この2人が監督だった時代、両者をまたがってエースの座にいたのが鈴木さんだった。鈴木さんの2人に対する比較評が面白い。途中ですが、続きは次回に。今日も1クリックお願いします
2012.03.13
コメント(0)
-

佐々木信也さん、西本幸雄さんへのわだかまり。その理由は?
■佐々木信也さんは、その昔、フジテレビ「プロ野球ニュース」の総合司会を12年間にわたり務めた名物スポーツキャスター。「こんばんは、プロ野球ニュース」で始まるフレーズは今も懐かしい。この佐々木さん、湘南高、慶應義塾大を経て、高橋ユニオンズ、大映ユニオンズ、大毎オリオンズで活躍(1959年引退)した、れっきとした元プロ野球選手である。wikipediaによると、高橋ユニオンズに入団した56年は、新人ながら154試合に全イニング出場しシーズン試合出場の日本タイ記録を達成した。また新人での全イニング出場は史上初。後に長嶋茂雄さんも記録するが(59年)、新人選手の全イニング出場は、現在も佐々木さんと長嶋さん2人だけ。■佐々木さんは自著『「本番60秒前」の快感』(ベースボールマガジン社)に、大毎オリオンズの監督だった西本幸雄さん(故人)にわだかまりがあったことを吐露している。その理由は今から50年以上前、1959年に遡る。この年、シーズンを終えた佐々木さんは球団代表から突然呼びだされ、自由契約を言い渡された。まさに青天の霹靂。だれが自分のクビを決めたか問い詰めたところ、来季から就任する監督であることを知った。その新監督が西本さんだった。後に佐々木さんと西本さんは「プロ野球ニュース」でキャスターと解説者という関係で一緒に仕事をすることになったが、佐々木さんは怒りをグッとこらえ、常に大人の対応をしていたが・・・。ところがある日(80年頃)、ラジオ番組で佐々木さんと西本さんが対談する企画が持ち上がった。この番組中、佐々木さんの、それまでこらえていた西本さんへの怒りが爆発する。佐々木「これまで黙ってましたけれど、私のクビを切ったのが西本さんだというのは知ってました。なんで私のクビを切ったのですか?」西本「一度、キミに謝ろうと思っていたんだよ」佐「遅い! 冗談じゃない。ちゃんと理由を教えてください」西「当時、オリオンズには八田正、須藤豊、平井嘉明、小森光生、そして佐々木信也と、力が拮抗した内野手が5人いたんだよ。そうなると、どうしても人数が合わない。内野手をひとりやめさせなきゃいけなかったんだ」佐「なんで、そのなかで私を選んだのですか?」西「クビにしても、一番食いっぱぐれがなさそうなのを選んだんだ」自由契約の真相にカッとなり、「そんなバカな話はないでしょう!」とまくしたてたことを覚えています。ただこの日をもって私の胸の奥に潜んでいた、西本さんへのわだかまりが氷解しました。このことは西本さん自身も日経新聞『私の履歴書』で、同様のことを述懐している。球団から選手削減をつきつけられた事情があったことも告白していた。■まだ佐々木さんの心にわだかまりがあった頃のエピソード。1960年、日本シリーズ第2戦でスクイズを敢行し失敗した西本さんの采配を、新聞各紙が一斉に叩いたことがあった。中には「ペース乱れた? 西本作戦 とにかく打つこと 併殺が恐くてスクイズ」という記事があった。「併殺が怖くて」という表現に悪意すら感じるが、実はこの記事は、引退後に評論家になった佐々木さんの署名記事である。西本さんへの当時のわだかまりを表した、せめてもの佐々木さんの抗いだったのかもしれないと、ボクは思っている。 今日も1クリックお願いします
2012.03.11
コメント(0)
-

東日本大震災復興支援マッチ、侍ジャパンvs台湾~駒澤大OBたち、新井貴浩、中畑清、二宮至、平田薫、栗橋茂、木下富雄、石毛宏典、そして太田誠・元監督
■今日(3月10日)、東日本大震災復興支援マッチ「日本対台湾」戦が行われている。侍ジャパンが結成されたのは、実に3年ぶり。試合開始に先立ち、新井貴浩選手会長が「プレーを通じて、被災された方たちに元気を与えたい」と挨拶した。新井貴浩(広島工高-駒澤大)。駒澤大時代は名将・太田誠元監督の門下生である。太田さんの座右の銘は「姿即心、心即姿」。姿すなわち心を表し、心すなわち姿を表す。その太田さんが新井を叱ったエピソードを。ある打席で新井は甘い球を見逃し、「しまった」という顔をした。結局、その打席は凡退してしまうが、凡退したことではなく、「しまった」という表情に対し、太田さんは一喝した。「あの表情に、お前の弱さが出ている。敵に隙を見せるな」■テレビ中継したTBSの解説者は中畑清・横浜べイスターズ監督。中畑も新井と同じ太田門下生。太田さんは著書『球心、いまだ掴めず』(日刊スポーツ出版社)で、印象深い選手として中畑の名前を挙げている。中畑は太田さんが監督就任した直後に入学した、いわば太田門下の1期生である。その中畑が4年生になった1975年、全日本大学野球選手権大会に出場した駒澤大は、決勝でエース・斉藤明夫(元・大洋)を擁する大阪商大を破って優勝を決めた。これが駒澤大にとって初めての全国優勝だったため、一層強く記憶に刻まれていると太田さん。また中畑持ち前のガッツも印象深いという。「私がミーティングで選手を叱りつける時、いつも私の正面に立って、それを受け止める男がいた。のっぽで頬もそげているが、それでいて筋肉の塊のような男である。それが中畑だ。安積商業から入ってきた中畑は、高校時代、無名の選手だった。だがバットから弾き出される打球には、勢いがあった。なにより闘争心がむき出しで、勝負の世界に生きるための条件を備えていた」■同書には、中畑をはじめ多数の教え子たちの思い出が綴られている。ちなみに、中畑の同期生には二宮至、平田薫(いずれも元・読売)がいた。その2学年上には栗橋茂(元・近鉄)、木下富雄(元・広島)、逆に1学年下には森繁和(元・西武)、大宮龍男(元・日本ハム)、3学年下には石毛宏典(元・西武)がいた。今日も1クリックお願いします
2012.03.10
コメント(1)
-

杉内俊哉、古巣相手に炎上~鹿児島実高時代、木佐貫洋とのライバル関係
■以下、デイリースポーツより。巨人の杉内俊哉投手が9日、ヤフードームで行われたソフトバンクとのオープン戦で先発し、5回8安打7失点(自責6)と打ち込まれた。移籍後初めて臨んだ古巣との一戦。二回、長谷川に2ランを浴びるなど6失点。続く三回には新外国人のペーニャに来日1号ソロを打たれた。悪夢のようなマウンドを降りた杉内は「久々に7点。嫌ですよ。打たれるの嫌ですから。二回は久々に焦りました。こういうのを止まらない、というんだと思っていました」と、振り返った。■今季から読売に移籍した杉内俊哉。ボクは杉内の名前を聞くと、以前読んだ『松坂世代』(矢崎良一著、河出書房新社刊)にあった「鹿児島実高のエースだった杉内にとって、甲子園は『行きたいところ』ではなく『行かなければいけないところ』だった」という一節を思い出す。経済的に恵まれない家庭に育った杉内は、高校時代から「俺は絶対にプロに行く」と公言してはばからなかった。小さい頃、母親から「おまえはプロ野球選手になるんだよ」と育てられ、家族の将来が自分の左肩に懸かっていることをひしひしと感じていた。だからプロに行くため、杉内にとって甲子園は単に『行きたいところ』ではなく、甲子園で活躍することが必須条件、『行かなければいけないところ』だった。高校3年の夏、鹿児島県大会の決勝はエース・木佐貫洋(現・オリックス)を擁する川内高と対戦し、下馬評を覆して、鹿児島実が優勝した。当時を振り返った木佐貫のコメントが同書に紹介されている。「スギウチ君は17歳とか、18歳という当時から、背負っているものをはっきりと認識できたんでしょうね。家族や身近な人のために、自分が頑張らなければいけないということを。当時のボクにはそれがなかった。その差が勝敗を分けたんだと思います」。■杉内vs木佐貫。ボクはあっけらかんとした木佐貫の性格のほうが好きだけど、木佐貫が読売時代に奪取できなかった背番号「18」を、今季、杉内が背負う。これも何かの因縁?と思うが、木佐貫にそんな卑屈な考えはないだろうな、きっと今日も1クリックお願いします
2012.03.09
コメント(0)
-

近況~斎藤佑樹、大石達也、戸村健次
■まず日本ハムの斎藤佑樹(早稲田実-早稲田大)。「佑、4度目の先発も5回3失点!栗山監督『0点』」(報知)。今月3日、ヤクルトとのオープン戦に先発したが、毎回被安打となる5回8安打3失点(自責2)と精彩を欠いた。栗山英樹監督は「0点」と辛口採点。日刊ゲンダイでは吉井理人コーチのコメントが紹介されていた。「練習中、適当に流しているところが見える。気持ちの面とパワーをつけることが必要。高校時代を100とすれば昨年は80、今は90」とも。では大学時代は?と聞きたくなったが、吉井コーチの真意を忖度すると「大学時代は80未満」と言いたかったと予想する。もし当たっていれば、ボクも同感だ。高校時代は相手に1点もやらずに9回を投げ切る投手というイメージがあったが、大学時代は6回を投げ、必ず2~3点以内に抑える安定感のある先発投手といったイメージ。高校時代と比べて多少レベルが落ちたように見えた。まぁ、吉井コーチの苦言は期待の裏返しでもある。今の成績はパッとしないが、札幌ドームの開幕投手は内定しているらしい。■西武・大石達也(福岡大大濠高-早稲田大)。「大石『いいところなし』二軍へ」(日刊)今月8日、オリックスとの練習試合に先発し、4回6安打4失点(自責3)と打ち込まれた。1回2死一塁から、新外国人の李大浩に先制の2ラン。2、4回にも1点を失った。試合後、2軍の教育リーグでの調整を言い渡された。「いいところなしです。すべてにおいて、あまり良くなかった」と唇をかんだ。大学時代、斎藤の後に登板し、勝利を決定づけた守護神・大石が真価を発揮できない。大学時代も先発は不得意だったから、クローザーに徹したほうが良いと思うが、いかが?■最後に楽天・戸村健次(立教新座高-立教大)。「戸村、トルネードで6回0封!開幕ローテ前進」(報知)7日、軽く腰をひねるトルネード気味のフォームで、戸村は思い切り腕を振った。先発で6回5安打無失点。無四球で投げきり、「試したい部分をしっかりできて、ゼロに抑えられたのでよかった」。納得の投球で開幕ローテを大きく引き寄せた。星野監督も「四球を出さなかったのが奇跡。普通にいけば力はある。勇気を持って腕を振ればな」と成長を認めた。四球を出さなかったというのは、星野さんの言うとおり奇跡だ。戸村のトルネードをイメージできないが、今年こそ1勝目を挙げてほしい。できれば斎藤佑樹との対決で決めてほしいが欲張りすぎか? 今日も1クリックお願いします
2012.03.08
コメント(0)
-

首都圏の大学野球、とりわけ投手の観点から見ると、日本ハムが我然おもしろい!~斎藤佑樹、大塚豊、乾真大、糸数敬作、八木智哉、多田野数人、宮本賢、そして栗山英樹
■球春到来は間近。最近の各メディアでは競って優勝予想が始まっている。どこが優勝するかなんて、ボクにとっては興味の外。ただ過去の首都圏の大学野球、とりわけ投手の観点から見ると、日本ハムが我然おもしろい。■まず斎藤佑樹(早稲田実-早稲田大)がいる。2007年全日本大学野球大会のMVP、そして10年明治神宮大会でチームを優勝に導いた。他にもたくさんいる。大塚豊(創価高-創価大)。ボクが東京新大学リーグを観戦した時、創価大のマウンドにはいつも大塚がいた。09年全日本大学野球選手権ベスト4。栗山英樹監督の高校の後輩でもある。乾真大(東洋大姫路高-東洋大)。08年春、東都大学リーグの最優秀投手、ベストナイン。大学通算の奪三振率は9.76と異常に高かったが、「突然制球が乱れる投手」という印象がボクにはある。09年全日本大学野球選手権の準々決勝では乾と上記の大塚豊が投げ合い、大塚のいる創価大が勝利した。糸数敬作(中部商高-亜細亜大)。06年明治神宮大会の優勝投手。決勝では早稲田大の宮本賢(現在は日本ハムのチームメイト)と投げ合い勝利した。八木智哉(日本航空高-創価大)。大学通算35勝。05年全日本大学野球選手権では49奪三振の大会新記録を樹立した。大塚豊は大学の後輩。多田野数人(八千代松陰高-立教大)。当時の東京六大学リーグでは「左の和田(毅)、右の多田野」と並び称された。立教大のチームメイトに上重聡がいた。現ホークス・大場翔太は中学時代に多田野に憧れて、八千代松陰高に進学したエピソードがある。宮本賢(関西高-早稲田大)。06年明治神宮大会で主将としてチームを準優勝に導いた。wikipediaによると、早稲田の後輩・斎藤佑樹に右ひざを曲げて投げるフォームを助言したのは、この宮本だったという。■他に監督の栗山英樹のことを忘れてはいけない。創価高から東京学芸大に進み、野手そして、なんと投手としても活躍した。野手としては通算打率.389の記録を残し、東京新大学リーグ歴代3位の記録をもつ。投手としても通算勝利数25を記録し、当時のリーグ新記録を樹立した(現在は大塚豊の41勝)。 今日も1クリックお願いします
2012.03.06
コメント(2)
全14件 (14件中 1-14件目)
1