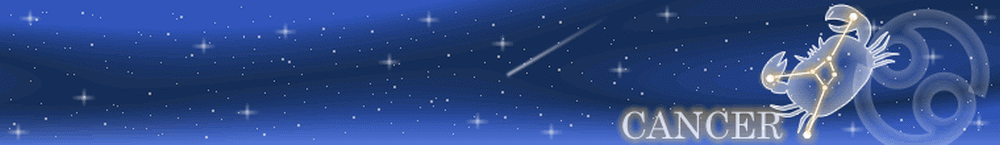2008年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

ぼくと1ルピーの神様
本著を知ったのは、ラジオ放送。 浪速のモーツアルトとして高名な、作曲家キダタロー氏が、 夕刻に放送されている番組の中で、紹介されていたのが本著。 興味を持ち、早速購入して読んでみたが、素晴らしいの一言! 私も、この一年の間に、結構な数の書籍を手にしてきたが、 本著は、私にとって、現在のところ、今年のNo.1である! もちろん、2008年は、その終了まで、あと1か月余りあるから、 本著を上回る書籍に出会えれば、それはまた嬉しい限りなのだが。 ***お話しの舞台はインド、そしてそのベースは、「クイズ・ミリオネア」。主人公のラム・ムハンマド・トーマスは、クイズ番組に出演し、超難問を次々にクリア。遂には、全問正解を達成し、見事、賞金十億ルピーを勝ち取る。しかし、後日、不正を行ったとして、彼は逮捕されてしまった。そこに至ったのは、番組制作側の事情があった。実は、番組側に、賞金として手渡すだけの資金が、まだ用意できていなかったのだ。そこで、制作者は、ラムの不正を証明する手助けを、警部に依頼する。そして、ラムは、警部の目の前では、ごく簡単な問題にすら、答えることが出来なかった。 ***ラムが全問正解を成し遂げたのには、理由があった。それは、出題された問題が、全て、彼のこれまでの人生と関わっていたこと。ラムは、彼の無実を証明しようとする女弁護士に、これまでの自分の人生を語り始める。そして、ここで語られる数々のエピソードこそが、本著の肝である。ラムの人生からは、インドで暮らす人々の、生々しい実体が伝わってくる。それは、日本で暮らす私たちには、想像も出来ないようなところも多い。「格差社会」ということが、日本でも、近年、多く語られるようになってきたが、インドにおける、その激しさ、厳しさ、哀しさには、呆然としてしまう。 ***私の脳は、「カタカナ」というものを、すんなりと受け入れない構造になっているらしい。おかげで、高校時代に、日本史の方は、最後まで何とか授業についていけたものの、世界史の方はと言うと、途中からチンプンカンプンになってしまった。だから、本著を読む時には、人名がグチャグチャになり、混乱してしまった。インドの方とは、普段、めったに接する機会はないので、彼ら、彼女らの名前に、それほど馴染みがないせいもあるだろう。それ以上に、算数とか、「BRICs」と呼ばれるほど、経済発展していることぐらいしか私たちが、インドという国について知らないことを、本著は教えてくれた。 ***本著を原作とする映画“SLUMDOG MILLIONAIRE(スラムドッグ・ミリオネア)”が、11月12日に、アメリカで限定公開されたらしい。ただし、日本での公開は、まだ未定とのこと。映画館でとは言わないまでも、DVDで良いから、ぜひ見てみたいなぁ。
2008.11.24
コメント(0)
-

わが子に「お金」をどう教えるか
「お金」をどう教えるか、というタイトルですが、 どんな風にすれば、「お金」を儲けることができるのかとか、 如何にして「お金」を使いこなせば、良いのかとか、 そういったことを、子どもたちに教えるための本では、決してありません。 つまり、流行の「金融教育」について、述べようとしているのではないし、 「企業経営」等について、述べようとするのでもありません。 著者は、「お金」を通してしか「世の中」を見ようしない現代社会の風潮に、 疑問を投げかけ、子どもたちに「正しい目」を持たせようと、呼びかけているのです。 ***生まれた時から、「消費者」「お客様」という立場に、慣れ親しんできた子どもたち。そんな彼ら、彼女らにとって、その居心地の良さを保障するのが「お金」。「お金」さえあれば、上から目線で大人(販売者・店員)をも、見下ろすことができ、(何と言っても、売り手にとって、お客様は「神様」なのですから!)、欲しいものをいくらでも手に入れ、人だって意のままに動かすことができるのです。そんな体験を積み重ねてきた結果、「お金」を尺度としてしか、周囲を見ることができなくなった子どもたち。「中学受験をしないのは貧乏人の子どもだから……」と、塾代を払えない子をバカにする同級生。「あの子のお父さん、リーマンでしょう……」と、私立中学校に入学した子どもが、突然差別される立場になる現実。でも、これって、子どもたちの世界だけのことでは、決してありません。大人たちだって、と言うか、大人の方が「拝金主義」に汚染されきっている。そんな大人たちが、次のような子どもたちの質問に、ちゃんと答えることは、なかなかに、難しいのではないでしょうか?「お金持ちって偉いの?」「高級レストランの方が、安いお店よりも美味しいものが食べられるようね?」「勉強ができると、お金持ちになれるの?」「一流のプロになれば、高収入が得られるようになるの?」著者は、これらの質問に、大人として、如何に答えれば良いのか、そして、世の中を正しく見つめるためには、どんな目を持てば良いのか、そして、そんな目を子どもたちに持たせるためには、大人として、どんな風に関わっていけば良いのか、について語っています。子どもたちの質問に、「世の中、お金だけじゃないよ」とか「お金じゃ買えないものだって、あるんだよ」という一言で済ませずに、その次の一言を、きちんと用意しておくことが、大人としての務めであり、そのことで、大人自身が、正しい目を持つことが出来るようになる気がします。
2008.11.24
コメント(0)
-

親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと
冒頭の「はじめに」の部分だけで、 著者が語ろうとしていることが、十分に伝わってくる。 わずか3ページの紙幅を用いて書かれた、とても短い文章だが、 そこに書かれていることは、どこまでも深く重たい。 本著を読む数日前に、たまたま読み終えていた 『子どもが育つ条件』と共通する部分も、あちこちで見られた。 例えば、「お母さんまかせ」(p.43)のエピソードなど、 まさに、そこで述べられていた「子育てにおける父親不在」の典型である。第1章の中で述べられていることの中には、私としては、ちょっとついていけないなあというところが、いくつかあった。「心の暗闇に触れない」で語られる、下駄の鼻緒のエピソードで、兄に対して憎しみの感情を抱いたというところなど、私にはピンと来ないし、認めたくない。 第2章では、著者の子ども時代が語られる。いつも感じることだが、やはり、人というのは、育った環境や経験によって、形づくられていくものだ。著者が著者たる所以は、やはりここにあるんだなぁと、大いに納得させられる。第3章は、前述した『子どもが育つ条件』と、最も関連が深いところ。そして、私が著者に共感する部分が、最も大きかったところ。「人間は結局他者を理解し得ないから、相手の分からなさを、そのまま、その人の真実、その人が大切にしているものと尊重して、我慢する」とか、「分かっているけれどやれないこと、そして、やれない人がいることを知ることが大事で、善悪についてのそういう複雑な事実を、親が子どもに伝えられたら素敵だと思う」なんかは、本当にそうだなぁと思う。そして、第4章。 はじめに流行の教育コースがあるのではない。 生身の子供がいるのです。 子供に従うしかない。 それが一番リアルなことだ、というように思います。 子供が「なにを好きか」を基準にする他はない。 それを助けることしか、親のできることはない、と思います。(中略) 大事なのは「時代の基準」ではなく「その子の現実」であり、 「親が子供にしてやれることの基準」は、 「他ならぬその子」にしかないのだというように思います。(p.174)子供は、自分の意志で、なるようになっていく。その意志は、彼を、そして彼女を、これまでの人生において取り巻いてきた、実に様々で複雑なものによって、少しずつ形づくられてきたもの。だから、短い時間に、いくつかの言葉で、簡単にどうこうできるような、単純明快で、柔なものでは、決してない。子供が、その意志を形成していく過程において、親というものは、どのように関わっていくべきなのか、そして、その関わりは、どれほどの影響を及ぼすものなのか。できることは「ほんの少し」かも知れないが、そのことの持つ意味合いは、とても大きいように思う。 注)文中で示した頁の数は、文庫版におけるもの
2008.11.23
コメント(0)
-

子どもが育つ条件
著者は、自分の立ち位置を明確にし、 自分の考えの方向性を、鮮明に打ち出している。 最近、こんなにハッキリした主張を目にすることはあまりなかったので、 ある意味、とても新鮮な感覚を味わうことが出来た。 本著では、「子ども」そのものが取り上げられている部分は少なく、 『子どもが育つ条件』というタイトル通り、 「子ども」を取り巻く環境、なかでも、母親と父親に焦点が当てられている。 また、その母親と父親を取り巻いている、社会の有り様についても言及している。第1章では、母親が育児不安に陥る要因として、「社会からの孤立感」「自分喪失の不安」「夫との関係への不満」の3点を示している。また、それと共に、子どもがどう育つかという問題は、実は、その親たち夫婦の関係の問題が重要であると指摘している。第2章では、「授かる子」から「つくる子」への変化の中、子どもの価値が変わり、「少子良育戦略」の定着が、不登校をはじめとする様々な問題に影響を及ぼしていること、「先回り育児」を代表とする、子ども不在の「よかれ」という親の善意が、自分の子どもを、しっかりと「育て上げ」られない結果に繋がってしまい、「育て直し」や「育て上げ」を、他に求めなければならなくなっている現状を指摘している。次に、第3章では、「便利さ」の広まりや「食事」の有り様等、社会の変化と連動して、家族のかたちや機能、家族メンバーの心理が変化したことを指摘し、家族の中で個人化が進み、夫婦の性別分業役割はもはや機能せず、結婚がリスクとして問われていると述べている。何を求めて結婚するか、子どもをもつこと、親になることが、自分にとってどのような意味・価値をもっているかを、事前に検討する必要があるのだと。第4章は、本著の肝となる部分であり、著者の主張が、最も明確に打ち出されているところ。子どもには、生まれながらに個性と気質があり、その成長のため必要なのは、応答的な人と環境であるとする。 現在行われている子育て支援の多くは、 支援の対象を「育てること」や「育てている人」としています。 このことは、「子育て支援」という言葉に端的に示されています。 しかし、はたしてそれは正しいあり方なのでしょうか。 結論からいうと、本来、何よりも支援すべき対象は、子どもであり、 「子どもの育ち」でなければならないのです。(P.163)そして、子どもの世話は「親が一番」なのか?と問いかけ、幼少期から、社会で子どもを育てる意義の大きさを唱える。「子育て支援」から「子育ち支援」へと、向かわねばならないと。第5章では、子育てによって、大人自身が育っていく価値の大きさ、そして、それを保障する社会の体制や、ワーク・ライフ・バランスについて述べている。「親の成長・発達」から「子どもの発達」をとらえようとした本著の指摘は、幼児期の「子育て」のみならず、その後の「子育て」についても、実に大きな示唆を与えてくれた。
2008.11.23
コメント(0)
-

千住家にストラディヴァリウスが来た日
何と言っても、その素晴らしい筆力に、心底驚かされた。 高名な3人の兄弟妹の母親が、その子どもたちについて書いた書物ということで、 正直、素人のエッセイ程度のものしか期待していなかったのだが、 そんなレベルのものからは、遙かにかけ離れた、素晴らしい作品だった。 とにかく、表題となっている『千住家にストラディヴァリウスが来た日』という たった一つのテーマだけで、全編を描ききっている。 そこに余分なものは、全く見当たらず、実に洗練された仕上がりとなっている。 千住3兄弟妹の母親は、やはりその母親であるだけの能力の持ち主だった。 ***私は、千住真理子さんの演奏を、これまでに2回だけ拝聴したことがある。それは、まだ、本著に登場するストラディヴァリを手にする前の時期であったが、華奢な体を存分に使いながら、魂を込めて、楽器を鳴らしているという印象だった。そして、今は、新しい楽器も手に入れ、さらに素晴らしい音を奏でていることだろう。しかし、本著で描かれているのは、そういった音楽的な話ではない。もちろん、本著の主人公は、ある意味で「ストラディヴァリウス」という楽器なのだから、ストーリーが展開する場面や空間は、必ずと言っていいほど、音楽と繋がっており、登場する人物も、音楽に包まれた生活を送っている人たちだ。それでもなお、本著を通じて伝わってくる感動は、音楽そのものが、もたらしているのでは、決してない。それは、音楽との関わりが深い、千住家という家族の有り様、それ自体が、私たちの心を大きく、そして強く揺さぶることによって得られる感動なのだ。それにしても、何と素晴らしい家族なんだろう。家族の核として、常に一本筋の通った、実直で揺るぎない存在感を見せる父親。そして、自分たちのそれぞれの目標に向かって、遮二無二突き進んでいく子どもたち。その家族が、家族たるまとまりを発揮するための、要となっている母親。 ***しかし、あれほど高名な兄弟妹たちの家だから、いくらストラディヴァリと言えども、それを手に入れるのに、これほどまでの苦労や困難があったとは、想像していなかった。もちろん、名器に出会うには、よほどの幸運に恵まれなければならない。そういった点で、入手がそれほど容易でないことは予想できた。だからこそ、本著で描かれているストーリーの中核は、類い希なる名器との「運命的な出会い」についてだろうと、私は思っていた。ところが、それは、名器入手における障害のうちの、一つに過ぎなかった。千住家は、私が予想していたよりも、質素で堅実な家計で成り立っている世帯だったのだ。やはり、よほどの企業・実業家でもない限り、安易に手出しできない金額というものがあるのだと、あらためて痛感した。そして、高名になっても、そんな簡単に、莫大なお金を稼ぐことは出来ない、メジャーリーグで活躍する選手なんて、本当に特別な存在なのだと言うことを痛感した。そんな経済的困難を、千住家が一致団結し、正々堂々と、正面からクリアしていく姿は、神々しくさえあった。誰にも変な頼り方をせず、正規の方法で、莫大な借金をするために奔走する様は、結束した家族の力を、思う存分に見せつけてくれた。まさに「千住家」に、ストラディバリウスが、やって来たのである。
2008.11.23
コメント(0)
-

校長を出せ!
『サンデー毎日』の記者が描いた「現代学校模様」。 なぜ親は、誰が見ても叶えられない要求を学校にぶつけるのか? なぜ教師は、「できないものはできない」と言わないのか? 教育現場に蔓延る「怪物」の正体を見極めようとする。 そのキーワードは、「親と話が通じない。 それが今、現場の教師を最も悩ませていることのひとつだ。」(p.22)の一文。 決して謝らず、開き直り、教師に「私はあなたより上の人間」と言い放つ親。 担任なんていつでも辞めさせることができると思う親。そんな親に対し、萎縮するばかりの教師たち。このような状況を生み出した背景の一つに、「学校選択制」があると著者は言う。学校をサービス業としてとらえ、学校との関わりを、どれだけメリットがあるかで判断する親。あたかも商品がずらりと並べられたコンビニで、好きなものだけを買い求める客のように。ところが、学校選びの段階では熱心な親も、入学後は丸投げ状態。その言動は、大人の判断が伴わない、幼児的発想によるものであることもしばしば。一方、子どもへの過剰な期待が、親同士の摩擦を生むことも。そして、そんな親のニーズに応えられない教師や学校に対しては、過剰な攻撃を加える。多くの親は、自分の子どもを『勝ち組』にしようとまでは思わなくとも、『負け組』にだけは、絶対させたくないと願う。結果、塾・習い事での前倒しが始まり、学校は学ぶ場ではなく、既習成果を『見せる場』となる。そして、クラブチームや塾での人間関係は、学校でも消え去ることはない。 ***本著のまとめは、p.223にこのような形で示されている。 1.成果主義がはびこる中、親自身が競争主義に巻き込まれ、 特に子どもが「負け組」になることを恐れる。 親同士がバラバラにされ、不安をあおられた親が個々に学校へ要求をぶつける。 2.学校は「サービス業」として振る舞うことが求められており、 「顧客」である親の無軌道な要求に対し、理にかなった態度を貫けない。 3.個々の教師も成果主義にからめ取られ、バラバラにされている。 親のクレームを恐れ、業績評価を下げないために「隠蔽主義」「事なかれ主義」に走る。 4.そのような学校に対し、親は疑心を抱くようになり、 ますます要求やクレームを先鋭化させる。そして、その後に続く記述は、納得できるものだ。 人々は実は「モンスターペアレンツ」を欲しているのではないか。 人間であるはずの親を「怪物」と呼び、 自分と区別することで安心したがっているのではないか。 モンスターペアレンツはあくまでも「現象」だ。 そこに目を向けさせることで、教育のかたちをゆがめる「原因」を覆い隠す意図が、 どこかに存在するのではないか、と私は疑う。最近、この種の書物は多数発行されているが、中でも、本著は極めて優れた現状分析が示されていると感じた。
2008.11.16
コメント(0)
-

ウェブ進化論
さすがに、名著と言われるだけのことはある。 日進月歩のジャンルを扱いながら、 発行から2年半以上の時を経ても、 決して古さを感じさせることはなく、その価値は色褪せていない。 私自身、本著を読んで、「グーグル」の本当の凄さに気付くことが出来たし、 「ロングテール」という見方・捉え方も知ることが出来た。 さらに、「ブログ」の増殖と総表現社会の到来についてや、 「オープンソース」の持つ可能性についても、認識を新たにした。 *** 情報をインターネットの「こちら側」と「あちら側」のどちらに置くべきか。 情報を処理する機能を「こちら側」と「あちら側」のどちらに持つべきなのか。 このトレードオフが、これからのIT産業の構造を決定する本質である。(p.059)実際のところ、これまで「こちら側」で受け持たねばならなかったことがらが、近年、どんどん「あちら側」で請け負ってもらえるようになってきている。ウイルス対策なんかも、その一例だろう。そして、「作業場であるインターネット世界」で、必要な作業を、オープンソースを使ってこなし、インターネット上に、そこでの情報を蓄積するようになるのかもしれない。さらに、「作業場であるインターネット世界」への扉となる「こちら側」のPC等のスペックは、さほど大きな問題でなくなってしまう日も、近い将来にやって来るかもしれない。もちろん、その時には、「あちら側」の情報管理体制は、大きく問われることになる。というか、もう既に「クッキー」等を通じて、かなりの個人情報を「あちら側」は握っている。アマゾンや楽天に接続するやいなや、「最近チェックした商品」が表示されるのは、正直言って、かなり気持ちの悪いものだと、私自身は思っている。「知る権利」と「プライバシーの権利」の問題は、今後益々大きな問題となっていくだろう。 2004年秋にロングテール論が脚光を浴びたのは、 ネット書店がこの構造を根本から変えてしまったという問題提起があったからだ。 提唱者は米ワイヤード誌編集長のクリス・アンダーソン氏。 米国のリアル書店チェーンの「バーンズ・アンド・ノーブル」が 持っている在庫は13万タイトル(ランキング上位の13万いまでに入る本)だが、 アマゾン・コムは全売り上げの半分以上を 13万位以降の本からあげていると発表したのである。(中略) リアル書店では在庫を持てない「売れない本」でも、 インターネット上にリスティングする追加コストはほぼゼロだから、 アマゾンは230万点もの書籍を扱うことが出来る。(p.100)買い物に関しては、ネットの発展で本当に便利になった。以前であれば、余程のコネがない限り、決して手に入らなかったようなコアな商品でも、検索すれば、書籍でも、音源でも、たいてい手に入るようになった。しかも、そんなにとんでもないお金を払わなくても。本当に有り難い時代になったと思う。 メディアの権威側や、権威に認められた表現者としての 既得権を持った人たちの危機感は鋭敏である。 ブログの世界を垣間見て「次の10年」に思いを馳せれば、 この権威の構造が崩れる予感に満ちている。 敏感な人にはそれがすぐわかる。 基盤を脅かされる側の新しい現象に対する反応はまちまちである。 しかし総じてウェブ社会のネガティブな面ばかりをメディアが取り上げがちなのは、 こうした危機感が形をかえて表出しているという面が少なくない。(p.146)なかなか鋭い指摘である。こういう切り口に、これまで、私は出会ったことがなかったので、まさに「目から鱗が落ちる」といった気分。玉石混合でも、参加母体数が膨大であり、その石を篩い分けるシステムが向上すれば、これまで知られることのなかった玉が発掘されるのは、当然の成り行きであろう。 コレラは19世紀の病気という印象が強いが、発展途上国ではシリアスな問題だ。 処方にカネがかかるか高いスキルが必要か、そのいずれかの治療法しかなく、 貧しくて医療スキルも低い国では、相変わらずコレラに苦しめられているところが多かった。 従来の組織的手法ではこの問題が解決されなかったのだが、 ネット上にこの課題が提示されたとたん、わずか数カ月の間に、 関連分野のさまざまな領域の見ず知らずのプロフェッショナルたちがネット上で協力しあい、 低コストでしかも訓練なしに使える新システムが開発され、 その課題は解決されてしまったのである。(p.176)まさに、インターネット世界ならではの、素晴らしい出来事。こういった「オープンソース現象」「マスコラボレーション」が、さらに広い分野で展開されることが望まれる。インターネット世界の将来は明るい、と感じさせられるお話しだった。
2008.11.16
コメント(0)
-

医療保険は入ってはいけない!
TV等で盛んにCMが流れている医療保険。 入院なんかした時には、とってもお金がかかりそうだし、きっと役立つんだろうな。 でも、ちょっと待てよ……民間医療保険の保険料って、 その中に、保険会社の経費や利益が上乗せされているんですよね……。 つまり、民間医療保険の加入者を全体としてとらえた場合、 加入者が受け取る額よりも、加入者が支払う額の方が、絶対に大きい! 加入者のために保険料を支払っているのでなく、保険会社のために支払ってる。 家計に余裕があれば、安心料と割り切り、支払い続けるのもありでしょうが……。皆さん御存知のように、医療費の実際の負担は原則として、3割。例えば、医療費が100万円かかると、窓口で30万円支払うことになります。ところが、医療費は、26万7千円を超えると、その超過部分については、1%の自己負担で済むことになっているのです。つまり、26万7000円分については、その3割の、8万100円を支払わねばなりませんが、100万円から26万7千円を差し引いた73万3000円分については、1%の7330円でいいのです。だから、本当に負担せねばならないのは、何と合計で8万7430円!窓口で余分に支払った21万2570円は、後日還付されてきます。もちろん、これは公的医療保険から支払われた医療費のみについてのお話しで、保険給付対象とならない食費、差額ベッド料、高度先進医療費は含まれません。中でも、曲者は差額ベッド料で、下手をすると余分なお金を支払うことに。この料金については、きちんと予備知識を持ち、病院と折衝しておくこと。 ***本当に必要なんですかね? 民間医療保険。と言うのも、病気やケガに対する備えの手段は、民間医療保険以外にも色々あるのです。公的医療保険や貯蓄、勤務先の福利厚生制度等がそれ。そもそも、業務上の事故やケガなら、労災で、医療の自己負担なんてないのです。サラリーマンなら、ケガや病気で4日以上継続して仕事を休み、給料がもらえなくなると、健康保険から、4日目以降、標準報酬日額の6割の傷病手当金がもらえるし(休んでいる間も、6割以上の給料が出ていれば、もちろんもらえませんが)、組合管掌健康保険に加入していれば、付加給付で負担は少なくて済むのだとか。 ***本著の結論。公的医療保険に、月々たくさんお金を納めてるんだから、最大限利用しましょう。公的医療保険料は、誰かを儲けさせるための仕組みではないので、加入者全体が納めた分だけ、加入者全体に戻ってくるようになっています。ですから、私たちが想像している以上に、実は充実した内容になっています。公的医療保険料で足らない部分は、それほど大きなものにはならないはずなので、自力で何とかできるよう、普段から貯蓄をしておきましょう。民間の医療保険に頼らずとも、その分を貯蓄に回しておけば、いざという時、医療費以外の様々な用途にも転用可能です! と言ったところでしょうか。
2008.11.16
コメント(0)
-

親たちの暴走
最近の大学の入学式には、親も出席するのだと聞いて、 「大学生ともなれば、もう一人前、親なんか出てきたら嫌だろうに…… 最近の親は、どこまで子離れできないのだろう」と驚いていたが、 アメリカでは、もはや、そんなレベルを遙かに超えていた。 ヘリコプターペアレントと呼ばれる親たちは、平然とキャンパスに乗り込む。 そこで、新入生のためのオリエンテーションに堂々と出席すると、 履修科目選択や登録手続に口を出し、その後も、成績や規則に苦情を申し立て。 さらには、学友とのケンカにまで割って入るのだとか。そして、親たちは「ヘロパット(ヘリ親の略)」から、戦闘機「ブラックホーク」へと進化。携帯で常に連絡を取り続け、子どもと共に、或いは子どもに代わって行動し続ける。しかも、そんな親の行動を、子どもは歓迎していると言うから、呆れるしかない。調子づいた親たちは、子どもの結婚まで手配してしまうのだ。 ***一方、イギリスでは、教師に対し暴力に訴える、フーリガンペアレントが横行。イギリスでは、1986年に体罰が禁止されたが、その後、1995年の校長刺殺事件以後、生徒から教師に対する暴力が問題となり、さらに、20世紀末あたりから、保護者の教師に対する暴力が激増している。 教師を20年続けているが、かつては入念に準備された授業こそがすべてだと信じていた。 面白く興味深い授業なら、生徒は十分についてきた。 しかしいまや、授業はじめの10分から15分は、生徒を席に座らせ 机の上に載せたものをおろさせ、おしゃべりを止めさせるのにかかる。 午前中はともかく、昼食後の午後の授業を行うのはもう不可能だ。 授業らしい授業は行えず、教師として給料をもらっているのが恥ずかしい。 私は先だって転職した。 そこは苦労が多い職場と心配してくれた人もいるが、 30人の子どもを1つの部屋に閉じ込める苦労に比べたら、ものの数ではない。 私の娘も教師になりたいと言う。 しかし私は引き止めている。 かつて教師は最高の仕事だったが、今は最悪の職業になってしまった。(p.160)これは、イギリスの中学校に勤めていた40代女性のコメントだ。ここに至った社会的背景の中には、現在の日本とも共通する部分が多々ある。イギリスやアメリカを手本に進めている日本の教育改革の、辿り着くところはこれなのか?いや、もう既に、その兆候は、かなりハッキリとした形で現れてきている気がする。イギリスにおいては、時代の変化にともない、公立学校の役割が変わってきたという。学校は単に子どもたちが学ぶ場ではなく、地域の人の心を癒すといった社会的サービス提供の場としての役割を求められるようになったのだと。教師って、一体何なんだ? ***著者の「日英米のモンスターペアレント」問題に対する姿勢は、本著の締めくくりとなる「第5章 『モンスターペアレント』と呼ばせないために」で見事に示されており、冷静かつ公平な分析・指針が光っている。p.74に掲載されている「運動会の玉入れ競技」のエピソードもたいへん興味深かった。
2008.11.03
コメント(0)
-

あなたの職場のイヤな奴
とにかく「クソッタレ」の連発。 ここまで連発されると、少々うんざりかも……。 連発されればされるほど、気分爽快になっていくというより、 何だか、逆にモヤモヤ、イライラしてくるような気が……。 最初に「クソッタレ」の正しい定義が示されているが、 その時点で、既に、もうかなり怪しい。 「クソッタレ」には、一過性のものと、鑑定書付きのものがあるとしているが、 いずれにせよ、その判断基準は、かなり主観的かつ一方的であるように思う。書いてある内容としては、なかなか目の付けどころが良い部分もある。「つねに勝っていれば文句を言われない?」や「急流下り作戦」、「小さな勝利を積み重ねよう」で書かれていることなんかは、「!」である。しかし、そう言った優れた部分までが、「くそったれ」の連発でかき消されてしまう。「くそったれ」という言葉を使ったところが、本著の肝であり、売りであり、それ故に、色んなところで、本著が結構読まれた理由になっているようだが、私としては、もう少し言葉を選んで、主観的な視点に偏り過ぎず、本著が書かれていれば、もう少し、受け入れやすものになったように感じる。
2008.11.03
コメント(0)
-

千里眼の復讐
私は、これまで松岡さんの書いた『催眠』や『千里眼』 それに『マジシャン』や『蒼い瞳とニュアージュ』のシリーズは、 最新刊の『千里眼 優しい悪魔』を除いては、 ほぼ全て読んできています。 この「ほぼ」というのには理由があって、 私は、基本的に一度読んだ作品は、 その後、新たに書き直されたとしても、読まないことにしているからです。 お金も時間もかかりますからねぇ……。ですから、ハードカバーで出版された作品については、全て、ハードカバーで出版された段階で、私は読んできたので、逆に言うと、同じタイトルの作品が、文庫として新たに出版されたとしても、そちらの方を手にすることは、全くありませんでした。ところが、松岡さん、途中から、文庫版として書き直した作品をもとにして、新たな作品を展開させるといったケースが増えてきたので、もとのお話しか知らない私にとっては、ちょっと厳しい状況が出てきました。話が、うまく繋がってこない……、でも、そこは目をつぶってガマン。そんな私なので、松岡さんが、小学館から角川へと、文庫版の出版社を乗り換えた後も、新シリーズは、きちんと読み進めていますが、千里眼のクラシックシリーズや、その他のシリーズの完全版については、手にしないことにしていました。ところが、そうもいかない状況が発生してしまったのです。何と、松岡さん、クラシックシリーズにおいて、「書き直し」ではなく、全く別な「新しい作品」を書き始めてしまったのです。それが、この『千里眼の復讐』。前作に当たる『運命の暗示』でも、もとのお話から、かなり変更があったらしいのですが、タイトルは、以前出版された時のまま、同じものが掲げられていました。ですから、あくまでも「書き直し」のレベルだったわけでしょう。ところが、『千里眼の復讐』は、お話として、既刊の作品と重なる部分が全くなく、さらに、タイトルまで完全に変更してしまった、正真正銘の新作。これでは、私としては、放置しておくわけにはいきません。新作なのですから、読むしかない、ということになったわけです。 ***山手トンネル内でタンクローリーが爆発炎上。その構内に閉じ込められた人々に対し、デスゲームの幕が切って落とされる。主犯は、友里佐知子に鬼芭阿ゆ子、そして緑の猿・ジャムサ。イリミネーターという刺客を次々に送り込み、血の海地獄が形成される。構内に閉じ込められた美由紀が、いつもの如く大活躍。心強い(?)協力者も現れて、デスゲームを次々にクリアしていく。そして、なぜ、このゲームを、友里が行ったのかという理由も見事解明。それを逆手にとって、見事な逆転勝利。 ***個人的には、人間が次々に殺されていく、この手の話は好きではありません。しかも、美由紀が中学生に対し、特別な思いを抱くのも、ちょっと……。『洗脳試験』に比べると、かなりの長編作品に生まれかわっているけれど、お話としては、あくまでも次作への繋ぎにすぎないという印象です。
2008.11.02
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…
- (2024-09-12 00:00:14)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2025年 1月号』 冒頭…
- (2024-12-04 09:00:10)
-
-
-

- アニメ!!
- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…
- (2024-11-14 14:54:38)
-