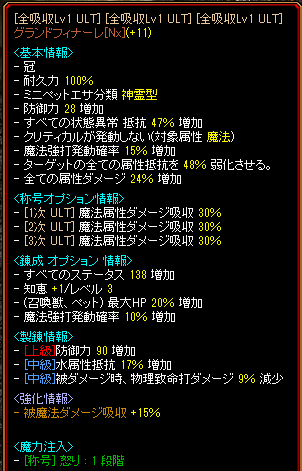2020年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

白髪一雄展 東京オペラシティーアートギャラリー
はじめて白髪一雄を知ったのは、それこそリニューアルオープンしたアーティゾン美術館(ブリヂストン美術館)のこの作品です。タイトルは、「観音普陀落浄土」↓この画家の作品のタイトルは、無題も多いのですが、このように仏教的(密教)なものや水滸伝の英雄の名前を付けたものが多く、漢字が並んでなにかぞくぞくするような感覚になります。初めて見た時に、厚塗りの絵の具の中の色の混ざり具合、グラデーションが美しくうっとりと見とれました。筆で描くのは大変だろうと思っていたのですが、後日、この画家の作画方法をギャラリートークで聞く機会があり、唖然としました。それ以来、強烈にこの画家の名前が脳裏に焼き付けられ、機会があると楽しみに足の指の跡を探しています。10年ほど前に横須賀美術館で見た展覧会は、今でも強烈な印象が残っています。10年ぶりの今回の展覧会は、そんな白髪の初期のまとも?な時代の作品から、独特の抽象画まで生涯にわたる作品が60点あまり展示されています。初期の頃のちょっと不気味かつほのぼのとした味わいの絵も面白かったです。(どちらかというと抽象画っぽいのですが)あのアクションペインティングがはじまって、しばらく経って、獣皮に赤い絵の具を塗りたくった作品などが現れます。血の匂いと暴力的なエネルギーが感じられて、頭がクラクラとしてきます。水滸伝の英雄たちのイメージに当てはめたとのことです。その後、白髪は僧侶となり、密教の世界を具現化するような絵に変わっていきます。打って変わって、静謐さが心に突き刺さるような色彩表現に変わっていきます。足ではなく、板切れ(長いへら)で描いたそうです。そして、晩年は再びにフットペインティングに回帰していきます。とにかく、驚くほどの厚塗りの作品があったり、勘弁してくれと叫びたくなるような激しさを持つ作品など、何が何だか分からないが「美」を味わうことのできる素敵な展覧会でした。
2020年01月25日
コメント(0)
-

見えてくる光景 コレクションの現在地 アーティゾン美術館
新装オープンしたアーティゾン美術館に開館2日目の日曜日の朝、出かけました。日時指定の前売りを購入し、スマホの画面を見せて入館します。飛行場並みにセキュリティゲートをくぐっての入場です。広々とした空間を長いエスカレーターに乗って、6階の展示室に向かいます。現在は石橋財団所有の作品を中心に「見えてくる光景 コレクションの現在地」が開催されています。5年ぶりに見た懐かしい絵の数々。そして新収蔵の作品も多数ありました。今回の新収蔵作品のひとつにアンリ・ファンタン=ラトゥールの静物画がありました。花瓶に生けられた花々のみずみずしさ。いい絵が加わりました。その他の新収蔵作品では、松本俊介の絵もよかったです。全体的にはキュビズムの絵画から内外の抽象画が多かったような気がしました。マーク・ロスコの大作もありました。ロスコの明るい作品はあまり日本では見たことがないので、東京に来てくれてうれしいです。展覧会自体は2部構成となっていて、第1部では「アートをひろげる」と題して、国内外を問わずに140年間の作品を時代別に並べています。第2部では「アートをさぐる」と題し、装飾・古典・原始・異界・聖俗・記録・幸福と7つの観点別に作品を展示していました。日本美術のコーナーでは、暗い部屋に金色に輝く洛中洛外図屏風が展示されていました。この屏風だけでも、じっくり眺め、ずいぶんと間がかかりました。今後、ここにどんな作品が展示されるのか楽しみです。私が生まれて初めて、出かけた美術館が、ここブリヂストン美術館でした。高校1年の時、中学校の担任だった先生に連れてきてもらいました。そこでモネの「黄昏のヴェニス」を見て、なんと美しい絵なんだろうと感動したのが、私の美術館巡りの原体験となっています。その後、何度この美術館に来たことでしょう。新たなアーティゾン美術館にもこれからたびたび通うことになりそうです。
2020年01月22日
コメント(0)
-

ニューヨーク・アートシーン 埼玉県立近代美術館
今回の展覧会は、アメリカの現代アートの変遷という構成となっており、初心者にとって、とても分かりやすい展示であった。といっても、それぞれの作品が、分かりやすいものばかりではない。そこは、現代アート、「なんだこれは!」と思うもの、難解なものも多数あり。昔はそれぞれの作品を理解しようと努めてきたが、今は、難解なもの、分からないものはスルーして、美しいもの、楽しいものだけをキャッチしようと思っているので、現代アートを見るのも好きになってきた。だいたい、今回も出展されているデュシャンの泉を美しいと思う人がいるのかどうか。楽しいと思う人はいるかもしれないが、私はまったくスルーでした。今回の展示は、はじめに大好きなマーク・ロスコが出てきて、もうグッと来てしまった。特に滋賀県立近代美術館のナンバー28がいい。もわっとした黒枠の中の、濃い茶と茶色。上部に鮮烈な白の色面。ロスコの絵のに立つと、自分が生まれてくる前に見ていた光景はこんなものだったのではないかといつも想像するのです。今回のチラシにもなっているトム・ウェッセルマンのグレート・アメリカン・ヌードもいい。見ていて、理屈抜きにして楽しめる。背景のモディリアーニの絵もいいし、マティスっぽいピンクの色面だけのヌードも美しい。トム。ウェッセルマンのもう一枚のシースケープ#8も楽しい。上部に突き出した一本の足。横尾忠則っぽさがたまらない。リキテンスタインとウォーホルはそこそこにして次のコーナーへ。モーリス・ルイスやフランク・ステラも色面構成がきれいなので比較的好きな画家。特にモーリス・ルイスの作品は、画家の意図ではなく、偶然によって生まれる美しさ。そこが楽しい。ミニマル・アートとコンセプチュアル・アートのコーナーは、観念的すぎて分からないのでスルー。草間彌生さん、ごめんなさい。河原温のキャプションを読んで、この方、最後まで人前に現れなかったのかとそんな感想を持ちました。最後、新表現主義のコーナーで、また心が活気づきました。杉本博司の写真はいつ見てもいいし、バスキア作品にまた出会えて嬉しかったです。依田寿久という画家は今回初めて知りましたが、赤と黒の画面のパワーに痺れました。調べたら、息子さんの依田洋一朗の展覧会は以前、三鷹で見たことがあり、昨年夏にこの親子3人の展覧会を三鷹市美術ギャラリーで開催していたのでした。次回、竹橋か木場に行ったときは要チェックだと確認しました。
2020年01月05日
コメント(2)
-

令和元年12月に読んだ本
12月の読書メーター読んだ本の数:17読んだページ数:5990ナイス数:253なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか(祥伝社新書321)の感想現在は、断捨離、本は買わない。図書館に予約。家にあるものは捨てていくというポリシーを貫いていたのですが、書店の誘惑に再び捕らわれてしまった。読了日:12月02日 著者:嶋 浩一郎定年後 - 50歳からの生き方、終わり方 (中公新書)の感想実際に定年した自らを振り返る。再就職したが、眉間にしわを寄せている自分がいる。うーん、いい顔になっていない。読了日:12月02日 著者:楠木 新鏡の背面の感想キリスト教系福祉施設で焼け死んだ女性。その実態は聖母か稀代の悪女か?という謎を追うミステリ。長かったけれども、読み応え十分。途中、オカルト方面に入り込むが、バッサリと解決してくれてすきっとした。延々と読み進めてきた割にもっとドラマチックな結末となり、カタルシスを感じたかったとは思う。読了日:12月06日 著者:篠田 節子終わった人 (講談社文庫)の感想身につまされました。いくら功成り名を遂げても、終わってしまえばそれまで。現役の頃のときめきが忘れられないと、大きなしっぺ返しが来る。それにしても9千万円個人で払っても、まだ残りがあるなんて!読了日:12月08日 著者:内館 牧子歪笑小説 (集英社文庫)の感想業界の内情暴露。面白い。抱腹絶倒の短編集。中にはほろりとする作品もあり、いい味わい。ラストの広告には唖然!読了日:12月08日 著者:東野 圭吾事変の夜 満州国演義二 (新潮文庫)の感想関東軍による謀略に次ぐ謀略。満州傀儡国の誕生まで。天皇暗殺まで画策していたのだろうか?疲れるが、歴史の勉強になる。読了日:12月10日 著者:船戸 与一定年ゴジラ (講談社文庫)の感想20年前から気になっていた本。高齢者の話だと敬遠していたら、いつか当事者となってしまった。当時は雇用延長制度なるものはなく、今とちょっぴり感覚が違う。作者によれば自分の父親世代を想像して描いた作品とのこと。早く還暦を迎えた作者の話を読んでみたい。(まだ数年後)第4章「夢はいまもめぐりて」には泣けた。亡き母への愛、故郷への思いがどっと押し寄せる。解説を鷺沢萌が書いていた。故人の「がんばらなくていいよ」という言葉が、胸に刺さる。読了日:12月13日 著者:重松 清さよならの儀式の感想宮部みゆきのSF短編集。宇宙人、タイムスリップ、ロボット、レプリカントなど多様なSF体験ができる。少年犯罪を描いた「聖痕」。類似作品をいつかどこかで読んだような気もするが、ネット社会に潜む悪意を描いて面白い。読了日:12月15日 著者:宮部みゆき営繕かるかや怪異譚 その弐の感想不動産には興味があるが、家には思いがこもる。そう考えると中古物件には心配が多い。心理的瑕疵有なんて物件はゾッとするが、どんなものか知りたい気持ちもある。今回もほとんど古い家屋にまつわる怪異。しかし、どの話もきちっと解決されていて一安心。読了日:12月18日 著者:小野 不由美逃亡小説集の感想犯罪小説集に比べ、肩の力を抜いて読むことができた。どこかで聞いた事件が元ネタだが、「逃げろお嬢さん」は、エリカからのりピーを思い起こしタイムリーだった。どの主人公も、冷静になれば逃げてもどうしようもないと分かるのだが、そこはそうはいかない人間の悲しさがあふれ出ていた。読了日:12月20日 著者:吉田 修一珍品堂主人 - 増補新版 (中公文庫)の感想古美術を扱った本ということで手に取った。海千山千の骨董品屋である主人公をめぐるドタバタ劇。骨董の世界は面白そうだが火傷しそう。モデルは秦秀雄という実在の人物で蘭々女は北大路魯山人であるとのこと。ほんわりとした終わり方は好き。読了日:12月21日 著者:井伏 鱒二沙高樓綺譚 (文春文庫)の感想都会の不思議な建物で繰り広げられる奇譚を語る会。背景は上々。語られる内容もそれぞれ興味深く読んだ。「糸電話」のストーカーは怖い。「立花新兵衛只今罷越候」の幽霊話は笑える場面もあり面白く読めた。読了日:12月22日 著者:浅田 次郎いちまいの絵 生きているうちに見るべき名画 (集英社新書)の感想私は国外に出たことがないし、専門性も著者の足元にも及ばないが、著者とはほぼ同世代なので、アートに関していろいろ被るところも多く、非常に身近に感じられた。なるほど、著者が選んだ26作品の中でも、ダントツなのはピカソとダ・ヴィンチか。自分だったらと思いながら、楽しく読みました。読了日:12月23日 著者:原田 マハマルセル (文春文庫)の感想日本の展覧会で、実際にロートレックの絵が盗難にあったという事件を始めて知った。この小説はその事件を題材に、世界的な贋作つくりの組織や、主人公の出生の秘密などを絡めたミステリ。話が大きくなり過ぎてどうなることかと思ったが、なんとか落ち着いて良かった。読了日:12月28日 著者:高樹 のぶ子お孵り (角川ホラー文庫)の感想現在も残る限界集落での大量殺人事件をめぐるサスペンスホラー。そこに生まれ変わりとか新興宗教、シタイという公安組織など絡めて、話が大きく広がっていくが、さくっとうまく収斂されていく。山羊原麻織捜査官シリーズになりそうな感じ。読了日:12月30日 著者:滝川 さり大相撲の見かた (平凡社新書)の感想長年、相撲を見ているが、なんとなく分かっているつもりでいた言葉の意味を再確認した。現役力士の取り組みの見どころ解説の部分は、すでにほとんど残っていない力士が多いので、もう少し別の企画にしてほしかった。読了日:12月30日 著者:桑森真介レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想ホラーなのかと期待していたが、そうではなかった。中年男が過去のトラウマから脱却した話を語る「沈黙」と「七番目の男」が良かった。読了日:12月31日 著者:村上 春樹読書メーター
2020年01月01日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1