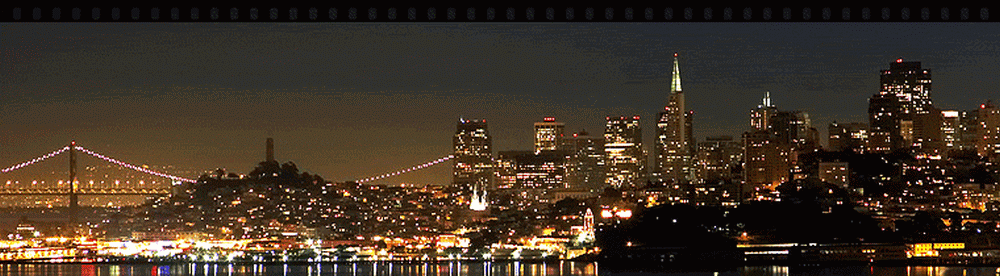2008年11月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-

誰だって最初から出来る人なんていません!!
本日は、私としては過激なことを言います。勘違いしないで頂ければと思っていますが、、、私の管轄は接客サービスなのですがその中でも力を入れて管理しているのは主に営業部門です。営業マンとして新しく入ってきたり配属されてきた社員を指導する際、必ずやっているのが、徹底的に元気と誠実さと感謝の気持ちを教え込むことです。これが理解できない社員はいずれは辞めてもらいます。どの部署にいても役に立たないからです。理解しているかどうかは1週間ごとに書かせるレポートとヒアリングで判断します。レポートはこの1週間自分は元気と誠実さと感謝の気持ちをどう実践したか、です。それを更にヒアリングで確認します。肝心の営業マンとしての指導もしますが我社の営業マンとしてやっていくためには、最初の半年くらいがうまくいかなくても気にしない、です。最初はミスを織り込んで考えていく。誰だって最初は原木なんです。うまくいかないことだらけです。一生とはいかなくても、5年、10年と続けていくつもりなら、最初の半年がうまくいかなくても気にしない、です。その間に徹底的に元気と誠実さと感謝の気持ちを自分のものにしてくれたらいいんです。結婚式やお葬式だったら、“ちょっとぐらい失敗してもいいや”なんて思えませんよね。でも、これから営々とやっていくつもりならば最初はミスを織り込んで指導していくんです。「すべてを糧にしていく」んです。勘違いしないで頂きたいと思っているのは、適当にやっていいとは絶対に思いませんし、ミスを開き直っていいとも思いません。全力で、あらん限りのことをやって、それでもうまくいかなければ陳謝し謙虚に受け止めて、次に活かすということを身につけて欲しいんです。『 同じ過ちは2度と繰り返すまい 』唇をかみしめる悔しさがあるからこそ、次に活かせるのだとしたら一度失敗しなければ改善できませんよね。最初からうまくいって、次からもず~っとうまくいったら改善なんて必要ないのですから。だから、やりたい!と思ったらやってみる。全力でやってみる。うまくいかないことは次に活かす。“やってみたいな~でも失敗したらどうしよう。。。”これが一番良くないですよね。糧にするチャンスをフイにしているかも・・・元気と誠実さと感謝の気持ちを身に付け、営業マンとして最初の2~3ヶ月がうまくいかなくてもそのうまくいかなかったことを成長の糧としていくことに気づいたとき、ほうっておいてもどんどん勉強する人間になる、と信じて今後もときに優しくときに厳しく、熱血管理職は行く!ン?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.30
コメント(2)
-

伝えられなければ「ないのと同じ」です
どんないいい商品でも上手に伝えられなければ『0』です。話し方と内容がそろって、初めて本来の価値が出ると思うんです。例えば、とんでもなく上手な話をする営業マンがいるんだけれど商品にまったく価値がないとします。売れるでしょうか?売れますよね。エスキモーに氷を売れるような営業マンですから、何でも売れます。では、買ったお客さまはもう一度その商品を買うでしょうか?買いません。では逆に、話がめちゃくちゃ下手で、何を言っているの変わらない営業マンだけれど商品は素晴らしい!という場合はどうでしょう。売れるでしょうか?その営業マンからは、滅多に売れないでしょう。買ってくださった数少ないお客さまの多くが、もう一度買ってくださるかもしれません。でも、買ってくださる方の人数がそもそも少ないので、広まっていくのは非常に遅い。この不況下では、そのうちに販売中止になってしまうかもしれません。やっぱり、内容+話し方の両方がないと【大損】してしまうんですヨ。内容はご自身で考えることが第一ですが肝心の話し方は、1人では身につけられません。人前で話す経験と、内容をもっと良くするためにどうすればいいか?気づかせてくれる、教えてくれる機会やアイテムが必要です。素晴らしい話し方を身につけて、あなたのお客さまを増やし商品やサービスで喜んでくださる方をもっと増やしませんか?伝えられなければ、ないのと一緒なのですから。今、十分に伝えられていますか???こんな本を読んでみては如何でしょう?結構勉強になりますヨ。『なぜあの人は人前で話すのがうまいのか?』中谷彰宏著 今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.29
コメント(0)
-

ノートを活用しましょう!!
みなさ~ん、こんにちは。私は毎日仕事やプライベートで在ったことや、思ったこと、気付かされた事などをノートにメモるようにしています。時折そんな中から適宜、社員にシェアしたりしています。いつの間にか結構なページになっています。内容はこんな感じです。◆~◆の間がメモです。◆「本来の自分を確認するんだ」 誰でもが過去から現在までの中で、自分の姿はこういうものだとそれなりに承知をしている。でも本来はもっと巨大な自分もあるはず。「本来持っている可能性」の現実化をしてきたとするならば、「もっと違った自分の姿」も作れたはずだ。けれども、自分が自分に妥協をしていたために、そのような自分を発見できずに今を生きている方々がたくさんいるのではないか?◆ここまで。いいたいのは、本来貴方が持っていた可能性を開くためには、優れた先輩を目標にしてトライをすることも素晴らしいことですし、そのようにしてトライをし続ける中に初めて、自分も気がつかなかった本来の自分の確認が、やがて自分でできるようにもなって参ります。自らが想像できない自分にはなれません。「あの人のように、あの人を超えて」と明確にして、その人との距離を近くしていく。本来の可能性を実現していく中で本来の自分を確認していくッちゅうことを言いたいのです。 ◆「人生に対する責任を!」 健全な会社はその正しい経営努力があってこそ健全に発展をしていく。人も様々な努力を積み重ねていく中でこそ伸びていく。伸びていく中で少しずつ幸福が現実化出来てくる。それが本来の姿では。人は誰でも、本来的にのびる可能性を持っている。ならば、その能力の花を咲かせるのは、自分に対する責任ではないか。どんな花を咲かせるのか?それは夫々の個性によって色々だけれど、一切は幸福になることが全ての目的である。◆ここまで。要するに、人は誰でも幸福になる権利があるのです。それを実現させるのもさせないのも、全ては自分ですから、自分に対する責任は他の誰にもなくて、ただただ自分の中にこそあるのです。自分の人生、それはその人の自分の人生経営に等しいと考えます。 ほんの一部ですが今読んでも結構いいこと書いてるなっと、自画自賛(笑)続きはまたいつか書きますネ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.28
コメント(1)
-

できる人は返事もいいもんです!!
アンマやら白馬やら、大相撲もいよいよモンゴル相撲と名前を変えてもいいのでは?マッ、今の相撲に興味はありませんからどうでもいいですけどネ。さて、本日のお題「返事」って~やつに移りやしょうかぃ。(お?江戸っ子?)私は生来物事はハッキリしないのが一番嫌いなのです。うじうじグズグズもごもごと腐ったような応対しかできないやつは信用しません。こういう輩にできるやつは滅多にいたためしがね~んでやす。(役人にはわんさか・・)そんな私に対し、さっき社内で名前を呼んだのに返事をしない人間がいましたので、「呼んだけど聞こえなかったのか?」と聞いてみると、聞こえていたと言う。「だったらちゃんと返事をしなさい!」とカミナリを落としました。カミナリ「あのないいか、返事をする時に、大きな声で「はいっ!」と言うか、さらに手を挙げて「はい!」と返事をするか、聞き取りにくい小さな声で「はぁ~ぃ」と言うか、、、呼んだ人は、どの返事が気持ち良いんだろう?なんて考えてみたことはあるかい?お前さんヨ。」その人は、用事があったから声をかけたのです。返事の良し悪しによって、どちらの人に用事をお願いをするか、また、どちらの人に(今後)良くしてあげるかというと、当然!良い返事をしてくれた人、態度でも表してくれた人、ということになりますネ。人間は、ヒトから好かれたいと思っている。好かれたいと思っているのに、好かれようとする努力をしません。好かれようという形を、自分で作りません。人間同士は、思っている心(気持ち)だけでは通じません。形にしなければ、相手には伝わらないのです。ですから素直に、「はい」という返事を形にして、相手にわかるようにすることが大切なのです。「はい」は「拝」です。相手を拝む心、自分自身を拝む心です。「はい」と言ったことを行動に移すと、素直で謙虚になりませんでしょうか?さらに、返事をするとき、「はい」と言っているでしょうか?あるいは「はいはい」でしょうか? 「はいはい」と言う返事は、本当に人(相手)をバカにしています。「はい」は「拝(おがむ)」、尊敬する言葉です。ですから、大きな声で素直に一回「はい」と答える。「はい」の返事が大切なのは、社内でも、お客様に対しても同じです。自分がお客様として店に行ったとき、店員が「はい」と返事をしてくれれば気持ちが良いのと一緒です。我が人生は、常にメリハリ、ハッキリいきたいものです。私はいきます。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.27
コメント(2)
-

良い書は、良い師に出会うのと同じですヨ!!
「引き寄せ」って後出しジャンケン? のような気がする今日この頃、皆さん今日は!本のお話です。引寄せたりしなくても人には先人の書がありますぞぃ!!中国の古典はまるでスルメのようですネ。噛めば噛むほど味が出てきますもんネ。本当に中国の古典のエキスである格言や諺はなかなか味わい深いものがあるものです。また、我が国の歴史小説や日本の精神性を主題にした本、先人たちの人生を書いた人物書など、人生を語ったものや生き方の中での戒め、日々の生活の道筋を説いたもの等我々の人生に大きな影響を与えてくれるものが多くあります。時には人生の生き方を説いてくれるし、またある時は処世術や事業の勘所、ビジネスマンの精神性などを教えてくれます。これらの書に共通するのは、昨今の企業の不祥事等にみられる、経営者がやってはいけない事や、企業倫理や経営者の人身掌握術など様々な事を語りかけてくれます。中国古典に出てくる格言や諺は一見難解なように思われますが、現在発行されているものの大部分は、誰にでも分かるように平易な口語体で書かれ解り易く解説もされています。だから私のような者が読んでも十分理解できるのです(笑)。色々な本を読んでいると、心に残る言葉や感動する言葉に出会うものです。またハッと目の覚める言葉や心の底から抉られるような言葉に頭を打たれることもあります。伊藤肇氏の「十八史約」などは、遥か遠く中国の歴史の舞台を生きた人達が、戦い、語り、生きた中に現代に生きる我々に通ずるエキスが書かれていてとても勉強になりますヨ。中国古典の中には数千年から数百年前まで書かれたものまでありますが、どれをとっても現代に通ずる知識と知恵、人間の根源的な生き方が根底にあります。事業で困難にぶつかった時はそれを解決する教えがあり、これから新しい事業に挑戦しようとするときは知恵やエネルギーを与えてくれる。人生の苦労を背負った時にはそれを乗り越える勇気をくれたりするのです。家庭でのいざこざや対人関係のトラブルにあった時には、それらをおだやかに解決する方法を教えてくれるものですし、自分が過信や慢心のときには自らを戒められます。「良書に出会うは良き師に出会うが如し」といわれますが、偉人や先人たちは「座右の書」や「座右の言葉」などをもち、常に自分の側に置いて愛読したといわれます。そしてその「座右の書」の言葉がその人に知恵や勇気、エネルギーを与え大きく導き大成を成し遂げさせたといえるのではないでしょうか。良書は人生を豊かにする先哲、先人からの言葉が宿っている「言魂」といえます。我々は尊敬する人や畏敬の対象とする人のお話や言葉を素直に受け入れられるものですよね。そしてその言葉に触れるだけで身震いするほど感激や感動を得られ、心が素直になり、なんのわだかまりもなく行動に移せるのだと思います。言葉とは不思議なものですね。心に響く格言、諺、言葉、書で出会うことで自分が磨かれ、人生がより豊かになる、事業の成長に導かれるのではないかと思うのです。 皆さん本を読みましょう、良書をネ!!今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.26
コメント(3)
-

自分を愛することも、必要ですヨ!!
皆さんの「心のビタミン」にでもなれればいいナと思いつつ毎日書き込みしています。今日はちょっと自己愛と言葉について私の短観を書いてみます。自分に価値があると思えなければ、厳しさに耐えられません。途中で嫌になったとき、あきらめたくなった時、くじけそうになった時、最後の砦は自尊心だと思います。自分を尊敬できるか?自分に自信があるか?自分が好きか?自分を愛しているか?自分の人生に満足しているか?私は、まだまだですネ。一生こうやって、「まだまだ」といいながら上を目指すんだろうな~と思ったりします。(それがいいのかは、分かりませんが)間違って頂きたくないのは、自分中心に考えようと言うことでなありません。念のため!!普段我々が何気なく使っている「言葉」ですが、言葉には「言霊」と言って、不思議な力があるようです。「叶う」という漢字は、「口で十回言うと叶う」と書きますね。それくらい何度も言っていると本当に実現するということで、言葉の力を大昔から人々は感じていたということになるのではないでしょうか。 言霊(ことだま)とは、一般的には日本において言葉に宿ると信じられた素敵な力のこと、と検索すると出てきました。ところが驚いたのは、日本だけでなく他の文化圏でも、言霊と共通する思想が見られる、という事実があります。う~む、言葉の力はあなどれません!今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.25
コメント(1)
-

だるまさんが転んだ?
昨日わが社のオーナーと話していた中でとてもいい話がありましたのでシェアしますネ。結構かんたんそうで難しい内容かもしれません。よ~くかみ締めてみてください(笑)。みなさんよくご存知の、選挙の時など目に墨を入れるだるまのモデル、そう「達磨大師」さん。その達磨さんがある日ある時お弟子から聞かれたそうです。「お師匠様にはその力があるのに、なぜ人を救わないのですか?」150歳まで生きたといわれる達磨さん。多くの方がその教えを請おうとしていました。でも、達磨さんは口を開こうとしない。「なぜ、あなたには伝えるだけの言葉も、知識も、経験もあるのに伝えないのですか? その言葉で人を救うこともできるのに、なぜ救おうとしないのですか?」だるまさんが転んだ・・・じゃなくて一言だけ伝えたそうです。「全世界を見られる存在になったら、なぜそうしないのかが分かる」その理由はこうです。話を聴きに来る人が、私(達磨)の答えだけを求めているならば、却って本来の姿を誤らせてしまうからだ。ただ答えを得ても意味がない。その答えを得るまでの苦労、大変さを味わうからこそ気づけることがある。成長できる。ということなのですネ。達磨ならどう考えるか?を会得するには、自ら行動、確認しなければならない。人を救う力があるとして、別の行動を通してその人の力を最大限に発揮しているならば、その人のしていることは間違っているのか??自分が正しいからといって、他の人は間違っているといえるのか?全力を尽くして行っていることがあるならば、それでいいのではないかと思います。どんな仕事でも、家事や育児でも、趣味でもスポーツでも貴方の全力を注げることであればいい。全力を尽くす中で誰かに答えを求めるならば、その答えをその身で体験し、確認することが大事なんだと教えられました。改めて体験、確認することの必要性を実感しました。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.24
コメント(1)
-

あなたも千里の駿馬になりましょう!!
ホント、中国の古典には成功哲学がたくさんありますネ。本日はこれです。『世有伯楽、然後有千里馬』<世に伯楽あり、然る後に千里の馬あり>と読みます。「伯楽」とは、中国では馬の資質を鑑定する名人の事です。日本で言えば、馬の売買人の「馬喰(ばくろう)」の名人の事をいいます。ご存知でしたか?「千里の馬」は中国の古典に登場する「一日千里を走る駿馬」でとても優れた馬の事をいいます。昔、中国である男が自分の持っている駿馬を売ろうして、毎日毎日、馬市に行くが、いっこうに馬が売れません。男はこの馬は駿馬だから高く売りたいと思っていますが、売れないどころか馬に目を止めてくれる人もおりません。そこで男は伯楽に行って「どうか馬市にいって私の馬の周りをゆっくりと廻り、去る時は後を、繰り返し振り返り見てください。謝礼はたっぷりさせて頂きます。」と頼んだ。伯楽は、さっそく馬市に行ってその馬の周りを廻り、去りぎわにも振り返り振り返りしてその馬を見た。すると、この馬は伯楽が目を止めるような優れた馬であると言う事で、馬はあっという間に数十倍の高値で売れたという。この馬も、ただの男が持っていたのでは、ただの駄馬にしかすぎない。「千里の馬」も伯楽がいたからこそ、その資質と価値が見いだされたのですネ。現代に置き換えると、こうなります。企業は人なりと言います。優秀な社員によって会社は伸びます。しかし社員の能力を見い出し伸ばすのは社長や上司の能力です。どんなに優秀な社員がいてもその能力を見いだす力が社長や上司に無かったら、その社員はただの駄馬にしかすぎないのです。経営者の中にはややもすると自分の力に自信を持ち過ぎて、社員の能力を見い出してやれない人も多いようです。社員からしてみれば、自分が能力を発揮できるのは、自分の能力を見い出してくれる経営者や上司に巡り合った時なのです。このような意味あいで、社長は社員の資質を見い出し活かす「伯楽」といえるのです。どこの会社にも埋もれた「千里の馬」がいるものです。それを見つけ活かすのが社長や上司の仕事と言えます。<世に伯楽あり、然る後に千里の馬あり>まず経営者や上司が、社員の資質を見い出す事のできる、自らの資質を磨く事であります。そうすれば「千里の馬」=優秀な社員も育つ事を教えてくれておるのであ~ります。伯楽を目指すか~!!ン?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.23
コメント(2)
-
カフェってぇものは・・・・
そろそろカレンダーの準備でしょいや~、今日も忙しかったです。朝一から婚礼の迎賓一般宴席の迎賓そして送賓新たな迎賓とず~ッと続き、今やっと事務所に戻ってこれを書いています。少々疲れました。今美味しいコーヒーを飲んでいます。そこで本日はまたまたコーヒーの薀蓄です本日は「カフェ」についてお話したいと思います。これをお読みになられている方は多分コーヒーを好きな方と思いますので、普段カフェに行くという方も多いのではないでしょうか?私も仕事上お客様との待ち合わせなどでカフェにはよく行くほうです。いわゆるカフェといわれるお店ですが、10年前と比べますととても、高いレベルに進化していると思います。一昔前の「喫茶店」と比べて論じることはとても出来なくなっています。店の内装にしても昔の喫茶店は何か画一的な内装がほとんどだったように思います。それがいまやイタリア型のものもあれば、フランス型、アメリカ型のものもあり、変り種として和風カフェという形態もあるほどバリエーションが増えていますネ。このように色々と多くの進化が見られるなか、特にすごくなったなぁと感じるものが「ケーキ」です。海外でもこんなに高いレベルでケーキのバリエーションが楽しめる国はそうそうありません。これはレストランなどで食事をした後に出るデザートにおいても然りです。日本のレストランで出てくるデザートはいまやかなり高いレベルになっていると思います。もちろん昔の「喫茶店」でもケーキはありました。やはりコーヒーと共にケーキがあれば、双方の味わいがより引き立つからですネ。ただ昔「喫茶店」で用意していたケーキの大半は「ドライ=乾き物」と言われるものでした。たとえば、「アップルパイ」や「チョコレートケーキ」「レモンパイ」といわれるものです。これはどうしてかというと、これらの種類のケーキは、冷凍庫にいれておけば日持ちがしたからです。日持ちがするということは、それだけムダが出ません。だから日本のカフェで楽しめるケーキというのは、当初はそれほど種類がなかったはずです。それが今やどうなったか?東京、大阪といった大都会の人気のカフェと言われる店に行くと、多くの種類のケーキが用意されています。それらには生クリームやフルーツが当たり前のようにトッピングされています。これは冷凍保存の技術と、運送形態の進化につきます。この二つが進化したおかげで今の日本のデザートはすばらしく進化しています。コンビニエンスストアで売っている廉価なデザートにおいても、味の面ではかなりのレベルであることは、専門家も認めているところなそうです。いよいよここから本題で、問題はそういう風に味が進化・向上したケーキ等を味わいながら一緒に飲むものは、それと同じレベルのものでなければいまや受け入れられることができないという点です。皆さんもご承知のように、これまでのカフェにおいては、案外コーヒーの質というものはあまり重要視されていませんでしたよネ。しかしこれほどケーキが進化してきているということは、それと比例してコーヒーの品質にもこだわる店がもっと増えてくることになってくるでしょう。美味しいケーキとコーヒーが味わえるカフェ。カフェファンの私にとって、それはとても嬉しく楽しいことです。皆さんは如何です?えっあまりこだわらない?・・・ダメですよ、何事も今より一歩でも深みを求めるようにしてくださいましな。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.22
コメント(2)
-

みなさ~ん 大好きです!本当にありがとう・・・。
すみません、いきなりわけのわからないことを。。。でも、本当なんです。こうして、ほぼ毎日ブログに書き込みしているのを読んでくださっている皆さん。私は、あなたが大好きです。なぜならこうしてブログを読んでくださっているから。毎日2時間かけて書いているブログ。「今日は何をお伝えしよう?」毎日、それを考えながら出勤しています。仕事中もそれ以外も24時間、題材を探しています。車に乗っていても、近くのスターバックスで抹茶ティーラテの出来上がりを待っていても、打ち合わせをしていても、ご飯を食べていても、「次のメールで伝えられることはないかな?」って無意識のうちに探しています。こうして、毎日のように書き込みを続けているうちにコメントをくださる方も少しずつ増えてきています。(いやらしいコメントやトラックバックもありますが)最初の頃は、アクセスはありますがコメントとかはなく、本当に砂をかむような状態で書き込みをしていました。手探りではじめたブログでしたが、やはり手応えがないと寂しいもんですネ。でも今は、毎日アクセスしてくださる方もでき、時々はコメントをいただける方もいらっしゃいます。本当にうれしいです。皆さん大好きで~すありがとうございま~す。これからも皆さんの支えがあるんだということを励みに、益々生意気な薀蓄を語らせて頂きますので何卒宜しくお付き合いをお願いいたします。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.21
コメント(4)
-
値引き?
そろそろカレンダーの準備でしょ本日のテーマは【値引き】です。うだつの上がらない営業マンは、「安くすれば物が売れる」と思っています。ところが、お客様は、安ければ買うか?というとそうではなく、お客様は「“高くて良いものを安く”買いたい」と求めているのです。これは旅行に行ってお土産を買う時、「安くて良いものはないか?」と探しますが、それは上げる方の都合で、もらうほうにとっては(安くて良いものではなく)高くて良いものをもらいたいと思うのと同じです。そこで、値引きをしなくても売れるためにどうするかというと“商品に付加価値をつける”ことです。例えば、昔は若かったお嬢さん達(失礼)に「これは、あの韓流スターが使っていたのと同じマフラーですヨ」と言ってお土産を渡すと、3,000円で売っていたマフラーが、30万円の価値になるのです。大切なことは、値引きをする前に、どうやってこの商品に付加価値をつけていくか、です。安易に安くするより付加価値を付けて高く売ったほうが、同じ商品を売っても、売れるのですネ。そのためには、お客様がどういう価値観をお持ちか?ということを、常にお客様を見て研究することが必要なのです。実際に数字を使って検証しますと、例えば、原価40円、売価100円の商品を6%値引くとどうなるか。1.通常売り上げ(100)-原価(40)=粗利益(60)2.値引き売り上げ(94)-原価(40)=粗利益(54)値引き(-6)した分だけ、粗利益がなくなるのです。お客様から値引きを要求されるのは、我々が正しいサービスを提供し、お客様の要求を満たし、不満を解消していないからということも大きな要因です。物販の企業であっても、ライバル会社に勝つために「値引きすれば良い」と考えるのは、間違いです。先ほど数字でお見せしたように、値引きした額だけ粗利益が減ってしまうのです。100円の売り上げを6%値引くと、粗利益も6%減ると思いがちですが、そうではなく(60円に対し6円)“粗利益は10%減る”のです。ですから、その商品で値引きをするのではなく、商品を換える。最悪、その商品で値引きをしてしまったら、しばらく経ってから、定価の違う商品を売り、値引き額を取り戻すのです。契約する際、お客様は「安くしなさい」と、値引き交渉に積極的です。こちらは契約するときには、一度にすべての契約をとりたいと思います。でも、(ライバル会社から見える)商品だけは値引きして契約し、(見えない)他の商品で“段階を追って”契約するのが優秀な営業マンです。カーディーラーも同様、お客様が「車を安くして欲しい」と言ったら安く車を売り、定価で売れる保険、その他のカーナビなどのオプションを定価で売るという売り方をしています。値引きを要求されたら、最小限度の値引きをし、契約してしばらくしてから追加商品を入れ、値引き分を取り戻すのが正しいし、これが出来て初めて出来る営業マンですネ。サービス業でも物販業でもお客さまの言いなりの営業マンではダメ!駆引きが上手に出来て初めて「営業マン」ですヨ。そこまでいけないものは「御用聞き」といいます。あなたは御用聞きで満足ですか?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.20
コメント(0)
-
中国の古典は成功哲学の宝庫でござ~る!!
そろそろカレンダーの準備でしょ「前車の覆るは後車の戒め。」またまた中国古典の中で見つけた言葉をご紹介致します。漢の時代の賈誼(かぎ)が文帝に献策した文章の中の言葉だそうです。賈誼は秦の始皇帝の滅亡をこの言葉に引用して述べたといわれます。賈誼は、漢代の前の秦を「前車」になぞらえて、秦が僅か二代で滅亡したのは秦の始皇帝による強権、悪政の無理が祟ったからであり、拠って、前車のひっくり返ったのを教訓にし政治にあたれば、民衆は安心し政治は安泰するといいました。それを取り上げた文帝は秦の失敗に学び、民衆の声を聞き自ら倹約を旨とした政治にあたり、治績をあげ名君になったという話であります。要は前車のひっくり返るのを見たらその二の舞を踏むな、と云う歴史の教訓です。私達は、他人の失敗に自分はそんな失敗はしないとか、こうすれば良かったのにと訳知り顔で批判批評はしますが、それを自らの教訓や戒めにすることは以外としないものです。また自分の失敗は認めたがらないし、逆に成功したことは誰彼構わずにやたら吹聴したいものです。失敗を失敗として受け止めないし、その原因すら分かろうとしないのです。世の中の成功した人の話はたくさん聞きますが、失敗者の話は陰口では聞いても公の話題にはなりません。成功者は、その人の素質に天の時、地の利が味方し成功すると云われますが、同様に失敗者には失敗した人たちに共通するものがあると思われます。お客様を粗末にしたり、社員を道具のように使ったり、会社の現実に目を向けようとしなかったりと色々ありますが、大方の失敗者の原因は共通するそうです。「殷鑑遠からず夏后の世にあり」【殷の人(治世者)が戒めの手本とすべきことは、遠い時代にあるのではなく、すぐ前の夏の国(王朝、夏の桀王)が悪政により滅びたことにある】という言葉もあります。歴史は勝者の物語が多いのですが、敗者の物語でもあります。同じ失敗をしないためにも、先人の失敗に学ばなければなりませんネ。成功の事例に学ぶことも大切ですが、前車の覆る、要するに先人の失敗体験に学ぶ事がより有益であると思う今日この頃です。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.19
コメント(0)
-
菜根譚から「母恃久安 母憚初難」を・・・
そろそろカレンダーの準備でしょ中国の古典「菜根譚」の中に「母憂払意。母喜快心。母恃久安。母憚初難。」という言葉があります。これは「払意を憂うることなかれ、快心を喜ぶ事なかれ、久安を恃むなかれ、初難を憚る事なかれ」ということです。「母憂払意。母喜快心。母恃久安。母憚初難。」と一見意味が難解そうな漢文ですが、意外と易しいです。その意味は「思い通りにならないからとてくよくよするな、今万事が上手く運ぶからといって喜ぶな、今の幸せに心を許し何時までも続くと思うな、事の最初の困難に挫けたり逃げたりするな」という事なのです。菜根譚の著者、洪自誠は『長い人生や日々変化する経営の中では何をやっても思い通りにならない時がある。そんな時は苛苛したり、くよくよするな。そのうち状況が変化しチャンスが到来するものだ。何をやっても思い通りに行かない時は、次の時期を待つ充電期間とでも思ってじっくり高ヲる事が大事だ。また反対にやる事なすことが順調に運び笑いが止まらない時もあるものである。そんな時は有頂天になったり自慢したりするなと言うことである。人間は好調な時に、また順調な時の驕りや過信が後に大きな失敗に陥ったりするものである。失敗の原因というものはこの順調な時に芽生えるものである。順調であればあるほど足元をしっかり見つめておきなさい。』と言っています。日本でも「驕る平家は久しからず」という言葉がありますが同じような意味だと思います。今が幸せだったり良好だったりすると、ついつい今の幸せがこのまま続くと思いがちになりやすく、その心地よさで努力、精進しなくなるから気をつけよと戒めています。我々の生活は、今が幸せであっても予想のできない突然の不幸や苦難困難な事件に見舞われる事があります。事業においても今が順風満帆でも取引先の突然の倒産や取引の事件に襲われる事もありますが、こんな時普段からの心構えがないと途端にまいってしまいます。故に普段からの物心の備えを怠ってはならないと「菜根譚」は教えているのです。ある企業とお取引させていただいていますが、その会社を訪問する度にこの社長の経営姿勢に感動します。それは、1.社内が明るい事。(まず声が大きい。ハキハキして気持ちがいい。)2.徹底したコスト意識を社員全員で共有している事。3.社員全員が営業である事。お客様一人一人に親切である事。4.社員がいつも危機意識を持っている事。(特に社員全員がいつも危機意識がある事には関心いたします。)ここの社長が社員に毎日話している事は、1.「今日は確かに売れて利益がでた。有難いことである。でも明日お客様がまた来てくれる保証はなにもない。また近くに競合店が何時できるかもわからない。だから今日のお客様を一人一人大事にしよう」ということに徹しているというのです。2.「今月は確かに売れて利益がでた、でも来月天候異変で売り上げが落ちるかもしれないし、大型店の進出があるかもしれない。だから今月しっかり売り上げし利益を出しておこう」と、今月の業績を必ず達成する事に社員全員一丸となって取組む事にしているといいます。3.「今期は確かに売り上げも利益も出たし計画も達成できた。でも来期の予想は全くつかない。だから今期のできる事は今期にしておこう。来期に持ち越さない」と毎日毎日社員に語りながら25年やってきているそうです。今期確実な成長と多くの利益を出しながらも「母喜快心、母恃久安」の心で普段からの心の備えを怠らない経営姿勢を持ちながら経営をされているのでした。25年の経営者人生のなかでこの事を一日も忘れず、どんな高収益の時も心を緩めた事がないといいます。それが今日のこの会社の企業風土になり、社員一人一人の行動になっているのだと思います。それと「母憚初難」も経営者にとっては噛み締めておきたい言葉です。「最初の困難に、挫けて逃げてはならない」というのですが、事業はライフサイクルがありますから今の事業だけでは必ず衰退がきます。絶えず新しい事に挑戦し続けなければならなりません。それが新しい商品開発であったり新規事業の立ち上げであったりするわけです。また新しい販路の開拓もしなければならない、というように何時も新しい事に挑戦し続けなければならないのが経営者の仕事です。しかし新しい事というものは予想のつかない事ばかりであり、思い通りに行かない事も多いものです。正に「初難」がつきものです。どんなに綿密に立てた事業計画であっても、なかなか思い通りにいかない方が多いのです。思わぬ事に出くわしたり、計画では予想もしない事が発生したり、幾多の困難に遭遇するものなのです。予想のつかないことが多かったり思わぬ苦難に遭遇するから事業も人生も楽しい。という人がいますが、しかしこの事を楽しめるようになればいいのですが、新しい事業は資金や時間、資源に制約があったりして楽しんだりしている余裕などないしとても楽しむ境地になどなっていられない。故にまた苦難と戦わなければなりません。「母恃久安 母憚初難」は、「今に満足するな、最初の困難から挫けるな、逃げるな、腰砕けするな。」と言っています。困難、苦難にあたっても必ずそれを乗り越える道がある事を信じて粘り強くやり続ける事だと教えています。王陽明の「伝習録」に「人はすべからく事上にあって磨くべし」(人須磨在事上)とありますが、困難は自分を磨いてくれる最もいい機会なのです。「母憂払意 母喜快心 母恃久安 母憚初難」は、自分に驕らず普段から自らを戒めなければならないのだと思いますネ。 菜根譚は中国の明の万暦年間(1573~1619)の人、洪自誠が残した随想集です。菜根とは、菜っ葉や大根のような事という事ですから、人間の生き方のもっとも普遍的なとか自然的な事を意味しているのではないかと思います。「常に菜根を咬み得れば百事なすべし」という「小学」の言葉が「菜根譚」の背景となったようです。中国の古典は、読むものに強い倫理観や道徳観を求めたり、潔癖なまでの生き方で説いたりしているものがあります。 また処世や事業訓においては成功の法則を説いたもの、失敗の原理を説いたものがありますし、王道、正道を説きながら一方では凄みのある処世術を説いているものもあります。中国の古典は二千年前に書かれたものから数百年前に書かれたものまでどれをとっても、現代の我々の生き方の指針としても本当に新鮮に語りかけてくれます。最後に、こんな言葉もあります。子曰く、過て改めざる、これを過ちと謂う。(通釈)孔子が言った。(過失は誰にでもある・しかし)過失を犯した時、それを自分で反省し、改めなかったら、それこそ、本当の過失というものだ。どうです?お勉強の一助になれば幸いでござるが。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.18
コメント(0)
-

流水の清濁はその源にありますのじゃ・・・太宗
唐の太宗の言葉で、「流水の清濁はその源にあり」という言葉があります。「流水」が澄んでいるか濁っているかは、源の善し悪しにかかっている。君子と人民の関係を河にたとえて言えば、君子は源であり人民は流水の様なものである。臣下は君子の行いを見ながら物事を行うものである。君子が誤った事をしておきながら、臣下にまっとうな事を期待するのは、濁りの源をそのままにして流水の澄むのを待つようなものであり、どだい無理なことである。これは要するに、上に立つ者、組織の長たる者を戒めたことばです。流水の源とは組織のトップのことであり、会社で言えば社長であり上司のことです。特に中小企業は社長そのものが会社であり、社長の生き方がそのまま社風になります。それ故に会社は、社長の「方針」、「行動」、「言動」によって、社員の行いや言動が左右されてくるものです。社長が公私混同をすると社員も公私を混同しがちであり、社長のお客様に対する姿勢が、社員のお客様に対する態度となり現れます。社員が元気だと会社全体も元気になるのです。だから、たまに社員を注意したり叱ったりした時の効き目は、日頃の社長の姿勢によってきまるのですヨ。日頃の社長の経営に対する情熱や真剣さ、普段からの率先垂範の姿勢は、社員の信頼を得るものであり、会社の活力の源になります。皆さんお分かりですネ。 流水である社員が、清流であるか濁流であるかは、それはその源である社長の姿勢によってきまるのです。ただ、「水清くして魚棲ず」ともいいます。いつも聖人君子の様な社長では社員も疲れます。社長も人間、弱さもあれば欠点もある。堕落するときもあればサボリたい時もある。それはそれで良いと思う。ただ、気が付いたらそのままにせず、すぐに正せばいいし直せばいい。このような姿勢が大事ではないかなと思います。会社の盛衰は日頃から社長の姿の中にあると言っても過言ではないではないでしょうか。「流水の清濁はその源にあり」って奥深い、いい言葉ですネ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.17
コメント(0)
-

「日本人として、凛としていたい・・」
今日はちょっと硬く行きます。橋下大阪府知事よ!教育問題は一歩も引くな!ガンバレ~!!「日本人として、凛として・・」今日の日本が抱える最も深刻な問題は、経済的豊かさの影で国民の精神性の崩壊が癌細胞のようにこの国を蝕んでいることであると私は思うのです。特に日本人の国や社会に対する意識の低さは、先進諸国の中では最低でありますが、アジア諸国の中でも中国、韓国やその他の国に比べても日本はかなり低いのではないでしょうか。我々は戦後の経済成長の中で、経済力が国の力であり豊かさだと強調され、精神的豊かさや倫理や道徳観の大切さに目を向けてこなかったのです。特に国民の国に対する意識、要するに国民の国家観はその国の国民力を示すと言われますが、日本人にはこの国家観なるものが大きく欠如しているのです。はたして、この日本国の国民には国家観なるものがあるのだろうかとすら思うのです。戦後教育の中で、自由と平等、人権を徹底的に刷り込まれ、個人の自由と人権だけが尊重され、時には個人の人権が社会の秩序よりも優先されたり、自由の名の下に勝手な振る舞いをすることも許されてきたのですネ。そして、この国の政治からも国民からも、国に対する意識や倫理道徳観が喪失していったのです。嘗ては日本人が持っていた礼儀正しさや倫理道徳観はすっかり消え伏せて、子供から若者、大人までが好き勝手に行動する国になってしまったのです。些細な出来事ですが、先日コンビニの前を通った時の事です。コンビニの前の路上でカップめんを食べ、容器を路上に散らかしたまま立ち去ってゆく若者がいましたが、これを見て誰も注意するでもなく横目で見て素通りしてゆくだけでした。私が注意をしたら始末をして帰りましたが、コンビニの店員も注意することもなく、売れればそこで終わりなんでしょうか。あまつさえコンビニでカップめんを買えばお湯まで提供しているのです。偉そうに、明るい社会に貢献などを経営理念にしているコンビニが一方ではこんな若者達を作っているのであります。こんな事は社会の中の小さな出来事の一つではありますが、昨今同様のことは山ほどあります。一昨年あたりまで学校の入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を実施しない学校が多くありました。学校教育の指針である学習指導要領で実施するように定められているにもかかわらず、国歌を歌わないのは個人の思想信条の自由であると教師も生徒も反対したのです。長年にわたり教室の中では、一部の偏向的先生の国旗国歌の反対思想を、純粋無垢な生徒に徹底的に刷り込んできたのです。毎年入学式の時期になると、学習指導要領に定められた国旗掲揚、国歌斉唱を実施しようとする校長先生側と一般教職員とがトラブルを起こしてきましたが、文部科学省や教育委員会の強い指導で是正されて、去年あたりから多くの学校で整然と実施されはじめました。そもそも国旗、国歌は思想信条の対象でしょうか?我々は、この国があって先祖があり、親がありそして自分がいることを忘れていないだろうか。この国には古くから(西暦701年頃)元旦には日章旗が掲げられていたし、君が代もその源は古今和歌集(西暦905年)と言われています。それは悠久のときから育まれながら代々受け継がれてきた日本の文化であり、伝統であり歴史であります。そして、今日国民統合のシンボルなのです。国旗国歌は独立国のシンボルであり主権国家としての証でもあり思想信条の対象ではないのです。これを次世代にしっかり受け継いでいくのが、今日をこの国日本で生きている我々の役目ではないでしょうか。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.16
コメント(1)
-

洞察力で差をつけよう!
洞察力は、物事の在りようを深く考えて理解するというのではなく、物事の在りようを直観的に見抜く力と言えるでしょう。主観的な思いを介入させずに、物事をあるがままに観察するとき、その時、物事の在りようが直視され、そしてそれが展開していく様相が閃く様に感じられるのであり、物事の推移が直観的に理解されるのです。それが「洞察力」であると私は思います。私は会社でたまに昼食代をかけてジャンケンをしますが、負けたことは滅多にありません。なぜジャンケンで勝つかというと、ジャンケンをする場合、多くの人は「勝つジャンケン」をしますが、私は「負けないジャンケン」をしするからです。勝つジャンケンだと負けますが、負けないジャンケンだと引き分け(あいこ)になります。引き分けになった時、相手が他の手に変えるか、変えないか、だけわかれば勝つ確率は飛躍的に上がるのですヨ。例えば、チョキであいこになったとしたら、相手が変えなければチョキのまま、それがわかればグーを出せば勝てます。チョキ以外の手(パーかグー)を出すことがわかれば、私がパーを出せば、勝つか、またはあいこのままです。私がどのようにそれを洞察しているかというと、常日頃、食事をしながら相手が「先にトマトを食べる」か「先に肉を食べる」か、「次は、ジャガイモを食べる」など、いつも予測と計算をしているのです。計算通りなら、ジャンケンはいつもと同じで良い。計算が違うと、今日は違うからいつもと同じ手は出さない、と仮説を立てているのです。「そんなことを考えながら食事をしていたら、不味いんじゃないの?」と言われますが、違いますヨ。ジャンケンで負けた食事は、もっと美味しくありませんヨ!(笑)つまり、殆どの人間は常に自分自身のことや自分の周囲のことばかりに気をとられているので、状況を客観的に判断したり、物事の全体的な在りようを俯瞰で観ることが苦手のようです。人間は、自己を主体にして物事を考えますから、我欲という主観を交えることなくして、物事を客観的に把握することができないのです。自己の周囲で生じる物事に関わるとき、ほとんどの人がその事柄に対して自我の思いを絡めてしまいます。我欲という主観が常にそこにあるのですから、当然のこととして物事を客観的に観ることができないのです。自我は、物事の在りようを客観的に認識せず、常に自分の都合のよいように解釈して、物事を自分の好む色合いに染めあげてしまいます。それがどんなに自分なりに深く考えた上での理解や判断であったとしても、それは物事を洞察して得た理解や判断ではなく、あくまで自己を主体にして、自分の都合のよいように勝手に解釈しただけのことなのです。洞察力を得るためには、自分自身を訓練することが必要でしょう。まず第一に、自分自身と自分の周囲で起こっている物事を注意深く観察することであり、状況や物事の推移を、主観を交えずに、ただ観照していくことだけに専心することです。第二に、自分自身についてのことや自分の周囲の種々様々な物事や事物事象について深く考える癖を身につけることです。すなわち、すべての事柄に対して深く熟考できる能力を培い、また物事を論理的に考え、そして物事が連関している様相を思惟できるような思考力を身につけることでしょう。けれどもそのとき、主観的な解釈をしてはならず、ただ物事を観じ、そしてそのありようを理解することだけに努めることです。このようなものの見方が確立されると、自然に洞察力が身についてくるようです。やがて人は、物事は理法に則ってあるがままに展開していくさまがよく理解できるようになるでしょう。そうなったとき、人は、物事が顕れ出る様相に対して自己を効果的に介入させることもできますし、また、物事が展開するであろう先の流れも読めるようになると思います。洞察力を身にそなえた人は、現象界の事物事象は法則に基づいて現れ出てくることを理解していますので、あらゆる事柄に対して的確に対処できるからです。また、自分の周囲で物事が生じるや否や、その先の動きが直観的に洞察できますので、自分をどのような事柄に対しても拮抗させることなく自然に調和させることができるのです。従って、人が一たびこの世に生を受、与えられた生を充分に生き、そして自己の生を見事に開花させるためには、物事を深く熟考する「思考力」と、物事の有様を正しく見抜く「洞察力」を身につけることが非常に重要であるということになりますネ。なんか、まとまりが無くなりましたかネ?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.15
コメント(0)
-

二代目はこう育てるんです。
以前の職場で経験したことです。ある日、海外留学から帰国した息子が自分の会社に入ってくると、親の社長はこういいました。「こいつは生まれながらに後継者という重責を担っている。この責任からは逃げられない宿命なんだ。そこで今日から社長室長とするので皆そのつもりで厳しく指導してやって欲しい。」と。一同あ然です。ただの親ばか!丸出しですよね。実質ナンバー2じゃないの?「厳しくしてくれって?こいつの性格じゃ恨まれるだけだろ!』。このときから私の愛社精神は静かに引き始めたのです。零細企業によくある二代目の入社の際、社長は「厳しくしてくれ」と社員に言います。でも、社員はゼッタイに厳しくなどしません。いつかその息子が自分の上司になると思えば、やらないのが当然です。さて、次に良くやるのが、優良な会社の社長が、系列会社に息子を預けることです。こちらも同様、系列会社の人達は、腫れ物に触るようにして、ゼッタイにその息子を厳しく育てません。でも、どちらもマトモなのです。ですから、社長はまず最初に、息子を(まったく違う)第三者に預けるのが良いのです。預けられた息子達はみな、たくましく育っていきます。自分の会社に戻って、他で修行していた時にはよく殴られた(叱られた)という経験が、本人自身の価値観ともなって、良い社長になっていくのです。甘くしてあげるのは人をダメにするけれど、厳しくしてあげるのは、人を成長させます。どちらが良いかは、人が育つほうです。でも本当に「厳しくする」というのは大変です。身内だと甘くなってしまうのは、しかたがないのですが、お互いに相当気をつける以外にありません。甘くならないためには、第三者にナンバー・ツーになっていただくという方法もあります。組織の実力は、社長の実力ではありません。ナンバー・ツーの実力に正比例するというのは、ナンバー・ツーが社長の方針に対して横を向いていては、組織が成り立たないからです。以前の職場はそういう点でやはり間違いました。初めからみんなの上においてしまったので下ずみもなく誰も尊敬もしませんでした。挙句「自分が一番的」になったいくのに時間はかかりませんでしたなぜ、すべて自分が一番じゃなければならないのでしょうか? もしそうなりたい人が居るなら、すべてにおいて自分より劣る部下を採用すれば良い。会社でいうと、大卒をすべてクビにして、全員小学生にすれば、自分が一番になることができます。そういう組織でライバル会社に勝てるでしょうか? 勝てませんね。ですから、組織としての役割が大切で、二代目が組織の中でどちらを向いてがんばるかが重要なのです。そんな馬鹿親子についていくのがあほらしくなって、私は辞職したんですヨ。でもあの自己中アホ親子のおかげで現在の素晴らしいオーナーに巡り合えたのですから、感謝感謝今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.14
コメント(1)
-

あなたの人生を変える「80対20の法則」・・・またまた法則のお話
いつもご愛読ありがとうございます。さすがに11月です。朝晩めっきり冷え込んでまいりましたネ。寒くなると食べたくなるのは、鍋! 我が家ではキムチ鍋が定番です。体は温まり、作るのも簡単! 加えるキムチは炒めておくこと。これがぐぐっとおいしくなるポイントです。これから鍋を囲む機会が増えてきますね。皆様の定番鍋はなんでしょうか?さて、あなたは「20対80の法則」を知っているだろうか?イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が発見した冪乗法則である。経済以外にも自然現象や社会現象等様々な事例に当て嵌められることが多い法則なのです。最近は特にネットワークビジネス界でよく利用されているようですネ。 たとえば、20%の商品やサービスによってその会社の収益の80%が占められていたり、、、また、たとえば、20%の有能な人によって、全体の80%の実績が作られていたり、、、たとえば、20%の行動によって、結果の80%が決まってしまったり、、、以上のように、経済活動や普段の生活でピタっと当てはめることができる不思議な法則のことです。提唱者の名前を取って「パレートの法則」ともいうそうです。この法則は、何も人間だけの話ではなく自然界の現象や、働きアリなど他の生物にも当てはめることができるのです。そして、あなたの1日の生活の中でも20%の作業によって、その日やったことの80%が決る。あなたの1日の生活で、この20%に当たる作業はなんだろう?もしかすると、読書の時間かもしれない。実践する前に、色々なことが頭に浮かんで「どんな本がよいか分からない」→「自分には難しそうだ」→「やる時間がない」という天才的な思考回路が働いて、結局、何も進まない、という人が多くいる。面倒臭さが邪魔をして読書に取り掛かれず、手をこまねいている80%の時間をできるだけ20%に持っていかなければいけないよネ。それが心がけると、あなたの1日は素晴らしく充実感のあるものとなるだろう。作業を邪魔をする気持ちは無視して20%の作業を取り掛かってみよう!今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.13
コメント(0)
-

コーヒーの薀蓄の続きですヨ
前回は新豆(ニュークロップ)と古豆(オールドクロップ)についてお話しました。今回ももう少々このことをテーマにお話しましょう。現地より収穫されてから、一年以内の期間しか経過していない状態の豆を新豆(ニュークロップ)、収穫されてから一年以上の期間が経過している豆を古豆(オールドクロップ)に分けられるといういうことを、前回お話しましたネ。この「古」、もしくはオールドという言葉は、印象としてあまりいい感じにとらえられません。そのためコーヒー業界において今の主流は、新豆のほうが良いとされています。しかし味の評価というのは、一方向にだけ向いているというわけではありません。ある程度のレベルのものに達したものでものであればそれぞれの美味しさがあり、人によって評価が別れるのは当たり前です。だから、単純に新豆こそ最高、古豆は味が劣ると言えるわけではありません。ただ焙煎した豆と同様に生豆においても、どのような状態で保存されていたのか、ということは重要なポイントとなってきます。生豆が産地から日本に運ばれてくる方法は、原則船便で運ばれてきます。この過程において生豆にダメージを与えてしまう原因となるのは、「温度」と「湿度」です。日本に運ばれてくるには、たいてい赤道直下を通過します。この際普通のコンテナに入れた状態であれば、コンテナ内の温度と、湿度は双方ともにかなり高くなります。この高温度、高湿度が豆にかなり大きなダメージを与えます。これを防ぐためには特別注文として、低温状態をたもったコンテナに入れて運ぶというサービスが船便にはあるんですネ。この低温状態にたもったコンテナは「リーファーコンテナ」とよばれるんだそうです。このリーファーコンテナで運ばれてきた豆は、倉庫に保存されるわけですが、この倉庫内においても低温状態に保たれていなければなりません。このコントロールした状態を保つことは、言うまでもありませんが人の手間もかかりますし、コストもかかります。新豆はこの保存の期間をできるだけ短くして、新鮮な状態の生豆の味わいを楽しむということになります。お分かりだとは思いますが、コントロールされていない環境下でただ単に期間が経過した生豆は、古豆として評価されることはありません。期間をあけることで味に良い効果があらわれたとしても、それには再現性がありません。同じ影響がでる環境を作り出せるとはいえないからです。これはワインにも同じことが言えます。醸造されたビンテージワインもコントロールされた環境下のカーフ(貯蔵庫)に入って寝かせてこそ醸造という効果があらわれます。同じ年代に製造されたワインだとしても、極端な話そこいらの戸棚におかれていたのでは、醸造の効果は期待できません。言いたいことは、新鮮な状態で楽しむにしろ、時間をおいた状態で楽しむにしろ、人の手間とコストがかけられているかどうかということが重要なポイントになるということです。もうお分かりだと思いますが、単なる放置を醸造とは言いませんネ。どうです?お勉強になりましたでせうか?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.12
コメント(0)
-

組織は全て2:6:2の原則で出来ているのだよ!
以前に「7:3の法則」についてお伝えしましたが、今回はそれと同様ですがもっと踏み込んだ内容の「2:6:2の原則」について書きますネ。まずは身近な例として、巨人(ジャイアンツ)がなぜ優勝できないか? それは、4番バッターばかり揃えているからです。野球は、4番バッターも必要ですが、俊足の2番バッ ターも大切ですし、打てないけれども守備が上手な8番バッターも必要。それぞれ役割があるのです。城の石垣は、大きな石だけでは作れません。小さな石もないと、築くことができません。同様に、常に『2・6・2の原則』で、頑張る人も居て、頑張らない人も居て、それなりの人が居るのが、会社なのです。その会社で、全体の8割の人が前を向いて行くと、後ろの2割の人が科学変化を起こす。残った2割がまだ『2・6・2の原則』で変わり、最後に残った2割は、辞めて他の会社に行くのです。ですから、“常に新陳代謝のある会社”が良い会社なのです。皆さんもお分かりのように組織でも、クラブ活動でも、遊びでも、全員が一致団結して同じ精神状態で同じ方向を向いていることは、あり得ませんよね。常に、2割は先行して行動し、2割は「やりたくない」などと不満を持っています。残り6割が周りでその様子を見ていて、強いほうに流れます。「やりたくない」ほうが強いと思えば、どどっとそちらに流れ、「行動する」ほうが強ければ、そちらに流れる。強い2割+流れた6割の8割になって、残った2割が付いてくるかというとそうではなく、この2割がまた2・6・2に分かれるのです。この残った最後の2割が、辞めて他の会社に行く。どの会社も、これを繰り返しています。それが自然なんです。普通に考えると、一人も社員が辞めずに、みな一緒に仕事をしているほうが良いと思うかもしれませんが、そうではありません。溜まった水にボウフラが湧くのは、水が動かないからです。川の水は常に流れているので、ボウフラは湧きません。澱んでいてはダメなんです。流れていること、動いていることが、自然界の原理なのです。「2・6・2の原則」は常にあり、それを知っていて行動することが大切なんですネ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。お蔭様でただ今飲食宿泊と50代サラリーマンで2冠王です。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.12
コメント(0)
-

こんなときだからこそ 「温故知新」 <故きを温ねて新を知る>
「温故知新」 <故きを温ねて新を知る>今日のような日本や世界情勢のときこそ、歴史や先賢の生き方から学ぶのが良いのではないでしょうか。歴史や先賢の行き方は、幾多の困難や危機を乗り越えて来た生き残る為の普遍的な原理であり神髄であります。また処世術であり、知恵であります。それは人生(事業)の困難や危機に直面した時、どんな姿勢で臨んだらよいかを故事や諺、歴史訓として現代に伝えております。我々は、困難や危機に直面するとそれにどう対処したらよいかも分からず、ただ考え込んでしまったり、対応に時間がかかったり、時には対応を間違ったりすることがあります。また狭い了見で身の回りの情報に頼ったり、自分にとって都合の良い人に相談したりしますが、しかしここで得られる答えの多くは対症療法的方策です。 こんな時本当に必要なのは対症療法やハウ・ツウーの短絡的方策ではなく、困難や危機に望む姿勢、志その中にこそ根本的な解決の処方があるのです。それを教えてくれるのが幾百万年の歴史の中で培われた多くの先達の知恵、両親や祖父母が経験した人生の体験から生まれてきた知恵や処世術にあります。故事や諺、歴史訓「故きを温ねて新を知る」この故事はあまりにも知られた言葉でありますが、これをもう一度噛みしめてみたいものですネ。 我々を取り巻く経営環境は、まだまだ厳しい。高水準の企業倒産、まだまだ続く地価の下落や売上不振、価格競争からくる利益率の低下、大企業のリストラによる中、どんな厳しい環境の中にあっても、それを乗り越える知恵や方法はあるものです。それは、先賢や歴史はどんな知恵でどんな姿勢でどんな方法で乗り越えて来たかを学ぶ事にあると思うのであります。 今日も1クリック、ご協力宜しくネ。お蔭様でただ今飲食宿泊と50代サラリーマンで2冠王です。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.11
コメント(0)
-

経営者・幹部には苦労こそ生きがいである
先日私の敬愛する社長さんとお会いしたときに気付かされたことを書きますネ。「私は事業が今一番順調なときです。」と穏やかに話されました。売上は前年比20%、経常利益12%と言う立派な経営をされている、温厚で優しい思いやりの心が満ち溢れたお人柄で、この人ならこの業績も当然と思いました。一つ一つの言葉を大事に話される中に、この社長の人柄、人生を感じさせられました。その話の中で、この社長も業績の非常に悪いときがあり倒産の危機に立たされ、自殺まで考えた事もあったと聞かされ驚かされました。あまり詳しいお話は伺いませんでしたが、本当に辛い苦しい経験をされているにも関わらず、その苦労が顔に少しもでていないのです。そのお顔からは幾多の苦労を乗り切り、まるで経営者として人間として悟った表情を漂わせておられるのです。だからこそこの温厚な人格者にも、長い社長業の中で自殺まで追い込まれるような苦労を何度も経験をされている事に、経営者の厳しさを改めて教えていただきました。この社長は、この危機をある言葉との出会いによって乗り切れたと云われました。それは「努力の方向が正しければその努力は報われる。永遠の苦労もないし、永遠の順調もない。」と云う言葉に励まされ、「よし死ぬ覚悟でもう一度やってみよう。」と一念奮起し今日に至ったと云われました。世の中には倒産の危機まで落ちた経営者は何人もおります。でもそこで立ち直ったのは、その危機でいろんな事を学びそれを教訓にして経営に生かした人達です。失敗や苦労、危機をただの失敗や苦労にせず、教訓にしてその後に生かすことが出来るかどうかが、その後その経営者の価値を決めるのではないでしょうか。経営は順調な時ばかりではないし、だからといって辛くて苦しい時ばかりではない。経営とは謂わば「ゴールの無いマラソン」なのですから、辛い時もあり苦しい時もあるのであって、それにうち勝ち乗り越えられるかどうかが経営者としての腕の見せどころであり、経営の醍醐味でもある。そして経営者の生き甲斐がここにあると思うのです。松下幸之助は経営10ヶ条の中に経営者は苦労こそ生きがいであるとありますが、苦労を有り難いと受け止められるようになりたいものである。重要なのは順調な時に「傲らず」、苦しいときには「卑屈」にならないことであると思う。どんな時でも目標を失わず情熱を持って挑む意志の強さと謙虚さを持つことだと思わされた今日この頃でした。皆さんはどうですか?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.10
コメント(1)
-

「社風」は経営者の生き方の反映です。
企業倒産や企業の不祥事が年々増加をいたしております。特に最近大きな社会問題を起こし国民を不安に陥れた商品の偽装事件や、産地偽装のために商品ラベルを張り替えたりする企業倫理や道徳観のカケラもない事件を起こした会社等々、マスコミを賑わす事に事欠きません。 最初は小さな出来心から始まった不祥事や不注意は、その事を放置しておくと、大企業と言えどもやがて企業倒産へ追い込まれる事になるなります。「千畳の堤も蟻の一穴から」と言いますが、私達はこれまでもこの様な事は新聞やテレビ等のマスコミでイヤというほど読んだり見たりしてきましたが、いつの時代なっても一向に後を断ちません。このことは儲け至上主義一辺倒でとにかく儲かれば何をしても良いと云う事から来ているのでしょう。事件を起こす企業の経営者や社員に、企業の倫理観や道徳観の前に金儲けがありそれが最優先されてしまう社風が出来上がっているのですネ。 かと思うと、真面目に一生懸命頑張ったが倒産に追い込まれる中小企業も数多くあります。朝早くから夜遅くまで額汗して頑張ってもなかなか経営がうまくいかないことがある。やがて経営に行き詰まる。何とも惨いことであるが現実でもある。これは経営者として自覚の甘さや経営に対する厳しさの不足、頑張りの方向の間違いがあるからだと思います。ある名経営者が「経営の方向が正しくその方向に向かって努力すれば、必ず努力は報われる。」と言っておられましたが、要するに経営者としての正しい経営姿勢と、経営の方向性を見失い、単に「頑張る」という言葉の魔術にはまってしまった結果ではないでしょうか。 今日の厳しい経営環境の中、企業として成長し続けるには、商品力、マーケティング力、商品開発力が重要な事ではありますが、最も大切なのは、それらを育て活かすことのできる、企業文化、社風であります。どんなに良い商品も、どんなに素晴らしい技術や真心のこもったサービスも、皆社員一人一人の心の反映であり経営者の理念、姿勢の反映です。これこそが企業文化であり社風であると思います。商品一つ一つ、製品一つ一つ、サービスの一手一手に企業文化が反映されるところに、不祥事も不注意もありませんし、お客様を惑わしたり社会に迷惑をかけたりすることはありえません。ましてや、経営の方向を見誤り倒産の危機に出会う事は無いのです。たとえ危機に遭遇しても良い企業文化、社風があれば、その危機は乗り越える事ができるのです。良い企業文化が良い社風を作り良い社員を育み、良い商品やサービスが作られ良いお客様に恵まれるのです。「社風」は経営者の生き方の反映であると思います。そこに繁栄の原点があるのですネ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.09
コメント(1)
-

無意識とは潜在意識なのです。
『あなたが無意識を意識しない限り、 それはあなたの人生を支配する』この言葉はあなたも知っているであろう、そう、かの有名なスイスのカール・ユングの言葉です。 ユングの創造する無意識ユングは精神科医であり心理学者で哲学者でもある。彼は特に「無意識」という存在を大きく定義しました。今では誰もが知っている無意識という言葉、これはユングが広めたと言っても過言ではありません。因みに、人間にはどこの国の人でも、どんな人種の人でも共通の無意識があるということも言っています。あなたも聞いたことがあるであろう神話の研究やシンクロシニティの概念もユングが最初に考えたものといわれています。まあ、ユングが何をしたかは別として、自分の無意識が自分の人生にメチャメチャデカイ影響を及ぼすことは私たちの世代の人間は大体知っています。それは「潜在意識」とも呼ばれています。もしあなたが、無意識なんて自分の中にはない!と考えているなら、残りの人生は苦労する事になるでしょう。無意識はあなたの人生の最大の味方にもなれば、最大の敵にもなりうるのです!お分かりになりました?全て経験したことは「無意識」に残るんですネ。それを使いこなせるか否かは自分自身ってことです。1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.08
コメント(0)
-

老舗の品格とは?・・・・・・「不易流行」にあり
「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」。俳聖松尾芭蕉は『奥の細道』の旅の間に「不易流行」という概念を体得したと伝えられます。 また倫理研究所の創始者である丸山敏雄は、自然の法則から「易不易」の原理を発見し、永続的に繁栄するためには「易(変わる・変える)」と「不易(変わらない・変えない)」の両面バランスが重要であると指摘しています。「易不易」のバランスを常に図るのが経営者の役割です。経営者が社員と共に現場で走り回り、汗を流すことも大切ですが、経営者ならば脳に汗をかくくらいに「易不易」のバランスを考えることが不可欠でしょう。経営計画を明記して、社員はもとより取引先やお客様にも分かるよう具体的な方策までも噛み砕いて示し、繰り返し徹底して実行に移す努力が必要なのです。なぜなら、会社全体を見渡せて、目先のことに振り回されることのないポジションにいる人、つまり経営者にしかできない仕事だからです。考えることを厭い、バランスを失った経営者ほど、「汗と努力が足りない」「売り上げは足で稼げ」「気合が足りない」と社員ばかりを責めてはいないでしょうか。老舗経営の本質は「不易流行」であるといわれます。歴史が古いというだけでは、「老舗」とはいえません。真の老舗とは、つぎの五つの項目を満たした企業のことだと思います。一、無理な成長をしない。二、安いというだけで仕入先を変えない。三、人員整理をしない。四、新しくよりよい生産方法や材料を常に取りいれていく。五、どうしたらお客様に喜んでいただけるかという思いを、常に持ちつづける。 老舗と呼ばれるような会社や店は、いつの時代にも、最先端の製造方法や経営手法、材料を用いてきたはずです。変革をくり返し、常に新しく生まれ変わってきた結果、厳しい競争に耐えて生きのこり、老舗と呼ばれるようになったのですネ。 企業にとって「易」とは、時代に合った営業手法や会計方法を市場調査で探り、お客様のニーズにどう応えるか。改善努力を怠らないことです。「不易」とは、会社の目的や存在意義、創立の精神などのポリシーを変えないこと。自社に倫理を確立することでもあります。この二つのバランスを保つためには、両者を無関係に捉えず、常に不易にあって易を考え、易にあって不易を考えることが重要です。目的や存在意義に沿って方法や手段を改善し続けるという、「順序」を守りたいものですネ。みなさん!今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.08
コメント(1)
-

オバマ大統領 バンザ~イッ!
先日の米国大統領選挙で歴史的勝利を収めたバラク・オバマ氏(47)は5日午後(日本時間)、数万人の支持者を前に、「変革が米国に到来した」と勝利宣言した。ケニア人留学生の父と白人の母の間に生まれた米国初の黒人大統領。人種の壁を超え、若者や貧困層、富裕層など幅広い人々を魅了したのは、リンカーン、ケネディ元大統領らの再来とも評された数々の名演説にあった。日本のへなちょこ政治家たちは、この強い「言葉の力」から何を感じ取るだろうか。 オバマ氏を一躍有名にしたのが2004年7月の民主党大会での演説でした。「リベラルのアメリカも保守のアメリカもない、あるのはアメリカ合衆国だ」。オバマ氏はこの演説で俄然、大統領候補として注目を集めた。 さらに、ポスターにも使われた「CHANGE(変革)」をはじめ、「Yes we can(きっと私たちはできる)」「Let us keep that promise-that American promise(米国の約束を実現しよう)」など演説の言葉が、歌になるなどの社会現象も生まれた。 「人々のための政治を行う、という一貫したメッセージがこめられており、彼の発言には人の心をつかむ力がある」と仰っているのは、「オバマ語録」の翻訳を担当した翻訳者の中島早苗さんです。インドネシアで少年時代を過ごすなど、多文化にまたがる生い立ちに加え、「リズム感のある伝わりやすい言葉が、幅広い支持につながった」のではないかと。 一方でオバマ氏は「私は政治的点数稼ぎに自分の人種を使う人間ではない」「この選挙は黒人対白人の戦いではない。過去対未来の戦いだ」とも発言している。 「オバマ『勝つ話術、勝てる駆け引き』」の著者で、米大統領の演説分析を行う大阪大学外国語学部の西川秀和非常勤講師は「人種間の溝を強調せず、白人票も取り込んだことが勝因」と分析し、さらに加えて、「アメリカンドリームの体現者という人物像や、エリート、貧困層ともにウケの良い経歴に加え、パフォーマンス能力も非常に高い」とも指摘しています。 西川さんによれば、オバマ氏の演説はほとんどが即興で、「ささやくように話したかと思えば大きな声を出す。身のこなしは、俳優出身のレーガン元大統領以上だった。オバマ氏にとっては、テレビもいいが、実際に演説を聞いてもらうのが支持を増やす一番の方法だったはずだ」と。(これってかつて目白の闇将軍といわれた「角さん」こと田中角栄元総理大臣の話法にも通じます。古いか?) アジアやヨーロッパでも熱狂的な人気を誇るオバマ氏だが、外交政策はどう変わるのか。オバマ氏は「共和党のマケイン上院議員の主張は9割がブッシュ大統領と同じだ。『ブッシュ政権3期目』は認められない」と、その違いを訴えているが、東京大学法学部の久保文明教授(米政治)は「対アジア政策を遂行するためには、日本との同盟関係が友好な柱という考えは持っている。民主党が重視する輸出入についても主な敵は中国という意識があるのではないか」と予想しています。 一方、対テロ政策については「テロリストがどこに存在しようと、一方的に彼らを攻撃する権利を、私たちは常に持っておかなければならない」と強硬姿勢を示すものの、北朝鮮については「イデオロギーと幻想のみで動いている国だ」と批判するに留まっています。久保教授は「圧力をかけるというより交渉路線で取り組むのではないか」とみています。 「完璧(かんぺき)な大統領にはなれないが、国民に正直であることを約束する」、選挙戦最終盤オバマ氏は確かこう訴えていたのが印象的でした。私が当選を予感した一瞬でしたヨ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.07
コメント(0)
-

トータルサービスは・・・?
凡そ人間には器用な人と不器用な人が居ます。また、専門性が高くなればなるほど、そのテリトリーは小さくなります。サービス業に関して言うと、お客様が求めているのは何でも一通り出来る人(店)ではなく、専門的に優れている人(店)だと思うのです。ピザだけ作っている人(店)のおいしいピザ、 ラーメンだけ作っている人(店)のおいしいラーメンというようにネ。ラーメンは作れるけれどヘタ、カレーライスも作れるけどヘタ、ピザも焼けるけどおいしくない、という人(店)は、求めていないと思うのです。「トータルで全部できる」という人(店)を、お客様は求めていないと思うのです。色々なことをすべて出来る人が社員になってくれたら良いなぁ~と考えがちですが、そんなスーパーマンみたいな人は居ません。理論的には正しいかもしれませんが、現実的にそういう人は居ないし、お客様は誰も、そんな人を求めてはいないのです。それよりは、皆で分担をして、自分、あるいは自社の得意なことに特化をして、お客様に喜んでいただく、選んでいただくことが大切なのです。以前の職場で、ある日突然「人員削減策として今後は一人の人間がどの部門もこなせるようにせよ!」という方針が出されたことがありましたが、私は「反対」しました。「そんな優秀な人は滅多に居ません」というのが私の答えです。宿泊だ、婚礼だ、宴会だ、レストランだと、我々の業界にも商品やサービスがたくさんあるんです。人が育つまでに時間もかかります。それより、専門性を追求したほうが良いのです。○○さんは宿泊、□□さんはレストラン、△△さんは宴会、というように専門性を持たせたほうがうまく行きます。そしてちゃんと成長が見られたら次の適正を探してあげればいいのです。一人がすべてをやるのは理想ではありますが、それができる人は本当に少ないのです。稀にしか居ない人を中心に物事を考えてはいけません。オールマイティーを揃えようとしてはいけません。今の職場は、「この人がすべて出来る」というオールマイティーな人を、社長が求めていません。だから業績が上がっているのです。経理も、サービスも、営業も、婚礼や宴席も、わが社の事業をすべてわかるには、一年に一回ペースのスピードで配転しなければなりません。たった一年でコロコロ仕事が変わることに皆さんは耐えられますか。多能行は理想ではありますが、こなせる人はそうそういるものではありません。結局どれも中途半端になって挙句、お客様に迷惑がかかってはどうしようもありませんからネ。皆さん、社員は大事に育ててくださいネ。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.06
コメント(0)
-

列子の愚公移山
中国の代表的古典文学に、列子が書いた「愚公移山」という滋味豊かなものがあります。余りにも有名なのでご存知の方も多いのでは。内容は簡単に言うと、「小利口な者より愚直な者の方が大きな仕事を成し遂げる事ができる。」ということを意味します。「物事は粘り強くやれば、きっと目的は達成される。努力はどんな難事業でも成し遂げる事ができる。」なんて事を言う時に使われますネ。これは現代でも充分通用する内容と思い取り上げました。「愚公移山」とは大雑把には次のような内容です。 昔、中国に大行山と王屋山という二つの高山があり、人々は村に出入りにするのに遠回りをしなければならなかった。北山の愚公という老人は90歳になろうといていましたがこの二つの山を取り除き平らにし、遠回りをしなくても良いようにしようと考えたのです。隣近所の多くの人は愚公を馬鹿にし、表立っては賛成し陰では陰口を叩きながら笑っていた。 中でも一番の反対者は奥さんであったのです。「これまで小さな山も崩せなかった人がどうして2つの山を崩して平らにできようか」と疑い、反対したのでした。また崩した山の土を捨てるのに海まで持っていかなければならず、これをもっていくだけで片道1年もかかるのです。それを見ていた隣人は「90歳にもなって老い先短いのに、山の端くれも崩せないだろう・・・」と言いましたが、愚公はそれにこたえて、「貴方こそ愚かな心の持ち主でだ。お前さんのように決まった事しか考えられない人には分かるまい。わしが死んでも子供がいる。子供は孫を産む。その孫はまた子を産む。次々と子供を産んでいく。子孫は尽きる事はないが、山は今以上には大きくならないし増えないのだ。」と。これを聞いた天帝は愚公の一途な心に感心し、二つの山を神に背負わせて平らにしたと言う話です。 要するに、人間は知識の有る無しとかではなく、自分が腹をくくって決めた事を一途に信じて実行する事でどんな困難、苦難と思われるような事でも、やがて実ると言う事を教えてくれているものです。遠大なる大事業でも、一見不可能だと思われるような障壁も「愚公移山」の志をもってやれば、やがて天が味方しそれを乗り越え実現する事ができるということですネ。 松下幸之助の言葉にも「辛抱強く根気強く」という言葉があります。「一旦志を立てて事を始めたら、少しぐらい上手くいかないからといって投げ出したりしてはいけない。時に失敗して、志を挫かれる事があっても、気を取り戻してまた取り組みなさい、辛抱強く、根気良く努力を積み重ねいく。そうした時に始めて物事は成し遂げられる。成功とは成功するまで続ける事である」というのがあります。 また倫理法人会の「万人幸福の栞」にも「自信のないことは失敗する。練習すると言う事は、その仕事なり競技になれて間違いのないようにするのが、その形から見たところ、その実は信念をつけるのである。信念を練り固め、練り上げるのである。きっと出来るぞ、きっとやるぞ、と動かぬ信念がその事を成就させる」とあります。 現代はスピードが速く、次から次と新しいビジネスが世に出てきます。また商品のライフサイクルも以前より非常に短くなりましたし、新しい商品も次から次と洪水のように溢れ出てきます。消費者の生活スタイルもどんどん変わり、企業もそれに適応していかなければ取り残されます。確かに時代のテンポにあった経営をしなければなりませんが、何事にも「易」(変わる)「不易」(変わらない)があります。時代の変化に合わせて仕事のやり方や既存事業の変革、新しい事業の創造などは、的確に時代を捉えて時代の潮流に乗りながらやらなければなりません。 以上のように時代の変化に適応しながら人、物、金、情報を有効活用して事業の最適化を図っていく事がこれからの経営に求められます。しかし如何に時代が変わろうが、文明が進歩しようが、仕事に取り組む姿勢や理念、企業としての倫理観や顧客に対する姿勢は変えてはならないのです。「愚公移山」で言われるように、物事の成就はテクノロジーの力や文明の力だけではなく、目標を明確にし、その目標に向かって辛抱強く根気良く取り組む姿勢や情熱が物事を成し遂げる信念となり、物事を成就に導くのだと思います。愚公翁の壮大な志は正にこのことを我々に教えてくれていると思いませんか。 今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.05
コメント(0)
-

経営者さん、社員と共に思いの共有・実行を・・・基本です
今日お会いした社長さんの愚痴「社員がわかってくれない・・・・」を聞いて少々怒っています。 強い企業を作るには経営者の考えや思い経営理念を社員が理解をし、共有しなければならないと言われます。会社は何の為に存在し、どんな目的の為に事業をし、これからどんな会社になろうとしているか等、社長としての考えや理念を明確に社員に示し、それを社員と共に実行し実現していくことこそが経営の本質であると思います。 経営者の仕事は、強い経営と安定した永遠の成長をさせる事であり、その基となるのが経営者としての考えや理念です。それを1日中考え続ける事であり、どんな事があっても実行し続ける事です。これを365日毎日毎日続けるのですからストレスも溜まりますし、心身ともに疲れもします。これを心地よく感じるようになれば本物の経営者なのかもしれません。終局的に経営者の仕事はこれだと言われれば当然そうかもしれません。 以下にちょっと系統立ててみますネ。・「経営者の心社員わからず」 「うちの社員は俺の言う事を分かってくれない」「あれほど重要な事が末端まで伝わっていない」「何をやっても長続きしない」と言う嘆きというかボヤキを聞きますが、これって実は多くの経営者が持つ共通の悩みのようですネ。 「お客様第一主義」等の経営理念や経営方針、「社内や敷地内にゴミが落ていたら拾おう」「整理整頓」「報、連、相の徹底」などのスローガンを掲げてスタートするのですが、何時も初めの掛け声だけでなかなか続かない、いつの間にか誰もがやらなくなってしまう。 経営者はイライラするが社員は「笛吹けど踊らず」です。「継続は力なり」で、これを続ける事ができたら強い会社になる事は分かっているのですが、なかなか続かない厳しい現実を目の前にし落胆するが、 そのうち経営者自身も掲げた方針を忘れてしまい、壁に貼られたスローガンだけが活き活きと見えるだけっていうのがよくあるパターンですネ。 経営者がいくら立派なビジョンを打ち上げても、また崇高な理念を掲げても、それが社員の心に響き社員の腑に落ちなければ社員は行動に移らないし、やっても長続きしない。 経営者の考えや経営理念、方針は社員が行動に移さないと、その理念や方針がどんなに立派でもお客様には伝わらないし経営の実効が上がらない。実行されて初めて経営理念であり方針であるのです。故に経営者は実行しないし、実行しても長続きしない社員の姿をみるとイライラしストレスも蓄積するのですが、経営者の考えや思いは社員から見れば、「社長はあんな立派な事言って」「社長の都合ではないか」と思っているくらいなのです。 経営者が会社をよくする為に、また立派な会社にする為に真剣に考えに考え抜いたものであっても、社員には「親の心子知らず」で、ただの言葉にすぎないのです。 それは社員には経営者の立派な理念やビジョンより、給料が下がる事やリストラされないかという明日の自分の生活の方が現実的な問題であるし、経営者の事業に賭ける本当の心や、経営の現実的な問題と戦っている経営者の苦労が分からなのです。 ・「分かるまで話す」 経営者の悩みは、そんな社員に自分の考えや思い、理念や方針を伝えるにはどうしたら良いかですが、私はその解決策は、社員が分かるまで何回も話し続ける事であると思うのです。何回も何回も繰り返し話すしかない。 「社員には何時も話しているのだから分かっているはずだ」とか「どうせ幾ら話しても分からない」と、話す事を止たり諦めてはいけないのです。1回や2回話した程度では社員に伝わりません。 子育と同じ様に1回や2回話したってなかなか伝わらないのです。時には10回20回話したって10%も伝わらない時もある。繰り返し繰り返し話をするうちに、「社長はこの事に本気なんだ」と共鳴し思いが伝わっていくのです。 「社長はこんな思いで経営をしている」「社長はこんな大きなビジョンを本気でやろうとしている」と社員に伝わった時、社員は社長の思いの実践者、実行者となるのです。時には燃える火の玉のようになり期待以上の成果を出す事だってある。ですから社員に経営者自身の考えや思い、理念を伝える為には何回も何回も訴える事が大事なのです。 この事は本当にエネルギーのいる事なのです。 故にこれが最も重要な「経営者の仕事なんだ」と思うのです。だからこのエネルギーを惜しんではいけないし、ここまでして等と思ってはいけないのです。経営者がエネルギーを惜しんだり、言う事をやめたら社員に思いを伝える事はできないし、理念の共有もできません。 松下幸之助氏は、松下電器の成長期の頃に3年間毎日朝礼で自分の考え、思いを社員に話し続けたといいます。またホンダの創業者 本田宗一朗氏は創業間もない頃に、やはり朝礼で「ホンダは世界一のオートバイメーカになる」とみかん箱の上に立って、工場の従業員の前で話し続けたそうです。 それが今日の松下電器であり世界のホンダです。実は社員に話し続けるという事は、経営者が自分の意志を強くするために自分に話し続ける事でもあるのですネ。 どんな小さな会社でも経営者が社員に向かって真剣に話し続ければ最初は「そんな馬鹿な」とか「社長の都合で言っている」「そんな事できるわけがない」と言っていた社員も、いつの間にか社長の考え思いに共鳴、共感し最大の理解者、協力者になるのであります。 ・「思いの共有」 経営者の考えや思いを何度も何度も繰り返し繰り返し真剣に語り、結果その思いが社員に伝わった時、その考え思い理念方針が社員によって実践され目標達成に向かうものであると思います。ただ「やれぇ!いけぇ!」の叱咤激励ではダメなのです。何の為に、何故やらなければならないのか、どんな夢があるのか、をしっかり話し、その思いが社員の心に響き共鳴した時、初めて経営者と社員が一緒になった経営理念、経営方針の共有が始まるのですネ。 如何ですか?愚痴っている余裕なんてないのですヨ。世の社長さん方! 社員はあなた自身を投影した結果です。 経営は経営者一人で出来るものではありません。経営者という指揮官と社員という実行者がいて初めて実行出来るのです。この両者が共に思いを共有し目標に向かった時、本当に強い組織ができ成長の基盤ができるのだと思います。私は以上のように確信しておりますが理想論でしょうか?今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.04
コメント(0)
-

刀は砥をもって而る後に能く利なり
最近、孫子や故事成語に再び興味がわいて、昔のノートの書き込みなんか読み返してるんですが、今日はその中からチョコッと書きますネ。『刀は砥をもって而る後に能く利なり』、これは刀というものは砥石にかけて入念に研げば、鋭い切れ味がするものだが、磨いた刀でも長いこと使わないと、錆びて使えなくなるという事です。若い時は人一倍勉強し自己啓発を怠らず仕事にも精魂込めて頑張った人でも、歳をとると勉強もしなくなり仕事も今まで以上には頑張らなくなるものなんだそうです。歳を重ねると過去の自分に満足するのか、勉強したり何か新しい事に手をかけるのが面倒くさくなるのか、頑張らなくなる。また人生を長く生きていると過去の経験にとらわれて何か新しいことを取り入れたり挑戦したりしなくなるし、自己を磨くことに努力をしなくなる。そのほうが楽でもあるからです。人間向上心と意欲を失ってはいけないですね。サムエル ウルマンの書いた「青春」という詩があります、何度読んでも心に響くいい作品ですヨ。『青春とは人生のある期間ではなく心の持ち方をいう。バラの面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなくたくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱をさす。青春とは人生の深い泉の清新さをいう。青春とは臆病さを退ける勇気、やすきに付く気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。時には、20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。年を重ねただけで人は老いない。理想を失うときはじめて老いる。歳月は皮膚に皺を増すが、熱情を失えば心はしぼむ。苦悩、恐怖、失望により気力は地に這い精神は芥(あくた)になる。60歳であろうと16歳であろうと人の胸には驚異にひかれる心、おさな児のような未知への探求心、人生への興味の歓喜がある。君にも我にも見えざる駅逓が心にある。人から神から美、希望、よろこび、勇気、力の霊感を受ける限り君は若い。霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ悲嘆の氷に閉ざされるとき20歳だろうと人は老いる。頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり80歳であろうと人は青春の中にいる。』いいですネェ。刃物を研ぎながら刃先を指で触ると研ぐ度に刃先が鋭くなっていくのが良くわかります。錆びた脳みそも磨けば段々と活性化され記憶力や思考力、気力も充足されてくるのではないかと思います。自分の人生を豊かにするには絶えず自分を磨かなければならない。「剣!磨かざれば光なし!」磨くのは自分であると自分に言い聞かせる今日この頃です。 今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.03
コメント(0)
-

国を治むるは樹を栽うるがごとし
中国史上最高の名君と言われる、唐の第2代皇帝太宗の言葉の一つにいいものがありますのでご紹介いたしますネ。それは「治国楢裁樹」です。太宗は「本根揺がざれば、すなわち枝葉茂栄す。君よく清浄ならば、百姓なんぞ安楽ならざるをえんや」と言っています。木というのは、根や幹がしっかりしていれば、枝葉は自然に繁茂するものだ、ということです。 企業経営で言えば経営者の経営姿勢や言動、行動をみて社員は行動しているし、それによって会社の成長も社員の幸せも決まってしまうということです。組織というのはリーダーの人間力や指導力、統率力で性格や強さが決まります。ですから、トップの普段からの行動や言動というものが組織に大きく影響を与えるので、行動は率先垂範し身勝手な言動は慎まなければなりません。松下幸之助氏は「商売、経営に発展の秘訣があるとすれば、それはその平凡なことをごく当たり前にやることに尽きる」と仰っています。経営者が常日頃から経営理念や経営方針を当たり前に実行する姿勢みて、社員一人ひとりが経営理念の真髄を知り、経営方針の実行を身をもって行う。そこに会社発展の秘訣があるのだと言うことであると私なりに解釈しております。会社はリーダーである社長の性格、思考、行動の仕方でその性格も決まりますし、社員の仕事に取り組む姿勢やお客様に接する態度も決まります。社員というのは社長から言われたことに、一見その通り従っているように見えるけれど、実のところ普段からの社長の言動をみてそれと同じようにやっているだけなんですネ。経営者は常に謙虚でなければならないと思いますネ。 今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.02
コメント(1)
-

コーヒー豆の一考察
今日はコーヒーのお話です。この薀蓄を何かの話題にお役立てください。コーヒー豆はお米同様に「新豆(ニュークロップ)」と「古豆(オールドクロップ)」に、大別することができます。現地より収穫されて一年以内しか時間が経過していない豆を「新豆」、収穫されてから一年以上経過した豆を古豆と呼びます。新豆であれば、生豆の内部により多く水分量を含むということになります。味を表現する苦味、甘味等々といった成分はこの水分の中に多く含まれることになります。ということで、コーヒーは新豆であれば、それだけ味わいが複雑かつ深いということが言えます。次に、新豆に反して古豆ですが、じつはメリットもあります。焙煎がしやすいということです。コーヒーの焙煎の肝は豆の表面から芯まで均一に火をあてることにあります。豆の表面はよく火が通っているが、内部の芯に火がいき通っていない。これではだめなわけです。新豆は水分量が多いわけですから焙煎時、豆に均一に火を通すということが難しくなります。古豆は水分が抜けているわけですから、生豆に火を均一に通すことが、新豆の状態よりやりやすくなります。カンタンに言うと、焙煎はきれいに仕上がるわけです。味の面から言うと、水の量がすくなくなっているということは味の鮮烈さに欠けるといえます。これは言葉にするとマイナスのように聞こえますが、味覚の面から言うと、かならずしもこれはマイナスになるとはいえません。ワインも同様ですが、ヴィンテージワインは、時間の経過のため、味がボケているということになります。しかしこの味のボケが、味覚に対してプラスに働くということが、ままあります。これが味覚の複雑なところです。コーヒーも同様に、時間が経過して、生豆中の水分が少なくなったため味の鮮烈さがかけた事が、味にプラスの効果が働くことがあることがあります。ですから結果的に、かならずしも新豆のほうが古豆より勝っているとはいえないとも言えるわけです。しかし原産地から見ると、コーヒー豆は、新豆の状態で楽しまれることを前提に研究し、栽培、生産しているということがいえます。原産地の一部の農園は、美味しいコーヒーを作り出すために想像以上の研究を重ねています。どの品種がいいのか?どれくらい農地の環境を整えればいいのか?その分野は想像を超えるほどです。通常コーヒーの生豆は麻袋に入れて輸出されますが、現在一部の農園では生豆をアルミパックに真空包装して輸出するほどです。もちろんコストはかかります。なぜそういうことをわざわざしてくるのかというと、それは生豆の鮮度を保たせるためです。彼らがなぜこれほど情熱をかけるのかというと、やはり良いものを作って生活をよくしていくこととともに、自分たちのブランドを世界に発信していきたいと考えているからです。新豆の味が必ずしも古豆より美味しいと、単純に言うことはできません。しかし原産地の人たちが、情熱をかけて苦労の末作り上げた銘柄のもつ持ち味を、楽しんでいただきたい。このことがあるので、世の自家焙煎珈琲が売りの喫茶店オーナー様へ、扱う銘柄は可能な限り「新豆」の状態のものを使用していただきたいものです。今日も1クリック、ご協力宜しくネ。人気ブログランキングへも1クリックを
2008.11.01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- 可愛い🎄しろたん クリスマスツリー…
- (2025-11-17 20:02:57)
-
-
-

- 今日の出来事
- たくさん寝れるの幸せ
- (2025-11-18 01:47:48)
-
-
-

- ☆手作り大好きさん☆
- Snow Man ハンドメイド 宮舘涼太❤️…
- (2025-11-17 22:10:04)
-