全1343件 (1343件中 1-50件目)
-

西山・・・川平ルートで
16日(日)夏から秋になった実感が無いまま急に寒くなって、あちこちで紅葉の便りも聞きますが、東北ではクマのニュースばかりですね。餌のドングリが大凶作だから、冬眠するために食いだめしたくてもお腹がすいて人里に下りてくるのでしょうが、どんどん人家や庭に入ってくるから東北の方々は大変でしょうね。クマはかわいいキャラクターになるから殺処分しないで欲しいという声もあるけど突然出くわしたら襲われるから仕方が無いのかも・・・我らは野生動物のテリトリーに入って楽しんでいるので気を付けないといけませんね。東北の登山者は最近は山登りはどうしているのかしら?と気になります。今回は久しぶりに犬山市の西山に登りました。西山は2023年に登ってい以来で、川平ルートは2021年以来なので4年ぶりです。登山口の林道は突き当たりまで、距離は短いけれどとても荒れていて一瞬林道に入るところがわからないほど、木や草が生い茂って車一台がやっとの道は、木の枝で車の側面を擦りながら進みました。もう今回でこの道は通るのはやめようと思うほどでした。少し進んだら車止めのチェーンの向こうに左の沢へ下りる看板が有ります。以前は無かったロープが付けられ、板も渡されていますが板は苔むして滑りそうなので、沢の石を渡ります。渡り切ったらすぐにすごい斜面に取り付いてジグザグに切られた道をよじ登るように登って行きますここは帰りには気を付けないと・・・落ち葉で滑りやすい。ぐいぐい高度を上げて第1展望台木曽川の流れが真正面に見え向うの街は美濃加茂かしら・・・まだまだ斜面は続きます。第2展望台第一展望台から真正面は坂祝町の街かしら・・・第2展望台を過ぎてからは広くて緩やかな尾根の道今までの急斜面がウソみたいです。第3展望台へ左へ行けば第3展望台は展望の良いところです坂祝町の町の向こうは美濃加茂市マンガン鉱の跡以前行って見ましたが、すごい絶壁を木を掴んで下りてみたけれど絶壁に人が一人通れる穴が開いているだけの状態でした。どうやって採掘したものを上に上げたのかしら?と思うほどでした。登山道に戻るとき、すごい斜面をよじ登りながら2度目は無いなと思ったほどです。黒いのがマンガン鉱でしょうか、いっぱいこのあたりの登山道に落ちています。天神山山腹を巻いて行くときこのルートで一番きれいな黄葉ですこのルートは登山口以外は、ほとんど自然林なのでいい感じ左へ少し登れば天神山山頂天神山山頂(313m)女性3人組さんがお昼ご飯を食べていましたので山頂の写真はこれだけ、帰りにゆっくり写しましょう。伊吹山今日は天気が良いけれど、遠望ははっきりしません。御嶽が正面に見えるはずなのに、見えません。左前に猿喰城が見えています。その奥に冬によく登る明王山や金毘羅山が見えています。この時期はモチツツジの狂い咲きがポツポツ分岐を左へ行けば第4展望台へ大岩の上KIKIの向こうに見えるのは第5展望台木曽川の流れが青くとても綺麗第5展望台の一段下でゆっくりランチタイム本当は御嶽山が見えるのですが・・・JR高山本線の列車が結構頻繁に走っています。2両編成や8両編成などいろんな車両が走っています。目の前の山は、採石場で石を採り続ければあと100年位で無くなりそうですねお昼ご飯の後は第5展望台の岩の上で証拠写真向うに見えるのは鳩吹山です。先ほどランチしている時に、一段下でランチしているカップルと話が盛り上がりいつまでもお話が途切れなかったけれどまだ目的の西山に行っていないので、切り上げて向かいます。今日は遠望が利きません。鳩吹山への分岐我らは西山へ向かうので右へ西山山頂(340m)4等三角点が有ります。昔は「両見山」という表示も有りました。あったかい山頂広場は誰ももう居ません。4等三角点(点名 西山)これだけ丁寧にかこまれているのは珍しいですね。途中で御嶽山と木曽川がとても綺麗に見えるビューポイントがありますが今日は御嶽山が見えないので残念天神山まで戻ってきました。太陽が西に傾いてもう誰も居ません。ゆっくり休憩して、さあいよいよ下山です。(振り返って写した写真)ゆるい下りの尾根道はずっとこのまま歩いていたいけれどこの先第2展望台を過ぎたら、気を使いながら一気に激下りです。落ち葉と、落ち葉の下に隠れている小石の石車に気を使いながら(一度石車に乗って危なかったわ)登山口まで下りてきましたが、ここの登山口まで車で入るのは今日で最後です。だから今日はいっぱい思い出の写真を撮りました。今が一番登山にはいい時期です、クマに気を付けて楽しみましょう。
2025.11.20
コメント(2)
-

大湫宿と本陣山
8日(土)今まで何度も、好きな中山道の馬籠宿から妻籠宿まで歩きました。今回は同じ中山道でも大湫宿と本陣山を歩きます。たまたま国道19号線近くを地図で眺めていたら大湫宿を見つけたのです。中山道大好きなKIKI はさっそく飛びつきました。そして本陣の北裏の本陣山は、登山の山でもあるのでセットで楽しめるではありませんか!! 旧中山道の大湫宿は江戸の日本橋から京都の三条大橋までの69宿(532Km)の内岐阜県(美濃の国)を通る17宿のうちの一つで江戸から47番目の宿場です。我らの車は、国道19号線から県道65号線を北へ、途中から一車線の細い急斜面をグングン登って行きます。モミジの大木の並木が右側の川沿いに続いています。そして突然開けたのどかな景色は大湫宿です。本陣跡の駐車場に向かいます。斜め向かいには丸森(森川邸 今は観光案内所になっています)ここで案内図のチラシを頂いて登山開始向かいは大湫コミュニティセンター静かな大湫宿です。大湫小学校跡のグランドの横から山に入っていきます。以前はグランドの一段高いところには校舎が建っていました。登山口登山道は少し荒れていて、最初から急斜面です。ところどころ標識があるので安心して歩けます。ホウノ木の葉っぱがいっぱい落ちています。向うに看板が有り氷餅池思ったよりも山の中にしては大きい池ここで作った氷餅を将軍家に献上していたそうです。あと少しで本陣山の山頂本陣山山頂(633m)二等三角点(点名 大湫)植林に囲まれて展望は有りません。証拠写真だけ撮って進みます。植林が無ければこれほどの展望なのね進んでゆくと岩の上に祠が・・・保々家改石祠となっていますが、改石って何かしら?しかし、保々家は大湫村の開基なのね植林の中をほとんど平行にすすんで行くと鳥の根(東屋)とっくに12時を過ぎているので、ここでお昼ご飯を頂くつもりでしたが展望も無く日陰で暗いので、やめて進みます。少し下がったら腰かけ岩ですが、もっと大きい岩を想像していたのでなんだ~こんな岩だったの~と少しがっかり荒れた道を下って、笹藪に突入矢印の標識が有るからいいけど、なければ少しためらいますね。石畳の道に出て、琵琶峠に向かいます。とても立派な石畳で、熊野古道の石畳より石が大きく坂道を緩やかに段差をつけているのでとても歩きやすい。広くなったところにベンチと標柱ここに琵琶峠と標柱が有るのでてっきりここが琵琶峠かと思いました。八瀬沢の一里塚までまだまだ緩やかに登ります。石畳は坂になっていないので、滑りにくく歩きやすい。石畳の坂道は苔がついていると雨の後は濡れてずべりやすいので坂になっているとさらに滑りやすい。写真で凸凹になっているように見えますが、少しずつ石の高さで段差をつけてくれています。熊野古道の石畳は坂になっているので下りは怖かったのです。一部狭いところもありますが、比較的広い石畳です。標高585mの高所にあり、全長730mの国内最長級の石畳です。ここで文学碑と見晴らし台という表示に惹かれて脇にそれて登ります。文学碑その向こうに新しいあずまやがあり、水晶山とその奥に屛風山系の山々が見えています。ここで遅いランチです。暖かい風の無いところでゆっくりお昼ご飯を頂いて再出発。道を下って行くと丸い土饅頭のようなものが二つ並んでいます。八瀬沢一里塚です。来た道を振り返って、植林の中の明るい鞍部がどうやら琵琶峠です。我らは文学碑とあずまやに行ったために琵琶峠を迂回してしまったようです。戻り道はちゃんと琵琶峠経由で戻ります。馬頭観音と皇女和宮様の和歌が記されています。皇女様がここを通った時に、以前はもっと見晴らしがよかったので遠くに見える伊勢湾を、琵琶湖だと思って京都を思い出して和歌を詠んだそうです。それと、もう一つ琵琶峠の名前にまつわる話は京に琵琶師の修行に行った青年が、修行途中であきらめて実家に帰ろうとしてここまで来て休憩していたら風に揺れる木々の音が素晴らしく木でさえ素晴らしい音を奏でるのに、自分は途中で諦めようとしていると反省して京に戻って念願の琵琶師になれた、という逸話があるそうです。琵琶峠東上り口ここにも馬頭観音がまつられています。風情のある峠への東入口ここからは舗装道路を大湫宿に向かって歩きます道路の横に休憩場、ここから安藤広重が大湫宿を描いた場所です。当時は坂道で、今も緩やかな坂道ですが、車だと坂道の感覚が少なくあっという間に過ぎてしまいます。ここにも馬頭観音様石橋の欄干ですが一つしかないね・・・グルリと周りを見渡せば、道路の反対側に片方の欄干の石が有りました。宿場の入口の看板美濃の国の17宿の名前が書かれています。大湫宿は海抜510mの高地で美濃の国で最も高所にあり急坂が続く難所でもありました。宿場の入口には高札場幕府からのお知らせを掲示するところキリシタン や バテレンと書いてます。大湫宿の碑観音堂綺麗な天上絵 しかし、ガラス越しなので反射して見にくい毎年7月の半ばに御開帳が有るそうです。いい音がする鐘おまいりする時に鳴らしてもいいと書いてあるので一つだけ突かせて貰いました。神明神社のご神木2020年7月の豪雨で倒れたご神木(樹齢670年)を切って屋根をつけて保存している。脇本陣保々家の家です。一般公開されていないので門から写しました。門田屋(旅籠)二階の防火用の虫籠窓が素敵ですね。時代劇に出てくる防火用水の桶まるでタイムスリップしたみたい以前は旅籠だった建物を撤去して公園になっているそうです。小さいけれど風情のある門と飛石と紅葉の木ベニマンサクマユミ澤瀉屋旅館として再建され近々オープンの予定だそうです。屋号丸森(森川邸)に戻ってきました。観光案内所になっています。朝は大湫宿の地図と本陣山の地図を貰いました。大きな建物で、塩の販売で儲けてこのあたりでも指折りの富豪となったそうです。中は大きな梁がとおしてあり、屋根には越屋根(煙出し)が付けられています。越屋根(煙出し)が有るのはお金持ちの象徴だそうです。皇女和宮様の徳川家茂将軍への降嫁の行列や大湫宿の町並みを神明神社の倒れたご神木の枝の木を使って再現した精巧な細工すごい精巧で一軒一軒の建物の特徴を再現しています。和宮様は輿の中お供の数は京都から5000人ほど、途中で駆り出された人や将軍家から迎えに来た人も入れて30000人ほどの人数です。行列の初めから終わりまで、宿場より長いのですべての人は大湫宿に泊まれず、皇女和宮様と主だった人は本陣にその次の位の人は脇本陣に泊まり、あとの人は仮小屋を建てたりもっと先の宿場や手前の宿場に分泊したそうです。観光案内所の方がご親切に説明してくださいました。丸森(森川邸)のミニチュアにも、ちゃんと越屋根がついていますね。観光案内所の方々といつまでも話が尽きないけど、またの再会をお約束してお別れしました。風情のある石畳はとても印象的で、こじんまりとした大湫宿も静かでまるでタイムスリップした感じでよく保存されています。国道19号線や高速中央道が土岐川沿いに作られたのでそれより高いところにある中山道大湫宿は、幸いにも開発されずに残ったのです。またまた、大好きな中山道にまた一つ大好きな宿場が出来ました。紅葉はもうちょっと先でしたが、静かな宿場町や静かな本陣山を歩けて懐かしい日本の昔の姿が、現実の人の生活と共に今でも残っているのを見て貴重な文化財を後世に残して行きたいと思いました。しかしこの宿場の静寂はいつまでもつのだろうか・・・
2025.11.12
コメント(0)
-

見行山・・・山頂の変化にびっくり
11月3日(月 文化の日)父の誕生日でもあり、父の弟(叔父)二人の誕生日でもあるこの日岐阜県八百津の見行山へ一年ぶりに行ってきました。土日は用事があり、三連休の最後の日に登りました。登山口の福地いろどりむらの駐車場は二台の車が停まっています。三台目に我らの車を停めて、いろどりむらの方へ向かいます。キャンプ場のいろどりむらは来るたびに変わってゆきます。建物が一つ増えていました。写真左端が古民家を移築した母屋です。斜面を下りてキャンプ場から見たら水車小屋や、新しい家も出来てます。キャンプサイトの奥から山に入ってゆきます。今日はシロモジの黄葉を期待してやってきましたがあまり黄葉していませんね登山道は少し荒れていて、藪漕ぎ状態のところもありますが人気の山なのに皆さんはどこを歩いているのかしら・・・林道を横切って登山口すぐに獣除けの鐘が新たに設置されています。昨今クマ出没のニュースばかりですからね。我らもカンカン鳴らして山に入っていきます。来るたびに石が積まれていく石仏みたいな石今日は花が無いので、ツルキキョウの赤い実でも目立ちます。クリのイガがいっぱいこのあたりはクリが多いので餌が多くクマが里に下りてくることが無いのかしら・・・しかし、山はクマのテリトリーだから今日も笛を吹きながら歩きましょう。植林の尾根をジグザグにのぼり、右の方へ折れたら明るい自然林の林に向かいます。一株だけセンブリを見つけました。アカマツの多い斜面で、ここから好きな道です。ポツポツとシロモジが出てくるところですが一週間早かったね~、黄葉していません。標高777m黄葉していたらこの辺りは真黄色ですがまだまだ緑色です。あと少しで展望地です。写真左のシロモジも少しだけ黄葉していますが・・・サンキライの実が赤く色づいて802m展望地あと400mで山頂ベンチは壊れていますが、登山口のいろどりむらが下に見えています。南西側の展望伊吹山が目立ちます少しズーム足元の登山口の集落といろどりむらの母屋少しズーム再び歩き出します黄葉や紅葉はまだまだですねシロモジがいっぱいなので、黄葉したら黄色の登山道になるのですが・・・一週間ほど早く来過ぎました。この登山道は好きな道ですここが一番斜度がきつくて頑張りどころアカマツが生えている山頂が見えてきましたここを登ったら山頂雲一つない青空です。エ~何でしょうか、すごいことになっています。今はやりの山頂にテラスです。横に去年12月に個人の方が寄贈されたと看板が有ります。山頂にテラスが出来るのが流行りなのかしら・・・この山にもテラスが出来ているとはびっくりです。去年11月に登った後に出来たのですね。貸切だと思ったら、テラスで無線をやっている人が居ました。御嶽山は雪を被って冬装束です。中央アルプスもしっかり雪を被っています。南側には伊勢湾が光っています。ズームで名古屋駅ビルと光る海山頂はメチャクチャ風が強くて寒くて立っていらません。とてもお昼ごはんを食べることもできませんからいったん下って風を凌げるところを探してランチです。持ってるジャケットとレインウェアの上を着ても寒いとても寒そうなKIKIです。右となりの笠置山の向こうに恵那山恵那山も少し雪を被っていますね恵那山は山頂まで樹林帯ですから、木が雪で白くなっています。見行山山頂(905m)で証拠写真二等三角点(点名 見行)ここにも鐘が有ります。メチャクチャ風が強いし寒いので下山します暖かい防寒用のジャケットを持ってくるべきでした。これほど寒いとは思ってもいなくて、もう完全に冬用装備が必要です。獣除けの鐘は全部で三個設置されていました。全部鳴らして、笛吹いて、大きな声でおしゃべりしながら歩きました。今日はシロモジの黄葉を見るつもりでしたが、来るのが一週間ほど早かったですね。しかし山頂にテラスが出来ていたり、キャンプ施設も新しい施設が出来ていたり獣除けの鐘も設置されていたり、来るたびに変わる山でした。しかし、変わらないのは、御嶽展望です。今年は御嶽山に登っていないので、ここから眺められて良かった~~
2025.11.07
コメント(0)
-

屏風山・・・もう山は冬
今月の湿地の花はリンドウとウメバチソウリンドウは木道の近くに咲いていましたがウメバチソウは遠くて望遠で写しました。28日(火)土日は天気が悪く、月曜は地域の用事で珍しく平日の火曜日に登山です。最近の屏風山は土日はすごい人で、駐車場も遅いと停めることが出来ないという状態ですが平日は貸し切り状態でした。登山口にツリガネニンジンが咲いています。咲き方がツリガネニンジンらしくないのですが花はツリガネニンジンですね風が冷たく、相棒はもう冬の下着に厚地の山シャツですが暑がりの私は夏のシャツのままでした。しかし、稜線に上がったら風がすごい状態で、止まったら寒くて秋を飛び越えて山はもう冬です。ここから先は風がビュービュー音を立てて吹いている中を歩きます。かえる岩石仏様いつも通りおまいりして登ります。登山道の笹は刈り取ってくださったので歩きやすくなっています。名古屋方面が開けているところから望遠で何とかぼんやり名古屋駅前ビル群が蜃気楼のごとく浮かんでいますコウヤボウキくるりんと巻いた花弁が可愛いです。センブリ実はこの花を確認しに来ました。先回9月21日にここで花がついていない状態の茎と葉っぱをたくさん見つけたのです。センブリのようだと思って、花が咲くこの時期にやって来たのです。やっぱりセンブリでした~~登山道にいっぱい咲いています。今まであまりこの時期にこの山へ来たことが無かったのです。初めて登った2000年10月28日はまさしくこの日でしたがその日は、別の登山口から登ってほかの事に気をとられていました。それは登山口で捨てられた子ネコがなついてきて離れてくれなくて結局山頂までついてきて、山頂で一緒にご飯をたべて一緒に下りてきて相棒の実家の家の猫になったのです。そういうことで、子ネコのことばかり気を取られカメラもフィルムカメラだったので写真があまり無かったのです。分岐左は稜線歩きで屏風山へ、右は沢沿いを湿地へひとまず、左へ急斜面をグングン登って行きますこのルートで一番標高を上げる所ですあと少しで、一番高い稜線にたどり着きます。後は緩やかなアップダウンの繰り返しで屏風山へ。稜線歩きは西から吹いてくる風との闘いです。山頂はきっと風が強くて寒いだろうからお昼ご飯を途中で風の来ない所で食べようと東側へいったん下って、風の来ない暖かいひだまりを探してゆっくりランチタイムです。再び歩き出してすぐに、黒の田山標高がわかりません屏風山系で一番高い八百山(800m)登ったり下ったりして屏風山山頂です。シンボルツリーのアカマツが輝いています。反対側の開けた所から東北方面に恵那山が見えるはずですが山頂に雲がかかっているので恵那山らしくありません。一等三角点(点名 屏風山)登山者が多くなって、屏風山山頂(794m)は草が生えなくなりました。以前はもっとモシャモシャしていたような。最近はこの表示の山を一日で歩く若者が多いそうですが私たちはこの屏風山と黒の田東湿地で十分です。山頂は予想通り風がメチャクチャ強くて寒くて、恵那山の展望も今一つなので大急ぎで写真を撮ったら下ります。途中で木の間から東北の方が見える所で恵那山の山頂に掛かっていた雲が少し上空へ上がったので恵那山らしくなりました。馬ノ背山(767m)この先で黒の田東湿地へ下ります。湿地が見えてきました向うにシルエット状に月山がわかります。貸切の湿地ゆっくり花探しです。リンドウは足元に咲いていました。湿地の中にもポツポツ木道から1m位だから何とか写真が写せます。木道から3m位離れた水の中のシラタマホシクサの中にウメバチソウが咲いていますが遠すぎて私のコンデジではこれが限界です。暖かいテーブルで、温かい飲み物を頂いて至福のひととき。今年はこの湿地に季節を変えて何度もやってきました。季節を変えたら咲いている花も違って楽しめますね。ヤマラッキョウ (ユリ科ネギ属)これも木道から3m以上離れた湿地の中なので遠すぎてこれが限界一つだけ木道近くで咲いていましたシラタマホシクサは花期が長いのですね。しかしもうドライフラワー状態でしたサワシロギクはもう終わりです、花は咲き終わりは白から紅色に変わります。イワショウブも種になっています。ゆっくり一時間貸切の湿地でのんびり過ごして太陽が西に傾いているので、下山しましょう。センブリがいっぱい咲く登山道を歩きながら3~4つの木橋を渡って朝の分岐まで戻って一周しました。後はエコーの森を通って登山口まで戻ります。今日は時々クマよけに笛を吹きながら歩きました。あちこちでクマが人里に下りてきているニュースを見ます。私たち登山者はクマのテリトリーに入っているのでもっと出会う可能性は高いので通りますよ~~と笛で知らせています。北海道のトムラウシでヒグマとバッタリ出遭っているので二度とあのような怖い経験はしたくありませんから遭う前に知らせようと吹いています。いつも付けている熊鈴は、あまり遠くまで響きませんからね。今日は思った通りの花に出会って満足でした。センブリの花が咲いていたし、湿地にウメバチソウも、リンドウも咲いていました。シラタマホシクサが花期が長くて、長い間楽しめるのも知りました。季節を変えたら同じ山でも楽しめるからこの屏風山が年中人気なのもうなづけますね。
2025.10.30
コメント(0)
-

段戸山…雨上がりを待って
19日(日)天気が今一つはっきりしなくて、段戸山と岩岳の二つ登るつもりでしたが段戸山のみとなりました。登山口に向かう時から時々雨に降られ登山口に着いたときは結構な雨でした。車の中で止むのを待っていたら、小降りになったので歩き出しました。笹でズボンが濡れるから始めから上下のレインウェア完備です。作業用の林道がどんどん作られて登山道が寸断されています。しかし尾根を外さず登って行けば、ところどころ古い看板もあり間違わずに登れますが、数年前は新しく出来た林道をかなり上まで歩いてしまい結果的には余計回り道をしたのです。登山口に表示があります昔、この表示が見つからず、駒ヶ原山荘から登ったこともありました。藪漕ぎをして大汗かいて、やっと今の登山道に合流した時はホッとしたものです。駒ヶ原橋橋を渡ってすぐの左の笹藪の中に標示が有りますが、もうこの藪の中を歩かなくてもまっすぐ登れば林道に出るので、ここはたぶん誰も歩かないでしょう。林道を横切って尾根を登ってゆきます。下に登山口の橋が見えています。以前一度だけ出来たばかりの林道を歩いてしまって、結果的に遠回りしたことが思い出されます。食べられそうなキノコがいっぱい尾根上には、ところどころでこの表示が出て来て誘導してくれます。センブリリンドウ科 センブリ属仲間にアケボノソウが有ります。今日の花は センブリ です。漢方薬で、昔はおばあちゃんがセンブリ茶を飲んでいました。間違って口にしたらとても苦かったわ登山道のあちこちに咲いています。とても手入れが行き届いた植林です。枝打ちがしっかりされていますね。雨に濡れてとても綺麗に咲いています。雨上がりの登山道は、木の根は要注意この写真の辺りは木の根が少なくて歩きやすかったけれど木の根がいっぱい露出している所は緊張しました。左の下は新しく作られた林道で、木が伐採されて明るくなっています。尾根上で90度右に折れて下ります。やっと登ったのに下るのは納得できないのですが・・・登山は登りだからと言って、登りばかりじゃないのです。暑くなったので、レインウェアの上着だけを脱いで歩きます。時々藪漕ぎクリがいっぱい落ちてます。東北では今年はクリやどんぐりが大凶作だとニュースで知りました。だからクマが餌を求めて人里に下りてくるとか・・・この辺りは豊作なのかしら・・・この山はあまり岩が有りません。登山道沿いで唯一の岩です。春はこの辺りはカタクリが群生するところです。笹の背丈が低くなってきました。笹も無くなって、山頂が近い段戸山山頂途中で追い越していったカップルが居ません。ということは向こう側に下りたのですね。段戸山山頂(1153m)今回で8回目です。二等三角点(点名 段戸山1 )が有ります。地面が雨でぬれてべたべたなので、立ったままおにぎりを頂いてすぐ下山します。こんな天気なら山頂から富士山も見えませんものね。今日は我らの他に一組が登っただけです。山頂のシンボルツリーブナでしょうか・・・この木は大きくなり、周りの木も大きくなって山頂からの展望は一か所だけになってしまいました。以前の写真を載せてみました。↓2020年5月1日この日は天気が良かったこともありますが、周りの木も背が低くおまけに梯子が掛かっていたので登れば展望が得られたのです2020年5月1日私が登っています。もうこの梯子はありません。センブリがいっぱい咲いている所まで下りてきました。獣の足跡、カモシカかな?下山して車の後ろでウィンナーと卵を焼いてお昼ご飯の続きを頂いてのんびり秋の山を楽しんで帰宅しました。当初はもう一つ、この近くの岩岳にも登るつもりでしたが、雨が止むのを待っていたので、二つ目を登る時間が無くなりました。去年も二座目の岩岳を下山した時は日没ギリギリになったので、焦って歩いたことを思い出します。「秋のつるべ落とし」という通り、陽が落ちるのが早くなったので、今日はこの段戸山一つで良しとしましょう。
2025.10.25
コメント(0)
-

各務原権現山・・・航空祭を見るために
12日(日)各務原自衛隊の航空祭は19日から12日に変更になってブルーインパルスの演習も無いということでガッカリしながらも山の上から見るために登ることにしました。去年11月17日に偶然、継鹿尾山に登ったら航空祭の日で登っている途中から頭上で爆音がしていました。その時に継鹿尾山山頂で知り合った飛行機が詳しいお兄さんが今年は各務原権現山に登って飛行機を見るというので私たちもその山に登ることに。登山口の伊吹の滝不動の駐車場は、かろうじて一台分が空いていてなんとか停められました。境内の裏から登って言います。狂い咲きのモチツツジが咲いています。この時期は蚊が多くて、私はすぐに狙われてたくさん刺されて、痒い痒いジグザグに登って行きますが、私の周りは蚊がブンブン付きまとっています。左は六所神社の分岐やっと尾根上の稜線歩きです。これで蚊とも離れられるかと思ったけれど・・・この山に初めて登ったのは2005年1月で、この山が2002年4月に山火事でほとんど丸焼けになった3年後です。2005年1月の写真この稜線は焼けた木が立ち枯れていました。だから下界の景色が見えて、まるで森林限界の上を歩いているみたいでした。右下の蘇原の街や各務原自衛隊基地を見ながら歩きました。木の茂り方が上の写真とは大きく違います。北山休憩舎これは帰路に写したもので誰も居ませんが朝はたくさんの人が休憩していました。今は緑が戻って左右は見えません。ほとんど水平移動で、この辺りは気分よく楽に歩けます少し登りになったらこの稜線の一番高いところに鐘のある展望岩場鐘の向うには岐阜城(左のピーク)と百々ヶ峰(右の高い山)この看板は初めて登った時から有ります。だいぶん年季が入っていますね以前はこの周りは木が無くて、山頂まで見渡せてここから山頂の鳥居まで見えていました。そしてこの石段も下界から見えていました。今では木のトンネルの中の一直線の急斜面の石段を登りますたくさんの人に追い越され汗びっしょりになって、フーフー言いながらやっと山頂近くまで登って来ました。たくさんの人が同じ方向に座って、航空祭の飛行機を見ています。多度神社これは帰りに写したもの、登った時はいっぱいの人が居ました。お昼ごはんを頂きながら、航空祭を見ています。何とか写せたのはこれだけF-15 だと思います。こちらの方へ旋回してくれたので何とかお腹を写せました カメラの望遠で、各務原自衛隊基地を写してみたらC-2 が滑走路を動いてるたくさんの人が見学していますねあれほどたくさんの人がいたのに下りてしまって誰も居ません。お昼になって戦闘機が飛ばないので変だな~と思っていたら、今日は近所のお祭りと重なったので飛行は遠慮したらしい。戦闘機の爆音の代わりにお祭りの太鼓の音が聞こえています。山頂のモミジは少し紅葉し始めています。帰る前に北山の方へ行って見ましょうここを右へ来るたびに変わる、北山山頂KIKIの後ろのピークが各務原権現山の山頂向うに見える山並みは各務原アルプス~関南アルプスです。望遠で見たら明王山(左の鉄塔)と金毘羅山(右)が見えています2cmくらいの可愛いスズメこの北山は昔は何もなかったけれど来るたびにどんどん変わっていきます。ベンチも椅子もたくさんできています。昔一人で登った時に、権現山の山頂は人でいっぱいでしたから1人でこの北山の木に囲まれた小さな広場でご飯を食べた記憶があります。その頃から比べたらものすごく拓けました。2005年1月の写真北山山頂はこの小さな看板だけでした。初めて登った時は今から20年も前なので若くて元気でしたから昼前から登り始めたのに、この先から雪の残った北側の急斜面を下りて隣の芥見権現山まで足を延ばしたのです。2005年1月の写真芥見権現山へ登る途中です。斜面はほとんど丸焼けの状態です。木が無く岩が露出しています。今では木が茂ってこんなに岩が多い山だとはわかりません。権現山に戻る途中で金華山の岐阜城の方を見て遠く名古屋駅前のビル群各務原権現山を後にして、下山しましょう。長い一直線の石段を下ります。鐘のある展望岩場から金華山と百々ヶ峰を見て誰も居ない北山休憩舎再び途中から蚊に付きまとわれながら伊吹の滝に下りてきました。今日は航空祭の戦闘機の編隊飛行を見るのを楽しみにして各務原権現山に登ったけれどほとんど飛ばず、遠くてあまり見られませんでした。この時期は蚊に集中攻撃に遭うし私的には冬の方がこの山は良いなと思いました。
2025.10.17
コメント(0)
-

長者ヶ岳 1336m・・・二日目の山
4日(土)静岡の山、2日目は田貫湖岸から登る長者ヶ岳です。前日は越前岳でしたが車中泊はとても寒くて夏のシュラフは失敗でした。長者ヶ岳に登る前日の車中泊はそれほどでもなく爽やかでよく眠れました。朝、登山口に向かうと目的の田貫湖キャンプ場の北サイトは工事中で10日まで入れません。仕方が無いので休暇村富士から登る登山口に変更します。休暇村富士の建物の裏側の林道突き当りから登ります。 植林の中の登山道は荒れていてとても歩きにくいジグザグ道が続きます。この手前で、林道がすぐ横に見えたので、林道で登るほうが楽かと思ってKIKI 1人が林道の方へ下りたのが間違い登山道とずんずん離れてしまい、相棒の歩いている正規の登山道まで戻りました。(余計な事をしたため、無駄に疲れてしまいました)段差も有るので大変です。この道は下調べをちゃんとやっていませんでした。柵は東海自然歩道らしいですね自然林の中は気持ちがいい 主稜線との分岐ジグザグ道が終わって長者が岳の主稜線の登山道へ合流する分岐に到着誰がやってくれたのね分岐にはベンチが有って、今まで見えなかった富士山展望地でもあります。昨日と変わって今日は富士山はガスにまとわりつかれています。山頂は雲で隠れてるシモバシラシモバシラが最盛期でいっぱい登山道に咲いています。地図上の1059mピークはどこかな?少し植林の中ここで下りてくる男性二人組とすれ違ってその後トレイルランの若者と出会ってこの辺りが地図上の1059mでしょうかトリカブトこの辺りは起伏も少なくて歩きやすい大きな木食べられそうなキノコ自然林だから気分よく歩ける前方に何か見える、何だろう・・・このあたりで雨が降って来た、このまま小雨が続き止むだろうと思っていました休憩のテーブルとイスでした。ここで相棒はレインウェアを着て私はレインウェアの上着を手を通さずザックの上から掛けて雨除けにして歩きました。でも雨はやむどころかどんどん降ってきます。このあたりでちゃんと着ればよかったけれどそのまま歩きます。何度も階段が出てくるのでそのたびにその上のピークが山頂かと期待しますが、外れます。何度この景色に騙されたことか・・・ああ、やっと本物の山頂ですここでレインウェアの上着をちゃんと着用して雨足の強くなった中で、傘の下で立ったままおにぎりを食べたのです。足元には田貫湖天気が良ければ目の前に富士山がバーンと見えるはずですがガスの中ではっきり見えません。キャンプ場が見えます。一瞬 二等三角点かと思う、三等三角点(点名 熊平)前進したら天子ヶ岳です。我らはここで下山します。雨に濡れたから寒いのかと思ったら、山頂は12度しかありません。寒いはずです。富士山の温度計ですね(笑)雨に濡れてきれいな緑の景色の中を下ります。分岐の手前で富士山が樹間から見えました。山頂より見えています。分岐から見えた富士山まるで墨絵の世界です。山頂では真っ白な雲の中にすっぽりと隠れていましたが白黒の墨絵のようでも姿が見られて良かった~~ありがたくて手を合わせてしまいました。下山したら雨がやんでいて下山後田貫湖キャンプ場の南サイトから登った長者ヶ岳を眺めてみましょう。なだらかな山が長者ヶ岳です。今回は富士山を見る山に登ろうということで静岡の越前岳と長者ヶ岳の二つにしましたが静岡に向かって車を走らせている時から富士山が見られて越前岳はずっと登りも下りも富士山が見られて長者ヶ岳は雨で山頂では見られなかったけれど、分岐で見られて三日間富士山を堪能出来た山旅でした。やはり富士山は日本一の高い山で美しい山で、日本人が大好きな山ですね。
2025.10.11
コメント(0)
-

越前岳・・・富士山展望の山
10月3日(金)今年は高い山は八ヶ岳の天狗岳で遠い山には行っていないので、久しぶりに富士山を間近に見ようと静岡の愛鷹山塊の最高峰、越前岳に登ってきました。2003年4月に丹沢山と塔ノ岳の帰りに、初めて越前岳に登ったきりで22年ぶりでした。もう一度登りたいと思いながら、他の山を優先したためなかなか二度目は無かったのです。十里木高原から登るので遮るものが無く富士山のすごい展望です。2003年に登った時はデジカメでは無かったのであまり写真がありません。パソコンに取り込んだ少ない写真を見ても、あまり記憶が蘇らなくて記憶は登山口と馬の背からの展望だけでした。今日の天気は本当は良いはずなんですが曇っています。ススキの向こうの電波塔が第一目標です。この長い丸太の階段は、段差がある上にこの先かなり崩れて歩きにくい。休憩するたびに振り返って富士山を眺め高度を上げると富士山の周りの景色も広がって何度も何度もシャッターを押すことに・・・デジカメだからできるけど、以前のフィルムカメラなら簡単にまばたきみたいにシャッターは押せませんね。富士山の周りは青空になってテンションも上がります。前回は4月でしたので、富士山の山頂に雪が有り富士山らしい姿でした。ここがてっきり馬の背だと思っていたら違いました。電波塔の広場です。可愛い展望台があります。展望台から下から見えていた電波塔です。ミヤマアキノキリンソウその先は登山道が荒れていて、真ん中は通れません。年賀状に使えそうな写真ばかりです。目的の越前岳もう一つの電波施設、反射板と鉄塔青空はすぐに雲が出て、アッという間に空は変わります。宝永火口や、ジグザグの登山道、点々と小屋が見えます。ホソバトリカブトここが、馬の背見晴台三等三角点(点名 越前ヶ岳)があります。もうほとんど青空が無くなりました。富士山を眺めて大休止富士山の一番高い剣ヶ峰の、気象観測ドームがあったところに今は何か施設がありますね下山後調べたら、剣ヶ峰山頂にはこんな施設が出来ています。以前に登った時はドームを撤去工事中でその後に登った時はドームが無くなっていました。今までは歩きやすい登山道でしたが岩岩の歩きにくい道になって岩をよじ登り、木の根を掴んで木の根に足を掛けずーっとこんな道が続くのか?・・・記憶が無いのですが。岩々の道が終わってホッとしたら木の根の道が始まります。登山者が増えすぎて、登山道が荒れてしまったと聞いています。22年前に登った時は、確かに人が少なく誰も登って来ませんでした。コウヤボウキ登山道が荒れてえぐれて、比較的歩きやすい道を選ぶのが大変です。みんな様々なところを歩いています。しかし植林では無く自然林なのが良いですねアキチョウジシモツケソウオヤマリンドウ立派なブナ崩壊地山土は滑りやすくて、ここは気を使います。しかしここからは富士市や、富士宮市、駿河湾が見られます。青空は無くなって、雲も六合目あたりに湧いてきて下山するころは富士山は雲の中なのかな・・・駿河湾と富士市、富士宮市街勢子辻分岐選ぶ道を間違えたら、段差の道になります。ここでは写真の後は右の道を選びました。貸切の 越前岳山頂(1504m)木の向こうに富士山がかろうじて見えていますが、そのうち木が大きくなったら隠れてしまいそう。以前の三角点があった所に、もう一つの山頂標識です。三角点が無くなったので、昨日新しい三角点が設置されたばかりです。昨日、登山口にやってきたら、ちょうど国土地理院の方4名が下りてこられて、新しい三角点を埋めてきたところだとおっしゃった。出来立てほやほやの二等三角点です。点名 印野村山頂広場にはオヤマリンドウが最盛期で咲いています。お昼ごはんには早いので、おやつを食べて貸し切りの山頂であちこちウロウロ写真を撮りまくりでした。清水港最後に新しいピカピカの三角点と富士山花が終わったシモツケソウに囲まれた、可愛いお地蔵さんにも手を合わせ次々とたくさんの人が登ってきて、座るところも無いぐらい大賑わいになったので下山しましょう。お昼ごはんは馬の背見晴台まで下りてきて、このテーブルで頂きました。曇っては来たけれど、富士山は最後まで姿を見せてくれています。雲が湧いてきているのでてっきりこのまま隠れるのかと思ったら夜寝るまでずーっと姿を見せ続けてくれました。越前岳を振り返って馬の背の展望台まで下りてきて展望台と富士山とKIKI最近は富士山の見える山に登ってもなかなか富士山は姿を見せてくれませんでした。22年ぶりにやってきた越前岳では、最後までしっかり富士山を見られて感激でワーワー言いながら登って下りてきました。やはり日本人は富士山は日本一のお山で特別な思い入れが有りますね。このあたりの人はずっと富士山を眺められるからうらやましいわね~明日は田貫湖の横の山、長者ヶ岳に登ります。
2025.10.08
コメント(2)
-

碁盤石山のトリカブト
私の中では碁盤石山の花はトリカブトです。27日(土)西納庫登山口から登ります。10mほど斜面を登ったら稜線の合流点に到着左は面の木園地へ、碁盤石山へは右です。今日は爽やかで、登山日和です。一本道の尾根を行きます足元にはほとんど花が終わったママコナ感じの良い稜線歩き階段を一気に下ったら木戸洞峠です。木戸洞峠の少し日の当たる広場にいつもトリカブトの群生があります。今年も咲いていました。これで富士見岩のトリカブトが咲いているのがわかります。咲き始めなので枯れた花も無く、蕾もいっぱいあるのでとても綺麗です。木戸洞峠から碁盤石山山頂へ一気に登ります。水平なところが無く、ひたすら登ります。途中で山栗拾いして遊んでいました。山頂が見えてきた碁盤石山山頂(1189m)二等三角点も有ります。途中ですれ違った人は単独の男性追い越していった人は単独の男性と一組のカップル今日は珍しく人に出会います。お茶を飲んで少し休憩して、富士見岩の方へ前進します。山頂から少し下ると、尾根に水場の標識尾根の上から谷の水場をズームで写してお水が流れています。山頂に何も施設が無いから、ここの水はきれいでしょうね私の好きな尾根ブナ林は良い感じですシカが飛び出してきそうな景色です。いよいよ、目の前のピークがトリカブトが咲いている所トリカブト(キンポウゲ科 トリカブト属)アセビの大木の周りはトリカブトの群生です。初めて登った時は1995年12月でその後何度も冬から春にかけて登っていますが、この花の時期に来たことが無く、これほどの群生は2023年9月30日に登った時に初めて知りました。この花を見たくて、この時期に最近は登っています。以前はこの群生地に碁盤石山山頂という看板が有りました。だから初めて東納庫登山口から登った時は、ここが山頂だと思って、本当の今の山頂には行かずに下山したのです。次はアセビの森を越えて大好きなモミジの森を歩きます。モミジの森を振り返ってまたまた、富士見岩の手前にもトリカブトの群生地こんなに綺麗ですが猛毒の花です。富士見岩この岩の上から富士山が見えたとか・・・この近くの段戸山の山頂から富士山が見えたので、まんざら嘘でもないでしょう。平山明神山、大鈴山、右端は鹿島山ズームアウトしたら一番奥に三ツ瀬明神山その右の一番奥に宇連山富士見岩の近くの木陰でお昼ご飯を頂いて食後の飲み物もゆっくり楽しんで、天狗の奥庭まで下りましょう。碁盤石の横に、以前は碁盤石山の謂れの看板が有りましたが今は朽ちて落ちています。昔の写真(2006年3月)です。味のある文字で掘られた説明文です。天狗がひっくり返した碁盤の石が点在しています。碁盤石山の磐座(いわくら)この辺りにもいっぱいトリカブト昔の山頂だといわれたところまで戻ってもう一度トリカブトの群生を見て帰りましょう。碁盤石山の山頂に向かって急斜面の階段を登ります。階段の途中で振り返ったら樹間から富士見岩のピークのシルエット碁盤石山の山頂を下って、木戸洞峠を越えて最後の登りのこの階段は102段車の駐車させている西納庫登山口への分岐を通り過ぎて面の木園地の方へ少し歩いてみたのです。茶臼山高原道路を左下に見ながら緩やかに登ったり下ったり面の木園地の手前のトンネルの手前までやってきました。この尾根の下が茶臼山高原道路のトンネルですが、今日はここまでです。富士見岩のあたりでのんびりしすぎたので井山から面の木園地へ行く時間は有りませんから引き返して登山口まで戻ります。今日は予想通りトリカブトの満開を見ることが出来ました。大好きな碁盤石山山頂から富士見岩までのブナ林やモミジの林もいい感じで何度来ても碁盤石山は好きな山です。
2025.09.30
コメント(2)
-

屏風山系の小松洞山と黒の田湿地
21日(日)先週と同じに、今回は屏風山系の小松洞山と黒の田東湿地です。8月24日に来た時は、小松洞山は当初山頂だと思っていたところがヤマップだと鉄塔のピークになっていたので行きなおしです。そして黒の田東湿地の花も変わっているかな?と思って。今日はいつもと反対に登山口に入ったところから逆に駐車場を写してみました。今日も駐車場は最後の一台分しか空いてなくて、なんとかギリギリで停められました。先週は歩き出したらすぐに登山道の両脇にポツポツと咲いていたホトトギスはほとんど見当たらず一週間で花が終わってしまったのかとガッカリしながら、でも探しながら登ります。分岐で左の小松洞山へ向かいます。前回はこのあたりが山頂だと思いましたが今日はどんどん下ります。一番下った鞍部から登りを期待しながらどんどん進みます。なかなか登りになりません。ヤセ尾根を進みます。このピークが山頂かと思ったら、そのまま進むことになります。またヤセ尾根山頂からの尾根に取り付き、左へ向かいますが帰りにはここでまっすぐに向かいそうで要注意です。まっすぐへ向かう踏み跡の方がはっきりとしているからです。相棒がここは気を付けないとまっすぐ下ってしまう、と言ってくれました。左に向かったらすぐに山頂の114番鉄塔です。小松洞山山頂 593m証拠写真を撮ってピークですが木が茂って展望も無いので戻りましょう。種になったシライトソウ先ほどの分岐を直進して次は湿地に向かいます。春はシライトソウがいっぱい咲いていた群生地には種になったシライトソウを確認してまた来年も咲いてくれそうです。かえる岩ガマガエルの顔ですね。アレレ~~??笹刈りされてますよ~~驚いていたら、早くも下りてきた三人組さんが今朝笹刈りをしながら登って行く地元の三人組がいたとおっしゃってました。先週この石仏様の周りだけ笹刈りしたのでよくわかりますね。観音様におまいりして登りましょう。下界が見える所で瑞浪市や、土岐市、多治見市等の集落を見て今日は名古屋市の駅前のビル群まで見えています。そしてその右後ろに鈴鹿の鎌ヶ岳まで見えています。エコーの森にやってきました。いつも思うのですが、なぜエコーの森なのでしょうか?最近は屏風山に登るときはいつもこの分岐を左へ行き、黒の田山経由で登ります。湿地へはこのまま直進。せせらぎを左に見ながら何度か橋を渡りながら歩きます。このあたりの背の低い笹の中にホトトギスたくさんを見つけました。感じの良いせせらぎの道です。せせらぎに掛かった橋を何度か渡りまたまた橋が月山への分岐を過ぎて歩いていたら、電動の草刈り機を持った三人組さんとすれ違い草刈りのお礼を言ったら、「先週下見に来たら石仏の周りだけやってくれた人が居た」と言われたのでそれは私たちのことですねと、お互いにお礼を言い合って別れました。やはり地元の方が登山道を整備してくれているのですね。ありがたいことです。湿地の外周です。湿地のこの木道には写っていませんがちょうどお昼なので、たくさんの人が木陰で休憩しています。我らも一つだけ空いていたテーブルでお昼ご飯を頂いてのんびりしましょう。今日もここでゆっくり花探しです。ホザキノミミカキグサミミカキグサミミカキグサは2mmくらいの小さい花で、木道からは遠いから、コンデジでは写しにくいのです。これは何とか大きく写せました。シラタマホシクサは花期が長いようで、今日も綺麗です。キセルアザミとカマキリキセルアザミの茎に、逆さに止まってじっとしているカマキリずーっとこの状態です。シラタマホシクサの中にイワショウブ粉を振りかけたような、シラタマホシクサの群生イワショウブ開花後、数日たつと花の先端からは花先が赤く色づいています。ミヤマウメモドキ先週よりも実が赤く色づいています。この湿地にはミヤマウメモドキがとても多いのです。キセルアザミサワギキョウも花期が長い花ですね木道にシオカラトンボサワヒヨドリこの花は先週は蕾でしたとても綺麗な紫の花は目立ちます。湿地をいろいろな角度で写してみましょうこの木陰にテーブルと椅子があります。のんびりしていたら、誰も居なくなって貸切です。別の方向から広場を写して今日も貸切の湿地です。真ん中の木道です三本ある木道の一番右端の木道サワシロギク最盛期を過ぎた花は花弁の色が暗紅色に変わります。先週は真っ白でしたが、これも綺麗ですね。キセルアザミの群生貸切の湿地に別れを告げて、月山経由で帰りましょう。笹の背が低いので、ところどころ笹刈りしてくれています。月山山頂 794m三角点は有りませんが、御嶽神社の石碑があります。途中で左の樹間から、先週登った田代山が見えています。この辺りは笹の背丈が少し高いので、笹刈りはありがたいです、歩きやすくなっていますね(振り返って)石仏様まで下りてきました。お礼まいりして車までもどりました。今日は爽やかな風が吹いて、今までになく暑さも感じなくて秋を感じながら歩けました。私は暑がりで汗かきだから、里山なら夏よりも秋や冬の方が歩きやすいのです。暑かった夏もやっと秋の気配かな・・・
2025.09.23
コメント(0)
-

田代山と黒の田東湿地
15日(祝 月)まだまだ猛烈に暑い夏日が続いています。8月24日にもやって来た笹平の屏風山登山口の駐車場は三連休の最後の日だからきっと登山者は少ないだろうと思っていたら、駐車場に着いたら車がいっぱい。何とか停めることが出来ましたが、少し遅かったらもう停められなかったのです。8月24日は月山と小松洞山と黒の田東湿地のサギソウを見に来ましたが今日は田代山と黒の田東湿地に向かいます。田代山は山岡町にあるので、屏風山系の中には入らず以前2022年7月に登っていますが、それほど昔ではないのに全く記憶がありません。私には印象の薄い山のようです。チェーンを跨いで、林道を歩いていきます。両脇にはヤマジノホトトギスがあちこちに咲いてなかなか足が進めません。これはたくさん花がついています。かえる岩このさきから笹の道になります8月に来た時、石仏様が笹に埋もれていたので今度来たら笹刈りしようと、鋏と鎌を持ってきました。埋もれていた石仏様が姿を現してお詣りしやすくなりました。以前は笹刈りされていましたがこの頃は管理されていないのでしょうか。これで石仏様がわかりますね。観音様のようです。笹刈りでたっぷり汗をかいて、再出発です。ヤマジノホトトギスを探しながら歩きます。ほとんど樹林の中で展望が無いルートですが下界が見える所で一休み笹神山や大栂との分岐エコーの森はきれいに下枝が刈られて手入れがされています。月山から下りてくる道を右に見て黒の田東湿地に到着前回8月に来た時はシラタマホシクサも咲き始めていました。盛りは過ぎていますがまだまだ綺麗です。まるでコンペイトウです。一つだけマクロで写したくて苦労しました。木道の上に寝そべって、ピントがなかなか合わず・・・今は イワショウブ の時期です。お昼ごはんまで湿地でゆっくり花探ししてお昼ごはんを頂いた後は田代山へ向かいます。寿老の滝へ向かうルートの途中で田代山への分岐があります。寿老の滝は左へ、田代山へはまっすぐ進みます。ほぼ一本道ですが、ルートがグニャグニャ曲がってこの写真のブナの大木もグニャと曲がっています。私は記憶が無いのですが、相棒はこの木を覚えていました。真ん中が裂けているのに、生きて成長している「根性の木」ですね。「頑張りの木」とも名付けましょう(笑)突然広い林道のような道に合流して植林の中を下ります。田代山山頂かと思ったら、違っていましたこんなふうに騙されるピークが何度かあって・・・くねった木登山道の真ん中にくねった木が、なよっと立っています。やっと本当の田代山の山頂(819.8m)三等三角点も有ります。証拠写真を撮って、展望も無いのでお茶だけ飲んで戻ります。戻る途中で右の木の間から屏風山が見えています。寿老の滝との分岐まで戻ってきました。も一度湿地まで戻って、暖かい飲み物を作ってのんびりしましょう。シラタマホシクサキセルアザミイワショウブイワショウブの後ろにはシラタマホシクサが白く輝いています。粉を振りかけたようなシラタマホシクサの群生サワシロギクサワギキョウはなんとか最後の花です。でも紫の花は失敗無く写せます。シラタマホシクサの中のイワショウブアキアカネが木道のロープにとまっています。この木陰で前回と同じようにゆっくりのんびり私たちだけになってしまいました。貸切の静かな湿地を堪能して帰ります。石仏様におまいりして車まで戻ってきました。この夏、二度も黒の田東湿地にやってきましたが来る時期が変わると、咲く花も替わって楽しめるものですね。
2025.09.17
コメント(0)
-

岩巣山
31日(日)メチャクチャ暑かった8月も今日が最後の日です。しかしまだこのブログを書いている9月でも暑い日が続いています。各地の気象台始まって以来の暑さを更新し続けています。瀬戸の岩巣山へミヤマウズラを見るために行ってきましたがこの暑い時にわざわざ低山は暑いだけなので本当は登りたくありません。絶滅危惧種では無いけれど、なかなか珍しい花に惹かれて登りました。ミヤマウズラ(ラン科 シュシュラン属)どなたかのブログで、「この地域ではミヤマウズラは絶滅危惧種ではないからわざわざ あえて場所を特定して載せます」、と書いておられたけれど一昨年、昨年と順調に生育していたのが今年は群生の真ん中がごっそり盗掘されています。親切に場所を特定したからなのか、そんなことをしなくても悪い人はどこにでもいるから仕方がないのでしょうか。でも私はあえて場所を特定しません。本当に山の花好きな人が、探して見ればいいと思うのです。あまり興味の無い人や、エゴの人に知らしめることはないと思うのです。せっかく順調に生育していた株を、心無い不心得者が採っていったのでしょう。山野草はその花に適したその場所でしか咲かないから、自分の庭で自分だけのものとして咲かそうとしても咲いてくれないと思います。今年は2月に岩屋堂から登っています。今回は白岩の里の登山口から登ります。用意をしていると、すでに一台停まっていた車の登山者が下りてきてミヤマウズラの話になって、盗掘されていると聞いてガッカリしながら登ります。小堰堤何度も登っているので登山口で写真を撮るのを忘れて歩き出し小堰堤でスタートの写真を撮りました。次は大堰堤大堰堤の左の階段を登って高巻きします。樹林の中だからまだましですが名古屋は今日は40度越えるとか・・・木の下でも暑い暑い。登山道は東海自然歩道なのでところどころにベンチここでお茶を飲んで一休み最後の登りこの急登を登り切ったら目印の大きな木があってその木の横でランチを食べたことを思い出します。写真の右奥にその木が見えてきました。右の大きな木が私たちの目印の木です。この木から先は稜線歩きです。稜線までは川沿いを歩くので風が吹くところでは、「ああ~風が気持ちい」となるのに稜線歩きでは、日当たりの良いところではジリジリと焼けそうになります。岩巣山山頂への分岐いつもここで、岩巣山の山頂をながめて岩巣山山頂(481m)今回で14回目です。岐阜の山歩きの会の方達があまり広くない山頂の片隅でランチしています。山頂から少し南東側に開けた岩場元岩巣のピークが見えています。山頂にある温度計は34度爽やかな風の吹く山頂はこの温度です。下界ではやはり40度になっているでしょうね元岩巣への最後の登りここは鈴鹿と同じザレザレの白い砂山です。元岩巣のピーク三国山アンテナ群が特徴で、山頂まで車で行けるのですがもうだいぶん長い間行ってません。元岩巣のピークここに以前、去年の夏は峠の会が作られた山頂標識があったのに抜かれて有りません。他に小さな標識もあったけれど、すべて取られています。山頂にも峠の会が作られた山頂標識がありましたが、抜かれています。誰が抜いたり、外したりすりのでしょうか・・・標識ぐらいあってもいいのにと思います。ゴミを残したり、展望のためと言って木を切ったりするのはいけないけれど標識位は有っても良いのではないでしょうか。私はピークで記念の証拠写真を撮って帰る人なのでそう思います。小さな5mm位の花が15~20個茎について下から順番に咲いています。去年の私のブログの写真と比べて、群生の真ん中が30センチほどすっかりありません。倒れているのも有り、雨も最近降ってないのでかわいそう。頑張れ~と祈るしかありません。山の花はそこでしか生育できないのでそっとそこで咲いているのを見るだけ、写真を撮るだけにしておきたいものです。今回は色々と考えさせられる山行きでした。
2025.09.02
コメント(2)
-

黒の田東湿地のサギソウと月山・小松洞山
24日(日)夏風邪なのかコロナなのか、わからないけれどダウンしていましたがやっと回復して二週間ぶりにサギソウを見に行けました。この暑い時に炎天下を歩く気力も体力もないのでちょうどサギソウの時期でもあるし屏風山系は樹林の中を歩くので、炎天下を歩くよりは少しはましかな?笹平の駐車場にはすでに車が4台停まっていて、早くも下りてくる人がいます。暑いから早朝から登ったとおっしゃっていました。車の横にはアキノタムラソウがいっぱい咲いています。植林の中を歩いて最初の分岐で、屏風山や湿地は右へ行くところを今回は左の小松洞山の方へ立寄ります。私は初めてで、相棒はこの間一人で行った所です。植林の中を緩やかな踏み跡は続きます右の岩の先から急斜面になってそこを登り切ったらピークです。小松洞山山頂(593m)は特徴は無いけれど10mほど先に大きな丸い岩がどっかり埋まっています来た道を先ほどの分岐まで戻って、いつも通り行くとかえる岩尾根の左の笹の中に石仏が埋まっています。石仏様に、今度来るときは周りの笹を刈ってあげましょうとお約束して進みます。左へ行けば大栂、笹神山方面、まっすぐは通常の屏風山ルート、右の薄い踏み跡は、月山経由のルートです。今回は病み上がりなので主峰の屏風山山頂を目指さず、湿地が目的なので月山経由のルートを選びます。月山山頂(794m)屏風山と同じ標高です。途中はずっと同じような景色なので写真は無ありません御嶽神社の石碑月山を下りきったら湿地が近くですサワギキョウ思ったよりもたくさんのサワギキョウが咲いています。アカマツの広場の木陰で、ランチタイムお昼ごはんは少し遅くなったから、花の写真よりまず腹ごしらえです。サギソウ前回のサギソウは一つしか咲いてなくて遅かったけれど、今回は丁度花の盛りに来れました。いっぱい群生しています。湿地には入れないので遠くからだとこれくらいサワシロギクサワシロギクシラタマホシクサの中にサギソウシラサギが舞っているようです。木陰の無い木道は暑い、暑い右の湿地は粉を振りかけたような、シラタマホシクサの群生キセルアザミホザキノミミカキグサ2mm位だから私のコンデジではこれが限界です。15分くらい木道で寝そべってやっと写せた一枚です。炎天下でフラフラになりました。サギソウ飛んでいますね~~~ホザキノミミカキグサ黄色はミミカキグサホザキノミミカキグサより写すのが困難でしたミカヅキグサ(カヤツリグサ科)サワギキョウ湿地の縁の低木には木陰がありますが行けません。ほとんど貸切来る人がいますが、我らより長居をする人はいません。私たちは今日はここが目的地ですからランチの後は写真を撮って、ゆっくりのんびり過ごしました。普段イケイケどんどんの相棒も、「こんな風に過ごすのもいいね」と言ってくれました。帰りにヤマジノホトトギスをみつけたけれどピンボケ道の駅に立ち寄って帰宅しましたがこんな暑い時期でも、暑い低山に登る人がたくさん居ました。病み上がりのKIKIは湿地のサギソウが目的でしたがたくさんのサギソウが咲いててうれしい~~~今日は思った以上にたくさんの花が咲いていました。
2025.08.30
コメント(0)
-

大栗山のオオキツネノカミソリと夏焼城ヶ山
9日(土)天気の都合で珍しく土曜に山へ。豊田市(旧稲武町)の大栗山へオオキツネノカミソリの群生を見て夏焼城ヶ山へ2年ぶりに行ってきました。先週と先々週にはあまりの暑さで体調を崩しヘロヘロでやっと登った感があります。今回は元気に登ったのに、下山後夏風邪ひいて日曜から金曜までダウンしていてやっと今日ブログをアップすることが出来ました。旧稲武の大栗山のオオキツネノカミソリはこの辺りでは有名でいつもたくさんの人が見に来ています。県道80号から少し歩くだけで、大栗山に登らずに見ることが出来るから登山をしなくても見られるからでしょうね。私たちは林道の札場峠から大栗山を目指して花を楽しんで昼ご飯の後、夏焼城ヶ山に向かいます。アキノタムラソウ道路沿いの草むらに咲いていました。よく見たらあちこちに。フシグロセンノウフシグロセンノウは目立つ色なので車を走らせていてもわかります。フシグロセンノウの写真を撮るために車を停めて歩いていたら、アキノタムラソウを見つけたのです。この写真の左上にも写っています。取りつきは急斜面で、ジグザグに高度を上げたら稜線に出ます。大栗山と城ヶ山の標識はたくさんあり、稜線を外さなければほぼ一本道。岩場も無くフカフカの道で膝にやさしく歩きやすい。最近いつもヘロヘロのKIKIも今日は足取りが軽い。緩やかに登ったり下ったりしたら大栗山の山頂を越えて右の急斜面を下ると大キツネノカミソリの群生地です。しかしいつも思うのですがこの峠のような一番の鞍部に、大栗山の山頂標識があるのです。手前のピークか、この写真の向うのピークか、山頂がどちらかのピークなら理解できるのですが・・・こんなこと思うのは私だけ???急斜面を下ったら、獣除けのフェンスの扉を開けて入ります。しかし、びっくりあまり咲いてないよ~~~一昨年の今頃来た時は山が一面オレンジになっていました。でもよく見たら咲いている株の周りに、新芽がいっぱい出ています。このあたりが一番咲いています。今年は裏年かと心配しましたがフェンスで保護されている区画には新芽がいっぱい!!!蕾は色が濃いですねフェンスで保護されていない通路にもいっぱい咲き始めています。この谷は入れないようにフェンスでしっかり保護されています。お盆ぐらいが一番最盛期でしょうねケヤキは今はあまりありませんがオオキツネノカミソリは保護されて、こうしてみんなが見にやってきますね。どんどん下ってきて振り返ったらオオキツネノカミソリの群生地の入口の休憩舎もっと下ったらここが入り口私たちは逆コースを上から歩きました。オオダイコンソウカラマツソウまだ蕾です、咲いたら花が白くフワフワとしてとてもかわいい昼ご飯の後は、城ヶ山に向け再出発アカマツが多い稜線を歩きます。先ほどよりフカフカで膝にやさしいおととしはこのまま このピークを登ってしまいましたが左に巻き道があります。巻き道を来たらブナの木峠別のルートの合流点でもあります。いつか井の入登山口から来たいな~~緩やかに登ったり下ったりを5回ぐらい繰り返したらやっと「山頂まで500m」の標識が出てきました。これからはひたすら城ヶ山本体の山頂への登りになります。擬木の階段がひたすら続きます終わったと思ったらまたヤセ尾根を登ってまた擬木の階段夏焼城ヶ山の山頂右に昔からある小屋掛けで、以前冬に来た時に風が強くて寒くてお昼ごはんはこの小屋掛けで風を凌いで助かったことを思い出します。私が二階から手を振っています夏焼城ヶ山山頂889mの看板大川入山雲が多くて遠望がありません。今日は真正面に見えるはずの恵那山すら見えません。目の前の稲武カントリーは良く見えます。大船山と風の森の13基の風力発電の風車が見えます。ここからはちゃんと13基全部見えるのですね~~数えてみてね展望台の一階には正月登山の団体写真が貼ってあったり軍隊の航空監視哨があった時の写真などが貼られています。ここが夏焼城趾で、この近くの武節城の「詰めの城」であったことが書かれています。二等三角点が草の中に埋もれています。夕日が西に傾いています、誰も来ることも無く貸切の山頂を後にして誰にもすれ違わない登山道を戻ります。今日はほとんどすべて樹林の中の尾根歩きでした。だから炎天下で具合が悪くなった時みたいに、軽い熱中症のようなことにもならず最後まで元気に歩けました。チャンチャンと終わりそうなのですが、帰宅翌日から風邪のような具合で今日の朝までダウンしてました。寝冷えなのかな~~とも思うので皆さんもお気を付けください。
2025.08.14
コメント(4)
-

蛇峠山と高嶺
3日(日)連日茹だるような酷暑の中を、車を走らせて涼しいところを求めた結果長野県阿智村の蛇峠山と高嶺に登ってきました。しかし涼しいかと思ったのに途中で出会った登山者が、登山口では29度だったということでどおりで暑くて暑くて登り始めからフラフラでした。蛇峠山は初めて登ったのが2000年10月それからしばらくは登らず2回目は2019年、今回で5回目です。しかし今回はすごくたくさんの人と出会って年々登る人が増えている山です。馬の背にある電子基準点大船山と巨大風車今日は雲が多くて展望は期待できません。馬の背から蛇峠山の山頂にある鉄塔の先が見えています。木陰だから涼しいと思いきやメチャクチャ暑くてフラフラです。頭まで痛くなって、たぶん軽い熱中症です。しばらく休んでいましたが、あまり良くならずフラフラで歩きます。ウツボグサはきれいに写せました。のろし場の手前の電波施設に近いところは舗装道路を歩くのですが、その照り返しの暑いこと!!雲の間に見える青空の憎い青さ。レーダー雨量計施設御在所岳の山頂にもあるそうです。のろし場武田信玄ののろし場向うの鉄塔は山頂手前にある鉄塔です。以前はその横でランチしましたが、虫が多くて閉口しました。蛇峠山の山頂(1664m)二等三角点があります。展望台は登ってみても、周りの木が高くなって何にも見えないので今回はパス。のろし場の奥にはヘリポートと南アルプスの展望地がありますが今日は雲が多くて何にも見えません。下山途中で見つけた花は初めて見た花です。ミズチドリラン科 ツレサギソウ属私がヘロヘロで登山を楽しむことが出来なくて高嶺ならほぼ平行移動なのでのんびりならば歩けるだろうということで高嶺に移動します。以前は林道が崩壊で通れなかったのですが修復されて通れます。長者ヶ峰の駐車場に車を停めて、暖かい飲み物を作ってのんびりして展望を楽しもうと思いましたが、雲が湧いていて午前より天気が悪くなっています。駐車場には無線愛好家の車が3台停まっていてすごく大きな高いアンテナもいっぱい立てて、発動機を動かしてすこし山頂の雰囲気が壊れて残念です。最近はどこの山もハムをやっている人の車が増えている気がします。向うのアンテナのいっぱいある山が先ほどの蛇峠山です。大船山と風の森の風車高嶺に向かって林道を歩くと、大船山と風の森の風車が、蛇峠山から見たよりもっと近くに見えます。どんどん天気が悪くなっているような気がします。奥に高嶺が見えてきましたがもう空は低い雲が垂れこめています。目の前のピークが高嶺(1599m)最後の登りは笹の中の藪漕ぎで先ほど下山中、遠くに雷が鳴り雨がパラパラしていましたがその雨で濡れた笹でズボンがぐっしょりです。高嶺山頂(1599m)ゆっくりしたいところですが展望が無く仕方が無いので下山しましよう。少し西の方に歩いたら大川入山の方が少し雲が切れて見えました。しかしこの後車まで戻る途中、虫につきまとわれネットを被りさらに雨が降ってきて、車まであと少しのところでバケツをひっくり返したような土砂降りになって下着までびっしょり濡れて、今日に限って着替えを忘れたため車のエアコンが寒くて震えながら帰宅しました。今日は暑くて軽い熱中症のような状態になったかと思えば土砂降りに合って濡れて寒くて震えたりで大変な日でした。
2025.08.05
コメント(0)
-

浅間山・・・絶滅危惧種のサクライソウを求めて
サクライソウ27日(日)お天気が良いのはうれしいけれど、暑い日が続いています。日本で一番暑いところにもなった多治見市から登る、浅間山に登ってきました。登山口は多治見市ですが、山頂は可児市になる浅間山。ここには絶滅危惧種のサクライソウが咲くというので真夏の暑い時期の低山は、ただ暑いだけなのできついのですが頑張って登ってきました。登山口は小名田緑地、特養陶生苑の横にある小さな公園に車を停めて歩きます。特養ホームの横の舗装道路を歩きますが、舗装道路の照り返しでメチャクチャ暑くて、すぐに汗が噴き出ます。ここが日本一暑い町にもなった多治見だとここで改めて感心することしきり。道路の突き当りの配水池のゲートが出てきたら山に入ります。早くあの木陰に入りたいよ~~山腹を巻く細い道ですがしっかり踏まれています。木陰はギラギラ太陽から日差しをさえぎられるのですが風が無く暑い暑い林道に出るのですが、右の方へ歩いてしまって鉄塔のあるピークに来て山頂と反対側だと気が付いて戻ります。あまりの暑さに少し気分が悪くなって、林道の木陰でしばらく横になっていました。林道は突き当りになって、細い踏み跡を進みます。しっかり踏み跡があるので、たぶん山頂に行くのでしょう。もうすぐ山頂浅間山と書かれた古い標示と展望広場です。感じの良い浅間山山頂(372m)ほど良い広さの、岩場のある広場意外に貸切なのでテーブルを使わせてもらってランチです。南側が開けています。真正面の足元の住宅地は桜が丘の住宅地でしょう。一番奥の左のなだらかな山は岩巣山、猿投山はさらに奥の鉄塔がたくさんある山です。木陰でゆっくりお昼ご飯を頂いて展望を楽しみます。次は浅間神社へ向かいます。踏み跡は2ルートあって左のルートで行くことにします。赤い鳥居の広場に出ました。鳥居をくぐって進むと拝殿と本殿と広場が見えてきて後で知ったのですが7月にはこの神社の祭礼があったそうです。だから広場で何かを燃やした跡があったのですね。ここは海抜370m可児市で一番古い神社でコノハナサクヤ姫をお祀りしているそうです。富士浅間神社と同じですね。四隅をヒサカキで囲んでしめ縄が掛けられている石何でしょうね・・・サクライソウを探し回って山頂の展望地へ戻ります。もう一つのルートで山頂の展望地へ戻ります。今日は誰にも会わず貸し切りでした。同じ道を戻ります。浅間山(美濃富士)登るときは気が付かなかったのですが富士山のような三角錐の形ではなく、なだらかな山の形です。サクライソウは絶滅危惧種で、1903年岐阜県の恵那山で桜井半三郎氏により発見されました。植物学者の牧野富太郎氏が発見者の桜井氏の名前をとってサクライソウと名付けたそうです。1978年8月15日 この地の久々利のサクライソウ自生地が国指定天然記念物に指定され1996年1月25日 多治見市の高社山のサクライソウも市指定の天然記念物に指定されたのです。今年の正月の初登りで高社山に登った時に説明看板が有り、ぜひサクライソウを見てみたいと思ったのです。去年は真夏の暑い時に、岩巣山のミヤマウズラを見に行きましたが今年はサクライソウでした。初め探しても見つからず、あきらめかけましたがやっと二株見つけて、帰りかけたら普通に林道沿いに見つけてへェ~~こんなところに咲いているわ~~~さすが自生地です。サクライソウサクライソウ科 サクライソウ属多年草の葉緑素を持たない腐生植物背丈10センチくらいで、茎は1mmほど、花は2~3,4mmピントがなかなか合いません。10センチくらいで目立たないのでサンバイザーを後ろに置いてみました。右後ろにも1本咲いています。ほとんど白に近いクリーム色です。ほとんど絶滅に近い植物なので、もし興味があるなら不用意に林床を踏み荒らさないように気を付けて会いに行ってくださいね。
2025.07.29
コメント(4)
-

困った時の寧比曽岳
21日(月 祝)20日は選挙で山には行けず、21日に12回目の寧比曽岳に登りました。寧比曽岳は、以前平山明神山に登る途中でヒルの襲撃に遭い逃げ帰って、その代わりに登った山でもありコロナの時は県外に出てはいけないということで一年間の間に何回も登った山でもあります。私にとっては「行く山に困った時の山」です。私たちは遅かったので、駐車場に着いたら満車で停められません。少し広くなった路肩に停めようか迷っていたら早く下山してきたカップルの車が出たので停められました。登山口植林の中の階段を登ります。緩やかに登って行く広い登山道植林の中ですが、間引きもされているので、明るく歩きやすい亀の甲石のピークここから下ってまた登り返す、緩やかに登ったり下ったり・・・最初のベンチ東海自然歩道なのでところどころベンチがあり登山道も危険なところも、くしゃくしゃのところも無く整備されています。風が無く暑くて、汗が噴き出る中を登ります。この頃にはたくさんの人が下りてきました。ここからは急斜面の登りが続きます気温は23度名古屋市内に比べたら天国です少しだけ自然林で、その後ずっと植林の中です。急斜面の植林の終わりに近づきました。その向こうに自然林が見えています。ここからは気持ちの良い自然林の中をゆるやかに歩きます。ここが一番好きなところです。登山道の真ん中にあったシンボルのようなアカマツが倒れています。緩やかに登ったり下ったり水場の看板この看板が有ると、山頂は近いのです。山頂のあずまやが見えてきました。冬はこの辺りは霧氷でとても綺麗です。寧比曽岳山頂(1121m)に到着少し葉っぱが赤いドウダンの木の根元に三等三角点があります。目の前は筈ヶ岳その向こうの左は猿投山、右は岩巣山今日は展望は良くありません。山頂から南アルプス方面が見えるのですが今日はダメです。唯一、茶臼山が秀麗な姿を見せてくれました。ズームにすると、一番奥の三角錐の茶臼山と、右の風車のある井山と、その右奥になだらかな萩太郎山が見えています。展望が良い時は下の3枚の写真のように、富士山も南アルプスも見えるのです。(2025年5月11日撮影)ぼんやりですが、ズームで富士山南アルプス右から聖岳、兎岳、赤石岳、荒川三山塩見岳山頂でランチ後のんびり過ごして下山しましょう。後から下山した若者たちに、途中でどんどん追い越されて・・・登山口に下りてきました。車は我らの車と、山頂直下ですれ違った、登って来た人の車だけ残っています。寧比曾岳は私たちにとっては、行くところに困った時やあまり時期を選ばずに登れるので、ありがたい山です。今回は先週の八ケ岳のゴロゴロ岩と苔に疲れたので、今日は楽ちんに登れて、登山道も足にやさしい山が良いなということで困った時の寧比曽岳に登りました。
2025.07.26
コメント(0)
-

入笠山
13日(日)二日目は入笠山です。長野県富士見町から登る、三百名山の入笠山は簡単に登れる割に山頂からのすごい展望で、最近とても人気の山です。2000年9月に初めて登った時は、山頂では人が少なくあまり登っていないようでしたが、その後登るたびに人が増えています。マナスル山荘近くの登山口から登ります。左に花畑を見ながら登ります。帰りには花畑の中を通って下りましょう。分岐で岩場コースと迂回コースに分かれます。岩場コースで登りましょう。帰りには左からの迂回コースで下りてくるつもりが忘れてそのまま岩場コースで下りてきてしまいましたサルオガセがいっぱいついています。この木はまるでしだれ柳のごとくです。あと少しで山頂入笠山山頂(1955m)二等三角点があります。残念ながら、せっかくの展望の良い山頂からは雲が多く北アルプスや中央アルプスは山並みが見えません。東側の展望も八ヶ岳が見えるはずですが・・・残念赤岳・阿弥陀岳が少し見えています。南側は雲が多いがかろうじて、切れ間から甲斐駒ヶ岳が見えています。でもすぐに隠れてしまいました。山頂でのんびりしていたら、北アルプスの方の雲が少し切れて槍ヶ岳が見えてきました。続々と登ってくる人がいっぱいで山頂は人だらけです。山頂でのんびりして、途中のお花畑でお花探しをしながら下山して、お昼ご飯の後、入笠湿原で散策しながらお花探しです。ヤナギランイチヤクソウウツボグサハクサンフウロシモツケソウヨツバヒヨドリクガイソウお花畑はたくさんの人が散策していますが陰が無くて暑い暑い山の上でもこれほど暑いのですから、名古屋は今頃沸騰しているでしょうね。ヤマオダマキこの花は好きです。特にもっと高山のミヤマオダマキが好きです。アヤメニガナチダケサシキバナノカワラマツバ(蕾なのでキバナかシロバナかわからないけど、たぶんキバナでしょう)サワギク(ボロギク)ウバユリ花が咲く頃には葉(歯)が無いということから姥百合(うばゆり)と言われます。入笠湿原まで10分ほど舗装道路と沢沿いの木陰の道を歩いていきます。右後ろの斜面はゴンドラから下りてくる人でいっぱいでしたがこの写真にはちょうど写っていません。富士見パノラマスキー場のゴンドラに乗って入笠山にやってくる人はまずこの湿原からスタートなので湿原の入口は大賑わいです。標高1734m、面積18500ヘクタールのこの湿原は6月ごろに咲く可愛いスズランで有名です。たくさんの人がいるのに、広い湿原は写真には人が入っていません。アヤメが終わって、ノハナショウブがいっぱい咲いています。咲き残りのクリンソウダイコンソウモウセンゴケクサフジハクサンフウロアキノタムラソウ(アキギリ属)イチヤクソウ今回の山行きは八ヶ岳の天狗岳と、入笠山でした。久しぶりに高い山は、最近は6キロも太って体が重く年のせいで体力が無くなっているし、ヘロヘロで登りましたが翌日の入笠山はのんびりお花を楽しんで帰宅しました。もう少し体を絞らないと、と思いますが夏なのになんでも美味しくて・・・絞れません
2025.07.23
コメント(0)
-

天狗岳(八ヶ岳)
12日(土)八ケ岳の天狗岳(東天狗・西天狗)は今回で4回目初めて登ったのが2000年7月、2回目が2007年6月、3回目が2012年7月です。2回目に登った時はヤンババさんと一緒で、今まで登った中で一番天気と展望が良かったのです。八ケ岳を登るときはいつもヤンババさんを思い出します。登山口は唐沢鉱泉ここまでは車で入れますが、私が来た時はすでに駐車場は車がいっぱいで仕方がないから少し下がって、広くなった路肩に停めました。唐沢鉱泉は以前より白樺の木が大きくなって隠れていますね。イブキジャコウソウ歩き出しから花を見つけてうれしい~~沢を渡ると山に入っていくリンネソウ八ケ岳特有の針葉樹と苔そして岩の道岩の重なった道は歩きにくい木の橋は真ん中の踏み跡を歩かないと滑ります。いよいよ、岩・岩・岩の道木の根の道濡れた木の板の橋滑りやすいから緊張します鉄ネットの橋苔の付いた岩だらけ鉄ネットの橋ここは大きな苔の付いた岩がゴロゴロで歩きにくい鉄ネットの橋は助かりますが、あまりたくさん付いて無いので橋が無いところは岩・岩・岩を越えていくのが苦労です朽ちかけた丸太の木橋こわごわ渡りますしかし、この道の記憶がほとんどありません。黒百合ヒュッテの広場たくさんの人が休憩しています東天狗岳に向けてここからが正念場昔の記憶が無いので、東天狗の山頂はギザギザの岩の向こうかと思ったら全く違っていました。黒百合ヒュッテを振り返って高度を上げたらヒュッテがだんだん小さくなって先ほど下から見えたギザギザの岩についたら目の前に、水がない擂鉢池(以前は水がありました。)その向こうに本当は天狗岳のツーピークが見えるのですが・・・ガスで見えませんガスで天狗岳の山頂が見えませんこのあたりは擂鉢池や点在する小さな池やハイマツやコケモモ等の高山植物で作られた、まるで日本庭園の石庭ようで「天狗の奥庭」と言われています。空もガスで白い中を天狗山頂に向けて進みます。山頂はまだまだ先です歩きにくい岩岩の道を頑張って!!でもお腹がすいてヘロヘロです。ガスが少し薄くなって諏訪湖の方が見えました。標識の向うの岩場は東天狗の山頂か?いいえ違います、あの岩場を越えてまだ先です。途中でガスの切れ間に、天狗のツーピークが見えました。まだまだ先は長そう~~ウへ~歩いてきたルートを振り返ったらずーっと向こうに北八ヶ岳の蓼科山がガスの下に見えます。やっと東天狗の山頂の岩場が見えて来ましたガスが切れて山頂が顔出してくれました振り返ってあと少しです、頑張ろう~諏訪富士と言われる秀麗な形の蓼科山(2531m)が見えています。東天狗の山頂にいっぱいの人やっと山頂が見えてホッ!!東天狗岳の山頂(2640m)北八の蓼科山をバックに。反対側は西天狗岳をバックに証拠写真です。八ケ岳の主峰の赤岳の方はガスが掛かっています 残念。ここでやっとお昼ごはんですが、疲れすぎて食欲がありません。おにぎりを何とか一つ食べて西天狗へ向かいます。東天狗のガレを下りて、登り返します。西天狗岳は丸く女性的と言われます。西天狗の丸い山頂のズーム途中でなんとか、なだらかで大きな硫黄岳の向うに赤岳や阿弥陀岳の方がガスが薄くなって見えてきました。硫黄岳の爆裂火口が荒々しい。西天狗の山頂手前で東天狗岳を振り返って。東天狗岳は尖っていて男性的です。西天狗岳山頂(2646m)二等三角点日本二百名山です。西天狗の山頂では、東天狗でも一緒になった男性二人組としばらく話をして雲の切れ間から阿弥陀岳が見えています。ハイマツの間の西尾根を下ります。この先は結構急な斜面の下りで、メチャクチャ慎重に下りて相棒が左の展望が開けたと叫んでいる~~根石山荘と箕冠山(みかぶりやま)その後ろに大きな硫黄岳、その右に横岳のギザギザが少し見えて赤岳、中岳、阿弥陀岳が見えています。ヤッタ~本日の一番の写真ズームで横岳諏訪湖が奥にうっすら見えています。西天狗を下りきって振り返ったら西天狗岳の上空は雲が多いけど青空がみえています。でも、第二展望台についたら、また雲がのしかかっています。この天狗岳のルートは数少ない標識で唐沢鉱泉への標識。もう誰も登っても、下りても来ません。この先30分ほどで唐沢鉱泉登山口です。しかし岩岩岩、苔苔苔の道になり慎重に下りてきました。次は今回出会った花たちです。イチヤクソウトンボソウゴゼンタチバナコケモモハクサンシャクナゲミヤマダイコンソウイワツメクサオンタデヨツバシオガマムカゴトラノオコバノコゴメグサキバナノコマノツメ久しぶりに高い山に登ったから、たくさんの高山植物に出会いました。日頃出会えない花たちで出会えて、ああ~高い山に来たんだな~と感慨もひとしおでした。今回は天気が良かったものの、雲が多く展望が今一つでしたが2007年6月は登山歴の中で一番といえるほどのよい天気、展望でした。下↓をクリックして見てください。八ケ岳の天狗岳の見たものは
2025.07.19
コメント(2)
-

大船山の巨大杉と風の森の巨大風車
6日(日)恵那市上矢作町の大船山と風の森へ。初めて登ったのは1999年今回で5回目です。いつも大船山下山後は、風の森の巨大風車を見に立ち寄っています。大船神社までは、林道のこの道の先にこんな神社があるなんて想像もできないくらい細くて狭くグニャグニャの林道をグングン登って行きます。大船神社の鳥居から登ります。神社の森は、たくさんの巨木が残っています。階段を登って鳥居をくぐって参拝します。写真に見える拝殿の向こうに小さいけれどりっぱな本殿もありこの神社は創建時は大船寺だったそうで、神仏混淆であったため法印(山伏)と禰宜の両者がいたそうです。宿坊も30軒以上あり栄えていたそうですが明治になって神仏分離令が出されて神仏混淆が禁止されさらに明治5年には修験禁止令も出されて修験者である山伏たちは、僧侶か神官のいずれかの道を選択することになり神官に転向してこの神社で祀ることになったそうです。その後明治35年の失火で山門を失い拝殿は名古屋の宮大工 伊藤平左衛門により再建され令和4年(2022年)7月12日に岐阜県の重要文化財に指定されました。登る前に弁慶杉を見に行きましょう。源義経が弁慶を伴い奥州下向のおりにこの大船寺に立ち寄り弁慶が杉の小枝を土に刺したのが大きくなったという大杉です。大きさだけでなく木肌がほかの木と違って、白く輝いて神々しくものすごい存在感です。右側の枝は数年前の台風で折れたそうですが、左の枝はまだ元気です。大船神社のすぐ上には 大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)山の神様だからしっかりおまいりします。荒れた急斜面で、先週の丸山を思いだします。修験者たちがこの斜面を駆け上ったのでしょうか・・・しかし今の我ら登山者は、すぐに山腹を右に巻くように登っていきます。大きく行ったり来たりしながらジグザグに高度を上げて小笹が出てきたら斜度が緩やかになりほぼ山頂稜線だとわかります。面白い木があります。折れてもグッと上に向かって成長している木です。乗馬の木ですね~~(年を忘れています)あと少しで山頂大船山山頂(1159m)山頂らしくゆるく丸くカーブした広場です。大木の左奥(写真では中央)に御料局三角点があります。以前ここは小さな笹藪で、その中に埋もれていました。山頂標識が無くなっていますが、三等三角点と、切った木に大船山と標高1159mが書かれています。山頂を奥まで進んだら、木の間から展望が開けて風の森の風車が12基見えています。全部で13基あるそうですが山頂からは12基しか見えません。右端の「高嶺」1599m特徴ある高嶺の山頂高嶺の右端はなだらかな長者ヶ峰御料局三角点と、向こうに三等三角点クモキリソウ(ラン科クモキリソウ属)昨年は丁度花盛りの頃でした。しかし今回は花の盛りの終わったこれ一本だけ。あちこちに咲いていたのに、どうしてなくなってしまったのでしょう。ヒトツボクロや、クモキリソウなどラン科の花は出会えてもその次の年にまた会えないことが多くてこのまま年々消えてしまうのでしょうか。もう一度会いたいな~~下山後は風の森の監視舎の駐車場に車を停めて風車の横を登って行きます。風の森は以前は大船牧場で、そのまま牧場の後に巨大風車を設置しているのです。牧場の北側にあるアライダシ原生林アライダシ原生林へ入っていきます。去年は別の入口から入っていったけれど30分ほど歩いて行っても何も無いので戻って来たのです。今回の入口から入ったら何があるのか・・・湿地に人工的に切株を埋めて通路にしていますね去年より何かありそうだと期待して進みます。何度も沢を渡ります。しかしそれにしても、朽ちた丸木の橋は怖い踏み抜きそうで恐る恐る・・・いくつもある木橋は怖くて怖くて・・・林道のような広い道に出たよ~このまま進んでいくととても水のきれいな池手を洗ったらとても冷たい水でした。池の先は広場で、小屋とトイレがあります。案内看板ですが、全くわかりません。今日はここで戻りましょう。去年より収穫はありました。巨大風車は今日は廻っていません。そよ風の牧場跡を歩いて左端の山が大船山ギラギラ暑い一日でした。しかし山の森の中は涼しくて、木陰では昼寝が出来そうなくらい爽やかでした。まだ夏になったばかりなのにこの暑さは異常です。しかし、緑の木や草は目にも優しく木陰では生き返ります。一週間に一回でも山に入ってきれいな空気を吸って爽やかな風に吹かれて生き返れるから、31年間も続けてこれたのかな~~~いよいよ夏山です、どこに行こうかしら・・・
2025.07.10
コメント(0)
-

19年ぶりの丸山と天狗棚
天狗棚展望台のササユリ29日(日)愛知県津具村の丸山へ19年ぶりに登ってきました。十年ひと昔というから、ふた昔ぶりの山です。丸い形から名付けられたという丸山は2000年に初めて登り、2006年に2回目に登って以来ご無沙汰していました。以前の山頂はカヤトの広場でしたが、今回驚いたことにカヤトは消えて、雑木がぎっしり繁茂して展望は全くなく以前の面影が全くありませんでした。比較するためにリンクを貼り付けておきます。丸山2006年4月道の駅つぐ高原グリーンパークの横から林道丸山線に入って舗装が途絶える手前の広くなった路肩から登ります。一本の木に丸山登山口と書かれた木の札が掛かっています。以前はもっと手作り感のある可愛い標識がありましたが、無くなっています。字が薄くなっていてわかりにくいので持っていたマジックインキでなぞって濃くしました。植林の中をまっすぐ登って行きます。植林が終わって、自然林になったら急登が始まります。水平なところが無いくらい、すごい急登が続きます。両手を使って、木の根を掴むところもあり帰りの心配をしながら登っていきます。背の低い笹藪が出てきたら、少し斜度がゆるやかになって写真も写せます。しかし、展望も無くひたすら登るだけなので、登る途中の記憶が無いのが理解できます。オブジェのようなアカマツが出てきたらほとんど水平になり山頂が近い。私はすっかり記憶が無く、まるで初めての山のようです。そして森の入口のようなところが丸山山頂(1161m)私の唯一の記憶はここはカヤトの広場でしたが今は全くカヤトは有りません。茶臼山と萩太郎山も見えていましたが今は木がいっぱい成長して、どこからも木の間から見える景色は有りません。古町高山にあった山頂標識に字体が似ています。とても上手な字ですね。三等三角点(点名丸山2)(ということは点名丸山1があるのでしょうか・・・)山頂から少し進んでみたけど、森が広がっていて展望はありません。以前の背の低い木が19年の間に成長したのでしょう。所要時間も40分ほどで登れるのでお昼ごはんを持たずお茶だけ持って登ったので写真を撮ったらさっさと下山です。しかしこの下りは、斜度がきつくてメチャクチャ緊張しました。いったん滑って転んだら、途中で木にぶつかって止まらないかぎりかなり下までそのまま落ちてしまうだろうと思ったら、慎重に慎重に・・・登るのと同じくらい時間をかけて下りてきました。お昼ごはんは道の駅つぐ高原グリーンパークの片隅で頂いて次の山、天狗棚に向かうために面の木園地を目指します。面の木園地は、以前のコンクリート造りのトイレと休憩場が数年前に撤去され何もなくなって駐車場だけ残っています。登山口の大きなヤマボウシは丁度満開です。芝生広場の向うの井山の風車は今日は全く回っていません。今は無風なのですね。低い雲が空を覆って、傘とレインウェアとお茶だけを持って登ります。登山口の登山者数の記録のためのカウンターを押してスタート気持ちの良いブナ林を登って行きます。バイケイソウがちょうど咲き始めたばかり登山道は階段が整備されていますが朽ちかけて歩きにくいブナ林の新緑は爽やかで好きです。ここは標高が高く寒いので、今が新緑です、ベンチがある分岐ここで右側の山腹を巻くルートで、天狗棚展望台へ先に行きましょう。山腹を巻いて行く緩やかに登って行く(これは振り返って写したもの)天狗棚山頂からの道と合流帰りはこちらの方へ直進して天狗棚山頂へ向かいます。いつも思うのですが、新興宗教の石碑でしょうか・・・石碑のすぐ下の鉄階段を下りたら祠とササユリ以前よりササユリは増えていてうれしい展望台と言っても、尾根上の広場です。右の木の間から、遠く「三ツ瀬明神山」が見えています。真正面はこの間登った、「白鳥山」と集落を挟んで「大峠」真正面のヤマボウシの向こうは「萩太郎山」そして、先ほど登ったまん丸の「丸山」「丸山」の右の「茶臼山」(木の向こうで分かりにくい)真正面のヤマボウシの横には鉄階段この鉄階段は東側の登山口駐車場から登るルートで、急斜面に付けられて長いのでKIKIはあまり好きじゃなくて最近はここから登っていません。次は尾根道を天狗棚山頂へ向かいます。分岐を過ぎて、岩の露出帯を登って行きます。しばらく岩の露出帯を歩きます。ブナの原生林虫がまとわりつくのでネットを被っています。左は車を停めた面の木園地のルートへの合流点天狗棚山頂(1240m)ブナの原生林しか、他に何にもない山頂です。三角点はこの先の「1200高地」にあるのでここには標識しか無く、標識が無ければ通り過ぎてしまいそうです。今日はここで戻ります。下山は先ほどの合流点まで戻って下ります。登りに見たバイケイソウをもう一度写して、今日の花はバイケイソウです、名古屋は今日も暑かったようですがこの茶臼山近くの面の木園地や津具高原は標高が高くて爽やかでした。木陰を歩いていると下界の暑さを忘れてしまいます。しかし6月でこの暑さは先が思いやられます。だんだん地球が沸騰しているようで、そのうち生物が住めるような星ではなくなるのではないかと心配です。
2025.07.03
コメント(0)
-

笠置山・・・今年もやってきました見どころいっぱいの山へ
22日(日)このところ毎年のように登っている笠置山です。はじめて登った時(1996年7月)は、それほど魅力を感じなかったのに雨が多い6月で、あまり花の無い時期に行く山が無くて笠置山は花以外に楽しめる山なのでここ数年この時期に登っています。 望郷の森の駐車場に向かう林道沿いに、オカトラノオが目立ちます。途中の看板に目を惹かれ、車を停めて向かいましょう写真の右奥のカーブミラーの先が少し広いので、そこに停めて。散策道となっています。ピラミッド型の石に線刻と盃状穴があります。頂点から見て同心円状に二本の線刻がわかります。線刻の下に盃状穴もわかります。古代人が雨乞いなどの祈りのために彫ったペトログラフです。説明板林道の反対側にもピラミッド石があります。去年はササユリが一本咲いていました。今年は一本に二つ咲いています。まだまだ咲き始めたばかりできれいです。この辺りは標高が高いので、みたけの森より一ヶ月ほど遅いのですね。このピラミッド石にも同心円の線刻があります。大きさは、私と比べてみましょうこの時期はサンキラ(サルトリイバラ)の実が可愛い。望郷の森キャンプ場の管理棟今日は驚くほどテントが多くてほぼ9割ほど埋まっています。帰り支度をしているキャンパーとは反対に我らは登りしたくをして歩きます。こんな景色は見たことが無いほどテントだらけ。キャンプ場だから当たり前なのですが今までテントが張ってあるのを見たことが無いのです。向うに見行山が見えるのですが、今日はぼんやりかすんでいます。見行山天気予報は今夜から雨なので、ぼんやりとかすんでいます。炊事場の横の林道を登って行きます。コアジサイが満開山に入口にある大きな看板看板の真ん中が現在地ここから山の中に入ります。展望台を二つ見て山頂の笠置神社の奥宮へ行きます。トトロの森のような苔むした岩だらけの道ですが整備されています。私たちはこの道が好きです。しかしこの道で人と会ったことがありません。どういうわけか、こんなに見どころが多いルートなのにいつも貸切です。「くぐり岩」と「瞑想の小屋」が見えてきました。ザックが引っ掛かるほど細い岩と岩の間をくぐるように・・・ロープも付いているので助かります。これ以上太れば通れないかも・・・瞑想の小屋の向こうに、展望台も有ります。瞑想の小屋は広く、去年はここでお昼ご飯を頂きました。奥の展望台へ行って見たけどこんな景色です。ガスガスで空なのか山なのか、ほとんどわかりません。天気が良ければ、白山や御嶽山まで見えるのですが残念。ここで雨が降ってきました。今日はそこでランチはせず山頂へ向かいます。次に亀天水神の岩へ向かいます。どこが亀なのか?あそこか、あれかなど言いながら近づいたらよけいわからないね、この辺りで一枚写してみたら何だか右の方を見ている亀のようです。ツクバネソウ去年もここで咲いていました。雨で葉っぱが濡れています。樹齢150年の大山桜です。山頂直下の二階建て展望台ですが階段がだんだん腐って、とても登りにくいので今日は展望もないからやめです。山頂は笠置神社の奥宮(この写真は帰路に撮ったものです。)ここに到着した時は雨が降っていて昼ご飯をどこで食べようかとウロウロ探し回りましたが途中でブヨにまとわりつかれたままで到着したので雨とブヨとを避けたいのですが避ける所が無くて神社の裏の軒先でしばらく戸惑っていました。笠置山山頂(1128m)の笠置神社奥宮境内には二等三角点がありしばらくしたら雨がやんだので風が通る右側のベンチで、ネットを被ってランチタイム。神社の右向こうでランチしていた親子たちが前を通りかかったので子供さんたちに虫よけシールと、虫よけスプレーをかけてあげて「ヒカリゴケ」を探しに行ったけどわからなかったからヒカリゴケは見てないというので、相棒が案内をしてあげました。ヒカリゴケはすごい光っていたと大喜びで帰って行かれて我らもランチの後向かいます。ヒカリゴケの岩の向うには「百畳岩」とても巨大な岩が天を突きさすように立っています。たぶんこの先には「千畳岩」もあるようです。この山は巨岩がゴロゴロいっぱいある山です。梯子の横にヒカリゴケと看板が有るので、ここまでくればわかりますがこの途中に、ヒカリゴケの説明看板が有るのですがそのところにも小さな梯子があるので紛らわしいのです。そこで探し回ってわからなくて、もどる人が多いそうです、私たちも初めての時はそうでした。この二列の梯子を登って向こうの大岩の間までいくと岩と岩の隙間に光っています。ここはとても湿気が多くて、岩がびっしり濡れています。いつもジメジメしていて、苔にはとても住みやすい環境です。去年より範囲が少し広くなっているような気がします。このところ雨が続いたからでしょうか。天然記念物なので大切にしたいですね。そっと写真だけ撮って帰りましょう。帰りは笠置神社の参道を下ります。私の好きな道です。いつもここにはタツナミソウが群生しています。「物見岩」と「あずまや」まで下りてきて物見岩のはしごを登ってみたけどやっぱりなんにも見えません。恵那山とそのふもとに恵那市の街が見えるのですが。周回の林道をブラブラ車まで戻る途中モミジイチゴ甘くておいしい大き目の5個ほど食べてクマさんのおやつを少し横取りしました。またブラブラ・・・エゴノキの花がいっぱい道に落ちてます。見上げたらエゴノキの花がぶら下がってます。誰も居なくなったキャンプ場みんな帰ってしまって、私たちの車だけ残っています。登り始めてしばらくしたら雨が降ってきて、その後意外に天気が良くなって太陽まで出てきたけどまた曇ってきました。こんな梅雨の時期は展望を期待する山はだめで、花もササユリなどの咲き残りを期待するしかないし低山では地味な木の花くらいしかありません。高い山で雨が降った中を縦走するのも修行みたいだし軟弱者のKIKIにとっては展望以外に楽しめるこのくらいの山がちょうどいいのかもしれません。しかし今回はブヨに集中攻撃に遭って、帰っても痒くて大変でした。これからは虫対策必携ですね~~
2025.06.27
コメント(0)
-

みたけの森のササユリと鬼岩公園の鬼の一刀岩
13日(金)今度の土日は用事が重なったので、前倒しで金曜に出かけることにしました。まず、みたけの森でササユリを見てお昼ご飯を頂いて鬼岩公園へ移動して、蓮華岩の鬼の一刀岩まで登って松野湖畔を散策しました。5月にもキンランを探しにここに来ました。向うに見えるのは南山溜池アジサイの青がとても綺麗。6月生まれなのでアジサイが好きです。オカトラノオ(サクラソウ科トラノオ属)ササユリすでに終わっているかと、ほぼあきらめの気持ちでしたがまだ綺麗に咲いているのが残っていました。キンラン四兄弟の花の後です。秋葉溜池の岩の上で鴨が二羽、やすんでいます。ササユリの群生地色の濃いのも有ります。まだ残っていて良かった。電気線で保護されています。ウツボグサムラサキ色はあまり失敗が無くきれいに写せます。先ほどの鴨が気持ちよさそうに泳いでいます。今日はメチャクチャ暑くて、森の中でも暑いから鴨ちゃんたちがうらやましい。南山溜池から前回登った朝日の塔が見えています。(望遠で写しました)次は高原湿原と夕日の塔へ行きます。ポツンと一輪咲いているササユリの後ろの赤い木が気になります。 近づいたら背の高い赤い木が数本あります。モミジでした。この時期でもとても紅葉(といえるかどうかわかりません)がきれいです。シャラノキ(ナツツバキ)8センチくらいの大きな毛虫がいっぱい木にも道にもウヨウヨこの木の葉っぱは食べつくされて丸裸で枝だけになっています。スズカケの径からせせらぎの径へ高原湿原今回で二回目です、初めて来たときはカキランが咲いていましたが今回はあまりめぼしい花は有りません。ハッチョウトンボ小さくて動きが早いのでなかなかきれいに写せません。きれいな赤いのはオスです。メスは薄茶色で地味です。トウカイコモウセンゴケピンボケですネジキモチツツジ夕日の塔ケヤキの大木の木陰でお昼ご飯を頂いてこの後は鬼岩公園へ移動します。国道21号線沿いのドライブインの広い駐車場に車を停めて陸橋を渡って鬼岩温泉の方へ向かいます。ドライブインのお店は来るたびに、一軒ずつ廃業されて駐車場だけが広くて寂しい感じがします。ユキノシタがとても綺麗ありふれて珍しくも無いけど、群生はとても綺麗です。鬼岩公園の入口鬼岩温泉には二軒の旅館が残って営業しています。昔はもっとたくさんの旅館があったようです。谷を登るルートは三つあります。一番左は蓮華岩コース真ん中は岩屋コース右は白岩・展望台コース岩屋コースは渓谷沿いの岩の間を登って行き関の太郎という鬼が住んでいたという岩屋があるのでこの鬼岩公園の一番のメインコースですが通行止めの部分があるようなので今回はやめて蓮華岩コースで登り、松野湖の散策の後も蓮華岩コースで下ります。双ツ岩休憩所ふたつ岩一つの岩に見えますが、真ん中に割れ目があり二つの岩です。谷の向こうに臼岩が見えます。臼のように大きな岩が重なっています。蓮華岩休憩所鬼岩公園で一番高いのは蓮華岩です。休憩所の左の岩に登るまえに鬼の一刀岩の案内看板の通り行って見ましょう。初めは左の割れ目が一刀岩の割れ目だと思っていました。ところが看板をよく見たら右側の割れ目です。私がストックで指し示している割れ目です。本当にスパッと切ったようです。鬼滅の刃のアニメの人気にあやかっています。このアニメのおかげで観光客が戻って来たようですがしかし今日は平日なので貸切です。蓮華岩の一番上に登ってみて、松野湖の方を眺めてみたけど御嶽山や恵那山は見えません、かろうじてうっすら笠置山だけわかりました。蓮華岩の上に登って端まで行くと鬼の一刀岩を上から見ることが出来ます。見事に切れていますね。2021年6月に臼岩・展望台コースから蓮華岩を写した時の写真。これで蓮華岩が一つの岩でなく、蓮華の花のようにいくつかの岩が一番大きな岩を囲むように並んでいるのがわかります。松野湖畔は車で通れます。ちょうど一台の黒い車が堰堤を通っていました。今日は展望が悪く、笠置山がうっすらみえるだけで恵那山も御嶽も見えません。今からあそこまで行って見ましょう。蓮華岩から松野湖まで森の中を歩きます。レンゲが少し咲いていました。蓮華岩の近くにレンゲの花・・・堰堤までやってきて、今日は水がとても多く満水です。堰堤から振り返って蓮華岩の方を見たら岩と御嶽山の標識が見えます。湖畔でのんびりした後、蓮華岩コースを下って帰りました。
2025.06.21
コメント(0)
-

白鳥山
7日(土)設楽町の津具から登る白鳥山へ。今回で8回目。最近はこの時期に咲くコアブラツツジや、チチブドウダンの花が見たくて登っています。広場には車が1台停まっていて先客があるようです。登山口は白鳥神社60段ほどの急斜面の石段を登ります。途中でシソバタツナミソウの蕾白鳥神社は正月2日に行われる花まつりで有名な神社です。社殿の正面の階段の一段が、腐っていたのが修理されていました。参拝して登山開始大ヒノキのおかげでKIKIが細く見ます。社殿の前の一本の大ヒノキの説明板この看板の内容よりもっとヒノキは大きいと感じます。看板が作られた時より成長してるのかしらね。トイレの左横から登ります。すぐに分岐があり我らは今回も、右の急斜面から反時計回りで登ります。まっすぐの道は帰路で下りてくる道です。こちらの左上の方から登ります。登り始めたら巨木がたぶんシデの仲間でしょうね沢を横切って、急斜面をジグザグに高度を上げて行くこの表示が無ければまっすぐ進んでしまいそう急斜面の植林の中を頑張って登ると汗が噴き出て来ました。この辺りで踏み跡が薄くなって、去年は少し迷ったところです。今年は赤テープがあってそれを頼りに進んだらすごい良い道に出たよでもそれもつかの間で、荒れた道をよじ登って赤テープのある踏み跡がしっかりついている道に出たら標識が倒れてたので、起こして持っていた針金で修理して進みます。大きな岩の上に出たら大峠が目の前に見えます。その大岩の下は「仏岩」でした。いつも思うのですが、何が仏岩なのか???この岩でしょうか???ここで相棒がぎゃ~ッ相棒が手を置いた岩の横にヘビが、それもマムシがとぐろを巻いていたそうで大騒ぎです。岩の隙間にマムシが移動してくれたから良かったけれど恐る恐る岩の下をのぞいたら、模様がマムシ柄でした。噛まれなくてよかった~~~ほとんど毎週山に登っていますがあまりお目にかかりたくないものです。私たちの大騒ぎで、一組の登山者が、何事かとやってきましたが岩の隙間のマムシちゃんを見て下りて行きました。結局、今日山の中で出会った登山者はこのカップルだけでした。小広いところに出たらヌタバ池と標識がある池いつも水があるので、水が湧いているのかな?池に枝が被る木には、モリアオガエルの卵がぶら下がっています。富士見岩の方へ行って、そこでランチです。富士見岩の手前はコアブラツツジの落花がいっぱいこの辺りはコアブラツツジの木がたくさんあります。富士見岩名前からして、富士山が見えるのでしょうか・・・ぼんやりとして遠望がありません。南アルプス方面が開けている所です。コアブラツツジ地味ですが可愛い花です。今がちょうど花盛りです。コアブラツツジつぼ型でとてもかわいい隣にチチブドウダンの木が一本だけありましたが花は終わっていました。遠くの枝に少しだけ咲き残りがあったので望遠で写したけれど・・・いつも通りゆっくり一時間ほどのランチタイムでしたが誰も来ません、今回も貸し切りでした。次は「帝岩」から正面の大峠を眺めて大峠の右奥に、三ツ瀬明神山がかろうじて見えています。白鳥山山頂(968m)山頂は大岩の上です。今まであった立派な山頂表示は朽ちて落ちています。木の間から萩太郎山と、その左向こうに茶臼山が見えています。しかし今日は霞が掛かったようではっきりと写せません。下山は周回する形で、屏風岩の方へ下ります。山頂からグングン下って、屏風岩へやってきました。しかしいつも思うのですが、登山道からは屏風岩というほどの直立した大きな岩に見えないのです。谷の下から見たら屏風のように屹立しているのでしょうね。その先は夫婦岩一対の巨岩が門のように並んでいます。さらに水晶採掘場岩が穴だらけです。今は採掘してはいけません。無断で採掘すると犯罪になります。アカマツの尾根をどんどん下っていきます。この辺りは爽やかな風が吹いて気持ちよく下って行けます。松の木の足元に表示。この表示が無ければ直進してしまいます。左へ下りて沢を横切ります。この辺りは風が無く蒸し暑い。沢を横切って山腹を巻いて神社に下りてきました。帰路で古町高山へ立寄っていきましょう。1996年12月に初めて登って以来ご無沙汰の山です。広域道路の横に登山口の表示朝、この表示を見たので帰りに立ち寄ることに。伐採地の鉄塔巡視路登って右の植林の方へ行きます登山道入り口の看板植林の中をジグザグに登って行くもうすぐ山頂古町高山山頂(1055m)植林の中で展望が無い山頂だから一度登って以来、来なかったのね~~とてもうまい字で、素敵な看板です。追加の一座なので、山頂の証拠写真を撮ったらさっさと下山しましょう。今日はチチブドウダンと、コアブラツツジの花を期待して来ましたけれどチチブドウダンは終わっていました。花はドンピシャの時に来るのは、なかなかむづかしいです。しかし29年ぶりに古町高山に立ち寄って久しぶりに一日2座を登りました。最近は楽ちん登山ばかりやっているので、久しぶりに頑張った日でした。
2025.06.12
コメント(2)
-

屏風山・・・登山口もいっぱい人もいっぱい
6月1日(日)瑞浪の屛風山へ行ってきました。この山は今から25年前に初めて登った山です。登山口もたくさんあって、最近は笹平から登っています。2022年に登った時に初めて見つけたヒトツボクロを見たくて最近は毎年登っていますが、初めて見た時以来見ることが出来ません。葉っぱすら見当たらず、絶滅してしまったのでしょうか。下のリンクを張り付けたブログはヒトツボクロを初めて見つけた時のブログです。クリックしてみてください。思い出の屏風山2022年6月のブログ2000年10月 初めて屏風山に登った時の写真山頂の看板が変わっています。登山口から山頂までついてきた子猫と。下山後、相棒の実家の猫になり、天寿を全うした猫ちゃんです。笹平登山口二年ほど山仕事用にこの駐車場が使われて、この駐車場が使えなかったけれど山仕事の工事も終わったようです。すでにたくさんの車が停まっていましたが何とか停められて出発シソバタツナミソウ歩き出したらすぐにたくさん咲いています。幸先が良いな~と思ったけれど目的の花には出会えませんでした。山仕事用の林道から離れて山道を登って行くシライトソウがたくさん咲いています。この間の米田白山ではこの花を目的に登ったのに咲いていませんでした。今年は花が遅いのでしょうか。シライトソウシュロソウ科 シライトソウ属かえる岩石仏だんだん笹の中に埋もれていきますね。分かっているから探しながら登りましたが初めての人はわからないで過ぎてしまうでしょう。左へ行けば「大栂」今日は大栂の方には立ち寄りません。登り切ったら手入れの行き届いた植林「エコーの森」という看板が有ります。植林の中にもシライトソウが咲いています。分岐で黒の田山へ向かうために左の沢に下り沢を横切って登って行く途中で振り返って写しました。ここからひたすら登ります。結構な登りが続き、暑くて汗が噴き出てきます。植林の黒の田山(754m)黒馬の分岐大草からの登山道との合流点合流点のすぐ横は馬ノ瀬山(767m)シソバノタツナミソウの群生今日はピンボケばかりです。展望台と書かれているけれど展望地です。土岐市や瑞浪市が見えています。遠く名古屋の駅前ビル群も蜃気楼のように見えています。ギンリョウソウ珍しくはないけれど、これはきれいなので写しました。八百山(800m)屏風山山系の中で一番高い屏風山山頂(794m)りっぱな一等三角点があります。向う側からは恵那山が望めますが、今日は雲がかかっていてはっきりしません。風が通る山頂でランチタイム着いたときはたくさんの人が休憩していましたが食事中に全員下山してしまいました。山頂を下る途中に二組が登ってきて今日は屏風山は大賑わいです。次の黒の田湿地に向かう途中で登って来た単独の男性も、「どこの登山口の駐車場もいっぱいでやっと停められた、この山でこんなに混んだのは初めてだ」とおっしゃっていました。ウソみたいに誰も居ない貸し切りの黒の田湿地今の時期は、めぼしい花が無くて・・・これ な~んだハルリンドウの花の後です。面白い状態です。ノギランモウセンゴケ咲き残りの小さなハルリンドウ遠くて小さいのでなかなかピントが合わず木道の上で、寝転んでやっと一枚だけピントが合いました。湿地のテーブルでお茶タイムしてゆっくり抹茶オーレを頂いて時期的に花は少なかったけれど、貸し切りの湿地を堪能しました。沢沿いの道を通って登山口まで戻ります。今日はヒトツボクロを見たくてやって来たけれど去年から無くなって、今年は葉っぱすら出ていなくて絶滅したのか心配です。張り付けた以前のブログの写真が、貴重なヒトツボクロの写真になったのかな・・・
2025.06.06
コメント(0)
-

小幡緑地
25日(日)毎週毎週土日の天気が悪く、山に行けてませんでした。今回も土曜日はしっかり雨が降ったので日曜日は朝に雨が上がったばかりではヒルの猛攻撃に遭うのが嫌で、近場でお茶を濁すことにしました。名古屋市内の守山区にある小幡緑地は、近いのに行ったことが無くその隣の尾張旭の森林植物園の有料の植物園はよく出かけていました。雨が上がって昼食の後、のんびりと出かけることにしました。小幡緑地は本園と中央園、西園、東園とバラバラに広がっています。管理棟や野球場、テニスコートなど球技施設は西園にあり本園は大きな緑ケ池や竜巻池の周りに、芝生広場や児童園、森の中の散策道などがあり中央園は水生園、野鳥園があります。東園はゲートボール場や、芝生広場があります。初めてなのでひとまず本園へ行って見ましょう。駐車場の横の看板で歩くコースを確認します。まず、北側のウォーキングコースを歩いて、忠霊塔をめざし、その後緑ヶ池の周りを歩いて中央園の水生園へ向かいましょう。雨が上がってたくさんの人出です。右の駐車場から、向うの芝生広場を見たらたくさんの子供たちが遊んでいます。一本、薄紫の花がいっぱい開花している木があります。何だろう・・・と近づいたらセンダンでした。「センダンは双葉より芳し」と言われるほど有名だけど私は初めて見ました。木の道や土の道を歩いて高いところを目指したら一番高いと思われるところに、ひっそりと忠霊塔があります。たぶんあまり人は訪れることは無いのでしょうね。緑ヶ池いくつかある中で、一番大きな池です。本日の目的である、マメナシの木花はとっくに終わっていましたが、梨にそっくりな1㎝位の実がついています。説滅危惧種だと看板に書いています。花の時期にまた来てみましょう。池の縁をぐるりと歩いていると水辺のあずまや向う側から歩いてきました。たくさんの人が魚釣りをしています。3センチ以上のすごい棘のある木が実をつけています。なんだろう????この後水生園へ向かいましたが、歩けるところはフェンスに囲まれ巨木でうっそうとした場所で何にも見えず、ほとんどが保護区で入れないのでそのまま、八竜緑地という看板につられて、そこに向かいます。道端に ヒナギキョウ意外に車が通る舗装道路を必死で登って登り切ったら、なんと高級住宅地が広がっています。個性的な豪邸を眺めながら八竜緑地に到着。個人の所有地を市に寄贈されたという八竜緑地です。新池と雨池の二つの池があるということですが私たちは新池だけ周回して帰りました。テイカカズラ藤原定家(ふじわらのていか)と式子内親王の愛に関する伝説が名前の謂れです。藤原定家が亡くなった式子内親王を忘れられず葛に化して彼女の墓に絡みついたという話です。ネジキ並んだ白い釣り鐘のような花が可愛いクロミノニシゴリ東海地方の湿地で見られる希少植物です。池にかかった九曲橋のような橋池の向うに、水の中に何か立っています。池の周りをまわって確かめに行って見ましょう。石仏のような・・・お地蔵様でした。なんでわざわざ水の中に?池の縁の湿地にトウカイコモウセンゴケ本園の竜巻池にもどってきて駐車場に帰ってきました。4時間以上歩き回って、初めての小幡緑地散策でした。つぎは山に登れるのかな・・・
2025.05.28
コメント(0)
-

東山動物園・・・コモドドラゴン(コモドオオトカゲ)
16日(金)名古屋市の東山動物園にはインドネシアの固有種である、コモドドラゴン(コモドオオトカゲ)という絶滅危惧種のとても大きいトカゲの「タロウ」がいます。インドネシアのコモド島に生息してる世界最大のトカゲです。タロウのお母さんが、上野動物園からシンガポール動物園に貸し出されているうちにタロウが生まれ、上野動物園にタロウが返される予定でしたが飼育場所が無いということで、東山動物にやって来たということです。ということで現在日本で飼育されているのは東山動物園だけです。2024年8月に日本へ来た当初はすごい人で見るためには長時間並ばないといけないのでこの日を待っていました。連休や土日は混むので平日に、自宅から歩いて東山動物園へ。タロウ君は、おメメがクリクリで可愛い爬虫類は大嫌いですが、顔の輪郭はワニっぽくて目は丸くてワニより可愛いしかし牙には毒があるそうで、飼育員さんは気をつけないと大変ですね。決めポーズこの後、イケメンゴリラのシャバーニを見て東山動物園はイケメンだらけですね~~
2025.05.19
コメント(2)
-

花の追っかけ~~2025年 第6弾 ベニドウダン
寧比曾岳の山頂のベニドウダン11日(日)今回の花の追っかけ~は寧比曽岳のベニドウダンとレンゲツツジでしたがあいにくレンゲツツジはまだ蕾でした。去年も同じ頃に登ったのに今年は花が遅いようです。寧比曾岳は今回で11回目初めて登った時は1995年12月で雪が降っていました。翌年1996年に登ってからは、18年ほど登って無くて2014年に久しぶりに登ったのです。それ以来また6年ほど遠ざかり、2020年はコロナで県外に行けないので一年間で3回登って、それ以来毎年登っています。私たちはいつもスタートが遅く大多賀峠の駐車場には車がいっぱいでした。しかし、下りてくる人もたくさんいるので車は停められて、ゆっくりのんびり用意をして歩き出します。この辺りは寒いのでしょうまだ山際のチゴユリが満開です。登山口には自転車の若者がいっぱい休憩していたので、写真はスルーして登山口の階段を登ってここでスタートの写真このルートの寧比曽岳は、ずっと樹林の中を歩くので山頂までは展望がありません。しかし東海自然歩道なので、登山道は整備されところどころ標識もベンチも有り、歩きやすい道です。本当に亀の甲のような割れ目です。ほとんど植林の中を歩きますが足元は歩きやすく膝にやさしいルートです。今日は風が無いのでここでお茶を飲んで一休みいよいよ木の根の道唯一歩きにくいところです。崩れた丸太の登山道この斜面を頑張って登ればいい感じの道になるので、最後の頑張りどころ植林と自然林の間の道いい感じの道になりました緩やかに登って行く、好きな道11度です。寒がりの相棒は、寒い寒いと言いながら登っていました。我らを追い越して言った若者二人が、早々と下りてきて「山頂では8度でした」と言っていたので去年の同じ頃を思い出しました。去年は天気も雨で、山頂で寒くて震えながらご飯を食べたのです。斜度もゆるやかになり山頂まであと少しここは自然林の中を歩くので明るいし登山道も歩きやすい冬は樹氷や霧氷の素敵な道になります。スタートが早い人はどんどん下りてきます。左に水場帰りに立ち寄ってみましょう。寧比曾岳山頂(1121m)今日は青空で暖かい、しかし夕方から天気は下り坂です。KIKIの後ろにはベニドウダンが3~4本あります。開いていますが、まだ花が小さく南向きの一番大きく開いているのを選びました。三等三角点山頂に着いてすぐに、富士山が見えました。うっすらですが、初めてです。南アルプスの南側(右から聖岳、兎岳、赤石岳、荒川三山)結構はっきり見えています。南アルプスの北側(右から塩見岳、白い雪の三角の山は間ノ岳、一番左は北岳)小屋でお昼ご飯を頂いているうちにもう空は青空が無くなっています。恵那山恵那山の右に中央アルプス目の前の風車のある山は大船山中央アルプスのズーム南側方向目の前は筈ヶ岳(985m)初めの頃は、2回筈ヶ岳まで足を延ばしていますが最近は行っていません。奥の方は豊田の街から名古屋の街まで見えていますが写真でははっきり写っていません。レンゲツツジはまだ蕾固し南アルプス三角錐の聖岳(真ん中)の手前に、聖岳の形にそっくりな三角錐の山は愛知県で一番高い 茶臼山その右手前は、風車のある井山井山の右肩奥から、なだらかな萩太郎山が見えています。もう一度、塩見岳(右)から北岳までの山並みを見て目の前は段戸山、その向こうの山の間に富士山がうっすら見えています。結局、他の人が下山した後まで展望を楽しみ、我らはゆっくり下山します。途中の水場まで立寄りましょう。植林の中の急斜面を30m下りていくと沢の源頭(写真の真ん中)に水場があります。塩ビ管からポタポタ水が落ちてきますが別のところからにじみ出る水が、3mで流れになっています。水を汲むのは結構大変かもね。大きなブナの木面白い形の赤松の巨木がいっぱい朝は登山口で写せなかったのでゴールで写しました。愛知県は平野が多く高い山は少ないのですがこの寧比曾岳は若者に人気の山でしょうね。登山道が整備され、走って登れるのでトレイルランで登ってくる人が多いようです。何度も登っているのに、今日は初めてぼんやりですが富士山が見えました。富士山を見るとテンションが上がりますね。さすがに日本一の山です。
2025.05.13
コメント(0)
-

花の追っかけ~~2025年 第5弾 キンラン
キンラン5日(日)花の追っかけ~~第5弾はキンランです。去年も同じ日にキンランを探しに行っていました。岐阜県御嵩町のみたけの森今回で12回目です。初めの頃はササユリを見に行っていましたが3年前からキンラン探しに出かけています。園内の入口に「みたけの森」と彫られた大石園内の木はもうしっかり緑です。下の池は、南山溜池行けの縁の道を歩いて緩やかに登って行くとササユリの自生地に。今はまだササユリの蕾すら出ていませんがよく探すと、半日陰にキンランが輝いています。去年も咲いていた所です。1㎝位の花ですが、開いているのをみたら確かにランです。この辺りには5株ほど咲いています。ゆっくり撮影タイム再び歩き出したらいつものところに、次はホタルカズラ(ムラサキ科 ムラサキ属)特別珍しい花ではないが、KIKIは初めてここで見た花です。足元には蕾のキンランササユリの自生地の斜面です。今は笹がいっぱい笹の中にキンランを探しますが、ありません。新緑がまぶしいです。次の池は、秋葉溜池いつものところにキンラン四兄弟ヤマツツジ芝生広場左の方へ緩やかな勾配の広場です。このヤマツツジは色が濃くて綺麗です。どんどん登って汗かいて、一番高いところの稜線を歩いてツクバネウツギの向こうに「朝日の塔」園内の反対側の西端には「夕日の塔」があります。塔の上から北を眺めたら、納古山(右はし)が。納古山の左奥にうっすら白山東には恵那山が見えています。しかし今日は天気がいい割に、もやってぼんやりです。秋葉溜池の向こうに御嵩町の町キンラン四兄弟をもう一度眺めてホタルカズラボケ駐車場の近くまで戻ってきてこの素敵な芝生を眺めながら、木陰でランチしましょう。朝よりたくさんの人がやってきていますが広い園内ではあまりわかりません。でもササユリの時期にはすごい人がやってきます。次に向かった米田白山の駐車場にサギゴケがいっぱい。今日の二つ目に向かったのは米田白山(273m)です。東回りで山頂に向かいます。二ノ坂の途中で、一番右はしの納古山と飛騨川が見えています。納古山の左に御嶽山の山頂部が見えています。特徴的な納古山の山頂、今日もたくさん登っているでしょうね。この写真では御嶽山が写っていません。新緑の中、KIKIは何を見てるのかな・・・山頂稜線を歩いて馬の背岩から納古山と、その手前に米田富士(愛宕山)がきれいな円錐形です。モチツツジの向うが馬の背岩馬の背岩はその名の通り、長い巨岩がヤセ尾根に露出しています。向う側は絶壁です。これで馬の背だとわかります向うのマツの木に隠れているのは恵那山次はタイタニック岩誰が名付けたのか・・・怖くて端っこに立てないので座っています。(そこに行くのに苦労しました。笑)向うに恵那山が見えています。風が強くてサンバイザーが飛ばされそう「早く写して~~もう怖いよ~~」自分でそこまで行っておきながら、怖いと叫んでしまいました。タイタニック岩のこちらの岩は立っていられます。足元が絶壁では無いので。この稜線はモチツツジが満開最後は「白山槍」一番上に槍のように尖がった岩がありますがさすがにそこには立てません。この岩の向側は絶壁です。KIKIが指さす方には・・・御嶽山そして米田白山の山頂(273m)です。二等三角点があります。今日は5月5日こどもの日チャント日付が替えられています。この山頂の石で、誰かが日付を替えてくれるそうです。山頂から南の方を眺めていたら森の中に白い建物が見えます。カメラの望遠で写してみたけどわかりません。帰宅して地図で確認したら、花フェスタ記念公園の花のタワーでした。船を形どっているそうです。確かに山頂から見たときに、森の上に船が浮かんでいるようでした。展望台最後に展望台でゆっくり展望を楽しんで本日の最後の花の追っかけ~~ですがシライトソウ(ユリ科 シライトソウ属)残念ながらまだ蕾ばかりです。一番開いているのでも、この花くらいです。去年も同じ5月5日に登っていますが、いっぱい咲いていました。今年はシライトソウはまだ蕾です。なぜなんでしょうね、自然はわかりません。春の花の追っかけは~~次はどんな花でしょうか
2025.05.07
コメント(2)
-

花の追っかけ~~2025年 第4弾アカヤシオとカタクリ
27日(日)今回の花の追っかけ~~は瓢ヶ岳のアカヤシオとカタクリです。瓢ヶ岳は今回で12回目最近はアカヤシオの時期と、シロヤシオの時期に年2回登ることもあります。中美濃林道登山口初めの頃はふくべの森から登っていましたが、最近はずっとここからです。ミヤマシキミ(ミカン科)黄色い花のシキミはモクレン科どちらも実は有毒気分の良い登山道をのんびり歩きます。今日は天気が良く、暑くなる予報ですが展望は良くありません。シロモジの花がいっぱいまだ新緑ではなく、芽吹き始めの枝だけの木がいっぱいヤブデマリ なのか オオカメノキなのか遠くて下からしか見えないしどちらもスイカズラ科なので見極めが付きません。稜線に到着したらアカヤシオの群生地ちょうど満開青空にピンク色の花がきれいに映えます。まだ蕾も有るので、8分咲きかな満開の時期に来れました。しかし今年は咲いている木が少ないですねいつもこの木だけは、色が濃くて花付きも良く一番きれいです。この木は近づくことが出来るので花が大きく写せます。シロモジこの辺りはシロモジも群生しています。全体的にこの山はシロモジもとても多い。暑いぐらいの暖かい登山道をのんびり歩きます。次はカタクリを探しながら・・・カタクリは葉っぱが1枚では花が咲かず2枚になったら花が咲きます。1枚葉がいっぱいありますが、花が咲いた後すらありません。でも、やっと見つけました。今年は可児の鳩吹山のふもとのカタクリの群生地に行っていないのでここのが初カタクリです。まだ、咲いたばかりの乙女ですね。美人さんばかりです。この子はもっと若いですね。この辺りはあちこちにカタクリが咲き残っています。この先の階段を登ってピークが奥瓢(おくふくべ)山頂です。奥瓢山頂(1160m)奥瓢山頂から少し下って前方に瓢ヶ岳の山頂が見えてきました。笹の足元にカタクリを探して今年も会えましたね~~~山頂の手前にアカヤシオの群生例年はもっとたくさんの花が咲いていたような気がしますが・・・瓢ヶ岳山頂(1163m)私の左に見える山は高賀山です。高賀三山(高賀山・瓢ヶ岳・今淵ヶ岳)の主峰です。山頂のシンボル、アズキナシまだ蕾です。高賀山その右奥にうっすら、平家岳(左)と滝波山(右)の山並みが続いています。写真ではぼんやりですが、平家岳の山頂はまだまだ雪です。平家岳のズーム手前に低くポコンととんがった山がうっすら見えるのが蕪山です。滝波山のズーム御嶽山と乗鞍もかろうじて肉眼では見えましたが写真ではだめです。去年のシロヤシオの時期の、この瓢ヶ岳からの大展望のブログをリンクしましたクリックしてみてください↓瓢ヶ岳の大展望日当たりが良いので暑い山頂でゆっくり一時間以上かけてランチタイム。さて、のんびり下山しましょう。山頂手前のアカヤシオにサヨナラして瓢ヶ岳の山頂にもお別れして同じ道を戻る途中でシデコブシ四兄弟やはり、このアカヤシオが一番色が濃く花付きが良いですね~~この山一番のアカヤシオをもう一度じっくり眺めて車に戻りました。今回の花の追っかけはアカヤシオとカタクリでした。瓢ヶ岳の標高まで登れば、カタクリにも会えました。背の低いカタクリの写真を撮るのに寝そべって写しますが貸切の登山道で納得いくまでゆっくりと写真タイムが取れてやはり自然の野山の花を見に行くのは誰にも気兼ねもせずマイペースで写真が写せるのが良いです。次の追っかけはどんな花でしょう~~
2025.04.29
コメント(0)
-

花の追っかけ~~2025年 第三弾 イワカガミ
19日(土)花の追っかけ~~第三弾は 鬼飛山のイワカガミです。岐阜県川辺町の鬼飛山は今回で5回目です。県道80号沿いの大谷公園の駐車場に停めてまず大谷山・八坂山へ大谷山八十八ヶ所巡りの始まりKIKIの後ろの階段を登ります。写真より急階段で、早くも暑くて汗が噴き出ます。写真からはそれほどでもないように見えますがスタートからすごい斜面で、ジグザグに登って行きます今日は天気が良くて暖かくすぐに汗びっしょりになり、今年初めての夏日です。大谷山は岩山なので岩が露出しているところだらけです。ところどころの岩の上の石仏に手を合わせ尾根の開けたところにあずまやがありいつもここでお弁当を食べたら良いな~と思いながら実現しません弥勒菩薩様と、地蔵菩薩様のセット岩の露出帯の岩屑は石車になりそうです岩の急斜面をジグザグに登るなんと読むのでしょうね阿弥陀如来様不動明王様千手観音様大日如来様と地蔵菩薩様のセットジグザグのいくつかの支線は省略して進まないと、全部回っていられません。なにしろ、八十八体の石仏があるのですから。十一面観音様と地蔵菩薩様森の中から急に開けたところが大谷山山頂(215m)向うの高い山は、午後から向かう鬼飛山です。大谷山山頂の奥の一段高いところに秋葉神社があります。実質ここが山頂ですね。神社の後ろの木の間から、北西方向にみのかも健康の森の高木山の展望台が見えています。神社の北側の斜面にイワカガミの群生がありちょうど花の見頃です。急斜面の水はけのよいところを好むのですね斜面の下側に回り込んで写真タイム隣の鬼飛山でイワカガミを見ようと思っていましたが大谷山にもこんなに群生しています。白い花ばかりですが一番きれいな時で枯れたのがほとんどなく見頃です。高い山のピンク色のコイワカガミも可愛いですが低山のイワカガミも良いものですねゆっくり写真を撮って、八坂山へ向かいます。ミツバツツジもまだまだ見頃いったん谷に下りて、登り返したら隣の八坂山への稜線歩き、新緑がきれいです。八坂山は八坂山城という山城があったので城郭の石積みがところどころ残っています。本丸があったと思われる広い山頂広場崩れかけた石積みの一番高いところが八坂山山頂(225m)メチャクチャ凝った山名板ですね東側の開けた所から飛騨川と川辺町の町が見えます。山城の石積みが、少しそのまま残っています。そのうち崩れきってしまうのが心配です。コバノミツバツツジ色が濃くてとても綺麗です。山頂広場のあちこちに、石垣が残っています。城跡研究の人にはとても興味深い石積みです。少し低くなったところが展望地で、御嶽神社があります。飛騨川の向こうに三角錐のきれいな形の米田富士(愛宕山)さらに右に目をやると、米田白山の山並み御嶽神社に参拝して下山します。次に向かう鬼飛山を眺めながら下山ここも休憩に良いところです、昔なら○○曲輪と言って、お城の施設の一つがあった所でしょうね。鉄の階段を下りる途中で大谷公園を眺め今日はあそこでお昼ご飯を頂きましょうね。シャガの花が盛りです。向うに藤棚があるので、藤棚の下のベンチでランチ。今日は夏日で暑いので日陰が良いです。ゆっくり一時間のお昼ごはんの後は鬼飛山へ向かいます。大谷公園の斜面には芝桜が咲いてきれいです。川を渡って鬼飛山の尾根に取り付きます。いきなりの急登ロープが有るので下りは助かります。下に大谷公園の駐車場が見えています。展望の開けた所で休憩一番右端の高いところを目指しますが、ここからいったん少し下ります。(え~え~下るの? いやだわ~と思ったけれど、さほど下りません)大楠公園との分岐分岐はこの先にもう一つあります。鬼飛岩向うの大谷山へ鬼が飛んだという岩マネしないようにだって納古山が見えています(写真はズームです)ここが大楠公園からの、もう一つの分岐可愛い鬼たちがお出迎え来るたびに増えて豪華になります。保存会の方でマメな方がいるようです。一刀石置いてある刀で、へっぴり腰ですがエイヤッと・・・第一見晴らし台鬼の横顔だそうです。角が無いですね(笑)第二見晴台のベンチに座って下界を眺め細工がしてある看板の鎖を引っ張れば鬼たちが出てくるので子供さんは喜ぶでしょう。(KIKIもいつも喜んでいます)鬼門岩の上には鬼瓦がたくさん丁寧な木の説明板がたくさんできていました。とても勉強になります。左は先ほど居た、八坂山の御嶽神社の広場です。この看板のおかげで、先ほど見た、コシアブラに似た木が、タカノツメだとわかりました。コシアブラと同じウコギ科だそうで、この木の葉も食用出来るそうです。タカノツメすすんで行くとまたまた鬼づくしの看板がおにまんじゅうです。名古屋近辺では、サツマイモの入った蒸し饅頭をおにまんじゅうというのです。その横に、助っ人募集の看板も。ご丁寧に刀までちゃんと備えています。若い男性たちのインスタ用ですね~~まだ新しくて、屋根までついています。雌雄異株のツクバネの木この木はオスだそうで、後ろにメスの木があり羽子板のツクバネにそっくりな実がなるそうです。そして、いよいよ山頂の手前のイワカガミの群生地です。午後の斜めの陽がいい感じに葉っぱが光っています。イワカガミ(岩鏡)という名前どうりですね。アレレ、黒い服でしゃがみこんでいるのは・・・クマじゃなくHARUさんです先週に続いて今週も知り合いに出会いました。HARUさんとは、2年前 2023年の3月23日、岐阜県富加町の梨割山で出会ったのです。その時は他に二人の女性と大きなワンちゃん(トキ君)が一緒でした。我らが遅い時間に梨割山に登ろうと登山口から少し登ったところで下山してくるHARUさん達に出会って、梨割山には登っただけで加治田城には行ってないという彼女達と城跡までご一緒してそこで別れて以来です。私はすっかり顔を忘れていたのですが、彼女の方が覚えていてくれて声をかけてくれました。その時のブログです。記念にイワカガミの中で、ツーショットの写真を撮ってここでしばらく山談義です。あの後、彼女はマクロや望遠の一眼レフカメラまで購入してしっかり山にはまり込んでしまったようです。一緒にイワカガミの写真を撮って膝が悪いので、しゃがむことが出来ないKIKIは寝そべって写真を撮ります。彼女もしゃがみこんで撮っています。ピンク色がかったのもあってかわいいお互い花のきれいな時に来れましたね~~山頂近くの斜面はイワカガミの群生地この後、鬼飛山山頂(291m)まで一緒に行って、HARUさんとは大楠公園との分岐で別れて我らは登りと同じ道を下山します。登りには気が付かなかったけれど真っ白な花をいっぱいつけている大木が一本ナンジャモンジャ(ヒトツバタゴ)かな??途中で、下りはウラジロコースで下りましょう。大谷公園(右上)との間の川を渡って車まで戻りました。今回も知人と出会って、しっかり山頂で山談義でした。またどこかでお会い出来るといいですね。HARUさんお元気で、たくさん山登ってくださいね~~~今日の花の追っかけ~~はイワカガミでした。可憐できれいで、清楚な白いイワカガミもいいけど白い群生の中に、薄くピンクがかったのも可愛いですね。物言わぬ健気な花の追っかけ~はまだまだ続きます。
2025.04.22
コメント(0)
-

花の追っかけ~2025年 第2弾 アカヤシオ
12日(土)岐阜県川辺町の納古山に今年もアカヤシオの追っかけ~です。昨年同じ頃に登って以来、今回で17回目です。昨年はアカヤシオの頃に2回登って、1回目は早すぎ、2回目は少し遅い状態できれいな花の盛りを見ることが出来ませんでした。今年はどうかな~~車を停めて歩き出そうとしたらすぐそばの川の対岸にミツマタが群生していました。望遠で久しぶりにミツマタを見ることが出来ました。手毬のようにかわいい丸い花です。明るい林道歩きかぶと淵看板が有りますが良く見えません、望遠で写して帰宅して読んだけど、少し意味不明です。木曽義仲がなんちゃら・・・登山口沢を詰めて登ります。すぐに、「天使のブランコ」すごいツタがまるでブランコのようですが以前より垂れ下がって沢の中に落ちています。きれいな植林の中を進みます植林は暗くて嫌いですが、ここの植林は明るいのです。かえる岩カエルの口に手を突っ込んでいますが、わかりにくいですね。ゴリラ岩背中を見せている、マウンテンゴリラです。写真より実際に見るほうが、まるでゴリラに見えます。名古屋の東山動物園にはイケメンのマウンテンゴリラのシャバーニがいますよ。沢の源頭に近づいたら植林からツバキの自然林に変わります。例年ここはツバキの落花で、地面が赤く染まるほどなのに今年は裏年なのでしょうか本当に椿の花が少なくてびっくりしました。沢のほぼ源頭で、登山道は大きく左に回り込みます。「分岐」という看板が有りますが、いつもどことの分岐なのか?と思います。足場の悪い山腹を巻いて、尾根の急斜面を登る見上げたら岩、岩、岩岩をよじ登ってここからはツツジの尾根歩き開けた所の岩場から、谷を眺め対岸の尾根は南尾根で、遠見山からのルートです。向うの南尾根から、遠見山から登ってくる登山者の話し声が聞こえます。南尾根のあちこちのヤマザクラが満開ヤマザクラが意外に多いのですねさあ、ここから尾根の急斜面をジグザグに登ります。ミツバツツジが満開で、それを見ながら頑張ります。この尾根はアカヤシオは無いのですが、ミツバツツジがきれいに咲いています。ツツジのトンネル急斜面ですが、ツツジを見ながら、休憩しながらアセビの向こうに写真では見えないのですがコブシの残り花が咲いていて、その向こうの尾根は西尾根です。最後の急登りは、心臓が口から出そうなくらいバクバクして喘ぎながら・・・あそこが分岐です。南尾根との合流点右の南尾根から続々登ってくるし山頂から下山する団体さんも次々通過する。最近は遠見尾根から来る人が増えました。岩の露出した尾根昨年、遠見山から登って来た時はここで足が攣って、しばらく歩けませんでした。台形の笠置山の左に、見行山見行山の山頂部のズームです。マツがまばらに生えているのが特徴です。笠置山の右の雲の下に、うっすら恵那山が見える・・・見えますか中央アルプスの山並みまだ雪を被っています。手前の右の岩場の文人風のマツがいつも素敵で、あそこに行きたいなあ~と思います。中央アルプスのズーム真ん中右は空木岳と南駒岩だらけの尾根くぐり松この大岩の右横に単独の男性が、山頂の人混みを避けてお昼ご飯を頂いていました。山頂はすごい人だそうです木和谷の初級・中級コースとの分岐山頂に行く前に、アカヤシオの群生地に行って見ましょうヒカゲツツジこのクリーム色が好きアカヤシオ八分咲きですが、蕾が少なくて裏作なのか、年々木が弱っているのか・・・数年前の素晴らしい咲き具合からは程遠く少々がっかりアカヤシオのトンネル西尾根の付け根の群生地唯一、満開の一本御嶽山御嶽山と左に乗鞍岳一瞬、人が少なくなったので山頂で証拠写真(632m)中央アルプスノコリンの右向こうに白山が見えていますが。写真では写ってません。山頂全景去年はもっと人がいっぱいでした。今年はまだ少ない方です。山頂の東側のアカヤシオの群生地は、一本も咲いていません。その代わりヒカゲツツジがいっぱい咲いています。山頂でテーブルを半分譲ってくれた男性二人組と昼ごはんを食べながら山談義で盛り上がって2時間も居座ってしまいました。そして山頂に一人の単独の男性を残して下山しようとしたらその単独の男性から、声をかけられました。なんとなんとアミーゴさんでした。なんと奇遇なのでしょうか。最近はアミーゴさんのブログを訪問していませんでした。もうブログをやっていないとのことです。でもブログでよく訪問してくださったので懐かしくて・・・またどこかでお会いできるといいですね~~~私たちとアミーゴさんが一番最後です。アミーゴさんは木和谷の方へ下山して我らは登って来た西南尾根を下ります。展望の良い岩場で最後に谷を眺めて尾根の末端の岩場を慎重に下ります。ミツバツツジの最後の見納め沢沿いを歩いて、締め殺しの木大蛇みたいに絡みついてすごいツタですね。人間の胴回りくらいの太さのツタです。これほどグルグル巻きつくのに何年かかったのかしら・・・明るい谷を下って車に戻りました。今日も一番最後まで山に居て、しっかり山を堪能しました。今年の納古山のアカヤシオは少なくて残念でした。枝についている蕾も少なくて、来年はどうなのかな???花の追っかけはまだまだ続きます。
2025.04.16
コメント(2)
-

花の追っかけ~~2025年
シデコブシモクレン科 別名ヒメコブシ花弁が神具の紙垂(しで)のようなのでシデコブシと言われる5日(土)いよいよ春の花の追っかけが始まりました。犬山の八曽自然休養林のシデコブシからです。八曽自然休養林は通称「愛岐丘陵」といわれその中に八曽滝や八曾湿地、黒平山、岩見山、焼山等の低山があるのです。そしてその中の八曾湿地は、6.53haの広さの湧水湿地で尾張北部では最大の広さです。この時期はシデコブシやハルリンドウが咲いて登山だけではなく、花も楽しみの一つになります。亀割駐車場には思ったほどでなく、車が少ないたぶん家族連れで満開の桜を見に行っているのでしょうか。歩き出して駐車場を振り返ったら満開の桜が一本管理道路は両脇にポツポツとコバノミツバツツジが咲いています。例年は満開の中を歩きますが、今年はまだ蕾が多くてこの木が一番咲いています。勝手に名付けた「ツツジ街道」(今年はまだ五分咲き)りっぱな山神様におまいりをして八曾湿地に向かいます。ショウジョウバカマこの先に、シデコブシの咲く八曾湿地があります。橋が新しくなっています。丸太のままじゃ無く表面を平らに削って切込みも入っています。滑らなくて助かります。まだまだ先始めなので、蕾の方が多いけどきれいに咲いています。看板にはシデコブシの他、ハルリンドウ、ミミカキグサ、モウセンゴケ、シラタマホシクサなどが咲くとありますが、シデコブシやハルリンドウ以外は地味なのでわかりにくいでしょうねシデコブシは湿地の西側の縁に多く咲いていますハルリンドウは何年か前はまるで絨毯のように密集して咲いていましたが今年はまだまばらに咲いています。これからどんどん芽が出るのでしょうか・・・あれほどの群生は見たことが無いほどでした。湿地の真ん中は保護のため歩かないようにしたいものです。向うに観賞テラスがあります。ピンクが薄いのや、濃いのや色々咲いています。ハルリンドウこの花が一番たくさんの花や蕾がついていました。花弁の根元が濃いピンクで、先端になるほど薄くなるグラデーションが可愛いショウジョウバカマも負けじと咲いています。一か所だけ湿地を横断できるところがあるのでそこから対岸の東側に進んで観賞テラスまで行って見よう湿地のほぼ全景が見られるようですが広すぎて向うのシデコブシが見にくいのです。テラスの右横のシデコブシ数本はまだ蕾です。スズカカンアオイ地面から顔を出すカンアオイの地味な花沢にかかる橋は、古くて老朽化したものから改修されて新しく架け替えられています。この橋はまだ古いままです白いショウジョウバカマ黒平山へ向かいます一の門との分岐毎回、黒平山へ向かうたびに左となりのピークが気になっています。山頂あたりに松があり、なんだか素敵な山頂のようなきがします。しかし、調べてみてもルートが無いしブログもUPされていない、誰も登ってないのだろうか・・・黒平山への分岐から、黒平山へ登り始めたら龍神様が左にひっそりと・・・昔はこの辺りには宗岳寺というお寺があったということで石仏やロウソク立て等、仏具が残っています。立派な石垣が残っています。この辺りにはお寺の本堂などが有ったのでしょうか。この門みたいなのも、シダに埋もれています。黒平山山頂(327m)祠の後ろに三角点があります。珍しいことに、誰も他に登山者は居ません。祠の右後ろに、二等三角点(点名 黒平)があります。北西側に回ってみたら木と木の間から、明王山と金毘羅山が見えています。ズームして見たら鉄塔のある明王山とその左に金比羅山が見えていてその後ろの雪山は能郷白山左端は尾張富士と尾張本宮山(左)が並んでいます。少しだけ入鹿池が見えています。貸切の山頂でお昼ご飯を頂いて下山します。先ほどの登山道の分岐から、山伏の滝(八曽滝)の方に少し下ってアカマツの枯れた木のある展望の良い場所から東の方を眺めたら高社山が近くに見えて、その右に春日井三山も見えています。登山道を分岐まで戻ってきたら天気が良いのでツツジの花が開いています。実は今日は、いよいよ気になっている隣の山に挑戦します。地図をあらかじめ見て調べていました。八曽黒平山の南東に位置するピークに登るにはいったん下って鞍部を登り返さないといけません。ずっと登山道を歩きながら下りられるところを探していました。はじめ見当をつけたところは、途中で足元が見えなくなるほどのシダの急斜面を下りなければならなくて危険なので途中で引き返して次に見当をつけた所を下りる時はいつでもやめて引き返す覚悟で下り始めました。一番下の谷底に目印になる大木があったので、そこで赤テープをつけて今度は登り返しです。踏み跡の無い急斜面を、ところどころ四つん這いになりながら登れそうなところを探しながらやっと山頂らしきところに到着ヤッター、ヤッター、ヤッターマン黒平山の南東峰(308m)思った以上に素敵な山頂です。一か所だけ向うの東側が開けて見える所から枯れ木の向こうは高社山です。今年正月の初登りの山は、色々なところから見えています。目の前の森の中に目立っているのは何の木?ズームで満開の桜の木だったのね~~山頂で証拠写真私たちが最初かと思ったらすでに登って来た人達(峠の会)がいて、りっぱな山名板がありました。これで標高もわかります、ありがとう~~山頂らしい山頂です。広さもほどほどあって、苦労してやって来たかいがあります。踏み場もないはどの雑草が生い茂り、展望もないような山頂かと思っていました。そこには木のベンチもあり、暖かい飲み物を作ってしばし休憩後ろの黒平山を振り返って見ますが雑木が茂っていてなんとなく山が見える程度です。登り着いたところの一本の木に赤テープをつけておきましたがそれを回収しながら下山しましょう。出来るだけ同じ道を辿ろうとしましたがあまりにも急斜面なので、結局下りやすいところを適当に下りて一番底の鞍部の、先ほど残した大木の横に付けた赤テープを回収して登り返し。黒平山の登山道に戻って、無事に長年気になっていた無名峰に登頂できました。KIKIは勝手に黒平山の南東峰と名付けましたけど。(笑)スズカカンアオイ花がいっぱい咲いています。管理道路の脇のツツジは朝よりも花が開いてとても綺麗です。いつも黒平山に登るたびに、隣のピークが気になってあの山頂はどんな感じなの 誰も気にならないのと思っていました。残念ながら、途中の写真はすごい急斜面なので写せなかったのです。登るのに必死で、四つん這いになりながら登ったし下山時はすごい斜面なので、木を頼りに掴みながら下りたので写真どころではありません。念のために持ってきた赤テープは回収できなければただのゴミになるので山頂に残した一本だけであとはつけていませんし、付ける余裕もなかったのです。今日は花の追っかけが出来た上に、長年の気になる山にも登頂出来たしとても大満足な日でした。
2025.04.10
コメント(2)
-

折平山へ再び・・・高根山へ周回
30日(日)先週の折平山は、出発の遅れと登山口を間違えたこと天狗様探しに意外に手間取ったことなどから折平山山頂へ行くのがやっとでした。当初は天狗様探しの後、折平山から尾根を縦走して高根山まで行ってそこから下山する予定でした。今週もう一度やり直して、高根山まで行きましょうと出かけてきました。林道の入口にはタチツボスミレが咲いていて、いよいよ春の花のシーズンですね御嶽神社先週に続いてきているので、迷わずどんどん進みます。舗装の林道は終わって、チェーンの向うから未舗装の林道になります。ウラジロのいっぱい生育している所を過ぎて沢を左下に見下ろしながら進みます。先週はこのあたりから、右足首がねん挫したみたいに痛くて右足をかばいながら歩きました。それも時間切れになった原因の一つです。舗装の林道にぶつかったら、前方に登山口が・・・看板の前はツバキの落花盛んです。前方の暗いところから階段が続きます。この階段は結構段差があって、痛い痛いと半べそかきながら手すりにすがって登ったところです。この山は大きな石がいっぱいあって先に進むほど岩がいっぱい出てきます。この先には岩に霊神の名前が彫ってある岩がいっぱい出てきます。左下の不動の滝を見に行きましょう。落差3mも無い小さな滝で、水量も少なく水が流れてなければ滝だと思えないほどです。登山道に戻って登ると天狗岩→という岩が現れ天狗岩の文字の下には手の形で→を示しています。○○霊神と彫っている岩だらけ摩利支天という文字も彫られています。摩利支天山は御嶽山にもあるので、御嶽講の信仰の彫刻なのかな・・・不動明王の祠の方へ行って見ましょう。道にかぶさるように突き出た岩があります。大岩の下に不動明王様の祠先週はここでランチでした。祠の先にも大岩があり、岩に○○霊神といっぱい彫られています。今からあの鉄塔の方へ登って行きます。いい感じの登山道回り込んだら先ほどの祠の上の大きな岩の上に二つの立派な石碑登る途中で見下ろしてパチリカンアオイの根元に花が咲いています地味ですが可愛い展望台にやってきました先週よりは展望がありますが豊田市郊外の山が見えてきました焙烙山(左)と六所山(右)です。隣の猿投山恵那山は頭の上に雲がかかり右のほうは南アルプスが雪を被っています。写真ではわかりにくいですね。鉄塔の方へ登る途中で鉄塔の裏のピークには天狗の羽団扇が木の根元にありここからは天狗様探しの領域ですそして天狗様1猿投山の方を見ています。大きな岩の上に鎮座されてます。今から折平山へ向かうので天狗様探しはこれでおしまいです。先週はさんざん苦労して、天狗様を探して時間切れになったので今日は天狗様1だけ見て先を急ぎます。縦走路はこの先はヤセ尾根です。この辺りまで風も無く暖かく快適に登ってきました。先週はここを下山して、天狗様2を発見できたのです。今日は「折平山 旧めぐみの森」の表示どうりに進みます。このあたりで向うから単独の男性が下りてきました。少し話をしてすれ違います。ヤセ尾根が続きます。風が出て来てメチャクチャ寒くなってきました。寒いので、どんどん進みます。先ほどの天狗様までは全く寒いとは思わなかったのにこの稜線は風が強く、冬に戻ったようです。折平山と高根山への縦走路の分岐お昼ごはんをどこで食べようか・・・山頂は先週もメチャクチャ風が強かったので折平山の山頂ではランチは無理なので、途中で風を凌ぎランチが出来る場所を探しながらすすみます。折平山へ不本意ですが、入ったん下ります。登り返しは風の強いヤセ尾根歩きが続きます。いかに風が強いか・・・落ち葉が登山道にはありません。落ち葉が風で吹き飛ばされて木の根だけが浮き出ているヤセ尾根ここが山頂だと一瞬喜んだピーク90度右へ曲がってあと少しです右にある看板は東京大学の演習林には立ち入らないようにと書かれていますが瀬戸の岩巣山にもありました。そこからこの山より南まで青い線で囲まれたところが、東大の演習林だそうです。すごく広い範囲ですね。折平山山頂(628m)三等三角点がありますが、風が強くて寒くて寒くて立っているだけで凍死しそうです。ランチ場を探し回りましたが、ここでは無理なので先ほどの分岐まで戻りましょう。証拠写真だけ撮って持っているものをすべて着用して防寒しますがレインウェアでは全く暖かくないのです。隣には電波塔だらけの三国山分岐まで戻ってしばらく前進して太陽が当たっているピークで、笹に囲まれるように風を凌いでお昼ご飯を頂きましたが食べ終わったら暖かくなるより寒さの方がひどくて早く歩こう、体を動かそうということで前進します。この辺りから登山道が狭くなり踏み跡もかすかになっています。風と共に雪が舞い落ちるような寒さの中を進みます。めぐみの森の方へ進みます。登ったりおりたり、起伏のある稜線が続きます。分岐左の「めぐみの森」のほうへ少し尾根を下って進んだら背丈に近いほどの笹藪の向うに展望台が見えてきました。この展望台は老朽化していて登れないようロープがしてあります。展望台の足元を回り込んで、少し木の無くなったところから三国山の方を見て先ほどの分岐まで戻り稜線を進み植林の中を登ったら高根山山頂(605m)山頂は南側は植林北側は自然林に囲まれて展望は有りません。寒いので写真を撮ったら下山します。林道戸越西市野々線→の看板を下ります膝が悪くて踏ん張りの効かないKIKIはこの急斜面が滑りそうで怖くて、へっぴり腰で下山しました。こんな石がゴロゴロ石畳町の名前の由来だそうです(山たまごさんのブログより)やっと林道に下りてきました(最後のこの斜面の下りも苦労して・・・)下りた所より5mほど先に、看板と下りやすいところがありました林道は松の倒木がいっぱい道をふさいでいます20分ほど歩いたら登山口に戻ってきました。後はのんびり車まで戻ります。先週は時間切れでしたが今回は天狗様は一体だけ見て、高根山まで縦走しましたが途中で出会ったのは単独の男性二人だけもっとたくさんの人が登っているのかと思いましたが意外でした。隣の猿投山は駐車場がいっぱいになるほどの登山客でしたが折平山と高根山は静かな登山を楽しめました。しかしメチャクチャ寒かった~~~山はまだ冬の装備は欠かせませんね~~
2025.04.04
コメント(2)
-

折平山・・・三天狗探しのおまけつき
烏天狗(からすてんぐ)三天狗の一つで、一番探すのに苦労しました。よくこんなところに・・・と思います。23日(日)春は花粉症を持つ人にとっては花が咲き出す良い時でも、浮かれていられない時期です。KIKIも長年アレルギーの薬で症状を抑えていました。ところが先日、菜花のお浸しをいっぱい食べたら顔が真っ赤になって痒くて痒くて、熱も有り・・・まるで中国京劇のお化粧のようになってしまいました。菜花だけのせいではなく、もう一つ常備薬の塗り薬「○○○○○軟膏」を肌荒れに塗っていたことも重なったようです。「○○○○○皮膚炎」というのもあるそうです。万能薬だと思って、何かあれば塗っていました。ということでしばらく化粧も出来ず、家でおとなしくしておりました。 症状もほとんどなくなったので、やっと23日(日)は山にでかけることにしました。豊田市の折平山です。初めての山で、ブログで見つけた山です。猿投山の北東、標高628m藤岡町の北曾木の集落の後ろにそびえる山です。面白いことに三天狗探しというおまけに興味を惹かれて出かけましたが、すごい斜面の登り下りで、最近左ひざの調子が悪いのに足を引きずって帰ってきました。八柱神社ここを目印に、車を走らせましたがわからないのでスマホで検索したら藤岡町内には八柱神社が20社ぐらいあることがわかってびっくりです。少し探してやっと見つかったら、駐車場には車がいっぱい!!どうしようと待っていたら、出ていく車があって停められました。八柱神社社殿は新しく可愛い神社です。参拝して出発。ところがこれが間違いでした。山たまごさんのブログを参考にしましたが良く調べもせず、ここが出発地点だとおもい横の沢沿いの踏み跡を登ってしまったのです。赤テープも有ったので・・・しばらく登って、間違いに気が付いて30分のロス梅が満開この橋を渡って右へ林道天狗岩線の起点から出発右の沢の横には「水神社」分岐から左へところが民家がいっぱいなので間違いかと思って、ここでもウロウロしばらく進んだら右上に御嶽神社がありこれで良し!!舗装が無くなって通行止めのチェーンの向うへ落ち葉を踏みながら進みます。道幅が狭くなったところへ倒木またいで進みます左右からの舗装の林道に突き当り向うに看板と階段があるのでああよかった、これで間違いない。ここまで来るのに迷いました。「天狗岩展望台」天狗伝説が書かれています。ここから本格的に山登りですが階段が続くので、うへ~~擬木の階段段差が結構あるので、帰りはつらいな~~岩が出てきました植林ではなく自然林なので良いですが結構な斜面をジグザグに階段がつけられ良い天気なので暑くて暑くて汗びっしょり段差のある階段どこまで続くんだろう・・・階段が無くなってホッとしたら不動の滝の看板左へ下りて、しめ縄のはられた石碑3m位の落差の滝ですが水量が少ないので迫力の乏しい滝です。水量が多いとそれなりに立派なのでしょう。まだまだ擬木の階段が続きます。上に、石碑が3つしめ縄が張られた立派な石碑がいっぱい左へ登る階段を登らず、まっすぐに行って見ましょう。不動明王が祀られている祠お昼も過ぎてしまったので、お腹がぐーぐいってます。この祠の前をお借りしてランチタイム祠の後ろの踏み跡を少し進んで見たら御嶽講の霊神様をお祀りしている大岩がいっぱいランチの後、先ほどの通り過ぎた階段まで戻って登ります。いい感じの山道になりました。また擬木の階段松の多い山です。後で落ちた松葉が問題になります。道が二つにわかれ、左は普通の山道右は展望台我らは展望台のほうへ階段だらけです。山腹を巻くように階段がつけられ階段の上に展望台なかなか立派な展望台です展望台の斜面の上部には鉄塔と看板天狗岩の謂れが書かれています。これを読めば三体の天狗像を探したくなります。まず、展望台に登って下界を見てみましょう下に見える集落は石畳という集落でしょうね春霞というか、花粉と黄砂でかすんでいます。鉄塔の後ろの高いところを目指すと天狗の羽団扇(はねうちわ)が木の根元に落ちてますよ~~いよいよ天狗さんに出会えるのですね天狗様1苦労しないで見つかりました!!天狗様の横顔この岩には登れるので近づいて写真ゲットです。猿投山の方をご覧になっているようです。岩の下に回り込んで右に先ほどの鉄塔が見えています。岩の上には天狗様1ところが次の天狗様1と烏天狗様を探すのに下ったり、登ったり小一時間掛かって見つからず、もうダメかとあきらめて山頂に向かうつもりでしたが大岩を回り込んだらとても分かりにくいところに烏天狗様岩の上に乗っかってる岩のくぼみに鎮座していました。下からは見えないのでわかりにくく探し回ったところはすごい斜面で、松葉の落ち葉で滑ります。膝が悪いので踏ん張りがきかないKIKIはロープまで使って下りたりして普通に歩いていてはわからない所にありました。松葉スキーとやらがあるように落ちた松葉はとても滑りやすく、怖いよ~~こわいよ~~と半べそをかきながらやっと見つけた烏天狗様です。時計を見たらスタートが遅く、登山口で迷ったのでロスタイムもあり烏天狗様探しに時間がかかって、もう山頂に向かわないと時間がありません。「天狗様2」 をあきらめて山頂に向かっていると「天狗様2 不動滝」 の標識があったので山頂へ向かってここまで戻ってきて下山時に「天狗様2」を探しながら下りようということで大急ぎで山頂に向かいます。ヤセ尾根登ったり下りたり、この山ほど登り下りの多い山は最近では珍しい稜線に登り着いたら少し平行移動ああ、山頂だ~~と思ったら違います三等三角点のある折平山山頂(628m)木で囲まれてあまり展望が良く無いけど、山頂らしい山頂です。木の影で分かるように太陽は西に傾いて焦ります。先ほどの分岐まで戻ってきて下山しながら「天狗様2」を探しましょうこの岩かな~~と思ったけど違います天狗岩と標識がある「天狗様2」こちらの岩の向うの大岩に鎮座されています。岩と岩の間は大きく離れているので長い梯子を渡さないととても天狗様に近づけません。西日に照らされて逆光です。この「天狗様2」はこちらを向いておられる。何とかズームで。これで三天狗様を見つけることが出来ました。登山口でウロウロして、烏天狗で探し回り時間切れで折平山だけ登れました。こんな斜面だらけです大急ぎでここまで下りてきましたら17時です。冬なら山の中はすでに真っ暗です。まだまだここから林道を下らないといけません。車に戻ったら17時半でした。予想外に天狗様探しに手間取った一日でした。もっとわかりやすいところに天狗様があるのか、と思っていましたがすごい斜面を登ったり下りたりして天狗様探しの写真も撮れず、はじめ思っていた隣の高根山にも行けず折平山は侮れない山でした。しかし、元気な若者なら面白い山でしょうね。
2025.03.26
コメント(0)
-

天下峯・・・岩の上から天下を望む
9日(日)豊田市の天下峯に登ってきました。毎年冬になったら登る山で、今回で11回目です。今回は途中に高速道路の入口が出来たせいで、いつも通る道路がわからなくなって、道を間違ってしまいスマホのナビで道を探してたどり着いたけどいつもの駐車場ではありません。王滝湖駐車場ですって、始めてきましたがここはどのあたりでしょうか看板で確認したらいつもの駐車場は下の方の2番の駐車場なので、今日は目的の天下峯に少し近いようです。身支度して王滝湖を目指します。御嶽山の王滝湖と同じ名前ですが水はほとんど溜まっていません。ロウバイの向こうの赤い橋を目指します。去年ここまで歩いてきたところです。この橋を渡って、バーベキュー広場に向かいます。しかし、今までバーベキュー広場でバーベキューしている人を見たことがありません。夏ならいっぱい居るのかしら・・・焙烙山(左)と 六所山(右)溝状の登山道ひとたび大雨が降ったら本当に溝になりますね。山からでたら、突然のどかな農村風景目的の天下峯は一番左端でしょう。八紘ぶどう園の横を通って、再び山に入っていくと松平隼人助親正の墓徳川家康の始祖、大給松平の武将松平親氏を祖として、4代目の隼人助親正はこの地で居を構えたそうです。五輪塔のお墓です。造花ですが、いつもおまいりされているようです。山姥の足跡どれが足跡なのかな~といつも思います。産の神三つの神様を祀っているから、三の神ではないの?と思うのだけど。山頂直下まで道路が来ていて、舗装道路の登り坂を登って、天下峯のピークの最後の取りつきに到着。ここから先の岩山は、岩登り、ボルダリングの人がいっぱい練習しているところです。山頂は岩場で狭いので、ここでお昼ご飯ベンチがあり風も避けられ、頭は日陰、足元は暖かいので最近はここでお昼を頂くことが多いのです。ランチの後、山頂に向かいます。天下峯山頂(360m) 徳川家康の祖先、徳川親氏がこの山頂の岩の上で天下泰平を祈願したところと言われていますが確かに良い展望です。m)正面には 焙烙山と六所山がデーンと聳え遮るものがありません。中央の左寄りに豊田スタジアムと右奥に名古屋のビル群伊吹山名古屋のビル群のズームこの後、三角点峰へ向かいます。以前は少し藪漕ぎでしたが、今は行く人が増えたせいか踏み跡もはっきりあり、藪も無くなっています。砦跡地確かに天下峯の山頂は大岩だらけで砦が築かれません。ここからいったん大下りします。木にはクマがつけたと思われる生々しい傷跡があちこちに。一番下の峠のような、乗越のようなところまで下りてきました竹藪の登り返し。以前は竹の倒木がすごく多くて、歩きにくくて一番悩ましいところでしたが今回は歩きやすくて、覚悟してきたけれど拍子抜けです。竹藪を過ぎたら、巨岩だらけの斜面を登ります。三角点峰に到着三等三角点「点名 仁王」フェンスに囲まれた反射板の向こうに行って見ましょうゴロンゴロンと巨大な岩が転がっています。同じ道を戻って山頂には寄らず帰路につきます。傾いた夕日が木々の影を幻想的に延ばして歩きやすい道を、スタートの王滝湖までトコトコ朝ののどかな農村風景地まで戻ってきました。天下峯が夕日に照らされています。天下峯の奥の焙烙山(684m)ズームで見たら、電波塔と展望台が見えます。ひまわりの形をした面白い展望台だったと記憶しています。周りの木が大きくなって展望が悪くなっていますね。王滝湖かけ橋に戻ってきました。ここから駐車場に戻る前に梅園の方へ行って見ましょう。残念ながら梅はほんの少ししか開いてません。紅梅はもっと蕾固し今年は異常に開花が遅れています。目の前のつり橋の向うは梅園ですが、花は開いてません。毎年冬になったら王滝渓谷と梅をセットで見ながら天下峯に登っていますが、今年は梅の開花が遅れて満開の見事な梅がまだ見られていません。ぐずぐずしてたら桜が咲いちゃうよ~~~
2025.03.10
コメント(2)
-

尾張本宮山・・・梅が無い梅まつりと相澤山とブルーインパルス
1日(土)日曜の天気が今一つなので土曜日に尾張本宮山に登ってきました。登山口の大県神社は2月19日から丁度「梅まつり」です。いつも、もうすこし早いこの時期に梅まつりと併せて登っていますが、今年は残念ながら梅はまだ咲いていません。蕾も硬くて梅は有りませんが、その代わりブルーインパルスが花を添えてくれました。いつもの駐車場に停めて大県神社に向けて歩きます。天気も良く暖かいので、梅はまだですがたくさんの参拝者です。正面の山の斜面の梅園の梅はまだ蕾だから、ほとんど人は歩いてません。そこを横目に山に向かって歩いていく宮池大きな鯉がいっぱい泳いでいます。宮池の上の池は西洞池池の堰堤の端を奥に歩くと相澤山の看板があり歩きやすい道が続きます。前回登った時は、ここから登らずもっと先の姫の宮の赤い鳥居から登りました。思ったより遠回りですが緩やかで歩きやすく、いい道です。前方が明るくなって開けています。西の方の展望が良い岩場です。先週から山デビューした若者としばらく話をして相澤山山頂(206m)に到着その先、下りの途中で八大龍王の岩穴。先ほどの若者と一緒に下ってきました。岩穴の中に八大龍王様がまつられています。ここに下りてきて、本宮山の登山道に合流我らはこの展望台の下でお昼ご飯若者たちは先に進みます。ゆっくりお昼ご飯の後、本宮山に向けて再出発雨宮社雨宮社の裏の岩場はすごい展望しかし今日は春霞で、あまり展望はよくありませんたくさんの人が行き交い、今日はどうしてこんな人出なのだろうと思っていたら下りてくる人が、小牧の自衛隊の航空祭の予行演習の日だと教えてくれました。真正面の富士山のような形の山は尾張白山のピークその手前の反射板のある山は徹当山斜面が削られている右の山は天川山恵那山雪が少なくなりました山姥社能郷白山能郷白山の左の山々は美濃の山々でしょうか能郷白山とその右は奥美濃の山々尾張本宮山山頂の大県神社奥宮山頂に登り着いたら写真では写っていませんがすごい人でした。皆さん西の方を向いて待っています。尾張本宮山の山頂(293m)一等三角点の前で証拠写真角を補修された一等三角点はさすがに立派です大県神社奥宮の社と一等三角点石仏群せっかくだからヒトツバタゴ、入鹿池の方面へ少し下ってみます。山頂に戻ってきたらすぐに爆音がして、航空祭の飛行が始まりました。6機の編隊飛行です。すごい間隔の狭い飛行でスモークを出しながら飛んだわ~~と思ったらブルーインパルスです。初めてブルーインパルスの飛行を見ました。私のコンパクトデジカメではこれが限界それに逆光です。名古屋駅前ビル群登って来た時はもっとたくさんの人がいましたが団体の皆さんは下りていきました。この山でこれほどたくさんの人がいたのは初めて見ました。去年、継鹿尾山の山頂で出会って、飛行機の写真を撮っているT.SさんにLINEしたら今ちょうど小牧のエアポートウォークにいるということでまたまたいろいろ教えていただきました。雨宮社の岩場に下りてきてもう一度展望を楽しみます。もう戦闘機はこちらの方へ飛んできません。先ほど相澤山から下りてきたときに信貴山近道という看板を見つけたのでいつもと違って今日はこのルートで信貴山へ向かいます。信貴山への車道途中で朝の若者カップルに出会って、彼らは山頂から入鹿池の方へ下り、下の道をぐるりと廻って信貴山へ立寄りここを登って来たのです。若いから体力が余ってるんですね。先ほどの車道を登り返し再び山道を登ります。やっと信貴山に到着多宝塔きれいな極彩色で好きです。どこの神社仏閣も作られたときはこんな色だったのですね。本堂に向かう途中で、木が切られて展望がとてもよくなったので入鹿池が近くにはっきり見ることもでき御嶽山も乗鞍岳も見えます。ズームで入鹿池の向こうに八曽黒平山の奥が中央アルプスズームで黒平山の向こうに三角錐の笠置山その奥に中央アルプス(右が空木岳と南駒ケ岳)焼山とその左に257峰木曽駒ケ岳と中岳と宝剣岳尾張白山のピークと徹当山の反射板二つ信貴山 泉浄院本堂本堂の屋根を見上げて可愛いけど立派な鬼瓦です。この後、本宮山の登山道へ戻って大県神社(姫の宮)へ戻ってきました。夕日に照らされた梅園だけど、まだ蕾固し。小牧自衛隊の航空祭の目玉ブルーインパルスの飛行の写真をT.Sさんから送ってもらいました。私のコンデジでは小さいので彼の写真をあらためて載せてみます。両端の二機が傾いて飛んでいます。機種は小さいT4です。二人乗っているのもわかりますねスモークを出していない時です。ブルーインパルスのアクロバット飛行すごい!!衝突しないで円が描けてます。ヘリによる救助訓練を披露早期警戒機 E-767空飛ぶレーダーです。やはりコンパクトデジカメでは撮れない写真ばかりです。T.Sさんありがとうございました。(実はKIKIは登山を趣味とする前は飛行機の写真を撮りに行ってました。)今日は梅は見られなかったけれど、ブルーインパルスの飛行をいい天気で見ることが出来ました。去年11月と今日と、意識せずに登ったら山の上でたまたま航空祭の戦闘機の飛行を見ることが出来ました。長年登山していますがこんなことは初めてです。
2025.03.05
コメント(0)
-

瀬戸の岩巣山・・・岩屋堂周回
23日(日)13回目の瀬戸の岩巣山へ行ってきました。冬に散歩にもってこいの山で、去年は2月に登りましたが今まで冬ばかり11回登っているのに去年は初めて夏に、それも2回登ったのはなぜか・・・その答えは後ほど。スタートから急斜面を鉄塔巡視路の硬質ゴムの階段を登ります。写真より実際はもっと急斜面でしす。だからジグザグに登り、やっとゆるかやになりました。昨日降った雪が残っています。一番最初のピークには、何やら建物の跡地に到着名残のタイルが残っています。石積みの後もここで小休憩していたら、単独の男性が登ってきて追い越して行き少し下って、うっすら残った雪のあるヤセ尾根を歩きまた石積みこの後、犬を連れた単独の男性とすれ違って引っ張っていく犬のリードを持って、先ほどの急斜面を逆に下りてゆくのは怖いだろうね~~と話しながら見送り高度を上げると雪が多くなり葉っぱの上の雪が滑ります。また、単独の男性とすれ違ってだんだん雪が多くなり雪中歩行もどきが味わえました。女性の二人組とここですれ違ってチェーンアイゼンをつけていたので、このルートの下りでは安心ですね。それにしても今日はすごい人が登っています。このルートで人とすれ違ったことがありませんでした。見上げたら前方に鉄塔が・・・枝の向うなので写真ではわかりませんねその鉄塔が近くなり鉄塔の下でお昼ご飯です。岩巣山の山頂は狭く、その奥の岩場は平のところが無いのでここの方が暖かくていいですね。また、単独の男性が下りてゆかれ、今日は岩巣山は大賑わいですね。お昼ご飯の後は再び岩巣山山頂へ向けて出発先ほどランチした鉄塔と、その左に下界の街が・・・遠くのビル群は名古屋駅前です。今日は晴れていますが、雲が多く展望が今一つですね。その先で、元岩巣が見えました。一番奥は猿投山ですが、その手前の雪のあるところが元岩巣です。岩巣山山頂(481m)三等三角点がある狭い山頂あまり展望が良く無いのでここでは証拠写真だけここに峠の会の山頂の標柱がありましたが、抜かれています。ここで奈良県からの単独の男性と話をして岩巣山もなかなかメジャーな山になりましたね。元岩巣の山頂奥の岩場です。元岩巣に向かう途中で、岩巣山や下界の展望の良いところで岩巣山山頂と下界の街を眺めて名古屋の駅前ビル群名古屋ドームが見えてますね岩屋堂の方面に下ります。反対の白岩の方から去年の夏は二回登りました。元岩巣のピークの手前左は元岩巣のピークへ、右の道は岩屋堂へ下る道まず元岩巣のピークへ元岩巣も雪がうっすら積もっています元岩巣から隣の三国山のアンテナ群元岩巣のピークここには峠の会の標柱が抜かれず残っています。南側に回ってみたら、私の指す方には猿投山私の向うには下界の街が・・・少しズームで、伊勢湾が光っています。ここから先は、岩屋堂に向けてひたすら下山します。展望台まで下りてきました。いつも思うのですが、この下りはとても長く感じます。展望台の横の、この岩の上でお湯を沸かして暖かい飲み物を頂いて小休止太陽が西に傾いて逆光です。さあ、再び岩屋堂に向けて下りましょう落石防止工事が終わって危ない登山道上の岩にはワイヤーロープを掛けられています。こんなロープで落石が防げるのかな?崖の巨大な岩を回り込んで岩だらけの登山道を急激に下ります。岩屋堂に下山しました。岩だらけの山だから岩巣山というのが納得です。おまいりをして本日の周回は終了。ついでに、夏に二度登ったのはこのミヤマウズラに会いたくて登りました。冬はこんな状態なのですね。残念なのは花の株を盗る人がいて、盗った人に戻すように看板が掛けられていました。しかし、故意に花を盗んだ人が、看板を見てここに戻すとは思えません。看板はかえって、花に興味の無い人にまで、ここに花があるとわざわざ教えているようなものです。だから私は貴重な花はあえてブログで場所を特定しません。興味のある方が調べて分かればいいと思っています。以前、白山の釈迦ヶ岳に絶滅危惧種のアツモリソウを見たくて登った時に私たちの翌日には、その花がグチャグチャに踏みつけられていたと他の方のブログで知りました。たくさんの人が貴重な花を楽しみに登っていますが中には心無い人がいて、盗ったり踏みつけたりするそうなのです。物言わぬ健気な花たちを踏みつけたり、自生地から株を盗んだりしても花は環境が変われば咲かないと思うのです。その花たちはそこで咲くから奇麗なのだし、その環境でしか咲けないのです。花に興味のある人たちが、そっと見守ってあげればいいと思うのです。皆さんはどうおもわれますか。
2025.02.28
コメント(0)
-

八曽の山・・・初めての焼山
15日(土)先週、八曽の岩見山へ登ってその山頂でお昼ご飯を頂いていたら隣の焼山の尾根に、二人の人が立っているのが見えました。以前から近々焼山に登ろうと言っていたので俄然その気になって、今週はその焼山へ。駐車場から舗装道路ではなく、山道をキャンプ場の方へ焼山は巌頭洞(がんどうがま)の上の山で岩山で急斜面で直立しているので地図で一番等高線の幅が広くて緩やかに登れるところを探しました。キャンプ場の外れから取りつきます。登る途中で右下には、以前は今井パイロットファームという果樹園だったところが今はソーラーパネルが敷き詰められています。踏み跡はしっかりついていますが下りで迷いそうなところもあります。257mピークに到着峠の会の標識がありました。ピークのすこし前方には開けたところがありそこからは先週の黒平山が見えています。岩見山も見えています。先週、岩見山の山頂から見えた、人が立っている所はどうやらここのようです。黒平山(左)と岩見山(右)が同時に見られ展望が意外によくてびっくりそしてさらに目を右に向けたら前方に目標の焼山がとんがっています。先週、隣の岩見山から見たときは尖がっているようには見えなかったのです。目の前の焼山を見ながらそれほど下ることなく、焼山に取り付いて登り返したら焼山の山頂(266m)図根三角点が石に囲まれています。ここにも峠の会の銅板の標識があります。古い「岩山」の標識もあり、昔は岩の山だから岩山と言われていたのですね。山頂の左からは御嶽山と乗鞍岳まで見えてすごいすごいとテンションが上がりっぱなしその左に、三角錐の笠置山の後ろに中央アルプスの雪山がズラ~リ焼山は展望がないと思い込んでいましたが大違い山頂の少し先に行くと、尾根の続きに岩の露出帯が見えその向こうに本宮山と尾張富士が並んでいます。黒平山の左に中央アルプスさらにその左に御嶽山山頂で記念写真誰も来ないと思って狭い山頂でお昼ご飯です。何度も御嶽山を眺めてしまいます。笠置山の向こうに中央アルプス雪山の山並みの左側の一番高いところが木曽駒ケ岳ズームで黒平山の左肩の向こうに恵那山が少し見えています。横の木がもっと大きくなったら見えなくなるかもしれないけれど黒平山が見えています。またまた御嶽山と乗鞍岳焼山山頂からの尾根続きの岩の露出帯へ少し下りてそこから山頂を写して相棒が山頂に戻ってKIKIを写してくれましたわかるかな~~~これならわかるね~~黒平山と右手前に岩見山ズームで岩見山の山頂部分を写したけど誰もいませんねそんなことをしてずいぶん長く遊んでいたら先ほど行ってみた岩の露出帯からヤッホー~の声がして単独の男性が登ってきました。我らと反対に、乙女の滝の方から登って来たのです。少し話して、この先は岩稜帯で痩せ尾根があるというのです。我らは未踏のルートを下るのは初めからやるつもりがないので同じ道を下ります。焼山の手前の先ほど通過した「257m峰」を見ながら下ります。振り返って焼山同じルートで帰ってきましたがそのうち乙女の滝から登ってみようという課題が出来ました。冬は里山を毎週のようにウロウロしてお茶を濁していますが寒くてもそれなりに装備して暖かいひだまりでささやかなお昼ご飯を頂いてそれだけで幸せです。町の中の舗装道路では膝が痛くて階段もやめてエレベーターやエスカレーターを使うのに山道はなんと膝にやさしいのでしょうか。自分のアンヨでのんびり歩ける幸せをしみじみ感じています。
2025.02.20
コメント(0)
-

八曾(黒平山と岩見山)
9日(日)犬山の八曽自然休養林の山へ行ってきました。初めはキャンプ場から川沿いを巌頭洞に向かって歩き岩見山に登るつもりで歩き出しました。地面には雪が残っているのでテンションが上がります。亀割の駐車場は8割ほど停まっています。自然休養林の入口とは反対にキャンプ場に向かって歩き始め静かなキャンプ場2張のテントが張られています。雪の後のこんな寒い日でもキャンプする人が居るのですね。今はキャンプは夏という概念は無く冬キャンとか言ってわざわざ冬にキャンプするらしい。キャンプ場を過ぎて川沿いに進み始めたらすぐに通行止めの看板木橋が老朽化で危険につき通行止めだそうです。Uターンしてまた駐車場に戻り八曾自然休養林の入口から管理道路を歩くことにします。この30分のロスタイムは後で響くことになります。メチャクチャ良い天気で暖かいけど、空気が冷たいので頭からフードを被っています。「山の神」いつも通りおまいりをします。1番の山の神から12番、13番の方に歩いて看板にはありませんが、12と13の間にある岩見山への分岐を目指します。木の中にある分岐標示がわかりにくいけど分岐から入ったらすぐにまた通行止めの看板が有りましたが岩見山までは行けます。木の上からバッサバッサと雪が落ちてきて冷たい途中で岩見山への案内があります八曾は広くてまだ歩いたことのないルートがあるようです。雪景色良いですね~~~岩見山の山頂(250m)尾張本宮山(左)と尾張富士(右)が真正面に見えます。少しズーム隣の岩がごつごつしている焼山の向こうに伊吹山が見えています。雲と同化しているのでわかりにくいけれど・・・お昼ご飯は寒いから、おでんを温めてそのおつゆを味付けし直してうどん玉を入れて卵とネギとわかめを入れて玉子とじうどんです。30分のロスタイムで、お昼ご飯を食べる所を変更してこの狭い山頂で頂くことにします。しばらくしたら、お昼も過ぎてるので誰も来ないだろうと思っていたけどカップルがやってきて同じようにお昼ご飯を用意し始めました。先にランチが終わったので、出発して次は展望台に向かいます。管理道路を少し歩いたらヘリポートと展望台があります。以前ここで消防隊がヘリコプターで救助訓練していました。あずまやの方まで登ってあずまやからヘリポートの向こうに今から向かう黒平山が見えています。今日は雲が多く御嶽山が見えません看板の12番に少し戻って黒平山に向かいます。この道は初めて通る道で、わくわくしますね~~初めはほとんど平行移動で歩きやすくこのままこんな感じならいいね~~と言っていたら、斜面が出て来てどんどん下ります。たぶん川の谷底まで下るのでしょう。川というか、沢というか木橋を渡りますがうっすら積もった雪が滑る、滑るこわ~いよ~横に渡した横木を踏んだらダメだとわかっているけど丸木も滑るし・・・この橋は人が歩いた気配が無いのでたぶん滑るだろうから、橋はやめて沢を渡りました。結局3つ位橋がありましたが、怖くて橋より沢を渡ったほうが良かった。この斜面がすごい斜面で胸突き八丁です。このあとは、いつも「山の神」から黒平山へ行くルートと合流するのですが夜に宅配の荷物が届くので、帰宅してといけない時間が決まっているのでこの調子で黒平山山頂には行け無いかもしれない、それなら引き返す時間が来たら、そこから躊躇なく戻ろうということで歩きました。朝の30分のロスタイムがここで響いてきたのです。八曾の外周道路の分岐に到着右へ行くと黒平山です、大急ぎで山頂へ。左へ下れば、八曽滝(山伏の滝)で、山は右の方へ山頂一帯には昔、大きな寺があったそうでその面影のある石仏や石垣などが点在しています。黒平山山頂(327m)には朽ちた祠と石仏がありその奥(KIKIが立ってる所)には三角点があります。二等三角点(点名 黒平)北西側だけが開けています。真正面にアンテナのある明王山とその左に金毘羅山が見えています。ズームで見たら明王山にはまだ人が居そうな感じですね。祠が来るたびに朽ちていきます。この祠が朽ち果てるのはもう時間の問題ですね。また来ますね、とおまいりをして大急ぎで下山しましょう。山の神へのルートで戻りますが新しい木橋が出来ていました。しかし、木が出来たてのツルツルで、怖い怖い相棒は橋を渡ったけど、私は沢を渡りました。この橋は迂回できないので、怖いよ~とワ~ワ~言いながら渡ることに・・・山の神まで戻ってきてホッとしています。駐車場の入口のゲートまで戻ってきました。今日はスタートから通行止めで予定変更してロスタイム30分で帰宅時間に合わせるのが大変でしたが何とか予定通りの山に登れて楽しかった~~寒くても家にこもらず、外を歩いて粗食でも山での食事も美味しいし毎週一回でも自分のアンヨで歩き続けるのが目標です。それがいつまでできるかな~~~
2025.02.14
コメント(0)
-

小牧アルプスの東側の山々を歩こう。
1日(土)この冬の散歩の小牧アルプスも3回目です。今回は小牧アルプスの東側の山々で「児の森」から西山~本堂ヶ峰~東天川山~東山~安手奈山天川山を除くすべての山々を歩きました。駐車場は車がいっぱい停まっています。いつものごとく我らは出遅れ組で出発。小牧環境センターの横を登ります。ここからスタート左へ行けば先々週のトンボ池の方から登るルートで今日は右の階段が多いルートで、最短で「児の森」へ向かいます。サザンカの休憩所天気予報より天気が良くて暖かくて登山日和です。しかし、名古屋駅の方はもやって見えません。階段が出て来て急斜面を階段で高度を稼ぎます。最初のあずまやここでいっぷく休憩次の休憩所ウソみたいないい天気「児の森」の駐車場数台停まっています。正面の西山に向かって歩きます。西山のピークは鉄塔の左です。わくわく小屋ここでまたいっぷくしてお茶を飲んで今日はどんぐりの小道を歩きましょう。正面をジグザグ登るのです。ムササビ峠から西山の鉄塔の横を通って西山山頂(277m)その後は青空小屋の前のベンチでお昼ご飯を頂いてお昼ご飯中に空は曇ってきて名古屋駅前ビル群はぼんやり浮かんでいます。青空小屋とその前の広場(左)本堂ヶ峰に向かって再出発するころにはもう今にも雨が降りそうな厚い雲に覆われてしまいました。本堂ヶ峰山頂(276m)天川山を迂回するため、鉄塔巡視路の硬質ゴム階段を登ります。天川山と東天川山の間にある鉄塔の東側からの展望。天気が悪くなってきて遠望は有りません。東側に視野を向けたら、八曽の黒平山は見えています。よく見たら、八曽の黒平山の左にぼんやり御嶽山が見えています。イエ~イズームで写してみましょう。御嶽山の左奥に乗鞍岳も確認できました。東天川山(280.8m)前回、東山まで足をのばして確認したので東山までは簡単に行けますね。東山(273m)この後は久しく通ってない山道を安手奈山に向かって歩きます。何とか残っている踏み跡と、古いテープを頼りに尾根を外さず林道を目指して歩いたら下に林道が見えたので林道を横切って再び山に入っていきます。山に入るところは、昔の写真をコピーして持ってきたのでわかりました。目標の大きなシイノキこの木は昔の写真や、他の方のブログにも写っています。目印になる木ですね。次の大きなシイノキの横には木のテーブルがあります。この山には椎の大木がいっぱい残っているようです。相似形の木枝ぶりがそっくりな木が並んでいます。正面にアンテナの擁壁が見えたら以前はそこをよじ登っていましたが谷をぐるりを回って鉄塔管理道路に楽に取り付けるところに小さな梯子が掛かっている所を登ってアンテナに向かって道路を少し登ったらNTTドコモのアンテナアンテナの裏山に登って安手奈山山頂(273.3m)三等三角点「点名 せん谷」どんどん空が暗くなってきているので大急ぎで戻りましょう。目印のシイノキの大木東山の山頂を通過東天川山の山頂には立ち寄らずせいいっぱい頑張って歩きます。児の森(ちごのもり)の駐車場から森に入って白山神社には立ち寄らず、登りに使ったルートを目指して階段の多い道を下ります。山はもう誰もいない、と思ったら若い単独の男性が追い越して行きました。それからは、本当に私たちが一番最後になったようです。下界の灯りが瞬いて、久しぶりにうす暗い森の中を歩きました。車に戻ったら日没です。このところ久しぶりに小牧アルプスを歩きました。気になった東側の山々の山道をルートを探しながら歩いて昔は若くて元気だったから、西端の徹当山から東端の安手奈山まで通しで平気で歩いたものですがこのところは半分ずつ数日に分けてのんびり歩きました。災害級の寒波が来ているので寒がりの我らはお天気と相談しながら、山を選んでのんびり冬の散歩を楽しめたら良いなと思っています。
2025.02.04
コメント(0)
-

弥勒山・・・小鳥と遊ぶ
26日(日)小牧アルプスに行くために車を走らせていたらメチャクチャ天気が良くて、山々がくっきり見えるので行き先を変更して春日井三山の弥勒山へ・・・駐車場はほぼ満車状態でわれらはいつもの出遅れ組です。駐車場に何とか停めて直接、弥勒山に登る最短ルートで登ります。緩やかにコシダの生える登山道を登って行くとたくさんの人が下りてきます。午前中サクッと登って昼前には下りてくる人が多いようです。林道に出たらしばらく林道を歩きます。林道歩きはあまり好きじゃありませんが舗装道が少ないので、まだましかな・・・みろく小屋が見えてきました。たくさんの人が休憩しています。林道から離れて弥勒山への最後の登りです。今日は両膝と、骨折した左足首が痛くて調子が悪いからこの程度の山でよかった明るく開けている所が山頂です。山頂に着いたら、やはりすごい人です。山がガスらない前に写真を撮っておきましょう。御嶽山中央アルプス少しズームで、三ノ沢山が右手前にどっしり。左の雪山が木曽駒ケ岳その右が中岳、その右の雪の少ないとんがりの宝剣岳恵那山この間より雪が少なく感じます南側のあずまやの方から伊吹山を見て伊吹ドアライブウェイがはっきりわかります。白山連邦少しズームついでに名古屋駅前のビル群の中に名古屋城昔は濃尾平野の見まわせる場所だったのに今はビルに囲まれて小さく見えます。ヤマガラと遊びましょう。今日はすでにたくさん餌をもらってあまり手に乗ってくれません。弥勒菩薩の祠にお参りしてヤマガラさんを待ちますが・・・来てくれなくて外来種のソウシチョウがやってきました。最後にもう一度御嶽山日頃登山に縁がない人がたくさん登ってきていて雪山が見られたと喜んでおられる。二等三角点の横で弥勒山頂(437m)証拠写真です。少し人が少なくなって、やっと写真が撮れますね。ヤマガラさん食べて~~~いつも警戒心が強くて、地面近くや木の下枝に居るソウシチョウお昼を食べて下山後築水池にやってきました。築水池の向こうに、先ほどの弥勒山(奥)右手前の山は大谷山写っていませんが、右端に道樹山三つの山で春日井三山です。弥勒山の山頂のあずまやもう誰の姿も見えません。治水碑大谷川の氾濫を防ぐために明治35年に堰堤が作られ、その後、繰り返し堰堤が壊れるので、大正12年に農業用ため池として改修されて出来たのが今の築水池です。きれいな池を眺めていたら水鳥がこちらへ泳いできました。写真を撮って帰宅後調べたら絶滅危惧種Ⅱ類の ホシハジロ です。オスばかり5羽泳いでいました。頭が褐色、胸は黒、目は赤いのが特徴です。トリは詳しくないのですが、絶滅危惧種だとわかったらとても興味が湧きますね。今日は当初の目的地をかえて弥勒山で雪山眺望と小鳥さんと遊びました。すごい人がいっぱいで、春日井三山は地元をはじめ周りの都市からもやってくる人気の山だとわかりました。
2025.01.30
コメント(0)
-

小牧アルプス再訪・・・徹当山から東の山々へ
19日(日)先週は小牧アルプスの東側の山々を歩きました。そして再び、今週は小牧アルプスの西側の山々を歩き、時間が余ったので先週飛ばした東側の東天川山と東山を探してきました。先週と同じ環境センタ―の近くの駐車場に停めて歩き出します。看板の絵地図の現在地から、先週は右の道から、右上の「児の森」を目指しましたが今日は真ん中の北新池の南を通って、左端の道の途中で展望台へ行きます。突き当りの稜線から、地図には書いてませんが久しぶりに徹当山に行って、白山神社へ向かいます。ここから左へ階段を下ります。北新池の向こうに見える鉄塔が、三角点のあるところで、その右の鞍部を越えて尾張白山神社のあるピークです。北新池は 小牧トンボ王国とあり、別名 トンボ池と言われています。トンボ池を過ぎたら、治水堰堤の谷をジグザグに高度を稼ぎぐいぐい登ってゆきます。ジグザグが終わったら落ち葉の斜面を登ります。結構急斜面をまっすぐ登るので暑い暑いと汗かきながら・・・やっと緩やかな道になって休憩舎に到着ここでいっぷく、お茶を飲んで一息します。すぐに展望台に着いて、登ってみますが周りの木が大きくなって何にも見えません。以前、この展望台が出来たばかりの頃は下界が見えたのに・・・しかし、先ほどのトンボ池から見えた鉄塔に近づいたので近く大きく見えます。その右のピークが白山神社のピークです。稜線分岐に到着右に行くと鉄塔のある三角点ですが我らは、左の徹当山へ向かいます。徹当山は鉄塔や反射板がいっぱいありフェンスの横には三角点ではありませんが、「名古屋土木事務所 三級基準点」があります。地面に埋められて落ち葉で隠れていますが、周りは石で囲まれ落ち葉を払いのけたら埋められて金属の円盤が出てきます。奥のフェンス沿いからは、北側の尾張富士(右)と尾張本宮山が見えるのです。先ほどの分岐まで戻って大きな鉄塔のあるピークまで行くと三等三角点「点名 野口」がありここは以前鉄塔が出来る前は、木に囲まれた展望が無い場所でした。今は鉄塔を設置するのに周りの木が切られ、展望が良い明るい場所になりました。お腹がすいたので、写真を撮ったら白山神社のピークに向かいます。ここからこの稜線の中で一番の大下りです。白山神社のピークに向かうのに、この大下りは一番いやなところです。鞍部から今度は、急斜面の登りが始まります。一番の急斜面は、ゆっくりのんびり息が上がらないように、一歩一歩登らないと冬なのに汗が噴き出てきます。白山神社(260m)に到着お社の後ろから以前は入鹿池が見えたのに木が大きくなって見えません。由来が書かれた看板には日本武尊や大山祇命をはじめ大巳貴命などを祀っていると書かれています。登山をする私たちには大山祇命は山の神様ですからしっかりおまいりしましょう。この境内の片隅でお昼ご飯を頂いて再出発です。「児の森」の方に下る途中には、御嶽神社がまつられています。後ろの木の間からは以前は御嶽山が望めましたが木が大きくなって残念ながら、ここから見られません。「児の森」の駐車場に出てきました。車がいっぱい停まっています、今日は何かイベントがあるのかな・・・わくわく小屋の前の広場では、木を伐採してシイタケの菌を打ち込んで、シイタケの原木つくりをやっています。関係者はここまで車が入れるのですね。西山の外周道をのんびり歩いて今日は高社山はなんだか霞んでいますね。この外周の道は歩きやすくて好きです。目の前の奥に天川山が見えています。今日も、天川山を迂回するため林道に出て、しばらく林道をあるいたら鉄塔巡視路の硬質ゴムの階段を稜線に向かって登っていきます。稜線手前は少し藪なところもありますが稜線に出たら右の東天川山へ向かいます。小牧市最高峰の天川山(281m)が鉄塔の向うに見えています。八曾の黒平山が目の前です。鉄塔設置で東天川山の手前は大きく様変わりしています。東天川山(280.8m)昔の写真からここがピークだとわかりましたが以前あった陶器製の山名板は無くなっています。それから戻ろうと思いましたが、せっかく久しぶりに来たので東山のピークを探そうということで古いテープを頼りに探し回ったら東山(273m)のピークも山名板も何もなくなっていましたが以前の写真を頼りにここが山頂だとわかりました。今日はここで戻りましょう。わくわく小屋に向って同じ道を戻ります。ここの景色はやはり好きです。車が一台も無くなった「児の森」の駐車場の片隅で、暖かい飲み物を作って帰路に就く前にいっぷくして先週と同じ階段の多いルートを下山しました。このところ毎週小牧アルプスを歩いています。夜床についたら、天川山を通らずに東天川山に行きたいなとなんだか気になって、心に引っ掛かるルートを確かめたくて今週もやってきました。昔、通れた道が通れなくなったりして天川山に行けなくなって気になって気になって・・・せめて東天川山に行けたら、と思って行ってみました。
2025.01.23
コメント(3)
-

小牧アルプス
13日(月)三連休の天気予報で一番ましな、最後の日の13日月曜日に小牧アルプスの東側の山に登ってきました。小牧アルプスは2015年2月に初めて登りましたがその後2022年まで10回登っています。その名の通り、いくつかのピークがあり、色々なルートでいろいろな登り方が出来るので飽きることなく楽しめる山々です。2015年2月のブログには小牧アルプスの紹介が詳しく書いていますのでまず、そちらをクリックしてみてください。2015年2月11日の小牧アルプスのブログ小牧アルプスの続き小牧市の環境センターの右側の駐車場に停めて歩き出します。すでにたくさんの車が停まっていて、たくさんの人が登っています。少し登ればいくつかのルートの分岐に到着私たちは、看板の右上の「児の森(ちごのもり)」を目指します。天気予報より良い天気で、青空が出て風も無く暖かく登山日和です。自然林の落ち葉を踏みながら、緩やかな階段を登ってゆく2022年12月もこのルートで歩いています。ここから階段ばかりになって階段嫌いの我らは、ヒーヒー言いながら登ることに。階段は続く階段の途中で右側に下界が見え、名古屋駅前のビル群がニョキニョキとシルエットで浮かんでる2022年にはここでお昼ご飯を頂きました。その時は降雪の後で、周りは雪だらけでしたが、暖かいおでんとうどんでお腹の中から暖かくて幸せでした。まだまだ階段次の休憩所これを作った時は展望があったそうですが周りの木が大きくなって全く展望が無く残念ながらあまり利用されていないようです。いったん大下りして登り返したら左は白山神社、右は児の森の分岐です。私たちは右へ行きます、帰りに時間があれば白山神社に立ち寄りましょう。児の森(ちごのもり)の駐車場ここまで車で登ってくるのに、すごい斜面の山道が凍結しているかもと思って今回はここには車で来ませんでした。やはり山の北側斜面は雪が残っています。ここは冬はいつもこの状態です。しかし「わくわく小屋」の周りは暖かいひだまりです。この広場はいつも感じが良くたくさんの人が行きかっています。さて今日はどの道を歩こうかな・・・一番外周のうぐいすの小道を歩いてキツツキの小道から西山へ登ります。途中で、尾張富士のきれいな姿とふもとの入鹿池を見て入鹿池は少ししか見えていませんが小舟でワカサギ釣りをしています。西山までまっすぐの階段登り切ったらいい感じ西山 山頂(265m)鉄塔が出来て山頂付近は木が切り取れられその代わりにススキなど、低木や草の藪になっています。数年もするとまた山に戻るのでしょうね。ムササビ峠この広場はとても感じが良く好きなところです。奥の高いところにあずまやがあります。あずまやの前の温かいところでお昼ご飯にしましょう。木の下の暗いところにあるあずまやの「青空小屋」夏はそこは涼しいのですが、冬は陽の当たるところのほうが暖かくていいですね。今日はおでんと玉子とじうどんです。食事の後は「本堂ヶ峰 276m」山頂とは言え通路のような所です。そこから県有林の境界線を下って小牧アルプスの主峰の天川山(281m)へは行かず、南側の林道に出ます。天川山は鉄塔設置工事で立ち入りがむづかしくなり、天川山、東天川山、東山を迂回するため林道を歩きます。鉄塔工事の時は車両が入るために雑草も綺麗に無くなっていましたが今は雑草の藪になっています。でも、こんな雑草も無い広い道になったりするのです。目標の分岐まで30分くらいかな、と思っていましたがずいぶん歩きます結局、当初思っていた山に入る分岐がわからず安手奈山のNTTドコモのアンテナまで林道を1時間も歩きました。昔はこのフェンスまで山道を通ってこれたのです。すごいきれいな青空にアンテナが映えます。この施設はメンテナンスが行き届いてとてもきれいなままです。安手奈山 山頂(273m)三等三角点「せん谷」があります。帰路に、以前はよじ登った擁壁を見て山の中を戻ります。大木と休憩ベンチこの大木は以前から目印でした。歩いた林道の途中に下りてきて当初考えていた山に入る分岐がどこかわからないまま同じ林道を戻りました。西山の外周を歩きながら八曾が見える展望台で八曾の後ろに雪山(中央アルプス)がうっすら見ることできました。その右に目をやると・・・なんと先週の高社山が見えています。少しズームで秋葉神社を探しながらの下山途中で、採石場の看板がありましたがその採石場が見えています。笠置山の後ろには雪の中央アルプスが見えています。笠置山より左が三ノ沢山から宝剣岳、木曽駒ケ岳の稜線右が濁沢大峰から檜尾岳、東川、空木岳、南駒ヶ岳の稜線です。ズームで右から三ノ沢、とんがりの宝剣岳、ぼんやりしている一番高い木曽駒ケ岳空木岳の右に南駒ケ岳御嶽山は木が大きくなって、見にくくなっています。わかるかしら・・・わくわく小屋の前の広場に戻って来た時は太陽がかなり傾いています。大急ぎで同じ道を戻りますが、白山神社には立ち寄れません。山の中はもう薄暗くなっています。2022年以来、ここには来ていませんでしたがしばらく来ないと山は変わってしまうのですね。記憶も不確かになり、木が大きくなり景色が変わってしまって以前と同じルートがわからなくなっていました。白山神社のあたりはたくさんの人が登っているので変わらないけれど天川山から安手奈山には人が入れなくなっているのです。しかし、この山はいろんなルートを自分のペースで歩けるので今日は小牧アルプスの東側を歩きましたが、西側も近ぢか歩きたいと思っています。
2025.01.15
コメント(0)
-

初登りは高社山・・・三社詣りも
5日(日)あけましておめでとうございます本年もよろしくお願いします。もう初登りされたでしょうかKIKIの今年の初登りは多治見市の高社山です。高社山は今回で3回目だと思っていましたが相棒は3回目で、私は2回目でした。私が初めて登ったのは2014年12月29日でその7年前に相棒は一人で登っていました。今日は下り坂の天気で展望が期待出来無いから、ゆっくり登れる高社山でも久しぶりに登ろうかなんて思っていたら、なんとなんと思いがけず予想外の展望でした。この鳥居の前の広場までは、狭くてすごい急斜面の道を登らないと行けません。駐車場は無く、車は道路端に2台分のスペースしかないのですがここの広場までは勇気がある人しか車を持ってこれません。登山口は幟があるのでわかりますが車を停めるスペースに困ります。幸い私たちが着いたとき、1台の車が出てくれたので停められました。今日は高社神社が初詣です。そして愛宕神社にも詣でます。高社神社の沿革の碑正二位大県明神 大荒田之命を祀っていると書かれています。ここは、サクライソウの自生地ということですが絶滅危惧種のサクライソウは見たことが無くとても興味が湧きますが、夏の暑い時に400mほどの低山はただ暑いだけなので、はたして探しに来れるかどうか・・・有名な牧野富太郎先生が、発見者の桜井氏の名前から命名されたそうです。登り口から急こう配で、ジグザグに登ります。二股に分かれている所で、相棒は左の尾根を歩いて私は尾根の脇を歩きますがこの写真の先で危ないところがあり木で止めていました。下りにはこの道は使ってはいけませんね。尾根に取り付いてホッとしています。この後、下ってきたご夫妻と、しばらく山談義で話が盛り上がりました。地元の方で、こんな良い山が地元にあるなんて羨ましいですね。その先で、右は高社神社、左に行くと愛宕神社と山頂の分岐我らは先に右の高社神社へ向かいます。ヌタバにしめ縄が張り巡らされています。前回来た時もそうで、この山は登山口の鳥居前の広場とこのヌタバだけは記憶していました。その先で愛宕神社と秋葉神社の分岐まっすぐの石段を登れば高社神社山の中にしては広い境内と、石造りの立派なお社です。初詣でお山に登らせていただき、怪我無く無事に下ろしていただく感謝をお祈りして山頂に向かいます。先ほどの分岐まで下りて愛宕神社の方へ向かいます。下の分岐からの道に合流愛宕神社の標識この先で四人家族とすれ違って、他に登ってくる人が居るのですね。愛宕神社二社目のおまいり小さいお社ですが、しめ縄と御鏡餅が飾られています尾根を奥まで進んだら反射板のある展望台多治見の街が一望できます。こんなに良い展望だったとは記憶が無く、はじめての山みたいです。ここでお昼ご飯今日は風も無く暖かく、カップ麺のお昼ごはんを頂きながらゆっくり展望を楽しみました。隣には春日井三山恵那山と中央アルプスも見えています。恵那山は頂上あたりは雲が被っています。少しズームで右の山並みは中央アルプス春日井三山の右奥に伊勢湾が光っています。ランチの後は山頂目指して奥に進みます反射板の後ろは前回来た時は木が無くて広場でした。10年の歳月は、こんなに木が生えています。山頂稜線の雑木林を奥へ進みます。落ち葉はいっぱいですが、ほとんど水平で歩きやすい三等三角点のある高社山山頂(417m)途中で秋葉神社の標識があったのでそちらの方へ向かいます。すぐに秋葉神社は有ると思っていました。この先砕石会社の私有地があるようで、有刺鉄線で止められています。左の斜面を下るように看板が有ります。滑りやすい落ち葉の斜面をどんどん下って、谷底から隣の斜面を登り返す踏み跡があるのでその急斜面を登りながらどのあたりで引き返そうかと考えていました。秋葉神社が斜面を登り切ったこのピークに有るものだと思って頑張って来たのに何もありません。山頂からかなり下ってしまって、引き返すにはすごい登り返しです。相棒と相談して、もうこのまま一か八か下るしかありません。どこかの登山口に下りてから、登った登山口まで下の道を歩く覚悟です。山頂の愛宕神社と高社神社の看板が出てきました。秋葉神社はどうなったの????急斜面をひたすら一直線に下ります、反対に登るのは大変な斜面です。どんどん一般調子で下ったら、やっと秋葉神社の看板あきらめなくてよかった~~と笑顔が出ます。しめ縄と御鏡餅の飾られた小さな祠におまいりして三社詣りが出来ました。さらにどんどんくだったらすごい展望地へ御嶽山と乗鞍岳御嶽山のズームすごい雪です。先ほどよりきれいに雲が無くなった恵那山恵那山のズーム笠置山の向こうに中央アルプス三社詣りが出来た上に、御嶽山や乗鞍岳、恵那山が見えました。結局、50mほど横に下りてこれました。知らない集落に下山して歩く覚悟をしていましたが登りの登山口のほぼ横に下山出来て、三社詣りもできて周回も出来たのでこれは年の初めからすごいついてたね~ととてもうれしいことと大喜びでした。久しぶりの高社山でしたが、とても良い展望でおまけに三社詣りできて今年の初登りはとても素晴らしい登山になりました。今年もたいした山には登れませんがのんびりゆっくりマイペースで登ります。また「KIKIの山行き」ブログに遊びに来てくださいね。
2025.01.06
コメント(4)
-

広幡町の八幡宮から物見山へ・・・今年最後の冬の散歩
正月飾りの門松の飾られた広幡の八幡宮29日(日)今年最後の冬の散歩に出かけたのは豊田市の広幡町の八幡宮から海上の森の物見山でした。ここ一ヶ月は毎週、海上の森のあちこちへ出かけ特に物見山には色々なルートから登りました。一年の最後はやはり、この間下山地にした広幡の八幡宮から物見山にしようということで、八幡宮の駐車場からスタートです。この八幡宮から登るのは今回で三回目初めて登ったのが2018年2月で西広見三角点経由で物見山へ登りました。2回目は2024年1月に西広見三等三角点にだけ登り先週は胸形神社から西広見三等三角点に登経由で物見山に登りこの八幡宮に下山して椀貸池の駐車場まで周回しました。予想以上に良い天気になりました。八幡宮の石段を登ります。先週はここに下山してきて、この石段のあまりの急こう配に怖気づいて車道を下りたのでした。登りなのでゆっくり一歩一歩慎重に登ります。ここまでは、まだこう配はましですがこの先からまるでオーバーハングしているかのような傾斜です。おまけに写真ではわかりにくいのですが奥行きが20センチ位で、靴の長さより短くて足を斜めに置かないとはみ出るのです。最後の62段は怖くてヒーヒー言いながら登りました。転んだら一気に下まで落下します。この階段はお年寄りには危険な階段です。登りに使っても、下りに使うのは命がけですね~~登り切ったら、正月の門松が飾られた立派な社殿に参拝して今年一年無事に山に登れたお礼をして境内はかなり広く風格のある八幡宮です。奥にある津島神社(右から二つ目 天王社)おまいりをして尾根を進みます。落ち葉で埋め尽くされた明るい尾根このルートは面白いマーキングがいっぱい赤いスプレー缶が見えたら稜線が近いのです。勝手に名付けたインデアンののろし場ここからは海上の森の外周の稜線歩きです。物見山登山道に合流今までは誰にも会わなかったけれど合流したらたくさんの登山者に出会います。聖徳太子の古墳の一本のモミジ落葉していますが、まだまだ頑張っています。物見山山頂(327m)今日は底冷えするほどの寒さです。ここにはベンチも有りますが、寒くて誰も食事していません。4.5度ですが、奥の木陰にもう一つ寒暖計がありそれは3度でした。寒いはずです~~物見山山頂のシンボルツリー 「アズキナシ」です。小豆くらいの大きさの実がいっぱい落ちています。いつもとは違う方向から写真を撮ってみました。寒いので写真を撮ったら早々に下山します。聖徳太子の古墳にはサカキと御鏡餅が供えられています。いつもの支尾根でお昼ご飯を頂いて後は同じ道を戻ります。インデアンののろし場に戻ってきました。ここから八幡宮へ来た道を下ります。津島神社に戻って来た報告をして八幡宮へ戻り帰りのついでに、先週の胸形神社に立ち寄って年末のおまいりをしてきました。胸形神社も正月飾りの門松が飾られて、お正月の準備万端です。ここでもこの一年無事に山に入り戻ってこれたお礼とまた来年も登らせていただくことをお祈りして、一年の締めくくりをしました。今年は夏にコロナに罹患して、不本意な夏でしたが怪我も無く、楽しい山歩きが出来たので良しとしましょう。冬は近場の散歩でお茶を濁していますが毎週のように山に入って心も体もリセットしています。同じような里山をウロウロして目新しさがありませんがいつもブログを見てくださってありがとうございます。また来年もよろしくお願い申し上げます。
2024.12.30
コメント(2)
-

椀貸池から西広見三角点と物見山
22日(日)今年も残り少なくなりました。今週と来週で山行きも終わりです。このところ3回続けて物見山へ行っています。今回は豊田市広幡町の椀貸池の胸形神社から西広見三角点経由で物見山へ、そこから広幡町の八幡神社へ下りてきて舗装道路を歩いて椀貸池まで周回してきました。椀貸池は改修工事中でフェンスに囲まれ水が抜かれています。だから、池の方には行けず、胸形神社の参拝者用の仮設階段を道路からダイレクトに登って神社まで歩きます。胸形神社参拝してトイレの横から山へ。初めは踏み跡が薄く、テープも無いことからもしかして違うのかと思って神社本殿まで戻ってウロウロ登山口を探し回りました。しかし本殿の周りには山に入れるところも無く結局、もう一度トイレの裏から山に入ることにして落ち葉で踏み跡が無いまま、第六感だけで歩いてゆきます。フカフカの落ち葉に埋まって歩きにくいルートを10分ほど歩いて行って初めて、赤テープを見つけてたまにある古い赤テープを頼りに何とか進んでゆく落ち葉がいっぱいで踏み跡は全く隠れています。テープが無ければここは歩かないと思うほどの背の低い笹の藪藪が終わったら目の前のピークが西広見三角点だと思うけど斜面が急傾斜になり、足首まで埋まるほどの落ち葉で滑りやすくて踏ん張りがきかずズルズルと滑ってしまい、最後に苦労しながら登ることに。途中から直登するのをやめて、右へ回り込んで山頂へ西広見三角点(236m)に到着ルートを直登すると三角点ピークには、ここにたどり着くのです。(私はあまりの急斜面なので、回り込んだのでここにはたどり着いていません)やはり毎回思うのですが、西広見三角点は風の通り道で寒くて写真を撮ってすぐに再出発石の門物見山からの登山道に合流してインデアンののろし場枯れた木ののろしのモニュメントの修理をしています。物見山に登って、ここから広幡の八幡神社まで下るのでまたここに戻ってきます。物見山の登山道に合流この後は登山道から外れて、支尾根の温かいひだまりで一時間ほどかけてお昼ご飯をゆっくり頂いて再び物見山に向けて歩きます。山頂直下の聖徳太子の古墳と言われる場所モミジが盛りを過ぎて落葉していますが、まだまだ綺麗です。物見山山頂(327m)今日は遠くの遠望があまり良く無く伊吹山や鈴鹿の山々は見えません。名古屋の駅前のビル群今日は5度です、風が吹いてメチャクチャ寒い体感温度はもっと低いです。同じ道をインデアンののろし場まで戻ってきました。再び枯れた枝で修理しましょうここから、広幡の八幡神社に向けて支尾根を下ります。このルートは赤テープがあるのでわかりやすいフカフカの落ち葉で足が埋まっています。緩やかに登ったり下ったりの起伏を下って最後のピークが目の前に・・・津島神社のピークです五つの祠が祀られています。右端に五社の名前の紙があります。一つ一つお参りをして石段を下って全景八幡神社の境内は広く本殿はもう門松が飾り付けられ、お正月の準備が出来ています。(正面からの写真はピンボケでありません)本殿参拝後、階段を下ろうと思いましたがメチャクチャ急斜面で石段の幅も狭いのでやめて津島神社と八幡神社の間の車道を下ります。八幡神社鳥居をくぐって集落の舗装道路を30分ほど歩いて、椀貸池まで戻りました。今日は海上の森の外周の西広見三角点と物見山をつないで冬の散歩をしてきましたが椀貸池からの西広見三角点は初めてのルートで相棒は、初めてのルートを探しながら歩くのが楽しかったと大満足でした。久しぶりに、ルート探しにチョット緊張しながら歩くのも新しい刺激になって、だらけた脳に良いと思います。テレビで学者が、一週間に一回ぐらい森のキャンプが体に良いと言っていました。森の木から出るフィトンチッドとやらの成分が良いそうです。30年間毎週山に入って、マイナスイオンやフィトンチッドを浴びたり吸ったりしているのは体に良いのですね~~これからも山の中の徘徊を続けていきたいな。
2024.12.25
コメント(0)
-

西広見三角点と物見山・・・瀬戸の海上の森を徘徊
15日(日)このところ毎週土日はあまり天気が良く無くおかげで近辺の里山巡りでお茶を濁しています。瀬戸の海上の森は色々なコースで歩けて、自分の好きな時間で歩けるので冬にはちょうど良い散策地です。今週も天気が今一つなので、近場の瀬戸の海上の森にしました。先週も歩いて二週続けてなので、今週は豊田市との境界上にある西広見三角点と物見山のセットです。まず、あいち海上の森センター本館の駐車場に車を停めて先週と同じ吉田川沿いを歩いて五差路を目指します。今日は寒くて風も強いのでさすがに車は先週より少なくそれでもすでに歩いている人が居るのでしょう。吉田川沿いのここから山に入っていきます。五差路物見山登山口急斜面になったら、登山道から離れてかすかな踏み跡を西広見三角点へここは一番気を遣うところです。初めて西広見三角点へ行ったときは、吉田川の源流を遡り笹藪漕ぎをして行ったものですがそこのルートの入口に通行止めのロープが掛けられそのためよけい笹藪がひどくなったので反対に西広見三角点から物見山へのルートを探し今回はそのルートを、物見山登山道から外れて西広見三角点へ目指します。いつもの登山道になりホットしている所私が名付けたインデアンののろし場立て掛けている木がだんだん朽ちてきて、狼煙が小さくなったような気がします。石の門このルート上にはあまり石が無いのでとても特徴的です。この後、二差路を左の尾根に乗ってわかりにくい尾根の交わった所を右へピークを一つ越えたら二つ目のピークが西広見三角点(236m)のピークです。ここはいつも風が強くて、メチャクチャ寒いところです。今日も写真を撮ったら大急ぎで下山します。次の物見山へ向かう途中で暖かいひだまりを探してそこでゆっくりランチタイム今日はカップ麺とおむすびとウインナ―炒め。風も無く暖かいのでゆっくり食後のドリンクも頂いて冬の散歩はこれが一番楽しいね~~と言いながらのんびり休憩食後は完全武装のまま物見山へ向かいます。午前中物見山への登山道から外れて、西広見三角点へ行ったところまで戻って物見山へ取りつきます。山頂直下には厩戸皇子の古墳と言われる岩が転がっている所にはきれいなモミジが一本、紅葉の盛りです。落葉の一枚も無いので、今が最盛期で先週よりも綺麗です。物見山山頂(327m)山頂には誰もいません。私たちを追い越していった男性が二人いましたが周回するのか、猿投山の方へ行かれたのか・・・先週は5度でしたが、今日は6度ですが風が強く体感温度はもっと下です。名古屋のビル群を見て、今日は同じ道を下ります。途中で、先週ランチした支尾根を探したりしながらのんびり下山しました。毎週のように土日の天気が、北の方はあまり良く無いので瀬戸の海上の森の散歩ですが山の中の暖かいひだまりを探して、そこでのんびりささやかなお昼ご飯を頂くそれだけで命の洗濯をして、心もリセットできます。30年もこんなことをして過ごしてきました。いつまでできるのかわかりませんが、いい趣味に出合えたと思ってます。
2024.12.17
コメント(2)
-

瀬戸の海上の森・・・万博の開発から逃れて
8日(日)お天気はどこもあまり良くないので、近場の瀬戸の海上の森(かいしょのもり)と物見山に行くことにしました。2018年11月、鈴鹿の山で骨折した後リハビリで歩いたのが瀬戸の海上の森でした。松葉杖を突きながらゆっくり歩いていたら、小学校3~4年世くらいの男の子が駆け寄ってきて私の正面に立って、「おばあさん長生きしてください」と言って走っていきました。私は「ありがとう」と答えながら、呆然と見送りました。心優しい少年のやさしい、いたわりの言葉はうれしかったけど、「おばあさん」や「長生きしてください」、とは私はどれほどの年齢に見えたのでしょうか・・・今でも海上の森に来たら思い出すのです。海上の森は愛知万博の会場になるはずでしたがオオタカの営巣が見つかって、保護するために開発から逃れて自然のまま残されることになった貴重な森なのです。おかげで身近に自然に触れ合える貴重な森として私たちハイカーにはありがたい森なのです。駐車場に到着したら、急に雨が降ってきて30分ほど車の中で待機して雨が止むのを待ちました。雨が止んだら青空が出て、今日は変な天気です。あいち海上の森センター本館の駐車場に車を停めて吉田川沿いの道を歩きます。名も無い池を左に見て広久手第2池(赤池)の手前を、左の山へ入ってゆきます。五差路に到着今から物見山へ向かいます。物見山登山口ところどころ段差のある登山道雨でぬれている木の根は滑るので、踏まないように気を使いながら日が差して、さっきまでの雨は嘘のよう岩がゴロゴロ出て来たらここからはもっと急斜面をジグザグ登りです。木の根と段差で、迂回しながら少し斜度が緩くなって、歩きやすくなりました。しかし寒くて、稜線上は風も強くてお昼ご飯をどこで食べようかと悩みながら歩いて登山道から外れて、風の来ない日当たりの良い支尾根まで下がって、そこでゆっくりランチタイムです。しかし、食後歩き出して再び登山道に戻ってきたら寒いこと!!慌ててマフラーをすっぽり頭から被って防寒対策です。再び歩き始めたら、山頂直下に厩戸皇子(聖徳太子)の古墳と書かれています。登山道で唯一のモミジの木があります。物見山山頂(327m)山頂の手前ですれ違った女性は、雪が降って山頂に到着した時はメチャクチャ寒かったとその時は気温が0度だったと言っていました。今は5度です。風の無い暖かい支尾根でランチをしている時少し雨を感じたのですが、木の下だったので濡れなくてその時山頂では雨が雪に変わっていたのですね。私たちが支尾根に行かずそのまま、山頂に向かっていたら昼ごはんは寒い山頂で食べられず、震えあがっていたことでしょう。山頂から瀬戸の街と左奥に名古屋のビル群です。意外にはっきりと見えています。足元に目をやったら次に向かう「里山サテライト かたりべの家」が見えています。ズームで移築した古民家です。山頂から同じ道を下りずに、林道の方へ下ります。登山道とほぼ平行にあるグニャグニャの林道を下ります。去年には無かった砂防ダムがいっぱい作られています。それほど急斜面ではないけれど、すごい公共投資がされています。瀬戸は財政が豊かなのかな?それとも愛知県が豊かなのかな?弘法堂弘法堂の横の柵ごしに農村風景が広がっています。庭の鈴なりの柿が見事です。かたりべの家から、先ほどとは反対に物見山を見て暗いところが物見山山頂海上川沿いを四ツ沢にむかって、舗装道路を歩きます。ここから図根三角点に向かって登りこのピークが図根三角点があるピークです。図根三角点のピークから太陽が西に傾いて景色を赤く染めています。向うに見えるのは岩巣山名古屋のビル群瀬戸市の街稜線を歩いていたら、物見山(左)が見えました。先ほどまであそこにいたのです。太陽が傾いて、もうすぐ陽が落ちます。赤池のモミジの大木駐車場に戻る前に、赤池のモミジの大木を見に立ち寄って17時閉門の30分前に戻ってきました。朝は雨で待機をしていましたが、ほぼ一日海上の森で遊べて私たちには貴重な自然が残っていてありがたいことです。今日はこの冬一番の寒さで、いよいよ冬の防寒対策が必要になりました。
2024.12.10
コメント(0)
-

水晶山と竜吟の滝・・・紅葉の竜吟湖の周回
1日(日)岐阜県瑞浪市の水晶山と竜吟の滝に行ってきました。ここでも思いがけず名残の紅葉に出会えてチョット得した気分です。竜吟の七滝の入口青空と紅葉がお出迎え沢沿いのモミジはすでに紅葉が終わり、葉っぱが落ちてしまってるけど入口のモミジはまだまだ綺麗です。しかし昨日でモミジ祭りは終わり、夜間照明などを片付けています。でも、まだまだ綺麗な紅葉が残っていて嬉しい~~~一の滝二の滝三ノ滝の手前で、右の斜面を登ってゆきます。ここでも階段状の登山道沿いにモミジが残っています。振り返って途中のあずまやから山頂が見えています。アカマツが数本見えている所が山頂この後分岐を、いつも山コースで登ります。ロッククライミングの岩場が見えてきたら今日は、そこから山頂へ直登します。すぐに単独の女性に追いつかれて、その人に先を譲って私たちは私の膝のペースに合わせて登ります。急斜面をがむしゃらに登れば、あと少しで山頂山頂直下の岩場今日は、雪を被った恵那山(右)も中央アルプス(左)も見えています。山頂広場水晶山山頂(459m)思ったより登っている人が少ない中央アルプス雲が多くて山座が同定できません。恵那山もうっすら雪を被ってきれいです。私たちがお昼ご飯を頂いた場所は山頂広場の東南端で写真からは絶壁の横みたいに見えます。確かに、この岩のすぐ後ろの岩から下は絶壁です。単独の男性が登ってきて、しばらく山談義をしてかなりゆっくり昼休憩を取り次は竜吟湖の周回ハイキングに向かいます。今まで何度も来ていますが、竜吟湖の周りは歩いたことがありません。もらったウォーキングマップに湖コースが紹介されています。周囲2.3Km50分 手ごろなので寄り道しましょう。山頂から「やすらぎの小径」「こもれびの小径」を通ってトイレの横を湖の方へ一軒の民家の前の道を通って湖の縁の周回コースです。意外に道幅が広く、雑草がモシャモシャしている所は無くとても歩きやすい湖に注ぎ込んでいる沢を眺めて思いがけない名残の紅葉に癒されて貸切の紅葉狩りです誰にも会いません~~~モミジを独り占め相棒は今年初めての紅葉だと喜んでいます。とても贅沢な瞬間でした湖に下りられるところで水晶山を眺めて湖の端っこの堰堤が見えてきましたほとんど一周して、七滝巡りの道に下山します。滝沿いの道へ合流しました。梵天の滝昇竜の滝少し紅葉も残っていますあんま滝どこがあんまなのかわかりません。最近の若い人は「あんま」はわからないでしょうね。えびす滝これもどこが「えびす」なのかわかりません。縁結びの樫途中で繋がっています、とても珍しく、どうしたらこうなるのか?三の滝別の場所からの 三の滝七つの滝巡りをして登山口に下ってきました。竜吟岩今まで木に覆われていてよく見えなかったけれど周りの木を切ったので、岩の全体がわかるようになりました。すごい一枚岩でほぼ垂直です。地元の人が、この岩を使って町おこしを考えているようです。今までと違うルートで山頂にも登ったり湖の周回で名残の紅葉をたっぷり見ることもでき一日遊んで命の洗濯が出来ました。30年近く毎週こんなことをして、気分転換できるのは幸せなことです。元気で自分の足で歩いて山に登れるというのはこの上ないしあわせ、ささやかですが、何にもかえがたい幸せです。
2024.12.06
コメント(2)
全1343件 (1343件中 1-50件目)
-
-

- 登山をして、自然や景観に関心を
- 秋の日向山(1,660m)山梨百名山(後編…
- (2025-11-20 06:00:18)
-
-
-
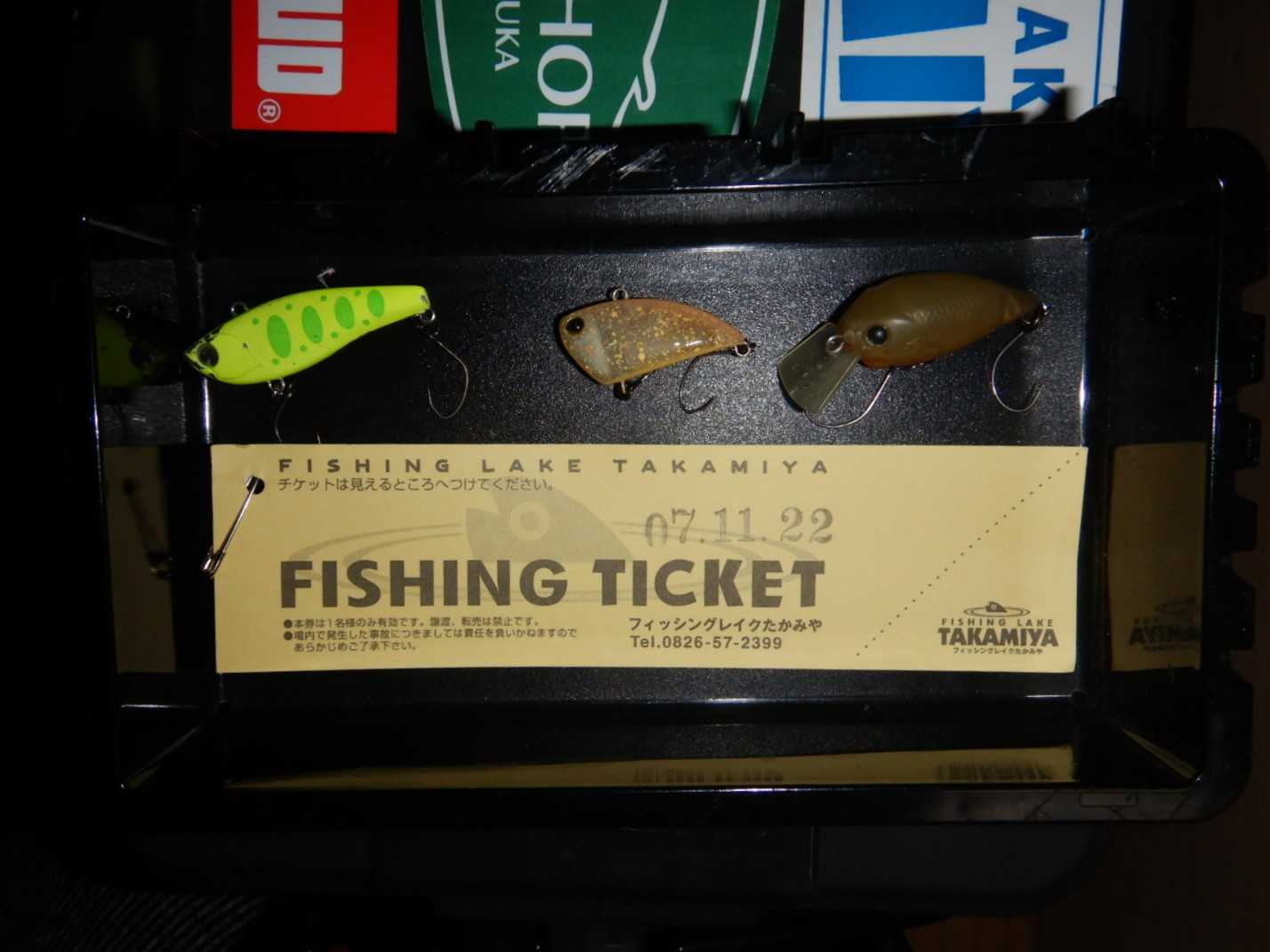
- 管理釣り場のルアーフィッシング
- かなり厳しかった
- (2025-11-26 18:30:07)
-
-
-

- 海釣り・船釣り
- 津久見の港へアジ・アオリイカ釣りに…
- (2025-11-21 22:18:34)
-







