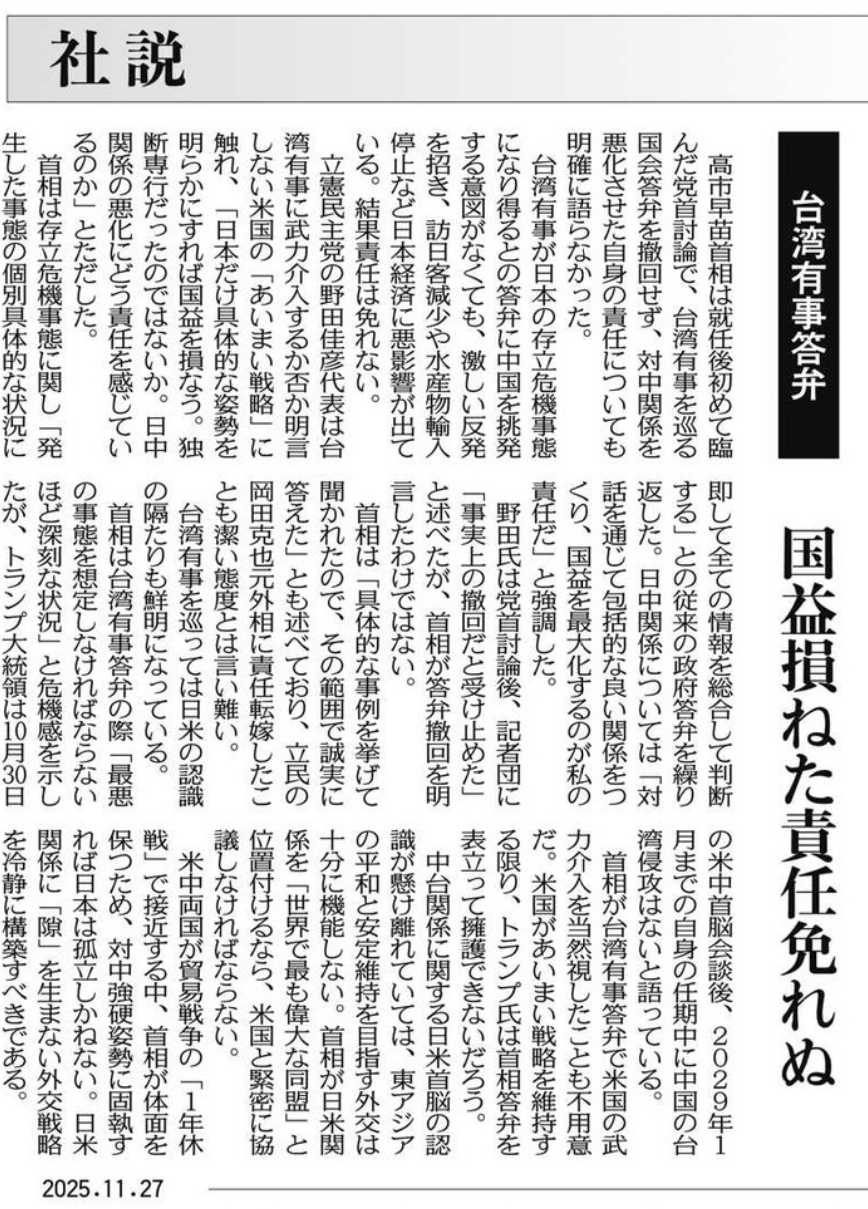2019年02月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
大道芸
大学は一応、春休みになだれ込み、今日も比較的のんびりした日だったので、お昼休みを利用して少し足を延ばし、近くの梅園に行って梅を見てきました。 ま、それはいいのですが、たまたまそこに大道芸の人が来ていて、火のついたスティックでジャグリングなどをしておりまして。 で、人垣になっていたので、つい私も見てしまったのですが、まあそれなりの内容で。 しかし、私が感心したのはその大道芸人の最後のパフォーマンスですわ。 大道芸で何が難しいかというと、多分、芸を見せた後、最後に観客からお金を取るところではないかと思う訳ですよ。芸を見せるだけなら誰でも出来るけれど、お金を取るとなると、これはまた別問題。勝手に芸をしているのだから、その芸に対してお金を払うかどうかは観客次第。下手をしたら、芸が終った途端、観客が輪を解いてどんどん帰ってしまうかもしれない。その時、どうするか。 ところが、今日見たその大道芸人は、そこが徹底していたんです。 まず、最後の芸(久寿玉割)は取っておいて、その最後の芸をやる前に、自己紹介をする。高校卒業後、大道芸一本で飯を食っていると。これでお金がもらえなかったら、自分は飢え死にするんだとハッキリ言う。そして、大道芸をやる時は、果たしてお客さんが来てくれるかどうか毎回ものすごい不安を覚えると告白する。 それなのに、今日はホントに心温かい観客に見ていただくことが出来て、本当に自分は幸せだと。それを大げさに涙を流して語るわけ。 それがあまりに大げさなもので、観客誰もが「これは芝居だ」と分かるわけですよ。だけど、それをあまりにも恥ずかしげもなくやるものだから、逆に大衆芝居を見ているような面白さを感じてしまう。 で、そういう愁嘆場をひとくさりやった後、締めの久寿玉割をして、それでお金を集め始めるのだけど、その際も、「お金は畳んで袋にお入れ下さい」などと暗にコインではなく札をくれとほのめかす。で、本当にお札を入れる人がいると、そのお札を高々とかざして、「これが見本です!」などと笑いを取る。 まあ、逞しいもんですわ。だけど、芸を見せて、泣いて見せて、笑わせて、それだけド派手にやれば、観客も「まあ、面白かったから、少しはずむか」という気にもなる。 でも、ここまでやって大道芸もプロと言えるのだろうなと。だからワタクシも、プロの芸を見せてもらったということで、おひねりをあげてきました。勉強させてもらったからね。 というわけで、今日は思わぬところで思わぬ勉強をさせてもらった日になったのでした、とさ。
February 27, 2019
コメント(0)
-

ピエール・ルメートル『悲しみのイレーヌ』を読む
忙中閑有。珍しくフランスの刑事もの小説を読んでしまいました。ピエール・ルメートルという人の書いた『悲しみのイレーヌ』というのですが。 実は家内がこの作家の書いた『その女アレックス』という小説を読んですごく面白かったそうで、それよりも前に書かれた『悲しみのイレーヌ』を続けて読んでみたら、こちらも面白かったと。で、そんなに面白いのなら、私もこの二作を書かれた順に読んでみようと思って、まずは『悲しみ』の方から読んでみた次第。 何しろ刑事もののサスペンスですから、あまり細かくその内容を明かすわけにはいきませんが、確かに結構面白かったです。 ま、最初はちょっとグロいのよ。猟奇殺人というか、女の人がすごい殺され方をするので。 で、カミーユという刑事が、この事件を追い始めるのですが、その過程で、どうやらこの殺人事件は、殺人を描いた小説の殺し方を正確になぞったものであることが分かって来ると。で、第二、第三の殺人事件も、それぞれ別な殺人小説の通りの頃され方をしている。 とまあ、そんな感じで、犯人は次にどの小説をなぞって人を殺めるつもりなのか、それを阻止する方法はないのか、と、捜査が進んでいく・・・ ・・・のですが! この小説の5分の4くらいを占める「第1部」を読み終わって、「第2部」に差し掛かったところで、読者は驚愕の事実を知ることになる・・・。 その辺りのことは言えねえ、言えねえ! ま、小説の結構として、なかなか面白い構造になっております。 さて、せっかくこの小説を読破したので、その後日譚ともいうべき『その女アレックス』の方も読んでみようかな。悲しみのイレーヌ (文春文庫) [ ピエール・ルメートル ]その女アレックス (文春文庫) [ ピエール・ルメートル ]
February 26, 2019
コメント(0)
-
アカデミー賞
先ほどまでアカデミー賞授賞式の模様を見ていたのですけど、作品賞、『グリーンブック』でしたね。まあ、これがとるか、『ローマ』がとるか、あるいは『女王陛下のお気に入り』がとるかと思いましたが。 『グリーンブック』、『ローマ』、『ブラック・クランズマン』あたりは早く観たいものですなあ。あと、『バイス』も、クリスチャン・ベールの鬼気迫る演技が見たい。 しかし、あれだよね、『ボヘミアン・ラプソディ』も『グリーン・ブック』も、『バイス』も、『ブラック・クランズマン』も、みーんな実話じゃん。ゼロからのフィクションでいい映画って、もう作れないの? そこがね。物足りないなと。 あと、このところ監督賞とるのメキシコ人監督ばっかりだよね! ま、いいけど。 あと、今回の授賞式は「司会なし」でしたが、これも、ちょっと物足りなかったかな。毎年、司会者のキツいギャグを楽しみにしていたもので。 あと、受賞者がスピーチする際、紙に書いたものを読み上げるのって、ちょっと興醒めだよね! それにスピーチの内容も、人の名前を読み上げるのばっかり。関係者全員に感謝する必要はあるのだろうけど、こちらとしては、聞いたこともない人たちの名前を読みあげられてもねえ。 とまあ、色々物足りないところはありましたが、それでもやっぱり観てしまうのは映画好きの性でありまして。 ともかく、これから受賞作品が日本でも公開されていくので、それを楽しみにすることにしましょうかね。
February 26, 2019
コメント(0)
-

追悼・小宮路敏先生
昨年(2018年)11月14日に、玉川学園小学部で音楽の先生として長年教鞭を執られた小宮路敏(こみやじ・びん)先生が亡くなられたということを、今日になって知りました。先生は1936年1月のお生れですから、享年82ということになります。 私は小学校時代に先生に音楽を習ったわけですが、本当に素敵な先生でした。すらっとバランスのとれた細身の体躯、やや天然パーマ気味な髪の毛をきれいに整えられていて、お顔立ちは面高で鼻が高くハンサムで、服装はいつも洗濯したて、アイロンかけたての真っ白なパリッとしたシャツを身に着けられて、まるでお洒落なイタリア人の音楽家のようだった。 そして何よりも素敵なのは、その笑顔! いつもニコニコと明るく優しく微笑まれていて、私は笑顔以外の先生のお顔を思い出すことが出来ない。 でまた、先生の音楽の授業が素晴らしくて、生徒たちが音楽室に入って来ると、すかさず先生が軽快なピアノを弾かれるので、授業の時間が始まる前に、我々子供たちは歌いながら席に着く。もうその時点で我々は歌う気満々で、歌う楽しさ、音楽の喜びが子供の胸にまで入り込んでしまう。 そして、先生の授業は、子供たちに飽きる隙間を一瞬たりとも与えないんです。慣れ親しんだ歌を立て続けに二、三曲、楽しく歌ったかと思うと、次は新しい歌を口伝えで一節ずつ教えてくださり、ああいい歌だなと思う間もなく、次は縦笛の練習となり、合奏となり、時に見本となる外国のオーケストラの演奏をレコードで聴かせてくれ、そして最後はやはり皆で歌を歌い、ああ楽しいなと思っているうちにあっという間に授業が終ってしまう。そして音楽室を後にする時には、先生がピアノを弾いて名残惜しい気持の我々の背中を押して下さる。この間、先生の笑顔と、我々を励ましてくれる温かい言葉と、思わず元気になってしまうようなハイテンポでリズミカルな授業運営に、我々はあたかも魔法にでもかけられたように音楽の楽しさを堪能するのが常でありました。 あんなに楽しい音楽の授業なんて、日本中どこを探したってないでしょう。 それから大分歳月が経過し、たしか今から10年くらい前のこと、私の大学での教え子のSさんが、卒業後に小学校の教員免許を取ることになり、玉川大学の通信教育で学ぶことになったのですが、通信教育と言っても年に何度か「スクーリング」というのがあり、実際に玉川学園まで出向いて対面授業を受ける必要がある。 で、かつて私が学んだ学び舎にSさんも短期間ながら通うことになったわけですが、その頃、小宮路先生は、玉川大学の講師として大学で音楽を教えてもいらしたので、ひょっとして先生の授業を取る機会もあったのではないかと思い、後でSさんに尋ねたんです。「スクーリングで、小宮路先生の授業を取らなかった?」と。 するとSさん曰く、「取りました!」と。そして、こんなに素晴らしい音楽の授業は初めてだった、と。 久しぶりに小宮路先生のお噂を耳にし、私もとても嬉しかったことを思い出します。 玉川学園を定年で去られた後、小宮路先生が「牧心塾」という私塾のようなものを開かれ、ここを活動の拠点として、後進の指導に当られているというのを風の便りで聞いて、まだまだお元気なのだなと思っていたのですが、昨年の秋ごろ、玉川学園に勤める友人から「小宮路先生、身体の具合があまり良くないようだ」ということを聞きまして。 でもその後の話を聞かなかったので、持ち直されたのかなと勝手に思っていたのですが、今朝、ふと気になってネットで調べたところ、小宮路先生ご逝去の報が出ていて、それで遅まきながら先生が昨年の初冬に亡くなられたことを知った次第。 ああ、ついに、と思って色々、ネット上で検索を繰り返すと、やはり先生のお人柄を慕う人は多いらしく、先生の思い出が様々に語られております。その中で一つ、小宮路先生が現役の先生でいらした頃、指導ノートの裏に書いて座右の銘にしておられた一文が載っていたので、以下、それをここに再録します。 「神様 今から子供達の前に立ちます音楽する心をまちがって伝えることがないように導いて下さい。あらかじめ曲を選び、その時になってあわてるような醜態を演じることがありませんように。音楽の時間の雰囲気をやわらかいものとすることができますように。緊張から支配し、表現したいことの半分もできなかったと子供達に後悔させることがありませんように。まず、自分自身がすべてを主にゆだね楽な気持ちでその場にのぞむことができますように。いたずらに先を急いだり、子供達に無理を強いたり、いいわけをしたり、急に笑ってごまかしたりすることなくいつもゆとりをもって子供達から才能を引き出すことができるように知恵を与えて下さい。もし、よい表現ができず、結果が出ないまま別れるようなことになってもなおそこに神様がおられひとりひとりの心を開いてくださったと信じ次に備えることを得させてください。主にあって!! アーメン」 これを読んで、私は絶句します。私が子供の頃、あれほど楽しんだ音楽の授業、あの毎回の明るくほがらかな授業の前に、小宮路先生がこれほどの覚悟をされていたとは・・・。そして、授業がうまく行かなかった時でも、そこに神が居られたと信じる強さを持つことを、ご自身に課せられていたとは。 まこと、小宮路敏先生は、玉川学園小学部の最も良い時代を体現された唯一無二の先生でありました。ここに謹んで、先生のご冥福をお祈りいたします。合掌。【中古】 歩いてゆこう / 小宮路 敏 / 玉川大学出版部 [単行本]【メール便送料無料】
February 24, 2019
コメント(4)
-

大須散歩2
昨日、大須にある「バナナレコード」という中古レコード・CDの店でビーチボーイズの『フレンズ』というアルバムを買ってきて、昨日から聴いているのですが、なかなかいいよ。サーフィン系の音楽ではなく、もっとずっとしっとりした感じ。編曲や楽器の選択にブライアン・ウィルソンの才気は十分に感じられるし、ビーチボーイズ特有のコーラスの美しさもある。面白い。Beach Boys ビーチボーイズ / Friends / 20 / 20 輸入盤 【CD】 ところで、何で大須でビーチボーイズかと申しますと、先日、たまたま大須の近くに行く用事があって、そのついでに大須界隈を少しだけ散歩した結果、予想外に面白かったものですから、このところ大須に興味津々なのよ。名古屋の周辺の町の中では、ここが一番面白いというのは前から言われていることですけど、今更ながら、大須にはまるというね。 まあ、感じとしては、雰囲気的に下北沢にちょっと似ているかな。下北沢をアーケード街にしたら、大須になる、みたいな。やたらに古着屋とかあったりして。それでいて、若者だけの町でもない、というところも含め。あと、劇場も近くにあるしね。 そう、それで昨日、今度は大須を散歩するというのを主目的にここに行ってしまったと。 それでまず「メガ・ケバブ」という店でケバブサンドで昼食をとり、そこからブラブラとお散歩。途中で納屋橋饅頭の「揚げまん棒」みたいな、バエる甘味を買い食いしたりしながらね。で、古着屋を見たり、先ほど言ったバナナレコードでCDを買ったり。あと、ここは中東とか東南アジア系の食材店なんかもあちこちにあるので、そういうところで変わったスパイスを入手したり。 そして、松屋コーヒー本店でちょっとコーヒーブレイクしたり。 溶けたチーズがビヨーンと伸びる韓国風ホットドッグ「ハットグ」を食べたり。 あと、時計屋さんもあちこちにあるので、私が興味津々の「セイコー5」のカッコいい奴を探したり。 そして、大須ベーカリーで美味しそうな菓子パンをゲット。さらに「オッソ・ブラジル」というブラジル料理店で有名な鶏のローストをまるまる一羽分をゲットして、これは帰宅後の夕食のおかずに。 とまあ、そんな感じで半日、面白く過ごして参りました。それでも、まだまだ行ったことのない店、行ってみたい店が沢山あるので、もう1,2回、散歩に行ってもいいかなあ。 次はあれだな。「猫飛横丁」なる古本屋にも行ってみたいな。
February 23, 2019
コメント(0)
-

処分した本を買い戻したい!
2年ほど前に、研究室に置いてあった自分の本をかなり大量に処分したことがありまして。もう、書棚に三重に本を置いてもスペースが無くなってしまったもので。 私は基本、本を処分するということがないので、その時は自分としてはかなり思い切ったことをしたわけでありまして、それによって発見もありました。 本を処分するということは、ある時代の自分自身の記憶や、ある時代の自分が抱いていた希望や野心を捨てることに等しいのよね。そういう、自分にとってはかけがえのないものを、人生の残りの時間と天秤にかけて、「もうこの本と関わることはないな」と判断する切なさ・・・。これを味わうのも、一つの人生勉強かなと。 だ・け・ど・・・。 あとから考えて、「アレ、捨てなきゃよかった~!」と後悔することが結構ある。実際、もう何度もありました。 で、昨日もそういうことがありまして。 卒論審査が終った後、同僚と大学の近くの美味しいうどん屋さんで昼食をとっていた時、たまたま話題がフランスの言語学者ソシュールの研究者として名高い丸山圭三郎のことに至りまして(一緒に行った同僚が言語学と哲学の先生だったもので・・・)。 で、丸山さんの本で何が一番印象的だったかという話になり、私が『言葉・狂気・エロス』という本だという話をした。 これ、講談社現代新書に入っていたものなんですが、この中で丸山さんがエロティシズムを語るくだりがあって、そこで丸山さんが持ち出す例がすごいのよ。 ある時、若き日の丸山さんが、ゼミ生の女子学生と男子学生と共に3人でドライブに行ったと。で、その女子学生というのが学内でも評判のマドンナ的存在の人だったらしいんです。 ところがそのドライブの帰り道、渋滞にはまり、トイレに行けなくなってしまったそのマドンナが車内で失禁するという事態に至る。 ゼミの先生のみならず、ゼミ仲間の男子学生の前でのこの失態に女性としての羞恥心だけでなく、学内のマドンナとしてのプライドも崩れ落ち、苦悩に身もだえする女子学生を前に、とてつもないエロスを感じたと、丸山さんはその本の中に書き記している。まさに狂気と紙一重のエロスというか。 で、私はこの箇所がすごく印象に残っていて、そのことを同僚たちに告げたのですが、二人共この本を読んでいなかったようで、「えー! 丸山さんって、そんなことを本の中に書いちゃう人なの~!! 意外ーー!」と驚いておりました。 で、うどん屋から大学に戻って、私がその本の実物を見せようと思ったわけよ。で、 あ゛ーーー! この前、処分した中にこの本も入っていたんだーーー! となった次第。 たまたま別な同僚がこの本を持っていたので、ちゃんと証拠を示すことは出来たのですが、それにしてもこの本くらいは取っておけば良かったなと。 もう一回、買い直すか・・・。 というわけで、処分した本を買い直したいと思うことって、多いなと。 ままならぬことの多い人生でございます。これこれ! (今は講談社学術文庫に入っているようです。) ↓言葉・狂気・エロス 無意識の深みにうごめくもの【電子書籍】[ 丸山圭三郎 ]
February 22, 2019
コメント(0)
-
本年度卒論指導終了~!
昨日の修論審査に続き、今日は卒論の口頭試験とその後の成績付けがあり、これをもって今年度の卒論指導関連の仕事がすべて終了~! 毎年疲れるけど、教育面で言えば、大学教員として一番重要な仕事だからね。それが終わったとなると、それなりの感慨があります。 いつも思うんだけど、仕事っていうのは、なんだかんだ言って、一つずつ終わっていくもんですな。忙しい時には「あー、もうダメだ~! 何一つ終わらない~!」と思うけれど、結果的に見ると、すべての仕事に一応の片が付いていく。修論指導も終わったし、卒論指導も終わったし、後期の授業も終わったし、期末試験も終わったし、その採点も終わった。 あと、抱えている原稿が二つあるけれども、これもいずれ近いうちに終わるでしょう。 そして、来年度のシラバスを書く作業も、締め切りまでには終わるでしょう。 父が亡くなる少し前、病院に入院していて、あっちもこっちも悪くて、担当のお医者さんからは、熱も下げなきゃいけない、食欲も出さなきゃいけない、歩く練習もしなきゃいけない、みたいに色々言われていて、「やるべきことが沢山あって大変だね」と慰めると、「そうだな、一つ、一つだな」と返事をしたんです。 「一つ、一つだな」と思ってやってれば、いつかは終わる。それが、父から学んだ最後の教訓かな。確かにそうだもんね。 さてさて、喫緊の課題の原稿二つ、「一つ、一つだな」と思って、頑張りますか。
February 21, 2019
コメント(0)
-
プリウス3連発
先輩同僚がプリウスを買ったそうで・・・。 それも、3回連続で。2代目、3代目と乗り継いで、今度発売される4代目の後期型を買われたと・・・。 なんなん? いやあ、気が知れないなあ。 だってさ、この世にクルマって色んな種類あるんだよ? こんなに沢山自動車メーカーがある国なんて日本以外そんなにないし、さらに外車も含めたらたーくさんある。 なのに、プリウス連続3回? それはさあ、「僕はもう、残りの人生、食事は全部うどんにする」って言っているようなもんじゃん? いやいや、この世には他にも旨いモノは沢山あるよ、うどんだけにしないで、他のものも食べてごらんよ、って言いたくなるでしょ? で、先輩同僚にもそういう風に説得したんですけど、先輩曰く、「だって、プリウスの燃費が良すぎて、一回これに乗ったら、他のには乗れないよ」ですって。 いやあ、そうかも知れないけど、クルマって、運転する楽しみってのがあるじゃないすか。燃費だけで決めるなんて、そんな・・・。 で、さらに驚いたのですが、先輩は、この新しいプリウスに試乗もしていないらしい。試乗会は人が殺到するので、試乗会が開かれる前日に行って、その場で判子押してきたとのこと。 もう、燃費が抜群によくて普通に動けばいいんだ・・・。 でも、そのプリウスの納車が数カ月先ということは、先輩以外にもそういう人がたーくさん居るってことですよね。うーん。わからん。 人生で買えるクルマの数なんて多寡が知れている。だからこそ、次の愛車をどれにするか、知力・体力を尽くして吟味するのがクルマ好きにとっての最高の楽しみなのになあ。試乗もせずに連続3回同じ車種買うなんて、人生に対する冒涜じゃないだろうか。 逆に、最初に買ったプリウスを30年くらい乗る、というのだったら、私にも理解できるけどね。それは、たまたま買ったそのクルマがすごく好きで手放せないということだから、そこにはクルマへの愛がある。それは分かるんだよなあ。 まあでも、トヨタって、先輩みたいな人を相手に商売しているんだろうな。 ま、いいわ。どうせワタクシには縁のないメーカーだし。
February 20, 2019
コメント(0)
-
追悼・内田正人
ザ・キング・トーンズの内田正人さんが亡くなりました。享年82。 まあ、何と言っても「グッドナイト・ベイビー」ですわなあ。 昭和44年というと、私がまだ幼稚園の頃だと思いますが、大ヒットしましてね。 で、子供心に「一体何だろう、これは?!」と思いました。大人の男がファルセットで歌うというのが、「え?」っていう驚きを与えた的な。で、そう考えてみると、「これがプロの歌い手というものか」というのを最初に認識したのが、ひょっとしたらこの曲、そして内田正人の歌声だったかも。 歌詞もすごいもんね。「今夜はこのまま、お休みグッドナイト」だから。幼稚園生なりに、「ん? これはただ単に赤ちゃんに『お休み』と言っているわけじゃねえな?」と感じましたもん。よく分からないが、大人の世界だなと。 昨日のブログで、「昭和の人間に共通するアメリカに対する憧れ」という話を書きましたが、内田さんだって、やっぱりアメリカの黒人音楽、特に「Doo Wop」に憧れて憧れて、それでああなったわけでしょ。 そういう意味で、内田さんやキング・トーンズの歌ってのは、昭和の人間にはよく分かる。 となると、また一つ昭和の灯が消えたわけだ。寂しいねえ。 ということで、内田正人さんの御冥福をお祈りいたします。向こうでオーティス・レディングとかと一緒に歌って下さい。
February 19, 2019
コメント(0)
-
アメリカの印象
来年度のゼミ生は既に7人に決まっているのですが、その中の一人は留学予定で、実質6人・・・だったのですが、今日、その6人のうちの一人がふらりと研究室にやって来まして。 何かと思ったら、その子も来年度留学することになったと。 ふーん、そうなんだ。じゃあ、4月からのゼミ生は5人なわけね。 え゛ーーーー! じゃあ、その再来年度のゼミ生(6人の予定)は、来年度の積み残し2人が加わるので、総勢8人ということになるじゃんか! 今年度の倍か・・・。 死ぬな。 ま、それはいいのですが(よくない!)、留学するって、どこに留学するの? と思って聞いてみたら、「オーストラリアでーす」だって。 もうね、猫も杓子もだよ。今、うちの学生で海外留学するというと、ほぼ全員オーストラリアね。 っていうか、なんでアメリカに行かないんだよ! アメリカ文学・文化が専門のワタクシのゼミに入るんじゃないのか? で、一応、尋ねてみた。なんでアメリカに行かないの? すると、返ってきた答えは、「だって、危なそうなんですもん」。 これも、うちの学生の定番の答えね。アメリカは危ないと。 なんだろうね? 私が子供の頃なんか、アメリカは憧れ以外の何モノでもなかったぜ。『わんぱくフリッパー』見て、『ララミー牧場』見て、『ルーシー・ショー』見て育ったら、当然そうなるって。今、日本の若者の大半は、アメリカ=やばい国、行ったら殺される国と思っているのかねえ? でも、そんな風に思っている国の文化なんて、研究できないじゃん? すべての研究の基本は、対象に対する憧れなんじゃないのか? っていうか、逆に聞きたい。オーストラリアに憧れるべき何があるのかと。ワタクシなんざ有袋類しか思い浮かばねーよ。コアラとかカンガルーの研究、したいか? まあ、よく分からないな。 でも、とにかく、アメリカの印象が「危ない場所」でしかないって、日本の若者文化も、変わったもんだねえ・・・・。
February 18, 2019
コメント(0)
-
合同稽古会
共に締切の近い(っていうか、一つはとっくに越しているんだけど・・・)原稿を二つ抱えて、昨日からウンウン言っているのですが、あんまり煮詰まってもアレなので、今日の午前中、八光流柔術の昇段演武を兼ねた三道場の合同稽古会に参加して参りました。 こういう催しは1年に2度くらいあるのですけれど、普段稽古をしている仲間とはまた別の方たちと稽古が出来るという意味でなかなか面白い体験になります。 同じ八光流でも、道場によって・・・ということはつまり師範によって、少しずつやり方、教え方が異なるところがあるので、それぞれの門下生には、所属道場の指紋のようなものが残っているわけよ。だから、違う道場の門下生の方と稽古をすると、いつもと違う手ごたえがある。これがね、すごく勉強になるわけ。 でも、いいよね、武道って。まったく見ず知らずの人でも、組み合えばすぐに色々分かるものがある。あ、この人はこの技は上手いけど、この技は俺の方が上手いなとか。でまた、それがお互いに瞬時に分かるので、この技については教えてもらおう、この技については教えてあげよう、という役割分担がすぐに決まる。 門下生同士でもそうなのだから、別な道場の師範の先生に教えてもらえるというのはもっと面白いわけね。今日はS先生に随分教えていただいて、頭の中がメモ書きだらけ。こいつを後でノートに書き出すのですが、今日は2ページ分くらい行きそうです。 ということで、今日はいい気分転換になりました。ここから、もう一度原稿の方に向き直って、せいぜい最善を尽くすとしましょうか。
February 17, 2019
コメント(2)
-
「ATキャンパーの秘密基地」でまったり
「まーさんガレージ」というサイトを見つけて以来、楽しみにしてちょくちょく動画を見ているんですけど、最近ね、このサイトにまた新たな展開と言いましょうか、ホンダの名車「ビート」をレストアするという、まさにクルマ好きからしたら魅惑のプログラムが始まっちゃいまして、これが実に楽しい! お勉強の合間の息抜きに、この動画を堪能させていただいております。これこれ! ↓まーさんガレージ・ビート編 が! 最近、また別な面白サイトを見つけちゃったのよ。 題して「ATキャンパーの秘密基地」。これまた恐らく私と同世代と思しき、ということは「まーさん」とも同世代と思しきおっさんが、軽ワンボックスをコツコツとキャンピングカーに仕立てていくというものなんですけど、これがまた面白いのよ。 まーさんのキャラクターが物柔らかであり、かつ生真面目なのに対し、こちらの方は独特のユーモアというか、言葉のセンスがあって、それを聞いているだけで面白い。これこれ! ↓ATキャンパーの秘密基地・FFファン取り付け編 お二人共、趣味とはいえ、趣味のレベルを越えた技術力と装備を持っていらして、本格的。いやあ、こういうのを楽しむ人生ってのも、いいもんですなあ。 というわけで、面白サイトを見つけて、なんだかんだ楽しんでいる私なのでありました、とさ。
February 16, 2019
コメント(0)
-
カルディ大好き!
今日は大学はお休みだったのですけど、このところ勤勉に勉強しているし、今日はちょっと息抜きしてもいいんじゃないかい? と思って、本当は大須辺りに行って気晴らししたかったんですけど、どんよりとした空模様にこの寒さ。これじゃあな・・・。 というわけで、その代りに・・・というのにはあまりにもお手軽過ぎますが、3時ごろ買い物がてら近所のイオンモールに入っているカルディに行ってきました。カルディって、あの基本コーヒー屋さんで輸入食料品なんかを置いているお店のこと。 白状しますけど、ワタクシ、カルディって好きなのよ。否、大好きと言っていいくらい。 大体、店頭で無料コーヒーを配るというところからして良くない? (ま、今日はなぜか配ってませんでしたが・・・) 小さなカップながら、ちょっと甘めのミルクコーヒーを飲みながら買い物できるって、それ自体ステキ。 で、それを飲みながら店内をウロウロすると、目に入ってくるのは様々な海外の食料品。日本の地方ものもあるけど。これが好奇心をくすぐる! 大体、珍しい食料品が所せましと置いてあるって、何とも言えず楽しいよね! だって、食料品ってさあ、要するに基本、美味しいもの、じゃん? で、美味しいと分かっていながら、それが海外のものだったり、見たことのない地方のものだったりすると、「美味しい・・・のだろうけれども、どんな味なんだろう?」ってなるわけじゃん? つまり、「分かっていながら、分からない」ということになる。私が好きなチョコレート、なんだけど、海外ブランドだから食べたことない、一体どういう風に美味しいんだろう? ってなるわけで。 熟知していながら、未知である。こんなに好奇心をくすぐるものって、他にない。と思う。ワタクシは。 だからさあ、鬱病の人とか。カルディに連れてくればいいんじゃない? 少しはハイにならないかなあ。ダメか? あと、あのカルディの店舗の棚の配置。あれ考えた人、天才。 仮に、コンビニみたいな配置だったと思いなよ。魅力半減すると思うよ! あの、入り組んだ妙な棚の配置、思わぬところで思わぬものに出くわすみたいな、メビウスの輪のように、店の一番奥に入り込んだと思ったら、すぐ入口の隣りでした、みたいな、あの迷路みたいな棚の作り、あれがいいんですよね~。 例えば、自分の家の書庫があんな風だったら、さぞ面白いだろうと思いません? まさに「知の森」みたいじゃん。自分の蔵書ながら、ああいう入り組んだ棚に本を並べたら、熟知しているはずの本と初対面のように出会うことも出来そうだ。 ってなわけで、私の愛するカルディでハワイのコナコーヒーやら、スペインの甘口ワインやら、豚ばら肉のワイン煮のレトルトやら、パスタ用鴨のラグーソースやら、そんなものをしこたま買って、ちょっとした息抜きをしてきた私なのでありました、とさ。カルディ、最高!
February 16, 2019
コメント(0)
-
呑みニュケーション!
後期の授業をすべて終えたもので、昨夜は家内と家の近くの焼き鳥屋さんに行って打ち上げをしてきました。これ、半期の授業を終えた後に行なう恒例行事なんですが。 で、ごく庶民的な焼き鳥屋さんのカウンター席に座って、家内はジントニック、私は日本酒の熱燗をいただきながら、様々な焼き鳥串をはふはふと頬張るという至福を味わってきたという。 で、まあ、そこまではいつものことなんですけれども、昨夜はいつもと違う一味が加わりまして。 というのも、我々が座ったカウンター席のお隣で一人飲んでいた先客のおっさんが居たんですわ。余程の常連らしく、店の店員さんたちとも親しげで、異なる銘柄の焼酎を3本もボトルキープして、それをとっかえひっかえ楽しんでいる。 で、そのうち、その見知らぬおっさんが我々に話しかけてきたわけよ。 ひゃー、出た~! これが、居酒屋あるあるの、客同士交流って奴か!? まあ、私は居酒屋で飲むなんてことがあまりない男なので、こういう呑みニュケーションってほとんど・・・否、一度も経験がなかったんですわ。 で、色々話しているうちに、そのおっさんが私より一つ年上ながら、同じ4月生まれということが判明。 そして私が柔術をやっているのに対し、そのおっさんは空手をやっていることが判明。 そして、実はそのおっさんは高校の英語の先生で、そこの部分もご同業であることが判明。 ・・・とまあ、なかなかの奇縁だったのよ。 で、私がもしお酒が飲める方であったならば、ここからさらに親交が深まるところだったのかも知れないけれども、私はもうお銚子一本の日本酒で真っ赤な顔になっておりますので、残念ながらそういう方向には行かず。 ま、それだけのことだったんですが、それにしてもね、居酒屋で隣席の人と話をする、なんてことを生まれて初めてやったものですから、ちょっと面白かったです。
February 14, 2019
コメント(0)
-

斎藤美奈子著『日本の同時代小説』を読む
斎藤美奈子さんが書いた『日本の同時代小説』という本を読みました。 この本、斎藤さんご自身が書いた「はじめに」によると、明治以来の日本の近代小説の流れを簡単に知ろうと思ったら、中村光夫の『日本の近代小説』と『日本の現代小説』(共に岩波新書)を読むのが簡便でよろしいのだが、いかんせん、この二著は1960年代の話で終ってしまう。しかし、今やそこから50年も経ったわけだから、この50年間の日本の小説の流れを、そろそろ誰かが概観しないといけないのではないか・・・ってな意図で書かれたと。 まあ、そうなりますと、私自身が生まれた頃から今日までの日本の小説を概観するということになりますわなあ。そういう本を読んだら、私も何か勉強になるかも。 と、思ったものだから、つい、読んでしまったわけよ。 で、読んだ感想なんですけど、うーん、驚いたね。 つまりね、私が生まれてこの方、日ノ本の国で書かれた数々の小説の中で、私が「読みたいな~」って思うものは、ほぼ一冊もないんだ、ということが判明した、という意味で。 特に2000年代から先がひどいよ。ケータイ小説とか全然読みたくないし、架空戦争小説とか、テロ小説とか、ディストピア小説とか、まったく読みたくない。このあたりになると、変な設定の小説、人がイカと結婚する、といったような小説、やたらに人が殺されたりする小説しかないのか、って感じ。 普通の小説ってないの? 日本には? 私の日本の小説観って、谷崎とか芥川あたりで止まっているんだけど、それで正解なんだ、ってのがよく分かった。 そう言えば最近、グラミー賞の授賞式を見ていて、もう、私が知っているのは、おばあちゃんになったダイアナ・ロスくらいしかいないじゃないかと思いましたけど、アメリカのロック・ポップ史に関しても、私はほぼ1980年代までで止まっている。で、そこから先のものにはあまり興味が持てず、一生、1950年代半ばから1980年代までを無限ループする懐メロだけでいいなと思っていますけど、小説の世界に関しても、「懐メロ」ならぬ「懐小説」だけでいいのかな。 思うんだけど、「懐メロ」番組ってのがあって、年寄りには人気があるんだから、小説の世界でも、「懐小説」だけを掲載する文学雑誌とかあったら、案外、じいさんたちに売れたりするんじゃない? 最新号に載っていた露伴の『五重塔』はやっぱりいいなあ、みたいな。 それはともかく、『日本の同時代小説』という本を書くに当たって、斎藤美奈子さんは一体、何冊の同時代小説を読破したのか。50年分の通史を一人で書くのだから、大変だよね! それとも、日本文学の専門家なら、そんなこと当たり前なのかしら。 で、私も自己啓発本の研究をしている以上、同じような本を書けなくてはいかんのかな。そうなると、こちらは150年くらいの歴史があるから、もっと大変だよな・・・。ま、ワタクシの場合、ずるいからもっと省エネで行くと思いますが。 とまあ、そっちの方が読んでいて気になっちゃった。 とにかく、日本の現代小説って、ほとんど訳が分からない、そら恐ろしい世界なんだなというのは実感できる本でございます。興味のある方は是非。日本の同時代小説 (岩波新書) [ 斎藤美奈子 ]
February 14, 2019
コメント(0)
-
修論提出!
今日はうちの大学の大学院の修士論文提出締切だったんですが、私が面倒を見てきた院生がついに修論を提出しまして。 まあ、色々事情があって、昨年は提出出来なかったのですけれども、今年はその反省に立って指導法を変え、かなり積極的に尻を叩いたわけ。 それでも、間に合うのかどうか、ぎりぎりのところだったんですけど、ついに提出に漕ぎつけたと。 まあ、出してくれれば点をつけられますけれども、昨年みたいに「書けませんでした・・・」なんて言われてしまうと、こちらとしてはどうしようもないもんね。 ということで、昨日は一日、「明日、提出します」というメールがくるか、「今年もダメでした」というメールがくるか、ハラハラして待っていたのですが、夜になって「提出します」というメールが来た時は嬉しかった! それでも昨夜は「出すつもりだったけど、お昼12時の締め切りに間に合いませんでした」と言われる悪夢にうなされまして。 だから、今日、本当に出したという報告を本人から直接聞いた時は嬉しかったっす。 まあ、これで2年越しで指導責任を果たしたかな・・・。 ということで、今日は枕を高くして寝ようかな。
February 12, 2019
コメント(0)
-
リリー・フランキーを賞味する
YouTube とかで動画を見ていると、CMが入ることがあるじゃない? で、先日、何の動画を見ていた時だったか、UHA味覚糖の「さけるグミ」のCMが入ったんですわ。 で、それを見て驚愕。 リリー・フランキーさん主演のそのCMがめちゃくちゃ面白かったのよ。これこれ! ↓さけるグミCM で、これ見て思ったんだけど、リリー・フランキーってのは、俳優として相当の実力者だなと。だって、こんな下らないCMでも、思わず見せるんだもんね。 いやあ、リリー・フランキーって、日本映画によく出ていて、評価されている俳優なのでしょうが、私はそういう映画を見ないので、それほどのものか?って思っていたのよ。だけど、このCMを見て、彼のことを見直しました。すごいと思う。 惜しいのは、小津安二郎レベルの監督が今も日本に居て、彼みたいな俳優を適材適所で使えたら、ということなのですが。まあ、それを言ったらおしまいだけどね。 それにしても、このCM、笑えるわ~。
February 11, 2019
コメント(0)
-

スティーブン・ワッツ著『デール・カーネギー』(上・下)を読む
スティーブン・ワッツという人の書いた『デール・カーネギー』(上・下)(原題:Self-Help Messiah: Dale Carnegie and Success in Modern America, 2013)という本を読了したので、心覚えを付けておきましょう。 これね、『人を動かす』『道は開ける』の二著で20世紀半ばのアメリカの自己啓発本市場に君臨したデール・カーネギーの伝記なんですけど、すっごく面白いよ。めちゃくちゃ面白い。 先日、「論文、書き上げちゃった」とか自慢げに言っておりましたが、その論文にはデール・カーネギーについて触れた部分があって、そこはこの本を読む前に他の資料を使って書いちゃったのだけど、この本を読んだおかげで大分あちこち修正が必要であることが判明。良かった、実際にこの論文が世に出る前にこの本読んでおいて! っていうか、アレだね。論文っていうのは、ひょっとして詳細な資料を読む前に書く方がいいのかもね。ある程度あやふやな情報を元に、自分の言いたいこと中心に論文の骨格を作ってしまってから、こまかく正確な情報を読むと、確かに最初に作った骨格を適宜修正する必要には迫られるものの、詳細な資料を先に読んだ場合に比べて、何処をどう直せばいいかすぐ分かる。 逆に、最初に詳細な資料をたーくさん読んでしまってから論文を書こうとすると、あまりにも多種多様な情報に引き回されてしまって、その中からどれを取捨選択して自分の言いたいことを言えばいいのか分からなくなる可能性があるからね。 ま、とにかく、この本ですよ。 例えばカーネギーが、自己啓発本ライターになる前、一時期俳優になる夢を持っていて、そのための演劇学校に通っていたことは他の資料で知っていたんですけど、その演劇学校が、実は名門中の名門だったということは知らなかった。カーネギーがかなり本格的に俳優の道を目指していたことが、こういう細かい事実から分かるわけよ。 あ、それから第1次世界大戦後、カーネギーがヨーロッパで暮していた時期があり、その頃、作家を目指して小説を書いていた、なんてことも、この伝記を読んで初めて知りました。 その意味、分かる? つまりね、カーネギーは、ある意味、「ロスト・ジェネレーション」に属していたってことですよ。ヘミングウェイやフィッツジェラルドより10歳くらい年上ではあるけれど、もし彼にそっち方面の才能がもうちょいあったならば、我々は彼を自己啓発本の著者としてではなく、ロス・ジェネの作家としてカウントしていたかも知れないっていうね。 あと、彼のかなり奔放な女性関係のこととか、本書を読んで初めて知りました。カーネギーの母親というのは、キリスト教的な意味でかなり厳格な人で、カーネギーが演劇の道に入ろうとした時も相当怒ったようですけど、結局そういうことが逆に作用したのか、彼はそういうキリスト教倫理にはかなり反抗的で、夫のある女性と長年付き合って子供まで作っていたりするのよ。不倫、不倫。 だけど、じゃあ、許しがたい男なのかというとそうではなく、逆にすごく律儀に愛人や愛人の子供、それどころか、愛人の夫にまで尽くしていたりする。そういう面白いところがある人なのよ。 で、『人を動かす』が売れてからは、金回りも良くなって、相当人生を楽しんだみたいですが、それでいて教育ということにかけてはまったく手を抜かず、自分の作った自己啓発学校を最後までちゃんと面倒見た。根っからの教育者であったんですなあ。 で、晩年は愛人の他に奥さんも出来、さらに63歳にして娘を授かるという幸福にも恵まれるのですが、そのすぐ後にアルツハイマー病にかかり、67歳という若さで亡くなると。なかなか波乱万丈な人生でございます。 で、本書はそういうカーネギーの人生を辿りつつ、彼が成し遂げた仕事についてもきっちり考察・評価をしているのですが、その辺については今書いている論文の参考にする予定。 とにかく、カーネギーに興味のある私にしたら、相当楽しく読了することが出来た本だったのでした。【バーゲン本】デール・カーネギー 上 [ スティーブン・ワッツ ]
February 10, 2019
コメント(0)
-
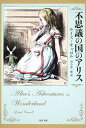
『アリス』ものが苦手
卒論の口頭試験というのが近々あるのですが、そのために、他の先生のゼミの学生が書いた卒論を幾つか、副査として読まなければならないんですな。 で、たまたま『不思議の国のアリス』についてあれこれ調べた卒論を読んだのですが・・・。 ・・・よく分からん(爆!)。 いや、卒論自体はそこそこよく書けていて、例えば最初にアリスがウサギの穴に落ちるシーンがあるけど、あれはちょうどこの作品が書かれた頃にロンドンに地下鉄が作られた時代性が反映しているんだ、とか、別な解釈ではあれは子宮回帰願望の象徴と考えられているんだ、とか、まあ、色々お勉強したことが書いてある。なるほどな、ってなもんですわ。 だけど、まあ、根本的な問題として、私自身、アリスものに興味がなくて、通して読んだことがないという。私が学生の頃、かの高山宏先生が『アリス狩り』って本を出されてえらく話題になったことがあって、英文科の学生としては当然読んでいなくてはならないんですけど、私、この本も持っているけれども、これも読んだことがない。だって、原典をそもそも読んだことがないのだから。 要するに、いかんわけですよ。怠慢、怠慢。 いつも言いますが、私、何か頭のネジが一本くらいずれているのか、ある種のものに対してまったく関心が向かないというのがあるのよ。で、児童文学がまさにそれ。 だから、アーサー・ランサムの『ツバメ号とアマゾン号』とか、小学生時代、私を見込んだ国語の先生から激賞されて読め読めと勧められたけれども、わずか数ページで挫折。その他、『ナルニア国物語』とか、『ドリトル先生』とか、そういうのも全くダメ。同じ理由で、『指輪物語』とか『ハリーポッター』とかも読む気になれない。子供向けの本で好きだったのは、スウェーデンのアストリッド・リンドグレーンの諸作品くらいしか思い出せない。 で、一方、最近の大学生(特に女子学生)は、卒論のテーマにやたらと児童文学を選びたがったりするのよ。 それもどうかと思うけどね・・・。彼女たちの頭の中で「アリスもの」はディズニーランドと同列になっているんじゃないか? なんでもっと、こう、大人の小説に興味を持たないんだろう。 ま、女子学生に限らず、業界人の中にも児童文学を云々する学者さんは結構いて、「日本イギリス児童文学会」とか、そういう学会もあったりする。もっとも噂では、児童文学系の学会も最近はひところの勢いがないという話ではありますが。 ま、とにかく、困るのよね、児童文学系の卒論。一応、文学だということで私に白羽の矢が立つもので。 しかし、そうは言っても、あれか。そろそろ私も『アリス』の一つや二つ、読んでおいた方がいいのか・・・? いやあ、でもやっぱりキツイな! 50代半ばのおっさんが『アリス』を読むのって! 不思議の国のアリス (角川文庫) [ ルイス・キャロル ]
February 9, 2019
コメント(0)
-

風邪対策必勝サプリ、からの「鴨すきうどん」、からの・・・
ワタクシ、何故かインフルエンザにはなぜか異様に強い免疫があって、周辺患者だらけでも全然平気なんですが、普通の風邪はよく引くんですわ。 で、これまで色々な市販の風邪薬を試してきたのですが、今シーズンはまったく飲んでない。何故ならば・・・ そう、風邪対策の強い味方を得てしまったのよ~! それは「i Herb」というサプリメントの会社が出している液体サプリ「エキナセア&ゴールデンシール」なのであーる。ガーン! あれ、風邪かな、ヤバいな・・・と思った時、このサプリを1ミリグラム、スポイトで吸い上げまして、水に溶かして飲みますと、アーラ不思議、翌日には復調しているという。もう、これほど顕著な効果って、体験したことがないよ。これこれ! ↓エキナセア&ゴールデンシール 実は二、三日前も怪しかったのですが、これを飲んで復調。素晴らしい。 さて、風邪も復調したことだし、今日は気晴らしに昼を外で食べるか、ということになりまして、お昼、丸亀製麺に行っちゃった。ほれ、今CMで「鴨うどん」の宣伝やっているじゃん? あれが食べたくて。 で、私は「鴨すきうどん」、家内は「鴨ねぎうどん」を注文したのですが、どちらも旨い! いいよね、600円台でこういう美味しいものが食べられるのって。幸せ。 で、あんまり幸せだったので、すぐに家に帰らず、そのまま馴染みの古本屋の「まゆ」という店に行ったのですが・・・、ガーン! なんとこのお店、店売りをやめてネット販売の店に特化した由。ただ、店頭の30円棚だけはそのままということで、平松洋子著『夜中にジャムを煮る』(新潮社)の「良」クオリティの本を30円でゲットして参りました。『中古』夜中にジャムを煮る この本、30円ならお買い得だったのではないでしょうか。ネット上では6000円近いじゃん! そしてさらにさらに、アヴァンセというパン屋さんにも寄って、「バブカ」をゲット。これがまた旨いのよ。 ってなわけで、今日はちょっと息抜きの日でしたが、このところ頑張って色々やっていたので、たまにはいいのではないでしょうか。
February 8, 2019
コメント(0)
-

ウェイン・ダイアー著『「最高の人生」を手に入れる人がやっていること』を読む
ウェイン・ダイアーの書いた『「最高の人生」を手に入れる人がやっていること』(原題:You'll See It When You Beieve It, 1989)を読了しましたので、心覚えを付けておきましょう。 ウェイン・ダイアーと言えば、主著『Your Erroneous Zones』(1976) が大ベストセラーとして超有名なんですけど、本書にはダイアー自身の経歴が語られている部分があって、その意味で興味深いところがある。 で、本書に拠りますと、ウェイン・ダイアーの両親は、彼が2歳の時に離婚した・・・というか、父親がのんだくれの酷い奴で、勝手に家族を捨ててどこかに行ってしまったんですな。で、当然、一家は貧しさの中、苦労することになるわけで、ウェインも父親に対する恨みつらみを募らせながら成長したと。 だけど、その後大学の先生になったダイアーの元に、父親が既に死亡して、ミシシッピ州のビロクシ―という町の墓地に埋葬されたらしいという噂が届く。で、たまたまミシシッピ州に行く用事があった彼は、少し足を延ばして父親の墓を見てみる気になったと。 で、コロンバスで新車のレンタカーを借り、その父親が埋葬されたという町を目指すのですが、その際、おろしたてのレンタカーに、とあるモーテルの名刺が挟まっていたと。ま、それは気にせずビロクシ―の町に行って、あちこちの墓地に電話をかけ、父親メルヴィル・ダイアーの墓はそちらにありますか?と尋ねたんですな。 そしたら、ある墓地が、「ある」という返事をした。そしてその墓地の場所を尋ねると、なんとそれは、レンタカーの中に名刺が置いてあったモーテルの隣りにあったと。 で、まるで何かに導かれるようにその墓地に行って、最低の父親だった男の墓を詣でるわけ。で、そこでいきなり泣いてしまった。これまでずっと抱いていた怨みも蒸発し、すべてを水に流すことが出来た。つまり、父親を「許す」ことが出来たんですな。 で、この体験、いわば父親との和解を機に、ダイアーの人生が変わり始めると。ニューヨークに戻った彼は、『The Erroneous Zones』をさらさら~っと一気に書き上げ、それはベストセラーになって次々と取材されるようになり、講演の予定もびっちり。一躍時の人となったんですな。そして以後の活躍は人も知る通りと。 つまりダイアーは、若い頃の「恨みつらみの人生」が、父を許したことによって劇的に変わったわけ。その意味で、本書はその自分の体験を元にした、「変わること」と「許すこと」を主題にした本と言うことが出来るのでありまーす。 で、じゃあどうして人間は「変われる」のか、と言いますと、人間存在の本質が肉体ではなく精神にあるから。巷間よく「人間とは精神を宿した肉体」みたいなことが言われますが、ダイアーに言わせるとそうじゃないと。むしろ「人間とは肉体を宿した精神」だと(何じゃそれ?)。要するに、人間とは精神・魂だと。 だから、その精神を中心に考えれば、後のことはどうでもよくなるし、それにこだわらなくなる。歳を取るに従って肉体は衰え、容姿も衰えてくるけれども、そんなもん、どうでもいい。精神の方は着実に進化するわけだから。それに世の肩書とか名誉とか、あるいは他人からの評価とか、そういうものも肉体に貼りついているものだから、どうでもいい。 で、その肉体を離れて、精神中心主義を奉じる方向で自己改革すれば、すべてが変わってくる、とダイアーは言います。 ま、この辺の考え方ってのは、明らかにニューソートね。ダイアーは典型的なニューソーターです。 で、ダイアー自身も、この考え方に出会って、自分を変えた。 まず、彼は大学の先生をやっていたんですが、確かに大学の先生をやっていれば、ある程度の収入は保証されるし、安全ではある。だけど、これが本当に自分のやりたいことか? と自らの魂に尋ねてみれば、そうではないと魂は答える。じゃあ、どうすればいいか? 自分の魂に寄り添う道を選ぶしかないでしょ。 ってなわけで、ダイアーはある日突然学部長の所に行き、家族に相談もせず「辞めます」と宣言(無茶しよる)。で、家族に「大学辞めてきた」って事後報告したら妻も子供たちも「いいよ! 頑張って!」と応援してくれた(ほんまか?!)。で、そこから先に名前を挙げた『The Erroneous Zones』を書き上げ、最初はその本を自分で大量購入して、自ら手売りして回ったと。で、そのうち、じわじわとこの本の評判が上り、やがて大ベストセラーになり・・・今日の自分があると。 自己啓発本ってのは、要するに勝ったモン勝ちの世界だからね。勝ち組のダイアーには、以後、何でも言えるようになる。ダイアーはエマソンの例の「人は、自分が一日中考えているものになる」という言葉を引いて、自分も幼い頃からライターになろうと思い、いつか有名なライターになって、有名なテレビ番組『トゥナイト・ショー』に出て、人気司会者スティーヴ・アレンと話をするんだ、と思い続けてきたけど、実際に実現したもんね、と言うのですけど、そう言われちゃうと、読者としてはグーの音も出ない。 っていうか、私自身、小さい頃、母と『徹子の部屋』を見ていて、自分もいつかこれに出たいと思ったことがありましたけど、どうなんだろう。今からでもその思いを強くすれば、出られるかな? 徹子さん、待っててね!! で、以後、この本は、自分の周りの環境というのは、自分の内面を映した鏡でしかないのだから、自分を変えれば、世界は変るんだよ、ということを、色々な言い方で言います。 で、その中でも特に彼が強調するのは、「許す」という側面ね。 まあそれはダイアー自身が、父親を許すという体験をした後で、人生が激変した、という体験に基づくのでしょうけれども、とにかく許しなさいと。 つまり、人に対して怒りを持ち続けることは、要するに、その憎い相手によって支配されているようなもんじゃないかとダイアーは言うわけね。そういう支配から脱するには、もう相手を許してしまうしかない。 ダイアーは「許し」について、マーク・トウェインの言葉を引用するんですけど、これがなかなかいい。「スミレを踏むと、スミレはかかとによい香りを残してくれる。許しとは、その香りのことだ」というのですけどね。いいでしょ? ダイアーによれば、そもそも宇宙には偶然というものはない(ニューソートの考え方)のだから、自分が人生の中で出会う敵たちもまた、完璧な宇宙の仕組んだことである。あらかじめプログラミングされていたことなのね。それは、そのことによってその人が何かに気付き、成長する契機になるとあらかじめ分かっているから、宇宙はそのように仕組んだのであって。 だから、嫌な人に会い、嫌なことがあったら、それに囚われることなく、「ああ、そうか、これは自分を成長させるために仕組まれたことなのだな」と思って反省すべきは反省し、宇宙の道具に使われた相手のことはさっぱり許すと。 そういう、「完璧な宇宙のプログラム」という大所高所があることに気付けば、許しと自己成長を同時に達成するのは簡単。まあ、ダイアーが言っていることってのは、そういうことですな。 でもね、私にはこういう説教は役に立ちます。私も怒りっぽいし、敵を作り易いからね。ダイアーが提示するこういう考え方を受け入れて、もっと平和に暮らしたいなと、つくづく思うのよ。反省。 ってなわけで、この本を読むと、ダイアーが自己啓発ライターとしていかにニューソートに根差しているかが分かるし、ダイアー自身の個人的な経歴もある程度分かるし、自分にとっても反省を促されるところが多かったです。 あと、ダイアーがエマソンの「人は、自分が一日中考えているものになる」という文を引用していることも分かったしね。 あ、あと、ダイアーはラム・ダスと友達なんだ、ということも分かった。ラム・ダスって、スピリチュアル系の自己啓発ライターなんですけど。まあ、ニューソートとスピリチュアルは紙一重だからね。人間存在は精神であり、その精神は不滅だ、という考え方で共通するわけだから。 ダイアーも言ってます。自分の本質は精神であって、精神は不滅であり、滅びるのは肉体だけだということが理解できてから、病気や死ぬことが怖くなくなったと。ただ、そういう風に怖くなくなると、逆に健康的に暮すことの意味も分かって来て、むしろ以前より健康に気を使うようになったんですと。なるほどね。 ま、とにかくダイアーってのは、20世紀後半のニューソート系自己啓発ライターとして、落とせない人ではあるなと思いましたね。「最高の人生」を手に入れる人がやっていること すべてを“劇的”に変える起爆剤! (知的生きかた文庫) [ ウエイン・W・ダイアー ]
February 7, 2019
コメント(0)
-
七宝焼への提言
今日は野暮用がありまして、津島市というところに行って参りました。 で、途中、「あま市」というところを通過したのですが、ここは七宝が有名なところで、「あま市七宝焼アートヴィレッジ」なんて施設もある。ということで野暮用を済ませて家に戻る途中、この『アートヴィレッジ」に立ち寄って、七宝の何たるかを学んで来た次第。 で、七宝というのは、銅板を叩いて曲げて壺やら皿の形にした後、そこに墨で図柄(下絵)を線描し、その線の上に針金みたいなものを貼り付けていくんですな。まあ、それによって細かいステンドガラスの枠みたいなものができると。 で、その針金で囲まれたところに様々な色のガラス性の釉薬を入れていく。そしてそれを焼くのですが、一回焼いたくらいでは針金の枠とその内側で段差が出来てしまうので、その段差が無くなるまで何度も釉薬を入れては焼く、という作業を繰り返す。 で、段差が埋まったら、今度はその表面を研いでツルツルにする。そうすると、普通の陶器では出せないような、極彩色の艶やかな図柄のついた壺なり皿なりが完成すると。まあ、そういう具合なんですな。 で、七宝の技法はエジプトにまで遡るそうで、それが中国を通って日本に伝えられたらしい。だから、私なんかが勝手に想像していた以上に、長い歴史を持った技法なわけですよ。 ところが、やっぱり日本人の職人ってのは一旦技法を習得した後、そこから自分なりの工夫を加えてしまうんですな。 例えば、針金の枠を使わないで模様を直接描いてみるとか。 あるいは、一旦七宝焼きを作った上で、それを酸に浸して下地の銅板を溶かし、ガラス性の七宝の部分だけを残す、なんてこともやったりするんですと。そういうのは、銅板がないから透けていて、ガラス細工のようにも見える(ただし、非常に繊細で壊れやすいのだとか)。 まあ、日本人の好奇心と工夫好きと器用さがよく出た世界なわけね。 で、アートヴィレッジには、古の職工たちが作った七宝の器なんかが展示されているんですけど、まあ、見事なものですよ。 で、なるほどね~と思いながら、どうせなら何かお土産でも買っていくかと、アートヴィレッジのお土産品コーナーに行ってみた。すると・・・ まあ、何て言うの? 昭和っぽいわけ。そこに置いてある品々が。 例えば七宝を象嵌のようにほどこしたツゲの櫛だとか。ありがちなペンダントとか、ブローチだとか。男性向けにネクタイピンだとか、カフスボタンだとか。 一言で言ってダサい。どうしようもなくダサい。センスのかけらもない。 いやあ、七宝って、日本が誇る工芸なわけじゃん? で、昔の職工たちは、ものすごく高い美意識の下、素晴らしいデザインのものを作ったわけじゃん? なのに、現代の七宝職人たちは一体、何をやっているのかと。こんなダサいもん量産したって意味ないじゃん。少しは勉強して、センスのいいもの作って、高級宝飾店で売れるようなもの作らなくてどうするんだって。 七宝って、宝石や黄金や真珠などの「宝」を七つ集めたくらい素晴らしいもの、という意味でしょうが。そう考えると、たとえば田崎真珠がすごくセンスのいい真珠のアクセサリーを世界に向けて売り出しているのなんかと比べて、七宝は大分遅れているんじゃないかい? ということで、今日は七宝の何たるかを勉強し、感心したりガッカリしたりしたワタクシだったのでありました。
February 6, 2019
コメント(0)
-
迷う英語教科書選び
大学改革のあおりを受けて所属の科がお取り潰しとなり、新たに所属することになった科は、私自身の専門とはまるでかけ離れたものになってしまったので、結局、来年度は教養英語ばっかり持たされる羽目になってしまったワタクシ。 ということで、来る4月から「英語コミュニケーション」みたいな科目ばかり担当するんですけど、そうなると問題になるのは教科書選び。これがね、難しいのよ。 最近、どこの大学も語学の授業が減らされていて、かろうじて残った授業では「TOEIC対策をやってくれ」というようなことをよく言われるのですけど、TOEIC向けの教科書でいいのがなかなかない。 よくあるのが、単純な問題集。でもそれだと、ただひたすらCDプレーヤーで教科書に付属したCD音声を流し、「はーい、じゃ次、問の2番やるよ。音声が始まったら、自分のテキストの正解だと思う番号に丸してね」みたいなのをずっとやることになる。 これ、別に私がやらなくてもいいじゃん? CDプレーヤーのボタンを押せる人だったら、誰でも勤まるよ。 かといって、TOEIC対策の教科書の中には、妙なノウハウを教えるものがあって、例えば「相手がこういう尋ね方をしてきた時は、迷わず3番目の選択肢に丸をすること」みたいなことを教えることになっちゃったりする。自動車教習所でよくある、「バックミラーに3本目のポールが見えたら思い切りハンドルを左に切って」というアドバイスと同じで、実際にはまったく通用しないノウハウなんですな。 そういうのもねえ・・・。 もちろん、その中間みたいなのもあることはあるんだけど、教科書に書いてあることを読み上げるだけになりがち。それだったら学生がそれぞれ自分でやればいいんだけど、どうせやりゃーしないから、語学の授業中に強制的にやらせる、という感じですな。 つまんないね! しかし、そうはいってもそろそろ来年度の教科書を決めなければいけない時期に差し掛かりつつあるので、なにか選ばなくちゃならない。こまったわ~。 はあ・・・。ため息しか出ないね。
February 5, 2019
コメント(0)
-
日本人のエマソン好き
秋に某学会で、エマソン関連のシンポジウムに参加することになったので、少しずつ資料を集め始めたのですが、その過程で今から百年以上も昔、日本で出回っていたエマソン関連の本に『エマーソン氏一語千金』なるものがあると気づきまして。 これ、1897年に日本で出た本なんですが、W・C・ガンネットという人のエマソンについての本を、蓮沼磐雄という人が翻訳したものらしい。 ま、それはいいのですが、私がこの本に興味を抱いたのは、そのタイトルゆえ。 『エマーソン氏一語千金』。 すごいタイトルだよね! で、おそらくこれはエマソン語録なんだろうと見当をつけ、国内では同志社大学の図書館がこれを持っているらしいので、それを取り寄せようとしたわけ。そしたら、図書館の司書の人から、「取り寄せなくても国会図書館のデジタル・アーカイブ」に載ってますよと指摘されてしまった。 で、デジタル版ならすぐ読めるということで、実際にチラ見したんですけど・・・これこれ! ↓エマーソン氏一語千金 なるほどね。 想像していた通り、これはエマソンの諸著作の中から、そのエッセンスとなるような文章を取捨選択して選び出したエマソン語録ですな。 で、訳者の方も「序」に書いているけれども、エマソンの文章は論理的な起承転結がなく、いきなり核心を突くような言葉で始まって、ふいっと終わってしまうと。だから、西欧人の文章の中でも一番読みにくいのだけれど、その幽玄な思想を読まず嫌いするのはいかにも惜しい。だから、その語録を集めた本書を苦労して訳したので、もってエマソンの神髄に触れていただきたいと、まあ、そんな趣旨らしい。 思うに、エマソンは文脈ではなく、箴言として読め、という流れは、明治時代から既に日本に定着していたのであって、この本なんぞはその証拠になるんじゃないかなと。 で、本書の中で著者のガンネットが言っているんですけど、エマソンの著作は数あれど、もし一つだけしか読めないってーのなら、『処世論』を読めと。 そのせいかどうか、エマソンの『処世論』は、1910年という早い時代に高橋五郎という人が日本語に訳しているんですな。 で、ここでも私は『処世論』というタイトルが気になるんですけど、これって要するにいかに世過ぎをするか、という論、つまり自己啓発本なんじゃね? つまり、エマソンは語録で読め、それも、自己啓発本として読めと。そういう話なんじゃないかと。それが20世紀初頭の日本で、既に定まった見方だったんじゃないのかと。 どう、この見立て? ま、とりあえず高橋五郎訳の『処世論』を取り寄せているところでございます。
February 4, 2019
コメント(0)
-
墓参、そして豆撒き
ひゃー、今日は小学校時代の恩師の墓参りをしてきました〜。 しかし、今年は参加者が少なくて二人だけ。多い時は6人くらいの時もあるのですが。しかし、まあ、お子さんが受験だとか、仕事だとか、足の骨を折って入院中だとか、そういうこともありますよ。 で、本来メインであるそちらの方が案外簡単に終わってしまったので、今日は午後からプランBを発動し、ひたすら母孝行。母の誕生日が近いものですから、お昼は某ボテルの中華レストランでご馳走し、午後は家の掃除に精を出した次第。 そしてこのあとは某デパ地下で買って来た豪華恵方巻きで夕食、そして豆撒きをしてから名古屋に戻ることに。 で、深夜零時くらいに名古屋に戻ったら、今度は名古屋の自宅で豆撒きをする予定。根性あるでしょ? 浮き世の鬼はあくまで殲滅させるのよ。 これでなあ、東京と名古屋がもう少し近いといいんだけど。例えば東京静岡間くらいの距離だとね、大分楽なんだけどな。まあ、そんなこと言っても仕方がないんだけどね。 さてさて、それではそろそろ下に降りて、夕食でも食べに行きますかな。
February 3, 2019
コメント(0)
-
謝恩会の招待
ひゃー、今日は午後から秘密の仕事があったのですけど、それを終えた後、クルマを飛ばして実家に戻ってきました。そう、明日は小学校時代の恩師の墓参りがありますのでね。 もう先生が亡くなってから37年が経つのかな。先生は53歳で亡くなったのだけれど、もうその年齢を私は越してしまった・・・。先生なくば、今の私はないと思っているので、今まで一度も欠かすことなく2月第1日曜日は先生の墓前に立ってきました。で、今年もそれを守ったわけ。 根が893なもので、義理は欠かさないのよ。 さて、そんな義理の固まりの私のところへ、先ほど、今年度のゼミ生の一人からメールが届きまして。 何かと思えば、謝恩会の出欠を取りたいと。 もう・・・がっかりだよ。 大学で4年も勉強して、その成果がこれか・・・。 もちろん、大喝してやりました。お前は自分の結婚披露宴に上司や親戚や友人を招くのに、メールで出欠確認するつもりなのかと。 顔を洗って出直してこいと。 まったく、我がゼミ生ながら恥ずかしいったらない。どこへ出しても恥ずかしい。 もうアレだな。こいつらの謝恩会なんて出なくて良きだな。 まあ、私があまりに時代遅れなのかもしれないけど。
February 2, 2019
コメント(0)
-
ウィキペディアに引用される
所属大学に「リポジトリ」というのがありまして、その大学の教員が論文を書くと、そこに登録されて、ネット上で世間様に公開されるわけ。 で、毎月月末になりますと、自分の論文がどのくらいダウンロードされたか、各教員に知らされるんですな。無論、このダウンロード数によって、自分が書いたどの論文が世間の注目を集めているか、一目瞭然になると。 で、昨日、1月分の統計が出たのですが、これを見ますと、やっぱり自己啓発本関連の論文のダウンロード数が圧倒的に多いんですな。それ以前の純文学の論文を全部合わせたものの10倍くらいのアクセスがある。この数字を見ると、この方面に切り込んだのは正解だったなと、改めて思います。 しかし、今回の数字を見ますと、この他に、数年前に書いたアメリカの「ブッククラブ」についての論文へのアクセスがやけに多いんですわ。 で、ふうむ、なんだか妙だなと思って、ためしにウィキペディアで当該のブッククラブを調べてみると・・・ わー! やっぱり。ウィキペディアのその項目で、拙論が参考文献の先頭に挙がっているじゃないの。 わっはっは。またまたウィキペディアに引用されたわい。 まあね、学者ってのは、論文が引用されてナンボの世界ですから。誇らしいことでございます。 こういうちょっとした成果が、やる気を上げるのでありまして。よーし、今日ももういっちょ、頑張りますか!
February 1, 2019
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1