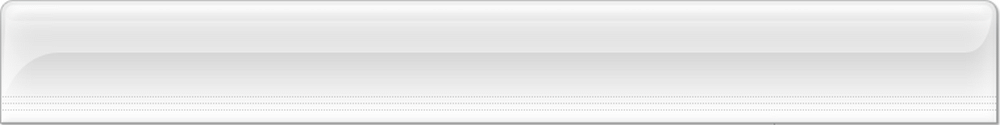2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年05月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
浪曲のすすめ
浪曲のすすめ浅草・木馬亭13:00~15:40あずまりえ「国定忠治」(三味線:渡辺京子)東家三楽 「アラビア久(ひさ)」(三味線:渡辺京子)休憩木村若友 「塩原孝子伝」(三味線:沢村豊子)東家三楽 「左甚五郎」((三味線:渡辺京子木馬亭通いを続ける知人の女性2人が、お気に入りの「おじいちゃん浪曲師」を聞いて欲しいと企画した会。2人の知人・友人を含めて客席は満席。私は、お客さまを整理する場内整理などをちょこちょこと。去年、三鷹の「玉川福太郎追善浪曲会」の後に、tさんから「アラビア久」がいかにすごいかを聞いていたので、「アラビア久」を聞くのが楽しみだった。東郷平八郎、乃木希典と並んで日露戦争の立役者として知られる兒玉源太郎。そんな兒玉の懐から銀時計をまんまと盗んだスリの久(ひさ)。こっそり銀時計を返そうとした時に運悪く捕まってしまった久。アラビア馬を手懐けたことからついた呼び名が「アラビア久」。そんな話から意外な事実が。いかにも浪曲らしいご都合主義のストーリーなのですが、三楽師匠の力でぐいぐい引きつけられました。二席目の左甚五郎を含め、三楽師匠は啖呵読みなので浪曲特有のわかりにくさがなくていいですね。使う節も単純というか啖呵に抑揚がついたくらいに抑えているので筋から置いていかれることもない。はじめての人にはぴったりの浪曲です。御年97歳の若友先生も舞台ではとてもしゃきっとしていて、本当に今聞けただけでお得でした。浪曲をはじめて聴く人も、何度も聴いている人も満足のいく会で、楽しかったです。
May 31, 2008
コメント(0)
-
浪曲大酋長 春野恵子勉強会
浪曲大酋長 春野恵子勉強会下北沢・ビッグチーフ(ニューオリンズバー)20:00~21:00おしゃべり 春野恵子「天狗の女房」 春野恵子 (三味線:一風亭初月)初月インタビュー 聞き手:春野恵子わかりやすく説明するために、どうしても坂本ちゃんのケイコ先生と言わざるを得ないのですが、この人の浪曲を聞くのは始めて。念願の。下北沢の小さなニューオリンズバー。30人も入ればいっぱいという感じの会場。客席には「ちりとてちん」で落語好きの床屋をやっていた人もいる。「天狗の女房」というお話。内容がすごい。水木しげるの妖怪話みたい。鉄砲で撃たれた天狗の夫を見殺しにする妻(人間)。見るも恐ろしい山姥になってしまっていた。妻だって本当は人間の結婚するはずだったのに天狗に無理矢理さらわれただけなのに。恵子さんは節も啖呵もバランスが取れていて、新人とは思えないほど腰が据わっている。ネタがあっていたのか、すごく聞きやすかったし眠くもならず、30分間気持ちが途切れることなく話に集中できてよかった。トークを聞く限り、気持ちも一本気だし、集中力も高そうだし、熱意もあるし。みんなから期待されるのもわかりますね。
May 30, 2008
コメント(0)
-
ルミネtheよしもと 4時6時
ルミネtheよしもと 4時6時16:00~18:30佐久間一行Bコースシンクタンク椿鬼奴あべこうじバイキングどんぴしゃ大木こだまひびき-休憩-雨上がり決死隊 スペシャルコント雨上がり決死隊(宮迫・蛍原) /大山英雄 /ジャリズム(ナベアツ・やましたしげのり)/FUJIWARA(藤本・原西)/ガリットチュウ(福島・熊谷)/ハリセンボン(近藤・箕輪)Y新聞でもらったタダ券の期限が明日までなので、ぎりぎりで。やはり、あべこうじの漫談のリズム感は、何度聞いても心地よい。緩急の付け方が絶妙。よーいドンで始まって持ち時間10分近くをこちらの集中力を途切れさすことなく、最後まで導いてくれる。心地よい音楽に乗せられている感覚。去年のR-1決勝で、何であんなにこけたのかだけはわからないままだ。雨上がり決死隊コント。そりゃテレビの有名人がうじゃうじゃ。ナベアツもちゃんとあのネタやりまくり。みんなの勢いでダーという感じで芸達者のアドリブ的な一発ギャグを楽しむ感じで、リラックスして見られる。コントは、蛍原演ずる漫画家の元にアシスタント志望の宮迫がやってきて、FUJIWARAもハリセンボンもやってきて…そこにお約束のやくざ登場と、コントの筋はめちゃくちゃで、オチもないのだけれど。
May 30, 2008
コメント(0)
-
都家歌六 復活上演落語会
都家歌六 復活上演落語会 『壁金』CD製作公開録音13時30分~お江戸日本橋亭三遊亭金兵衛「」三遊亭とん馬「犬の目」山遊亭金太郎「」都家歌六「壁金」休憩おしゃべり 歌六(聞き手・金太郎)SPゲスト・サキタハジメ都家歌六 「のこぎり音楽」落語家でありながら寄席では「のこぎり音楽」しかやらない歌六師匠(御年78歳、川柳師匠と同じくらい))が、去年から落語をやりはじめ、あまりやり手のいない「壁金」(飴や)という落語のCDを制作するということで行ってみる。平日の午後いちで、午前中は台風の影響で雨。ゆったりとした会場で聞く。客席は落語ファンよりのこぎり関係の人多め?歌六師匠の存在は知っていたけど、どちらかというとサキタハジメ氏ののこぎり音楽を聴いて、のこぎり音楽の魅力に気づき、その後何人かののこぎり音楽を聴いた時にみんながみんな歌六師匠のCDを聞いたのがきっかけというので改めて歌六師匠に注目してみたくなった次第。逆輸入だ。歌六師匠は二つ目の時から「のこぎり音楽」に転向して以来、落語をほとんどやってこなかったようですが、最近になって「自分は落語家」と、落語の稽古を始めたようです。今回は『壁金』という古典落語をCD化するそうでその収録もかねて。『壁金』は「孝行糖」に近い飴やの話(古典落語)。売り声の枕から入り、飴やの売り声がきっかけで一騒動。「飴の中から太田さん(?)と金太さんがとんで出たよ」。演題がオチそのものなので、ネタばれしてるのですが、「孝行糖」と同じくらいばかばかしい。落語への意欲を取り戻した歌六師匠にもっと落語での出番があるといいですね。「おしゃべり」には客席に見に来ていたサキタ氏も加わり、2人の出会いなどをちょこっと。
May 20, 2008
コメント(0)
-
「ガリヴァー・ウエハース」
「ガリヴァー・ウエハース」14時~15時30分横浜にぎわい座のげシャーレ琵琶法師で俳優の伊藤哲哉氏による、バンジョー弾き語り一人芝居。ガリヴァーが日本にやってきて今年が300年なんだそうです。伊藤氏は、当時ガリヴァーの通訳を担当していた日本人の末裔となり、ガリヴァーの冒険を語っていく。小人の国や巨人の国、踏み絵の話(郵政民営化の)、天空城「ラピュタ」の話、不老不死の話、大発明(言語の覚え方)など、スイフトの「ガリヴァー旅行記」に出てくるエピソードを面白く味付けしている。実際、私は「ガリヴァー旅行記」の中身を知らないので、今日の話を聞いて、「ガリヴァー旅行記」の一端がつかめた。可愛らしげがある「ガリバー」の操り人形、天空城「ラピュタ」のセット、食べると言葉が覚えられるウエハースと、フラットな舞台に、工夫をこらした大道具・小道具が登場して楽しい。ラピュタの下にある国では、ウェハースを研究していて、そのウェハースを噛まず、水を飲まずに飲み込むと言葉が覚えられるんだそうだ。観客には本物のウェハースがタダで配られる。「噛まず、水を飲まずに食べてください」「あっ、でも、このペンで書かないと駄目なんです。ウェハースはタダですが、このペンを700円です」ですって。ガリヴァー・ウエハースだから「ウエハース」まっとうすぎて面白い。よく見たらチケットもウエハースだった。劇中歌も何曲か。「天空城ラピュタ」とか。「不老不死」の歌は、老人になってから死なないから、大変なことになっていく。原作・ジョナサン・スイフト脚色・稲田和浩、伊藤哲哉照明・渋谷博史衣装・美術・石田百合宣伝美術・齋藤瑞江企画・製作・吉岡孝子、菊地廣
May 18, 2008
コメント(0)
-
第28回「東西落語研鑽会」
第28回「東西落語研鑽会」 18時30分有楽町よみうりホール林家市楼「あみだ池」 柳亭市馬「片棒」 桂文珍「風来坊」(「アドバルーン」金語楼(改作)」仲入り 笑福亭鶴瓶「回覧板」(私落語) 柳家花緑「竹の水仙」チケットありますメールを久々にいただきありがたく購入。相変わらずですが、ここのお客さんは最初から笑う気満々で、反応すこぶるよし。「片棒」がこんなに受けてるのを久々に見た。市馬師匠の腕もあるけどそれ以上に。文珍師匠、あれだけ受けた片棒の後、やりづらいのに、枕でどんどんつかまされた。やはり吉兆ネタのいじり方は、さすが地元関西だけあって、東京の人たちのいじり方とは1腕も2腕もちがいますね。面白かった。演題は「アドバルーン」を変えなくてもいいのに。ネタバレするってことなのか? よくわからん。「アドバルーン」自体が昭和的でいい。鶴瓶師匠、鶴瓶噺の時にちらっと聴いた、奥さんのレイコさんを元に作った私落語。立ちでさらっとやった時より当然いい。結局は、夫婦愛を見せられてる感じもしなくないけど、それはそれで面白いし。花緑さんの「竹の水仙」無理しないで等身大でキャラ作っているんですね。だから、登場人物がみんな若くて活き活き。宿屋の主人「開業以来、一文なしを泊めた数39人、甚五郎で40人目」という設定は、本人なのか誰かが入れたのか、わかりませんが、具体的な数値を見せることで、説得力が出ますね。最後に甚五郎に「一文なしを40人も泊めるようなお人好しだから、水仙作って儲けたお金をやるんだ」と言わせる演出は、設定が生きているのでうが、ドサ過ぎて私なんかは引いてしまうのですが、今日のお客さんにはきちんと届いているし、まあこの規模の会なら「あり」でいいのかと。
May 15, 2008
コメント(0)
-
新作落語・聖せめ達磨学園 vol.14
新作落語・聖せめ達磨学園 vol.14なかの芸能小劇場19時~21時30分(前説)天どん、今輔三遊亭たん丈「金田一探偵事務所」春風亭栄助「あの姉妹」立川らく里「落武者峠」ゲスト/寒空はだか 休憩三遊亭ぬう生「選挙ホスト」林家きく麿「ロドリゴ」打ち上げの席で会の名前が変わることがあるそうです(らく里さん枕より)前説には披露目中の新今輔さんも駆けつけるなどその仲間思いなところがいい。「あの姉妹」は、○のう姉妹のパロなんですが、いかにも言いそう。ネタの種を、きちんと最後までストーリーとして作り上げるところがすごいですね。「選挙ホスト」ぬう生さんのホストシリーズは、どんどんよくなっていって面白さもアップしていきますね。リアルホストからは離れる(今は不良の兄ちゃんでも通じる)のだけれど、ホストの翼君というキャラができていて、翼君がいろんなことをしでかすのが面白くて仕方ない。そして、今しか使えない旬のネタもたくさん入っていて、おばさん候補にエドはるみのギャグ言わせたりしてるし。「金田一探偵事務所」たん丈さんの行く末がちょっと心配になるけど、想像もつかない落語ですごい(面白いとかそんなのは置いておいて)
May 13, 2008
コメント(0)
-
瞳、厚姫
瞳、厚姫朝ドラの「瞳」になって1ヶ月。今1どころか今2くらいで面白くならず。おかげで朝の目覚めが悪。里親制度、ヒップホップとなじみの薄いテーマを扱っているけど、それは興味深いし、演技陣も悪くないし、筋だって普通に見られる。でも、主人公は理想の若い子でなくて、結構いい加減だったり、冷めていたりする今どき風。それが朝ドラっぽくなくていいのですが、あまりリアルに近づけると、感情が入り込めないんですかね。ベタを排除してしまうと、こうなるのか~と、面白い発見。今期のサラリーマンNEOは、コントの出来に落差が大きいのですが、厚姫は久々ヒット。篤姫のパロをNHKがすぐやってて、厚かましい姫、姫島厚美を堀内敬子さんがやるセンスがオモロ。
May 11, 2008
コメント(0)
-
オンエアバトル 5/30分
オンエアバトル 5/30OA分NHK。10本見て審査するのはかなり疲れる。面白いかどうかで判断してる周りの人たちは本当にすごい。左隣りは11歳の男の子とそのお母さん、右となりは女子高生。100人の投票で、結果は現場の雰囲気のままほぼ順当に出てるわけで。(前説) さじたり?(男女コンビ。おかまコント)WエンジンなすなかにしピースジェニーゴーゴーしずるCUB&MUSI(カブトムシ)三日月シュガーミスマッチグルメニッケルバックプラスマイナス
May 10, 2008
コメント(0)
-
物語・落語現代史(1回)
物語・落語現代史(1回)中野ZERO視聴覚室19時~21時東京かわら版の連載に一区切り付けた夢月亭清麿師が落語家の身体から生まれた物語として落語史を語るというもの。今日から毎月1回、全12回。第1部 落語形式で清麿がテーマについて語る第2部 今岡謙太郎氏(武蔵野美術大学教授)とテーマについて討議。第1回目のテーマは、柳家金語楼。吉本と東宝、浅草、古典と新作、鑑札に登録されていた「寄席」の状況など興味深い話題が続く。近世芸能専門の今岡謙太郎さんは、早稲田の寄席演芸研究会出身で落語家を目指したこともあるそうなので、しゃべりが達者というか落研にいる落語マニアタイプで、普通に上下を切ってしゃべる。今後、プロレス的なバトルもできそうで期待は広がります。1回目ということで、お客さんも入っていて、おじさん的な人から、学生っぽい人までいろいろ。第2回は6月3日(火)「昭和10年~15年/戦争に向かって 講談・浪曲ブーム」詳細は
May 9, 2008
コメント(0)
-
桂歌之助独演会(東京、第一回)
桂歌之助独演会(東京、第一回)19時~21時20分新橋・内幸町ホール桂二乗「牛ほめ」桂歌之助「青菜」三増れ紋 曲独楽桂歌之助「骨つり」 中入り桂歌之助「善光寺骨寄せ」「骨つり」「善光寺骨寄せ」と、東京ものには珍しい噺が2席。骨つながり、五右衛門つながりという趣向もあって意気込みを感じる会。「骨つり」は「野ざらし」と源流が同じですが、噺のコンセプトや聴かせどころは全く違う、「地獄八景」を作った米朝師匠らしい味付け。「骨つり」の流れは、茂八と若旦那の釣果談義→骨つり1→回向1→幽霊1(女)→隣家の喜六→骨つり2→回向2→幽霊2。東京の寄席でかけられる「野ざらし」は、尾形清十郎と隣家の八五郎→骨つり(で切る)。続くストーリーは、骨を釣った八五郎を訪れたのは、勘違いした太鼓持ちだった。「善光寺骨寄せ」は「お血脈」と同じなのですが、、地獄でバラバラになっている五右衛門の骨を寄せ集めて元の身体に戻してから善光寺に送り込む。骨を集めるシーンで、実際に骸骨の人形使って見せるのが趣向で、先代歌之助師匠の持ちネタだったそうです。それを継いだ当代が、昨年初のネタ下ろし。今日が3回目。私は先代の骨寄せを見たことがないので、今回が初めて。現時点では骨がちゃんと組みたたるかどうがというところに注目が集まってしまって他のところまで手がまわらないのですが、とりあえずこんなアホなことをやる人は先代以外いなかったそうなので、アホなことを継いでやっていこうというのがいかにも落語らしくていいですね。エンタメ的に見たら本当にいろいろ工夫の余地ががあるので、よちよち歩きのこの噺の今後が楽しみになる。江戸版はほぼ漫談なので、腕のいい人がやればふんだんに笑わせられる大爆笑噺になるのですが、それを捨ててまで「形」を見せるのがいかにも上方らしい。
May 7, 2008
コメント(0)
-
大演芸まつり 浪曲大会
大演芸まつり 浪曲大会国立演芸場13時~16時澤会長から託された武春さんの企画で、若手の顔見世公演。2006年、2007年入門の若手(年齢的にも)4人(男2名、女性2名)のお披露目。『もぎたてカルテット』という微妙なネーミングは置いておいて「我々の頃は国立の舞台を目標に修行して、晴れて国立に立てた時はうれしかった。今回は、若手に最初に大きな舞台を踏ませ、そのうれしさや感動を励みに、また出てみたいと思って欲しい」(武春)と最初に飴をやって頑張らせようと。東家一太郎「水戸黄門」(二村邦夫作、三味線・佐藤貴美江)浪花亭友歌「男の花道」(三味線・沢村豊子)玉川太福「不破数右衛門」(三味線・玉川みね子)澤雪絵「愛染の峰」(三味線・佐藤貴美江)浪曲大喜利(司会・武春、友歌、雪絵、太福、一太郎、三味線・豊子、貴美江、みね子、構成・稲田和浩) 中入り口上(司会・春日井梅光、澤孝子、三門柳、、三遊亭金馬、東家浦太郎、国本武春)国本武春「紺屋高尾」(三味線・沢村豊子)早大一文卒の元TVディレクター、国立大卒、元電器屋店員、演歌歌手と、バラエティ豊かで立派な経歴を持つ4人。浪曲をものにするのって、本当に時間がかかるのだな~と最近やっとわかりかけてきたので、辞めずに地道にこつこつと頑張って欲しいですね。こちらも見続けないと、という気になります。とにかく満員大盛況で出演者の知り合い関係も混じっていたのか、若い人も結構いました。一太郎さん、4月8日に木馬の初舞台を踏んだばかりとか。台本をなぞるように丁寧に演じてた。「水戸黄門」の台本、若き日の光圀を描いているのですが、すごいです。いきなり性に目覚めた光圀は、遊郭通いを始めてしまう。なぜか「ポルノ」という台詞が出てきたり、側近から「フォーカス・フライデーされたら困ります」とか(もうフォーカスないけど)「エイズになったらどうするんですか」と言われてる。改心して勉強に励んだら今度はさくら茶屋の女の子(おその)との恋物語。と思ったら、おそのと、そのの父が浪人に惨殺されて、怒りに震える光圀。いざ敵討ちかと思ったら、側近の機転で仇相手が先に詰め腹切らされていてカタルシスなし。エロとジェットコースター展開と尻つぼみ。物語としては、いろいろ入ってて面白いけど、ドラマ性は一切ないというか感情移入を完全に廃した変な本。初めて覚える浪曲がこれでいいのだろうか。大福さん、声の出し方が福太郎さんとそっくりだし声もでかい。音程が安定すれば安心して聞けるようになるかも。友歌さん、丸顔の原千晶みたい。現役演歌歌手の本領で他の3人より聞けるしいい。演歌の人特有のがなくなって、序々に浪曲に近づいていく過程を見るのは面白そう。浪曲大喜利、台本の存在など微塵も感じさせない自己紹介や「もぎたて作文」など見どころたくさん。口上は梅光さんのボヤキ司会がオモロ。
May 6, 2008
コメント(4)
-
渦18 春風亭栄助独演会「くらえ丼飯っ!!」
渦18 春風亭栄助独演会「くらえ丼飯っ!!」19:30~21:00しもきた空間リバティ春風亭栄助 1人コント「落語家育成スクールNRC」春風亭栄助「野ざらし」東京ガールズ 俗曲春風亭栄助 「リアクション指南」木村万里さんの渦産業主催ライブ。1日~4日までの初日の今日は「らくご渦」。周囲の人の話をつなぎ合わせると栄助好き派と普通派(あえて苦手派とは言わず)に分かれるようですね。でも万里さんにははまっている栄助さん。システム化されているものにツッコミを入れていく栄助スタイル。正面からでなく、あくまでも斜めから裁いていくところが、いかにも落語家らしくていい。「NRC」(New Rakugoka Creation)は、吉本のNSC(New Star Creation)を落語風にパロったものだし、「リアクション指南」は、熱湯風呂をパロッたもの。決してアイデアだけで終わらせず、キャラクターを作っているので、安易なパロディではないのです。恐らく子供の頃から積み上げてきた笑いのセンスに、落語家独自の修行が加わってのことかもしれません。このあたりは感覚にフィットするかしないかという部分が大きいので、好き嫌いで分かれるのはわかるような気がします。東京ガールズさん(小糸、小寿々、小夏)は、久しぶりに見ましたが、やはり紫文さん効果なのでしょうか。東京ボーイズを意識してか三味線1本笑いの構成がしっかりしてますね。「なんだこれ?」的な反応から序々に引き込まれていくのがわかります。初めての人でも時間かけて笑わせていくのは、TVで主流のワンフレーズ芸ではできないところです。
May 1, 2008
コメント(2)
-
『すべては音楽から生まれる』茂木健一郎
『すべては音楽から生まれる』茂木健一郎PHP新書昨年12月刊行。図書館でリクエストしておいたらやっと回ってきた。副題は脳とシューベルト。脳科学者が理屈をこねるというよりは、ライブ体験を通して、音楽はいいよということを言ってる感じの本。茂木さんの高校時代、文化祭では毎年学年でオペラを発表するしきたりがあり、2年の時にやった出し物で主役の女の子がハプニングで1オクターブ高い声で歌って、そのまま歌いきってしまって感動した。などというエピソードも書かれている。後半から怪しい様相を見せ、しまいには上手くできた広告本を読まされた感じになってくる。(引用)--------------音楽における体験の豊かさや感動の深さという点では「ライブ=生演奏」に勝るものはない。どんなにすばらしいライブでも、録音では、演奏会場での感動と同じものを享受することはできない。脳へのサインを送る力というものを考えると、CDやDVDの音は、ライブ演奏を決して超えられないのである。(中略)もちろん、毎回すばらしい演奏に出あえるとは限らない。ただ、可能性は常にある。それは身を委ねる価値のある可能性だ。一回性の出会いを求めて、私はコンサートホールに足を運ぶ。それが「生きる」といことであり人生そのものであるかもしれない。----------------------冒頭1章では、音楽はいかにライブに限るかを語る。演芸や演劇も「ライブが一番」という主張と同じなので、共感する部分は多い。1992年3月、NHKホールで茂木さんが聞いた演奏に触れている。シノーポリが指揮したウィーンフィルのシューベルトの交響曲「未完成」。-----------------客席にいる私にも「歌え、鳴り響け」と訴えかけているかのようだった。そんな音楽体験をしたことがある。-------------そうそう、いろんな所で聞いたり見たりしていると、そんな体験が積み重なってくるものだ、と共感を覚える。で、最後の章になると、ゴールデンウィークに開催されるクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」のついて触れ、プロデューサーであるルネ・マルタン氏との対談を掲載している。「ラ・フォル・ジュルネ」を知らなかったので調べてみたら、GW期間、東京国際フォーラムや丸の内界隈いたるところで生のクラシック音楽の演奏が聴けるらしい。チケット代も2000円、3000円くらいの低価格。いろんな人にクラシックを聴いて欲しいといったイベント。無料イベントもあったりして有楽町近辺がクラシックに囲まれる。わかりやすく言えば「大銀座落語祭」と全く同じ(わかる人にしかわかりやすくない)。で「ラ・フォル・ジュルネ」の今年のテーマがシューベルト。うーん、何だかこの本を読んだら、ラ・フォル・ジュルネに興味を持ってチケットを買う人が続出してしまいそうだ。『R25』に近い、相当仕組まれた感じもしなくない。実情はどうなのかわかりませんが。しかも、この本とのタイアップでクラシック・コンピレーションアルバム「脳とクラシック」、「脳とシューベルト」、「脳とモーツァルト」が、4月30日にエイベックスから3タイトル同時リリース…。たまたま自分が読んだのが4月29日で、明日にでも始まろうというタイミング。(今年は5月2日から6日まで)。おかげで今日、神田で取材を終えた後、有楽町のビックまで買い物に行き、ついでに様子を見て来てしまった。イベントとしてはとても面白そうで、仕事さえなければ是非行ってみたいところだが、「大銀座落語祭」同様、主要なチケットは結構売れてしまっているようです。
May 1, 2008
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 楽天ラッキーくじ
- 楽天ラッキーくじ更新情報(2025/11/…
- (2025-11-20 20:09:48)
-
-
-
- 楽天市場のおすすめ商品
- ◆仙台発祥!牛たんの名店のご紹介
- (2025-11-20 18:30:10)
-
-
-

- ジャンクパーツ
- 秋原他でのお買い物250111ハーフその…
- (2025-02-15 18:03:22)
-