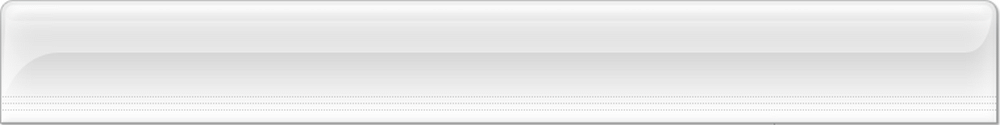2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年09月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
古今亭志ん朝 追悼 落語会
古今亭志ん朝 追悼 落語会国立小劇場 18:30~落語研究会40周年記念。東京K版のプレゼント応募で当選。久々の表側の小劇場。落語研究会独特の雰囲気も久しぶり。古今亭朝太「道灌」三遊亭歌武蔵「猫の皿」古今亭志ん輔「お見立て」お仲入鼎談 志ん橋・志ん輔・朝太 司会…竹内香苗(TBS) 林家正蔵「岸柳島」古今亭志ん橋「抜け雀」命日の1日を前に開催。それぞれがマクラで志ん朝との想い出を語る趣向。朝太さん師匠に直接稽古つけてもらった時に録った「道灌」のテープ、宝物といいながら先日探したら無くしちゃっただって。鼎談は司会のTアナがあまりお上手でないため盛り上がらず。最後の挨拶、上から順で一番下で締めるって…。
September 29, 2008
コメント(0)
-
ルミネtheよしもと 9/29 2回目
ルミネtheよしもと 9/29 2回目新宿ルミネ15:00~17:30(ネタ組)オリエンタルラジオしずるロバートハリガネロックパンクブーブートータルテンボス大木こだまひびき休憩新喜劇「幸せになるためのドレス」ほんこん(130R)/大山英雄 /本田みずほ /芦澤和哉 /功力富士彦 /シベリア文太/内海仁志/ジパング上陸作戦/三瓶/ほかオリラジの生ネタは初見。ロケット団などに近い、割とオーソドックスな漫才にオリラジ風味。ネタのブリッジがかなりロケットなどと比べるとかなり間が空くスローテンポで間が不安。トップだからか意図的なのか。もう少し数を見たい。ロバート、形は昔のネプチューンなんだけど、秋山の天才的な切り口で斬新なコントに。天才故に一般受けしにくいからC-1は難しいのかもしれないのですが。新喜劇は2度目のねたですが同じねたでもオモロイ。大山英雄もガリレオ映画化で再バブルか。
September 29, 2008
コメント(0)
-
おくりびと
おくりびと松竹ピカデリー新しくなった新宿松竹はじめて。おくりびとは一番でかいホール(580席のところ)でやってた。スクリーンが異常にでかい。観客も多かったし、口コミで広がっている感じの客層。今月号のシナリオ誌に載っていて、立ち読みで読んだだけでも面白かったのですが、絵で見るとまた違った味わいに。納棺師の映画だから、死体はいっぱい出てくる。しかし、体をふいたり化粧を施していく作業は様式美にあふれていて、死体との向きあい方にも優しさがにじみ出ている。納棺師になったばかりの主人公(モックン)とベテラン社長(山崎努)の関係は、師匠と弟子の関係でもあり、納棺師の様式美を身につけるためにモックンは師匠の山崎努から心を学んでいくのです。脚本の小山薫堂さんのオリジナル脚本もつぼを得ているうえに全体が優しい。滝田洋二郎監督と2人の人柄のよさが出ているんでしょう。納棺師って職業が映画では最初から差別されてて、夫が納棺師やってると知った広末が「子どもに胸を張って言える?」とか「辞めるまで実家帰る」と言ったり、友達が納棺師やってると知っていきなり冷たい顔する。構成上必要とはいえ、現実にそんな差別的な職業なんだろうかという疑問もわくところですが、山形の田舎だし、昔ながらの地域はそれはそれであるのかもしれない。シナリオ読んでて、えっと思ったモックンが欲情して広末に襲いかかるシーンも本当に襲いかかってた。先週までドラマで「くそアマー」「なんだと」と言ってた元レディースの総長とは全然違うカマトトキャラですが、広末ってこんなによかったっけと思わせる演技でござんした。モックンは元チェロ奏者ということでチェロ弾くシーンやチェロの音楽もたっぷり。チェロっていい響きなんですねぇ。鳥の唐揚げをがぶがぶ食いまくってチェロ弾いた時は、ちゃんと手を拭いたのだろうかと心配になった。
September 27, 2008
コメント(0)
-
瞳終了
瞳終了やっと終わった。どっちかというと、とんでもの部類に入るドラマだった。大抵は1ヶ月でキャラになじむのに、これに限っては3ヶ月くらいかかった。キャラにさえなじめばストーリーなどはたいしたことないのが朝ドラなのですが、今回はすごく厳しかった。ラッパ屋のお芝居好きとしては鈴木氏の力量が発揮できなかった環境が惜しいところ。巨人がメイクレジェンドと言っても、2chでずっと「レジェンド」とか「棒」とか言われてきたエグザイルメンバーがいるので、ピンと来ない。
September 27, 2008
コメント(2)
-
国立演芸場9月中席
国立演芸場9月中席国立演芸場18:00~21:00柳家小んぶ「道灌」鈴々舎わか馬「黄金の大黒」ホームラン 漫才柳亭市馬「粗忽の釘」神田茜「あの頃の夢」古今亭菊志ん「禁酒番屋」仲入り松旭斎すみえ マジック三遊亭小金馬「祇園祭」ぺぺ桜井 ギター漫談柳家小満ん「二階ぞめき」知人から半ば押しつけられるようにいただいたチケットで。国立の寄席独特の雰囲気がいいですね。色物の出番の時は必ず緞帳をおろすし。茜さん久しぶりに見た。茜版の芝浜「あの頃の夢」。がちがちの古典ファンに伝わらないのがもどかしい。菊志んさんのロングヘアはいつまでやるんだろう。切らないうちに見れたらラッキーです。すみえ先生のマジック「チャラララララー」と、マジックの定番の音楽で始まる定番の手品は久しぶり。ベタの真骨頂。おしゃべりも楽しい。
September 19, 2008
コメント(2)
-
亀田鵬斎
亀田鵬斎NHK教育のてれび絵本という番組(7時45分~50分)で、今週と来週はえほん寄席をやってて、柳家さん生師匠で「亀田鵬斎」という落語を聴いた。ものすごく単純明快な落語なのですが、雰囲気があって面白い。亀田鵬斎って書家(儒者)だけで落語ができてしまうとかも。
September 19, 2008
コメント(0)
-
第一回 大江戸落語勉強会
第一回 大江戸落語勉強会おたのしみ『講座・高座』 野方区民ホール19:00~21:00講座「江戸塾」 ~寄席の楽しみ方あれこれ~ 講師 井上和明(東京かわら版発行人)瀧川鯉八「」初音家左吉「紙入れ」仲入り初音家左橋(補導出演)「親子酒」マギー裕基 マジック古今亭志ん八「黄金の大黒」ご近所だし、行ってみたいと思って「東京かわら版」見たらご招待ありと書いてあったの応募したら当たった。地元民以外、かなり行きづらい場所なので、どんなお客さんが来るのだろうという興味もあり。高座そのものより落語会そのものが興味深し。前座からマジックまで、全員が法政の落研出身者らしく、スタッフにも若手ボランティアみたいな人がいたり、キャピキャピのお姉ちゃんが受け付けやってたり。変なおじさん(P)が前説やったり。江戸塾は、講師を招いて落語や江戸文化についてお勉強するコーナー。第一回は東京かわら版の井上社長。聴き手のおじさん(井上氏と同年)が、どちらかというとしゃべりたがりのタイプだった。途中で前座の鯉八さんを招き入れて、前座の役割などを聞いていた(入り時間、下っ端前座と立て前座の違い、お茶出しなど)。寄席芸の面白さが見られたのは左橋師匠の高座。客席に、一般人と違うところで独特な笑い方を発する車椅子の男性がいました。親子酒の導入部にお酒を「キ○ガイ水」といって禁酒する下りがあるのですが、左橋師匠はそのフレーズを入れずに普通に流していた。ちょっとしたことですが、流れを読んだ高座に改めて関心させられました。
September 18, 2008
コメント(0)
-
桂歌之助上京 Vol.10
桂歌之助上京 Vol.1013時30分~16時玉川太福 浪曲「不破数右衛門の芝居見物」(曲師・玉川みね子)桂歌之助「イタリア報告」~「軒付け」~踊り「木遣り崩し」仲入り都家歌六 のこぎり音楽桂歌之助「くっしゃみ講釈」年に1回、私がプロデュースする公演。何やかんやで10年目(通算11年目)。企画を立ててブッキングして、チラシ配って、当日は受付もするし打ち上げの心配もする。どんな演芸会でもそうですが、プロデューサーは何でもやらないといけない。今年は歌六師匠ののこぎり音楽をぜひやりたかった。去年、繁昌亭で歌之助と競演したことを聞いて、東京でも見てみたい、見せてみたいと、すぐにアプローチしました。ちょうど、その頃サキタハジメ氏の出るテレビを見ていてのこぎり音楽に改めて興味を持っていた時期だったのでジャストタイミング。浪曲の玉川太福さんは、東京かわら版4月号の演芸年鑑がきっかけ。プロフに出身大学が出てて同窓と知ったから。浪曲も好きな自分が放っておくわけがない。すぐに姉弟子の奈々福さんに連絡とって紹介してもらった。さらに正月にラジオで聞いた米朝師匠と歌之助の対談で米朝師匠から「踊り」をやりなさいとハッパをかけられていたので踊りもリクエスト。結果的に、浪曲、踊り、のこぎり音楽、さらに歌之助の2席(浄瑠璃、講談、漫談)もついてバラエティに富んだ会に。バラエティ公演は、敬遠する人も多いのですが(幕の内弁当より単品弁当が好きな人もいるので)、何だかんだいって多くのお客さんに集まっていただけてほっとした。落語のお客さんに浪曲をどの程度わかっていただけるか、常に不安ではあるのですが太福さんにはわかりやすいネタを選んでいただき、みね子師匠には出弾きで弾いていただき、いい高座になりました。同窓で演芸関係者としてバックできたら。のこぎり音楽も大勢の方に満足していただいたようで何よりです。客席に回って聞きたかったくらい。そして、歌之助君もマクラから飛ばして最後まで勢いが途切れることなくお客さんを満足して返す。安心して任せられるから自由にできるんですな。イタリア報告は、これで一席の落語になるのでこれから高座にかけられて研ぎ澄まされていくのが楽しみ。マクラの創作能力としゃべりのテクニックは埋もれさせておくのはもったいないので何かうまく仕掛けらないだろうかと。
September 14, 2008
コメント(0)
-
末廣亭深夜寄席
末廣亭深夜寄席新真打卒業公演21:30~23:00三遊亭あし歌「宗論」三遊亭歌彦「初天神」春風亭栄助「生徒の作文」古今亭菊可「巌流島」古今亭志ん太「豊竹屋」21日からは真打昇進する5人の卒業公演。毎度混雑する会なのですが、開演15分前についたら明治通りまで行列ができていた。渋々並んで、桟敷席の2列目に強引に座って見る。5人で90分なので、演者はほとんどマクラを振らず。初天神も天神に向かうところから入って飴までのコンパクト版。栄助さん、せめ達磨でやった「犬のキ○タマ」を寄席の高座でやるかどうかどきどきしてたのですが、そこはなしの栄助版新・生徒の作文。志ん太さんはさすが真打という迫力の芸。顔芸、声芸で根こそぎ持ってく面白さでした。
September 13, 2008
コメント(0)
-
『怪談牡丹燈籠』 花組芝居
『怪談牡丹燈籠』 花組芝居東池袋・あうるすぽっと(豊島区立中央図書館のあるビル)19時~21時40分(途中休憩15分)チケ代それなりにするのですが、島唄を一緒にやってる方が照明チーフやってるし、稲田さんもブログで褒めてたので当日券で。行って正解。おもしろかった。三遊亭円朝の『牡丹燈籠』全編通しを2時間30分足らずで見せる。お露の幽霊が新三郎を呪い殺す「お札はがし」はサイドストーリー。刀屋の一件で飯島平左衛門に父を斬り殺された孝助。何も知らずに剣の達人である飯島平左衛門に仕えた。その中で孝助は本当に仇を討つ相手に気付き、仇討ちを果たすまでの壮大な因縁話。演劇というビジュアルで見せてくれるので、複雑な人間関係もすっきり理解できる。頭の中で組み立てなければならない落語と比べてはるかに楽をしてる気分。その分、感情に訴える部分は少なくなるのですが、舞台転換のスピードとかジャズとか現代的くすぐりとかいろんな演出や遊びが楽しい。照明さんの仕事も素晴らしい。演出の加納さんも言ってますが、『牡丹燈籠』の本を全編読む必要がなくなる。断片的に知ってる『牡丹燈籠』ってこんな話だったんだと。落語の知識がある人なら面白く見られると思う。小屋は300のキャパでいい感じ。後方に空席が結構あったので、平日ならたぶん余裕。週末の連休はわりと埋まっているらしいのですがどうなんだろう。東京公演は15日まで。
September 11, 2008
コメント(0)
-
新作落語・聖せめ達磨学園 Vol.16
新作落語・聖せめ達磨学園 Vol.16なかの芸能小劇場19時~21時25分(前説)きく麿、らく里(NHKの新人コンクールについて)前座 鈴々舎やえ馬「卒業式の掛け合い練習」三遊亭ぬう生「研修ホスト」林家きく麿「白湯を一杯」ナイツ(ゲスト) 「漫才」(ドラエモソ、ドラゴソボール、オリソピック) 仲入り春風亭栄助「生徒の作文’08」三遊亭天どん「スイカ泥棒」6、7割の入りというのが、いつものせめ達磨らしいといえばそうらしくもあり。でも女性率が高いんですよ。7割くらい。いろんなこだわりが楽しめた会。きく麿さんは白湯(さゆ)にこだわる人の話。「何で白湯にこだわるんだろう?」と、自分の中でずっと考えているだけで面白いし、栄助さんは何で犬のキンタマにこだわるんだろうとか、天どんさんはストーリーにスイカ泥棒が出てこないのに、スイカ泥棒にちょいちょいこだわるんだろうとか。人の考えるこだわりがとてもよく引っかかる。ぬう生さん、ホスト経営の翼くん、とうとうお寺に社員研修に行っちゃったよ。翼くんはどこへ向かおうとしているのか、毎回楽しみ。ブレイク前の狩野英孝とほぼ同じ時期から始めたホストキャラ。どちらのキャラも面白い。今日一番受けたのはナイツで、今のナイツは敵なしの状態か。
September 10, 2008
コメント(0)
-
第29回「東西落語研鑽会」
第29回「東西落語研鑽会」 18時30分有楽町よみうりホール桂まん我「船弁慶」橘家圓太郎「かんしゃく」柳家喬太郎(全国落語台本コンクール佳作授賞作)「出てきて!おとうさん」全国落語台本コンクール授賞式 (喬太郎、正蔵)仲入り〈京の噺特集〉林家正蔵「祇園祭」春風亭小朝「池田屋」桂小米朝「愛宕山」(以下長文失礼)振ってわいたように訪れて過ぎた1日。8日(月)22時30分頃に着信。「落語台本コンクールで佳作に選ばれました。今年は優秀賞がなくて佳作が2本です。で、明日喬太郎さんやります。来られますか」「私が出したのが高座にかかるってことですか?」「はい」「普通にチケット買ってます」「表彰式もありますからよろしくお願いします」昨年の受賞者の方も直前に連絡きたみたいなことを言ってたのですが自分がそうなるとは。弱ったが本音。研鑽会のコンクールは過去の例からしてしっかりした古典新作か短編小説系が選ばれる傾向にある。恐らく、主催もそっち系の話を求めているはず。一方、自作はギャグ多めの現代新作。人間の機微や人情など1つも描いていない。書いた時も佳作あたりに引っかかれば思っていて、実際にそうなったのですが。超一流の演者がやるとはいえ、1000人の観客の前でこのネタかけていいんだろうか? プログラムの中に入って耐えられるのだろうか? の不安のほうが大きい。自作のネタが高座でかかるのは初めてではないし、コンクール入賞も含めて他の落語会等で7、8本はかかっている。うれしいというより、受け入れられるのだろうかという、ネタおろしする落語家さんと同じ感覚。しかも観客の期待値は高くないわけで。で、自己分析。喬太郎さんはキャラを際だてながらほぼ原作通りに運んでくれたので、ネタ全体のあらがよくわかった。本当に演者の喬太郎さんには感謝です。この調子だと短い準備時間しかないはずなので。原作の構造は「起承転結」の基本原則に則ったもの。誰が聴いてもどこが「起」でどこが「転」か理解できるようになってる。セオリー的には「承」のエピソードを承<承<承と大きくしていかなければならないのですが、そのあたりが単調。切っていいエピソードもある。ネックは、漫才コントみたいなところ。作品読み返して、コントだよな~と思ったほどで、ストレートに流れていく。落語っぽくするなら、伏線を張ってダイナミックに動かしたり、承のどこかで大きな芝居をさせるところがあったりもう一ひねりしたいところ。また、「転」から「結」に至る流れや、サゲもかなり弱い。とまあ、設定が受け入れられるかどうかも含めて、いろんな反省点があるのですが、それも含めて生の高座は勉強になる。演者さんの力量は大いにありますが、このくすぐりは受けるんだとか、ここはネタのせいで盛り上がらないんだなど、お客さんの反応が直接わかるのもならでは。ドラマでも映画に演劇にしろ、初稿がそのまま作品になることはない。何人かの手を経たり稽古を経て、数回書き直して決定稿になる。でも、落語の場合は初稿GOもあり得る。噺を作ってくれるのも直してくれるのもすべてはお客さん。演者でも作者でもないというところが落語的であり、怖いところ。雑誌、書籍、広告、Web等で記事を書く仕事を10年以上していますが、生のリアクションが得られる機会はないだけに、この針のむしろ感は居心地が悪い。どこかに行きたくなりますが、そのむしろ感は悪いわけではない。課題は、小品志向から脱して、大きなドラマを書くことですかね。わかりやすいけど何かしら心に残るものを。ブログ検索、Google検索すると、ここにヒットする率が高いので、できるだけわかりやすくまとめてみました。余談 もう1本の佳作「2/3の嘘」は吉本の漫才「2丁拳銃」の小堀氏作。9日~15日まで神保町花月で上演中の『本当の嘘』(脚本:小堀氏)の原案だそうなので、当日上演できなかったものは神保町に行けば芝居で見られるのではないでしょうか。全体の感想小米朝名前で「愛宕山」。導入部の「ひばりがピーチクパーチク」は、「ちりとてちん」の渡瀬さん演じる「愛宕山」で渡瀬さんがひばりはピーチクパーチクだと直したもの。米朝版は「ひばりがチュンチュン」。上方の人にはよく知られたエピソードかもしれませんが私は初耳でした。圓太郎さんの「かんしゃく」も十八番ネタだけに面白さが際だつ。時間つなぎのマクラも迫力あり。
September 9, 2008
コメント(11)
-
両国寄席「好二郎改め三遊亭兼好真打披露興行」8日目
両国寄席 「好二郎改め三遊亭兼好真打披露興行」開演前にせっかくだから両国国技館。理事長辞任の日を飾るため、国技館前にはキー局が全局集合。6時からのニュースで使うんだろうなぁ。お江戸両国亭 18時~20時40分東京かわら版の単独インタビューにも抜擢された好楽一門の新真打。10日興行の8日目。立川松幸(立川流)「手紙無筆」三遊亭橘也「新聞記事」三遊亭萬窓(協会)「真田小僧」三遊亭上楽 「宮戸川」古今亭菊春(協会) 「目黒のさんま」 三遊亭楽麻呂 「ちりとてちん」 仲入り 真打披露口上(兼好、楽麻呂、司会:上楽)三遊亭円左衛門「金明竹」 春風若イチロー 腹話術三遊亭兼好 「こんにゃく問答」 やはり注目の落語家さんにはお客さんが集まるんですね。今日もほぼ満員。番組の流れ(ちりとてちんとか金明竹、腹話術までも)を採り入れたギャグをところどころに。いかにも寄席らしい楽しい落語に。兼好さん、親分のキャラをそれほどボスキャラに設定せず。当人のフラを活かした、いい感じの親分。春風若イチロー先生、驚愕の初体験。本家イチローもびっくり。腹話術なのに思い切り口が開いてる。しかも腹話術で「雑俳」。
September 8, 2008
コメント(2)
-
「歓喜の歌(ドラマ)」&「はじめての落語」
「歓喜の歌(ドラマ)」北海道テレビ開局40周年記念スペシャルドラマ。「水曜どうでしょう」のスタッフが制作。原作は立川志の輔師匠の新作落語。映画は、落語原作に忠実に作ってありましたが、ドラマは制作上の都合もあってか設定をだいぶ変えてました。落語や映画は、2つのママさんコーラス同士がダブルブッキングするんですが、ドラマはコーラスと市政報告会がバッティングするので、コーラスは1チームです。そのため、役所の事務担当(大泉洋)の説得からクライマックスの作りも変わってきます。また、落語や映画の重要アイテムだった餃子も(あえて)外しています。ただし、物語の核となるテーマ(名もない普通のママさんたちが、それぞれが家庭の事情を抱えながらも、コーラスや歌を生きる喜び、生きがいに明るい人生を送っている)は変わっていません。なので、クライマックスのコーラスシーンは、知っていてもジーンと来てしまいます。また、小樽オールロケで、小樽の風景が劇中にほどよく盛り込まれていて、北海道らしさが感じられました。コーラスを撮ったところは小樽市民会館?劇中は見え見えの「大樽市」なんでですが。テレビ的なあざとさを感じたのは、コーラスの主人公の女性(田中裕子)がガンに冒されてて、次の年に延期したら、舞台に立てるかどうかわからないという設定。落語でこの設定やるとドサで野暮とバカにされるのですが、そのあたりが地方的な発想かと。劇中、抗ガン剤でカツラかぶっていると言われても、落語的な発想で見ると「そのカツラはいつ飛ぶんだ」になってしまうんですよね。---------------------真裏でやってた「日本テレビ男子アナ はじめての落語」日テレ男子アナ6人が2ヶ月で落語を覚えて大銀座落語祭で披露する企画の楽屋裏ドキュメンタリー。仕掛けは小朝師匠。各アナに教える師匠連は最前線の落語家ばかり。芸能人の落語の時はまだ遠慮がありましたが、一応素人の男子アナにつける各師匠の稽古が面白かった。弟子に教えるのはその何十倍も厳しいとは思いますが、各師匠たちは手を抜くことなく精一杯教えていて、アナたちも真面目にやってて。「蝦蟇の油」をやった菅谷アナは、実際に筑波山まで蝦蟇の油売り口上を見に行って刀で半紙を切ってみるほどの熱心さ。市馬師匠の家が、馬生師匠の家より大きそう(だし新しい)のには驚いた。落語部分は触りのみ。本編はDVD買ってねだそーです。(アナ対師匠)ズームイン羽鳥『あくび指南』(馬生)アナウンサー大喜利藤井『お菊の皿』(正蔵)メレンゲ菅谷『蝦蟇の油』(市馬)3分クッキング高橋『やかん』(三三)ノア森『片棒』(扇遊)アサリ研究家桝『宮戸川』(花緑)
September 7, 2008
コメント(0)
-
夢月亭清麿 物語・落語現代史(5回)
夢月亭清麿 物語・落語現代史(5回)中野ZERO視聴覚室19時~21時第5回 昭和30年代 寄席文化・落語文化の頂点「ラジオ落語の全盛」と称して都市(江戸・大阪・京都)だけのものだった落語がラジオ電波を通して、日本人全体に拡がり、落語が日本人全体のものになる。。ラジオ落語の第一人者として先代の三遊亭金馬(1985~1964)を取り上げる。昭和34年に金馬師匠が出版した「浮世断語」(うきよだんご)は、落語家の符牒や身内の誰がああだ、こうだなど、雑学・うんちく・エピソードのオンパレードなんだとか。そんな話からフリーならではの先代金馬師匠の動きを解説。昭和35年代に拡大再生産された時代劇(チャンバラ)から様式美を愛する日本人に触れ、様式化された中にほんの些細な変化を楽しむのが日本人の原点であると力説する清麿師匠。そのあたりは共感するところも大いにあり。落語を演じるにしろ作るにしろ、まず様式(型)を身につけることは大事のような気がします。冒頭で大野桂先生(演芸作家)と喜久亭寿楽師匠の思いで話を。そのせいもあってかテンション高めのしゃべり。やっと自分たちでもわかる落語家さんが出てきたせいか、前のめりで聴けるようになった。前回までは歴史上の落語家さんたちが多く、講義を聴いてる感じがしたので。お客さんの数も序々に増えてきた気がする。落語の流れを系統的に知りたいと思っている人がいるんでしょう。資料もたくさんありますが、自分で編集して整理するのは大変なので、この一連の講演を聴くだけかなり考えがすっきりするはず。現役の落語家から聴けるというのもかなり貴重なのではと。第6回は10月3日(金)「古典落語の王様/文楽と志ん生」
September 5, 2008
コメント(0)
-
落語娘
落語娘新宿ミラノあまり気分が乗らなかったのですが、大して人気もなく上映期間が短そうだから、とりあえず見ておくか。ということで1000円デー。今月号の「シナリオ」誌にシナリオ全文と脚本家の人インタビューが載ってて、全部読んでいったので、ストーリーは知ったうえ。どんな映画になるのかなぁと。脚本家のいうとおり、原作小説にほとんど忠実に作ってあった。前半の女流落語家と師匠との関係や女流落語家へのセクハラや偏見的なものがあって、後半、平佐(津川)が因縁深い怪談噺へ挑戦する話へ流れていく。シナリオだと、後半が平佐(津川)が主役にしか読めなかったのですが、映画ではそうでもなくてミムラの存在感はさほど消えてなかった。シナリオでも原作小説でも、この話そのもののオチがよくわからなかった。映像で見てみるとこういうことなんだとわかってすっきり。映画評の中には「津川とミムラの落語が下手」とかありましたが、それは見当違い。役者さんのやる落語として器用でうまくできてました。これより下手な落語家なんていっぱいいるし。何度か書いてるかもしれませんが、役者さん(初めての人)の落語は、カミシモが深くなる(角度が広くなる)んですね。首振る距離が長くなれば人物の切り替えに時間がかかるわけで、どうしてもテンポは悪くなる。ミムラの寿限無も津川さんの「緋扇長屋」もどちらもそうだった。その点、唯一本職の落語として登場して披露した笑福亭純瓶さんがやった「緋扇長屋」の一節はさすがプロって感じがしました。おそらく予算もなかっただろうし、原作小説に沿って作ってあるため、派手ではないし、すごく面白いというわけでもない。この原作を面白い映画にするのは、どんな脚本家も監督も苦労すると思うので、まあこんなもんでしょう。「緋扇長屋」のストーリーは、喬太郎さんと中原監督で作ったそうですが、再現ドラマを作ると安っぽくなってしまうのが逆に新しい発見。ただ、赤の他人である70近いおじいちゃんと20代中ばの若い女性が、「師弟関係」という絆で結ばれていて、お互い口悪くののしりながらも、弟子は師匠を尊敬し、師匠は弟子を気にかける。そんな関係がよく出ている映画です。「緋扇長屋」を所有している未亡人を2人して訪ねるシーンはほのぼのとしてよかった。
September 1, 2008
コメント(2)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-
- 楽天市場のおすすめ商品
- ◆仙台発祥!牛たんの名店のご紹介
- (2025-11-20 18:30:10)
-
-
-

- デジタル一眼レフカメラ
- 大人のリカ活&ミニカメラ サウンド…
- (2025-11-14 10:36:31)
-
-
-

- パソコンサポーターがすすめるパソコ…
- ◎中古 ノートパソコン PC パナソニッ…
- (2025-11-22 18:40:01)
-