2011年02月の記事
全42件 (42件中 1-42件目)
1
-
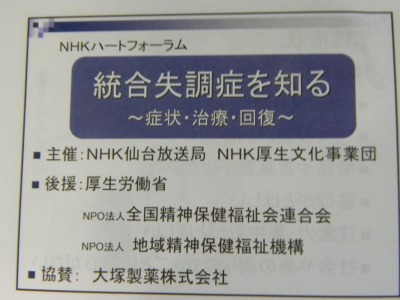
フォ-ラム「統合失調症を知る」を聞く
2月は今日で逃げる。 昨夜半よりみぞれ。里山は白く煙っている。 日中、気温が下がって本格的な雪降りとなった。 小生の妻は統合失調症。連れ添って30年をゆうに超える。 その間に入退院を繰り返し、幾たびも修羅場をくぐった。 随分落ち着いたとはいえ、最近も幻聴があるようで突然感情が悪化する。 昨日、NHKハートフォーラム「統合失調症を知る」を仙台国際センターに聞きに行った。 やっと妻を誘い出したのだが、タカを11時までに施設に送らなければ間に合わない。 タカは思うように動かず、妻の同行を促したがこれも動かず、ばらばらに。 妻が会場に来るか確実性はない。電話で妻に電車を指示。小生は軽トラで仙台へ。 モールの駐車場に置いて、地下鉄とバスを乗りついで会場へ。 妻は到着していない。参加証は妻持ち。訳を話して入れてもらう。20分の遅刻。 広い会場はほぼいっぱい。空席を探してもらって座る。 出演者は、福島県立医科大教授の丹羽さんと東北福祉大ホスピタル院長の浅野さん。 「統合失調症」は100人に一人が発症する身近な病気。 ・どんな症状が現れるのか ・どんな治療法があるのか ・どうすれば再発を予防できるか ・回復力を高めるために当事者や家族には何ができるか 途中から患者の男性も登壇して、体験をまじえて話してもらった。 妻とうまく付き合えなくなることが多々ある。 大再発をするなど入退院を繰り返した。子どもたちには大変迷惑をかけた。 医師たちからは“病気がさせている”のだから(仕方がない)と言われてきたが、それを耐えるのは大変だった。 昨日の話を聞いて“病気がさせている”ことの中身が分かったような気がする。 妻の場合は、幻聴(神の声?)にさまよい、思いもよらない言動になっているのだろう。 そんな時、頭にきてぶつかる。それは悪化させていたのだ。 とは分かるけど、「ごめんなさい」の一言もない、と引っかかる。 つまり、こちらのコントロールができていなかったのだ。 以前「精神分裂症」(統合失調症の前」は家族の病と言われていたが、そういう意味だったのだと多少客観的に見直すことができたような感じがする。 いい話が聞けたと帰路につくが予定通りにいかなかった妻の顔が気にかかる。 我が家に着くと案の定薄暗いのに灯りがついていない。 炬燵にもぐって幻聴に悶々としているか眠っているか・・・ いつものことだから気にしてもしょうがないと玄関を開けると、明かりがついた。 「いま帰ったとこ」と妻。「えっ、どこから?」と訊くと「フォーラムよ」と 遅れたけれど聞いたと言う。 帰ったら説明しようと思っていたので、聞いてもらってよかった。 今回のフォーラムは小生には妻の症状を客観的に見直せきっかけになりそうだ。 「いい話だっただろ」と言うと「ガチャンと牢屋に入れられるみたいで大変なんだから」と返す。これ以上はさわらぬ神にたたりなし。 昼飯抜きだったので、ラーメンでも食うかと誘うと「おごってくれるなら」と調子いい。 近くの幸楽園で安上がりの晩飯を食って一件落着 皆さんの周りにも、きっと悩み苦しんでいる方がいらっしゃると思います。 後日、今回学習したことを自分の復習をかねてお伝えします。
2011.02.28
コメント(4)
-

雪の中は安全な生育場所
金曜日の「ぼちぼち村」。 Kさんが2度雪かきをしてくれたお蔭で、通路は黒い土が見え始めた。 わだちには雪解け水がせせらぎを作っていた。 ほだ木置き場では、雪の中で生長したシイタケが顔を出した。 ナメコも所々に芽を出していた。 雪の中は適度の湿度と0度くらいの温度が保たれるので、ゆっくり育つのだ。 雪の中で活動している動植物はけっこう多い。
2011.02.27
コメント(4)
-
「税の自主申告説明と生活相談会」第3回を開く
午後「税の自主申告説明会と生活相談会」を開く。 税については、昨年生活保護を受け始めた人が申告用紙を持ってきた。 申告は国民の権利であり、その使われ方を監視する義務があるという観点から、生活保護受給者のHさんがSさんに付き添われてやってきた。 もともと所得税はかからないのだが、申告をすることによって非課税証明書の発行が簡単に引き出せるなどのメリットがある。 配布したチラシを見たという生活相談の人もやってきた。 派遣切りにあって、食べるにもこと欠くというSさん。 事情を聞くと雇用保険もないというので生活保護の申請が必要と判断。 来週の火曜日に同行することになる。 この町でも生活に困っている人がたくさんいる。 なのに拾いきれていないのが現状だ。 我々にとっては3千枚のうちの1人に役に立てればありがたい。 これからもがんばろう!
2011.02.26
コメント(0)
-

ねぼけまなこ
春の作付けにと畑の土をスコップで耕していたら 「お~~い はやすぎるぞぉ・・・」とダルマガエル。 突然起こされて寝ぼけまなこ。 「真っ二つ!」なんてならなくてよかった。 この時期は気をつけていても傷つけることが多い。 土の中にそっとかえしてやった。 お昼前の気温、4℃。 今日の気温は平年並み。
2011.02.26
コメント(0)
-

枯れ草焼き
急に春めいてきた。 昨日、「ぼちぼち村」のある白石市市街地では16度近くまで上がったという。 我が家の周りでは、あちこちの田んぼから煙が上がる。田お越しの準備が始まった。 師走の大雨で、コンバインで刈り取った短いわらが下流部に分厚無く溜まった。 このままでは、田お越しができないのだ。 それは畑も同じ。 枯れ草を残したままでは、トラクターで耕してもらえない。 そこで枯れ草を燃やすのだ。 我が畑では、キクイモ・コスモス・シソ・モロヘイヤ・枝豆などの茎が対象。 害虫退治とジャガイモの種芋の切り口消毒用、更に肥料にと役に立つ。 欠かせない早春の農作業だ。 3年前、薄暗くなってから燃やしたら、消防車がやってきたことがあった。 近くで事故があったので、明るいうちに焼いてほしいと言っていたが、暗くなってからの方が幻想的で美しい。 郷里熊本では「阿蘇の野焼き」が有名だ。ちょうど今ころが盛りだ。
2011.02.25
コメント(0)
-
ろう者の税申告について
昨夜、散髪屋のTさんたちがやる「手話サークル」を訪問。 “ろう者の税の申告がどうなっているか”よけいな心配をしに行ったのだ。 みんなが集まるのは、死後地が終わって夕食を済ませてくるので7時半を回るころ。 来た人から話をかけるけど、通訳者のOさんがきて本格的な説明となる。 ここにくる人たちは、みなさん重度の聴覚障害者(全聾)。身体障害者2級という。 十分ではないけれど、障害者年金で生活できているという。 障害者年金だけの人は無税なので申告しなくても問題はない。 Tさんのように仕事をしていると申告が必要となる。 彼は町の相談会に行っているそうだ。 国保料について訊くと、年金から支払っていて問題はないとのこと。 地デジについては、チューナーの申請時にUHF用とBS・CS用とを選択させられる。 Tさんは文字放送が多いCSがよかったのにUHFを選んで失敗したと思っていた。 説明が徹底していなかったのかもしれない。 NHKの視聴料は、自宅用は無料。Tさんの店舗用は半額負担だった。 昨日は重度の人たちだったっが、軽度の人たちには歪が生まれていないか気になった。
2011.02.25
コメント(0)
-

浜の畑に植樹
我が家に生えた幼木を浜の畑に移植した。 ウメ・アオキ・ケヤキ・ヤブツバキ・ヤマザクラ、どれも自然に芽を出したもの。 我が家では狭くて育てられないのだ。 これはウメの木。6年生くらい。 畑の周りに風除け(いぐね)として植えているが、どうなるものやら・・・ 以前は畑の脇の堀の水をかけていたけれど、海水が混ざっていて枯れるのもあるようなので、途中阿武隈山地の湧き水を汲んでいってかけるようにしている。 熊本の郷里(松橋町)の神社の掃き溜め(ごみ捨て場)から採取したクスノキ。 10年生くらい。3度、寒さに耐えられず葉を枯らしたが超えてきた。この冬は耐えた。 子どものころは、この神社のクスの大木の根元は遊びの場、一休みの場。 小生にとっては、その子どもだから大事なのだ。
2011.02.24
コメント(2)
-

餅つきようの“杵”いただく
先日、骨董屋の友だちMさんから餅つきようの“杵”をもらった。 材はケヤキ。硬い。 ところが、先端にひびが入り腐れ出していた。 「ここは切り取って使ってね」といいながら、dennsou ノコギリを持ってきて伐りだした。 次にグラインダーを持ってきて磨いてくれた。 その切り口は、とても美しかった。左は腐れた部分。 臼は「ぼち村」に2個あるのだ。今年のイベントでつかp
2011.02.23
コメント(0)
-

どじょっこ掘り
♪し~がこもとけて どじょっこだ~の ふなっこだ~の・・・♪ 今朝、田んぼにスコップとバケツを持ったじいちゃんが自転車でやってきた。 どじょっこ掘りだ。 「どこかいねべか」(いるところは知らないか)と訊かれたが、見かけたところはない。 冬の楽しみの一つだが、最近はやってくる人が大変少なくなった。 高齢化が進んでいることと、どじょっこもへっているためだ。 じいちゃんは辺りを見て回っていたが、どこも掘らないで帰っていった。 蔵王連峰のパノラマ(大河原町から) 右が北蔵王・雁戸(がんと)山、左は南蔵王・不忘山。
2011.02.23
コメント(0)
-

『税の自主申告』第3弾チラシ配布
午後近くの団地で『税の自主申告説明会』第3弾のチラシの各戸配布。 30年近く前にできた中規模の団地。 歩いてみると、傷みのひどい家や空き家が目につくようになっていた。 子どもたちもたくさんいたけど、下校時間になってもちらほら。 残り少なくなって見上げると、 「オナガガモ」?の群れ。 北帰行間近か? 2時間ほどかかって配布を終わる。 そこへSさんが心配してやってきた。 心配されることではなかったのだけど・・・チラシの効果があることを願うのみ。
2011.02.22
コメント(0)
-

がらくたも雪の中ではオブジェ
今朝も真っ白な霜。流しの水道凍る。 日向の霜は間もなく解けたが、日陰ではそのまま残った。 「ぼちぼち村」は、まだまだ雪の中。 大きな味噌桶。かまくらの中みたい。 物置の屋根の雪は、下に届きトンネルを作った。 雪の中の「オオアリクイ」は様になる。 がらくたも雪の中では生き生きとしたオブジェに変わる。
2011.02.22
コメント(2)
-

北帰行はまだだった
きのうの夕方、タカを施設に送ったあと。 いつもの休耕田のハクチョウを観察に行った。 金曜日は5羽だったのに、この日は80羽くらいに増えていた。 まだ北帰行は始まっていないようだ。
2011.02.21
コメント(2)
-
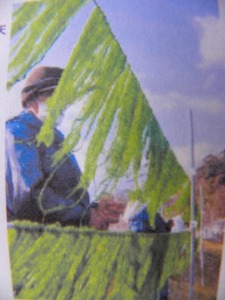
「アオノリ」採りの思い出
光の春がやってきた。 畑の陽だまりにはハコベの緑がみずみずしい。 春一番の緑を見ると「アオノリ」採りを思い出す。 子どものころのこと。 あのころは落ち穂拾いやからいも(さつまいも)拾いと収穫の終わった田畑からその場しのぎの糧を得るような生活だった。 寒に入った晴れた日の日曜日、お袋と近所のおばちゃんたちと数キロ離れた不知火海の干拓地の堀に「アオノリ」を採りにでかけていた。 竹竿の先に、鍵に折った番線(太目の針金)をくくり付け、一斗袋(布製の米袋)を持って。お袋たちは歩き、オレはギーガタン ギーガタンと自転車で荷物運び。 現場は不知火の海の堤防のそば。時には潮の引いたガタ(潟)の中を流れる川だったり。 巾5・6メートルの堀には、満ち潮の時に海水が上り「アオノリ」にとっては好条件。 竿で一かきすると、長く伸びた「アオノリ」がかかってくる。 「寒のり」は濃緑で、味も香りも最上級だ。 アシの枯れ葉などのごみが絡んでいるが、そのまま水を絞って米袋へ突っ込む。 袋はたちまちいっぱいに。これを洗い場に(勝手に作っている)運んでごみや汚れを洗う。 熊本とはいえ、麦畑を走ってくる北風は冷たかった。 当時はゴム手袋なんてないから、素手。 指はかなわなくなり、じっと我慢してやっていると血が通いだす。あとは大丈夫。 袋いっぱいのアオノリを自転車の荷台に2つも積むとハンドルが浮く感じになる。 ふらふらしながら帰り着く。 子どもでも男の仕事だった。 昼から庭先の狭い畑に張った綱にアオノリを干した。 一部は生で佃煮にしてくれた。旨かった。 (昨年の熊本日日新聞より) 海苔の香りの中に、透きとおる緑はそれは美しかった! 天気がよければ2・3日でちりちりに乾き、夜、古新聞の上で手もみで粉にした。 もみ残ったものは、炭火の上で乾かしていたが焦がすこともあった。 次の日曇ったり雨が降ると大変だった。 室内に取り込んでも熱を持ち、色も香りも劣化。売り物にならなくなるのだった。 売るといえば、どこに売っていたのかは記憶にない。 売っても、ちょっとしたおかず代にしかならなかったと思う。 あのころは、みんな貧乏で、やさしかった。 懐かしい思い出。
2011.02.21
コメント(2)
-
「税の自主申告」説明会開く
先週の土曜日、チラシをまいた「税の説明会と自主申告」を開いた。 派遣村にやってきた「賃金未払い問題」のNさんもやって来た。 自主申告をして所得税3万8千円ほどを取り戻すため、アドバイスを受けて申告書を作成して帰った。 ところが、しばらくして戻ってきた。 家に帰ったら、会社から源泉徴収書と未払いの8か月分の明細書が送られてきていたと。 そこにはもらっていない2百数十万円の収入が書かれていたので訂正を求めることに。 また24日には、民商の無料法律相談で弁護士に相談することになった。 会社はいよいよ倒産に近づいているようだ。 労働局の担当者からは、早く見切りをつけて雇用保険をもらいながら職探しをするように勧められたと言う。 他には、最近会員になったSさんも、手伝ってもらいながら申告書を仕上げていた。 生健会は、相談者が安心して生活ができるように知恵をしぼろう。 みなさんも是非「自主申告」をされることおすすめします。
2011.02.20
コメント(2)
-

春はゆったりと
霜が下り氷が張ったが、快晴! 春の暖かさがやってきた。 我が家の梅の蕾も膨らみだした。 ぼやけた飛行機雲が2本3本、ゆったりと流れていった。
2011.02.20
コメント(2)
-

くっきりの南蔵王連峰
日中、春めいた暖かさとなった。 夕暮れの南蔵王連峰。 右端の灯りは澄川スキー場のナイターのもの。 中ほどの煙は、師走に降った大雨で流れ着いた稲わらを燃やしているところ。 最近はあちこちで煙が上がっている。稲わらは春の田起こしの邪魔になるのだ。
2011.02.19
コメント(0)
-

雪解け近い「ぼちぼち村」
きのうの「ぼちぼち村」は霰混じりの雪。 スコップで駐車スペースを掘る。 薄くなっているけど、雪面にかんじきの跡が続いている。 誰だかかんじきを履いて「村」に下った人がいる。 入り口の吹き溜まりは1mを越えるが、この時期ともなると雪はしまって歩きやすくなる。 前日の雨でずいぶん解けた。 かんじきの跡をたどると、電気のメーターへ向かっていた。 検針の人が降りてきたのだ!こんなことは初めて これまで冬は一定額で、春になってから調整していたのだったが、厳しくなったのか? 屋根の雪は、母屋と流しの上を除いてはほとんど落雪。 軒下の雪が、あと30cm足らずで軒に届きそうな所も。 物置ではトンネルができた。 ダム湖は田植えのために湛水しだしたようだ。 右(西)側は凍り始めている。 水を抜いていなければ、数年ぶりに氷上釣りができただろうに・・・ザンネン
2011.02.19
コメント(0)
-

ハクチョウの旅立ち
今日はタカのお迎えだ。 我が家に帰るときは、意味の分からないおしゃべりがいっぱい! ルンルンなのだ。 ハクチョウが群れる休耕田。 みんな北へ向けて旅立ったのか? 今日は5羽だけ・・・
2011.02.18
コメント(0)
-

電事連の「プルサーマル」広告
夜半からの雨は明け方に上がる。 ベランダを隣の黒猫が鈴を鳴らして行った。 おとといの地元紙の気になった広告。 広告主は電気事業連合会(日本原子力発電KK・電源開発KK・日本原燃KK)。 「これからのこども エネルギークイズ 問題:原子力発電で使い終わった燃料をリサイクルする計画は?」 こどもたちに「プルサーマル」という名称を植えつけようというねらい。 リサイクルはいいことだというイメージは定着した。 そこに「プルサーマル」を乗っけようというわけだ。 子どもの時から「プルサーマル」をすり込んでおけば(当たり前のことという意識付け)「プルサーマル発電所」の増設がしやすくなるとでもいうのか。 広告の中には、危険性や子々孫々に残される廃棄物処理の問題を考えさせるもの一切なし。 電事連(電気事業連合会)は、学校教育の中にも入り込んで原発推進の教育を進めている。 このままでは、原発関連のつけは子どもたちの肩にのしかかっていく。
2011.02.18
コメント(0)
-

先輩も介護保険を・・・
午後86才になる職場の先輩Fさんを訪問。 女房が、奥さんから「風呂に入るのが大変になってきた」と聞いてきたと言うのだ。 伺うと、足腰は不自由になってきたが、まだ一人で入れるとのこと。 ただ、滑ったり転んだりするといけないから奥さんが見守っているのだそうだ。 介護保険の話をしたら、「老々介護だけど、もうしばらくは大丈夫そう」と奥さん。 まぁ~、ひと安心 西の山際に、日は沈んでいった。
2011.02.17
コメント(0)
-

薪ストーブ
夜中の月明り、サクラの梢を地面に映していた。 今朝はきつい霜が降り、雲が覆う。こんな日は底冷えの寒さになる。 我が家には大きな薪ストーブがある。 若い頃は丸太を買ってきて、自分で割って焚いていたが、雑木を伐り出す人がいなくなり仕事も忙しかったものだからしばらく焚かなかった。 ナラの薪を買うとなると、高くて焚ききれる物ではない。 宝の持ち腐れになっていた。 そくへ3年前から薪ストーブにこりだしたポン友の整備工場の社長。 「薪(建築廃材)が集まりすぎて置き場に困った。焚くなら持っていって」と言うので、この前から暇をみて伐っては運んでいる。 廃材なので釘やかすがいやボルトがついたままだから気をつけないと、チェンソーの刃は瞬間にダメになる。 ほとんどがスギ。柔らかくて焚くとたちまち燃えつきる。 いっぱいに突っ込んでおくと2時間は持つ。 燃えない金属は灰の中に残るので、溜まったらふるいで取除き資源ごみとして出す。 宵の口から夜中まで焚く。 柔らかい暖かさが家中に広がる(全館暖房に近くなる)のがいい。 炎の揺らぎ、はぜる音、やすらぐ。
2011.02.17
コメント(2)
-

まずは よかった よかった
雪の蔵王連峰が鮮やかに輝いた。 (村田町より) 昨夜は放射冷却で冷えこみ、台所の水は昼近くまで凍っていた。 昨日は「税の自主申告書を作ろう」の案内ビラを寒風の中で各戸配布をしたが、今日は朝から川崎町のKさんの生活保護の申請に付き合った。 川崎町は北蔵王の麓。 Kさんは60代前半。秋までは町の草刈りの仕事でなんとか生活してきたが、冬に入って仕事が無くなり行き詰ってしまい「派遣村」に駆け込んだ。 というわけで町の福祉課に同行した。 車の所有で引っかかるかと心配したが、担当職員は県交渉で確認したように「半年くらい使っていく中で検討しましょう」と柔軟に対応してくれた。 事前に同行を頼んでおいた川崎町内の酪農家Tさんが保証人を引き受けてくれて、その場で申請書を提出。判定を待つことになった。 Kさんが、今日の生活にも困ると言い出したので、職員は社協の方に緊急用の食料があるといって直ぐ手配してくれた。 これでなんとか急場をしのげそうだ。 安心はできないけれど、ひとまずよかった よかった Tさんにも感謝!
2011.02.16
コメント(2)
-

ああ~春がくる、はるがくる!!
ゆうべの淡雪は、日が上るにつれ音をたてて解け出した。 この雪だれの音は、子どものころ解け出した雪と遊ぶこともできなくて、あばら家からぼんやり眺めていたあの音。土の、芽吹き呼ぶような早春の音。 (あのころ、熊本でもこんな雪が積もっていた) 白石市弥治郎のこけし工人吉紀さんを久しぶりに訪問。 工房のあるこけし村は、まだまだ雪がいっぱい。 重い戸をあけると、来客が一人。 黒石市(青森県)の工人仲間だという。 話が盛り上がっている最中に義則さん外に出て行く。 戻ってくると、右手にずしりと重い者? 金華山の増えすぎた間引きシカの太ももだ。 「まだ生乾きで」と言いながらナイフで数切れ削いでくれた。 冷薫にしたという味は、いい塩味で旨かった! 酒の肴には最高だ。 切り口からすると、我々が初物か・・・ なくなる前に2・3回は訪問だ! ああ~春がくる、はるがくる!!♪
2011.02.15
コメント(6)
-
ああ~すっきりした!
午後Sさんを訪問。 去年からしばらく上がりこんで話をしていなかったので気になっていたのだ。 Sさんはラーメン屋を経営していたが火災で店と居宅全焼。 それで母親を亡くし、奥さんは大やけど。 ようやく立ち直った3年後、奥さんは脳梗塞で倒れる。 それから一人で切り盛りしていたが更に3年後、奥さんはうつ状態になり自殺。 店も繁盛しなくなり3年後に自己破産。(小生が勧める) 大きな不幸が3年おきに3回連続した。 今は年金で一人暮らし。 顔は鬼瓦で威勢がいいが、中身はいたって気が小さく心配性。 でも、ギブアップはしない。 権力には強く、男気があって困っている人の面倒見がいい。 まるでとらさんみたいに、人情の世界にどっぷり浸かっているような男だ。 今はやくざから金を借りた男性の面倒を6・7年もみている。 これは彼の特技とでもいえようか・・・ 3時間たっぷり話を聞くことができた。 Sさんも俺もすっきりした
2011.02.14
コメント(2)
-

「ぼちぼち村」は雪の中
久しぶりに「ぼちぼち村」に行った。 入り口は除雪車の雪だまりでふさがれていた。 厚くてがちがちになっている。 奥は吹きだまりで長靴ではもう通れない。 ダム湖が凍っていれば、ワカサギ釣りの人たちが踏み固めるのだが、白石市は氷上釣りをさせまいと水を抜いて冬の楽しみを取り上げたのだ。 Kさんの除雪では間に合わないので、この次はかんじきを持ってこよう。 入れないのは旧不忘分校も。 除雪のたびに積み上げるので高さ4mを超えようか。 何かあった時にどうするのだろう。白石市の所有物なのに、管理は? と心配になるが、除雪車の運転手任せになっているという。 分校の上には旧県道がある。道幅4m。 その脇に不忘地区の名所の一つ「天狗の飛び石」と呼ばれる大きな溶岩が2つある。 その一つ、岩相の悪い「オオカミ岩」(小生命名)がにらみをきかせている。 オオカミウオの顔にそっくりなのだ。 その反対側には「ツルアジサイ」のドライフラワーがアカマツを飾っていた。 蔵王山麓は豪雪地帯。 でも、眠ってばかりではない。雪の下ではノネズミの仲間が縦横にトンネルを掘り、ノウサギやカモシカやキッネにタヌキにエゾリスが雪面を動き回っている。結構にぎやかなのだ。
2011.02.14
コメント(4)
-

これがいつものパターン
今日は冷たい北風が吹きぬける冬晴れとなった。 日曜日はタカを施設に送る日。 家を出る前は「デカレンジャー」を見て笑い声を響かせている。 デカレンジャーになりきっているのだろう。 声をかけると自分でテレビのスイッチを切る。 そこからは冷たい表情に変身する。 デカレンジャーは消えるのだ。 タカが辛けりゃ親も辛い。 施設まで沈黙が続くこともある。 気分を転換するために、ゲームセンターや大きなスーパーを回ることもある。 施設近くの休耕田のハクチョウ。 蔵王おろしの冷たい風の中で、這いつくばって餌を食べている。 群れはこの前から半分の50羽くらいになった。 もう旅立ったのか、餌場を変えたのか・・・ なんてタカに言っても分からないけど、切りかえるのだ。 施設に着くと、振り向きもせず園舎に駆け込んでしまう。 今週も楽しく過ごせますようにと、担当者にお願いして急いで去る。 これがいつものパターン。
2011.02.13
コメント(0)
-

宮城生健会 県の福祉課と団体交渉
昨日の雪空は腫れた。 雪の解け出した草むらでは、カラスたちが餌をあさっている。 先週は「仙南派遣村」にこられたNさんの相談に同行した。 彼は観光バスの運転手。去年の6月から給料は払われていない。今月で9ヶ月目。 労働基準監督署に相談し、11月支払いを約束した文書がきたが履行されず預貯金は底をついている。 我々は生活保護を申請するか、会社を辞めて雇用保険をもらいながら未払い賃金を請求し次の仕事を探すかを勧めたが結論は出ず。 先週の木曜日、宮城県生連(生活と健康を守る会)は、県の福祉課と交渉を持った。 ※「生活と健康を守る会」は、行政に対して団体交渉権をもっているのだ。 主な交渉内容は<生活保護に関して> ○申請書を窓口の見えるところにおき、誰でもてに取れるようにすること ○車の保有を認める用件の緩和をすること ○保護決定書の内容を受給者に分かりやすいようにすること ○扶養義務者の調査は、申請者の意思に反することは行わないこと ○生活保護利用者が生活福祉資金をりようできるのはどんな場合か? ○生活保護法第25条1項の職権保護の県内における実施状況は? <国民健康保険制度について> ○国庫負担率を削減前に戻すよう国に働きかけること ○資格証発行はやめるよう強く国に働きかけること ○保険証の発行を要請した加入者には直ちに交付すること ○法44条に基づく医療費自己負担分の減免制度の周知徹底を ○児童の医療費助成制度について、国の制度として整備するよう国に強く働きかけを ○都道府県単位への広域化の動きは、加入者に一層の負担増をもたらすので慎重な検討を <生活福祉資金について> ○申し込みから融資までの期間がかかりすぎるので、実態に合った運用の改善を ○緊急小口融資制度は即決できる制度に変えること ○制度の広報を強化するとともに、窓口の職員の研修を徹底し活用しやすい運用にすること 以上が宮城県生健会がの主な課題である。 生健会の交渉者は24名だった。県は5名の担当者が対応した。交渉時間1時間15分。 県からの回答は質問提出3週間後、交渉の前日に届いたという。 交渉の中身は、全般的に当たらず触らず、のらりくらい。 分析して生かせるところを見つけたい。 困っている人は、今困っている。 だから、緊急な対応が必要なのだ。のらりくらりで最後は拒否されるのでは生きていけなくなるのだ!
2011.02.13
コメント(0)
-
NHKスペシャル「無縁社会」から
昨夜からの水雪は朝までに7cmほど積もったが、昼までにかなり解けた。 空は曇天。タカは昼近くまで起きなかった。 こんな日は誰でも這い出したくないもの。 その間NHKスペシャル「無縁社会の衝撃」(再放送)を見た。 10代の若者たちにまで「無縁社会」が広がりだしているとは・・・ショックだった。 夜間高校を中退していく生徒の涙が哀れだった。 今月初め、ハローワークで会った商業高校3年生から聞いた「200名のうち150名の就職が決まっていません」という返事が思い出された。 このまま仕事が見つからなかったら、楽しいはずの青春が灰色になってしまう。 そういう中から「無縁社会」が低年齢化し、拡大していくのだろう。 最近こちらの生健会でお世話する生活保護の申請者は、一人世帯がほとんど。 政治は危機感をさほど感じていないのでは? 番組は終わりに「結縁社会」を作ろうとしているNPOなどの民間活動を紹介していた。
2011.02.12
コメント(4)
-
ドラマ「風をあつめて」を見た
今朝、珍しくテレビドラマを見た。 NHK障害福祉賞45年記念、ドラマ「風をあつめて」。 新聞のテレビ番組紹介欄より。 原作は、熊本市在住の浦上誠さんの手記「私たち夫婦の普通の家庭」。 浦上さんの長女・杏子(ももこ)さんは、生後7ヶ月で「服山型筋ジストロフィー」と診断され、20歳までは生きられないと告げられる。杏子さんは20歳で天国へ。 夫婦が同じ劣性遺伝子を持っているため、生まれる子どもの4分の1の確立で発祥するという。夫婦は望みをかけて2人目を生む。だが、2人目も筋ジストロフィーの娘さん。 ドラマはそれを受け入れ、乗り越えていく生き様を描いたもの。 欄は、原作者の話として、次女は胃ろうで気管切開をしているのでテレビがお友だち。遊園地とか連れて行ったほうがいいのかと思いながら、家族でテレビを見ているのが私たちの「普通の家庭の過ごし方」と紹介していた。 小生にとってこのドラマは、ふるさと熊本のことであり、障害児を持つという同じような境遇に引き込まれた。熊本弁や阿曽の風景も心地よかった。 二男のタカはダウン症。 ガラス室の中で管をつけられた茶色の我が子。「ダウン症と思われます。詳しい検査は日赤に頼みます。現在は二十歳くらいまでは生きられます。」という産科医の言葉を上の空で聞いていた。上の子どもたちと同じように元気に生まれて来るものと思い込んでいたからショックは大きかった。 大きな障害を持ったこの子を育てるということは・・・家族の犠牲が想像がつかないほど大変になるという思いが頭の中をぐるぐる駆け巡った。 そして、「先生、あの酸素の管を間違って踏んでいいですか・・・」と出そうになるのを何度か飲み込んだ。 日赤に移って、検査の結果が伝えられた。「染色体異常がたくさんありました。ダウン症候群です。」心の中では間違っていて欲しいと願っていたものだから、あの時は頭の中か目の前かが真っ白になり、思わずしゃがみこんでしまった。立ち上がると「今は40歳くらいまで生きられるようになってます。ダウン症の人は周りを幸せにしてくれますよ。」と慰めてくれた。この主治医にはその後長くお世話になった。 更に動脈開存症もあり循環器病センターで2度の手術。 女房は精神状態が乱れに乱れ、精神科に入院を繰り返した。 なんて、ドラマを見ながらこんなことが昨日のように思い出された。 今は、この子がいてくれてよかったと心底思う。 ただ、申し訳なかった、すまなかったという気持ちは一時も離れない。 今日は金曜日、今から我が家の宝子タカを施設に迎えに行く。 彼が戻ってくると、我が家には明かりがともる。
2011.02.11
コメント(2)
-
詩「地下足袋」
昨日の雨は止み、淡雪はすっかり解けた。 蔵王山で雪を落した雲が、ちぎれながらゆっくりと太平洋へ向かっていく。 ある新聞の投稿詩。 普段は目をやらない欄なのに「地下足袋」が呼んだ。 地 下 足 袋 冬が来てシルバーの除草の仕事が無くなりそれまで履いていた地下足袋を正月あけに洗い始めた外の水道でバケツに洗剤を入れて地下足袋を浸して置き束子でこすりだすと山仕事に地下足袋を履いていた父が思い出されたこの山間の村で生まれ一生この村を出ることもなく八人家族を養うために働き敗戦の戦後の食糧不足から結核を病み「俺が死んだらあの世でも働くから棺桶に地下足袋を入れてくれ」と言って死んだ父「おとっちゃ今年も俺は負けないぞ」 作者金井利正さんとおとっちゃの思いが、土の香りとなって伝わってくるようだ。
2011.02.10
コメント(4)
-
気がめいる「税の申告」
夕方から雨。 雨は雪より冷たく感じる。 先日、生健会で税の申告は国民の権利と教わったので、権利の行使に行った。 午前中の雪ですいていると思ったが、小生と同じ思いの人は結構多かった。 1時間の待ち時間では足りなかった。 小生はこんな金の計算は大の苦手! この前は電卓もいらないと研修したのだったが、まるで試験の山が外れるみたい。 現職の時は事務任せだったが、自分の税は自分で計算すべきだったのだが・・・ タカは療育手帳のAで重いランク。 障害者控除30万円。これは22歳までで23歳からは26万円になるのだそうだ。 理由は、大学卒業年齢が22歳でそれまでは金がかかるから特別控除だという。 タカは大学なんていけっこないのに、分かるようで分からない。 こんな決まりがいろいろあるのだから、小生には複雑な迷路に入り込んだようなもの。 小生を知っている担当者で、終わってから特別に説明をしてくれたが、拒否反応のある小生にはやっぱり分かるようで分からないようなハイ・ハイだった。 生健会では、12日・19日・26日の3日間「税の申告会」をやることになっているのだが気の重くなることである。
2011.02.09
コメント(0)
-

春の淡雪
天気予報通り、朝から雪降り。 湿っぽい細かな雪で3cmくらいの積雪。 右下にカラス。 このカラス、小一時間たって外を見ると、まだ止まったまま。 そこでいい顔を一枚! それからもしばらく止まっていた。 腹をすかして困っているのかな?餌は雪の下。 困っているのはカラスだけではなかった。 キササゲの梢にはモズ?が止まってきょろきょろしていた。 鳥たちは、もう春を感じて活動を始めているのだろう。 <おわび> 先日、浜の畑でモズの「いけにえ」としてイナゴの串刺しを見てもらいましたが、「いけにえ」ではなく「はやにえ」でした。 昆虫を「はやにえ」にしているのでアカモズ?かも?しれません。
2011.02.09
コメント(0)
-

おだやかな日に・おとといのタヌキさん
昨日の暴風は仙台で最大風速29.1mを記録し、夜中まで吹き続けてやっと鎮まった。 今朝は蔵王連峰がくっきり! 国会は荒れているけれど、穏やかな一日になりそうだ。 夜も晴れ。 おとといのタヌキさん、三日月さんに旅立っていた。 明日は雪の予報。
2011.02.08
コメント(4)
-

九二一工房訪問
腫れているが。昼から風花交じりの強い北西風がごーごーと唸っている。 久しぶりに九二一つあんの工房へ行く。 新しい電気窯が入り、初めての本焼きが始まっていた。 2月1日に満91歳になったばかりの九二一つあん(大正九年二月一日生まれから命名されたとのこと)、3食分の弁当を持ってきたが、今度の窯は全自動で一晩中ついていなくていいと弟子さんからいわれて喜んでいた。 1年前はスギの伐採を始めたころ。 今は見晴らしがよくなった庭先からは太平洋が一望できる。 地球の丸さが見えるようだ。 (手前の低地は縄文から弥生の時代にかけて豊かな遠浅の入り江だった。 周辺には貝塚がたくさんある。) 下ではSさんが週1回やってきて、残ったスギ丸太で薪を作っている。 パカッ パカッと割れる音が響く。気持ちがよさそうだ。
2011.02.07
コメント(4)
-

今夜、タヌキさんが三日月さんのところに旅立ちます
今日の昼飯は、女房は「男の料理教室」のご招待とやらで仲間と出かける。 で、「あなたたちはどうする?」と言うので、 「おれはタカと旨い物を食べに行くから心配しないでいい」ということになった。 しかし、考えてみると、年金支給の前だ。旨い物は食えない。 ということで、タカと近くのジャスコに弁当を買いに行った。 短い隧道をくぐると、右手に狭い休耕田。 白い枯れ草の中に、茶色のかたまりが! タヌキ?と、気になったのでバックする。 普通はこれだけで逃げられてしまうのだが、うずくまっている。 車を降りて、ドアを閉めても反応がない。 ゆっくりとは動いている。犬でも猫でもない。タヌキさん。 毛なみはとてもきれいだ。 「どうしたんだろうね。タヌキさん」と話しかけながらジャスコへ。 タカは“サケのり弁”を買ってにこにこ。家に帰って食べることにする。 帰りのタヌキさんは、 薄い日差しの中で丸くなっていた。 どんな異常が起きたのか、天に帰るしかなさそうだった。 タカが弁当を平らげてしばらくして帰ってきた母親。 夕方には施設に戻るタカを、珍しく送っていくと言うので、付き添う。 帰り、4度目のタヌキさんの沸き脇へ。 いなくなっている!と近づくと、 下の田んぼに落っこちていたのだ。 まだ、おなかの辺りがゆっくり動いていた。 鼻先まで行って観ると、 出血は観られないけど、目と耳の間の皮がめくれている。 原因は多分これだろう。 西の空に細い三日月さんが昇った。 今夜、タヌキさんは三日月さんの所に旅立つことだろう。
2011.02.06
コメント(2)
-
「仙南派遣村」開く
きのう午後、第6回「仙南派遣村」を開く。 相談者7名。男性のみ。 小生が担当したのは3名。 Aさん(50歳代前半)・・・母親と2人暮らし・持ち家 雇用と資格取得について 介護の仕事に着きたいが資格がない。資格を取るには資金がない。 ハローワークでの募集も応募したが希望者が多く外れる。 アルバイトのようなことで食いつないでいるが、回数が減って月10万円程度。 ということで雇用担当から生健会へ。 これでは生活が不安定なので生活保護を受けながら資格取得を目指すことを勧める。 Bさん(40歳代)・・・友だちのアパートに世話になっている 未払い賃金の請求の件 未払い賃金については雇用担当から一般労連を通して請求することになる。 食住などの生活は友だちに世話になり、自立できていないということで生健会へ。 生活の自立のために生活保護を受けようということになり、来週福祉課に同行する。 Cさん(40歳代)・・・両親と3人暮らし・持ち家 精神障害あるので、会社を辞めさせられるかもしれないという心配 この件については、具体的になってからのことになる。 母親の介護が大変な様子なので、家族の問題として生健会へ。 介護保険の活用を勧めるが、Cさんにはこだわりが強く話はまとまらなかった。 でも、このまま頬って放っておいてはいけないケースだと気になっている。 <はんせい> 相談に来る人たちの中には、困りごとのどこを解決したらいいのかがはっきりしないことがある。当たり前のことだが、話をしていて気がついたり、我々に指摘されて分かったりする。 この次から、相談の背景にあることを読み取るつもりでのぞもうと思った。 あんなこともこんなことも訊いておかねばならなかったとか、こういうアドバイスも必要だったとか、小生の勉強不足とか反省することがいっぱいだった。 次回は6月。
2011.02.06
コメント(2)
-
教職員組合が「生活保護制度」の学習会
昨夜は教職員組合の主催で「生活保護制度の学習会」が開かれた。県内初! “教職員に、目の前にいる子どもと親(家庭)の困りごとにちょっとアドバイス(ちょいアド)ができるようになってほしい”ということが狙い。 講師は「県生活と健康を守る会連合会」の事務局長。 参加者は、教師が小中高合わせて8名、生健会3名、町議2名。 と少なかったが、年度末の金曜日の夜。仕事が終わらない人、疲れきっている人も多く、もっととは言えない。 内容は、配慮された資料をもとに「生活保護制度」の理念と「権利」の捉え方に始まり、生活保護費の計算の仕方まで実習となった。 2時間の予定を大きくオーバーしたが充実した学習となった。 教組では、このような学習会を全支部に広げることにしたそうだ。 子どもを育てるということは学校だけで、きょうしょくいんだけでできる物ではない、みんなで、社会全体で取り組まなければならない大仕事なのである。 「子は宝」を忘れてはならない。
2011.02.05
コメント(0)
-

うらやましいなぁ~
先月変わった自転車で東北を旅しているスイス人を紹介したが、数日前は隣町で荷物をいっぱい積んで、いかにも旅をしていると思われる若者を発見。 渋滞で駐車スペースもないので、追い越して反対側にあるコンビニの駐車場に入る。 車の間から見えたのは「日本一周・愛知」の表示。 愛知県の若者が日本一周の旅をしていたのだ。 どんなコースをたどっているのか分からないが、北から南に向かっていた。 うらやましいなぁ!
2011.02.04
コメント(2)
-
エッ~~~ホントぉ~!!!18才に春はこないのか!?
最高気温9℃。 昨日までと打って変わった春陽気。 午後1時間ハローワーク前で「派遣村」のチラシ配布。 きのう若い人が目立つようになったと書いたけど、 ついに高校生がやってきた!!! 生徒は近くの県立商業高校。 3月1日の卒業式を目前にして、就職が決まらないのだ。 訊くと、「なんと!卒業者200名のうち、50名しか決まっていない。」のだそうだ。 この高校はギターの演奏有名で、これまで100%の就職率を誇ってきた。 それが、こともあろうに4分の3が未定という。 菅総理は数日前の国会で「ハローワークにどんどんよこして下さい。」というようなことを言っていた。 出てきた女生徒たちに訊くと「だめでした。ありません。」とがっかりしていた。採用するのは総理大臣ではないのだからなぁ・・・ 近くに農業高校もあるけれど、どうなっているのかなぁ? 18才に春はこないのか!!?
2011.02.03
コメント(4)
-
後期高齢者医療「新制度」の広域連合議会を聞く
昨日、仙台市で「宮城県後期高齢者医療新制度」について、県内市町村の担当議員が集まって広域連合議会(連合長は仙台市長)が開かれ、その傍聴にいってきた。 後期高齢者医療制度は不評で、民主党のマニフェストでは廃止するということだったが、昨年12月に「新制度」なるものをまとめ2013(H25)年から実施予定。 「新制度」は、健康診断を努力目標から義務」に戻したこと以外多くの改悪と問題がある。 (宮城の受診率は20%を少し超える程度で大変低い) ○すべての世代で保険料負担が増大する ○国の支出を減らし、県と市町村の財政負担を増やす ○健康保険組合にますます財政負担を課すため、組合の解散に拍車をかける ○国保を都道府県に単位化(広域化)して国民に負担増を押し付ける入り口にする ○高額療養費の自己負担限度額は、所得に関わらず同額とし、新年度から引き上げる など 「短期保険証」は県内21市町村で145人に発行されている。 月額1万5千円以下の低年金の人ばかりだという。 議題は条例の一部改正と、補正予算と、23年度予算。 質問者の4人は、多くの問題を抱えている「新制度」に関わるものばかり。 連合長(仙台市長)は挨拶で、「政権が先送りをしているので不透明・・・」と述べ、答弁の中でも「先行き不透明。これが最大の課題」と繰り返しながらも、国保税の広域化(値上げにつながる)を求めていった。 反対、賛成の討論を受けて採決。反対4で問題山盛りの予算案が可決された。 いつものパターンだけれど、もっと真剣に討議してもらいたいものだ。 病気になっても医者にかかれない人、ためらう人がいることを考えてほしいものだ。 「あ~ア!」ため息の出る傍聴になった。 傍聴者13名。
2011.02.03
コメント(0)
-
「第6回仙南派遣村」チラシ配布
5日に「第6回仙南派遣村」を開く。 そのお知らせを2市1町の地元紙に織り込んだ。困窮者は、新聞を取っていない人も多い。 また、月曜日からハローワークの前でチラシの配布。 昨日とおとといは午後1時から配った。 入る人と出てくる人の両方に配布できるので大変効率がいい。 年が明けて違うのは、若い人が多いこと。 高校卒業後2・3年など。 ある若者に訊いた。 「卒業して何年目?」 「3年目」 「仕事についていたの?」 「うん、辞めたんです」と照れ笑い。 と、ここまで聞けば「どうして辞めたのよ。がまんしなきゃ・・・」と言いたくなる。 しかし、本人にしてみるとそんなものじゃないだろう。 悩んでなやんで、辞めさせられるような状態だったかもしれない。 自分のやりたい仕事に就けるのは至難の業だ。 自分に向いている仕事だって見つけられていないのかもしれない。 この社会、それを甘いと叱咤激励できようか!? 小生の時も大変な就職難だった。 やりたい仕事はと~い向こうにしかなく、手の届かないものだった。 そんな中でもコネのある者は、エッと思うような所に決まっていったことを思い出す。 今日は午後仙台に行くので朝一配布。 今朝も冷え込んでハローワークの入り口はつるつる。 求職でやってくる人より職員の数の方が多いくらい。 個人の努力では、どうにもならないことも多い。 それを打ち破るのは、やはり若者だ! それを支えるのはおれたちだ
2011.02.02
コメント(0)
-

ダウン症のタカの成長
今朝も3cmほどの積雪。 のち青空広がり、気温はゆるみ車の雪解ける。 車の雪といえば、この前の日曜日のこと。 「お出かけするから、車の雪を落として。」と頼んだら、 にこっとして「う~ん」と気に入った時の甘ったるい返事。 無理だと思ってやらせたことはなかったけれど、見ていたのだろうブラシをうまく使う。 ところが素手に雪が落ちてくるので詰めたくなる。 チャンス到来だ!これまで手袋は嫌がって一度もはめたことがなかった。 「冷たいねぇ。手袋をはめるとあったかいよ。」と声をかけると受け取ってはめようとするが簡単にはいかない。 「親指さんはここ・・・」と入れてやるとぬぐこともなく雪落としを楽しんでいた。 周りの大人たちは、こんなことはできないだろうと、決めてしまいがちだが、まかされると嬉々としてやってくれる。失敗しても遅くても
2011.02.01
コメント(0)
全42件 (42件中 1-42件目)
1









