2022年06月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

イワツバメの営巣、ツバメの三番仔、若鳥顔見世、猛暑と鳥たちの観察記
柏市柏の葉キャンパス駅周辺では、ツバメ、イワツバメ、ヒメアマツバメとツバメ科の鳥たちの姿と出会うことができます。一枚目から四枚目の写真は、昨シーズンヒメアマツバメがつくった巣をベースにイワツバメが巣を作り始めました。巣の土台を作り上げていきます。最初はコンクリートの壁面にへばりつき、ふんばるベースをつくりあげペアが共同で巣材を運搬していました。また、近くの商業施設の軒下では三番仔と思われるヒナが巣の中にいて親鳥が餌を運び込んでいました。さらに、この間までは巣の中にいた若鳥が酷暑を避けて軒下に横一線に並んで涼んでいるようでした。このほか、近郊の調整池には、ダイサギ、チュウサギ、カイツブリの親子連れ、コチドリの姿がありました。中でも、ヒバリが水際で調整池の入ろうかどうしようかと迷っている様子を目撃。それぞれが酷暑を生き抜くために懸命。(写真)2022年6月30日撮影
2022.06.30
コメント(0)
-

手賀沼沿岸のサシバとヨシゴイ観察記
梅雨明けをした手賀沼沿岸を訪ねました。朝からすでに28度をこえ、日中は33度前後まで気温が上昇。こんな酷暑の中でもサシバは、今年誕生した幼鳥に与える餌探しに余念がなく、水田の一角の電柱にとまり餌を捕獲していました。その後、手賀沼沿岸の葦原地帯にヨシゴイの姿を探しに移動しました。水面にはコブハクチョウの親子が移動いる光景からスタートし、葦原の一角をヨシゴイが飛翔したり、葦づたいに移動していました。巣にいる雌にプレゼントする餌を持参したり、巣を補強する葦を嘴で折り、巣に運搬したりなかなか雄も忙しい様子でした。(写真)2022年6月29日撮影
2022.06.29
コメント(0)
-

おはようツミ、高層住宅街での観察記(2)
鳥友の街の高層集合住宅の谷間にある公園の一角でツミが営巣しています。その様子をリポートします。24日にはじめて足を運び、成鳥雌が餌をヒナに与えるそぶりを披露していました。今日は、公園の木陰で待機し、暮らしぶりを観察しました。巣をみると、綿羽に覆われたヒナが少なくても2羽以上観察できました。雌が巣に滞在している間は、夏のお日様からヒナを守るのに雌は羽を精一杯広げて日陰をつくり、ヒナを覆っていました。時折、雌は巣を離れますが、それでも高層住宅の屋上から眼下の巣を監視。カラスが巣の近くへ飛来すると2秒程度で巣に帰還し、追い払う動作を繰り返します。今朝は、巣のとなりにある木に雄が待機していたので、落ち着いている様子でした。(写真)2022年6月29日撮影
2022.06.29
コメント(0)
-

ササゴイの羽色、いろいろ
昨日、都内の公園にササゴイを見に出かけました。幼鳥、第一回夏羽、成鳥といろいろな羽色の個体を観察できました。一枚目の写真は、上面が暗褐色で喉から胸の縦斑もまだはっきりとしていない幼鳥です。まだ巣立った島の縁で周囲の様子を見ていることが多く、成鳥が餌を運搬してくるのをひたすら待っていました。二枚目、三枚目は幼鳥が成長した個体で、昨日は水に浸って涼んでいる光景や成鳥の真似をして水面を凝視し餌を捕獲するような仕草も披露していました。三枚目は、第一回夏羽で上面が暗褐色で、肩羽、雨覆に褐色の羽が残っています。成鳥と同様に飛翔することが可能であり、近くの河川まで餌を探しに出かけていた模様です。最後、四枚目は、翼に笹の葉模様がある成鳥です。何度も幼鳥たちへの餌を運搬して島に飛来する際はキューと鳴き声を出して出現。(写真)2022年6月27日撮影
2022.06.28
コメント(0)
-

アマサギの分布域拡大から一転して減少へ
今月19日にアマサギの出会いたくて稲敷市まででかけたことをご報告しました。その際、バードリサーチ(2019)が、全国鳥類繁殖分布調査結果について紹介しました。「1990年代は34コースで記録されていたのが,今回は18コースと減少している。(中略)地域別に見ても特定の地域で減少しているわけではなく、全体的に減っており,特に関東や九州では大きく減っていると」報告しています。拙宅の亭主から1980年代には世界的に分布を拡大していたことが安齋知己さんが報告しているよと指摘をもらいました。安齋(1991)は、アマサギだけが急速な分布域拡大と個体数が増加していると指摘しています。「もともと1930年代に南アメリカ、50年代にフロリダ、メキシコなどの中央アメリカ、70年代には北アメリカで繁殖が報告されるようになった。アフリカから北には1961年にスペインで、69年にフランスで繁殖が報告されるようになった。日本で急速に個体数がふえたのも第二次世界大戦後のことである。(中略)アマサギの分布域はほぼ全世界に広がり、日本においても北へ北へと広がっている」と報告しています。ところが2000年代以降、特定の地域ではなく全体的に減少しているとバードリサーチが報告していることを考えると、わずか30年ほどの間に今度は減少に転じていることになります。アマサギは他のサギと混合でコロニーを作り繁殖します。ところが、近年は人間の生活域に近いところにコロニーが作られないように牽制される傾向もあり、そのような影響なのかどうか興味のあるところです。(引用)安齋知己.1991.世界的に分布域を拡大 アマサギ.動物たちの地球.第6巻.p72-73.朝日新聞社.バードリサーチ.2019.全国鳥類繁殖分布調査ニュースレター第14号.p6.
2022.06.28
コメント(0)
-

都内都市公園のササゴイ観察記
ササゴイの若様が複数誕生している都内の公園に出かけました。木陰もあり、比較的近い距離で観察でき、最近は喫茶専門店もオープンして魅力的なスポットに変化しつつあります。さて、肝心のササゴイですが、11羽もの姿がありました。翼に笹の葉模様があり、頭は灰青色の帽子状になっている成鳥、頭部に産毛が残っている若鳥、上面が暗褐色で翼の各羽縁が黄褐色な若鳥、などいろいろな個体を観察できました。あまりの酷暑で産毛が残っている若鳥は、小島の浅瀬で水につかり涼んでいました。このほか、飲み込めるかしらと心配になるサイズの大きな魚を捕獲したカワセミ、翼を怪我していて2シーズン目の越夏となさったホシハジロの姿もありました。(写真)2022年6月27日撮影
2022.06.27
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(25)
巣にはヒナの姿がなく、成鳥雌の姿もない事態が発生したと鳥友K-tsuminetさんから連絡をもらい、早朝から現地に向かいました。林には複数のハシブトガラス、ハシボソガラスが営巣木の近くまで飛来していましたが、ブラインドから確かに巣を見てもヒナは一羽も確認できず、近くに成鳥雌の姿もありません。営巣木を確認すると密猟されたような痕跡はなく、林全体を確認してもヒナたちの羽毛が散乱してような様子もありません。カラスに襲撃されて親子共々どこかに退避しているのであればいいのですが。二時間ほど林の中を探索していると、上空をツミ成鳥雌が飛翔している姿を発見。と同時に雌とヒナに与える餌を捕獲して帰還した成鳥雄は、いつも通り巣の方向にむけて鳴き声をあげ、食べやすい大きさにちぎっていました。(写真)2022年6月26日撮影
2022.06.26
コメント(0)
-

セッカの雌雄を識別する
ホームグランドの手賀沼沿岸や茨城県稲敷市周辺、河川敷や埋立地などで見かけるウグイス科のセッカの雌雄の識別について質問をもらいました。ある図鑑を見ると雌雄同色で尾羽は丸尾で軸斑が黒く、先端は白いと記されていたとのことでした。上田(2006)は、セッカの生態、生活史、羽色、生態について知見や文献で記述されている内容を整理し報告しています。その中で雌雄については、つぎのように述べています。「繁殖期のオスの頭部上面は一様な褐色であるのに対し、メスの頭部上面は淡い褐色の地に黒褐色の縦班が存在するため、一見してザクザクした感じになる。この縦斑はメス幼鳥ではよく目立つが、成鳥ではいくぶん不鮮明になるので注意が必要。またセッカでは中央の2枚を除く、10枚の尾羽の先端部に白色部があらわれるが、この白色部分がオスでは鮮明であるのに対し、メスではかすかに褐色がかっている」茨城県稲敷市浮島で2020年5月に観察した個体を見ると、たしかに尾羽先端部に白色が現れています。これに対して、2016年7月に浮島で観察した個体の尾羽先端部をみると褐色がかっています。(引用文献)上田恵介.2006.生態図鑑.セッカ.Bird Research News Vol.3 No.5.p2-3.バードリサーチ.(写真)2020年5月3日茨城県浮島で撮影、2016年7月10日茨城県浮島で撮影
2022.06.25
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(24)
鳥友K-tsuminetさんのおすまい街にツミの様子を見に立ち寄りました。到着し、巣の様子を見ると一羽のヒナの姿があるだけでそのほかの姿はありませんでした。ところが、ヒナの鳴き声と成鳥の鳴き声と成鳥がカラスを追い払う声が聞こえました。その方向に目をやると、地面の低い位置の切り株に綿羽から幼羽に変わった幼鳥の姿がありました。現地からK-tsuminetさんに連絡をとり、若鳥に怪我はないこと、近い距離を翼を使って飛翔できること、親鳥が幼鳥のすぐそばまで飛来していることを伝え、アドバイスを得ました。うまく飛べず巣から地面に落ちた可能性が高いので親鳥が給餌や誘導をするうちに飛べるようになると思いますから、そのままにしてくださいとお話しを聞かせてもらい、現地をあとにしました。その後、K-tsuminetさんから別エリアで営巣・産卵したツミのペアの様子を見に立ち寄りました。高層集合住宅の谷間にある公園の一角に巣がありました。頭上から雄の鳴き声がしたので見上げてみると成鳥雄夏羽の姿がありました。橙色の胸から下面の色、足に獲物を持って引きちぎっていました。その姿がなくなったと思ったら雌に獲物を渡して渡去。雌は餌をヒナに与えるそぶりを披露。その後、日差しからヒナを守るように巣に座り込みました。(写真)2022年6月24日撮影(最初の5枚はいつもの林での個体、それ以外は集合住宅エリアの個体)
2022.06.24
コメント(0)
-

アオハズクの子育てと餌について
鳥友から昨日観察してきたアオバズクは、産卵後の子育て時期にはどんな餌を与えているのですかと質問をもらいました。夜行性の鳥なので、報告はあまり多くないと思いますが調べてみましょうと返事をしました。給餌に関する報告はかなり少なく、谷口一夫さんが1983年に日本鳥学会誌に繁殖期におけるアオバズクの残し餌と題する報告(第32巻.p145-152)と富沢章さんが2001年にStrixに報告しているアオバズクが捕食する落とし餌からの検討(Strix.2001.第19巻.p121-127.日本野鳥の会.)と題するものに記されていました。谷口(1983)および富沢(2001)によると、アオバズクは育雛期間中に甲虫類を主に給餌し、雛の生育初期にはガ類を高頻度に給餌すると報告されています。ただし、育雛期には給餌内容がどのように変化するのかがからなかったので文献をさらに調べました。すると、日本鳥学会誌の2020年第69巻第2号223-234に育雛期間の進行に伴うアオバズクの給餌内容の変化とのタイトルで報告がありました。育雛初期から中期は、チョウ目を主に給餌していたとありました。一方、育雛後期には営巣環境中での優占ていたコウチュウ目を高頻度にヒナに与えていたと記されていました。さらに、興味深かったのは、アオバズクは,育雛期間を通しチョウ目の頭部、胸部、腹部、およびコウチュウ目の腹部を給餌し、消化器官が未発達なヒナに柔軟な外骨格のみを選んで与えていたとの点です。消化器の発達具合を考えて与えているとも考えられる点が勉強になりました。
2022.06.23
コメント(0)
-

佐倉市のアオバズク観察記
例年、佐倉市内に飛来し産卵・子育てをしてきたアオバズクですが、昨年はなぜか姿が見られずでしたが、先週今シーズンは渡来したよとニュースをいただきました。まん丸の頭と黄色の虹彩、下面の縦斑、しっかり観察してきました。眼下を通行する市民の方や近くの道路を通る救急車の音、三脚などを設置している方が気になるらしく何度かその方向を凝視していました。(写真)2021年6月22日撮影
2022.06.22
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(23)
鳥友K-tsuminetさんのおすまい街にツミの様子を見に立ち寄りました。今朝はとうとう三兄弟揃って登場してくれました。孵化後2週間程度で生え始めた幼羽は約4週前後で揃います。ふわふわした綿羽が少し残るものの、上面は幼羽となりつつあります。愛くるしさにくわえて、一羽が大きくあくびを披露してくれて観察している側はメロメロです。林に到着したばかりは、成鳥ペアの姿が見えず心配しましたが、雄が捕獲してきた獲物を瞬時に雌に渡したと思ったら、雌は餌を待つジュニアのもとに移動。食べやすいサイズにして与えていました。(写真)2022年6月21日撮影
2022.06.21
コメント(0)
-

アマサギに会いたくて稲敷市へ(コジュリン、オオセッカなどの探鳥記)
ホームグランド手賀沼沿岸では、一昨年頃よりアマサギの姿を見かけなくなりました。これまででしたら、柏市と印西市の境界の水田地帯に小さな群れが見られましたが、今シーズンも姿を見かけません。そこでアマサギの姿、コジュリン、オオセッカなどの姿を求めて稲敷市へ出かけました。浮島、近郊の干拓地、水田地帯を探索して回りました。真夏並の暑さと日差しの中、アマサギ29羽もの群れが水田の畦で休んでいる姿を発見。成鳥夏羽の頭と背がオレンジ色の個体、嘴の色が淡く額にオレンジ色のない若鳥、頭にオレンジ色がまばらに残る夏羽から冬羽に移行している個体、実にいろいろな羽色を堪能しました。このほか、干拓地でコジュリン、オオセッカ、囀っていないのに頭の羽毛が逆だっていたオオヨシキリ、干拓地で最も個体数の多いヒバリの姿を目撃。(参考:アマサギの減少)バードリサーチ(2019)は、全国鳥類繁殖分布調査の結果を整理し報告しています。アマサギについては、「1990年代は34コースで記録されていたのが,今回は18コースと減少している。(中略)地域別に見ても特定の地域で減少しているわけではなく、全体的に減っており,特に関東や九州では大きく減っていると」報告しています。引用:バードリサーチ.2019.全国鳥類繁殖分布調査ニュースレター第14号.p6.
2022.06.19
コメント(0)
-

コチドリの成鳥雄、雌、若鳥、ヒナの特徴について
鳥友から柏の葉近郊で観察したコチドリの識別について質問をもらいました。特徴を整理し、提供します。(1)成鳥夏羽雄嘴基部、過眼線、前頭は黒く、黒い前頭と褐色の頭頂の間に白い線があります。(写真)2022年6月17日柏の葉、2011年6月4日柏市内で撮影(2)成鳥夏羽雌過眼線の黒色に褐色味があります。大部分成鳥夏羽雄とかわりませんので、成鳥冬羽から夏羽の換羽中の個体は注意が必要です。(写真)2022年6月17日柏の葉、2009年7月4日柏市内で撮影(3)幼鳥頭から上面は淡褐色で各羽に羽縁があります。上面は鱗模様にも見えます。なお、前頭に黒色はありません。(写真)2022年6月17日撮影(4)ヒナ雛は生まれた時はふわふわの綿羽に覆われています。孵化してから二週間ほど経過すると幼羽が明らかに分かるようになります。昨日観察したヒナは幼羽がわかるようになっているので二週間ほど経過しているものと思います。(写真)]2022年6月17日柏の葉、2021年6月26日印旛沼沿岸で撮影
2022.06.18
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(19)
鳥友K-tsuminetさんと毎年通っている林から直線距離で2キロ程度しか離れていないエリアの木で営巣しているツミの様子を観察しに出かけました。雌がずっと巣の中にいる様子をまず確かめた後、雄はどこで見守っているのだろうと周囲を見渡すと高層集合住宅の屋上に設置されている地デジアンテナにとまっている雄を発見しました。下面は濃い橙色の成鳥雄夏羽でした。あいにく曇天と距離があったので証拠写真の域を出ませんが記録しました。いつも観察している林での雄の見張り台とは違って地上から30メートル程度の高さから巣のあるエリアを見下ろしてカラスやオナガが巣に接近すると鳴き声をあげて急降下し追い払っているとK-tsuminetさんから話しを聞いていましたが、ツミの雄としたら腕利きのパイロットでないとできない芸当なのだろうと思いました。なお、巣の具合を見ていると、周囲に羽毛がついている部分があり、雌が時折体の方向をかえているのでお腹の下にヒナが存在する可能性が高いと思います。(写真)2022年6月16日撮影冒頭の写真のみ2021年4月に撮影したツミの雄を使用しています。
2022.06.16
コメント(0)
-

梅雨の手賀沼探鳥記(水鳥のヒナ誕生、チュウサギの虹彩の色)
久しぶりにホームグランド手賀沼とその沿岸を探索して歩きました。しかし、沼の水面はたっぷりと水が入っているため、浅瀬の草原や葦原に営巣をする多くの鳥たちは子育ての機会を奪われたままの状態が続いています。しかし、そんな条件下でもコブハクチョウやヨシゴイたちは、産卵し子育てに入っています。写真は、下手賀川の水面を子供連れで移動していたコブハクチョウファミリー、残っている葦の中に営巣をしているヨシゴイ、沿岸の谷津田で子育てに入っているサシバの姿です。このほか、水田に複数のチュウサギの姿があり、姿を見ていたら虹彩の色の違うチュウサギを発見しました。チュウサギの虹彩は黄色ですが、今日観察した個体は橙色をしていました。飾り羽も一際目立つ個体で婚姻色の個体なのかとも思いました。(写真)2022年6月14日撮影(ヨシゴイの1枚のみ2020年7月撮影のもの)
2022.06.14
コメント(0)
-
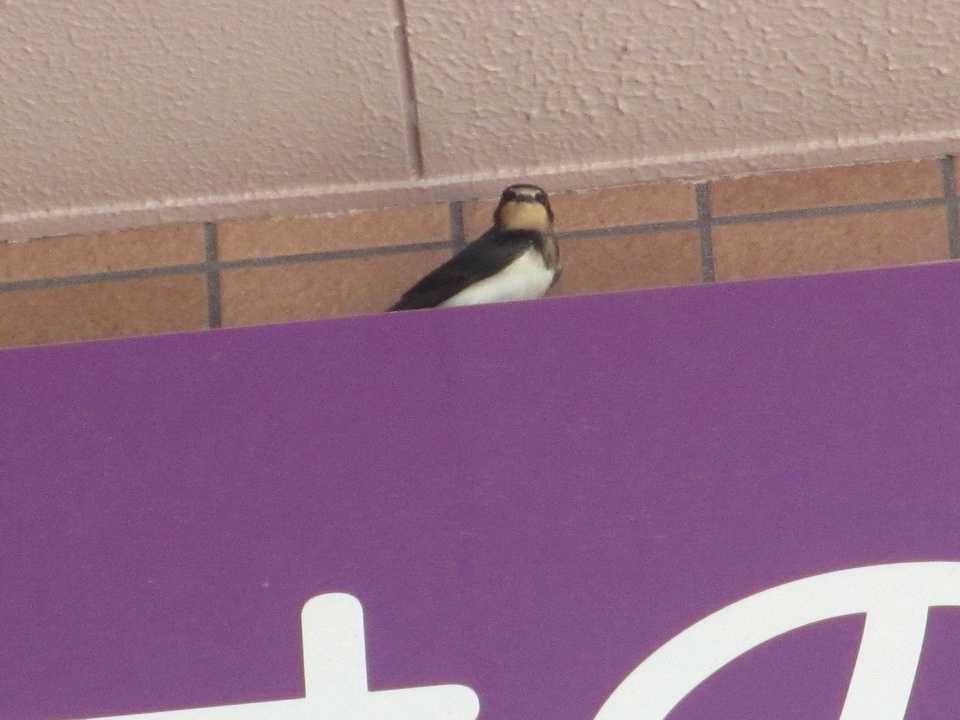
ツバメの話題、二題(若鳥の喉の色と成鳥の尾の長さ)
(若ツバメの喉の色)今朝、わが町のスーパーに隣接するビルの軒下に巣立ち間もないツバメの幼鳥がとまりしばらく休んでいました。喉の色も成鳥に比べると薄い黄土色で下面は白色。えっ、幼鳥の下面には赤褐色味があると記している図鑑があったことを思い出しました。帰宅してから画像ライブラリーと図鑑を何冊か復習してみました。確かに巣立ち間もない若鳥では黄土色のものが多い結果でしたが、2012年7月にわが町の一角で撮影したツバメの若鳥では成鳥並に赤褐色になっていました。(写真)2022年6月13日、2012年7月16日、2021年7月3日、2020年7月12日撮影(尾が長いツバメはもてる?)藤田(2008)は、ツバメの分布、生活史や興味深い話題を整理し報告しています。その中に、ヨーロッパのツバメでは尾羽の長いオスがメスに好まれることを紹介しています。ところが北米では、尾羽の長さではなく,オスの喉の赤さがメスの選り好みの対象になっている地域があることを述べています。地域差による選り好みの違いがあることが興味深いと指摘しています。(引用)藤田剛.2008.ツバメ.Bird Research News Vol.5 No.4.p4-5.
2022.06.13
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(20)
千葉県の鳥友nankashibirdさんが住む街のチョウゲンボウの様子を見に立ち寄った後、鳥友K-tsuminetさんと合流しツミの林に立ち寄りました。ツミの雄がいつもの見張り台の枝で林全体ににらみを効かせている姿を見ながら、ブランドに入れていただき巣の様子を観察させてもらいました。タイミングよく巣の中から綿羽に包まれたヒナが登場しました。その後ろでは、母さんツミが周囲を厳重警戒している姿。ブラインドに入っているとはいえ、視線が合うと緊張します。短時間で観察はきりあげ、林の一角に移動しました。(写真)2022年6月12日撮影
2022.06.12
コメント(0)
-

千葉県都市部のチョウゲンボウ観察記(その7)
千葉県の鳥友nankashibirdさんが住む街のチョウゲンボウの様子を見に立ち寄りました。商業施設の屋上に成鳥が巣の方向を凝視し、周囲に複数飛来しているカラスに警戒をしていました。巣のある換気口には、最初幼鳥二羽の姿のみでした。うち一羽がとても活発で、翼を広げたり、伸びをしてみたりを繰り返していました。下面が淡いバフ色であり、成鳥とは違った印象のある色でした。そんな光景を観察しているうちに、今度は3羽のヒナが横並びに登場。孵化して一ヶ月弱が経過しており、そろそろ巣の外に出て親をめがけて飛び出し、そのそばにとまるという光景を目撃するのも目前ではと思われます。(写真)2022年6月12日撮影
2022.06.12
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(19)
鳥友K-tsuminetさんからヒナ誕生のうれしいお知らせをいただき、ツミが飛来している林へ出かけました。到着直後、巣の様子をみると雌は座り込んでいる模様で、雌もヒナの姿も確認できずでした。しかし、その後、いつものように雄が捕獲してきたスズメのヒナを足にぶら下げて帰還しました。鳴き声を何回もあげた後、雌が餌を受領したあと、巣に帰還した際に白いふわっとしたものが動くのがわかりました。おそらく第一綿羽が揃っていない個体がいるので雌がヒナを抱いているのでしょうとK-tsuminetさんからお話しを聞きました。あわせて、2キロ程度しか離れていないエリアの木でツミが営巣している内容も伺い、現地に案内してもらいました。巣はけやきの上部の枝が茂っている部分にありました。状態を見てみると、たしかに尾が見え、数度その向きを変えた後、雌が腰をおろしました、その後、キィキィキィと鋭い鳴き声がしたと思ったら雄が獲物を持って出現し、受け渡しが行われ雌が受け取ったのを目撃。座り込む直前に脇に横斑があることが判明しました。モバイルギアで過去のライブラリーを見返すと、4月7日にさっきまで観察していた林で目撃した若鳥と同じことが判明。そうか、成鳥ペアと一緒だった後、ここに来ていたのだと感慨深く観察しました。(写真)2022年6月11日撮影最後の写真のみ2022年4月7日に撮影した若鳥雌(虹彩が黄色)
2022.06.11
コメント(0)
-

茨城県北部のサンコウチョウ観察記
茨城県北部の那珂川沿いにある林道を訪ねました。お目当てはサンコウチョウは、杉林の一角に雄2羽、雌1羽、別の林で雄が各2羽を発見しました。林の中をギッギッと濁った声を出してからツキヒホシ、ホイホイホイと囀りを繰り返していました。夏鳥以外では、ミヤマカワトンボがじっくり観察できるフィールドです。写真は雌個体で雄ほど翅は濃くなく、薄い褐色に濃い褐色の帯が目立つのが特徴です。腹部は雄ほど金属光沢は強くありません。(雄の翅は濃い褐色をしており、腹部は青味がかった金属光沢色)国内のカワトンボの中では最大で、威圧感がある大きさです。(写真)2022年6月10日撮影
2022.06.10
コメント(0)
-

ヒメアマツバメの巣は何からどうやってつくられているの?
6月4日に柏の葉公園近郊でヒメアマツバメの巣を発見した旨をリポートしました。鳥友から巣はどのように作られているものなのかと質問をもらいました。堀田(2012)は、ヒメアマツバメの分布や生息環境、生活史などを整理し報告しています。それによると、巣は雌雄共同で、空中で羽毛や植物の葉、茎などを採集し,それらを唾液で貼り付けて半球状の巣を鉄筋コンクリートづくりの建造物の庇下などにつくる。造巣期間は長く,1歳のペアで約5か月,2歳以上のペアで約2か月かかると述べています。また、内部は羽毛などでしっかり裏打ちされている写真を掲載しています。写真は、一枚目はイワツバメの古巣の上から作った巣、二枚目は同日に観察した昨年使っていたものです。三枚目は昨年7月11日に観察した巣とヒメアマツバメ、四枚目は2019年9月19日に観察した巣とヒメアマツバメ、五枚目は2018年8月22日に観察した巣とヒメアマツバメです。柏市でヒメアマツバメが観察されたのは2015年のことですが、産卵・育雛した確証は得ていないので根気よく観察をしてまいります。(引用文献)堀田昌伸.2012. ヒメアマツバメ.Bird Research News Vol.9 No.6.p4-5.
2022.06.09
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(18)
鳥友K-tsuminetさんの街のツミが飛来している林へ。昨日は雨降りで肌寒い一日でしたのでペアがどうしているかと心配しながら訪ねました。到着して10分ほど経過すると林の外からツミの鳴き声がすると、足に獲物をぶらさげた雄がいつもの見張り台に帰還。枝のどこかに獲物をおいた後に羽づくろいをはじめました。風切羽の手入れからはじまり、尾羽を広げたり、胸から腹の羽毛を広げて通気しているような動きをしていました。一方、巣に入っている雌の様子をブラインドから観察すると、4日とは体の向きが反対に変化しており、雌のお腹の下にヒナが存在するのではと推察しました。(写真)2022年6月7日撮影
2022.06.07
コメント(0)
-

コウノトリのヒナ成長と喉の赤い部分
昨日、野田市のコウノトリの里を訪ねたことをリポートさせてもらいました。鳥友よりヒナの喉の赤い部分はどうなっているのかと質問をもらいました。私も同じことを疑問に感じてセンターの方に質問したことがあります。喉の皮膚が裸出した部分が赤く見えているとのことでした。一枚目は昨日のヒナ、二枚目は2018年3月31日時点のヒナで誕生から一週間経過していたヒナ、三枚目は2016年6月12日に観察したヒカルで、誕生日2016年3月28日ですので誕生から56日目の状態です。四枚目は親鳥ペアです。個体を比較してみると、誕生から一週間ですと喉の赤い部分がない状態ですが、今年の24日目のヒナではもう喉の部分がかなり赤くなっています。2016年に観察したヒカルは角度の関係からか喉の赤い部分は目立たなかった印象です。(写真)2022年6月4日、2018年3月31日、2016年6月12日、2021年7月28日撮影
2022.06.05
コメント(0)
-

野田市のコウリトリの里訪問と柏の葉近郊のヒメアマツバメ観察記
5月12日に誕生したコウノトリのヒナの様子を見に野田市コウノトリの里を訪ねました。生後24日をむかえたヒナは育ての母が体で日陰をつくってその下にいました。順調に生育しているようで成鳥のアイリング(目の周りの赤い模様)が少し出ていました。生まれたばかりのヒナではアイリングは出ていないので、はじめて観察しました。このほか、市民農園の管理棟の軒下に営巣しているツバメの親子の姿、水田地帯の一角にサシバの姿を見つけました。その後、柏の葉公園近郊に移動し、ヒメアマツバメの様子を見に立ち寄りました。昨年までの営巣場所はくずれおちていて気配がなかったものの、北方向に新しい巣を発見し巣の様子を撮影していたら中からヒメアマツバメが飛び出して外に出かけていきました。(写真)2022年6月4日撮影
2022.06.04
コメント(0)
-

おはようツミ2022年観察記(17)
鳥友K-tsuminetさんの街のツミが飛来している林にでかけました。到着したばかりのときから雄が見張り台の枝に姿がありました。30分以上動かず、このまま推移するのかと思ったら、近くの枝に移動。葉がしげっているところを嘴でつつくような素振りだったので角度をかえて観察すると、獲物の小鳥を食べているのがわかりました。何度か甲高い鳴き声をあげて雌にアピール。雌の反応がないので巣に近い枝に移動してまた鳴き声を出したりを繰り返しました。その後、雄の鳴き声に呼応するように雌が雄の居場所に合流し、一瞬で餌を受け取り再び巣に帰還。どこで食べるのかと思ったら巣の縁で食べ始めました。K-tsuminetさんのブラインドからその様子を記録。私は記録できなかったものの、雌がヒナにちぎって餌を与える動きをしていた由。(写真)2022年6月4日撮影
2022.06.04
コメント(0)
-

茨城県の街で巣立ちをむかえているチョウゲンボウ観察記
かつて水戸街道の宿場町として賑わった街の橋梁で長年チョウゲンボウが営巣・子育てをしています。2週間ぶりに現地を訪ねました。前回、巣の中からジュニアたちの鳴き声が聞こえていたので、そろそろ巣立ちかなと期待しつつ複数の営巣箇所を観察して回りました。姿を現した幼鳥だけで計7羽、成鳥が4羽を観察できました。ひとつの巣で3から4羽誕生するとして前回確認した6つの巣で誕生したとすると単純計算すると24羽ものジュニアが誕生となります。近々ににぎやかな状態になるものと思います。アップした写真は、お腹がいっぱいで巣の中で瞬膜をとじていて私に気がついて片目をあけた後両目で視線があった光景、巣のそばに雄が飛来しカラスなどの外敵を監視している光景、巣立ちをした幼鳥が外に出たのはよかったのですが、うち1羽が動けなくてもう1羽が激励しているように見えた光景、巣の中で羽ばたき巣立ち直前の幼鳥、第二綿羽が少し残っていた幼鳥の光景です。(写真)2022年6月2日撮影
2022.06.02
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1










