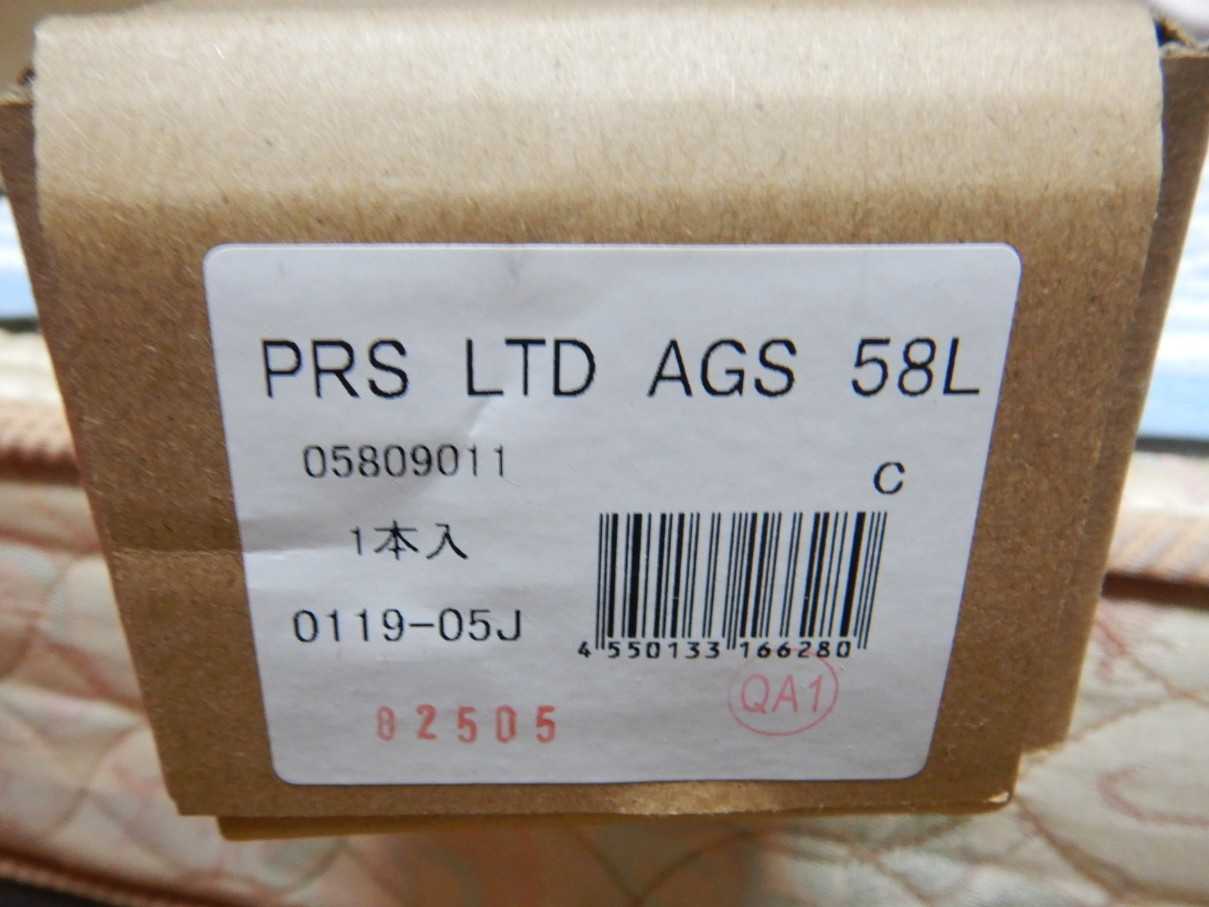2022年09月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

房総のむらで出会ったエゾビタキ、キビタキ、マミチャジナイ観察記
千葉県栄町にある房総のむらは、古墳群や里山環境が保全されているエリアです。この時期には、ヒタキ類、ツツドリなどの秋のわたりの小鳥たちが立ち寄っていくのを目撃できるところです。今日、現地を訪ねましたら、エゾビタキ、キビタキ、マミチャジナイ、エナガなどの姿を見つけました。胸から脇に白地の灰褐色の縦斑、二等辺三角形で内側にへこんだ嘴が特徴のエゾビタキ、上面がオリーブ色で喉が白っぽく、バフ色の翼帯と下面の汚白色があるキビタキ若鳥から第一回冬羽に換羽している個体、エゾビタキがミズキの実をついばんでいたそばにマミチャジナイの姿を見つけました。(写真)2022年9月30日撮影(マミチャジナイのみ2019年10月都内で撮影)
2022.09.30
コメント(0)
-

親友の誕生日は柏の葉公園でのツツドリでお祝い
昨日、柏の葉公園でツツドリと出会えたことを今日誕生日の鳥友に話したらぜひ見てみたいということで連日でしたが柏の葉公園に出かけました。ランチとお祝い用のケーキを買い込み、公園のベンチで待機。昨日よりも広場には人出がないこともあり、到着直後からツツドリが登場。桜の木でモククロシャチホコを捕獲し、ムクの木に運び平らげていました。通常型の後ろ姿、正面、その後餌をくわえて登場した若鳥と思われる個体、ムクノキ幹にキツツキのように止まった個体といろいろなポーズを観察。鳥友も大満足の模様。その後、隣の流山市の水田地帯に移動し、渡りの途中に鳥たちを探索。田んぼの中に敷いてある稲わらの上で休憩していたタシギ、農道脇に現れたノビタキ、耕地を移動するセグロセキレイ、ハクセキレイの若鳥の姿を観察。(写真)2022年9月27日撮影
2022.09.28
コメント(0)
-

柏の葉公園で見かけたハイブリッドのカモについて
今日、柏の葉公園にでかけた際、バーベキュー場隣接のボート池でマガモのエクリプス似の個体を観察しました。黄色の嘴でマガモと違って嘴爪の黒さはなく、背の上部と肩羽は赤褐色でマガモの灰白色と違っていました。また、マガモの中央尾羽の外側に巻羽となっている点もありませんでした。マガモを原種とした家禽アオクビアヒル、アイガモのハイブリッドの可能性が考えられました。マガモはなぜ交雑しやすいかを拙宅の亭主に話しをしたら、マガモとカルガモのDNAはまったく同じだよ。種が分化して時間が経っていないか、交雑して遺伝子が溶けてしまったと研究者の西浦功さんが報告している由。(参考文献)バードリサーチニュース概要版2014年10月号. 日本産鳥類のDNAバーコーディング.この内容の中に、日本列島内の種間・種内の遺伝的差異と構造と題する報告があり、種間変異が1%以下の種として、マガモとカルガモは両種の遺伝的差異は0%、アカコッコとアカハラは0.15%,カッコウとツツドリは,0.3%の違いしかなかったと記されています。つまり、マガモとカルガモの遺伝子レベルでは同一種と言えるということです。ただし、種の分類にする際の総合的知見による判断で別種とされているとのことです。(写真)一枚目:2022年9月27日撮影のハイブリッドのカモ二枚目:2022年1月松戸市で観察したマガモの雄三枚目:2008年9月手賀沼沿岸で観察したマガモの雌
2022.09.27
コメント(0)
-

柏の葉公園で復数のツツドリを発見
青空が広がった今日は、ヒタキ類やカッコウ科の鳥たちを期待して柏市柏の葉公園に出かけました。県民プラザ前の池にはまだカモの姿はなかったものの、ツツドリが桜の広場と公園隣接地といったり来たりを繰り返しているのを発見。桜の枝に複数回止まってくれたものの、光線や枝に隠れてとまってなかなか思うように記録できませんでした。かろうじて、何枚かツツドリの特徴がわかるものを記録できました。このほか、桜の木には小群のシジュウカラ、コゲラが飛来。虹彩は暗色と思っていたコゲラ、よく見ると橙色に見えました。カモの仲間は、カルガモとアイガモの姿があったのみで、コガモ、ヒドリガモなどは見られずじまいでした。(写真)2022年9月27日撮影
2022.09.27
コメント(0)
-

水元公園のミゾゴイ、キビタキ、ヒドリガモなどの観察記
連休最終日になってようやく青空が広がりました。ミゾゴイが飛来したと耳にしていたので、都内水元公園に出かけました。その姿は薄暗い林の一角にありました。餌をとるので短距離を動いていましたが、枝や葉っぱの影に隠れて思うように記録がなかいませんでした。しかし、現地で集まった面々が公平に見られるように整理をし、通行者に注意を払ってくださった皆さんには感謝しています。一瞬でも目にできてうれしかったです。その後は、カワセミの里方面を探索し、サンコウチョウ、キビタキ、ヒドリガモ、カルガモ、カワセミなどの姿も観察できました。(観察したキビタキのメモ)キビタキは下面が汚白色で喉が白く、雌個体でした。ただし、動きが活発でバフ色の翼帯が確認でくきなかったので若鳥が第一回冬羽の換羽しているものかどうかは不明です。(観察したヒドリガモのメモ)一羽は脇の羽が大きく丸みがあるように見えましたので雌の非繁殖羽と思われました。(カワセミの観察メモ)その姿はキャンプ場からカワセミの里にかけての小合溜の水域にありました。(写真)2022年9月25日撮影
2022.09.25
コメント(0)
-

9月から10月のコガモの羽色
雨続きでなかなかフィールドに出かけられません。湖沼にはコガモなどのエクリプス羽を観察できる頃なのですが、かなわないので画像で復習しています。(1)成鳥雌エクリプス1枚目の写真は、2016年9月に手賀沼で観察したコガモです。下嘴の橙色が目立ちました。嘴は雄であれば、嘴全体が黒いですから、雌とわかります。また、上面は若鳥のほうがより黒っぽく見えますがそうではないで成鳥と思われます。また、最外三列風切の黒条の出方は長く、先端に届いています。アメリカコガモであれば、黒条の出方は短く、先端には届きませんのでコガモと同定できます。(2)成鳥雄エクリプス2枚目の写真は2020年10月に手賀沼で観察・撮影したコガモです。嘴全体は黒く、上面には黒っぽさがありましたので、コガモ雄のエクリプス羽とわかります。また、目より上の部分は暗色で眉斑はありませんでした。この点から不明瞭な過眼線と眉斑がある雌個体ではなく、雄とわかります。なお、三列風切が長い印象がありました。(3)雌生殖羽写真は、2014年3月に手賀沼で観察・撮影したコガモです。嘴基部と側面が黄色で三列風切に橙褐色の斑が表れています。1枚目の写真の個体の三列風切には橙褐色がないので違いがわかると思います。
2022.09.24
コメント(0)
-

八柱霊園のツツドリ、エゾビタキ観察記
熱帯高気圧が台風にかわる影響で三連休はほとんどが雨との予報のため、秋の渡り鳥との出会いを期待して千葉県松戸市の八柱霊園を訪ねました。例年、カッコウ科の鳥たちが立ち寄っていく林エリアではツツドリの若鳥の姿、エゾビタキの姿がありました。ツツドリの若鳥は黒っぽい個体、赤っぽい個体を見かけることがあり個体変異が実に多い傾向にあります。今朝、観察できたのは赤っぽいものでした。観察した個体は尾羽の白斑がはっきりとしていて、野鳥図鑑670(2014)が尾羽の白斑はホトトギスほど目立たないと記していますがそうではありませんでした。エゾビタキは、顎線が明瞭で上面が褐色、大雨覆先端と三列風切の羽縁が幅広く白く、下嘴は黒色でした。合計4羽以上の姿を見かけました。(写真)2022年9月22日撮影
2022.09.22
コメント(0)
-

モズのはやにえと高鳴きをめぐる言い伝え
モズの高鳴きがよく聞こえてくる時期となりました。浦本(1988)が述べているように、モズは冬には雌雄別々に一羽ずつなわばりを占め、そのなわばりの所有を宣言しあうのが高鳴きです。高鳴きが聞こえるようになると、昆虫、ムカデ、ミミズ、トカゲ、カエル、ネズミなどを捕まえて食べているのを目撃します。野本(2016)が述べているように、はやにえからそのむ地域の生物相の一旦を知ることができるのでフィールドを歩く時に参考になります。また、「モズの高啼き七十五日」との言い伝えがあり、モズの高鳴きを初めて聞いてから75日目に霜が降りだすとされています。農作物の収穫も作業の目安としている地域もあるようです。モズについてのいくつかの地域の言い伝えについては、日本野鳥の会埼玉がホームページで紹介はしていますので、下記に紹介します。#日本野鳥の会埼玉 野鳥の声を楽しもう No12モズ.https://www.wbsj-saitama.org/yacho/koe/12.html・モズ(百舌鳥)の高鳴きは晴天の兆し(千葉・富山・高知・福岡)・モズ(百舌鳥)の高鳴きは七十五日の上天気(広島)・モズ(百舌鳥)が来るとその年はもう大風がこない(熊本)・モズ(百舌鳥)が鳴き始めると風が吹かない(愛知・奈良・福岡)・モズ(百舌鳥)が早く鳴けば、早く寒さ冬が来る(滋賀・大分)・モズ(百舌鳥)が鳴くと雪が降る(岐阜)(引用文献)浦本昌紀.1988.もず.四季の博物誌.p386-387.朝日文庫.野本康太.2016.おすすめモズのはやにえ探し.自然保護 NOV. / DEC. 2016 No.554.p22-23.日本自然保護協会.(写真)2018年 2月 3日千葉県我孫子市にて撮影2018年10月29日千葉県我孫子市にて撮影2021年 1月17日千葉県我孫子市にて撮影
2022.09.21
コメント(0)
-

暗闇でイソヒヨドリが囀る
9月に入って千葉県北西部のJRの駅前にある商業ビルとその周辺で真っ暗になった夜間にイソヒヨドリの「ホイピリーチョチョ」「ヒィーチョイピー」とさえずりが聞こえました。あたりは真っ暗でしかも繁殖期はもう終わっているのに不思議な感じでした。ビルを移動しながらその屋上で囀り、明らかにテリトリーを防衛している雰囲気でした。帰宅後、拙宅の亭主にそのことを話したら、イソヒヨドリの雄は周年なわばりを維持すると文献に報告があったと思うと教えてもらいました。亭主のライブラリーを探してみると、伊澤雅子さん、松井晋さんがBird Research News(2011)に「よい営巣場所の確保は次の春のメスの確保に結びつくことから建物を中心としてなわばりを形成している」と記載がありました。また、「オスはなわばりの中の高い位置にとまり、見張りをしている」とも記されていました。(写真)暗闇で観察した商業施設で子育てをしていたイソヒヨドリのペア2022年4月7日撮影(引用)伊澤雅子・松井晋.2011.イソヒヨドリ.Bird Research News Vol.8 No.8.p4-5.
2022.09.20
コメント(0)
-

セイタカシギの共同的一夫ニ妻について
バードリサーチ(2022)が述べているように、セイタカシギは日本国内では繁殖期は5~7月,一夫一婦制で繁殖すると記載している文献がほとんどだと思います。ところが、北川(2000)が1985年以来行っている調査・観察結果から1羽の雄と2羽の雌からなるトリオが生じることが判明し、雌と雌つがいが形成され、繁殖期にむけて共同的一夫ニ妻に発展する可能性が見つかったと報告しています。興味深い報告なので情報提供します。(トリオ形成の3つのタイプ)(1)雌、雌のつがいに雄が参入両雌が雄を受け入れる場合はトリオが形成されることになるが、繁殖期が近づき雄が2羽の雌のうち1羽に対し、あるいは雌同士の敵対関係が強くなると雌同士のつがいは解消し通常のつがいが形成される。このタイプは、非繁殖期に一時的に形成される。(2)両雌が雄に敵対し雄の参入を許さない場合両雌が雄に対して敵対し雄の参入を許さない場合、雌、雌のつがいが維持される。1996年から1999年にかけて4年間継続された。(3)両親に娘が参入する場合繁殖地から親子で越冬期間を過ごし、繁殖地へ前年の子を伴って移動してくる。親がなわばりを形成し営巣すると親鳥は若鳥に対して攻撃的になるが若鳥に対する敵対行動が強くないと若鳥は親の産卵後もなわばりにとどまり、娘が両親の巣に卵を生む機会ができ、共同的一夫ニ妻に発展する。(引用)北川珠樹.2000.セイタカシギとその繁殖地・越冬地としての湿地・干潟の保護・保全に関する研究.2000年度宝ホールディングス ハーモニストファンド 報告書.p5-11.https://www.takara.co.jp/environment/fund/aid/h12report.htmlバードリサーチ.2022.Bird Research News.2022年6月.p1-2.
2022.09.20
コメント(0)
-

北海道のノビタキは大陸に直接渡っていた
私が野鳥を見始めた1980年代はじめの頃、当時の探鳥会リーダーが渡り鳥について説明するときは本州伝いに南下して大陸に渡ると説明を聞き、そのエビデンスも確認しないまま、信じていました。ところが国立研究開発法人森林総合研究所は、ドイツヘルゴランド鳥類研究所、オーストラリアディーキン大学、北海道大学、山階鳥類研究所と共同で、2014年にジオロケーター(小型の計測機器)を草地性のノビタキに北海道で装着し、その渡り経路を追跡しました。2015年に回収した結果、本州を経由せず北海道から直接大陸に渡っていたことが判明しました。繁殖を終えたノビタキは大陸に移動して中国を経由し、主にインドシナ半島で越冬していたことがわかりました。従来刊行されている文献を見返してみましたが、言及しているものは見当たりませんでした。エビデンスを確認しないまま、ノビタキの渡りを理解していたつもりでいたことを後悔しています。なお、森林総合研究所(2016)は、前記の調査との結果にくわえて北海道のノビタキについてつぎのように記しています。「1 万3 千年ほど前の北海道は、最終氷期にあり寒冷で乾燥しており、草地が広がっていました。当時の北海道は、サハリンを通して大陸とつながっており、マンモスをはじめ草地性生物の多くが大陸から渡来してきたとされています。ノビタキなどの草地性鳥類もこの北回りのルートで北海道に定着し、このルートが現在も遺産として残っているのかもしれません」(引用)森林総合研究所.2016.北海道の草地性鳥類(ノビタキ)は大陸経由で南下してインドシナ半島で越冬する-小鳥の新たな渡り経路を発見-.プレスリリース2016年8月22日付.
2022.09.19
コメント(0)
-

手賀沼沿岸でノビタキと再会
9月も半ばをすぎノビタキとの再会を期待してホームグランド手賀沼沿岸を探索しました。その姿は、いつもの水田地帯の一角にありました。眉斑が淡褐色で背と肩羽に黒斑が点在していたので若鳥と思われました。ノビタキを目撃した後、過日クイナの声がしていた葦原でしばらく待機してみました。すると、葦原の中からクイナが登場。ずんぐりとした体型、額から頭頂、後頸、体上面が赤褐色で黒い軸斑が目立ちました。脇から下腹、下尾筒が白黒の縞模様が素敵でした。このほか、モズに追尾されて葦原に飛来したカワセミ雄、頭部から体上面が褐色で黒い縦斑があり、眉斑と喉から下面が白色のセッカの姿を見つけました。(写真)2022年9月17日撮影
2022.09.17
コメント(0)
-

野鳥は片目をつぶって眠っている?
昨日、茨城県南部でシギ・チドリを観察してきました。その折、アオアシシギが目をつぶって寝ているようにも見えました。そういえば、野鳥たちの眠りはどうなっているのだろうと帰宅後文献を紐解いてみました。はばたき(1988)に、閉じた目と反対側の脳半球には睡眠脳波が見られ、開いた目と反対側の脳半球には覚睡脳波が認められると記され、休憩場所のない大空を飛びながら脳を半分ずつ休めているとも考えられていると報告されていました。地上で休んでいる場合、両目をつぶって眠っているのか、片目をあけているのかを観察してこなかっただけに次回から注視してみないといけませんね。(引用文献)はばたき.1988.神戸市立王子動物園.第24号.p13.(写真)アオアシシギ:2022年9月15日茨城県稲敷市オバシギ:2022年9月10日千葉県船橋市三番瀬キアシシギ:2022年8月14日千葉県習志野市谷津干潟ハマシギ:2022年9月3日茨城県稲敷市
2022.09.16
コメント(0)
-

茨城県浮島周辺のシギ・チドリ探鳥記
9月も半ばとになり、茨城県南部のシギ・チドリの様子を見に出かけました。蓮田エリアの東端からスタートしシギ・チドリの姿を探索しました。東端のエリアには、コチドリ、セイタカシギ、タシギ、オグロシギ、コアオアシシギ、アオアシシギ、クサシギ、イソシギ、トウネン、ハマシギ、ウズラシギが羽を休めたり、餌を物色していました。また、その後訪ねた中央部ではウズラシギが蓮田と草原の中で羽を休めていました。なお、オグロシギが移動していた蓮田の画像に写っている黄色の花はアメリカミズキンバイです。近年、拡大傾向にあり、蓮田にどのように影響が出てくるか注視が必要です。(写真)2022年9月15日撮影
2022.09.15
コメント(0)
-

秋の手賀沼にアオアシシギがやってきた(秋の手賀沼探鳥記)
9月に入りはじめてホームグランド手賀沼とその沿岸を訪ねました。スタート地点の柏市側の水面の杭にミサゴが止まっている姿を発見、また入江になっている葦原の中に復数のゴイサギの姿を見つけました。その後、手賀沼大橋から東寄りの水面と沿岸を探索すると、浅瀬で餌を物色して歩いていたアオアシシギを発見しました。上面が褐色がかり各羽縁が角張っいる印象があったのでアオアシシギ若鳥と思われました。さらに水田との縁を探索すると、バッタやイナゴなどの餌を探すダイサギ、コサギ、電線に翼帯1本の小鳥の姿と電柱にはチョウゲンボウの姿がありました。小鳥は、お腹が黄色っぽく、翼帯は1本。田んぼのすぐ脇の電線に止まっていたこともあり、横顔だけ見ているとえっなんの種類だろうと思いましたが、シジュウカラと判明。(写真)2022年9月13日撮影
2022.09.13
コメント(0)
-

ハマシギの羽色のいろいろ
猫背のようなスタイルで頭をあげることなく干潟で餌をあさる光景を見かけるハマシギ、トウネンよりも大きいのですが、10日に三番瀬でトウネンを遠目に観察していた御婦人からあれはハマシギですねと質問をもらいました。ハマシギのほうがトウネンより大きく、嘴がハマシギでは長くて下にまがっています。また、背の斑紋が不明瞭で一様に見えることが多いなどのポイントをご案内しました。ハマシギの足、嘴の長さ、形を覚えて置くことで多種との識別に役立ちます。夏羽、若鳥、冬羽などの写真をアップし、その特徴を整理しました。(1)夏羽写真は2015年5月に印西市の水田、2015年5月に三番瀬で観察した夏羽です。上面の赤褐色、腹部の黒が目立ちます。(2)第一回冬羽写真は、2014年9月に三番瀬で観察した第一回冬羽、2021年2月に谷津干潟で観察した第一回冬羽です。上面は灰褐色で各羽縁は白色です。嘴はサルハマシギに似ていますが短く、湾曲は小さいです。(3)夏羽から冬羽に換羽中写真は2014年9月に三番瀬で観察した夏羽から冬羽に換羽中の個体です。額から頭頂にかけて茶色が残り、腹部には黒さがかなり残っています。肩羽に灰色の冬羽が見えています。
2022.09.12
コメント(0)
-

オバシギの羽色を復習
昨日、三番瀬でオバシギと出会えました。オバシギは、シベリアの東北部のみで繁殖し、インドから東南アジアやオーストラリアのみで越冬する極東の固有種です。ところが、守屋(2019)が指摘しているように、日本に飛来している21種のシギ・チドリのうちオバシギなど12種は繁殖が終わった秋の渡りの時期の個体数が減少しています。近縁のコオバシギに比べると個体数は多いものの分布が狭いことから出会えなくなるのではないかと心配されます。昨日、観察した幼羽、第一回冬羽、夏羽、冬羽の写真をアップし、観察なさった際の参考となれば幸いです。(1)幼羽一枚目は、昨日観察したオバシギ幼羽です。胸の黒色斑が密で帯のように見えるのが特徴です。二枚目は2014年9月に三番瀬で観察した幼羽です。一枚目と比べると頭部の褐色が強い印象です。(2)夏羽三枚目から五枚目は2020年8月に三番瀬で観察した夏羽です。肩羽に赤褐色の羽があり、肩羽と胸が黒色味が強いのが特徴です。(3)夏羽から冬羽に換羽中六枚目は、2017年7月に三番瀬で観察した夏羽から冬羽に換羽中の個体です。肩羽の赤褐色の羽があります。(引用)守屋年史.2019.極北で繁殖するシギ・チドリに与える気候変動の影響.Bird Reseach Water Bird News 2019年3月号.水鳥通信.p4-5.バードリサーチ.
2022.09.11
コメント(0)
-

三番瀬のシギ・チドリ探鳥記
大潮で干潮が10時53分でしたのでそれに合わせて三番瀬を訪ねました。夏休みが終了したものの、たくさんの潮干狩り客が干潟に入っているので、シギ・チドリは、到着時は浦安側と船橋埠頭側の干潟に分散していました。その後、海浜公園から干潟への入場口正面の干潟突端に移動し採餌をしていました。頭から上面が灰黒色で羽縁が白く、その内側の軸斑は黒く、脇腹に黒斑があるオバシギ幼鳥の姿が復数ありました。胸の黒斑が密で帯のように見えました。また、上面に白い白斑があるキアシシギ幼鳥の姿もありました。このほか、シロチドリ、メダイチドリ、オオソリハシシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、トウネン、ミユビシギ、ハマシギ、ウミネコの姿を観察しました。(写真)2022年9月10日撮影
2022.09.10
コメント(0)
-

ツツドリの成鳥雄、雌、若鳥の識別
昨日、都内の公園でツツドリ成鳥雌を観察してきました。参考までに成鳥雄、雌、若鳥の画像をアップし、特徴を整理しました。(成鳥雌)一枚目、二枚目の写真が昨日観察した成鳥雌個体です。頭部は青灰色、黄色のアイリング、嘴は下嘴基部に黄色味があり、虹彩は黄色がかかった褐色。腹には太めで間隔の広い黒色横斑が見えました。また、胸には褐色味がありツツドリ雌個体とわかりました。(成鳥雄)三枚目の写真は2015年9月に野田市で観察・撮影した個体です。下面に褐色味はなく、光彩は暗色でした。(若鳥)四枚目の写真は、2018年10月に都内の公園で観察・撮影した個体です。上面は幼羽と成鳥羽の灰色が混在していますが、全体的には褐色に見えました。(雌の赤色型)五枚目(2019年9月に都内)、六枚目(2017年8月野田市)、七枚目(同左)の写真は、成鳥雌の赤色型です。上面全体のベースが赤褐色で黒い横縞とコントラストが印象的です。なお、赤色型は雌のみです。
2022.09.08
コメント(0)
-

都内の公園でツツドリと出会う
東京都と埼玉県の境界にある公園の一角にツツドリの姿を探しに出かけました。現地到着から13時頃までは登場せず、ハシブトガラス、シジュウカラ、オナガの姿のみ。午後から雨が降り出す予報だったので切り上げようとしたら、2羽の鳥影が桜の木の中に。待機していると、桜の枝にツツドリの姿が出現してくれました。頭部は青灰色、黄色のアイリング、嘴は下嘴基部に黄色味がありました。この他、虹彩は黄色がかかった褐色。腹には太めで間隔の広い黒色横斑が見えました。観察した個体の胸は褐色味があったことからツツドリ雌個体でした。(写真)2022年9月7日撮影
2022.09.07
コメント(0)
-

柏市と松戸市の境界のサシバ観察記
昨年、柏市と松戸市の境界にある公園の一角でサシバの姿を目撃したこともあり、今シーズンも現地を訪ねました。現地は車の往来の激しい国道沿いにあるにもかかわらず、公園のある一角だけは昔からの景観がかろうじて残っています。現地に到着した直後、小高い山の一角をすーと飛翔するタカの鳥影。しかも、木のてっぺんに止まりました。頭から上面が褐色で眉斑があり、胸から腹には褐色の縦斑があるので幼鳥と判明。その直後、もう一羽が出現。こちらも幼鳥でした。何度か稜線を飛翔し、姿を消したと思ったらセミらしきものをくわえて登場し、たいらげている姿も目撃。帰宅後、前年の観察メモを確認すると、9月3日と4日でしたのでほぼ同時期。公園の一角が渡りの途中の停留場のようななのでしょうか。(写真)2022年9月3日撮影
2022.09.05
コメント(0)
-

茨城県浮島周辺のシギ・チドリ探鳥記
二週間ぶりに茨城県南部のシギ・チドリを探しに出かけました。蓮田エリアの東端からスタートしシギ・チドリの姿を探索しました。西端ではアオアシシギ、セイタカシギの姿、その後立ち寄ったエリアではコチドリ、コアオアシシギ、ソリハシシギ、トウネン、ヒバリシギ、ウズラシギ、ハマシギ、キリアイの姿を見つけました。この中でトウネンは、画像を見直している最中です。ヨーロッパトウネンのように見えても初列風切が尾羽から突出しない個体や若鳥のいろいろな個体が複数目に入ってきたことによるものです。(写真)2022年9月3日撮影
2022.09.03
コメント(0)
-

アカエリヒレアシシギの話題いろいろ
9月から晩秋にかけて港や内湾、水田、湖沼などにアカエリヒレアシシギが飛来することがあります。この鳥についての興味深いリポートを紹介します。なお、アップし画像は2020年10月3日に茨城県稲敷市で観察した夏羽から冬羽に換羽中の個体です。(1)アカエリヒレアシシギはコゲラ、ヒヨドリに類似江村(2011)は、アカエリヒレアシシギの舌表面を電子顕微鏡で観察した結果を報告しています。それによると、肉眼では細長い爪楊枝状を呈し、舌全体の形態しコゲラに、舌尖の先端はヒヨドリに類似していたと記しています。また、その構造は、口腔内に入った食物が確実に食道に流れ込み、口腔外に押し出されない装置であると考えられると述べています。(引用文献)江村正一.2011.アカエリヒレアシシギの舌表面の走査型電子顕微鏡による観察. 医学と生物学.第155巻.第1号.p1-6.(2)野球場に飛来したアカエリヒレアシシギ桑原・小島(1993)は、北海道興部町営球場にナイターの試合中に飛来した件を報告しています。それによると1993年9月13日21時頃、ナイター中に約100羽の群れが飛来したと報告しています。球場内の外野に人がいるにもかかわらず地上に降りた個体がおり、人間との距離は1.5mだったと述べています。飛来した要因については、球場の光源に鳥の群れが集中して引きつけられたことをあげています。なお、過日8月30日西武対楽天戦でアカエリヒレアシシギが球場に飛び込んだとのニュースは記憶に新しいところです。このほかにも2021年9月5日横浜スタジアム、2017年8月30日に仙台市Koboパーク宮城でもアカエリヒレアシシギがーの群れが飛来したことがメディアで取り上げられています。(引用文献)桑原和之・小島紀行.1993.北海道紋別郡興部町町営球場へのアカエリヒレアシシギ の観察記録.鳥類標識誌.第8巻.第2号.p53-59.
2022.09.02
コメント(0)
-

秋に町中で見かけるオオタカとサシバ若鳥の識別
9月に入り、市街地の一角にタカ類が立ち寄る姿を見かけることがあります。特に、オオタカとサシバの若鳥は短期間滞在する姿が見られることがあります。それぞれの若鳥の特徴を整理してみました。(1)オオタカ若鳥1枚目、2枚目の写真は柏市で2007年4月に見かけたオオタカ若鳥です。白い眉斑と虹彩が黄色が目立ちます。サシバは虹彩が暗色です。また、耳羽は淡色です。サシバは暗褐色です。この2点はまず確認したいポイントです。くわえて、顔から喉に縦斑が見られることが多いように思います。(2)サシバ若鳥3枚目、4枚目の写真は2016年7月、2009年9月に見かけたサシバ若鳥です。眉斑がはっきりしていること、下面には縦斑があります。また、虹彩は暗色です。オオタカでは静止している際は初列風切から突出している尾羽が長いので確認したいポイントです。
2022.09.01
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1