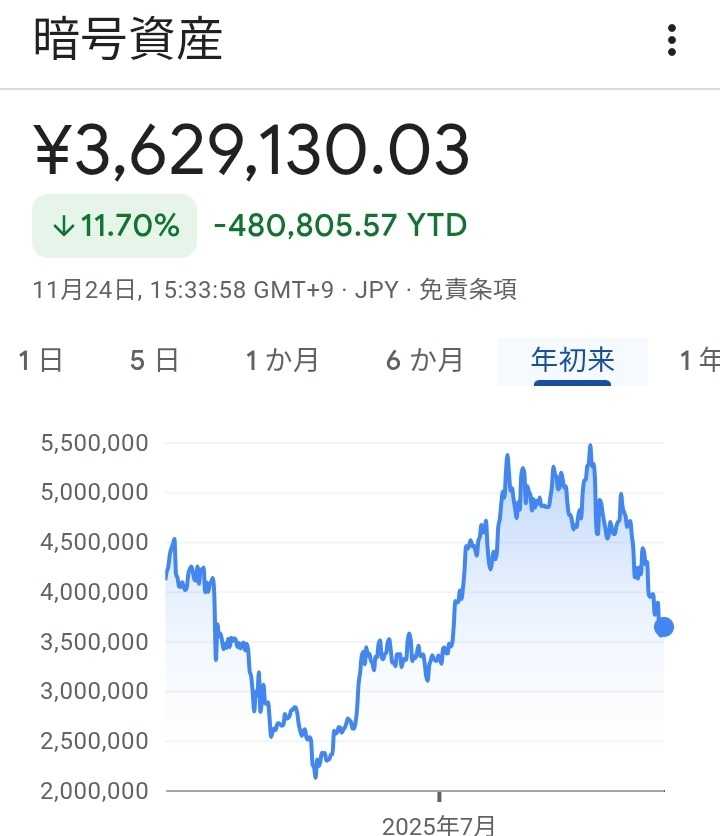2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年12月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

大晦日の今日
境内は着々と新年をお迎えする準備が進んでおります。本日31日午後10時半より、皆様からお預かりいたしました、「形代」を祓い清める「年越の大祓」神事を斎行致します。続きまして、1月1日零時より、「元旦祭」を斎行致します。元旦祭の最中も勿論、お参り頂けますし、社殿内の祭事も外からご覧頂けます。授与所では、御神札・御守・おみくじなどご用意しております。境内の様子などは明日UP出来ましたら、お伝え致します。初詣は烏森神社へ・・・こちらは新しいおみくじの「心願色みくじ」「願い札」の結び處です。野立て傘と色ごとの紐をかけた、「心願色みくじ」の「願い札」専用の結び處となります。お願い事を書いた、「願い札」を願いを込めて結んで下さい。後ほど、神職がこの紐ごと(色ごと)に、願い事が叶いますよう、御祈願致します。「心願色みくじ」は1月1日零時より授与となります。
2006年12月31日
-

『初詣』
参道に「初詣」の小幟がたちました。そして、賽銭箱ヒ右側の「年越の大祓」のご説明は、机の上に小さく書いているものがあるので、取り外し、1月1日零時から授与される授与品の御案内へと掲示が変わりました。また、授与所の横にも掲示板を新設致しました。授与所でお並びの際、ご覧いただければと思います。さて、いよいよ明日は大晦日。31日です。「年越の大祓」は夜の10時30分斎行致します。祭事にて形代を使うため、少し早めの時間までにお持ち下さい。夕方までにお持ちいただければ、十分間に合います。まだ、お納めでない方は、どうぞお早めにお持ち下さい。その大晦日から元日にかけて、参拝者の方に「皐月会」による、甘酒が振舞われます。初詣は烏森神社へ。。。
2006年12月30日
-
初詣・元旦祭
平成18年も残りわずかになりました。当社「烏森神社」では、初詣の皆様を「皐月会」の甘酒接待でお迎え致します。(今年は例年より多く用意されるそうですが、なくなり次第終了とのことです。)境内の整備も順調に進み、都会の中でも緑や癒し等を感じていただければ・・・と思います。12月31日から1月1日に日付が変わると、社殿では「元旦祭」が行われ、「年のはじめの歌」を合唱致します。同時に多くの参拝の方がお賽銭をお入れになり、「パチパチ」と拍手の音が鳴り止みません。元旦祭終了後は、神職がお参りの方をお清め(お祓い)致します。元旦より授与される、「稲穂の開運御守」や「心願色みくじ」(おみくじ)などで境内・授与所は賑わい、お正月の雰囲気をより一層感じられます。授与所は1月1日は毎年大体2時半頃まで明々としており、境内はその後も、参拝の方がいらっしゃいます。元々参拝は24時間可能な神社ですが、元旦は社殿内を明け方まで明るくしておりますので、是非お参り下さい。
2006年12月29日
-

お正月に向けて~2~
境内の様子も随分お正月に近い雰囲気となりました。 社殿正面の様子 授与所の様子12月31日 「年越の大祓」神事 午後10時半斎行 ※形代をお納め下さい。 1月 1日 「平成十九年度 烏森神社 元旦祭」 零時斎行皐月会による甘酒の無料接待がございます。 「稲穂の開運御守」 と「心願色みくじ」は1月1日零時より授与を行います。 心願色みくじ願い札結び處 手水舎横の箱型掲示板 の様子「心願色みくじ」 初穂料500円この「心願色みくじ」は全てが当社独自のおみくじです。「おみくじ」・「願い札」・「願い玉」が授与されます。◆「おみくじ」は色ごとにその内容が異なります。◆「願い札」に願い事を書き、結んで下さい。後ほど神職がご祈祷いたします。◆「願い玉」には「玉」だけでなく、小判とフックの金具が付いたので、携帯電話などの持ち物につけることが出来ます。この「願い玉」色ごとにその願い事が叶うように御祈願致しております。「心願色みくじ」の授与は1月1日零時からです。古札・神棚の注連縄などのお焚上げを授与所にて受け付けております。授与所は朝9時~夜6時までとさせて頂いております。お焚上げは大きな神棚や熊手・破魔矢などはお焚上げ出来ませんので、こちらではお預かり出来ません。御神札・御守の授与などはこちらにお越し下さい。しんばしネットさんの当社「初詣」の御案内のページはコチラ
2006年12月27日
-

授与所と授与品のお知らせ
本日より、社務所にて行っておりました、御神札・御守・おみくじなどの授与を社殿向かって左下の神札授与所にて行います。御用の方は、授与所にお越し下さい。新しい御守の御紹介を致します。 開運御守新橋烏森のキャラクターの「こい吉」君の御守です。 交通安全裏に角度変更可能な吸盤が付いております。 厄年御守護 前厄・本厄・後厄の厄年御守こちらはご自宅に。 各厄年の御守は普段お持ち頂ける様な小さいカード型のものです。 出張安全御守場所柄、ご希望が多くございました「出張安全」の御守です。各初穂料などは御守の御案内(コチラ)をご覧下さい。新春からは新しいおみくじの「心願色みくじ」の授与を始めます。
2006年12月26日
-
神札授与所
明日より、社殿向かって左下の「神札授与所」にて、御神札・御守の授与を致します。社務のお時間は、午前9時頃~午後6時頃までです。時間内にいらっしゃれない方は、お電話にてご確認下さい。
2006年12月25日
-

天皇誕生日
今日は天皇誕生日、祝日です。今上天皇のお誕生日をお祝いする日です。皇居では一般参賀がございます。宮内庁のページをご覧下さい。天皇のお誕生日を国家として初めて祝ったのは、明治元年9月22日(旧暦、1868年)に天長節として祝ったときです。明治6年(1873年)の太陽暦採用後、11月3日に変更。その後、即位した天皇の誕生日にあわせて天長節が定められました。戦後、天皇誕生日として国民の祝日と定められ現在に至ります。なお、皇后の誕生日は「地久節」と呼ばれますが、戦前においても国家の祝日にはなっていません。皇居に程近い、今日の新橋は清々しい快晴です。良いお天気になりそうです。
2006年12月23日
-
冬至について
今日は「冬至」です。冬至は二十四節気の一つ。12月22日ごろ。および、この日から小寒までの期間のことを言います。太陽黄経が270度のときで、北半球では太陽の南中高度が最も低く、この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなります。そのため昼が一年中で一番短く、夜が長くなります。この日を境に、一陽来復、日脚は徐々にのびていきます。「タタミの目、一目ずつ日が延びる、米一粒ずつ延びる」などといいます。『暦便覧』では「日南の限りを行て、日の短きの至りなれば也」と説明している。気象統計学的には、東京など太平洋側の地方は夏至のころより、冬至の12月や1月の方が日照時間が多いとされています。従って、昼が短くても冬至頃が、太陽の暖かい光をいっぱい受けられることになります。太陽恵みによって穀物や野菜をつくる農民にとって、この日は太陽の強さの復活を祈る日となりました。昼の長さは9時間45分で夏至の日と比べますと、約に5時間の差がつきます。 この日について様々な言い伝えや風習が残されています。「冬至に天気が良ければ翌年は豊作」「冬至に雷が鳴れば雨が多い」「冬至に南風がふけば地震・日照り・大雨」「冬至に雪が降れば豊作」という伝えがあります。 『冬至過ぎれば寒さ本番』日本では、この日に柚子湯に入り小豆粥や南瓜を食べると風邪をひかないと言われています。冬至かぼちゃを食べて金運を祈り、冬至風呂(柚子湯)に入って無病息災を祈る行事を各家庭で行います。中国北方では餃子を、南方では湯圓(餡の入った団子をゆでたもの)を食べる習慣もあります。古代には、冬至を1年の始まりとしていました。その名残で、現在でも冬至は暦の基準となっています。太陰太陽暦では、冬至を含む月を11月と定義しているが、19年に1度、冬至の日が11月1日となることがあり、これを朔旦冬至と言います。朔旦冬至が正確に19年周期で訪れることは、暦が正確に運用されているということです。暦の正確さは、政治が正しく行われていることの証であるとして、朔旦冬至は盛大に祝われました。これまでで最後の朔旦冬至は1995年、次の朔旦冬至は2014年です。◆ゆず湯◆「冬至の柚子湯に入ると無病息災」といわれています。冬至と湯治の語呂あわせもあります。ゆず湯に入ると肌がスベスベになる美肌効果があったり、冷え性やリュウマチにも効き、体が温まってカゼをひかないとも言われています。これらの効能は、ゆずに含まれている芳香成分――精油の働きによるもの。ゆずの精油にはピネン、シトラール、リモネンなどの物質があって、これらは新陳代謝を活発にして血管を拡張させて血行を促進します。ノミリンなどには鎮痛・殺菌作用があるので、体が温まり、カゼも治るのです。◆かぼちゃ◆この夜はカボチャを食べます。そのほかにこんにゃくや小豆粥を食べる習慣もあります。カボチャやこんにゃくは輸入品であり珍しい野菜を神に捧げたのが始まりのようでカボチャを食べると魔除けになり、また中風や風邪にかからないといわれています。小豆粥は中国の風習からで赤い色は災厄を祓うといわれています。現在は野菜が季節に関係なく供給されていますが、西洋野菜が日本に入るまでこの時期に取れる野菜は少なく、保存できる野菜も少なかったのです。かぼちゃは保存がきき、保存中の栄養素の損失が他の野菜に比べて少ないので、冬至の時期の貴重な栄養源でもありました。江戸時代中期から風邪や中風の予防にかぼちゃを冬至に食べる風習が根付いたといわれています。これは、当時、冬場に野菜がとぎれてビタミン類が不足することからで、これは、日本かぼちゃしかない時代に始められた風習です。かぼちゃの栄養成分の特徴は、なんといってもカロチンを多く含んでいることです。カロチンは、体内でビタミンAにかわって肌や粘膜を丈夫にし、感染症などに対する抵抗力をつけてくれます。「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」といわれるのはその為です。◆一陽来復◆冬至は一陽来復ともいいます。陰が極まって陽が帰ってくること、境から運が向いてくる転換の日でもあるとされます。「冬至冬中冬初め」といわれるように本格的な冬への準備の日でもあります。寒さも本番です。皆様も風邪をひかないよう、お気を付け下さい。
2006年12月22日
-

参道・授与所について
いよいよ、年末が近付いてまいりました。今年も31日の大晦日の夜には皐月会の皆様のご協力で、甘酒の無料接待をご予定しております。初詣は是非当社へご参拝下さい。さて、、、今日は参道について少しお願いがあります。神社の作業などの為、境内に車両を入れる為、烏森通り側の道路の切り下げを行いました。その為でしょうか?道路側より、バイクを参道に乗り入れる方をお見かけいたします。参道は神社の境内であり、ご参拝の方が通られます。かなりのスピードでバイクを乗り入れされているので、大変危険です。どうか、参道はバイクの乗り入れをしないで下さい。参道と知らずに、バイクで通られる方もいらっしゃるので、参道に写真のような看板を出しました。自転車や歩行の際、少し狭くなりますが、ご了承下さい。例年通り26日より、社殿左下の授与所をお開け致します。御神札などの授与品や御用の際は、授与所までお越し下さい。
2006年12月20日
-

お正月に向け~境内~
本日、お正月に向け、神社の鳥居に高張と竹・松が付きました。境内整備に伴い、社殿下に竹などを植えておりましたが、今回は鳥居の左右にまだ小さいですが、「榊」の木の鉢植えを置きました。昼間はこのような感じですが、夜になるとこのような雰囲気になります。(この夜の写真は昨年のものです。)お正月の準備をしております。新しい御守や護符などをご用意しておりますが、また改めて御案内致します。
2006年12月16日
-
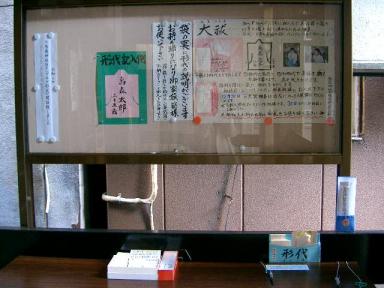
お知らせなど・・・
明日、15日より、「年越の大祓」の形代を社殿向かって、賽銭箱右の掲示板のところにご用意致します。 「夏越の大祓」では、本当に多くの方の形代をお預かりし、神事を斎行致しました。自身の1年間の罪・穢れを形代に移し、神事にてお清め致します。どうか、形代をお納め下さいますように。また、年末も近くなり、ご参拝の方が多くいらっしゃいます。お神輿のライトアップと、本年度の神輿渡御の様子のVTRの放映も行っております。 新橋の街でもチャリティーの行事が明日15日開催されます。場所は機関車広場です。「新橋クリスマスチャリティーイベント」詳しくは・・・しんばしネットのページへクリックしてご覧下さい。烏森通りには・・・当社の大神輿と氏子神輿をデザインした旗があげられています。 大きな交差点にはこちら↑ 烏森神社のシンボル、八つ棟型の大神輿と氏子神輿がデザインされています。 通りにはずらっと新橋のマスコット「こい吉」くんの旗が。
2006年12月14日
-
お歳暮について ~事始め~
お歳暮の時期です。今日はその「お歳暮」についてお話します。歳暮とは、文字通り年の暮れ、1年の終わりを告げる季語で12月の季語でもあります。これが転じて、一般には、暮れに世話になった人に対し感謝するなどの歳暮周りと呼ばれる年中行事が行われる事が多くあり、 このときに贈り物がされ、この贈答品がお歳暮と呼ばれていました。現在では「歳暮」「お歳暮」といった場合、この贈答品、または贈り物の習慣を指すことが一般的になり、日頃お世話になっている方に、1年間の感謝を込め、又、来年もより一層のお付き合いを願う為の贈り物です。古来、お正月には、お盆と同様に先祖の霊が帰ってくると考えられていました。ご先祖様と年神様(歳神様(としがみさま))を迎えるための祝い肴として新巻鮭・ブリをはじめ、米・野菜・酒などいずれも食料品を中心としたもの(古くは「歳暮の礼」とか「歳暮の賀」といわれています)を親元へ持参していたものが、次第に目上の人や日頃お世話になった人などへお正月用品を贈る「お歳暮」の習慣に変わったといわれます。お歳暮は一般に、12月初めから12月20日頃までに届くようにします。お正月の準備に必要な品を贈るので準備を始める12月13日「事始め」ごろに贈る習慣がありました。関東と関西では贈る時期もすこし違うようです。関西では12月の始めから中旬あたり、関東では11月下旬から贈られるようです。しかし、あまりにも早いのも考えものです。昔から12月13日は、1年の締めくくりとして、新年の準備を始める日とされています。ですので基本はやはり12月中旬がふさわしい時期かと思われます。今日はその丁度「事始め」の13日ですので、それにちなんだお話を致しました。 ちなみに、韓国でもお中元やお歳暮に似た習慣があり、旧暦8月15日と旧正月に肉類や調味料などを贈るようです。また中国では、旧暦の8月15日には月餅という餡や卵の黄身が入った菓子を、ミャンマーでは10月にお世話になった人に食料品やロンジーという民族衣装を贈ります。 ※事始めについて事始めとは、新年を迎える事をはじめるという行事です。お正月に向けて家の周りを掃き清める「煤払い」や、門松などに使う松を取りにいく「松迎え」などを行う日とされています。また、事始めは師に対して「事始めの餅」いわゆる鏡餅を送るしきたりという意味合いもあります。特に京都祇園の「事始め」は有名です。 祇園では、12月13日になると芸妓や舞妓が京舞の師匠宅や御茶屋さんへ次々と訪れて、今年一年のお礼と来年のあいさつを行います。早々と飾り付けられた鏡餅を前にして「おめでとうさんどす」のあいさつが交わされ、芸妓や舞妓は師匠から新しい舞扇をいただいて帰るそうです。事始めは、江戸幕府が12月13日から正月の準備を始めたことに由来するといわれ、今でも芸事を行う人々の世界では新年を迎える行事として欠かせないものなのです。
2006年12月13日
-

おみくじ
アド街ック天国での放送翌日は日曜日でしたが、TV効果は大きいのでしょうか、普段の日曜日とは違い、ご参拝者の方が多かったように思います。さて、先日社殿下に設置した竹ですが、まだ植えたばかりで弱いので、どうかおみくじなどを結ばないで下さいますようお願い申し上げます。「幸運おみくじ」を結んでお帰りになりたい方は、写真の手前にある、竹ではない木に結んでください。社殿向かって、左下手前の木です。今はすでに何本かおみくじが結んであります。
2006年12月12日
-
今夜の『出没!アド街ック天国』
「TV東京」系で放送中の「出没!アド街ック天国」ですが、今夜の放送は「新橋」の街が取り上げられます。夜9時~新橋の街のどんな情報が放送されるのか・・・楽しみですね。是非、ご覧下さい。新橋駅に程近い「烏森神社もランキングに入っているのでしょうか?!見所です!!
2006年12月09日
-

イルミネーションな新橋の街
新橋駅前もイルミネーションで華やかな感じになりました。 15日には「新橋クリスマスチャリティーイベント」が行われます。駅前のイルミネーションとは話が変わりますが、竹のライトアップに続き、境内の右側の狛犬もライトアップを試験的に行っております。明日9日(土)は「新橋」を取り上げた「出没!アド街ック天国」の放映日です。
2006年12月08日
-
大雪<たいせつ>
大雪二十四節気の一つ。山の峰は積雪に覆われ、里にも雪が降る頃。北国ではこの頃に降った雪は根雪となり、春まで大地を覆います。大雪は二十四節気の1つで12月7日頃。および、この日から冬至までの期間をさします。太陽黄経が255度のときで、雪が激しく降り始めるころ。十一月節。『暦便覧』では、「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明しています。鰤やはたはたの冬の魚の漁が盛んになり、熊が冬眠に入り、南天の実が赤く色付くころ。平地も北風が吹きすさんで、いよいよ冬将軍の到来が感じられます。この時節、時として日本海側では大雪になることもあります。今日の新橋は一日中曇り空の寒い日となりました。
2006年12月07日
-

社殿下左右の様子
境内整備が続いており、ご参拝者の方々には大変ご迷惑をお掛けしております。本日、社殿下左右に鉢植えの竹を置きました。また、お正月に向け、急ピッチで整備を行っております。 社殿下向かって左側の様子 社殿下向かって右側の様子ちなみに、左下の1番前にある小さな木をお正月の(普通の)おみくじを結ぶ専用の木にしようと、検討中でございます。決まりましたら、またご案内致します。社殿下右側に入る、入口の様子。緑が増えると、雰囲気が変わります。
2006年12月06日
-
来週9日(土)の「アド街ック天国」にて・・・
毎週土曜日夜9時~「TV東京」系で放送中の「出没!アド街ック天国」ですが、来週は「新橋」の街が取り上げられます。12月9日(土)夜9時~アド街はすでに3回目ですが、今回はどんな新橋の街の情報が放映されるのでしょうか?楽しみです!!勿論、新橋の街の中心に御鎮座する「烏森神社」も毎回何位かに入っているので・・・今回もきっと・・・。是非来週の「アド街」をご覧下さい!
2006年12月02日
-
12月 ~師走<しわす>~
師走<しわす>一年の最後の月であり、区切りをつけて新年を迎える準備に忙しい月です。日本では旧暦の12月を師走<しわす>と呼び、現在では新暦の12月の別名として用います。「師走」の由来には諸説あります。一般には、12月は年末で皆忙しく、普段は走らない師匠さえも趨走<すうそう>することから「師趨<しすう>」と呼び、これが「師走<しはす>」になったとされています。師は法師(お坊さん)であるとし、法師が各家で経を読むために馳せ走る「師馳月<しはせつき>」であるとする説も一般的です。普段は落ち着き払ったお坊さん(禅師)も忙しさのために走り回る、ということからきた呼び名です。また「年果つる月<としはつるつき>」「為果つ月<しはつつき>」が「しはす」となったもので、「師走」は宛字とする説もあります。12月を師走とした一番古い文献は『日本書紀』の桓武天皇紀で「十有二月」と書いて「しわす」と読ませています。語源については『奥義抄』によると、12月は僧を迎えてお経を読ませるので、僧が東西に忙しく走り回ることから「師走り月」。又『類聚名物考』によると、春夏秋冬四季のおしまい、つまり「四季はつる月」からきているとしています。◆師走の異称◆旧暦では冬の終わりにあたるので、春待月<はるまちづき>・梅初月<うめはつづき>・極月<ごくげつ>・限月<かぎりのつき>・暮来月<くれこづき>・臘月<ろうげつ>・建丑月<けんちゅうげつ>・ 三冬月<みふゆつき>・厳月<げんげつ>・三冬月<さんとうげつ>・ 弟月<おとづき/おとうとづき> ・乙子月<おとごづき>・除月<じょげつ>・窮月<きゅうげつ> ・氷月<ひゅげつ> ・親子月<おやこづき>・ 暮来月<くれこづき> ・暮古月<くれこづき> ・年積月<としつみづき> ・限りの月<かぎりのつき> ・苦寒<くかん> ・晩冬<ばんとう> ◆旬の味◆魚介類:カキ、ナマコ、ハタハタ、鱈、金目鯛、ホッケ、フグ、ムツ、ワカサギ、タコ、アンコウ、ブリ、エビ、カニ、新のり 野菜・果物:白菜、しいたけ、かぶ、ごぼう、ウド、みつば、大根、ナメコ、ナガイモ、ニンジン、ネギ、白菜、ブロッコリー、玉ねぎ、ミカン、リンゴ、ユズ、だいだい◆季節の草花◆寒椿、水仙、枇杷、君子蘭、シクラメン、ポインセチア、寒牡丹、薮小路や千両、万両などの実~12月の行事~・祝日 天皇誕生日 (12/23) ・冬至 (12月22日)・クリスマス (12/25) ・大晦日 (12/31)年越し・・・「年越の大祓」当社では12月31日「年越の大祓」の神事を午後10時半より責任役員・総代参列のもと、執り行います。15日より、社殿向かって右側にある掲示板ところに例年通り「形代」をご用意致します。6月の「夏越の大祓」では今まで以上に非常に多くの方の形代をお預かり致しました。12月の「年越の大祓」も是非、神社に足をお運びになり、形代をお納め下さい。1年の穢れを形代に移して、神事にてお清め致します。清らかな心身で新年を迎えられますよう・・・。
2006年12月01日
全19件 (19件中 1-19件目)
1