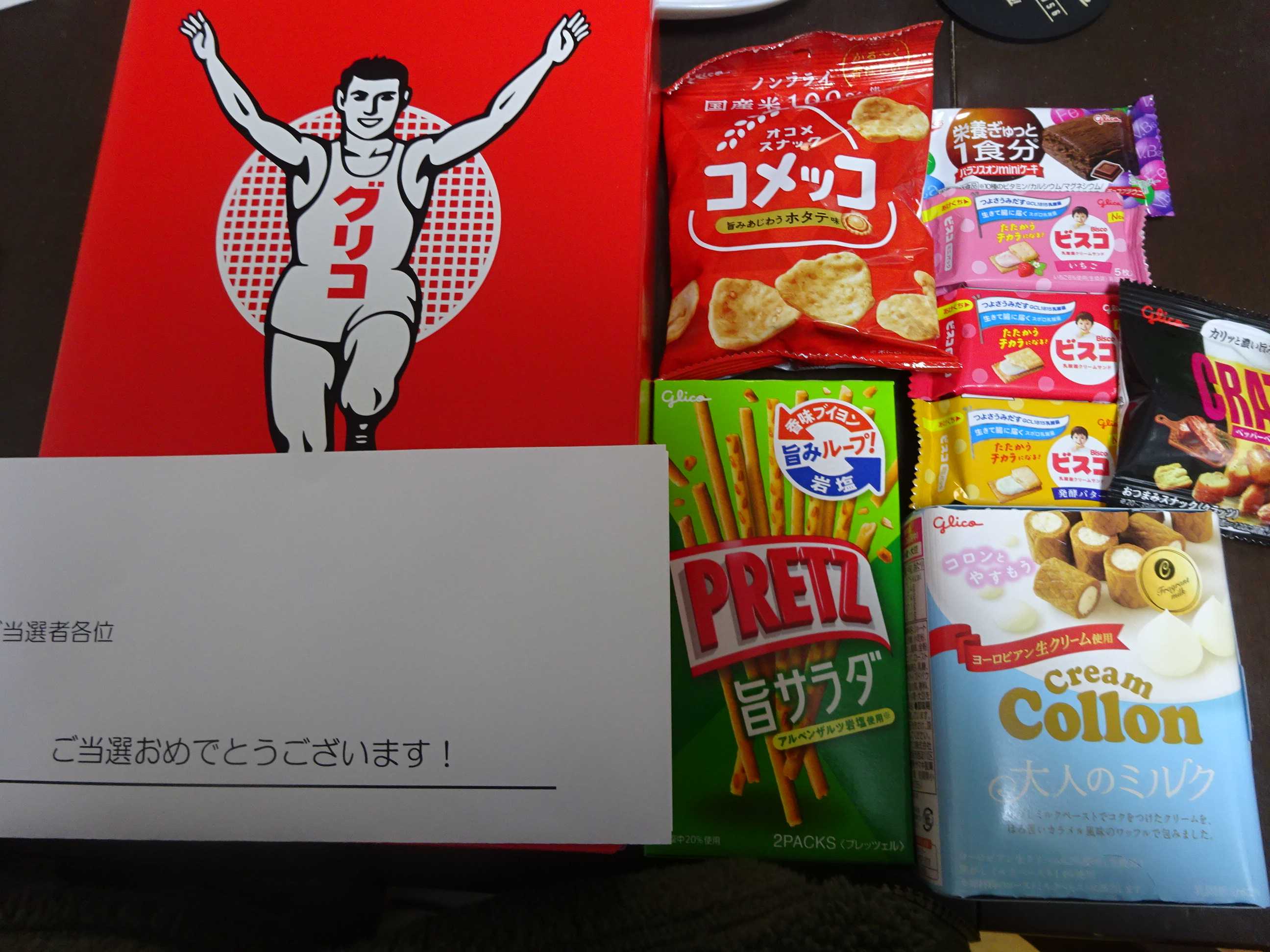2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年08月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
暦の種類
古くから人々が農業、漁業生活や社会生活を営むうえで、暦はなくてはならないものでした。今日は世界の暦の種類を大まかに御紹介致します。まず、「暦」とは・・・ 暦とは日を単位として、年・月・週などによって数える体系である「暦法」、それによって予知する事項を記載した「暦本(頒暦)」の両方をさします。~原始的暦法~主として生産活動にそって決められており、農業・漁業・採集・牧畜などの生活を営む上で必要な自然の移り変わりを目安にしています。気象や動植物などの気候的変化にもとづく自然暦が用いられます。原始的暦法には明確な暦法や連続性がなく、しばしば長期間の計算されない期間を含んでいます。(例)アイヌの暦、アメリカインディアンイロコイ族の暦 ~太陰暦~月(太陰)の満ち欠けによる周期的変化を基にした暦法です。1ヶ月を29日(小の月)あるいは30日(大の月)、1年を12ヶ月と定めています。太陽年と比べると1年で約11日ほど短くなります。(例)イスラム暦(ムハンマド暦・回教暦または回暦とも呼ばれます)~太陰太陽暦~太陰暦に太陽暦の要素(季節変化、二十四節気など)を取り入れて作られた暦法。日本において明治5年まで使用されていた暦もこの暦法によります。旧暦。(例)中国暦、バビロニア暦、ユダヤ暦、ギリシア暦、ヒンドゥー暦~太陽暦~地球が太陽の周りを一周する時間を一年の単位(一太陽年)とする暦法です。季節とのずれはありませんが、月の運行とは一致しない欠点があります。現在、世界の共通暦として用いられているグレゴリオ暦はこの暦法です。新暦。現行暦「グレゴリオ暦」は古代ローマ暦に起源をもち、エジプト暦の影響により太陽暦となり、それを修正したものです。(例)グレゴリオ暦、ユリウス暦、 エジプト暦、イラン暦、マヤ暦
2006年08月30日
-

夜の境内に・・・
社殿向かって左下に新しい竹垣が出来、その中にある最近剪定をした竹を眺めていた今夜・・・なんと、トンボを発見しました。そのトンボは一匹・・・他の竹にもいないかと目を凝らしてみると・・・ここには同じ竹に3匹もくっ付いていました。他の竹にもいるのでは?!と思い、見ていくと・・・なんと、沢山付いているではありませんか!!驚きました。昼間はトンボが沢山飛んでいるのを見かけますが、なんと、こんな場所でトンボが夜に寝ている(休んでいる?)なんて・・・。試しに一匹に手を伸ばすと、すぐに捕まえられました。やはり、寝ているような感じです。ほかの場所にももしかしたら・・・と思い、見てみれば・・・ 手水舎のそばにも・・・鳥居のそばの植木にも・・・榊の木にも至るところにとまっていたのです。本当に驚きました。トンボの種類も色々と見えて、ちょっと面白い発見でした。
2006年08月27日
-

竹垣が出来ました。
社殿左下の鉄柵を外し、竹垣を作成しておりましたが、完成致しました。しばらく、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びし、ご協力に感謝いたします。 → 以前の写真 現在の写真併せて行っております、参道の店舗内装改修工事はもうしばらく掛かりそうです。最近、暦の通り朝夕は凌ぎ易い気候になりつつあります。今日の朝方、ザ~っと夕立のような雨が降り、驚きました。現在も日差しは雲で遮られています。
2006年08月25日
-
処暑<しょしょ>
本日は処暑<しょしょ>。処暑は二十四節気の1つ。および今日から白露(9月8日)までの期間を指します。天文学的には太陽黄経が150度の時。丁度この頃は地球が太陽から一番遠い所に位置することもあって、15度動くのに16日掛かります。処暑の「処」の字には「とまる」とか「とどまる」という意味があるそうです。「暑さがまだ、停っている」という意味です。今日の新橋も予報以上に晴れて、暑い日となっております。江戸時代の『暦便覧』では、「陽気とどまりて、初めて退きやまむとすれば也」と説明しています。暑さが峠を越えて後退し始め、そろそろ涼風が吹き始める気配と暑さもなんとなくおきまる頃とされています。朝夕には次第に冷気が加わり、少しずつ過ごし易くなっていくのでしょう。実際には、立秋を迎えた時、これで暑さも峠を迎えたと早合点した人も少なくなかったでしょうが、一年の内で最高気温を出すのは立秋から処暑までが最も多く、処暑から次の白露までも暑さが厳しいようです。 綿の花、稲の花が咲き、稲が実りはじめ収穫も間近といった時期で、二百十日・二百二十日とともに台風襲来の特異日とされています。
2006年08月23日
-

竹垣の工事の様子
先日より、社殿左下の竹垣の工事のお知らせをしておりますが、現在の様子を画像でお伝えいたします。 → 社殿の右下側と同じ竹垣が写真のようにほぼ出来ております。もう少しかかりそうですので、ご了承下さい。お盆休み・夏休みもほぼ終わったのでしょうか。新橋にも沢山の人が帰っていらっしゃったようです。周辺のお店も平日でも先週はお休みが多かったのですが、今週は普段通りの営業をされているようです。お盆の期間はやはり参拝の方も少なかったのですが、今日は普段と変わらず、お仕事帰りの方々も多くお参りされていらっしゃいます。「お帰りなさい・・・」そんな気持ちになります。
2006年08月21日
-

境内の竹垣工事
社殿左下(竹を植えていたあたり)の黒い鉄柵を取り外してから、しばらく経ちました。コーンを使用して、土の部分に足が入らないようにしておりました。その為、皆様にはご迷惑をお掛け致しております。本日より新しい竹垣を作る作業をしております。また、竹垣が出来上がるまで、しばらくお時間を頂きます為、参拝の折にご迷惑をお掛けすると思いますが、どうかご了承下さい。→ 以前の様子 現在の工事の様子
2006年08月19日
-
夏の日
今日も新橋はカンカン照りのお天気です。昨日は急に雷雨があったりしましたが、雷雨の後も涼しさはありません。普通なら、雨が降れば気温が下がるのでしょうが、期待していた以上には下がらず、蒸し暑いままでした。アスファルトが日中に熱を持ち、それが持続して・・・雨の力でもその熱は下がりません。熱を持ったアスファルトの影響で、日のない夜でも気温が下がらないのです。そんな気候の中で、「土」の大切さや、植物や自然の大切さを実感してしまいます。アスファルトしかないーと言っても過言でないこの周辺に「土」のある生活をどうにか取り入れて欲しいと思ってしまいました。今日は境内参道の店舗の内装を少し綺麗にする工事が入っております。ご参拝の際、ご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご了承下さい。
2006年08月18日
-
終戦記念日の今日
~終戦記念日~昭和20(1945)年8月14日、政府はポツダム宣言を受諾し、翌15日の正午、昭和天皇による玉音放送によって日本が無条件降伏したことが国民に伝えられました。天皇が初めて肉声をラジオで公開し、敗戦と降伏を発表したという意味で、このラジオ放送は国民に大きな衝撃を与えました。この日をもって、アメリカとの戦争が事実上終了しました。内務省の発表によると戦死者は約212万人、空襲による死者は約24万人とされております。「戦歿者を追悼し平和を祈念する日」昭和38(1963)年5月14日の閣議決定により同年から8月15日に政府主催で「全国戦没者追悼式」が行われるようになり、昭和40(1965)年からは東京都千代田区の日本武道館で開催されました。昭和57(1982)年4月13日の閣議決定により「戦歿者を追悼し平和を祈念する日」と制定されました。この日に太平洋戦争における全戦没者に対して国を挙げて追悼の誠を捧げるとともに平和を祈念する為に設けられました。政府主催による「全国戦没者追悼式」が行われます。また、全国各地においても追悼式が行われます。終戦記念日はたまたまこれがお盆にあたることから、民俗学的に言えば、両者が混交して死者の魂を追憶し、供養すべき日として言わず語らずのうちに日本人の意識のなかに根付いています。戦没者の方々に追悼の念を捧げ、更なる世界平和を祈念いたします。
2006年08月15日
-

日差しの中の花
今日の新橋は大変日差しも強く、暑い一日でした。日差しが強くても、しおれず境内に夏の花が咲いていました。鮮やかで綺麗なオレンジ色の花です。
2006年08月14日
-

お盆について
今日は旧暦のお盆。全国的には旧暦でお盆の行事を行うところが多いです。「盆」は、もとは「非常な苦しみ」という意味の梵語「盂蘭盆会」を略したものです。「盆」の正式名称「盂蘭盆会」とは、インドのサンスクリット語の『ウラバンナ-逆さ吊り』を漢字で音写ししたもので、『逆さまに吊り下げられるような苦しみにあっている人を救い法要』と言う意味なのです。お釈迦様の弟子の一人、目連尊者が母を救う話に由来しています。古代インドから中国を経て、飛鳥時代に日本に伝わったと言われていますが、盆に先祖の霊がこの世に帰ってくるという考え方は日本独特のもので、日本の古代信仰や農耕行事と仏教が結びついたものだといわれています。わが国では、推古天皇の14年(606年)に、はじめてお盆の行事が行われたと伝えられています。「日本書紀」の中に、推古天皇14年に寺院で4月8日と7月15日に斎(とき 僧の食事)を設けたと出ています。4月8日はお釈迦さまの誕生日で花祭りの日です。7月15日は目蓮尊者が母親を救済した日です。この両日に、すでに推古天皇の時代、寺院の行事としての供養が行われていたことが、文献に残されているわけです。同じく「日本書記」には、斉明天皇の時代(657年)に飛鳥寺の西で孟蘭盆会が営まれたと記されています。当時は仏教が大いに台頭した時代であると同時に、日本古来の死者儀礼の伝統が生きている時代でした。死者の霊は、やはり近くの山の上にいてくれるか、あるいは自然と合体してくれていると考えられていました。その霊を迎える儀式が孟蘭盆会なのです。こうした考えは、次第に江戸時代以後、民衆の中に根をおろし、全国各地で盛んになっていきました。お盆の行事は、毎年7月13日から16日までの4日間にわたって行われます。現在では全国的には一か月遅れの8月13日から行うところが多く、月遅れのお盆というわけです。日本各地で行われるお盆の行事は、各地の風習などが加わったり、宗派による違いなどによってさまざまですが、一般的に先祖の霊が帰ってくると考えられています。日本のお盆行事は、違いはあるものの、家族や一族があつまりご先祖を供養し、亡くなられた人を偲び、今日ある自分をかえりみるという行事として行なわれることに違いはありません。仏教的行事の意味合いが強いですし、神道(神社)とは直接関わりがないように思われますが、日本古来の祖先を大事にする心、自分を省みる・・・古来の日本人の思想は神道的思考と通ずることが多いのではないかと思われます。「お盆」は家族や一族が集まり、故人の思い出を語り合うことは大変意義があり、千古の昔から変わらない日本独特の素晴らしい風習です。「お盆」には迎え火や送り火で、祖先が行き来する道筋を照らし、お盆の間は、供物や盆踊りなどで祖先の霊を慰めます。こうしたお盆の行事から、京都の「大文字焼き」や徳島の「阿波踊り」九州北部での「精霊流し」があります。 また、夏祭りのメインイベントの打ち上げ花火は元来、精霊送りの行事であったとされています。13日の夕方に迎え火を焚き、先祖の霊を迎えます。期間中には僧侶を招きお経や飲食の供養をします。16日の夕方、送り火を焚き、御先祖さまにお帰りいただきます。~「薮入り」について~農耕民族の習慣と仏教が混じり合った日本のお盆には、先祖の霊を慰め、秋の豊穣をお願いする気持ちが込められています。古くは一年に二回、8月16日と1月16日だけは、「薮入り」といって里帰りが許される習慣がありました。「薮入り」という言葉は奉公人が盆・正月に国許、親元に帰ることを言うのですが、丁稚さんと呼ばれる見習い期間中の奉公人は最初の三年間は薮入りをもらえなかったそうです。十に満たないあどけない子供のことですから、辛い丁稚奉公から解放され親元へ帰って、里心が付いたら駄目という配慮から薮入りを与えなかったとも言います。武家奉公の女中さんは一日か三日、あるいは七日の暇を許されました。また、転じて奥さん(嫁)が実家に帰る事も「薮入り」と言っていました。当時、「薮入り」以外は簡単に家に帰ることが出来ませんでした。このように、「薮入り」の嫁いだり働きに出て家を離れた人々も故郷に戻って来られるのが「お盆」の期間だったのです。レジャーなどない昔は、懐かしい家で日頃の垢を流し、幼なじみと盆踊りに興じてひとときの骨休めをしたのです。滅多に帰れないからこその「薮入り」で、今ではそのような制度や境遇の方がとても少なくなったのと、お盆休みを利用して旅行などに出掛けたりする人も増え、「薮入り」という言葉は日常会話に上らない言葉になってしまいました。
2006年08月13日
-

お天気と境内の自然
昨日は、台風一過で気持ちの良い晴天でした。暦の上では「秋」・・・秋の訪れを感じるような、涼しい夜でした。しかし、今朝はどんよりとした雲に覆われジメジメとした感じで、昼前から日が差し、大変蒸し暑い日となりました。そんなジメジメの暑い中、未だ境内の紫陽花は2輪となりましたが、咲いております。また、境内の竹の青々さで、涼しさを感じることが出来ます。暑くても、根付いた竹は、小さな芽を青々と茂らせ、日々成長しているようです。~お知らせ~社殿向かって、左下の黒い鉄柵を現在取り外しております。土の部分にお入りになりますと足下が汚れてしまう可能性がありますので、どうかお入りになりませんよう、お気を付け下さい。
2006年08月11日
-
立秋の今日
今日は「立秋」です。立秋は二十四節気の1つで秋の気配がたち始めるという意味のもの。また、この日から処暑までの期間のことをさします。暦の上ではこの日から立冬の前日までが秋です。まだ暑い盛りですが、朝夕には少しずつ秋めいて感じられる日が多くなってゆきます。天文学的にいうと、太陽黄経が135度のときで、「初めて秋の気配が表われてくるころ」とされています。七月節。秋は7月から9月までで、立秋(7月節気)、処暑(7月中気)、白露(8月節気)、秋分(8月中気)、寒露(9月節気)、霜降(9月中気)です。『暦便覧』では「初めて秋の気立つがゆゑなれば也」と説明しています。立秋は、暦の上では秋となるのですが、実際には「残暑」が厳しく、一年で最も暑い時期となります。また、昨日皆様に遅ればせながら「暑中お見舞い」を申し上げましたが、今日からは暑中見舞いではなく「残暑見舞い」を出すことになります。歌では・・・秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかされぬる 藤原敏行木の間よりもりくる月の影見れば心づくしの秋は来にけり よみ人しらず(『古今和歌集』)○秋の七草○ 萩・ 撫子・ 薄・ 女郎花・藤袴・ 葛・ 桔梗 立秋の今日は台風の影響で、現在の新橋は雨が降っています。台風は7・8・9号と今のところ3つの台風が発生しているようです。今後、特に上陸の可能性のある台風7号の接近に十分ご注意下さい。台風の概況はコチラをご覧下さい。
2006年08月08日
-

暑中お見舞い申し上げます
暑中お見舞い申し上げます本当に暑い毎日が続いております。皆様 体調にはくれぐれもご注意されご自愛のほどお祈り申し上げます。写真は今日お昼過ぎの新橋の空。飛行船が飛んでいたので、写真を撮ってみました。駅側の神社入口付近からの撮影です。
2006年08月07日
-

本日「土用の丑の日」
今日は、以前お話致しました、「土用」の「丑の日」です。実はすでに土用の丑の日は7月23日に「一の丑の日」がありました。一の丑の日(7月23日)は、今年は暦の関係で日曜日だったということで新橋周辺の鰻屋さんは休みが多いのもあり、鰻を焼く煙が立ち込める・・・ような風景は見えませんでした。が、8月に入り、本格的夏を迎えた今日の「二の丑の日」、そして新橋の街が一番賑う金曜日の今日は、鰻屋さんもお客様をお迎えする準備で大変なのではないかと思われます。「二の丑の日」とは、夏土用の期間に丑の日が2度ある場合、2度目を「二の丑の日」と言います。「二の丑の日」が暦によりあったり、無かったりしますが、大体「一の丑の日」の方が盛んなようです。今年は特別ですね。
2006年08月04日
-

8月 <葉月>
梅雨も明け、いよいよ夏本番!!八月一日です。新暦では夏の盛りの八月も旧暦では秋。月の異称や季語も秋を想像させます。代表的な異称「葉月」は、中国では月に生えると信じられていた桂の葉の月という意味があります。日本では、旧暦8月を葉月<はづき>と呼び、現在では新暦8月の別名としても用います。葉月の由来は諸説あり、以下の通りです。木の葉が紅葉して落ちる月「葉落ち月」「葉月」であるという説が有名。『年浪草』には「葉月とは、この月や粛殺の気生じ、百卉葉を落す。ゆえに葉落月という。今略して葉月と称す」と書かれています。他には、稲の穂が張る「穂張り月<ほはりづき>」という説や、雁が初めて来る「初来月<はつきづき>」という説、南方からの台風の襲来の多い月と言う意味で「南風月<はえづき>」という説などがあります。どれも、やはり今の8月のイメージとは約1ヶ月ほど早い秋を彷彿させます。○「葉月」の異名「建酉月<けんゆうづき>」・「壮月<そうげつ>」 ・「桂月<けいげつ>」・ 「素月<そげつ>」・ 「観月:かんげつ>」 ・「木染月<こぞめづき>」 ・「秋風月<あきかぜづき> 」・「月見月<つきみつき>」 ・「紅染月<べにそめづき>」・ 「雁来月<かりきづき>」・ 「燕去月<つばめさりづき>」・ 「草津月<くさつづき>」・「ささはなさ月」旧暦8月15日は仲秋の名月ということから月見月、観月、仲秋、等の異称があり、さらに深まり行く秋の月であることから、秋風月、木染月、萩月、燕去<つばめさり>月、雁来<はづ>月、唐<もろこし>月、壮<は>月などの別称が伺えます。○旬の味魚介:穴子<アナゴ>、スルメイカ、鰹<カツオ>、鰈<カレイ>、鱸<スズキ>、蛸<タコ>、鮑<アワビ>、ホヤ、秋刀魚<さんま>、ハゼ、いさき野菜と果物:枝豆、インゲン、カボチャ、ピーマン、トウガン、トウモロコシ、トマト、ナス、キュウリ、ゴボウ、山芋、スイカ、梨、桃○季節の草花○百日紅<さるすべり>、向日葵<ひまわり>、百日草、カンナ、白粉花<おしろいばな>、柳蘭<やなぎらん>、駒草、夕菅<ゆうすげ>、朝顔<あさがお>
2006年08月01日
全15件 (15件中 1-15件目)
1