2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年07月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

椿の実
社務所の玄関のあたりに、椿の木が植えてあります。以前は、たくさんの花を付けていました。この写真は春先の椿の写真です。これが・・・・ ↓その花の後に実が付きました。本当にたくさんの実が付いていて、驚きます。また、5月23日の記事で書いた、由緒書の横の鉢の花がまた咲いていました。日々何かと成長を見せる植物の変化を見ると、人も負けられないな・・・と思わせられます。
2006年07月31日
-
梅雨明けの今日
今日の新橋の日中は、今までのモワモワした暑く、湿気の多い空気ではなく、すきっとした爽やかな風が吹き、カラッとした空気で大変過ごし易い日でした。それもそのはず、関東甲信地方は6月9日梅雨入りしてから、今日30日午後、梅雨明けしたとみられると気象庁の発表があったそうです。31日以降とみられていた梅雨明けですが、梅雨前線の活動が次第に弱まり、晴れ間が急速に広がった為、今日の梅雨明けの発表としたそうです。梅雨明けの発表は関東甲信地方だけでなく、中国、近畿、東海、北陸の各地方で梅雨明けしたとみられるとのこと。今年の梅雨明けは、梅雨前線が停滞した為、平年に比べて北陸は8日、関東甲信、東海、中国は10日、近畿は11日遅く、昨年よりはいずれも12日遅く、梅雨明けしていないのは、東北だけとなったそうです。いよいよ夏、本番です。さて、今日は・・・「明治天皇祭」明治45(1912)年のこの日に崩御した明治天皇を記念して、大正2(1913)年から大正15(1926)年まで祭日になっていました。昭和2(1927)年からは、嘉永5(1852)年9月22日の明治天皇の誕生日を太陽暦に換算した11月3日が「明治節」という祭日になりました。今では11月3日は 「文化の日」(自由と平和を愛し、文化をすすめる日)として国民の祝日となっております。 「大正」の由来は中国の『易経』の「大いに享を正すをもって天の道なり」からとったものです。
2006年07月30日
-

常設の「幸運おみくじ」
「幸運おみくじ」をご用意してから2週間と少し経ちますが、たくさんの参拝者の方がお引きになっていらっしゃいます。当社は特に夜間の参拝者の方も多く、その為お賽銭箱の横におみくじ箱を設置し、常時お引き頂ける様にしております。ところで、神社では一般的におみくじは木に結び付けているのをよく見かけます。木々のみなぎる生命力にあやかり、願い事がしっかり結ばれますようにとの祈りを込めて、人々はおみくじを木の枝に結びますが、その結ぶという行為そのものに、私たちの祖先は神秘的な力を信じていたのです。そして、現在でもその伝統は生き続けています。神道では、「結び」の信仰があり、結び方によって実現を願ったり、心を鎮めたりします。おみくじを木に結ぶことも願いが結ばれるようにとの祈りを込めた民間の風習といえるでしょう。しかし、木におみくじを結び付けることは木を傷めることになりますし、境内の木々にやたらとおみくじを結ぴつけられては、景観がそこなわれることもあります。当社の「みくじ掛」は年始(正月)の何日間か授与しておりました、「心願色みくじ」の専用みくじ掛けがありますが、これは常時境内にはありません。ですので、お引きになった、おみくじは心願が達成するまで、おみくじに記されている教訓を戒める意味で待ち歩き、そののちに神社へお礼を込めて納めるのが最もよい方法とされておりますので、どうか大事にお持ち下さい。又、境内の木に結び付けられてましたおみくじは、取り外しお焚上げさせて頂きます。
2006年07月29日
-

久しぶりの太陽
今日は、大変夏らしい、日差しの強い日となりました。ここ最近は、雨が降ったり、降らなくても曇りの日が続いていたので、今日のようにお天気で太陽がギラギラした真夏の日差しを浴びたのは本当に久しぶりでした。境内に4月ごろ植えた、竹は根付き、大きく育っております。そして、今日は特に太陽の光を浴びて、大変美しく見えました。日を浴びて、竹の色も鮮やかで美しいです。また、社殿向かって左下の榊は何故か不思議な生え方で、枝が伸びていました。上に伸びています。太陽の日差しが恋しいのでしょうか?
2006年07月26日
-
「土用の丑の日」と「大暑」
先日、土用の入りのお話を致しましたが、今日はその土用の期間の「丑の日」です。今日は鰻屋さんが大変繁盛する日でもあります。今日はなぜこの「土用の丑の日」に「鰻」を食べるようになったかをお話致します。まず、復習。。。土用については・・・立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間のことでした。その中で十二支が「丑」の日を、「土用の丑の日」。今日がその日なのです。とくに夏の土用の丑の日が有名で、暑さを乗り切るために鰻を食べる習慣があります。ちなみに土用の丑の日に鰻を食べるようになったのは江戸時代のこととされております。夏の土用の時期は暑さが厳しく夏バテをしやすい時期ですから、昔から「精の付くもの」を食べる習慣があり、土用蜆、土用餅、土用卵などの言葉が今も残っています。また精の付くものとしては「ウナギ」も奈良時代頃から有名だったようで、土用ウナギという風に結びついたのでしょう。鰻を食べる習慣についての由来には諸説あります。・幕末の万能学者、蘭学者として有名な讃岐国出身平賀源内が、夏場に鰻が売れないので何とかしたいと近所の鰻屋に相談され、「本日丑の日」と書いた張り紙を張り出したところ、大繁盛したことがきっかけだという話。これが一般的なきっかけだと言われております。・江戸時代に発行された書物『江戸買物案内』の「う」の項目にでてくるお話です。文政年間(江戸時代後期 1820年代)の夏のこと。田和泉橋(かんだいずみばしどおり)の鰻屋春木屋善兵衛(はるきや ぜんべえ)のところに、殿様からかばやきの大量注文がありました。一日では作りきれないので、子の日と、丑の日と、寅の日の3日間かかってかばやきを作り、かめに入れて涼しい床下に保存しておきました。そして納品の日に出してみたところ、子の日と、寅の日に作ったうなぎはいたんでしまったが、丑の日に作った分だけは、悪くなってなかったのでおいしく食べることができたというお話。それ以来、この日に食べる鰻は美味しいとされ、次第に「土用の丑の日に、うなぎを食べるとよい」という風習になったと言われます。・万葉集には大伴家持が、夏痩せの友人に鰻を食べるように勧めている和歌が収められています。・丑の日の「う」からこの日に「うのつくもの」、例えば「うめぼし」「うどん」「ウリ」「牛」などを食べると病気にならないと言う迷信があり、「鰻」もこれに合致した食べものであったとも、「うし」の文字がウナギを連想させたためだとも言われております。「土用の丑の日」になぜ鰻を食べるようになったのかという諸説は紛々あるのですが一年で最も暑気が強く蒸し暑い気候の中、夏負けしないよう、猛暑から身を守るという庶民の知恵が生んだ産物と言えましょう。また、今日は最も暑い日とされる、大暑です。二十四節気の1つで、本日、および今日から立秋までの期間のことをいいます。太陽黄経が120度のときで、快晴が続き気温が上がり続けるころとされます。旧暦六月中気。暦便覧には「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」と記されています。夏の土用が大暑の数日前から始まり、大暑の間中続きます。小暑と大暑の一ヶ月間が暑中で、暑中見舞いはこの期間内に送るものとされております。東京は大暑とはいえ、今年は未だ梅雨で湿気の多い一日でした。カラッとした、夏のお天気になるのは予報ではまだ先になりそうです。
2006年07月23日
-

新橋こいち祭
昨日の新橋の街は予想以上に「こいち祭」は盛り上がっていました。一番心配だった雨も、祭りが終わる9:30くらいまでは、全く降る様子もなく、会場の駅前、桜田公園、駅周辺、勿論当社の境内も沢山の人で賑わっておりました。その様子を少し画像でご覧頂きたいと思います。 境内で行われた"JassinTokyo"さんのLIVEの様子です。 Jassと一緒に第一ホテルさんのオリジナル限定カクテルも好評でした。 駅前の通りでは、縁日が出ており、お子様がたくさん楽しみ、桜田公園内ではやぐらを囲んでの盆踊りが盛大に行われました。今日は今現在小降りの雨が降っております。メインイベントとなった、「浴衣美人コンテスト」の決勝は今夜7:30~9:00の予定です。新橋機関車広場の特設ステージが会場となります。
2006年07月21日
-
土用の入り
現在は、太陽黄経がそれぞれ27度、117度、207度、297度に達した日を土用の入りの日とし、立夏,立秋,立冬、立春の前日までを土用としています。・春の土用 : 黄経27度の点を通過する瞬間から立夏(45度)まで ・夏の土用 : 黄経117度の点を通過する瞬間から立秋(135度)まで ・秋の土用 : 黄経207度の点を通過する瞬間から立冬(225度)まで ・冬の土用 : 黄経297度の点を通過する瞬間から立春(315度)まで そのため、それぞれの土用の日数は必ずしも18日ではなく、19日のこともあります。今日はその夏の「土用の入り」の日に当たります。まとめると、「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間のことを指します。一般的に「土用」というと、「夏の土用」を指すことが多いです。その中で十二支が「丑」の日を、よく聞く「土用の丑の日」といいます。今年の夏の「土用丑の日」は大暑にあたる23日(日)になります。(丑の日の話は、又改めてお話致します。)本来は「土用」は春、夏、秋、冬の年4回あり、土用の丑の日は年に数回ある事になります。では、「土用」とはなんでしょうか。元々「土旺用事」と言ったものが省略されたものです。古来中国ではの五行説(陰陽五行説・・・中国の春秋戦国時代に発生した、陰陽説と五行説が結合した思想)では、天地間、世の中のの全てのものはすべて木火土金水の五つの要素からなり、その盛衰、消長などによって定まると考えます。五行説では、あらゆるものを木火土金水の五つに分類して当てはめる思想の為、今も昔も「四季」をこれに当てはめようとしましたが、「春を木」、「夏を火」、「秋を金」、「冬を水」に対応させたまではよかったのですが、「五季」とはなりえませんので、「土」が余ってしまいました。これでは都合が悪いので、「土の性質は全ての季節に均等に存在するだ!」とこじつけて、各季節の最後の18~19日を「土用」としました。つまり、春夏秋冬からそれぞれ終わりの約18日を削り、合計72日を土の分として割り当てることにしました。つまり、これが土用です。したがって土用は夏だけではなく、春、秋、冬にもあるのです。異なる季節と季節の間に「土用」を置くことで、消滅する古い季節とまだ、充分に成長していない新しい季節の性質を静かに交代させる働きをする時期だそうです。土用の入りの今日の新橋は不安定なお天気です。午前中は曇りでしたが、これから弱い雨が降る予報となっています。現在、新橋駅前では、すでに「こいち祭」が始まっており、夕方から夜にかけて各会場とも盛り上がりをみせるのですが、予報だけでいうと、生憎のお天気模様のようです。当社で2日間予定しております、JassinTokyoさんによる「JassLIVE」(無料)もテントを出して行う予定でおります。また、第一ホテルさんによる「カクテル」(\300-)の販売もされる予定でございます。本格的なJassLiveと本格的なカクテルを是非お楽しみ下さい。
2006年07月20日
-

海の日
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」「海の日」(7月第3月曜日)7月20日の「海の日」が祝日化したもの。2003年から7月第3月曜日に変更されました。 「海の日」とは、当初「海の記念日」として、海を知り、海運の重要性を広く国民に知ってもらうため、昭和16年に定められたものです。「海の記念日」は、明治天皇が明治9年(1876年)東北地方ご巡幸の帰途、それまでの軍艦ではなく灯台巡視の汽船(灯台視察船)である「明治丸」により航海をし、青森から函館を経て横浜にご安着された日が7月20日だったことから、昭和16年(1941年)に逓信大臣村田省蔵の提唱により制定され、以来海運、造船、港湾などの海事産業や船員等これらに従事する人々についてより理解を深めてもらう為に、全国各地でいろいろな行事が開催されてきました。「海の日」の前身は海運・海事関係者の間で、長年にわたり「海の記念日」として親しまれてきた、いわば業界内の祝日なのでした。島国海洋国の日本にとって海は生活・産業・文化等の関わりと海の重要性を考え、近年になって国民の祝日「海の日」を設けようとの国民運動が大いに盛り上がり、日本にとってかけがえのない海について理解を深めてもらうことを目的に、日本船主協会を始め海運・海事関係のさまざまな団体が続けてきた推進運動が実を結び、その結果、平成7年2月に国民の祝日に関する法律の一部改正が行われ、平成8年(1996年)から14番目の国民の祝日として7月20日は「海の日」と制定されました。
2006年07月17日
-

新橋の街「こいち祭」
昨日の記事で「新橋こいち祭」のことを少しご紹介いたしましたが、駅前をはじめ、新橋が「こいち祭」の雰囲気で盛り上がりつつあります。その様子を今日は写真で御紹介いたします。駅前のSLの前には大きな看板が立てられています桜田公園駅側入口からみた様子 街の中には小幟や提灯が付けられております。神社駅側の入口付近にも「烏森神社」と社名入りの提灯がさがりました。
2006年07月16日
-

新橋こいち祭
7月20日(木)・21日(金)と「新橋こいち祭」が今年も開催されます。詳しくはコチラをご覧下さい。このこいち祭の当社社名が入ったうちわが出来上がりました。このお祭は神社の祭礼とは直接関係ありませんが、新橋の街をあげてのお祭りです。今回で11回目のこいち祭は、毎年大勢の人たちで大変賑います。会場の駅前SL広場、櫻田公園などの屋台では、色々な種類の屋台が出てお祭気分を存分に味わえます。尚、当社境内では「JassinTokyo」さん主催のライブが予定されております。
2006年07月15日
-

幸運おみくじ
今まで当社の「おみくじ」はお正月の期間だけでした。その期間以外に、ご参拝の方からおみくじを引きたいとご要望がありましたので、今回お賽銭箱紆右横の掲示板あたりに「幸運おみくじ」をご用意致しました。「幸運おみくじ」初穂料300円おみくじの中に、「巾着」「クローバー」「貝」「馬」「鳩」「桃」「鍵」「扇」のどれか1つ、縁起物が納められております。初穂料はお賽銭箱にお入れいただき、ご自分でおみくじ箱から引いていただけるようになっております。掲示板左下にこの縁起物のご説明書きをご用意しておりますので、宜しければお持ち帰り下さい。尚、このおみくじ箱は常時置いてございます。当社は特に夜間の参拝の方が大変多いので、遅い時間に参拝されても、おみくじはお引きいただけます。
2006年07月13日
-
お中元と神様の関わり
現在行われている「お中元」の形が定着しはじめたのは明治30年代といわれております。1年の上半期の区切りの意味で、6月下旬から8月上旬までの間に、日頃お世話になっている方々に贈り物をするようになりました。さて、この「お中元」の由来を今日はお話致します。お中元の起源は古く、古代の中国にまでさかのぼります。古代中国の道教には天神(神様)を「三元」の日に祭るといった、「三官信仰」というものがありました。この三元とは陰暦の1月が「上元」、7月が「中元」、10月が「下元」の「三元」であり、それぞれの十五日に三官(の神様)が生まれたと言われております。~三官といわれる神様とは~天官(天神様):上元(1月15日)生まれの福をもたらす神様 地官(慈悲神様):中元(7月15日)生まれの善悪を見分けて人間の罪を許す神様 水官(水と火を防ぐ神様):下元(10月15日)生まれの水害など災害を防ぐ神様 お中元のもとになったのは、この三官のなかでも地官(慈悲神様)。7月15日に行われていた誕生を祝うお祭が、仏教の同じく7月15日の「盂蘭盆会」(お盆)の行事と結びついたことから、お中元が始まりました。中元は日本に伝わり、お盆の行事と混じり合い、親類や隣近所に仏様に供えるお供物を送る習慣ができたようです。そのため地方によっては、この「お中元」を、地方によっては「盆供」や「盆礼」と呼んでいるところもあるそうです。その後、江戸時代になってからは1年の半ばにあたる中元の7月15日に、1年を半期に分けて盆と暮とに区切り、先祖へのお供えと共に商い先やお世話になった人に贈り物をする習慣ができたようです。その頃から、庶民一般の贈答行事へ広まり、今では「お中元」と言えば「中元の贈答品」を指すようになりました。「お中元」は元々は「神様をお祀りする」意味があったのです。
2006年07月12日
-

「祓詞」の一節
~祓詞~「かけまくもかしこきいざなぎのおほかみ掛介麻久母畏伎伊邪那岐大神つくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらに筑紫乃日向乃橘小戸乃阿波岐原爾みそぎはらひへたまひしときになりませるはらへどのおほかみたち御禊祓閉給比志時爾生里坐世留祓戸乃大神等もろもろのまがごとつみけがれあらむをばはらひたまひこよめたまへともほすことを諸之禍事罪穢有良牟乎婆祓閉給比清米給閉登白須事乎きこしめせとかしこみかしこみもほす聞食世登恐美恐美母白須」これは神事には欠かせない「修祓<しゅばつ>」の際、奏上される祝詞「祓詞<はらえことば>」です。古事記の記述では「筑紫<つくし>の日向<ひむか>の橘<たちばな>の小戸<おど>の阿波岐原<あはぎはら>(日本書紀では檍原と記されている)に到り坐して、禊ぎ祓ひたまひき」とあります。妻である伊邪那美命<いざなみのみこと>を悲しみのあまり追って、黄泉<よみ>の国(死の世界)へ行く伊邪那岐命<いざなぎのみこと>は、そこで様々な恐ろしい目に遭い、黄泉の国のその穢れ(汚れ)を祓う為にこの場所で「禊祓<みそぎはらえ>」をした、と古事記のお話にあります。「筑紫」は九州全体をいい、「小戸」は水門を意味します。「橘」「小戸」「阿波岐原」「檍」は現在でも宮崎市内の地名として残っています。つまり・・・九州の(筑紫の)宮崎県の(日向の)宮崎市の(橘の小戸の)阿波岐原。阿波岐原はみそぎの発祥の地であるとされ、近くに実際、みそぎの池(御池)があります。この場所、この池で伊邪那岐命は禊祓をしたとされているのです。 ~禊池の写真~そこにある神社・・・江田神社(創建不詳)は、国産み神話で知られる伊邪那岐命、伊邪那美命の両神を祀ります。このような伝承が残っていて、実際にその場所が存在していたりすると、神話の時代のお話も身近に感じられることが出来ます。九州、特に宮崎は神話の多い地方ですから、歴史を辿れば神話と繋がる・・・といったことが多いかも知れません。非常に興味深い地方です。
2006年07月10日
-
形代神事の写真の掲示
昨日の夜より「形代神事」(当社:6月30日、港区支部:7月5日)の写真を少しですが、賽銭箱の右横の掲示板に掲示致しております。ご参拝の際、ご覧頂ければと思います。
2006年07月08日
-
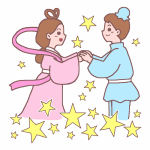
七夕
本日は「七夕」の日です。七夕は7月7日または8月7日に多く行われる祭です。五節句の一つにも数えられ、古くは、棚機とも表記し、今日一般的にたなばたと発音するのはその名残であります。元来中国での行事であったものが奈良時代に伝わり、もとからあった日本の棚織津女の伝説と合わさって生まれました。~七夕の起源~日本古来の豊作を祖霊に祈る祭(現在のお盆)に中国から伝来した乞巧奠などが習合したものと考えられています。もともと盆行事の一部が独立した行事として、行われるようになったと言われており、笹は精霊(祖先の霊)が宿る依代が起源だと考えられています。七夕は盆行事の一環として、祖先の霊をまつる前の禊の行事でありました。人里離れた水辺の機屋に神の嫁となるべき処女が神をまつって一夜を過ごして、翌日七夕送りをして穢れを神に託して持ち去ってもらう祓えの行事でありました。盆に先立つ、物忌みのための祓えでありました。また、畑作の収穫祭として七夕を迎えることも日本古来からの信仰でありました。この時代は麦を中心として粟・稗・芋・豆を主食としていた時代で、米中心の稲作より古く、日本固有の信仰として存在していました。麦の実りを祝い、キュウリやナスなどの成熟を神に感謝したのです。この祭りのとき、人々は神の乗り物としてキュウリの馬、ナスの牛を七夕に供えました。それがまた盆行事として習合して盆踊りになり、祖先の乗るキュウリの馬とナスの牛に引き継がれています。日本固有の畑作の収穫祭と盆迎えの祓えの信仰が中国の星や乞巧奠の風俗と混じり合って、現在のような七夕が成立したものと考えられます。青森の「ねぶた祭り」も七夕の変形と言われているようです。織女や牽牛という星の名称は 春秋戦国時代の『詩経』が初出とされています。七夕伝説は、漢の時代に編纂された『文選』の中の『古詩十九編』が文献として初出とされており、南北朝時代の『荊楚歳時記』、その他『史記』等の中にも記述があります。日本の棚機津女の伝説は『古事記』に記されており、村の災厄を除いてもらうため、水辺で神の衣を織り、神の一夜妻となるため機屋で神の降臨を待つ・・・「棚機津女」という巫女の伝説です。「たなばた」の語源はこの巫女に因みます。日本では奈良時代に節気の行事として宮中にて行われていました。また、万葉集では大伴家持の歌などに七夕に纏わる歌が存在します。万葉集で七夕は他に「織女」と書かれていますが、新古今和歌集では「七夕」となっています。このことから「七夕」の字は平安時代に当てられたものであることがわかります。~万葉集の中の七夕の歌~「織女し 船乗りすらし 真澄鏡 きよき月夜に 雲起ちわたる」大伴宿禰家持意味:七夕の夜、織姫が船でゆくのであろう。その透明な月夜に雲がわいている。これは家持の歌、有名な歌です。「天の川 楫の音聞こゆ 彦星と織女と今夜逢ふらしも」 詠み人知らず意味:天の川の船のかいの音が聞こえている。彦星と織姫が今宵会っているのだろうか。万葉の七夕の歌は、伝承そのものを歌っているものもありますが、それになぞらえて、なかなか会えない恋人たちの歌になっているものもあります。これも、作者が、だれかが恋人にこっそり会いにいくことを知っており、それを歌っているとも考えられます。万葉集には、この歌とよく似た、天の川を彦星が船で渡っている..という歌が百首近く入っています。なお、七夕は万葉集は棚機という字があてられています。「織女の五百機立てて織る布の秋さり衣誰れか取り見む」読み人知らず意味:織女が多くの機をたてて織った布でできた、秋用の衣を、いったいだれが見るのだろう。(それは彦星である)飛鳥・奈良時代は、歌を読む人々に中国の七夕伝説がそのままの形で広まっている様子がわかります。万葉集の七夕の歌は、その前の但し書きから、七夕の日に読んだようです。宮廷行事の歌合わせの席ででしょうか。この五百機という言葉は、江戸時代に歌集「五百機集」というので使われています。この歌からとったのでしょうか?七夕の行事は本来、宮中行事でありました。平安時代の宮中では熟瓜(うれうり)・梨・大角豆(ささげ)・茄子(なす)・桃・大豆・干鯛(ほしだい)・薄鮑(うすあわび)などの山海の産物をお供えし、梶の葉に古歌を書き、琴を飾って祈りました。織姫が織物などの女子の手習い事などに長けていたため、江戸時代に手習い事の願掛けとして一般庶民にも広がったようです。~織女星と牽牛星の伝説~こと座の1等星ベガは、中国・日本の七夕伝説では織姫星(織女星)として知られています。織姫は天帝の娘で、機織の上手な働き者の娘でありました。夏彦星(彦星、牽牛星)は、わし座のアルタイルです。夏彦もまた働き者であり、天帝は二人の結婚を認めました。めでたく夫婦となったが夫婦生活が楽しく、織姫は機を織らなくなり、夏彦は牛を追わなくなりました。このため天帝は怒り、2人を天の川を隔てて引き離したが、年に1度、7月7日だけ会うことを許されていました。しかし7月7日に雨が降ると天の川の水かさが増し、織姫は渡ることができず牽牛も彼女に会うことができないのです。その時は、二人を哀れんでどこからか無数のカササギがやってきて、天の川に自分の体で橋をかけてくれるといいます。中国や日本で使われていた太陰太陽暦では、必ず七夕には上弦の月となるので、これを船に見立てることもありました。~七夕の風習~祭は7月6日の夜、つまり7月7日の早朝に行います。殆どの神事は、「夜明けの晩」(厳密には午前1時)、つまり朝の前の夜に行うことが常であり、7月7日の夜明けの晩とは7月7日の早朝となります。午前1時頃には天頂付近に主要な星が上り、天の川、牽牛星、織女星の三つが最も見頃になる時間帯でもあります。全国的には、短冊に願い事を書き葉竹に飾ることが一般的に行われています。短冊などを笹に飾る風習は、江戸時代から始まったもので、日本以外では見られません。この時の笹を7月6日に飾り、さらに海岸地域では翌7日には海に流すことが一般的な風習であります。尚、楽曲の「たなばたさま」にある五色の短冊の五色は、五行説にあてはめた五色で、緑・紅・黄・白・黒をいいます。中国では五色の短冊ではなく、五色の糸をつるす。さらに、上記乞巧奠は技芸の上達を祈る祭であるために、短冊に書いてご利益のある願い事は芸事であるとされています。この他、各地に様々な風習が残っています。日本の伝統的行事である七夕は日本でこそメジャーですが、世界ではこのような星のお祭りは珍しいそうです。本日、境内には「七夕」の曲が流れております。
2006年07月07日
-

支部「形代神事」斎行~長野~
長野は朝から雨が降っており、予定しておりました諏訪大社春宮での「形代神事」は悪天候の為、場所を室内に移して、執り行いました。まず、神事の前に斎主・祭員以下(神事をご奉仕する神職)で、諏訪大社秋宮にご参拝致しました。雨の中の参拝でしたが、大変清々しい気持ちになれました。 さて、「形代神事」ですが、画像にてご覧頂きたいと思います。 皆様の形代はこの神事にて(再度・・・当社の神事)祓い、清め致しました。祭事は古式にのっとり厳粛に執り行い、滞りなく斎行申し上げました。多くの皆様からお預かりいたしました形代は支部の神職がお焚上げを致します。次の大祓神事は12月31日の「年越の大祓」です。
2006年07月05日
-

明日・・・
各地では大雨の被害などもニュースで取り上げられていますが、今日の東京は梅雨とは思えないほど日差しの強い夏のようなお天気です。5月頃、新芽が出始めた境内の榊も太陽の光と雨の恵みを受け、すっかり大きくなり、普通の葉の色になりました。 新芽の時の様子明日は東京都神社庁港区支部・港区支部青年会・港区神社総代会の行事である「形代神事」を諏訪大社春宮にて執り行う予定(天候により場所は変更になる場合があります)でございます。6月15日から30日まで、非常に多くの方々の形代をお預かりしておりますが、それを持って行き、港区のほかの神社でも納められた形代と一緒に、神事とお焚き上げを致します。神事は当社禰宜もご奉仕する予定でおります。その様子なども含め、出来ましたら画像なども添え、後日UP致したいと思います。
2006年07月04日
-

半夏生<はんげしょう>
半夏生は雑節の一つで、半夏(烏柄杓)という薬草(半化粧という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているようになるころとも)が生えるころの時期のことです。「ハンゲ」はサトイモ科カラスビシャク半夏とは漢方の名前で量次第ではつわりや咳止めの薬になるのですが、これは実は毒草です。七十二候の一つ「半夏生」から作られた暦日で、かつては夏至から数えて11日目としていたが、現在では天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっています。毎年7月2日頃にあたります。春分の日から数えるとおおよそ100日目、夏至から11日目。(太陽暦では7月2日頃で、この日から5日間を言います)農家にとっては大事な節目の日で、この日までに農作業を終え、この日から5日間は休みとする地方もある程です。半夏作ともいい、田植えの目標の日とされていました。この日は昔から天から毒気が降ると言われ、井戸に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりしました。関西ではこの日に蛸を、讃岐では饂飩を食べる習慣があります。この頃に降る雨を「半夏雨」といい、大雨になることが多いです。・・・今日の東京は午後から雨でした。。。ところで、半夏生に関西ではなぜタコを食べるのでしょう?農村では、半夏の天候によって豊作になるか凶作になるかを占ったり、麦の収穫祭をおこなうなど、農業にとって大切な目安の日です。関西地方では、田に植えた稲の苗がたこの足のように大地にしっかりと豊作になるようにとの願いから、たこを食べる習慣があって、甘露煮、柔らか煮、酢だこ、天ぷらなどが作られます。ただし、たこを食べる習慣も、ところによってかわります。また、饂飩についてはどうでしょう?この時期が麦秋、麦の刈り入れ時期にあたることから畑作の祝い日とする地方もありました。新麦を神に供え混鈍を食べる習わしがありました。混鈍は麦の粉に肉やあんなどを入れて丸めて蒸したもの、うどんの前身です。かくして、半夏生の日にどんが食べられるようになりました。また、讃岐うどんで有名な香川県の農家では、農繁期が一段落する半夏生の日(この頃)に日頃の労をねぎらい、うどんを作って食べる風習がありました。その習わしにちなんで、この半夏生の日を、県生麺組合が「さぬきうどんの日」に制定し行事などを行っているそうです。今現在、残っている慣わしや風習は、何かしら農業と深い関わりがもたれているのが良く分かります。
2006年07月02日
-
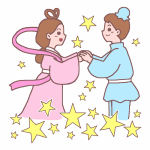
7月 <文月>
旧暦7月を文月と呼び、現在では新暦7月の別名としても用いています。文月の由来は、旧暦の7月は稲の穂がふくらみ始める季節なので、「含月」「穂含み月」・同じく、旧暦の話ですが、稲の穂の膨らみを見る月であることから「穂見月」さらに、七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝す風習があるからというのが今の定説となっていますが、詩を書いた文を供える月であったことから「文披月」ただ、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもので、元々日本にはないものであることより、農業(稲作)の前説が相応しいのではないかと思われます。○「文月」の異名○文月以外に、次のような異名があります。秋が始まる月であることから「秋初月」、七夕の月であることから「七夜月」・「棚機月」、七夕を愛でる月であることから「愛逢月」また、女郎花の花が咲く月であることから「女郎花月」、蘭月などの呼び名があります。○旬の味○魚介:鰻(うなぎ)、烏賊(いか)、鱚(きす)、泥鰌(どじょう)、太刀魚(たちうお)、蜆(しじみ)、鮑(あわび)、鱧(はも)、穴子、鮎(あゆ)、カワハギ、キビナゴ、蛸(たこ)、雲丹(うに)、鯒(こち)、野菜と果物:オクラ、茗荷(みょうが)、ししとう、枝豆、スイカ、メロン、なす、紫蘇、ピーマン、苦瓜(にがうり)、とまと、冬瓜(とうがん)、きゅうり、ししとうがらし、モロヘイヤ、レタス、ブルーベリー、杏(あんず)○季節の草花○花:睡蓮(すいれん)、撫子(なでしこ)、桔梗(ききょう)、露草、昼顔、さぎ草、ほおずき、山百合、夏椿、ムクゲ ○7日は七夕○夜空では7月に入ると夏の大三角形が天頂に上ってきます。わし座のアルタイル、こと座のべガ、はくちょう座のデネブです。アルタイルとべガは天の川を挟んであります。この星はご存知の通り彦星と、織姫の星です。7月7日は七夕ですが、梅雨の真っ最中でなかなかこの星を見る事ができません。8月の旧暦の七夕の方が星見には適しているのでしょう。今年の7月7日の夜空はどうなるでしょう・・・。
2006年07月01日
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 11/24発売♪バニラビーンズ 切れはし…
- (2025-11-24 11:41:32)
-
-
-
- ひとり言・・?
- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…
- (2025-11-22 22:12:52)
-
-
-

- 政治について
- 集団ストーカー・テクノロジー犯罪の…
- (2025-11-24 13:16:06)
-






