2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年11月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

ライトアップ
当社は夜間の参拝の方も多くいらっしゃるので、社殿内も夜遅くまで、境内は出来るだけ明るくするよう努めております。さて、社殿下の左右にある竹ですが、向かって左側だけを試験的にですが、下からのライトアップをしております。
2006年11月29日
-
新年のご祈祷のご予約
新年のご祈祷(社運隆昌・災禍消除・事業発展・工事安全・・・等々)の申し込みを受け付けております。社務所まで直接お申し込みにいらっしゃって頂くか、お電話にて日時等のご希望・ご予約を承っております(FAXでの申込用紙をご用意しております)。今年も1月4日(木)と5日(金)が会社初めの企業が多く、両日、比較的午前中はすでにご予約が多く入っております。ご祈祷がお決まりの際は、ご予約はお早目にお勧めいたします。当社のご祈祷は、一社ずつ行っております。(但し、社殿が狭いため、着席される場合40名程度が目いっぱいです。それ以上の会社・企業のご祈祷は御起立または社殿の外に出てしまう場合もございます。ご了承下さい。)授与品は天照皇大神宮の御神札(神宮大麻)、当社の御神札(祈願と社名をお書きしたもの)・・・こちらは神棚用の紙の御神札と神棚に入れない場合の木の御神札の2種類ご用意しております、正月限定授与の開運御守、お供物です。新しき年を向かえ、清々しい気持ちで、ご祈祷を受けられ、会社の社運隆昌をお祈りしましょう。
2006年11月27日
-

勤労感謝の日・新嘗祭について
本日は勤労感謝の日、国民の祝日です。「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日」として昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日です。戦前はこの日が祝祭日の「新嘗祭」(宮中では天皇が新しい米などを神殿に供えた祭事)が、戦後に「勤労感謝の日」として国民の祝日になりました。新嘗祭は、五穀の収穫を神に感謝する祭礼で、「しんじょうさい」ともいわれます。新嘗祭の「新」は新穀を、「嘗」はご馳走または食べるを意味します。宮中では天皇が新穀を神々にお供えし、自らも召し上がります。『古事記』に天照大御神が新嘗祭を行った記述がみられるように、たいへん起源の古い祭礼です。古来、農業を産業基盤とする日本では、春のはじめに「祈年祭」で五穀の豊穣を祈願し、「神嘗祭」で初穂(新米)を最初に神々に捧げ、収穫を終えて「新嘗祭」で神々に感謝を捧げました。ここで「神嘗祭」と「新嘗祭」の違いを考えてみましょう。新嘗祭に先だって、これによく似た神事である「神嘗祭」という行事があります。こちらも戦前は祭日でした。神嘗祭は皇祖である天照大神を祀る伊勢神宮に天皇が幣帛を捧げ、宮中からこれを遙拝する儀式です。神嘗祭は伊勢神宮で行われ、10月15~16日(外宮)、16~17日(内宮)でその年に収穫された穀物や酒などを天照大神に供えます。「新嘗祭」はこの「神嘗祭」からおよそ一ヶ月遅れて行われます。内容は重複する部分が多いのですがよく考えると違いもあります。それは神嘗祭が「神に供える」だけなのに対して、新嘗祭は「神を祀り、自らも食す」という点です。神嘗祭は感謝を申し上げるだけですが、新嘗祭は感謝し、その新穀の生命力・霊力を天皇自らが食し、体内に入れる儀式も兼ねています。明治6年(1873年)から昭和22年(1947年)までは「新嘗祭」の祭日とされておりました。天皇が新穀を天神地祇(天上の神様・地上の神様)に勧め、また、親しくこれを食する祭儀です。明治5年までは旧暦11月の2回目の卯の日に行われていました。明治6年から太陽暦が導入されましたが、そのままでは新嘗祭が翌年1月になることもあって都合が悪いということで、新暦11月の2回目の卯の日に行うこととし、明治6年ではそれが11月23日でした。翌明治7年には前年と同じ11月23日に行われ、以降11月23日に固定して行われるようになったのです。戦後は皇室典範からこの儀式は除外されましたが、法的にはこの儀式を行う必要はなくなっても、皇室においては重要な宮中行事として継続されています。皇室での儀式は、23日の夕方から始まり翌日の未明まで行われます。また、各地の神社での新穀感謝の祭事は続いております。当社「新嘗祭」は18日に斎行申し上げました。
2006年11月23日
-
小雪
小雪(しょうせつ)は二十四節気の1つです。11月22日頃、および、この日から大雪までの期間を言います。天文学的に言うと、太陽黄経が240度のときで、僅かながら雪が降り始めるころ。木枯らしが吹きはじめ、各地でみぞれが降り、やがて雪に変わります。火の気が恋しく感じられる。小雪とは、冬とは言え、まだ雪はさほど多くないという意味です。十月中。『暦便覧』では、「冷ゆるが故に雨も雪と也てくだるが故也」と説明しています。
2006年11月22日
-

新橋機関車広場の機関車
新橋のシンボルとでも言えましょう、新橋西口・日比谷口の機関車広場にある、「機関車」の塗装も終わり、綺麗になった様子です。 今までの塗装は普通のペンキ塗装だったそうですが、今回は機関車専門の塗装を施したそうです。
2006年11月20日
-

新嘗祭斎行
18日午後一時より、責任役員・総代参列のもと、平成18年度 烏森神社新嘗祭を執り行いました。 お供えしておりました白濁酒は神酒拝戴の際、参列者の方にお飲み頂きました。また、お供えしております「稲穂」は来年度(平成19年度)の正月に授与される「開運御守」に付けられる為、神事後本殿にしばらくあげております。(平成十八年度のもの)
2006年11月19日
-

新嘗祭
ポールを設置し、今日始めて国旗掲揚を致しております。新嘗祭は1時より斎行致します。
2006年11月18日
-

明日の祭事 「新嘗祭」
明日午後1時より、責任役員・総代参列のもと、「新嘗祭」を斎行致します。「新嘗祭」とは今年の五穀豊穣を感謝申し上げるお祭りです。今年収穫された米で作った「濁酒」をお供えし、新年(正月)に授与致します「開運のお守り」につける今年収穫された「稲穂」をお供えします。また、港区支部で「御田植え祭」「抜穂祭」を行いました「稲穂」もお供えいたします。祭事の様子などは、日曜にUPする予定でございます。去年の新嘗祭の様子はこちらをご覧下さい。
2006年11月17日
-

社殿前にポールを設置
社殿前左右にポールを設置いたしました。これは、国旗や社名旗を揚げる為のポールです。新橋は爽やかな感じの天気、空が綺麗な午前中となりました。
2006年11月15日
-

ブログ開設1周年!!
早いもので、この烏森神社HP兼ブログを開設して、早1年が経ちました!!普通のHPと違って、更新しなければならない→逆に更新することで、日々の様子等をタイムリーにお伝え、発信出来るということで、ブログ形式のHPとさせて頂きました。この1年、神社の祭事・行事、お知らせはもとより、境内の様子・季節のお話などで更新して参りました。「いつも更新を楽しみにしているよ」と言うお声を、氏子さんや崇敬者の方から頂いたり、毎日アクセス数が伸びたり・・・本当に嬉しい限りです。励ましのお言葉、ありがとうございます。また、アクセスしてお読み頂いている皆様に感謝いたします。今後ともこの場を通して、皆様に「烏森神社」をもっと知って頂けるよう、神社・神道を身近に感じ、興味をお持ち頂けるよう、努力して参りますので、宜しくお願い致します。
2006年11月13日
-

木枯らし1号
今日は朝から晴天の青空かと思いきや、日中は気温がそれ程上がらず、昨夜からの強い風も止まないままの、肌寒い一日となりました。今日は空に寒気が入り、札幌や青森、東日本の軽井沢や松本でも「初雪」を観測しました。そして、関東地方では、木枯らし1号が吹きました。ちなみに「木枯らし1号」とは・・・木枯らしとは、日本において晩秋から初冬の間に吹く、風速8m/s以上の北寄り(北から西北西)の風のことで、冬型の気圧配置になったことを示す現象のこと。凩とも表記します。この風速8m/s以上の北寄りの風が晩秋の今日、今年初めて吹いた→1号と言う訳です。境内の七五三の幟も、パタパタと翻り、風の強い一日でしたが、昨日の用に雨ではなかったので、七五三の参拝者の方も一安心されていらっしゃいました。明日は風も収まり、朝から穏やかに晴れる見込みだそうです。但し、気温差が大変大きいようです。日中は今日より3℃から6℃ぐらい高めで、ポカポカ陽気の予報ですが、朝の気温は10℃を下回る所が多く、冷え込みはかなり厳しくなりそうです。風邪をひかない様にご注意下さい。
2006年11月12日
-
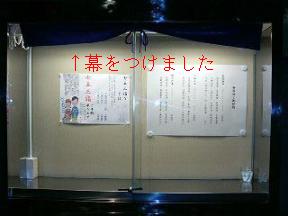
境内のこと
皆様のご協力により、工事も進んでおります。今日は、先日、設置いたしました箱型「掲示板」に幕をつけました。写真では少し分かりづらいですがUP致します。 ~現在の状態~ ~設置当日の様子~また、水道管の工事も無事終了し、この掲示板横の手水も出るようになりました。今日は社務所前の榊の木に、久しぶりにメジロがやってきました。そう言えば、榊の実も熟れてきております。可愛い声で、鳴いていました。
2006年11月10日
-

社殿前に幕
本日より、境内の本格的工事が行われております。社殿前には、「幕」が付けられました。左が烏の社紋で、右が左三つ巴の社紋の幕です。幕広く長く縫い合わせて、 物の隔て、または装飾として用いるもの。
2006年11月09日
-

七五三についてのお話
男女児とも三歳を髪置、男児五歳を袴着、女児七歳を帯解の祝として、いずれも11月15日産土神に参詣する行事。今日は七五三詣りの元になったお祝い事、「髪置」と「袴着」「帯解」をご説明致します。もともと、歳祝いの儀式が七五三詣りに由来しているのです。「髪置の祝」は現在では、男女とも3才の11月15日に行われています。11月は一陽来福の月であり、15日は満月の日であるといわれます。髪置きの親として両親から子孫繁盛であり寿命長き目出度き人を依頼します。この髪置というのは胎髪を取り(それまで、剃って短いままだった髪を)この日より髪を伸ばし始める儀式を行うものです。髪置きの親は鋏を取り左の鬢を三度、右の鬢を三度、中の鬢を三度、挟むまねをし、(女子の場合には右から始めます。)綿を額より後ろに撫でかけて、熨斗と共に水引で結びます。綿を白髪に見立てて、小児の長寿を祈願したものです。子どもが将来白髪頭になるまで長生きするようにという祈りを込めて、白髪に見立てた綿帽子を子どもの頭に載せる行事が、「髪置」です。「袴着」は古くは男子7歳のとき着初めといいましたが、現在では5歳の年に行われています。因みの親には子孫繁昌にして、寿命長久な人を頼み、袴の腰をあてさせ、紐を結んだものです。小人は紐付きの着物で出て碁盤に乗り吉方に向かい、紋服等に着替え角帯を締め袴をはかせます。袴は因みの親が腰をあてさせ、紐を結びます。この日から、自分で袴を穿けるようになるというけじめの儀式です。「袴」という大人が公の場で身につける衣服を男児が着用すると言うことで、現代では少し早い気もしますが、男として社会の一員としての自覚を持ってもらうという儀式です。 「帯直し」は女子7歳の11月15日に行います。つけ紐を除いて帯をする所から帯解きの祝いともいわれます。帯親には目出度い女の人を頼みます。帯は帯の親より贈られる、白地一筋、紅梅一筋または色は好みの物二筋、模様は宝づくし、鶴亀等のお目出度い物を縫い織りにし、常の帯より細くし(厚板の付け帯とくけ帯とする)たものです。帯の親は小人に小袖を着せ、帯を取り二重回して後ろで両締めに結びます。この日から一人で帯が結べるようになっていくというけじめの儀式です。帯は「魂をその内にしっかりととどめおく」ものだそうで、帯を締めることによって、身を持ち崩すことのないようにと言う願いを込めるものとか。以上、これらの習慣が一つになったのが七五三です。江戸時代に呉服屋がこの3つの行事を1つにまとめたのがきっかけとも言われています。また、「7つ前は神の子」といわれ、昔は医療・衛生的に子供の成長が困難だった時代、大人になる子供は幸福とされていました。7歳までは成長が不安定とされていたのです。その為、7つまでは神様がその子供の運命を決めるものと考えられており、子供の成長を無事に神様にお祈りするという気持ちがこの七五三詣りの1番の起源と言えるでしょう。では、何故11月15日なのでしょう。元は、11月の吉日を選んで七五三の行事が行われており、「11月15日」と決まっていたわけではないのです。日付が現在のように固定されてきたのは江戸時代の中頃のこと。三代将軍家光が、後の五代将軍綱吉(幼名徳松)の病弱であることを心配し、これの無事成長を祈るために、袴着の儀式を執り行ったのが11月15日だったのです。庶民もやがてこれにならい現在のように11月の15日に歳祝いを行うようになったそうです。また、11月15日は旧暦では満月であり、二十八宿の鬼宿日で、どんな祝い事にも最高の日とされることから、この日に祝われるようになったといわれています。最近ではご家族のご都合により、七五三に近い、土日が1番多くお詣りがございます。当社では七五三詣りのお子様に授与品の1つとして、「子供守り」を授与しております。
2006年11月06日
-

御祭神の御利益の掲示
先日完成したばかりの、手水舎横の箱型の掲示板には、御祭神の御利益の掲示をしております。烏森神社でお祀りしている、「倉稲魂命・天鈿女命・瓊々杵尊」の三柱の神様の御利益を神様ごとに掲示しておりますので、ご参拝の際、ご覧下さい。工事は休日に行っておりませんので、ゆっくり目の進行です。完成にはしばらく時間が掛かりそうです。ご参拝の際には、足元や景観が悪く、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、どうかご理解とご協力をお願い申し上げます。
2006年11月05日
-

「文化の日」
今日は『文化の日』祝日です。1946年のこの日、平和と文化を強調した日本国憲法が公布されたことを記念し、昭和23年(1948年)に「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として国民の祝日に制定されました。(日本国憲法施行日の5月3日は「憲法記念日」の祝日になりました。) 天長節(「明治節」)明治6年(1873年)から明治44年(1911年)までの祝日。 明治天皇の誕生日。明治5年(1872年)までは9月22日に行われていましたが、明治6年(1873年)の太陽暦の採用にともない、9月22日を太陽暦に換算した11月3日に変更されました。明治45(1912年)年7月30日の明治天皇の崩御に伴い廃止され、昭和に入ってから「明治節」として復活しました。 明治節明治時代の天長節のこと。11月3日は明治天皇の誕生日で、戦前は四代節のひとつ「明治節」という祝日でした。明治天皇と皇后の昭憲皇太后を祭神とする明治神宮では、11月3日に例祭(秋の大祭)が執り行われます。また、宮中(皇居)では本日「文化勲章の授与式」(文化の発展に功労のあった人々に文化勲章が授与される式)が行われます。文化勲章は昭和12年(1937年)に制定され、紀元節(2月11日)、天長節(4月29日)などに表彰式が行われてきましたが、戦後の昭和23年以降は、11月3日の文化の日に贈られることになりました。ほかに文化功労者および各種褒章の受賞者の伝達式などが行われます。また、この日を中心に文化庁主催による芸術祭が開催されます。またこの日は晴天になる確率が高く、「晴れの特異日」として有名です。やはり、今日も大変良いお天気でした。11月の祝日・休日は特に七五三でのご参拝の方がいらっしゃることが多いのですが、今日のようなお天気であることをお祈りしております。
2006年11月03日
-

「雨どい」と「箱型掲示板」
お知らせいたしました「雨どい」と箱型の「掲示板」ですが、境内修繕(水道管)工事などの途中ですが、雨どいと掲示板だけは完成致しましたので、画像をUP致します。境内での工事・作業が続いております。ご参拝の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、どうかご理解とご協力をお願い申し上げます。
2006年11月02日
-

11月 <霜月>
立冬を迎え、暦の上では冬となります。七五三や酉の市で華やぐ中、紅葉から落葉の季節となり、寒い地方には冬将軍が訪れます。コートを羽織る季節となり、風邪もひきやすくなりますので、ご注意下さい。立冬を過ぎると白鳥が渡りはじめ、冬は駆け足でやってきます。日本では、旧暦11月を霜月と呼び、現在では新暦11月の別名としても用います。「霜月」は文字通り霜が降る月の意味です。他に、「食物月」の略であるとする説や、「凋む月」「末つ月」が訛ったものとする説もあります。◆霜月の異称◆10月に出雲に出向いた神々が戻ってくることから「神帰月」。旧暦では真冬であるために「雪待月」・「雪見月」他に・・・「神楽月」・「子月」・「建子月」・「暢月」・「子月}・「達月」・「辜月」・「葭月」・「復月」・「章月」・「霜降月」・「霜見月」・「天正月」・「竜潜月」・「露隠端月」・「黄鐘」・「星紀」・「仲の冬」・「仲冬」 ~11月の行事~11月3日 - 文化の日(日本)11月15日 - 七五三(日本) 11月23日 - 勤労感謝の日(日本)当社では11月18日(土) 責任役員・総代参列のもと、新嘗祭を斎行致します。 ◆旬の味◆魚介類:かます、かれい、金目鯛、わかさぎ、むつ、ふぐ、あさり、あおやぎ、ほっけ、アマダイ、イクラ、カニ、カキ野菜・果物:ほうれんそう、にんじん、三つ葉、白菜、しいたけ、なめこ、カリフラワー、かぶ、里芋、レンコン、舞茸、銀杏、みかん、りんご、きんかん、柿、花梨、かぼず、密柑、キウイ◆季節の草花◆背高泡立草、山茶花、柊、磯菊、りんどう、石蕗、菊
2006年11月01日
全18件 (18件中 1-18件目)
1









