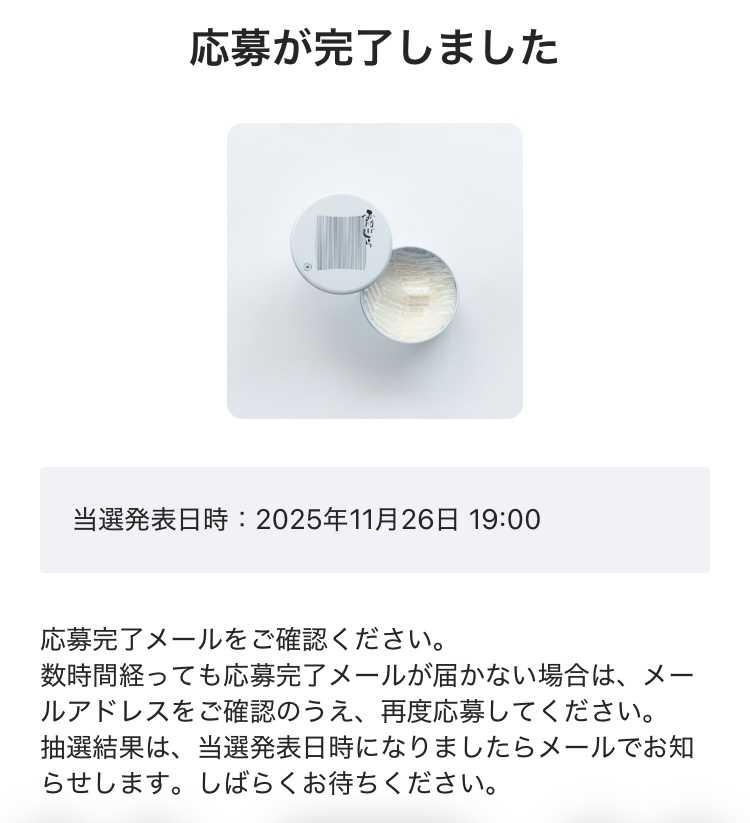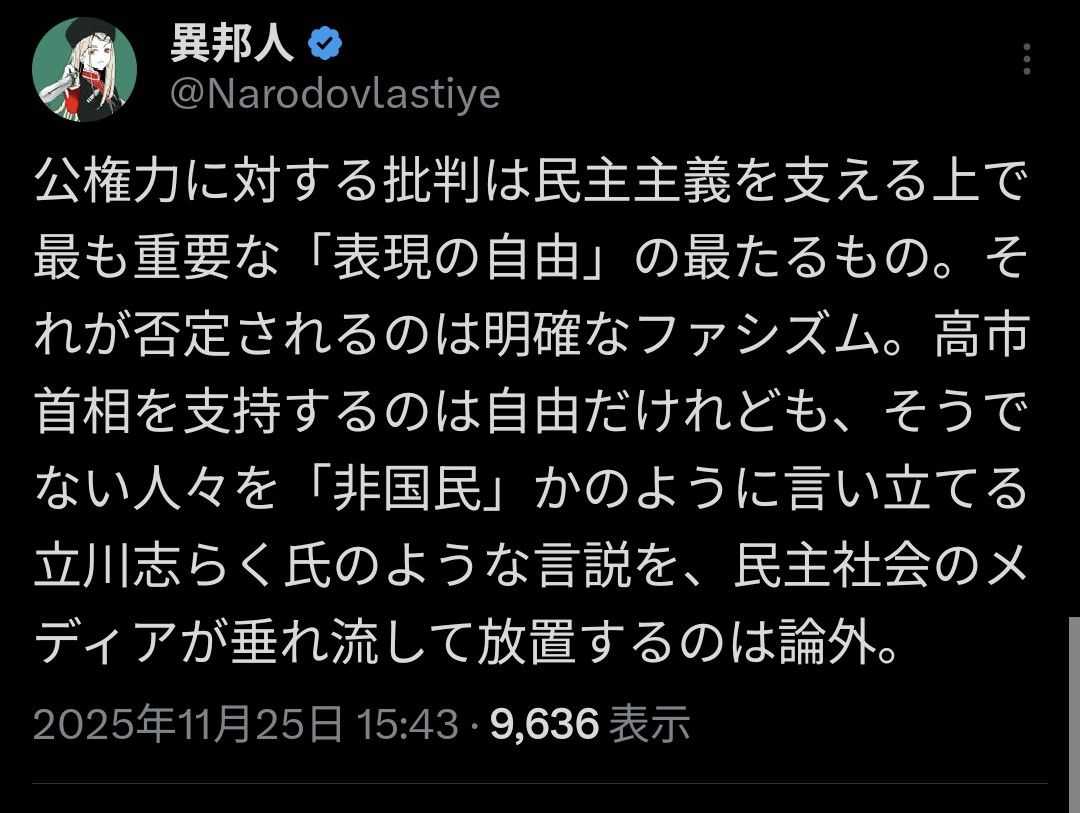2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年09月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
生涯で一番の運動会 の巻
土曜日の朝、車で仕事場に向かっていると、体操服のお子さんを後に乗せた自転車が数台走っています。マリア様の像が屋根についている修道院付属の幼稚園の運動会のようです。いつものかわいらしい制服ではなくて、体操服に赤白帽です。幼稚園の前に来ると、何台も車が止まっていて先生が迎えています。「駐車場はこちら」とか「自転車はここから」とか書いた手製の看板を持ったお母さん方が道路に立って誘導しています。そこを通り過ぎ、小学校の前に来ると、こちらもお子さんの手を引いた親御さんが入っていきます。公立幼稚園の運動会のようです。信号で止まったので見ていると、お子さんが親御さんの手を引いて、「早く、早く」とでも言っているような光景が見えます。鉄棒では、手伝いの年配のおじさんが、久しぶりの鉄棒を楽しむように、ぶら下がったりいろいろしています。カメラお母さん、ビデオお父さんが、大量発生しているのでしょう。ビデオを構えていると、「おとうさ~ん」なんて、競技中でもこっちに手を振る息子達を思い出します。人生で一番の運動会でした。今日はいい天気で良かったです。今夜は、家に帰って再びビデオで運動会を楽しむのでしょう。
2006/09/30
コメント(12)
-
英語導入 の巻
文部科学大臣が、小学校授業への英語導入に疑問を呈しました。私は、英語の授業がどんどん小学生低学年に入っていくのには反対です。国立教育大付属の小学校では、随分前から授業があり、将来に向けて実験しているのだろうとは思っていました。「その成果がある」という結論で、小学校の指導要綱に入ろうとしているのだと思います。英語の授業が、現在の授業数にプラスされて、必須授業になるのなら賛成ですが、国語の時間などを削って導入されるなら反対です。今の公立小学校は、土曜日がお休みになり、授業数がかなり少なくなってしまいました。特に道徳という、生きていく底辺になる大切な時間が削られました。宗教が薄い日本人には、道徳は大切だと思います。テクニックを知っても、それをどう使うかが需要で、科学技術は諸刃の刃です。使うのは人間で、人の心が最も大切です。英語も国語も同じ言語ですが、言葉には、日常会話が出来ればいいという段階ではなく、人への細かな配慮や敬う心、手を差し伸べる心など、いろんな要素を含んでいると思います。クラブの先輩の文書を読んで思うのですが、語彙の豊富さ、簡潔な表現、表現方法の適切な言葉の選択など、見習うべき点が多々あります。そして、とても埋められない大きな差があると感じる時があります。戦前の義務教育を受けた大学生と、私の世代の大学生とは、レベルが違うのは重々承知ですが、小学校の国語教育の差を感じます。使う漢字だけでも、相当数の訓練の差を感じます。でも、そういう方たちが英語が出来ないかというと、結構出来ます。ならば、英語を高学年に導入し、少しづつ低学年に下げて、他を削るより、国語を増やす方がいいように思います。いろんなことを頭の中に整理したり、それを他の人に伝える時、1つの言語の習熟度がいります。会話をしなくても物が購入できるスーパーやコンビニの影響で、「ありがとう」や「すいません」と知らない人に物を訊く行為すら減っているように思います。敬語が使えない人が明らかに増えています。語彙のなさや言い回しの幼稚さから、気心の知れた狭い範囲の人としか話さない人が増えているように感じます。人に伝わらないイライラから、物を投げたり、手を上げたりする、幼稚園児のような意思の伝え方をする人がいます。学問の基礎である国語の充実と、英語導入なら何も削らずに授業数をオンしての導入をした方がいいと思います。「愛国心」という言葉を憲法に入れることが問題になっていますが、日本語教育を充実するだけで、日本という生まれた国を愛し親しみを持つことになると思います。
2006/09/28
コメント(12)
-
今でも、うちの子の様子を の巻
園児の列に車が突っ込んで園児が命を落としました。ニュースによると、公園に散歩に行く途中だったそうです。わが家の子供達は、1才から保育園に通いました。長男が生まれた時、私は学生をしていたので、家内は子供の世話をしながらお店もしていました。お母さんが恋しくて店に来ようとします。でも私製作の柵に阻まれ、泣き叫びます。従業員さんがいないときは、仕方なく抱っこしながら接客したりしていました。そこに救いの手を差し伸べてくれたのが保育園です。市に相談に行くと、いい所を紹介してくれました。大きな公園のすぐ近くで、雨が降っていないと、毎日公園や近所の神社にお散歩です。小さな子は、1日中室内にいるとストレスがたまります。日曜日に、1時間でも外に出ると、それだけで随分機嫌が違います。 数度、我が子達の一団を見たことがあります。歩けない子は、四方に囲いがあるスーパーの荷物運びの台車のような乗り物に乗っています。歩ける子は2列に並び、列の間に両方に電車のつり革の輪のようなものが付いた長いロープがとおります。そのロープの前後を先生が持ち、園児がその輪を持つことで、綺麗に1列に並んで歩けます。それを見たとき、素晴らしいアイデアだと思いました。この年頃は、いくら言葉で言っても、列は乱れます。何かを見つけたら、手を離して走っていく子も当たり前のようにいるでしょう。みんなに気を配りながら、大変な仕事だなあと思いました。そしてありがたいと。排便の習慣も、お昼寝も、絵を書くことも、字を読むことも・・・何かみんな保育園の先生に教えてもらった気がします。うちの車は少し大きいので、日曜日に子供と独身の先生を乗せてスキーに行ったこともあります。保母さんOGを数人雇ったこともあります。子供達にとっては、親以外で最初に長い間一緒にいる人です。先生の人柄は、その子の対人関係に大きく影響すると思います。みんないい先生ばかりで、感謝感謝です。もうお母さんになった先生と今でも年賀状のやり取りがあります。今でも、うちの子の様子を気に止めていてくださいます。今度の事故は、運転手さんのスピード超過と不注意が原因ですが、その場で子供達を守れなかった先生には、大きな心の傷になったと思います。保育園のお迎えに行くと、先生が「・・君、お父さんのお迎えよ」と子供を呼びにいき、その日の子供の様子を話してくれます。どの先生でも、受け持ちクラスの子供達全員の様子は、把握しているのでしょう。事故で駆けつけた親御さんに向ける顔がないように思います。「申し訳なくて・・・申し訳なくて・・・」だと思います。ニュースで先生が立ち会って現場検証をしていました。「無念」の気持ちなんだろうなあ・・・事故を起こしたドライバーさんは、日頃からスピード超過を常習していたのでしょう。「たまたま」ではないはずです。起きてしまったことは、もう仕方ありません。正直に、真面目に、事故と向き合って欲しいです。次男が小学生の時、自転車に乗っていて車に跳ねられました。数人で道路を渡った時、最後だった次男の自転車の後輪に横から車がぶつかりました。一緒にいた子や、事故を見て知らせてくれた方の話では、車はスピードを相当出していたそうです。それでも、子供達も無理に道路を渡ったのだろうし、幸い怪我だけで助けてもらったので、お釈迦になった自転車の保証だけで、それ以上の損害賠償はしない旨伝えました。その時ドライバーの彼から出た言葉には絶句しました。「スピード違反で、累積点数があり、今回のが人身になると免許がなくなります。免許がなくなると仕事が出来ません。物損事故に出来ないでしょうか?」全く反省していないようです。一歩間違えば、人1人死なせてしまったかもしれないのに、自分の保身のことしか頭にないようです。何度もスピード違反で反省の機会が与えられていたのに、反省しないからどんどん大きな事故を起こすことになります。世の中そういう風に流れるものです。私は、当然きっぱり断りました。自分のしたことを棚に上げて、権利ばかり主張する人が増えています。そういう人や、そういう人の周りには、そういう考えや血が流れていくので、人から助けの手が差し伸べられない辛い人生になるのは見えていますが、そういう人が起こす事故や事件に巻き込まれる善良な方はいい迷惑です。愛国心など学校で教える必要はないと思いますが、道徳心を養う授業はとても大事だと思います。今回の事故で、亡くなられたお子さんのご冥福を・・・怪我をされた園児さんや先生の1日も早い回復を・・・ご親族の心労はいかばかりか・・・
2006/09/27
コメント(7)
-
来月は の巻
日曜日は、レースでした。レース運営やコーチより、やっぱり選手が面白いです。来月は、3人乗りの全日本があるので、がんばらんとあきません。先週金曜日の夜に、ジュニアクラブの集まりがあり行ってきました。ジュニアは中3で区切りになり、来春高校生になる子が多いので、コーチングの人員配置の見直しをしなければなりません。コーチングも大切ですが、安全はもっと大事なので、自身がヨット経験のある親御さんをうまく配置しないと・・・でもお子さんと離れたクラスを受け持っても、やっぱり気持ちが盛り上がりません。親子はセットで移動です。経験者の親が少なくなるので、私も空いた時中級クラスの助っ人に入ることになりました。まあ自分の活動を優先しながら、ボチボチ手伝うことにします。小さな子と一緒にいると、よそのお子さんでも楽しいんですよね。
2006/09/26
コメント(4)
-
目に見えないもの の巻
先日、映画『出口のない海』を観ましたが、その時読んでいたのが同じく横山秀夫さんの『クライマーズ・ハイ』です。それを読み終えました。そして今度は、『出口・・・』を読んでいます。1985年8月12日、日航ジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落した。その当時、著者は群馬の上毛新聞の現職記者でした。その時地元で経験した様々な思いを著書にぶつけているように思います。主人公悠木は、新聞社に勤める記者だが、そのチーフになった時、部下の駆け出し記者をプッシュしすぎて自殺に追い込んだ経験がある。チーフという位置は自分に合っていないと、一匹狼の遊軍記者として応援記者をしている。一方会社の「山に登ろう会」に入り、山歩きから登山の世界に入り、そこの中心になっている同僚安西から、崖登りの日本有数の難所衝立岩制覇を誘われる。衝立行きを明日に控えた日、運命の日航機事故が起きる。浅間山荘事故以来の県内大事件に新聞社は、すぐに事故チームを立ち上げ、悠木がその全権チーフに任ぜられる。一方の安西も、その時過労で倒れていた。事故の描写などは少ししか語っていませんが、この事件を題材に新聞紙面の製作の流れが細かい。記者としての真摯な向かい方、被害者や遺族に配慮した誌面の言葉の選び方、詳報・速報第一の記者部門と印刷や輸送・宅配などのルーチン第一のロジスティック部門の折り合いなどで、新聞社内部で様々な軋轢を生む。大事故で始まった数日間の新聞社での出来事を縦糸に、過労で倒れてしまった同僚とその家族への思い、過去の自殺させてしまった部下への負い目、さらには仕事を理由に自分の家族、特に息子とうまく行かなくなってしまっていることなどを横糸として、読ませる作品です。事故から17年後、亡くなった元同僚安西の息子と共に登る、というよりサポートされながら登る衝立岩での描写と、上述の事故当時のことがパラレルして書かれているが、最後2人だけの登山で語られる言葉が、ジンと染みてくる。仕事と家族、かけがえのない友の家族との交流・・・愛や心という目に見えないもので人生は動いており、それから外れた人生の空しさを想像させます。横山秀夫の作品は、人の業のなせる悲しさなど暗い面を鋭く描写するものが多く、私には重めの作家ですが、この作品は、そういう中では、読後感のすがすがしい作品になっていると思う。秀作です。
2006/09/23
コメント(8)
-
多くの幸せが断ち切られた の巻
映画「出口のない海」を観てきました。回天という太平洋戦争末期に日本海軍が実戦投入した人間魚雷の話です。「男たちの大和」とは、スケールが違いましたが、その分、登場人物の心の動きを、より深く自分に置き換えて観れた感じです。立場の近い父親の視点で観ていたかな。息子から入隊することを告げられた時、「そうか、まあじっくり考えなさい」のような言葉を返しますが、多分私も、そうしか言えないだろうなと思いました。いろんな思いは胸を過ぎるだろうが、息子の決めたことに、軽々に反対意見は言えないし、さりとて賛成もできない。「お国のためにしっかりがんばりなさい」なんて、心にもない言葉も言えない。親や家族、その他いろんなことを考えてだろうなと思えば、彼の決断を尊重するしかないという気持ちです。ベトナム戦争の時、「nineteen」という歌が流行りました。コアの兵士は19才で、多く戦死したのも19才ということを知ってショックを受けたことを思い出しました。大統領や総理大臣がどれほど偉いのか分かりませんが、戦争なんて、年寄りが勇ましい言葉で決めて、自分は行かずに、よそ様のかけがえのない子供を法律で縛り、強制的に死なせるものなんだと分かりました。戦国武将のように、自分が先頭に立つことさえありません。父も同じ年頃に、ボルネオ島で蛸壺と言うのを経験しました。自分で穴を掘り、爆弾を抱えて中に入り、1晩過ごします。上を戦車が通ったら自爆するのです。その1晩が耐えられず発狂する者がいます。命令に逆らうと上官に撃たれるし、何があろうと感情を押し殺して耐えました。背中とお尻に弾を受け、たまたまマラリアで出撃出来なかった日に、父の部隊はほぼ全滅しました。実際の戦死トップは飢え、続いて味方からの狙い撃ち(戦闘が始まると日頃恨みを買っている人が後から味方に撃たれます)だと父から聞きました。戦争なんてそんなものです。再びの理不尽な悲しみがないよう、行動しようと思いました。映画を観て、原作でもっと深く感じたいという願望が増しました。今、同じく横山秀男さんの「クライマーズハイ」を読んでいますが、次はこの本です。
2006/09/22
コメント(4)
-
SINに感謝 の巻
「シンガポールで開催されるらしいです」昨日ジュニアクラブのメンバーの方からメールが入りました。うちのジュニアヨットクラブの今年最後のナショナルチーム遠征が、アセアン選手権です。11月の初めに、バリ島で予定されていました。過去形になってしまったのですね。バリ島でも起こりましたが、世界的なテロの影響です。国際大会なので、政府が安全の保証ができなかったのでしょう。ジュニアヨット関係者は、子供達に国際的な交流を持たせようといろいろ手を尽くしたと思いますが、ここはキャンセルしかないと決めたのでしょう。仕方ないことです。ジュニアの国際大会でも、国際情勢や国力・国情というものを感じます。日本にいれば、安全なんて気にかけることはありませんが、急激に発展しているアセアンでも、国の安全には脆弱なものを感じます。軍の力の国の中での大きさを感じます。比較的安定して、その地域では一番の軍事力を持っているタイでも、ジュニアの国際大会の回りを軍の警備艇が数隻囲んでいます。ミャンマーなんて、内陸の湖でしたのですが、宿舎からその会場まで、武装政府軍が前後に付いたバスで、選手や役員が朝夕移動し、岸には武装兵士がたくさん取り囲みます。私がタイに引率したときは、空港で軍の幹部に出迎えられ、VIP室に通されて、子供達にジュースやお菓子が出ている間に、入国手続きが終わった。大会会場までのバスが用意されていて、軍の方が空港を出るまでついていた。大会には、国王の家族が見え、閉会式では全選手に握手し、メダルのプレゼンテイターをしていた。大会にいるタイ人の異常な興奮ぶりに違和感を覚えたが、担当のタイ人に聞いたら、「握手して一緒に記念写真を撮れるなんて、あなた方はなんて幸運なんだ」と言っていた。日本では、たかが子供のヨットレースだけど、安全や政情不安がいつでも付きまとうアセアンの国では、きちんとした国際的なチャンピオンシップを無事執り行うことは、大きなもののようです。うちのクラブから、2人アセアン代表を出しているので、今度の大会がキャンセルになり、がっかりしていると・・・冒頭の朗報が舞い込んできた。あの地域ではもっとも経済力があり、安定しているシンガポールが、大会を丸ごと引き受けることになったそうです。昔、マレーシアでの大会を引率することになっていた。あの時は、「ラニーニャ」という異常気象の影響で、大会予定会場の水位が高くなりキャンセルになってしまった。やはりシンガポールが受けてくれた。でも今回以上に急だったので、「アセアンチャンピオンシップ」ではなく、一般の国際レースという感じになってしまった。日本のジュニアの協会から、派遣中止の連絡があったが、正直迷った。次男も選手だったが、まだ14才。来年もチャンスはある。でも15才の選手もいた。監督という立場だったから、協会の派遣の有無に関係なく、彼らを引率することは出来た。でもしなかった。「はっきり言って、今でも悔いています」その後どうなったか。中学生の精神的に微妙な年頃には、目標が自分の努力とは関係ないところでなくなってしまうことは、影響が大きかった。「次男が勉強しなくなった」小学校からヨットも一生懸命やっていたが、勉強もやっていた。自分の意志で中学を選び、受験して入った。毎学期成績によってクラス落ちしたり、クラスが上がったりする学校で、入学以来ずっとトップクラス40数人に居続けていた。小学校からのヨットでの目標は、ナショナルチームに入り、日の丸を胸に海外レースにチャレンジすること。やっとつかんだ海外レースの場を失う・・・目標が、フッと消えてしまい、成績が急降下してしまった。学校に、親子で呼び出された。私が学校に行き、2人でクラス落ちの話を聞いた。「よっぽどの成績を取らないと、高校1年は1つ下のクラスになります」「正月開けの高校入試、模擬試験、冬休み明け学校内試験、いずれかで学年トップ3に1度は入ること」がトップクラスに残る条件だった。2人で家に帰る電車で、次男に声をかけられなかった。「あほやなあ。勉強せえへんからやんか」なんて怒るのはたやすいことだけど、それを言われて息子は何か力になるだろうか?今一番ショックを受けて、悔いていているのは息子自身です。彼の人生なんだから、自分で打開するしかない。その力になってあげなければ・・・乗り換えの駅にある喫茶店に入り、「おいしいもんでも食べようや」フルーツパフェを注文するので、ついでに私も同じ物を。10年以上ぶりのフルーツパフェです。腹が減っていたら、マイナスの思考になるので、まずは腹ごしらえです。「まあいろいろあるわ。でもな、命がなくなるわけやないから、できるだけがんばり~な。きっと出来るとおもうで。賢いもん」叱る言葉や注意する言葉はなしで、「大丈夫やって」なんて、何の根拠もないのに、言ってました。ここを支えられるのは、親しかいません。こういう時にこそ、親が必要です。ポロポロ涙を流しながら、2つも連続でフルーツパフェを食べていました。それから数ヶ月、猛烈に勉強し始めました。大晦日の夜、恒例の家族での近所の天神さん参りで、「お~久しぶりやなあ」と息子に声をかけてしまいました。部屋に閉じこもって、同じ家にいるのに顔さえ合わさなかったから。結果は、3つともクリアしました。全国模試の英語は、なななんと、2桁の成績でした。高校受験前の中3がみんな受けるので、分母は何万人とか何十万人とかだったと記憶しています。ヨットでがっかりして、ゲームセンターに行っていたようです。何となく気づいていましたが、それを注意しませんでした。これは、子供達に対する小さい時からの私たち夫婦の接し方です。命に関わることでなければ、出来るだけ言わない。世間様が、頭を打ってくれるから、そこで親が下支えして、どうするか自分で決め行動するのを待つ。「僕らの血を受けた子供達だから、絶対いつかいい方向に向かう」という信念がないと、小言を言ってしまいがちだけど、小さい時からそうしてきたので、このときも前向きな行動を取った。担任の先生は、毎晩電話を下さり、「応援してるぞ」って励ましてくれた。アセアン大会がキャンセルになっても、無冠の大会でも参加させていれば、こんなことにならなかったと、悔いているが、子供は見事に親のミスを跳ね除けて、それをいい経験に転嫁させた。でも今回は、「チャンピオンシップ」はそのままのようだし、期間も同じ。ただ開催場所が変わっただけだから、みんな元気に参加してほしい。私の息子のような子が出ないように・・・それにしても、シンガポールには、感謝感謝です。
2006/09/21
コメント(8)
-
がはは の巻
日曜日に家内に聞いたのですが、土曜の夜、東京に就職した長男から電話があったようです。「僕は元気にしてるよ。敬老の日だから、何か送るので、家内の実家のお婆ちゃんの住所を教えて欲しい」という内容だったそうです。私たち夫婦にも・・・まあ家内にだろうけど、何か送ってくるそうです。家内が嬉しそうに話してくれました。「俺はもう敬老の日の対象になったの?」というのもありますが、素直に嬉しいです。子供達とは、父と子というより、遊び仲間みたいな感じで接してきたけど、普通に育ったようです。トランプやゲーム、屋外でのキャンプやスキー、こういうのはこちらも面白いので、真面目に接したけど、もっと真剣に接しないといけないところほど、いいかげんな接し方だったように思います。親として、何かを教えてあげたというより、教えてもらった方が多い感じで、身体が丈夫だったこともあり、かなり楽な子育てだったように思う。それに、少しづつ大きくなり、いろんな事が出来るようになるのが、私へのプレゼントだった。これからも、新しい家庭を作って次の代を育てていくのだろうが、それだけで大きなプレゼント。ほんと、その他に何にもいらないな。ただ元気で・・・それだけ。そして出来れば、いつも笑顔で、「がはは」と笑っているのを見ていたい。眉間にしわを寄せて叱ったり、親子喧嘩なんてしなかったので、これからもこんな感じでやっていけたらいい。
2006/09/19
コメント(13)
-
漢字が読めないセーラー の巻
日曜日は、ジュニアクラブ主催のヨットレースでした。私はOBなので、特に運営をするわけでもないのですが、いよいよ台風が来そうなので、船のもう一段の台風対策のこともあり、レースに間に合うように行ってきました。ハーバーに着くと、見知った他クラブの方がチラホラおられます。艇長会議に、小さなセーラーも立派な艇長として出席です。セーリング・インストラクションというレースの説明書を手に持ち、レース委員長の説明を聞いています。漢字が十分読めない子もたくさんいると思いますが、ここは艇長としてしっかり聞いていなければ。商工会議所の後援がついているので、その方の挨拶もあります。出艇申告のサインをして船に向かいます。ひらがなばかりのたどたどしい名前も並びますが、ハンディキャップはありません。台風に吹き込む強めの東風が朝から吹いていますが、小さな子も元気に出て行きます。中学生が、小さな子の出艇を手伝って、それから自分達が出て行く姿に、いいクラブだなあと思いました。うちのクラブは、親御さんが全員コーチです。ヨットの経験がない方でも、陸上のことやなんやかや、いろいろ指導するところはあります。親御さんたちがなんとなく、小さい子を手伝ってあげてねとお願いしてきたのでしょうが、自分達が小さな時苦労した記憶もあるのでしょう、すごく自然でした。楽しそうに手伝い、指示する姿がいい感じです。素直ないい子達です。元気に出て行ったけど、風が上がってきたので、走れなくなった小さい子からチラホラ、レスキューに引っ張ってもらって帰ってきます。スロープに近づくと船を降り、船を引っ張ってお母さん方が持ってきたトロリーに乗せます。手伝ってもらいながら引っ張り上げ、帰着申告をして船の片付けです。海上では怖かっただろうに、笑顔です。「帰着申告したらぺろぺろキャンディーをあげる」というお母さん方のアイデアはさすがです。「もうちょっとガンバレなかったのか?」なんて言う方はおられず、「お帰り」とか「ご苦労さん」とか。レースではトップ艇にはるか離されて、悔しかっただろうと思うが、それは自分で消化すること。「もっと練習しなくちゃなあ」とか「次は・・ちゃんには負けないぞ」とか、いろんなことを心に刻んでいるように思う。大人が、それに追い討ちをかけても意味のないこと。小さな傷に塩をすり込むようなことだと思う。ただ技術的なアドバイスでいいと思う。親やコーチがきつい言葉で、それを指摘したり、時には「愛のムチ」という美辞の元、目下な者や我が子に暴力を振るう。その暴力は、自分を制御できない弱い者が、自分の気持ちを発散するためにしているだけで、暴力を振るわれた者には、ありがたいという気持ちは残らず、敵愾心のみ残る。最近周りで、そういうのや腹立ち紛れの暴力が問題になったので、がっかりしていました。暴力の連鎖です。ちょうどこの日母校大ヨット部の練習に、オーストラリアのシドニーオリンピック優勝選手が来ていた。彼は、日本製のセールを使っていることもありよく日本に来ている。先週終わった中国でのワールド帰りに寄ったのかもしれない。去年の470ナショナルチーム選考会にもオープン参加して、次男とレースを競った。彼らトップセーラーやそのコーチは、決して暴力など使いません。funを選手に感じさせるコーチングをします。楽しむ・笑顔が一番の上達の源泉です。暴力やひどい言葉は、心に深い傷を刻みます。それを清算するために、自傷行為から自殺、自分より弱い立場の人に対する暴力の連鎖が起こります。自分がそういうことをされても、自分でその連鎖を止めなければなりません。そういう気持ちがムクムクとして来ても、じっと我慢で、温かい言葉に言い換え、その相手に与える。そうすると信頼につながり、いずれ伝えたかったこと以上のものが伝わるでしょう。人は、暴力などなくても、言葉というもので伝えられます。『ドロシーローノルトの子は親の鏡』・・・とてもいい詩です。この日のレースの子供達とお母さん方を見ていると、温かいものが流れてきます。「何も言わなくても、きっとうまくなるよ」っていう子供を信じている感じ、いいですね。子供達は数年後に、その期待以上のものを親御さんに届けてくれるでしょう。
2006/09/18
コメント(6)
-
いい感じの照明 の巻
昨夜は、仕事を終えて速攻で船に行ってきました。台風対策です。台風がこちらに来るかどうかわかりませんが、雨風の強くないうちに対策だけはしておこうと、飛び出しました。陸上に置いてあるレース艇を数本のロープで、ハーバー地中に埋め込んだリングに固縛します。照明は夜間でもついていますが、薄暗い中、梯子で船に登り、ロープを落としてゴソゴソやってる姿は、どう見ても怪しいです。ガードマンの巡回があれば、声をかけられるのは見えています。次に、セキュリティーカードで桟橋入口を開け、海上係留してあるクルージング艇に向かいます。ここは釣り禁止なので、魚影はとても濃いです。昼でも夜でも、魚が跳ねます。桟橋を渡る私の振動で眠りを覚ましてしまったのでしょう。怒りのジャンプが、あっちでポチャリ、こっちでポチャリです。船と桟橋が当たるところのクッションを増やします。いつもは適当に縛っているのですが、「こっちから風が吹いたら」を仮定し、船をいろんな方向に押して、数本のロープで均等に船の重さを受け止めるように、長さを微妙に変えます。最後に、反対側の桟橋からのロープを1本から3本に増やし、更にそちらからより引っ張って、桟橋からちょっと離した位置で船をあまり動かないようにします。四方のロープがゆるいと船が動き、ロープへの一瞬の負担が増えます。張度を高めにしておくと、船の動きが制限され、一瞬の負担を軽減できます。台風のスピードがあまり上がらず、大阪への最接近は、18日になりそうですが、925hpという強さなので、17日には、もう一段の台風対策が必要になるかもしれません。高校でヨットと言うものに出会ってから、台風という言葉が出ると、船と繋がってしまいます。艇庫といっても、昔からの既成事実で、今で言えば砂浜を不法占拠した建物でしたので、海面からそれほど高いところに艇置き場があるわけではなく、高潮で船が持っていかれたり、強風で飛ばされることも心配しなければなりません。それで、いよいよ台風が来るという日は、部員みんなで艇庫に泊まります。まあ、練習をする状況でない艇庫で、気心の知れた面々と過ごすので、楽しくもありました。最近は、母校も立派なヨットハーバーに居を移し、がっちりした艇庫に船を収め、ハーバー職員も待機しているので、全員で待機というのはないようですが、OBの使う大型艇の場合は違います。1人で作業をしながら、船を守ろうと必死だった学生時代のことを思い出されます。遠くに、母校の立派な艇庫も見えます。あんな立派な艇庫だったら、大雨の中、潮が上がってきたと、大騒ぎで船に走り、少しでも高いところに船を移動させる経験も出来なかったな。一旦作業になると、カッパを着ていても意味がないほど濡れてしまい、ヤケクソで走り回ったりしていたな。強風で艇庫のガラスが割れたと、応急で板を打ち付けることもなかった。自分達の寝場所にレース艇を上げて、その片隅で、寝ることもなかった。ウォッチと言って、外洋ヨットが交代で休むように、スケジュールを組んで下級生が、数人でずっと外の船を見張ることもない。家族は自分の家の心配と、わざわざ台風が来ると言えば、より危険な海に向かう息子の心配もしなければならない。なんと言っても、息子の艇庫は、防波堤の外の海側の番外地にあるからなあ。でもまあ、あの時代は「またか」と思いながら、楽しかった。よく朝起きてみるとレスキューが沈んでいて、お金がないので、若い人力を頼ってみんなでサルベージした。何故か、サルベージの方法までクラブに先輩から伝わっていた。不便であったけれど、身体を張って船を守ったという充実感があった。より船に愛着が湧き、船の履歴にいろんな物がつく。作業のためにクルージング艇の上に上がり、「さて、当時と変わっていないものは・・・」。「音だな」カラーン、カラーン。マストから何本も出ているワイヤーがマストに当たる音。大体この音で、寝ていても今の風速が想像できた。作業を終え、桟橋を歩いていると、入口のドアの向こうのベンチや会談に、アベックさんが数組いてはります。ここは、ハーバーのガードマンさんはいるし、桟橋にはいい感じの照明が点いていて、デートスポットでもあるなあ・・・ここが私の学生時代と絶対的に違うところだな。
2006/09/16
コメント(6)
-
学園祭シーズン の巻
昨日の続きです。文化祭、学園祭シーズンになってきました。昨日の日記には、私の高校生の時の学園祭の事を書きましたが、今日はそれを書きながら思い出した長男の文化祭の話を書きます。私の両親は共働きでした。よって、家に帰っても、「おなか減った」と叫んでも、「はいよ」って出てくることはありません。それどころか、「今日は夕食作る時間がないから、作ってね」と言われることもありました。母から作り方を教えてもらい、買って来る材料を書いてもらい、買い物に行きます。それを適当に作ります。小学校の3年ぐらいから6年ぐらいまで、本当によく作りました。料理も作り始めると面白く、高学年の頃は、毎日のように作っていました。中学からは、電車通学になったので帰宅が遅くなり、あまり作らなくなりました。そういう環境だったので、小学校のクラブは、サッカー部とともに家庭科部にも所属していました。家庭科部は、たった1人の男の子・・・のはずだったのですが、もう1人いました。こういう経験があったので、大学のクラブでの食事当番には困りませんでした。結婚した頃は、家内より料理が上手だと自信がありました。家内と私も共稼ぎなので、日曜日は家内の主婦お休みの日です。昼食と夕食は私の担当です。ついでに言えば、裁縫はずっと私の担当です。子供達は、「ボタンが取れた」と私のところに持ってきます。小学校の長期休み明けの雑巾縫いは、定番の仕事でした。食事の方ですが、子供達が物心ついて来ると、日曜日のお父さんの料理の日には、「なに作るの?」なんてまとわりついてきます。お母さんのように手際よくありませんが、子供達に手伝ってもらいながら、やる気満々で作っていました。時にはおやつも作りました。という長い長い前置きがあって、長男君が中学になって、ん?高校だったかな?文化祭で模擬店をすることにしたそうです。メンバーで不要品などを持ち寄って、お客さんに買ってもらおうと考えたようです。そのときの長男からのリクエストは、「お父さん、ケーキ作ってや」でした。家内が好きなチーズケーキや、時にはロールケーキなどを日曜日のおやつとして、たまに作っていました。それを売ってみたかったのでしょう。「素人のお父さんが作った」というのが、いい感じだったのかもしれません。「売れるか?」と、半信半疑で作りましたが、速攻で売り切れになったそうです。それ以来数年間は、「・・パパのケーキ」として花形になったそうです。文化祭が近づくと、ケーキを考え・・・といってもチーズケーキとロールケーキのみですが。前日から夜を徹して作りつづけました。職人が1人で、家庭の道具だけなので、たくさん作れず、毎回完売でした。長男の考えた、「・・パパのケーキ」というキャッチフレーズが、妙な購買意欲を掻き立てたのでしょう。何でもやりたがりの長男は、何処でも目立つこともあり、ケーキを作るけったいな親父として、私も有名になったようです。PTAの役員の話が来てしまいました。
2006/09/14
コメント(8)
-
学園祭シーズンの始まり の巻
世の中は、学園祭シーズンに入ったようです。大学の学園祭は、10月後半から11月前半が多いのだとおもうけど、受験高は大学受験に向けて、9月に学園祭をやってしまうところもあるようです。修学旅行を夏前に済ませてしまうところもあります。そういう話を聞いて、高校生だった頃の事を振り返りました。大学付属で同じ敷地内に大学があり、しかも日程が同じだったので、学園祭は盛り上がりました。運動部だったので、文化的は発表もなく、ステージに立つこともなく、有志で集まって模擬店を教室でしました。「お化け屋敷」です。お化け屋敷の恐怖量は、光度に反比例すると思ってします。つまり、暗ければ暗いほど怖いです。真っ暗であれば、ただ歩いているだけでも怖いです。我々のグループは、教室をできるだけ真っ暗にしました。そこに黒い布で迷路を作りました。ベニア板で四方を囲い、所々ベニアのない壁を作ります。そこに、交代で人を配します。真っ暗な迷路を、壁を触りながら歩いてきたお客さんが、布だけの頼りない部分にくると、壁がフッとなくなった感じになり、悲鳴があがります。不意にお客さんの肩に手を置いたり、足に手を触れたり・・・もう大変な騒ぎです。迷路になっているので、行き止まりでバックする時の恐ろしさ。迷路から出られないのではないかという別の恐怖。悲鳴と共に、大評判になりました。その横の部屋で、メンバーの親の会社からジュースを買って、それを販売しました。恐怖の後は喉が渇くようで、結構売れました。学校まで運んできてくれたメンバーのお父さんの嬉しそうな顔も思い出します。子供を持つ親になって、そのときのお父さんの笑顔の意味が分かりました。子供に頼まれることは、親の喜びなんですね。このお化け屋敷には、最後オチがあり、泣いてしまう女の子が結構いて、先生にかなり叱られました。そういうのをやりながら、大学の模擬店を覗き、破格の安さの焼きそばを食べ、落研の落語を聞きました。夕方になると自分所の模擬店を片付け、大学の方に行きます。毎年、そこそこ有名なバンドが来るので、それが目当てです。一番印象に残っているのは、矢沢栄吉がいてたキャロルというバンドです。黒の皮ジャンとバイクがトレードマークで、なんと会場までバイクで爆音を響かせながら乗り付けました。その後に始まった大音響で、すごく興奮しました。男子校だったので、校舎に女の子がいることも、学園祭の楽しみでした。私も、知り合いの女の子に声をかけておいたのですが、5人ぐらいで来てくれて、かなり鼻が高くなりました。反対に、女子高の学園祭のチケットをもらって、ドキドキして行った事もあります。女の子のように友人を誘うことなどできずに、1人で行ったのですが、受け付けで彼女がいて、ホッとしました。携帯電話なんてものはなかった時代ですから、たった1人の知り合いに会えなかったら、ただ赤面しながら駆け抜けるように帰るのみです。子供の文化祭のことも思い出しましたが、それは明日書くことにします。
2006/09/13
コメント(8)
-
人生のお終い の巻
日本経済新聞の「私の履歴書」、今は三浦雄一郎さんが書いていらっしゃいます。このコーナーは、一応チェックし、興味のある方の時だけ、熱心に読んでいます。オリンピック・アルペン競技で、未だに唯一の日本人メダリストである猪谷千春さんの家と同じように、三浦さんの親父さんもスキー狂です。猪谷さんは、以前に本で読みましたが、大胆と言うか乱暴と言うか、豪快に好きな事に一直線です。今のように娯楽が多くないので、こうなるのかもしれません。東北大だったかのスキー部のコーチをしに、三浦さんのお父さんがラッセルしながら合宿している山小屋を目指します。小学生の雄一郎さんは、そのラッセルの後を追うのですが、お父さんは振り返ることすらしません。遅れてしまうと「死」が待ち受けているので、必死で追う。暗くなって合宿所に着いたら、学生達に驚かれ、翌日から一緒に練習をする。猪谷さんは中学生のとき、地元で行われた全日本選手権の前走をしたら、誰もその記録を超えられず、自分は結構速いと自覚したということでしたが、三浦さんも同じような経験をしたと書いてありました。技術などが未熟なそのスポーツの黎明期なるがゆえの出来事だと思いますが、野生の強さを感じます。三浦さんは、スノードルフィンと言うスキー学校を北海道でしています。SIAという国際メダル検定の系列校です。スノードルフィンは、何故か兵庫県にもあり、シーズン会員になって毎週お世話になっていた時期もあります。シーズン会員になると、リフトと学校とコーヒーがただになります。週1日しか行けないけど、元は取れる。休みの前日、仕事を終えると速攻で家に帰り、ウエアボックスと板・ストック・靴、それに布団を車に放り込んで、一路雪山を目指します。12時前にスキー場の駐車場に入り、布団を敷いて耳栓をして眠ります。いつも通りの時間に朝起きて、一番のリフトに乗り、一滑りしてから午前の学校に入り、夕方学校が終わると、最後の一滑りして仕事場に帰り、閉店まで仕事をします。こんな冬の生活を10年近くやってたように思います。コブに飛ばされて腰をしこたま打った事。幾分トップを上げ気味に、フワッフワッとリズミカルにターンを返す新雪の感触。新雪で転んで板が外れ、1時間以上ももう1本の板をスコップにして捜した事。すぐ近くの急斜面で雪崩が起こり、捜索に加わったけどインストラクターが助からなかった事。雄一郎さんの「私の履歴書」を読みながら、いろんなことを思い出します。このコーナーに声がかかると言うことは、そろそろ人生のお終い・・・人生を整理しながら振り返り、どういう心境で書いているのだろう・・・なんてのも考えました。
2006/09/12
コメント(3)
-
ヨットはあったんや の巻
日曜日は、母校のインカレ団体戦予選でした。船で観戦することになり、ジュニアの時にお世話になった、他校の出場選手の親にも声をかけておきました。昼から雨という予報もあり、ゲストさんのカッパを数セット背負い、海用の双眼鏡やお茶と氷満タンのウォータークーラーを車から降ろし、首にかけたり手に持ったりで、大荷物です。一旦船に置いて、エンジンを回すと快調に一発で回ります。週末にしか乗らないので、いつもエンジンがかかるか心配です。大会本部で成績表のチェックです。大学のヨットは、2人乗りだが形の違う2つの艇種があります。各クラス3艇の合計得点の着順=得点で競います。各クラス上位3校が全日本への切符を手にします。母校は、2日目を終えて両クラス4位です。片方は、8レースで3位と100点差なので、最終日の3レースでよっぽど走らなければ苦しいです。もう一方は、1位だけが少し離れていますが、2位と4位までが9点しか差がなく、ほぼ同点という感じです。船に戻ると、メンバーがやってきます。久しぶりの同期のY君は、長男君が母校高校1年生でヨット部に入部しました。数年後の楽しみが増えました。トルコで考古学の発掘をし、その後ドイツに留学していた先輩のお嬢さんが、お母さんと共に来ました。数ヶ国語を操り、何処にでも就職できそうな才媛です。私の次男がオランダ中心に1人旅していたとき、切羽詰ったらこの人に連絡しようと思っていました。トルコ語は、日本語と動詞の並びなどが同じだそうで、覚えやすいそうです。ドイツは、自然がとても綺麗だそうです。レースは、9レース目も10レース目も、先週のインカレ個人選手権で全国制覇したエース君がトップで、他の2艇もまあまあで、どうやら3位には入れそうです。それを見て、お昼なのでハーバーバックしました。風が5m/sぐらいで、少し波があり、ゲストの女性がこの状態で食事を海上で摂るのは、かわいそうです。桟橋に戻ると、早速シェフがカレーうどんを作ります。単身赴任の経験が、短時間でおいしい食事を作る腕にしました。私のようなできれば食事は作りたくない者から見れば、大変ありがたい先輩です。この日の会費は、300円でお代わりもしちゃったし、大変満足です。その後船の掃除や、壊れそうな部品の交換などをして、解散になりました。桟橋をハーバーハウスに向かって歩いていると、向こうから大先輩がゴミを両手にやってきます。そのままハウス内のコーヒーショップで、話す流れになりました。もう70才を過ぎておられますが、数年前の大学ヨット部OB戦で、この先輩のクルーをしたことがあります。まだまだ十分に速く、年齢ハンディキャップもあり優勝してしまいました。会社で、モータークルーザーを買ったそうで、その掃除をしていたようです。1億を越す豪華なクルーザーですが、アジアの大型モータークルーザーの供給基地は台湾だそうです。粉塵のないクリーンな工場で、コンピューターに連動した機械が、FRPの船底を磨く様は、素晴らしいの一言だそうです。ちょっと名の知れた会社の社長さんですが、こと船に関することなら、掃除でも何でもするようです。「そりゃ昭和24年からヨットに乗ってるからなあ。アメリカ人にそのことを話したら、広島や東京の焼け野が原の映像から連想して、日本にヨットなんてなかったなんて言うのよ。でもあったんや。幻の戦前の東京オリンピックに向けたヨットがあったんや。長年覇を競った仲間がどんどん欠けていき、寂しいもんよ。もう先あんまりないから、海だけは最後までやってたいわ。いつでも乗りに来てくれや」って・・・そういうことを話していると、低い黒雲が垂れ込め、大雨になりました。この日は、1時間ほどでやみ、家路につきました。その後、船から持ってきたGPSの説明書を、船で操作した手順に従って、重要な所だけ分かりやすく、そして大きな字で書いてマニュアル製作しながら1日を終えました。
2006/09/11
コメント(8)
-
負け犬なんて言葉、好きじゃないな の巻
皇室に男の子が生まれました。男系に限られていた皇室典範を、女系にも広げようとする議論が棚上げになったそうです。この議論の高まりで、男系と女系など知らなかったことを知りました。私はこれまで千年以上も続いてきた天皇という継承が、もし途切れるのならとても残念です。多分世界に類を見ない継承で、日本の特徴だと思います。日本の歴史の根の部分に絡んでいることでもあります。女性天皇は過去に存在しましたが、男子の人材難のときのピンチヒッター的な感じで、すぐに男系に戻っています。そういう感じで典範すれば、絶えることはないと思うのですが、法律に明文化されたことで、窮屈になってしまったのかもしれません。今度生まれたお子さんは、3番目の天皇継承者だそうですが、新聞によると継承順位は、天皇の子から天皇の兄弟やその子孫、さらに天皇の叔父やその子孫まで付いています。十分なような気がしますが、専門家から議論が起こるということは、それでも該当者がいない場合を明文化しておかないといけないのかもしれません。天皇は国家の象徴ということになっていますが、皇族の中からも、制度改正に反対意見がたくさん聞こえる議論は、やめといた方がいいように思います。ところで、私の母親は美智子皇后と同じ栃木県出身です。美智子さんの実家は正田醤油ですが、美智子さんの母親の実家が、うちの本家でもあります。そこの娘の娘が私の祖母です。小学生の頃、お盆で本家に何度か行きましたが、大勢の親戚が集まっていたのを思い出します。現在の本家の当主の実質の生活は、街中にあり、小学校の運動場のような大きな庭がある家でしたが、山のかかりにある元の本家は、山の中に家屋が点在している感じで、周りの風景に馴染んでいました。戦争までは、多くの書生さんが住んでいた寮のような建物があり、近在の優秀な子の学費などの面倒を見て、成人後は展開しているいろんな事業の番頭さん格に育てて家の安泰を図っていたそうです。昔のことだから、結婚は本人というより家同士のつりあいが影響したのでしょう。祖父の家も大きな商売をしていて、そちらは番頭さんに任せて、祖父は戦前近衛兵の隊長で皇居に詰めていたそうです。祖父が天皇さんからもらった勲章をお盆になると出してきて、神棚に飾ります。母は、五女という女の子ばかりの末っ子だったのに、女学校から戦後すぐ大学に上がりました。男性に混じって相当勉強したらしいですが、田舎の末っ子の女子で大卒というのは、恵まれています。そういうのを思うと、私なんて今一にも至っていない感じがします。でも、国は今よりずっと貧しかったのに、こういう家があるということは、多くの生活に窮する家もあったわけで、総中産階級と言われる少し前の日本の方がいいように思います。社会も、物騒なことがなく安定していたと思います。それが、「負け犬」だとか「セレブ」だとか「勝ち組」なんて、2極に分ける風潮が広まり、治安が悪くなっていってます。いい方向に進んでいるか、疑問です。
2006/09/09
コメント(8)
-
ほんまに? の巻
高校生のお子さんが、通信教育の試験で、偏差値85点という結果をもらったそうです。点数じゃなくって、偏差値?どうなったらそういう偏差値がでるのか、不思議だそうです。1科目だけがそれで、全然あかんのもあるので、総合すると落ち着くところに落ち着いたそうですが、偏差値85なんて私も見たことがないので、ビックリです。偏差値というのは、平均偏差からの乖離率だったと思います。最高で75・最低25の間にほぼ100%の人が入ると理解しているので、それを越えた残り1%未満に入ったのでしょう。みんなの平均がかなり低く、友人のお子さんは他を圧倒して飛びぬけた成績だったのでしょう。この成績表は、神棚に祭られ永久保存されるべきと思いました。まあ、他の教科にひどいのがあり、どうやら神の域には達していなかったのが、大阪人というかタイガースファンの愛嬌というところでしょう。もしうちの子が、そういう偏差値を連発したら、神の子イエスの父親であって父親でないヨセフの立場になりそうです。どう考えても、自分の血が行ってるように思えないし、妻の子ではあるが・・・処女降臨なんて・・・まあ、いろんなことを想像させてもらいました。それにしても、ものすごい偏差値があるものです。
2006/09/07
コメント(3)
-
知った顔が多いと の巻
先の日曜日までの3日間、全日本学生ヨット選手権個人戦が行われていました。お手伝いしている学校から2艇参加し、10番代と20番代でした。この2艇がいて何故3艇での団体戦地区予選で3位に入れなかったのか・・・という思いはありますが、ヨットレースはそういうものですね。そのレースで優勝したのは、母校の後輩でした。彼は、ジュニア出身選手で、トップ10の過半はジュニア出身です。ジュニアの子達は、小さい時からの海外を含めて、レース経験が豊富であることと共に、大学は違えど、上位選手とは子供の時からハーバーで遊んでいた仲なので、落ち着いてレースに臨めるのが大きいと思います。中学の受験の時、小学校から1人だけその学校を受験したので、心細くドキドキして試験会場に入ったのを覚えています。入学後、友達になった子で、同じ学校から10人以上入学した子がいました。彼は、別にドキドキしなかったそうです。長男の中学受験第1志望不合格で、付き添いが辛くなってしまった家内に代わって、次男の時は私が付き添いました。正門を入ると、大手塾に通っていたので、後ろも振り向かずに自分の塾の旗を見つけて駆けていきました。合格発表で、学校に向かう道ですれ違う帰りの子を見て、何か合図を送っていました。次々同塾の子が帰ってきて、その表情から合否を判定し、「僕、合格したわ」って、一変に明るい顔になりました。彼らの表情で合否を判定し、彼らの実力と自分のそれとを比べて、「落ちるわけがない」と確信したのでしょう。人は、実力を知っているヤツの顔があると、落ち着くようです。本番で、周りが知らない子ばかりだと、みんな自分より実力が上のような気がします。でも知った顔があると、実力が上の子も下の子もおり、得体が知れている分だけ有利になるような気がします。入学テストは、日頃の勉強も大事ですが、模擬テストなどテストと名がつくものの経験回数も大きなウェートを占め、レースはレース経験の豊富さが本番でのいい結果に繋がります。子供達を教えていると、そういうことがよく分かります。元の才能はそれほど差がないのです。でもレース経験でどんどん差が出来ていきます。レースで負けを経験し、他クラブの同じような子と友達になることは、次の練習の意欲につながり、それが大きな差になっていくような気がします。さて次の週末は、母校の全日本団体予選です。まさか予選敗退はないと思うのですが、よりよい結果を期待したいしています。
2006/09/05
コメント(4)
-
GPS の巻
日曜日は船に行ってきました。2週ほど、琵琶湖行きが続いていたので、お盆以来の船です。この日の課題は、GPSです。6月にGPSをつけて、7月末に初めて使用し、あまりの誤差に閉口してしまいました。ここはじっくり学習する時間が必要だと思ったのですが、動いている船の中で、文字を追っていたら酔うのは必然です。全く平気で揺れる船内で料理を作ったりする人がいますが、私はすぐに変な気持ちになるので、外にいることにしています。じっくり船内にこもって機械とにらめっこしました。視野の中でちょろちょろ動いたり、しゃべったりする車のGPSが、どうも好きになれず付けていない影響もあるのでしょうが、取り扱い説明書がかなり難しい。FURUNOという世界を席巻している日本のレーダー会社の製品ですが、使う人が限られていて、海用という障壁が有り、車用のように競争がないからだと思うが、一見分かりやすそうで、飛んでいるところがある。悪戦苦闘して、やっとこ、何となく使えそうな感じまで理解できました。主な目的地データを入れようと、ハーバーカウンターで近隣の港のデータをもらってきました。名前を入れて、緯度経度データを入力して、記憶させます。記憶した所に行く時は、目的地を選んで運行ボタンを押せば、目的地方位・距離・今の速度から換算した到着時間まで表示されるので、最短で目的地に着けるはずです。実際にこのハーバーを目的地とすると、50mとなり、ちょうど事務所と船との距離ぐらいで、中々いい感じです。しかしまあ、実際に運用してみないと、本当の所はわかりません。次回が楽しみです。船用のGPSは、陸上とは違う仕様になっています。陸上のは、高度とかもあると思うのですが、海用はそういうのはありません。でも、魚群探知が出来、深度もわかります。魚釣りはしないので、魚探は使いませんが、ヨットの場合深度はとても重要です。ヨットは、風に吹き倒されないように、船底から錘がぶら下がっています。だから、実際は2m以上の深さまでクリアな所でないと航海できません。3mの深度になれば、こわごわの感じになり、5mは欲しい所です。深度5mより浅くなるとアラームが鳴るようにセットしましたが、ハーバー出入り口などで、頻繁に鳴るようなら、設定変更をしなければなりません。さてさて、どうなることやら。
2006/09/04
コメント(6)
-
見えない力 の巻
「あれ、これ1回見たことあるぞ」とか、「これ1度経験したことあるけど・・・」というのを、時々経験します。誰でもあると思うのですが、私は年数回です。「次、こうなるぞ」という予知能力だったら、使いようもありますが、私のはいつもそれが過ぎ去った後、「あれ、今のは前にも経験したわ」と既知思い出し能力とでもいうような、もののようです。インド洋地震で、象さんが予知して逃げて無事だったとかありましたが、人間も昔はいろんな能力を持っていたのでしょう。シャーマンも昔はたくさんいたのに、今はほとんどいなくなりました。その代わり、飛行機とか自動車とか、すごい能力がなくても練習すれば誰でも高速移動できる新しい魔法を手に入れました。もう10年も前になりましたが、阪神大震災に遭ったとき、最初の揺れの少し前に目を覚ましました。5:45といういつも起きるはずのない時間ですが、何故か目を覚ました後に揺れがきました。その後の余震も、何度か「なんか揺れそうだな」と思った後、揺れが来たことがあります。震災の前に、小さな地震が何度も起こる群発地震が続いていました。多分、あの揺れで、地震感知能力が研ぎ澄まされ、本震の前に起きたのだと思います。こういう能力の敏感な人が、シャーマンや預言者と呼ばれ、世の中の理屈が今ほどわかっていなかった時代に重宝されたのだと思います。そして、人の力ではどうしようもないことや理解出来ない事を、神な業としたのでしょう。私は、特定の宗教を信奉しているわけではありませんが、神の業は信じているし、魂の甦りも信じている。ヨチヨチ歩きの時から教会に通い、小学校では日曜学校で遊び、中学でそういう濃い教育を受けたからだと思う。小学校の時だったか、幼稚園の時だったか、アラスカの物語か何かに触れたとき、「僕、ここ知ってる」と感じたことがあるので、それ以来前世はここで生活していたんだなと思うようになった。いろんなことを自分の意思で、始めたりするが、どうもそうするようになってたんじゃないかなと思うところがある。赤ちゃんの時の大病は、母親の知識で助かったし、次男の小学校の時の交通事故も、自転車に乗ってて車に飛ばされたのに、車は突っ込んだのが後輪の足は大丈夫で、飛ばされて落ちたスグ横に電信柱があったり、頭をぶつけていても不思議がない。長男の交通事故も、私のワンボックス車と交換していたから助かった。彼の車だったら、トラックに踏んづけられていたんじゃないかな。太古の昔から脈々と続いている生死のどこかで私の先祖が切れていれば、ここに私はいない。私の存在そのものが奇跡で、目に見えない何かが、私を生かしているように思う。昨日、仕事場の前の道で、携帯電話に向かって延々怒鳴っている人がいた。待ち合わせに来なかったようで、怒っていらっしゃる。私は、上記のような考えがベースにあるので、その光景を聞きながら、「会えて車に乗ったがために、ぶつかって怪我をしていたかもしれないし・・・そんなに怒らなくても・・・」なんて、思っていた。私なら、「忘れてたんだ。じゃあまた今度ね」ぐらいしか言わないだろう。やっぱり私って、変なんだろうな。うまく事が運ばなくても、そういう風になってたのかって、悔しいけど落ち込むというところまでは行かない。子供達に対しても、彼らを守って動かしてる何かとてつもなく大きな力でそうしようとしているのだからと、ただ一緒に遊ぶだけで何も言わずに、彼らの行動を見て楽しんでいる所がある。
2006/09/02
コメント(6)
-
ビームライト の巻
昨日の日記に漁船の高速化を書きましたが、象徴的な光景を見たことがあります。はっきりとは分かりませんが、今は1隻で漁をするのはどちらかというと少数派なのかもしれません。大体、数隻で船団を組んで漁をします。海を走っていて、漁船を見つけたら、僚艇を捜して、網を引いている具合を予想します。数隻で1つの網を引いて、追い込み漁をしているときもあります。誤って、網の中に突っ込んでしまうと、えらい迷惑をかけてしまいます。最近の漁船は、漁師さんの勘に頼るのだけではなくて、ハイテク装置で効率のいい漁をしています。高い確率で、好漁場を見つけられるので、早くその場所を確保するために、船団同士のスピード勝負になります。随分前に、夜中の3時とかに大阪湾にいると、神戸や明石の方から、すごく明るいスポットライト(強烈なビームライト)を前方に向けたボートが、グングン和歌山の方に向かうのを見ました。最初見たときは、海上警察の取り締まりかな? と思いましたが、近づいてくるのを見たら、細い船型のいかにも速そうな船でした。「あれ、何か知ってる?」と一緒に乗っていた海のベテランさんに聞かれましたが、分かりませんでした。船団の中の、場所取り専門の船だそうです。だから漁具は乗っていません。「巡視船だろうが、全く追いつけないよ」とのことです。確かに、爆音を響かせるパワーボートに匹敵するスピードで、海を切り裂いていきます。数年前に、北朝鮮のカムフラージュ漁船の追跡劇がニュースに流れましたが、あれよりずっと速かったと思います。各漁協間に、出漁時間とかの暗黙の了解があるとかで、それがこう言うスピードボートに繋がったと、教えてもらいました。1つスポットライトが点くと、あちらにもこちらにもスポットライトが点灯し、それぞれが猛烈な速さで和歌山沖の漁場を目指して競争です。凪いだ暗い海に、数本のスポットライトが走る様は、中々見物です。そういう船がのが数艇行き過ぎた後、しばらくしてから、よく見る漁船がそれを追って行きます。これでもかなり速いのですが。あんな夜遅く、というか朝早く、海の上で何をしていたのか覚えていません(多分釣り?)が、普通の陸上の暮らしをしている私には、かなりラッキーな遭遇だったと思います。風が強く波が立っていれば、もう少し遅く走るだろうし、数船団が急いで目指す好漁場の存在がなければ、そういうのもなかったと思います。
2006/09/01
コメント(4)
全20件 (20件中 1-20件目)
1