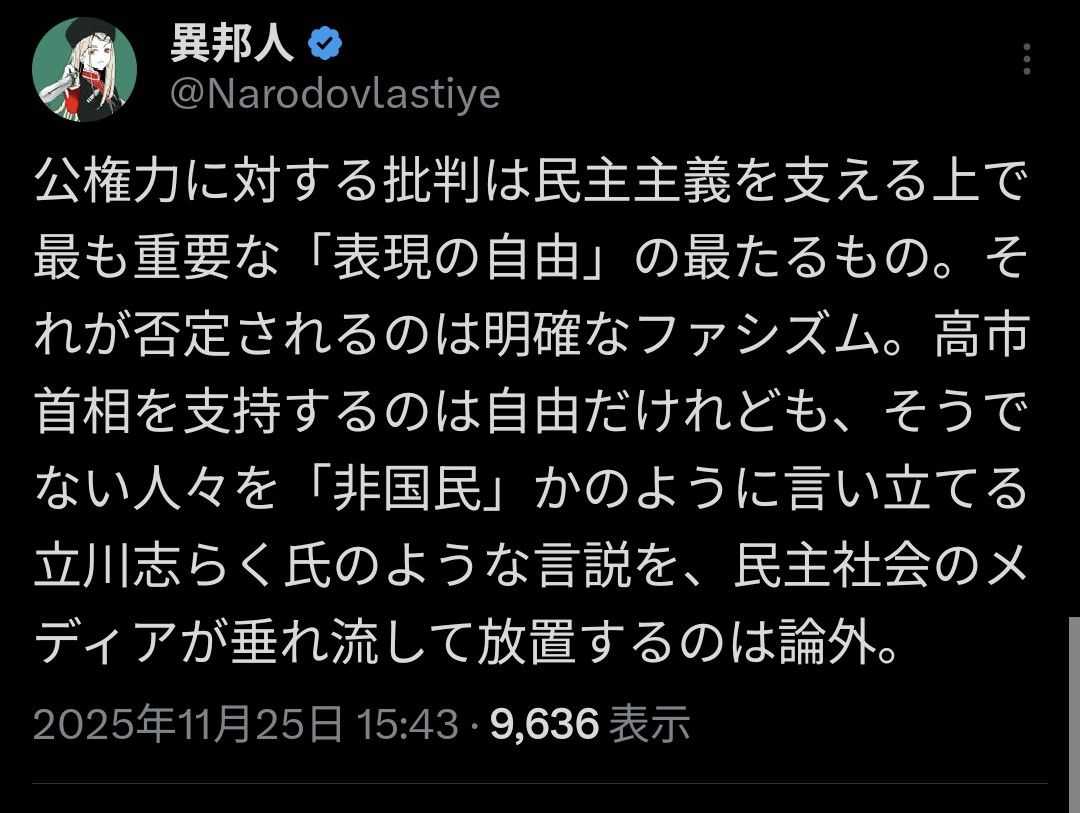2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年12月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
また来年 の巻
2006年も終わろうとしています。今年もいろいろあったが、最も考え感じたのは、人の生き方のように思う。私はどうも結果より、そのプロセスに心を動かされるようです。一生懸命だったり、不運で落ち込んでも再び立ち上がり前を向いて歩き始める姿であったりに惹かれる。結果には、結構淡白だと思う。そう考えると、NHK大河ドラマになるような司馬遼太郎より、藤沢周平の下級武士の心意気により惹かれるのも納得がいく。藤沢周平の描く男、特に武士はいいが、女性の方がより凛とした生き方をしている。より即物的で結果重視になり、持っている物の多寡で人をランキング付けする風潮の強まった現代人が、忘れてしまった日本人の美しい心に惹かれているのかもしれない。今年は、再び新渡戸稲造の「武士道」が売れたようだ。ハリウッド映画「ラストサムライ」で、英国の騎士道に通じる日本の武士道が脚光を浴び、昨年の藤沢周平「蝉しぐれ」も後押ししたのかもしれない。「武士道」の中で、新渡戸さんは、かつて士にとって最も重んぜられたのは廉恥心であると記している。『武士の教育において守るべき第一の点は品性を建つるにあり、思想・知識・弁論等知的才能は重んぜられなかった。廉恥心は、少年の教育において養成せれるべき最初の徳の一つであった。虚言遁辞はともに卑怯と看做される』かつて武士の精神的支柱を支えた考えが、藤沢周平の登場人物の生き方に描かれ、未だに多くの人の心を打つようだ。藤沢作品の映画「武士の一分」が日本アカデミー賞を総なめしたのもうなずける。世知辛い世の中になってきたからこその回帰かもしれない。品性のない勝利、品性のない生き方は、人から共感を得ないし、社会を良い方向に向けないと思う。今年は、久しぶりに甲子園ボールで母校を応援してきた。残念ながら法政に負けてしまったが、その後神戸新聞の記事を読んでいると、のコーチが決戦を前に選手にある詩を披露したと書いてあった。その一節を読んで驚いた。それは、ヨット部の部訓そのものだったからです。現役時代の総監督だった故Kさんが、ヘルシンキオリンピック出場の土産として持ち帰ったドイツ人スポーツ哲学者カール・ダイムの著書の一節で、ヨット部のウェブサイトにも載せている。立ち寄ったヨットハーバーの壁に掛けてあった言葉に感銘を受け、著書を持ち帰り、独学で翻訳した言葉。現役時代、いつもこの言葉が壁にかかっている艇庫で寝起きした。勝利を目指したが、この部訓に恥じる行為のないよう、全員で部訓を唱えた。何度も書き換えられ、今も同じように艇庫に行けば、すぐ目に付く。ヨット部の部訓を最後に、今年の日記を締めくくろうと思う。『如何なる闘いにもたじろぐなかれ但し偶然の利益には 如何なるものでも騎士的に潔く棄てよ最強の相手を求め、彼を汝の友とせよ威張らず、誇りをもって勝て言い訳をせず品位をもって負けよ 勝利より大切なのはこの態度なのだ汝を打ち破った者に最初の幸福を汝が打ち負かした者には最初の感激を与えよ汝と汝のチームに対して願うべきはただ一つ 常に最善の者が勝つことを汝の身体と精神をそして心構えを常に清潔に保て汝自身の汝のクラブのそして汝の国の名誉をけがすなかれ』自分に、そして我が子に、この気持ちで接してきたつもりです。仕事場のいつも食事する所の正面にこの言葉を飾っている。毎日目にして、恥じない生き方をしようとしている。どうやら、いずれ新しい家族を作るだろう子供達も、こういう生き方が出来ているように思う。また来年も、このように生きたいと思う。
2006/12/31
コメント(6)
-
インクジェット官製はがき の巻
インクジェット用の官製はがきを買ってきました。義理母の喪で、年賀状が出せなくなったので、その代わりにするつもりです。例年なら、12月に入ると年賀状を製作し、20日過ぎには投函していたのですが、母の状況がよくなく、PC製作だけしてプリントアウトをギリギリまで先延ばししていました。年賀状の購入も先延ばししていました。家内に相談すると、「わからないから、もう出しちゃえば」という返事でしたが、「でもなあ・・・」と、この状態にしていました。私の年賀状は、前年の我が家の出来事を書けるだけ書く、読む年賀状です。写真にフィルターをかけて白っぽくしてハガキ大にして、その上に文字を書き込みます。私が年賀状をもらった時、年始の定番文句だけのものは、この方に年賀状を出したっけと考えるだけです。写真の載ってるものや、文字の載ってるものがあると、嬉しくなります。自分が出すのもこうなるだろうからと、我が家の近況を面白おかしく書くスタイルに変更しました。もう10年ぐらいこのスタイルです。そうすると、久しぶりに会おうかと電話があったり、会ったとき我が家の話題が呼び水になって話が広がったりして、いい感じになりました。久しぶりに会う遠くの親戚も、子ども達の進学やら趣味やらを知っているので、「この子がヨットやってる子やねえ」とか「ライフル、まだ続けてるの?」なんて。来年のは、既に作っていた定番の挨拶部分を、年賀状を失礼させて頂いた旨の事に変更して、その後はいつもの家族の近況報告にしました。写真は、次男の全日本でカメラマンさんが撮ってくれたヤツです。あとはプリントアウトするだけですが、年が明けてから投函することにしました。
2006/12/30
コメント(2)
-
母 の巻
クリスマスの朝、6時半には仕事場に着いて、仕事を始めていました。一通り、この日の価格などの設定変更を終えて、いつもの朝のお勤めのために本を読んでいると、電話の呼び出し音です。始業前でもあり、まあいいかと放っておいたら、5回の呼び出しで切れました。「あれ、これは・・・」嫌な予感です。店同士の連絡は、接客中の事も多く、FAXのやり取りが主ですが、電話をする場合は、5回で切るように決めています。この時間帯、5回で切れるのは、家内からの連絡のようです。再び呼び出し音が鳴り、今度は1回で切れました。これはFAXに自動切換えになったようです。お勤めから出て電話のところにきてみると、「様態が急変したようです。病院に向かいます」・・・・・・私の父ではなく、家内の母のようです。1週間前に病院に行ったときは、自分で足が上げられるようになったと喜んでいたのに、私は仕事で家内だけが行ったクリスマスイブの日は、家内を認識できていないようだったそうです。そして翌朝のクリスマスの日に・・・家内の店の人の手配をして、慌しく開店後のバタバタをしていると、再び電話が入り、「ダメだったわ」と家内の泣きながらの声が聞こえてきました。とっさに、何も声をかけることが出来ず、ただ、「ああ・・そう」と言っただけでした。すぐに子供達にメールを入れ、母も店をしていたので、向こうの従業員さんも連絡しているだろうが、こちらからも連絡すべく、連絡先リストを作りながら・・・涙が・・・止まらなくなりました。お客さんに失礼なので、店の奥のほうに引っ込みながら作業をすることにしました。子供達から連絡が入ります。次男は、車ですぐに向こうに向かいます。東京の長男は、この日からの出張をすぐに段取りつけて、急いで帰るとのこと。「年末で大変やし、多分明日のお通夜に間に合えばいいよ」と言うと、「何、言うてんねん。僕のお婆ちゃんやねんで」と一言でした。午後には、葬送の日程が入り、各取引先、うちの方の親戚にそれを流しました。翌日から、私も仕事から抜けることになるので、人の配置などをしていました。次男が昼から、長男が夕方から、喪主である義理兄・義理姉・家内を手伝いました。その日遅く、一旦3人は自宅に帰って来て、翌日からは家族4人で向こうに向かいます。仕事の関係で、家内と長男が朝一番に出発し、私と次男は遅れて出発。昨夜、全てが終わり帰ってきました。受け付けなどは、兄の医院の職員さんや母の店の従業員さんがやってくれて、ほとんど手間要らず、割合楽だったように思います。さらに、子供達が、婆ちゃんにとって孫達が、みんな一人前になっていたのが、私達を楽にさせました。特に、宴会隊長が特技の長男が本領発揮です。姉さんには、3人の子がいますが、2人は女の子でそれぞれ赤ちゃんを抱えていて戦力になりません。うちの子2人と、その2人の間の年の姉さんの子の3人ががんばりました。うちの長男は、最後の夜、寝ずに婆ちゃんに寄り添い、いろんな段取り、そして親戚の集まる場を和ます会話と、親から見ても光っていました。親戚から、お嫁さんを斡旋されそうな雰囲気でした。元々、そういう性格ということもありますが、彼はかなり株を上げたはずです。ついでに私達夫婦も褒められちゃいました。会社勤めはまだ1年になりませんが、新薬の臨床担当病院を回っているので、よりしっかりしてきているようです。体育会クラブの主将経験も役立っているように思います。OB会の大先輩方との対応もそつなくこなせるようになり、今回見ていても年配の方にも気軽に声をかけ、お婆ちゃんに気に入られていました。婆ちゃんの肉体は、いなくなっちゃったけど、がんばる力と周りに温かい心は、2人の娘を通して5人の孫に伝わって、息づいているように感じます。既に3人ひ孫がいますが、これからひ孫は更に増え、婆ちゃんの心は広がっていくでしょう。
2006/12/28
コメント(6)
-
ゆずのお風呂 の巻
昨日、お風呂に入ると、ゆずが数個浮いていました。そうか、ゆず風呂の日か。冬至。これから寒さはさらに増しますが、昼の長さは確実に長くなっていくな。春に向かって、何かいい感じです。ゆずのいい香りに包まれて、湯船で本を読んでいました。お気に入りの藤沢周平です。でももう新作が出ることはなく、惜しむように間隔をあけて読んでいます。いつものようにヨーグルトを抱えてTVのスイッチをひねると、これまた藤沢周平の「たそがれ清兵衛」の映画がやってました。最後の30分ぐらいでしたが、見入ってしまいました。映画としては、いいんだけど・・・いいんだけど、どうも引っかかります。山田洋次監督の藤沢周平は、好きになれません。他の作品の登場人物とごっちゃにして、「たそがれ・・」の原作と違いすぎます。もっとシンプルで、シンプルだからこその深さを感じるのが、私が藤沢作品に惹かれるところです。所詮原作と映画は別のものなのでしょうが、明治維新まででてきて、何か藤沢周平のある作品のエッセンスだけ抜き取られて、かわいそうだなと思ってしまいました。別の題名をつけて、参考として藤沢周平の各作品名を載せたらいいのにと思ってしまいました。「武士の一分」のように、原作の「盲目剣・・・」とは違う題名にしたらいいのに・・・大監督だから、自分の色が出ちゃうんだろうな。藤沢作品は、山田さん以外で、「蝉しぐれ」のように原作に忠実に作って欲しいと思います。お風呂で読んでた本も、数日で読み終えるでしょうが、映画になったらいいなという作品がありました。「三月の鮠」
2006/12/23
コメント(6)
-
わかったぞ の巻
日本アカデミー賞優秀賞の発表で、「武士の一分」がいろんな賞を総なめぎみだそうです。その中で、キムタクさんの奥さん役だったあの人・・・が壇れいさんという名前だということを知りました。宝塚歌劇団出身だそうです。さすがに、落ち着いた演技をしていました。以外だったのは、35才という年齢。28才ぐらいじゃないかなと見えました。ミスユニバースなどの美人コンテストに選ばれるような雰囲気の美人です。私は、もう少しかわいらしさが入ってる方が、好きですがね。娘役トップで宝塚を退団したそうなので、これぐらいのお年になるのでしょう。これからですね。中学・高校に通う沿線に宝塚があるので、あそこの生徒さんは毎日たくさん見ていました。制服をきちんと着こなし、崩れた感じがなく、スッとしています。電車で座っちゃダメなので、みんな立っていました。色はグレーの淡い色ですが、サファリ帽みたいな制帽で、同じ色の2ピースの制服です。同じ沿線に、関西の女子私立中学で一番偏差値の高い神戸女学院があり、こっちは制服がないので、対照的でした。先頭車両が、聖心女子中高の子達を加えて、3校の生徒が乗る車両になっていました。今のように、女性専用車両ということはありませんでしたが、あの車両に男が乗るのには勇気がいります。宝塚の子は、男女交際禁止なので、聖心か女学院にGFがいる男の子だけが、先頭車両に乗る感じです。私も先頭車両に乗りたくて仕方ありませんでしたが、こればっかりは・・・宝塚の子は、勉強の他に踊りから歌、毎日厳しく鍛えられます。うちのお客さんに、宝塚歌劇団を最近退団した人がいますが、芸能プロダクションに所属して、仕事で全国を飛び回っています。おしゃべりの仕事だったり、大物歌手の舞台俳優だったり、聞いていると面白い話もありますが、決して練習や仕事を休まない姿勢を感じます。歌劇団の時は、宝塚公演が終わると東京公演が始まり、その間に次の公演の練習だとかで、歌舞伎役者さんのようなハードさでした。宿命かもしれませんが、ストーカー対策もしていました。そういうのを、明るくニコニコしながらしゃべるんですよね。芸とともに、人格も鍛えられてる感じがしました。壇れいさん・・・頭の隅に置いておきます。
2006/12/22
コメント(6)
-
祖母井さん の巻
日本経済新聞のスポーツ欄の「スポートピア」というコラムに目が止まりました。この日は、Jリーグ千葉GMの祖母井秀隆さんでした。どんな人なんだろうと、興味のあった方です。祖母井さんは、現日本代表監督のオシムさんを千葉の監督に引っ張ってきたGMです。オシムさんの著書でも紹介されており、当時レアルマドリードなどのヨーロッパの大クラブとのオシムさん争奪戦で勝利しました。Jリーグで一番予算の小さな千葉が、何故レアルなどに勝てたかというと、祖母井さんの熱意と行動力でした。オシムさんの自宅などを訪問し、熱心に誘いました。オシムさんは、旧ユーゴ出身で、最後のユーゴナショナルチームの監督です。内戦によって、奥さんや子供さんと離れ離れになり、数年間安否もわからない辛い時代をくぐってきました。祖母井さんの熱心さと行動力が、サラリーとは違うところでオシムさんの心を捉えたのだと思います。『JリーグのJEF市原・千葉に、お世話になって12年が過ぎようとしている。私が10年勤めた大学を退職し、サッカーのプロの世界に飛び込んだのは、ちょうど阪神大震災が関西を襲った年である。実家は全壊し私のアパートも半壊した。この地震によって私が生まれ育った神戸は破壊され、私も知人を失った。そんな状況下でJEFへ行くのは正直言って相当迷った。プロの世界は厳しく、結果が出なければファン、親会社、そしてメディアからも徹底的にたたかれる、言い訳が通用しない世界である。妻に相談したら、私の仕事が子供の育成をサポー卜するような内容だったので、すぐに理解してくれた。私はなお複雑な気持ちだったが、未来ある子供たちの役に立てるのならと結局、JEFに行く決心をした。最近、折に触れて思うのは、今、私たちが生活している環境のことである。私には到底理解できない事件が毎日のように起きている。私にはそれら社会問題が、今日の倫理なき経済競争の所産に思えてならない。ヒューマニズムは脇に置かれ、エゴイズムというか自己中心的な社会に急激に変化し、みんなで助け合って生きてきた時代から個人で生きていかなければならない厳しい時代になってしまった、と。皮肉なことに、そう思う私が毎日接しているプロの世界とは、勝ち負けだけが問われる無慈悲な競争社会である。勝者のみがたたえられるプロスポーツの風潮は、今の社会の流れを後押ししているのかもしれない。諸般の事情でユース年代の育成から、切った張ったのGM稼業に軸足を移した私には内心、恍恨(じくじ)たる思いもある。妻がカトリック教徒ということで時々、教会へ行くことがある。どの教会にも、みんなで助け合って生きていこうとする雰囲気がある。多くの人々がいろんな分野に関心を持ち、因つている人たちに温かい事を差し伸べようとしている。私は今年限りでJEFを去り、フランスのグルノーブルで新しい職に就くことになった。JEFでやり残したと残念に思えるのは、そのような平和的な雰囲気をつくれなかったことである。クラブの強化や運営だけではなく、人としてしなければならないことが何かをスタッフや選手、あるいはファンに対して十分に問いかけられなかったことである。これから21世紀のスポーツに必要なのも、過激な競争社会から失われつつある人間的な営みをスポーツを通じて取り戻すことだろう。JEFも同様で、やみくもに優勝だけ目指し、人間的な温かさを失うようなことがあれぼ、意味のない活動になってしまう。最後に、JEFを愛するファンヘ、人に愛されるクラブづくりをサポートしてください。これまで長い間、ありがとう。』オシムさんの著書では、祖母井さんの熱心さは書いてあったが、本当に心動かされた人間性や雰囲気については、載っていなかった。そういう何かが、このコラムを読んで少し分かった気がした。奥さんがカソリック信者ということで、教会のあの雰囲気も、祖母井さんに影響し、何より奥さん自身が大きな影響を与えているのだろう。私は、学校に上がる前は、母に手を引かれてカソリック教会に行き、小学校時代は、日曜学校と称するプロテスタント系教会で、礼拝した後友達と遊んでいた。中学はプロテスタント系だったので、毎日礼拝と日曜日には地元の教会に通った。教会というのは、仏教でも同じなのだろうが、キリスト教の教義を教える場ではない。地域の集会所なんだと思います。賛美歌を歌い礼拝はするのだが、献金があり、寄付活動のお知らせもある。牧師さんの他に、地域の人の話がある。学校の礼拝では、時々各界の一流の方の話や芸能などがあり、これがとても面白い。阪神大震災で被災して家を失った親戚のおばさんが、うちに来ずにずっと通っていたカソリックの互助精神に身をゆだね、一信者さんの家に厄介になったのも、カソリックにしっかりしたコミュニティーがあったからだ。おばさんと言っても、もう80才を越えているし、関西に2軒ある親戚の1軒は被災して同じく家を失っている。唯一の1軒がうちです。うちも被災しているが、住む家はある。おばさんの個室も用意できる。私も家内も、話し合う以前におばさんを迎える意思は決まっている。隣には、より年齢の近い私の両親も住んでいる。うちに来るものとばかり思っていた。でもおばさんは、同じ教会の一信者さんの方を選んだ。その方の家にお邪魔し、ご夫婦にも会ったが、夫婦でカソリック信者さんで、お金の事など何も出ずに、辛い人がいれば助けるのが当然という感じでした。価値基準が違うと感じました。「よろしくお願いします。何かあれば、うちまで連絡ください」としか言えなかった。今のように健康保険や年金がない時代のより所が、このコミュニティーで、そういう人を助ける行為を是とする精神的基盤がカソリックが提供していたというわけだと思う。辛い世の中を生きていく中で、教会のコミュニティーに所属することで、心の平安を得ていたのだと思う。イスラム教にも、仏教にも、長年人々を惹き付けてきた宗教には、そういうのが脈々と伝わっているのだと思う。私も祖母井さん同様、このまま競争が讃美される社会が進むと、一部の勝者と多数の敗者の社会になってしまう感じがする。勝者とて、それを維持するために、激烈な競争を続けなければならない。競争から降りれば、それは敗者への道なのだから。フィリピン・インド・・・2極化した社会の大多数の敗者の生活は、あまりに辛いものです。1970年代の日本が、最も優れた社会システムを持っていたように思う。バブルやその崩壊は、社会システムが問題だったのではない。その再生のために、金融機関が被ったマイナスを、規制緩和で弱者を切り捨て、強者の間での効率のいいシステムに変更した。商売をしているので、上得意さんにお客さんを絞ると効率は良くなるのは分かっている。そういう上得意さん向けの施策をしながらも、一般のお客さん向けのものもしていないと、いずれ会社の活力が減退するのが現実。一企業が顧客を絞っても社会全体に及ぼす影響はまずないが、能力のある人もそうでない人も抱える責任がある国がそれをすると、滑り落ちて生きていけない人の反発が、犯罪などの形で起きる。フロンティア開発にまだ余裕があるアメリカの競争万能システムは、共存共生社会の日本には合わない。ヨーロッパ諸国が、規制強化に進んでおり、福祉国家の北欧諸国が経済的にも強いことも見なければならないと思う。1970年代の日本が、終身雇用・年金の充実で、真面目にやっていれば安定・安心した生活が送れていたのと、北欧福祉国家は同じなのではないか。明日の生活の安定が予想できると人は優しくなる。「中学生が集団で、お年寄りのバッグをひったくる」これは、弱肉強食を是とする道にハンドルを切った日本の大人の行く末を暗示していると思う。今の中学生が、いずれ大人になることを忘れてはいけない。子供の行動は、大人の行動の縮図。子供は、大人の行動を敏感に感じる。
2006/12/21
コメント(6)
-
22世紀も夢じゃない の巻
朝、TVを見ていると、六甲山の山の中で、3週間も飲まず食わずで生き延びた方が会見をしていました。何故、これほど長い間生き延びられたのか不思議です。お医者さんの話では、急激に体温が下がり、すぐに冬眠状態に入ったからだそうです。何と、その体温が22度だそうです。海や冬山遭難なんかだと、生命を維持するために、手足の血行を遮断し内臓と脳を守るそうです。だから、凍傷を負うような状態の方の手足を急激にさすって、いきなり手足の血行を復活させると、手足のより低い血液が内臓や脳に流れ、心臓発作を起こしそこで死亡したり、脳の障害に繋がります。こういうのは、スポーツ指導者資格の勉強で習ったし、海で遊ぶ者の心得として知っています。体温30度で意識を失い、25度はもう死体の体温ですので、仮死状態が3週間続いたということです。「脳の障害もない」ということで、遭難者本人がごく普通に会見していたので、驚きました。遭難翌日、天気がよく、気持ちいいなと思ったのが最後、眠りつづけていたようです。これを見ながら、SF小説「夏への扉」を思い出しました。1970年代の作品ですが、米軍の一個師団をアラスカの氷の下で温存するという軍事技術である冷凍睡眠技術が民間に普及して、保険会社が実用化しています。主人公は、共同経営者の裏切りのショックで、2000年に蘇生する契約で、1970年に冷凍睡眠に入ります。2000年には、タイムトラベルが実験段階ではあるが存在していて、主人公は再び1970年に戻り、反対に共同経営者を出し抜き、再び冷凍睡眠で2000年に戻ってくるという物語です。このSF小説から遅れること100年、2070年ぐらいになれば、安全な冬眠技術が民営化されているかも・・・何て思いました。もしそうなれば、この日会見を開いた○○さん、後年、冬眠技術の父とかいう立派な銅像にでもなってるのかなあ・・・もう少し技術の進歩が早ければ、私も22世紀を迎えられるかもしれない。でもお金がいるなあ。ビルゲイツなら、実用化前でも、大金を積んで喜んで体験者になるのではないか?やっぱりスタントマンの度胸も必要だから、ジャッキーチェンの方が先か?こういうのはNASAが、技術独占しそうだから、向井さんが日本人第一号かも?空想を膨らませながら、楽しい通勤になりました。
2006/12/20
コメント(2)
-
笑顔の側転 の巻
日曜日は、甲子園球場に行ってきました。高校野球でもなければ、タイガースのイベントでもありません。ジャニーズ系の運動会なら、違う意味で楽しかったのかもしれませんが、それでもありません。母校の校技でもあるアメリカンフットボールの大学日本一を決める「甲子園ボール」です。最近の宿敵Ritsさんを4年ぶりに破って、4年ぶりに甲子園ボールに駒を進め、日本一にチャレンジです。西宮の地元だけあって、ヤクルト横浜戦よりは多いのではないか、楽天オリックスよりは確実に多いと思われるお客さんが集まりました。キックオフ1時間前に着いたKG応援席では、チアリーダーさんが、スクールカラー・ブルーの応援ハリセンを配っています。前の人の頭をハリセンしないように注意しなければなりません。クラブの先輩方10名ほどで陣取っていたので、鼻の下を伸ばし気味に「ハーイ、ください」。母校ロゴ帽子をかぶった人やロゴシャツの方もいました。ヨット部のOBは他にも多数来ていたようですし、中学からの同級生にも会えました。プロ野球の試合では味わえない大学スポーツの雰囲気は格別です。私のヨット部現役時代は、甲子園ボールが決まる秋のリーグ戦最終戦は、クラブの練習をやめて、全員で部旗を持って試合の応援に来ていたほどのアメリカンキチの集まりでした。この日も先輩方は、母校のチャンスに思いっきり盛り上がり、反対の場合はシュン太郎で、周りの人達に笑われていました。でも担当の先輩が干物を忘れたおかげで、七輪を囲んでの宴会が始まらなくて良かったです。七輪と網を持ってきた先輩は、「なんで干物忘れるねん。メールに書いてあったやろ」と言うし、干物担当の先輩は、「スタンドでできるわけないやろ。あんなもん冗談に決まってるやろ」って、漫才をしているようでした。聞きながら笑うしかありません。横の通路には、兵庫県警さんがいてはりましたから、七輪など出し始めたら、間違いなく逮捕されていたでしょう。皆さん、ウィークデーは難しい顔してそうやのに、その反動でしょうか。横で笑顔で見ている奥さん方は大人やなあと思いました。家内と一緒に行かなくて良かったです。「あんな人達と縁を切りなさい」と言われそうでした。試合の方は、法政の最初のワンプレーでタッチダウン取られ、いきなり第1クォーターで2タッチダウン差の14-0です。後半追い上げ、押せ押せムードになってきたところでカミナリが鳴り、数十分の試合中断になってしまいました。再開した雨中の熱戦で法政が息を吹き返し、45-43であと2点追いつけませんでした。試合には負けましたが、前のチアリーダーさん達は、ずっと動き回っていました。まるで体操選手のように、肩の上に乗って、さらにその上に乗って、人間3段ピラミッドを笑顔でやってました。一番上が、後に倒れ、ちゃんと下で数人が受け止めます。あれをサッサッと笑顔でやるからすごいです。一緒に応援してた先輩の友人の娘さんは、去年まで母校チアリーダーをやっていて、親父さんは大きな車を買い、彼女達を満載して試合会場や練習に送迎していたそうです。我が息子のヨット運びより、何倍も魅力的な仕事です。もう1人、女の子がいたらよかったなあと、いろいろいいように想像しながらの帰りでした。「お父さん、ファイト」なんて言いながら、あの笑顔であのコスチュームで側転されたら・・・ところで、何故か私が網持って帰ることになりました。「次、網使う時持って来いよ」って、無理して奥さんに買いに行って貰った手前、綺麗なままでは持って帰れないのでしょうが、私だって干物焼くさらの網だけ持って帰って、相方さんの「あんた、今日何してきたの?」の質問に何と答えりゃいいのさ。ということで、車の中に隠しておくことにしました。七輪も押し付けられなかったのが、せめてもの幸いでした。
2006/12/18
コメント(8)
-
出口はある の巻
朝日新聞の連載「いじめられている君へ」この日は、漫画家松本零士さんでした。お題は、『夢は大きいほどいい。人生を支えてくれる』『あなたはいじめられて悔しい思いをしているだろう。涙を流しているかもしれない。その涙は恥ではない。有史以来の英雄むどんな人でも、泣いたことのない人など、ひとりもいないはずだ。絶望しないでほしい。いつか笑う日がくることを信じてほしい。あなたの人生ははじまったばかりだ。目の前には、時間という宝物がある。無限大の可能性が届る。未来は両手を広げであなたを待っている。人はみんな何かをなしとげるために生まれてくる。それぞれ果たすべき役割がある。自分は何のために生まれてきたのか。それはいまわからなくてもいい。必ずわかるときがくる。いずれ、自分はこうなりたいという夢が見えてくる。それが、どんなに大きな夢でも恥ずかしがることはない。夢は、欠きければ大きいぼどよい。年をとればとるぼど、夢は縮んでいく。だから夢の土台は大きくかまえなければいけない。あざけられたり、ひやかされたりしてもかまわない。いちど見つければ、あとは夢があなたを支えてくれる。だれに何を言われても気にしなくていい。大人には時間がない。あなたにはある。なにより自分の人生は自分で決めるべきものだ。さびしくなったら、ひとりばっちではないことを思い出してぼしい。お父さんとお母さんがいたから、あなたがいる。お父さんとお母さんも、そのお父さんとお母さんがいたから、生まれてきた。あなたの体の中には、ものすごい数の先祖代々の思いと夢がつまっている。あなたは、それほど多くのものを受け継いでいる、とても大切な人間なのです。』「人は何かをするために生まれてくる」「決めるのは自分」通った中学で教えてもらい私を救ってくれた言葉と同じように感じました。「神様は、世の中に必要な人にしか生を与えない」「あなたの心に浮かんだ・・したいは、神様からあなたへのお願いです。それがどんなに大変そうなことでも、自分の心に素直に従えば、神様から約束されたあなたの一番輝く場所に導かれます」私はこのように教えてもらったけど、同じ意味ですね。私の場合は、親からの「もっと、もっと、・・・」という期待に応えられず、自信を失い、自分をダメなヤツだと能力の縮小を起こし、ナイフを眺めて安心する人間になっちゃったけど、自死したり引きこもりしたりする子の気持ちが、何となく分かる気がする。私に中学の先生がいたように、きっと出口はあります。いじめによる居場所喪失、期待に答えられない不甲斐なさ、漠然とした将来への不安、いろんなことから逃れようと自死を選ぶ中学生高校生、後数年すればそれらが気にならなくなります。あと少し、もう少しなんだけど・・・
2006/12/16
コメント(6)
-
心とリンク の巻
日曜日、義理母の入院している病院を訪ね、毎日曜日夕食まで義理母に付き添う家内と分かれ、荷物を積んで家に帰って来ました。家に戻り、玄関のクリスマス電飾スノーマンをゴソゴソ動かしていると、コードがおかしくなりました。これはやってしもたかな?とコンセントを入れると、やっぱり電気がつきません。配線を外し、スノーマン君を室内に持って入り、分解して断線を直していると、すっかり暗くなっていました。改めてスノーマンを現場復帰させ、電飾にスイッチを入れると、ベランダのピカピカも始まりました。道路からそれを見ていると、ちょうど歩いておられたご夫婦が、歩きながらですが、ずっと我が家を見上げてくれていました。少しは綺麗だなと思ってくれたかな?幸せな気持ちをちょっとお届けできたかな?と思うと、無性に他を観にいきたくなりました。ちょっとだけですが、自分の家もデコレートしようと思うきっかけになったおうちは、去年からもうやっていません。屋根にあがってデコレートしていたお父さんは、病気にでもなったのだろうかと心配ですが、他の定番の家をスクーターで回り、途中で新たなイルミネーションハウスも見つけました。幸せ・優しさ・笑顔・思いやり・温かさ・・・そういうのがその家から夜道に溢れてきているように感じます。サンタさんはすごいわ。これから何百年も世界一の有名人でありつづけるでしょう。病院からの帰り、家内の実家に寄って、もう使わないいろんな物を積んだのですが、近所に住んでいる義理姉が一緒でした。うちは遠いので、日曜日だけ義理母の世話に家内が行っていますが、その他の日は義理姉が行っています。僕らが付き合い始めたとき、義理姉は長女を抱えて働いていました。当時兄が学生だったからです。僕らと同じように、学生時代に知り合った姉夫婦は、卒業して結婚したのですが、兄は再び別の学部に入り直しました。僕らは片道4時間のデートで、姉夫婦の家まで生活用品や食料品を運びました。姉達の一番苦しかった時を知ってるので、姉は、私に対して気さくに話してくれます。母の様態を気にかけながらも、先週より良くなったと明るく話しています。それと、兄が、「今だけしか親孝行できないから、いくらでも休んだらいい」と姉を休ませてくれるそうです。兄は小児科なのですが、他学部卒業してからの入学だったので、医局などの学閥では異端で、大学での先が見えたので開業しました。その時の条件が、「姉が一緒に働いてくれること」でした。人当たりのいい姉を頼りに開業しました。今は、いろんな方が働いてくれていますが、やはり一番の頼りが姉です。「俺のことはええから、婆ちゃんの世話を十分したらいいから」と言ってくれるの、と姉は兄に感謝していました。母は、秋口まで第一線で店を切り盛りしていました。母が入院してからは、従業員さんに任せていました。でも、現場復帰を諦めて、お店を閉めることになりました。お店と住居が一緒だったので、家内と知り合ってからずっと通ったお店から商品がなくなり、がらんとして、さびしいものです。母にもしものことがあったら・・・と思って、年賀状の製作が進みません。義理父が亡くなったとき、財産分与はいらないと、私から母と兄夫婦に伝えました。母に何かあっても、姉夫婦にそう伝えようと思っています。というより、既に分かっているでしょう。兄夫婦がみんな決めてくれたらいいです。お金とか土地とかそんなのは要らないです。唯一大切なのは、家内の親戚との普通のつながりです。がんばり屋さんで、人に優しい人たちと親戚付き合いしているだけで、我が家の家族にも、特に子供達に大きなプラスがあるはずです。家系の品位って、とても大切だと思っています。そういうのを考えながら見て回ったイルミネーションハウスは、妙に私の心とリンクしました。
2006/12/15
コメント(10)
-
綺麗な人 の巻
「武士の一分」を観てきました。原作は、藤沢周平の短編です。山田洋二監督が撮った藤沢作品の前作「たそがれ清兵衛」同様、きらりと光る短編の掘り起しです。藤沢周平さんの作品は、短編でも読者を唸らせるので、題材には事欠かないのではないでしょうか。ただ、山田さんが撮ると、原作から離れた作品になるので、あまり好きではありません。熟慮され完成された作品を、山田風にアレンジされるのが、どうも・・・昨年の「蝉しぐれ」のように、原作を忠実に再現する方が、作品としてはいいと思うのですが。山田さんの藤沢作品前2作に比べると、アレンジが少ないということだったので、観にいきました。仕事の関係でいつも最終上映になるのですが、若い女性が多いのにビックリしました。時代劇なのに・・・キムタクさん主演の影響ですね。外人さんも多いなと感じました。映画「ラストサムライ」や、新渡戸稲造の「武士道」が英語版で売れているそうなので、日本の建前を大事にする恥の文化が注目されているからかもしれません。映画の方は、やはり原作から離れて、原作にないシーンや欠落したシーンが気になりました。随分前に読んだ短編なのに、結構覚えているものです。原作を知らなければ、どうってことないのでしょうが、原作の淡々としたスタイルの方が好きだな。尺八など効果音が多く使われていて、シーンを盛り上げていますというのが分かりますが、一昔前の映画スタイルに感じました。最近のは、音楽や効果音が減り、会話や自然の音、さらには沈黙をうまく使っていて、より深く伝わる感じがします。作り方に、今一満足できないけれど、原作のエッセンスは脈々と流れていました。いいですね、藤沢作品。NHK大河ドラマになる司馬涼太郎のヒーロー物もいいですが、少禄の下級武士家庭の真っ直ぐな生き方は素敵だと思います。主役・奥方・中間の3人がとてもいいです。中でも奥方さんが、落ち着いた雰囲気があり、綺麗で、目を引きました。藤沢さんの作品には、綺麗な女性が付き物ですが、いい配役だったと思います。知らない人ですが、私が知らないだけで、準主役ですかキャリアのある人だろう。きっと、この仕事でステップアップされると思う。いい映画でした。
2006/12/14
コメント(4)
-
子供の時見たドラマ の巻
「HOOT」カール・ハイアセン作を読みました。星1つです。帯に、「全米書店員が選んだ一番お気に入りの本」と書いてあります。ミステリー作家ハイアセンさんのヤングアダルト路線第一弾だそうです。出身地のマイアミヘラルド紙の記者として、ピューリッツァー賞候補に2度選ばれたという経歴だって。グリーンフラッシュという、カリブの島で見られる自然現象から知った『フラッシュ』というヤングアダルト作品が、あまりに痛快だったので、この本を購入しました。『フラッシュ』は、不法賭博の船からの海洋汚染、といってもトイレの汚物をそのまま海に流す行為を、主人公と妹が解決していくという筋立てでした。この『HOOT』は、パンケーキの全米チェーンが進出を予定している敷地に、保護鳥類に指定されているアナホリフクロウが生息する事を知った主人公達中学生が、それを守ろうとする物語ですが、そのやり方が『フラッシュ』同様、ユーモアがあり痛快で、警官や現場監督の登場人物のキャラクターも面白く、笑いながら楽しく読めます。変に真面目で眉間にしわを寄せた議論になりがちな環境問題を、こういう読ませる本で、子供達に伝えるというのが、アメリカの余裕だなあと唸ってしまう。この作家のアダルト向け作品も今度読んでみようと思う。一部抜粋しておきます。『一時間ほどして、うとうとしかけたところ、部屋のドアをコンコンとたたく音がした。母親がおやすみなさいを言いに来たのだった。披女はロイの手から本を取りあげ、スタンドの明かりを消した。それからベッドに腰掛けて、気分はどうかとたずねた。「ヘトヘト」ロイは言った。彼女は毛布を優しく首まで引き上げた。本当は十分すぎるほど暖かかったが、ロイはされるがままになっていた。母親とはそういうものだ。そうせずにはいられないのだ。「いい子ね。私達がどれほど愛しているか、よく分かってるわよね」うっ、いよいよきたぞ。ロイはそう思った。「でもね。今晩あなたが病院でしたことはいただけないわ。その子を救急治療室に入れるために、あなたの名前を使わせてあげるなんて・・・」「あれは僕の考えなんだ。あの子が言い出したわけじゃないよ」「親切心からしたのは分かってるの。でもやっぱる嘘は嘘。間違った情報を伝えることはね。これはとても大事なことよ」「うん、分かってる」「それにね、父さんもわたしも、あなたがトラブルに巻き込まれるのを見たくない。いくら友達のためでも」ロイは片肘をついて体を起こした。「あの子はきっと、本当の名前を言うくらいだったら逃げてたよ。僕はそうさせたくなかった。あの子は病気だったんだ。お医者さんに診てもらわなきゃいけなかったんだ」「それはよくわかるわ。信じてちょうだい」「熱で気を失いそうだっていうのに、あの人たち、次から次へとくだらない質問をしてたんだ。ぼくのやったことは正しくないかもしれない。でも、また同じ立場になったら、やっぱり同じことをする。絶対に・・・」ロイはやんわりと非難されるだろうと覚悟していた。しかし、母親はただ微笑んだだけだった。両手で毛布のしわをのばしながら彼女はいった。「なにが正しくて、なにがまちがっているのか境界があいまいな場面に立たされることは、これからもあると思うの。そのときには、心と頭が別々の判断を下すかもしれない。でも、いちばんだいじなのは、そのどちらにも耳を傾けて、自分にとってベストだと思う決断をすることよ」たしかにあのとき自分がしたのは、そんな決断だったとロイは思った。』親子で意見が違う場合でも、親の意見を子供に押し付けずに、判断基準とともに、自分で決めることの大切さを伝えている・・・アメリカの一般家庭の親子の関係は、現在でもそうなのだろうか?子供の頃見た、アメリカTVドラマの親子の姿が再現されているようでした。自分と違う意見でも、子供の考えを尊重する姿勢。自分で考えるように促す姿勢。自分もこうありたいなと思いました。
2006/12/13
コメント(0)
-
墓のない人生は、はかない の巻
日曜日は、また義理母のお見舞いに行ってきました。家内の実家から荷物を運ぶ用事もあったので、今回は車で向かいました。子供たちの手が離れ、家内と2人で車に乗っていると、子供が生まれる前の時間に逆戻りしたようです。でも会話の内容が、親達の体調の事など大分変わりました。まずお墓参りです。高速を下りて実家に向かう間にお墓があり便利です。お花やお水の入ったペットボトルを持ち、竹の林を歩いていると、風が強いので、葉っぱの触れ合うカサカサという音と、幹が当たる音かな?ポーンという音も聞こえます。その狭い道を抜けると、古くからある地区の小さな墓地に当たります。「何か変な音・・・怖いね」と家内が訊くので、竹が当たる音じゃないかなと答えながら、子供と2人で来たことを思い出しました。子供はいろんな悪さをし、世間様から怒られることで、社会を学んでいきます。世間や先生から、しっかり怒られたら、それ以上親が言うことはないですが、怒られもせずペナルティも受けない時があります。これは十分反省しないといけないなという時、2人でここに来ることにしていました。私は、どうも世間一般から言えば、相当甘い親のようで、子供を叱ったり小言を言うことはまずありません。不得手のようです。「爺ちゃんのとこに行くぞ」って、車で1時間半かけてここに来ます。手をつないで、懐中電灯を持って、夜中お墓に来て、ただ掃除して、手を合わせるだけですが、とても効き目があったように思います。車で他愛のない話をしていても、何故自分がお墓に行くのか分かっています。子供達も知ってる爺ちゃんの骨が、実際にこのお墓の下にあるというだけで、1人で自分と向き合うことができるのかもしれません。実際に子供と来たのは、2~3度だけですが、車を運転できるようになって、夜中に「お墓に行ってくるわ」って1人で出かけたこともあります。「これは反省しなきゃ」と思うことをしでかしたのかもしれません。入学の報告に家族で行ったこともありました。長男は就職が決まった時、1人で爺ちゃんに報告に行ってました。彼女とのデートで墓参りをしたのも聞きました。爺ちゃんの前ではごまかせないし、爺ちゃんに紹介することで正直になれるのかもしれません。不動で、無言のお墓は、現世に生きる家族の重しやより所なのかもしれないな。自分と向き合う場所なのかも知れません。私は、子供の時から先祖のお墓には幾度も足を運びました。小さな時は、親の真似で手を合わせていただけ、少し大きくなると「アレが欲しい。こうなりたいのでお願いします」という願いになり、最近は「家族無事でありがとうございます」という感謝になりました。今回は、父も義理母も入院中ですが、「どうか治して下さい」ではなくて、「家族無事でありがとうございます」と手を合わせて心で感謝しました。そのまま、親がいなくなることになっても、きっと同じ感謝の言葉しかお墓の前では浮かばないでしょう。「長い間、ありがとうございました」なのかもしれません。病院に着き、婆ちゃんに「来たよ」って声をかけると、じっと私を見ながら「あんたんとこも大変やのに悪いねえ」って、うちの父親への心配の言葉が返ってきました。このお母さん、好きなんですよね。家内と知り合ってすぐに実家に行き、お母さんと話して、なんて素敵なお母さんだと思いました。家内は親から叱られた記憶がないらしいです。いつもニコニコして、でも仕事はしっかり出来て、綺麗にしていようとしてて、家庭に温かさが溢れていました。家内の家が羨ましく思うとともに、家内はきっとうちの家庭もこの雰囲気にしてくれると確信したものです。病院で婆ちゃんの足をさすりながら、「むくみ、大分引いたねえ。ようなってるねえ」って声をかけると、「足も上がるようになったよ」って、嬉しそうに足を上げてくれました。1週間前は、足動かなかったんですよね。今、お姉さんが買って来た本読みと百マス計算のドリルを1行するのが日課です。20代は教師だったので、かつて教えていたドリルを、今やってる感じかな?私は荷物を車に積んで先に家に帰りましたが、遅く帰ってきた家内は、「おかしいのよ。突然2たす2は4、3たす3は6なんて言うの。でもね、2たす3みたいなべつの数字の計算は難しいみたい。それはちょっと難しいわね、近所に住む家内の姉さんが相手の時は、ヒントをくれるのに、って私に言うの、おかしいでしょ」って笑顔で話してくれました。ほんとは、実の母親なので、悲しく辛い光景のはずなのに、楽しそうに話す家内を見ながら、また好きになってしまいました。あの母にしてこの娘ありってとこです。がんばり屋さんでやさしい子供にも恵まれ、私はかなり幸せな人生のようです。この家内と、このお母さんからもらったもののように感じ、思わずハグしてしまいました。
2006/12/11
コメント(8)
-
自分で感じて の巻
「勝ち組、負け組」「負け犬」これらの活字が目に入ったり、耳にすると、いやな気分になります。それを表情に表すことはありませんが、あまり気持ちのいいものではありません。高額な腕時計をしていれば、その人は立派だとでもいうような番組、服装の合計金額を計算する番組、その番組の意味を考える事自体ナンセンスなんだろうけど、それを持つことで勘違いしてしまう人を作るかもしれない。勘違いさんが、それを持っていない人への蔑みの視線に力を与えるかもしれない。収入の多寡や所有物など、唯物的なものの基準でしかないのに。人の個性はいろいろで、好きなものもいろいろ、やりたいこともいろいろ、みんな違うから世の中が成り立っている。そこにあるのは、優劣ではなくて、違いだけだと思う。何も持たずに生まれてきて、プラスもマイナスも全てを置いて天国に帰っていく。そしてまた次のキャラクターを得てこの世に戻り、次の人生が始まる。お金持ちになったり、いい仕事をしたり、素晴らしい記録を作ったりしたら、素晴らしいと褒める。それだけでいいのではないか、それに比較するようにそうなれなかった者を出してくる必要はないように思う。それは、敗者や弱者に、他がはっきり分かる色のラベルを貼る行為にしか見えない。高額報酬を得ていたのに、それをあっさり辞めて、老人介護施設の一職員として働いている知り合いがある。障害者支援施設を運営し、多くの障害者に働いて収入を得る喜びを提供している知り合いがいる。医師の資格や技術を利用して、紛争地域で医療・農業灌漑に汗を流す人がいる。所有物としての物質には恵まれない人生だが、私などより魂のレベルが数段上だなと思う。私の通った小学校には、養護クラスがあった。校舎の片隅にあったのではなく、校舎から運動場に出たところに独立した建物としてあった。同年代の知恵遅れの子達が通ってきていた。変なの?とは思いながら、よく一緒に遊んだ。遊んであげなきゃなんて、もちろん思わず、自然に一緒に遊んだ。ドッチボールはうまくないけど、校舎の脇のあり地獄の場所を知っていて教えてくれた。妙に馴れ馴れしくて、いつも笑顔なのが、教室のみんなとは違って、毎日遊ぶことは出来なくても、たまに遊ぶのには、新鮮で楽しかった。だから、毎日休み時間になると、誰かが養護教室の子と遊んでいた。運動会にも、同じように参加していた。リレーだって、養護クラスの子だけで、チームを組んで出ていた。いつもビリになるんだけど、アンカーの子への声援は、そりゃ大きかった。知らない子じゃなくって、いつも一緒の校門をくぐってる子だったから・・・子供ながらに、ビリになっちゃってるけどがんばってるなあ、という気持ちがあったのだと思う。息子達の小学校の運動会でも、養護学校の子が参加していた。でもそれは、私の子供の時と大きく変わっていた。全く別施設になって、日頃の交流のない子が、小学校の運動会にゲストとして来ているようでした。養護学校の子だけの演技があった。リレーは、小学校のクラスに、養護学校の子が1人か2人加わる。健常の子が養護の子の手を持って2人で走っている。進行の先生のアナウンスは、養護の子のがんばりを強調している。これって、健常者の自分の優しさを披露する自己満足にしかなってないんじゃないかと思った。養護の子だって、ちゃんと1人で走れるんじゃないの?健常の子が引っ張ってるリレーを見て、親御さんは感じるのだろう。遅くても、出来なくても、1人でやれることはやる姿を見たいんじゃないのかな?そういう姿が、私が小学校の時湧き上がった応援のように、先生のアナウンスがなくても自然に発生する源になるような気がする。アナウンスは、生徒に応援を強要しているように感じた。生徒を信じて自然に任せれば、自然に応援すると思う。同じ行為でも、どっちがプラスになるか。やる前から、こうしなさいとやらされた行為と、自分で感じて自発的に行動した行為。「負け犬」や「負け組」が活字になり、話題を集める大人の世界が、子供のいじめを醸成しているように思えてならない。
2006/12/09
コメント(4)
-
波の力はすごいね の巻
白石康次郎さんって、知っていますか?ヨットレーサーですが、オリンピックなどの方ではなく、地球1周レースなどの外洋大型ヨットレーサーです。かつて堀江健一さんが太平洋を1人で渡った時は、大洋横断は冒険でした。でも、船の性能がよくなり、気象情報やGPS情報を海の上で受信できる時代になると、お金と時間さえあれば誰でも可能になりました。大西洋横断レースに、数百隻が参加する時代です。まるで、ホノルルマラソンのような感じになってきています。ヨーロッパでは、堀江さんより、斉藤実さんのような大洋横断レーサーの方が有名になり、それに続いているのが、白石さんです。TVにもたまに出ているし、TV番組とレース中に定期交信さえしているので、知名度が上がっています。その白石さんが、昨日オーストラリアのフリーマントルにフィニッシュしました。今出場しているのは、単独世界1周レースです。たしか3年に1度開催されており、今年の参加艇は6艇です。スペインをスタートして、第1レグのフィニッシュがフリーマントル。しばらく休憩と船の修理の期間があり、第2レグのフィニッシュがアメリカ。そして最終第3レグでスペインに最終フィニッシュします。前回白石さんは、1つ小さめのクラスに参加し完走しています。そして今度は、全長60フィート(約20m)のクラス1にエントリーしました。いろんなレースを経験し、やっとこ大洋横断レースの世界での最高峰セーラーになりました。優勝を狙う数名は、新艇にニューセールでレースに臨みましたが、白石さんはお金も面もあり、中古艇に中古セール、少々ニューセールも新調してレースに臨んでいます。クラス1の大洋横断経験がないので、トップスピードで突っ走るというより、どちらかというと風力が上がってくると、早めにセールを小さくして完走狙いです。これがよかったのか、スペインをスタートしてすぐに嵐に遭った艇団は、4艇が船に重大なダメージを受け、途中の港に緊急避難する羽目になりました。白石さんのダメージは、それほどでもなく2番になりました。非難した艇は、修理し随時レースに復帰してきました。白石さんは、その時点で、大きなリードがありましたが、赤道無風地帯でのコース取りでミスって、2艇に抜かれてしまいました。でも再び上位艇にトラブルが発生し、フリーマントルは2番でフィニッシュしました。トラブルを起こした1艇は、相当ひどかったようで、艇体放棄してしまいました。危険な状態になったので、白石さんともう1艇が救助に向かい、先に着いたもう1艇の方が乗員を乗せ、フリーマントルに向かっています。大洋レースでは、他艇の救助がもちろんレースに優先され、フィニッシュ後に時間修正されるでしょう。白石さんの船は、常時17ノットぐらいのスピードが出ていました。時速30km/hぐらいのスピードですが、車のように平坦なアスファルトの上を走るのではなく、波のでこぼこ、しかも数メートルから十数メートルのでこぼこの上を走るのだから、とんでもなく過酷です。そんな状況を走れる大型ヨットが艇体放棄しなければならない海象での救助をするのだから、想像も出来ない世界です。白石さんのウェブサイトには、毎日のように本人のレポートと写真が載りますが、破れたセールや、曲がってしまったパイプの写真に、「波の力はすごいですね」というコメントを添えるだけで済ましてしまう精神力には参ります。相当船も傷んでいるようで、万全の修理をして、次のレグにスタートして欲しいものです。
2006/12/08
コメント(2)
-
心に届く歌唱力 の巻
数日前、2日連続、TVで平原綾香さんの歌を聞きました。ながらTVだったので、どういう企画なのか分かりませんでしたが、『クリスマス・リスト』という曲を歌っていました。ほんとに短い曲ですが、じっと聞きながら涙が溢れてきました。確かに涙腺は弱い方だけど、自分でも何なんだというほど、歌が染みました。平原さんは、ジュピターといういい曲を歌っていた人というのは知っていましたが、TVで見たのは初めてです。大きな声が出るわけでもないのに・・・目を引くコスチュームでもないのに・・・心に届くというか染みる歌唱力は、エクセレントです。気になったので歌詞を捜してみました。ナタリーコールのカバー曲だそうです。『戦争が起きないように引き裂かれないように友達がいて、正義が勝つこと愛は終わらないこの幻想は無邪気だと人は言うけれど一途な思いの中だけに、真実は見える』「正義は勝つ」には、大抵の戦争は、双方が正義を旗印にするので、引っかかりますが、「幻想は無邪気だと言うけど、一途な思いの中に真実は見える」には、深くうなずきました。小さな時から、自分と違う考えでも、多数の賛成意見のある方が通るのは、仕方ないなと思うけど、多数派が少数意見を持ってる者を、さまざまな圧力で駆逐しようとするのに、無償に腹が立つ方でした。小学生の時の喧嘩は、みんなこれです。数人で1人をからかっているのを見ると、無謀にもいつも突っかかっていき、やられて泣くのがいつものパターンです。弱い者いじめがすごく嫌いです。大人になっても、「あなたの言ってることは正しいことだけど、そんなことしたって、勝ち目ないよ」とよく言われます。自分と考えが違っても、勝ち馬に乗った方が得だという生き方を否定しようなんて思いませんが、裸の王様を指摘した子供のように、誰かが思いを言わなければ、何も始まらないと思うのです。1人目がいるから2人目3人目が手を上げ、やがて東西ドイツの壁が崩壊するのです。ポーランドのワレサさん、もっと前に手を上げた誰かがいたから、共産主義に封殺されていた真実が開放されたと思うのです。素晴らしい翻訳者とアレンジ、それに心に訴える歌唱力。『幻想は無邪気だと人は言うけれど、一途な思いの中に真実は見える』
2006/12/07
コメント(0)
-

ピューリツァー賞 の巻
先日、息子がチャレンジした全日本に、毎月購読しているヨット雑誌の取材が入っていました。去年、3人乗りヨットの全日本で私が選手として写真が載りましたし、数年前、ジュニアの全日本の事務局長をした時は、私のレースレポートが数ページ載りました。ヨットなんていうマイナーな世界なので、こういうのはよくあります。今回、取材に入ったカメラマン兼レポーターさんは、フリーの方で、自分でウェブサイトを持っています。そこにいろんな写真が載り、息子のいい写真もありました。それを、3000円で買っちゃいました。前回買った時は、小学生の時の全日本でした。まだ息子もかわいかったし、最初で最後の全日本かもしれないと思って、その写真でTシャツまで作ってしまいました。しかも、息子用・家内用・私用と、数サイズ作りました。出来上がったTシャツを着て、笑っている私に、我ながら割れば、親ばかを通り越して、あほなヤツやなあと、ツッコミを入れました。さすがに、今回はTシャツにしようとは思いませんが、もう二十歳を過ぎた息子なのに、相変わらず親ばかやなあと思います。娘ならわかるけど、息子だもんなあ・・・それのリカット・リサイズ版がこれです。2人乗りの艇長(まん中)が息子で、左にいる船から飛び出して、船がひっくり返らないようにバランスを取っているのが、息子とコンビを組んでくれてるクルー君、大学1回生です。右に見えるのは、後続艇のクルーです。接近戦ですね。カーレースだったら、テール・トゥー・ノーズってヤツです。スタートして、風上の第1マーク目指して数十艇がバトルを繰り返し、やっとたどり着いたマークを、今まさに回ろうとする瞬間です。息子の視線の先は、第1風上マークで、接触しないように、しかもギリギリ最短距離を回ろうと、鋭い視線です。船に隠れて見えませんが、片手は舵をコントロールして、もう一方はセールコントロールするシートを忙しく動かしているはずです。そして足は、落っこちないように、フットベルトにかけています。波を切った泡沫が降って来て、頭はもうずぶ濡れですが、これがまたいいです。頭の中は、次の風下マークに向けて、速攻で風下用セールを上げることや、次のマークへのアプローチまでにあるバトルも考えているのでしょう。さらにリカット・リサイズすると、こんなです。整った顔をゆがめて、しびれるねえ・・・こんなの見たら、惚れるよ。世の女性方は、ほっとかないでしょう。私も学生時代同じ艇種に乗っていたから、いくらでも語れます。しか~し・・・いかんせん、ヨット競技は、観客が近くにいないんですよね。地形の影響を受けた気まぐれな風を少しでも避けるために、数十艇のレーシングヨットが集まってても、岸からは豆粒ほどにしか見えないところでやってるんですよね。観客ゼロの国立競技場でやってる天皇杯サッカーの試合のようで、参加した選手は熱く語れるけど・・・でも親ばかな私は語りますよ。目立たないと写真に収まらないので、1度だけトップ回航したそうだから、その時の写真かもしれません。20枚ほどしかサイトに載っていなかったので、プロから見てもいい写真だったのでしょう。私から見たら、当然のことながら、他を圧倒したピューリッツァー賞ものの素晴らしい1枚です。フェチな親ばか発言を御赦しください・・・失礼いたしました。
2006/12/06
コメント(10)
-
迅速な行動と立派な対応 の巻
今朝、ニュースを見ていたら、自民党の郵政造反議員が自民党に戻ったというのをやっていました。安倍さんが、また一緒にやりましょうということを、戻られる議員さんに声かけしていた。また、ご批判は私が受けますと、国民向けにしゃべっていた。コメンテーターさんや新聞社のコラムニストさんなんかは、あの郵政民営化選挙はなんだったんだとか、小泉改革から昔の自民党に戻る、というような話をしていた。そういうのが、多くの有識者の意見なのかもしれないが、私はよかったと思っている。自民党は批判にさらされ、支持率が落ちるということだが、私は反対に自民党を見直しました。親方日の丸体質になった国鉄がJRになり、電電公社がNTTになり、いろんな批判もあるのだろうが、大枠では成功していると思う。ならば、この流れは止まらないだろう。いずれ郵便も民営化されるのは時代の流れのような気がする。小泉さんが、自分の任期中にと、時を急いだのは分かるが、やり方があまりにひどかったと思う。政治は食うか食われるかの世界かもしれないが、1つの意見の違いだけで、党の造反分子として、刺客候補さえ立てて、当選を阻止するやり方は、学校内のいじめとあまり変わらないのではないかと思う。もう何度も書きましたが、当時あれを見ながら、学生運動がどんどん精鋭化して、排他的になり、分裂を繰り返しながら、少数の最精鋭分子が集まった連合赤軍内で、内部リンチで殺人者を出して瓦解していったのに似ているように思った。日本の政治は、イギリスやアメリカのような2大政党で、政権交代が日常に起こる緊張感を選択しました。ならば、2大政党になろうとする党は、懐大きくいろんな考え方の議員を内包しなければ、党の拡大は望めません。個別案件で、多数派が少数派を追い出し、新人議員を新たに加えることを繰り返していれば、いずれ土台は揺らいでいき、ある時を持って一気に崩壊していくでしょう。ベテラン社員を切って、パートやアルバイトに変えすぎて、おかしくなる会社と一緒です。私は、選挙では、人を見て投票する方です。講演会を聞きに行くこともありますが、大体は公約や話し振り、全体から受ける雰囲気で選びます。政党の多数意見にイエスマンなだけの議員には魅力を感じません。反対意見でも、きちんと自分の意見を言う人が好きです。党内で、違う意見を言いづらい雰囲気は、力を持った少数意見が通るかつて軍備拡張に進んだ道に繋がるかもしれません。今回の安倍さんの行動は、とても良かったと思います。首相になって、これだけ迅速に、しかもキングメーカーだった小泉さんのやった代表的なことを反故にするのは、中々出来ない事だと思います。しっかりした首相のように思います。少数の方を追いつめすぎない、美しい日本の心だと思います。それに対して、何も言わなかった小泉さんも、中々立派だったと思います。現首相である安倍さんへの礼儀だと思います。違う考えでも、ここで党のトップを潰しては、長い目で見てマイナスだと思ったのかもしれません。どんな手段でもいいから、勝てば官軍という時代ではないように思います。そこに至るプロセスは、次の世代を担う子供達が見ています。恥ずかしくない行動を見せたいものです。
2006/12/05
コメント(4)
-
勉強、がんばれよ の巻
日曜日は、秋季近畿北陸学生ヨット選手権でした。新チームになった秋からの練習成果を計る大会です。大抵の大学は、このレースを区切りに、オフに入り、後期テスト明けから春の練習開始です。朝、土曜日の成績を見ようと、ハーバーを息子と一緒に歩いていると、R大艇庫から声がかかりました。息子とは小学生からのライバルN君で、高校生になると、同じ高校ヨット部のチームメイトになりました。大学では再び分かれて、同じ琵琶湖で覇を競った仲です。彼も今春学部を卒業したので、母校のコーチをしています。相変わらず明るく、感じのいい青年です。ジュニアの時、私が監督で、N君も息子も選手として参加する海外レースがありました。メンバーを見て、即、彼をチームのキャプテンに指名しました。ニコニコ明るく、冗談が上手でみんなを笑わせてくれます。こういう子がいると、チームがうまくまとまります。誰かがへまをした時でも、明るく前向きに解消できます。でも、彼は何不自由ない境遇ではありません。お父さんが小学校の時倒れて、ずっと寝たきりに近い生活でした。大学生の時、お亡くなりになり、みんなでお通夜に行かせてもらいました。私のような、他クラブの人にでも分け隔てなく、誰にでも親切にジュニアのヨットの教え方などを披露してくださる方でした。いつも年賀状には、ベッドでのそのお父さんを中心にした家族写真が使われており、お母さんを中心に、家族の温かさを感じました。そういうことがあっても、彼は、以前と変わらず明るく笑っています。息子が彼の事を教えてくれました。就職した会社辞めてんて・・・柔道整復師の専門学校に行くんやって。会社の営業成績、全国一やってんで、すごいやろ。多くの人が知ってる化粧品会社に就職して、トップセールスを記録したそうです。彼の笑顔と性格を知ってるので、それには違和感がありませんでしたが、何故辞めたんかなと気になりました。「あいつ、昔っから、マッサージとか好きやってん」練習の後など、チームメイトのマッサージなどをよくしていたそうです。彼と息子は、学部を卒業してもまだ勉強してる仲間として、妙な連帯感があるような感じです。長男の時もそうでしたが、この次男も、学部を卒業してからの方が、より一生懸命勉強している感じがします。彼と息子は、お互い励ましあって勉強して欲しいです。その後、レースが終わり再びハーバーに戻りました。ここのハーバーにある、彼の出身でもあるジュニアクラブに顔を出すと、ちょうど忘年会でした。「のりまきさん、いい所に来たね」とか「鼻が効くなあ。イノシシと鹿肉あるで、まあおかけな」と閉会式が終わるまでお邪魔することにしました。しばらくすると、彼がやってきました。アルコールが入ったかつて教えてもらったお父さん方を、家まで送りましょうかと、やってきました。気の利く優しいやつです。「柔道整復師、いいで」と、知り合いの同じ職業のヤツの事を紹介してやりました。「勉強、がんばれよ」
2006/12/04
コメント(6)
-
甲子園 の巻
寒くなってきました。こう寒くては、ウォータースポーツでもないだろう、という感じですが、明日の日曜日は、琵琶湖で近畿北陸ブロック学生秋季選手権があります。レースを見に行こうと思っています。大抵の学校は、このレースを最後にオフに入ります。次は、2月の後期テストが終わってからです。新チームになってからの練習の成果を計る指標になるレースです。次の週は、クルージング艇でのレースが計画されています。私は、両親や義理母の様子もあり、今のところ参加しない方向でいます。この時期になると、気になるのがアメリカンフットボールです。かつては無敵を誇ったわが母校も、京都との2強時代を経て、最近は立命との2強、というより立命が1歩リードという勢力図です。大学アメリカンフットボール秋季シーズンは、前年の1位と2位が他校と当たって、最終日に2強対決というのが日程になっています。最近は母校と立命が、毎年最終戦を戦っています。一昨年は母校が勝って同率に追いつきましたが、プレーオフで負けてしまい、4年連続で立命が、大学日本一を争う甲子園ボールに出場していました。今年も全勝同士で最終戦を迎えました。下馬評では立命有利だったのですが、それをひっくり返して、久しぶりに甲子園ボールに出場することになりました。さらに、昨年卒業生部員の不祥事で春のリーグ戦を辞退していた京都が3位になり、ガタガタにならずに良かったと思っています。部員も関係者も、背水の陣でモチベーションを保ったのでしょう。こういう後は、強くなるものですから、来年は京都も2強に食い込む活躍を見せるかもしれません。先月末の日曜日は、息子のレースで江ノ島から帰ることばかり考えていましたが、その日のアメリカン立命戦勝利で、今週は甲子園ボールのメールが飛び交っていました。結局ヨット部の2~3年先輩方と、アメリカンフットボール部のOBが集まる席で観戦することになりました。母校は、中学からアメリカンのクラブがあり、ヨット部もアメリカンのリーグ最終戦は、練習を午前中で切り上げて、スタンドの応援に駆けつけるほどの熱の入れようです。甲子園ボールだと、多くのヨット部OBが来ており、下手するとぐっと上のOBにつかまるかもしれません。野球の六大学の早慶戦が、他クラブも含めてOBの同窓会になってると聞きます。母校の場合は、リーグ最終戦や甲子園ボールがそういう感じです。体育会に入った同級生の顔を見るのが楽しみです。体育会はいくつになっても上下関係が変わらず、後輩はどうしても太鼓持ちを覚悟しなければなりません。勝利して大学日本一になるのは嬉しいのですが、2次会2次会と連れまわされるかもしれません。その点、先輩とは言いながら、2つ3つの年の差なら、いつでも抜けられます。この観戦を手配した先輩のメールにも、『アメリカンのOB席やから、気遣いはいらんで』と入っていました。しらふの時は、大先輩にいくらでも付き合いますが、アルコールが入ったら勘弁願いたいです。なんと言っても、向こうは「サンデー毎日」な結構なご身分ですからね。甲子園ボール、クリスマスが終われば、高校サッカー、高校ラグビー、大晦日、箱根駅伝、ライスボールと、冬のスポーツが続きます。楽しみです。
2006/12/02
コメント(4)
-
クリス・クリングルさん の巻
子供へのクリスマスプレゼントにいいなと思う本の紹介です。「34丁目の奇跡」 ヴァレンタイン・デイヴィス 片岡しのぶ訳 あすなろ書房私の勝手に書籍採点は、星3個の最高得点です。素晴らしい同名の映画を観たことがあります。この映画に原作があるとは思っていませんでした。さらに驚いたことに、1947年というから戦後すぐに製作された映画で、その脚本家が封切りと同時に小説化にしたそうです。私の観た映画は、そのリメイク版だったようです。この小説も、戦後すぐに書かれた作品を忠実に再現した英語版を翻訳したものだそうです。この本を見つけた時は、即決で購入しました。ニューヨーク近郊の老人ホームに、サンタクロースにそっくりな老人が暮らしています。名前をクリス・クリングルと言い、本物のサンタさんと名前まで同じです。ある日、担当のお医者さんから、もうここにはいられないことを聞かされる。ここのホームは、心身ともに健康な人が入所する施設で、痴呆のあるホームに移ることを奨められる。または精神病院に入院するかです。クリスは、各種の検査でも心身健康と診断されているのだが、ただ一点、自分をサンタクロースだと信じている妄想癖のあることが、ネックになっている。施設を出ることにしたクリスは、大通りのクリスマスパレードを見ていた。ニューヨークの2大百貨店の1つが毎年行うパレードです。サンタ役の人のムチの振り方がぎこちなく、クリスはその使い方を教える。でもそのサンタさんはうまく出来なかった。寒さもあるのだろうが、ポケットからアルコールのビンを出して、ちびちびやっているからのようだ。それを見つけたパレード責任者のドリスは、その場でサンタさんをクビにしてしまう。しかし、サンタさんがいないクリスマスパレードなんて・・・と、横にいたクリスが目に入る。「サンタさんの仕事をしないか?」雇用書類に書き込まれる名前を見て、?と思うが、パレードの出発時間は迫っている。クリスのサンタさんは、とてもよく似ていると評判で、そのまま百貨店のサンタ役に雇うことにした。翌日からクリスは、サンタの衣装でサンタの椅子に腰掛け、百貨店で働き出す。子供達がクリスの前に並び、1人1人膝の上に乗せて話を聞き、話をする。クリスは、サンタの事、おもちゃの事をとてもよく知っていた。このメルシー百貨店で売っていなかったり、品切れだったりしたら、それを売ってる他店の場所や値段まで教える。それに気づいたドリスは、自分をサンタクロースだと言う妄想癖のこともあり、クリスを解雇しようとする。でもお客さんの評判はすこぶるよく、社長は大喜び。ドリスは、一度結婚に失敗している。夢物語を信じることをやめ、目に見えるものしか信じず、仕事でのキャリアを積むことと、娘のスーザンの子育てが生き甲斐です。幼いスーザンにも、現実をきちんと教えるので、友達がみんな幼く感じて、1人で遊ぶことが多い子になっている。ドリスには、弁護士のボーイフレンドのフレッドがいる。彼は、ドリスの現実主義を少しでも変えようとするが、うまく行かない。寝場所のないクリスは、フレッドの家に居候するようになり、スーザンに変化の兆しが見え始めた。自店の私欲から離れた子供のためを思ったクリスのサンタの評判は、うなぎのぼりで、社長がクリスの接客方法を全店舗で推奨するように号令をかける。これにマスコミが飛びつき、2大百貨店同士のお客さんの紹介し合いがきっかけに、ニューヨーク中に広がっていく。これはお店同士だけではなく、足を踏まれても、笑顔で返すなど、日常のこまごましたいさかいの元が、ことが解く笑顔で解決していく社会現象にまで発展していく。でもクリスを良しとしない人もいた。メルシー百貨店の警備責任者は、いつかこの痴呆老人は、ひどいことをしでかすと考えていた。そこでクリスを騙して精神病院に入れてしまった。フレッドがクリスを精神病院から救い出すために立ち上がる。多くの子供達・親達の声援、マスコミの感心を集めた法廷闘争が始まる。気に入った所を引用しておきます。あまりに有名な、ニューヨークサン新聞の社説に似てるかな?『フレッドはすっと立ち上がる。「信じる気持ちは常識を超えるはずだ。きみって、常識を捨てられない人なんだ」「私だけでも常識を捨てなくて良かったわ。常識は役に立つのですから」「ねえドリス。何を恐れている?何故クリスのような人を信じる気になれない?この世には、目に見えない善いものがいっぱいある。愛とか、喜びとか、幸せとか・・・そういうものをもっと信じようじゃないか」』『さて、クリスマス当日。朝早く目覚めたスーザンは、こっそり居間に行ってみた。ツリーの下には、かわいいパッケージがいくつも置かれていたが、クリスに頼んでいたものは、なかった。ドリスが起きてきたとき、スーザンは泣いていた。クリングルさんはやっばりサンタクロースじゃなかった。ドリスは、娘を抱きしめてやったが、スーザンはその腕をふりほどいた。「ママが言ってたとおりよ。あたし、よくわかった。サンタクロースなんて、いないんだ」ドリスは、以前の自分のセリフを開かされた気がして、悲しくなった。「ママが問違ってたわ。スーザン、クリングルさんを信じなくちゃ」とはいえ、どうして信じられよう? 百貨店で働く貧しい老人が、クリスマスの願いをかなえてくれるサンタクロースだなんて・・・!「信じる気持ちは常識を超えるのよ」それはフレッドの言葉だった。言いつつ、ドリスは、今、その意味を噛みしめた。だが、スーザンにはそんな難しいことはわからない。「心から信じなかったら、なにも実現しないわ」ドリスは、つらい経験から、それを学んでいた。万事順調にいっているときに信じるのは簡単だ。けれど、なにがあろうとも信じてこそ、本当にと言えるのだろう。「スーザン、あなたがクリングルさんに書いたあのお手紙のおかげで、ママはとっても勇気が出たの。今度は、ママがあなたに勇気を分けてあげる番みたいね」スーザンはしばらく考えていた。それから、はっきり言った。「ママ、わたし信じるわ」』
2006/12/01
コメント(10)
全21件 (21件中 1-21件目)
1