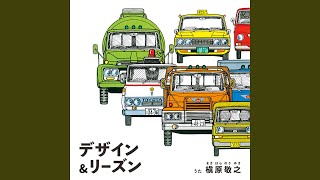2014年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
とんだ会長をもってしまったNHK
NHKの新会長になった籾井勝人とは、一体何者なのか? これまで名前も聞いたことのないような人物が会長に推されるや、記者会見でとうとうと慰安婦問題をしゃべりはじめた。おまけにオランダの「飾り窓の女」の話まで出して、記者団の顰蹙(ひんしゅく)を買うや、あわてて談話を取り消した。その後各方面から批判されると、今度はNHKの全職員に詫び状を出している。こんなトップがいるものだろうか?本当なら全職員に、会長としての抱負を語り「一緒にがんばろう」と語るべきなのに、最初からペコペコ頭を下げたのでは、誰ひとりこの会長についていこう、という職員はいないだろう。ここは周囲から慰留されたとしても、自分の意思で辞めるべきだった、と思うのは、私だけだろうか? もう職員は「飾り窓会長」として、心の中でバカにするだけだろう。まさにお飾り会長であり、スタートから窓際に座らされた会長だ。一体この人物はどんな経歴をもっているのだろうか? 恐らく多くの視聴者は私と同じで、ほとんど知らないのではあるまいか? マスコミによると、三井物産の副社長から、日本ユニシスの特別顧問に転じた人物、となっている。経歴はわかったが、どういう業績をあげた人物なのか、まったくわからないというより、全然業績がないのだ。つまりこれまでトップとして、多くの人々に知られる識見もエピソードもない。NHKもなめられたものだ。少なくともこれまでは、それなりの有名経営者が会長についていたが、今回は二流の経歴しかもっていない人物が会長になった。やはり力のない人物は、視野が狭く、いっていいことと悪いことの区別もつかなかった。職員のあきらめ顔が目に見えるようだ。
2014/01/30
-
小澤征爾の履歴書
この1月の日本経済新聞「私の履歴書」は、世界的指揮者、小澤征爾が書いている。私がこれを読んでいて驚いた点は2つ。1つは驚くほどの記憶力の高さだ。もう1つは、こんなにも多くの人たちの世話になっていたのか、というエピソードだった。私は小澤より4歳上だが、子どものときから世話になった人たちの名前など、どうやっても思い出せない。ところが彼は、いとも易々と、それも姓と名まで出している。それに放浪中のホテル名まで、きちんと書いているではないか! 恐らくこれは指揮者ならではの記憶力なのだろう。長い交響曲の指揮をするには、まず曲をすべて暗符するのではあるまいか?仮に暗記力が衰えたら、指揮者の椅子を去らなければならないのだろう。もう1つ、小澤征爾には、数々の若い時代の成功談が伝わっている。日本を去ってフランスに渡り、かの地のコンクールで華々しくデビューしたと私は思っていたが、彼の履歴書を読むとそうではなかった。むしろ本当に多くの人々から援助してもらっている。また彼も、それらの人々の名前を1人ひとり挙げているのだ。自分の力だけで成功したのではないことを、明らかにしている。ふつうだと、成功者ほど自分の力を誇示するものなのに、彼は違った。お世話になった方々を無視する人も大勢いる。そういう風潮の中で、天才と呼ばれた小澤征爾は、むしろ多くの人々に世話になったことを、隠そうとしない。私にはこの姿勢が、とても快く思えるのだ。いや快く思えるだけでなく、「人間はこうあるべきだ」と、かえって自らを反省させられてしまった。この姿勢を貫いているからこそ、小澤征爾は多くのファンに賛えられているのだろう。いい履歴書を読ませてもらった。
2014/01/23
-
あなたに息抜きの場所はない!
近頃は「犯罪者を逮捕」のニュースに接すると、ほとんどの場合、犯人は街の防犯カメラに捉えられている。先日も川崎の地検支部で取り調べを受けていた容疑者が脱走したが、その直後からこの男の姿が、あちこちのカメラに映っていた。いつの間にか防犯カメラから監視カメラ時代に移ったような錯覚に陥るほど、カメラの数がふえているのだろう。実際には犯罪多発地区や、逃走に使われる各駅やガソリンスタンド、服装を取り替えるトイレなどに重点的に配置されているのだが、なんとなく誰かに監視されているようで気味が悪い。ところが今年は「ウエアラブル技術元年」と位置づけられている。超小型のコンピューターが衣服や眼鏡、腕時計などに組み込まれ、いわば全身が監視される状況になっていく。一面では実に便利な世の中になるのだが、都合の悪いことに、まったくウソがつけない世の中になってしまうのだ。現在、タクシーの運転手さんは、車のコンピューターによって、完全に監視されているといわれる。それを同じで、すでに一部の企業や病院では、これらのウエアラブル機器を身につけることが義務化されている。これによって、構内のどこにいたか、どこを歩いていたか、すべて上司に把握されることになったという。もうこうなると、私生活はなくなってしまう。男も女も、浮気ひとつできなくなるのではあるまいか?ウエアラブル技術元年とは、24時間監視社会の誕生といいかえてもよさそうだ。一見便利そうだが、ノイローゼやうつ人間がこれまで以上ふえるかもしれない。よろこぶべきか、悲しむべきか、人によって大きな差になりそうだ。
2014/01/17
-
正月の本の読み方
9日間の正月休みも、終わってみれば短かった、とふり返る人も多いのではあるまいか? 私もその口で、結局何もできずに仕事始めを迎えてしまった。それでもちょっぴり利口になったのでは? と思うのは、長い間の習慣だが、正月は新刊を読むより、古い本を手当たり次第に本棚から引っ張り出して、面白そうなところだけ拾い読みするのだ。新しい本は休み中ではなく、仕事で動いている時期のほうが勉強になる。ビジネスが動いているときは、私たちの頭の中も活発となる。ところが年末年始の時期は、どうしても頭の中がのんびりしてしまう。今年のように9連休ともなると、一時的にビジネス脳が停止したような感覚に襲われてしまった。こんなときすぐれた本を読んでも、すぐ活用することができないだけでなく、そのよさまで見逃してしまいそうだ。その点、古い本を10冊でも20冊でも手元に置いて、パラパラとめくっていくと、思いがけないヒントが出てくる。特に私は歴史書と数十年前に出た出版関係の本を、書棚から抜いてくるのだ。すると思いがけなく、NHK大河ドラマの主人公になる黒田官兵衛の逸話が飛び出してきたり、大名や武将の名言が胸を打つことになる。あるいは30年前、40年前には、どういう種類の本が売れていたかを知ることになる・たとえば大災害のあとには、どういう本がよく売れたかも記されている。あるいは「清貧」と「贅沢」をすすめる本は、株価と連動していることもわかる。いま清貧を説いても、誰も読まないだろう。そんな正月休みを終えて、いよいよ新しい年の仕事に突入したが、こんな小さい知識でも、そのうち活用することになるかもしれない。私にとってふだんの勉強ほど、自信につながっていく。
2014/01/09
-
今年のおバカさんは誰か?
「週刊文春」には「今週のバカ」という連載がある。昨年春から始まったので、これまで29人が登場しているが、いずれ劣らぬバカばかりだ。といっても、バカが悪いとはいえない。楽天のマー君こと、田中将大投手の夫人の里田まいは「おバカタレント」としてテレビで珍回答を繰り返し、都内の女子高生300人に聞いた質問でも、里田はおバカタレント第2位にランクされていた。にもかかわらず、マー君と結婚したことで、いまや全国の若い女性たちの間に「私もおバカになりたい!」と、バカブームが起こったくらいだ。とはいえ、やはり大勢の人たちに「バカ」と認定されるのは、気持ちのいいものではあるまい。「週刊文春」では、読者アンケートによる「2013年のバカ」を発表しているが、そのベスト(ワースト?)5には1位の朴槿惠を筆頭に、山本太郎、猪瀬直樹、鳩山由紀夫、みのもんた、とつづいている。これはなかなか味のある選択で、恐らく多くの人が納得するのではあるまいか? ただし、この中には人物的にバカな人と、バカな言動、行動できらわれている人の2種類がいるようだ。私がこの中で、人物的にバカなのではないか、と思うのは鳩山由紀夫だ。それにつづいて山本太郎ではあるまいか?鳩山由紀夫は宇宙人といわれているが、実際には沖縄問題を、ここまでこじらせた張本人といって過言ではない。私はあまり他人の悪口をいうタイプではない。いや、恐らくいったことはないと思う。人にはそれぞれ立場があり、バカな発言や行動をとってしまうこともある。私自身、何回も失敗している。問題はそれを反省するかどうかなのだが、どうも鳩山由紀夫には、その反省が見えないのだ。私はむしろ、永久に1位でもいいと思うのだが。
2014/01/02
全5件 (5件中 1-5件目)
1