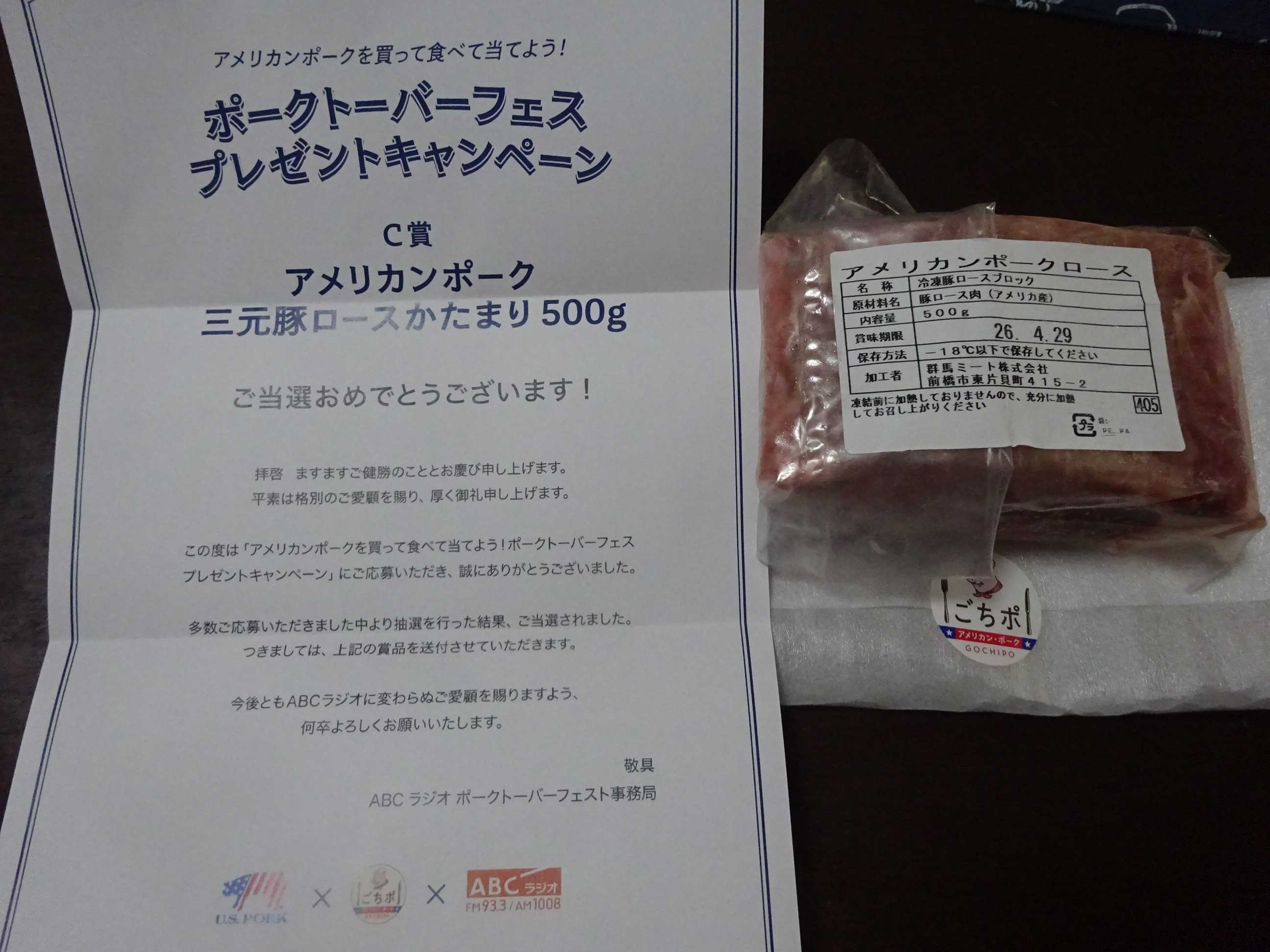2014年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
ヘリコプター体験記
某日、東京新木場ヘリポートからヘリコプターに乗り、東京上空を回った。人によっては怖いと思うかもしれないが、バブル華やかなりし頃は、ゴルフ場の往復をヘリのサービスをする豪華なクラブもあった。あるとき私は西武系列のゴルフ場でプレーしていた。忘れもしないその13番ホールで、しばらく待たされたのだ。前にプレーしている組はいないので不審に思ったところ、堤義明会長がくるという。それは面白いと思っていたところ、なんと東京からヘリでやってきたのだ。フェアウェイに降り立って、2打地点からグリーンに向かい、18番を終えると、そのままヘリに乗ってさっと帰ってしまったのだ。だからまったく顔もプレイぶりも見ることができなかった。同組のメンバーは、堤氏の悪口ばかりだったが、私は財界人の一面を見た思いで、興味を抱いてしまった。そんな思い出があったので、ヘリに乗りませんかと誘われたとき、大喜びだった。実際乗ってみると、怖いという気持ちはまったく起こらず、タクシーより安全ではないかと思ってしまった。実際乗った時間は15分くらいなのだが、操縦士から「30分くらいに感じますよ」といわれた通り、意外に長く感じてしまった。初体験としては、15分くらいで丁度いいのではあるまいか?ひとつだけ感想をいうと、上から見る皇居は予想外に狭いと感じたことだ。これはほかの体験者もいっていた。戦争中、米軍機が攻撃しようと思ったら、正確に皇居を銃撃できたろう。高々度を飛ぶ飛行機からではわからないが、ヘリのように低空を飛ぶと、また違った目で東京が見えるものだ。
2014/10/31
-
一般家庭に外国人のメイドが
安倍内閣は成長戦略の1つとして、女性の活躍を掲げている。それを自分の内閣でも実現してみせようとして、5人も女性大臣をつくったのだが、あっという間に2人が失脚、残りの3人も、それぞれ危うさをもっている。女性の社会的活躍は、そう簡単ではないということを、自らの手で証明して見せてしまった感じだ。それでも今の国会で外国人家事支援人材(いわゆるメイド)の活用法が提出される予定だ。これは結婚によって失われる女性の労働力が、580万人にものぼることを考えて、少しでも現場復帰してもらおうという政策なのだ。これまでは外国人をメイドとして雇用することは、一部の特定分野の人しかできなかった。それを一般家庭でもメイドとして働いてもらえるよう、法改正をするのだが、東南アジア系の外国人女性にとっては、よろこぶべき状況となる。日本に来ても満足に仕事がないという人々が多いからだ。特にフィリッピン系の女性たちは、メイドとして歓迎されているだけに、もし法改正が通れば、彼女たちにとって大きなメリットとなる。フィリッピン人女性はもともと英語が話せる上に、エグゼクティブ向けのサービスに慣れており、一部の家庭では、よろこばれるのではなかろうか。ただ一般的にいうと、メイドとしてでなく、時間給による家事手伝いが欲しいのが、ふつうの家庭主婦の願いだろう。それでも子どもを預けられて家庭仕事から開放されるならば、働くことに意欲的な女性たちは、彼女たちを歓迎するだろう。多分いつの間にか、外国人の女性が日本人家庭で働く姿が、違和感なく見られる日がやってくるに違いない。そういう形にならないと、人口減と高齢社会に悩まされる日本としては、社会が活発化しないだろう。
2014/10/23
-
彼も残虐我も残虐
つい先月のこと。ラーメン店で口論した客をなぐる、蹴るの暴行を働いたあと、悠然と酒を飲みラーメンセットを完食した男が現場で捕まった。「どうせ男は死ぬだろうから、最後の晩餐だ」と警官にいっていたというから、この男の残虐さには驚くほかない。私たち人間はどこまで残虐になれるのだろうか? 一体、残虐さは人間の本能なのだろうか? 子どもは本能的に残虐だという。それは痛みというものを知らないからだ、と説明する学者もいるが、それは違う。子どもは痛みを知っているから、いじめで快感をもつのだ、という学者もいる。私たちは大人になると、子どもの時期のいじめを忘れてしまう。自分はいじめなどしたことはないといっているけれど、実はいくらでもしているらしい。人によっては教育程度が上がれば残酷な行為はしない、というが、だったら朝日新聞の、日本人全体をおとしめたペンの残虐さを、どう説明するのだろう?私たちは、もともと残酷、残虐性があるのだ、と思うほうが正しいのではあるまいか? 自分を大事にするあまり、敵対する人間を刃向かわせないよう、いろいろな刑罰を考えるのが人間なのではないだろうか?昔から「虫も殺さない顔で心は鬼」という言葉があるが、どんなに優しい女性でも、口は残酷で心は冷たい。上位者ほど自分の手を下さないで、残酷な命令を下す。また誰でも自分の生活が追い詰められれば、残酷にもなりうるのだろう。人によっては「人間は美しいもの。残酷な行為をする人は、人間の屑」というが、その屑に、自分でもなりかねないと思っているほうが正しいのではないだろうか? どうも自戒しなければならないような事件が、続発するような気がしてならない。
2014/10/17
-
言葉の意味は時代と共に
言葉づかいが混乱している。といっても、言葉は古くから使われてきたものなので、変化して当然だ。古文に「いとをかし」という表現があるが、これは「情緒がある」というのが、本来の意味だ。ところが現在では「おかしい」「変だ」「こっけいで面白い」となっている。こういった例は、いくらでもあるだろう。言葉は時代と共に変化するものであり、あまりかたく考えるのは、よくないかもしれない。私の書いた古い本に『キレる男の着眼と発想』という1冊があるが、いまでは絶版になっている。というのも「キレる」の意味がまったく違ってしまったからだ。この本を書いた当時は「頭のよい」「鋭い」という意味だったが、いまは「ムカつく」「イラッとする」という意味に変わってしまった。わずか20年くらいで大きく変わってしまったのだ。ある新聞によると「世間ずれ」も大きく変化しているという。本来の意味は「世間を渡っているうち、ずる賢くなる」というものだが、いまは「世の中の考え方からはずれている」と解釈する人のほうが、多くなってしまった。「そろそろ議論も煮詰まってきました」も、話し合いが行き詰って、結論が出せない状態をいうらしい。正しくは「意見が出つくして、そろそろ結論が出る状態になっている」という意味だが、こうなると、正しい解釈が必ずしも正しくない、ということになりそうだ。このほかにも「断トツの1位」と、スポーツニュースでも使っているが、これは「断然トップ」と「1位」がダブっている。昔の「馬から落ちて落馬して」の類だが、それも笑えなくなってきた。「今現在」「一番最初に」など、私を含めて誰でも使うからだ。
2014/10/10
全4件 (4件中 1-4件目)
1