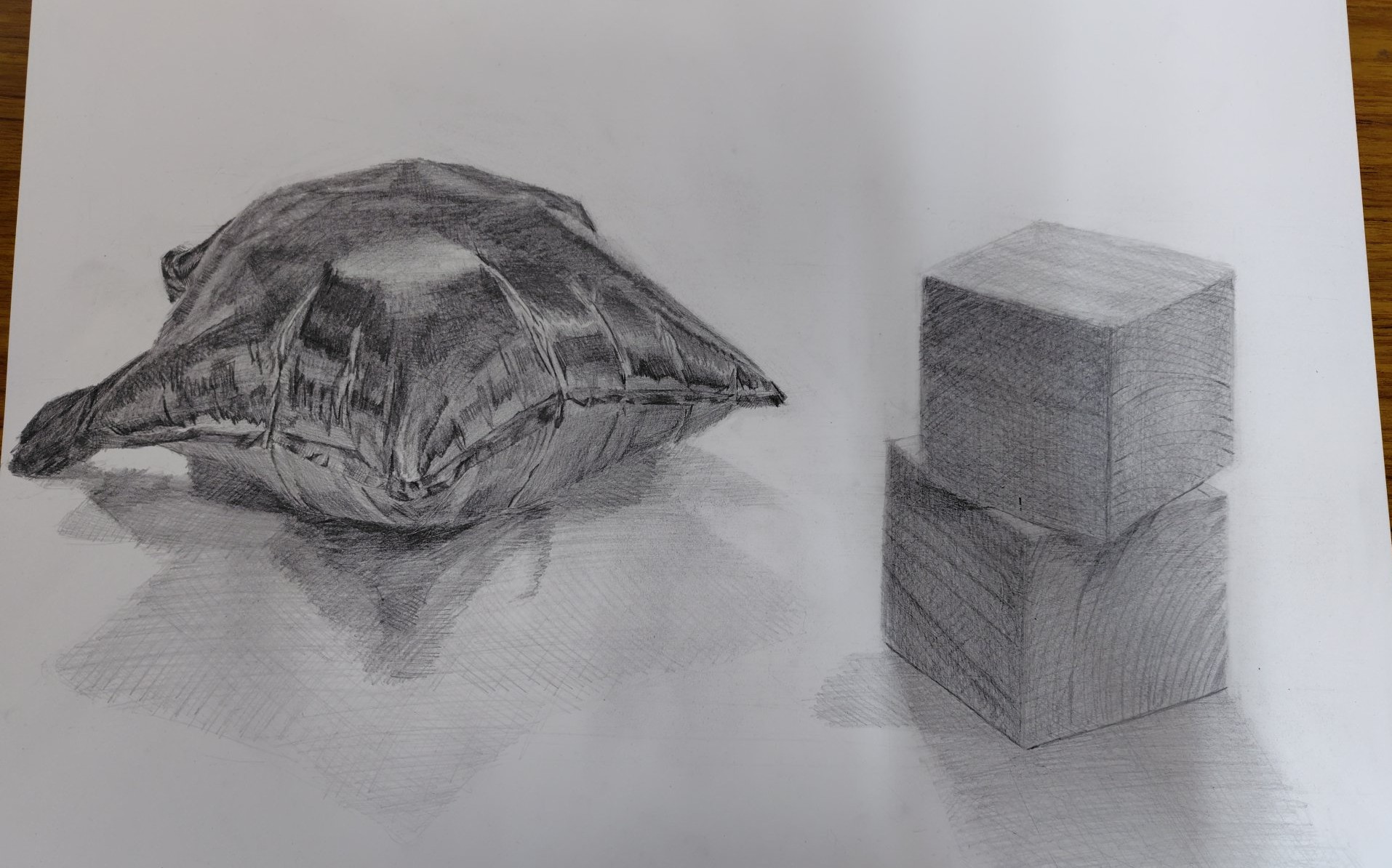2018年05月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
乱歩と三島の話題作ながら(後編)
『黒蜥蜴・湖畔亭事件』江戸川乱歩(春陽文庫) さて、前回の続きです。 女賊「黒蜥蜴」の魅力とは何かを考えていたら、タツノコプロダクションを経由して幼年期のエロスにまで飛んでしまいまして、収拾がつかなくなりました。 改めて考え直してみます。 そもそもなぜ私が本作をあまり面白いと感じなかったのかといいますと、それはいかにも通俗小説めいた語り口のせいでありました。例えばこんな感じ。 読者諸君は、もしかしたら、「作者はとんでもないまちがいを書いている。緑川夫人は早苗に化けて、岩瀬氏の隣のベッドに寝ているではないか、その同じ緑川夫人が、廊下からはいってくるなんて、まったくつじつまの合わぬ話だ」と抗議を持ち出されるかもしれぬ。 だが、作者はけっしてまちがってはいない。両方ともほんとうなのだ。そして、緑川夫人はこの世にたったひとりしかいないのだ。それがどういう意味であるかは、物語が進むにしたがって明らかになっていくであろう。 実際私は、こんな「釣り」の文章に辟易したのですが、しかしこうして書いてみると、本当にこんな文章は、表現として寿命が切れていると考えていいのかどうか、少し興味深いものが残ります。どうなんでしょうねぇ。 とにかくそこで私は、戸惑うままにこうなったら三島戯曲を読まざるをえまいと考えまして、図書館で借りてきました。これです。 『決定版三島由紀夫全集23・戯曲3』 この中に『黒蜥蜴』が収録されているのですが、この全集の編集ポリシーなのかよく知らないのですが、本書には戯曲ばかり、初出年月順に並んでいます。 つまり本書は、昭和32年1月から37年3月までに発表された戯曲が入っていて、ちなみに『黒蜥蜴』の一つ前の戯曲は『十日の菊』となっており、これはなかなか興味深いです。 三島の生き方の美意識に直接つながりそうなまさに「重い」『十日の菊』の次に、『黒蜥蜴』がくるという順番が、小説でいう「レシ」としての『黒蜥蜴』の成り立ちを象徴している気がします。 つまりエンターテイメントとしての『黒蜥蜴』ですね。 三島由紀夫は、生涯の自らのテーマを追及した小説群の一方、たくさんのエンターテイメント小説も書いています。(先日たまたま深沢七郎の文章を読んでいましたら、三島由紀夫に文学的テーマなんてないといったようなことが書かれてありました。深沢なら分からないでもない論旨ではありますね。しかし、確か、太宰治や坂口安吾は、同様に志賀直哉には文学的テーマはないといっていましたよね。なるほど一概に文学的テーマが大事なわけでもなさそうです。) そして、わたくしが思いますに、それらのエンターテイメント作品はよく似た特徴を持っています。 本戯曲も一緒で、例えばこんなセリフ。 明智 今日も何事もなく日が沈む。この大都会、白蟻に蝕まれたやうに数 しれない犯罪に蝕まれこの大都会に日が沈むんだ。殺人、強盗、誘拐、 …………、言葉にしてみれば他愛もないんだが、みんなその一つ一つ に人間の知恵と精力と、怒りと嫉妬と、欲望と情熱がせめぎ合つてゐ る。その一つ一つが狂ほしい道に外れた人間の、それでも全身的な表 現なのだ。こいつのどこから手をつけたらいい? 依頼主か。こりや あ自分のことしか考へない。犯罪の本質にいつも向き合つて、その焔 の中の一等純粋なものを身に浴びなければならないのは僕なのだ。僕 には犯罪の全体が見える。それはたえず営々孜々とはげんでゐる世界 一の大工場みたいなものだ。(略) この長セリフはさらにもう少しだけ続くのですが、ここに描かれているものが時代と共に古ぼけていくイメージなのはやむなしとして(それは「エンターテイメント」の宿命でもありましょう)、私が気になるのは、大上段に構えて提出されるイメージの断定です。 そこには、これ以外のイメージは許さないといった「押しつけ」に近いものがあり、そしてそれが、三島のエンターテイメント小説に一貫して現れる読者への「啓蒙主義」のように思います。 ということで、三島戯曲の『黒蜥蜴』についても、……うーん、何だかそりが合わないような書きぶりになってしまいました。しかしこれは、いわば「木に縁りて魚を求む」の類でありましょうか。 そういえば、冒頭の乱歩の文庫本に並禄されている『湖畔亭事件』は、いかにもおどろおどろしい乱歩節がゾクゾクと面白い「変わり味」探偵小説で、「予定調和」の大団円もとても楽しく読めました。 しかしこちらの作品は、やはりネットなどの乱歩ベストテンには、入っていないんですがねぇ。なぜなんでしょうか。 よろしければ、こちらでお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末 にほんブログ村 本ブログ 読書日記
2018.05.27
コメント(0)
-
乱歩と三島の話題作ながら(前編)
『黒蜥蜴・湖畔亭事件』江戸川乱歩(春陽文庫) ……かなり、というほどでもないですが、まぁ少し久しい昔に買った文庫本です。 以前から読もうと思っていたんですね。 乱歩は昔から気になっていた作家ですが、さほどまとめて読んだわけではありません。 ある時、意を決して乱歩作品を片っ端から読んでやろうと思ったことがあったのですが、ちょうどその時、わたくしの読書の「先達」とも言うべき女性から、「やめとき、失敗作も山ほどあるで」といきなりのアドバイスをいただき、あっさりなるほどと納得してしまいました。 で、なぜ『黒蜥蜴』なのかと考えますと、やはり三島経由かな、と。 三島由紀夫は一時かなりフェイヴァレットでしたから、そして三島の戯曲は、或いは小説よりも出来が良いといわれていましたから、そんな三島戯曲の元になったお話で、しかもそれが乱歩の原作だとくれば、そこにはグロテスクとアラベスクの饗宴、と思ってもさほどピント外れではありませんよね。 というわけできっと私は本書を入手し、しかし、これもよくあるパターンで、入手しただけで放ったらかしにしていたというわけでした。 で、いよいよ今回読みました。 もう、あっさりと白状してしまいますと、ちっとも面白くなかったんですね。 いえ、ちっとも面白くなかったは、少し語弊のある書き方でありましょう。 「グロテスクとアラベスクの饗宴」なんて、われながら訳の分からないものを期待しながら読んだからそうなのであって、はじめから乱歩の通俗小説と思って読んでいたら、それなりの面白さは充分感じられたはずであります。 しかし、そんなわけで面食らった私はネットでちょっと調べてみました。 乱歩作品ベストテンみたいなものを。 するとやはりベストテンの中に本作が入っていたりするんですね。 えーー? そんなにレベルの高い作品かぁ? と。 雑誌に本作の連載が始まると、とても評判になったなんてことも書いてあります。 さらに、後述の展開で私は三島由紀夫の文書を読んだのですが、やはり三島が褒めています。(しかしこれについては、これをもとに戯曲を書いたのだから、まぁ、当たり前ではありましょうが。)こんな感じの文章です。 「黒蜥蜴」は江戸川乱歩氏の唯一の女賊物であり、又、探偵に対する女賊の恋を扱つた点でも、唯一のものだらうと思ふ。私は少年時代に読んで、かなり強烈な印象を与へられたが、石原慎太郎氏なども戦後の少年期に読んで同じやうな印象を抱いたと言つてゐたから、原著の普及は十分でなくとも、テレビによる名探偵明智小五郎の名の普及と共に、十分現代の読者にアッピールするものを含んだ作品と思はれる。(「『黒蜥蜴』について」) 参考までに、乱歩の原作は昭和9年に雑誌『日の出』に一年間連載されています。『日の出』は、講談社の雑誌『キング』がバカ当たりしたので、新潮社が二匹目のドジョウを狙って創刊した大衆雑誌です。 そして上記の三島の文章は、三島戯曲『黒蜥蜴』が昭和36年に『婦人画報』に発表され、翌年東京で初演されるに際して書かれた文章です。 よく読めば、なんとなく「種明かし」が書かれていますね。つまり、…… 1.女賊物である。 2.少年時代に読んで強烈な印象を与えられた。 3.石原慎太郎も戦後の少年期に読んで同様の印象を持った。 ……うーん、ここまで来て私は、なぁんだ、そういう事だったのかと思い、いきなりお二人の女性(いちおう、「女性」)を思い浮かべました。 その「女性」とは、アニメ制作会社タツノコプロダクションの作品『タイムボカン』と『ヤッターマン』の「マージョ様」と「ドロンジョ様」であります。声はどちらも名声優小原乃梨子さん。 美人で悪人でサディスティックでマゾヒスティック(ドロンジョ様は毎回「お仕置き」までされます)で、このアニメが放映される日の夕方の時間帯には、日本中の若いお父さんがテレビの前に息子と並んで鎮座して見ていたという、あの伝説の名キャラクターです。 ……えっと、ちょっとヘンな方向(かつ個人的には興味深い方向、つまり幼年期の無意識なる性の目覚めというところですかね)に向かいつつある感じになってきましたので、ちょっと間を置きます。「興奮」を沈めますね。 ということで、このお話、次回に続きます。すみません。 よろしければ、こちらでお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末 にほんブログ村 本ブログ 読書日記
2018.05.12
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1