2009年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

ハッピーバースデー
先日放映されたTVドラマを見ました。 主役のあすかを演じた大橋のぞみちゃんも、なかなかの好演でした。 期待していた以上に興味深いお話しだったので、 ドラマを見ながら、ネットで本著を発注してしまいました。 本著を読んでみると、ドラマでは時間の関係か、 お話が随分カットされていることが分かりました。 ドラマ化されるとき、こんな風になるのはよくあることだけれど、 今回の場合、お話しの前半部分だけがドラマ化された感じになっています。自然の中で、祖父や祖母の愛情によって声を取り戻し、一回り強くて大きな人間になったあすかは、家に戻った途端転校することになります。その転校先の学校で、あすかが大活躍する様が、実に爽快で素晴らしいのですが、そのあたりのことは、ドラマでは一切触れられていませんでした。そして、あすかの勇気ある行動や言葉の数々が、いじめにあっていた友人やクラスの仲間、養護学校に通う友人や家族、教師、さらにはあすかの兄をはじめとする家族など、周囲の人たちをどんどん変えていくところが、実は、このお話しの最大の肝なのです。原作は、1998年に青少年読書感想文全国コンクール中学校の部の課題図書にもなった児童書版『ハッピーバースデイ 命かがやく瞬間』。そして、本著は原作では描かれなかった母・静代の心の闇や、娘のあすかを愛せない理由を明らかにした文芸書版。機会があれば、児童書版も読んでみたくなりました。
2009.11.28
コメント(0)
-

1Q84 BOOK2
最後の頁を読み終えたあと、 しばらくの間、本を閉じることが出来なかった。 呆然と思考停止したまま、心のやり場を見つけきれず、 身体も感情もそこで留まっているしかなかった…… もちろん、これまで読んだ作品においても、 こんなふうに、エンディングで行き場を失ってしまうことは多々あった。 それこそが、村上作品の真骨頂と言えるかもしれない。 しかし、今回はこれまでとは比べものにならないほどに茫然自失……エンターテイメントの面から言うと、これまでのどの作品よりも『1Q84』は面白かった。スリルとサスペンスに満ち溢れ、テンポよく展開する活劇に、次から次へとページを捲る手を止めることができない。青豆のお話しには『必殺仕事人』的色合いを持たせつつ、そこに純愛、ラブ・ストーリーがしっかりと埋め込まれている。一方、天吾のお話しでは、文学賞への危険な挑戦を描きつつ、村上さん定番の「書く」ことや「父と子」についても描いている。そんな二人の接点として「さきがけ」という宗教法人が登場。そこには『アンダーグラウンド』を執筆したことの影響が、とても色濃く感じられる。そして、その執筆経験が、これまでの村上ワールドと相まって、この作品で、見事なまでの新しい世界を構築させたのである。その新しい世界を象徴するのが「リトル・ピープル」という存在。もちろん、それが何ものであるかは判然としない。そして、もうひとつの象徴が「空気さなぎ」。天吾が、最後に空気さなぎの中に見たものは……このお話しでも、たくさんの人が次々に死んでいく。その理由は様々だが、お話しの展開の中で、とにかく色んなものが失われていく。そしてエンディング直前、作者は予想外の流れを用意し、実にあっけなく、読者からも奪ってしまうのである……それ故の茫然自失…… ***しかし、読者には朗報が。『1Q84』の第3部を村上さんが執筆中だという。『ねじまき鳥クロニクル』は、第1部と第2部が執筆された後、間を置いて第3部が書き下ろされた。『ねじまき鳥クロニクル』では、村上さんは第1部・第2部を発表する前から、実は、第3部を書くことを決めていたようだが、とりあえず、第1部・第2部を一つの完成した作品として先に刊行したという経緯がある。『1Q84』については、どのように考えていたのか明らかでないが、とにかく『1Q84 BOOK2』を読んで、茫然自失状態になってしまった読者にとっては、その心のやり場を見つけられる可能性が出てきたことに、ホッと胸をなで下ろしたことだろう。もちろん、私もその中の一人である。
2009.11.28
コメント(0)
-
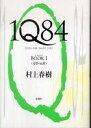
1Q84 BOOK1
1か月程前、『アフターダーク』を読み終え、『1Q84』を読み始めた。 そして、第1章を読み終えた頃、 本棚で順番待ちをしていた『村上春樹はくせになる』に、ふと手が伸びた。 この新書は、私が『1Q84』の先を読み進めることを強く押し止めた。 先に『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』を読むことにした。 それを読み終えると、『村上春樹はくせになる』を読んだ。 『1Q84』の第2章以降を読み始めるのに、ずいぶん遠回りをしてしまった。 しかしこの遠回りこそが、『1Q84』を読むに値する人間に、私を変えてくれた。そもそも『1Q84』について言うならば、私にとって、3冊くらいの遠回りは全く大した問題ではない。そう、この『1Q84』を読むために、私は、これまで何冊の作品や書物を読んできただろう。長編は『海辺のカフカ(上巻)』、『同(下巻)』 に始まって、青春三部作の『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』、『羊をめぐる冒険(上)』、『同(下)』『ノルウェイの森(上)』、『同(下)』、『ダンス・ダンス・ダンス(上)』、『同(下)』『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド(上)』、『同(下)』『ねじまき鳥クロニクル 第1部』、『同 第2部』、『同 第3部』『国境の南、太陽の西』、『スプートニクの恋人』とすべて読破。 短編集で読み終えたのは、現時点で『神の子どもたちはみな踊る』のみだが、本棚には順番待ちのものが数冊並んでいる。その他のものでは『ふしぎな図書館』、『辺境・近境』『シドニー!1.コアラ純情篇』、『シドニー!2.ワラビー熱血篇』、翻訳では『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読み終えた。あと、関連本では『村上春樹にご用心』、『謎とき 村上春樹』を読んだ。翻訳や関連本も、本棚で読まれる日が来ることを待っているものが数冊ある。とにかく、『1Q84』を読む前に村上さんの長編は全部読んでおこうと決め、ここに辿り着いた。だから、3冊くらいの遠回りは本当に大した問題ではない。そして、『アンダーグラウンド』を読み『約束された場所で』を読んだからこそ、さらに『村上春樹はくせになる』を読んだからこそ、気付き・理解できることがそこにあった。 ***「青豆」と「天吾」、二人を中心に据えたお話しが交互に繰り返される。村上さんお得意の、読者にはお馴染みのパターンだ。青豆は、自分がよく知っている世界、これまでそこにいたはずの「1984」年とは違う別の世界「1Q84」年に、自分が今では身を置いてるらしいことに気付いている。そこでは、警官の制服や所持している拳銃が違うし、自分の知らない事件が起こっていた。おまけに、空には月が二つも出ている。それでも、その事実にさして驚いたり戸惑ったりせず、すんなりと受け入れ、その世界に合わせて行動しようとする彼女の姿は、普通の感覚なら驚きだ。そんな彼女の周りには、老婦人と彼女に仕えるタマル、環というかつての親友(自殺した)に代わる新しい友人・警官のあゆみがいる。一方、天吾は、予備校で数学を教えながら、小説を書く柔道の有段者。出版社で編集に携わる小松に、17歳の少女ふかえりが書いた『空気さなぎ』という作品を新人賞の最終選考に残すよう推薦したことがきっかけで、その作品を書き直すことになる。もちろん、それがある意味において詐欺行為であることを承知しながら。最初、何の接点も見い出せない青豆と天吾の二人だが、それは突然に繋がってしまう。二人は小学校で同級生だったのだ。幼少の頃、天吾は日曜になると、父に連れられNHKの受信料の集金につき合わされた。一方、青豆は母に連れられ、証人会という宗教団体の布教活動につき合わされていた。4年生の秋、青豆が理科の実験の時間に、その布教活動のことで級友から揶揄される。その際、手を差し伸べ、自分の班に移ってくるように言ったのが天吾。それ以後、二人は言葉を交わすこともなかったが、12月初めの午後、青豆は天吾の手を握り、じっと彼の顔を見あげた。その後、両親と決別した青豆。そして、父と決別した天吾。その場限りの奔放な性生活を送る青豆。そして、既婚・年上のガールフレンドと週に一度の関係を持ち続ける天吾。しかし、青豆はこれまでに愛した唯一の男性として天吾をとらえ、秘めた思いを胸に、再会の日を持ち続けている。一方、天吾の青豆に対する感情は、それほどハッキリしたものではない。それどころか、今、二人が同じ世界にいるのかどうかすら本当のところ分からない……それでも、今後二人を結びつけるかもしれない、このお話の鍵を握る存在がある。それは「さきがけ」という宗教法人と「リトル・ピープル」。10歳の少女・つばさを救うため「さきがけ」に挑みかかろうとする青豆。17歳の美少女・ふかえりを通して「さきがけ」と関わることになるであろう天吾。『空気さなぎ』のストーリーがどのようなものなのかが、まだ明らかにされていない。それが明らかになるとき、お話しは確実に前進していくことになるのだろう。青豆と天吾の出会いはあるのか?そして、村上さんは「さきがけ」の将来にどんな結末を用意しているのか?
2009.11.23
コメント(0)
-

村上春樹はくせになる
『アフターダーク』を読んだ後は、 いよいよ『1Q84』を読み始める予定だった。 ところが、その前にヒョイッと手にしてしまったのが本著。 村上さんの代表作について、文芸評論家の清水さんが書き記したものである。 ところが、本著の始まりは『アンダーグラウンド』について。 その時点で、私はまだそれを読んでいなかったし、読む予定もなかった。 なのに清水さんは「序」において、その作品が村上さんにとって ターニングポイントになる重要な作品であると述べる……読むしかない……。と言うことで、本著を読むために『アンダーグラウンド』を読み、さらに『約束された場所で』を読むことになってしまった。随分時間がかかったが、この二冊を読み終えて、本著を読んだことはとても大きな意味があったと、今では思える。これまでにも、村上さんの作品について述べたものとして、『村上春樹にご用心』や『謎とき 村上春樹』を読んだが、本著ほど、各作品を深読みし関連付けて、村上ワールドを語っているものはなかった。そう言う意味で、本著は村上作品に対する新しい視点を私に与えてくれた。しかし、ちょっと深読みが行き過ぎて、作品そのものを楽しむというよりも、作家・村上春樹の姿を、何とかその中に見出そうとし過ぎているような気もする。もちろん、そこで著者が述べていることの多くは、至極妥当なものだとは感じるが……そんな中、次の記述は、私をノスタルジックな感慨に浸らせてくれるものだった。 60年代はまだ日本は貧乏な発展途上国だった。 舗装されていない道路がいっぱいあったし、食べ物の種類も娯楽も少なかった。 田舎は田舎らしかったし、庶民は庶民らしく、学生は学生らしかった。 子どものころから大学生になるあたりまで、ほぼそういう日本の姿が続いたので、 それが私たちの世代にとって脳裏に刻まれている日本の原像なのである。(P.151)著者は私よりは世代的に上の人物ではあるが、この文章に描き出された日本の姿は、私の記憶の中にも確かに存在する。なのに、それを知る者の多くが、普段そのことをすっかり忘れ去ってしまっている。そして、何か大切なものを、そこに置きざりにしてしまったような気がする。
2009.11.22
コメント(0)
-

オリの中の虎
岡田さんがオリックスの監督に就任したのは10月14日。 私が本著を書店で購入したのが11月9日(発売開始は11月5日)。 そして、本著に記された発行日は11月20日。 こんな短期間に新書が一冊完成し、発売された。驚きのスピードである。 もちろん、本著は岡田さんがオリックス監督に就任する前から企画され、 ある程度(と言うかほとんど)出来上がっていたのだろう。 それにしても、プロローグの内容は未だにホットでタイムリーなもの。 これを巻頭に持って来たベースボール・マガジン社は、さすがである。それにも増して、岡田監督の就任後の動きはスピーディーである。秋期練習を公開したり、チーム再建に向け渇を入れる言葉を次々に発表したりさらには選手登録明を公募したり、田口選手や矢野選手の獲得に意欲を見せたり等々。そこには、仰木監督や野村監督ら、名将に似たものを感じる。 「マイナス思考」というと、消極的で受け身の悪い意味になってしまうけど、 おれの監督としての気持ちの持ち方はずっと 「マイナス思考」「マイナス覚悟の思考」であったよな。 だからこそとてつもないことが起こっても、冷静でいられる。 最悪のことを考えているから、何があってもしっかり受け止められる。 「打たれる」と思って見ていたら、打たれても「ああ打たれよった」ってことだけやん。(p.034) 野球の監督は、悪いこと考えて、ええこと起きればそれでええ、というんがおれの考え方。 やられたときにどうする、それを先に考えておいたら、ベンチでどっしり構えられる。 あたふたしたところは、相手チームにも、自分とこの選手にも見せたらあかん。(p.043) 打つほうもそうや。ここで打ってくれへんかななんて、思わん。 そう思うてないのに打ったら、ああ打ってくれよったでええやん。 願望、願望でベンチから見とったら、そんなんどないもならんわ。 願い事というんは、なかなか、かなわんもんや。 願望でさい配しとったら、あかん。(p.052)徹底した悲観論というか、危機管理意識というか……岡田彰布とはこういう人だったんだということを実感できる発言の数々である。確かに、岡田監督の采配にはバタバタとしたところが、ほとんどなかった気がする。先を読みながらチームを指揮しているとは感じていたが、その根底にある考えには気付かなかった。 1.自分が黙っていたら、相手が勝手にしゃべる。 2.自分が動かんかったら、相手が動く。 3.相手が動くと、対策を立てられる。 4.サインを出すから見破られる。 5.サインを出さんかったら、見破られない。 6.メッタに打たん選手が打ったら、次は打つ確立は低い。 7.ずっと打っている選手が打てなかったら、次は打つ確立が高い。 8.出番の少ない選手が打ったら、続けて使って凡退させるより、 いい感触のままベンチに下げたほうが、次の出番でいい結果が出る。 9.ドラフト上位で獲った選手は、そのときがベストの状態だから、 打ち方や投げ方を指導者が変える必要はない。 10.何もしないのが一番いいさい配。 11.ベンチが何もせず、普通に勝つチームが一番強い。(p.054)「岡田の法則」とある記者が名付けたものである。最後の二つが、岡田監督がめざすさい配、チームづくりである。 その翌年から阪神の一軍監督になった野村克也さんは、 「プロ野球で教えるべきことは、選手の短所を直してやることや」と言う。 おれは逆なんやなあ。二軍は特に、長所を伸ばしてやるべきやと思う。(p.135) おれがほかの監督と決定的に違うのは、こういう野球をやりたい、というのがないことよ。 おれは預かった戦力でどう勝つかが、監督のさい配やと思うてる。 だから戦力も見ずに、戦力とは関係なく、こういう野球をやりたいとか、 おれのやりたいのはこういう野球やとかいう人の意味が分からん。 だから最高のさい配は、何もしないことよ。 何もせず勝てる戦力が、一番強いということやねん。(p.141)試合に勝つことが目的という岡田監督。このチームを、この戦力で勝たせるためにはどうしたらいいかを考えるという岡田監督。いつも通りの勝ちパターン、安心して見ていられるけど、面白くない試合をするチームにオリックス・バファローズを変貌させてくれることを願っている。
2009.11.22
コメント(0)
-

約束された場所で
タイトルに“undergrond2”という表記が見られるように、 『アンダーグラウンド』の続編である。 地下鉄サリン事件の被害者側にスポットを当てた『アンダーグラウンド』に対し、 本著は加害者側となったオウム真理教の信者や元信者たちが主役である。 村上さんのインタビューに臨む姿勢にも、大きな違いがある。 『アンダーグラウンド』では、語り手が語りたいことを語りたいように語ってもらう 徹底した聞き手であったのに対し、 本著では、村上さんの思ったことや聞きたいことを、相当語り手にぶつけている。8人のインタビュイーには、やはり共通するところが多い。教団内での立場や事件後にとった行動は、それぞれに違いながら、あちら側にいる彼ら彼女らの心の内に漂っているものには、同じものがあると感じた。そして、村上さんが言うように、こちら側にいる私たちの心の内にもそれは確かに存在する。ところで、私自身は、本著の中で、信者や元信者へのインタビューの中よりも、村上さんと河合隼雄さんとの対談の中に、興味深い部分が断然多かった。 たとえばさびしい人気のない夜道で棒を持った変な男とすれ違うとします。 実際には162センチくらいのやせた貧相な男で、 持っている棒もすりこぎくらいのものだったとします。 それがファクトです。 でもすれ違ったときの実感からすると、 相手は180センチくらいの大男に見えたんじゃないかと僕は思うんです。 手に持っていたのも金属バットみたいに見えたかもしれない。 だから心臓がどきどきする。 それでどっちが真実なのかというと、あとのほうじゃないかと思うんです。 本当は両方の真実を並列しなくちゃならないんでしょうが、 どちらかひとつしか取れないとなったら、僕はあくまで断りつきですが、 ファクトよりは真実を取りたいですね。 世界というのはそれぞれの目に映ったもののことではないかと。 そういうものをたくさん集めて、 総合していくことによって見えてくる事実もあるのではないかと。(p.282)この村上さんの発言には「なるほど!」と頷かざるを得ない。確かに、私たちが感じ、考え、そして生きているのは「真実の世界」の方なのである。しかし「真実の世界」にばかり生きようとすれば、他者との共存は難しくなってしまう。なぜなら「真実の世界」は、一人ひとり独自の世界であり、全く別物なのだから。それ故、人々がこの世に共存し、この社会を成立させていくためには、共通認識としての「ファクト」が、絶対必要不可欠なものになってくる。逆にその大前提がなければ、人々は安心して過ごすことができない。「真実の世界」を社会に持ち込み、共有を強要する人に対し警戒心を抱かずにはいられない。 たとえば「鉄人28号」という物語がありますね。 ああいう類のヒーローはばあっと空を飛んで人を助けに行きます。 小さい子どもがそれを読んで、自分でそのつもりになって、 風呂敷を首に巻いてパーっとやっているわけです。 しかし実際にはそれで2階から飛んで死んだ子がいるかというと、それはいません。 子どもっちゅうのはすごいんですよ。 ストーリーがものすごく生きているんですが、 それと外的現実とのあいだをきれいに調整しているんです。 ときどき物語を真っ向から批判する人がいます。 ファンタジーとか言って、魔法の杖を使ってひょいと空を飛んだりしている、 これはけしからんと。 子どもが魔法の杖を使えば勉強ができるなんて思ったら、 こつこつと勉強しなくなるじゃないかと。 でもね、必死に勉強すれば偉くなりますなんて言うほうがもっと大嘘です(笑)。(p.286)この河合さんの発言こそが、「ファクト」と「真実の世界」との折り合いのつけ方の極意ではなかろうか。
2009.11.22
コメント(0)
-

アンダーグラウンド
読み切るのにとても時間がかかった。 ページ番号の最後の数字は777。 分冊にしてもよさそうなボリュームの本だが、 村上さんは、そんなこと絶対にしないだろう。 そう、これは全部読み切ってこそ価値がある本だ。 それまでに時間がどれ程かかろうと、 途中で読むことに飽きてきたり、苦痛を感じたりしようと、 とにかく、最後まで読み切らねばならない。本著は、1995年に発生した地下鉄サリン事件に関わった人たち62人に村上さんがインタビューしたものをまとめた作品である。インタビューの内容は、事件そのものについてだけでなく、それぞれの人たちのこれまでの人生や日々の暮らしぶりにまで及んでいる。もちろん、新聞やTVが事件そのものについて報道する場合、こんなにプライベートなことにまで踏み込むことは、通常ありえないし、そこまでするのは、また別の部分の仕事となる。なぜなら、それを成し遂げるには多くの労力と時間を要し、即時性にも欠けてしまうから。だが、村上さんはこの目も眩むような膨大な作業をほぼ自力でやり遂げた。読むのが大変なほどだから、インタビューしてまとめ上げる苦労は推して知るべしである。しかしその労力があったればこそ、私たちはあの事件の奥底に、これほど多くの人たちの人生が存在したことを、改めて認識することができたのだ。 ***いつも通りの行動の中で、あの事件に巻き込まれた人たちがいる。そうではなく、あるきっかけで、その日は通常と違う行動になってしまったために、あの事件の現場に遭遇することになってしまった人たちもいる。ちょっとした偶然の積み重ねが、その人を当事者にしたりしなかったりしている。そう、たった電車1本分の発車時刻のズレによって、或いは、乗り込んだ車両の場所の微妙なズレによって、さらに、事件発生後に歩んだ道のりや、そこでとった行動によって違いが生じた。その違いは本当に微々たるものだが、その結果の違いはあまりにも大きい。事件に巻き込まれた人たちには、あの事件が発生する前には、その一人一人に、それぞれ別の人生があった。そして、事件に遭遇した後も、一人一人に別の人生がある。そして、事件への思いも、またそれぞれである。当たり前のことだが、新聞やTV報道で事件の表層ばかりをなぞっていると、そんなことを、ついつい忘れてしまいがちだ。どうしても、事件そのものやそれに関わった人々を一括りのものとして認識しようとし、ステレオタイプな思考に陥ってしまう。 ***最後に、膨大な数のインタビューの後に掲載されている、村上さん自身が、地下鉄サリン事件に言及した「目じるしのない悪夢」の一節を示す。 このような言い方は、あるいは無用な誤解を招くかも知れない。 しかし今述べた仮説を延長していった場合に到達する きわめて広いグラウンドの真ん中に立って、私は実はこう思っている。 「こちら側」=一般市民の論理のシステムと、 「あちら側」=オウム真理教の論理とシステムとは、 一種の合わせ鏡的な像を共有していたのではないかと。 もちろんひとつの鏡の中の像は、もうひとつのそれに比べて暗く、ひどく歪んでいる。 凸と凹が入れ替わり、正と負が入れ替わり、光と影が入れ替わっている。 しかしその暗さと歪みをいったん取り去ってしまえば、 そこに映し出されている二つの像は不思議に相似したところがあり、 いくつかの部分では呼応しあっているようにさえ見える。 それはある意味では、我々が直視することを避け、 意識的に、あるいは無意識的に現実というフェイズから排除し続けている、 自分自身の内なる影の部分(アンダーグラウンド)ではないか。 私たちがこの地下鉄サリン事件に関して心のどこかで味わい続けている「後味の悪さ」は、 実はそこから音もなく湧き出ているものではないだろうか?(p.744)
2009.11.08
コメント(0)
-

パパママムスメの10日間
もちろん『パパとムスメの7日間』の続編である。 あのお話しから2年が経ち、小梅は女子大生に。 ケンタ先輩との清い交際は、まだ続いている。 語り口調も、ちょっと大人に近づいたようだ。 恭一郎は、新設された新商品企画開発部の部長になっていた。 部内には、あのレインボー・ドリームを開発した時と ほぼ同じメンバーが集まり、平和で穏やかな日々を過ごしている。 何と、あの西野さんまで、そこにいるのだ(信じられない!!)。そこに、今回は恭一郎の妻であり、小梅の母である理恵子も絡む。3人は大雨の中、近くに落ちた雷の衝撃によって、心と体が入れ替わる。パパの身体にムスメの心が、ママの身体にパパの心が、ムスメの身体にママの心が。前回に比べ、相当に複雑。初めての経験故、最も混乱してしまった理恵子は、お話し全体を通じて活躍度がやや低調で、あまり良いイメージが残らなかった。ハンバーガーショップでのバイトが上手くこなせないだけならまだしも、調子に乗って酒を飲み過ぎ、昔懐かしい曲に合わせ踊りまくるだけでは、あまりに寂しい。それに対し、前回と同じ状況となった小梅は「勝手知ったる」とかなり余裕を見せつける。会社で行動を共にするメンバーがほぼ同じという幸運にも恵まれていた。それでも、中嶋に、新開発商品「スイッチ」の商品リストから原材料だけを抜き出し、まとめておいてくれと指示したのは、駆け出しの女子大生にしては少々出来過ぎか。そして、今回の「スイッチ」絡みのビジネスシーンで、最も際立った活躍を見せたのは、理恵子の身体を借りたままの恭一郎。理恵子の姿のまま、商品研究所部長の室田を訪ね、真実を語ることを迫った際の言葉の数々は、まさにMVPものである。さて、冒頭部分と関連づけられた、親子3人・絶体絶命のシーンのオチは、ある程度予測がつくものとはいえ、誰もが納得するものだろう。そして、もしこのお話しに続きが描かれるとしたら、今度は、理恵子がMVPを獲得できるようなものにして欲しい。
2009.11.07
コメント(0)
-

パパとムスメの7日間
TVドラマが放映されているときは、あまり真面目に見てなかった。 それでも、パパは舘ひろしさん、ムスメは新垣結衣さんというイメージが、 しっかりと頭の中にインプットされてしまっていた。 そして、本著を読んでいても、そのイメージが抜けきることはなかった。 お話しは、五十嵐さんの作品だから、間違い無し・文句なしに面白い。 パパとムスメが、それぞれに一人称で語るパートが、 交互に繰り返されることになるが全く違和感がなく、流れはとてもスムーズ。 まぁ、ムスメの語り口調が、こうして活字になるとなかなかスゴイと感じたが……。それにしても、この作品では、父親と高校生の娘の距離感が、実に絶妙に描かれている。エンディングも、決して説諭調に陥ることなく、見事なしめくくりである。そう、7日間くらいお互いの身体をチェンジし、相手の立場を経験しただけでは、父と娘の距離感なんか、そう簡単に縮まりきることはないのである。だからこそ、このお話しの始まり、ビデオの中で動きまわる、幼い小梅を見つめる恭一郎の姿には、父親なら誰もが、心を震わせてしまう。そして、「わかるよ、うん、とってもよくわかる」と肩を叩き、声をかけてあげたくなる。一方、御前会議での小梅の奮闘ぶりは、このお話の最大の見せ場である。このエピソードがあるからこそ、このお話しは、その辺にあるありふれたフツーの作品ではなく、流石の五十嵐作品となった。そして、このエピソードは、恭一郎の姿を借りた小梅だからこそ成り立つのである。さて、この作品において、五十嵐さんがパパの立場に立って、パパの心境を描くことは、それほど難しいことではなかっただろう。しかし、五十嵐さんがムスメを描くことは、そう簡単ではなかったはずだ。表面的な言動を描くことはできても、内面の機微を描き出すのは難しい。実際のところ、女子高生は、この物語のムスメに共感できたのだろうか?そして、ここに描かれたムスメの心境は、スタンダードな感覚なのだろうか?そんなことがハッキリとは分からず、そんなことがいつまでも気になってしまうのが、オヤジという存在である。文庫版、巻末の解説は、あさのあつこさんによるものである。短い文章ながら、女性としての視点に満ち溢れ、男性作家の作品を見事に補っている。これまた、流石である。
2009.11.07
コメント(0)
-

しがみつかない生き方
香山さんのこれまで著作の中でも、売り上げ数は相当上位になるのではないか。 もちろん、次々に新しい著作を世に送り出し続けているのだから、 これまでの彼女の著作は、どれもそれなりには売れているのだろうが、 ランキング上位をこれほどキープし続けたのは、初めてではなかろうか? なぜ、本著はこれほどまでに売れたのであろうか? そう言う私も、新聞広告を見た瞬間「これは買いだ!」と思った。 それは「<勝間和代>を目指さない」という見出しが目に入ったから。 それ以後、週刊誌でもこの二人のことが、結構取り上げられた。しかしながら、実際本著を手にして読んでみると、予想以上にライトでアラカルトな一冊である。そして、本著は序章と10の章からなっており、そのテーマは、現代受けしそうな内容のオンパレードである。 序 章 ほしいのは「ふつうの幸せ」 第1章 恋愛にすべてを捧げない 第2章 自慢・自己PRをしない 第3章 すぐに白黒つけない 第4章 老・病・死で落ち込まない 第5章 すぐに水に流さない 第6章 仕事に夢を求めない 第7章 子どもにしがみつかない 第8章 お金にしがみつかない 第9章 生まれた意味を問わない 第10章 <勝間和代>を目指さないどれもこれも、「……べき」「……であらねば」と思って日々頑張っている人たちに、「もっと肩の力を抜いて……」という癒しの言葉が、見出しとして見事に並んでいる。確かに、勝間さんの著作とは、真逆の方向性が見て取れる。そして、そういう言葉を求めている人は、実はとても多く、それ故売れに売れている。さて、私は『二重洗脳』を読んだ直後、本著を読んだので、この二つの著作の間にある類似性に、大いに驚かされることになった。そして、現代人はある意味、色んな依存症に冒されている、洗脳されているのかも知れないと気付かされたのだ。 論理療法では、この「……べき」や「……ねばならない」を含む思考が、 不適切な感情を引き起こす「誤った思い込み」の代表例だとし、 これを「イラショナル・ビリーフ」(論理的でない信条)と呼びます。(中略) そうした「べき思考」を持っていると、何かうまくいかなくなると、 「だから自分はダメなんだ」とか、 「もう幸せになれない、生きている意味がない」と思ってしまいます。 うつ病にかかりやすい人は、性格が几帳面でまじめなことがわかっています。 こういう人は、もともと「ちゃんとすべき、そうしなければダメ」と考えやすい人と言えます。 (『二重洗脳』p.165~)本著は、洗脳された人々に「気づき」を与えることで、ドーパミン神経を回復させ、元々感じられたはずの安らぎや幸福感(本著で言う「ふつうの幸せ」)を取り戻し、現代社会にはびこる「歪曲した理想像」への依存症から解放しようとするものなのだろう。さすがに、精神科医・香山リカである。
2009.11.07
コメント(0)
-

二重洗脳
カタイ本である。 内容でなく、本そのものがカタイ。 コシのあるイイ紙を使ってるからのようだが、 読んでいて、本を持つ手がとても疲れた(と言うかイタかった)。 本には、やはり適度なシナリが必要なことが分かった。 あまりに薄すぎて、頼りないペラペラなものは論外だろうが、 その逆も、とてもヤッカイなものであると今回気付かされた。 読むことに集中しきれないまま、最後まで読み切った。さて、本著で言う「二重洗脳」とは、「ごほうび」と「恐怖」による「洗脳」。「恐怖」に裏付けられた「ごほうび」からは、人は簡単に抜け出せなくなってしまう。カルト教団は、この「ごほうび」の魔力を最大限に利用しており、また、このカラクリは、依存症のもたらす効果に極めて似ているのである。薬物を使用すると、脳からドーパミンが無理矢理搾り取られ、神経の感受性が低下する。すると、通常ならドーパミンが出て、開放感・幸福感が感じられるはずのことに対しても、ドーパミンが出にくくなっているので、幸せを感じることができなくなってしまう。そして、開放感・幸福感の不足を補おうと、また薬物に手を出してしまう……本著ではこれを「失楽園仮説」とよび、度々登場する言葉となっている。つまり、薬物使用が、日常的な幸福・楽園を喪失させてしまうという考え。この悪循環は、タバコやアルコール、その他諸々の薬物によってだけでなく、ギャンブルやゲーム、セックスにおいても発生する。レバーを押すと気持ちよくなる、レバーを押すこと以外に楽しいことは何もない、そしてレバーを離すとビリッとくる。こんな実験を徹底的に行われたネズミは、もうレバーを押し続けるしかない。カルト教団が用意する「暴力的な恐怖」の効果は絶大である。 *** 「人は他人にあいさつすべきだ」と思っていると、無視されると腹が立ちます。 「先生は生徒から愛されるべきだ」と信じていると、嫌われると激しく落ち込みます。 これに対して、「あいさつするのが、愛されるのが望ましい」くらいに思っておけば、 「残念だ」くらいで済むでしょう。(p.165)本著「SETEP4」では、はまった脳をリセットする方法が紹介されている。それは「気づき」の連鎖で「誤った思い込み」をリセットし、依存行動をストップすることでドーパミン神経を回復させ、安らぎ・幸せ・ストレス対処力を回復させる。さらに、フラッシュバックを反復学習で克服し、依存症から解放されるというもの。依存症に陥っている人にとっては、どの段階の行動もそう簡単なことではないだろう。「思い込み」を「気づきの連鎖」で「リセットする」ところから、相当難しいと思う。ましてや、それを受けて「依存行動をストップする」のは並大抵のことではない。それでも、本著の中に示された実例は、そんな人たちにも光明となる可能性がある。
2009.11.07
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1










