2009年02月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
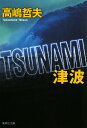
TSUNAMI 津波
『M8』から6年後の物語。 瀬戸口誠二は日本防災研究センターの地震研究部長、 松浦真一郎は陸上自衛隊の一等陸尉、 河本亜紀子は防災担当副大臣として活躍している。 そして、新たなキャラクターとして、黒田慎介が登場。 大浜市役所防災課職員で、 太平洋沿岸地域の市町村防災課職員に呼びかけて、 独自の地震、津波ハザードマップを作っている。黒田は日本防災研究センターに通い、瀬戸口の研究を手伝っていた時期があるという設定。黒田の活動は、物語序盤では、あまり注目してもらえていないが、最後のクライマックスシーンでは、彼の活動が大きな役割を果たすことになる。また、黒田の彼女は美智というサーファー。物語終盤で、ある大物人物の娘であることが判明する。 ***東海・東南海・南海の三つの海溝型地震が起こると、日本列島の半分を飲み込んでしまう大津波が発生する。『M8』による平成大震災の時、都知事として、瀬戸口たちと大活躍した漆原が、今度は、総理大臣として、この危機に立ち向かう。『M8』に比べると、地震・津波発生後の危機に瀕した街の様子や人々の描写が詳細・鮮明で、その恐ろしさは比較にならないほど。そんな中で、特に目を引くのは、米軍ニミッツ級原子力空母に乗船していた松浦と、大浜原子力発電所四号機、第二班の当直長・三戸崎俊一の活躍。そして、私が個人的に、本著の中で最も心に残った部分は、名古屋で地震が発生し、大きな被害が出ているにも関わらず、大浜の海岸に、サーフィンの世界的イベントを断行しようと、多くの若者たちが、続々と押し寄せ、騒いでいるのを、黒田が、苦々しく見つめている場面。 <神戸から大阪に向かう電車で、ふと武庫川の河川敷を見ると野球をやってるんだ。 中学生くらいの子どもたちだった。 川を渡るとテニスコートが見えて、のんびりテニスをしている。 ほんの十数分前の光景はビルが倒れ、家が崩れ、瓦礫の山が続き、 焼け野原が広がっていた。 その中にすべてを失った被災者が立っている。 瓦礫の中にはまだ遺体があるかも知れないんだ。 これが同じ時間、同じ空間で同時に起こっている。 なんだか、嘘みたいな気分だった> 昔、聞いた、阪神・淡路大震災の話を思い出した。 これは誰から聞いたのか-。瀬戸口先生だ。(p.312)実際、この通りだった。ただし、武庫川あたりなら、まだ多少なりとも、震災の空気というものを感じることが出来た。しかし、さらに東進し、大阪まで行ってしまうと、本当に別世界だった。人々の動きも、表情も、何もかもが、以前と何も変わっていない。神戸が、そして、淡路や芦屋・伊丹・宝塚・西宮等がすっかり変わってしまったというのに……。それらが連続した空間であることが、私にはとても信じられなかったことを思い出した。 ***エンディングでの瀬戸口と河本亜紀子の会話、そして、瀬戸口の黒田の会話だけは、本当に余分だった。そこまでの盛り上がった気分、感情の昂ぶりが、一瞬にして冷めてしまった。災害三部作最終作『ジェミニの方舟』を読むのを、躊躇してしまう。
2009.02.27
コメント(0)
-

ピアノの森 11
佐野先生から、誉子の異変を指摘される司馬先生。 そして、コンクール辞退と治療専念を、誉子に勧告する司馬先生。 さらに、佐野先生は、司馬先生に、カイと阿字野壮介のつながりを指摘。 そんなカイが、JAPANソリストコンクールに出場することも伝える。 誉子に何も知らせぬまま、飛行機に乗せ、 誉子を大分のコンクール会場に連れて行く司馬先生。 会場には、佐野先生の姿が。そして、もちろん阿字野も。 いよいよ、誉子の前にカイが姿を現した。待ちわびた感動の涙の瞬間。 手を…手を……治したい!! あなたと同じ…舞台に立ちたい!! ああ…こんなにも……あたしは、ピアノが弾きたいカイの演奏は、控え室でモニターを眺めるM響のメンバーの心までも捉えていた。 「どう思う?」 「どう思うも何も、こんな『月光』……今まで聴いたことがあるか?」 「荒削りだが何とも新鮮だ。優等生の俺たちには持って来い…のカンフル剤だと思わんか?」 「はは…聴けば聴くほどドキドキするぜ!」 「初めてマジで採りに行く?」 「このコンクール…“ソリスト・コンクール”とは名ばかりで… 実際は、この後にやる音楽会のオマケ的存在だったけど…」 「ははは、人聞きの悪いコトを言うな。これまで欲しいヤツがいなかっただけだ」 「でも…無名の16歳の少年に、M響が“ソリスト”として声をかけるんだぜ。 これは前代未聞だぞ」演奏終了の瞬間は、本当の演奏を目の前で聴いたかのような感動が、私の胸に押し寄せてきた……。この作品は、本当に凄い!!そして、誉子は、会場前の公園の森の中で、カイと久しぶりの対面を果たす。
2009.02.21
コメント(0)
-

ピアノの森 10
冴ちゃんが登場してから、 何だか、お話しの雰囲気が変わっちゃったなぁ……。 これまでは、あくまでも「ピアノ」のお話しだったのに、 「ラブ・ストーリー」になってしまってる……。 周囲から、男についての色んなことを吹き込まれ、 疑い、迷い、振り回され、男を信じられなくなる女。 そんな心の行き違いや誤解を、何とか解消しようとする男。 ま、それも森のピアノで解決してしまうけれど。本巻後半の主役は、丸山誉子(待ってました!!)。カイと再会することを夢見て、ピアノコンクールに出まくっている。その奔放な演奏は、審査員の心をも動かし、特別賞は取り続けているが、コンクールの演奏としての評価を得ることは、やはり出来ないでいた。その演奏スタイルに業を煮やし、誉子から去っていく浪花音大教授。その様子を見ていたのが、あの司馬先生。 私は、今回審査員をやらせていただいた司馬と申します。 これで7回目かな。キミの演奏を聴くのは…。 キミさえよかったら、僕のところにレッスンに来ないかな?それに対して、誉子が発した言葉。 一つ質問していいですか? 7回聴いた…ってことは…もしかして“全日本学生コンクール中部大会”の予選も? じゃあ、一ノ瀬海という男のコのピアノ、覚えてますか?「もちろん!特別のピアノだったからね」と答える司馬先生。そりゃそうだ、あの審査の時、誰もが論外としたカイの演奏を、先頭を切って評価しようとしたのが司馬先生だもの。佐野先生だって、あの時点では、ホンネを表には出していなかった。 じゃあ、どうして一ノ瀬海は予選を通らなかったの? どうして落ちたの?司馬先生に、鋭く問い質す誉子。たしなめようとする白石を、制止するように答える司馬先生。 いや…簡単な答だよ。 それは…審査員全員がボンクラだったからだ そんなボンクラには教わりたくないかい?そして、誉子は、司馬先生のもとで、レッスンを受けることになる。う~ん、ピッタリの組み合わせだ!!目指せ!ショパン国際ピアノコンクール!!しかし……その推薦オーディション会場に現れた佐野先生。誉子の演奏のレベルの高さに満足しながらも、その異変に気付く。そんな佐野先生は、マリアのピアノに夢中。その演奏に心酔し、姿を消したマリアの行方を追う。そんな中で、かつて憧れていたピアニスト・阿字野壮介が、ピアノ科教授として、大学に復帰していたことを知る。
2009.02.21
コメント(0)
-

ピアノの森 9
カイがピアノを教えている大貴少年によって、 「心を正常に戻す時間」を与えられた修平。 そんな修平の前で、久しぶりにピアノを弾くカイ。 そして、逃げずに、このピアノを超えることを、心に誓う修平。 修平に、ピアニスト時代の阿字野のビデオを見せてもらったカイ。 その演奏の凄さに、そして、これほどの腕を持ちながら、 それを失ってしまった阿字野の苦悩に思いを馳せ、涙するカイ。 このピアノを、世界の全てを超えろと、カイに声かけする阿字野。さて、本巻のメインは、ここから。父・洋一郎のピアノリサイタルに、久しぶりに出かける修平。そこで、修平は、身近にいた父の、本当の偉大さに初めて気付く。そして、自分自身の目指すところを発見する。リサイタル開始前、会場にやってきた音大生の女の子たちが、父・洋一郎のピアノについて話している。その会話が、修平の耳に聞こえてくる。 「どうして雨宮洋一郎が、日本で唯一、会場を満席にするピアニストなのかわかる?」 「えー、一種のブランドでしょ!世界にも通用する“癒しのピアノ”の…」 「そんなの答えになってないわよ!音大生のくせに~!」 「じゃあ、教えてよ!」 「シィー、終わったらね」 その演奏に、大きく心を動かされる修平。そして、終演後。 「ねえ、会場を満席にする理由わかった?」 「なに?教えてよ」 「雨宮洋一郎のピアノを聴くと心が落ち着くのよ。 それは彼の持つスケールが要因してるかも…って チャンスがあったら、一度はナマで聴いておきなさいーって、阿字野先生がおっしゃって…」 「ヤダ、また阿字野先生の受け売り?」 「そうよ。だってあたしは、阿字野壮介教授を崇拝する…彼の優秀な教え子よ。 でね…阿字野先生がピアニストには二種類あるって言うの。」 「うまいのとヘタなの?」 「ううん。もう一度聴きたいか、そうでないかですって! 雨宮洋一郎氏は前者の最前線にいるピアニストだって!」その後の父と子の対面の場面は、本当に超感動的!!さらに、番外編「調律師・カイの巻」では、誉子との絡みが絶妙!そして、新たなるキャラクター、彫り師の冴ちゃん登場。マリアファンの冴ちゃんは、遂に二人で飲みに行く機会をゲット。たっぷり飲んでから、二人で冴ちゃんの家へ。実は「俺、男なんだ」と、カミングアウトするカイ。そして、二人は……
2009.02.21
コメント(0)
-

内側から見た富士通「成果主義」の崩壊
「成果主義」を他社に先駆け導入したものの、 その失敗により、大きなダメージを被ることになった富士通。 なぜ、富士通において「成果主義」は、成功に至らなかったのか? 当時、富士通人事部に在籍した著者が、その原因を明らかにする。 シリコンバレーで大きなメリットを生み出したシステム・理論を、 「年功序列」でガッチリ固定されきった環境に、いきなり持ちこんだ富士通。 しかも、そのねらいは、実は「人件費抑制」だった。 上辺だけの「成果主義」導入の危うさ……。シリコンバレーに多く見られる企業群と、日本国内で十分成熟してきた大企業とでは、当然のことながら、その企業の置かれた環境や、社会的地位・役割等は、かなり違う。また、その職場における、社員の労働に対する姿勢や想いにも、大きな開きがあるだろう。さらに、日米における差というものも、決して見過ごせないものがある。これらの壁を打ち破り、「成果主義」というものを企業内に根付かせ、それを企業発展の大きな起爆剤とすることは、そう容易いことではないだろう。まさに、日本の企業から、グローバル・カンパニーへと、完全に生まれかわる覚悟が必要。社員も、日本企業で働くのではなく、外資系企業で働く気概を求めらることになる。それだけの覚悟が、企業・社員の双方に、本当に出来ているのかどうか、それが、「成果主義」を導入する際、最大のポイントになると私は思う。どちらか一方に、その「つもり」がなかったとすれば、それは、成功に至らずとも、決して驚くべきことではない。ましてや、双方ともに「実は、本気というほどのものでは……」という状況での導入なら、失敗するのは、火を見るよりも明らかである。富士通の場合は、どうだったのか?著者が言うように、トップや管理職の問題だけだったのか?「成果主義」を成功させるためには、企業も社員も全てが変わらなくてはならない。さらには、それを取り巻く社会そのものや、国民性までも変えてしまう必要があるのではないか。「労働」というものに対する「意識」、「企業で働く」ということに対する「意識」。これらの「意識改革」なくして、「成果主義」に未来はない。
2009.02.21
コメント(0)
-

島国根性 大陸根性 半島根性(読書後)
本著のタイトルを見て、とても興味を引かれ 「読みたいな」と思って、購読候補に挙げ、 そんな記事を書いてから、もう2年が過ぎてしまっていました。 やっと読み終えての感想は、「やっぱり面白かった!!」 日中韓の政治的ケンカは、激しく頻繁。 それも、戦後の平和が60年も経過した現在に至っても、未だに継続中。 と言うより、著者によると、戦前より、今日のケンカの方が、 はるかに激しく、幼稚さに満ち、たいへん感情的なのだとか。そのケンカの原因は、やはり相互理解ができていないから。 中国や韓国の人々と付き合えば付き合うほど、 「あの国のことはわかりにくい」という結論に至っている。 「中国はまことに不思議な国である」とか、 「韓国や北朝鮮はまことに不可解な国柄だ」と。 中国、韓国もそれはしかりで、「日本は本当に不可解な国だ」と皆がいう。 なぜこうなるかといえば、よく似ているという思い込みが、 かえって理解の壁になるからだ。(p.21)三国は、地理的に近い場所に存在し、そこに暮らす人々の外見も大変似ています。それ故、相手を「他者」として見ることが、基本的に出来ていないらしい。「漢字文化圏」や「儒教文化圏」というふうに、三つの国は、同じ文化圏なんだと思い込んでしまいがちなんだとか。 漢字こそ東北アジアの文化を統合し交流するための万能手段であると思い込むことが、 むしろ理解の妨げとなる。 実際同じ漢字でも、日本、中国、韓国では、意味や中身が違うものは、いくらでもある。(中略) つまり、中国は「漢字文化専用文化圏」、 日本と韓国(半島)は「漢字文化借用圏」として認識しなければならないと思う。 こう認識すれば、互いに異質な文化圏であるという前提で、 他者を本当の他者として見ることができるし、 理解をスムーズに運ぶための一助にもなってくれるだろう。(p.25)なるほど!!同じ東アジアのご近所で、お付き合いをしてきた期間も、とっても長いということで、「似たもの同士」とか、「同じものを共有する仲間」とか、「相手は、こちらのことをよく分かってくれている、理解してくれている」と思っていることが、どうも、色んな場面で、話がうまくまとまっていかない原因のようです。そこで、著者は、日中韓・三国の文化や国民性の違いを、様々な観点から指摘してくれており、これがどれも本当に面白い。「水」や「土」「木」「石」にまつわるお話は、私に新しい気付きを与えてくれ、どれもこれも思わず「!!!」の世界でした。中でも、「和」の国として日本を、「闘」の国として中国を、そして、「情」の国として韓国を捉える視点には、大いに納得。 「われわれ中国人はいつも自ら平和を愛すると好んでいっているが、 しかし実は闘争がとても好きである。 他人が争うのを見ることも好きであれば、自分たちの闘争を見ることも好きである」(p.138) 韓国語のわからない外国人が、韓国人同士の会話を聞いたりすると、 まるでけんかをするような様相だし、 テレビドラマに映る韓国人もつねによく食べ、よく話し、よく笑い、よく泣く。 このように感情を表現し、伝えることによって、韓国人は「情」を分かち合う。(p.145) こんな本著の中で、私が最も「目から鱗」だったのは、日本は「賛否両論」が許される国であり、中韓は、それが許されない国であるという部分。 原理原則の強い中韓の社会では、敵方とはつねに妥協しない争いを求められ、 その戦いこそ正義である。 多元的思考を許す日本と、多元的思考を抑制し、一元的思考を強要される中国、韓国。 中国や韓国社会が対外的行動をする際、つねに内部の争いが起こる原因は、 このような思考を統一するためのプロセスが必要なせいである。(p.222)事が起こったとき、その原因を内側(自国)に求め、探そうとする日本。それとは逆に、原因を外側(他国)に求め、その原因をつくった相手を攻撃しようとしがちな中韓。相手は、これほどまでに、自分とは違うのだということを、しっかりと理解しそれを認めて付き合っていくことで、はじめて、三国関係の未来が開けるような気がしました。
2009.02.21
コメント(0)
-

どんな仕事も楽しくなる3つの物語
百頁チョットのコンパクトな一冊。 とっても親切な駐車場の管理人のおじさんと 日本一のタクシー会社づくりを目指す運転手さんと 警察で講師をするようになったペンキ屋さんの物語。 とってもコンパクトな一冊だから、 あんまり過度な期待を寄せてはいけません。 それでも、どの物語も、心がホッコリ温かくなって、 こんな風に働けたらいいな、と思えるお話しばかりです。三つの物語の後には、「仕事が感動に変わる、五つの心構え」が載ってます。そのポイントは、次の五つです。 1.仕事の意味を考える 2.ものごとを前向きに受け止める 3.自己原因で考える 4.自分の可能性を信じて、自分らしくやる 5.目指すことを、あきらめない(p.56)このように、本著は、実にオーソドックスな自己啓発本です。そんな中で、私は、「あとがき」が、一番共感するところが大きかったです。 もし、百年前であれば、このような生活をすることはできなかったと思います。 数え切れないほどの人々の努力の結果、いま私は世界中のおいしい食事を、 日本にいながらに味わうことができますし、 その気になれば、飛行機に乗って世界中のどんなに遠い国にでも、 一日で行くこともできます。 それはある意味、百年前の王侯貴族でも成し遂げることができなかったことです。 このように考えると、今この時代に生きていることだけでも、 大いに感動することができるかもしれません。(p.103)「できるかもしれません」なんてものじゃないですね。こんな風に考えれば、本当に「感動の嵐」です。 私たちは、一人で生きているように感じられることがあったとしても、 実はたくさんの方々とのつながりの中で生きているのです。 見知らぬところで、私たちは本当にたくさんの方々に支えられながら生きています。(p.105)日々感動、日々感謝!!
2009.02.20
コメント(0)
-

卒業式まで死にません
『友だち地獄』を読んで、その存在を初めて知り、 ちょっと、気になったので購入して、読んでみました。 本著に掲載されている、彼女の日記から漂う雰囲気は、 決して「死」を連想させるような、暗いものではありません。 彼女の最後の日記が書かれたのが、1999年3月17日(水)。 別冊宝島445『自殺したい人びと』に掲載された 「いつでもどこでもリストカッター」が書かれたのが、1999年3月22日(月)。 そして、南条あやさんが他界したのが、その8日後。先程書いたように、日記からは「死」の影は、それほど強く感じられません。むしろ、努めて明るく、リストカットや精神科通い、そこで処方される薬について書いています。もちろん、薬には、すっかりはまり込んでいたようで、危うさを感じずにはおれませんが……。あ、それと、カラオケも、とっても好きだったようですね。このように、日記から漂う雰囲気が、思いの外明るいものであるのは、この日記が、インターネット上で公開されたものである上に、それが、当時、すでに、かなり注目を集める存在となっていたため、その日記を読んでくれる人たちを、かなり意識していたからであるとも思われます。それに比べると、「いつでもどこでもリストカッター」については、これまでの自分を振り返り、自分自身の内面を見つめたうえで、これから先どうするかについて、考えているようなところがあるように思えました。この辺りの日々で、彼女に、何らかの変化があったのかもしれません。しかしながら、彼女に婚約者がいたことなど、日記やその他の文章からは、私は、想像もしていませんでした。つまり、肝心な所は、彼女は日記で全てオープンにしてたわけではないと言うことでしょう。日記に表現されているのは、あくまでも「ネットアイドル・南条あや」の世界だった。彼女の本当の姿を知り、彼女がなぜ死に至ったのかを知るには、本著に掲載された日記等だけでは、決して十分ではなさそうです。パソコンで、文字がズラ~ッと並んでいても、読むのが全く気にならない方は、 「南条あやの保護室」で、本著に掲載された分以外の日記も読むことが出来るので、どうぞ。
2009.02.18
コメント(0)
-

超・格差社会アメリカの真実
アメリカという国が、どんな風に出来たかがよく分かる。 アメリカという国が、どんな人たちによって創られたかがよく分かる。 そして、アメリカという国が、金持ちの間で完結する世界であり、 もちろん、そんな人は、ごく限られた存在であることも。 政治・金融・産業・軍事における特権階級が厳然として存在するにも拘わらず、 アメリカ国民は、「機会は平等に与えられている」と、本気で信じ、 「お金を儲けられることが正しいことであり、正しいやり方」だと思い、 あるべき姿と現実のギャップを埋めながら、理想の姿を実現すべく頑張っている。一方、教育においても、エリート層と貧困層との差は、歴然としている。エリート層の子どもたちは、一部の私立校へ、貧困層の子どもたちは、こぞって公立校へ。そして、そこで、階級差が、さらに固定化されていく。慌ただしい商業地区から隔離された高級住宅地に住む者がいる一方で、暴力的な犯罪が多く、危険で購買力が低い地域に住む者もいる。格差社会の上に成り立っている国・アメリカ。そして、日本における「格差」と、アメリカ「格差」とでは、質が違うと著者は言う。 日本で格差現象が深刻な懸念となっていることは事実だろうが、 問題を把握する枠組みは、アメリカの格差問題とはかなり違う。 ひとことでいえば、日本の格差は「職業選択と労働報酬」の問題であり、 アメリカの格差は「資産」の問題だからだ。(p.278) アメリカは機会均等でスタートし、人々が自由に生きることを容認して、自由を実現した。 しかし、平等は後回しにされて、その結果生じた現実の不平等は、 個人が自由に生きる機会も奪いつつある。(中略) 他方日本は、個人の自由を後回しにして、世界でも最高水準の平等を達成した。 しかし、人々の精神的束縛は、今社会秩序が乱れつつある中で、 むしろ強まっているように見える。 その原因は、現象面で見れば、平等を維持するため、互いに牽制しあう圧力が増して、 身動きがとれなくなっているためだ。 が、その圧力が増している原因は、アメリカの影響で精神的成長がないがしろにされ、 独立した自由な精神や自尊心を見失ってきたことにあるのではなかろうか。(p.282)そして、ヨーロッパからの留学生たちが、アメリカ人についてコメントした言葉が印象的だ。 「僕らはシェークスピアを読んで人間の本性について考えた。 でも、ビジネススクールのアメリカ人学生のうち、 何人がシェークスピアを読んでいると思う?」 「人間の価値と、その人の経済的価値とは違う。 でも、アメリカではそれがひとつになっている。」(p.174)日本も、こんな風に言われてしまう日が、やがて来るのだろうか……。本著を購入して、もたもたしている間に、文庫版が発売された。値段も安い上に、新たに「第9章 アメリカ発世界経済危機はなぜ起こったのか?―レーガン以降のアメリカ政権の経済政策を検証する」まで、追加されている。これから、購入される方は、こちらの方がいいのでは?
2009.02.18
コメント(0)
-

千里眼 優しい悪魔(下)
ノン=クオリアと手を組んだジェニファーに対抗して、 何と、メフィストのダビデと行動を共にする美由紀さん。 川田洋行社長・川田修三の依頼に法外な報酬を要求するダビデ。 それを無視し、川田の疑問に無報酬でヒントを与えてしまう美由紀さん。 川田氏に差し出された絵葉書の謎がすべて解決したとき、 川田氏は軍事産業を中止、新型クラスター爆弾開発放棄も決意。 しかし、ジェニファーは、川田洋行の核兵器製造機に、既に辿り着いていた。 そして、ダビデの力を利用して、それを北朝鮮に持ち込んでしまう。一方、美由紀さんは、沙希からパーフェクトシャッフルの手ほどきを受けている。一体、これに、どんな意味があるのか?それにしても、今回のお話しは、朝比奈さんや嵯峨くんだけでなく、沙希まで登場して、なかなか豪華キャストです!さて、北朝鮮に入国したジェニファーは、予想通りにダビデを裏切り、走行兵員輸送車から崖下へと突き落とす。この辺だけは、個人的に、かなり疑問……。ダビデって、こうもあっさりと、こんなことになるようなキャラなのか?まぁ、とりあえず、ダビデは命を失うようなことは、もちろんなく、優しい北朝鮮の子どもと、その母親によって救われる。そして、ダビデは、自分を救ってくれた、この家族のために、無実の罪で逮捕されている、その家の主人を救い出そうと、行動を開始。一方、ジェニファーは、ノン=クオリアに裏切られ、絶体絶命のピンチに。そこへ現れたのは、これまた予想通りにダビデ。そして、核兵器製造機の中からは、何と美由紀さんが登場。日本でパーフェクトシャッフルを練習していたのは、西之原夕子だった……。事件は無事解決し、ジェニファーの新しい人生が始まった。そして、ダビデは、これまでのようには、もう、美由紀さんの所へ現れない?さらに、由愛香と舎利弗が結婚。エンディングは北朝鮮、妻と子どもの元へ、男が帰ってきた。
2009.02.17
コメント(0)
-

精神科医はなぜ心を病むのか
最近、こちらの方面の書物も、かなり数多く読んでいるけれど、 本著は、それらの中でも、異彩を放つ、衝撃的でスペシャルな存在。 そこで明かされる、精神医療界の内幕には、圧倒されっぱなし。 さすがに、各方面で高評価を得ていることが、大いに頷ける内容。 医療界において、精神科が置かれているポジションや、 そこで勤務する精神科医の実体、 さらには、高まる精神科へのニーズと不足する医師やベッド…… 私たちが知らなかった深刻な状況が、これでもかと言うように伝わってくる。精神科医の育成システムが、きちんと整備されていないことが、様々な問題の一因となっているのは確かなよう。引いては、それが「精神科の診断は当てにならない」と言われることにつながっていく。患者数が増加するなか、対応し切れていない現場の実情。そして、薬の問題になると、さらに深刻な状況。薬の使い方が、ちゃんと分からないまま、患者に処方しているの?さらに、そこには製薬会社と精神科医の癒着もあるらしい。何を信じ、誰を頼ればいいのか……。最後の章は「精神科医に頼らずにできること」、付録は「ダメな精神科医の見極め方」。う~ん、本当に「これでイイのか精神科?」っていう感じ。皆さん、簡単にうつ病になんかなってる場合じゃないようですヨ!
2009.02.14
コメント(0)
-

ピアノの森 8
おっ!修平くん、何か突然大きくなってるぞ! お話しは、前巻から、いきなりの5年後からスタート。 海外留学中の修平くんが、久々の帰国で空港に降り立つ。 けど、どうやら、今はスランプに陥っているらしい。 その原因は、留学先の先生から見せられたビデオ。 それは、若き日の阿字野の演奏。 父・洋一郎と同じように、修平もとりこにしてしまったその演奏。 しかし、修平のスランプの原因は、実は、もう一本の別のビデオだった。それは、日本に旅行したバイオリン科の女の子たちが、撮影してきたビデオ。そこには、ピエロに扮した演奏家たちの路上パフォーマンスが映っていた。それを見て、突然、指が動かなくなってしまった修平。修平は、そのピエロ、実はカイに会うため、日本にやってきたのだった。懸命にカイの行方を捜す修平、しかし、何者かがそれを阻み続ける。父・洋一郎からの情報を元に、さらに捜索を続ける修平は、カイの家へ。そこで、出会ったベンちゃんの仲立ちで、やっとのことで再会に成功!でもカイ、マリアっていう女の子に変装して、クラブでピアノを弾いてました!そのクラブには、あの佐賀先生の姿が。随分、マリアちゃんに入れ込んでるようだけど、彼女が、実はカイだってことには、気付いてない様子?でも、ここから何かが始まりそうなことは、確かでしょう。そして、そんなカイから、逃げることを止めた修平、そして父・洋一郎。 ……て言うか、逃げられないんだ 僕がピアノを弾いている限り…… だってカイくんは、僕の後ろから追ってきているわけじゃないからね! カイくんたら、ずっと先を走ってたよ!カイの住まいで一夜を過ごし、寝覚めた修平は、そこで、カイの努力の跡を目の当たりにする。建物中に残された、カイの勉強の跡・落書き……。カイが、ただ気楽で、自由なんかじゃ、決してなかったことを知る。これにて、4巻から8巻までの、5巻連続一気読みは終了。さて、それでは、これより、続巻を発注するとしましょうか。
2009.02.14
コメント(0)
-

ピアノの森 7
カイを森の端から外の世界へ送り出し、 ピアノの世界へ羽ばたかせようとするレイちゃん。 レイちゃんを守るため、森の端に拘るカイ。 そんな時、カイは、ホコ天で透明なピアノに出逢う。 新しい仲間との、緊急路上ライブは大成功。 久々の演奏で「ピアノは俺の生命」と悟るカイ。 一方、修平は、コンクール全国大会小学生の部で見事に優勝。 そして、カイより先に世界に飛び出すことを決意。路上ライブを終えたカイは、ベンちゃんに置いてけぼりをくって、迷子に……。カイが目指したのは、あのレッスン室。朝、そこで目覚めると、阿字野がいた。男と男の大事な話の始まり。 俺はピアノがやりたい! それも、これまでみたいに遊びで弾くんじゃなくて…… 本気のピアノだ「わかった」と答え、レイちゃんの気持ちを、カイに伝える阿字野。そして、外国への留学を勧める。しかし、カイから返ってきた言葉は、 俺はどこにも行かない! 外国に留学する必要もない! 俺は阿字野にピアノを教えてくれって言ってるんだぜ! 阿字野先生に!! 先生は… 俺の先生はここにいるじゃないか!! 日本にいるじゃないか!!カイの言葉に、逆に腹をくくらされた阿字野。二人の新たな挑戦が始まった。
2009.02.14
コメント(0)
-

ピアノの森 6
修平は、カイの学校を去っていく。 そして迎えた、全日本学生ピアノコンクール中部南地区本選。 修平は、ショパンのワルツを完璧に演奏。 カイによって覚醒した誉子は、自分のピアノを弾く。 ここが本巻のクライマックス・シーン。 誉子が、すごく可愛くてカッコイイ!! 細かいミスには目もくれず、自分の演奏を貫き通した彼女の姿は、 審査員・佐賀の心をも揺さぶり、議場で「異議あり!!」の声を発させる。 結果は……満点優勝・雨宮修平、そして、丸山誉子は、審査員特別奨励賞を受賞。 でも、佐賀先生 本人にとって、こんな賞をもらっても意味があるんでしょうかね? 別に全国大会に行けるわけじゃないし……審査員・司馬の問いかけに答える佐賀。 バカだね司馬ちゃん。 全国大会を狙ってたコなら、 わざわざ本選にピアノの弾き方を変えて臨んだりはしないさ。 それに、ホコリをかぶった古くせー このピアノ界を変えていく第一歩だ 本人にとっては、まだ、わからないだろうけど、 コレには大きな意味がある。カイのピアノを認めなかった、カイのピアノを拒否した本選に、ケンカを売りに来た誉子は、見事にコンクールの常識をくつがえした。本選に、一発、強烈なパンチを決めた。カイのピアノが、人々の心を変えていく……。そんな、出来事を全く知らないカイだったが、ピアノを弾きたい思いを断ち切れず、あのレッスン室へ向かった時、落雷……。森のピアノが焼けてしまった……。新たな展開の予感。
2009.02.14
コメント(0)
-

ピアノの森 5
いや~、まいった…… 何だか、とっても、感動してしまった…… マンガを読んで、こんな気分になったことって、あんまり記憶にない。 それくらい、本当に素晴らしかった。 お話自体は、とってもシンプル・明快。 わざとらしい小細工は、全く用いられず、そのため、複雑で難解な部分は、皆無。 なのに、心に湧き起こる、この感情の昂ぶりは、一体何なんだ……。 まるで、カイの演奏を、実際に間近で聴いたかのような気分。 ***阿字野が自分に教えてくれた方法で、誉子をリラックスさせるカイ。様々なプレッシャーのせいで、緊張ガチガチだった状態からカイの言葉で解放された誉子は、束ねた髪を振り解き、表情も一変して穏やかに。何だか別人のように、可愛い女の子に変身してしまいました。予選が始まると、雨宮修平は、完璧な演奏を披露して、審査員を唸らせる。誉子も、遂に実力を発揮して、見事な演奏、審査員の注目を浴びる。会場には、修平の父であり、有名ピアニストである雨宮洋一郎の姿も見られた。そして、雨宮は、カイの演奏が始まると、そこに、自分が追い求めた阿字野壮介の音を聴く。しかし、カイは演奏を中断。弾き始めたばかりで、まだ一つのミスさえしていないのに……それは、モーツアルトのおばけたちに「楽譜を返せ」と迫られて、今の自分の演奏は、ただの阿字野のコピーに過ぎないと気付いたから。ネクタイを解き放ち、靴を脱いで投げ捨て、アリンコ一匹を観客に、森のピアノの演奏を開始する。「この音だ!そうだ一ノ瀬!これがおまえの…おまえのピアノだ」阿字野の心の中の言葉が、全てを物語る。カイの演奏に圧倒される雨宮洋一郎、修平、誉子、そして会場の聴衆。「俺のピアノが……弾けた!!」演奏が終わると、会場からは歓声・拍手が湧き起こり、アンコールの声が。ピアノ素人のおじさんからの「ありがとな!」が、その極めつけ。本選の課題曲は、ショパンの『華麗なる大円舞曲』と『小犬のワルツ』。そのことを知ったカイは、本選に出て、聴衆の前で、ショパンを弾きたいと、阿字野に告げる。そして、結果発表。修平、誉子は、予選を通過。しかし、カイは落選……。 彼のピアノには順位をつけられないんだよ コンクールのワクにはまらないんだ 規格サイズじゃないんだよ 残念だが、これがコンクールの限界… いくら権威を誇っても、これが今の日本の現状なんだ!雨宮洋一郎の、息子修平への言葉の持つ意味は重い。そして、洋一郎の心の中の言葉 ……だとしたら、阿字野の取る道は一つ……! 阿字野は一ノ瀬を……その予想通りに、阿字野はカイの母・レイちゃんに、こう告げる。 一ノ瀬さん 一ノ瀬を…カイを…世界に出してみませんか?ホント、ス・ゴ・イ!!!
2009.02.13
コメント(0)
-

ピアノの森 4
「タダでピアノを教わったことを引きずって生きたくはないんだ!」 阿字野との取り引きが正式に成立し、 ピアノコンクール出場が決定したカイ。 その後、雨宮修平とカイは、森のピアノが阿字野のものだったことを知る。 「カイくんが全力で僕と勝負しなかったら、その時はキミと絶交する。」 雨宮の言葉に、全力で、課題曲であるモーツアルトのK280の練習を始めるカイ。 そして、阿字野から、昔、彼が演奏したK280の録音テープを聴かされ、 K280の楽譜は、200年後の森に棲む少年に託したものだという話を聞かされる。楽譜を託したモーツアルトから、森に棲む少年への遺言は「おまえのK280を弾け!」。阿字野の演奏テープを聴くことで、阿字野の真似は上手くなっていくが、自分のピアノ演奏というものを、見つけることが出来ないカイ。モーツアルトの幻影たちが、「楽譜を返せ」とカイに迫り続ける。そして、いよいよコンクール当日。阿字野とレイちゃんとカイの3人で、会場に到着。出場者控え室の中は、ピリピリとした空気が漂う。中でも、誉子お嬢様は、執拗に雨宮修平の存在に拘り、険悪ムードを撒き散らす。そんな誉子が、本番前に行方不明?お嬢様に仕える白石から、誉子にまつわる身の上話を聞かされ、彼女を一緒に捜して欲しいと頼まれるが、あっさりと断るカイ。ところが、カイは会場の片隅で、しゃがみ込んで泣いている誉子に出逢う。 ***カイと雨宮修平は、予想外にも、あっさりと仲直りしてしまいました。二人は、もっと陰険な関係になっていくと思ったんだけど……修平はイイ奴に逆戻り。ま、この方が、私自身は嫌な気分にならずにすむので、とっても有り難いです。その代わり、タカコお嬢様が、とっても鬱陶しい存在として登場。それにしても、カイって、本当に素直。おかげで、ストーリーが、ほとんどもつれることなく、どんどん、よどみなく流れていく。韓国ドラマとは、対極のストーリー展開で、ホント、私好みです!!
2009.02.13
コメント(0)
-

千里眼 優しい悪魔(上)
このタイトルを見て、 「あの人は~、あ~くまっあっ」なんて口ずさんでしまうのは、 ランちゃん大好き、とんねるずのノリさん世代。 ただしこの曲のタイトルは『やさしい悪魔』で、「優しい」じゃありません。 物語のスタートは、インドネシア。私が行ったことのある唯一の外国。 その時訪れたジョクジャカルタの地名が登場すると、頭の中は一瞬であの頃へ。 ボロブドール観光に出かけた際、手作りの土産物を持って、「千円、千円」と 私たち観光客のあとを、いつまでも付いてきた子どもたちの姿が、やけに鮮明。 ***インドネシア沖地震で発生した津波に飲まれ、記憶を失った女性。その弟くんは、姉の持つ莫大な資産を手に入れるため、記憶を取り戻そうとします。そこで雇われたのが、何と、我らが美由紀さん。しかし、即座に弟くんの魂胆を見抜き、さようなら!そこで、弟くんが、次に頼ったのが、メフィストのダビデ。彼女の記憶を取り戻すためには、ショックを誘発する元を断てばよいと、アフリカ南部で核爆発を起こし、計算通りに記憶を蘇らせることに成功。でも、結局、弟くんは、美由紀さんによって御用になってしまいます。舞台が日本に戻ってくると、懐かしい朝比奈さんや嵯峨くんが登場。嵯峨・美由紀のコンビで、少女のボタン恐怖症を見事に見抜きます。一方、アフリカのサワディラカでは、ダビデが少女のボタン恐怖症を一週間で克服。さらに、少女とその父である大統領との間にあった、過去の忌まわしい出来事までも看破。続いては、ジェニファー・レイン登場。美由紀さんの命を執拗に狙いますが、悉く失敗して、遂に警察のご厄介に。そんなジェニファーを救ったのが、あのノン=クオリア。組織を危機に追い込んだジェニファーと激しく対峙するメフィスト。美由紀・ダビデ・ジェニファーの三つ巴の戦いの始まりです!
2009.02.12
コメント(0)
-

なぜ生きる
ここに書かれている事柄を十分にくみ取り、 それらを自分の血肉として、生きていくことは、 そう容易いことではないように感じた。 「生きる」ということは、それほどに意味深長なこと。 特に、親鸞や『歎異抄』に関わる事柄が前面に押し出された後半部の記述は、 それと知らずに、本著を購入した者にとって、 読み進めるだけでも、相当骨が折れる作業であろう。 ましてや、一読でそれらの記述に共感するに至るのは、至難の業かもしれない。しかし、そんな境地にいきなり至らずとも、そこかしこに、日々生きるヒントを得ることは出来そうだ。例えば、次の、南の国でのアメリカ人と現地人の会話から。 ヤシの木の下で、いつも昼寝をしている男をつかまえてアメリカ人が説教している。 「怠けていずに、働いて金を儲けたらどうだ」 じろりと見あげて、男が言う。 「金を儲けて、どうするのだ」 「銀行にあずけておけば、大きな金になる」 「大きな金ができたら、どうする」 「りっぱな家を建て、もっと金ができれば、暖かい所に別荘でも持つか」 「別荘を持って、どうするのだ」 「別荘の庭のヤシの下で、昼寝でもするよ」 「オレはもう前から、ヤシの下で昼寝をしているさ」 こんな幸福論の破綻は、周囲に満ちあふれている。(p.123)思わず、「自分が、本当に求めているものは何なのか」問い直したくなるお話し。さらに、次の一文は、人間社会というものをズバリ言い表している。 人間の価値判断は、いかにいい加減なものなのか、 「今日ほめて、明日悪く言う人の口、泣くも笑うも、ウソの世の中」と、一休も笑っている。 自分に都合のよいときは善い人で、都合が悪くなれば悪い人という。 己の時々の都合で他人を裁き、評価しているのではなかろうか。 人の心は変化するから善悪の判断も変転する。 「昨日の味方は、今日の敵」の裏切りがおきるのもうなずけよう。(P.211)何だか、人間不信に陥りそうで、イヤーな気分になってしまう内容だが、「そんなものに煩わされるのはバカらしい」と割り切ってしまえば、他人の目を気にし過ぎず、自らの意志・判断で行動していくきっかけには、十分なるお話し。そして、酒好きな男が、禁酒を決意した記念にと、著名な博士から揮毫してもらった「今日一日禁酒」のお話しも、なかなかのもの。 “今日一日禁酒”の紙を部屋の壁に張りつけた男は、時計とにらめっこしながら、 明日の来るのをひたすら待った。 夜になり十二時が近づくと、一升ビンをグイと引き寄せ、ノドをグーグーうならせる。 十二時の時計を合図に「さあ、のむぞ」と、酒を手にした男が壁を見て、 「あっ、今日もまた禁酒か」と叫んでがっくりする。 「今日一日」とは、死ぬまでのことだったのか。 「今日」の真意を知った男は死ぬまで酒を断ったという。(p.264)「今日を生きる」ということの意味を知り、「明日を生きる」ということの意味を知る。そして、「生きる」ということは、全てを「過去」にしていく営みと知る。
2009.02.11
コメント(0)
-

性同一性障害
2000年の2月22日に第1刷が発行されている。 現在では、「性同一性障害」という言葉も、 かなり広く世間に認知されるようになってきたが、 20世紀末の当時は、まだ、知る人ぞ知るというレベルだったのではあるまいか。 記述された内容自体にも、時代を感じさせられる部分がある。 発行から9年の時を経て、法的整備等は、当時と比べ、かなり前進している。 しかしながら、本著を読むことで、 改めて気付かされることや、初めて知ったことが、私にはとても多かった。 ***性同一性障害と言っても、様々な段階が存在する。異性の服装を纏うことで安心できる「トランスヴェスタイト」、社会的に異性として扱われれば安心できる「トランスジェンダー」、さらに、完全に異性の身体を望んでやまない「トランスセクシャル」。リアルライフテストを実施し、それぞれの段階で、どのような問題が発生するかを体験。自分自身が、その段階で満足できるのか、できないなら、次の段階に進むのかどうか、これらのことを、自分自身が判断していく。 ***これまで思っていた以上に、大きな問題であることを、本著で知らされたのが、「反陰陽」について。この部分についての記述は、かなり医学的・生物学的で、スラスラ読み進めることが出来るようなものではなかったが、クラインゲルター症候群の発生率が、約750人に一人という記述には、正直驚いた。これは、GIDとは比較にならないほどの高確率である。さらに衝撃的だったのは、旧東ドイツの村長が、1998年11月に、村民からリコールされた次のエピソード。リントナー氏は、男性として村長に立候補し、対立候補に圧勝した。就任後も財政再建や議会運営に手腕を振るい、高評価を受ける。そんなリントナー氏は、ずっと女性として生きていきたいという願望を持っていた。そして、医師から性同一性障害の診断を受け、女性として生きた方がいいと勧められる。そこで、ある日の村議会から、女性として執務すると宣言。これまでの実績や村民との信頼関係、さらに、自身が属する民主社会党が、性差別撤廃を掲げ、性的少数者への社会差別をなくすための法案づくりに取りかかっていた時期だったこともあり、議会も村民も、自分を理解してくれるに違いないと、自信を持ってのカミングアウト。しかし、結果は……。 「村長の仕事も何ひとつ怠らずがんばってきた。それなのに、なぜという気持ちです。 ドイツの人たちには、寛容の心が欠けているのだろうか。 もう村にはいられないだろうから、村を出る。 来年の夏には、計画通り性転換の手術を受けるが、その後はドイツを出るつもり。 北欧かオランダか、少数者にやさしい国で暮らしたい」 カミングアウトしたことが、リントナー氏にとっては、 職も住まいも国さえも失わせる結果になったということになる。(p.210)「日本では、どうなるだろう?」と思いながら読んでいると、次のような箇所が出てきた。 性的なマイノリティーへの法的な整備という点では、 日本はおそらく一番遅れていることは否めない。これは、本著発刊当時の状況であるから、その点を踏まえて、読み進める。 しかし、社会的な受け入れという点では、どこかアジア的なあいまいさを残した日本の方が、 先に行ける可能性はあるのではないか。 原科教授も塚田医師も、日本社会の寛容さに期待できるのではないかという希望を口にした。 「一般市民ってことの比較では、日本人は欧米人よりやさしいんじゃないかと思う」 そう言ったのは、虎井氏である。(p.215)今まさに、日本は、それが本当かどうか、試される段階に突入した。
2009.02.11
コメント(0)
-

悩む力
日々、人は、様々な悩みと向き合いながら生き続けている。 そして、悩みを一つ解決したかと思えば、 また、別の悩みが、どこからともなく、新たに湧き起こる。 生きている限り、悩みが潰えることはない。 現代を生きる私たちの「苦悩」は、 「近代」という時代と共にもたらされたと、著者は言う。 それは、「グローバリゼーション」の始まりと時を一にする。 孤独の苦しみ、変化に耐えなければならない苦しみ等が始まった。そんな「個人」の時代が訪れた頃生まれたのが、マックス・ウェーバーと夏目漱石。二人は、時代の波に乗りながらも、決して流されることなく、「悩む力」を振り絞り、近代という時代がもたらしたものに向き合い、百年前、それらを様々な書物に書き残した。そんな二人の書物にスポットを当てながら、「個人」として生きること、「自我」「自由」について考え、「マネー(金)」「働く」ということ、「知性」についてや「生きること」「死ぬこと」「愛すること」の意味を考えていく。 そのような作業を通じて、現代を生きる私たちが、どのようにして悩みを乗り越えていくか、悩みながらどのように生きていくかを探ろうとするのが本著である。なかなか哲学的で、私が普段読んでいる書物とは、かなり趣が違い、著者の言わんとするところを、しっかりととらえ切れなかったような気もするが、「漱石も読んでみようかな」という気にだけは、させられた。最後に、本著の中で、一番印象に残った部分を書き留めておく。 不自由だからこそ、見えていたものがあった。 自由になったから、見えにくくなったものがある。 これは恋愛に限らないことですが、 自由の逆説と言えるものなのかもしれません。(p.136)
2009.02.11
コメント(0)
-

ナイスの法則
スラスラと一気に読み切りました。 しかも、時間もそれほどかからずに。 肩の力を抜いて、気楽に読むことが出来るので、 気分転換には、最高の一冊です。 ただし、人に優しくしておけば、親切にしておけば、 それが思わぬ所で、新規契約や自分にとって大変有益な結果となって返ってくる といったことを、あちこちで例示しまくってるのは、 筆者が、現金な人間と受け止められかねないと心配になりました。さて、本著の中で、私が、特に印象に残ったのは、次の箇所。 誰しも功績を認められたいと思っています。 多くの人の心の奥には、成功を称賛し、失敗をバカにする想像上の観衆がいます。 しかし、それは、逆効果だというのがわたしたちの意見です。 第一、観衆は、いないのです。 どの人も自分のドラマに没頭しすぎるから、他人の目が気になるのです。 11世紀の学僧アティシャ・ディパンカラはこう言っています。 「称賛を期待することなかれ」(p.57)それでも、やっぱり気にしてしまうんだなぁ、これが……。これさえ気にならなくなれば、とっても気分は軽やかで、心も自由なんだけど……。 ほとんどの人は、自分の人生を他人の人生と比較します。 妹は最近また子供を授かったけど、わたしのほうが社交的だとか。 親友のほうが収入が多いけど、わたしの仕事のほうがおもしろいとか。 人は、このようにいつも比較して、あまり差がなければ大体は安心します。 もう比較するのはやめにして、あなたの人生を生きてはどうでしょうか。 他人が成功すれば自分が負け犬になったかのように考えるのは、やめにしましょう。 そのためにはどうすべきでしょうか。 人の昇進をうらやみ、嫉妬心にさいなまれているのなら、その人に花を贈りましょう。 姉が広々とした別荘を購入したなら、姉を自分の小さなアパートに、夕食に招きましょう。 なぜ、そんなことをするかって? 豊かな視野から行動を起こそうとすると、豊かな気持ちになれるからです。 その心の豊かさを感じはじめると、他人の人生なんてそれほど気にならなくなりますよ。(p.60)「本当ですか?」と、本に向かって、思わず聞き返してしまいました。私は、そんなに上手く出来そうにないんだけどなぁ……。ネガティブですか? 相手の意見を聞き、質問をするときは、その相手を立てて、その意見に敬意を払いましょう。 「ダメ!」と一蹴して相手に口ごたえさせないような態度を取らなければ、 相手にもこちらの意見に耳を貸す状況が生まれます。 わが子と真正面からぶつかり合うのは、つらいかもしれませんが、 それは、親の究極の権利なのです。(p.140)有無を言わせぬほど、完膚なきまでにねじ伏せても、お互いにとって、良い結果には結びつかないと言うことでしょう。やはり、多少なりとも、相手が身を引き、逃げ込める余地を残しておいてあげないとね。まぁ、これぐらいは、ちゃんと実践しなくちゃいけないと思います。 楽観主義者は、売り込み電話で断られたとき、相手が恐らく多忙であるのだろう、 または、機嫌が悪いのであろうと自分自身に言い聞かせます。 それは、一時的な現象であり、自分の能力とは関係なく、 たまたま運が悪いことに相手の都合の悪いときに電話をしてしまったと解釈します。 または理由についてはまったく考えもせずに、次の電話をかけるでしょう。(P.156)この後、悲観主義者の場合について述べられているのですが、どんなことが書かれているのか、だいたい想像がつくと思います。めざせ、ポジティブ・シンキング!!(ただし、過度に楽観しすぎるのも考えものだとは思いますが……) 今日、人々の間で無礼の度合いが史上最悪になっています。 2005年10月に発表されたアソシエーテッド・プレスの世論調査によれば、 アメリカ人の70%が20年前よりも無礼になっていると感じており、 最大の反則者の例として、大声で話す携帯電話利用者、駐車スペースを横取りする者、 公共の場で汚い言葉づかいをする者を挙げています。 これらの反則をする人の多くは、なにも悪い人たちではありません。 ただ、気づいていないのです。(中略) 誰もが自分独自の映画の中で主役を務めているようなもので、 他人にもそれぞれ独自の映画があることを忘れているのです。(p.206)最後の言い回しが、私は、とっても気に入ってしまいました。そして、アメリカでも、日本と同じようなことになっているんだなと、改めて知りました。それとも、ひょっとすると、どんな場所でも、どんな時代でも、こんな風に「昔に比べて今は……」と考えがちなのかもしれないとも思いました。
2009.02.10
コメント(0)
-

教育の正体
教育を語る書物は、今や、書店に行けば、どこでも所狭しと並んでいるが、 本著は、そんな中でも、かなり異彩を放つ存在のように感じた。 と言うのも、私がこれまで目にしたものとは、趣がかなり違っており、 米長邦雄氏との対談も含め、ひじょうに興味深く読み切ることが出来たからだ。 まず、出だしで語られる、日本の大学の黎明期のエピソードが、とても面白い。 国立大学と私立大学の設立された意味合いの違いや、 アカデミズムとプラグマティズム、ユニバーシティとカレッジの違い等の記述には、 なぜ、こんな事も知らずに、これまでやってこれたのかと、大いに反省させられた。続いて、反省させられたのは、義務教育に関する次の一文。 教育権は国にあると言いだしたのはフリードリッヒ2世(大王)で、 これは世界最初の画期的な発言だった。 教育権は国にあり、親は子供を学校に差し出す義務がある。 これが義務教育で、国家に子供を教育する義務があるとは言っていない。 国家には教える権利があり、親には子供を差し出す義務があると言ったのである。 ナポレオンに対抗するためには、強くてタダの軍隊が必要だと言ったのである。 タダの軍隊というのはナポレオンが発明した徴兵制で、ドイツにもそれが必要だが、 そのためには、子供のときから愛国心や団体行動力を叩き込まなければダメだと言った。 親は反対したが、やがてついでに職業教育もしてくれるのならと、ある程度賛成に変わった。 その複合物が義務教育なのである。(p.54)「そうだったのか……」と唸るしかない、衝撃の事実。何で、これまで、こんな事すら知らなかったのだろうと、またまた反省しきり。そして、さらに文章は、次のように続いていく。 そのように、いろいろな制限がついているのに、日本の親は国を信用してありがたがって、 子供の教育を全部学校に向かって丸投げする。 受け取ってはいけないものも入っているのに、国や日教組は受け取る。確かに「丸投げ」&「何でも受け取り」の関係になっているのが、現在の保護者と学校との関係。「受け取るべきもの」と「受け取ってはいけないもの」を明確にし、「受け取ってはいけないもの」は、きちんとのしを付けてお返ししないと、これから先、学校は立ち行かなくなってしまうだろう。さらに、PISAの2006年国際調査結果に対する筆者のコメントは、実に鮮やかである。 受験者のスクリーニングはどうなっているのか、をいえば、 日本の場合は無作為に選ばれた全国6000人の高校一年生が受けたそうである。 日本人の高校進学率は96%で、その高校を選ばすに全員が受けた。 ところが、韓国やシンガポールでは、まず高校へ行くのは一部だから、 もうすでに選ばれた人だ。 しかも世界学力コンクールともなると、成績の悪い人は受けさせないのだから、 中国の金メダルみたいなもので、そんな各国比較は成り立たない。 だから、各国比較によれば、日本は下がってきて二十番といっても、わたしは信じない。(p.74) 一方、本著では、「国益」とか、「国家戦略」等、「国」という語が、あちこちで見られる。このような特性を持つ本著を読むとき、著者の考え方が、一体どういった方向性をもつものなのか、しっかりと把握した上で、読んだ方が良いのではないかと思われる。例えば次の一文に、筆者の考え方の特性が、垣間見られる。 しかし、この人たちが全国民を引っぱって 昭和の日本を世界最強国の一つにする働きをしたと思うと感無量である。 連合艦隊をつくり、ゼロ戦をつくり、アジアの植民地を解放して独立させ、 しかも日本国内は焦土と化しても、日本人の誇りを失わなかったのである。(p.31)その点さえ抑えておけば、本著は、他の書物には見られない、ちょっと違った角度から、教育というものを俯瞰させてくれる良著である。
2009.02.10
コメント(0)
-

ピアノの森 3
遂にと言うか、やっとと言うか、 いよいよ、ドラマの幕開け! カイの物語が、本当の意味で始まりました。 きっかけは、ショパンです! あの、誰にも音の出せない森のピアノを弾きこなすカイが、 何と、ショパンだけ弾くことが出来ない……音すら出ない……。 その頃、雨宮修平、覚醒!! いよいよ、ライバルらしい雰囲気を漂わせ始めました。ショパンを弾くために、阿字野に教えを請うカイ。そして、タダで教えてもらうのはイヤだというカイ。それに対し、弾けるようになるまで、自分とピアノから逃げないことを要求する阿字野。取り引きの成立。始まったのは、指の練習曲、音階の……カイにとっては、楽しくも何ともない、苦痛でしかないレッスン。それでも投げ出さないカイ。そして、ショパンが弾けた(割とアッサリ、さすがに天才!?)。さて、いよいよカイと阿字野のコンビは、あの全日本学生ピアノコンクールを目指すことに。そこでは、雨宮修平との対決が待っている!私は、まとめ買いした3巻までを読破したので、4巻以降をこれから発注します!!
2009.02.10
コメント(0)
-

ピアノの森 2
ピアニスト阿字野の過去が、明らかになり、 そして、森のピアノの正体や過去も明らかに。 一方、カイは、雨宮修平によってモーツアルトに出逢い、 さらに、阿字野によってショパンに出逢う。 カイの才能に驚愕し、一緒にピアノをやろうと誘う阿字野。 ピアノは一人で弾くものだと、全くその気がないカイ。 息子のため、何とか阿字野の教えを請おうと画策する雨宮母。 今のところ、まだ、それほどの拘りを見せていない雨宮修平。物語は、まだまだ序盤。カイがピアノというものに、本気で向き合ったとき、ドラマが始まる。カイと修平の間のライバル関係も、そこからスタートする。さて、どのようにして、カイは、ピアノという楽器と向き合うことになるのか?一方、カイと母・怜ちゃんの生活の舞台・森ノ端。そこで交わされる会話や行動は、まさにR指定ものだけれど、何だかとっても微笑ましく、温かで、人間味に溢れ、ホッとさせられる。この人間模様も、本作の魅力の一つになっていくのだろう。
2009.02.10
コメント(0)
-

ピアノの森 1
『のだめカンタービレ』については、まず最初にTVドラマを見て興味を持ち、 続いて、コミックスで既刊のものをまとめ買いして読破、 それ以来、新たに発行されたものについても、全て読み続け、 TVアニメも、録画予約して全話見るほどに、ハマリきっています。 そんなわけで、『ボクたちクラシックつながり 』を、少し前に読んだのですが、 そこで登場した『ピアノの森』にも、大いに興味がわき、 今回、とりあえず、1巻から3巻まで購入して、読んでみることにしました。 すると、期待に違わず、面白い!!主人公のカイは、音楽を聴いただけで、ピアノが弾けてしまうという天才少年。そして、他の誰も音が出せない、森のピアノを弾きこなし、ピアニストの息子で、カイの学校に転校してきた、同級生の雨宮修平をも魅了するほどの音色。これは、のだめを連想させるもので、十分に魅力的なキャラ(ただし、実際には『ピアノの森』の方が、連載開始時期は、3年ほど早いのです)。また、将来ライバル関係になりそうな、雨宮修平も、今のところは、カイに大変好意的で、イイ人っぽいので、心穏やかに二人を見ていられる。ただし、これは転校してきたばかりの雨宮が、悪ガキのキンピラにいじめられているのを、カイに助けられたことを感謝しているからであって、この先態度がどう変貌するかは不明。一方、雨宮母については、初登場シーンから、今後、カイにどんな態度をとるか見え見えです。さらに、カイの学校で音楽教師をしている、元有名ピアニストの阿字野も謎めいていて、なかなか良い感じ。おそらく、カイがこれから活躍する際に、大きな役割を果たすことになるのでしょう。ところで、カイの母親の登場場面では、思わず「これって、R指定作品か?」と叫びそうになりました。でも、よく考えて見れば、本作は、青年漫画誌に連載されていたのですから、こんなものですよね(お子様たちに、堂々と「面白いから、読んでみたら?」とは、言いにくいかな……)。
2009.02.09
コメント(0)
-

この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ。
タイトルに、本著の全てが集約されています。 子どもについても、自分についても、 まずは、現状を受け入れることからスタートするということ。 「否定」からでなく「肯定」からスタートするということ。 もちろん、目の前に「否定」したくなるような現実が展開されれば、 それを何とか良い方向に改善してやりたいと思うのが親心。 それで、ついつい否定的な言葉を投げかけることになってしまう。 でも、それでは、子どもは変わってくれず、逆に反抗的に……。子どもは子ども、自分とは別の人格を持つ存在だと、ハッキリ割り切り、線を引く。そして、自分は自分で、出来ることをやる。子どもは子どもで、自分で考えて行動させていく。自分じゃない子どもという存在を、親が力づくで動かそうなんて、決して考えてはいけない。自分以外の存在を、自分の思いのままに動かすなんて、そんなこと、決して出来ることではない。出来るはずがない。子どもという別の人格を、丸ごと受け止める覚悟を、親は持たねばならない。そんな風に、丸ごと受け止めることができるに値する親子関係というものをつくりたい。そのために、普段何をすればいいのか、どんなことを心がければいいのか、そのヒントが、本著には溢れています。
2009.02.04
コメント(0)
-

10代からの子育てハッピーアドバイス
『子育てハッピーアドバイス』のティーンエイジャー版。 平成19年の3月に発行されたものなので、 当時、大きな問題となっていた「いじめ」や、それを原因とする「自殺」、 そして「不登校」の問題等を中心に、明橋先生がアドバイスしてくれています。 「子どもが10代になると、甘えと反抗の行ったり来たりが、とても激しくなる」 に描かれている、その時々で、コロコロと態度が変わる子どもの姿は、 思春期の子どもを育てた経験のある者なら、誰でもが思い当たる内容。 また、「友だちが何より大事」と思ってしまう時期だということにも、大いに納得。そして、「10代に反抗するのは、子どもの心が、健全に育っている証拠です」で述べられている内容には、全ての親が、救われる思いがするのでは?さらに、『「肩の力を抜く」「あきらめる」ことも大切』に至っては、親としての悟りの境地かと……まさに『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと 』です。 ***ただし、「いじめは、学校が、真剣に取り組むべき 最も重要な問題の一つです」に示された、明橋先生の考える「いじめ対応」については、素直に共感できる部分もありますが、「これで、いいのか?」と思える部分もありました。特に、そう感じたのは(6)~(8)。マンガでは、加害生徒が、すんなりと、素直に自分の非を認め、その保護者も、「いじめ」行為の背景にあった「家庭や保護者の問題」について、学校や教師が改善を求めると、それを素直に受け入れて、反省しています。しかし、ここに描かれたような美しい展開は、あまりにもドラマ的。こんなに上手く話を持っていくためには、学校や教師が、それ相当の時間と手間をかけて、生徒や保護者と、強い信頼関係・心と心の繋がりをつくりあげねばなりません。でないと、加害生徒は、素直に自分の非は認めないでしょうし、保護者も「プライベートなことにまで、学校が口を出すな!」と激怒するでしょう。事が起こる前に、そのような良い関係が、すでに出来上がっていればいいのですが、そうでなければ、学校・教師と加害生徒・保護者との間に、そんな関係が構築され、マンガで描かれたような、きちんとした指導が為される日まで、被害生徒とその保護者は、じっと待つしかありません。 ***本著後半部分に掲載されている、読者からの質問に対する明橋先生のお答えは、たいへん示唆に富んだ、参考になるものばかり。サラサラっと読めて、スッと腑に落ちる内容が多いところが、『子育てハッピーアドバイス』シリーズの、良さですね。
2009.02.04
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 貯金兄弟/竹内謙礼・青木寿幸
- (2025-11-22 17:06:22)
-
-
-
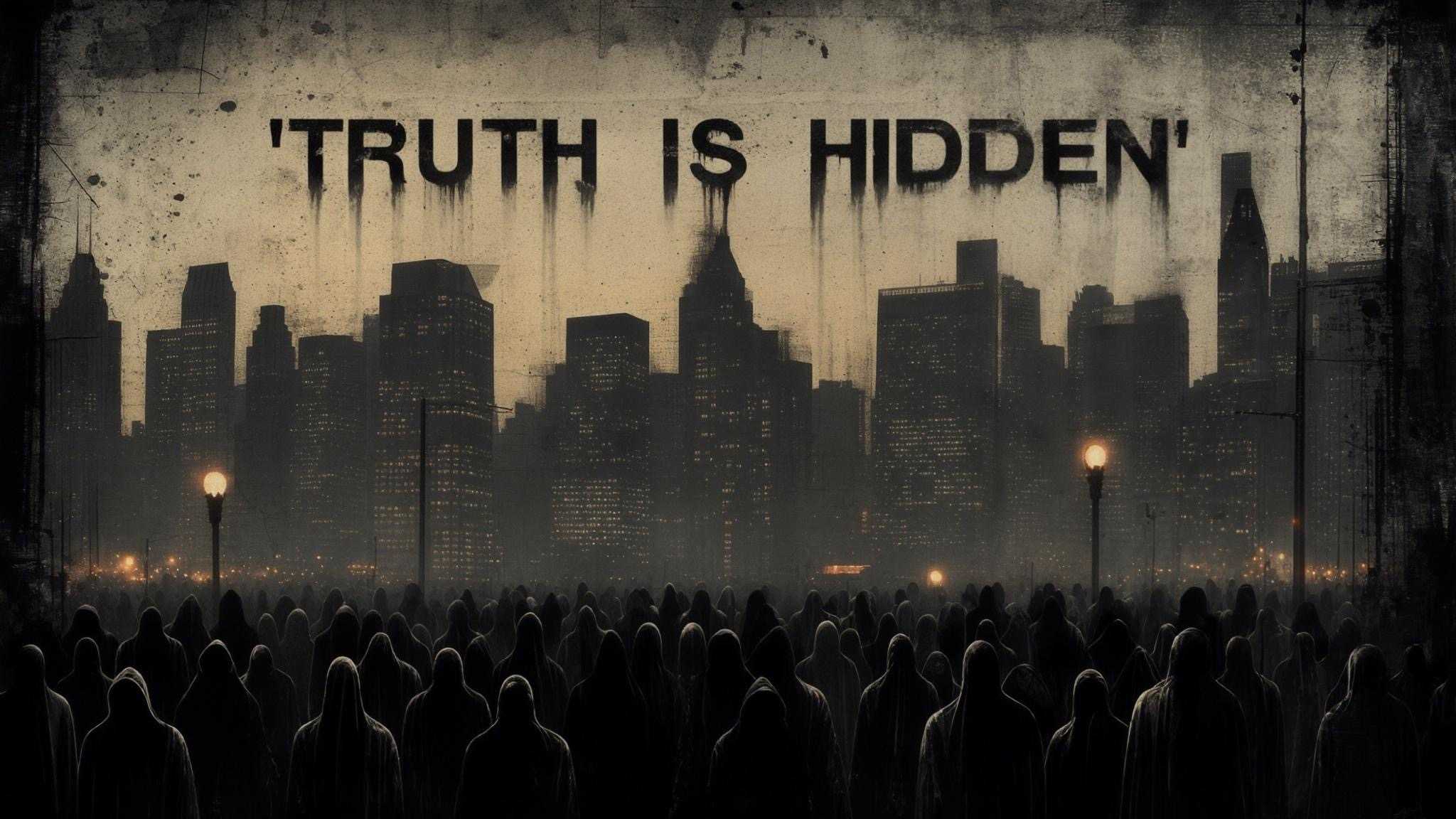
- 人生、生き方についてあれこれ
- 陰謀論はなぜ生まれるのか|権力の不…
- (2025-11-21 12:57:17)
-
-
-

- お勧めの本
- ★「トラブルについての四つの法則」…
- (2025-11-22 08:08:56)
-







