2009年10月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

弱者の兵法
先日から日本シリーズが行われている。 私としては、この舞台に野村監督が立っていることを願っていた。 さらには、巨人をも破り日本一の座にのぼりつめることを。 そして、それでも楽天が野村監督を解任できるか見たかった。 しかし、クライマックスシリーズ第2ステージの初戦黒星が響き、 残念ながら、その願いは叶わなかった。 もちろん、クライマックスをシリーズ終盤からの勢いで勝ち抜いたとしても、 巨人との戦力差はあまりにも大きすぎ、日本一は極めて困難だったろう。それにしても、よくぞこの戦力で長いシーズンを乗り切り、Aクラス入りを果たしたものだと思う。おそらく、他球団の監督が今年の楽天を率いていたら、最下位争いをしていただろう。そして、来シーズンの成績は、現時点において極めて心配なものである……。 *** 人間は何のために生まれてくるのか - 私はやはり、「世のため、人のため」だと思っている。 人生と仕事を切り離して考えることはできない。 とすれば、人間は仕事を通じて成長し、 成長した人間が仕事を通じて「世のため、人のため」に報いていく。 それが人生であり、すなわちこの世に生を受ける意味なのである。(p.54)まさに、哲学である。そして、さらにこう続ける。 であるならば、野球という仕事を選んだ人間は、 レクリエーション感覚で野球に取り組んでいいわけがない。 全身全霊、全知全能を懸けて対峙してくれなければ困る。 だからこそ私は結果よりも過程、すなわちプロセスを重視する。 その意味で、プロフェッショナルの「プロ」とは、プロセスの「プロ」であるといえる。 プロセスによって、人間は成長するのである。(p.54)この言い回しは、他でも度々登場する。もちろん、これは野球だけでなく、他の職業についても同じことが言えるだろう。それ故、野村氏の著作は本著に限らず、ビジネスマンによく読まれる。 中国のことわざに、こういうものがある。 財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すを上とする。(中略) 私が「人材を育てる」という意味は、たんに選手として一人前にするということだけではない。 その前に、「人間として一流」にしたかがどうかが大切なのである。 そう考えれば、名監督の条件とは -これまで述べたことを覆すようだが- 優勝回数や野球の知識といった目に見えるものだけではないのである。(中略) 監督の仕事とは「人づくり、試合づくり、チームづくり」であると私は自分に言い聞かせている。 そして、なかでも大切なのが「人づくり」だと考えている。(中略) 「人間的成長なくして技術的進歩なし」 - これを理念にしている自分の考え方は間違いないと私は信じている。(p.151)これも、野球に限らないことであるが、野村氏が嘆くように、残念ながら他のビジネスの世界でも、「人づくり」に力を注いでいる管理職は、そう多くない。 そういうアドバイスができるかどうかは、その指導者が現役時代にどれだけ悩み、考え、 試行錯誤しながら、どれだけ創意工夫を重ねたかで決まるといっても過言ではない。 名選手が名指導者になれないのは、ここに理由がある。 「おれができたのだから、おまえもできる」といって、自分のやり方をおしつけるか、 「なぜできないんだ」と頭ごなしに叱ってしまう。 その意味でも、現役時代に「感じ」「気づき」「考える」ことが大切なのである。(p.220)これは、とっても分かりやすい。天才肌の人ほど、その天才を他人に伝えることは難しいのだろう。逆に、他人に伝えることができないことこそ、それは天才の領分なのだが。 逆に大逆転をくらった阪神の岡田彰布監督は、Vを逸した責任を取って辞任することになったが、 逆転されたことばかりがクローズアップされ、 一時は巨人を一三ゲーム離したという事実にほとんど着目されることがなかった。 この年の阪神は、戦力ではやはり巨人に見劣りした。 それが最後に踏ん張りきれなかった最大の理由だったと思うが、 限られた戦力を使い、あれだけ独走したこという意味では、 岡田はもっと評価されてよかったはずだ。(p.155)こんなことに気付き、こんなふうに言った人が、どれ程いただろう?そう言われてみれば、確かにその通りなのである。そして私は、密かに来期のオリックス躍進を相当期待している一人だ。
2009.10.31
コメント(0)
-

千里眼 キネシクス・アイ
初版が発行され、半年余りが過ぎた現在、 2巻に分冊された文庫版が既に書店に並んでいる。 全くもって驚異的なスピード!! こんなこと、松岡作品以外では到底考えられないことだろう。 まさか、加筆や修正まで行われているのか? さすがに、文庫版にはDVDは付いてないだろう。 しかし、DVDに関する各方面からのコメントを総合すると、 これから本著を購入する方は、文庫版で十分かも知れない。さて、本編のお話しの方は美由紀が小学6年生時のエピソードから始まる。しかし、これが本当に小学生らしくない……28歳の女性なら許せても、12歳の女の子となると、ちょっとそれは……と言うような少女・美由紀の大立ち回りである。しかし、お話し全体としては、さすがに松岡さん。あちこちに散りばめられたエピソードの欠片が、ストーリー展開と共に様々な形で接合され、後になって、それらが重要なキーワードであったことに気付かされる。その辺の仕掛けは、これまでの作品にも増して今回上手く出来ていて感心!! ***先にも述べたように千里眼シリーズでは、岬美由紀は永遠の28歳という設定。それ故、色んなエピソードが次から次へと起こり、それらを超人的な能力で解決していくという経験を、どれだけ多く積み重ねても、美由紀自身には、時間の経過というものが加わっていかない。これは、『サザエさん』的に、その日その日のお話しを単発的に提供するという場合には、それほど無理は生じないのだが、千里眼シリーズのように、あるエピソードがあって、そのエピソードの結果が次のエピソードに繋がっていく場合には、かなりきつい。一体どこをどのようにすれば、そんなに数多くの難事件を28歳という年齢の1年間で解決しきれるのか……ということになってしまう。このように、千里眼シリーズは、時間の経過ということに関しては、物語のスタートの段階で、既に大きな矛盾をはらんでいる。 ***さて、今回のお話しの時代設定は、 「北京オリンピックの開会式にも……」(p.197)とあることから、どんなに昔のことと見積もっても2008年以降ということになる。それ故、美由紀が小6の時のエピソードは、1992年以降のお話。 ウインドウズも3.1になって使いやすくなった。(p.7)ウインドウズ3.1の発売は1992年3月だから、これも上手く辻褄が合う。さらに、 「いま流行っているTHE……虎舞竜だっけ、『ロード』って歌……」(p.20)『ロード』は全部で13章もある曲だが、ここで話題となっているのは、常識的に考えて、1993年1月に発売された、その年の日本レコード大賞で「ヒットシングル賞」を受賞した曲だろう。即ち、28歳の美由紀が活躍するエピソードは2009年のお話し、12歳の美由紀が活躍するエピソードは1993年のお話しということになる。 ***さて、どうして今回のエピソードの時代設定を、こんなに検証したかといえば、今回のお話しにおいて、その記述内容に若干疑問を感じた箇所があったからだ。それは、息子・編朗の宿題プリントをそのまま提出すると、父・鷲見が代行したことが教師にばれる理由を、美由紀が説明しているシーン(p.95~)。まず、鎌倉幕府の成立年を答える問題についての美由紀の解説。 「社長さん。鎌倉幕府の成立年について、一一九二とお答えになってましたね?」 「息子さんの教科書を見ればわかりますけど、今年から変わりました。 うちの学校では一一八五年です」次に、645年の出来事と絵踏についての解説。 「いまの小六なら乙巳の変と書くべきところです。 あと、江戸幕府が隠れキリシタンを探すためにおこなったことは、 もう踏み絵とは呼びません。絵踏です」さらに、旧一万円札の聖徳太子の絵が載ってない教科書については、 「別人の可能性が高いといわれているからです。 名前についても、聖徳太子というより厩戸皇子とするのがふつうです」これは、『いつのまにか変わってる地理・歴史の教科書』あたりが情報元のような気もするが、1993年の小学校の教科書が、美由紀の説明しているようなものだったかというとやや心配。松岡さんが、実際に1993年当時の小学校の教科書を入手し、その記載内容を元に、この文章を書かれたのであればよいのだが……。
2009.10.31
コメント(0)
-

千里眼 キネシクス・アイ(DVD)
かなりのボリュームの書籍、厚くて重い。 小説本編は525ページもあり、そこにDVDが付いている。 即ち、小説がメインでDVDはオマケという扱い。 それでも2,400円という価格設定からは、単なるオマケでは済まされない。 冒頭に「DVD収録の映画を先に御覧頂いてから、 小説本編をお読みになられると、より一層楽しめます」とあるから、 やはり、このDVDを見ないわけにはいかない。 そこで、著者が脚本・監督を務める87分の撮り下ろしオリジナル・ストーリーを鑑賞。しかし、この「超大作シネマDVD」、実はあまり評判がよくないのである。色んなサイトのコメント欄が、かなり厳しい意見で埋め尽くされている。そんな事前情報を知った上で、私は鑑賞を始めてしまったので、ちょっとばかり、負の先入観をもちながら画面を見つめることになってしまった。そして、負の期待は現実のものとなる……冒頭から「あらららら……こりゃ、ヒ・ド・イ」。最新鋭の戦車、戦闘機、軍事関連建造物等、全てが実にオモチャオモチャしていて、まるでTVでカラー放送が始まった「ウルトラマン」初期のような映像。映画なら「ゴジラ」でも、もう少し「リアリティ」を持たせようという努力が画面に感じられた。でも、それは仕方がない。このストーリーに本気でリアリティを持たせ、実写化しようとするなら、とんでもないお金がかかってしまうだろう。劇場公開&相当の観客動員が見込める、大ヒット間違い無しの作品であるならば、それくらい多額の制作費でも、ひょっとすると計上できるかも知れないが、このDVDにそれを求めるのは酷というものである。だから、あのステルス機の微妙な揺れや不自然な動き等には、だれもが皆、最初から目をつむる覚悟をして、この作品に相対するという姿勢が要求されるのである。そうです、やっぱりこのDVDはあくまでもオマケなんです。お話しの方はかなりアラカルト的で、つくりとしては少々荒っぽいように感じた。何の予備知識も無しにこのDVDを見た人は、いったいどれくらい理解できるのだろう?時間の関係で、そんなに細かい所までいちいち描写してはいられないのは理解できるが、全体として、少々説明不足の感が否めない。もちろん、「千里眼シリーズ」にすっかり浸りきっている私にとっては、大半の登場人物がどのようなキャラであるか既にインプットされているため、お話しの方は無理なく自然に流れていき、しっかりと楽しむことが出来た。それでも、国連と美由紀の関係等、一部繋がりが分かりにくい所もあった。結論、このDVDは「千里眼シリーズ」岬美由紀ファンへの、著者からの、大きな大きな10周年プレゼント。忙しい中時間を割いて、私たちのために動く美由紀を見せてくれた松岡さんに心から感謝いたしましょう!でも、奥田さん、とっても綺麗なんだけど、美由紀は、あんな場面であんな物言いはしないだろうとか、あんな表情は浮かべないだろうというところが、私の中では結構あった。ファンの間でイメージが出来上がっている人物を演じるということは、とても難しいですね。
2009.10.18
コメント(0)
-

他人に軽く扱われない技法
他人に軽く扱われないようにするためには、 他人が自分の重厚さに気付かないではおれないほどに、 自らを磨き高めていくのが本筋であろう。 もちろん、それはそんなに簡単なことであろうはずがない。 そのような自分をつくろうとすれば、時間も労力もうんとかかる。 そんな努力の積み重ねを、全く厭わないような人であれば、 本著のようなものを手にすることはないのではないか。 そもそも「他人に軽く扱われる」という次元のことなど気にもとめないだろう。ということからすると、本著を手にする人が期待するものは何か?おそらく、時間も労力も出来るだけかけずに、自分を大きく立派に見せる方法を知りたい、そのことによって、他人から軽く扱われないようにしたいということではないか。そして、本著はそんな読者のニーズに正対し、しっかりと応えようとしている。すると、その答えはどうしても「虎の威を借る狐」になってしまう。でも、それは仕方がないことだ。事実、私を含め本著を必要としている読者は、残念ながら今のところ「狐」なのだから。ということで、本著に示されているノウハウの一部については、全くもって、清々しさや潔さを感じさせるものではない。そんな人の言動を見て、爽快感を覚えることは、まずなかろう。逆に、嫌悪感を抱いてしまう人の方が、圧倒的に多いのではなかろうか。そのノウハウというのは、大風呂敷を広げ、虚勢を張るだけのことなのだから、それを実行する人は、本当に底が浅く薄っぺらな人間である。そんなことを続けていると、いつかは(いや、すぐに)見破られてしまい、他人から、より軽く扱われることになってしまうのではないかと心配になる。 ***と言いながら、本著には、普段から誰もが心がけておけばよいと思われることが、数多く書かれているから、ある意味驚きである。冒頭の「話の内容や言葉づかい、話し方」に、その人の品格が表れるのは事実であり、それによって、世間の人たちがその人物の格付けを行っているのは、絶対に事実なのである。さらに、私が本著で最も心に残ったのは、次のフレーズである。 ある特定分野のスペシャリストになってしまえば、 その他のことが全然できなくとも、だれも笑わないのである。(p.183)まさに、そうなのである。 「僕は、経理も、事務も、営業も、販売も、秘書も、何でもできるんですよ」 というのは、自慢にもなりはしない。 どうせどれもこれも中途半端な能力であると思われるのがオチである。 そもそもゼネラリストの能力を誇るような人間は、 結局は、誇るべきものが何一つないことなど、だれでも知っている。(p.182)この部分は、私にとってかなり耳の痛い話であり、人生最大の課題なのである。自分という存在のブランド・イメージを確立するため、スペシャリストに徹することができればよいのだが……しかし、これも実行するとなると、決してそう簡単にはいかないものなのである。
2009.10.18
コメント(0)
-

なぜあの人は人前で話すのがうまいのか
スラスラ読める。 あっと言う間に読了。 付箋を一箇所も付けることもないままに。 スッキリ、軽快な読後感。 ただし、本著は細かい所まで具体的に指南する、 かゆいところまで手が届くようなハウツー本では決してない。 つまり、読者は「模範解答」を本著の中に求めてはいけない。 著者は自分の仕事を「24時間365日、気づく感性にする」こととしているのだから。 考え方・気づきを自ら学んで、 毎日自己紹介の仕方を自分でチェックできるようにしていくことが大切です。(p.133) ***コミュニケーションの始まりは「自己紹介」。そして、「今しか使えない自己紹介」をめざす。つまり、「最近のエピソード」を織り交ぜつつ、「場」に応じた自己紹介をする。そのために、10個の基本パターンを用意し、9個は捨てる。話のネタは1つに絞り、聞き手の反応を見ながら、次に繋がるように話す。「それから」は使わない。言うことが決まらないうちは話さず、話すときはその前に何秒で話すか決めておく。ダラダラと「それ」「あれ」「その」を多用する話はしない。大勢の人の前で話すときも、一番聞いてくれる人に向かって話す。1対1の情熱で、エネルギーを集中する一人を探して、話し倒す。司会者が紹介してくれるとき、聞き手の中から自分を見ている人を探しておく。広めの会場なら、左右に1人ずつターゲットを決める。スピーチのときは「入り方」と「終わり方」だけ、事前に決めておく。冒頭には、その時起こった面白い話をもってくる。質疑応答は、質問した人だけに答えればいいのではなく、質問の背景を読み取りながら、その場にいる全員に役立つ答えを心がける。積極的に聞き、積極的に考え、積極的に話す。本気で話す。覚えて話すのではなく、考えて話す。前の人の話を踏まえて話す。 ***話すときの心構えとしてはこんな感じか。しかし、本著を読んで分かったようなつもりになっても、いざ、これを実行してみると、そう簡単にはいかないだろう。そうやって失敗を積み重ねるの中で、自分らしい話し方をつくりあげていこうということか。「話す」ことに正対して、しっかりと考え、積極的に実行することが肝要である。
2009.10.18
コメント(0)
-

桃 もうひとつのツ、イ、ラ、ク
最も興味深かったのは本編後にある小早川さんの文章。 出版社に勤務する編集者である彼の 「そんな私にとって、小説とは読むのに時間がかかるわりに 実益が伴わないものでしかない」という気持ちはよく分かる。 ところが、そんな小早川さんが姫野作品をベタホメなのだ。 もちろん、文庫本の「解説」部分なのだから、当然といえば当然なのだが。 それに比べ、『ツ、イ、ラ、ク』とほぼ同時期に刊行された 二十代と四十代の二人の女性作家二作品には、とても厳しい言葉を投げかける。二十代の女性作家とはおそらく綿矢さんのことで、その作品は『蹴りたい背中』。四十代の女性作家の方は直木賞受賞の角田さんで、その作品は『対岸の彼女』。この二作品と比べ、『ツ、イ、ラ、ク』が売り上げや評価で大きく水をあられていることに、小林さんは強い憤りを感じ、言葉を荒げる。 なぜそんなに差がついているのか? 試しにそれらの作品を読んでみて、私の頭の中は疑問符だらけになった。 いずれも、私にとってはそれこそ「ふーん」と思うだけの作品だった。(p.300)確かに、『ツ、イ、ラ、ク』が直木賞を獲れなかったことについては、当時、大いに物議を醸すことになったのだが、それにしても「解説」という場の文章にしては、珍しいほどに挑戦的かつ感情的だ。さらに、この「ふーん」については、その前段でこのように述べている。 もちろん仕事に直接関係ないとはいえ出版社の社員である以上、 文芸時評で話題の小説も読むこともある。 しかし、たいていは「ふーん」という感想で終わってしまう。 まあ悪くはないが、とくに読まなきゃいけないとも思えない。 読んだ、という手応えがない。 少なくとも私は、こんな小説ばかりならこの世からなくなっても困らない。 そして、仕事や家庭を持つ忙しい大人の多くが、 私と同じように思っているのではないかと考えている。 立花隆だって「小説は読まない」と言っているではないか。(p.294) この部分を読んでいる段階では、大いに共感していたのだが、その後の展開は先に示した通りで、読んでいる側としてはヒューンと興醒め、一歩二歩とジリジリ後ろに引いて行かざるを得なくなった。「世帯主がたばこを減らそうと考えた夜」についても褒めすぎ。 父の苦労を人間の苦労だと、父の努力を人間の努力だと、 当然そうみなされるべき自明の事実として受け取れるのは、娘だけである。(p.250)そうかなぁ……残念ながら、同意しかねる。まぁ、このパートの主人公である夏目雪之丞が自意識過剰で、父として我が娘を見る目が無い故に、勘違いしているということにしておこう。ただし、これに続く次の部分は本当に良く分かる。 自分と血をわかつ、庇護るべき存在。 女ではない。 雪枝と瑞穂を、雪之丞は愛していた。 なによりも娘たちから愛されたかった。だから、雪之丞の喫煙量が激減したことは本当によく分かる。しかし、共感するのは、彼の父としての娘たちへの思いだけである。他の諸々の事柄については、私には全く理解不能で気分が悪くなるだけ。こんなお話しに共感して泣くなんてことは絶対に出来ませんよ、小早川さん! ***それ以上に気分が悪くなったのが「青痣(しみ)」。景子の歪んだ感情の噴出ぶりは、あまりにも強烈すぎて目眩を覚える。思春期前後の女の子たちのドロドロとしたものの全てが、そこに凝縮されている。しかし、それらの少女の行動は、次の言葉で何とか埋め合わされている。 あのころに、わたしがしでかしたこと、言ったこと、そのほとんどに、私は羞恥する。 そしてわたしは消し去りたい。 あのころには、自分の言動に羞恥しなかったことを。 十代という醜い無知を葬りたい。鈍感な傲岸を、主観のばけもののような肥大を。 (p.119) あのころの瑣末な自意識を嗤えるまで視界が広くなった、現在の風通しのよさを、 わたしはよろこぶ。 あのころには、瑣末なことが、生死を決めるほど重要だった。 あの無知で甘ったれたぶかっこうさを、 ただ涙のみで綴ったり撮ったりした無知で甘ったれてぶかっこうなものを、今では笑える。(p.169)『ツ、イ、ラ、ク』のスピンオフ・ストーリー集としての本著の中で、最も多くのページを費やした中核とも言うべき作品だけに、他のお話しに比べると、濃密でその完成度は高い。それ故の、コミックス化。
2009.10.12
コメント(0)
-

アフターダーク
文庫本も出ているのだが、今回は単行本で読んでみた。 理由は、古本屋さんでは文庫本より単行本の方が安かったから。 確かに、持ち運びには文庫本のほうが圧倒的に有利。 でも、久しぶりに単行本を読んでみると、活字が大きくて読みやすい! このお話に出てくるマリも、分厚いハードカバーの本を読んでいる。 夜のデニーズで一人、一行一行しっかりとかみ締めながら。 タカハシ君の言葉を借りると 「女の子が普通バッグに入れて持ち運ぶサイズじゃない」らしい。さて、お話しの方はと言うと、これまでの村上作品とは一線を画する内容。最大のポイントは、オチがないこと!?もちろん、これまで読んだ村上さんの作品においても、最後の最後で、行き場の無さや頼りなさに戸惑うことは多々あった。しかし、この作品のその度合いは相当なものである。「えっ……これで終わり……ですか……」といった感じである。タイトルを見直し、『アフターダーク(上)』となってないか確かめたくなった程である。このまま(下)が描かれ続けていても何ら不思議はない、という所で終わってしまっている。そう、一夜の物語は、その全てがと言っていいほど、どのお話しも、一応の決着というものを見ていない。エリはまだ眠り続けたままだし、白川は何事もなかったかのように、これから自宅で眠りにつこうとしている。謎の覆面の男も誰だか分からないままだし、テレビの向こう側の世界も、どこなのか全く分からないままのナゾだらけだ。唯一、マリとタカハシ君のお話しだけが、ある意味完結し、未来へと向けて流れていこうとしている。しかし、これが日常というものの、本来持っている姿なのであろう。一夜限りで、あれもこれも、色んなことが一切合切完結してしまうなんて、絶対にありえないことなのだ。そう言う意味では、このお話はリアリティに満ち溢れている。つまり、今この瞬間が訪れるまでの様々な出来事については、色んな視点から、事細かに語ることはできたとしても、一瞬先の未来については、どう頑張っても語ることはできない。そんな現実の一コマを、この作品は描ききろうとしたのだろうか。 ***それでは、このお話の中で私が心に残ったフレーズを。 「私には、下の二人が選んだ人生の方がまともみたいに思えるんだけど」とマリは意見を述べる。 「そうだよな」と彼は認める。 「ハワイまで来て、霜をなめて、苔を食べて暮らしたいとは誰も思わないよな。たしかに。 でも長男には、世界を少しでも遠くまで見たいという好奇心があったし、 それを押さえることができなかったんだよ。 そのために支払わなくちゃならないものがどんなに大きかったとしてもさ。」(p.26)これは「ハワイのある島に、三人の兄弟が流れ着いた話」についてのマリとタカハシ君との会話。海岸に近く、魚もとれる場所で暮らすことを選択したいちばん下の弟、果物が豊富に実っている山の中腹で暮らすことを選択した次男、何か月も飲み食いせず、誰よりも遠くの世界を見渡せる山のてっぺんまで辿りついた長男への一言。 「中学生のときに、中古レコード屋で『ブルースエット』という ジャズのレコードをたまたま買ったんだよ。(中略) A面の一曲目に 『ファイブスポット・アフターダーク』っていう曲が入っていて、 これがひしひしといいんだ。 トロンボーンを吹いているのがカーティス・フラーだ。 初めて聴いたとき、両方の目からうろこがぼろぼろ落ちるような気がしたね。 そうだ、これが僕の楽器だって思った。 僕とトロンボーン。運命の出会い」(p.29)これは、タカハシ君がマリに自分とトロンボーンとの出会いを語っているシーン。うん、こういうのってイイな。ラブホの名前『アルファヴィル』について、マリとカオルが語り合うシーンもイイ。(p.82) 決断さえすれば、そんなにむずかしいことではない。 肉体を離れ、実体をあとに残し、質量を持たない観念的な視点となればいいのだ。 そうすればどんな壁だって通り抜けることができる。どんな深淵も飛び越すことができる。 そして実際に、私たちは純粋なひとつの点となり、二つの世界を隔てるテレビ画面を通り抜ける。 こちら側からあちら側に移動する。 壁を通過し、深淵を飛び越えるとき、世界は大きく歪み、裂けて崩れ、いったん消失する。 すべてが混じりけのない細かい塵になって、四方に飛び散る。 それからまた世界が再構築される。新しい実体が私たちを取り囲む。 全ては瞬きをひとつするあいだの出来事だ。(p.153) これは、「こちら側」と「あちら側」との世界を行き来する村上ワールドの視点であり、『アフターダーク』の「私たち」つまり「物語の語り手」ともなっているものに関する部分。問題は、この一文から何を読み取ることができるかだ。そして私は、これにて村上さんの長編小説は一つを除いて全て読破。そう、『1Q84』を読む前に、村上さんの長編小説を全て読んでしまおうと決めてから、途中、短編や訳書等に寄り道しながらも、4か月程でようやくここまで辿りついた。既に、『1Q84』は2冊まとめて発注済み!
2009.10.12
コメント(0)
-

スプートニクの恋人
これまで私が読んできた村上作品とはちょっと違う。 それは、これまで私が読んできた村上作品は、 そのどれもが、村上さん自身を投影したかのような主人公、 つまり男性視点「ぼく」の物語だった。 ところが、この作品は「すみれ」という女性メインで話が始まる。 途中で、いつものように「ぼく」が登場することになるのだが、 その後もしばらくは、「すみれ」ともう一人の女性「ミュウ」とのストーリー。 『ノルウェイの森』の「直子」「レイコさん」の関係に近いものを二人に感じた。しかし、『ノルウェイの森』の「直子」「レイコさん」の物語に比べると、こちらのお話しは明るいトーンに満ち溢れ、軽快に心地よく進行していく。「心の闇」といったようなものとは、全く無縁のような女性二人が眩しいほど。ただし、それは途中までのこと。「ミュウ」からの電話で「ぼく」がギリシャに行くことになったところ辺りから、お話しの色合いが一転……そう、村上ワールドの始まり。二人の女性の「心の闇」に「ぼく」は引きずり込まれていくことに。「こちら側」と「あちら側」、二つの世界とそれらを隔てるもの。 *** すみれの家のレコード棚にあった『モーツァルト歌曲集』。 エリザベート・シュヴァルツコップフの歌と ヴァルター・ギーゼングのピアノ伴奏。 母が大好きな曲で、その歌曲の名前「すみれ」を自分の娘につけた。 「スプートニクの恋人」。 それは、すみれがミュウのことを心の中で呼ぶようになった名前。 ジャック・ケルアックのことを思い出そうとして、 「ピートニク」のことを「スプートニク」と言い間違えたから。 ***それでは、このお話の中で私が印象に残ったフレーズをいくつか。 「あんまりにもすんなりとすべてを説明する理由なり論理なりには必ず落とし穴がある。 それが僕の経験則だ。 誰かが言ったように、一冊の本で説明されることなら、説明されないほうがましだ。 つまり僕が言いたいのは、あまり急いで結論に飛びつかないほうがいいということだよ」(p.82)これは、ぼくがすみれに言った言葉だが、なかなか示唆に富んでいると思う。ところで「一冊の本で……」と言ったのは、誰なんだろう? 「でも仕方がないわね。すてきなことはみんないつかは終わるもの」(p.168)これはギリシャのコテージで、すみれがミュウに言った言葉。ありふれた普通のやりとりのなかでの、普通の言葉なのだが、なぜか心に響いた。旅も人生も、そうなんだなぁ……と。 誰かが、何かが、ぼくの中から立ち去っていく。 顔を伏せ、言葉もなく。 ドアが開けられ、ドアが閉められる。 明かりが消される。 今日がこのぼくにとっての最後の日なのだ。 これが最後の夕暮れなのだ。 夜が明けたら、今のぼくはもうここにはいない。 この身体にはべつの人間が入っている。(p.272)この感覚こそが、村上ワールドそのものだという気がする。 ***ところで結末、本当にもう一度電話がかかってくるのかな?私としてはちょっと、と言うかかなり心配なんですが……。そして、村上さんは「先生」という職業について、スーパーの警備員が発した言葉(p.278~)のように捉えているのかな?まぁ、この作品が書かれた頃と現在とでは状況が随分違ってはいるのだが。
2009.10.12
コメント(0)
-

20世紀少年(読書後)
およそ2週間かけての一気読み。 最後の結末も含め、映画は結構原作に沿いながら、 そのイメージを損なわないよう作られていると思った。 もちろん、これだけの長いお話しだからどこまでも忠実にとは行かない。 原作でイイ場面と思えるようなシーンも、映画ではカットされてたりする。 と言うか、私自身も映画館で見たのは『最終章 ぼくらの旗』だけで、 それ以外は『もう一つの……』と題されたTV放映版を見ただけで、 映画については、全てを見たわけでは決してない。そんな当たり前のことにやっと気付いたのは、つい先日。それまで『もう一つの……』は、元の映画作品+未公開・新撮影シーンと思っていたのだが、元の映画作品の上映時間とTVの放映時間を比べれば、そんなことは絶対にありえない。つまり、映画と原作を比べて、私が何かを語るためには、『第1章』と『第2章』はDVDで見直す必要があるということ。そんなことに気付いて、録画してあった『もう一つの第1章』を見直すと、成田空港でケンヂ・ユキジが万丈目と遭遇するシーンなんかは、確かに、話が全然繋がっていないのである。これを最初TVで見たとき、自分自身がどう理解したのだろうかと、今となっては、とても不思議に感じてしまう。それ故、近々DVDを借りるためにTSUTAYAへ走ることになるだろう。さて、原作の方に話を戻すと、最後の結末は、ミステリーの大原則をほぼ外してしまっているのでちょっとキツイ。「こいつ……でいいの……?」と思った人は、ヤマほどいるだろう。もちろん、これだけのお話しを最後までしっかりと、誰もが納得する形でまとめきるということが、どれほど難しい作業であるかは十分に理解できる。それでもやはり最後には、「こいつだったか……!!」と思わせて欲しかった。カンナと蝶野のシーンなんかは、とってもイイ感じで締めくくられてるし、ケンヂとユキジの恋の行方についても「はあ……まあ一応告白してたか………」を含めて今後に何かを期待させるものに仕上がっていただけに、とても残念。そうそう、コイズミと神様のラストシーンも、個人的には好きだ。さて最後に、この文章の締めくくりとして、本来なら私なりの「原作と映画」についての結論を記さねばならないところだが、先に記したとおり、映画についてはTV版『もう一つの』しかまだ見ていない。それ故、本物の映画がどの程度原作のエピソードを拾い上げ、また、それを描ききっているかが分かっていない。つまり、安易に「原作と映画」を比較できるような立場に、現時点の私はない。『第1章』と『第2章』を全て見終えた暁には、再度この文章を締めくくる作業をしたい。
2009.10.12
コメント(0)
-
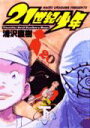
21世紀少年(下)
長かったお話しも、いよいよこれで終わり。 ヴァーチャルアトラクションの中に入り込んだケンヂ。 ナショナルキッドのお面を被った少年と遭遇。 それは、サダキヨ?それとも、もう一人の“ともだち”? その少年は言う、「ここのルールがわかってない」と。 そして、お面の下の彼の素顔は…… その顔に腰を抜かすケンヂ。 「キャキャキャ」と、走り去る少年。 なんなんだここは…… くそ~~~~~~。 現実のようで現実じゃねぇ…… 当たり前か…… 結局、もてあそばれてるだけか!! ここにはここのルールと辻褄があるってか…… どうすりゃいいんだ……ヴァーチャルアトラクションの世界との交信を試みる現実世界のカンナ。少年・ケンヂの夢の中に入り込み、サングラスかけたヒゲのケンヂへの伝言依頼に成功。原っぱの秘密基地で、反陽子ばくだんのリモコンのありかを探るが、なぜかボーリング場へ。そこで、1年後の少年ケンヂと再会し、ついに見つけた見覚えのないリモコン。その裏面には「ほんものはテーマパークのひみつきちのなか」と記されている。そこに現れた万丈目。現実世界のカンナとの交信を試みる。その声を聞き、現場に急ぐカンナとユキジ。 正義は……死なないのだ……!!現実世界に戻ってきたケンヂは、巨大ロボットと対決。ユキジは、リモコンを手にした敷島博士の娘と対決。サナエのリクエストに応え、コンチが『ボブ・レノン』をラジオから流す。そして、巨大ロボットは「片足が上がる瞬間を狙えばイチコロよ!!」。ケンヂは再びヴァーチャルアトラクションの中へ。やるべきことをやるために。しかし、それはヴァーチャルアトラクションの中の出来事。現実世界では、すべてが過ぎ去り、二度と元には戻らない出来事。すべては「もしも」のこと。そして21世紀。現実に立ち向かい続ける、あの頃少年だった大人たち。そう、20世紀少年たち。その意志は、後の世代へと受け継がれていく……
2009.10.11
コメント(0)
-

21世紀少年(上)
巻頭カラーページは、あのコンサート・シーン。 そして、小学校に円盤が墜落した後の顛末が描かれる。 田村マサオは息を引き取り、サダキヨは一命をとりとめる。 そして覆面の男は…… ケンヂが覆面を剥ぎ取ると、そこにはフクベエの顔が。 しかし、彼はフクベエではなかった。 おまえは………誰だ……? 覆面の男のリクエストに応えケンヂは歌う。そして、お話しは16巻のあのシーンへと辿りつく。 おまえが………こんなふうに死ぬとは思わなかったよ。 ごめんな……マルオにこの男を知っているのかと尋ねられ、知らないと答えるケンヂ。しかし、ケンヂはその男の死に自責の念を覚えている……場面はケンヂのバッヂネコババ・シーンへと繋がっていく。フクベエとヤマネ君とナショナルキッドのお面を被った少年。そして、フクベエとヤマネ君に見放された少年の独り言。 最後のばくだんがあるんだ。 反陽子ばくだん…… それで世界は終わり。 ……て、夢の中の大人の僕が言うんだ。ケロヨン、マルオ、オッチョ、ヨシツネ、コンチ、ユキジ、ヤン坊マー坊が集結。その頃、ケンヂはヴァーチャルリアリティーゲーム、即ち“ともだちランド”のヴァーチャルアトラクションの中に突入しようとしていた。決着を付けるために。ヴァーチャルアトラクションの中で、大人のケンヂが少年ケンヂとご対面。“反陽子ばくだん”発想のネタ元はスーパージェッターかワンダースリーか。いずれにせよ、マンガだと判明。その後、ヴァーチャルアトラクションで出口を見つけられなくなってしまった万丈目とも再会。万丈目は、ナショナルキッドのお面を被った少年と交わした言葉をケンヂに再現する。 マネのマネなら、 ケンヂのまねのフクベエのマネ…… あいつらは“細菌兵器”って言ってたんだけど、 僕はちょっと違うかな。 僕だったら、“反陽子ばくだん”仕掛けるね。 仕掛けるところは決まりだ。 “ばんぱくばんざい。ばんぱくばんざい” あそこしかないね。ナショナルキッドのお面を被った二人の少年、二人が出会ったときの会話。一人が、今度転校するんだともう一人の少年に伝えた。一人が「“反陽子ばくだん”ってどう思う?」と、もう一人の少年に尋ねた。さらに“反陽子ばくだん”のリモコンのかくし場所が書かれたメモを手渡した。メモを受け取ったのはサダキヨの方?そして、少年はそのメモをかくした……原っぱの秘密基地に。ジジババでバッヂ万引き犯にされてしまったナショナルキッドのお面を被った少年。「僕はやってない。僕はやってない!!」と否定するもののフクベエは彼に向かって言い放つ「こんな悪いことしたんじゃ、死刑だな」と。さらに「おまえは今日で死にました。」と。ホント、登場少年の中で一番のワルは、どう見てもフクベエだな。
2009.10.07
コメント(0)
-

20世紀少年(22)
22集のMVPはコンチ! 北海道でのケンヂとの再会シーンもヨカッタが、 何と言っても東京でラジオ放送したときのDJっぷりがイイ。 ケンヂに直接呼びかけ、「俺はコンチだ!!」と名乗るシーン。 ウルティモマン“宇宙特捜隊バッヂ”も登場。 もちろんウルトラマンの“科学特捜隊バッヂ”がオリジナル。 流星、流星、流星、胸に輝くこのマーク。 あの頃、確かに絶大なる価値を持っていたんだヨなぁ、あのバッヂ。そんなバッヂをジジババでネコババケンヂ君。これが全ての始まりなのは映画と同じ。小学校で対面するケンヂと覆面の男。手には大型ロボットのリモコンが…… 敵に渡すな大事なリモコン 鉄人鉄人早く行け ビューンと飛んでく鉄人28号。そう、敷島先生の改良型2足歩行大型ロボットのリモコンは、残念ながら、敵の手に渡ってしまっていたのだった。ケンヂを“悪の大王”と罵る覆面の男。 俺……全部覚えてる。 ごめんな…… ずっと後悔してた…………この言葉に動揺する覆面の男。 なんで、おまえ覚えてるんだよ!! おまえがあやまったら、全部終わっちゃうじゃないか!!ケンヂは答える。 もう終わりなんだ。 俺たちの遊びは終わりだ。 全部話すよ。 万博会場に集まった人たちの前で、 俺がやったことを全部話す。 それで全部おしまいにしょう。そして、映画では登場しなかったキャラ“お面大王”が登場。やっぱり、生きてたんだね。サダキヨ。万博会場が血の海になるのを阻止したサダキヨ。「僕は……いい者だ。」オッチョが2機の円盤を撃破した後、13番がヘリに乗ったまま円盤に突っ込み大爆発。その残骸が覆面の男とサダキヨに激突?死んだのか……二人とも?この後のコンサート・シーンは、映画の方がヨカッた。漫画では、とってもあっさりと終わってしまう。くどくてある意味臭いけど、私は映画の方が好きだな……あのシーンに関しては。そして、これでお終いと思いきや、まだ続く。これも映画と一緒。ということで『20世紀少年』は終了したけれど、『21世紀少年』へタイトルを変え、まだ続くのです。
2009.10.06
コメント(0)
-

20世紀少年(21)
コンチと13番がご対面。 即ち、それは今野裕一と田村マサオの出会い。 場所は北海道「銘菓白のソナタ」。 「白い恋人」と「冬のソナタ」とが合体した場所。 そこからヘリに乗り込んだ二人は“ともだち”に会うため空へ。 一方、ケンヂは東京目前カベの前。 そこで、蝶野から太陽の塔内部での不思議な出来事を聞く。 「ケーンーヂくん。あーそびーまーしょ。」そこでは、子供が笑いながらかくれんぼをしていた。一人か二人……塔の中で笑い声が反響していた。 よばれちゃしょうがねえな…… 行くか、万博へ……UFOが現れ、ペンキを撒き散らしての予行演習。新幹事長になった高須は“ともだち”の子供をご懐妊。 誰でもいいのよ。 今そこにいるのが“ともだち”。“しんよげんのしょ”の続きを書いたのはナショナルキッドのお面を被った少年。サダキヨではない、もう一人のナショナルキッドのお面を被った少年。フクベエとヤマネ君は、それを嘲り笑う。「こりゃないよ。」「なっ、クックックッ。」黙り込むナショナルキッドのお面を被った少年。「火星移住」そして、彼が最後のページに書いた内容は何?そんな孤独な少年のすぐそばをケンヂ達がジジババでアイスを食べようと走り抜けていく。ありゃりゃ、ケンヂと一緒に走ってるのはマルオにヨシツネ。と言うことは、ナショナルキッドのお面を被った少年は、この二人ではないわけだ。う~んっ……映画とは違ったな。じゃ、いったい彼は誰なんだ?閑話休題、UFOからばら撒かれるウイルスを避けることができる場所、それは万博会場。カンナはそれに気付くと、都民全員をそこに非難させようと決意する。一方、覆面の男は全世界に告白「“よげん”なんてウソだよ。全部僕がやったことだ。」そして「さようなら、みんな。ケーンヂくーん、あーそーびーまーしょ。」
2009.10.06
コメント(0)
-

20世紀少年(20)
20巻のテーマは“キリコを探せ”。 突如として(?)みんなで一斉にキリコを探し始めた。 一番乗りしてたのはケロヨン。 そう、アメリカで息子とソバ屋をやってる男。 13巻で既に探索を開始し、15巻で目標を捉えてそこを目指してたんだから、 一番乗りは、当然と言えば当然か。 しかし、あの“血の大晦日”に彼がやって来なかった理由は最低…… でも、その自責の念こそが、炎の中からキリコを救い出す原動力となったのだ。マルオがケロヨンのもとに辿りついたとき、キリコはヤマネが生み出した最終ウイルスを相手に、自らを実験台にして24時間一本勝負を開始。その間、マルオの問いかけに、カンナの父親、そして“ともだち”はフクベエだと語る。そして、アメリカから帰国後に会った“ともだち”はフクベエではないとも。一方、“ともだち”の本丸で“ともだち”と対峙するカンナ。そして、目の前の“ともだち”は自分の父親ではないと気付く。すると、カンナに“絶交”を突きつける覆面の男。やはりこいつは、カンナの父親、フクベエではないらしい……。その頃、万丈目は既に死んでいた……高須に陥れられたオッチョとユキジ。そして、“ともだち”の本丸脱出途上、空飛ぶ円盤を発見。そして、リバウンドでパンパンに戻ったマー坊と再会。さらにヤン坊や敷島博士、そして進化した巨大ロボットにも出会うことに。さて、覆面の男の正体は……鍵を握るのは、少女時代のキリコにしゃべりかけてきたサダキヨではなく、もう一人のナショナルキッドのお面を被った少年。フクベエやヤマネ君と一緒にいた少年。こいつは、一体誰なんだ?ひょっとして、映画でも覆面被らされていた人物と同一?まぁ、確かにアイツは漫画(原作)の中でも、結構怪しい要素が多い。ケンヂ達との距離感に“ともだち”の仲間たちと近いものを感じる。さてさて、人体実験開始から24時間が経過した。キリコは死ななかった。キリコの作り出したワクチンが、そう、人類が勝利したのだ。そして、『20世紀少年』は残すところ2巻となった。
2009.10.05
コメント(0)
-

20世紀少年(19)
ストーリー進展ペースは確実に遅くなっている。 19巻はケンヂが関東軍のお城に乗り込んで、 その主と対峙するというシーンまで。 その主は映画とは違っていたけれど……。 もちろん、覆面の男の正体も 映画とは違っているのかもしれない。 でも、まだその部分については謎を残したまま。 火星移住計画と人類滅亡計画……『マグマ大使』のゴア、『宇宙戦艦ヤマト』のデスラー『仮面ライダー』のショッカー、『黄金バット』のナゾー『ドラゴンボール』のピッコロ大魔王、『北斗の拳』のラオウ『サイボーグ009』の黒い幽霊団、プロレスのタイガージェット・シン。「本当の悪」を名乗る男が求めるものは、悪と対峙する正義の味方。この男が、プラットホームで「キリコの大切な男」の背中をドンと押した。その指示を出したのは“ともだち”。「キリコの声」が録音されたカセットテープを聴かせながら。その時の、その男の問いかけ。 あのさ…… あなた、こないだの人と同じ人?“ともだち”の答え。 どういうこと?その男の返事。 フフ……誰でもいいや。 どっちにしろ、“ともだち”だもん。ところで、あの時キリコの声を録音してたのは、確かヤマネ君……だよね?
2009.10.04
コメント(0)
-

20世紀少年(18)
「登場少年紹介」で紹介されている 北の果てからギターを持ってやって来たC調男・矢吹丈の絵は、 私の中では玉置浩二さんのイメージにぴったんこカンカン。 「田園」歌ってる頃の玉置さん。 もちろん、矢吹丈の正体はケンヂであり、 ケンヂのモデルになったのは遠藤賢司さんであり、 その代表曲は、何といっても「カレーライス」なのは周知の事実。 でも、この絵はどう見ても、私の中では玉置さんなのだ!ともだち暦元年、カンナと中国マフィア・タイマフィアの面々との久々の再会。そこで繰り広げられた大芝居。カンナにワクチンを打たせるための大芝居。「おまえは希望の星だ……おまえは私達の……娘だ……」映画でも、このシーンはヨカッタな。カンナが知ってる「ケンヂの歌」。そして、ラジオから流れてくる「ケンヂの歌」。「こんなフレーズ……聴いたことない……」武装蜂起中止をメンバーに伝える氷の女王・カンナ。しかし、その後カンナとオッチョは親友隊に捕まってしまう。二人が連行された部屋では、万丈目が待っていた。そして彼は言う「“ともだち”を殺したい。」と。一方、マルオと春波夫の方は、TTVで万丈目の過去を次々に知ることに。その時、話題にのぼったのが『日米対抗ローラーゲーム』。東京ボンバーズの中心選手は、漫画にも名前が登場する佐々木陽子にミッキー角田。ボビー加藤も結構目立っていたが、それ以上にインパクトがあったのは、実は実況をしていた土居まさるさんだったりして。さて、三か月ほど前に開かれた“ともだち”一味の定例会議。そこでは、ウイルスがばらまかれ、世界が滅亡した後の様子についての報告がなされる。地球上の人類生存率はヨーロッパで48%、アジアでもほぼ同様の数字、アメリカの被害が最も大きく41%。 そんなに生き残っちゃったかあ…… もう一回……何かやらなきゃダメかな……答える万丈目 もう……十分だろ……そして、覆面の男は小さな声でそっと呟いた フクベエだったらどうしただろう…………この男……誰だ!?
2009.10.04
コメント(0)
-

20世紀少年(17)
今巻もセリフ付きの表紙。 ただし、今回はそこからいきなりお話しが始まるわけではない。 今巻の表紙になってるのは第8話の表紙部分。 背景はコミックスの表紙用に、ちゃんと修正・アレンジしてある。 カツオの活躍で、オッチョは仁谷神父との再会に成功。 一方サナエは、氷の女王ことカンナとの接触に成功。 しかし、カベの外ではワクチンをめぐって悲惨な状況になっていたのだ。 オッチョの記憶……多くの絶望…… 絶望に打ち勝つ方法などない…… ただ…… 歩き出すだけだ……オッチョは師匠の言葉を胸に、また歩き始めたのだった。その頃、蝶野巡査長は疑問を感じながら、北方検問所で勤務していた。その村の人々が隠れながらコッソリと聴いてる歌。ラジオから流れるその曲は、村人達にとっての希望。スパイにアジトを知られたため、そこを引き払う準備を進めるカンナと仲間達。カンナの部屋では、ラジカセからケンヂの歌声が流れてくる。その曲が終わると、プライベートテープを全てサナエに手渡してしまうカンナ。「あたしにはもう必要ないから」と言いながら。そのシーンで、サナエがカンナに問いかける。 この曲……これで終わりですか?それに対して答えるカンナ。 そうよ。その反応に「?」のサナエ。その理由は、アジトのソバ屋を出た後のサナエの言葉の中に。 知ってる……… プライベートテープ……? カンナさんしか持ってない…? じゃあなんであたし、この曲聴いたことあるの…? この歌は、あそこで終わりじゃない。 あたし、この歌の続き知ってる…!!そして、コイズミが発見したエロイムエッサイムズのダミアン吉田が路上で歌っていたのは、3年前の2015年、西日暮里の十字路で出会ったという男が歌ってた曲。それは、各地で受信されているというラジオの曲と同じものだった。吉田がその男に名前を聞くと、逆にお前の名前はと聞き返してきたという。「エロイムエッサイムズのダミアン吉田です」と答えると、その男は「じゃあ、俺は悪魔くんだ」と名乗った。そして北方検問所にバイクの男がやって来た。その男は名前を問われると、逆にお前の名前は聞き返した。「自分は星巡査である!!」との答えにその男は「星くんか…それじゃ俺は……矢吹丈だ」と答えた。ケンヂ見参!!
2009.10.03
コメント(0)
-

20世紀少年(16)
巻頭は「登場少年紹介」を含めて初のカラーページ。 しかも、表紙からお話しが始まるという斬新さ。 おそらく、週刊ビッグコミックスピリッツでの体裁を そのままコミックスで再現したのだろうが、なかなかスゴイ。 ただし、そこから始まるお話の内容は、とっても重い。 ハットリ君の歪んだ人格には吐き気を覚えるほど。 1970年の夏休みの真実が、そこで展開される。 万博には行かず、“首吊り坂の屋敷”を演出した二人の夏休み。そして第6話から、突然(?)ヤマネ君がお話しに加わる。三人で“しんよげんのしょ”について語り合ってる。場面はあの夜の理科室、ドンキーと三人との対決シーンへ。ところが、ドンキーが窓から飛び降りた後には意外な展開が…… おまえが………こんなふうに死ぬとは思わなかったよ。覆面の男が最後に見たイメージ。過去の記憶を読み取って入力(ヴァーチャルアトラクションへ?)している最中、システム異常が発生してしまい、そのときに見たイメージ。それは間違いなくケンヂの台詞だろうが、何を意味するのか?続くともだち暦3年のシーン、町並は1960年代よりさらに前の時代の様相を呈している。棒高跳びでカベを乗り越え、この町(東京)に入り込んできたオッチョ。それを手助けするサナエとカツオの姉弟。放送終了後のテレビからは武装蜂起を呼びかける声が……氷の女王。淀橋テレビセンターでの騒動の後、ガッツボウルで神様と出会った三人。そこで神様はオッチョに問いかける。 欲しいオモチャを苦労もせずに手に入れ続けて、 ついには欲しいものがなくなったとしたら…… その子どもはどうするね?地球はどうなってしまうのか?
2009.10.03
コメント(0)
-

20世紀少年(15)
ルチアーノ神父、ペリン神父、そしてニタニ神父。 本巻は、まずこの三人の神父のお話を軸に進行し、 それらは、それぞれにイイお話しに仕上がっている。 中でも存在感を示しているのがペリン神父、現ローマ法王。 そんな三人が“ともだち”をめぐって歌舞伎町に集結。 蝶野刑事もなかなか頑張って仕事している。 そして、ローマ法王を迎えての一大イベントで“ともだち”復活。 それを太陽の塔から狙撃する13番。ローマ法王を凶弾からかばい、倒れる“ともだち”。そして“ともだち”はホンモノの神になる。「りんりんとでんわがなって、すべてのじゅんびがととのうだろう」防毒マスクにスーツ姿のセールスマンは、彼の使者。噴出された霧は美しい虹となり……世界滅亡、西暦が終わった。そして、ともだち暦3年、あの男が復活!!これにて、映画の第2章の部分が終了。5巻半ばで第1章の部分が終了したことからすると、第2章の部分には、随分紙幅を費やしている。というか、映画では描かれていなかったことが、5巻からこの15巻までの間には、ずいぶんあった。もちろん、これを全て原作に忠実に再現するとしたら、とんでもない時間を要し、第3章なんかでは、とてもエンディングを迎えることはできないだろう。
2009.10.03
コメント(0)
-

20世紀少年(14)
ヨシツネとコイズミが入り込んだヴァーチャルアトラクション。 そこは1971年8月の世界。 しかし、以前コイズミが来たときとは何かが違ってる…… そう、あの秘密基地のあった空き地にボウリング場が建っていた。 これは“ともだち”が作り出した嘘の1970年ではなく、本当の1971年? “首吊り坂の屋敷”の肝試しの真実が、そこにはある? そして、そこに集う者・未来からの侵入者が次第に増えていく。 万丈目、カンナ、そしてあの男が……。中目黒で高須が見たのは誰?中華街でユキジが見たのは誰?オッチョが追いかけていたのは誰?西麻布であの一味の女が見たのは誰?1971年8月、ドンキーが理科室で出会ったのはサダキヨとヤマネ君。そして、そこには首を吊ったフクベエも……そして、奇跡の復活?それをトリックと言い放つドンキー。そんなドンキーに“絶交”を迫るサダキヨ、ヤマネ君、フクベエ。ドンキーが窓から飛び降りた後、本当に起こったこととは?万丈目が知っている真実(だったはずのこと)とは?しかし、目の前で今起こっていることが真実なのだと語るあの男……覆面の男。そして、覆面の男は、首を吊ったフクベエの足を引っぱり殺そうとする……それにしても、ドンキーって見かけによらず(失礼!!)、なかなか理知的というか現実的というか科学的というか……、ずいぶんイメージ変わってしまったな。カンナとの対話は、ある意味とってもカッコ良かったヨ。
2009.10.03
コメント(0)
-

20世紀少年(13)
あの忍者ハットリ君のお面には、そんな意味があったのか…… 遂にヨシツネが、お面が語るものに気付く。 教科書の写真を撮った男、 小学校の時クラス全員のスプーンを曲げた男の正体に。 “ともだち”は死んだ…… けれど、まだ私は確信できないでいる(映画のお話しを引きずりすぎ?) とにかく13巻では、偽のカリスマの死後、残されたメンバーたちの間で、 粛正……血なまぐさい裏切りや権力闘争が始まった。とにかく、ここに来て映画とは全く異なる展開に突入した。もちろん、春波夫とケンヂの関係が語られたり、ケロヨンがアメリカで登場したり等、部分部分についてはオーバーラップするところはある。でも、コイズミの扱いは、映画では考えられないほど益々重要なものになってきている。なのに、彼女だけが関わっている部分のお話しは、映画ではほぼカット。さらに、ケロヨンがニューメキシコ州で出会った少年が、ケンヂの話をする部分はとってもイイんだが(ちょっと感動!)、映画ではなかったと思う。さらに、キリコのお話しはとっても濃密。ヤマネ君とのやりとりやニューヨーク州、ハイマートリヒトでの孤独な奮闘ぶりは、このままいくと、自らがまいた種によって世界を壊滅させてしまうかもしれないという危機を何とか自分の力だけで回避しようとする、悲壮感に溢れる姿で満ちており、とても痛々しい。さぁ、次巻ではいよいよカンナが“ともだちランド”のヴァーチャルアトラクションに乗り込む。
2009.10.03
コメント(0)
-

20世紀少年(12)
今回、まず気になったのは「登場少年紹介」の部分。 そこに初めて「いままでのあらすじ」が登場したのだが、 その記述の中に「?」な部分を見つけてしまった。 それは「経済成長著しい1960年、ケンヂ達は生まれた」というところ。 これのどこが「?」なのかというと、 1960年生まれの人間は、大阪万博が行われた1970年には、 小学4年生(早生まれでない限り)のはずなのである。 でも、万博開催の年、ケンヂ達は小学5年生という設定だったんじゃないの。本巻の中でもヨシツネが次のように語っている。 万国博覧会が一九七〇年。 その年、僕らは小学五年生……さらにヨシツネが 一九七一年は何があったときだっけ?と問いかけたとき、ユキジはこう答えている。 小学校六年生の時…………ということは、ケンヂもヨシツネもユキジも、そろいも揃って、皆早生まれっていうこと?でも、その確率は結構低いと思われるのだが……つまり、これらの言葉から普通に考えれば、ケンヂたちは1959年生まれのはずなんだけど…… ***もう一つ気になったこと……いや驚かされたことは、本著に挟み込まれていた一枚の紙切れ。更紙のような紙に書かれた「ひみつ集会のお知らせ」。実は、これを最初見たとき、かなりドキッとしてしまった。ただ、私はこの本を古本屋さんで購入したので、ひょっとして、元の持ち主が遊び心で書いたものが挟み込まれたままになってしまったのかもしれないと考えた。それともイタズラ心で、この本を売るときにわざと挟み込んだのかなとも考えた。しかしながら、漫画に登場する「ひみつ集会のお知らせ」とその紙切れを比べてみると、あまりにもその字体が似すぎているのである。紙切れに書かれている字は印刷したもののような感じではなく、何かのインクで書かれているような感じがするし……どうなってるんだ?ちょっと、不気味になってネットで検索してみると、すぐに謎は解明された。やっぱり、これは印刷物で、元々本著に挟み込まれていたものらしい。ただし、これが挟み込んであったのは初版本のみということ。私の手元のものを見ると、確かに2003年5月1日初版第1刷発行となっていた。 ***さてお話しのほうはと言うと、ここにきて、ヤマネ君の存在が大きくクローズアップされることに。そう“しんよげんのしょ”をつくったのはヤマネ君だったのだ。そこに辿りつくまでのオッチョと角田君の活躍は、ミステリータッチでスリル満点。そして、ケンちゃんライスを食べてるときのあの子どもたちの不可解な反応の鈍さの裏に隠されていた秘密も明らかになる。それは、ともだちがつくりだした偽のシチュエーションだったのだ。そんな嘘つきの「ともだち」の正体も、遂に明らかになった(はず)。でも「ともだち」、本当に死んだの?
2009.10.02
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1










