2007年06月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

ひとつ、ひとつ
志 錬世の中に完璧などあるだろうか。少なくとも、柔道に完璧などあり得ない。死ぬまで修行。死ぬまで精進。その時々の自分を見つめ、劣るところを高め、秀でたところを更に高める。その時々の自分を見つめ、目標を定める。その時々の自分を見つめ目標に、ひとつ、ひとつ近づける。完璧などあり得ないのだから、焦らず。 大きな課題でなくても良い。 課題を多くすることもない。しかし、その課題を「意識」する。 具体的にして「意識」する。 「意識」して確実に「克服」する。ひとつ、ひとつ確実に「克服」して行く。 日々、修行。日々、精進。
2007.06.30
-

追い込み
大きな大会が目前の日曜日に迫っています。残された稽古は、昨日を含め、土曜日と二回。土曜日は、打ち込み、投げ込み中心にするとして、昨日が追い込む上での最終日となりました。レギュラーを立たせての1分、30秒、15秒の乱取を行いました。みんな、大分、根を上げてたかな~しかし、感じたことは、レギュラー以上に当たりに行く子供達。「レギュラー」と「レギュラーになれなかった子の差」が思った以上にあると言うことです。何がって実力以上に気持ちの問題です。「次こそは、こいつらを倒して、俺がレギュラーになってやる!」と言う貪欲な気持ちが見られませんでした。「レギュラーには、かなわないや~」と言うふぬけた感じの子が多く見えました。今後、夏から秋にかけても、いくつかの試合に参加して行きます。その全ての大会の団体戦で優勝を目指します。そのためにも、その時々のベストメンバーで団体戦のオーダーを組みます。全員がレギュラーになれる様に全力を尽くして欲しいと思います。みんなガンバレ
2007.06.29
-

必勝法 其の五
志 錬 《其の四 岡野功先生の八つの必勝法。四つ目である。四、最初から全力でぶつかれ相手を甘く見て力を抜いてかかると、途中で、手ごわい、と気がついても調子の切りかえができない。どんな相手にでも最初から全力をつくせ。勝負に絶対など在り得ない。先月まで実力が劣っていた者が、見違えるように強くなることは、決して珍しいことではない。体が小さいから実力が劣る訳ではない。弱い道場の子だから実力が劣る訳ではない。女の子だから実力が劣る訳ではない。劣勢だからこその策も侮れない。「獅子は兎を屠るにも全力を以てす」つづく 其の六》よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.28
-

三歩 進んで、二歩 さがる
日曜日に主催した合同稽古は充実したものとなりました。それは、稽古で意識を高めることを促し、ご家庭での話し合いで促した、子供達とのコミュニケーションの成果であると確信します。そして、迎えた昨日の稽古・・・残念ながら、序盤の回転運動からダラケ感が目立ちました。私は、あえて見て見ないふりをしていると・・・「声を出さない」「手を抜いている」「仲間と無駄話し」などなどしかし、私が、本当の意味で残念だったことは、チームとしての姿がなかったことです。ダラケたといっても、中には、合同稽古から継続した意欲で取り組もうとしていた子も見受けられました。ところが、その意欲の高い子が低い子に足を引っ張られてしまうことです。本来であれば、意欲の高い子が低い子を引っ張り上げなければなりません。これは、キャプテンを始めとした6年生の役割でもあるのに、当の6年生達の意欲が低く感じられました。子供達を集めて、戒めました。最近の当たり前の光景になりつつあります。稽古は、立技から寝技への連絡乱取をしたあと、本来、試合も間近で追い込み稽古にしたいところでしたが、あえて“息抜き”を入れました。とは言っても非常に大切なものです。足技の一人打ち込みです。足払い前・後、大内刈、小内刈のステップワークを身に付けるのには最適です。最後は、乱取をして締めましたが、最終的には子供達の意欲が高まって来たように思いました。毎回の稽古が子供達の高い意識の元で行えるのであるば、最良です。しかし、そこは子供達。一気に改善は無理なんでしょうね。一度、話したくらいで高い意識を継続させられるものではありません。稽古もそうですが、ご家庭で毎回、簡単な反省会をして欲しいと思います。毎回、毎週、毎月、少しずつ、稽古とご家庭を通じてレベルアップして行きましょう幸せは、歩いて来ない。だから歩いて行くんだね。一日、一歩。三日で三歩。三歩、進んで、二歩さがる。
2007.06.27
-

柔よく剛を成す
志 錬与えた課題に意を傾けない子がいる。それが体が大きかったり、センスに恵まれた子であると尚のこと残念でならない。柔道とは、力比べではない。持ち得た力を如何に効率的に作用させるかの知恵比べである。だからこそ、「柔よく剛を制す」が成立する。しかし、力があったり、センスがあると小学生レベルでは、理など解せずとも勝利を得てしまう。結果的に、指導を蔑ろにする行為を招くのだと感じる。逆に体が小さかったり不器用な子にとっては、強くなるための蜘蛛の糸。必死に指導に耳を傾ける。この差が後の差につながる。例えば、幼い頃に体格差のあった両者。片や巻き込み的な技で勝利するのに対し、片や体全体を活かして相手を崩さねば勝利を得ることが出来ない。成長の過程で仮に両者の体格が同じになったとすれば、自ずと優劣は想像出来る。だからこそ、私は、体の小さい子や不器用な子にこそ、強くなって欲しい。何故なら、口で言っても判らない体の大きな子やセンスに恵まれた子でも、現実的に劣る子に負けることで、目を覚ます子もいるからである。体が小さく不器用な次男に、「お前が強くなることで、他の皆が強くなる。そうしたら、お前はどうする?」と質問した。「それより、もっと強くなる。」と返って来た。本心かとも思ったが、頑張って欲しい。「柔よく剛を成す」である。画像は、1976年モントリオール五輪にて小兵ながら日本悲願の無差別級を制した、上村春樹選手(現・全柔連専務理事)よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.26
-

主催合同稽古
昨日は、月1回企画している日曜練習日でした。そして、今回は、初の試みとなる他道場をお招きしての合同稽古となりました。1時から2時過ぎまでは、通常の少年クラブの練習です。そして、2時半からは、いよいよ、合同稽古。今回は、隣々街から鬼軍曹先生が20人弱の子供達を引率して来てくれました。さすがは、鬼軍曹先生が鍛えている子供達です。立技や寝技に限らず、スピーディーな動きをする子。粘り強い動きをする子が多く目に着きました。逆を言えば、少年クラブの子供達は、この辺が課題なのだと気付いたかな~。頭で「次に何をしようか?」と考えているようじゃ対応が遅くなってしまうよその状況、状況で素早く何をするのか体が勝手に動くくらいにならないとな最後には、練習試合をさせていただいたりして、お陰様で熱気ある稽古を行うことが出来たと思います。合同稽古の初回としては成功だったのではないでしょうか合同稽古に参加してくれた子供達ありがとう鬼軍曹先生を始めとした先生方、ご父兄の皆様、ありがとうございました。また、一緒に稽古しましょう次は、そちらにお伺いしますよ。 よろしくお願いしますね
2007.06.25
-

外泊学習
私達の住む市では、小学生の課外教育の一環として、小学5年生の時に3泊4日の海浜学園があります。今朝、旅立つ、長女を見送ってきました。最近、わがまま度が強くなってきた長女。親元を離れて、仲間との体験を通して“思いやりの心”を学んで来て欲しいと思います。私も中学校までは、ボーイスカウトに所属していましたので、この様な活動から得る精神的な成長は、計り知れないと思っています。水曜日に帰って来て、少しは変わってくれているでしょうか少年クラブでも今年から柔道・夏合宿をします。残念ながら、平日開催とのことらしく、私は、仕事で参加できないと思います。参加する子供達には、参加して何らかの課題を克服して来て欲しいですね。また、今後は、オヤビン先生に相談しながら強化合宿も企画したいですねー理想は、年3~4回くらいかな~近場で交通費を節約して、安い宿泊施設を探せば可能だと思います。勿論、ご父兄の協力も欠かせないだろうな~実現できるでしょうか強化合宿きっと、子供達を大きく成長させることができると思うけどな~
2007.06.24
-

メンタル・タフネス
志 錬プロ野球の米大リーグの先駆者の一人である長谷川滋利氏。もう、大分前の話しになってしまうが、3年近く前に彼のトークセミナーに参加したことがある。スポーツ競技者または、指導者20名限定の抽選に当選しての参加であった。その際、彼は、自分の事をこう言い切っていた。「私は、球が早いとか、フォークが落ちるとか技術的に一流だからメジャーリーガーなのではない。メンタル面で一流だからだよ」と。言い切れる自信が凄いと思った。しかし、彼に資質はあったのであろうが、最初から“強靭な精神力=メンタルタフネス”ではなかったらしい。メジャーリーグでの試合、練習、生活を通した厳しい環境とそれに打ち勝とうとする彼の努力の賜物でしかない。また、彼を支えたメンタルトレーナーを始めとしたコーチングスタッフも優れていたとも言える。私自信、彼の話しから、セミナーの直後にコーチングの書籍を購入したくらいに強い影響を受けたことを思い出す。残念ながら、セミナーの翌年、彼は引退した。彼の技量であれば、まだまだ、日本のチームでも活躍できたはずである。しかし、“メンタルタフネス”の彼のことです。決して、逃げたのではなく、自分や家族にとって最良の選択をしたのだと思う。今後の更なる活躍を期待したい。最近、子供達との接し方で悩むところもあり、新しいコーチングの書籍を購入した。この本を読んでいて、彼のことを思い出し綴ってみた。
2007.06.23
-

勉強は、・・・が問われます。
勉強は、「何時間やったか」よりも、「何をやったか」、「何ができるようになったか」が問われます。通勤の時に電車の中で見かけた、進学塾の広告コピーです。「何」かを高めると言うことは、「何」かを具体的にすることが大切です。勉強を頑張るではなく、数学を頑張る。数学を頑張るではなく、分数を頑張る。分数を頑張るではなく、分数のドリルで100点を取るまで頑張る。柔道でも同じです。漠然と柔道を頑張るでも低学年なら良いでしょう。しかし、高学年ともなれば、もう少し具体的な課題を掲げるべきです。技術的な課題。体力的な課題。精神的な課題。それは、その子それぞれです。火曜日の稽古は、最悪だったと綴りました。その状況をご家庭にも訴え、話し合いをお願いしました。そして迎えた、昨日の稽古。・・・確かに疲れてくると、声数も減っては来ましたが、基本的には声が出てました。私から求められて声を出すのではなく、自分達の意思で出すことで、稽古そのものが、「私の稽古」から「子供達の稽古」になってました。正に子供達が課題を意識して取り組んだ結果だと思います。結果、子供達も私も楽しい稽古が出来ました。稽古は、「何時間やったか」よりも、「何をやったか」、「何ができるようになったか」が問われます。さぁマルちゃん杯は、直ぐそこです
2007.06.22
-

柔道談義
昨晩は、ネットで知り合ったS&Tさん、京太郎さんの3人とで一杯やりました。3人は、ブログのやりとりで互いの環境は、概ね分かっているものの初対面です。S&Tさんは、柔道経験者。次男(高1)と三男(小6)が柔道に取り組まれています。京太郎さんも、柔道経験者。長男(中2)と次男(小2)が柔道に取り組まれています。経験者のオヤジと息子2人。なんか、私も含め、似たような感じです。。。お二人とも熱い 7時過ぎから飲み始めて、11時半過ぎまで飲んでたかな~。いゃ~、飲み過ぎました。具合が悪くて、途中下車して休んだくらいです。今度、どこかの道場を借りて、ブログ仲間による合同稽古をしようかとなりました。そうなれば、息子達だけじゃなく、少年クラブの希望者も連れて行こうと思ってます。実現できるか分かりませんが、実現したら楽しいと思います。しかし、柔道好きと飲む酒は、美味い楽しい
2007.06.21
-

気の緩み
キャプテンの優勝を始め好成績を残した日曜日。その直後となった昨日の稽古。みんなのモチベーションが最高潮となり、素晴らしい稽古となりました。・・・と、なると期待していました。しかし、稽古の序盤から声が出ていません。声を出すと言う効果もさておき、「毎回、同じことを言われても実践できない。実践しようとしない意識の低さでは、成長しないよ!」と言う私に「ハイ!」と答える子供達。しかし、声が出たのは束の間。また、出なくなってくる。子供達が自分自身で課題を自覚し、意識して改善しようとする気持ちが低いのだと思います。また、自分は、出していると主張する子もいました。自分だけが、出したから良いのではないのです。特に6年生は、後輩達に促さないと・・・キャプテンも真価が問われるのは、この辺の統率力であるとも思っています。日曜日の試合から課題の一つを取り上げて指導してみました。ポイントを絞って、強調して指導してみました。ところが、直後から、そのポイントを試みようとしない子供もチラホラ・・・。なぜ、課題を自覚し、意識して取り組もうとしないのか・・・。昨日の稽古には、子供達が自ら稽古しようとする意識が感じられませんでした。昨日の稽古は、ここ最近で最悪の稽古でした。誰に、この責任にある訳じゃない。正に指導者の責任。指導者としての真価が問われているのだと実感しています。子供達が、「やらされる稽古」ではなく、子供達が「自らやる稽古」に導かねばなりません。子供達が課題を自覚し、自らの意志で改善しようと取り組む意識。子供達自身とその支援者であるご家庭に理解してもらえるように訴え掛かるしかないと思っています。
2007.06.20
-

登竜門
志 錬昨秋の新人戦市大会において、敗した長男。以降の成長を測る場となった市中学校総合体育大会が本日、開催された。-55Kg級。新人戦3位の実績からシードの一角。・・・まずは、無難にベスト4を確保。そして、「決勝進出=県大会出場権」をかけて、学校の先輩(新人戦2位)と戦う。・・・一本に近い技有を背負投で奪っての優勢勝ち。そして、初の県大会出場権獲得。決勝は、新人戦の準決勝で圧倒され、4月に対戦した試合でも技有で敗れている相手(同級生・新人戦1位)。長男が決勝に進出したと言うことは、敗れた先輩は、県大会に出場できないと言うことでもある。先輩のためにも、県大会出場権だけで満足することなく優勝を狙うように促した。本人もその気に相違ない。結果は、・・・判定ながら旗3本を得て勝利した。5月にあった試合で不甲斐ない負けをしたことが、逆に、その後の稽古を良い方向に傾かせた。戦うごとに大きな挫折と僅かな成長を繰り返しているのが分かる。春、大河黄河の流れの急な三門狭(滝)を 挫折することなく登り切った鯉だけが 竜になると言われる言い伝え。登竜門。あくまでも市大会。決して登竜門を登り切ってはいない。よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.19
-

克服
昨日、開催された全国小学生体重別柔道大会県予選には、支部代表として7人の子供達が参加しました。その中で、6年生男子-50Kg級でキャプテンが優勝愛媛の全国大会出場の切符を手に入れました途中で昨年代表の子を破ったのを始め、決勝までの5試合オール一本勝ちの完全勝利でした。素質豊かな子でしたが、これまで県大会レベルでは結果を残すことが出来ませんでした。しかし、ここ1年の努力と成長は相当のものでした。自分自身で課題を掲げ取り組んだ結果なのだと思います。また、5年生女子+40Kg級で3位と言う結果も残せました。同日開催された別の大会でも、3階級で準優勝、1階級で3位の結果を残しました。目に見える成績の面での成果も出て来ています。しかし、子供達に本当に気付いて欲しいのは、キャプテンが優勝した意味、意義です。確かに成績の良し悪しも大切だとは思います。しかし、本当に大切なのは、試合を通して得た課題を次に活かすための稽古が出来るかです。これが出来るか出来ないかが、成長を左右します。勝てば良いわけじゃない。負けても悪いことばかりじゃない。要は、課題を意識して、その課題を克服する努力が出来るか出来ないかが大切。課題を意識した稽古をして、次の大会では、少しでも成長した良い結果を残そう
2007.06.18
-

啓発
「憤せざれば啓せず、ひせざれば発せず」昨晩、長男、次男、それぞれを強く叱りました。二人とも試合が迫っています。特に長男は、新人戦で逃した県大会への出場権を獲得するための地区予選です。にも関わらず、二人の啓発意識が低すぎる。漠然と稽古を繰り返すばかり。一生懸命に頑張れば良いと思っている。先日の稽古の時に、HORY先生もおっしゃってました。「教えてもらったことを、身に付ける努力をしなければ、向上しない。」そうです。稽古を一生懸命すれば強くなると思ったら大間違いです。意識の低い稽古を、漠然と何時間もしても強くなんかなれません自分が気づかずにいるところを、せっかく教えてもらっても、それを認識、理解して、向上するために身に付け様と努力しなければ成長なんてありません。長男、次男には、ここが欠けている。だから、同じ負け方を繰り返す・・・長男に至っては、技量的には、問題ないと思っています。問題は、啓発心の部分です。今の二人で出来るレベルで、各々の問題点を克服して、差し迫った試合に挑んで欲しいと思います。後は、天命を待つしかありません。
2007.06.17
-

空気の色
志 錬目に見えないモノの代表である空気・・・。しかし、心眼でみると色が見えてくる・・・。今年の初め、ある強豪道場の稽古を初めて観る機会があった。情熱的な指導者達の元で如何なる稽古なのか興味津々で赴いた。空気の色であれば、緊張感漂う青か、活気溢れる赤か…。・・・意外にも、私が感じた空気の色は、差し込む西日の影響もあったのだろうが、橙色であった。活気溢れる稽古であるのは間違いない。しかし、指導者の情熱の強さが出過ぎていないのである。子供達に、やらされていると言う感じはない。目標を成すために何をすべきか意識付けられているため、各々が自らの意志で動く。指導者が主人公ではない。あくまでも、子供達が主人公。指導者は、子供達の高い意識を維持する役割に徹し、稽古そのものは、子供達自らの意欲で動かしている感じである。重要な役割なのだが、スクリーンには出てこない監督、演出家のようなスタンスであろうか・・・。現在の道場では、子供達の士気を高めるために私の雄叫びが欠かせない。しかし、私の色に子供達を染めようとは思わない。染めてはならないのだと想う。子供達の今の色が何色なのか。これを理解した上で、その子に相応しい色に導いてあげることが大切なのだと考える。それには、私の雄叫びなしで、士気が高まるまでの子供達の自立が望まれる。そう、私が理想とする、橙色の空気の道場のように・・・。
2007.06.16
-

継続
志 錬続けることの大切さ。その大切さに、如何に早く気付くことができるかで、その者の将来が大きく変わると感じている。気付くのが、後になれば、後になるほどに、その大切さを痛感し、そして取り返しが利かないことを悟る。継続に裏づけられた努力の重さは計り知れない。見た目だけを繕った一夜漬けの努力の重さとでは訳が違う。あの時…と後悔したところで取り返しなど効かない。長い歳月で積み上げるからこその価値である。また、継続とは、思いのほか冷酷である。一時的な成果に満足して継続を怠るならば、それまで培ったものなど容易に崩壊する。継続の価値を継続させるのも、継続でしかない。“継続は力なり” 継続に終わりはない。OKさんの画像をパクってしまいました。ごめんなさい!
2007.06.15
-

残心
今日の強化稽古の中で、投げてから寝技への連絡の練習しました。“立技”だけが柔道でなければ、“寝技”だけが柔道でもありません。それぞれが一緒になって初めて柔道です。しかし、一般的には、立技優先の練習になってしまいます。また、安全面からなどで、立技と寝技を分けて練習しがちですので、投げてからの寝技への連絡が下手な子が多いのが現状です。武道には、“残心”(ざんしん)という言葉があります。様々な解釈があります。「武士が相手の息の根を完全に止めるまでは、決して気を抜かない気」です。それを姿勢で示すことを“残身”ともいいます。スポーツだと“フォロースルー”と言ったりもします。柔道においても、“残心”は、非常に大切です。投げて一本だと思って気を緩めたら、実は、技有で逆に抑え込まれて負けてしまう子を見かけます。また、投げて、直ぐに抑え込めば良いのに、何故か審判の方を見てアピールに一生懸命になって、相手を逃してしまう子も見かけます。投げてから寝技への連絡は、まさに“残心(残身)”が大切であると思います。とにかく、試合場に入る礼から試合場を出る礼までの間は、一瞬たりとも気を抜かない集中力が勝負には欠かせない心構えです。
2007.06.14
-

追い込み
17日は、全国小学生学年別柔道大会の県予選です。少年クラブからは、支部予選を勝ち抜いた5、6年生の7人が出場します。また、同時開催の1年生から4年生の個人戦にも、各学年男女1名づつ出場します。さらに、希望参加ですが、都内で開催される大会(個人戦のみ)にも、数人の子供達が出場します。と言う訳で、最近の火曜日の強化稽古(居残稽古)は、練習試合をしていましたが、ケガの心配もありますので、打ち込みを中心とした追い込みを行ないました。追い込みですから、私の声も、普段以上に大きく厳しくなります。慣れない子供達の中には、音を上げる子。いい加減な打ち込みをして誤魔化す子。なども見受けられました。これまで経験のない稽古がどんどん増えてきます。つまり、子供達の技量が高まって来ている証拠でもあると思います。強豪道場からすると、当たり前の稽古風景ですが、私達にとっては、まだまだ、試練ですね~さて、24日の日曜日の特別稽古には、鬼軍曹先生のところの子供達が出稽古に来てくれます。今まで、他の道場が企画された合同練習に参加するばかりの立場でした。しかし、今後は、主催する立場にもなって行きたいと思います。初めて主催する合同練習ですが、子供達と精一杯頑張って、笑われないようにしたいですね
2007.06.13
-

カウンター
技のスタートを一歩目だと思っている子供達が少なくありません。結果、打ち込みで、一歩を踏み出したまま、戻さずに繰り返すのでしょう。楽ですしね。私は、相手との間合いを取った形をつくることからがスタートだと考え指導しています。サッカーでボールを蹴る時に足を後ろに戻します。テニスでボールを打つ時にラケットを後ろに下げます。野球でボールを打つ時。バレーボールでスパイクを打つ時。様々なスポーツには、打つ方向や投げる方向と逆方向に下がる動作があります。テイクバックやカウンター、反動って呼んだりします。ここでは、“カウンター”と呼ぶことにします。止まっている大きなドラム缶を動かすのは、非常に大変です。しかし、反動を使って、揺さぶってから、動かすと比較的容易に動きます。静止した状態から急に動くには、膨大な力が必要なのに、動きがあるとスムーズにスタートを切ることができるのですつまり、技を掛ける前にキチンと戻る動作は、技をスムーズにスタートさせるためには欠かせない動作であると位置づけてます。※画像は、内股ですが、1がカウンター動作にあたります。 試合や乱取で技を狙い過ぎるため、一歩目を出したまま、半身に構える子がいます。※最初から画像の2の構えをしていることです。これでは、“カウンター”の動きが出来ません。結局、技自体は、決して悪くないのに、威力が半減してしまいますので、掛からなくなってしまいます。カウンター。伝えてゆきたい動作です。よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.12
-

好きこそ・・・
志 錬「水の中で浮かんでいることが心地良かったから」何かを極めるには、それを好きになることが最も大きな要因になると考える。そしてまた、その理由は、単純な方が良いのではないかと感じている。アテネ五輪の金メダリストの北島康介選手が水泳を好きになった一番の理由が先のコメントである。正に単純な理由である。好きになることこそが人に意欲を創造させるのではなかろうか。好きだからこそ、更なる「心地良さ」を求める様になる。北島康介選手にしても、最初は、水の中に居ること、泳ぐことだけで満足していた。それが勝利の喜びを経験し、その心地よさを求め、結果的にオリンピックと言う舞台での勝利の心地よさを求めて行った。 その舞台で勝利した時の言葉こそ有名な、「超、気持ちいい。」である。次の北京オリンピックでも、その心地良さを得るために挑むであろう。そして、自分が体感した心地よさを子供達などへの指導を通して伝えることも視野にあると言う。彼から水の中の心地よさを伝えもらった子供達が、その先の心地よさを求めて高まろうとする姿が想像されて頼もしくも微笑ましくもある。※本文は、昨年、8月29日に綴ったものの転載です。参考資料:JAL SKYWARD AUGUST 2006 アスリートインタビュー北島康介 1982年9月22日生 東京都出身 177cm,74kg B型 日本コカ・コーラ 所属 種目:平泳ぎ 2004年8月15日、アテネ五輪男子平泳ぎ100メートルで金メダル獲得。タイムは1分00秒08。インタビューで「チョー気持ちえぇ(超気持ちいい)、鳥肌ものです。」が 同年の新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた。
2007.06.11
-

責任の取り方
責任を取らせる方法には、大きく二つあると考えています。規律に従い、問答無用で厳しく処分することで責任を取らせる方法。そして、戒めはするものの寛大な処置をして更正を促す方法。どちらの方法で責任を取らせることが良いのでしょうか・・・。私の考えはケース・バイ・ケースであると思っています。昨日の稽古でこんなことがありました。以前、試合を控えたレギュラーの子が、不注意からケガをしてしまったと綴りました。私は、無責任さから、この子を厳しく叱りました。合わせて、連帯責任として他の選手も戒めのために叱りました。結果、レギュラーの責任の重さを子供達に理解させることができ、「雨降って地 固まる」結果的に良い出来事であったと思っていました。ところが、ケガをしていた子。そのケガも治りかけていた矢先に、「自分の不注意からケガをした責任を取るので、レギュラーを外して欲しい」とオヤビン先生に言って来たらしいのです。何故、今頃になって、そんなことを言ってきたのか私には判りませんでしたが、呼ばれた私は、その子に言いました。今のおまえにとって、レギュラーを外れることが、本当に責任を取る方法なのか?おまえは、それで責任を取ったと思うかもしれない。しかし、不注意でケガをした、おまえを許し、一緒に戦おうと言ってくれた仲間はどうなる?仲間を裏切ることにはならないのか?本当のおまえの責任の取り方は、レギュラーを外れることではなく、選手として試合に出て、誰よりもチームの勝利のために頑張ることじゃないのか?その後、オヤビン先生に任せて、その場を退きました。その子には、私の想いが届いたと思いました。あとは、ご両親に、その想いが届くかです。届くと信じたいと思います。なかなか、以心伝心とは行きません・・・。
2007.06.10
-

夢を授ける責任
志 錬スポーツは、子供達の夢の対象でもある。昨年のサッカーワールドカップ。プロの高い技術と志気にファンは興奮し歓喜を上げた。世界的なスポーツの祭典としてオリンピックにも劣らないものだったのだと思う。しかし、MVPにまで選出されたフランスのジダン選手。よりによって決勝戦で相手チームの選手に対する頭突行為で反則退場になった。この行為、サッカーをエンターテイメントとして捉える筋には恰好の話題であろう。当事者間に何があったかだけの興味本位で持ち切りであった。対して、私は言いたい。サッカーと言う競技はその様なレベルであるものなのかと。これでは、試合ではなく、興業である。頭突をして退場した選手でも、侮辱的な言葉を吐いたとされる相手選手でもない。その様な「行為」あるいは、行為を「誘発させる行為」が、夢見る世界中の子供達の面前で行われてしまうサッカーと言う競技に失望した。柔道においても、国際化の流れからか、国内においても変則柔道が眼に着く様になった。果たして、この選手達を柔道界は、どの様な眼で見るのであろうか。子供達は、夢の対象である、この選手達を、どの様な眼で見るのであろうか。サッカーにしても、柔道にしても、その他の競技にしても。子供達の夢を打ち砕く行為。あるいは、子供達に悪影響をもたらす行為は、夢の対象である以上、起こり得ない競技になって欲しいと願う。《謝罪》サッカーファンの方々にとって、遺憾に思われる発言かと思いますが、決してサッカーを否定する意味でなく、好意的だからこその発言であると、ご理解いただけると幸いです。
2007.06.09
-

伸びしろ
志 錬いつ完成させるか…。人は、得てして、直ぐに完成(完璧)品を求めたがる。本当に大切なのは、いつの時点で完成させるかだと考える。いつの時点とは、内部環境と外部環境に左右されるのではないだろうか。自分自身の心技体がバランス良くピークを迎えられる年代を、最も価値ある時代に合わせに自分自身の柔道を完成域に持って行く取り組みをすべきである。少年柔道において、同じ強いでも魅力に違いがある場合がある。軸になる得意技は勿論のこと、足技、後の先の技、寝技、組手までもが大人顔負けの柔道をする子。対して、技と言えば、内股と大内刈だけで、返し技もなければ、奇襲技もしない、組手もどちらかと言えば上手くない。それでも、強い子。どちらの子に魅力を感じるかである。小学生の今の完成を求めるか、将来に求めるかの価値観の違いであるが、伸びしろを残した範疇での強さこそ、少年柔道の魅力であると私は思う。雑で我武者羅な柔道をするが、磨けば光る可能性を持った子達が私の周りには沢山いる。
2007.06.08
-

中国語 講座?
って言っても真面目なやつじゃありません。な~んて読むか第一問 可口可楽答えは、 でした。次は、応用問題です。第二問 百事可楽はい、正解は、 でした。じゃあ、次は、お店シリーズです。第三問 肯徳基ほら、ほら、クリスマスには欠かせない…そうです。 です。じゃあ、次ね第四問 麦当労はい わかるかな でした。コカコーラ、ペプシコーラ、ケンタッキー、マクドナルド。こうして見ると、結構、おもしろいよね中国では、日本にはない漢字が使われている場合があるので間違っているかもしれませんが許して下さい。明日、日本に帰ります。
2007.06.07
-

中国 「食」 レポート
仕事で、昨日から中国の青島に出張に来ています。アオシマと書いて、チンタオと読みます。有名なのは、ビールかな~明るい緑色の瓶で見た目が良く、味も美味しくて、ビール好きの私は、飲み過ぎてしまいました。中国の食には、圧倒されてしまいます。現地では、生きた食材を選んで調理してもらうのが一般的らしいです。で、その食材達の風景です。 左上:スッポン 右上:巨大貝 左下:牛カエル 右下:ワニこの手の食材は、現地の人達だってあまり食べないらしいですが・・・とは言え、ん~、私には本場の中国料理は合いません。よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.06
-

心の糸
志 錬この時期は、全国大会出場を賭けた地区大会が多く開催される。 学生時代は、与えられるチャンスが極限られている。来年が何度も巡ってくることではない。その中でも、私から見て特に想いが強いのが高校の3年間。中学が高校に向けての育成期間。大学が高校の成果を受けての成熟期間と観れば、高校はその端境期間。それは、中学で成果をより高める期間でもあれば、中学で成し得ることが出来なかった目標に挑む期間でもある。また、この期間を終えた時の進路選択は、人生の中でも大きな岐路であるとも思える。その選択結果次第では、柔道との縁が切れてしまう者も少なくない。 理屈が判っていても、この期間の結果は、良くも悪くも後の人生設計に大きな影響を及ぼす位に、重要な位置付けになる3年間だと感じている。 ここ数週間で、勝利した者、敗れた者の結果や心境報告が届く。勝利者に対しては、祝福し、素直に喜びを分かち合える。しかし、敗れた者、特にそれが決勝であった者の場合は、心中を察すると言葉では表しようがない。たった一戦の結果が天地の差とも言える現実を与えるのである。 その一戦に、そこまで辿り着くための汗と、それを支えて来た人達の想いが込められているのである。単純な言葉で声など掛けられない・・・。 しかし、また、勝者は一人でしかない現実もある。必ず、一人の勝者と多くの敗者がいる。多くの破れた者達には、一度、切れた心の糸を張り直して、次なる道を歩んで欲しい。口で言うくらいに簡単ではないことは、私自身も充分に理解できるつもりである。しかし、張り直すと言う作業こそが、心を強くする重要な要素なのではないだろうか。 筋繊維も切れて再生するからこそ、太く強靭になる。自分を強くするための試練なのだと受け入れ、次に向かって歩み始めて欲しいと願って止まない。---------------------------------------------------------------------------本文は、実は昨年の7月に綴ったものである。優勝候補として挑んだ、中学最後の県総体で敗れた少年に向けて贈ったメッセージであった。「中学なんて過程であって、高校で頑張れよ!」と言う想いを込めて、、、先日、朗報が舞い込んだ、先の少年が高校1年生で挑んだ県総体-66級。見事、優勝の栄冠を勝ち取り、インターハイへの出場権を獲得したと言う。嬉しくない訳がない。よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.05
-

工夫
健康の三要素と言われているのが、「運動」「栄養」「休養」です。何が大切って、このバランスとも言われています。「運動」をハードに行なう場合には、それ相当の「栄養」と「休養」が求められます。先日の稽古の後で、ある先生がおっしゃいました。「疲れている時には、休むのも勇気。無理に稽古して、ケガでもしたら意味がない。」私もその通りだと思います。疲れている子に、無理にハードな稽古を強要するつもりはありません。しかし、ここにも「工夫」が必要です。稽古を大切だと認識しているならば、稽古の前に疲れるような行為をしないことです。稽古にベストなコンディションで望めるように、「休養」を取っておくべきです。しかし、学校行事などで、どうしても、稽古の前に疲れてしまうこともあります。ここで「疲れているので、稽古を休みます。」では、強くなれません。そう、疲れているなら、疲れているなりの稽古の方法を「工夫」するのです。ケガも同様です。ケガの度合いにもよりますが、道場に来て出来るメニューを「工夫」するのです。先生に相談して、別メニューにしていただくのも手です。また、見学して見取稽古をするのも良いでしょう。稽古の中で、先生が新しい技の指導をしてくれるかもしれません。休んで、道場に来なかったら、その技を全く知らずに終わってしまいます。私は、子供達に「工夫」の大切さを覚えて欲しいのです。柔道は、頭が悪くては強くなれません。ここでの「頭の良さ」とは、学校の勉強ではなくて、「工夫」することなんです。「出来ないこと」を「出来ない」で片付けるのではなく「出来る方法を考える」のです。是非、「工夫」することを意識して下さい。また、道場に来ると言う行為が、チームとしてのコミュニケーション、「チームワーク」を維持できると思っています。
2007.06.04
-

青少年まつり
今日は、市から助成を受けている複数の少年団体が参加しての“青少年まつり”が市内の緑化公園で開催されました。少年クラブとしても参加です。子供達は、午前と午後にステージで投げ込みなどのパフォーマンスを演じてくれました。観客より、「おまえ達だけで盛り上がってどうする」と言うような劇(?)もありました。ある意味、大笑いですまた、投げ込みの演舞では…。こんなに上手かったかと思えるような内股を見せる子なんかもいました。受の子の受身も上手だったよみんな100点満点でした。昨日の稽古の後にオヤビン先生が言ってました。「いつも張り詰めていると、切れちゃうよ。遊ぶ時は思い切り遊べ~。」今日は、みんな、思い切り遊んだようです。さぁ気持ちを切り替えて厳しい稽古が待ってるゾまた、強い日差しの中、多くのご父兄のご協力があって、出店した「フランクフルト」「チョコバナナ」「バルーンアート」は完売でした。収益金は、少年クラブの運営に充てられるとのことです。父兄の皆さん。そして、junko先生、お疲れ様でした。
2007.06.03
-

必勝法 其の四
志 錬 《其の三岡野功先生の八つの必勝法。三つ目である。三、仕掛人になれ勝負は後手にまわったら不利だ。あくまで先手をとることを考えろ。先手をとるためには、最初の一発はまず自分からかけること。それが単なるオドシでも自分より先に仕掛けられてしまうと、気持の立て直しをはかるのが容易でない。先手必勝だ。仕掛人とは、演出家。 同時に主役も自分自身。如何に主役である自分を勝利と言う形に導けるかを演出する。後手後手では、演出など出来ない。 仕掛けること。 先手を取ること。 そこに勝利がある。つづく 其の五》よろしければ、一日一回、クリック(投票)して下さい→
2007.06.02
-

世界一周
私が中学生の時に教わった寝技の打ち込みに「世界一周」と言うものがありました。抑込、逃方、返方、外方、などを変化することで身に付けるものでした。この方法を取り入れられている道場あるかと思います。長男の中学校でも行なっています。でも、「世界一周」って呼び方は、どうなのかな私が教わったのは、かれこれ30年も前のことです。講道館の少年部でも「世界一周」って呼んでいるようです。偶然、同じ呼び方だったのかそれとも、普通に使われている呼び方なのかまぁ、どっちでも良いのですが、興味深いのは、同じ世界一周でも指導者によってパターンが違うことです。GUTS式(教えてくれた先生のをパクリって手を加えたのですが・・・)(取)袈裟固→(受)えびと肩ブリッジで返す→(取)上四方固あるいは、崩上四方固に変化→(受)逆えびで四つんばいに逃げる→(取)帯取返・ネルソンで返し横四方固に変化→(受)えびで足を二重絡みする→(取)受の上半身を極めて絡まれた足を外して縦四方固に変化→(受)えびで逃げる→(取)バランスを取りながら袈裟固へ変化→(取)おまけで後袈裟固に変化今まで、寝技をまともにしていなかった子供達には、難しそうですが、繰り返すことで、出来て当たり前の技術になってくるはずです。そして、これを一通り覚えることで、寝技の基本の、ほとんどを身に付けることが出来ます。不足しているのは、上下の攻防、四つんばいの下からからの攻めでしょうかもちろん、あくまでも基本レベルですので、上級者には、もっとレベルの高い技術も加えて覚えて行って欲しいと思います。
2007.06.01
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- GOLF、ゴルフ、そしてgolf
- いなばオープン@千羽平GC
- (2025-11-15 14:59:11)
-
-
-
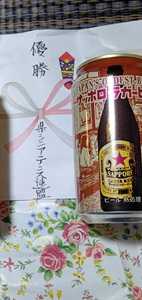
- テニス
- テニスの日々 ~下手の横好きが良い…
- (2025-11-15 00:10:04)
-
-
-

- マラソン&ランニング&ジョギング!
- 神戸マラソン2025(応援)
- (2025-11-17 15:41:22)
-







