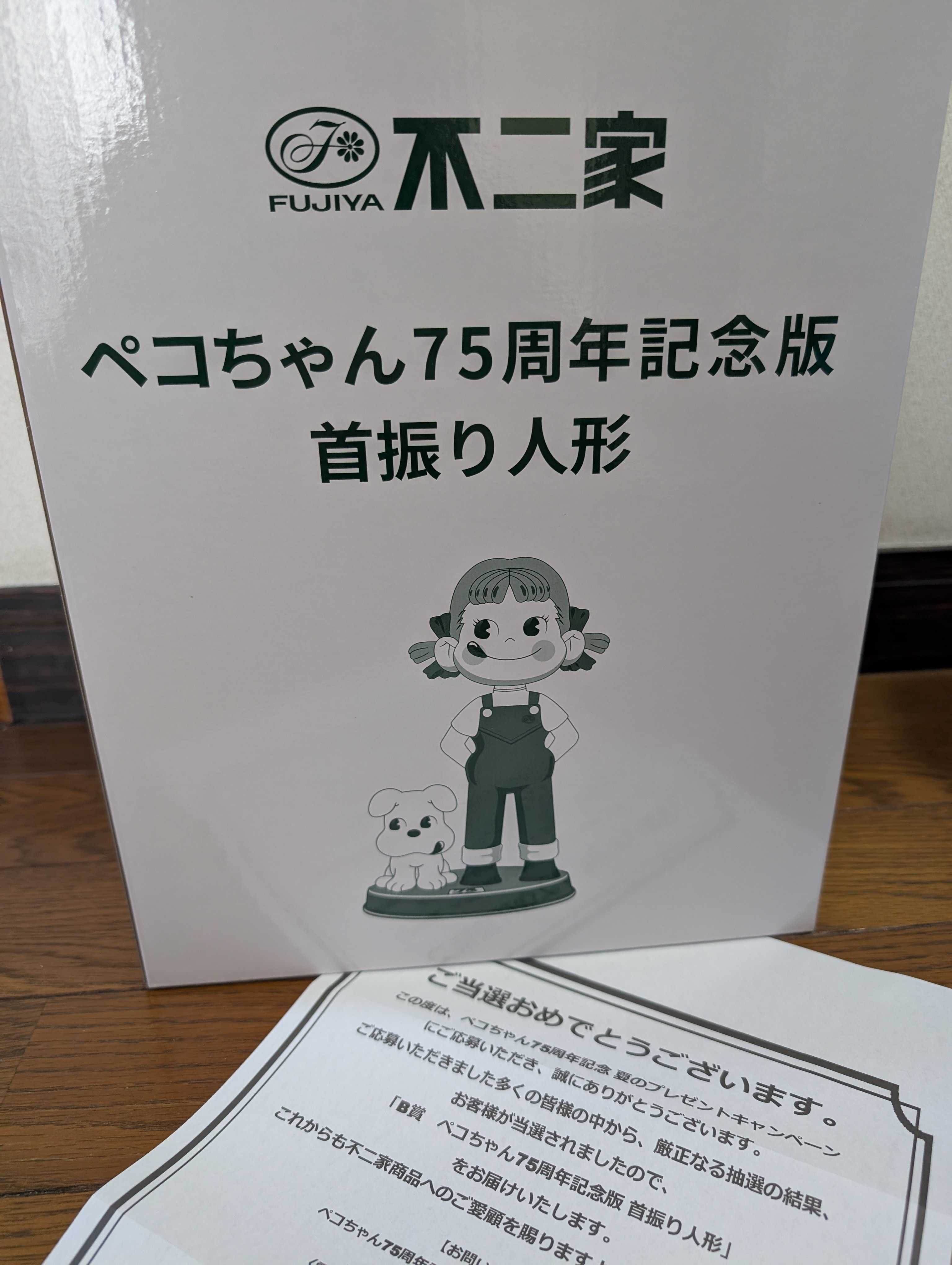2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年07月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
前者の欠点を克服していく法をめぐる論理の流れ
宮台氏は、「連載第二一回:法システムとは何か?(下)」でルーマンが語る法理論について説明をしている。これを前回の流れと関連させて考えてみると、ハートの法理論が不十分であった部分を補ってそれを克服するものとしてルーマンの理論が提出されているように見える。ハートの理論も、それ以前の理論の不十分なところを克服するものとして考えられていた。この一連のつながりを論理の流れとして受け止めると、論理的には非常に興味深いものになる。その登場する順に、基本的発想(法というものの捉え方)と、それから発生する問題点を整理してみようと思う。まず最初のものは1 法実証主義:法は人が置く(pose)ものだとする立場、「法=主権者命令説」。 これは「主権者による、威嚇を背景とした命令」が法だとするもの 法内容の恣意性が克服できない問題がある。 自然法思想:自然法=神法あるいは、人間的本性に基づく自然法という考え。 近代の自然法論は事実上「法=慣習説」。 この説では、近代社会で日々反復される法変更(立法)を基礎づけられない。という二つが挙げられていた。それぞれが法現象の一側面を合理的に説明していたが、それぞれに問題点も指摘されていた。この考え方は、法現象の基礎に何か固定的な前提があって、その前提のもとに現実がある程度合理的に(論理的に)説明されると考えている。法は合理的な全体性(構造)を持っているという見方になるだろうか。これは、どちらも整合的に説明できる部分があるものの、その前提の下では不合理も生じる。足して2で割るわけにはいかないので、この不合理を克服するには新しい発想が必要になる。そこで登場するのが、論理的な全体性が把握できるとする前提そのものを「言語ゲーム」という捉え方で棄ててしまおうとするものだ。把握できるのは現象だけであり、その現象がどのように生れ・変化していくかという事実とメカニズムの関係を記述することに努力する。まとめると次のようになるだろうか。2 ハートの言語ゲーム論的な法定義 法現象を「責務を課す一次ルール」と「それに言及する二次ルール」の結合だとする考え。前者は、社会成員が相互に一定内容の責務を課し合う言語ゲームがあるという事実性に対応する。後者は「責務を課す一次ルール」が孕む問題に一定形式で対処し合う二次的な言語ゲームがあるという事実性に対応する。この二次ルールに基づくゲームは、一次ルールに基づく言語ゲームを外的視点から観察し、伏在していたルールを可視化、問題に対処する。 二次ルールには、相互の責務を最終確認する「承認のルール」、相互の責務を変える「変更のルール」、違背を確定して対処する「裁定のルール」がある。例えば、立法は、立法者や立法手続や内容制限を与える「変更のルール」に従った、二次的なゲーム。この考えは、強者が法を恣意的に解釈できないという事実に対して、そこにルールがあるという事実性で整合的に説明する。法を守らせる行為についても、そこにルールがあるということで理由を説明できる。しかし、なぜルールがあるのかということに関しては説明は出来ない。それが「言語ゲーム」というものであるように思う。ルールがそこに存在しているということがいえるだけだ。変更に関してもルールがそれを説明する。これは、法現象がなぜそのようになっているかというメカニズムの説明には役に立つように思う。しかし、その根拠が示せないのだというのは、論理的にはあまり気持のいいものではない。現実がそうなっているからそうなのだという説明は、論理的にはトートロジー(同語反復)に当たるものだと感じる。トートロジーは確かに正しいのだが、論理的には無内容になる。法の場合は、その起源を論理的に解明することはあきらめなければならない対象だと理解しなければならないのだろうか。現実にはそのような対象が存在していても仕方がないと思われる。論理は万能ではなく限界があるものだからだ。このハートの理論は、それ以前の理論の不備を克服したが、これでもまだ克服されない欠点があるという。それは、宮台氏によれば、「ハートの議論は、単純な社会の法現象と複雑な社会のそれとを関係づける卓抜なものですが、難点がありました。憲法(最高基準)を参照しながら行われる変更のゲーム(立法)が憲法を如何ようにも変え得るという近代実定法的な事態を、うまく記述できないのです。 そこでは究極の承認のルールと変更のルールが円環します。かかる円環がある場合、言語ゲーム論的には単一のゲームと見做されます。ハートはこの円環を線形に引き延ばすので、変更不能な最高基準を持つ高文化の法と、そうではない実定法を区別できないのです。」と説明されている。これの理解はなかなか難しい。法現象の二次ルールでは、紛争処理に再して、紛争当事者がそれぞれの主張の法的な理解を「承認」し、法律に照らしてどのような処理をすることが妥当かという「裁定」を納得することが必要だ。それがあれば、「手打ち」という紛争処理は終了する。このとき、時代が代わり人々の意識が変わってくると、「承認」や「裁定」のときの法律理解が変わってくる可能性がある。そうであれば、法律を「変更」するという手続きも必要になる。だが、この「変更」のルールは、近代社会ではその最高の基準としての「憲法」があり、普通の法律はこの憲法に違反しない範囲で「変更」が行われる。しかし、現在の社会では、この最高法規としての憲法でさえも「変更」の可能性が生じている。そうすると「変更」された憲法によって、また法律が「変更」され、その「変更」に基づいて「承認」や「裁定」が行われるという、行為のループ(円環)が見られるようになる。近代社会では、憲法は最高法規という意識があるのだが、ハートの「言語ゲーム」では、それは「変更」可能なほかの法律と区別がつかなくなる。この区別をつける発想がルーマンのシステム論的な法の理解だというわけだ。「ハートは「単純な/複雑な社会」の二段階で法進化を記述しますが、ルーマン「原初的な法/高文化の法/近代実定法」の三段階」で捉えると宮台氏は書いている。どのような発想が、その捉え方を可能にするのだろうか。ハートの言語ゲーム論としての解釈では、最高法規の憲法も普通の法律も、円環の中で同じ言語ゲームになってしまうのでその違いが記述できなかった。ルーマンは、これにどのような区別を与えるのだろうか。それをうかがわせる宮台氏の言葉は、「ハートは「単純な/複雑な社会」の二段階で法進化を記述しますが、ルーマン「原初的な法/高文化の法/近代実定法」の三段階です」というものだ。ハートでは二段階になってしまうので、複雑な社会の中の区別がつかなくなる。ルーマンは、複雑な社会を二つに分けるのでここに区別が現れるということだろうか。それでは、その区別は具体的にはどのように現れるのか。「高文化の法は、法的決定手続が法適用(裁定)にのみ限定される段階。近代実定法は、それが法形成(立法)にまで拡張される段階」だと宮台氏は語る。近代実定法がもっとも進んだ法の形として提出されている。ハートの理論も、近代実定法が出てくる以前であれば、その区別も必要なく、社会に対して整合的に適用が出来たのではないかと思われる。ルーマンは、近代実定法と高文化の法とをどのように区別するのだろうか。キーワードとなるのは「制度化することの制度」という言葉で、これは法というものを一つの制度と考えたとき、新たな制度を確立するための制度というものが存在していると指摘できるところにある。言語ゲームとしてそこにそのような機能があることしか指摘できないというのではなく、制度としての存在を主張できる。その制度が発生した起源については言えないかも知れないが、制度として存在していることが指摘できる。制度というのは、宮台氏の定義に寄れば、社会成員の誰もが予期として持っていると期待できるルールのことだった。これが言語ゲームのように、自然発生的に社会に存在しているのではなく、新たに制度として認めさせるような手続きが法制度の場合には見られると指摘する。つまり、法はその変更について法によって規定されているという再帰性が見られる。そして、この法によって変更された法は、それが法的手続きを踏んでいるということによって、制度としての正当性を獲得することになる。このように法変更を見ると、法的手続きのどこかに憲法が最高法規であることを記述しておけば、制度としてそれが他の法とは違うということを示すものになるだろう。そうなれば、言語ゲームとしては同じものであっても、「制度化する制度」において両者に違いが出てくるということになるのではないかと思う。これで問題が片付いて、法システムについては終わりかと思うと、宮台氏は「彼の弥縫策的アイディアは、決定手続における「制度化の制度」が、決定の事後に予期を整合的に一般化する(制度を生み出す)とするものです。ですが、法的決定手続を「制度化の制度」と見做す彼の考えは誤りです」と語り、これでもまだ不十分だと指摘する。法律で決められていて、制度として確立するなら、誰もがその予期を持つように「一般化」されるのではないかと僕などは思ってしまうのだが、一体どこが間違っているのだろうか。宮台氏の判断の理由は、「ルーマンは法的決定手続が予期の整合的一般化を改変するとしますが、裁定と立法が規範を示すとの新派刑法理論的発想は、大半の人々が判決や法律を知らないという伝達問題によって、裏切られます」というものだ。制度という規則の面では、その手続きで法変更がされるだろうが、「大半の人々が判決や法律を知らない」のであれば、社会成員の誰もがそう予期をするという、予期そのものが存在しないことになりかねない。それが「裏切られます」という指摘なのだろう。論理の展開はルーマンの段階でも終わらなかった。これを最後の段階までもっていくには「決定の人称性」という概念が必要になるという。この概念がつかめたとき、ようやく法システムの論理展開は終わる。これによって法システムの秩序が保たれるということの整合性がようやく見て取れるようになる。「決定の人称性」という概念をどのように理解すればいいかという具体的な論理展開は、またエントリーを改めてじっくりと考えてみようと思う。今回は論理の流れを見て取ることで満足することにしよう。
2008.07.30
コメント(0)
-
「言語ゲーム」の概念を機能的側面から考えてみる
宮台氏は、「連載第二〇回:法システムとは何か?(上)」の中で「ハートの言語ゲーム論的な法定義」というものを紹介している。「言語ゲーム」という概念は、これまでも何回か考えてみたが、その概念をつかむことが非常に難しい、高度に抽象化された概念である。具体性がほとんど感じられない。イメージとして思い浮かべることの難しい概念だ。たいていの場合は、「言語ゲーム」という概念をまず理解して、その理解の基に、ハートが語った法定義の理解を試みるという順番で思考を展開していく。しかし、「言語ゲーム」の概念が難しいので、これを逆に考えて、ハートがどのような目的を持って「言語ゲーム」を利用しようとしたのかを考えて、ハートが「言語ゲーム」に求めた機能を逆にたどって、そこから「言語ゲーム」なるもののイメージをつかむようにしてみたらどうだろうかということを考えてみた。このような理解の方向があるというのも、一度敷かれた道を後からたどる人間の有利さというものだろう。先駆者であれば、誰も考えたことがない概念を駆使しなければならないので、このような、迷路の出口から逆にたどるというような思考の流れを考えることは出来ないだろうが、後からたどるものにはそのようなことも許されると思う。コロンブスの卵は、最初にそれを発見した人間には天才性が必要とされるが、後からそれを知る人間は、単にその合理性をたどる技術があればいい。その技術を論理というものが与えてくれるのではないかと僕は思う。さて、ハートの目的は、宮台氏に寄れば「「法=主権者命令説」に依拠すると「法内容の恣意性」を克服できず、「法=慣習説」に依拠すると「法変更の可能性」を基礎づけられません。「成員一般が受容するだろう」との期待される「手打ち」を、威嚇が慣習かのいずれかだけではもたらせません」という問題の解決だった。「法=主権者命令説」も「法=慣習説」も、どちらも不十分な定義として、そこから解決の出来ない問題が論理的に導かれてしまう。両者の不十分さを補って、この問題を解決する論理として「言語ゲーム」が利用されていると思われる。宮台氏も、「「法=主権者命令説」と「法=慣習論」の難点を双方取り除くことを目指した法理論をH・L・A・ハートが『法の概念』(1962年)で提唱します。ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論を下敷きにした理論は画期的で、社会システム理論にも影響を与えました」と語っている。「言語ゲーム」という発想が、どのようにして難点を取り除いているかが発見できれば、そこから「言語ゲーム」の概念をつかむということも出来るのではないだろうか。「ハートは法現象を「責務を課す一次ルール」と「それに言及する二次ルール」の結合だと」まず考えたようだ。一次ルールに関しては「社会成員が相互に一定内容の責務を課し合う言語ゲームがあるという事実性に対応します。ゲームの内的視点(当事者の目)には一次ルールは見えていません」と語られている。責任というのは、行為の意味をたどることによって、その行為を選択したシステムにそれが帰属していくものだと考えていた。その行為を選択したシステムが個人としての人格システムであれば、その責任は個人に帰し、それが組織などであればその組織のシステムが責任を負う。その行為の選択というコミュニケーション(選択接続の束)が、一定のルールに従って判断されるとき、そのシステムは安定した秩序を持つだろう。このルールを1次ルールと呼ぶのだろうか。「ゲームの内的視点(当事者の目)には一次ルールは見えていません」ということの意味が今ひとつつかめないのを感じている。当事者には、その責任が自分にあると言われたときに、そのルールに納得して責任を引き受けるということが出来ないのを指して、「ルールは見えていません」と言っているのだろうか。ここで考えているのは、紛争が発生したときの法的処理であるから、当事者が納得して自分の責任を引き受けてしまえば、その紛争は終わってしまう。何らかの法的な処理が必要だということは、当事者はその責任がどこに帰するべきかというルールが見えていないということを前提にしてもいいということになるのだろうか。二次ルールに関しては、「「責務を課す一次ルール」が孕む問題に一定形式で対処し合う二次的な言語ゲームがあるという事実性に対応します」と宮台氏は説明している。紛争が起きたときに、互いに責任を相手に課すという行為について、どのようなときにそれができるかというルールがあるという指摘と理解していいのだろうか。これには「相互の責務を最終確認する「承認のルール」、相互の責務を変える「変更のルール」、違背を確定して対処する「裁定のルール」」という3つがあるようだ。それぞれのルールには次のような説明がつけられている。承認のルール「会社設立のために登記関連の法律を調べるなどの場合のみならず、判決理由で法の在処に言及する場合も、議会で修正すべき法に言及する場合も、用いられます。その意味で立法や裁判の営みは、その「内部」で「承認のルール」を前提とします。」変更のルール「立法や裁判のゲームを支配する「変更/裁定のルール」自体の妥当性も、その「外部」に存在する、最終的に何か(憲法や皇帝の言葉など主権者の命令)を参照してルールを確認するというゲーム(を支配する「承認のルール」)によって、与えられています。」裁定のルール「裁判は、裁定者や裁定手続や内容制限を与える「裁定のルール」に従った、二次的なゲームです。立法や裁判を含めて、現行、何が互いの責務や権能なのかを我々が確認する場合、公文書や謄本(法テクスト)を参照します。これは「承認のルール」に基づくゲームです。」さて、このような発想で紛争処理の機能としての「法」の現象を分析すると、「法内容の恣意性」と「法変更の可能性」の両者がうまく説明できるだろうか。宮台氏は、「ハート理論は伝統的法理論の難点を克服しています」と語っているだけで、どのように克服しているかは説明していない。だからこれは自分で考えなければならないのだが、なかなか難しい。「法変更の可能性」は、二次ルールにおける「変更のルール」の中に見られるものだろうか。もし現実の社会の中に「変更のルール」なるものが存在していて、その事実性が見つかるなら、確かに「法変更の可能性」があると言っていいいだろう。しかし、このルールはどうしてあるのかということは皆目見当もつかない。現実にそれがあるからあるのだとしか言えないような気がする。これはご都合主義的な論理展開ではないのだろうか。この「法変更の可能性」を、権力者がそれを行う権利を持っていると考えると、権力者の意志で法が変更されるということを論理的に演繹することが出来る。そうするとこの面での論理はすっきりするのだが、今度は逆にその恣意性を克服できないという別の側面の問題が出てきてしまう。だから、恣意性を押さえるためには、人間の自然性というものが恣意性を制御するのだと解釈すると、今度はその自然性が法を変更するということの論理が展開できなくなる。これは、結局のところ、何らかの起源があって法が生まれたという発想をすると、そこに固定的な前提を置くことによって、論理的にはそこから演繹される方向が固定されてしまうということになるのではないだろうか。現実の法的な現象は、いくらでも予想外の展開が生れる可能性があり、その多様性をすべて生じさせるようなブラックボックスを設定するのは難しい。だから、法の根拠には、何らかの固定的な起源を設定してはいけないという発想も考えられるのではないだろうか。法は、固定的な期限によって発生するのではなく、現実に法現象が展開されているという事実性から、人々がルールを学び、そのルールが現実に合わされて解釈され変更されていくという現れが見えるだけの対象なのではないかとも考えられる。恣意性が制限されるのも、変更の可能性が見られるのも、現実にそのようなことが行われルールとして人々が承認しあうからこそそうなっているという解釈も出来るのではないだろうか。これは一見ご都合主義的な解釈に過ぎないように見える。しかし、ある種の社会現象には起源はなくて、単に現象が見られるだけだという発想は、ご都合主義的に現実をそのまま受け取ったのではなく、いったんは形式論理的な前提を置いては見たものの、そのような機械的な解釈では解釈しきれなくなって否定された後に、このような発想にたどり着いているとも考えられる。否定なしにご都合主義的に解釈したものと、否定を経て現実を再度違う視点で受け止めたこととの違いがここにあるのではないだろうか。弁証法でいうような「否定の否定」がここにはあるのではないかという気がする。法現象に対して、このような解釈を可能にする道具として「言語ゲーム」というものがあるのではないだろうか。「言語ゲーム」とは、ある種のルールの下になされている秩序ある人間の行動に対して、そのルールがなぜあるのかという起源は問わないで、今ある現象からルールを読み取ることで、その秩序が維持されていることを理解しようとしているのではないだろうか。「言語ゲーム」の中にいる人間の大部分は、そのルールがどのようなものであるかを知らない。ほとんどはそれは自明なものとして受け止められているのではないだろうか。そのルールは、その現象を「言語ゲーム」という捉え方をする人間にしか見えてこないのではないだろうか。このようなイメージで考えると、「言語ゲーム」というのは、あくまでも現実に存在する我々の世界について語っているのだという気がする。もしその世界が、ある種の前提を公理的に設定して、その世界の秩序を人為的に設計して構造化できるのであれば、そこには「言語ゲーム」は見られないのではないだろうか。そこに見られるのは、数学的な論理によって証明される定理が見出されるだけで、それは構造から必然的に導かれるものになる。意外なもの・予想外のものは一つもない。何があるかを知るには、正しい論理によって思考を展開すればいいだけだ。人間が現実に生きている世界は、特に言語によって成立している社会現象については、このような数学的モデルが通用しない、今ある秩序を発見することしか出来ない現象があるのかもしれない。そのようなものをウィトゲンシュタインは「言語ゲーム」という言葉で示したのではないだろうか。もし「言語ゲーム」という言葉で呼ばれるものがそういうものであれば、それはまったく説明に困るものになるだろう。論理的に説明できる対象であれば、それは何らかの前提を置いて、そこから導かれる形で合理性を納得できるように思うからだ。「言語ゲーム」そのものは言葉で語るには困るものだ。言葉で語ることが出来るのは、そこに見出すことが出来たルールのほうだけではないだろうか。
2008.07.28
コメント(0)
-
「法」の本質を求めることに有意義な意味はあるのか?
「連載第二〇回:法システムとは何か?(上)」で宮台氏は、「法」を「紛争処理の機能を果たす装置の総体」と定義している。これは、システムというもので社会を捉える発想からはごく当然の定義だと、今ではそのように僕は感じる。システムというのは、その機能に注目して設定するものだ。だから「法」をシステムとして捉えるのであれば、当然のことながら機能面を最重要なものとして定義し概念化することは必然でさえあると思っている。しかし以前の僕なら、三浦つとむさんが批判していた「機能主義」という言葉が気になって、機能を基礎的な概念として設定するのは、「機能主義」という間違いに陥っていないだろうかということが気になっていた。機能というものが、その対象の本質を果たして表現しているものになるかということが気になっていた。それは何か唯物論的な発想というものが、存在という「実体」を基本的なものとして考えていて、機能はあくまでもその「実体」の作用という働きを示すものであるから、本質は「実体」のほうにこそあるという先入観があったからだと思う。それが唯物論的な見方だと思っていたのだ。しかし宮台氏のシステム論の発想を知って、それをよく考えてみると、対象の「本質」を求めるという発想そのものが、実はあまり実りのないものではないかという感じもしてきた。実体にこそ本質があるとする見方は、実はその本質を固定的に捉える発想になるのではないかと思う。ある対象を把握すれば、その対象の本質だと思えたものは、それを実体的に捉える限りでは、その実体が他のものに変化しない限り本質も変わらないものになる。だが、本質というのは果たしてそのような固定的・不変なものであろうか。むしろ、本質というのは、その対象をどこから見るかという視点によって変わってくるのではないかという気がしてきた。三浦さんは、言語の本質を「表現」という性質に見ていた。「表現」という性質を失えば、それはもう言語は呼べないものになる。だから、頭の中にだけ存在するような「内言語」なるものは、三浦さんの言語論から言えば、言語の本質を失った言語ではないものとして判断される。これは論理的には極めてクリアーな分かりやすい考え方だ。どこにも間違ったところはない。そして、言語は表現であるからこそ、その機能の最重要な部分は、他者とのコミュニケーションにあり、コミュニケーションの本質はその過程的構造にあるのだから、三浦さんの言語論が「言語過程説」になるのは、論理的な必然性を持っているとさえ言える。三浦さんが言語の本質を表現に見ることから、その言語論も言語過程説というものになる。これは、逆に考えれば、言語過程説が正しいという受け止め方が、言語の本質を「表現」にあると判断させたとも言える。なぜなら、言語の本質を「表現」に見るのでなければ、必ずしもその過程的構造が重要にならないことが論理の展開として出てくるからだ。ソシュールの言語論は、言語の本質を、人間が持っている言語の社会性というものに見ている。個々のコミュニケーションが言語の本質ではなく、あくまでも社会的存在というものにその本質を見ている。そうであれば、その本質を持った対象としては、ソシュールがラングと呼び、三浦さんが言語規範と呼んでいる、社会的な存在こそがそれであるということになるだろう。三浦さんとソシュールでは、言語に対する視点が違うので、その本質の捉え方が違ってきている。これは、どちらが正しくて、どちらが間違っているという種類のものではなく、単に言語を見る視点が違うのであり、したがってそれを論理的に展開するアプローチが違っているだけなのだと今は思える。言語は複雑で多用な性質を持っている対象なので、その視点の違いによって何が言語の本質であるかという捉え方が違ってくる。宮台氏のこの回の講座でも、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」という捉え方が紹介されていて、そこでは、人間的なある種のルールが暗黙のうちに共有されていて、コミュニケーションによって互いに学びあって社会性を持続するという性質こそが言語の本質と捉えられていて、そのような現象をすべて「言語ゲーム」と呼んでいるように思う。「法」というのも、言語に劣らず複雑で多様な面を持っている。だから、その本質を捉えようと思ったら、自分がどのような位置でそれを見ているかという自分の立ち位置を意識することが重要だ。宮台氏の位置はシステム論であり、その位置から見る見方は、機能こそが本質になる。機能こそがシステム論では最重要なものだからだ。三浦さんが批判していた「機能主義」というものは、どのような対象を見ても、「機能こそが本質だ」という発想でその対象を捉えていたものだった。いつでも同じ発想で対象を見るので「主義」と呼ばれていたように思う。この「主義」こそが批判されるべきであって、機能を本質と見る見方は間違ってはいなかったのだ。それは、ある視点からは正しい見方であり、他の視点からは間違った見方になるというだけに過ぎない。どんな見方でも、その対象を深く分析することなく、いつでも同じ見方で機能を本質にするからそれは批判されなければならないのだ。この「主義(イズム)」がくっつく見方は、マルクシズムにしてもフェミニズムにしても、いつでも同じ視点で対象を見るという点では、批判されるべき「機能主義」と同じものになるだろう。それは、階級という視点で見ることが批判されるのではなく、いつでも階級を引っ張り出して解釈するところが批判されなければならない。対象によっては、階級という視点では分析できないものもあるのだと思う。フェミニズムにしてもそうだろう。常に男の持つ差別性という視点でのみ対象を捉えれば、そうでない捉え方をしなければならない対象に対してはそれは間違えるだろう。常に同じ見方ではなく、対象にふさわしい見方を探さなければならない。これは三浦さんが語る弁証法的な視点になる。ある対象、たとえば「法」に対して、無前提に「その本質は何か?」という問いを立てれば、それはいつでも同じ見方をしているという「主義」の間違いになるのではないかと思う。無前提に本質を求めるのでなく、「自分が解明したいと思っている視点で、もっとも重要になる対象の性質は何か?」という発想で対象を考えたときに、それにふさわしい本質が見えてくるのではないかと思う。そのような意味で宮台氏の提出する「紛争処理の機能を果たす装置の総体」という「法」の定義は、システム論においては最適なものであり、正しい意味での本質を語ったものになるだろう。この機能的本質を持った「法」は、その視点で現実のあり方を眺めてみると、次のような点が見えてくる。「紛争処理とは何か。紛争の抑止ではありません。紛争を公的に承認可能な仕方で収めることです。公的に承認可能な仕方とは、「社会成員一般が受容するだろう」と期待できるような仕方です。 「収める」とは何か。紛争当事者のどちらかが死滅するまで戦うことを以て「収める」こととし、その結果を「公的に承認」することもあり得ます。ただ、今日まで生き延びた社会はどこも、そこまでせずに、「手打ち」することを以て「収める」こととしています。」「法」の本質(つまり概念)を、実体的なものとしてイメージしていると、それは「紛争の抑止」であったり「正義の実現」であったりするものとして思い浮かべているのではないだろうか。そのようなイメージを持っている人は、上の宮台氏の説明には驚くのではないだろうか。「法」は、何が真理であるかを確定し、その真理を基に正義を実現するのではなく、社会成員の多数が納得する結論を提出することが本質的な機能となる。この微妙なニュアンスを宮台氏は「手打ち」と表現している。「手打ち」というのは、何が正しいかは確定はしていないが、表向きはこのようにしてお互いに納得しようという線で了解するものになる。正義感の強い人には、なかなか納得できないかもしれない。しかし、そのような機能があれば、「紛争当事者のどちらかが死滅するまで戦う」ことが避けられ、社会は一応の安定と秩序を保つことが出来るのではないかと思う。システム理論的には、そのような分析の方向がその視点によくかなうだろう。ただ、この発想には論理的に困難な展開を予想させる問題もある。宮台氏は次のように書いている。「ですが、もしそれだけが重要なら「始めから戦わない」選択こそが賢明です。当然「それだと強い者のやりたい放題になるだろう」との反問が予想されます。そう。「やりたい放題は許さない」との意思を社会成員一般が持つことを、我々は常に当てにしています。 「やりたい放題は許さない」という意思を社会成員一般が抱くと期待されている中で、紛争に際して「成員一般が受容するだろう」と期待できるような仕方で「手打ち」をし、それによって、紛争蔓延や復讐連鎖や相互殲滅を回避すること。これぞ、法の機能です。」「手打ち」というやり方は、強いものに圧倒的に有利なやり方になってしまう。そうすると、秩序を保ちたいと思っている多数の意図に反して、強いものがやりたい放題をするという無秩序が実現してしまうということが論理的に導かれてしまう。それがどうしてそうならないかというメカニズムを、システム論は解明しなければならない。小数の強いもののやりたい放題という意志を押さえて、多数の社会の構成員の意志が貫徹するように、社会の秩序を保つメカニズムは、法システムのどのような構造の中に実現されているのか。これを考えるには、「法実証主義」の立場と、「自然法論」の立場と二つのものがあるようだ。「法実証主義」では、誰よりも強いものとしての「国家権力」が、圧倒的に強い力で、多数の個人の中に突出した強い力の出現を防ぐことでこの秩序を確立していると考える。「自然法論」では、人間の自然な性質からこの秩序を説明しようとしている。どちらも、現実に当てはまる部分と当てはまらない部分が出てきてしまう。合法的な独裁者が出てきてしまえば、「法実証主義」の立場ではそのやりたい放題を阻止できない。また、人間的な自然性だけでは、法が変わることの理由を自然性の変化に求めなければならないが、それは「自然性」という概念に反するような気もする。この一長一短の考え方に対して、両者の欠点を埋め合わせる見方として、宮台氏はH・L・A・ハートが『法の概念』(1962年)で提唱した「ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論を下敷きにした理論」を紹介する。これは、「言語ゲーム」という概念そのものがとても難しいので、なかなか分かりにくい。じっくり考えたいものだが、すでにここまででかなりの長文になってしまったので、これは、改めて「言語ゲーム」の概念の考察とともに、宮台氏がここで語っている内容を次のエントリーで考えてみようと思う。
2008.07.27
コメント(0)
-
宗教システムの具体的現れと社会の中での位置付け
「連載第一九回:宗教システムとは何か(下)」で宮台氏は、「〈世界〉内の事象は基本的に偶発的ですが、大抵は事後的な前提挿入により馴致可能です」と語っている。これは、偶発性がある種の合理的解釈で片付けられるなら、それによって不安がもたらされることなく、それはやり過ごせるものになることを教える。「「病気に罹ったのは不摂生だったからだ」というとき、「自分だけ病気に罹る」という偶発性は「不摂生だった」という前提が持ち込まれることで、受容可能に加工されます」というわけだ。すべての偶発性がこのように解釈で切り抜けられるなら、その個人には不安もパニックもないだろう。しかし、「偶然の出会い・不慮の死等は、そうした前提挿入を以てしては納得不能な、前提を欠いたものとして現れ得ます。「個別の出来事」のみならず、なぜ「その」法則、「その」道徳が存するか、という具合に「一般的枠組」も前提を欠いたものとして現れ得ます」と宮台氏が語るように、すべてをやり過ごすことは、複雑化した現代社会では難しい。この、不安とパニックを起こしそうな偶発性に対して、それを無害化し受け入れ可能にする機能として宗教が存在する。「前提を欠いた偶発性は、期待外れの衝撃を吸収困難にし、意味あるものに意味がないという形で〈世界〉解釈を不安定」にする。これを無害化するシステムがあれば、社会はその働きによって安定し秩序を保つことが出来るだろう。これが宗教というものの、社会システムに対する基本的な存在の理由になる。システムとしてその存在を捉えるなら、このような機能を持つ装置として考えることがもっともふさわしい。この回の講座では、宮台氏は「前提を欠いた偶発性の現れ方は、社会システムのあり方に応じて変化します。また、受容可能なものへと馴致するメカニズムにも複数の選択肢があります。前提を欠いた偶発性の「現れ方」と「馴致メカニズム」の組み合わせが、宗教のバリエーションを構成します」と語り、宗教の実際の現れ方を、その機能面の分析から捉えようとしている。「原初的宗教では、前提を欠いた偶発性が共同体にとっての個別の出来事として問題に」なるという。原初的宗教の段階では、日常的な経験を破る突発的な出来事が、合理的解釈で処理しきれない偶発性になるだろう。たとえば、「天災・疾病・飢饉・狂気など」を「日常の慣れ親しみ(自明性)を破る出来事」として宮台氏は挙げている。これは原初的宗教では「聖俗二元図式を用いた一連の共同行為(儀式)による聖なる時間・空間への隔離(聖化)」による「儀式化の段階」が無害化の機能の現われとなる。それは宗教的に聖なるものであるから、我々に知ることが出来ない偶発性があっても仕方がないものとして受け入れられる。これは、よく考えると論理的には逆ではないかと思うが、気持を納得させるためにはむしろ逆の発想のほうがうまく行くだろう。つまり、偶発性があって、しかもその合理的な理由がつけられないからこそ、それを聖なるものとしてしまうことによって、合理的理由がないことをやり過ごせる。だが、これは理屈でそう受け止められるだけであって、実際に偶発性にパニックになっている人間は、このような理屈を考え出すことが出来ない。そのような人間は、むしろそれが「聖なるもの」であるということを前提なしに受け入れて、「聖なるものであるがゆえにそれは、非日常であっても仕方がないのだ」という受け止め方をした方が、それを受け入れやすいのではないかと思う。論理的には逆だと思うが、現象としては、それが「聖なるもの」であるという観念のほうが先行しているというふうに見えるのではないだろうか。だが、最初人々に受け入れやすいと思われていたこの前提が、やがて前提そのものに考察が及ぶ再帰性を帯びてくると、この前提そのものの偶発性が今度は気になってくる。「他でもあり得るのに、なぜ「その」図式なのか」ということに今度は合理的な説明をしなければならない。そのために持ち出される図式は「神によって秘蹟化された戒律」という了解形式として提出される「戒律化の段階」といわれるものだ。これが我々が普通にイメージしているキリスト教などの宗教になるのだろう。この段階の次に現れるのは、宮台氏に寄れば次のように説明されている。「中世的宗教になると、階層分化により社会が複雑化し、処理枠組が、共同体より個人のものとして意識され始めます。社会内に異なる信仰を持つ者が増え、戒律を秘蹟化する唯一神も、個人の主観に対応するものだと理解され始めます。これが「信仰化の段階」です。」みんなが同じように感じ・考えていた時代から、それぞれの個人に違いが生れ個性的になり、心というものがあると信じられるようになると、このように宗教にも個人的な意味が与えられるようになるのではないだろうか。宗教システムが共同体の機能であった時代は、社会システムとの分化はあまり進んでいないように見える。宗教システムが、このように個人のものとして機能する段階にまで至ったとき、それは高度に分化した近代の下位システムとして捉えられるのではないだろうか。「全体社会が宗教システムと無関連に作動するようになること」を宮台氏は「脱呪術化」と呼んでいる。宗教システムが個人のシステムになっていけば、それは全体社会との関連を失っていくのではないかと思う。さて、このように分化した宗教の姿を現代日本での宗教のあり方と重ね合わせてみると、「個別的問題設定」と「縮約的問題設定」と捉えられる二つに分岐するという。「前者は「世俗的=利益祈願型」、後者は「非世俗的=意味追求型」」だと宮台氏は語る。個別的問題というのは、特殊に個人的に関わってくるもので、「なぜ自分がそのような偶発性に会うのか」ということで問題化される。宮台氏が挙げる例は、「病気になった際「不摂生だった」という現実的関係を前提挿入できないと前提欠如が露呈します。この時「水子の祟り」等の超現実的関係を代替的に挿入するのが個別的問題設定です」と語られるものだ。これは、「現実/超現実の混同ゆえに「浮遊系」宗教」と呼んでいる。「これに対して、縮約的問題設定とは、自己と〈世界〉との関係一般に予め言及しておくことで、個別の出来事による期待外れに備えて、事前の免疫化を行うものです」と説明されている。これが縮約的と呼ばれているのは、後の説明で出てくるが、世界を縮めたり、自己を縮めたりして、世界の解釈を工夫して偶発性を処理しようとしているからだろうと思う。この縮約的問題を処理する宗教は、まずは自己を縮め、世界に対してほとんど無力なものとして解釈してしまうものだ。宮台氏は次のように書いている。「第一は「〈世界〉における包括」。〈世界〉の側を拡張することで自己と〈世界〉の関係を規定可能化するものです。〈世界〉は決められていて自己には極小の自由しかないとする把握です。教義学的には黙示録的で、覚悟を要求するので「覚悟系」宗教と呼べます。」自己の縮約は世界にとっては拡張となる。逆に自己を拡大していくと、相対的に世界は縮まっていく。次の宗教は世界の縮約として解釈される。「第二は「自己における包括」。これは自己の側を拡張して自己と〈世界〉の関係を規定可能化します。何かが辛いのは、辛い出来事があるよりも、辛いと感じる境地があるだけとする把握です。教義学的には仏教的で、境地の操縦を目指す「修養系」宗教になります。」この発想では、自己がほとんど世界と重なるくらいに拡大されている。逆に言えば、世界は自己と重なるくらいに縮められている。世界は、自己のコントロールでどうにでも出来る存在になってしまうのが、「修養系」と呼ばれる宗教ではないだろうか。「浮遊/覚悟/修養系」という3つの宗教の類型は、個性によってどれを選択するかが決まってくるようにも感じる。現世利益的なものを求め、現実に遭遇した偶発性をやり過ごせれば、気分は幸せになれる、ということを好むならば「浮遊系」の宗教を選びたくなるのではないだろうか。これを宮台氏は、「「幸せになりたい!」に応える「行為系宗教」」とも指摘していた。その意味は、このように考えられるのではないだろうか。「覚悟系」の宗教では、最終的に、「世界はそうなっている」というあきらめの気持がなければならないような気がする。黙示録的な宗教では、世界の終わりが語られていて、それは避けられないものとして覚悟を求めている。これは、そのような覚悟が納得した後に生れるのか、それとも黙示録を信じるということから生れるのか。それを信じたことのない自分には実感としては分からない。「修養系」の宗教の前提となっているのは、自分の世界という個別的なものこそが本当の意味での世界なのだという、独我論的な考えがあるのではないかと感じる。自分の世界こそが世界なら、それを自分がコントロールできてもいいはずだ。世界の存在はすべて自分の精神の反映だと思えば、精神を鍛えて修養することこそが偶発性の無害化ということになるのだろう。この宗教の現れは、人間に対して「超越」と「内在」という二つの重要な概念も生んでいる。「超越」というのは現実の世界を「超えている」ことで、「内在」とは現実の世界の「中にある」ことを意味する。このうち、「超越」というのは論理的には矛盾を帰結する厄介な概念となる。宮台氏は、「なぜ世界があるのか」という世界の存在に対する問いを例に挙げているが、この問いの答えが世界の中に見つかると考えると、それは世界を外から眺めていることにならないから、この答えは世界の外になければならない。すなわち答えは「超越」的だ。しかし、世界とはありとあらゆるものを指す。少なくとも人間が知ることが出来るのは、世界において遭遇するものだけで、世界の外にあるものは知ることが出来ない。したがって、「超越」は想像をすることは出来るが、決して見ることの出来ないものになる。概念はあるのに、それが存在するかどうかは決して分からない。このような「超越」の代表的なものは宗教における「神」になる。キリスト教では神の存在証明と言うものが問題にされたが、それは原理的に証明できないものだ。しかも、原理的にそれを否定することも出来ない。このような不条理な存在に対して、証明せずに、まずは信じるという態度を持つことが「信仰」というものになる。宗教を主体的に生きることが出来るかどうかは、この「信仰」がもてるかどうかにかかっている。宮台氏も、「従って近代社会における分化した宗教システムは、「信仰」というメディアが、超越/内在という二項図式を前提としつつ超越へと向けた動機形成と期待形成をなすことを通じてコミュニケーションを触媒することによる、コミュニケーションの閉じだと見做せます。」のように語っている。これがおそらく西欧的なキリスト教という宗教の現実の現れになるのだろう。しかし、「日本では、黙示録的意味論を有する「覚悟系」宗教としてのキリスト教以外に、「浮遊系」や「修養系」宗教が、大きな比重を占めています」と宮台氏は指摘している。このことは何を意味するか。宮台氏は「日本について見る限り、前提を欠いた偶発性を無害なものとして受容可能にする機能的装置としての宗教は、西欧キリスト教文化圏とは違って、「信仰」というコミュニケーションメディアによって閉じた下位システムを構成しているとは、到底言えません」と語っている。日本では、宗教においてもまだ分化が不十分だということだろうか。
2008.07.26
コメント(0)
-
機能(システム)としての「宗教」概念
宮台氏は、「連載第一八回:宗教システムとは何か?(上)」で下位システムの一つである「宗教システム」について書いている。下位システムとは、上位のシステムが、その機能の達成のために機能を分化してその内部に部分として作りあげたシステムになる。この下位システムに対しては、上位のシステムは「環境」となる。下位システムの存在の前提条件を供給するものとなる。この下位システムが「下位」と呼ばれているのは、単に部分として含まれているという関係だけではなく、上位システムの存続のための機能(秩序を保つための機能)を分け持つという「分化」という関係に注目してそのような呼び方をしている。注目するのは機能の分化である。システムというのが、そもそもある機能を達成するための装置と考えられているので、このような思考の展開は、システムの概念から導かれる流れとしては自然なものになるだろう。社会をシステムとして捉えるというのは、社会において秩序が達成されるための機能を持つ装置のメカニズムを解明するという理解のしかたになる。社会の全体性をいきなり捉えるのは難しいので、その一分野を受け持つ下位システムをまず解明しようという方向は、論理的にも理解しやすいものになるのではないかと思う。宮台氏は、「下位」という言い方が、単純に「部分」を意味するのではないということを次のように説明している。「システム存続に必要な諸機能の一部を分掌する下位システムを、単に全体に対する部分や部品と等置してはいけません。私たちが「部分システム」という巷で用いられる名称を使わない理由もそこにあります。部分や部品は必ずしも機能の分掌を意味しないからです。」「下位」という概念にとって重要なのは、「機能の分掌」なのである。これをもう少し分かりやすいイメージで説明すると、人体をシステムとして捉えた場合の、人体の「下位システム」についての例になる。宮台氏は次のように書いている。「ところが、下位システムと呼ぶ場合、単に下方のシステムあるいは部分のシステムではなく、「機能的分掌をなす」下方のシステムを指します。だから人体にとっての下位システムは単独の臓器や細胞ではなく、免疫システム・神経システム・循環器システム等です。」臓器や細胞は、人体にとって大事な部品ではあるが、それが全体の中でどのような機能を受け持っているから人体の秩序(生命を維持すること)が実現されているかということは、部品という実体の観察からはメカニズムが解明されない。人体が死を迎えれば、その部品も死んでしまうということや、部品の調子が悪くなれば人体という全体にも影響を与えるということは分かるが、分かるのはそこに関係があるということまでで、それがどのように働いているかというメカニズムの解明が出来ない。メカニズムを解明するためには、あくまでも機能に注目して、その機能が分化して働いているものが、人体という全体に統一されて、各機能がコントロールされている状態が人体の安定(秩序)というものになると考えられる。だから、機能に注目すれば下位システムは、「異物侵入を無害化する機能」の「免疫システム」、「外的刺激に即時に反応する機能」の「神経システム」、「リソースを運搬する機能」の「循環器システム」などが考えられる。このように考えると、社会の秩序維持のための機能を分化して受け持つ「宗教システム」は、どのような機能を担うのかということが重要になる。宮台氏に寄ればその機能は「前提を欠いた偶発性(=根源的偶発性)を無害なものとして受け入れ可能にする機能(を持つ装置の総体)です」と説明される。この、機能としての側面を捉えた定義が、社会システムを考える上での「宗教」の定義になり概念となる。これは一般的なイメージとはかなりかけ離れているのではないかと思う。一般的なイメージでいう「宗教」とは、個別具体的な現実にある「宗教」から作られるイメージではないだろうか。それはたとえばキリスト教であったり、イスラム教や仏教であったりするだろう。宗教的な信仰を持っている人に向かって、それは「前提を欠いた偶発性(=根源的偶発性)を無害なものとして受け入れ可能にする機能」として信仰しているのですか、などと聞いたら怒り出すだろう。信仰はそのような他人事で語るようなものではないからだ。しかし「宗教」を社会学という「科学」で捉えようと思ったら、それは徹底的に他人事として見なければならないだろう。そうでなければ客観性が損なわれるのではないかと思うからだ。「宗教」を主体的・主観的にしか見られない人は、残念ながらそれを「科学」として考えようと意図することはあきらめたほうがいいだろう。主体的・主観的な見方は、任意の他者が同意するものにはならないからだ。「宗教」というのは、歴史的には「聖なるものや聖なる体験を宗教と呼ぶ」言葉の使い方があったらしい。これは機能というよりも実体に注目した概念であり、その定義になるだろう。したがって、この定義で対象を見ると、「前提を欠いた偶発性(=根源的偶発性)を無害なものとして受け入れ可能にする機能」はないが、見かけが「聖なるもの」「聖なる体験」に見えるものを「宗教」の中に入れてしまうことが起こる。言葉が与える概念が、現実世界の見方を規定してくる。この定義からは、「聖なるものを非日常的体験やトランス状態によって──日常的体験やシラフ状態との差異によって──定義するのが経験に即します。でもそうすると、ドラッグによるトリップや、激烈な地上戦下の変性意識状態が、聖なるものとなり、宗教に算入されてしまいます」と、宮台氏が指摘するように、機能的にシステムに組み込むことの出来ないものが「宗教」の中に入ってしまう。システム論として「宗教」を考える上ではこの定義はふさわしくないといえるだろう。それでは「究極性や最高性を宗教的なものと見做す定義」は、システム論としての定義として使えるだろうか。これは、現存するいくつかの「宗教」には当てはまる気がする定義だ。キリスト教やユダヤ教・イスラム教の神は、その元をたどればすべて同じもので、唯一・究極な存在として捉えられている。しかし、この定義も宗教としてはイメージしにくいものが入り込んでしまう。「ケルゼン流の概念法学で把握された憲法は定義に合致するし、俗に言う「科学万能主義」の世界観も定義に合致しますが、私たちは比喩を超えて憲法や科学を宗教と呼ぶのを躊います」と宮台氏は書いている。機能に注目した定義としては、やはり宮台氏が提出する「前提を欠いた偶発性を無害なものとして受け入れ可能にする機能」というものがシステム論としてはふさわしいのではないかと思える。このような装置が、偶発性が引き起こすかもしれない社会全体に及ぶ不安やパニックを鎮めるために機能するとすれば、宗教という下位システムは、上位システムである社会システムの秩序維持のために、この部分の秩序を受け持つことが出来るだろう。宮台氏のこの説明は、論理的によく分かるのだが、よく分かるだけに困った問題もある。このように宗教を理解してしまうと、もはや宗教を主体的に受け止めて「前提を欠いた偶発性を無害なものとして受け入れ可能にする機能」として利用することが自分には出来なくなっていることを感じるからだ。僕は、もう宗教を信仰という形で感じることが出来ない。こうなると宗教なしに「前提を欠いた偶発性を無害なものとして受け入れ可能にする機能」を考えなければならない。今考えているのは、論理によって偶発性を納得するというものだ。宗教を失った人間は、その方向で不安を静めるしかないのではないかとも感じている。宗教を機能的に捉えるというのは、宗教的な幸福感を味わうことはあきらめなければならなくなるが、論理的にはその便利さがよく分かる。さて、この宗教の概念は、この回の講座で提出されているもう一つの問題にも関わってくる。宮台氏はコミュニケーションメディアというものについて語っているのだが、これがいったん分化した下位システムが、また「融合」して元に戻っていかないようにする機能を担っているという。コミュニケーションというのは、宮台氏の講座では、選択接続の束として定義されていた。メディアというのは、その選択接続を媒介するものとなる。これはなかなかイメージしにくいのだが、人体のシステムが分かりやすいので、宮台氏もこのメディアについての説明で次のように書いている。「空間的局域ならぬ下位システム同士の作動の、組込み合いがあるなら、それらが癒合せずに機能的分化を継続し得る条件が重要です。神経システムが電気信号だけを選択接続のメディアとし、免疫システムが蛋白質の物理的外形だけをメディアとするのがヒントです。」神経システムと免疫システムとして分化した下位システムが、再び融合して両方の機能を同時に実現したりしないのは、その媒介として考えられているメディアが、神経システムの場合は電気信号であり、免疫システムの場合は蛋白質の物理的外形だけだという違いがあるからだ。メディアがまったく違うので、それが媒介するコミュニケーション(選択接続)が、そのシステムでなければ実現されない。だから、その機能分化はもう再び融合することはないということだ。宗教システムのコミュニケーションメディアについては、次回の講座で詳しく説明されるようだが、それぞれの下位システムにおけるコミュニケーションメディアについては、この回では次のようなものが紹介されている。「コミュニケーションメディアは選択接続の閉じを与えます。経済システムは貨幣(所有/不所有)、政治システムは権力(罰回避/罰)、科学システムは真理(真/偽)、宗教システムは信仰(超越/内在)、法システムは法(正義/不正義)が、(所有への、罰回避への、真への、超越への、正義への)動機形成と期待形成を通じて、選択接続を媒介します。」それぞれの下位システムのコミュニケーションメディアはまったく違うものとして考察されている。これが下位システムの分化を安定させているものになっているのだろう。宗教システムが科学的真理を決定する機能までも持っていた時代がかつてはあった。今ではそれはない。これは、上のように機能分化した社会システムのほうが、そうでない社会よりも安定的で、ある種の強大な力を持っているからだと宮台氏は語っている。ということは、分化が未熟な社会は、分化が進んだ社会よりも安定性や強さの面で、問題があると言えるのではないだろうか。これは日本社会を考える上で重要なポイントだと思う。談合などの行為が、システムとしては、政治システムが経済システムに強大な影響を与え、分化を損なっているといえるのではないかと思う。よく考えてみたいところだ。
2008.07.26
コメント(0)
-
社会システムの下位システムへの「分化」という概念
下位システムとは、上位システムに対する概念として提出されているものだ。システムの場合は、あるシステムが部分的にもっと小さなシステムを含んでいるという状態が、全体と部分という対立ではなく、上位と下位という対立として把握されている。これは、上位システムが「環境」と呼ばれるものであり、下位システムの選択前提を与えているものという観点があることによって、上位と下位という見方になる。単に大きい・小さいという全体と部分という視点ではなく、あくまでも選択前提というシステムの根幹に関わる部分を見るために、上位と下位という区別をしているのだろう。社会というのは、人間の協働が見られるシステムでは最上位に当たるものになるだろう。現代社会は複雑な構造を持っていて、そのまま眺めていたのでは、どうして秩序が保たれているかがまったく分からない。そこにある必然性を洞察することが出来ない。そこでこの複雑な社会システムを、部分をなす下位システムに分けて把握することが考えられる。複雑すぎる現代社会のシステムは、もっと小さな単位に当たる社会の一部の機能に秩序を与えるシステムに分解される。これは、社会システムを把握するために、複雑すぎる全体を分解するという、一つの思考の技術を使っていることになる。しかし、実際は現実はその逆に、部分をなす特殊機能を果たすシステムが発達したからこそ、現代社会は全体の複雑化を増す方向へと進化してきたのではないかとも考えられる。そのようなシステムの捉え方が「分化」という概念に当たるような気がする。この「分化」という概念を持つことにより、社会システムの進化が見えてくるような気がする。さて宮台氏は、「連載第一七回:下位システムとは何か?」では、下位システムについて具体的な記述はしていない。社会が複雑化したときに、さまざまな社会的な分野で起こる問題をまず考察している。たとえば政治的な場面においては、単純な社会では、政治そのものに携わる人間は数が少なかっただろう。だから、社会全体の意志決定が必要なときも、少数者の合意を取り付けるだけですんでいたのではないか。それがだんだんと多くのものが政治にかかわるようになり、民主主義的な政治になれば、建前上はすべての有権者(成人として人権が認められた人々)が参加することになり、その合意を取り付ける複雑さは大変なものになる。このような社会では、「政治とは、共同体の全体を拘束する決定を産出する機能(集合的決定機能)を果たす装置の総体」という概念の下に設定されたシステムが、その定常的な秩序を保たなければ社会が成り立たなくなるだろう。また経済を「共同体の全体に資源を行き渡らせる機能(資源配分機能)を果たす装置の総体」として考えると、このシステムでは、複雑化し肥大した経済を持つようになった社会では、その資源をどう適正に配分するかが問題になってくる。一部の支配者が自由に資源を処分できるのであれば、その分け方に不満があっても社会全体の問題とはならないだろう。資源配分が、それに不満を持つ人間たちの間で問題になるのは、社会が複雑化し肥大したときになる。この考察の過程で宮台氏は興味深い指摘をしている。それは、経済としての資本主義を考えると、それは各人が自由に振舞うことで、結果的に需要と供給のバランスが生れると見なせる。資本主義という自由主義経済では、このような神の見えざる手によって資源の適正な配分がなされるという。そしてその発想に対するマルクス主義の問題提起がある。マルクス主義においては、自由主義経済は、資本の適正な配分ではなく、むしろ市場を自由に任せることによって無政府性が生れ、これが不適正な資源の配分を生み出すと捉えていた。これはどちらの発想が正しいかを科学的に決定することは難しいのではないかと思うが、物質的な豊かさをもたらす競争においては、マルクス主義ではなく資本主義が完全に勝利したというのが人間の歴史ではないかと思う。このマルクス主義に関連して東側の社会主義国家の捉え方を宮台氏は次のように語っている。「因みにマルクスはビュニガーリッヘ・ゲゼルシャフト(市民社会)を、市場の無政府性が一人歩きする怪物だと捉え、この無政府性を克服するために社会主義革命を構想しました。この構想に従って、二十世紀には「東側」と呼ばれる社会主義国家群が生まれました。 社会システム理論の鼻祖パーソンズは、東側のような政治の肥大した体制(後述)が生まれたのは、古典派経済学からヘーゲルを経てマルクスに至る「経済優位」の社会把握に問題があるからだと考えました。社会システム理論の構想は実はそこから生まれたのです。」僕は、マルクス主義というものは、理論的には仮説に過ぎなかったものが科学という真理だと錯覚されたために、その真理性が宗教的に信じられてしまったというイデオロギー性にマルクス主義の一番の失敗を見ていた。あれがイデオロギーにならずに、仮説として理解されていれば、その正しい部分を見分けようという発想にもなり、マルクス主義の正しい遺産は受け継ぐことが出来たのではないかと感じていた。しかし、上の宮台氏の文章を読むと、マルクス主義という理論体系そのものに「「経済優位」の社会把握に問題がある」という批判が成立しそうな気がする。経済という土台が、人間の意識を始めとする社会の上部構造(人間の精神面を反映する部分)を形成するという発想そのものに理論的な問題があると指摘しているように読める。このようなマルクス主義批判は、実はこれまで目にしたことがない。「存在が意識を決定する」という言い方は、何か正しいもののように受け取っていた。しかし、これは実は間違いではないかという指摘は、今なら頷けるものだ。マルクス主義の失敗はイデオロギーの問題ではなく、理論の問題だったのではないかと今は感じる。「政治の肥大した体制」も、経済をすべて支配するためには、すべての人々を絶対的に支配する体制が必要で、マルクス主義の理論的基盤から必然的に帰結するような気もしてくる。経済は、社会にとって重要な一部ではあるだろうが、それさえ押さえれば社会に秩序が生れ安定するというものではない。というよりも、経済というのはそう簡単に押さえきれる対象ではなく、システムとしてどのようなメカニズムをもっているのかを解明することが大事で、政治によってコントロールできるとする発想にそもそも間違いがあったような気もする。経済を国家が支配して、国家のコントロール下に置いている中国が、その上部構造である精神面で「拝金主義」が強くなり、西欧的な成熟した資本主義国家が、むしろ節度ある、物質主義を超えた道徳性を持っているように見えるのは、経済をコントロールするのではなく、その摂理を受け止めようとしているからではないかとも感じる。皮肉な現実だ。イデオロギーは宗教的な妄想を生むので、論理的な間違いを生みやすいということがある。だから、イデオロギー的な、論証抜きに真理性を信じるという傾向があるものに対しては、僕は論理的観点からの嫌悪感を感じてしまう。三浦さんが「官許マルクス主義」と呼んでいたものや、通俗的なフェミニズムなどがそのように感じるものだ。だが、これらはイデオロギーとしての問題だけではなく、実は根本的に理論の基礎に間違った前提があったかもしれない。宮台氏の上の文章を読んで、そのようなことを考えるようになった。社会システム理論は、宮台氏に寄れば「パーソンズは、経済機能(資源配分機能)や政治機能(集合的決定機能)を含めて数多の機能的達成をせずには存続できないものとして社会システムを捉え、かつこれらの諸機能を担う下位的なシステムが、どれが優位というのでもなく相互依存する形を考えました。」と語られるもので、下位システムに優位性というものを設定していないようだ。これはなるほどと思えるものだ。確かに経済というのは、食べていくのも大変だという環境にいては人間にとって最大の関心事になってしまうが、そのような条件がなくなれば、他のシステムを支配するほどの大きな影響を与えるものではなくなる。生活に余裕が出てくれば、人間というのは経済ではないものにむしろ大きな関心を持つ。「優位性」は普遍的なものではなく、特殊な状況で出てくるものに思える。社会全体のシステムの安定のためには、その社会にあるシステムのすべてに安定がなければならないだろう。どれか一つが不安定になったり、肥大しすぎたりすれば、それが他のシステムに影響を与えて社会全体のバランスが崩れ安定を失う。上位と下位のシステムはそのような関係にあるように思う。宮台氏は、「抽象的な思考図式とは次のようなものです。有機体システムとしての私たちは、免疫システム、神経システム、消化器システム、循環器システムなどの下位システムに支えられています。これら下位システムの間に優劣の関係はなく、相互依存の関係があるだけです。」と語り、上位システムの安定のためには、「相互依存」の関係が安定的でなければならないと語っているような気がする。これは納得できることだ。マルクス主義の発想よりも、社会学のシステム理論のほうが、現実には有効性を持っているような気がする。上の文章に続けて宮台氏は次のようにも語っている。「同様に、近代の社会システムは、資源配分機能を担う経済システム、集合的決定機能を担う政治システム、紛争処理機能を担う法システム、根源的偶発性処理機能を担う宗教システムなどの下位システムが、相互依存する形で成り立っている──こう考えるわけです。 むろんどんな社会システムでも、資源配分機能・集合的決定機能・紛争処理機能・真理探究機能・根源的偶発性処理機能などの遂行は不可欠です。ただ近代社会は、その他の社会と違い、これら機能的課題に従ってシステムを分化させる点が特徴的だと考えるのです。」ここに至って、近代社会の重要な概念として「分化」のイメージが前面に出てきたように思う。ある特殊な機能を受け持つシステムが優位であるような社会は、それは十分近代化されていないと考えられるのではないかと感じる。旧社会主義国家は、政治的な機能を持つシステムが肥大していたという点で実は十分近代化されていなかったといえるのではないかと思う。これは、現実の日本社会を見るときにも、どうも特殊な機能が肥大しているようなところが見えるので、そこにゆがんだ近代化の姿を見ることが出来るような気がする。コネが優先されていた教育界のシステムは、どうも分化が不十分だったような気がする。分化が進んだシステムでは、それをすべて支配下におくような強大な国家権力は現れにくい。そしてそれこそが近代国家だといわれる。そのような意味では、日本は近代国家であるのかどうかということはかなり論争的な命題だろう。分化という概念を、近代化と関連させて今の日本の姿を正しく解釈することに役立てたいと思う。
2008.07.25
コメント(0)
-
「自由」を脅かすものが存在しても、なおかつ「自由」の存在を主張できるか?
「自由」については、すでに「連載第7回 選択前提とは何か」で語られていて、それは「選択前提が与えられているが故に「滞りなく選択」できる状態だ」と定義されていた。具体的には(1)選択領域(選択肢群)が与えられ、及び/或いは(2)選択チャンスが与えられ、及び/或いは(3)選択能力が与えられた状態を指すと説明されていた。基本的には、「自由」の概念は、この定義で与えられるイメージによって理解される。それを再度「連載第一六回:自由とは何か?」で論じるのはどうしてか。それは、「自由」に対して、そのようなものがありえないという主張に反論するためであるように見える。人間の選択にはある種の制約があり、どうしても「自由」にならない限界が存在するのだから、「自由」というものが人間にはありえないのだという主張がいくつか語られる。この主張は、「自由」の概念の根源に関わるものだが、「自由」を、完全に制約から逃れているもの、つまり何ものにも縛られていないのだというイメージで捉えていれば、そのイメージにそもそも現実には「自由」がありえないということが含まれてしまう。すべての制約を取り外すということは、現実に存在しているという現実性を捨象してしまうことを意味する。それが現実に存在しているのなら、現実のある時間・ある場所を占めているということだけで、そこには制限が生じてしまうのだから、現実性を棄てない限り、すべての制約(しがらみ)から逃れることは出来なくなる。このような「自由」の概念は、原理的に現実性を持つことが出来ない。すべての制限がなくなった「自由」は抽象的な観念の世界にしか存在しない。それを、宮台氏は、現実にも「自由」が見つけられるのだということをこの回の講義では論じている。あるいは、別の観点で宮台の主張を理解すれば、現実に存在するであろう「自由」の概念をここで説明しているということになるだろうか。完全な抽象性を持った「自由」ではなく、現実性を持った「自由」という抽象概念を説明していると理解することも出来る。さて、「自由」を否定する主張を宮台氏は3つ紹介しているがその第一は、「自己決定は、問題ある既存秩序を補完することで、理想秩序が与える筈の選択前提(選択領域/選択チャンス/選択能力)から人を遠ざけるから」というものだ。これは自己決定における「自由」がありえないという主張になる。具体的には、「自己決定的な援助交際を批判するフェミニストの議論」の中にこの主張を見ている。宮台氏は、援助交際と呼ばれる少女売春について、それが自己決定で行われているという解釈で、その決定に際して「自由」な自己決定の選択が行われていると見ていた。しかし、それに対して「その振舞いのせいで家父長制が温存される」という批判が提出されていた。買売春に関しては「「プロの女だけ売れ」という議論」によって、家父長制と結合していたと宮台氏は指摘する。確かに、買売春一般は、「その振舞いのせいで家父長制が温存される」という面を持っているように見える。だが援助交際と呼ばれる少女売春には、買売春一般とは違う特殊な性質が見られるとも指摘している。少女売春は、「旧来の売春と違い、家父長制が想定する妻や娘のイメージを裏切ります」という。それは「プロの女」が売るものではなく、家父長制のもとではむしろ家父長の所有物として、他のものの侵害を許さない妻や娘を家父長の支配下から引き剥がすものとなる。家父長制が温存されるどころか、それを突き崩すものとなる。したがって、家父長制の温存のために、その反動としてそれを選択せざるを得ないという「不自由」から選択された売春ではなく、「自由」に自己決定で選ばれたのだと解釈することも出来るということだ。「自由な自己決定があり得ないとされる第二の理由は、自由(自己決定)は秩序(共同性)を脅かし、自由の前提を壊すから」というものだ。ある種の選択が「自由」に見えるのは、その選択を邪魔しない秩序というものがあって、邪魔されないがゆえに選ぶことができるという見掛けがあるだけだという主張だ。本当は、いつでも邪魔が入る可能性があり、本当の「自由」が社会に実現してしまえば、その秩序そのものまで破壊する「自由」までもが登場する可能性がある。「自由」によって「自由」が破壊されるという矛盾を「自由」ははらんでいる。だから、このような(ある意味で完全な)「自由」は存在しないという主張のようにこれは見える。この発想はホッブスに始まるというが、それは「「秩序のためには自由の断念が必要」とする観点であり「自由と秩序のゼロサム理論」と呼ばれる。この発想では、秩序が存在するなら、そこには「自由」はありえないという結論になる。まさに「ゼロサム」の関係に「自由」と「秩序」があるということになるだろうか。これに対し、宮台氏は、「脳死を巡る「死の自己決定」の現場を見れば分かるように、死を共同的に生きる親族が、本人を思いやって告知しないことで、告知さえあれば自己決定で選べる筈の「共同的に生きられた死」から、本人が遠ざけられてしまうという逆説」という具体例を出して反論する。これは、「自由」と「秩序」が「ゼロサム」であると思っていたのに、状況によっては、自分の体についての正確な知識という「秩序」があるほうが、「共同体的な死」を自己決定で選択するという「自由」がもたらされるという逆接を語っているものと受け取れる。これは、まさに「必然性の洞察」が真の「自由」をもたらすという具体例になっているだろう。自分の体が死を迎えつつあるという事実をまったく知らないほうが、自分の死について「自由」な選択ができるという「ゼロサム」関係はここにはない。秩序がないほうが「自由」だとはいえないのだ。「自由と秩序のゼロサム理論は、近代の再帰性を踏まえない実に幼稚な議論です」とこの考え方を宮台氏は批判する。自明性が確立していて、他の選択肢を考えもしないという状況であれば、選択肢がないことを我々は残念に思うこともない。そのような意味で我々は、そのような状況では「不自由感」を持たない。だが、それは近代以前の社会までだと宮台氏は指摘する。今まで自明だと思ったことに常に選択肢が生じるというのが、近代の再帰性というものだ。「自由」と「秩序」を対立させて「自由」を考えるのは、単に「秩序」を外れた選択肢を考えたこともないという、選択肢がないがゆえに「不自由感」を感じないというだけの「自由」であり、それは低レベルの「自由」であって、近代以後の社会ではそれを越えた「自由」が存在する。「自由な自己決定があり得ないとされる第三の理由は、自由に自己を決定できる自己など、存在論的にあり得ないから」というものを最後に考えてみよう。これは、まさに「完全な意味での自由」というものが現実にはありえないという主張をしているものと思われる。だから、これに反論するには、ここで考えている「自由」の概念は、そういう抽象的な完全性を持ったものではなく、現実に存在しうるものとして設定されているのだと反論すればいいのではないかと思う。これは、完全なものではないというイメージから、不完全なものだと思ってはいけない。そのようなイメージでは、現実性を持たせるためのご都合主義的な定義だといわれても仕方なくなる。それは不完全な「自由」ではなく、むしろ「自由」というものの本来の意味を持ったものとして提出されていると理解しなければならない。宮台氏は、「世界が因果的に決定されているのなら(カント自身が信じるニュートン的世界観)自由意思などあり得ません」と指摘する。因果律によって、世界のあり方がすべて決定されていて、ただ人間の今の段階ではそれが知られていないだけだと、現実の世界のあり方を受け止めると、法則に支配されて「自由」のない人間というイメージが生れてくる。果たしてこれは「自由」の本来の意味になるだろうか。このような考え方に対して、宮台氏は「因果帰属と選択帰属との混同」という答え方をしている。売春少女の例で言えば、少女が売春をせざるを得ない社会的構造など、因果律的にたどれる何ものかがあったとしても、それが少女の選択を決定したとするのは、「因果帰属と選択帰属との混同」になるのだと思う。そこに複数の選択肢があって、「どの選択肢を選ぶことも出来た」という情況があるのなら、その選択は少女自身に帰属するはずだ。この可能性の問題としての選択肢が存在していればそこには「自由」があったのだと判断するのは、たとえ因果的にはそうなると結果が読めていても、人間はその予期に反して行為を選ぶことが出来るという意味で「自由」なのだと判断するのではないかと思う。このように「論理(純粋理性)と倫理(実践理性)を分離した」のがカントであると宮台氏は指摘している。「人倫の世界では、意思が妨げられていない以上、別の行為を意思できた筈だと了解されます。その限りで、当事者に自由意思があった──殴らない選択も意思できた──と見做され、責任が帰属される訳です」という論理が、「自由」の本質を語った論理になるのではないかと思う。つまり、「自由」とは、意志によってどれを選ぶことも可能であるという選択肢が存在したとき、そこには「自由」があるといえるのだということだ。これは、「自由」の機能的な側面を語った定義になるが、それこそが「自由」の本質であると僕にも思える。ある特定のどれかを選ばざるを得ないという状況の下でも、そこに複数の選択肢が、可能性が0(ゼロ)でないという形で提出されていれば、そこには人間的な意味での「自由」が存在するのである。この「自由」の概念は、「必然性の洞察」が「自由」のもっとも高い段階であることを改めて教えてくれる。なぜなら、「必然性を洞察」したものは、その選択肢が一つであることを自ら了解し納得しながらも、積極的にその選択肢を選ぶことが出来るので、まさに自由意志で最適な選択が出来ることになるからだ。「必然性の洞察」によって一つの選択肢しかそこにないことが理解できても、それをいやいやながら選ぶのではなく、それが最適の選択だと理解できれば、気持の上でも最高の「自由」を味わうことが出来るだろう。宮台氏は、この回の講義を次の言葉で結んでいる。「結論。第一に、システム理論的な行為概念を踏まえた上で、自由ないし自己決定が因果帰属でなく選択帰属上の概念であることを弁えるべきです。その上で第二に、自由の前提たる秩序の確保をも自由な選択の対象と化する近代の再帰性に、十分敏感であるべきです。」「自由」が選択肢の存在という概念であることをわきまえて、今までは自明性として存在していた秩序の前提に対しても、複数の選択肢の可能性を与えることこそが「近代の再帰性」として語られていることではないだろうか。自明なものに選択肢が与えられて自明でなくなれば、予期が揺らいで不安になる。気持ちの上では「不自由感」が生れてくる。何を選んだらいいのかという選択能力の点で「自由」を感じられなくなるからだ。しかし、この「不自由感」は、人間の「自由」そのものが否定されたのではない。むしろ、新しい段階の「自由」へと進んだために、古い「自由」における必然性が分からなくなり「不自由感」が生れたのだ。この場合は新たな必然性を求めることが「自由」の回復になるだろう。我々は「自由」をそのように捉えなければならないのではないかと思う。
2008.07.24
コメント(0)
-
システムとしての「人格」……それは実体としての「人格」とどう違うか
宮台真司氏が「連載第15回:人格システムとは何か?」で説明している「人格」とは、システムとしての人格だ。システムというのは装置として比喩的に語られることが多い。その装置は、ある種の機能を持っているもので、関数のブラックボックスのようなものだ。その装置は、ある定常的な状態を保つように機能が働く。「人格」とは辞書的には「個人に独自の行動傾向をあらわす統一的全体」というような意味で使われる。その人が、その人であることの同一性あるいは独自性を感じさせる性質を指して「人格」が語られる。機能的な把握というよりも、実体的な属性として把握されているように感じる。これをシステムとして捉えるという時は、その要素を「行為」として捉えて、その「行為」がある「人格」に属するか属さないかを決める装置として「人格システム」というものがあるという捉え方をするようだ。「人格システム」は、準拠枠の違いという面で「社会システム」と対立する概念としても提出されている。準拠枠というのは、イメージ的には「社会システム」が社会全体をその行為の所属するシステムとして捉え、「人格システム」は、その行為の帰属先は個人になるというようなものになるだろうか。宮台氏は次のように説明している。「観察可能なのは社会でも人格でもなく行為ですが、一群の可能的行為を、コミュニケーション的纏まりに準拠して内外差異を設定すると社会システム、エンパセティカルな心理的纏まりに準拠して内外差異を設定すると人格システムになります。」「社会」や「人格」というのは、観察する対象としては実体的に存在しない。どれを「社会」とし、どれを「人格」とするかが確定しないのだ。その構成要素である「行為」しか観察する対象にはない。「社会」や「人格」は、それが同一性を保つような秩序を実現している原動力となっている装置として捉えられる。この装置の機能は、どの行為がそのシステムに属するかを決定するものになっている。コミュニケーション的纏まりというのは、行為と行為の選択接続をある程度客観的に記述したものになるのではないかと思う。その社会が何らかの秩序を持っていて、その秩序が成立するためには、行為の選択接続においてある特定の接続が許されて、それがループを作っているというシステムの特徴を持っていることが必要だ。これは社会全体に成立している選択接続なので、その構成員の個性に応じたものではなく、任意の・誰にでも成立するような選択接続になるのではないかと思う。このような準拠枠で、行為と行為の接続のすべてと、その社会で成立する接続(コミュニケーション)との差異を設定して社会を定常的に保つシステムを「社会システム」と呼んでいるように思う。「人格システム」になると、誰でもいい任意の人間ではなく、特定の誰かという個人の特性が関係してくる。それが「エンパセティカルな心理的纏まり」という準拠枠になるのではないだろうか。これはちょっと分かりにくい概念だ。「連載第一四回:役割とは何か?」では、「エンパシー(感情移入・同感)」という概念が提出されている。他者の気持や心といったようなものは、原理的には分かるはずのないものだ。それが分かったと信じられる原因となるものが「エンパシー(感情移入・同感)」というもので指摘される何かではないかと感じる。これは人間の心に関する概念となるのだが、心を持つものを人間だと考えるとき、心そのものはどのようなものかまったく分からないものになる。だが、心の働きである機能は観察できる。そこで、心の働きとしての「エンパシー(感情移入・同感)」というものを考えることで、社会と区別される個人というものを捉えようというのが、「エンパセティカルな心理的纏まり」という言葉になっているのではないだろうか。この心に関しては「心理システム」という概念もここで提出されている。これは「人格システム」とは違うものとして提出されているのだが、同一のものだと勘違いしやすいものでもあると指摘されている。それはどちらも「エンパシー(感情移入・同感)」という言葉によって考えられている概念だからだ。違いは、「人格システム」の場合はその準拠枠が「エンパセティカルな心理的纏まり」とされているのに対し、「心理システム」の場合は「エンパセティカル(同感的)に想定される」と表現されているところだ。宮台氏は次のように書いている。「宮台という人格(パーソナリティないしキャラクター)が宮台に属しうる行為の総体だとして、行為がそこに属しうるか否かを(他者や自身が)境界設定する場合にエンパセティカル(同感的)に想定されるのが、「心」、すなわち、心理システムという実体です。」「人格」と「心」は個人の中で一体となっているので混同しやすい。しかしその構成要素が違う。「人格」の場合は、観察可能な「行為」というものがその要素となっている。しかし「心」の場合には、観察できる要素はない。そこにあるのは、他者もそう思っているだろう・そう感じているだろうという、他者の心に対する想像で作りあげた対象だ。宮台氏も、「心理システムつまり「心」には観察可能な要素が皆無で、完全に想像的なものです」と書いている。宮台氏が「人格概念(ないし人格システム概念の適用対象の存在)は普遍的ですが、しかし「心」の概念(ないし心理システム概念の適用対象の存在)は普遍的ではありません」と語る言葉の意味はなかなか解釈の難しい内容を持っているように思う。「人格概念」が普遍的だというのは、それが人間のいるところではいつでも観察できる対象だということになるだろうか。だが「心」は普遍的ではないという。それは、「心」という概念が見つからない、「心」の働きだと解釈できない場合が想定できるということだろうか。原初的社会の人間たちは、「一つのものを誰もが同じように体験し、同じように体験するがゆえに同じように行為する」ということが見られる。社会全体に渡って共感があるので、その個人の特性に従って共感するということがない。わざわざ「心」というものを設定して他者に共感しようとする必要がなくなる。このような社会で、秩序に反するような例外的な行為が見られた場合はどうなるだろうか。そのような時は、「狐が憑いた・神が降りた等と理解され、儀式的な共同行為を行って、俗なる時空から聖なる時空へと切り離す形で無害化」するという。そのため「そうした社会には人それぞれに「心」があるという観念はあり得ません」と宮台氏は語る。そして面白いことに、この例外的行為の処理において、社会が複雑化してその頻度が増すと、上のように宗教的な処理がだんだん利かなくなり、それが「心」というものの存在の必要性になっていくという。「心」が違うから、行為にも違いが現れると理解されて、例外的行為という予期はずれに納得するのだという。これは、現在の衝撃的な事件を起こすものたちへの理解にも通じるものかもしれない。信じられないような行為をするものたちは、我々とは「心」が違うのだという理解をしたくなる人が多いのではないだろうか。「心」というものは、「心の概念は、期待外れの帰属先に過ぎません。すなわち「与えられた状況で各人が異なる心を持っていたので振舞いがバラバラになった」といった了解であって、シチュエイショナル(状況主義的)です」と宮台氏はあっさりと断言する。「心」は機能の一つに過ぎないというわけだ。これは、理科系の人間にとっては案外すんなりと頭に入ってくる言葉だが、情緒的な情感などに重きを置く文系的な人は、ちょっと違和感を感じるかもしれない。これに対し、「単なる心に比べて、個人性には更なる賦課が重なっています」と指摘される「個人性」の問題は、「意味論」として説明されている。それは「各人には入替え不能な内面がある」「各人には固有に一貫した心がある」という言葉で語られている。個人には、システムとして同一性を保つような「内面」「心」といったものが存在しているという主張が、ここで言われている「意味論」になるだろうか。「人格」と「心」とは区別しなければならないが、それは密接に結びついていて、「人格システム」の働きを考察するときに、どのような行為をその人格に属するものと捉えるかは、その「人格」を持った人物の「心」がどのような働きをして判断するかを捉える必要があるようにも感じる。「人格」の区別は「心」の区別に通じる。この両者を切り離して考察するのは難しいように感じる。この両者の区別は、心理学(精神医学)と社会学の考察の方向の違いにも関わって、次のような難しさも生む。「社会学の目標は、不透明な動きを示す社会を記述することで、特に実践目標(政策)は、問題を抱えるとされる人たちを生み出す社会的メカニズムを描き出し、かつ、制度や文化をどう変えればこうした社会的メカニズムを解除できるかという処方箋を考えることです。心理学は、現行の制度や文化を「前提にする」学問です。社会学は、現行の制度や文化を「疑う」学問です。社会学によれば、「社会」とは私たちのコミュニケーションを浸す暗黙の非自然的前提の総体で、非自然的前提の総体を明るみに出すのが社会学の目標です。ゆえに「個人が治ればいい」という心理学と、社会学の対立は避けがたい。現行の制度や文化を前提とする限りで「こうしたらいい」という心理学の提言が理に適っていたとしても、そもそも現行の制度や文化を維持するべきかどうかに疑問を呈するのが社会学です。例えば、家族の中に居場所が見つからない人に、なぜそうなるのか、どうすれば見つかるかを心理学者は語ります。でも社会学者から言えば、家族の中に居場所を見つけなければならない理由はないし、そもそも家族を営むべきなのかどうかさえ疑わしいのです。」精神医学が捉える心の病気は、果たして病気と呼んで治療の対象にすることが正しいのかどうか。社会そのものに問題がある場合は、むしろその社会に適応できずに、病気として現象してくる人々のほうがまともな場合もあるのではないかということだ。宮台氏は、「社会学の立場では「人格障害」は郊外化現象への合理的適応です。「人格障害」はむしろ正常性の証です」とも語っている。「人格」というイメージを、「人格者」というような、何か社会的に価値がある振舞いをする人からの連想で捉えていると、社会的に価値の低い行為をする人を「人格障害」と呼びたくなるかもしれない。しかし、「人格」というものを「人格システム」で捉えると、そのような価値観から自由に、ある種の行為を選択することに一貫性があれば、それは「人格システム」として捉えることが出来る。「人格」というものを、道徳的価値観で捉えるのではなく、システムとして客観的に捉える見方をした方が、現代社会においては社会全体を見通した捉え方になるのではないだろうか。そこでは文学的な情緒や味わいは薄れてしまうかもしれないが、心の病をやり過ごすためには役に立つのではないかとも感じる。心の安定にとっては、現実に適応して安心するばかりでなく、現実を突き放して社会全体を捉えることでその中の個人の安定を見るというやり方もあるのではないかと思う。
2008.07.23
コメント(0)
-
学術用語としての「役割」の概念
宮台真司氏が「連載第一四回:役割とは何か?」で語る「役割」という概念を考えていきたいと思う。この概念は、果たしてどのような目的の下で提出されているのだろうか。宮台氏は、「「役割」とは、ヒトに与えられるカテゴリー」だと語る。あらかじめ「役割」が分かっている他者は、その「役割」が与えるイメージによって何らかの「予期」を持つことが出来る。このような「役割」を持った人間ならば、こういう行動をとるはずだという「予期」だ。近代社会が、「予期」のコミュニケーション(選択接続の束)を基礎にしてそのシステムの秩序を保っているとすれば、その「予期」に影響を与える「役割」という概念は、「予期」がどのようになってそれが現実の行動にどう影響を与えるかを教え、システムの秩序の方向を把握することに役立つものとなるだろう。「役割」の説明の中に、「遂行性」という概念も紹介されている。これは「社会的事実としての同一性」として定義されている。これは「行為の意味的同一性」にも相当するという。ここで重要になるのは「社会的」ということなのではないかと僕は感じている。行為の「意味」とは、その選択接続の束で与えられ、すべての組み合わせの選択が選ばれるのではなく、特定の選択肢だけが接続されるというつながり方にその「意味」を見ている。その選択接続の束は、個人がそのように認識しているだけでなく、社会全体でみんながそう思っているという受け取り方が必要なのではないかと思う。これは「制度」という概念の説明のときにも出てきた発想だが、「社会」という言葉には、個人が勝手にそう思っているのではなく、誰もがそういうふうに思うのだということが、少なくとも個人の頭の中にそういう思い込みのようなものがあることが「社会」と個人のつながりをもたらすように思う。このような思い込みが「誰にも」あるときそれを「制度」と呼んでいるのだろうと思う。この場合の「誰にも」という判断は、厳密に行われるのではなく、たとえば統計調査のようなものである程度の割合が示されれば、「誰にも」という判断がされるのだろうと思う。「役割」という言葉も、社会学の中で登場するということは、これも個人が勝手にその「役割」があると思っているのではなく、社会全体でみんながそう思っているはずだということが基礎にあるものが重要なのだろうと思う。宮台氏はそういうものを「制度役割」とも呼んでいる。この「制度役割」が、本当にみんながそう思っているという「制度」の中での役割であれば、これが正当にその機能を働かせている時、社会の秩序が維持されるという帰結は常識的で納得のいくものになる。学問というのは、常識的な判断をより厳密に行うものという面がここで見られるのではないかと思う。しかし、この「役割」はしばしば裏切られる。これは「役割」というものが「ヒトに与えられるカテゴリー」だということに関係しているのではないだろうか。人は、意志の働きによって機械的な反応だけではなく、あえて規則に反する行動を取ることが出来る。「意志の自由」というやつだ。この規則に反することがらが社会の秩序そのものを破壊するか、秩序が維持される例外としてやり過ごせるかは「役割」に対する信頼が大きく関わってくるのではないだろうか。この発想を、いま話題になっているいくつかの問題に適用して解釈してみると、現実解釈として新たな視点が見えてくるような気がする。僕も教員をしているのであまり他人事とは言えないのだが、大分県での教員採用試験での不祥事は、不正をした人間たちの「制度役割」への期待に反する行為だったといえるだろう。試験の結果を改竄して、あらかじめ予定していた人間を合格させるというのは、試験を正当に行う「役割」を担っていた人々が、その「役割」を果たしていなかったということを意味する。このとき、道徳的・感情的な非難に流れるのではなく、その「役割」の違反がシステムとしてはどのようなメカニズムで起こっているのかということを理解するのに、この「役割」の発想が役に立つのではないかと思う。「役割」という観点から考えると、彼らは、社会的な「制度役割」は果たさなかったけれど、個人的に頼まれたという、依頼に対する行為としてはその「役割」を果たしていると考えられる。贈賄した人間の期待に応える「役割」を果たしたといえるだろう。この「役割」は、社会的にみんながそう思っている「役割」ではないので、あえて呼ぶなら宮台氏が紹介する「個人役割」というような呼び方になるだろうか。個人の利益になることが密約されて、ある種の不正が行われる結果となっている。社会全体の「役割」を考えれば、それが不正であることは明らかであるから、「制度役割」の自覚があれば、彼らもそのようなことは行わないというブレーキが利いたはずだ。それがなぜブレーキが利かなくなってしまったのか。これは「個人役割」と「制度役割」の複雑な絡み合いがそのような結果を招くメカニズムを作っているのではないかと思う。確かに「不正」という面でその現象を眺めれば、個人的な利益に関わる部分は「個人役割」と呼ぶにふさわしい感じがするが、あの不正が「大分県だけではない」といわれることの意味を考えてみると、個人の不正行為に見えたものが、実は教育界の隠れた常識を物語る、社会の「制度役割」と違う、もう一つの狭い社会(「教育界」という狭い社会)の「制度役割」と矛盾を起こしていたのではないかとも考えられる。有力者を通じて口利きをしたり、試験の結果が公式に発表される前にそれを知ったりするということが、「教育界」では公然と行われていて、誰もそれが不正だとは思っていなかったようだ。したがって、それを請け負う「役割」を持った人間が「教育界」ではあちこちにいたようだ。そのような人間の「役割」は、社会全体の「制度役割」との関係で見れば「個人役割」と判断したくなるが、狭い社会である「教育界」で考えれば、そこでの「制度役割」になってしまいそうな気もする。つまり、個人の良心でそれを防げるようなレベルの問題ではなくなる恐れがある。不正の温床がすでにシステムの中に秩序として盛り込まれてしまっているようだ。社会全体の秩序を壊す不正という行為が、実はその部分のシステムには、不正こそが秩序になるようなシステムとして組み込まれてしまっているような感じがする。このシステムの問題はかなり深刻な気がする。不正をすべて排除するためには、「教育界」のシステムをすっかり変えてしまうような、ある意味ではいまのシステムの破壊が必要だろうが、破壊が行き過ぎてしまえば、社会全体の利益となっている部分まで破壊されてしまう恐れがある。これをどの程度で良しと判断するかは難しい問題だ。明らかに不正で合格したという教員の資格を取り消すのは、不正を正す意味で正しいが、グレーゾーンにあるような教員に対して、それをどの程度で許容するかという判断はかなり難しいだろう。もっと大きな社会というシステムを破壊しないようにシステムの手当てをすることが難しい。すでに大分の教育界では、どの先生が不正で合格したのかということが、人々の疑心暗鬼として、教育界の信頼がすっかり落ちてしまったようだ。この信頼をもう一度取り戻すための「制度」の復興はかなり難しいだろう。「個人役割」と「制度役割」との弁証法的同一性とも呼べるようなこの矛盾の処理はたいへん難しいだろう。宮台氏は、「役割」についてこの他に「行為役割」と「体験役割」というものも紹介している。これは、「行為」というものがその「行為」を選択したものに責任が帰するという意味で、選択接続の束がどのシステムに属するかで、「行為」を選んだシステムと、選ばざるを得なかったシステムに分けて考えられている。「行為」を主体的に選んだと思われる人間が担う役割が「行為役割」であり、「行為」を選ばざるを得なかった、選択肢は他になかったという役割を担うものが「体験役割」と判断される。これは責任を追及するときに、「行為役割」を持った個人が見つかれば、それは個人の責任を追及するということになるだろう。果たして大分県の不祥事はどの個人が「行為役割」を担っているのかを見るのは重要だろう。組織が「行為役割」を担い、個人は組織の中でそうせざるを得なかった面があったのなら、個人の責任は少しは免罪されるだろう。個人が「体験役割」を担う時は、責任の大半は「環境」というものにあることになる。「環境」が「行為役割」を担うことになる。「役割」の概念は、その「役割」を果たしていないような出来事が社会に起きたとき、それをどう理解したらいいのかというヒントを与えてくれるような気がする。秩序の乱れに感情的に反応するのではなく、その秩序の乱れが根本的に社会を揺るがすものなのか、単に「制度役割」を理解していない個人の責任を追求すれば「制度」そのものは維持されて秩序が回復するものなのか。どちらにしても冷静に対処できる発想を与えてくれるだろう。この「役割」の概念は、人間の歴史としては、社会が小さな時代は個人としてよく知っている人間の間の信頼を基礎にした「個人役割」が、社会の拡大とともに「制度役割」にとって変わってきたと見ることが出来るだろう。このあたりのことで興味深いことを宮台氏は次のように書いている。「制度役割の出発点は原初的社会における血縁的続柄にあると考えられます。レヴィストロースが明らかにしたように原初的社会の婚姻規則は血縁的続柄によって詳細に指定されています。血縁的続柄は一つの形式で、複数の個人役割が入れ替え可能になります。」レヴィ・ストロースが主張した親族の基本構造なるものが、僕にはどうもピントこないというか「腑に落ちる」という経験が出来なかった。そのような構造が今の社会には見られないので、実感としてその構造に支配されているという感じがしなかったこともあるが、婚姻の相手が「制度」として決められていて、それが社会の秩序を保っているというイメージが今ひとつつかめなかった。しかし、その婚姻の関係というものが、「制度役割」として個人に与えられたものだと受け止めると、その「役割」に違反して物事を考えるのは、主体性を持った個人というものが生れてこなかった時代は、ほとんど不可能だったのではないかという気もしてくる。つまり、婚姻の規則は、レヴィ・ストロースが考察した対象の人々にとっては、まさに「制度」として確立していたのだろうと思えると、これがちょっと腑に落ちてくる感じがする。宮台氏は結びのところで次のように記述している。「血縁原理の支配ゆえに個人役割と制度役割とが未分化な原初的社会では、人格的信頼とシステム信頼も未分化のまま、潜在的可能性は使い尽くされていません。血縁原理が極限まで縮退する近代社会になって、初めて潜在的可能性が開花します。 近代社会では見知らぬ他人との相互行為の頻度が飛躍的に高まりますが、制度役割こそが、見知らぬ他人との相互行為に依存した複雑なシステム構築を可能にします。そのことが、匿名的相互行為の増大を疎外として扱う大衆社会論や管理社会論を生み出しました。 しかし実際は匿名圏と親密圏の創出が並行します。両者は血縁原理が十分縮退する19世紀以降初めて潜在性を開花させます。見知らぬ者を制度役割ゆえに信頼可能な社会で初めて、コミュニケーションの履歴のみで個人役割を帯びた者を信頼できるようになるのです。」「役割」という概念を使うと、このような帰結が論理的に導かれてくるような気がする。このあたりの論理構造については、もっと詳しく考えてみたいと思う。
2008.07.22
コメント(0)
-
論理の展開の理解とはどういうことか
宮台氏の社会学入門講座では、毎回その前の回の復習をしてから次の回の本題に入るような展開になっている。「連載第一四回:役割とは何か?」でも「役割」の説明に入る前に、その前の回で解説した「行為」についての確認を書いている。この確認を読んでいると、論理的な展開というものがどういうものかというのが見えてくる。宮台氏のこの講座では、社会学の基本概念を説明するのが主目的だが、それは、その概念が論理的に展開されてどのような知見をもたらすかを説明するのが本題となっている。現実に「社会」という対象に見られるような存在を観察して、ここにこのような側面が見られるという、現実の解釈を語っているのではない。基本的な概念として、このようなものを認めれば、その概念に含まれている論理的な前提から、このような結論が必ず(論理的に)導かれるという論理の展開が語られている。このような発想で物事を考えるというのは、「モデル理論」というようなものに当たるのではないかと思う。現実を観察してそれを解釈するのではなく、現実を抽象して、末梢的だと思われるような属性を捨象し、本質的だと思われるような属性のみを持った「モデル」を設定する。そして、この「モデル」に成立する論理的関係を考察して、「モデル」の間の論理的な法則を求める。この「モデル」は、本質だけを抽象した理想的な対象なので、単純化された面がはっきり見えれば、考察しやすいものになる。この「モデル」が現実に対しても有効性を持つかどうかは、板倉さんが語る「仮説実験の論理」によって確かめられるのではないかと思う。モデルの要素の間に成立する法則は、その要素の概念によって、要素が持つと考えられる属性の論理を展開して求められる。理想的なモデルの要素の間に成り立つ法則を、現実にも成り立つと考えるのは一つの仮説になる。現実の対象は、モデルの要素のように、理想的に末梢的な性質が捨象されているのではなく、まだ末梢的な属性を引きずっている。だから、その末梢的な属性によって仮説が否定されるような場合もある。そのような複雑な現象を考慮に入れて、未知なる対象の本質的な属性に対して実験が成立するかどうかを確かめ、これが常に成り立つことが確認されたときに、その仮説は科学となる。つまり、モデルの間に成立する法則は、現実にも有効性を持つことが証明される。モデルの間に成立する法則は、その対象が抽象的な概念から導かれるものなので、本来的には論理によって導かれる法則である。つまり数学に近いものになる。概念の定義が、ある意味では数学における公理のようなもので、法則が定理のようなものとして理解できる。モデル理論の解説において宮台氏の師匠である小室直樹氏が数学と論理学の重要性を強調していたのは、モデル理論がほとんど数学のようなものになるからではないかと思われる。論理の展開というのは、数学ではそれが前面に押し出されているのでわかりやすい。だが、他の理論でもそれは同じ構造を持っているものだろう。それは定義から論理によって導かれるのであり、現実は一応カッコに入れて捨象される。現実が参照されるのは、その概念のイメージがうまく浮かばないときに、イメージの助けを借りるために現実が利用されるだけで、現実に発見される属性が論理の展開に利用されてはいけないのだと思う。そうなってしまえば、論理の展開ではなく、単なる観察の解釈になってしまうだろう。論理の展開というのは、その考察している事柄が「科学」になるかどうかに大きく関わる。つまり、誰が考えても正しいという結論が導けるかどうかに関係してくる。論理というのは、視点の違いを反映しないものになっている。どの視点で対象を見ようとも、その視点の違いによって論理が変わるということはない。どのような視点に立とうとも、形式論理を破壊するような結論に達することは、人間には出来ない。論理的に思考しようとすれば形式論理に従わないわけにはいかないのだ。しかし、現実の観察を解釈するということになれば、それはどこから見ているかで見え方が変わり解釈が変わってくる。そして、その違う視点や解釈は、どちらが正しいということが客観的にはいえない。つまり、誰もが賛成する視点や解釈というのはないのだ。解釈が解釈にとどまっている限りでは、誰もが賛成するような「真理」を求めることは出来ない。そのような真理は、論理の展開によって初めて導かれる。数学の証明に違反して真理を求めることは人間には出来ないのだ。数学は最初から現実と無関係な対象を定義して論理を展開できるので、現実を無視しているというような非難は受けない。しかし、現実から抽象された対象を設定している「モデル理論」においては、その抽象によって棄てられた現実の属性がどうしても気になる人には、それが「現実を無視している」ように見えてしまう。これは現実を無視しているのではなく、無視してもいいと思われる末梢的だと判断された属性を無視しているだけなのだが、その属性が末梢的だと思われるということは一つの解釈に当たるので、その解釈に賛成できない人は、これを「現実を無視している」と感じるのだろう。モデル理論における抽象が、「現実を無視している」のか、「現実の本質を抽出して見やすくしている」のかは、その全体像を把握した後にしか分からないだろう。その現実の中で当事者として対象を眺めている時は、当事者としての体験が、ある視点だけを特別に重視させる可能性がある。そうなれば本質を抽象するということは無理になるだろう。当事者の視点ではなく、その世界を外から眺めるメタ的な視点で全体を見なければならない。宮台氏が語る社会学に関しても、その抽象が妥当であり蓋然性があると納得できるのは、おそらくその社会学の全体像が、おぼろげながらも見えてきたときになるだろう。初学者の段階ではなかなかそこまでの判断は出来ないように思われる。だから、ここは一つ宮台氏への信頼感から、宮台氏が抽象した概念こそが現実の本質を抽象したものだと受け取って、その論理展開を追いかけていこうと思う。そして、その論理展開が把握できたときに、社会の全体像に一歩ずつ近づいていくのだと信じたい。さて「行為」という概念の復習については、これが決して現実の「行為」を眺めて観察した結果として語られたものだと受け取るのではなく、ある意味では天下り的に定義された「行為」の概念から、その定義に含まれていると思われる内容を論理によって取り出すと、このような主張ができるのだという風に受け取って理解しようと思う。「行為」の定義としては、1 物理的なものではなく、意味的なものですというのがまず最重要なものとして語られる。これは、「物理的」という属性を代表するものとして「行動」という概念が設定され、これと対比されて「意味的」なものを担う概念として提出されるのが「行為」だとするものだ。人間の現実的な運動(時間や位置情報の記述によって記録される)を、物理的な側面だけを考察する時は「行動」と呼ばれ、意味的な側面を含んで考察する時は「行為」と呼ばれるというのが抽象的な概念になる。現実にそれ以外に観察されるさまざまな属性は末梢的なものとして捨象される。次に2 行為の意味は、行為の潜在的な選択接続の可能性──先行しうる行為の束と後続しうる行為の束──によって与えられます。と語られる部分は、「意味」のほうの定義として語られていると受け取れる。この定義は、「意味」という言葉が含んでいる、複雑で多様な姿を、選択接続という視点のものだけを残して他を捨象するために行っているように思う。「意味」の概念をここに限定することによって、誰が考えても論理的に考えればそう結論せざるを得ないという論理の展開が求められるのではないかと思う。3 行為には出来事性と持続性の二重の相があります。これは、「行為」が意味的なものだという定義から導かれる論理的な結論ではないかと思われる。「行為」は、物理的側面としての運動の部分も含んだ概念だ。人間の活動の運動としての側面がまったく見られない「行為」というのはその意味を考えることも出来ない。その行動が、時間的にどのような行動から続いて起こっているのか、この次にどのような行動につながっているのかが、選択接続としてある決まりにしたがっているなら、それは「行為」の意味として受け取れると理解される。だから、「行為」に伴う行動的側面を「出来事性」と結びつけ、意味に関わる本来の部分を「持続性」に結びつけることが出来る。意味は、その定義からいって、「選びなおし」をしない限り持続するものだからだ。4 出来事性を持続性へと回収する際に帰属処理が行なわれますが、システムに生じた出来事が、システムの選択性へと帰属される場合がシステムの「行為」であり、環境の選択性へと帰属される場合がシステムの「体験」です。これは「行為」と「体験」という二つのものを区別するための定義が提出されていると考えられる。これは、行動としては同じものが、あるシステムに対しては「体験」となり、その上位のシステムに対しては「行為」となるという、弁証法で言えば直接的同一性を捉えた発想になっている。これは「行為」の定義そのものから導かれるものではなく、「行為」とは違う概念を設定することで、そこから展開される論理を見ようとしているように思う。システム理論という全体の中で設定される一つの概念と考えられる。5 法実務に見るように、当初は宮台へと帰属された個人行為が、都立大の組織行為として問題化(再帰属化)されたり、それが更に東京都の組織行為として問題化(再帰属化)されることがあり得ます。これは、4で定義された「行為」と「体験」が、上位のシステムや下位のシステムの関係で、行動としては同じものが「行為」として選択されるか、「体験」として選択されるかという意味の「選びなおし」が行われるのだと理解できる。これは「行為」と「体験」の違いの定義から導かれる法則性として受け取れるだろう。6 こうした内部責任を問う再帰属化の連なり(=選択接続)の最終単位が個人行為になります。責任を問われた個人が、個人の内部にある何か(無意識等)の責任を問うといったコミュニケーションは許されていません。この6が定義なのか法則性なのかを理解するのは難しい。個人よりも下位のシステムは、「行為」と「体験」という違いを判断するときには存在しないとここでは主張している。個人よりも下位のシステムに「行為」を押し付けて責任を問うことはできないということだ。これは現実を眺めればそう思えないこともないが、現実の解釈にしてしまえば、これは論理の展開としては受け取れない。「無意識」というものが、個人と独立して存在するものなら、それに「行為」を押し付けることが出来るが、これが個人と一体化したものであり、ある意味でフィクショナルに設定した個人の一部だと定義すれば、これは「無意識」の定義から導かれる法則になるのではないかと思う。宮台氏は最後に「遂行性」というものを語っているが、この理解はかなり難しいので、エントリーを改めて考えてみようと思う。
2008.07.21
コメント(0)
-
思考の展開という概念運用のための「行為」の概念
宮台真司氏が「連載第一三回:「行為」とは何か?」で提出する「行為」については、すでに一回説明されたものである。その時は、外に現れる客観的観察の対象としての「行動」に対して、意味的な要素をもつものとして「行為」が定義された。つまり、「行動」としては同じだと見なされても、その意味が違う場合があり、「行為」としては違うという判断がなされるときがあるというわけだ。「行為」の同一性の判断には意味の判断が伴うので、「行動」の同一性の判断よりも難しくなる。「行動」というのは、外に現れた形で同一性が判断できるので、客観的な測定可能なデータで同一性の判断ができるだろう。時間や位置情報を測定してデータとし、それが同じであれば「行動」としては同じだと判断することが出来る。ある意味では、そこにこめられた「意味」を捨象して、意味に関係のないデータで判断するのが「行動」だともいえる。「行為」と「行動」は、それぞれの概念が互いに否定あるいは補完の関係にあって概念が確定される。ソシュールの指摘にかなうような性質を持っている。この「行為」の概念は抽象的ではあるがイメージはしやすい。意味が理解できれば、「行動」は同じだが「行為」としては違うということも想像できる。宮台氏は、「馬鹿だな、お前は」というような言葉を言うことが、その意味の違いによって「愛情表現という行為」になったり「軽蔑の行為」になったりすることを指摘していた。これが「行動」としては同じだが、「行為」としては違うというイメージだろうか。もちろん、意味が同じだと見なされたときに「行為」も同じだという判断がされる。この「行為」というのは、選択接続の連鎖を考えることで、社会におけるシステム(つまり「行為」という要素間に成立するループの存在)を見るための道具になる。社会をシステムとして捉えて、そのシステムがどういう性質を持っていて、どのような方向に向かって運動していくかという思考の展開において重要な対象となる。その概念をうまく運用することで、社会をシステムと考えた場合の論理が展開される。論理の展開の道具として概念を考えた場合、それを固定的に捉えた実体的な見方よりも、変化を捉える機能的な把握の仕方のほうが役立つように思える。意味という概念も、それがどのような機能を持っているかで理解して、「選びなおし」「否定性」「示差性」「二重の選択性」などという側面から同一性を判断したほうがやりやすいという便利さがあった。「行為」についても、実体的な捉え方の概念はイメージしやすいが、論理の展開のための運用に便利な形で捉えるには機能的な側面に注目したほうがいいのではないかと思う。そのような機能的な側面からの捉え方は、次のような宮台氏の説明から読み取れるのではないだろうか。「意味とは、刺激を反応に短絡せずに、反応可能性を潜在的な選択肢群としてプールし、選び直しを可能にする機能でした。これを踏まえると、行為の意味とは、行為の潜在的な選択接続の可能性の束によって与えられます。選択接続をコミュニケーションと呼びます。」「行為」の持つ意味を、「潜在的な選択接続の可能性の束」によって考えるということが「行為」の機能を把握した見方になるのではないだろうか。「行為」が「行為」として捉えられたとき、その物理的なデータを表現するだけの「行動」ではなく、意味を含んだ対象として捉えたとき、その意味は次の行為の選択につながる「選択接続の可能性」という機能を持つという捉え方がここで語られているように思う。「行為」は個々の「行為」が独立してその意味を問われるのではなく、次の「行為」につながる意味をその機能として持っている。このつながりが、システムのループに関係しており、システムの考察を進める論理の展開という、概念の運用に役立つのではないだろうか。このあたりを宮台氏の説明で読むと、次のようになるだろうか。「例えば打撃行為は、投球行為を先行させうる限りにおいて、かつまた走塁行為を後続させうる限りにおいて打撃なのです。だから社会システムが行為からなるとは、潜在的に可能な選択接続(コミュニケーション)の総体の、一部が定常的に実現するということです。そして、その一部の実現の仕方が確率論的な非蓋然性を示す度合に応じて社会秩序があると称し、かつまた社会秩序が一定の条件を満たす場合を社会統合があると称します。」「行為」の選択接続の可能性の機能を概念としてまとめた言葉は「コミュニケーション」として語られる。これがシステムを考えるための道具となる概念だ。この概念をよりはっきりさせるために、宮台氏は「体験」という概念も提出する。これは「行為」とは違うもので、「行為」の概念を補完するものになっている。この概念を把握することによって、「行為」という概念がよりはっきりしてくる。「行為」という対象だけをただ眺めているのではなく、このような言葉で他の概念を指し示すことによって、「行為」によって切り取られる世界の一部がよりはっきりしてくるのだと思う。ソシュールが指摘することをこの考察の経験から確認できる。「行為」には出来事性と持続性が観察できると宮台氏は指摘する。出来事性の部分は「行動」と同じものと考えられるのではないだろうか。それはそのときのデータとしては記録されるが、「行動」としての現実が終わってしまえば出来事性は消える。これは持続しないという点で持続性と違う概念として捉えられる。「行為」の意味に関する部分は、それが持続するという持続性に関わってくる。意味は「選びなおし」によって修正されなければ、一度選ばれたものが持続する。その行動が終わったときに消えることがない。このような考察を下にして、「行為」と違う概念である「体験」を、宮台氏は次のように定義する。「「出来事」性を「持続」性へと回収する際に「帰属処理」が行われます。システムに生じた「出来事」がシステムの選択性へと帰属処理される場合がシステムの「行為」であり、そうでなく、システムの環境の選択性へと帰属処理される場合がシステムの「体験」です。」これも機能的な捉え方の定義になっている。これは機能として捉えているので、実体的に捉える辞書的な定義とはまったく違うもののように見える。この機能的な定義は、概念の運用において便利だと思われるが、実体的な辞書的な定義とどう関連しているかが見えないと、この定義そのものがイメージしにくくなるのでそのあたりのことを考えてみよう。この定義による「行為」と「体験」が具体的にはどのような現れ方をするかというと、宮台氏は次のような例を語っている。「法実務の場面を考えれば分かります。男Aの強盗行為と見えたものが、裁判過程を通じて、ボスBの脅迫行為によって「強盗させられる」という男Aの体験だったと分かり、罪を免じられることはよくある話。そこにあるのは、判事Cによる認定(帰属)行為です。さらに判事Cの認定行為に見えたものが、後になって別の男Dの脅迫行為によって「認定させられる」という体験だったと分かることもあり得ます。「分かる」と言いましたが、分かるという私の体験が、観察者の観点から行為として帰属処理されることもあり得ます。つまり何かが行為であるか否かはいつも議論の余地があると同時に、何かが行為であると言うときには必然的に「帰属処理されるシステム/帰属処理するシステム」のペアが前提とされています。その際、帰属処理されることは体験で、帰属処理することは行為です。」出来事の持続性・すなわちその意味がコミュニケーション(選択接続)としてどこに帰属するかが「行為」の判断に機能的に関わってくる。その選択が、コミュニケーションとしてシステムのものだと判断されるとシステムに帰属されると判断される。そうなれば、その選択をしたことの責任は当然システムにあると判断されるだろう。だからこそそれはシステムの「行為」である、つまりシステムに責任があると帰属されると考えているのではないだろうか。その帰属先がそのシステムにはなっていない時は、その選択はそのシステムがしたのではないと判断され、システムには責任がない・すなわち主体的な意味での「行為」になったのではなく、受動的にそれを経験したという「体験」と判断されるのではないだろうか。強盗という行為が、実行犯個人の選択で行われたのであれば、その選択が帰属するその個人(人間をシステムと捉えれば一つのシステムになる)の責任であり、個人の「行為」であると判断される。しかし、その個人を含む集団のボスの命令で行った行為であれば、その選択の帰属先は、その集団のシステムであり、ボスの権限が大きければボス個人の選択として帰属することになるだろう。その場合は、実行犯の行為は、選択の余地のないものとして主体性のない「体験」として分類されるというわけだ。「行為」と「体験」を、その選択の帰属先を決める機能を持つものと把握することによって、コミュニケーションの連鎖を捉えることが出来る。論理の展開に役立つ概念となっているのではないかと思う。この「行為」と「体験」の概念は、社会における何らかの行為における責任の問題を考える上で役に立つ概念ともなるだろう。それが逸脱行為という、社会の秩序を乱すような行為であれば、その責任を追及して正すことは社会の秩序維持にも貢献するだろう。正しい判断が秩序のためのコミュニケーションのループを作るなら、社会学の発想が社会に貢献することにもなるだろう。最後に宮台氏は文脈の問題を提出している。これは、行動として同じものに見えても、その文脈によって意味が違ってくる、違う「行為」となるものの問題だ。これは、それが逸脱行為にあたるものなのかという意味の了解において重要になってくる。逸脱行為なら、その責任が誰のものであるかという「行為」の帰属先が問題になる。しかし、それが逸脱行為ではなく、文脈から理解すれば当然のことであったり、止むを得ないアクシデントだったりすると了解できる場合もある。この場合は、「行為」の帰属先がどこであろうと、その責任を問うことや非難することは間違いになる。文脈の問題は複雑な現代社会で生きる我々には深刻で重要な問題になると思う。この後説明される「役割」という概念と関連させてよく考えてみたい問題だ。
2008.07.19
コメント(0)
-
「社会統合」の概念
宮台真司氏が「連載第十二回:社会統合とは何か?」で解説するのは「社会統合」についてだ。これは、「社会」の「統合」について説明しているものと考えられる。この二つのうち「統合」のほうは「二つ以上のものを合わせて一つにすること」と辞書的には説明される。この言葉に特に専門的に特別な意味は含まれていないように思われる。しかし「社会」という言葉には、その視点の違いによってさまざまな異なる見え方があるように思う。その見え方の違いによって「社会統合」の概念が違ってくるだろう。「社会」というものをどのようなものとして見るかで、その「統合」すなわち「何によって構成されているか」という、何が合わさって一つの「社会」という存在が見えているのかというイメージが違ってくるだろう。仮説実験授業の提唱者である板倉聖宣さんが、社会科学について語るとき、社会というものの難しさは、個人の感覚がそのまま拡大して社会の法則性が予測されることがないということだと指摘している。社会は個人の延長として見通すことが出来ない。目の前に見ている事実から、ある種の判断をしても、それは特殊な側面を見ているだけで、社会全体を見ていることにならないことが多いということだ。個人に当てはまることが必ずしも社会には当てはまらない。社会を見るには、全体を把握するための道具が必要で、板倉さんはそれを「統計」というものに見ていた。板倉さんが論じた社会の法則に「道徳」と「法律」の問題がある。「道徳」というのは、個人にとってそれを守ることがよいこととされる規律のことだ。それは時に破られることがあるが、それを守るという意志は、あくまでも個人の倫理観という主体性に委ねられている。それを破ったときに、社会的な非難の目を浴びるかもしれないが、実質的な懲罰を受けることはないのが「道徳」だ。それに対し、「法律」を犯した時は、強大な権力によってその罪に対応した罰を受ける。ある種の強制的な力によって守らせるというのが「法律」にはある。法律は、社会全体の意志に関わっているものとして捉えられる。道徳的に正しいものを法律にした場合、社会はどのようになるかを考察したものが板倉さんの『禁酒法と民主主義』『生類憐れみの令』という授業書だ。どちらも道徳的には正しい主張なので反対することが難しい内容を持っていた。しかしそれが法律化されることによって社会には大きな混乱がもたらされた。「禁酒法」のほうは民主主義的な手続きによって、「生類憐れみの令」のほうは一人の権力者の命令によってできたという違いはあるものの、どちらもその法律が守れなくて困る人を多く出してしまった。この法律の混乱は、法律がなければ、道徳として主体的に「禁酒」も「動物愛護」の精神も守れたかもしれない人が、この法律によって守れなくなってしまうという皮肉な結果、つまり法律があることによって道徳的な退廃が起こるという、目的とは逆の結果を招くということがもたらされているように感じる。ここに、個人の法則と社会の法則の大きな違いを感じるものだ。板倉さんは、「規則を増やせば違反者が増える」という格言も語っているが、このような感覚こそが社会を見る目を育てることになるだろう。規則を作ることによって道徳的な意志を貫徹しようと思っても、守ることが難しい規則ならば、かえって違反者が増えて道徳性は退廃する。規則(法律)というのは、道徳のように「善きこと」を述べるのではなく、最低限これだけは守るという合意の下に作られるべきものになるだろう。それが社会の法則だということだ。さて、このように個人とは違う社会というものの全体性は、個人をただ寄せ集めただけの集団(集合)が社会だという「統合」のイメージではまったく分からなくなる。そのような「社会」のイメージは、こうであってほしいという期待を裏切る混沌としたものになるだろう。どのようなイメージを持てば、単なる個人の寄せ集めではない社会のイメージがもてるだろうか。社会は何が統合されているのか。そのイメージが正しければ、社会に出現する多くの現象を、その意味をもっと深く理解することが出来るようになるだろう。これを論じるのが、この回の講義の目的ではないかと思う。ここの存在(実体)が寄せ集まったものというイメージは、構造の入らない、ものの集まりという性質だけを持った、数学における集合の概念に通じるものだ。社会を個人が集まったものという漠然としたイメージで捉えると、数学的な集合として捉えているという比喩が使えるだろうか。これでは全体性を捉える「社会」のイメージは論理的に導出できない。個々の部分を観察して、個々の要素がどのようなものになっているかという視点しかもてないだろう。全体性の把握が出来ないのではないかと思う。全体性を把握するには、数学においてもその集合に「構造」というものを考えなければならない。たとえば単に数字を寄せ集めたものとして数の集合を考えるのではなく、そこに演算が成り立つことを考えると、演算の構造を数の集合を見る視点として導入したことになる。足し算や掛け算が成立したり、そこでの方程式に必ず解が存在するという構造が見られたりする。数学的には群という代数的な構造を数の集合に見ることになる。これは数の集合を全体として捉えた見方になる。「社会」というものの全体性を見るのも、そこに何らかの「構造」を見ることが必要なのではないかと思う。その「構造」が見えないと、「社会」全体を見ているようなつもりでも、結果的にはある特殊な側面からの一面的な見方をしていることになってしまうのではないだろうか。この「社会」の「構造」は、宮台氏がこれまで語ってきた、「社会」が持っているシステムとしての面に見ることが出来るのではないかと思う。システムは、互いに前提を供給しあう要素がループをなしているという「構造」を持っている。この「構造」を捉えることが、「社会」の全体を捉えることにつながるのだと思う。さて、そうであれば「社会」というものを、何が「統合」されていると考えるかは、そのループという構造をなす要素として何を考えるかということになってくるだろう。ループをなす要素が「統合」されている、そのようなものが寄せ集まって「社会」をなしているという見方が「社会統合」ということの概念になるだろう。「社会」においてループをなす要素としてこれまで提出されたものに「行為」というものがある。これは、ある行為の後に続く行為というものが、ランダムに何でも起こるというものではなく、社会の秩序に従って選択肢が限定されているという観察に基づく。この「行為」の選択の連鎖がループをなすことによって社会に秩序がもたらされ、「社会」の全体性を構成していると考えられる。「行為」というものは、「社会」を構成する要素としては一つの候補になるもので、「社会統合」は「行為」が統合されていると考えることが出来る。しかし、「行為」の選択肢において、それが限定されているのは、動物のように本能的に選択肢が決まっていて、相手の「行為」を刺激として、その反応として自分の「行為」が選ばれているのではない。人間は、意味を通じてさまざまの判断をすると宮台氏は指摘する。相手の「行為」の意味を受け取り、その意味に応じて次の自分の「行為」を選ぶ。この選択に関わって判断の基準として考えられているのは、「予期」というものになる。「予期」があるからこそ「行為」の選択にループの構造が生れると考えられる。そうであれば、「社会統合」は、「行為」の統合というよりも、本質的には「予期」の統合だと考えたほうがいいのではないか。宮台氏の解説はそのような方向になっている。「社会システム理論でも「社会秩序」は行為の織りなす秩序ですが、連載で述べた通り行為の同一性は「どんな行為に後続しうると予期され、かつどんな行為を後続させうると予期されるか」で決まるので、最終的には予期の配列と無関係に社会秩序を記述できません。お気づきの通り、社会統合を「行為の統合」だと見做す立場は、連載第八回で紹介した社会秩序の「合意モデル」と結びつく一方、社会統合を「予期の統合」だと見做す立場は社会秩序の「信頼モデル」と結びつきます。社会システム理論は、もちろん後者です。」と宮台氏は語っている。この解説の後半部分は、論理的な理解はやや難しいのではないかと思われる。「行為の統合」がどのような論理展開で「合意モデル」と結びつくかがすぐには浮かんでこないからだ。社会の要素が「行為」だと考えた場合は、「行為」と「行為」が選択の連鎖で結ばれているときに、その選択の仕方は、こうなるだろうという「予期」の判断よりも、こうなっているはずだという「合意」を前提として「行為」が選択されると受け止められるのだろうか。「社会統合」を「行為の統合」だと見なす立場は、「予期の統合」を排除する立場として提出されるのだろうか。もしそうであれば、「予期」を排するということから、「こうなるだろう」という判断が排除され、したがって「こうなるべきだ」という「合意」が前面に出てくることになると考えているのだろうか。「予期の統合」は、これから起こるであろうことの判断について「こうなるだろう」と思うことになるから、それは「信頼モデル」と結びつくというイメージが納得できる。しかも、「こうなるだろう」という「予期」の判断が、第三者がそう思うはずだという「制度」と結びつけばその信頼性は高まり、ループとしての繰り返しはより強まっていって、社会の秩序は安定したものとなることが了解できる。逸脱行為に対する対処の仕方、それが社会の秩序を壊してしまうかどうかという判断においても、「合意モデル」か「信頼モデル」かで大きな違いがあった。合意モデルでは、逸脱行為が合意そのものを壊すと判断されるので、これは秩序の破壊として深刻に捉えられる。しかし、信頼モデルでは、それはたまたま信頼が裏切られた例外的行為であると受け止められ、信頼そのものはまだ保たれていると判断されることもありうる。信頼モデルでは信頼そのものが壊れた、つまりその逸脱行為が例外的なものではなく、それが定常的なものになってしまったという認識にならない限り、システムのループが壊されたとは考えない。逸脱行為に対して、それにすぐ反応してパニックにならずにすむ。免疫性を持つことが出来る。その逸脱行為の現象から、何かを学ぶという姿勢が、信頼モデルの社会の場合には導き出せる。この信頼モデルの学習については、「真理システム」と「法システム」というまた興味深い概念があるようだが、これは後で詳しく語られるらしい。いずれにしろ、予想外の出来事に接したときに、感情的に混乱してしまってパニックになるよりは、そこから何かを学んで、今後そのような予想外の逸脱行為が生まれないようにするほうが社会にとってはいい方向のように思われる。そのためには「合意モデル」より「信頼モデル」のほうが有効になるだろう。したがって、「社会統合」の概念を、「行為の統合」ではなく「予期の統合」としてみる見方を自分のものにすることが重要ではないかと思う。この見方は、感情に流されて現実を見るのではなく、論理の展開からこれから起こるであろうことを正しく予想させてくれるものになるのではないだろうか。概念が思考に与える重要性を感じるものだ。概念を持つことによって現実を論理的に把握できるようになる。現実をじっと眺めたからといって、その概念が自然に自分の中に生まれてくることはない。概念(言葉)によって現実世界を切り取って理解するというソシュールの言い方が、実感として正しいのだという経験が出来るのではないだろうか。
2008.07.18
コメント(0)
-
機能的側面から見た「制度」の概念
宮台真司氏が「連載第十一回:制度とは何か?」で語るのは「制度」という言葉の概念だ。これの辞書的な意味は、「社会における人間の行動や関係を規制するために確立されているきまり」というもので、「ルール」という言葉で言い換えることの出来るものだろう。ルールは、明文化されているものもあるが、ある種の表現で語られるものという実体的な側面を持っている。この辞書的な概念は、そこに制度があることを判断するために観察に用いるのは便利だ。人間の行動がある種のルールに従っているように見えるところで、そのルールが個人的なものではなく、社会全体に行き渡っているように見えれば、そこに「制度」が存在することが分かる。そして、その従い方を観察すれば、具体的な「制度」の中身も観察することが出来る。観察という行為において、実体的な概念は、観察したものがそれであるかどうかという判断に役立つ概念になる。しかし、実体概念は、それがどのような論理展開で変化していくかを見るのはなかなか難しい。実体というのは、もともと変化しない固定的な姿をしているから実体として捉えることが出来るものだからだ。実体面を見ている時は、その対象は変化せず同じものにとどまる。論理が展開する様子を反映してくれない。それに対し機能的な側面に注目して概念を作ると、機能は関数的に他の対象に作用して、そこに何らかの変化をもたらす。「意味」の時は、その「選びなおし」や「否定性」という機能に注目して概念化した。これが、意味の選択の変化を呼び、選択接続という意味でのコミュニケーションの流れにつながってくる。そのコミュニケーションの連鎖が、システムとしてのループになっているかで、同じ選択に戻ってくるというシステムの秩序に結びついてくる。論理の展開が、システムの秩序を考える思考の展開として現れてくる。宮台氏が語る「制度」という概念も、この前の回の講義と関連していて、「予期」という概念を論理的に展開しようとするときに、「予期 」の秩序と結びつくものとして「制度」の概念が登場してくるという関係になっている。「制度」の機能が、「予期」のコントロールに結びつき、それが「信頼」の基礎になって秩序が維持されるという論理の展開が出来るような概念となっている。「制度」という言葉の機能的な側面に注目した定義は、「「任意の第三者の予期」について私が予期を抱いている状態のことです」と宮台氏が語るものだ。これはたいへん分かりにくい表現だ。特に、「制度」について辞書的な意味を理解している時は、この定義のどこにも「きまり」という言葉が現れないので、これがどうして「制度」なのだという気持になってくる。「任意の第三者の予期」が「制度」だと言うならまだ、それが社会的なものであるというイメージが湧いてくるが、「私が予期を抱いている状態」が「制度」だと言われると、それは何か社会性が薄れてしまったような気もしてくる。この分かりにくい概念を、具体例を用いて説明すると次のようになる。「例えば「警察制度がある」とはどういう状態でしょうか。「お巡りさんに訴えれば何とかしてくれる」と私が思う状態? 否。それでは単なる思い込みです。そうでなく、「お巡りさんに訴えれば何とかしてくれる」と皆が思うはずだと私が思う状態であるはずです。例えば仮にお巡りさんに訴えても何もしてくれなかったのなら、私は単に個人的に憤ったり納得したりするのではなく、皆の思い──任意の第三者の予期──を裏切る振舞いだとして私は皆に訴え、社会的反応を惹起しようとして騷ぎまくれる。それが「制度」です。むろん「制度」もまた別の自明性です。しかし特定の相手とのコミュニケーションの履歴が醸し出す、特定の相手に限定された自明性では、ありません。むしろ別次元の自明性を樹立することで、元の自明性を免除する機能を果すのです。」みんなが思うということに社会的な面を見て、そのみんなが思うということを私が「予期」として抱いている状態こそが「制度」と呼ばれていると宮台氏は指摘している。この状態というのは、私が、ある種の期待はずれを感じたときに、その期待はずれを問題として解決してくれるような方向へと社会を動員する機能を持っている。宮台氏は、例で「お巡りさんに訴えても何もしてくれなかった」という問題が生じたときを考えている。このとき、「お巡りさんに訴えたら何かをしてくれる」という私の「予期」は、私がそう思って訴えているということをおまわりさんに「予期」させて行動させるということに失敗したわけだ。私はお巡りさんの「予期」のコントロールに失敗したとも言える。このとき、社会は秩序を失ったものとして私の目に映るだろう。このような状態のとき、社会が秩序を失ったのではなく、そのお巡りさんがたまたま間違えていたのだと思えれば、私の「信頼」はまた回復する。社会は秩序あるものとしてまた私に映ってくる。私の個人的な思いだけでは、私が憤って訴えても、それを無視されたときに私が正しいという自信が失われてしまうかもしれない。だが、私の個人的な思いではなく、他者もみんなそう思うのだという確信があれば、その訴えを聞かない相手のほうが間違っていると、断固とした自信を持てるだろう。この「制度」の概念は、そのような機能を持っているという論理展開が出来る。この「制度」は、コミュニケーションの履歴から、他者の「予期」をコントロールしようという手間を免除させる。「制度」が存在すると確信できれば、相手がどのような振舞いをしようとも、その「制度」を頼りに自分の訴えのほうが正しいということが論理的に帰結できる。コミュニケーションによる努力をしなくてもよいという機能が、この「制度」の概念からは帰結する。「制度」というものが社会の秩序を維持するのに役立ち、「予期」のコントロールという機能を持っているという考察は、上のような「制度」の定義から導かれる。だからこそ宮台氏は、普通はあまり表現されない、上のような形の「制度」の定義を採用したのではないかと思う。上のような「制度」の概念の下で、それがもし失われた時はどうなるだろうかということを想像するのも興味深い。それはカフカが描いたような不安と不条理の世界を想像させるような気がする。みんながそう思うはずだと「予期」して、自分に対する不当な扱いを訴えようとしたカフカの主人公は、みんながそう思っていないことを見せられて自分がどう考えていいかまったく分からなくなってしまう。そこには「制度」が存在していなかった。「制度」が存在しない世界で、他者の「予期」をコントロールするには、個人的なコミュニケーションの連鎖でそれを相手に伝えなければならないが、カフカの主人公はそれにもすべて失敗しているようだ。カフカの主人公たちは、「予期」がまったく利かない不条理な世界に生きている。カフカは、来るべき大衆社会というものを、よく見知ったなじみのある仲間との生活をする社会ではなく、見知らぬ・何をするか分からない・「予期」のコントロールの出来ない人々に囲まれて暮らす社会だと想像したのかもしれない。この中で「制度」的な「信頼」を調達できなかったときに、いかに不条理な世界で生きることになるかを知らせているようにも思う。逆に言えば、「制度」が確立していれば、そこにはまだ秩序があり「信頼」があると言えるのではないかと思う。「制度」には、「予期」のコントロールの免除という機能とともに、期待はずれが起きたときにもパニックにならずに自分の正当性を主張してそれを通すことが出来るという機能もある。カフカの主人公のような不条理な目に会わなくてすむ。このことは、期待はずれへの対処の仕方が保証されているという余裕をもたらし、期待はずれが起こったときにもそれをやり過ごせるという「免疫性」をつけることにもなる。そのあたりのことを宮台氏は次のように書いている。「先に「二重の偶発性」についてこう言いました。私が他者がどう振舞うかとビクビクしないのは、価値合意によって他者の振舞いが決まっているからでなく、他者の振舞い次第で私がどう振舞うかについての「他者の予期」の操縦可能性に、私の注意が向くからだと。それに即せば、「制度」──「任意の第三者の予期」への予期──の存在によって、他者の振舞い次第で任意の第三者がどう振舞うかについての「他者の予期」を、自動的に当てにできてしまうので、私は「他者の予期」をわざわざ操縦する必要を免除されるのです。加えて、営々と築き上げた個人的関係の自明性が支える予期が破られた場合とは異なり、「制度」の自明性が支える予期が破られても──例えば皆の期待を無視して猫肉バーガーを出した場合でも──、社会的支持を当てにできる分、パニックにならずに済むのです。」「制度」というのは、大衆社会になった近代においては、非常にありがたい存在で、そのメカニズムはとてもうまく作られているのが分かる。秩序の維持には必要不可欠なものとなるだろう。この秩序が大事だと思う人間は、それを維持する機能を持つ「制度」が壊れないように配慮したくなるだろう。このことを価値観抜きに受け止めれば、「制度」というのは、秩序維持のための働きを持つもので、それが近代の大衆社会の「信頼」を生むと考えられる。「制度」というのは大衆社会において、「信頼」と秩序が存在するところにはどこにでも見つけることが出来る。宮台氏も、「ここでいう「制度」には、法制度や政治制度のように統治権力の正統性や物理的実力を担保とするものもあれば、習俗や道徳のように慣習的伝統を背景とするものもあれば、仲間内のルールのように面識圏の合意を背景とするものもあり、大きな外延を持っています」と語っている。「制度」がもたらす秩序を足かせのように感じてしまう人もいるかもしれない。そのような人にとっては、秩序の破壊こそが自由をもたらす価値あるもので、そのためには「制度」の破壊が必要だと考えるかもしれない。「制度」の維持を願い、それが守る秩序をよいものだと考えるのは、保守的な思想ということになるだろうが、それが正しいか間違っているかは微妙な問題だ。そうすっきりと答えを出すことは出来ないだろう。かつて日本にあった家制度は今ではほとんど消えてしまったようにも見える。それはある種の自由に対する足かせであったことは確かだったろうが、「家制度」がなくなると、それによって守られていた秩序や安心はなくなってしまう。それがすべていらないのだと考えるのは難しい。むしろ大切な秩序は、「制度」がなくなった後にも、別の形(他の「制度」など)で守る必要もあるのではないかと思う。そのように感じる僕は「保守的」になったのだなと思うが、これは、年をとって世の中が見えてきたからではないかと思っている。「制度」については、その存続の評価を客観的に行うことが出来ればと思う。それが今は存在していることの合理性と、やがては消えてしまうことの必然性が理解できればと思う。
2008.07.16
コメント(0)
-
「偶発性」の概念とそれが二重であることの理解
宮台真司氏が「連載第十回:二重の偶発性とは何か」で説明するのは「二重の偶発性」というものだ。ここで語られている「偶発性」という言葉は辞書的な意味に近い。それは基本的には「必然性」に対立するものとして理解される。宮台氏の言葉で言えば、可能性としては他のものでもあり得たのに、たまたま(偶然)そのようになっているというような現象が起こっているのを「偶発性」と呼んでいる。現実の我々の世界は「偶発性」に満たされている。必然性を洞察できる科学的真理もあるが、それは特定の対象にのみ適用できるもので、大部分は偶然そうなっているとしかいえないだろう。この偶発性に対して人間は意味の機能を用いてそれを理解しようとする。宮台氏は「偶発性に対処して選び直しを可能にする、否定性をプールする選択形式」を意味の機能として捉えて、我々の世界理解を説明している。現実には否定された他の可能性を選びなおすという機能を通じて我々はいま目の前にある世界を理解しようとする。我々の思考が論理の展開などというものを経ずに、目の前の現象を単純に受け止めて、それを刺激として反応するだけであれば意味の機能は必要ない。本能的な対応のメカニズムがあれば十分だろう。しかし人間は単に刺激に反応するのではなく、意味を経由して現実に対処する。これが過去の記憶からの学習や、未来の予測からの「予期」を形成するきっかけとなる。意味の概念から選択の持続の理解が生れ、それが過去や未来の概念を生み、人間の世界認識が深く広くなっていく変化をもたらす。この思考の展開において、他者の経験を自分のものにするというコミュニケーションも生れ、その過程で言語というものも生れてきたのではないかと想像される。この認識の広がりを持った人間が生き残りには有利になったのではないかと思われる。現在の人間が意味や予期といった機能を駆使できるのも、このような生き残りの結果として持続された能力ではないかと思う。さて宮台氏は、「意味を用いて、いちいちサウンドせずに世界を無根拠に先取りする営みが、予期です」と語っている。意味というのは、ある種の現象が起こった後に、事後的にそれを解釈して受け取るものだ。そしてその際に、「選びなおし」の可能性をプールし、選ばれなかったほかの意味を「否定性」としてプールしておく。予期は、まだ起こっていない未来を予測してその意味を先取りしておこうとするものだ。対象の必然性を洞察できるのであれば、この未来の先取りは確実に予測どおりになる。予期は期待通りの事実になる。しかし、現実の大部分は「偶発性」を持っているので、予期の大部分も「無根拠な先取り」にならざるを得ない。この「予期」が信頼というものを基礎においていれば、他の可能性は思考の外に置かれ、選びなおしの可能性も忘れ去られてしまわないだろうか。これはかなり危険な勘違いを呼び、失敗をする可能性を高くしないだろうか。しかし、予期の段階で意味を深く追求していたら、否定の可能性が気になって次の一歩の行動が取れなくなる恐れもある。こんなことをしたら期待通りにならないのではないか、ということが気になると、被害妄想的になり何をしても失敗しそうな感じがする。以前にうつ病の診断を受けたときのことを思い出すと、運転していた時にそのような感じを強く持ったものだ。他の車がすべて自分の邪魔をしているような強迫観念がぬぐえなくて困ったものだ。「信頼」というものがまったく出来なくて、次の運転が他の車の否定的な反応を呼び起こすのではないかという負の「予期」のほうが生れて、運転をすることが苦痛になっていた。今ではよほどのことがない限り、他のドライバーも安全運転をしているのだということを信頼して運転することが出来る。自分がそうできるのだから、大部分の人もそうできるのだという「信頼」を、根拠はないが抱いている。このようなものがあるので、複雑で「偶発性」に満ちている現実においても、一定の秩序を形成した行動を社会全体が取れるのだなと感じる。この秩序は、いったいどのようなメカニズムで保たれているのだろうか。これが今回の講義のテーマである「二重の偶発性」の問題であり、その処理をうまく果たすことが秩序の維持につながっていると言えるのではないだろうか。現代社会は、この問題を解決するシステムを持っている。だから秩序の維持ができるのだという論理的な理解になるだろうか。それでは、どのようにしてこの問題を処理しているのだろうか。具体的にはどのような姿が見えてくるだろうか。パーソンズ流の「価値共有による秩序問題の解決」に対しては、「ホッブスによる秩序問題の解決案と同じく、秩序のありそうもなさを、価値共有のありそうもなさに移転しただけで、解決と呼ぶには値しません」と宮台氏は指摘している。「信頼」という価値観があらかじめ確立していて、それに従っているから「二重の偶発性」が処理できていると考えるのは現実的ではないということだろう。現実には、価値観は多様であり、合意がないものが多い。それでも「信頼」が崩れないのはどうしてなのか。ルーマンによる解決を語った部分では、「偶発性の消去から、偶発性のやり過ごしへ」という言葉で宮台氏は語っていた。偶発性は消去できないと考えられているようだ。これは、現実の出来事のすべての必然性を悟ることは出来ないとも言い換えることが出来るだろう。だから、偶発性を消去するような努力は結果的には失敗する。偶発性は消去するのではなく、「やり過ごして」それが不安につながらないようなメカニズムを持つことが秩序を維持する処理の仕方になるということになるだろうか。このあたりの複雑な構造の理解には、宮台氏の次の文章が参考になるだろう。「パーソンズとルーマンのスタンスの違いを十分理解しましょう。一般に、私の行為と他者の予期(期待)との関係には二つのレベルがあります。第一は、私の行為が他者の予期に合致しているかどうか。第二は、私の行為が他者の予期を踏まえているかどうか。パーソンズは前者を、ルーマンは後者を重視しますが、両者は似て非なるものです。なぜなら、二つのレベルが論理的にズレる可能性があるからです。すなわち私は、他者の予期を踏まえた上で、あえて他者の予期に反する行動を取ることができるのです。パーソンズの場合、こうした振舞いは秩序への侵犯を意味しますが、ルーマンの場合は意味しません。この違いを説明するのに最もよい例は「社交術」です。日本人は社交術を、場の期待(周囲の予期)に合致した振舞いができるか否かのレベルで考えがちです。ところが西欧的な社交術の本質は、私の行為が他者たちの期待に応えるかどうかではなく、私が他者たちの期待に応えうる存在であることを他者たちに示すことで、私が他者たちを受け入れる意思を持つことを示すところにあります。」秩序維持のためには合意が必要だと考えると、その合意が崩れた時点で秩序が壊れたと判断してしまう。しかし、合意ではなく信頼こそが秩序のために必要だと考えれば、予期に反する行為があった場合も、それはたまたまそうなっただけで信頼は保たれていると受け止める「やり過ごし」が出来る。「他者の予期を踏まえた行為」というのは、そのような信頼を基礎にした考え方になるだろう。「社交術」というのは、人間関係を築く技術と呼んでもいいものかもしれない。相手が自分をどう思うかという、相手の持つ自分の行動に対する「予期」を、自分がそう思って欲しいものとして提供する(コントロールする)ことが「社交術」になるような気がする。宮台氏が語るところによれば、日本人というのは、結果として現れた事実が相手の期待通りであるかどうかが気になって、相手の「予期」をコントロールするという面を見ることができないという。だから、自分がまず相手の期待を「予期」して、それにかなうような行動を取ることが人間関係を築く基礎になっていく。これは、限りなく相手に迎合する方向へと向かってしまうだろう。自らの主体性をまったく出せないような「社交術」になってしまう。日本人の社交は、信頼よりも合意を基礎にして考えられているようだ。マナーや儀礼がうるさく言われるのもそのためだろうか。これに対し、外国人、特に社交の歴史の長い西欧の人間はどのような「社交術」を使うかは、宮台氏は次のような例をあげている。「F1のモナコ・グランプリの予選前日(木曜日)にモナコ王室が主催するパーティが開かれます。日本国内ではしばしば「タキシードの着用が原則なのに、日本の記者がフィッシュマン・ジャケットを着用したまま参加するのはミットモナイ」と非難されます。しかし厳密には的外れです。例えばアップル・コンピュータの創業者スティーブ・ジョブズであればTシャツとジーパンで現れるかも知れません。それでもいいのです。なぜなら、皆の期待を熟知した上で「ワザと外す」ことも、社交術の正攻法だからです。パーティのゲームを弁えた上で「ワザと外し」たことをプレゼンテーションできれば、私は自分がパーティに参加するだけの器量を持った存在であることを示し、パーティの参加者たちを受け入れる(ゲームをする)意思があることを示すことができるのです。」「皆の期待を熟知した上で「ワザと外す」こと」が、社交の相手の「予期」をコントロールすることになる。それが「ワザと」であることが分かれば、まともにやろうと思えば出来るのだという「予期」を相手に与えることが出来る。「予期」のコントロールこそが「二重の偶発性」の問題を解決する方法になるということが分かる。宮台氏は次のようにまとめている。「器量があるところを相手に示せれば社交術としては成功で、その上で相手が自分を受け入れるかどうかはもはや相手の問題だというのが、西欧流の誘惑(ナンパ)です。だから相手がなびくかどうかに一喜一憂してビビる必要を免除されるのです。 これらの例に明らかですが、相手の予期を踏まえたとしても、私の行為は本来偶発的です。同じく、私の予期を踏まえたとしても、相手の行為は本来偶発的です。私たちはこれら偶発性に混乱したりしません。私たちの注意が、行為でなく予期に集中するからです。」「予期」をコントロールするには、自分がどの程度の器量を持った人間かを示すことが出来るかどうかにかかっている。それが出来れば、それを相手がどう受け止めるかという「偶発性」はさほど気にするものではなくなるというわけだ。これは、自分の行動を極めて主体的なものにするだろう。まずは自分の思い通りに振舞って、それが自分の器量を表しているのなら、その器量にふさわしい「予期」を相手に与えるだろうということだ。この信頼が、不安を抱かずに自由に行動できるという秩序へ結びつくのではないだろうか。しかし、これは日本人にとってはかなり難しいことではあると思うが。自分が相手にどう思われているかが気になっている人は、社会学が提出するこのような理論を考えてみると安心できるのではないだろうか。
2008.07.16
コメント(0)
-
機能的側面に注目した「宗教」と「他者」の概念
宮台真司氏が「連載第九回 予期とは何か?」で触れていた「宗教」と「他者」の概念についてもう少し詳しく考えてみようと思う。宮台氏は、ここで「宗教」について「宗教とは、前提を欠いた偶発性を、無害化して受け入れさせる機能的装置です」と語っている。ここで言う機能とは、「そのままでは不安を惹起する」「前提を欠いた偶発性を「世界体験」や「現にある社会」からかき集めて、「神」や「英雄」に帰属し、理解と儀式の対象にすることで不安を鎮める」というものだ。この宗教の定義(概念)は、極めて一般理論的な言い方ではないかと思う。あらゆる宗教に対してこの言い方が当てはまり、それは文脈自由なものとして、機能的側面を語りたいときに有効となる。つまり、宗教という概念を論理展開のための道具として使うには扱いやすい概念となっているだろう。しかしこの概念は、一般理論的であるがゆえに、普通の日常用語としての宗教というイメージだけを持っている人には、なんでこれが宗教なんだという引っ掛かりがあるのではないかと思う。日常用語としての宗教は、このような抽象された言い方ではなく、いつでもある特定の宗教と結びついたイメージで語られるのではないだろうか。それはキリスト教であったり仏教であったりするだろうが、宗教というのは、そのような具体性のイメージが普通は強く出てくる概念ではないかと思う。僕にとっての宗教はキリスト教でイメージされる。若い頃に半年くらい教会に通った。もう少しで洗礼を受けて、本物のキリスト教徒になろうと思ったことがあった。遠藤周作の一連のキリスト教に関する作品を読んで、自分なりにイエスが神であるという理解もしたと思っていた。イエスは奇蹟を起こしたから神なのではない。何があろうとも、最後まで自らを信じた人間に寄り添っていたということが奇蹟的なのだと感じていた。残念なことに、教会で出会うキリスト教徒の人々があまりにもいい人でありすぎたので、自分は彼らのように心からの善人になることができないという思いが生れてきて、彼らの仲間に入れないという諦めからキリスト教徒になることを断念してしまった。今の僕はもう信仰を持とうという思いは生れてこないのではないかと思っている。宗教を相対化して見るようになってしまったからだ。だから、いまの僕には、宮台氏が語る宗教の概念はよく分かる。そのように機能に注目する視点を持つことが容易に出来るのを感じている。宗教に対して、主体的に信仰の対象として受け止めている人間は、宮台氏の上記の定義を実感として理解することは出来ないだろう。客観的にそのような機能があることが見えたとしても、それは神がそのような力を持っているから、不安を静めるというようなことが出来るのであって、それを逆転させて、「不安を鎮めるため」という機能のほうが先行するとは考えられないだろうと思う。しかし、客観的な視点を持てば、宗教はそのような機能を持つものとして定義されるのに賛成するのではないかと思う。この定義は、社会の秩序を保つためのループをもたらす装置として宗教の働きを捉えることを容易にする。概念の運用という点で、システムの秩序を理解するための論理を展開できる。この論理が展開できれば、宗教という装置が利かなくなった時代に、それがいままで担っていた秩序の維持という機能は、果たしてどのようになるのかという論理の展開を考えることが出来るだろう。宗教を主体的に感じて生きることはすばらしいことだと思う。それは気持の高揚と幸福感を与えてくれるだろう。しかし、一回宗教を相対化して理解してしまった人間は、もはやそのような主体的な信仰にもどることは出来ない。そのように、不安を鎮める装置としての宗教が死滅したとき、「前提を書いた偶発性」はいかにして、決して解明できない前提を理解したと思えるようにするのにどのような手が使えるだろうか。その場合は、不安の中で恐れることしか出来ないのだろうか。宮台氏が語る社会学の学習が、このような偶発性の必然性の理解をさせてくれるなら、それを受け止めて不安を解消できるようになるだろうか。中途半端な理解では、ますます不安が高まってしまいかねないので気をつけなければならないと思う。宮台氏が語る機能としての宗教は、かつて社会を支配した「イデオロギー」と呼ばれるものにも似たような構造があったのを感じる。「イデオロギー」は、ちょっと考えると合理的な思考によって得られた理論的な結論を、正しいがゆえに信じていたように見える。しかしよく考えてみると、その出発点となる主張は、根拠なしに(証明なしに)信仰のように信じられているだけのものではなかったかと思う。社会はプロレタリアートとブルジョアジーに分断され、真理を獲得したプロレタリアートが社会の支配者となる時代が訪れる、というのはそれが正しいという根拠はどこにもなかった。ある意味では、正しくあって欲しいという願望は強くあったものだろうと思う。しかし、結果的にはこのような願いはかなえられなかった。でもあの時代に、このようなイデオロギーに取り付かれた人間は、このイデオロギーを信じていられた限りにおいては、信仰に生きた宗教者と同じくらいに幸福感をもてたのではないかと思う。人間の生活には、理解できないことや理不尽を感じることは数多い。それが理解できないままに自分に関わってくると、人間はそのような矛盾に押しつぶされてしまうだろう。それに耐えてがんばるためには、根拠がなかろうと、それを説明してくれる宗教が必要だという説明はうなづけるものだ。人間の生活に理不尽がありつづける限り、理解不可能なことがらが存在する限り、宗教も存在しつづけるのだろう。宗教に代わる「イズム」も生き続けるのかもしれない。宗教は、それを真理だと信じているので、そこからある種の「予期」も生れる。「信頼」を持続させるための「予期」を調達するという機能も宗教にはあるだろう。宮台氏は、「私たちにとっての世界は、起こったことや与えられたことの集積ではなく、予期によって構造化されています。世界の大半は確認したことではなく、想像したことによって成り立ちます」と語っていて、現実の社会認識は「予期」によって構成されるということを指摘している。「予期」されることというのは、実際に体験したことではなく、単純に言えば「信じられていること」で構成されているとも考えられる。これも宗教の重要性を語るものかもしれない。この「信じる」ということの中には、他者の経験を自分の経験のように受け止めるということが入ってくる。「他者」の概念も「信頼」と「秩序」という社会の特徴に深くかかわっている。我々は、どうして他者が言うことを信じられるのだろうか。他者が嘘を言ったり、勘違いすることも大いにありうるのに、それを疑うよりも信じるほうが多いように感じる。これはどうしてだろうか。仮説実験授業では、簡単に行える実験や、ちょっと工夫がいるけれども、その学ぶ対象の中心になるような真理を確認する実験は、それを実際に体験することによって科学の真理性を理解しようとする。その実験は、必ずしも自分で道具を操作する必要はないけれども、自分の目で見て確かめるということは必要とされている。実際の体験が真理の確信に大きな影響を与えるということがある。しかし、基礎的なことがらを現実の複雑な現象でも確かめようとすると、大掛かりな実験装置が必要になり、しかも非常に厳密な操作も必要になる場合がある。「物とその重さ」という授業では、せんべいを細かく割った場合でも重さは変わらないということは簡単に実験できるので、このような実験が授業の中に取り入れられている。これは、細かく割ることによって物が消えたように見えても、本当に消えたのでない限り、原子の増減はないということを確認するための実験になる。そのほか、人間の気持が重さに影響を与えないという実験では、体重計に乗ったときに力を込めてふんばっても重さが変わらないというような実験をしたりする。これなどは、体重計を準備するのがやや面倒でも、それをするだけの意義があると理解できれば、努力して実験の準備をすることになる。そのほか、水に溶かした塩が見えなくなって、消えたように見えても原子としては減っていないのでやはり重さは変わらないという実験をしたりする。このような実験のほかに、人間が物を食べて、物がなくなってしまっても、人間の体の中に物の原子がいっしょになっていれば、その合計が体重として計られるというような実験もある。この実験は、実験装置を準備することが困難で、どこの学校でもそれを直接体験することは出来ない。そこで、このような実験は、仮説実験授業では「お話」として科学者がこのような実験をしたという文章を読むことで実験の代わりとする。これは、それまでの実験で原子論の正しさをほぼ確認したと言えるので、子どもたちがそのような文章を読んだときも、確かに体重はものを食べた量を足したものになっているという話を信じることが出来るからだ。学んだ科学に対する信頼が、その話に対する信頼になり、他者の経験を信じるということが出来るようになる。仮説実験授業では、他者の経験を信じる基礎には、その経験が正しいことが、それまでに学んだ科学によって論理的に帰結できるということがあるからではないかと思う。信じるための根拠があるので信じるという感じだ。このような他者の経験の受け止めは納得が出来る。しかし、かなりの部分の他者の経験の受け止めは、あまり根拠を考えずに、何となく信じているようなものも多いのではないかと思う。ある種の権威があるから信じるというものもあるかもしれない。テレビや新聞のニュースを信じるというのは、それらにある種の権威を感じているからかもしれない。他者というのは、自分ではないということが絶対的なものとしてあるので、その経験を直接受け止めることが出来ない。だから、本来なら無条件に信じることは出来ないはずなのだが、かなり単純に信じている現象も見られる。他者という存在の難しさではないかと思う。他者というのは、単純には自分ではないものという概念(理解)になるが、機能的には「その体験を自分の体験のように受け止めて、体験の世界を広げることが出来るような対象」と語れるかも知れない。他者の概念は、日常用語的には単純で、哲学的に考えると決して理解できない難しいものになる。機能的な理解は、その中間にあるような気がする。その機能的な理解は、「信頼」や「予期」を考える上で、概念の運用に役立つような理解になるのではないかと思う。概念や定義というものは、それが指し示す対象の本質を抽象したものとして設定されるというイメージが以前の僕にはあった。そうでなければ、学問的な考察に値する対象にならないのではないかという気がいていた。しかし、それを実体的に捉えた場合は、それを解釈することに重点が置かれていくような気もしている。実体は観察できるので、どうしてもそれを捉えるときに解釈をするということに傾きそうだ。実体よりも機能に注目するというのは、論理として展開するということでは役立つのではないかと思う。機能は道具としては実体よりも役に立つのではないかと思う。宮台氏が語ることに、機能的な捉え方が多いのは、そのような理由によるのではないかと僕は感じている。
2008.07.15
コメント(0)
-
信頼の本質としての「予期」の概念
宮台真司氏が「連載第九回 予期とは何か?」で語る「予期」という概念を考えてみたい。この回の講座では「予期」のほかにも重要な概念がいくつか提出されているのだが、まずは「予期」という最重要な概念について、その明確なイメージをつかむことに努力してみようと思う。この「予期」はもちろん社会学という学問における専門用語で術語と呼ばれる学術用語になる。したがって、日常的に使用する辞書的な意味を持つ「予期」とは概念が違うだろうと予想できる。いつものように辞書的な意味をはっきりさせて、それをさらに抽象して、システムを考える上での「信頼」をより明確にさせうるような概念として「予期」というものの本質的な意味をつかんでみようと思う。「予期」を辞書で調べてみると、「前もって期待すること」と書かれている。まさに文字通り「予」という言葉を「予定」「予想」などに使われている「あらかじめ」「前もって」などという意味で解釈し、「期」という言葉を、「期待」という意味で解釈している。辞書的な意味は、「信頼」のときもそうだったが、やはり個人が持っている認識との関連でイメージされているように思う。「前もって期待する」というのは、個人の心の働きとしてそのような現象が想定されているように感じる。これを社会学で取り扱う概念として利用するには、個人ではなく、社会における「予期」として概念化する必要があるのではないかと思う。「前もって期待する」という言い方では、社会におけるものという感じがしない。それは、個人によって違うものが期待されてしまうような気がするからだ。このように曖昧であやふやなものが社会における「予期」だと考えてしまうと、それを論理の出発点として論理を展開しても、その結論も曖昧であやふやなものになってしまう。社会における「予期」は、個人的にそう思うというものではなく、ある程度客観的に、誰もがそう判断できるというものでなければならないだろう。そういう客観的なものとしての「予期」が、現に社会に存在する「信頼」と関係してくるのではないだろうか。社会にある種の「信頼」が存在するなら、その「信頼」が「予期」を形成する根拠となると考えられるのではないだろうか。この「予期」は、個人的にそうなって欲しいとかいう思いで期待するものではなく、そこに「信頼」があるので、「信頼」を信じている人間なら誰でもそのように期待するという「予期」になっているのではないだろうか。宮台氏は、「信頼は、むろん予期の一種です」と語っている。この意味は、「予期」というものが個人的なものも社会的なものも含んでいる概念であるけれど、社会的なものの一つとして「信頼」というものが「予期」として存在するのだという意味なのだと思う。「予期」というのは、個人の場合は単なる思い込みからの願望としての「予期」もあるだろう。そうなるかどうかは分からないが、ぜひそうなって欲しいという願いとしての「予期」だ。しかし、必然性の洞察が出来る人間は、その必然性から求められる結論に従った、ほとんどそれが起こるだろうことが確実であるような「予期」を持つだろう。板倉さんの「科学」概念でいえば、100%そうなることが期待できる予想を持つということになる。個人の場合の「予期」は、その個人がどの程度の世界の法則の必然性を認識しているかで、「予期」の段階が分化していくような気がする。社会において、「信頼」がもたらす「予期」というものは、「信頼」が根拠のないものとして捉えられていたので、そこに必然性の洞察があるとは考えられない。それが循環的に繰り返されてきたので、今度もそうだろうという根拠のない予想が立てられているだけだ。この必然性を欠いた「予期」は、まずは二つの層に分けて捉えられる。宮台氏は、「議論の対象を明示すべく簡単な分類学から始めます。予期には「死なないと思う」という積極的なものと「死ぬことを考えたこともない」という消極的なものがあります。積極的な予期には「だろう」という認知的なものと「べきだ」という規範的なものがあります。 信頼は二つの予期層からなります。最初は「刺すとは思わない(考えたこともない)」という消極的予期があります。未分化な予期層とも言います。社会システム理論ではこの段階を、自明性と呼びます。単純な社会では、自明性だけで信頼の大部分を調達できます。」と書いている。消極的・積極的という二つの層に分けられた「予期」としての信頼は、選択領域がないことが結果として自由の欠乏感を生まなかったという考察に似ている。「考えたこともない」という対象は、それの存在が認識の中に入ってこないので、それが「あるのではないか」という思いが生れず、不安というものを生まない「予期」になっているのではないかと思う。消極的という言葉は、何か余りよくないというイメージが浮かびそうだが、「予期」に関しては不安を生まないという幸せな状況をもたらすような気がする。ただ、その幸せは「知らぬが仏」ということわざで語られるような幸せで、単純な社会における「自明性」がもたらす幸せだといえる。複雑化した社会に生きる我々は、このような幸せを求めたくても、もはや手に入らない幸せになるだろう。我々の「予期」は、もはや消極的なものにとどまることが出来ず積極的なものにならざるを得ない。ということは、それまでは「考えたこともない」ことを考えざるを得ず、そのことから不安に苦しめられることになる。この不安を鎮めるための次の段階の「予期」は、認知的・規範的という、これもまた二つの層として考察される。不安というのは、そうあって欲しくないという損害を与えるような「予期」からもたらされる。この「予期」がもたらす不安を静めるには、その損害が避けられるものであるという「予期」を構成して安心感をもたらす方法がある。損害を避けるために取られる方法の一つが、認知的な方向を持つもので、合理的思考によって避ける方法を考えようというものだ。これはそれを避けるための必然性を洞察することで、避けることの「信頼」を高めることが出来る。その「信頼」が不安を鎮めることになるだろう。もう一つの規範的な方向というのは、不安をもたらす「予期」に対して、「そうすべきではない」という規範を社会に確立することを目指すものだ。人々がそのようなことをしないという「予期」を持つことによって、そのようなことがあるかもしれないという可能性を低める方向を取る。規範的意志の貫徹というような言葉で宮台氏が語ることもあるこの方向は、法的な意志の貫徹を強く主張するもので、犯罪に対する厳罰化の方向などがこれに入るように思う。「「だろう」は、違背に際して適応的に学習する構えがある予期です。すなわち当てが外れれば賢くなる方向で学ぶという態度と共にある予期です。「べきだ」は違背を学習せずに、予期に合わせて現実を変える構え──予期貫徹の構え──のある予期です。 違背可能性が意識される当初は、「考えたこともない」との消極的予期から「刺すこともありうるが刺さないだろう」との認知的予期に移行します。違背が現実的になると、更に「だろう」で構えるのか「べきだ」で構えるのか、予め態度先決されるようになります。」と宮台氏はまとめている。「予期」という概念のこのような機能的側面は、「予期」という概念を運用して思考を展開する際に、演繹的な方向を明快に示してくれているように感じる。概念を機能的に捉えるというのは、「意味」の概念のときにも感じたのだが、概念の運用という思考(論理)の展開においては重要な理解のしかたになるのではないかと思う。上の文に続けて宮台氏は、「個人から見ていろんなことが起こりうるという意味で複雑な社会──多様で流動的な社会──では、自明性だけでは信頼を調達し切れません。むしろ違背の可能性を意識しながらも、それでも前に進めるように、分化した予期層で信頼を調達する必要が出てきます。 単純な社会の自明性と区別される、複雑な社会における分化した予期層における信頼が、どんな形を取るのか。これを語るにはもう少し準備が要ります。いずれにせよ個人から見て複雑な、複合性の高い社会での信頼を考えるには、予期とは何かを知る必要があります。」とも書いている。現在の複雑な社会を分析するには、「予期」という概念が必要不可欠であり、その概念運用には、機能的な理解が重要だと語っているように僕には感じる。宮台氏は、この後に「世界」「社会」「現にある社会」というものについて説明を展開している。この3つの対象に対しては、それを辞書的に解釈するのではなく、新たな概念として理解する必要を感じる。宮台氏は、「ありとあらゆるもの全体」を「世界」、「ありうるコミュニケーションの総体」を「社会」、「現にある秩序(ありそうもない状態)をなすコミュニケーションの総体」を「現にある社会」と呼んでいる。「世界」や「社会」においては、考えられうる「すべて」の対象が含まれているので、そこには「予期」が存在しない。すべての起こりうることを「予期」するというのは、何も「予期」していないことと同じになるからだ。「予期」が問題になるのは、「現にある社会」であって、そこに構成されている「信頼」が人々に「予期」をもたらす。「現にある社会」は、現実にそこにある具体的な社会を指すが、「世界」や「社会」は抽象的な概念で、現実のものではない。それは「すべて」に言及しているからだ。もし「世界」についても、現に我々が目にしている限定された、我々の周りの「世界」を考えると、「社会」に対する「現にある社会」と同じような構造が見えてくる。宮台氏はそれを「偶発性」という言葉で語っている。あらゆる可能性を含んだ「社会」が「現にある社会」として実現されているのは、たまたまそうなっているからであって、必然性がないという意味で「偶発的」だ。同じように、ありとあらゆるものを含む「世界」に対して、現に我々の周りにある「世界」は「すべて」を含んでいないので、現にある「世界」はその存在は「偶発的」だ。「偶発性」という概念も、このように考えると重要なものであることが分かる。この回の講義では、この他に「前提を欠いた偶発性を、無害化して受け入れさせる機能的装置」としての「宗教」の概念についても言及されている。この概念も辞書的な、実体的な意味としての宗教とは違い、あくまでも機能的な、概念運用に便利なように考えられた概念のように感じる。また「体験地平の拡大」という機能をもたらす「他者」という概念もこの回で語られている。この「他者」の概念は、三浦つとむさんの「観念的な自己分裂」の問題や、ウィトゲンシュタインの「他者」の概念にも通じるようなものでたいへん興味深い。これらは、「予期」とは独立させてもっと深く考えてみたい概念だ。
2008.07.15
コメント(0)
-
社会における「合意」と「信頼」(個人の場合とどう違うか?)
宮台真司氏は「連載第八回 社会秩序の合意モデルと信頼モデル」では、「合意モデル」と「信頼モデル」という考察で、社会が持つ秩序(確率的に低い状態が実現すること)の出発点となるものを考えている。社会が定常性という秩序を持つのは、ある種の状況の変化が特定の選択肢をめぐってループする関係にあるものとして、特定のものが現実化することによって確率的に低い状態が定常的に維持されるからだと考えるのがシステムの考え方だと僕は理解した。このループは、そのどの状態が出発点になろうとも、ループである以上は、いったんその流れが生じれば安定的に定常性を保つようになる。だから、ある意味ではどこが出発点でもかまわないのだが、論理的な整合性が理解できる出発点として「合意」と「信頼」というものが想定されているように感じる。内田さんが語る構造主義では、現実の社会がどうなっているかは、現実のそれを観察することで解釈できるが、それがなぜそうなっているかという出発点は決して知りえないものとして、こうなっているからそうなのだとしか言えないものとして提出されていた。ただ、原理的には決して解明できないものの、その出発点としての「零度」の探求が構造主義であるとも語られていた。これは、フィクションとしての、数学で言えば公理のようなものを設定して、論理の展開のために便宜的にそう考えてみて、もしそれで論理的整合性が取れるなら、そのようなものを「モデル」として設定することで、現実の一側面の理解を深めようとしているように思われる。宮台氏がここで語る「合意モデル」と「信頼モデル」も、そのようなフィクショナルな設定がその後の論理展開をするための道具として提出されているように思う。だから、このような単純な対象がそのまま現実の複雑な社会に存在すると理解してしまうと間違えるだろうが、その捨象した部分と抽象した部分を具体的に意識し、その捨象と抽象の範囲で現実がよく反映していると思われるような現象の判断を厳密に考えれば、現実の社会についての理解に役立てることが出来るのではないかと思う。宮台氏が「合意モデル」の典型として提出するのは、ホッブスが主張するところの「自然権の譲渡」の合意が社会秩序の出発点に置かれるものだ。「自然権」というのは、「人が生まれながらにして持っているとされる権利」で、これを無条件で行使することが許されると、自分の利益のために行動することが一つの自然権の行使になり、「万人の万人に対する戦い」が生じたりする。この戦いは、自然権をそのまま放っておけば、常にこの戦いに備えなければならず、かえって自然権の行使がままならなくなる。だから、一人の巨大な権力を持った人間にその自然権を譲渡して、万人は自然権の行使の制限を受け入れるほうが、平和で安全な社会が築けるということに合意して、それを譲渡することを出発点として社会の秩序が形成されたと発想する。このような想像上の社会をモデルとして現実の社会を考えようというのが「合意モデル」という考え方になる。宮台氏に寄れば、この考え方は現在では否定されているという。宮台氏は次のように書いている。「今日的な社会システム理論は絶対にそうは考えません。社会の秩序の出発点には(自然権譲渡などへの)合意があるという思考。これはしかし、秩序のありそうもなさを、合意のありそうもなさと転送しただけで、合意自体がありそうもない以上、解決になりません。」僕も、現実の社会が合意によって形成されたというのは、解釈としては論理的整合性が取れるかもしれないけれど、それは大事な点が捨象されているような気がする。「合意モデル」の「合意」というのは、個人の「合意」をそのまま社会の「合意」に単純に広げてしまっているように感じるからだ。ホッブスの言うような「合意」は、社会によって合理的な考え方が出来るように教育された個人が、よく考えた上で出す結論として合意することの出来るもののように思われる。つまり、すでに社会の秩序が確立されている状況で生きている個人が出来る合意であって、社会が誕生する出発点の段階で出来る合意には見えない。「合意」によって形成される秩序というのは、すでに社会に秩序が存在し、その秩序ある社会で合理性を身につけた個人が行うものとして考えたほうが論理的な整合性がある。合意による秩序は、すでに秩序が存在するという前提のもとに確立される秩序ではないかと思われる。「合意モデル」というのは、秩序ある社会の中で、ある種の特殊な分野での秩序の確立を説明するときには、その分野での合意が成立しているかどうかに注目して説明できるというようなモデルになっているのではないかと思う。社会全体の秩序の確立を説明するためのモデルとしては現在の社会学では「信頼モデル」というものが使われているという。しかし、この「信頼」という言葉も、個人における「信頼」を、範囲や数を拡大しただけの単純な概念で受け止めると、すでに「信頼」が確立されているから社会の「信頼」ももたらされているという、「合意モデル」と変わらない構造になってしまう。社会における「信頼」と個人の場合の「信頼」は概念が違うように僕には感じる。個人の場合の「信頼」は、相手が信頼するに足る人間であることを根拠にして起こってくるものだ。つまり人間に対する事後的な評価によって「信頼」があるかどうかが決まる。しかし、社会における「信頼」は、素性の分からない一般大衆に対する「信頼」が問題になる。相手を知った上での「信頼」ではない。一般大衆を「他人」という言葉で置き換えると、「他人」への信頼は、「他人」がどう振舞うかが予想できないということから信頼が揺らぐことになる。逆に、「他人」の振る舞いが自分の分かる範囲内に収まるものであれば、それを「信頼」の根拠にすることが出来る。相手の振る舞いが予測できないものであることを「偶発性」と宮台氏は呼んでいるが、その「偶発性」は、自分の振る舞いによって変わったりするので、自分の振る舞いとそれに対応する相手の振る舞いと、「偶発性」が二重になっていることに注意を求めている。この偶発性をコントロールして「信頼」にまで持っていく考え方として、パーソンズは「価値の共有」という発想を提出しているようだ。しかし、これは「信頼」の根拠を「価値の共有」という「合意」に求めているという点で、「合意モデル」と変わらないと宮台氏は指摘している。社会の「信頼」が個人の「合意」を出発点として形成されるというのは、現実のモデルとしては、すでに「信頼」が成立していることを前提として「信頼」を説明するという、数学で言うトートロジー(同語反復)の主張になってしまう。個人の「信頼」を基礎にして考えると、社会の「信頼」は定義できない。個人と関係なく社会の「信頼」を考えるなら、それはどのような概念(定義)になるだろうか。宮台氏によれば、それは「根拠のない循環」と語られる。社会における「信頼」は、相手が信用に足るものなのかというような根拠などないのだ。それは単に、以前も信頼できたからこれからも信頼するという、信頼ができたという経験の繰り返し(循環)によって信頼されているに過ぎない。この「信頼」の概念は、まったく「信頼」に値しないような、頼りのない根拠しか「信頼」にはないのだと言っているようにも聞こえる。しかし、個人とは違う社会の「信頼」について考えると、このように考えざるを得ないのではないかという感じもする。何かの根拠があって社会に「信頼」が生まれたのだという論理の展開は、その根拠がどうして生まれたかということを追求していくと、どうしても何らかの合意(相手の理解)を元にした根拠にならざるを得ない。だが、それは「信頼」があってこそ生れる合意(理解)ではないのかとも思える。根拠があると考えれば、それはトートロジーという循環にならざるを得ない。現実に「信頼」があることが観察される状況を見ると、現実がそうなっているから、どこかで「信頼」が生れたのだろうけれど、その根拠は誰にも分からないとしかいいようがない。このような意味で「根拠のない循環」として語るしかないのではないかと思う。「信頼」は、その出発点は、根拠なくただ信じているというだけの宗教的信仰のようなものだったかもしれないが、我々に関心があるのは、それが安定的に維持されて社会の秩序を保っているということだ。「信頼」が生じた根拠については分からないが、それが安定的に維持されているというメカニズムについては我々に知りうることがあるかもしれない。これを解明するのが社会学という学問だということなのだろう。「信頼」は根拠のない循環なので、ときどき破られることがある。もし循環が破られたとき、「信頼」も失われてしまうようなら、社会の秩序も壊れてしまう。秩序の維持が社会にとって価値があると考えるなら、循環が破られたときにも「信頼」が維持されるようにメカニズムがコントロールできれば「信頼モデル」の発想は非常に役に立つものになるだろう。それは果たして可能だろうか。根拠のない循環によって維持されている「信頼」は、「論理的に確認できない前提に支えられています」と宮台氏は語っている。この前提を「コミュニケーションを浸す暗黙の非自然的な前提」という言葉でも語っている。この前提が存在していると、それが破られるような出来事が生じたとき、それは例外的な出来事だという処理が出来る。つまり、出来事が生じただけでは「信頼」は破られないという状況を保つことが出来る。社会の秩序は維持されるわけだ。しかし、その出来事が例外的なものではなく、それが普通だという認識を多くの人が持つようになると、根拠のない循環そのもののイメージが変わってきてしまう。そうなると「信頼」そのものも崩れてしまうだろう。社会的な不安が広まってくると、その不安によって失われる「信頼」がどのようなものになるかを考えることが重要になるだろう。不安のために「信頼」を失うのではなく、「信頼」を基礎にして不安を鎮める方法を模索したいものだ。「信頼」が失われているのではないかという指標として、「合意」を求める声が大きくなるということを観察してみるのは便利ではないかと思う。宮台氏は、例外的な出来事の存在を許さないような気分は、合意を求めるような方向に行くと語っているように僕には感じた。つまり、ある種の道徳的なルールを破った人間がいたとき、「信頼モデル」の考え方では、たまたま道徳的な信頼ルールを破った例外者が出てきたというふうに捉える。それは例外者であるから、道徳のルールそのものの信頼を破ったわけではない。ルールを信頼する多数者がまた根拠なき循環によって信頼を取り戻す努力をすればいいということになる。しかし、このルールを破った不届き者を許さず、ルールを100%完全に守らせるというふうに発想すると、道徳的なルールを法律にしてしまえと考える方向へ行く。「信頼モデル」から「合意モデル」へと発想が転換する。宮台氏は、近代社会は、もはや「合意モデル」へと退却することは出来ないと語っている。それは自由が失われてしまうからだろうと思う。この自由は他者を許容することから幅広い懐の深いものになるのだと思う。自分とは違う考え方や発想でも、それが社会の秩序を乱すほどの影響を与えないものであれば、信頼は失われないのだという判断から許容することが「信頼モデル」の社会の維持には必要なのではないだろうか。違う考えのものを許さないという、狭量な生真面目さが、社会の「信頼」を壊しファシズムのような、すべての人間に偏向した考えの合意を強いる、非近代的な社会を生み出してしまうのではないだろうか。現実の社会が、「信頼モデル」という抽象(捨象)にふさわしいものになるように努力したいものだと思う。
2008.07.14
コメント(0)
-
選択前提理解のための「自由」の概念
宮台真司氏は「連載第7回 選択前提とは何か」の中で「自由」の概念について詳しく説明している。これは「選択前提」という言葉の理解のために、その「選択」が「自由」に選べるということの意味の理解が必要だからだ。「自由」に選べないような、これしか選択肢がないというような「選択」は、本来の意味での「選択」とは呼べないからだろう。この「自由」については、三浦さんも何回も紹介していたが、ヘーゲルの「必然性の洞察」という言葉が「自由」の本来の意味(概念)であるという理解がある。「必然性」というのは、「必ずそうなる」ということであって、そこには「選択の余地はない」というニュアンスもある。そうすると「自由」もないのではないかという感じもしてくるのだが、この「自由でない状態がもっとも自由である」という、それが「自由」の最高段階だという認識は、弁証法的な把握であり、現実を深く広く認識したものだと思われる。必然性を洞察することが出来る人間は、何らかの行動において、自分が操作したい対象がどのような必然性に従うかをよく知っている。自分の目的に合うように対象を操作したいと思ったとき、その目的では絶対に操作できないという必然性が分かれば、賢い人間なら目的の方を変更するだろう。あるいは対象をそのままにせずに、目的を達成できるように対象に手を加えて変化させるというようなことを考えるだろう。あくまでも目的達成にこだわって、無理やりにそれを扱うということはない。「自由」というものを、自分の欲望を達成するためにわがままに恣意的に振舞うというような意味(概念)で理解すると、それが達成されないときに、そのような状態は「不自由」であって「自由」ではないという感じがする。それは欲望に支配されている状態であり、欲望からは「自由」になっていないと判断される。かつて羽仁五郎さんは、「自由と規律」という言葉を批判して、「自由」と「規律」を対立する反対物として認識するのは間違いだと指摘していた。「規律」に従わない、勝手気ままが「自由」だという感性を批判したのだろうと思う。これは正しくは「自由が規律」なのだと語っていた。つまり、自分が自分の目的を達成するために必要な行動をよくわきまえており、「規律」というルールを目的にかなうように利用できている状態こそが「自由」にふるまっていることになるのだと主張していた。結果的に「自由」であることが確認されることが「規律」というルールを達成するという関係にある。これが「自由が規律」だという意味だった。これも「必然性の洞察」という「自由」を語っていることになるだろう。「必然性の洞察」が「自由」だという認識(意味・概念の理解)は、現実の深い把握であり正しい認識であると思う。ただ、このように表現された「自由」は、その概念を運用して思考を展開するのはやりにくい。あまりにも抽象的過ぎて、それを現実に応用するということが難しいように思われる。意味の概念のときもそうだったが、これを運用して思考を展開するには、その機能面に注目して、機能が現実に発見される現象にその概念の適用が出来る存在が見られるのだとする発想が役に立つだろうと思う。そのような機能によって「自由」を理解するという解説が、宮台氏のこの回の講座には見られる。宮台氏は、「自由」の機能的側面を理解するのに、それを選択前提の段階と結び付けて、ある種の選択が「出来る」時に「自由」が、「出来ない」時に「不自由」が存在するというふうに、それが「出来る」か「出来ない」かという機能にしたがって「自由」の存在を理解するという概念の理解を解説している。選択前提の段階は3つの段階に分けられ、それぞれの段階での「自由」「不自由」が解説される。これは「自由」を直接理解するよりも、「不自由」のほうが直接的な理解がしやすいという。これなどは、概念の理解が実は、その概念が語る対象そのものを捉えるというよりも、そうでないものを並べて相対的にその概念の位置をラングの中で位置付けるという、ソシュールの「価値」の概念が思考の展開においては役立つという一つの例になっているのではないかとも感じる。選択前提の3つの段階について宮台氏は次のように書いている。「選択には前提が必要です。まず、選択領域、すなわち選択可能な選択肢群が与えられていなければなならない。次に、選択領域から現に選べなければならない。後者は、選択チャンスがあるので選べるという水準と、選択能力があるので選べるという水準とがあります。以上をまとめると、選択前提には三種類があります。第一は「選択領域」。第二は「選択チャンス」。第三は「選択能力」です。ちなみに前回紹介した「構造」概念は、選択前提の中でも、第一の「選択領域」を与える先行的選択という機能に注目したものでした。」「選択領域」「選択チャンス」「選択能力」という言葉で語られる3つの段階に対して、それぞれ「自由」「不自由」にも3つのレベルが対応する。これによって「選択前提」という複雑な意味を持つ概念の正確な理解を図ろうというわけだ。「未開社会には飛行機で移動するという選択肢がありません」ということの例で、「選択領域」がない場合の「不自由」を宮台氏は語る。しかしこの「不自由」は、社会に対して大きな影響を与えることがないので、「不自由」がマイナスの評価としては働かない。選択肢がないような選択は、それが存在しないという前提があるので、それが選べるはずがないという論理的な帰結をもたらす。そういう意味で「不自由」ではあるが、これは「自由」の欠乏を感じる「不自由」ではなく、その状況を外から眺めている、より高い段階の「自由」を手にしている人が認識できる「不自由」だ。未開社会に住んでいる当事者の人々は、そのような「自由」の存在を知らないので、その「不自由」を主体的に感じることは出来ない。「不自由」であっても、その欠乏感に苦しめられることはないのだ。「不自由」の欠乏感に苦しむのは、もう一つ高い段階の「自由」が手に入らないときになる。「選択領域」は示されていてそこにある(つまり「選択領域」においては「自由」だ)のだが、それを手に入れる手段がないために「選択チャンス」において「不自由」を感じるというのは、その欠乏感に苦しめられることになる。それが「欲しい」という欲望は感じるのに、それが手に入らないという欲望の達成が邪魔されるという意味での欠乏感だ。さらに、もう一つ上の段階である「選択能力」の問題では、「選択領域」も「選択チャンス」も「自由」に手に入れられるのに、何を選ぶかの最適な判断ができずに苦しむという「不自由」の問題が出てくる。この3つの段階のそれぞれで、目的にかなう選択が出来れば、それは完全な形での「自由」を手にしていると考えられる。そしてそれはヘーゲルが語る意味での「必然性の洞察」と重なる現象ではないかと思う。「必然性」の洞察の具体的な理解は、このような「選択前提」の3つの段階に対応する「自由」がすべて達成されたときと言えるのではないだろうか。この「自由」概念は、社会学的な考察においては有効な思考の展開をもたらす。社会の発達の指標に応じて「選択前提」の段階が対応すると考えられるからだ。「選択領域」として新たな分野が開けてくるというのは、新発見・新発明の時代に対応すると思う。進歩の最初の段階が、「選択領域」の開拓というものになり、これによって人間の「自由」は拡大される。「選択領域」の「自由」の拡大が、「選択チャンス」の「自由」に結びついてくるのは、経済的な発展によって多くの人にチャンスがもたらされるという、宮台氏の言葉で言えば「近代過渡期」に特徴的なものになるのではないかと思われる。日本でいえば、高度経済成長期で、人々がだんだんと豊かになり、それまでは贅沢だと言われていたさまざまな商品が手に入るようになってきた時代で、それを手に入れるという「選択チャンス」が社会に広がってきたときが「選択チャンス」の「自由」が拡大した時代だといえる。そして大部分の人に「選択チャンス」が示されたときに、何が最適な選択かという判断の問題が生じてくる「近代成熟期」の特徴が「選択能力」の「自由」が問題になる時代と言えるだろう。現在の日本がそのような時代だと宮台氏は語っている。これに対しては、就職氷河期などといわれてきた若年層は、選択の余地のない就職という現実に、とても「選択能力」の「不自由」の問題ではないという感覚もあるかもしれない。むしろ選択の余地のない現実は、「選択領域」の「不自由」の問題ではないかと感じる人もいるだろう。しかし、日本が「近代成熟期」だという判断は、日本の中の相対的な感覚の問題ではなく、日本が世界の中の先進国(G8の中の一つ)であるという判断から来るものだ。選択領域の幅が、後進国と呼ばれる国と日本では絶対的な違いがある。その相対的な位置付けからいえば、日本はやはり「近代成熟期」として評価されるだろう。秋葉原の事件によって明らかになった若年層の「選択領域」に関する「不自由」への怒りというのは、「近代成熟期」という時代に関わる問題というよりは、宮台氏が語る「アノミー」の問題として理解したほうが日本社会を理解するには正しいのではないかと思われる。「アノミー」については宮台氏は次のように解説している。「デュルケムは『自殺論』で、金持ちが急に貧乏人に転落して自殺する場合と、貧乏人が急に金持ちに成り上がって自殺する場合があることを発見します。共通して、従来までの前提が当てにできなくなるがゆえの混乱に由来すると見倣し、それをアノミーと呼びます。従来用いてきた手段(金銭)の不足も、従来抱いてきた目的(金持ちになる)の不足も、確かに混乱を招き寄せます。後にマートンが前者を「機会のアノミー」、後者を「目標のアノミー」と命名しました。今では「手段のアノミー」「目的のアノミー」とも言います。選択連鎖の概念を持ち込めば、選択連鎖の一部を構成する、選択前提と選択の特定の組み合わせにおいて、選択前提に関わるリソース不足が目的のアノミー、選択に関わるリソース不足が手段のアノミーです。手段は下位手段にとっての目的なので、相対的な概念です。」従来の日本であれば、どのような仕事であれ、一生懸命まじめに勤めることで、ある意味では「近代過渡期」の恩恵を受けるような「幸せ」とも呼べるような生活が期待できた。どのような選択をしようと、その選択に応じたチャンスを手にし、一定の満足が得られた。しかし、その前提が崩れて、一定の満足どころか、生きるだけでもたいへんな、しかも人間扱いされないひどい労働状況が「派遣法」をきっかけにしてもたらされた。これはそれまでの前提条件が崩れた「アノミー」として理解したほうが正確なのではないかと思われる。若者が「自分探し」に苦しんでいた頃は、「近代成熟期」の選択能力の欠如(何が最適の選択かが分からない)という「不自由」に苦しんだ時代で、派遣法によるひどい労働状況の仕事しか選べないという現在の状況は、近代以前に時代が逆戻りしたのではなく、近代成熟期でありながらそれまでの前提が通用しなくなった「アノミー」の時代だと理解したほうがいいのではないだろうか。時代が提出する「不自由」に苦しむ人々は、それが苦しくてもそれに耐えて未来を夢見ることが出来る。しかし「アノミー」に苦しむ人々は、自殺などの暴発的な状況を引き起こす恐れがある。そのような意味からいっても、現在の日本は「アノミー」の時代だと認識したほうがいいのではないだろうか。
2008.07.11
コメント(0)
-
「構造」という概念
宮台真司氏が「連載第六回 構造とは何か」で説明している「構造」という概念について考えてみよう。まずはこれの辞書的な意味から生まれてくるイメージを考え、その概念を考えてみよう。そして、宮台氏が説明する概念が、それとどのような面で重なるか、どのような面で違うかということを考えてみたい。「構造」という言葉は、辞書的には「仕組み」と言い換えられることがある。これはその対象の部分的な要素がどのように組み合わされているかということを見たときに、その組み合わせ方を「仕組み」と呼ぶことがある。部分と部分を実体的に見るのではなく、その関係を捉える見方になる。「構造」は対象の全体に渡るものだが、それは部分の間の関係として我々には直接見えるものとなる。また「構造」には、それが容易には崩れないというイメージがある。あるいは、容易に崩れるようなことがあっては困るものに対して「構造」を考えることが多いといえるだろうか。建物の構造などは、それが簡単に崩れてつぶれてしまうようならたいへん困ることになる。それこそ地震などが起こってもそれに耐えるくらいに強い「構造」が求められるといえるだろう。「構造」が強固に見えるのは、それが強固で変化しないからこそ見えてくるので、見えてくるということ自体に「構造」の強さが含まれているということも言える。このようなイメージは、「構造」が変化しないものであるという印象を与える。この「変化しない」という面を重視して「構造」概念を考えたのが宮台氏が紹介しているパーソンズの考え方になるだろうか。宮台氏は次のように書いている。「この用法は今も見られます。第三回で説明したように、パーソンズは均衡システム理論の導入が困難なので、次善の策として、諸変数を、変動しやすい/しにくいものに分離した上、前者の値を後者の存続への貢献によって説明する「構造機能分析」を提唱しました。彼は、変動しやすい変数を「過程」、しにくい変数を「構造」と呼び、過程のあり方が、構造の存続維持に貢献する機能を果たす度合によって決まると考えます。ですが過程の間に成り立つ関係を構造に含めると背理を来すことが証明されたことは、既に紹介しました。」「過程」というのは、一時的にその状態にとどまっているという感じがするので「変化」するものを呼ぶのにふさわしい言葉になるだろう。それに対して、「変化」しにくい対象を呼ぶ言葉としては「構造」という言葉がふさわしいだろう。「構造」は一時的にそうなっているのではなく、一定の期間そのような状態を保つ働きを持っているように見えるからだ。ここで語られている「構造機能分析」の背理というのは論理に関心のある人間としてはたいへん興味深いものだ。「過程の間に成り立つ関係を構造に含める」ということの意味が今ひとつつかめないので、どこが背理に陥るのかということがイメージできないではいるが。「変化しない」構造に「変化する」過程を含むことに背理という矛盾が生じる原因が見られるのだろうか。どこかに詳しく解説されているものがあれば読んでみたいものだ。「構造」というものを辞書的に、その言葉のイメージから概念を考えると上のようなものがつかめるのではないかと思う。この辞書的な意味の延長になるようなパーソンズの「過程」と「構造」の対比の概念は、残念ながら現代社会を分析する道具としては役に立たなかったようだ。それでは、この「構造」概念を役に立つような形にする新たな発想の概念はどのようなものになるだろうか。宮台氏は次のような書き方で新たな「構造」概念がどういうものになるかを示唆している。「ここで注目したいのが、証明者であるヘンペルやアシュビーが、構造を、過程の間に成り立つ関係、すなわち、諸変数の間に成り立つ関数だ、と理解したことです。理科系では完全に一般的ですが、こうした考え方が出て来る所以を、十分に理解する必要があります。」ここでは変化しやすい「過程」を変数として捉えて、その変数の間に成り立つある種の関係を関数と捉えることによって、関数のほうを「構造」と呼ぶという概念が語られている。これは、変数はそれが定義域に入っているものなら任意にどの値をとってもいいという自由度が変わりやすさを表現し、関数はそれが従うものとしてその関数が成立している限りでは関数自体は変化しないという面で代わりにくいものを表現していると考えられる。また、関数は数学的にはある集合を、単にものの集まりとして捉えているのではなく、そこに関数で示される仕組みがあるという捉え方にもなる。数学の群論などでは、群という「構造」を示すのに、二つの変数に一つの集合の要素を対応させる関数を考える。この関数がある種の条件のもとにあるとき、そこに群という「構造」があるという見方をすることになる。この関数をもっと卑近な例として考えると、次のようなものが「構造」として考えられる。宮台氏のあげる例は次のようなものだ。「諸変数の値は変わっても(1)諸変数の変域や(2)諸変数の間の関係は変わらない。カメレオンの色が変わっても(1)変わり方の幅や(2)どんな時にどう変わるかは変わらない。これを構造と呼ぶ。骨格も内臓配置も結局は、要素の絶対位置でなく位置関係を構造と呼ぶのだと。」「構造」の概念が、このように関数としてイメージされるのは、宮台氏によれば、「構造概念が着目する変わりにくさは、大黒柱のような「目に見えるもの」から、諸変数 の間の不変な関係とか、変換によっても失われない位相的性質とかいった「目に見えないもの」に移行しました」と説明される。これは、「構造」の概念がより一般化されて文脈が自由になったといえるだろう。この「構造」の概念なら、現代社会をシステムとして捉える見方に役立てることが出来そうな感じがする。なぜなら、システム自体もそれを直接見ることが出来ないように思われるからだ。見えるのは各要素の間で何がおきているかという、変数の変化だけで、関数そのものは直接見えないような気がする。これは、関数に注目する意識があって初めて見えてくるものになるのではないだろうか。さて、このような前提を元にして宮台氏が定義する「構造」の概念は次のようなものになる。「社会システム理論では、「目に見えるもの」から「目に見えないもの」への移行にもかかわらず維持されつづける構造概念の機能に注目した上で、「選択の前提になる先行的な選択」を「構造」と呼びます。但し時間的な先行ではなく、論理的な先行を問題にします。」これは、前回の講座で語っていた「地平」と「主題」という概念で理解するものになるだろう。「選択の前提になる先行的な選択」とは、「地平」を選ぶことになる。「コップ」と呼ばれる対象を「コップ」と表現した時は、それがどのような使われ方をするかという「用途」を問題にするという「地平」を選んだために、そのような呼び名が選ばれたと考えられる。もし「素材」という「地平」を選ぶなら、同じ対象であってもそれは「ガラス」という呼び名が選ばれるだろう。対象に対してある呼び名を選ぶということを一つの関数と考えれば、任意の対象は変数に当たるものになる。これの「地平」を選ぶということは、関数の定義域や値域を決定するということに相当するだろう。これによって、その地平では何が対象になるか、その対象の間にはどんな呼び名があるかという面で関係がつけられるということになるだろう。関数というイメージが強すぎると、「構造」は数学世界の中の出来事に限定されてしまう感じがしてくるが、「選択の前提になる先行的な選択」というイメージにすると、ものを考えるときの人間の思考の働きにおいてすべて「構造」を捉えることが出来るようになるだろう。社会を考える道具として使えそうだ。この「構造」概念について、さらに重要な点は次のものだと宮台氏は指摘する。「社会システム概念の中で構造概念は以下のように位置づけられます。第三回に述べた通り、システムは環境に対して開かれることで上方ならびに下方に開かれていて、だからこそ個体が死ぬと臓器や細胞のレベルでも死が訪れました。以下のように模式化できます。この模式で言えば、より下位のループにとって、より上位のループは、選択に論理的に先行する選択という意味で「構造」です。より上位のループにとって、より下位のループは、選択に論理的に後続する選択という意味で「過程」です。注目するべきは相対性です。あるループが構造なのは、より下位のループに対してです。下位のループに対しては構造であるようなループも、より上位のループに対しては過程となります。与件が構造なのか過程なのかは、上下隣接するどのループとループを取り出すかによって、変化します。」システムのループにおいて、「上位」「下位」という概念が、「構造」「過程」という概念に対応することが指摘されている。ここには、「構造」が同時に「過程」であるという、弁証法的同一性が見られることが指摘されている。三浦さんの言葉で言えば、この二つの概念は相対的に独立しているといえる。ある視点からは「構造」と見られるものが、別の視点からは「過程」として見られる。この相対性が社会システムの分析においては重要になるということがここで指摘されている。この重要性は「機能的に抽象化された「選択に論理的に先行する選択」としての構造概念を手にし、かつ準拠フレームを意識的に操縦することで、私たちは、変わりにくさとしての構造概念や、関数としての構造概念に拘泥していては得られない、様々な発見へと導かれるでしょう」と宮台氏によって結ばれている。「さまざまな発見」は、これ以後の講座で説明されていくのではないかと思う。新たな概念の獲得が、世界を切り取って、いままでは見えなかった世界の本質を見させてくれるという経験をさせてくれるのではないかと思う。
2008.07.09
コメント(0)
-
社会システム理解のための「意味」「行為」「コミュニケーション」という概念
宮台真司氏は「連載第五回 社会システムとは何か」では「社会システム」というものを説明している。これは、宮台氏が考察しようとしているシステム一般を表す「定常システム」に対して、それが社会の中に見つかるという意味での特殊性を持っている対象として考えられている。社会の中、すなわち人間が関わって構成されるシステムは、人間存在とは独立に存在する物質的で機械的な「定常システム」とはその性質を異にする。人間と独立に存在するシステムは、意志の問題が介在しないので、外から観察することによってシステムの働きを記述することが出来る。宮台氏は、対流の現象や排水のときに出来る渦巻きの現象をその例としてあげている。水を熱すると、その熱い部分と冷たい部分との作用で「対流」が起こり、それは熱している限り存在しつづけるという「定常システム」になっている。このシステムは、外からその熱量や温度を観察することによって、何が起こっているかを記述することが出来る。システムであるから、それが安定的に繰り返されるループになることも記述することが出来る。排水の現象に関してもそうである。しかし、これが社会に存在するシステムの記述になると、外から観察するだけでは、そのシステムを完全に記述することが出来ない。自然現象と違って、人間が行うことは、それが物理的に記述できる「行動」として観察されて、行動面では同じように見えても違うものと判断されることがあるからである。そこにはある種の意味が読み取れるために、行動としては些細な違いだ(末梢的だ)と思われるのに、意味として大きく違ってくるという判断がされて、同一ではないと判断される。このように意味を伴う行動を宮台氏は「行為」とも呼んでいた。社会システムを理解するには、人間の意志に関わる特徴を持つ「意味」「行為」「コミュニケーション」という概念を理解することが必要になる。これらを理解して初めて、社会システムにおける同一性というものが明確になる。その秩序を評価できるようになる。宮台氏は、野球というゲームを一つの社会システムとして例にあげている。これはいくつかのルールを元にして、秩序のあるゲームが行われ、どちらかの勝利によって終わる。そのルールは3つのアウトが判定されて交代するということが繰り返され、この繰り返しがループとして捉えられる。このループが、ランダムに行えばその行動が何が起こるかわからなくなるというものにならずに、ちゃんとゲームとして誰もが理解できる形に落ち着き、それが秩序として評価される。さて、野球においてピッチャーから投げられたボールをバッターが打つという行為が繰り返される。この行為において、バッターは1塁へ走ったり走らなかったりする。行動としてバッターの打つ行為を見ている限りでは同じように見えるのに、その後の行為が走ったり、走らなかったりと違ってくるのは、バッターの打つ行為の「意味」が違っていることに対応している。ホームと1塁、あるいはホームと3塁を結ぶ線の内部はフィールドと呼ばれるが、バッターが打った打球がフィールドの中に入れば、それは1塁へ走る打球となる。しかし、フィールドの外に出ればそれはファールになり1塁へは走らない。打球の「意味」が違ってくる。この「意味」の違いによって、ある行為の次の行為が違ってくるというのが社会システムの特徴だ。ある行為の次の行為がどんなものであるかがルールによって決められ、その行為の連鎖がループをなすなら、ある行為がそのループの中に入り込むことによって、そのシステムはそのループによる繰り返しで同一性を保つ。これが社会システムにおける秩序となるだろう。行為は意味によって同一性を判断される。したがって、社会システムにおいては、「行為」と「意味」の概念は非常に重要なものになる。ここで改めて「意味」の概念を考察してみると、これが概念として捉えようとするとなかなか難しい。三浦つとむさんも『日本語はどういう言語か』という本で「意味」の概念を考察していたが、この概念が難しいのは、それが感覚でつかむことが出来る実体的なものではないからだ。三浦さんが考察していたのは「言語の意味」というものだったが、これは、いくら言語を眺めてもそこに見えるものではない。三浦さんの結論は、言語で表現されているものを、言語の語彙から現実に存在する対象を想像し、その対象が表現者の脳にどのような認識をもたらしたかを、その言語を頼りに想像し、言語と対象と認識の間に関係をつけることが意味を読み取ることになるというものだった。意味とは関係性の理解というものだった。このような「意味」の捉え方は、なるほどとは思えるものの、概念として運用するにはちょっと難しさを感じる。関係性という概念が「意味」の概念と同じくらいに難しさがあるからだ。これに対して、宮台氏は「意味」の概念を直接に述べはしないものの、その機能を語ることで「意味」の概念の運用を語っている。宮台氏が提出する「意味」の機能は次の4つだ。1 示差性 意味の違いは、それが指し示すものの差異を表現する。意味の違う言葉を使えば、その言葉は意味の対象が異なることを表している。とかとかという言葉を使えば、その意味が違うことによって、それが指し示す対象が違うことを表す。意味の違いが差異性として理解されることを「示差性」と呼んでいる。2 二重の選択性 ある対象を表現したとき、その捉え方(認識)によって、意味の異なる表現が出来る。ある対象を「コップ」とも「ガラス」とも表現できる場合、この意味の違いは、意味の機能に二重の選択性があるからだと考える。一つの選択は、それを「用途」として考えたときの対象の名を選ぶというもので、もう一つの選択は、それを「素材」として捉えたときの素材の名を選ぶものだ。「用途」か「素材」かという選択は、ものの捉えかたの基本として「地平」の選択と考え、その「地平」の中で異なる名を選択することになるので、選択が二重になる。3 否定性 示差性によって、ある「地平」の元で選択された対象の名は、その「地平」に存在する他の名を否定することになる。「コップ」であると判断された対象は、「用途」という地平では、「皿ではない」「茶碗ではない」「カップではない」というような否定性を「地平」の中に温存すると考える。4 選びなおしの可能性 上の否定性で温存された否定性を帯びた名を選びなおすという機能が、4で語られる「選びなおしの可能性」というものになる。この機能によって、意味は変化する可能性をもつ。「コップ」だと思ったものが、実は取っ手がついていて「カップ」だったと言い換えるのは、意味の「選びなおし」をしていると考える。このような機能において同一かどうかが判断され、「意味」における同一性が「行為」の同一性の判断に結びつく。「意味」を機能的に捉えるのは、この同一性の判断において便利だからだと考えられる。「意味」そのものを概念として運用するのではなく、「意味」は「行為」の同一性を判断する道具として使われている。このような時は、意味それ自体の概念を問題にするのではなく、機能を捉えたほうが役に立つ結果をもたらすだろう。このようにして同一性が評価された「行為」の連鎖がループとなり社会システムの構造が明らかになっていく。「行為」の連鎖がループを作るなら、社会システムの要素は「行為」だと考えたくなるが、それは現在の社会学では「コミュニケーション」だと捉えられていると宮台氏は言う。これはちょっと分かりにくい言い方だ。「コミュニケーション」という言葉が普通の遣い方とは違うようなのだ。宮台氏は次のように書いている。「社会システム理論に限らず、システム理論では、選択と選択との時間的な接続をコミュニケーションと言います。人文諸科学でコミュニケーションというと、メディアで繋がれた送信機と受信機を挟む二人の間でメッセージが伝わることを言いますが、違う概念です。」ここでいう「選択」とは「行為」の選択を意味する。つまり、どんな「行為」をしたかということと同じ意味になる。ということは、コミュニケーションというのは、行為の連鎖という現象を言い換えたものと考えられる。考え方としては、社会システムの要素が「行為」であると捉えているのと同じことだ。それなのにどうしてわざわざ勘違いしそうな「コミュニケーション」などという言葉を新たな概念として使うのだろうか。それは「行為」という概念の中には、そもそも「連鎖」というような「接続」をしているという現象が想定されていないからだ。「行為」という概念そのものは、それが内的な意味を含んで判断されるという概念であって、続けて何かが起こるということは概念としては含んでいない。だが社会システムでは、選択の「接続」ということが重要で、それが連鎖のループを作っているということがシステムであることの決定的な根拠となっている。この連鎖の状況を作る「接続」を強調するために、「コミュニケーション」という概念を使うのだと思う。宮台氏は次のように書いている。「かくて、行為を要素する社会システムを、あえて「社会システムはコミュニケーションから成り立つ」と言いなす意図も、一層明確になります。行為は物理的に生成消滅しても、意味的に「持続」するので、たえず選択接続に道を開く、ということを示唆したい訳です。」この段階では、社会システムはまだその具体像を表さず、ぼんやりとした漠然としたイメージで概念化されている。文脈は自由だが、自由であるがゆえに雲をつかむようなどこかに逃げてしまいそうな感じがするものだ。宮台氏はこの講座の後のほうで、「人格システム」であるとか「法システム」「宗教システム」「政治システム」という、もう少し具体性のある現存するシステムに言及する。このような対象に対して考察すれば、いまはぼんやりとしている社会システムの概念が、もう少しイメージ的にはっきりしてくるのではないかと考えられる。いずれにしても、「意味」「行為」「コミュニケーション」という諸概念が、これらのシステムのループを発見するのに役に立つのだろう。とりあえずは、上のような概念の理解でさらに先を読み進めてみようと思う。徐々に理解が深まればいいのだがどうなるだろうか。
2008.07.08
コメント(0)
-
システムの「秩序」という概念
宮台真司氏は「連載第四回:秩序とは何か?」では「秩序」という概念を説明している。この概念も、普通に辞書的に受け止めている「秩序」という言葉の意味と、宮台氏がここで語っている意味とでは大きな違いがあるのを感じる。「秩序」という言葉が普通に使われる場面では、そこに望ましいと評価される規則性があるのを感じる。つまり「秩序」には価値評価が伴っているという感じがする。「秩序」がないと判断される場合は、それは価値が下がったように評価され、何とか「秩序」の回復を図るというふうに考えたくなる。「秩序」は安定をもたらすと考えられる。「秩序」のある経済は我々の日常生活を安定させ、安心して物を買ったり売ったり出来る。「秩序」のない経済は、たとえばインフレがひどくなった状態を想像すれば、物を売るにも買うにも、どこでそれをすればいいのかという判断が分からなくなり、人々の生活は困窮する。ひどく困った状態が「秩序」の乱れから帰結される。この「秩序」にまとわりついたイメージは、実は特定の文脈にくっついたイメージかもしれない。「秩序」そのものには価値的判断は本質的なものではなく、もっと一般性を持った特長が抽象されて、「秩序」の本質を押さえたような概念が「一般理論」の対象となるべきだと考えることも出来る。このような発想で提出された「秩序」の概念が、宮台氏がここで語っているものではないかと思われる。宮台氏がここで語る「秩序」は、それがあることに特別の価値を見出すものではない。それは概念的には、その反対物であるランダムで乱雑といえるような状況ではない、というものを示しているように見える。この「ランダムで乱雑」という状況を、価値判断抜きで捉えるには確率論的な意味付けをすることがもっとも有効だと考えて、「秩序」と確率論を結び付けて定義しているように思える。宮台氏は、黒球と白球を2個ずつ、合計4個の球を並べるという現象において、どのような状態が「秩序」があるかという例をあげて、この「秩序」概念を説明している。普通に印象として「秩序」の感じを考えると、バラバラに並んでいるなあと思えると「秩序」がないと感じるし、白が2つ並んでいる後に黒が2つ並ぶというような状況を見ると、白と黒が分かれていて何か「秩序」があるなあという感じがしてくる。これを感覚的な印象で判断するのではなく、誰が判断しても後者の方が「秩序」があると判断できるような定義をするのが、ここでの「秩序」概念の目的であるように思う。これを確率の考えを使って判断すれば、後者の方が「秩序」があると常に判断できるようになっていると、宮台氏の説明を読むとそう感じる。4つの球を順番に並べるとき、確率で考えると、最初の球の取り出し方は4通りになり、2番目は一つ少なくなるので3通りになる。以下3番目の選び方は2通りで、最後の珠は一つしかないから1通りの選び方になる。したがってすべての並べ方はこれらを掛け算して4×3×2×1=24通りの違う種類があることになる。もし「ランダム」という状況を、この可能な並べ方のどれが現れてもいいのだと定義すれば、「ランダム」の確率は 24/24=1になる。これに対して前の二つに白を、後の二つに黒を並べる並べ方は、最初の球の選び方は二つの白のうちの一つをとることになるから2通り、次の白は一つしかないから1通りある。この後ろに並ぶ黒は、二つの中から一つ選ぶので2通りの選び方があり、最後は一つしかないから1通りの選び方になる。これらすべてを掛け算すると2×1×2×1=4通りあることになる。したがって、この場合の確率は、 4/24=0.166666……という値になる。この確率計算において、相対的に確率の値が低いほうを、エントロピーが低いといい、エントロピーが低い状態を、エントロピーが高い状態(ランダムな状態)に比べて「相対的に秩序だっている」と呼んでいるようだ。「秩序」という概念は、このようにして価値判断と関係なく、状態を客観的に計算して判断される。この白球と黒球の集合は、その要素である球の間に何らかの関係があるわけではない。つまり、どの球が並ぶかは本来の意味でのランダムであって、そこに「秩序」が実現されることはおそらくない。つまり白球が二つ前に並んで、黒球が二つ後ろに並んだとしても、それは偶然そうなったのであって、いつでもそうなるような「定常システム」のような働きがあるわけではない。実際には、このような白球と黒球の状態は現実には「秩序」を持ち得ないだろう。問題は、その対象がシステムという特徴を持っているとき、つまり要素間に同一性の前提を供給しあい、その関係がループを作っているという状況が見られるとき、そこで実現されている状況は、実は確率的に低い・エントロピーが低い状況が実現されており、いつでも「秩序」があるという判断が出来るかどうかということだ。「定常システム」は、それが「同一性」という言葉で語られるようなある状況が常に実現されているということを観察できる。感覚的に「秩序」があるように見える。これが感覚の範囲の判断ではなく、誰が判断しても「秩序」があるといえるような、厳密な意味での「秩序」の概念が成り立つと、論理的に帰結できるかどうかが、システムの概念において最も重要なものであるといえるのではないだろうか。果たして、システムであれば必ずそこに「秩序」をもたらすといえるだろうか。システムの概念は、そこに「秩序」の実現を内的に含んでいるものになっているかどうか。論理によってそれが導けるだろうか。宮台氏は次のような論理展開でこのことを示している。「Aの変域がa1,a2,…,an、Bの変域がb1,b2,…,bmだとします。AとBの値の組合せはn×m通り。ところで今、Aがa1のとき次時点でBがb2となり、Bがb2のとき次時点でAがa2となり、Aがa2のとき次時点でBがb1となり、Bがb1のときAがa1となるとします。そうすると、任意の時点でのAとBの値の組は(a1,b2)(a2,b2)(a2,b1)(a1,b1)の4通りとなり、1時点でとりうる場合の数を比較すると、ループが存在しない場合の(n×m)分の4の状態しか現実化できない、つまり場合の数が少ないことが分かります。 時間的に見ると(a1,b2)→(a2,b2)→(a2,b1)→(a1,b1)→(a1,b2)→…と4通りの状態を循環的に遷移するので、エルゴード仮説の下では任意の連続4時点間で(n×m)の4乗分の4の生起確率で、秩序すなわち確率論的にありそうもない状態が現実化しています。 かくして定常システムは要素間の交互的条件づけという内部メカニズムの永続的作動で、確率論的にありそうもない状態を維持します。これを「内部的作動による秩序維持」と言います。初期状態が決める無限波及的均衡に注目する均衡システム理論にはない概念です。 」これは、数学が苦手な人には、ちょっとややこしくて分かりにくいかもしれないが、ポイントは (a1,b2)、(a2,b2)、(a2,b1)、(a1,b1)という状況しか、このシステムでは実現されないということだ。なぜなら、いまの状況がこの4つのうちのどれかであったとき、次の状態はシステムの内的動作で決まってしまい、他の可能性を排除してしまうからだ。ある時点で、この4つのうちのどれかが実現していれば、次の状況は (a1,b2)→(a2,b2)→(a2,b1)→(a1,b1)→(a1,b2)というループの成立から決まってしまう。これがシステムの機能だということは、システムの定義(概念)から導かれる。システムがシステムである限りでは、そこに「秩序」が実現されるというのは必然的なものになる。逆に言えば、それがシステムとしてのループの成立が出来なくなれば、それによって維持されていた「秩序」は失われるということも必然になる。そのような時には、状態は「ランダム」であることが普通になる。システムという概念は、秩序という概念を論理的に導く。秩序の分析にはふさわしい概念となっている。システムと秩序の論理的関係は、 それがシステムである →(ならば) それは秩序があるというようなものになっている。これを逆にした そこに秩序がある →(ならば) そこにシステムを発見できる(システムがある)ということが言えるかどうかが気になる。秩序があれば、そこで実現されている状況は「ランダム」ではない。確率的にはありそうもない現実がそこに実現されている。それは偶然そうなっているだけなのか、それとも何らかのシステムがそこにあり、そのシステムの機能としてそのようなありそうもない現実が起こっているのか。自然科学は、自然の中にいろいろなシステムがあることを発見して、自然の法則として「秩序」が実現されているのを発見したといってもいいだろう。それは偶然そうなっているのではなく、必然的にそうならざるを得ない法則性がそこにあるのだということを発見した。人間の現実・人間の世界において、秩序が実現されている状況は、偶然というものはないのだろうか。すべては何らかのシステムがあるのだろうか。これは決定論的な問いかもしれないが、もし偶然というものがあるならば、それはどのようなとき偶然と判断されるのか。構造主義は、秩序の背後に構造があるという発想のように見える。この発想では、秩序の背後にはシステムがあるのだという見方のようにも見える。それは常にそういえることなのか。それとも、そういえない場合があるのか。あるいはどちらとも決定出来ない場合があるのか。考えてみるのは面白いかもしれない。
2008.07.08
コメント(0)
-
「システム」概念の難しさ
宮台真司氏は「連載第三回:システムとは何か?」の中で「システム」というものについて語っている。「システム」については、これまでも何度か考えてきたが、その概念をつかむことの難しさを今でも感じている。「システム」という言葉を辞書で引くと「制度。組織。体系。系統」などという言葉が並んでいる。そのイメージは、それを構成する要素相互の間に関係がつけられていて、全体が一つのまとまったものとして機能する「全体性」を持ったものが「システム」と呼ばれているもののようだ。「身分制度」などという制度を考えてみると、それは社会における一つのルールのようなものとして現前する。生まれつき決まっている「身分」というものがあって、社会の中の誰もがその「身分」にしたがって生きていく。「身分制度」という「制度」としてのシステムは、誰もが「身分」に従って生きるという社会の秩序を維持する機能をもっている。個々の「身分」の人々の振舞いを規定する「身分制度」は、全体として社会のある秩序を維持するものとして働く。このようなイメージがシステムというようなものになるだろうか。学校という「組織」などは、それを構成するもの、たとえば人で言えば教員や生徒であり、物でいえば校舎や校庭、さまざまな道具(机・いす・黒板など)が、それぞれの役割を担当して、全体として教育という機能を持った秩序を維持する働きをする。これらの具体的なシステムは、その機能や役割・全体性を想像することは易しい。具体的なイメージで捉えられるからだ。しかし、宮台氏が語るシステムは、このような具体性を持った特別な文脈の下に語られるものではなく、自由な文脈の下でどのような対象であろうとも語ることの出来る一般性を持った概念として提出されているようだ。一般的存在としてのシステムを語り、その概念を使って一般理論としてのシステム論を展開するという論理の流れになっているようだ。この文脈自由なシステムの概念というのが、文脈が自由なだけに、具体的なイメージがすべて捨象された抽象的なものになっている。そのイメージはなかなか明確に頭に描くことが出来ない。ここに宮台氏が語るシステム概念の難しさがある。宮台氏が語るシステムの定義は次のようになっている。「「システム」とは複数の要素が互いに相手の同一性のための前提を供給し合うことで形成されるループ(の網)です。」特定の文脈のもとにある具体的なシステムを観察すると、そこにはいつでも「同一性のための前提」を供給し合う要素が見つかり、しかもその前提をつないでいくと一つのループ(円環的に閉じた関係図)が見出せるということが、この定義を立てる根拠となっているのだろう。そのような観察があれば、その現実から抽象される対象を「システム」と呼びたくなるのではないかと思う。だが、この定義はあまりにも抽象的過ぎて、「システム」が見せる現象がこの定義から導かれるという論理的整合性がまったく見えてこない。たとえば、現実のシステムが見せる「秩序維持」という機能が、どうやってこの定義と結びついてくるかを理解するのはたいへんだ。「身分制度」が維持される、「学校」という組織において一定の教育効果が期待できるという秩序の現れは、どうやってこのようなシステム概念から論理的に導かれていくのだろうか。実際の秩序維持が、このシステム概念と関係なく、現実を観察することによって得られる事実に過ぎないのであれば、何もシステムなどという概念を抽象化する必要はない。このシステムという概念は、それを論理の操作の中で運用することによって、システムの一般論を展開できるようなものになっているはずだ。それこそがシステムという新たな概念を設定することの意味・意義になるのではないだろうか。宮台氏は、システムの秩序に関する考察は、後にエントロピーという確率的な考え方を元にした概念で定義する。つまり、システムは最初の定義の段階では、そこに秩序があるという性質を定義の中には含んでいない。定義で確認されているのは、 ・互いに前提を供給する。 ・その前提供給の関係がループになっている。という二つのことを要請しているだけだ。秩序に関係していると思われるのは、互いの前提供給が、相手の「同一性」をもたらす前提になっているということだ。この「同一性」というものが、宮台氏では「秩序」という概念と同じものとして提出されている。システム全体の「秩序」ではなく、個々の要素の「同一性」という「秩序」が実現されるということがシステムの定義として提出されている。この要素の間に成立する「秩序」が、それがループになっているという性質から、システム全体の「秩序」として展開されるという論理の流れが、宮台氏が解説するシステムにはあるような感じがする。このようなシステム概念が、個々の要素の「秩序」にとどまらずに、全体の「秩序」をもたらすというのは、ちょうど数学の定理のように、この定義から論理的に導かれるものとなっているのではないだろうか。それがあるからこそ、システムの定義はこのような語られ方をするのではないだろうか。このシステム概念は、システムが「秩序」を持つということから抽象されて得られたのではないか。互いに前提を供給しあうループが存在するというのは、それは実際のシステムを観察するときに発見しやすい性質として捉えられるのではないだろうか。もしそうであれば、このこと(互いの前提供給のループが存在するという構造)が根拠になって、なぜ「秩序」が存在するかという問いに答えることが出来るのではないだろうか。これは逆に言えば、その前提供給のループが崩れたときに、それによって維持されてきた「秩序」も壊れるということを意味するだろう。これは一つの科学的な「仮説」となりうる。システムの中に前提供給のループを見つける、あるいは見つけられないという前提が確認されれば、その前提から、そのシステムでは「秩序」が成立する、あるいは「秩序」が壊れてしまうということが予見できるようになるのではないだろうか。このシステム概念が、本当にそれが「秩序」成立の根拠となるものだという論理的な展開はまだ確認していない。それは宮台氏が語るエントロピー概念と秩序概念を検討した後に、そう結論できるかどうかを見なければならないだろう。だが、この段階でも、もしそのような論理展開であるならば、このシステム概念の定義にはしかるべき理由があるのだということは理解できる。もしそのような理由がなければ、このシステム定義は、何か恣意的で勝手にとりあえずそのようにしてみただけなのだというふうに見えてしまう。数学における公理の設定も、その理論体系の全体を見て、何がその体系の定理であってほしいかという見通しがなければ、恣意的に勝手に公理を設定したように見えてしまう。公理など、そこに論理的矛盾が生じなければ何を公理にしてもいいのだという、絶対的な自由が公理の選び方にあるかのような錯覚を起こすだろう。実際には、数学においてはどのような体系を構築しようかという目的によって、ほとんど選びうる公理というものが決まってしまう。これこそがシステムの持つ秩序というものかもしれない。宮台氏の語るシステム概念が、論理的にどのような特質をもっているかを考えることは、エントロピーと秩序を語る回までとりあえず保留することにして、システム概念にとってそれ以外の重要な指摘を考えてみることにしよう。宮台氏は、システムを機械的なものと有機的なものの二つに分けて考察を進めているように見える。機械的なシステムは静的なものであり、それは均衡(釣り合いを取っている)という言葉で示されるイメージになる。一度秩序が確立されれば、それは均衡状態が続く限り静止した秩序を持つ。そこには変化というものがないという意味で秩序が成り立っている。変化がないのでいつまでも同一のままなのだ。これに対して有機的なシステムでは、そのシステムは外部とのコミュニケーションのもとにあり、何かが入れ替わるという変化が常に起こっている。変化が起こっていれば、それは秩序が破壊されているという結果を招く場合もある。同一性が維持されないと思われるからだ。しかし、有機体的システムでは、何かが変化しているにもかかわらず、その全体性は維持されている、つまり同一性が保たれていると判断される。このようなシステムを宮台氏は「定常システム」と呼んでいる。この定常システムにおいて、システムの本質的な概念である「ループ」というものが深く影響しているような気がする。「ループ」があるために、変化しているにもかかわらず、やがて元に戻ってくるという「定常性」を持つことが出来るのではないだろうか。社会学が対象とするシステムは「定常システム」として捉えられるという。これは後に「人格システム」「法システム」「宗教システム」「政治システム」などと呼ばれる対象として具体的に語られる。これらの同一性という秩序維持が、これらがシステムを構成しているということから導かれるものかどうか。もしそうであれば、これは社会学が提出する一つの「科学」的命題となりうるのではないだろうか。詳しく考えて見たいと思う。システムの概念は非常に抽象的なものであり、それを言葉で理解しただけでは頭に浮かんでくるイメージは貧困なものにとどまるだろう。この概念は、システムを利用した理論体系の全体像を把握した後にようやく明確に見えてくるものになるのではないだろうか。システムの構造がシステムの秩序と安定性に関わってくる。それが理解できたとき、システムの概念も捉えられたといえるのではないだろうか。とりあえずは、システムを単純な構造として、「前提供給」と「ループ」という言葉で理解しておこう。そして、これが「秩序」にどう関係しているかを、これからの社会学講座の展開で追いかけていくことにしよう。システム概念は、あくまでも秩序という現象の理解の道具として使われるという視点でそれを考えていこうと思う。
2008.07.07
コメント(0)
-
「近代」と「一般理論」の概念
宮台真司氏の「連載第二回:「一般理論」とは何か」では、「社会」という概念に続いて、「近代」と「一般理論」の概念について解説されている。この二つの概念も、辞書的な意味としてはぼんやりとイメージできるものの、明確に他のものと区別してこうだ、というような概念をつかんでいるとは言いがたい。これらの概念を明確につかむことは出来るだろうか。宮台氏は現在の日本を「近代成熟期」と呼んでいて、戦後の高度経済成長期までを「近代過渡期」と呼んでいる。イメージとしては、物の豊かさが飽和状態に達したかどうかで区別するという感じになるだろうか。また「近代」がスタートしたのは明治維新からという漠然とした理解もある。明治以前の江戸時代は「近代」ではないという理解だ。それでは、「近代」とそれ以前の決定的な違いはどこにあるのだろうか。板倉さんの『日本歴史入門』(仮説社)では、江戸時代は「身分制度の時代」と呼ばれ生まれつきで生き方が決まってしまう時代と捉えられていた。それが明治維新以後になると、一応は個人の努力によって運命を切り開いていける時代になった。学問による立身出世が可能な時代になっている。江戸時代だったら、どれほど有能であろうとも有力な家系に生れなければその才能を生かすことは出来なかった。しかし「近代」になった明治には、それまでなかった「自由」がかなり生れたという感じがする。「近代」については、いまもまだ「成熟期」という形で続いていると思われるし、身近に経験できるものなのでイメージは抱けるが、「近代」でないものを知ることが難しいので、差異による概念の理解は難しい。「近代」の概念はあまりにも豊富な内容を含んでいるので、「社会」の一面を見ているだけでは正確な概念をつかむことが出来ないのを感じる。宮台氏は、「近代」については後に詳しく言及すると書いていて、ここではまあぼんやりとしたイメージでもそれ以前の時代とは「何か」が違うものとして、特に「自由」の存在に大きな違いを見ることが出来そうなものとして捉えておこう。「一般理論」については、この第二回の講座ではかなり詳しく書かれている。これは「一般」と「理論」という二つの概念の単純な組み合わせで理解すると、具体的な対象についての「理論」というよりも、「一般」的な抽象的な対象に対する「理論」だというようなイメージになる。しかし具体性と抽象性というのは、同一のものが視点の違いによってある時は具体的なものとして理解され、ある時は抽象的なものとして理解されるという弁証法的な同一性(矛盾)を持っている。そうすると、対象の具体性と抽象性で「一般理論」を考えると、その理論が「一般理論」であるかどうかが分からなくなる。この区別が分かるような「一般理論」の概念(定義)は、「社会学では「一般性」という場合、文脈自由が指し示されています。特定の文脈に拘束されないことです」と宮台氏は語っている。「文脈自由」という特徴が本質的だということだ。ただし、この自由も「特定の文脈に拘束されない」という「特定の文脈」をどう見るかという視点に関わってくるような感じもする。これも、ある文脈が「特定」であるかどうかに弁証法性がありそうな感じがするので、「特定」という概念も検討する必要があるだろう。宮台氏は具体的な「一般理論」として経済学における貨幣の理論を例としてあげている。物の交換において「特定の文脈」とは、「交換当事者が互いに相手の持ち物を欲しがり、相手が欲しがる自分の持ち物を欲しないという「欲求の相互性」という文脈」を捉えている。何を欲求するかは人によって違い、「一般」化することができない。「特定」の状況だという判断だ。この文脈が、貨幣というものを設定すると消えてしまうという。宮台氏は、「誰もが貨幣を欲しがるとの前提で振舞えば済むようになります」というふうに貨幣の働きを指摘している。その個人が何をほしがるかという「特定」の文脈が、常に貨幣をほしがるということで一つに絞られてしまう。これが「一般」化であり、特定の文脈に縛られない「文脈自由」が実現されていると理解する。宮台氏は、貨幣のこのような「一般」性を「一般的購買力」とも呼んでいた。このような文脈自由な一般理論としては、社会学では「制度的役割による一般化機能」という例もあげられている。これはある種の人間関係において、たとえばマクドナルドの店でハンバーガーを買うときの店員との人間関係において、「店員が誰で、どんな人格で、どんな機嫌かといった雑多な文脈」は「特定の文脈」になる。これが「制度的役割」という了解がすべての人にあれば、このような文脈で人間関係を捉えなくてもすむようになる。相手が「マクドナルドの店員だ」ということが確認できれば、安心してハンバーガーを買うことが出来る。「特定の文脈」を意識する必要がなくなる。このように「貨幣」や「制度的役割」が特定の文脈を消してくれるなら、それに関する理論が「一般理論」として提出されることになるのではないかと思う。この「一般理論」に関しては、宮台氏は「(1)できるだけ多様な主題を、(2)できるだけ限定された形式(公式)で取り扱え るほど、理論の一般性が高いと見なされます。」とまとめている。これは自然科学の場合でいえば、武谷三男さんが提唱した三段階論における本質論的段階に当たる理論が、自然科学における最も一般性が高い「一般理論」だということになるのではないだろうか。天動説は、人間が地球上から見える視覚的データと整合性を取るという「特定の文脈」の下で正しくなるような理論だろう。ケプラーの太陽系に関する法則は、太陽系という特定の対象のデータとの整合性を取るという点でまだ「特定の文脈」が残る。文脈からまだ自由になっていない。しかしニュートン力学の段階になれば、質量を持つ物質という一般的な存在であれば、どの対象に対しても成立するという自由な文脈の下での法則性が提出される。最も高いレベルでの「一般理論」になるのではないかと思う。「一般理論」のイメージはこの説明でかなり明確になったと感じる。概念がかなりはっきりと見えてきた感じだ。科学というのは、最終的にはこのような一般性がもっとも高い理論を提出して本質論的段階が求められて終わるような感じがする。しかし、社会学の最近の状況は、このような一般理論が廃れているところに問題があると宮台氏は指摘する。一般理論の概念は、それが進歩発展の目標のように見えるのに、現実には必ずしもそれが目指されることがなく、むしろ個別的な、ある意味では末梢的だと思えるような分野に研究が集中しているようにも見える。これはどう理解したらいいだろうか。「一般理論が死滅しつつある理由の第一は「共通前提の崩壊」です」と宮台氏は語る。「共通前提」というのは、社会に生活する誰もが同じように考え・受け止めていた「前提」と考えられる。それがかつてあった時代は、自分が専門としている特定の領域の文脈で見えるものばかりを考えるのではなく、その共通前提で見えるものを考えるという傾向があったようだ。そうなれば特定の文脈というものが分岐せずに、共通前提という(ある意味では特殊な文脈かもしれないが、誰もが同じものを抱いているという点で一般化されている)一般化された文脈を持ちえたのではないかということが推論される。共通前提があった時代は「近代過渡期」と重なるようだ。それは社会に生きる人々の希望が単純に一つの目標につながっていた時代だとも言えるだろう。宮台氏も次のように書いている。「なぜ共通前提が崩壊したか。近代過渡期が終ったからです。近代過渡期とは、第二次産業(製造業)が中心という経済的に定義された社会段階。これに対比される近代成熟期とは、第三次産業(情報・サービス業)が中心という経済的に定義された社会段階です。ところが差異は経済に留まりません。近代過渡期には、郊外化で追いやられつつも村落的共同性が残存し、それゆえに「物の豊かさ」という国民的目標が成り立ち、それゆえに目標に近い「強者」と目標から疎外された「弱者」という差異が共通に主題化される。」国民的目標が一つに絞られていた時代は、その共通の思いが、そこから派生する論理的な結論を共有するようになり、感覚としても共通前提を持ちえたのだと感じる。そして、国民的目標がある意味で達成されたときに、その目標の下に一つにまとまっていた人々の心も、目標を失って共通前提を失ったといえるのではないだろうか。共通前提があるなら、その共通前提という文脈が結果的には一般性の高い文脈になりそうだが、それがない時は自分が関心のある特定の文脈に意識が集中しそうだとも考えられる。宮台氏は次のように書いている。「近代成熟期になると、郊外化で共同体が空洞化し、「物の豊かさ」が達成されたあと何が幸いなのか人それぞれに分岐し、人々が個室からメディアを通じて各自の別世界にコネクトし、「強者/弱者」図式では到底扱えない社会問題が噴出します。 それゆえ、まず「強者/弱者」図式を依り代にするドキュメンタリーが廃れます。ついでサブカルチャーも学問も同じく、手段は違っても共通の問題(戦後の再近代化、並びにそれがもたらす問題)を扱っているとの意識が廃れ、タコツボ化します。」共通前提の喪失は、どの立場の人間であっても最終的にはそれを考えようという目標を失わせる。それゆえに理論も一般化を目指すよりも、それぞれの個別の関心にもっとも答えるような方向で展開される傾向をもつ。「タコツボ化」するということだろう。学問の世界では、これらの状況に加えて「制度的な自己言及化」の問題があってさらに「一般理論」が衰退していくという。これは、他の世間と関係なく、その専門分野の学問業界内部で価値が高いとされる言説に研究者の意識が集中してしまい、世間の関心と専門家の関心が大きくずれてしまうことを意味する。共通前提がないので、世間がどのようなものに関心を持っているかではなく、自分が学問業界の中で高い地位を得られる問題は何かということに関心が集中するというわけだ。これはまさに「特定の文脈」での言説であり、「一般理論」にはなりえないだろう。「一般理論」という概念は、物事を理解する段階を考えるということでは、教育においては興味深いイメージを与える。これが廃れているということは残念なことで、僕などはむしろこのような理論のほうへの関心が高い。宮台氏は、最後に「皮肉です。社会学の一般理論を退潮させる原因が社会学の一般理論へのニーズを高め、社会学の一般理論へのニーズを高める原因が社会学の一般理論を退潮させる。とすれば、社会学の一般理論の退潮はむしろ一般理論へのニーズを表しているという他ないのです。」と語っている。このニーズが高まり、目から鱗が落ちるという見事な一般理論が登場するのを期待したいと思う。萱野稔人さんの一連の仕事が、そのような見事な一般理論の提出ではないかとも感じる。
2008.07.07
コメント(0)
-
宮台真司氏が提出する新たな概念
宮台真司氏が書いた「社会学入門講座」から、その科学性を評価してみようと思ったのだが、残念ながら法則性とそれから導かれる予想を読み取ることが出来なかった。これが読み取れなければ、板倉さんが言う意味での「仮説実験の論理」による「科学」の判定が出来ない。おそらく社会学における法則性は、その概念の難しさから来るのであろうが、簡単につかめるものではないのだろう。自然科学であれば、原子論や力学法則はその表現されたものが分かりやすいのだが、社会学では概念の難しさのせいで法則性が提出されたとしても、その意味を理解するのが難しいのではないかと思う。そこで社会学の科学性はひとまず置いておいて、宮台氏が語る社会学の学術用語としてのさまざまな言葉の概念について詳しく考えてみようと思う。その概念がうまくつかめたときに、もしかしたら社会学において、その科学性を評価できるような法則性の表現にぶつかるかもしれない。宮台氏は、「連載第一回:「社会」とは何か」という講座では、表題にあるように「社会」という概念について解説している。これは辞書的な意味では誰でも知っているようなありふれた概念だが、社会学ではもっと深みのある複雑な内容を持った概念として提出されている。宮台氏は「ある時代まで「社会」概念そのものが存在しなかった」と書いている。今社会に生きている我々は、周りにある「世界」(これは「現実」と言ってもいいものになるだろうか)を漠然と「社会」と感じている。そのようなものはかつてはなかったという。今では当たり前に周りにあるもので、それが何であるかがはっきり言えないものが、かつてはなかったという姿を想像することで、そのぼんやりとした「何か」が見えてくるかもしれない。人と人との関係というのは、人間が集団で生活し始めてからずっとあっただろう。その関係性が、あるときから「社会」というふうに呼ばれるようになったのはどうしてなのか。宮台氏によれば、「この概念が誕生したのは革命後のフランスのことで、革命の挫折(第一共和制から第一帝政まで)についての深刻な疑問が出発点にあります」と解説されている。フランス革命は、人々の間に次のような感覚をもたらしたという。「要は、皆よかれと思って革命をし、近代的な社会契約を結ぼうとした。それなのに、帰結が意図から程遠いものになってしまった。そのことから、個々人の営みが巡り巡って帰結する、個々人から見通しがたい不透明な全体性が存在するという意識が高まったのです。」「社会」が生まれる前の時代には、人々は親しい関係にある人たちの間で生活をしていたのだろう。そこでは、自らの行動が引き起こすであろう帰結は、経験的に誰もが見通せていたのではないだろうか。同じことが繰り返されて人々の生活が成り立っていた。生活が単純であり、それゆえ安定していたと言えたのではないだろうか。社会というのは、不特定多数の、名前もよく知らない匿名性を持った人々の間で生活をするというスタイルが普通の日常になったとき、「見通しがたい不透明な全体性」が感じられるようになって生れた概念なのではないだろうか。よく知っている人々ならその行動を予測することも出来るが、匿名性のある人の行動は予測することが出来なくなる。よく知っている人々は、自分を延長して考えれば理解できることが多いだろう。個人について言えることがそのまま集団に対しても言えることが多い。しかし、個人の延長ではない、まったく違う性質を持った匿名の人々の個性は、自分が知っている知識ではその延長として見通すことが出来ない。宮台氏が語る「社会」という概念は、それがこういうものだという具体的な属性を概念として提出することが難しいようだ。それは「このようなものではない」という概念で最初は捉えるしかないようだ。親しみのある人々と関係を持てるような集団ではない人間集団として最初はそのイメージが登場してくる。この「社会」の概念がはっきりと見えてくるのは、実は社会学という学問をある程度つかめた後になるようだ。したがって、この段階では「社会」に成立する法則といっても、言葉としては理解できるが、実際の法則性は概念としてはまだつかめない段階になる。それは「社会」概念をより明確につかんだ後にこのようなものかな、という感じで頭に浮かんでくるようになるだろう。それまでちょっと待つことにしよう。さて「社会」の概念は「不透明な全体性」という言葉で語られる。この概念がつかめれば「社会」の概念がつかめるわけだが、この言い換えは同じくらい難しい言葉になっている。この概念そのものをつかむのは困難だが、宮台氏は、このように「不透明な全体性」が生まれてくる原因に関して、社会学ではない他の理論がどのように法則性を捉えているかをいくつか説明している。無政府主義と呼ばれる考え方では、「個々人の顏の見えない大規模さが不透明な暴走をもたらす」というふうに考える。集団が大規模であることが「見通しがたい」ということの原因であるというわけだ。したがって、この「見通しがたい」ということを問題として捉えれば、つまりそれを「見通しやすい」ようにすることが解決だと考えるなら、無政府主義では、集団の大きさを制限することによって問題の解決を図ろうとする。これは極めて論理的な思考の展開だ。「大きい」ということに問題があるのだから、それを「大きくない」ように「小さく」しようという発想はまっとうな論理に見える。「無政府主義は、国民国家レベルの中央政府を否定し、国家の秩序維持機能を中間集団(家族でもなく国家でもない中間規模の地域集団や職能集団)のネットワークに置き換えようとする」という宮台氏の説明はなるほどと思えるものだ。ただ、これは「科学」として成立するかどうかは分からない。任意の社会集団に対して、このような解決方法が常に正しいという「実験」が成立するかどうかが分からないからだ。魅力的な発想ではあるが、その正しさは分からない。もう一つのマルクス主義は、「社会」の持つ不透明性の問題を捉えて、次のような考え方から解決方法を提出しているようだ。「マルクス主義は、恐慌を含めた社会の不透明な暴走は、市場の無政府性と、それを自らの利権ゆえに維持したがるブルジョア階級が支配する国家という暴力装置がもたらすものだと考え、プロレタリア独裁による市場の無政府性克服が処方箋だ、と考える思想です。」この「社会」の法則性を語る命題も、「科学」として正しいかどうかということはなかなか結論付けることが出来ないだろう。やはり「実験」が難しいからだ。「市場の無政府性」を持った「社会」は、必ずブルジョア階級の支配が見られ、不透明な暴走を起こすだろうか。かつての歴史は、マルクスの時代はそうだっただろうということを教えるが、これからの時代でも常にそうだといえるだろうか。そう言えるならこれは「科学」という真理になるが、そう言えなかったら「科学」にはならない。宮台氏は、「これに対し、社会学では、エミール・デュルケームが「国家(中央政府)を否定しない中間集団(職能集団)ネットワーク)」を構想し、『社会分業論』を執筆します」と書いている。ここで語られている「中間集団」というものが「不透明な全体性」という問題を克服するということが、もしかしたら社会学の法則性として提出されているのかもしれない。しかし、これも「科学」になるかどうかは分からない。いずれの法則性の提出も、現実の「社会」があまりにも複雑な構造を持っているので、それが一般化された形で命題として提出できないのではないかと感じる。ある視点(無政府主義的・マルクス主義的・社会学的)で捉えれば、その処方箋は上のように語られるが、その視点ではない別の視点で捉えた場合には、法則性そのものが違ってきてしまうように感じる。どの視点がもっとも有効なのかという評価を考えることも出来るだろうが、人間の歴史は、どれが正しいかという比較としてこの問題を提出しているのではなく、これが最も優れて正しいと信じた人々によって、その法則性を現実化しようとして「運動をした」という現象を教えているのではないかと思う。「社会」の概念は、この段階では完全には把握できない。「社会」の概念は、社会学というものの全体像をとりあえずぼんやりとでもいいから捉えた後に、何とか明確にする出発点に立てるというものになるだろう。100%明確にするには、社会学の全体像もそれなりにはっきりつかむ必要がありそうだ。このように、まだはっきりとしない「社会」概念ではあるけれども、「社会学」という「学」をつけた言葉の概念は、最後に次のように宮台氏はまとめている。「以上を踏まえて学問的に定義すると、「社会」とは、私たちのコミュニケーションを浸す不透明な非自然的(重力現象などと異なる)前提の総体のことです。そして社会学とは、この不透明な非自然的前提の総体が、いかに存続・変化するかを問う学問なのであります。」「社会」はつかみがたいものであるけれども、その全体性は確かに存在している。そしてその存在が持続する部分と変化する部分を捉えて、そこにある法則性を捉えるのが「社会学」という学問であるとここでは述べているようだ。この法則性は、具体的にはどういう形で述べられるだろうか。その論理展開を捉えてみたいものだ。その論理展開を捉えるための道具としての概念が、宮台氏の「社会学入門講座」では語られているようだ。宮台氏はその講座において、システムであるとか行為であるとか自由であるとかいう言葉の概念を解説している。それは社会の法則性を語るために必要な道具としての概念だ。この道具を駆使して論理を展開し、その結論として社会の法則性を語る命題が理解される。その概念を正確につかみ、論理の展開を追いかけることが出来れば、社会の法則性を語る社会学の命題が「科学」としての資格を持つかどうかの評価が出来るかもしれない。宮台氏の語る用語の概念の正確な理解に努力してみようと思う。
2008.07.06
コメント(0)
-
社会「科学」の可能性
自然科学の分野が「科学」であるという共通理解は、自然科学系(日本では理科系、宮台氏の言葉でいえば数学系)の人間にはだいたい共有されている認識だと思う。それは、板倉さんが語る意味での「科学」という概念で考えても、確かに「科学」だと納得できるものだ。自然科学で対象になるものは一般的な抽象的存在になる。物質の運動の法則を理論化しようとしても、それは目の前にある具体的な物質にのみ当てはまる経験的な法則ではない。その物質がこのように運動したからという経験を記憶しておいて、この次もたぶんこうなるだろうというような形で記述されるものではない。運動を考察する力学では、物質一般としてある「質量」を持った対象について成立する法則を求める。もっとも単純で考えやすいものは、その質量が1点に集まった「質点」というものを想定して、その質点にかかる力を考察する。「質量」や「質点」という概念が、力学の対象を一般的に扱うことを可能にし、その概念操作としての思考が力学のさまざまな命題を発見させ、それを「仮説」として考える。その「仮説」が常に成り立つ命題であるという「実験」を考案して、「仮説実験の論理」を経ることによって力学の「仮説」は、現実的な真理(相対的真理)となり「科学」になる。自然科学の場合は、対象を一般化するための概念を抽象化することが出来、ある法則性を再現する実験を人為的に設定することが可能になる。そのため、「科学」としての性格を持ちやすく、多くの分野で「科学」であることが確かめられた命題が存在する。それに対し社会「科学」系の場合は、長い間「実験」が出来ないということが、それが「科学」になることを阻んでいたようだ。僕は社会「科学」系というふうに、「科学」という言葉をカッコ付きにしておいた。これは「科学」という言葉を、板倉さんが語る意味で使いたいからだ。辞書的な普通の意味で「科学」を捉えれば、社会「科学」系の知識も、それなりに科学と呼べるものがあったと言えるだろう。エンゲルスは、マルクスとともに考案した社会主義を「科学的社会主義」と呼んで、それ以前の思弁的な「社会主義」と区別をしていた。この場合のという言葉の「科学」は、思弁的(すなわち頭の中で考えただけ)ではない、現実に有効な指針をもたらす命題を提出できる理論だというような考え方があったに違いない。をそういうふうに考えて概念化することも出来るだろう。だがそのような意味でのは、必ずしも「仮説実験の論理」を経て得た真理であるという前提を含んでいない。思弁的なだけではない、経験的な確かさがあるということがの条件として想定されている。このような知識は、経験した限りでは正しいかもしれないが、未知なる対象に対してもその理論を応用したときに、100%正しいという信頼感を持って適用できるかというほどの信頼感はない。いつでも同じ法則が適用できるということを、板倉さんは「馬鹿の一つ覚え」という比喩で語っていたが、それが出来るということが板倉さんの言う意味での「科学」だ。マルクス主義のさまざまな命題は、社会主義国家の崩壊とともに、必ずしも正しい命題ではなかったということが証明された。だから、これは板倉さんが言う意味での「科学」ではないことが確かめられたといえるだろう。そもそも「主義」という言葉が付着した言葉は、その真理性は宗教的な信仰のようなもので、信じている人間には真理だが、疑いを入れたい人間にはいくらでも疑うことが出来るというものになるだろう。現在の学問の世界では社会「科学」と呼ばれるものは数多く存在するが、その中に、板倉さんが言う意味での「科学」は極めて少ないようだ。問題はやはり「実験」という概念の捉え方によるものだろう。社会の現象は、人為的に操作することが出来ないので「実験」をすることが出来ないという捉え方になってしまう場合が多い。したがって、社会「科学」の命題は、現実の経験をよく考えて、経験する限りでの現象に対してはすべて整合的な説明がつけられるものだから正しい(真理だ)とされる発想になっているのではないかと思う。板倉さんがよく語っていたが、日本には教育という対象に関しては「科学」的真理を語った命題はないという。その正しさは、教育に対する真摯な姿勢から来る信念に基づいているという。心がけが正しいから教育としても正しいのだという信念だ。だが、これは教育効果というものを数字で測ったりすると、正しい信念と心がけの下でやられた教育が、必ずしも効果をあげていないという結果が出ることも多い。この場合、結果を見て、そのやり方は「科学」的には間違っているのではないかという主張は、教育界ではなかなか受け入れられない。それは信念や心がけが弱かったからだと判断される場合が多い。教育における命題は、事後的に解釈されることが多く、大部分は「反証可能性」を持たない。つまり大部分は「科学」ではない。このように考えると、社会「科学」の分野は「科学」になる可能性を持たないのではないかとも考えられるが、板倉さんは、仮説実験授業を提唱して教育「科学」を打ち立て、『日本歴史入門』(仮説社)を書いて、歴史「科学」を打ち立てたと語っていた。これらの教育や歴史が「科学」になったというのは、どのような根拠から主張できるのだろうか。これは「実験」というものの捉え方(その概念)が、普通の意味とやや違うことからきている。板倉さんの「実験」概念(実験観)では、社会「科学」の分野でも十分「実験」が出来るのだ。それは、人為的にある状況を設定して、その中で観察をするという「実験」観ではない。板倉さんが言う「実験」とは次のようなものを指す。未知なる対象に対してそれがどうなるかという現象に対する知識を持たないとき、自らの「仮説」を根拠にして論理的に予測を立てる。そして、その予測を、対象が未知であるときに明確に表現しておく。それは未知が既知になったときに、その予測が当たったかどうかが二者択一的に評価できるような形で表現しておく。解釈によってどうにでも出来るような表現はしておかない。このような準備をして未知なる対象の事実を既知になるように調べる。板倉さんの言葉で言うと、「仮説を持って現実に問い掛ける」というようなことになるだろうか。教育に関して言えば、仮説実験授業が発見した法則性が、これから授業をする一般的なごく普通のクラスで必ず成立するということが見られるかどうかを問うことが「実験」となる。この「実験」は、そのクラスがごく普通のクラスではなく、特殊性を持ったクラスであれば失敗する可能性がある。これは事後的に解釈してしまえば、「反証可能性」を否定することになり、「仮説実験の論理」に反する。この場合は次のように考える。ごく普通のクラスというのは、ごく普通であるからにはランダムに選んだとしても日本にはかなりの高い確率でごく普通のクラスが選ばれるはずだ。それをたとえば90%以上と設定しておく。だから、その対象がごく普通のクラスであるかどうかを事後的に判断するのではなく、「実験」の前にそれは90%以上あると設定しておく。つまり、仮説実験授業が、それを行ったクラスの90%以上で成果をあげるなら、その法則性は正しいのだということが「実験」で証明されたと受け取るのである。事後的に解釈するのではなく、事前に条件を設定しておくことによって、それを単なる解釈から「仮説実験」という概念に引き上げる感じだ。仮説実験授業の場合は、これから授業を行う前に予測するので、「実験」というイメージにふさわしい感じがするが、歴史の場合は、対象とするものが過去の事実なので「実験」ではなく解釈のような気がしてくる。だが、これも「未知」という概念が「仮説実験の論理」につながってくる。すでに既知になっている歴史事実なら、それを解釈して整合性を取るという論理展開になっていくだろうが、未知なる歴史的事実に関しては、それを知ってから整合性を取るということが出来ない。たとえ未知なる歴史的事実であっても、ある法則性に従えばこのようなこととして起こらざるを得ないだろうということを考えるのが、歴史における「仮説」から得られる予想になるだろうか。歴史的事実というのは、完全な形で残されている対象は少ない。権力者が残した歴史は、権力者にとって都合がいいように書き換えられている可能性が高いし、平凡な事実は特に記録しておくということがされずに、今のイメージで昔を想像して歴史的事実を捉えている場合が多い。未知なる歴史的事実や、勘違いしている歴史的事実を、どのようなものが本当に正確な事実なのかということが突き止められれば、それを突き止める前の予想はすべて「仮説実験の論理」における「実験」の前段階としての「予想」として設定することが出来る。板倉さんは、日本歴史において、江戸時代の農民は主として何を食べていたかという問題を設定した。そして、おそらく米を食べていただろうという予想を立てていたようだ。これは、それまで多くの人が描いていた江戸時代のイメージとはまったく違うものだ。江戸時代の農民は苦しい生活をしていて、白米を食べることなど出来ず、稗や粟を食べていたというイメージがかなり流通していた。板倉さんがこの予想を立てた基になった法則は、歴史の法則という感じではないが、原子論の考え方が基になっている。原子論では、原子が消滅したり付け加えたりというような、原子そのものの移動がなければ、その物質は増えもしないし減りもしないという命題がある。この命題を基に江戸時代の農民が最も多く生産していた穀物は何かということを板倉さんは調べた。この調査の正しさについては板倉さんは直接語っていないので板倉さんを信じるしかないのだが、さまざまな記録資料などを評価して、主に統計的な視点からそれを調べたようだ。その結果は、農民がもっとも多く生産していたのは米であり、しかも当時の農民は人口の90%近くを占めていたということだ。武士などの支配階級が米を農民から取り上げたとしても、彼らがそれをすべて消費することはおそらく出来ない。米を無駄にせずに消費するには、それが農民に帰って来るシステムがなければならない。米の生産が落ち込むような災害があった場合は、米が回ってこないために飢饉が起こることがあるだろうが、そうでない時は日本の農民は自らが生産した米を消費して生活していたと考えざるを得ない。そうでなければ日本の農民の大部分は死んでしまい、日本の国はなくなっていたかもしれない。日本の農民が江戸時代に米を食べていたというのは、もちろん直接見ることは出来ないし、記録に残っていないのでそれで確かめることも出来ない。だが穀物の生産量というものは記録を調べて確認することが出来る。この記録を確認する前に、原子論的な命題から「仮説」を設定して、その「仮説」を持って江戸時代の記録に問い掛ける、まだ未知のデータである穀物生産量を調べるということが「実験」になる。そのようにして板倉さんは、日本歴史のある事実に関して「科学」的な真理を打ち立てたと言えるのではないかと思う。宮台真司氏の社会学も、それは「科学」として打ち立てられたものだといわれている。その「科学」性を今度は考えてみようと思う。人間の意志の自由を社会学ではどのように処理しているのか。法則性の成立にとって例外性をもたらしそうな「意志の自由」は、社会学という「科学」ではどのように処理されて「仮説実験の論理」の適用がなされているのだろうか。宮台氏の社会学入門講座からそのような考察をしてみようと思う。
2008.07.06
コメント(0)
-
心理学や言語学は「科学」になりうるか
ソシュールは言語学を科学として確立したといわれている。それまでの事実の寄せ集めを解釈していただけの言語理論を、科学という理論体系として打ち立てたと評価されているのだろう。この解釈学から科学への飛躍は、その研究対象として「ラング」というものを提出したことに求められている。「ラング」の発見こそが言語学という科学を生む基になったというわけだ。「科学」という言葉の概念は、人によってかなり違うところがあるだろう。僕は、仮説実験授業の提唱者の板倉聖宣さんからその概念を学んだ。その概念は、「科学」と科学でないものを明確に区別し、科学の有効性をはっきりと分からせてくれるものとして、僕は板倉さんが語る以外の概念で「科学」を捉えることが出来なくなってしまった感じがする。そこで、板倉さん的な概念でソシュールが語る言語学が果たして科学になるものかというのを考えてみたいと思う。板倉さんが考える「科学」というのは、「仮説実験の論理」というものを経て、それが一般的・普遍的な真理であるということが確立された命題あるいは命題群(理論体系)のことを指す。「科学」というのは、現実の対象に対して成立する「真理」を意味する。そして、その真理は一般的・普遍的であることが特徴で、ある時間・場所・対象がたまたまそうであったという偶然成立した真理とは区別される。「仮説実験の論理」というのは、仮説を証明するための実験という検証についてのものだが、これは単に事実を発生させるということを目的として対象を操作しようとする「実験」ではない。それは必ず「未知の対象」に対して問いかけるという行為になっている。それまでの法則や知識を確認するために実験をするのではないのだ。「仮説」として提唱されている命題が、未知なる対象に対しても成立するかどうかを検証するための実験だ。この実験が確かに成立することが確認されれば、その事が「仮説」が現実的な真理になるということを示すものだと受け取る。それが「仮説実験の論理」というものになる。「未知なる対象」というものが、論理的には「任意の対象」と重なるものになり、それによって命題の真理性を現実に確認しようとするものだ。これは形式論理としては論理の飛躍になる。具体的な対象に対して確認したものは、それが「未知なる対象」であっても、形式論理としては決して「任意の対象」にはならない。しかし、それを「任意の対象」として解釈することに蓋然性があるという判断から、この蓋然性が、エンゲルスが言うところの「相対的真理」をもたらし、その真理性によって「仮説」を「科学」だと判断する。「科学」が真理だというのはそのような意味で言うのである。ソシュールの伝記的な事実には、比較言語学の分野において、今は失われてしまったがかつてあったであろう発音を予測していたというものを読んだことがある。ソシュールは、若い頃から、真理としては単に現象を解釈して整合性を取ったものではなく、未知なるものの謎を探り、一般的な理論から予測される個別的な「事実」というものを予測するという理論活動をしていたようだ。これは「仮説実験の論理」に近い行為のように僕は感じる。板倉さんは、「大地・球形説」というものを「科学」の中に入れている。これは、地球が丸い(球形だ)という命題が真理であることを主張するものだ。これは一見個別的な事実を語っているように見える。普遍的真理である「科学」と呼ぶのがためらわれるような感じがするだろう。しかし、この命題の結論には、一般的・普遍的に成立する法則が求められ、それを現実に適用することによって論理的な帰結として地球が丸いということを語っている。結論は個別的なことに関する言明であっても、その理論活動は、一般的・普遍的な真理が求められ、その部分を「科学」と呼んでもいいのではないかと思う。地球が丸いことは、地球の中にいて、そこから離れられない人間には、直接視覚によって確認することの出来ない事実になる。これは、地球上にいる限り、論理によって結論せざるを得ない命題となるだろう。これは、月食の観察や船から見える山の観察など、さまざまな推論を元にして論理が展開されるが、詳しく考えるのは項を改めてからにしよう。いずれにしても「仮説実験の論理」によって、一般的・普遍性のある真理が求められるというのが「科学」の必要十分条件となる。それは、未知なる対象に対して実験をする場合でも、常に成立することが確かめられるという経験がなければならない。経験していないことに対しては、経験する前に事実としての結果をいうことは出来ないが、予想することは出来る。そしてその予想が常に正しいというのが「科学」の必要十分条件だということになる。さて、このようにして確立された「科学」はいくつかあるが、まだ「科学」であるかどうかがはっきりしていないものに対しては、それをどう受け止めればいいだろうか。一つにはカール・ポパーが語ったような「反証可能性」を考えて、その理論を反証する試みが不可能だと結論されたときに、「それは科学ではない」と結論するという考えがある。これは「仮説実験の論理」から派生する見解としても理解できるので、一つの評価方法として納得できる。ある実験結果が反証を示しているように見えても、どんな反証を提出されても反証されないのであれば、「仮説」を検証する「実験」に意味がなくなり、それは現実に対する真理とはならない。そうであれば「科学」ではないと結論できる。しかし「反証可能性」を確認するための論理は非常に難しいのではないかと思う。その命題がつまらないものであれば、「反証可能性」はすぐに理解できる。しかし、それが現実世界の複雑な対象を深く捉えたものであるなら、その「反証可能性」を見ることは極めて難しい。「反証可能性」という言い方は、方法の一つとしては納得が出来るものの、実際にそれである理論を評価しようとすれば、なかなか評価できる理論がないというのが実際ではないかと感じる。「反証可能性」よりも見やすい視点として、その理論の構築が、現象が起こった後に解釈をするという「事後的解釈」が常に伴うものであるかどうかを見たらどうだろうかと思う。「仮説」というのは、未知なる対象に対して、その現象が起こる前に予測をするために提出される。事後的な解釈をすることが出来ないというのが「仮説」の基本的な特徴だ。もし、その理論が予測をするものではなく、事後的な解釈しか出来ないような体系になっていれば、それは「仮説」を設定することが出来ず、未知なる対象が従う法則を提出して予測することも出来ず、決して「科学」にはなりえないだろう。言語学というのは、三浦つとむさんの言語学でさえも、それはすでに観察された言語現象をよく観察して、その中から法則を読み取るという「事後的解釈」をするものだった。ある言語法則を「仮説」として打ち立てて、その法則を未知なる言語現象に対しても適用して、それが必ず成立するかどうかという「実験」はなされていない。板倉さんの言う意味での「科学」にはなっていない。三浦さんは自分の言語学が「科学」だと言っていたようだが、板倉さんが語る意味の「科学」の概念は、最後まで三浦さんは持ち得なかったとかつて板倉さんが語っていた。だから、本人がその言語学を「科学」だと呼んでいても、僕はそれはまだ「仮説」の段階にとどまっていたと思っている。では、その「仮説」の段階の三浦さんの言語学を「科学」という真理にするための「実験」はどのようにすればいいだろうか。これはきわめて難しいのではないかと思う。言語現象には、言い間違いや例外というものが極めて多い。何らかの法則を提出しても、その法則に反する現象がいくらでも見つかる。そして、それが例外であって、法則の本質は保てるのだと判断しようとしても、その言い間違いのほうが社会的に流通してしまえば、言い間違いが言い間違いでなくなってしまうという現象まで現れる。言語現象は、原理的に、それが正しい言語の使い方であるかどうかが証明できないという本質を持っているのではないだろうか。そのような本質があるからこそ、どうしてそうなのかは分からないけれど、みんながそう思っているということが社会的に「真理」になるような、ウィトゲンシュタイン的な「言語ゲーム」の考え方も生まれてくるのではないだろうか。言語現象は、原理的にそれを「事後的に解釈するしかない」のではないか。それを予想しようとしても、予想に反するものが肯定的に法則化されてしまうのではないだろうか。このようなものには、一般的・普遍性のある法則が求められないのではないだろうか。似たような理論体系に心理学というものがあるような気がする。心理学が対象とするものは、人間の「心」というものだが、この「心」というものは客観的に観察することが出来ない。「心」にどのようなことが起こっているかは、すべて主観の判断を通して知るしかない。そうであれば、どのような心理現象を予測しても、その予測に反するような主観を持つことが可能になるので、実験が成立したかどうかが信用できなくなる。フロイトが発見した「無意識」の考え方は、心理学において非常に重要な言明であり、それは心的現象を理解するのに有効性を発揮すると思う。しかし、「無意識」の存在を科学的に証明しようとしたり、ある心的現象が、「無意識」というものが存在するから起こるのだという法則を証明しようとすれば、それは「仮説実験の論理」による証明にならない。「無意識」は、その定義から言って、本人には決して意識化できない・分からないものだ。そして、外から観察できるのは「無意識」ではなくて、その人がどのように行動したかという姿が見えるだけだ。「無意識」の影響によってそれがおきたというのは、いつも事後的に解釈されることになる。日常生活における心的現象や言語的現象を対象にする限りでは、心理学も言語学も、板倉さんが言う意味での「科学」にはならないような気がする。心理学や言語学を「科学」として確立するためには、そのような対象を棄てて、新たに「科学」としての対象になるような概念が必要だろう。心理学では行動主義と呼ばれる考え方が、科学として確立できるような対象を発見しようと努力したらしい。しかしこれはあまりうまくいっていないようだ。心理学が個人の心理という個別的・具体的な対象を扱っている限りでは、これは「科学」にするのは難しいかもしれない。むしろ、広告業界などが、どのような広告が多数の人に影響を与え、購買意欲という「心」の作用を掻き立てるか、などという問題設定をした方が「科学」としての心理学に近いものになるのではないだろうか。ヒトラーの宣伝活動などは、心理学の対象としては興味深いものになるかもしれない。同じように、言語学も、個々の言語現象を対象にしていたのでは「科学」になりえないのではないかという気がする。ソシュールが個人の言語活動を、その研究対象から排除したのは、このような考え方があったのではないだろうか。一般性や普遍性を求めるには、個人を超えた言語の対象を設定して、そこに見出せる法則性をこそ求めるべきだと考えたのではないだろうか。ソシュールが設定したラングという新しい概念が、言語学を「科学」にするために役立ったのかどうかの評価はまだ出来ない。ラングについてそう判断できるほどの知識がないからだ。しかし、そのような視点でラングについて調べてみようかという意欲は湧いてきた。適切な概念は「科学」の成立に大きな貢献をする。原子論という「科学」には、原子の概念が重要な役割を果たした。言語学という「科学」において、ラングがそのような役割を果たしているだろうか。調べてみたいことだ。
2008.07.05
コメント(0)
-
言語の「価値」という概念は、思考の展開にどのような新しさをもたらすか
内田さんが語るソシュールには言語の「価値」という概念が登場する。この「価値」は辞書的な・日常的な意味とは違うものを含んでいる。そこには新しい概念が表現されている。この「価値」という言葉によって新たに発見された概念は、思考の展開においてどのような利用のされ方をしているだろうか。そして、この概念があるおかげで、言語現象の複雑な側面がよりはっきりと見えてくるということがあるだろうか。もしそのような有効性をこの概念がもたらすなら、人間は新たな概念を生み出す言語によって、現実世界を人間に理解できる形で切り取ったといえるのではないだろうか。さて「価値」というのは、それが何か貴重な、人間にとって大事だと思えるような性質を持っているというときに「価値がある」という言い方をする。だから、「言語の価値」という言い方を辞書的に受け取ってしまえば、「言語がいかに貴重で大事か」ということを指し示すものと解釈されてしまう。しかし、このような意味ならばわざわざ新たな概念として考える必要はない。辞書的な、それまであった概念で理解していても十分だ。ソシュールが語る「価値」は、それが個別的な性質として大事だとかいう感覚を生むものとして捉えられているのではない。つまり、自分にとっての個性的な「価値」を語っているのではない。社会の中で、誰もがそれを欲するというとき、多くの人がそれを欲望するということが確認されるとき、その対象は、他の欲望されないものよりも「価値がある」という判断をされる。この「価値」は、他の存在との比較によって相対的にそれが高いか低いかが判断されるものとして想定されている。この「価値」にとって重要な性質は、それがその対象固有の属性によって「価値」の高さが判断されるのではなく、他との比較によって判断されるということだ。「価値」の高さは、その対象物が現実世界の全体の中で占める位置によって決定される。同じ対象物が、違う位置にあるときには「価値」が変化すると考える。内田さんが語っていた例では、タイタニック沈没の場面のボートの「価値」と、公園の池でレジャーを楽しむためのボートの価値との比較だった。タイタニック沈没の場面では、それこそボートの「価値」は命と引き換えと言っていいくらいだから、全財産を出しても惜しくないくらいの「価値」を持つだろう。だが、池で楽しむためのボートに全財産を出すような人間はいないだろう。同じボートでも、そこでの「価値」はまったく違う。この「価値」の考え方は、経済学などでも「商品の価値」という新しい概念をもたらす。商品は物質的存在として固有の「使用価値」をもっている。その「使用価値」は、その使用の目的に一致する欲求を持っている人なら、その人に対しては大きな「価値」を持つ。だが、この個別的な「価値」の概念では、資本主義における商品の分析をすることが出来ない。商品というのは、多くの人がそれを欲するという「需要」が「価値」の大きさに関係してくる。この意味での「商品の価値」は、やはりその商品に固有のものではなく、それがどの程度供給されるかという相対的な関係も考慮して決定される。このように「価値」に新たな概念が発見されると、現実世界で、昨日まではそれほど「価値」が高くなかったものが、いま信じられないくらいに高い「価値」を持ったというような不思議な現象を見たときに、整合的な説明をつけることに成功する。新たな概念が、複雑な現実を理解するのに役立つという経験が出来る。このような新たな概念がもたらす有効性を、「言語の価値」という概念によっても経験することが出来るだろうか。もしそれが経験できるなら、ソシュールによって発見されたこの新しい概念は、ソシュールの偉大さを示すものとなるだろう。ソシュールが考える「言語の価値」も、他の存在(この場合は言語になる)との比較から生まれる「価値」になる。固有の使用価値(言語の場合は、何らかの意味を伝える媒体としての「価値」と考えられていた)を指しているのではない。しかしこの「価値」は、商品の場合のように、誰もが欲するという欲望の対象として想定することは出来ない。言語は商品ではないからだ。誰でも使おうと思えば自由に使える。財貨を差し出してその代償として手に入れるものではない。言語が、それに内在する固有のものと違って、他の言語との比較によって持ちうる「価値」とはどのようなイメージになるだろうか。それは示差性というもので語られていた、「他のもの(言語)ではない」という性質を指しているもののようだ。言語の「価値」というのは、その言語が指し示すもの(意味)が何であるかということをイメージするのではなく、それがどのようなものではないかという意味をもたらすものとして捉えられている。このように、否定の範囲を示す記号として言語の「価値」を捉えると、それはいったいどのような思考の展開をもたらしてくれるのだろうか。言語の示差性が「価値」の違いを示すという発想は、言語が現実世界と対応して表現されるという前提を置いたとき、現実世界の差異という現象が、言語の示差性として反映するという考えに結びつく。そして、これを反映という受動的な性質に止めずに、より積極的に言語の示差性によって現実世界の差異を明確にしていくという逆転の発想に結びつけることが出来る。言語の「価値」は、現実世界の差異を捉える認識と関係させることが出来る。「価値」の違う言語を持つことによって、現実の差異をどう捉えているかという違いもそこから読み取ることが出来る。「価値」の概念は、人間が現実世界をどう捉えているかという認識の問題を考えるという思考の展開をもたらす。これは「価値」という概念なしに捉えるのは難しい、かなり複雑な現象ではないだろうか。数学で数を学習するときに、数の言葉が乏しかった人間集団の例を出すときがある。その集団では、数の言葉としては1と2しかない。3以上はすべて「たくさん」という言葉で一括して表現されてしまう。また0(ゼロ)はたいへん難しい概念なので、このような乏しい数の語彙の集団ではもちろん0(ゼロ)という数の言葉もない。0(ゼロ)は概念化されていない。この集団では、1は一人称に対応する「私」と関係し、2は二人称の「あなた」と関係していると考えられている。三人称以上はすべて一括して同じだと捉えられている。この人々にとって、世界は1と2と「たくさん」という3つに区切られていることになる。1や2は、固有の性質からそれが考えられているように見えるが、「たくさん」は、固有の性質というよりも、それは「1ではない」「2ではない」ということから「たくさん」だと判断されている。客観的な物質的存在として網膜に映っている像としては同じでも、我々と世界の切り方が違う人々の姿がここには見られる。「世界の切り方が違う」という判断は、言語の「価値」という概念からもたらされるものではないだろうか。ソシュールが考える「価値」は、商品で言えば「使用価値」に当たるものではなく、「交換価値」に当たるものになる。これは、商品ではその商品という物質的存在に内在するものとは考えられていなかった。他の商品との比較によって、現象として現れるものとして捉えられていた。したがって、そこに「価値がある」というのは、ある意味では妄想であり、人間の頭の中にしか存在しない「価値」だと言ってもいいかもしれない。言語の「価値」という概念からも、言語が持つこのような妄想性が思考の展開としてもたらされるのではないだろうか。言語で表現されたことというのは、現実を反映して、現実に存在するものに名前をつけたのだとする解釈が出来るような経験が多い。そうすると、言語で表現することによって、そこで表現されたものが実在するという錯覚を起こしやすい。このとき、本当は存在しないものが存在すると考えてしまえば、それは妄想としての「価値」が、言語に内在する実体であると受け取ってしまった誤謬になるのではないだろうか。言語の「価値」は、言語によって引き起こされる「妄想」の理解に役立つかもしれない。宮台真司氏が憲法9条を論じるときなどに、それをベタに文字通り受け取るのではなく、ネタとして戦略的に解釈すべきだという主張をすることがある。これは、言語が持つ「価値」が妄想的になることをうまく利用すべきだと理解すると分かりやすいような気がする。憲法9条が、日本が国家としていかなる戦力も持たないと語っているのは、その固有の意味を了解すれば、戦争を行う能力のある軍隊は持たないという宣言だとしか理解できない。つまり、自衛隊といえども、憲法9条をベタに解釈すれば憲法違反になるもので、持つことが出来ないと考えなければならないだろう。しかし、この文章の「価値」は、日本が戦争に負け、しかもその戦争によって多大な被害を、交戦国だけでなく自国民にも与えたという状況の下で考えられなければならない。軍隊という戦力は、自国を守るためのものではなく、そのような大きな被害をもたらした原因となるような戦力を持たないという意味で、その「価値」を理解しなければならないだろう。言語表現を、その「価値」にしたがって意味を理解すると考えるなら、憲法9条で宣言したからといって、一切の戦力が日本からなくなると考えるのは「妄想」にしか過ぎないと理解したほうが正しいだろう。「戦力」という言葉は、その時々の状況によって、「何ではないか」という「価値」によってその意味が理解されるものになるのが言語の本質として正しいだろう。宮台氏によれば、朝鮮戦争の際に、アメリカが日本に対して戦争に協力し、参戦するように求めたという歴史があったらしい。しかしその要求に対し、時の首相の吉田茂は、憲法9条を盾にとって、アメリカの参戦要求を突っぱねたと言っていた。憲法9条をネタとしてうまく利用したのだという評価を宮台氏はしていた。確かにそのとおりだなと僕も思う。言語表現の解釈が時と場合によって変わるというのは、言語の「価値」の違いからもたらされる。それは、世界の切り取り方が違うことから生まれるものだ。だから、言語表現というのは、それを固定した意味で考えていても正しい評価は出来ないだろう。「価値」を正しく受け止めてこそ言語表現の評価も出来るのではないかと思う。このソシュールの「価値」の概念は、ウィトゲンシュタインが語る独我論において、個々人によって世界が違うという主張の解釈も整合的に行えるような感じがする。言語の理解というのは、共通部分が多いものの、個々人によって「価値」の違いが微妙に存在するのではないかと思う。それが、個々人の世界の切り取り方を違えてしまい、それぞれ独自の世界だと思わせるような根拠を生むのではないだろうか。ソシュールの「価値」という概念は、ソシュールの基本的な主張を支える重要な概念になっているのではないかと思う。
2008.07.04
コメント(0)
-
新しい概念の獲得は思考の展開にどのような影響を与えるか
ソシュール的な発想で考えれば、言語は、混沌として区別のはっきりしない現実に対して、言語で表現することによって概念の差異をはっきりさせ、現実にある構造を持ち込んでそれを理解しようとする。言語の発生と同時に、現実の対象を概念的に捉えることも可能になり、それが思考の対象ともなると考えているようだ。それを言語で捉える前は、それが存在していたとしても、その言語を持たない人間にはそれが見えていない。devilfish という言葉を持たない人間には、devilfish という存在は見えていない。従ってそれを考察の対象にすることも出来ない。思考の展開には言語が必要だというのは、野矢茂樹さんが語るウィトゲンシュタインの発想でもあった。三浦つとむさんは、かつてヘーゲルを説明した文章で、思考の展開というものを概念の操作で説明していたように記憶している。概念を操作するとしたら、そのラベルとしてつけられている言語を操作することにもなり、ウィトゲンシュタインが語る「論理形式」に従った操作のようなものになるのではないだろうか。違う側面から思考というものに切り込んださまざまな発想が、最終的には似たところに落ち着くというのは、それが真理である可能性が高いのではないかと思う。概念の獲得は、思考の展開に影響を与え、豊富な概念を理解している人間は、現実を広く深く捉えて思考することが出来るようになるだろう。そして概念が言語を通じて理解されるとしたら、語彙を豊かに持っている人間ほど思考も豊かになるといえるのではないかと思う。この語彙というものは、現在生きている我々は、言語の意味も言語を通じて教育される。その概念の理解は、現実の経験を通じてやられた方がより深い理解が出来るようになるだろうが、言語なしに経験を反省して言語を作り出すというやり方ではなく、まず言語としてのある言葉の提出があって、その言葉の意味を理解するために経験に助けを求めるという順番になる。ある種の言葉は日常的には単純な意味を持っていて、それを辞書的な意味として理解している場合が多い。しかしその単純な意味では複雑な現実を充分思考することが出来ない場合も多い。そこで同じ言葉でありながら「術語」と呼ばれる専門用語(学術用語)が新たに作られることがある。これは新たな概念が作られて、その概念で現実を切り取ってより複雑な構造を把握しようとするものだ。この「術語」を理解したとき、人間の思考の展開はどのような影響を受けて、現実をどのように深く広く把握することが出来るようになるかを考えてみたいと思う。マル激で宮台氏がよく語る言葉に「連帯」というものがある。これは辞書的には、「二つ以上のものが結びついていること」と説明されていて、労働組合で言えば、同じ企業内の労働者が協同で何かの要求をしたり行動をしたりすることを今までの日本では「連帯」と受け止めていたようだ。これに対し、サンディカリズム((フランス)一九世紀末から二〇世紀初頭のフランス・イタリアなどの労働運動における労働組合至上主義的運動と思想。労働組合による経済闘争と直接行動を重視し、最終的には、ゼネストで革命を成就しようとする。一切の政党活動を否定し、革命後も社会主義国家を認めず、徹底した組合中心主義を貫こうとする立場)の伝統を持っているフランスでは、「連帯」の概念は同一企業内におけるものとしては捉えられていないそうだ。フランスにおける「連帯」とは、労働組合と、直接的利害当事者である社会的弱者とが「連帯」するものであるという。若年労働者が著しい不利益をこうむるような法律が通ろうとするならば、労働組合と青年たちが「連帯」してそれに反対するということが真の「連帯」になるという。労働組合は直接的利害当事者ではないかもしれないが、そのような社会的不公正が行われれば、その結果は必ず労働者にも波及し、そのときになって労働組合だけが抵抗しても遅いという考えがあるように思う。そのような将来を予想するならば、広く社会的に「連帯」することが労働組合にとっても利益だと考えているのだろう。それがサンディカリズムの伝統ではないかと思う。このような「連帯」概念を持っていれば、労働組合の組織率がほんのわずかであっても、労働組合の行動は社会的な影響力を持ち、それこそゼネストを打てるほどの力を持ちうるともいえるのだろう。それに対して、「連帯」の概念が同一企業内の労働者のものに限られている、狭く単純な概念になっているとどうなるだろうか。青年労働者にとって著しい不利益となっている派遣労働を正当化する法律が提出されたときも、それが企業内労働者にとっては直接的な利害をもたらさないということから、労働組合がこれを放置し、抵抗しないという結果に結びつくだろう。若年労働者との「連帯」は日本の労働組合の概念とはなっていないのだ。派遣法に関しては、企業内労働者にとっては、その賃金の引き下げを短期的には防ぐという意味で、むしろ派遣法を通すことが利益のように映ってしまって、日本的な「連帯」概念では、かえって派遣法に賛成するというような逆転した結論まで出てきてしまったようだ。しかし、この判断は、やがては正社員の労働強化にもつながり、結果的には若年労働者の不利益が企業内労働者の不利益にも浸透してくるという皮肉な現状をもたらした。もしフランス的な「連帯」概念を日本の労働組合が持っていれば、派遣法が提出された時点でこれの問題点を指摘しそれに反対しただろう。しかし、「連帯」のより深い概念がなかったために、単純に企業内労働者だけで「連帯」する道を選ぶ思考をしてしまったというふうに見える。フランス的な「連帯」は、サンディカリズムというものの伝統がなければ把握できないもので、一つの学術用語のようなものと捉えられるだろう。そのような概念は、複雑で難しいものではあるけれど、労働組合を指導する立場の人間にはこれを学ぶ必要と義務があるのではないかと思う。それがなかったことの問題を宮台氏は指摘していた。仮説実験授業では、科学の最も基本的で重要な概念を、日常用語の範囲での理解ではなく、科学の「術語」としての理解を深めようとする。そうすることによって現実の捉え方が変わってくる。より深く広く捉えられるようになる。複雑な構造が、それまではぼんやりとしか見えていなかったとしても、新たな「術語」概念を獲得した後には、それがはっきりと見えてくるようにするのが仮説実験授業のひとつの目的でもある。原子の概念というのは、それが物質を構成する究極の単位であるということも重要だが、より本質的なこととしては、「原子は無から発生するものではない」事と「それが無に帰するようなものではない」ということではないかと僕は感じている。例外的には崩壊を起こして違う原子になってしまうものがあるけれど、概念としては、原子はそれが存在している限りはいつまでも存在しつづけるということがいえる。この概念がどのような思考をもたらすかというと、物質の重さの保存性というものを論理的に導くことになる。物質からそれを構成する原子を取り去ったり、あるいは原子を付け加えたりすることなく、その形を変える(固体を砕いたり、水に溶かしたり、縦にしたり横にしたり、人間では片足で立ったり、食べ物の状態を食べたりとか)だけであれば、重さは変わらないという結論を論理的に導く。仮説実験授業では、この論理の帰結が現実にも成り立つのだということを多くの実験を通して経験的に確認する。そうすることによって、目に見えない原子の姿を想像の中で見ることが出来るようになり、それが原子の概念となっていく。原子の概念を持っていると、物が消えてなくなったように見えたり、物が及ぼす影響が違うのではないかと思えるような状況にぶつかっても、原子としての出し入れがなければ重さは変わらないのだという、複雑な構造を重さという視点で正しく把握できるようになる。思考の展開にとって有効な概念を持っているというのは、それが単純な概念で捉えている時は、現実が不思議で訳のわからないものだという感想しかもてないが、適切な概念で考えれば現実にある種の現象が成立している合理的な理由がよく分かるという感覚をもたらすことになるだろう。仮説実験授業研究会の会員である牧衷さんは、力学の学習において、「慣性とは加速度0(ゼロ)の運動のことだ」という概念を持ったときに、力学全体の見通しが開けてきたという経験を語っていた。この場合は、加速度といった場合に、それは何らかの意味で速度が変わる状態が言葉のイメージとしてこびりついているので、それが変わらない0(ゼロ)だということを概念化することに難しさがあって、なかなか概念が獲得できなかったのではないかと感じる。この「0(ゼロ)の概念」というのは、案外と難しいのではないかと思う。この0(ゼロ)というのは、筆算の計算ではどうしても必要になるので、小学校で筆算を習うときには必ず教えられるのだが、それが単に筆算での計算操作の対象にとどまるなら、本当の意味での豊かな概念としての0(ゼロ)の意味を獲得したとはいえないのではないかと思う。普通の数は「ある」という存在を前提として概念化されている。これは経験からその概念をイメージしやすいので獲得も容易だろう。難しいのは、10進法という構造の下にその数を捉えることだ。これに対して0(ゼロ)というのは「ない」ことを基本的なイメージとして概念化されている。「ある」ことは直接的な経験として想像しやすい。しかし「ない」ことは、最初に何かが「ある」ことを想像した後に「ない」ことへの状態の変化を通じて理解することになる。この0(ゼロ)が、「ある」を基本とした量の体系の中に組み込まれる数であるという概念をつかむことはとても難しいのではないかと思う。0(ゼロ)の学習では、0(ぜろ)が「ない」ことを表すのに、それが「0個ある」という無理な言い方を習ったりする。「ない」ものをあたかも存在しているかのように扱うという発想の転換が0(ゼロ)の難しさにある。0(ゼロ)は現実には存在していない。しかし数としては、頭の中の観念として存在している。そして、これが存在していることによって数の体系は完結した全体的な構造を獲得する。すべての数が対等で一般化された対象として扱えるようになる。本来なら、現実の具体的な差異を示す複雑な存在というものが、量を示す数で把握すれば、どれも同じものとして計算の体系の中で取扱いが出来るようになる。複雑な構造の複雑性を失わずに把握する方法を与えてくれることが、0(ゼロ)という概念の重要性ではないだろうか。これは小学生で習うということでは簡単なもののように見えるが、その本当の概念を獲得するには、「学術用語」を理解するときのように深く考えなければいけないのではないかと思う。(0の掛け算や割り算を、単に計算規則として記憶するのではなく、その構造を把握することを考えるとこの難しさが感じられるのではないか。)新しい概念を獲得すると現実の見え方がすっかり変わってしまうのを感じるときがある。そして、この新しい概念の獲得は、ほとんどの場合言語を通じて行われる。僕は新たな概念を自分で作ったことがないので、概念が誕生する瞬間の経験はないが、概念を新たに獲得した後の経験はたくさんある。言語の学習とともに新たな概念を獲得し、その新たな概念が現実を深く理解させてくれるのを感じる。それはまさに、言語によって現実に深く切り込み、現実を切り取ってよりはっきりした姿を言語が見させてくれているように感じる。言語にそのような力を感じるというのは、ソシュールが語ることが正しいのではないかという確信を抱かせるものである。
2008.07.03
コメント(0)
-
他人の原稿に赤を入れることの容易さ
マル激の中で、神保哲生さんが何かの折に「他人の原稿に赤を入れるというのは誰でも出来るんですよね」というようなことを語っていたことが、妙に印象的で頭に残っている。これは神保さんが経験的にそういうことがよくあったということで語っていたことだった。記者の原稿というのはデスクに回されていろいろと修正されて完成するのだが、そのときの修正に赤ペンが使われるので、それを「赤を入れる」などと言う。これは、そのままの原稿があまりよくないので、よりよいものに修正するというニュアンスで受け取ると、「赤を入れる」方が元原稿を書いた記者よりも優れていると考えたくなる。しかしそうでないことも多いという。取材力も文章表現能力も記者のほうが上でも、その元原稿に赤を入れるのは可能だという。そして、それは決して恣意的に、デタラメに修正して「赤を入れる」のではなく、ちゃんとした方針に添って修正できるという。この方針は、必ずしもジャーナリズムの原則にのっとったものではなく、商業的に「売れるニュース」になるような方針で修正するとなれば、元原稿を書いた記者のほうがジャーナリストとしてはるかに優れていても、その方針に従った正しい修正が出来るということだ。他人の原稿に「赤を入れる」ということは、他人の原稿の中の「まずい個所」を探し当てて、それを「まずくない」ように書き直すということを意味する。ある意味では、あら探しをして、そのあらが見えないような工夫をするということになるわけだ。その人が、オリジナルではそれほど感心するような文章を書くわけではないけれど、他人のあらを探すことにおいてはなかなか上手だという文章に時にぶつかるときがある。あら探しが上手だというのは一つの能力かもしれないが、これはあまり上等な能力には見えない。あら探しに長けた人間は、ほとんどの場合建設的で共感できるような話の展開が出来なくなるからだ。文章表現能力が、あら探しをして罵倒するようなところに注がれて、そこだけが成長してしまうからではないかと思う。神保さんが記者として経験したような経験が、僕にもインターネットの文章を眺めているとそう感じられるようなことがたびたびある。表現としてやや稚拙なところがあるものの、なかなかいい視点から眺めている建設的な主張だなと思うことがある一方で、その主張に対して、その「稚拙な点」だけに的を絞って攻撃・罵倒するようなコメントを見かけることがある。建設的な面を見て、そこで議論すればもっと気持のいい有効な議論が出来るのに、どうしてそんな末梢的なことにこだわるのかなというのが、そういうコメントを見ていつも思うことだった。他人のあらがまず最初に見えてしまう人間は、そこに口を出さずにはいられないのかもしれないが、それはあまり上等な能力ではないということを知ったほうがいいのではないかと思う。誰でもやろうと思えば出来ることで、思慮深い人はそのような末梢的なことをしようと思わないだけなのだ。それは経験的によく分かることだが、このことを論理的に反省してみるとどうだろうかということに興味が湧いてきた。「他人の原稿に赤を入れる」ということは、ある前提を設定すれば、本当にそのようなことが簡単に出来るという論理的な帰結を求めることが出来るだろうか。経験的によくあることだということは、現実がある条件を満たしていて、それゆえにそのような現象がいつも起こるのだとも考えられる。現実が論理の法則にしたがっているということが、この事実から見えてくるかどうか。ちょっと考えてみたいと思う。さて、現実の条件の一つとして僕に浮かんできたのは、「文章表現というのは、現実をそっくりそのまま完全に映すことが出来ない」ということだ。これは、絵画などのほかの表現でもそうだろうが、特に言語による表現というのは、それが表現できる側面と、決して表現できない側面とがあると僕は思う。三浦つとむさんによれば、言語は対象の普遍的な面を捉えて概念化し、概念としての意味を表現として提出するという。言語表現の受け手は、この普遍化・一般化された意味をその言語の語彙として読み取り、それを頼りに具体的に表現された状況を考慮して、普遍的・一般的な意味と結びつく具体的な意味を解釈して、それを具体的な表現として受け取る。これが言語の過程的構造だと捉えて言語の性質を研究するのが三浦さんの言語過程説の立場だと僕は理解している。言語が事物の普遍的な側面を表現するというのは、ソシュールでも基本的にはそう考えていたように思う。だから、言語を捉える発想としてはこれは正しいものと前提してよさそうだ。この前提が、論理的には言語表現の不完全さを帰結するように思われる。言語は、現実の具体性を具体性そのままで表現することが出来ない。その具体性を、いったん普遍性のレベルで捉えて、たとえば具体的な「赤い」色を見ていても、それを言語で言う時は一般的な「赤い」という表現を使うしかない。それは今目にしている「赤い」を含む、一般的な「赤い」の範囲を語る表現だが、まさに今目にしている「赤い」をそのまま完全に映し出すことは出来ない。これは言語にとって宿命的なもので、言語を受け取った者の解釈によって、表現者が意図していなかったものを読み取ることは、言語表現の場合はいつでもそのような可能性を持つことが論理的に帰結できる。誤読は常にありうるということだ。このように言語表現に特有の性質から、解釈によるあら探しがいつでも出来るということが論理的に帰結できる。それは表現者が意図していないかもしれないが、「そうも読むことが出来る」ということから生まれる。これはかつて「差別語」というものを形式的に指摘して糾弾するような行為によく見られたのではないかと思う。だが、このあら探しは、それがあからさまな言いがかりである場合は、今度は逆にそれが無理であることが分かるのでだんだんと淘汰されていくものになるかもしれない。今は、形式的な「差別語」の指摘はあまり見られなくなったので、そのような末梢的なあら探しは淘汰されたのだと思いたいが、そういう揚げ足を取られないように、単に形式的な「差別語」を使わないようにしているだけなら、論理的な認識がまだまだ社会全体のものになっていないのだなと残念に思う。このような言語の性質からもたらされるあら探しの容易さに加えて、認識の不完全さから来る、それが表現していないこと・あるいは間違って捉えていることへの指摘からくるあら探しも見られる。これも三浦つとむさんが認識論で語っていることだが、人間の認識というのは、それを感じる感覚が制限されていることから、対象を完全に全面的に捉えることが出来ない。自分が注目している側面から見えることだけ(ある一つの視点から見えるもの)が見えているに過ぎない。当然のことながら、その認識を表現すれば、見えていないことは書かれない。したがって、それが「見えていないではないか」というあら探しはいつでも指摘することが出来る。問題は、この指摘が本質的なものなのか、それとも末梢的なものなのかということだ。本質的に重要なことであれば、それは建設的な指摘であり、単なるあら探しとは区別される。しかし、それが末梢的であり、その主張の中心的話題からいえば、わざわざ言及する必要もないと判断されたものであれば、むしろ書かれていないほうが正しいのであり、書いていないということを攻撃・非難することは的外れであるといえる。しかしながら、書いていないということが、あら探しとして非難・攻撃のように見えるので、事情を知らない人はそれが正当な批判に見えてしまうかもしれない。特に難しい問題を議論している人にとっては、それが難しいがゆえに、どうしてその事に言及していないかを説明するのも困難であるときがある。認識の不完全さを指摘して、そこに足りないものを指摘するのは、勝手な解釈で誤読して非難するあら探しとは違うものに見える。だから、この場合は、ある問題に対して表現者の視点よりも、あら探しをするほうの人間の視点に共感している場合は、あら探しを指摘するほうに共感を覚えてしまうだろうと思う。この場合、議論を建設的に導くには、違う視点を持っている人間が、その視点で新たにあら探しとは関係なく自らの主張を整理して提出することがあったほうがいいだろう。単に文句をつけるだけでなく、違う視点で対象を見ているなら、その視点で見たほうが有効な結果を導くということを説得的に展開しなければならない。そうでなければ、そのような行為が度重なれば、最初は違う視点の提出に注目していても、なんだ単にあらを探して文句をつけているだけじゃないかというような印象をもたれてしまう。そうなると建設的な議論はまったく期待できない。「他人の原稿に赤を入れる」という、他人の表現の欠点・不足した部分を指摘するというのは、表現と認識の持つ本質的な性質から、いつでもそれが行えるという指摘が出来る。つまり、誰でも違う視点を持つことが出来れば、弁証法の法則に従って、その表現の主張と正反対の結論を論理的に導くことが出来てしまう。あら探しをするには、その表現者とちょっと違う視点さえ持てば誰にでも出来るということだ。神保さんが経験的に感じていたことは、論理的にもそのような現象が起こりうることが証明できる。つまりウィトゲンシュタイン的に言えば「論理空間」に可能性として表現される命題になるということだ。このようなあら探しに対しては、表現者の主張に共感する身としては、何か「嫌だなあ」という嫌悪感を感じて、その内容までを検討する気にはなれないでいた。しかし、それが単なる文句をつけるだけのあら探しなのか、それとも違う視点を提出している、建設的な議論に発展させることが可能な「目の付け所」が違うだけなのか、という見方をすれば「嫌悪感」が少しは薄れるかもしれない。だが、これはあら探しだなと思われる主張は、たいていの場合、つまらない陳腐な視点を提出しているに過ぎず、単にあらを探すために違う視点を見つけただけというふうに見える場合がほとんどだ。本当に感心する共感できる主張というのは、やはり人に文句をつけるような表現ではなく、そこで主張している対象というものを、表現者がどのように独自の感性で捉えたかを語っているものが多い。批判というのは、批判の対象以上の見識を批判者自身が持っていなければ説得力を欠くのではないかと思う。その意味では、批判者として共感できたのは、たとえば佐高信さんなどが僕にはそうだった。佐高さんは、佐高さんが批判している人々よりも、教養の点においても人格の点においても品位が上であり、高い見識を持っていると思えたから、その批判も単なるあら探しではなく、正当で適切な指摘だと感じられたのだと思う。そういう意味では、あら探しは易しいが、本当の意味での批判はとても難しいといえるのではないかと思う。本当の意味での批判を展開するよりも、批判と関係なく、自らの主張をまとめたほうがきっと易しいだろうと思う。
2008.07.02
コメント(0)
-
原子概念誕生の瞬間を想像してみる
原子論というのは、「すべての物質は非常に小さな粒子(原子)で構成される」という主張の事を指す。これは今では科学的に正しいということが証明され、すべての科学者はこのことを前提として科学的な考察をしている。だから「原子論」については、それが正しいということや、その正しさが確立されてきた歴史というものはいろいろと解説してくれる資料は多い。僕の尊敬する板倉聖宣さんも、『原子論の歴史(上)(下)』(仮説社)という本で原子論の正しさとその「論」の歴史については詳しく書いている。だがここで想像したいのは「論」の正しさではなく、「論」の意味を正しく受け取るための「原子」の概念がどのように誕生してきたかということだ。「目に見えないほど小さい」とか「すべての物質の構成単位としての極限的なもの」であるとかいう「原子」のイメージがどのようにして生まれてきたのかということを想像したい。これはそのような問題意識で書かれた解説はまったく見つからなかった。「原子論」の正しさを解説する本はたくさんあるけれど、その元になった「原子」という言葉の概念はどのようにして獲得されたかということが書かれているものは見つからなかった。それで仕方がないので自分で想像してみようと思う。この想像が、ソシュールが語る「言語と概念は同時に生まれた」ということの理解に何らかのヒントを与えるのではないかと思うからだ。原子論を初めて唱えた人はデモクリトスだと言われている。デモクリトスは紀元前460年頃から370年頃まで生きていた人だ。デモクリトス以前には原子論が語られていないということは、原子という概念がまだなかったのか、原子論が間違いだと思われていて主張されていなかったのかどちらかではないかと思う。その周辺の出来事を見ながら、「原子」概念がどのように発生しうるかということを想像してみようと思う。デモクリトス以前の人でターレスと呼ばれるギリシア人がいる。ターレスは歴史上最初の哲学者と言われている。それはウィキペディアでは「彼が「最初の哲学者」とよばれる由縁は、それまでは神話的説明がなされていたこの世界の起源について、合理的説明をはじめて試みた人だという点にある」と解説されている。世界の起源について関心を抱いていたターレスは、この世界が「何から」構成されているかという問題も考えたようだ。ターレスの考えは「万物は水から出来ている」というものだった。このターレスが「原子」という概念を持っていたのかどうかは記述してある資料がなかった。板倉さんの本にもそのような記述はなかった。だから、ターレスが万物の起源として水を選んだのは、「原子」というものを知らなかったのか、「原子」を起源と考えるのが間違いだとして退けたのかは分からない。いずれにしても、万物の起源は「何か?」という問いから、その解答として「原子」という概念が生まれてきたのではないかという想像は出来るのではないだろうか。「原子」は、現在の最高の電子顕微鏡でも見ることが出来ないのであるから、その存在を五感で感じて、存在を認識したことをきっかけにして概念が誕生したのではなさそうだ。ターレスが万物の根源を水だと考えたのは、多くのものが水分を含むという経験がそのような主張を生み出すきっかけになったのではないかと思う。だが「すべて」という言葉が含まれる命題は、ある例外が気になるとどうも賛成しがたいものになる。どうも水が見つからない、というような存在が気になると、万物の起源を他のものに求めたくなる。アナクシマンドロスは「万物の根源は空気である」と主張したらしい。この理由は、板倉さんの本によると「水だって、熱すると気体になるので、<万物の元は空気だ>と言ったほうがいい」という発想があったのだろうと想像していた。またヘラクレイトスは「万物の根源は火だ」と言ったそうだ。これは火が持っている「変化をもたらす力」こそが<万物の根源>だと見た見方らしい。これも一つの見解としてはなるほどと思えるものだ。このような考え方に対して、根源を一つだと考えるといろいろと例外的に見えるものが出てくるから、いくつかの組み合わせだと考えたほうが論理的な整合性が取れると考えたものがいたらしい。エンペドクレスは「万物の根源は<土と水と空気と火>の4つの元素だ」と考えたようだ。それ以前の人間の説を全部取り入れてそれぞれの説を活かしたものとして、これもなるほどと思えるものだ。この考えは板倉さんによれば「土と水と空気は、それぞれ固体、液体、気体の代表で、火は変化させるものの代表ともいえます」と指摘していて、なるほどこれで「万物」と関連させることが出来るのだなと思える。これらの考え方には、「元素」という元になるものという概念は現れるものの、その「元素」は水であったり、空気であったり、火であったりと、新しく考え出された対象ではなく、日常生活の経験の中ですでに知られていたものばかりだ。だから、原子論誕生の以前では、万物の根源も経験的な知識を整理することで求められていたように感じる。それはすでに五感で感じてその存在が確認できるものばかりだ。考察の以前にすでに概念が確立されている言葉として「水、空気、火」などというものが使われている。そのようなことを考えると、デモクリトス以前には「原子」という概念はまだ誕生していなかったのではないかとも思えてくる。板倉さんによれば、デモクリトスは、このような万物の根源の説のどれにも賛成できなかったので、「いろいろ考えた末に、「すべてのものは、<もうそれ以上分けられないもの>、ギリシア語で言うと<アトモンなもの=アトム>から出来ている」と主張するようになったのです」と書かれている。「原子」(アトム)という概念は、このデモクリトスの考察から生まれてきたのではないかと感じる。「原子」というものは、このように論理の展開を元にしなければその概念がつかめないのではないかと思うからだ。それは五感で感じることが出来ないものだからだ。デモクリトスはどのようにしてこのような発想を得たのだろうか。万物の根源として、すでに知られている具体的なもの(五感で感じられるもの)を設定するとどうもうまく説明しきれないものがあるから、発想を逆転させていったのかもしれない。それ以前の発想では、現実に存在するあるものが「万物の根源」だという見方で、現実に存在するもので「万物の根源」に当たるものを探そうとしていたように見える。だがそれが探しきれないので、とりあえずは「万物の根源はある」という命題を正しいものとして「仮定」してしまって、その命題にふさわしい存在として「何か」をフィクショナルに設定するという発想で「原子」というものを考えたのではないかと想像できるのではないか。この逆転の発想は、視点を変えるという意味では弁証法的かなという感じがする。内田さんがソシュールを語ったところでも、「物が存在してそれに名前をつける」という発想を逆転させて、「ものに名前をつけることによって、その存在が人間に対する存在として思考の対象になった」という見方と共通するものを感じる。逆転の発想というのは、ものの考え方の技術としては、優れた人物に共通しているのではないだろうか。さて、「原子」という概念の誕生が、上のようにデモクリトスが逆転の発想によって生み出したものだと言えるなら、それ以前の人々には「原子」という概念がなく、「原子」という対象は見えていなかったといえるのではないだろうか。これはもちろん五感で感じることが出来ないので、現実の目では見えないのだが、それが存在としても考察の対象になっていないという意味で「見えていなかった」のではないだろうか。デモクリトスの考察によって、初めて「原子」というものが考察の対象になってきたとは言えないだろうか。「原子」の概念は、「原子」という言葉の誕生とともに生まれたような感じがする。この「原子」の概念は、誕生した時は文字通り<アトモンなもの>という「分割不可能なもの」という単純なものではなかったかと思う。考察の過程で「目に見えないほど小さい」という性質や他の性質が加えられて概念の内容が豊かになっていったのではないかと思う。この考察が出来るのも、一度概念として確立されて、それが思考の対象となったからだろうと考えられる。これは数学における公理論的な展開に似ているのではないかとも感じる。公理論における数学的対象は、概念としては、ある定義を満足するというだけの対象になる。それは実体としてどういうものであるかというイメージを最初に作り出すことが出来ない。ある定義を語る命題を提出して、その命題が真となるような対象として概念化される。だからその対象は、最初のうちはどういうものであるかがまったくつかめない。何かぼんやりとしたものとしてイメージされ、それがいくつかの定理に従うということが理解された後に、だんだんとその姿が明らかになっていく。「原子」というものも、最初は「分割できないもの」というぼんやりとしたものであったものが、いくつかの法則に従うということから、だんだんとイメージがはっきりして概念が完成されていったと見たほうがいいのではないだろうか。このような想像をすると、「原子」という概念は、対象の存在から発生した「あらかじめ与えられた概念」となっているとは考えられないものになっていると感じる。それは、その概念が「何であるか」という発想(つまり、対象の観察から得られるという発想)から生まれているのではなく、「何でないか」という発想(対象そのものは観察できないが、周辺にある他のものの観察から得られるという発想)から生まれているように見えるからだ。それは、「万物の根源」として、水ではない、空気ではない、火ではない、それ以外の「元素」でもない、という判断から、これらとは違うけれども、「根源を構成するもの」としてイメージされたように思える。これは、「根源を構成するもの」を観察して、何らかの発見をしたから見つけられたのではなく、それがあると仮定して、その仮定の元に命名されたように見える。これは論理的にはご都合主義だ。本来なら結論として「万物の根源はあるか?」という問いを考えなければならない。もし「万物の根源」がないとしたら、この問い自体が意味を持たなくなる。だが、この問いの答えはあると仮定して、その対象を想像することにしたということは、結論を先取りした、論理的にはご都合主義になるだろう。この論理的なご都合主義は、多くの場合は間違いとなるのではないかと思う。だが「原子」の場合は、その概念を持つことが、現実の存在の性質を深く捉えることに役立った。人間は、ある種の存在に名前をつけて呼ぶことによって、その存在を深く捉えることが出来るようになってきたのではないだろうか。そして、役に立つ概念だったものが言語規範として生き残ってきたのかもしれない。役に立たない概念は、いつしか誰にも使われなくなって、概念そのものが消えてしまったかもしれない。「原子」という概念が誕生したときを想像すると、それは言語の発生と同時に見られるように僕には思える。ソシュールが語ることは正しいのではないかと感じられるのだが、他の言語で「あらかじめ与えられた概念」に名前をつけたと考えられるようなものが見つかるだろうか。見つからないからそれがないのだというのは、論理的な帰結としては不十分だ。しかしなかなか見つからないことも確かだ。果たしてそういうものはどこかにあるのだろうか。
2008.07.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1