-
1

GASSHOW 訳してみました
Break Time(一休み)GASSHOW 訳してみましたGASSHOW 歌詞全文GASSHOW 歌詞と訳illion(野田洋次郎)氏の「GASSHOW」と言う曲に感銘いたしました。曲も歌詞も素晴らしいのです。恥ずかしながら、YouTubeで別件の動画から私も最近知ったばかりなのです。まず曲に耳が止まり、何て言う曲? と思っていたら12年も前の曲だった。そして調べて驚いた。「GASSHOW」と言う曲は東日本大震災(2011年3月11日14時46分に発生)の被災地支援のために作られた曲だったそうです。歌詞が古い言い回しをしているので、みなさんすぐに震災の歌とは気付かないかと思います。私もそうですが、震災の歌と言われて聞けばなるほどなのですが・・。タイトルの「GASSHOW」は「合掌(がっしょう)」の意で、文字通り手を合わせて拝むと言う意味内容にになっています。つまり、「GASSHOW」は東日本大震災のレクイエム(Requiem)だったのです。※ レクイエム(Requiem)はラテン語。本来はキリスト教や正教会での死者への追悼のミサから生じた語。死者への祈りから日本では「鎮魂歌(ちんこんか)」と訳された。被災者支援の曲ですから、実は内容も非常に重い。言われて気付く。無意識に心にひっかかったのに納得しました。メロディーも歌詞も非常に趣きのある素晴らしいもの。なぜ今まで知らなかったのか? iTunesで購入してここの所ずっと聴いている次第です。※ YouTubeでカバーで出している方も、ここの所なぜか? かなり増えました。先にも説明しましたが、歌詞は古い言い回しが使用され、抽象的な表現がされてもいるので若い方には解釈がちょっと難しい。※ 全体には古語が使われた韻文の形式で書かれている。「意味を教えてください。」と言う要望が多い理由です。わたし自身、意味を解説しているサイトを見たりしましたが、それらはワードの解説であって、完全に作詞家の意図を解説しきっている人はいない。解らなくて? 濁されている部分もみなさん多々ありました。私も何回も歌詞を見て理解を試みました。わたし自身完全に解釈するのは難しいかとも思いましたが、GASSHOW 訳してみました。これは私の解釈。作詞家の意図するところとは少し違うかもしれませんが、ストーリーは通るよう訳してみました。解りやすくする為に、英語の翻訳で言う所の超訳(ちょうやく)と言う手法で訳させていただきました。つまり歌詞を直訳した訳ではなく、歌の本意を解説的に訳したものです。もし、この歌を知らない方。ぜひ聞いてみてね。illionofficial さんがGASSHOWをYouTubeにもあげられています。リンク GASSHOW (illionofficial)先ず、歌詞全文をのせさせていただきます。次に歌詞と訳を挟む形でのせさせていただきます。GASSHOW 唄・作詞・作曲:illion(野田洋次郎)※ 野田洋次郎 (1985年~ )「illion」はソロ活動の名前で、ロックバンド(RADWIMPS)のボーカルでシンガーソングライター。GASSHOW 歌詞全文猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えとその裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)と引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよはじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはGASSHOW 歌詞と訳猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)突然起きた地震。そして起きた大津波。海が荒れ狂い。轟(とどろき)と共に海は地の上を這って迫り来る。容赦なく押し寄せる水は私たちが無垢に生活していた家々にまで届き、人を襲い海の底に引き込んだ。荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていったのだ。海が飲み込んだのは人の命だけではない。その人の想いと生きることへの渇望(かつぼう)も・・。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えと犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。八百万の神々様、どうか彼らの魂を救ってください。どうかお願いします。(( -.-人 その裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう突然の津波。そもそも何が起きたか解らずに海に襲われた人ばかりだったろう。「神様、助けて。」「誰か、助けて。」そんな絶叫もむなしく、海は容赦なく、彼らを飲み込んで行ったのだ。そして今も彼らの「叫び」は海に閉じ込められたまま、波間を漂い、ずっと木霊(こだま)のように、さまよっている事だろう。君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所君の匂いのする所に帰りたい。貴方が私の帰る場所だった。今、君はいない。私は(どこかに)進まなければならない。それは僅かに、指先に見える心もとない細い道でしかないけれど。万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない一生懸命生きて、働いて積み上げて得た幸せ。それらが一瞬にして壊され、まるでウソだったかのように現実から消えて無くなるのなら、真実さえ、受け入れたくはない。怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者もう、怒る気持ちも、涙も流さない。希望も夢も無く、私は現実の世界で淡々と生きている。残された者の現実は皆辛い。生きるのは苦しい。悲しみや痛みに捕らわれ続けているからだ。猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていった。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。幾年も積み上げて来られた人生をたった一瞬で葬り去られた無常に・・。果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く海に荒らされ荒廃した大地。私たちはどうしたら再び光を取り戻す事ができるのだろう。今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして今、できる事は祈りを込めて、海に飲み込まれた彼らの魂が戻る道しるべとなるよう街を復興させなければならない。出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ貴方と出あえたから今の自分がいる。虚無感でいっぱいだけどそれ(自分自身)は大事にするよ。運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)ともともと運命だったのか? 神の采配だったのか? 一瞬にして消えてしまったあなたの魂。引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよ貴方の命と引き換えのように残ったわが身。これも貴方の形見だから大事にするよ。はじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはもうこの世にいない貴方。貴方の遺物(遺骸の一部)さえ見つかっていない。貴方の体も魂もどこにあるか解らない。(拝むべき、墓も無い。)それでも、頼むから、この祈りの気持ちが貴方に届いてほしいと、初めて思った。切に願っているよ。東日本大震災で被災され、家族を失われた方々の気持ちを考えながら訳させていただきました。亡くなられた方々へ、深く哀悼の意を表させていただきます。自然災害とは言え、突然命を奪われた方々の無念さは言葉では言い表せない思いがあるでしょう。その気持ちは歌のように今も波間を漂っているかもしれない。魂はもしかしたら、まだ成仏されていないかもしれない。残された家族がそう思い悩まれているかもしれない事も想像に難くない。この「GASSHOW」と言う曲は残された者たちの苦悩の歌でもあるのだと、訳していて改めて感じました。逝った者も辛い。残された者はもっと辛い。せめて彼らの魂が全員救われてくれるなら・・。少しは心が晴れる。日本を統べる八百万の神々なら、彼らの魂を救いあげる事ができるかもしれない。私もそう願っています。m(_ _)million(野田洋次郎) 氏は短い言葉で非常に多くの事を語っていたのです。そして端的に被災された方々の気持ちを吸い上げて言葉にしている。作家ではなく、ミュージシャンなのに凄い方だな。と思いました。( ̄人 ̄)
2025年04月19日
閲覧総数 17080
-
2

信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)
リンク先名変更1576年(天正4年)2月、織田信長は安土城に転居した。(現在の滋賀県近江八幡市)つまり本拠とする安土城が完成したと言う事なのだが、信長はこの時に京都にも上洛の時に使用する屋敷の建設を思いついたようだ。(信長公記より)屋敷は調度、関白の二条晴良の屋敷跡の庭地を気に入り工事に当たらせた。余談であるが、この頃は大阪で石山本願寺の僧兵が挙兵し天王寺を奇襲。それに対処していた頃である。この頃信長が上洛時に宿所にしていたのは妙覚寺である。前回紹介したが、変の時に織田信長嫡男、織田信忠が宿坊していた寺である。上洛する時の為に京に屋敷を造るのは自然な事。信長もそれに習って屋敷を建てたのか? と思いきや、1577年(天正5年)7月より上洛時は二条の新邸に移ったものの、屋敷の完全なる完成を見るとあっさり皇室に献上してしまうのである。1579年(天正7年)11月(誠仁親王)に二条の新邸をあけ渡すと、信長は再び妙覚寺に居を移している。1580年(天正8年)2月。最初に上洛した時の宿所はやはり妙覚寺であったが、その5日後に本能寺に宿坊を変えている。日蓮法華の妙覚寺はもともと妙顕寺の僧であった日実が教義や後継問題の対立から離脱して開いた寺である。また、本能寺も同じく教義の解釈から妙顕寺に破却されて日隆が創建(1415年)した法華宗の寺であった事から、妙覚寺と本能寺は親しく繋がっていた可能性がある。二条の新邸建築以降は、上洛が重なる時は信忠に妙覚寺を譲り、信長は本能寺に宿坊したのではないか?と推察。本能寺に度々立ち寄るものの、本能寺の資料による本能寺への投宿は4回だけだそうだ。回数的に言えば妙覚寺のが圧倒的に多い。だからこそ4回目の本能寺投宿は府に落ちない・・ 信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)法華宗の寺、妙顕寺、妙覚寺、本能寺本能寺の再建織田信長と本能寺と種子島と鉄砲現在の本能寺は法華宗本門流の大本山となっている。本能寺の「能」の字「䏻」はヒでなく去になっている。これは度重なる火事をきらって・・こちらを使用していると言われている。寺町通りから入ると右に宝物館があり、正面に本殿が見える。ビルの左側は本能寺会館である。本殿と言ってもここに信長が宿坊していたわけでは無いし、まして場所も全く関係ないのであまり感慨はない。ほとんどみんなが目指すのは、この右脇の奧に位置する信長廟である。信長廟前の拝殿河原町通りの路地から入ると信長廟の裏手にあたり、ビルが途切れたすぐ右が信長公の廟となっている。(実際はお墓ではなく供養塔であるが・・。)右の石柱は350年目の祈念碑である。信長公の供養塔1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)の一ヶ月後、3男、織田信孝が父の菩提を弔う為に建立。中には信長公の太刀を納めて供養としていると言う。なぜなら、本能寺で織田信長のお骨は発見されなかったからである。(これについては阿弥陀寺の回で・・。)本能寺の再建本能寺自体の再建は同年1582年(天正10年10月)速やかに始まり、秀吉からも山城の国鴨川村40石の朱印地を寄進されたと言う。また大納言からの支援の他、種子島からも浄財が運ばれたと言う。その後1592年に前回紹介した秀吉の都市改革で移転を余儀なくされ現在地に。割と新しい物に見えるが・・。信長公の供養塔の左隣が変の時に戦没した諸霊の供養塔森蘭丸、兄弟の名前ももちろん載っている。いつもなら慎重な信長が、この時、ただのお小姓衆を30人ほど連れて本能寺に宿坊していたそうた。まるでお小姓衆の慰安旅行に思えてしかたがない なぜ彼は油断したのだろう?織田信長と本能寺と種子島と鉄砲信長、本能寺への3度目の宿坊が、石山本願寺に勅使を贈る直前1580年(天正8年)2月である。目的は武器の調達だった可能性も・・。まもなく、石山本願寺は白旗を揚げて大阪を撤退する意志を固めてきている。織田信長と言えば、長篠の戦い=鉄砲である。長篠の戦い1575年(天正3年5月)では鉄砲を用いて武田軍に勝利した事で知られているが、本能寺もまた鉄砲と火薬を調達できる独自ルートを持っていたのである。本能寺の資料に寄れば1462年~1486年にかけての法華宗の布教は種子島まで到達していたそうだ。日典上人の殉教。続く日良上人の努力により種子島、島民全てを本門法華宗に改宗させていた。そして1543年種子島に鉄砲(火縄銃)と火薬が伝来すると本能寺の有力檀家である島主種子島氏が本能寺を通じて足利将軍や管領・細川晴元に献上。さらに「本能寺の変」後には、本能寺として秀吉にも火薬を送っている事が寺の文章に残っているそうだ。鉄砲の日本伝来と普及に関して、その信憑性に疑問もあるが、確かに本能寺には鉄砲と火薬を手に入れる独自の種子島ルートがあったのは事実のようだ。鉄砲の普及に関しては当然、堺の商人の活躍があったのではないかと思う。宣教師達は16世紀後半の堺をベニスのようだと称している。そして富裕で利便のよい堺を狙って武将たちがやってくる堺の商人が屈服したのが織田信長であり、信長、長篠の戦いの鉄砲は、堺の鉄砲鍛冶の造った日本製だったと言われている。(大阪城を築くのは秀吉ではなく信長だったのだ。)しかし火薬の材料の一つ硝石だけは輸入に頼らざる終えなくて明や琉球から輸入されていたそうだ。信長が必要としたのは種子島経由の火薬ルートなのかもしれない。天正10年頃妙顕寺、妙覚寺、本能寺は非常にご近所なのである。そして信長が布教を許し庇護したイエズス会の南蛮寺もまたすぐお隣さんである。ただ、小説「信長の柩」で出てきた南蛮寺と本能寺を結ぶ地下通路は現実には不可能と思われる。なぜなら両者の間には西洞院川(にしのとういんがわ)が存在していたからだ。ところで前にも紹介していると思いますが、1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)当時季節と暦(太陰太陽暦である宣明暦)にだいぶ差異が生じていたのでユリウス暦orグレゴリオ暦にすると実は本能寺の変は1582年6月21日になるそうです。信長の墓所つづくリンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)リンク 信長の墓所 3 (蓮台山 阿弥陀寺-1)リンク 信長の墓所 4 (消えた信長公 阿弥陀寺-2)リンク 信長の墓所 5 信長追記と 細川ガラシャの墓リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名
2015年06月04日
閲覧総数 606
-
3
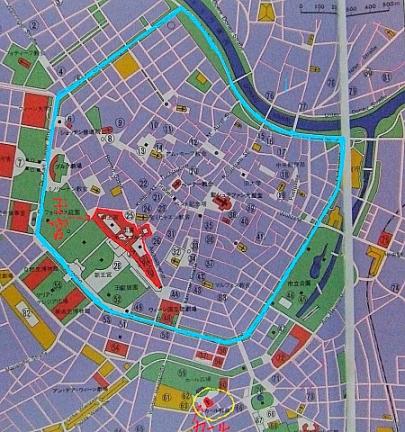
カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)
せっかくなので、「失われた帝都の遺産」の一つカールス教会も写真があるので行きましょう・・と思いながら書いていて迷走してしまいました新しい所に移る時には導入口に悩むのです。広げすぎて違う所に向かう所でしたカールス教会 1 (リンクシュトラーセ)オーストリア共和国(Republic of Austria) ウィーン(Wien)カールス教会(Karlskirche) Part 1ヴィーナー リンクシュトラーセ(Wiener Ringstraße)カールス教会は、リンクシュトラーセの外にあります。前回のベルヴェデーレ宮殿の近くです。でもその前にリンクシュトラーセの紹介から入りjます。なかなか納得の地図がなくて苦労しました図書館でゲット・・。ウィーン市内の地図です。写真上の川はドナウ運河です。マウスで加工したのであまりキレイではありませんが、ブルーで色づけした所がリンクと言われる環状道路です。写真下の黄色の囲みがカールス教会で、リンクの中の赤い三角が王宮です。ヴィーナー リンクシュトラーセ(Wiener Ringstraße)・・・・・城壁の撤去リンクは、正式名はヴィーナー リンクシュトラーセと言う旧市街を囲んだ環状道路です。リンクは、もとはウィーンの王宮や市を守る城壁と濠があった場所なのです。18世紀末頃からヨーロッパの多くの都市では中世以来の城壁と堀の撤去が始まり、それを環状道路として活用するのが流行していました。すでに安定し始めていた社会に城壁は無用の長物で、都市の発展を阻害するものだったからです。リンク沿いの物件だけ少し紹介ブルク劇場・・・・1741年宮廷劇場として創立。ヨーロッパで最も美しいと言われる劇場。現在のイタリア、ルネッサンス様式になったのは1888年の改修からで、大戦で破壊されたものが1955年に再建されている。国会議事堂(Parlament)・・・1883年完全にギリシャ神殿です。前に建つ像は女神アテナイ。デンマークの建築家ハンセンの設計。ブルク門(Burgtor)・・・1824年ヴィーナー リンクシュトラーセ(環状道路)の「ヘソ」と言えるこの場所は王宮への入り口ライプッィヒの戦勝記念の言わば凱旋門でしたが今は第一次大戦の戦没者らが奉られているそうです。ウィーン自然史美術館館リンクを挟さむブルク門の向こうにはマリア・テレジアの巨大な座像と美術館が対に建っている。城壁撤去の遅れウィーンはかつてトルコ帝国から何度も攻撃された経緯があり、城壁の取り壊しが他国よりかなり遅れていました。(市民は撤去を望んでいた。)ウィーンの城壁取り壊しの決断は、ナポレオン軍の進撃の前にはあっさり1夜で粉砕されたから・・とされています。(もはや近代兵器の前では意味が無くなった)皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は1857年撤去を表明。跡地に環状道路を設ける事と跡地の3割を公用地とし、残る7割を民間に売り渡したのです。そして、時代はちょうど産業革命が成熟して巨万の富を得たブルジョアジーが台頭してきた頃です。政府の売り出した土地を購入してりっぱな建物がどんどん建ったのだそうです。城壁取り壊しの遅れが、ある意味、新たな近代的な街づくりに役だった・・と言うわけです。そうしたこの時代を「リンクシュトラーセ時代」と言う、ウィーンを語る上での一つの文化として語られています。5つ星のブリストルホテル・・・・1892年創立カールスブラッツ駅最寄り、ウィーン国立歌劇場隣ウィーン国立歌劇場(オペラ座)・・・かつては宮廷歌劇場王宮のすぐそばにあるこの建物は、実は地下でカールスブラッツ駅につながっているそうです。そしてカールスブラッツ駅は、カールス教会の目と鼻の先なのです。今回はあくまで、カールス教会がメインなのでリンクの建物は一部だけ・・・参考に追加した写真のせいで、違う方向に行きそうでしたが・・・リンク沿いでなくても、その界隈には素敵な建物が沢山建てられています。またの機会に紹介します。カールス教会(Karlskirche)さて、カールス教会は、青いドームと両サイドの円柱が特徴の教会はバロック建築の傑作として知られていますが、城壁のある時代に城壁の外に建造された教会です。1713年、ウィーンで17度目の黒死病(ペスト)が流行して死者をたくさん出したおりにマリア・テレジアの父、カール6世(1685年~1740年)が建立を指示。「ペスト退散の守護聖人」、カール・ポロメーウス(カルロス・ボロメウス)に献げられた教会なのだそうです。教会の名前は聖人の名前カールから来ているのですが、アントワープにもカルロス・ボロメウス教会(改名して)があり、そこも恐らく同じ理由、黒死病(ペスト)に関連して改名したのかもしれません。もっとも、ペストの守護聖人は、地域によっても異なるようです。※ カール・ポロメーウス(カルロス・ボロメウスについては、2014年9月「ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)」の回で解明できました。彼はミラノ大聖堂の聖人となっているカルロ・ボロメオ (Carlo Borromeo)でした。リンク ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)着工は1723年で完成は1737年。設計はフィシャー・フォン・エルラッハ親子中心には高さ72mの緑のドームがそびえ、正面入り口はギリシャ神殿風の柱廊。左右にはトラヤヌス帝(古代ローマ五賢帝)の凱旋記念柱をモデルにしてポロメーウスの生涯がらせんに刻まれた巨大な記念柱がそびえています。建築の意図カール6世は、ペスト退散祈願と言うよりは世人の驚愕するようなバロックの教会を造る事で神聖ローマ皇帝としては、カトリックの威光と、ついでにハプスブルグ家の威光を内外に示す必要があったのではないか・・・と考えられます。なぜなら、いわゆるルターの宗教改革以降、プロテスタントの威力が増し、カトリックの権威も落ちかけていた時期でもあるのです。そこで宗教改革騒動を反省したカトリック側は、いかにも力強く、荘厳なイメージの礼拝堂を持つも豪華絢爛なバロック式の教会や修道院を盛んに建造したと言われています。因みに、プロテスタントでは修道院は全廃、聖母マリアや聖人、聖遺物の崇拝は一切否定され、教会内外のそれらは一切撤去されたと言う事です。礼拝に必要なのは神に近い荘厳さよりも礼拝の中身だ・・と言う理論です。次回、なぜリンクの説明もいれたか・・と内部です。Back number カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)リンク カールス教会 2 (失われた帝都の遺産)リンク カールス教会 3 (ウイーン・バロックの巨匠)リンク カールス教会 4 (天井画の聖人と黒死病)関連Back numberリンク ミラノ(Milano) 7 (ミラノ大聖堂 5 聖カルロ)リンク ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)
2010年07月28日
閲覧総数 852
-
4

新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)
写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました王は祝典など度々大宴会を催している。王の主催する宴会は食事だけでなく、スペクタクルな音楽劇(宮廷パレ)やコメディ・パレが催される。庭園にはそれらに合う彫像が並べられテーマにあった世界感が造られた。さらに仕掛け噴水や洞窟などアトラクションも庭に敷設され毎回非常に凝った物だったらしい。その華やかさは、すぐさま欧州中に伝えられ、フランス王の偉大さが伝えられたと言うが、実際どれだけ素晴らしいものであったとしても、それらは一瞬の風説である。その点、建築物は常にそこにあって消える物ではないので後世に形として残る。そしていつ見てもその偉大さを再認識できるだろう。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)は元の城館を撤去しない形で新宮殿を増築。それを見事にやってのけたが建築的にはかなりの制約が伴ったと言う。ベルサイユの窓は最初のルイ13世の小城館のサイズ(3.33m)に合わせられている。本来この大宮殿のサイズならもう少し大きく無ければならない。だからバランスと言う観点から宮殿を見ると少し微妙らしい。内部はまた別の問題がある。王宮であるので王宮としての部屋割があるが、元の城館のサイズは決まっているので決められたスペースの中で王の希望と実際に必要な部屋を組み込む作業はかなり苦労した部分だったらしい。王族のアパルトマンには「衛兵の間、控えの間、寝室」はセットで必要。部屋が3つあれば良いだけではない。衛兵の間には70人ほどの衛兵が詰めるのだ。また、フランス宮廷は儀礼ずくめ。王は目覚めから着替えまで臣下らに見守られる。最盛期には100人以上の臣下が列を作って見守ったと言う。王の寝室のところでまた紹介するが、ベッド前に敷かれた不思議な柵。臣下(見学者)らはその柵の向こうから王を見守ったと言う事なのだろう。かくして1670年、新城館の建物が完成する。が、それで終わったわけではない。(内装はまだこれから。)さらにプラン変更で改築も続いた。当初ルイ14世が欲しがったイタリア式のテラスは8年程で取り壊しが決まった。1678年大ギャラリーの建設が決まる。設計はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)に託された。1679年草案は国王付き首席画家になっていたシャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)に送られ以降画家と建築家の間でプランが詰められて行く。新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)Galerie des Glaces (鏡のギャラリー、鏡の廻廊、鏡の間)天井絵図国産の鏡戦争の間から先に触れたが、鏡の回廊は最初からあったわけではない。下は当初の図面。改築理由の一つは当初テララスに設置していたファウンテン(fountain)の水漏れが酷かった事らしい。※ 人口の泉? 噴水だったかはわからない。1678年から建設が始まり1684年完成。設計主任はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)テラスのファサードだった部分の残骸が屋根裏部屋に残っている。全長73m、幅10.50 m。ギャラリーは357枚のミラーが使用されている。全長73mの鏡の間には17のアーチ持つを窓が作られ明かりを取り込んでいる。もう一方の壁側には窓のアーチと対になるように鏡をはめ込んだアーチ型の装飾がされている。その鏡、故にこのギャラリーはGalerie des Glaces(鏡のギャラリー)と呼ばれる。最も日本では「鏡の間」と訳されて紹介されていたが、最近は「鏡の広廊(こうろう)」とするのもある。英語では鏡のホールになる。天井絵図テーマは「ルイ14世の治世の歴史」で、1661年に親政を開始してから1678年にニメーグで和平が結ばれるまでの歴史。ルイ14世の偉大さを示したエピソードなのである。中央には自ら統治する姿が描かれ、現実の王と古代の神々とが混在し「王権は神から委ねられた。」と、する王権神授説を視覚化した寓意画なのだそうです。1 1772年オランダと同盟を結ぶドイツ&スペイン2 敵中、ライン川の渡り3 王、13日でマースリヒト陥落4 1672年、王、オランダの堅固な要塞4カ所一斉攻撃命令5 1672年、王、陸海両軍の戦闘準備6 1661年、王、自ら統治7 フランス隣接列強の豪奢8 フランシュ・コンテ2度目の征服9 1671年、対オランダ会戦の決断10 1678年、6日でゲントの街と要塞を陥落11 ゲントの攻略にうろたえるスペイン人12 1678年、オランダは和平を受諾。ドイツ及びスペインから離反。残念ながら天井画の撮影をしていないので載せられませんが、来賓が来るたびに天井画の説明をしていた? 王の功績を知らしめるべく描かれているからね。もっとも最初の案は太陽神アポロンを中心とした内容であったらしい。本来はそれが一番自然。何しろ太陽王であるのだから・・。しかしこの案は中止された。原因はルイ14世の弟、オルレアン公フィリップⅠ世 (PhilippeⅠ)(1640年~1701年)が自身の城サン・クルー城(Château de Saint-Cloud)でアポロンに捧げた広間を造って公開していた事が原因らしい。王は弟をライバル視していたから同じ物を造くりたくなかったのだろう。次にヘラクレスの神話を王の偉業に重ねると言う案が出た。欧州では伝統的に君主はヘラクレスに例えられるからからしい。※ ヘラクレス(Hercules)フランスではエルキュール(Hercule)しかし神話も、取りやめ、実際の王の功績が描かれるにいたった。それは王自身が主役である宮殿とはっきり主張しているわけで、ある意味「神話の神にも並ぶオレ様」? 主張なのかも。上の絵図にはヘルメスがいるけどね。直接天井に描かれた絵もあれば、画布に描かれた後に天井に貼られた絵もあるようです。国産の鏡下の写真はウィキメディアから借りてきた写真です。実際に人も多くこのような撮影は不可能です。当時、ガラスはベネチアの専売特許でしたが、ベルサイユの鏡は全て国産です。鏡が非常に高価だった時代である。フランスはなんとか自国生産にこぎつける。しかも並み外れたサイズで、しかも品質が良い。それは技術的にもベネチアのガラス産業の根幹を揺るがすレベルとなったらしい。1672年、ルイ14世の財務総監であったジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert,)(1619年~1683年)はベネチア製品のフランスへの輸入を禁止したという。因みにベルサイユの大理石は南仏に王家専用の採掘場があったらしいが、大きな良質の大理石はベルギーから輸入していた。しかも戦争中でも、特別許可のパスポートを取り付けた荷には戦闘地域の移動が可能であったらしい。敵対国であってもお金次第で融通がきいたのね。シャンデリアの数は41個。大燭台(写真左右の金の燭建て)を含む見事な銀の調度品が置かれていたと言う。エンジェルと女神の2種のタイプがあるようです。下は同じ燭台です。ディアーナ(Diāna)狩猟の女神現在の復元は、1770年に執り行われた16世とマリー・アントワネットの婚礼祭典の飾りだそうです。もっとも最近はパーティーに貸し出したりするし、美術展もよく開催されているので仕様は時々変わるのかも。上の写真、左の鏡の壁が開いて人が出入りしています。最近は分からないが、めったに開かない王の住居部への入り口です。壁側の鏡にはところでころ蝶つがいがついていて、開閉ができる部分がある。下は平和の部屋側から戦争の部屋方面を撮影つまり南から北方面を撮影。窓は西に位置するのでどちらから撮影するかで色が異なります。また時間次第で光量が違う。何よりも今は人が多すぎて・・。下はデジカメになる前のアナログ写真の時代のギャラリーです。フィルムにスライド用を使用しているので割りと綺麗かも。時間にもよるが昔は人が少なかった。平和の間の入り口ランス大理石の柱が並び、その中にルイ14世のお気に入りのコレクションの古代彫刻が置かれています。(現在は数体のみ。)美しくなったこの廻廊からは、地平線まで見渡せるベルサイユの広大な庭を眺められる上に、窓から差し込む光と反射する鏡により光があふれるような輝きをみせる。鏡の間は、王室礼拝堂に行くための通路としても利用されていた他、王族の婚礼祝いの宴や、特派全権使節の為の歓迎レセプションも行われた。要するにパーティー会場にもなる「廊下」兼「イベントホール」である。王族の婚礼に際しては、伝統的に仮面舞踏会が開かれたらしい。ところで、フランス革命後の1871年プロイセン王がここで戴冠。そして、1919年6月26日は第一次世界大戦の講和条約として、ヴェルサイユ条約の調印がここでされた。戦勝国側が、敗戦国(ドイツ帝国)への報復措置である戦争の賠償責任に関する条件を盛り込んだこのベルサイユ条約はドイツとその同盟国の戦争責任を問い、莫大な賠償金を課したものだった。(当時のドイツGNP20年分)さらに、ここでの調印は、プロイセン王の戴冠に対する1871年の意趣返しも込められていたようです。つづくリンク ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間) 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー) リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃
2009年06月13日
閲覧総数 3225
-
5

グランド・ティートン国立公園 2 (スネーク・リバー)
グランド・ティートン国立公園 2 (スネーク・リバー)グランドティートン国立公園(Grand Teton national Park)スネーク・リバー (Snake River) アンテロープ・フラッツ・ロード (Antelope Flats Road)からシュワバッカー・ロード(Schwabacher Road)へ・・そしてスネーク・リバーへグランドティートン国立公園地図アメリカ西部5州の観光局が出しているMAPから借りました。参考です。スネーク・リバー (Snake River) グランドティートン国立公園の北にあるイエローストーン国立公園からの水脈が、ジャクソン・レイクを通ってスネーク・リバーとなっています。大型のゴムボートの乗船者は8~10名ほど。今回はスネーク・リバーの川下りをしながらティートン連邦の絶景を眺めるツアーです。スネーク・リバーは全長1670km。イエローストーン国立公園からの水脈は、やがてはコロンビア川(Columbia River)にそそぐのです。スネーク川はコロンビア川の中でも最大の支流なのです。イエロー・ストーン川(Yellowstone )ところでイエローストーン国立公園からの水脈にはイエロー・ストーン川もあります。イエロー・ストーン川はやがてミズーリ川に注ぎ、セントルイスの北でミシシッピ川に合流するのです。ミズーリ川(Missouri River)はミシシッピ川(Mississippi River)の最大の支流でもあるので、元をたどるるとミシシッピ川の水系もロッキー山系から来ているのです。大自然を感じる川下り・・・日本の川下りとはやっぱり違う形は白鳥にも似ているけど種類は解らない・・・。グランドティートン国立公園つづくリンク グランド・ティートン国立公園 3 (スネーク・リバー・オーバールック)
2010年06月17日
閲覧総数 592
-
6

ナイアガラのレインボーブリッジ
ナイアガラのレインボーブリッジ元祖レインボーブリッジ 国境をまたぐ橋1941年、アメリカ滝の近くに建設された3番目の橋「レインボー・ブリッジ」は、橋の真中が国境になっていて歩いてor車両でアメリカに渡ることができまる国境の橋です。それ故、橋の両側に税関があり、入国審査場があるのです。ベトナム戦争の折には「アメリカの若者が兵役を逃れる為に、この橋を渡り、国外逃亡した。」とも言われている国境です。滝の観光用でUターンする人もいて出入国のチェックが甘かったからかも知れません。カナダ側にあるスカイロン・タワーより撮影したナイアガラ川とレインボー・ブリッジです。左岸がカナダ、オンタリオ州右岸がアメリカ、ニューヨーク。橋を渡って双方から観光するのがおすすめではありますが、国境を越える橋なので、渡るのは容易ではありません。(アメリカ入国が厄介)パスポートだけでは駄目です。アメリカからカナダに渡り戻ってくるのは、(アメリカに1度入国しているので)たやすいですが、カナダからのアメリカ入国が厳しいかもしれません。昨年からアメリカの入国チェックが厳しくなったので、以前と違ってこの橋を渡るのも、より面倒になったのではないかと思います。(アメリカ入国前2~3日前までに事前に入国の打診をアメリカに入れて確認をとらなければならなくなった)以前カナダからアメリカに行くには、パスポート、入国カード、税関申告書とアメリカ入国税と橋の通行料が必要でした。今はそれプラスかな?(カナダの友人に問い合わせているので判ったらお知らせします。)国境渡りは別の回に書きました。2009年の情報なので今は変わっているかもしれません。リンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川の国境越 4 (アメリカ入国審査場)カナダ側より撮影アメリカ側から橋の向こう側、アメリカ(ニューヨーク州)の観光はナイアガラ州立公園から数ヵ所のビュー・ポイントがある。プロスペクト・ポイント公園の歩道沿いやプロスペクト・ポイント展望タワー(この橋の少し右側で霧で見えにくい)霧の乙女号のアメリカ乗り場の波止場からはアメリカ滝が至近距離で望めます。特にゴート島(川の中州)から見るアメリカ滝は、風の洞窟を通してブライダルベール滝の真下まで降りることができ圧巻です。カナダ側クイーンビクトリア公園の遊歩道よりレインボーブリッジとアメリカ滝を見る。カナダ側からカナダ側のクイーンビクトリア公園には手入れされた花壇があり、カナダ滝とアメリカ滝の眺めが最高です。滝付近には展望タワーが二つ滝付近では最も高い地点からの全景が望めるスカイロンタワーと、カナダ滝を見下ろすコニカ・ミノルタ・タワー(現在は名前が違うかも。)※ 滝の見学としては上からの眺望も押さえたい所です。ダイナミックです。カナダ滝のすぐ脇に展望スペース「テーブルロック」があり、真下で滝が落ちていく様子を見ることができます。かつてテーブル状に突き出ていた岩を現在の展望スペースとしたようです。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズは(前回も紹介)カナダ滝裏側のトンネルに行くことができ、展望デッキからはカナダ滝のすぐ脇下から滝が見えます。滝から少し離れた地点には1916年にスペイン人技師レオナルド・トーレス・ケベードによってデザインされたケーブルカーがワールプールにあり凄いです。ちょっと紹介・・と思ったのですが、写真がたくさんあり、どれも捨てがたいのでもう少し「イオン」たっぷりの写真を紹介します。ナイアガラのback numberですが、以前は写真が4枚程度しかのせられなかったので細切れとなっています。再編集したい所ですが、今は他で忙しいのでそのうちに。リンク ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)リンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)リンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラ・オン・ザ・レイク(Niagara on the Lake)
2009年06月24日
閲覧総数 312
-
7
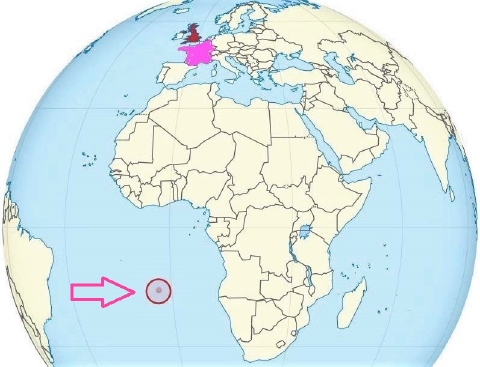
ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還
ワーテルローの戦い(The Battle of Waterloo)(1815年6月)後のナポレオンについては案外知られていないのではないかと思い、セント・ヘレナ島(Saint Helena)で亡くなりパリに帰るまでのナポレオンをちょっと紹介しておく事にしました。実はナポレオンと共にセントヘレナ島に渡った者は結構いるのです。特にナポレオンの側近として島に渡った者の中には、記録係もいるし、後に回想録を書く気満々だった人もいて、実際後に回想録が出されたりしているので島でのナポレオンの事は案外伝えられているようです。参考の為にウィキメディアコモンズからパブリックドメインの写真を借りてきていますが、オリジナル写真はパリの写真くらいです。パリの象徴とも言えるエトワールの凱旋門はアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦勝記念にナポレオンが造らせた記念碑なのです。彼は生きて完成を見る事はできませんでしたが、遺骸が祖国に戻った葬送の時に立ち寄っています。※ 凱旋門 (Arc de triomphe )の直訳は「勝利のアーチ」振り返れば、三帝会戦となったこのアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦闘こそがワーテルローの戦いの因縁になった闘いです。何しろオーストリアのハプスブルグ家を屈服させ、1000年近く続いた神聖ローマ帝国を解体。欧州の政治バランスを崩し覇権をフランスがかっさらった闘いだったからです。そしてそれはどう見ても勝利不可能な闘いでした。ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還セントヘレナ(Saint Helena)島当初のナポレオンの随行員ナポレオン最後の家最悪の医者ナポレオンの死因消えたナポレオンの本物のデスマスク遺体の返還請求Retour des cendres(灰の帰還)ナポレオンが造らせた凱旋門ナポレオンの眠るアンヴァリッド(Les Invalides)下にセントヘレナ(Saint Helena)島の位置を示しました。えらく遠くに追いやられてしまったのだと改めて思います実際、アフリカ海岸沿いに南下しギニア湾に入り西に進路をとりセントヘレナに向かった。※ セントヘレナはアフリカの海岸から1900km。ブラジルから3500kmの離島。当時は帆船。風が凪(な)いで航行できず、セントヘレナ沖に到着したのは出帆(8月9日)から67日目(10月14日)。上陸は1815年10月15日。ナポレオンの最初の感想は「気持ちの良い場所ではない。これならエジプトに残っていた方がましだった。」※ 遠征先のエジプトを密かに脱出し、フランスに戻りクーデターを起こしてナポレオンは皇帝になっている。ノーサンバーランド(Northumberland)号での航海の途中大砲に寄りかかるナポレオンNewcastle University のUniversity Library Special Collections から見つけました。※ この絵の複製は大量に販売されているようです。画家デヴッドにより大分美化された絵で宣伝されていたナポレオンですが、実際は170cmない小柄。しかも晩年は小太りしてずんぐりむっくり。一番リアル画像かもしれませんね。それにしても、哀愁(あいしゅう)感がハンパ無いセントヘレナ(Saint Helena)島島の発見は1502年。ポルトガル人によって発見され、島はヨーロッパとアジアを往復する船舶の寄港地として使われていたらしいが、本格的に入植するのはイギリスの東インド会社が補給基地としてかららしい。1660年の王政復古後、王(チャールズ2世)からの特許状を持って東インド会社は島の要塞化と植民地化を進めていた。※ 1658年建設された砦が現在のジェームズタウンそんな経緯があったから、当時の住民のほぼ半分はアフリカからの黒人奴隷だったそうです。ナポレオンが来る頃は広東貿易の寄港地として活用。当時の島の住人は5800人くらい。つまりセントヘレナ島はイギリス東インド会社が所有する大西洋上の船舶寄港地であった。下の写真は1790年の東インド会社支配下のセントヘレナ島とジェームズタウンの港を描いたエッチングです。ウィキメデイアからかりてきましたセントヘレナ島には砂浜の海岸が無い。1815年、この島にノーサンバーランド(Northumberland)号を旗艦として12隻の艦隊でナポレオンは来航する。ナポレオンを警備する名目で島には海陸の将校2181名が増えたらしい。とんでもない数である。捨て置かれた身のナポレオンにここまで経費を費やすか? とさえ思ったがやはりそれだけ大物だったと言う事なのだろう実際、英国政府はナポレオン派を警戒して島には部隊が駐屯したほか、海軍の艦船が島の周辺を警戒。また、隣の島であるアセンション島やトリスタンダクーニャ島にも英軍が派遣され警備。3000人の監視がついたとも言われている。※ナポレオンの死後、彼ら数千人の滞在者は島を去った。セントヘレナ島でのナポレオン (ウィキメディアからナポレオン救出の為に急襲されるのを恐れてか? 島には常に5隻の艦船がいたし、島の15カ所にナポレオンの状況を監視する信号所が設けられていた。散歩中、睡眠中などいちいち報告されていたようです。当初のナポレオンの随行員英国政府の計らいで、ナポレオンは3人の随行武官を選任する事ができた。武官の家族も一緒に同行。ベルトラン伯(42)・・皇帝の副官でエルバ島にも同行していた。妻ファニー。グールゴー男爵(32)・・砲兵科出身の将軍。ナポレオンを崇拝。モントロン将軍(32)・・1809年からの侍従。ナポレオンがエルバ等に流された時はルイ王朝に走り、戻ってくると再びナポレオンの元に。妻アルビーヌ。島で妊娠して出産。ナポレオンの子ではないかと考えられていたが、その子も亡くなってしまった。娘の名はジョセフィーヌ。ラス・カーズ(49)・・書記兼通訳として特別に追加。ナポレオン帝政下で枢密顧問。ナポレオンの回想録を書く気で参加。父子で参加。オマーラ(33)・・英国の海軍外科医召し使い10人・・オマーラ,ルイ・マルシャン,アリ・サン・ドニ,ノヴェラス,サンチーニら。※ 祖国フランスに残った将校らは軍法会議にかけられて処刑、投獄、流刑されている。セントヘレナでのナポレオンの住まいだったロングウッド・ハウス(Longwood House)ウィキメディアでパブリックドメインになっていた写真です。部屋室は36室。ナポレオンの住居には5つの部屋があったらしい。現在のロングウッド・ハウスはフランスがイギリスより買い取りして博物館になっているらしい。ナポレオン最後の家当初は副総督の別荘だった所を改築、ナポレオンに侍従してきた3将軍やその家族、召し使い10人、侍医、通訳などナポレオンを取り巻く人たちの家は増設され、それなりの屋敷にはなっていたようです。私たちの認識では今まで捕虜的な過酷な暮らしかと思っていましたが、行動範囲が恐ろしく限られていた事などを除けばフォンテーヌブロー宮殿の延長的な暮らしぶりだったようです。コックも居るし、ワインなども欧州や南アから美味しいのを取り寄せていたようです。何しろ貿易の寄港地なのだから結構いろんな物が得られたかもしれないですね。上の写真では清々しい感じですが、セントヘレナは気温的には悪くないようですが一年を通して曇天が多く、カビの繁殖はひどく夏には耐えられない蒸し暑さとなったようです。※ 天気の引用資料をミスりました。引用を隣の島から持ってきてました m(_ _)m当初降雨が多いとしましたが、実際は降雨は少ないけれど、一年を通して曇天が多く、湿度が高く蒸す日が多かったようです。日記にカビになやまされたとあったので露点は高くカビが繁殖したようです。セントヘレナは南半球です。夏のピークは3月ナポレオンは5月5日に亡くなったので、夏の終わり湿度は高い時期のようです。故遺体の腐敗は早く進み2日後にデスマスクをとろうとした時にはすでに困難な状況にあったようです病床のナポレオン これもウィキメディアからですが、ポピュラーな絵ですナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年8月15日~1821年5月5日)最悪の医者島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)(1769年~1844年)は、ナポレオンが逃げたら自分の責任。さらに殺されでもしたら一大事。その為に必要以上にナポレオンの行動に口を出し、ナポレオンを悩ませる元凶になった男。何より、サー・ハドソン・ローの罪はナボレオンの主治医を島から追い出した事。そして具合の悪くなったナポレオンの為に適切な医師を用意しなかった事。真の医者がいなくなり、ナポレオンの健康状態は悪化。困ったナポレオンは母に頼みコルシカ島から医者を呼んだ。それがナポレオンの最後を看取った医者アントンマルキ(Antommarchi)でありデスマスクの制作者である。が、ナポレオン自身は彼をヤブ医者と呼んでいたそうだ。※ François Carlo Antommarchi(1780年~1838年)※ アントンマルキも後に本を出している。ナポレオンはアントンマルキが無理に飲ませた当時の催吐薬(さいとやく)である吐酒石(としゅせき)により胃を余計に悪くしてしまう。飲んですぐに粘液を吐き出すほどに悪くなったのにさらに医師は吐酒石(としゅせき)を飲ませている。そして一日に何度も嘔吐を続ける状態に陥ったようだ。※ 吐酒石(としゅせき)・・・酒石酸アンチモニルカリウムの別称(K2Sb2(C4H2O6)2)「ナポレオンは殺された」よりすでに胃が食を受け付けなくなり弱り切った時に今度はイギリス人軍医により便秘の薬と言う理由で甘汞(かんこう)を飲まされる。その量は通常の10倍。甘汞(かんこう)は塩化水銀( Hg2Cl)。ナポレオンがいつも飲んでいたビターアーモンドの入った麦糖液と作用してシアン化合物が生成。2日(5月3日と4日)にわたり飲まされたナポレオンはタールのような物を排出したそうだ(上から出たのか下から出たのかは不明)そして5月5日に息を引き取った。これだけ見れば今で言う医療事故が引き金といえる。でもそもそもは体調の悪い何かがあってのこれら薬である。Death mask of Napoleon(ナポレオンのデスマスク) ウィキメディアから借りてきました。パリの軍事博物館に展示されているこのマスクはアントンマルキ(Antommarchi)の子孫の寄贈のマスクらしいです。ナポレオンの死因公式にはナポレオンの死因は胃がんと公表されている。それは先に紹介した島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)が、半ば強制的に胃がんで処理したかったからだ。万が一にも毒殺であればローの失態。責任問題である。持病でケリをつけて早く埋葬して隠したかったと言う事情があった。何しろナポレオンの体調が悪いので早く本国の医師に診てもらいたいと言う希望をローが退けてきた経緯がある。まさか本当に病気だったのか? あるいは毒殺だったら?・・と彼はおののいたのだろう。実際、ナポレオンの死の原因は何か? は非常に大きな問題である。今の科学で検査すればすぐにわかる事なのだろうが、フランス政府は遺骸の再調査の許可を出していない。その理由についてはまた色々ある。遺骸はナポレオン本人ではないかもしれないと言う不安もあるだろうが「胃がん死」が一番無難なのだろう。何にせよナポレオンの解剖はことのほか早く(24時間以内)に始まった。解剖医はアントンマルキ含む英国軍医の7人。胃の幽門あたりに潰瘍はあったらしいが、ガンが原因でない事だけはすぐにわかったらしい。問題は肝臓の肥大。しかし、これはローによって削除させられ本国には隠された。ところで ナポレオン胃がん説は、ナポレオンの父と妹が胃がんであった事から出た話であり、ナポレオン自身は生前これは胃ではないと否定しているし、「死んだら必ず解剖してくまなく調べて欲しい」と口癖のように言っていたそうだ。ナポレオン自身が不可解な体調不良に不審を感じていたのは間違いない。因みにこの時、ナポレオンの遺言で心臓が取り出され銀の容器に移されてからマリー・ルイーズに送られるはずであった。以前ハブスブルグ家の分割埋葬のところで心臓の事を紹介しているが、マリー・ルイーズがナポレオンの心臓を自分の棺に入れて眠ってくれるだろうと信じていたのかもしれない。ちょっと哀れだマリー・ルイーズは浮気して相手の子を身ごもり、ナポレオンとの間に生まれた皇子さえ捨てて、もはや完全にナポレオンの事なんか忘れていただろうに・・。※ 2018年6月「ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓」で心臓の保存について書いています。リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓消えたナポレオンの本物のデスマスクマスク造りを主導したのは英軍の六十六連隊外科医であったフランシス・バートン博士(Dr. Francis Burton)だったようだ。一応主治医であったアントンマルキであるが、彼は途中から補佐に入っただけ。バートン博士はデスマスクと胸像を作ろうとして、石膏が足りず、結局、顔面と頭頂部と頭の後ろの3つの部位の型を造り、後はパリで良質の石膏を手に入れてから作り直す予定だったと言う。ところが乾燥させている最中に肝心の顔面だけが持ち去られてしまった。理由は、すでに腐敗を初めていたナポレオンから型取りした顔ではあまりに醜く関係者には不満だったらしい。つまり当初制作したバートン博士のナポレオン像の型は消え、後にアントンマルキが別の若々しいナポレオンのデスマスクを造るに至ったようだ。そもそも、本当にアントンマルキが造ったかはわからない。造形師がいたかも・・。※ アントンマルキの新しい型からは6つのマスクが制作されたとされる。バートン博士は当然、自分に返還するよう抗議したようだが、所有権は注文主にあると主張され、最終的には英国政府もさじをなげたようだ。それ故、今出回っているナポレオンのデスマスクは、死後の顔ではなく、かなり美化された美しいナポレオンの顔なのだとされている。そもそも、ナポレオンの肖像画家であったダヴィットの描くナポレオンもかなり美化されて描かれている事は周知の事実。関係者はナポレオンの名誉を守った? と言う事なのだろう。それにしても亡くなったのが5月5日の夜。6日解剖。7日にデスマスクを採る。そして8日(4日目)には錫(すず)の棺に納められて溶接され、さらにマホガニーの棺に入れられて早い埋葬がされている。わずか2日ほどでナポレオンの体はかなり腐敗。すでにデスマスクを採るには無理があったとされているが、腐敗が進んだ理由の一つは解剖して開いたからだろう。そしてセントヘレナの暑さと湿気も進行を早めたのだろう。だからそれ故、20年後に掘りおこしたナポレオンの遺骸が、ことの外、保存状態が良かった・・と言うのが腑に落ちない。他にも理由はあるがそこに遺骸の取り替え説が浮上し、アンヴアリットに眠るナポレオンは本物か? 説が生まれたらしい。遺体の返還請求当初ナポレオンはセントヘレナのジェラニウム渓谷に埋葬された。本人の希望ではセーヌ川のほとりに埋葬してほしかったらしいが・・。ナポレオンが亡くなったのは1821年5月5日であるが、イタリアに亡命していたナポレオンの母后に知らせが届くのは7月23日。セントヘレナは遠い。ナポレオン自身が67日かけて島まで航行しているのだから・・。8月に息子ナポレオンの亡骸を返して欲しいと言う母の手紙がすくざま英国に送られた。それに対して、英国側は、フランス政府から正式な要請があれば返還の意志ありと伝えたとされるが、王政復古でブルボン王朝に返り咲いているこの時期にナポレオンがフランスに戻ることは不可能だったらしい。事情が変わるのは1840年のフランス7月革命で再びブルボン王朝が打倒されてからだ。ルイ・フィリップが王位に就くとにわかにボナバルト派の中でナポレオンの遺体を取り戻す動きが始まる。フランス政府も再び国民の中で起きているナポレオン人気にあやかるべく、公式に英国政府に働きかけることになった。ナポレオンは革命と自由の象徴として人気が復活していたからだ。英国のヴィクトリア女王も好意的であったらしいが、当時英国とフランスはアフリカ大陸の利権問題で微妙な問題もあった。それ故、この件で両国の平和維持が損なわれる問題になっては困る。お互いに譲歩しなければならない問題も含んでいた。英国としても、棺の中に本当にナポレオンが入っているか? は大きな不安材料だったようだ。確認の為に元の側近、ベルトランらが派遣されるも、万が一偽物であった場合も、英国に怒りを爆発させてはいけないと言い含められたようだし・・。Retour des cendres(灰の帰還)セントヘレナ島から船に積み込まれる棺 ウィキペディアから借りてきました。1840年7月7日、ナポレオンを連れ戻すべく船はル・アーブル港を出港。10月8日セントヘレナ島に到着。10月15日ジェラニウム渓谷の墓地で地下埋葬所の発掘が始まる。発掘作業は英国側が、しかも真夜中である。限られた関係者のみが墓に集まり、他の者は船から下りる事も禁じられ全てが秘密裏に行われた。棺の中を見ることが許されたのも数人のみ。この厳戒態勢がより皆の不審をかったらしい。さらに疑問の元になったのは1821年の埋葬時と1840年の発掘時の棺の状況の微妙な違い。加えて、英国のジョージ4世がナポレオン信奉者で1820年~25年あたりにナポレオンのミイラとなった遺骸を本国に運びウエストミンスターに置いたと言うまことしやかな話しがある。ここに英国がナポレオンの遺骸をすでに本国に運んでいたので別人でナポレオンの棺を造ったと言う説が生まれたのだろう。1840年12月14日にクールブヴォア(Courbevoie)に到着したナポレオンの棺 ウィキペディアから借りてきました棺を乗せた船はル・アーブル港からセーヌ河を遡ってパリまで到着。パリではナポレオンは葬列車に乗って市内を移動し凱旋門の下を通過。そしてアンヴァリッドへ。ウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。ナポレオンが造らせた凱旋門1806年、ナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まった凱旋門の完成は1836年。最初に紹介したように遺骸が祖国に戻った葬送の時に下をくぐり抜けてパレードしていますが、ナポレオンが最初に構想してから王政に移行し、再び共和制に政権が変わっているので、時の事情は建築デザインなどにも影響を及ぼしたようです。その為なのか?新古典様式とうたっている割には微妙。当初は帝政様式でデザインされてもっと装飾も多かったのではないか? と思うのです。ところで、現在は真下が無名戦士の墓碑になっているので車両の通行はできません。凱旋門は他にもありますが、放射状に道の集まるエトワールの凱旋門はナポレオンの葬送で遣われ、後にヴィクトルユゴーの遺体が安置され、第一次世界大戦の同盟国の勝利のパレード等国家的なイベントに利用される場となって行ったようです。無名戦士の墓(シャンゼリゼ方面こちらもウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。葬列はアンヴァリッドにもうすぐ到着。ナポレオンの眠るアンヴァリット(Les Invalides)オリジナル写真は外観だけですが、ナポレオンの墓地となっているパリのアンヴァリッドを紹介。これも古い写真ですが、外観は変わらないので・・正式にはオテル・デ・ザンヴァリッド( L'hôtel des Invalides)1671年にルイ14世が傷病兵を看護する施設として造った軍病院に始まり、廃兵院でもある。現在は一部軍事博物館となっているそうだ。付属の礼拝堂ドーム教会は、もともと聖ルイ(ルイ9世)の遺体安置のために建設された堂。そこに地下墓所が設けられ、ナポレオン・ボナパルト(フランス皇帝ナポレオン1世)の柩が中央に安置され、囲むようにナポレオンの親族や武将の廟が置かれている。Tombeau de Napoléon(ナポレオンの墓)私自身は中に入っていないので、ナポレオンの棺の写真を上下共に、ウィキペディアから借りてきました。建築家ルイ・ヴィスコンティによって設計されたこの墓は1861年に完成。思う以上に立派な葬列をもって葬儀が行われていたようです。ナポレオンがヒ素に犯されていたと言う問題は次回にその根拠を紹介したいと思います。Back numberリンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子 ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Greenナポレオン関連リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式
2019年02月22日
閲覧総数 5671
-
8

オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)
今回は石原裕次郎さんのヨットも係留されていたホノルルのヨット・ハーバーを紹介。オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島アラワイ・ヨットハーバー(Ala Wai Yacht Harbor)ワイキキからアラモアナに行く手前に州立のアラワイ・ヨットハーバーはあります。ハワイ・プリンス・ホテルのちょうど目の前なので、ワイキキあたりを周遊するトロリー・バスがハーバーの前に停車してくれます。(通常観光客が立ち寄るようなところではないですが・・。)レインボーの建物がヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジで、その左側にヨットハーバーが続くいています。写真左手にヨット・ハーバーが続き、ハワイ・プリンス・ホテルが建っています。プリンスのランチ・ブッフェは割とお奨めですアラモアナ・ショッピングセンターはこの写真のさらに左側、アラワイ運河を越えてすぐです。プリンスホテルからの撮影です。ヨットハーバーの左側の端(ワイキキ方面側)を撮影。ホテルの正面真下。様々なヨットやクルーザーが70隻近く係留。かなり広いです。ヨットハーバー 右側(アラモアナ側)ここは、アラワイ運河の海への出口にもなっています。ハーバーの向こうは、マジック・アイランドとアラモアナ・ビーチ。そして写真右がアラモアナ・ビーチ・パーク。アラモアナ・ビーチ・パークと写真右がアラモアナ・ショッピングセンター写真の係留場所は、プライベートのワイキキ・ヨットクラブだと思います。ワイキキ・ヨットクラブ(WYC)1944年37人の熱心なヨットマンにより設立。攻撃された真珠湾もあり船は粛正。アラワイでの軍の活動が縮小された戦争終盤から活動が始まり、軍の払い下げの小屋3つが最初のクラブハウスだったようです。優秀なヨットマンを輩出する名門ヨットクラブ。長く係留されている船の他に、一時的に寄港している船もいます。入国審査前の仮の係留場所があるようです。アラワイ・ヨットハーバーは州立なので係留料金はワイキキ・ヨットクラブよりはかなり安いようです。ところで、入国手続きはどうするのだろうか?外国から寄港した場合は、税関が来てチェックしてくれるまで、上陸できないようです。が、それ以前に出国前にいろいろ準備が必要のようです。(アメリカへのヨットでの入国は、船舶入国となりビザはB1とB2の一般旅行用ですが、事前に日本のアメリカ大使館でパスポートを預けてビザの取得まで時間も少しかかるようです。)さらに、入港には(相手国の領海に入ったら)船首に相手国の国旗、船尾に日本の国旗を掲げなくてはならないようです。海洋冒険家の堀江謙一さん1962年、太平洋単独航海に成功してヨット(マーメイド号)でサンフランシスコに到着した時も彼はパスポートを持っていなかったそうです。当時はヨットでの入出国が想定されていなかったからのようで、特に日本政府とはかなりもめたようですが、当時のサンフランシスコの市長は「コロンブスもパスポートは省略した」と、入国を受け入れてくれた上に名誉市民にまでしてくれると言う破格の英雄扱いをしてくれたようです。(さすがアメリカ人は太っ腹)ワイキキ沖のヨットとダイヤモンドベッド
2010年05月29日
閲覧総数 1222
-
9

水タバコ
イスラム圏の国に行くと、街でおじいさん達が吸っている奇妙な得たいの知れない物がある。麻薬か? それは水パイプとか、水タバコとか水キセルと言われる喫煙具なのだそうです。危ない怪しいものに見えてしまうのは私達の文化にはないからなのかも・・。そう言えば、不思議の国のアリスの中で芋虫? が吸ってましたね。水タバコエジプトでは「シーシャ/Shisha」トルコでは「ナルギレ/Nalgile」イランでは「ガリユーン/Ghaliyan」と呼ばれるようです。リンゴ等のフレーバー付けがされたタバコの葉に炭を載せて熱していぶして、出た煙をガラス瓶の中の水を通し吸う(水をフィルターとして煙を吸う)というタバコである。水の中を通す事でタールを吸収してくれるのか? タバコが軽いと言います。たばこを吸うというよりは「香りの煙りを吸う」感覚のようです。1回の燃焼時間が1時間程度と長く、重さもあり持ち運びはできないので、お店で吸い口だけ付け替えて、用具一式貸してくれるので、携帯する必要はあまりないようです。(一応携帯用の小型具も売ってはいますが・・・。)昼間の気温が高いインドや中近東で人気があると言われてますが、紙巻きタバコのある所ではあまり見かけないようです。下は、エジプトのアスワンのバザールにてここのお店で器具付きでタバコを吸わせてもらえるらしい。1時間はかなり長いですが、そう言えば葉巻も40~50分すると言ってました。余裕がないと据えない大人の楽しみ? のようですが・・・この男性通訳ガイドです。こんなにのんびりしていて大丈夫なのかな?たばこは皿の上の円筒の中につめられているようです。その上に炭?ここは、炭を入れる部分にふたカバーがされています。(トップの所)タバコのフレーバーは果物からスパイス、花、コーヒー、ガムなど多くの種類があり、日本でも通販しているようです。(楽天にもあるから自分で探してね)水タバコの容器は、大小様々で、30cm~80cm位が一般的のようです。下は、お土産屋で売られている水タバコ吸い器具以前、日本のタバコは日本専売公社の扱いだったので、なぜか水タバコの器具でさえ、海外からの持ち込みが禁止されていました。(お土産にできなかった。)今は大丈夫そうですが、ガラスなので壊れやすく重い? 下は、所変わってイランのイスファハーンのチャハイネ(喫茶店)です。ここでは若者達がコンパですか? お茶を飲んだりして皆と談笑しながら吸うのが案外多いと言います。左男性の手の先に見える白い部分(マウスピース)が交換できるようになっています。下はチャハイネの看板です。水タバコの絵が載っています。「水タバコやってます」と言う看板なのですね。ここの所押していて、生活の時間が完全にずれてしまいました。何とか戻さなければ・・。昼間は電話やメールが多く、宅配もよく来て起こされるので熟睡できません。いつぞやは、宅配のお兄さんに「具合が悪いんですか? 」と聞かれて、思わず「はい・・。」と答えてしまいました・・・。
2009年07月16日
閲覧総数 1219
-
10

古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)
ラストにback numberを追加しました。ミイラの容器(棺)の紹介です。古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)サルコファガス(sarcophagus)ウイーン美術史美術館のエジプト展示コーナーから御影石の石棺サルコファガス(sarcophagus)ミイラの話は前回しましたが・・。ミイラの収められていた容器がサルコファガス(sarcophagus)です。石棺全般をさして使用されます。古初期のミイラは、樹脂に浸した包帯で遺体を巻いただけのものであったようですが、そのミイラには生前の姿(顔)のマスクがとりつけられ、棺に入れられていました。中王国以降その棺は、人型棺と呼ばれ、通常は2重で構成されていたそうです。※ 特に一番目の人型の棺(ひつぎ)がコフィンと呼ばれたらしい。コフィンには死者の書が描かれている事も。※ ツタンカーメン王の場合は4重の木製金張りの逗子と珪岩製の石棺、3重の人型棺で特別多く、身分で例外はあるのでしょう・・最初の一つの棺は埋葬者の日常着ていた服装で描かれ、外側の棺は華やかに彩色された「ミイラ型」と呼ばれる独特な表現で、多数の象徴的な図で装飾された屍衣に包まれていたようです。各美術館に眠っているそれらは、絵画的に見ても非常に芸術性が高く素晴らしい物? 芸術作品? 棺と言えど、もはや貴重な美術品として存在しています。※ 死者の書、コフィンテキストについては以下にリンク 「死者の書」とカノプス下はルーブル美術館と大英博物館の所蔵の棺ですが、時代はわかりません。とりあえずその芸術性を見てください。木棺と金貼り棺なので、ぎりぎり末期王朝以前だと思います。ルーブル美術館所蔵の木棺上は全てフランス、ルーブル美術館所蔵の木棺人型でないのもある下はホルス(Horus)神古代エジプトでホルスは王。ファラオはホルスの化身ととらえられていたらしい。黄金の棺大法官イメネミネットのサルコファージュBC7(木棺) ロンドンの大英博物館Fロンドンの大英博物館G木棺つづく・・リンク 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)Back numberリンク 古代エジプトのミイラと棺 1 古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)リンク 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)リンク 「死者の書」とカノプス
2009年05月23日
閲覧総数 2339
-
11

ミュンヘン中央駅(München Hauptbahnhof)
鉄道関連のリンク先をラストに載せました。現在問題になっているシリア問題。安全を求めて欧州に逃れてきたシリア難民。とりわけ彼らが目指すのは欧州でも難民の受け入れに寛容なドイツでした。彼らは仲介者に莫大なお金を払い手はずを整えてもらい国外に脱出。ギリシヤからセルビア、ハンガリー経由でドイツ入りしたシリアの人々が降り立っていたのがミュンヘン中央駅です。(ミュンヘン南50kmに難民の収容センターがあるかららしい。)「ニンフェンブルク宮殿 1」の時に中央駅の写真だけ紹介していますが、ニュースに度々出てくるので、ちょっと予定変更してミュンヘン駅の紹介を先に入れる事にしました。ミュンヘン中央駅(München Hauptbahnhof)ミュンヘン中央駅構内に設置されていた地図を解りやすく修正しました。大きく二つのブロックに分けられる。赤い円が列車のプラットホーム(ここはすべて始発駅である) 黄色の円が飲食などの商業ゾーンである。A(南東)が正面口でB(南西)とC(東)にも出入り口がある。(BC間はメイン通路)A ミュンヘン中央駅の正面口 トロリー、バスの乗車はこちら開業は1839年9月1日屋根が低く小さく見えるが中に入ると結構巨大なターミナル駅である事がわかる。B(南西)側を出た所がタクシー乗り場向かいに見える黄色のビルはメリディアン・ホテルC(東)側は空港行きリムジンバス乗り場待合どころか歩道に立って待つだけなので雨だったら最悪です。尚、空港へのアクセスは地下鉄もある。地下鉄は調度この下から通路で行ける。A正面口から構内に商業施設を抜けると正面にインフォメーションがある。その真向かいに券売機がある。インフォメーションはチケットを売ってくれる所とそうでない所がある。長距離路線の場合、たいていネットなどで事前に購入して来る人が多いので(その方が早割がある。)券売機で購入する人は案外少ない。尚、券売機で買うと安いが、窓口で購入すると値段はもう少し高くなるし、車内で買うともっと高くなる。料金体系がかなり細かくあるので外国人には解りにくい。券売機は以前オーストリアで紹介したものと同じ2015年2月「ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)の中。「QBBの発券機」で紹介しているマシンと同じなので使用方法はそちらを参照してください。リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)ここはすでに駅中なのである。国内への路線は当然ながら国際列車の発着駅でもある。ブダペスト、プラハ、ウィーン、ザルツブルク、インスブルックなど近隣国への路線が多く発着する。改札は無い。しかし乗車前にチケットをマシンに入れて日時の刻印を入れる必要がある。ピンクの矢印の下にマシンがあるのだが、刻印をせずにマシンより先に行く事はルール違反となる。B(南西)側のゲートからの光景B口とC口間はメイン通路右が商業ゾーンで左がプラットホーム商業ゾーン以外にプラット・ホーム前に三角ブースの飲食スタンドが幾つも建っている。駅は深夜も動いているのでおそらく飲食店の何件かは夜も開いていると思われます。実はドイツには閉店法があり、土日など店は休まなければならない法律がありました。最近は世界的な常識や観光客の事もあり、土曜日のオープンは増えてきたそうですが、まだ日曜日に関しては中央駅前のデパートでさえもお休みでした。だから平日買い出しをしておかないといけません。レールジェットでザルツブルグから到着した時に隣のホームにいた列車です。ちょっと強面な感じかドイツっぽいな・・と思いました。Einsatzkommando COBRAÖBB Cobra LOK - Taurus 1116 Siemens欧州の駅の中でも、ミュンヘン駅は結構、駅中が栄えていました。シリアから来た人達はさぞ驚いた事でしょう。同時に新天地ドイツでの生活に希望の想いをはせている事でしょう。本当はシリア本国の内戦が収まり、イスラム国も消えて無くなればみんなハッピーなのですが・・。それにしても大量の移民にかつてのゲルマン民族の大移動が重なりました。ほぼ2世紀毎に欧州には大量の民族が流入し、ローマ帝国も滅びましたが、大量の民族流入そのものが、欧州と言う立地に必然的に起こる現象なのかもしれません。おわり関連のBack numberリンク ドクターイエロー(Doctor Yellow)リンク 東海道新幹線開業50周年の日リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)リンク ユーロスター(Eurostar)リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)リンク ブリュッセル中央駅(Brussels Central)リンク ブリュッセルのメトロとプレメトロ 1 (メトロとプレメトロ)リンク ブリュッセルのメトロとプレメトロ 2 (プレメトロのトラム)リンク 西武鉄道のレストラン列車「52席の至福」
2015年09月09日
閲覧総数 4983
-
12

秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)
今回は「大阪天満の造幣局 2」はお休みしてショートネタ。造幣局で見つけた豊臣秀吉の金の話を単独にしました。1935年(昭和10年)、造幣局の前を流れる大川(旧淀川)からとんでもないお宝が発見された。シジミ獲りの漁師が見つけたお宝は、さらに遡る事1615年(慶長20年)の大阪城落城の際に逃げる船から落とした遺物ではないかと考えられている。それは大阪造幣局のお宝となって今に展示されている「竹流金(たけながしきん)」と「菊桐金錠(きくきりきんじょう)」と名の付いた豊臣時代の金塊。秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)竹流金(たけながしきん)と菊桐金錠(きくきりきんじょう)秀吉の金配りと鉱山開発法馬金(ほうまきん)秀吉の黄金趣味竹流金(たけながしきん)と菊桐金錠(きくきりきんじょう)冒頭紹介した川からの拾いものの金塊であるが、竹流金(たけながしきん)は文字通り竹のような鋳型に砂金を流して造られているのでそう呼ばれているが、室町時代末期から安土桃山時代にかけて作られた秤量貨幣(ひょうりょうかへい)の一つだそうだ。※ 重さが一定していないのは、使用に際して必要分を削ったり切ったりして使うタイプだかららしい。一方、菊桐金錠(きくきりきんじょう)の方は重さの一定したナゲットだったらしい。共に言えるのは軍用や恩賞用として主に利用されるタイプの金で、流通用ではなかったと言う事だ。それ故大阪城、落城の時に慌てていて落としたものではないか? と考えられたのだろう。竹流金(たけながしきん)秤量金貨(ひょうりょうきんか)として必要に応じて切ったり削ったりして使われる金。ちょっとした旅行に携帯するのに便利。菊桐金錠(きくきりきんじょう)竹流金(たけながしきん)と違って、こちらは丸ごと与えられた。こちらは平の家臣ではなく、大名クラスの褒賞用サイズですね。どちらにも菊(きく)と桐(きり)紋(もん)が刻印されている。金塊なのに着物の小紋のような素敵な柄入り。考案した人はオシャレな人だったようですね。その桐(きり)の紋ゆえに豊臣秀吉が鋳造した秤量金貨(ひょうりょうきんか)と推定されたようだ。そして、菊紋は完成品に刻印される印だったと造幣局の説明にはあった。しかし、その紋は、正確に言えば五三桐(ごさんのきり)と十六葉菊(じゅうろくようぎく)なのである。これは織田信長の使用した家紋の中の二つにあたる。左1番目が十六葉菊(じゅうろくようぎく。右2番目が五三桐(ごさんのきり)竹流金(たけながしきん)は永禄(1558年~1570年)、元亀(1570年~1573年)、天正(1573年~1593年)時代の頃、豪族や大名らが、備蓄の軍用金として鉄砲や火薬など武器の支払いや、人を雇う時などの賃金として使う目的でストック。時に武功をあげた家臣の恩賞などにも利用されていた金竿らしい。※ 平の家臣には一削りとか? 今日はたくさん削ってもらえて嬉しい・・とか? かな?まさしくそれは織田信長(1534年~1582年)の時代にピッタリあてはまるオシャレな人だったらしいから、ひょっとしたら織田信長が最初に考案したのではないか? と考えが及ぶ。確証は何も無いけどね。秀吉の金配りと鉱山開発秀吉はいろんな物を信長から継承しているので竹流金(たけながしきん)のルーツが信長にあった可能性はあるが、菊桐金錠(きくきりきんじょう)のような重量の固定されたナゲットは秀吉の頃からかもしれない。何しろ、秀吉は何かとこれら金を大名や家臣(配下の武将)や朝廷の貴族らに配りまくっているからだ。※ 有名な話では、1589年(天正17年)に身分のあるセレブおよそ300人に大判5000枚を配ったと言う「金賦り(かねくばり)」という催しがあったとか・・。それらは秀吉の下に彼らをひれ伏させる事は当然、秀吉の行う事業を円滑にする為の文字通り試金石(しきんせき)になったのだろう。それにしてもそれら金はどこから来たのだろう?なぜ、秀吉はそんなに金持になったのか?太田牛一が書かされた秀吉の軍記物「大かうさまくんきのうち(太閤様、軍記の内)」の一説。「太閤秀吉公御出世より此かた、日本国々に、金銀山野にわきいで・・・」太閤秀吉公の世になってから日本各地で金銀が山から湧くように掘り出されるようになった。※ 太田牛一は織田信長の記録「信長公記(しんちょうこうき)」を書いた人である。それ故に秀吉により白羽の矢が立ったのである。秀吉は全国の鉱山開発を進めたのだろう。おそらく鉱脈を見つける技(わざ)を知っていた?「秀吉は山の者を使っていた」と読んだ記憶がある。山の者が鉱脈を見つけて秀吉に報告していたのなら納得。山野を歩く山伏などは植生で鉱脈を探りあてると聞くからね。かくして、鉱山開発が進められると、そこは直轄領とされ、全ての金、銀、銅は秀吉の元に集まるシステムが造られたのだ。秀吉の後に天下を取った徳川家康は、秀吉のシステムのほとんどをそのまま踏襲している。鉱山ばかりでなく、金貨に至ってもほぼ同じ物が造られている。次に紹介する法馬金(ほうまきん)も秀吉が最初に造ったものである。但し、江戸時代の金貨は幕末に向かう程に金の含有量が減らされて行くのである。財源不足で・・。資料は造幣博物館から豊臣秀吉が天下を取って、スケールが違うなと驚いたものがある 次に紹介する超巨大な法馬金(ほうまきん)である。法馬金(ほうまきん)(分銅金)上は徳川時代に造られたもののレプリカだが、形は計測用の分銅に同じである。大事な事を紹介し忘れていたが、前回、両替秤用分銅で紹介した後藤四郎兵衛家であるが、分銅のみならず、金の造作(大判造りなど)も後藤家が行っていたのである。※ 後藤家繭型分銅(ごとうけまゆがたふんどう)について書ています。リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局後藤四郎兵衛家は室町幕府の時代から御用達彫金師として刀剣の装飾など織田信長にも仕えている。いつの頃から大判の造作に携わったのかははっきり解らなかったが、秀吉と言うよりは、やはり信長の時代あたりからかもしれない。後藤家は豊臣方についた事から当初徳川にじゃけんにされるが、許しをもらい、徳川の時代も大判の製造を続けている。つまり大判小判の製造は幕府直営ではなく、民間企業による委託生産だったと言う事だ。※ 江戸に出たのは後藤四郎兵衛家ではなく分家? の後藤(橋本)庄三郎らしい。因みに、江戸の後藤家屋敷には敷地内に小判の験極印を打つ後藤役所が併設されていた。その屋敷跡が現在の日本銀行本店がある中央区日本橋本石町2-1-1らしい。法馬金(ほうまきん)(分銅金)は大判1000枚で造られた千枚分銅金(約165kg) と大判2000枚で造られた二千枚分銅金(約330kg) と言う巨大な金塊「大法馬金」と重さ375gの「小法馬金」とがある。※ 現存しているのは「小法馬金」のみ。重さではサイズ感がわからないかもしれない。正確に計っていないが、「小法馬金」は最長部6cmくらい。「大法馬金」は最長部38cmくらい。法馬金は何に使ったのか?大法馬金の表には「行軍守城用勿用尋常費」の文字が鋳込まれている。戦争となり、城を守ったり戦に出る時の軍資金であり、通常は使ってはいけない。・・と言う意味で、非常用の備蓄金と言う事のようです。確かにこのビックサイズであれば容易には盗めないですしね。最初に秀吉が造らせた事から太閤分銅金(たいこうふんどうきん)とも呼ぶようだ。大阪城にはこの大法間金が積み上げられていたらしい。でも現存は一個も見つかっていない。一方、小法馬金の方は結構見つかったらしい。ふと、思ったのであるが、徳川埋蔵金、みんなは小判だと思っているが、もし大法馬金であったなら、地中探査レーダーだけでは見つからないのでは? 金属センサーも併用しないとね。もう一つ秀吉が造った大判金貨を紹介。とてもきれいです。天正菱大判上が表 現存は5~6枚と言われるこの大判もまた後藤四郎兵衛家の作品。無名の大判に埋め金して量目を調整してあるそうだ。墨字で十両(量目)と記され、その下に製造責任者の署名と花押(かおう)(サイン)がされている。さらにその下に菱形の中に入った五三桐(ごさんきり)の印が押されている。金の品位が740/1000ですからK18(75.0%)に近いですね。下が裏秀吉の黄金趣味豊臣秀吉は、何かと言えば金を使用する。よほど好きだったのだろうと思われているが、確かにとんでもなく金が産出されて黄金三昧になれば、金でいろいろ造ってみよう・・と言う気にもなるのかもしれない。いろんな物を黄金で作ったと聞くが、珍しい物として外国人に紹介されているのが金の茶室である。秀吉の金の茶室を再現した部屋が大阪城の西の丸庭園の迎賓館にありました。見るからにこれは造りがチープですが、黄金の茶室は運搬可能な組み立て式の移動式茶室だったようです。看板にはGolden Tea Ceremony Room (Chashitsu)と書かれてました。黄金三昧とは、ちょっと成金的ではありますが、法馬金を見てちょっと考えが変わりました。法馬金はいざと言う時に削ったり切り取ったり、あるいは全部溶かして利用する資金です。同じ事が金の茶釜にも言えるのかもしれない。いざとなったら茶釜だって戦費に変われるのです。金は永遠に再生可能な物質なのですから・・。蔵の中でずっと眠っている法馬金よりも金の茶釜はみんなの目を楽しませてくれる。金の茶釜も金の茶室も贅沢と言うより話のネタ? 単純に秀吉の遊び心? だったのかもしれないなーと・・。因みに金は物質的に何の作用も無い金属ですから、金の茶釜で点てたお湯を使った茶は混じりけの無い茶そのものの味がしたはずです。鉄分を補う意味でも使われた鉄の茶釜の湯で入れたお茶とはやはり味が違ったはずです。茶の味を味わうより黄金を愛でて飲んだ茶の方がやはり美味しかったのでしょうけどね総じて思ったのは秀吉が金が大好きだったと言うより、金を利用して宣伝効果をあげていたと言う方が真理なんじゃないのか? と言う事です。まあ、金が嫌いな人はいないと思いますけどね さて、次回は「大阪天満の造幣局 2」で現在のコイン製造を紹介予定です。リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話秀吉関連として豊臣秀吉の正室、北政所(きたのまんどころ)の寧々(ねね)様の隠居した寺リンク 2017年京都 1 (圓徳院と石塀小路)リンク 秀吉の御土居(おどい)と本能寺の移転リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名リンク 秀吉の墓所(豊国廟)リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 1リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 2 (強者の夢の跡を消し去った家康)
2018年04月23日
閲覧総数 8468
-
13

フランス、カンヌの夏 1 (クロワゼット海岸)
長くなっているイエローストーン国立公園。ガイザーばかりで少し飽きてしまいました。で、今回は少し気晴らしに海に行ってみました。季節もちょうど今時分Break Time (一休み)フランス、カンヌ(France Cannes)クロワゼット海岸(Plage de la Croisette)フランス南東部の、地中海に面するコート・ダジュール(紺碧海岸)にある高級リゾート地。意外にもリゾート地となったのは19世紀初頭からだそうです。現在は毎年5月のカンヌ国際映画祭の開催地として有名ですね。海岸線の目抜き通りはラ・クロワゼット通り著名人や映画俳優が宿泊する高級ホテルや高級レストラン、ブティックが並ぶんでいる。ホテル前はプライベート・ビーチでその他は一般海水浴場に。インターコンチネンタル・カールトン・カンヌ(InterContinental Carlton Cannes)1964年以来行われているカンヌ映画祭に出席するのセレブの常宿だそうです。1954年には、ケーリー・グランドとグレース・ケリーの出演した「泥棒成金」(To Catch a Thief)(1955年公開)の舞台に。この時モナコの皇太子に見初められてグレース・ケリーはモナコの皇太子妃になるのです。以降数々の映画でこのホテルは使われた絵になるホテルなのです。最上階に7つの特別スイートがありショーン・コネリー、ソフィー・マルソー、ソフィア・ローレン、アラン・ドロンなどの著名映画スターの名前が付いていると言う。ハワイとは雰囲気が違う。ちょっと日本人には馴染みにくいかも・・・。会場はハーバーにとても近い。ホテル マジェスティック・バリエール(Majestic Barriere)カールトン、マルティネーズと並ぶカンヌを代表する大型デラックスホテル。創業は1920年代頃(はっきりしたデータがない)。80%の部屋が海に面したエレガントなホテルはカンヌ国際映画祭の会場のすぐ近くなので俳優さんや映画関係者も宿泊。ホテル・マジェスティック・バリエールの水上カフェ海から船でカフェに来る人も・・。やっぱりセレブの街・・・。カンヌ国際映画祭の会場は後編につづく
2010年07月10日
閲覧総数 282
-
14

古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)
大きく、編集。ミイラから離れるのですが、棺桶素材のレバノン杉。その「レバノン杉不足の問題」事情を入れました。紀元前4世紀頃、プトレマイオス朝の前章はアレクサンドロスの遠征でエジプトがその支配下に入った事。要するにギリシャ人の支配者が来たので、以降でエジプトの王朝は激変する事になる。アレクサンドロスはこの遠征でシリア沿岸のフェニキア人の都市を傘下に納めペルシャに入るが、この時フェニキア人最大の都市テュロスを壊滅させている。この事は地中海の交易事情を激変させた。会社で言えばテュロスは地中海の貿易商人であるフェニキア人の本社である。それを街ごと破壊してほとんどを虐殺。のがれたわずかの者がカルタゴに渡った。※ 以降フェニキア人はカルタゴを拠点に活動するが、アレクサンドロスの破壊により途切れた文化や産業は多かったのではないか? と予想される。レバノン杉はまさにテュロス含むシリアの木材であり、フェニキア人の大きな交易品の一つであったのだ。確かにレバノン杉は伐採のしすぎで枯渇し始めていた。今のシリア沿岸地帯は森がどんどん消滅して砂漠化をすすめていた。これに加えてアレクサンドロスによるテュロスの壊滅。レバノン杉を大きく輸入に頼っていたエジプトではかなり困ったはずだ。※ 不足した物はレバノン杉だけではなかったはず。古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)木造の人型棺からカルトナージュ(Cartonnage)へプトレマイオス王朝以降新王国時代以降、ミイラ造りは増え数は増加して行く一方、その棺の質は著しく低下していったようです。王侯や神官などの限られた人達だけのミイラ保存がもっと下層の者にまで広がった? のかも。ウイーン美術史美術館のエジプト展示コーナー木造の人型棺からカルトナージュ(Cartonnage)へ第22王朝には、容器の材質も変わって行く。ミイラを木造りの人型棺だけでなく、カルトナージュで造られた棺も現れます。その理由は恐らく棺を造る為の木材不足かと思われます。エジプトでは木材がほとんどとれないので木材は輸入に頼っていた。それがレバノン杉です。これらはフェニキア人らによって地中海を経て運ばれますが、高級品ですし、レバノン杉じたいが伐採のしすぎで枯渇してしまうのです。簡単に言えば、カルトナージュはクラフト仕立ての容器です。凹凸が表現できるカルトナージュはミイラを包み、亜麻布やパピルスを漆喰で固めたものに彩色を施したもの。変化自在のマスクの制作には特に向いており、安価で迅速に作れるといったいくつかの利点があったようです。おそらく、エジプトで豊富にとれるパピルスをベースに作られたのでしょう。しかし、外側の棺自体の装飾は簡素なものになってしまったようです。プトレマイオス朝の棺はこのタイプが多いように思います。カルトナージュのミイラは作成された時代により個性もある。衣装、網目状のビーズ細工、仮面、装飾が施された木板、などで覆われ様々なパーツをのせて飾られていったようです。因みに、グレコ・ローマン時代と言われるプトレマイオス朝後半or以降の古代ローマ帝国時代にはミイラには包帯が巧妙に巻かれた見事なものが多く見られるようになったといいます。プトレマイオス王朝以降古代ローマ人とエジプト人では死生観も全く違いますが・・。古代ローマの埋葬はそもそもギリシャ由来でした。「霊魂は地下において生活を続ける。」(遺体を墓所に葬ると同時に、魂も同じように葬る。)と考えられ、霊魂の埋葬を重要な儀式としていた。葬儀そのものに重点が置かれていたのです。何よりそして火葬が多かったようです。人間の体を火に帰す? 飛翔させて天に帰す? ※ ローマで暗殺されたジュリアス・シーザーは広場で火葬でした。しかし、エジプトでもプトレマイオス王朝はもともとはアレクサンドロスのディアドゴイであったプトレマイオスが継承したのでギリシャ文化が融合されている。エジプト古来の王朝とは全く違うので、その葬儀や埋葬方法も大きく転換していると考えられ考慮しなければならない。※ プトレマイオス朝の首都アレキサンドリアのローマ人の場合。遺体の葬り方はエジプト流にしているようです。また、ギリシア人から火葬の習慣を早くに採用していたローマ人ですが、キリスト教の浸透とともに火葬が減っていく。遺骸を残すエジプト式の方がキリスト教に近い事もある。が、キリスト教自体が中東で生まれているのでエジプトの影響があったのかもしれない。下はカルトナージュ技法の棺のようです。とても雑ですが・・。右はエジプト人とわかりますが、左は神官か豪商? でしょうか。サラセン人ぽい顔です。美的にはゼロですが、カルトナージュされたものが他になかったので参考まで・・。下はミイラの上に付けるマスクです。ルーブル美術館所蔵です。上もルーブル美術館です。リアルですね。下はひょっとしたらカルトナージュでできているかも? のマスクです。かつて、エジプト考古学博物館、ルーブル美術館、大英博物館、メトロポリタン美術館、ボーデ博物館でミイラと棺を見る事ができました。量と美しさで感動したのはボーデ博物館だったと記憶しています。ボーデ博物館は旧東ドイツのベルリン(東ベルリン)の博物館島の中にある美術館の1つです。プトレマイオス王朝と思われる時代のエジプトとローマ帝国の彩色豊かで美しい棺の数々が、「閉ざされていた東の壁の向こうに眠っていた。」と当時思ったのを記憶しています。(行ったのは壁崩壊後ですが・・。)1つ1つが美術的にずば抜けていて、コレクションのセンスが伺えて感激したような気が・・。あのコレクションはゲーリング空相? orヒットラー? が集めたのでしょうか?(ボーデ博物館には有名なネフェルティティの胸像もあります。)もちろんルーブルの棺やイギリスの棺は時代の古い木棺など考古学的にも価値の高い棺が多く、とても素晴らしいです。ミイラはともかく、遺跡発掘の金銭的オーナーになった人達が、自分の取り分としてかなりの量の遺跡の出土品を本国に持ち帰り、個人コレクションにしています。デンマーク、コペンハーゲンにあるニュー・カールスベア美術館(ビール会社社長)は、そういった意味で個人にしてはかなり膨大な彫刻コレクションを持っていました。まったく余談ですが、「ゲーリング空相が集めたコレクションはどうなったんですか?」 と、ドイツ人で、戦争当時国防軍側だった方(独の大学教授)に質問した事があります。彼は「アメリカに持って行かれた!」と冷たく答えてくれました。恐らく絵画などの良い物だけ持って行かれたのでしょう。それが今メトロポリタン美術館にあるかは判りませんが・・。Back numberリンク 古代エジプトのミイラと棺 1リンク 古代エジプトのミイラと棺 2 (容器) 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)リンク 「死者の書」とカノプス
2009年05月23日
閲覧総数 2414
-
15

フランス、カンヌの夏 2 (カンヌ国際映画祭)
Break Time (一休み)1回で収まらなかったので今回もカンヌです。選挙の開票速報を見ながらの書き込みです。かつて2回程選挙活動のお手伝いをした事がありますが、選挙は直接応援に関わると、実はとても面白い(ハマル)ものなのです。お祭りに近い感覚かもしれません。「戦って勝つ」と言う同じ目標に向かうので「同士」と言う特殊な連帯感が生まれますし、自分も出馬した候補者のような気持ちになって選挙に参加しているからです。それだけに落選した時は候補者と同じくらい落ち込むのですが・・・。フランス、カンヌ(France Cannes) Part 2カンヌ国際映画祭の会場 パレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレ映画祭のない時期はコンベンションセンターとしていろいろイベントへの貸し出しをしています。(この建物の裏手の方にカジノも入っています。)カンヌ国際映画祭(Festival International du Film de Cannes)ベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と併せて世界三大映画祭の一つに数えられています。1946年からフランス政府の主催により毎年5月に開催。最高賞(グランプリ)はパルム・ドール(Palme d'Or)と呼ばれる「黄金のシュロ」がモチーフ。過去の日本人受賞者1980年に黒澤明 監督の「影武者」1983年に今村昌平 監督の「楢山節考」1997年に今村昌平 監督の「うなぎ」2004年に「誰も知らない」で柳楽優弥 君が「カンヌ国際映画祭 男優賞」を受賞して話題になりましたね。ホール周辺の広場の石畳にはスターの手形がはめ込まれています。日本映画の巨匠 黒澤 明 監督の手形ハリウッド女優のシャロン・ストーン(Sharon Stone)の手形フランスの俳優 ジャンポール・ベルモンド(Jean-Paul Belmondo)の手形国際映画祭の会場のあるカンヌの西には小高い丘(シュヴァリエ山)があり、このあたりは中世の建物が残る旧市街.ル・シュケ(Le Suquet)と旧港があります。5月下旬から9月にかけて日中25℃以下になる事はないと言う。ヨットハーバーもともとはカンヌは田舎の漁村。カンヌは19世紀に貴族の別荘などが建てられてからセレブの街として浮上してきましたが、映画祭以外取り立てて、特に観光するような所もありません。時間があれば、強いて船に乗ってサント・マルグリット島とサントノーラ島に観光に行くのがよいでしょう。レラン諸島(Iles de Lerains )・・・写真はありません。カンヌから船で15分くらいの所にサント・マルグリット島とサントノーラ島を含むレラン諸島があります。古代ローマの時代よりこちらの方が戦略的にも地中海の要所とされ、7世紀~10世紀にはサラセン人が支配し、近年イギリスとスペインも侵略地として攻撃してきた諸島です。(島行きの船は一日に7~8本この近くから定期船が出ているようです。)サント・マルグリット島(Ile Ste-Marguerite)レオナルド・ディカプリオ主演の「仮面の男」の鉄仮面が幽閉されていた島でルイ14世の命で建てられたらしい牢獄の城塞跡があり独房も公開されつつ今は海洋博物館に。東西3km南北0.95kmの城塞と緑の島。サントノーラ島(Ile St-Honorat)東西1.5km南北0.4km。4世紀にシトー派の修道院が建てられて発展。島には7つの教会とレラン大修道院が島の南にあり、さらにその先に海賊から修道僧を護る為に建てられた要塞修道院があるようです。巡礼者が昔から立ち寄る島だったとか・・。旧港丘の左に12世紀に砦として建設された建物を利用したカストル博物館があります。(カンヌ・プロヴァンス出身の画家の絵画などが展示。)右は16世紀~17世紀に建造されたノートルダム・デスペランス教会があります。マジェスティック・バリエール(Majestic Barriere)のプライベート・ビーチここはホテルのプライベート・ビーチ。椅子やパラソルが並べられたセレブの空間。かたや向側は一般の大衆ビーチ。ハワイのビーチとは何かが違う・・・。そう、アメリカでは個(例えペアでも個別に寝ている)でビーチに寝転ぶけどここでは友人同士、カップルがベッタリより沿っている所が違うのかもしれない。さて、もっと時間があるならここを拠点にニースやモナコ、マントンの美術館に足を運んでも良いかも・・。電車は本数あるので日帰り楽勝です。
2010年07月11日
閲覧総数 241
-
16
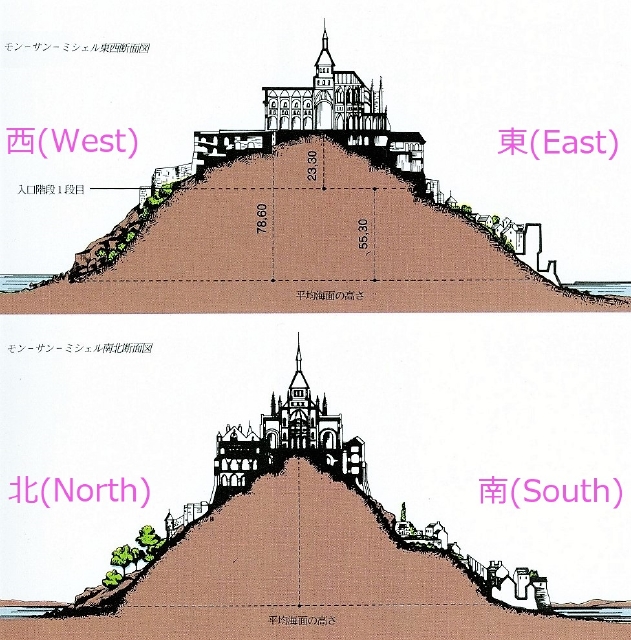
モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユ
back numberのリンク先追加しました。修道院とか、建築とか、要塞とか載せたいものが出てきて時間かかってしまいました。 f^^*) ポリポリ モンサンミッシェルは見所も多いから写真もたくさん載せたかったので結局分割しました。次回も「モンサンミッシェル」です。ついでにフランス王国の成り立ちも加えました。フランク王国カロリング朝(Carolingiens)の末、神聖ローマ皇帝(在位:800年~814年)となったカール(Karl)大帝(742年~814年)の孫の代でフランク王国は東西フランク王国と中部フランク王国(後のイタリア王国)に分烈する。843年ヴェルダン条約によりルートヴィヒ1世の遺児が王国を3分割して相続するが、870年メルセン条約で中部フランク王国は割譲。それらは後のドイツ・フランス・イタリアの三国の原型となる。しかし、割譲された王国も東フランク王国は、ルートヴィヒ4世( 893年~911年)。西フランク王国では、ルイ5世(967年~987年)987年を最後にカロリング朝の血統は途絶え断絶した。ところで、話しは西フランク王国に戻る。西フランク王国では5代目あたりから必ずしも王位はカロリング家の世襲ではなくなっている。有力諸侯や聖職者の推薦で決められたらしいのだ。それ故、西フランクでは諸侯の力が時に王より勝る事になったらしい。前回、ノルマン人(ヴァイキング)の話しに触れたが。「885年、ノルマンに定住した彼らはセーヌ川を遡り、直接パリに多勢で侵略に向かった。この時は3万人のノルマン人(ヴァイキング)が700艘の船でパリに襲来。」と紹介。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人当時のフランク王国はノルマン人がセーヌ川やロワール川の川口から侵略する事が増えて困っていた。この時フランク側の防衛で活躍したのがロベール家(Robertiens)のアンジュー伯、ロベール豪胆公(Robert le Fort)(830年頃~866年)だった。そして次いでパリ伯となっていたロベール家、長子のウード(Eudes)(852年以降~898年)(在位: 888年~898年)は885年のノルマン人のパリ襲撃でノルマン人を阻止し大活躍する。そのパリ防衛の功績で、ウード(Eudes)は諸侯に推挙(すいきょ)されロベール家初の西フランク王国の王となった。※ 因みに、ウードの次代王は、カロリンク朝のシャルル3世 (Charles III)(879年~929年)(在位:893年~922年)に戻っているが、シャルル3世がノルマン公国を公認(911年)した王である。そして、後にカロリンク朝が断絶した時、ロベール家出身のユーグ・カペー(Hugues Capet)(940年頃~996年)が諸侯の推挙で次代のフランク王国の王位に付いた。987年、これよりカペー朝(Capetian)(987年~1328年)の時代が始まるのである。また、これを持って西フランク王国は終わりフランス王国が誕生したと見なされている。ノルマン人(ヴァイキング)を撃退して活躍したロベール家はフランス王国の始祖となったのだ。欧州史は、あちこちで歴史が絡んで来るので大変です。でも、知っているのと知らないのとでは格段に面白さが違いますさて、写真は複数年、季節も混ざっていますので了解お願いします。モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユフランク王国からフランス王国へベネディクト会修道会の招聘(しょうへい)モンテ・カッシーノのベネディクト会修道院中世の修道院の役割ラ・メルヴェイユ(La Merveille)バットレス (Buttress)前に紹介していますが、トーンブの岩を崩す事なく教会堂は岩を覆うように増築され建設されたので、断面を見ると岩山の原型がわかります。下は南西正面角度の異なる教会を紹介ベネディクト会修道会の招聘(しょうへい)ベネディクト会修道会(Benedictine Order)(ラテン語: Ordo Sancti Benedicti)アヴランシュの司教オベール(Avranches Bishop Ober)(生年不明~720年)によって709年10月に開祖されたモン・トーンブ(墓の山)のモン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)はノルマンデイーとブルゴーニュのほぼ境界にあった。933年統合されモン・サン・ミッシェルもノルマンディー領に入る。しかし、ヴァイキング(ノルマン人)の襲来が酷くなってきた頃、避難? アブランシュに置かれていた司教座がドル=ド=ブルターニュ (Dol-de-Bretagne)に移転している。それが原因?モン・サン・ミッシェルの管理者(司教座)がブルターニュに移転したと言う事は、モン・サン・ミッシェルの管轄もブルターニュに移動してしまう? 危惧した? ノルマンディー公、リシャール1世(Richard I)(933年~996年)(在位:942年~996年)は966年、ノルマンディーのサン・ワンドリル修道院とイタリアのモンテカッシーナからベネディクト会派の修道士を招いてモンサンミッシェルに修道院を設立させた。もともとノルマンディー建国当初より、歴代公はベネディクト会を擁護していた事もあったらしい。ノルマン公国時代の首都があったファレーズ(Falaise)にあるリシャール1世(Richard I)像ウィキメディアからですが、下をカットしました。※ 3代目(在位:942年~996年)ノルマンディー公リシャール1世(933年~996年)はノルマンディー公国の統治に集中。内政の安定化とノルマン人同士のつながりを強化し西フランクで最も結束力のある国に成長させた。ベネディクト会を擁護していた方には見えませんね。まだヴァイキング感が抜けていないのですが・・。これは像に問題ありなのか?もしかしたらキリスト教に改宗するにあたり、指導してもらっていたのかもしれませんね。修道士の役割はそもそもそう言うものだから・・。狭い岩山の上に建てると言う制約条件が、他と違う独自性を持った教会となっている。つまり、通常なら横に増築される部屋が縦に積み重なる構造になっている。聖堂の内陣は東に向いて立っている。モンテ・カッシーノのベネディクト会修道院529年、モンテ・カッシーノ(Monte Cassino)の異教の神殿跡にヌルシア(Nursia)の名門出身のベネディクトゥス(Benedictus) (480年頃~547年)は洗礼者ヨハネに捧げた修道院を建立。530年頃、ベネディクトゥスは修道会則を定め共同で修道生活に入ったとされる。※ 聖人に認定されてから聖ベネディクトゥス(St Benedictus)と呼ばれます。聖ベネディクトゥスの戒律(Rule of Saint Benedict)は、全部で73章からなる修道院生活の規律が示されたもので540年頃に書かれた物と推測されている。中身は修道僧の規律となる生活に関する規範とクリストセントリックな生活(Christocentric life)を送る為の精神論だったとされる。多くは修道院と言うコミュニティーの中で謙虚に従順に在る方法や、修道院の管理に関する項目もあったが、食事の質や分量にまで言及されている。ざっと73規約を見たが、道徳に加え、かなり細かい行動内容にまで言及されている。学校の校則に近いものがあるそれは後に西ヨーロッパ中の修道会へ広がり中世ヨーロッパの修道制度の基本とされ導入されている。聖ベネディクトゥスが欧州修道会の父と呼ばれるのはそれ故である。※ 聖ベネディクトゥスは正教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会でも聖人とされている。しかし、実際の全容は解っていない。実は、聖ベネデイクトゥスの死後、581年頃、モンテ・カッシーノはロンゴバルト人(Longobardi)により破壊されその原本が失われているのだ。僧院が再建されるのは718年。※ 表に出たのは難を逃れたベネィクト会の修道士から聞いた話しを 後に教皇(Gregorius I)となる聖アンドレアスの修道士グレゴリウス(Gregorius)(540年? ~604年)が著した事から広まったとされる。当時の聖ベネディクトゥスとベネディクト会が実際にどのような活動をしていたのかは定かで無いが、僧侶たちは毎日8時間祈り、8時間眠り、8時間肉体労働、神聖な読書、慈善活動に費やしていたとされる。聖ベネデイクトゥスが修道院を開いた頃は、西ローマ帝国が無くなり、イタリア半島がロンゴバルト人に浸食され始めた頃である。東ローマ帝国の力はまだ多少あったが、 欧州は絶えず異民族の侵略にさらされよりいっそう暗黒の時代を迎える事になる。そんな中で修道士の活躍はより必要とされた。ベネディクト会では指導できる修道士の育成を積極的に行い各地に派遣もした。教師養成所のような所でもあったわけです。※ ベネディクト会(Ordo Sancti Benedicti)の修道院については以前ヴァッハウ渓谷 (Wachau) のメルク修道院でも紹介しています。リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 2 (メルク修道院)リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 3 (メルクの十字架) 「聖ベネディクトゥスがめざしたもの」について書いています。リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 4 (メルク修道院教会)下の写真、右の塔付きの建物がメルヴェイユ(La Merveille)の一部。塔はコルバンの塔。位置は北東のコーナーモン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)地図下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図から。メルヴェイユ(La Merveille)の建物は北側。ブルーは参道のメイン・ルートを示した。(土産物やレストランの中店通り)※ 参道の途中あちこち山頂の教会堂を目指す階段も存在する。中世の修道院の役割初期の修道院はキリストの禁欲思想に由来するものだったらしい。それは己自身を高める精神の修行が目的であった?しかし、中世中葉、ベネデイクトゥス以降の修道院は時勢により目的が違ってきた。彼らは己の精神修行よりもまずやらなければならない仕事ががたくさんあったからだ。荒廃した世の中の立て直しである。特に彼らは辺境地におもむき宣教よりも先に衣食住の復興や文化の復興もしなければならなかったからだ。輝かしいローマ帝国の文化はいつしか蛮族により荒らされていた。ローマ水道も破壊され、修復もままならず使用できなくなっていた。衛生的な水さえも手にいれられなくなり、文化度は所により原始生活にまで落ちていた所もあったらしい。辺境地に向かった修道士は大地を耕し、失われた文明を取り戻すべく活動を始めた。彼らの仕事には失われた書物の写本もあったが、とにかくギリシャ、ローマの古典、哲学や芸術、薬学や神学書の保存と研究と共に修道士はそれらを伝えるべく、学校や図書館を作り文化の向上に力を入れた。彼ら修道士は村落の立て直しなどにも貢献し、農作物を育てる事なども指導していたと思われる。農作物も修道院では必要で在るし、聖祭の為のワイン造りは必要不可欠。彼らはその技術も当然持っていたからだ。彼らはそうした人々に寄り添いながら福音を述べ伝え、宣教活動もした。命を落とす事も多々あったであろう。殉教(じゅんきょう)と言うワードはまさにこの頃から再び増えて行ったと思われる。一つ気になるのは、庶民の識字率の低さである。彼らは読み書きは教えなかったのだろうか?もっとも、貴族の婦人でも中世半ばまで文字を読めない人はあたりまえにいたらしい。※ 識字率について以前書いています。リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠リンク ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)メルクやザルツブルグの修道院で、彼らが写本していたのはラテン語の書物。大学など高学歴の人材育成に力が入れられていた?しかし ベネディクトゥスは高い学問を学びながら敢えてそれらを放棄させている。「学在る無知の教え」だそうだ。高い学問を一度は体験し、それらを軽んじる事は無いが、神の王国の前にそれらは必要無い。敢えてそれらを棄て、超越した世界に身を置く事を修行とした?それは高い学問を身に付ける事で悪徳の道に迷い、かえって身を滅ぼす者をたくさん見て来たベネディクトゥスの経験から来ているらしい。手前の建物がメルヴェイユ(La Merveille)呼ばれた建築。ネオクラシックのファサード? 一見ロマネスク風建築なのですが・・。聖堂の入口でもある。下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図ですが、をさらに解説を寄せて編集しています。左手前(北面)ゴシック3層構造のゴシック建築の部分であるが、全てひっくるめてラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる。ラ・メルヴェイユ(La Merveille)意味は必ず「驚異」とされているが、何? と思われるだう。ラ・メルヴェイユ(La Merveille)は不思議とも訳される。本意は オッドロキー と言うところかな?それはゴシックを越えた? 建築技術に加え、まるで空中庭園のような屋上の回廊のある美しい中庭の存在だ。メルヴェイユ(La Merveille)は北側に位置するのでモンサンミッシェル全景の写真撮影ができない。下は世界遺産の本から持ってきました。トーンブの岩を崩す事なく教会堂は岩を覆うように増築され建設された。何しろ、そこは古来より神聖な岩山であったからだ。モンサンミッシェルの勢力の拡大と共に岩山の教会は拡大していく。最初の大きな聖堂の着工は1017年。1144年完成。重々しいノルマンディー・ロマネスク様式だったそうだが、クリプト(crypt)の強度の問題か? 15世紀には ひび割れが生じ危険な状態に。しかた無く聖堂の前部を取り壊しテラスにした。下は3層の一番下段。半分は岩山だ。聖堂の内陣も一部壊し、クリプトをしっかり造ってから造り変えるに至った。1446年から1521年。新しくできた聖堂の内陣はフランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)。フランボワイヤンは「燃えるような」と訳されるが、「火炎のような」華麗にして華美な装飾スタイルである。いろんな時代がミックスされています。聖堂は次回に後陣と聖堂の向こうには、3層構造の建物が絶壁に垂直にそそり立つように建てられた。これがラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる建物だ。上の図のラ・メルヴェイユの1階には礼拝堂付き司祭の間と貯蔵庫が置かれた。※ 司祭の間は巡礼者への施しも行われていた。2階、客間(貴賓室)と騎士の間。3階、広い食堂と回廊付きの中庭。※ 中庭からの眺めが驚嘆に値する絶景となっている。再び上層階に上がる大階段のある東面から3層構造の建物なのに一見、控えめなバットレス (Buttress)だけで支えられている。下は補強となるバットレス (Buttress)の部分を色を付けて見た。一見垂直に見えて、実は非常に巧みに組み合わされた控え壁の構造となっている。それは北面サイドを見れば尚さら驚ろく。バットレス (Buttress)15世紀と言う時代である。ゴシック様式でこれだけ高い建物で垂直性を物つ壁はなかなか見ない。石積みだけの壁は高くなればなるほど下方に重荷が来るので壁は外に湾曲にたわむのだ。それは天井にヴォールト構造が取り入れられるようになるとなおさら壁への負荷は増した。※ ヴォールトは次回説明します。だから壁が外に破れるように崩壊するのを防ぐ為に柱なり壁なりで押さえ込む構造で補強される。それがいわゆるバットレス (Buttress)と言う建築構造だ。因みにモンサンミッシェルでも聖堂部を支えるバットレスはまた異なる。フライング・バットレス(flying buttress)と言う飛梁(とびばり)構造になっている。フランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)の部分それはノートルダム教会の聖堂だと確認しやすい。あそこは側廊の壁面もフライング・バットレスだらけなので。リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓因みにフランス語で「支え棒」の事を「アルク・ブータン(Arc-boutant)」と呼ぶらしくフランスの教会案内ではアルク・ブータンと説明されるかもしれない。それにしてもモンサンミッシェルのバットレス (Buttress)は奧が深い。計算され尽くし、かつ機能美さえも備わっている。最もモンサンミッシェルの場合、平地の建物とは異なり、裏側が岩盤により補強されている。1階の半分が岩盤なので可能だったのか?下は2階から3階の部。随所に見られる補強の構造に興味が湧く。3階のアーチは今はガラス? がはめ込まれている。危険だからでしょうね。227本の石柱で支えられた回廊式の美しい方形の庭園になっている。完成は1228年。聖堂より古い。回廊式中庭からの修道士の食堂 食堂は次回にアーチの向こうに広がる海原(うなばら)。見下ろすと目がまわりそうな高所で、空中庭園を想像?皆が感嘆したからラ・メルヴェイユ(La Merveille)驚異なのか? 不思議なのか?「驚異中の驚異」とも伝えられる。聖堂の翼廊の窓ですね。写真と解説を以前より増やした為に次回もモンサンミッシェル」です。なかなか写真のセレクトにも時間がかかり、また図解資料の着色などつまらない所で時間食っています。1週間程度で出せる予定です。緊急事態宣言5月31日まで延長されるようで、なかなか世の中が落ち着かないですね。とは言え、昨年に比べれば通常生活に近いかも・・。旅行は行けないけど・・。昨年から延期されていた姪の式が近づいています。ドレスを買いにデパートに行きたいが、デパートもドレス類は売れないので昨今はそう言う系は縮小されているそうです。でも来週こそ買い物に出かけなければ・・。ネットで失敗したので・・。飲食系だけでなく、そう言うイベント産業の人達も大変ですね。コロナ騒ぎに終息宣言が出されたとしても、完全にコロナ以前の世の中に戻る事は無い気がします。産業も形態も確実に変わって来る事でしょう。また、ネットが増えた昨今ですが、ネットではダメな分野は存在する。とは言え、今までと同じ事をしている企業はダメかも。コロナ後の新しい世界に生きる為に、誰もが進化しなければ。back numberリンク モンサンミッシェル 1 自然に囲まれた要塞リンク モンサンミッシェル 2 トーンブの歴史と大天使ミカエルリンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人 モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユリンク モンサンミッシェル 5 山上の聖堂と修道院内部
2021年05月09日
閲覧総数 1561
-
17
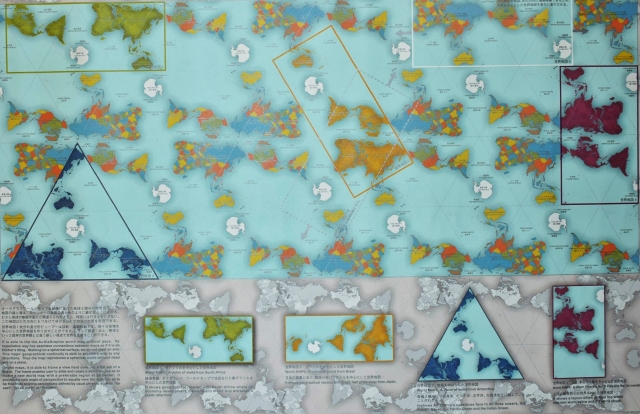
マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図
今回は地図の紹介と併せて「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回となっています。地図を見るのは子供の頃から好きで、今でも世界地図は数種持っていますが、世界を俯瞰(ふかん)して見たい私には一般的なメルカトル図法(Mercator projection)やモルワイデ図法(Mollweide-projection)の世界地図には不満があったのです。双方の長所は緯度、経度の線が直角に表されているので地理的な緯度や経度は解り易い。が、地球という球体を展開して表記している以上、赤道から離れ北や南に向かう程に面積や距離は実寸とはかけはなれ、広がって表現されると言う短所がある。つまり国のサイズや形は実際とはかなり異なってくる。と言う問題がどうしても生じてくる。結局のところ、どのような表記をしようとも平面の地図に完璧な図は存在し得ないのだろうが・・。さらに不満は、たいていの地図は南北の極が上下に固定されているので極地帯の距離感は普通以上にわかりにくくなっている点だ。加えて、日本の世界地図では日本が中心に据えられるという点も気に入らない。日本がどこに存在しているか? また、日本からの諸外国への距離間を知るには当然の配慮なのかもしれないが、両サイドに来るアメリカ大陸や大西洋、欧州は余計にゆがんで表現される。世界をグローバルに捉えたい時に中心に見たいのは太平洋なんかではない。だから子供の頃は平面の地図よりも地球儀をコロコロさせていた。地球儀って、必要ないようで、実は必要かもしれない。困ったのは、ブログを始めて平面地図がほしくなった時だ。以前、北極を中心にした地図の紹介をしたことはあるが、欧州を中心に据えた地図や大西洋を中心にした地図を探したいと思ってもなかなか見つからないのである。今回のような大航海時代を紹介する時にポルトガル視点、スペイン視点、大西洋視点、モルッカ諸島視点などで見たいし、考えたいし、紹介がしたい。その度に視点の変えられる地図が欲しかった。最近は、Googleのおかげで視点を好きな場所に変えて確認する事はできるようになったが、もっと広域に視点の変えられる平面世界地図があったらいいなと思っていた。実は、平面で視点の変えられるAuthaGraph projection(オーサグラフ投影)と言う手法で造られた地図を最近見つけたのだ。AuthaGraph World Map(オーサグラフ世界地図)は北極を中心に切り取ったり、南極を中心に切り取ったり、南米を中心に切り取ったり、アフリカ大陸を中心に切り取ったりできる地図なのである。現段階では小さな図しかないけれど・・。私の不満がカバーできる地図なのだ。今回は、このオーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)を紹介しつつ、それを使ってマゼラン隊の世界周航を一筆書きで紹介しようと考えたのです。でも地図だけで絵は足りない。残念ながらモルッカ諸島の写真は無い。どうするか?友人がパナマ運河就航の写真を提供してくれたので、それで行く予定でしたが、写真の中身に関して確認が終わっていないので、パナマの写真は別枠で次回にしました。そんなわけで今回は、ほぼ地図のみでマゼラン隊に触れます。 m(_ _)mマゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図オーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)とはモルワイデ図法(Mollweide-projection)による世界地図メルカトル図法(Mercator projection)による世界地図オーサグラフ(AuthaGraph)の利点「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) マゼランポルトガルとスペインの競争から始まったアジアの植民地化コロンブスの計画案を引き継いだスペインスペインによる太平洋の発見マゼランが遠征隊長に抜擢された訳と重要人物マゼラン艦隊の内紛問題インテル・カエテラ(Inter caetera)とトルデシリャス条約線 問題東に進んだポルトガルの成功Battle of Mactan の記念碑世界周航と太平洋航路の確立マゼラン亡き後マゼラン隊を率いたエルカーノアントニオ・ピガフェッタの著「最初の世界周航」トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書サラゴサ条約線と教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)マゼランのルート(Magellan Route)モルッカ諸島の利権を手放した件南米最南パタゴニア、マゼラン海峡オーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)とはauthalic(面積が等しい) & graph(図・グラフ) オーサグラフ(AuthaGraph)による世界地図大陸が複数、描かれているのには訳がある。下方左からグリーン・・南アフリカを中心にした世界地図オレンジ・・ブラジルを中心とした世界地図ブルー・・・南極を中心にした世界地図レッド・・・北極を中心にした世界地図どこを中心に切り取っても、世界の大陸や海の位置関係がわかるようになっている地図なのである。オーサグラフ(AuthaGraph)は、ほぼ等面積の世界地図投影法なのであるが、なんと日本の建築家が考案した地図なのである。※ 1999 年、成川肇氏(Narukawa Hajime)によって発明。※ 2016 年グッドデザイン賞、受賞。※ 上の地図は購入したポスターから撮影。地図帳のようなものはまだ販売されていないようです。オーサグラフ(AuthaGraph)による世界地図AuthaGraph(オーサグラフ)は、球面を96個の三角形に等分し、面積比を保ったまま四面体に移し、四角形に展開して作った多面体を統計して作った地図なのだそうです。故に、すべての海,陸の面積比はほぼ正確に表記され、かつ形の歪みも従来よりかなり低減しているという。それはネーミンが示すよう authalic(面積が等しい) graph(図・グラフ) 。中心だけでなく、どの位置から見ても大陸は変形していない。実に建築家らしい発想による地図ですね。最も、地球と言う球体を平面に展開しての地図であるから、経緯度線が無いと大陸同士の緯度が計りにくいかもしれない。モルワイデ図法(Mollweide-projection)による世界地図モルワイデ図法(正積図法)1805年、ドイツの天文学者・数学者カール・モルワイデ(Karl Brandan Mollweide)(1774年~1825年)が考案した地図投影法。地図の外周は、長径2、短径1の楕円形で表現。※ 比率は2:1緯線は水平。経線は中央経線以外は弧を描く。図の中心は正積なのだろうが、中心から離れるほどに歪む。日本の国を見てもらえば、形が変形しているのがわかるし、南極のサイズが大きくなりすぎ。メルカトル図法(Mercator projection)による世界地図中心(赤道)から離れるほど緯線の間隔は拡大して行くので大陸のサイズも拡大。本来、オーストラリア大陸とほとんど変わらない南極が異常なビッグサイズに表現されてしまう。北極圏のグリーンランドもしかり。メルカトル図法(正角円筒図法)1569年、フランドル出身の地理学者ゲラルドゥス・メルカトルGerardus Mercator)(1512年~1594年)が採用した地図(アトラス)で知られた。が、正角円筒図法自体は16世紀初頭にはすでに存在していたらしい。この地図は大航海の時代に向かい、航海用の地図の図法として有効であった。メルカトル無き後息子が継承して発表された世界地図はイギリスその他のヨーロッパ諸国とアジア・アフリカ・アメリカの諸図を加えた107図による地図帖形式で販売。その地図帖は、ギリシャ神話の天空を支える巨人の名をとり「アトラス (Atlās)」と命名された。地図帖がアトラス(Atlas)と呼ばれるようになったのはそうした理由だ。オーサグラフ(AuthaGraph)の利点大陸の相互関係を見るならオーサグラフ(AuthaGraph)。位置関係は断然解り易い。グリーンランド(Grønland)を挟んでカナダと北欧やロシア連邦が向かい合っている。ロシア連邦(Russian Federation)とアメリカ合衆国(united states of america)は近接している。同じく、英国 (United Kingdom)も思う以上にロシア連邦に近い。本来地球上の大陸は北半球に密集している。それ故、人口は歴史的に北半球に偏ってきた。地球全体での陸地と海の比率はおよそ3:7北半球全体の陸地の面積比は39.4%。南半球の陸地の面積比18.4%。北半球の陸地と海の比率はおよそ4:6 → 2:3 の割合になる。極からの北半球円周が赤道に相当。赤道より上(北半球)に大陸が集まっているのがわかる図。極からの南半球でも実際の大陸の位置関係は下のオーサグラフ(AuthaGraph)の方が正しい。下の図はどの角度、どの位置からも地球をカテゴライズできる地図となっています。地球は、6つの大陸(北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸)と3つの大洋(インド洋、太平洋、大西洋)からなっている。オーサグラフ(AuthaGraph)では、あらゆる大陸や海洋との位置関係がわかる。南極に行く船が南米から出航する。やはり一番近接しているからだ。サイズで言うなら南極はオーストラリア大陸より少し大きい程度?そしてブラジルやメキシコは、今までのイメージよりも大きいかもしれない。いろいろ発見が出てくるね「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) マゼラン先に地図ありき・・でした。それにマゼラン隊の世界周航の航路を載せてみよう。と思ったのが始まりです。そもそも「アジアと欧州を結ぶ交易路 」でマゼランの世界周航を載せるべきか? スルーしても良いか?欧州各国の以後のアジア植民地化を見据えた時に、やはりマゼランは触れておかなければならない問題でした。スペインとポルトガルがアメリカ大陸(中南米)を植民地にしようとも、香料諸島の富は絶大であり、あわよくば植民地に欲しい場所に代わりはなかったからです。結果、彼らの挑戦で世界が広い事を知る。同じ一つの球体の上で、別々の文明が存在していた事を知る。時に友好的に、時に支配的に文明は交流する事になる。今や飛行機でひとっ飛び、世界は近くになりつつあるけど、その昔、命かけて世界をつないだ彼らの航海の意義は大きい。ポルトガルとスペインの競争から始まったアジアの植民地化ポルトガルはエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)の元、ポルトガル国家としての事業で遠洋航海を始めた頃から香料諸島を目指していた。だから、どこの国よりも先に外洋に出て目的を果たした。因みに、ポルトガルはその過程でマデイラ諸島、アゾレス諸島、カナリア諸島、ベルデ岬諸島を発見して植民地開発をしている。また、エンリケ王子は資金源をたくさん持っていたからポルトガルにお金はあった。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1497年7月リスボンを出航したヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)は1498年5月インドに上陸。ポルトガルは東周りでアフリカ大陸南端(喜望峰)を回りインド洋に出る航路を開いたのだ。一方、レコンキスタで出遅れたスペインには航海技術も船も、航海士もいない上にお金もなかった。外洋への進出を願ったのは、国ではなく、国家という保証と名誉を求めた航海士と、ゆくゆく得るであろう利益をあてにした商人が持ち掛けた話だったからだ。だから資金のほとんどは航海士本人の借金とそれをバックアップした商人が用意している。※ コロンブスの時はフィレンツェに拠点を置くメディチ銀行とジェノバの商人がいた。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)当初のスペインは基本、船は航海士の持ち込みで、出来高の一部をスペインに献上するという形で新大陸の冒険航海が行われていた。新大陸で利益を得た以降のスペインは多少事情が変わった?※ マゼランの時はアウグスブルクに拠点を置くフッガー銀行とやはり商人がかかわっていた。マゼランの時に関しては、スペインが国として香料諸島のビジネスに参入したかったから? 商人クリストファー・デ・ハロの全額出資を断って、スペイン国が全て負担したらしい。スペイン王(カルロス1世)でもあるカール5世(Karl V)(1500年~1558年)が神聖ローマ皇帝になる為の選挙資金をフッガー家から借金していた話は有名だ。オーストリア・ハプスブルグ家はともかく、兼任しているスペイン王室自体はそんなに裕福ではなかったはずだ。また、フッガー家とスペイン王室のつながりはそこから始まっている。後々、スペインが香料諸島の利権をすべて、それもかなり格安で売り払ったのも、結局お金が必要だったからだ。ところで、メディチ銀行は1499年倒産していたので、代わるようにフッガー銀行が台頭してきたのかもしれない。フッガー銀行は現在も残っている。フッガー家の事書いてます。リンク アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設リンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家航海の話に戻ると、結果、スペインは特使のマゼランが西回りで香料諸島をめざして南米を回り太平洋航路を開き、アジアに到達(1521年)した。※ マゼラン自身は香料諸島到達前に途中フィリピン、セブ島で死亡。マゼランを引き継いだマゼラン隊はその後、香料諸島であるフィリピン南方のモルッカ諸島(Malacca Islands)に到達。たくさんのスパイスをゲット。※ 欧州から西周りルートでも香料諸島にたどりつけると言う事を証明した。だが、東から香料諸島に先陣していたポルトガルに見つかり、追われ、マゼラン隊は逃げるようにモルッカ諸島を脱出して帰国する事になる。その時点でマゼラン隊の船は2隻。太平洋航路を戻るルートをとった(逃げた)トリニダード号はポルトガルに拿捕(だほ)され船舶は沈められた。西に進み続け、インド洋航路をとった(逃げた)ヴィクトリア号のみが逃げ切り、スペインに戻る。この時、マゼラン隊は期せずして世界周航を果たした訳で、同時に世界が球体である事を完全に証明してしまった。 地球が球体と言うのは、また別の問題をはらんでいたが、それ以上に欧州人は香料諸島以外にもあるアジアの可能性を見いだしていた。それは以降、各国の航海術の向上を持って多くの国が競ってアジアを目指したからアジアは植民地ラッシュとなるのである。現在中国の特別行政区となっているマカオ(Macau)が1999年までポルトガルの海外領土だったのは当時の名残り。マゼラン隊の偉業が間違いなく、きっかけとなったのである。コロンブスの計画案を引き継いだスペインところで、なぜスペインは香料諸島をめざすに至ったのか?以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」のところですでに書いてますが、コロンブスの計画案は、西回りで大西洋を横断してのインディアスの発見と黄金の国ジパングの発見だった。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスコロンブスがたどり付いた場所はジパングではなかったし、アジアでもなかったが、コロンブスはすぐそこにアジアがあると信じたまま亡くなった。スペイン政府も当初は彼らがたどり付いた場所(中米)は、アジア東端の半島だろうと信じていたフシがある。だが、中米と南米北西部の植民地化を進める中で、新大陸(アメリカ大陸)は北と南の二つの大きな大陸でつながっていた事がわかる。そこに切れ目はなかった。※ 後にそこに運河を構築して大西洋と太平洋をつなげる事になる。次回パナマ運河やります。スペインによる太平洋の発見バルボアが黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)を探している時にパナマ地峡を横断。そこには広大な海が広がっていた。※ バスコ・ヌーニェス・デ・バルボア(Vasco Núñez de Balboa)(1475年~1519年)1513年、バルボアが「南の海」と命名した、それこそが太平洋だったのである。期せずしてバルボアは太平洋の発見者となった。だが、この太平洋の発見により、スペインはアメリカ大陸を越えるには、新たに航路を見つけなければアジアにはたどり着けない。と言う問題に当った。その頃、ポルトガルはすでに東周りでアフリカ大陸を越え、インド洋ににたどり着き、香料諸島に到達していたからスペインは西回りで香料諸島に行く遠征隊の航海士を慌てて探していたのだ。マゼランが遠征隊長に抜擢された訳と重要人物そもそもはマゼランの友人が経験のある彼をスペイン王に推挙したのである。重要な推薦人と仲間デュアルテ・バルボーザ(Duarte Barbosa)(1480年~1521年)1500 年~1516 年の間ポルトガル領インドの将校をしていた彼はマゼランの妻の兄? (同じ年に生誕した義兄弟)バルボーザは マゼランを強く推挙し、彼と共に航海に出るが1521 年4月、フィリピン、マクタン島の戦いでマゼランが亡くなった数日後、ラジャ・フマボン(Rajah Humabon)の晩餐会で彼も暗殺されている。生誕年と没年までマゼランと一緒。クリストファー・デ・ハロ(Christopher de Haro)(生没年不明)ブルゴス出身のカステーリャの金融家で商人。もともとハロはフッガー家の元、リスボンに拠点を置いていた商人。陰謀によりポルトガル王の信用を失い1516年、活動をスペインに移していた。1519年のマゼランの航海では 4分の1を彼が財政支援している。※ たぶんマゼラン個人の分の支援。また、マゼランを推挙し資金提供しただけでなく、後にエルカーノの遠征資金も提供している。結局、マゼランは途中で亡くなり、エルカーノも太平洋上で亡くなったから資金回収はどれだけできたか? 冒険航海に資金を出すのはロマンだけど、リスクが大きすぎですねフランシスコ・セラーン(Francisco Serrão)(生年不明~1521年没)マゼランの従弟。セラーンは1511 年に香料島であるモルッカ諸島に到達。テルナテ島(Ternate)で妻を娶り島に残った。セラーンはテルナテ島からマゼランに手紙で香辛料諸島の情報を送っていた。二人は結局会う事なく、セラーンも、ほぼマゼランと同じ頃に暗殺されたと考えられている。ところで、セラーンが居たテルナテ島(Ternate)はポルトガル配下である。エルカーノ率いるマゼラン艦隊は隣のティドレ島(Tidore)にたどり着く事になる。事もあろうに両島はもともと仲が非常に悪かったそうだ。フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)1550~1625年頃所蔵 The Mariner's Museum Collection, Newport News, VA実はすでにマゼランはポルトガルの元でヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)が見つけたインド航路をたどりインドへ行っていた。さらに彼は遠征で香料諸島であるモルッカ諸島まで行っていたのである。この経験を買われスペイン王はマゼランと契約したのである。ただ、マゼランは間違っていた。「西周りの方が航路が短いからポルトガルよりも安いコストで香料が手に入る。」と、プレゼンしたらしい。実際は、東周りルートで香料諸島に行ってはいたが、西周りルートの経験はもちろん無い。直面する太平洋航路がいかに長いか彼は全く知るよしも無かった。アブラハム・オルテリウスによる太平洋の地図(1608年) ウィキメディアから借りました。ブラバントの地図製作者、地理学者、宇宙学者アブラハム・オルテリウス(Abraham Ortelius)(1527年~1598年)図は太平洋の海図である。オルテリウスは近代的な世界地図(アトラス)の製作者として知られる。Nao Victoria ナオ船ヴィクトリア号のレプリカ 写真はウィキメディアからチリ、プンタ アレナス(Punta Arenas, Chile)ナオ・ヴイクトリア博物館(Museo Nao Victoria)展示2011年建造※ キャラック(Carrack)をスペインではナオ(Nao)、ポルトガルではナウ(Nau)と呼ぶ。実際のヴィクトリア号には砲弾もそなわっていたはずだが、艦隊は当初、トリニダードを旗艦とする5隻の船とされ、ほとんどが「nao」(キャラック船 )であったが船の詳細は不明で、どの船のイラストも存在しなかったらしい。だから後世のレプリカは実物とは異なるのかも。図はウィキメディアから※ 大航海時代の帆船については「アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人」のところで詳しく書いてます。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人ポルトガル人のマゼランによるスペイン特使としての香料諸島への航海が始まる。ただし、ポルトガルに察知されないよう、マゼランの直接指揮下にある船長以外には真の目的地を話さずスペインを出航したのである。1519年9月、5隻の艦隊を率いてマゼランはスペイン・セビリアを出発。ヴィクトリア号 (Nao Victoria) Captain Luis Mendoza・・キャラック船。旗艦。マゼラン亡き後、エルカノが船長としてスペインに帰還させた船。トリニダード号 (Nao Trinidad) Captain Ferdinand Magellan・・香料諸島から逃げ帰る時に拿捕。コンセプション号(Conception) Captain Gaspar de Quesada・・損傷が激しかった船はマゼラン亡き後、セブ島で沈めて処分。サン・アントニア号(Nao San Antonia) Captain Juan de Cartagena・・パタゴニア海峡で離反し逃亡。サンティアゴ号(Nao Santiago) Captain João Serrão・・サンタ・クルス川の河口 付近で難破。船団員270名のうち、1522年にスペインまで帰還できたのは18名。ただし、ほかの人員が全員亡くなったわけではない。逃亡やポルトガルに捕まった者も結構多い。※ 捕まった者はポルトガル・ルートで本国に帰還している。マゼラン艦隊の内紛問題ところで、スペイン王がポルトガル人のマゼランを抜擢した事自体が後の波乱の問題となった。マゼランは1519年9月、5隻の船を率いてセビリアを出港したのだが、南米のサン・フリアン湾(San Julian)で乗組員による暴動が起きる。謀反者は40人に上り処罰された。マゼラン以外の船長や航海士はスペイン人である。そこそこやり手の船長らは自分が選ばれなかった事に腹を立てて後にマゼランの暗殺を企てたと言うもの。実はポルトガル陰謀説もある。スペインが西周りで香料諸島に来れないようじゃましてほしかった。と言うもの。それもあり得そうな話である。かくしてサン・フリアン(San Julian)湾での反乱後、今度はマゼラン海峡の発見直前には食料船サン・アントニア号が脱走した。サン・アントニア号はスペインに帰還するのであるが、残されたマゼランらは、彼らが逃げたとは思わなかったらしい。帰国してから知る事になる。だが、サン・アントニア号の脱走のせいでスペインが西回りで香料諸島を目指している事がポルトガルに知れてしまった。やはりスパイがいたか?太平洋を横断して東アジアに到達したエルカーノらが、香料諸島から追われたのはそれ故なのだ。Nao Trinidad ナオ船トリニダード号のレプリカ重さ 150t、長さ 93 ft、26 ftのビーム、3 つのマスト、バウスプリットを備え、 メインマストの高さは82 ft。5 枚の帆と 5 つのデッキを備えている。建材はイロコ(Iroko) と松材。※ イロコ(Iroko) はアフリカ南部の広葉樹。比重の割に硬度もあり安価。チークの代替材として船やボートで使われる素材。トリニダード号 (Nao Trinidad)のレプリカはNao Victoria Foundation(ナオ・ヴィクトリア財団)により海事遺産の共有、歴史的な船の修復、建造など研究目的で建造されたらしい。浮遊博物館として世界を周航して展示。乗船も可能。上の写真はオハイオ州クリーブランド2022年のTall Ships Festivalの宣伝の時のもの。インテル・カエテラ(Inter caetera)とトルデシリャス条約線 問題ポルトガルが東周りで香料諸島に。そしてスペインが西周りで香料諸島に到達しなければならなかった理由のおさらいです。これも「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の中「世界を分割したトルデシリャス条約とサラゴサ条約」ですでに書いていますが・・。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1493年、ローマ教皇アレクサンデル6世(Alexander Ⅵ)(1431年~1503年)の教皇勅書「インテル・カエテラ(Inter caetera)」により「教皇子午線」が決められ、スペインとポルトガルの権利域が確定された。翌年(1494年)、両国は協議して「教皇子午線」を少しずらしトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)線を決めた。西経46度37分の東側がポルトガル。西側がスペインに属する。※ おそらくこの線は両国の利権的に納得の行くラインに子午線がずらされたものと思う。このずれた事によりポルトガルは後々ブラジルの利権を大きく獲得する事ができた。両国はトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)線を遵守しなければならなかったから、スペインは東には進めない。現段階では東方面はポルトガルの領域で、西方面の領域は全てスペインの領とされたからである。すでに地球が丸い事はうすうす解っていたから、ポルトガルが先に香料諸島に到達してしまった以上、スペインは西周りで香料諸島に到達して利権を行使(こうし)するしか方法が無かったのである。以前紹介した図ですが東に進んだポルトガルの成功アフリカ大陸を南下して喜望峰を回り、東に北上したポルトガルはインド洋に到達。さらに東に進み彼らは香料諸島に到達する事ができた。1499年バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)がインド航路を開いてからポルトガルは安定したインドへの航海ルートを確立していた。先にマゼランもインドや香料諸島に行っていた事(8年駐留? 1513年帰国)に触れたが・・。ポルトガルは1513年までのわずか14年の間に欧州の香料貿易を独占し、天下を取っていた。直接仕入れる香辛料はヴェネツィアがアラブ人から購入していた時よりも安価。イタリアの商人やドイツ商人(フッガー家)がこぞってポルトガルから商権を奪い合う事になる。つまり、16世紀までその地位にいたヴェネツィアから一気に富を奪いポルトガルはトップの大海洋国に成り上がったのである。それ故、スペインは、ポルトガル人の航海士フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)を航海士に抜擢して西のルート開拓を急いだ。この当時、スペインはまだ航海技術が乏しく、航海士には引き抜いたポルトガル人を雇っていたのが現状。スペインの看板を背負ったマゼランが(1519年9月)西回りでアメリカ大陸を超え、太平洋を横断しフィリピンに到達する。(1521年3月)そこがスペインが求めたアジアの東の果てであった。海図の本「Eary Sea Charts」からSea chart of Malacca,the Indonesian Archipelago,and the Philippines.モルッカ、インドネシア諸島、フィリピンの海図Petrus Plancius Amsterdam.C.1595地図にはスパイスも書き込まれている。下はフィリピンと南方の香料諸島 モルッカ諸島(Malacca Islands)を拡大。不完全さは下の地図と比べると一目。上が1595年当時。地図としてはよくできている。下は現在の地図 ピンクで囲った所がいわゆる香料諸島。モルッカ諸島(Malacca Islands)である。パプアニューギニアのすぐ西の海域ですね。Battle of Mactan の記念碑マゼランは太平洋を横断。目的の香料諸島が近い事を知りながら、不幸にもフィリピンで巻き込まれた戦闘の果て、命を落とす。マゼランが命を落とした場所にスペイン統治時代の1866 年にモニュメントが建てられた。フィリピン政府は2021 年の500周年記念でフィリピンのセブ島ラプラプ市にあるマクタン島にある記念公園のマクタン神殿(Mactan Shrine)を整備。以下写真2枚はフィリピンの観光局のものを利用させていただきました。マゼラン記念碑(Mallelan's Marker)高さ差30mの石のオベリスクマゼランのキリスト教の布教活動 (1521年) を讃えたもので、1866 年のスペイン植民地時代に建立。ラプラプ像(Lapu-Lapu Monument)高さ20m 像はブロンズ1521 年のマクタンの戦いでマゼラン率いるスペイン兵を破った英雄王の像。マゼランの義兄弟のバルボーザ(Barbosa)は 1521 年4月、マクタン島の戦いの数日後、マゼランから初めてキリスト教の洗礼を受けたセブ島の族長ラジャ・フマボン(Rajah Humabon)が開催した晩餐会で暗殺された。世界周航と太平洋航路の確立船長マゼランはフィリピンのマクタン島(Mactan Island)においてラプ=ラプ王(Lapu-Lapu)(1491年? ~1542年)との戦いで戦死した。だからこの時、マゼラン自身は香料諸島に到達していないし、まして世界周航はしていない。だが、マゼランが隊長として率いた船(ヴィクトリア号)が、結果敵に世界周航を果たしたので、マゼラン隊が世界周航を果たしたと言うことになった。最も、マゼランは東ルートで過去に香料諸島に来てはいる。理論的には彼は地球を一周しているのと同じ。この段階ではまだサラゴサ条約線は存在していない。香料諸島の領有権をめぐり、ポルトガルとスペインにとっては、トルデシリャス条約線の180度裏にも線引きが必要になったのだ。どうも、今回は教皇抜きに2国間で話し合いが行われた模様。実際、線引きはしたが、フィリピンをスペインが取り、モルッカ諸島の利権はポルトガルと、後々棲み分けをしている。マゼラン隊、マゼランとエルカーノが航海したルート図※ 緑の枠内(フィリピン)、マゼランが亡くなった場所。そもそも、もしポルトガルに追われて慌てて香料諸島を出る事がなかったなら、マゼラン隊は太平洋をもと来たコースをたどって戻っていたかもしれない。そして、もし両船が太平洋航路をとっていたなら、誰もスペインに戻る事はできなかったかもしれない。ポルトガルに追われた彼らは東コースと西コースの二手に分かれて逃げた。実際、トリニダード号 (Nao Trinidad)は太平洋横断の東コースをとったが、向い風と嵐により断念して戻どった所をポルトガルに拿捕(だほ)された。実は太平洋越えのルートは往路も距離があり大変であったが、それ以上に復路が困難を極めた。赤道を南下し、マゼラン海峡に到達する必要があったが、向かい風で東に進め無かったのだ。貿易風が東から西に吹いているからね。当時は帆船だから偏西風を見つけるまで誰も横断できなかった。危険なコースとされ、マゼラン隊以降、挑戦が試みられたが太平洋を西から東に渡るのに成功するまで40年近く要した。この往路太平洋越えの開拓は1565年にアンドレス・デ・ウルダネータ(Andrés de Urdaneta)がマニラ=アカプルコ航路を確立するまで、なしえなかったのである。参考に太平洋航路を確立した(16世紀頃)のスペインとポルトガルの航路です。ポルトガル航路に長崎が入ってますね。ウィキメディアから借りたマニラ・ガレオンの航路図を合体してポルトガル航路(Portuguese Routes)とスペイン航路(Spanish Routes)に仕分けしました。マニラ・アカプルコ航路は年に1回か2回の定期船となり1565年から19世紀初頭までの250年存在。太平洋横断し、定期便を持つ頃にはスペインはNao(キャラック船)から積荷が多く積めるガレオン船(Galeón)に移行。このスペイン貿易船はマニラ・ガレオンと呼ばれている。積み荷の大半は中国産だったそうだ。因みに、ガレオン船(Galeón)は砲列を増やして戦闘に特化した戦列艦ガレアス(galleass)に発展する。ガレアス船は1571年のレパントの海戦 (Battle of Lepanto)でヴェネツィア軍により登場。勝利に貢献している。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦マゼラン亡き後マゼラン隊を率いたエルカーノマゼラン亡き後、マゼランの隊の旗艦の一つ、ヴィクトリア号を率いたのはバスク出身の航海士ファン・セバスティアン・エルカーノ(Juan Sebastián Elcano)(1476年 ~1526年)である。1521年12月、エルカーノ(Elcano)は香料諸島(Malacca Islands)に到達する。しかし、隣の島にポルトガルが来ていた事を知る。彼らに知られれば捕まってしまう。1522年2月? マゼラン隊は詰めるだけの香辛料を積んで逃げるように香料諸島(Malacca Islands)を出発する。先にも触れているが、来たコースを戻るべく太平洋に向かった船と、危険のあるポルトガル領域を通過してアフリカを回る二手に船は分かれた。太平洋コースに向かったトリニダード号は戻ってポルトガルに捕まった。ヴィクトリア号を率いてインド洋を横断したのがエルカーノ(Elcano)である。ピガフェッタの著によればジョアン・カルヴァッジョ以下隊員50人が島に残留。帰国の船に乗ったのは47名とインディオ13名。※ 上記、60名は、ヴィクトリア号だけ? トリニダード号については語られていない。エルカーノはポルトガルに見つからないようインド洋での寄航は一切せず一気にアフリカ南端を目指した。しかし、喜望峰を越える為に9週間洋上で? 風を待つ事になる。寒さはひどく、船も浸水していたが、近辺はポルトガル領域。どこにも寄航しない道を選び天気が恵まれるまで待った。2ヶ月食料の補給もできなかったから、この間に21人が死亡。喜望峰の座標: 南緯34度21分29秒 東経18度28分19秒船は喜望峰でも停泊せず、北上して北大西洋上のヴェルデ岬諸島(カーボ・ヴェルデ・Cape Verde)まで一気に航海。※ 南半球から赤道を越え北半球に入る為に海流の関係で一気に北上はできない。ベルデ諸島の座標: 北緯14度44分41秒 西経17度31分13秒ここでやっと寄港し、食料調達をするも、ここもポルトガル領。13人が抑留された。前帆柱が折れて修理の必要があったが、慌てて出港。食料が不足しても、船が破損しても補修ができず、船は半壊しながらかろうじてスペインに戻ったのである。(1522年9月)モルッカ諸島を出港した時点で船員は60人いた。船員はほとんどが餓死か病死。ティモール島で逃亡した者、罪を犯し処刑された者、ポルトガルに捕らえられた者も多かったが、食糧が無くて餓死した者。病気になった者はもっと多く、無事に帰国した彼らもほぼ病気になっていた。だからスペインのサンルカル(Sanlúcar)に入港した時点で居たのは18人。2日後に船は華々しくセビリアに入港。航行総距離14460レーガ(約81000km)。地球を西から東に一周した。香料諸島で積んだ積み荷は18人を豊かにした。エルカーノはカルロス王からは生涯年金と紋章を受ける。ローマ教皇にも謁見している。その後のエルカーノは2度目の香料諸島と世界一周航行? を試み、太平洋上で壊血病と栄養失調により亡くなった。彼の失敗は、彼の物語を本にしなかった事だ。彼の成功は、当時皆に知られていたが、時がたち、彼は忘れられた。アントニオ・ピガフェッタの著「最初の世界周航」マゼラン隊の船で日誌をつけていた、ヴェネツィアのアントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)は、帰国後に「最初の世界周航(The first voyage around the world)」について著した本を書いた。教皇の薦めで著した本はマゼラン隊の乗組員による唯一の記録である。※ マゼラン隊の記録としては、彼らの帰国後にスペイン王の秘書トランシルヴァーノがエルカーノら乗組員3名からの聞き取り調査書した「トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書」が存在する。セブ島セブ市独立広場 アントニオ・ピガフェッタのモニュメントウィキメディアからかりて周りを少しトリーミングしています。アントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)(1491年~1534年)ピガフェッタの記録は、日記をつけていただけあって、立ち寄った民族や土地や、言語、食べ物の事など割と細かに書かれている。彼の関心はあくまで、特別な体験や知識にあった?ピガフェッタはセブやモロッカの単語と訳を単語集としてたくさん記録し残している。それが後の言語研究に役立っている。要するに世界周航で見た世界の話と経験した事がまとめられたエッセイなのである。タイトルの「マゼランの世界周航」から期待したのは現地の風俗より、マゼラン隊がいかに海峡を越え、太平洋を越え、モルッカ諸島にたどり付き、喜望峰経由で帰って来たのか? 難航海をいかに制したか? である。航海士目線が欲しかったが彼が航海士ではなかったのでそういう目線が無い。そもそもピガフェッタは直前交渉で船に乗船させてもらった身。とは言え、遠征隊の公式記録者として登録されていたらしい。それにしても疑問なのは、マゼラン隊長に対するリスペクトは感じられるが、彼の本には最後を率いたヴィクトリア号の船長ファン・セバスティアン・エルカーノ(Juan Sebastián Elcano)の事も全く描かれていない事だ。唯一、マゼランが亡くなった後に船長に選ばれた1人として名が出てくるが、その後置き去りにされ生死不明とされている。(・_・?)はて?また、もう一人のヴィクトリア号船長のドゥアルテ・バルボーザもそこで殺されているし、彼らを見殺しにしたジョアン・カルバッチョは最終的に島に残り帰国はしなかった。その辺の事情も全く無い。では誰がその後の船長なのか? 記述がないのも不思議。何にしてもヴィクトリア号はエルカーノがいたから無事に帰国を果たせたと言って過言でない。本来は辛い航海を制した船長へのリスペクトがあってもよさそうなのに・・。意図的にエルカーノの事を消したのか?どうも忖度(そんたく)があったから、マゼランに対する反乱など敢えて濁したらしい。もっとも、エルカーノは最初にマゼランに反旗をしたメンバーの一人であったから、ピガフェッタが彼を良く思っていなかった事は明白だ。トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書カール 5 世の廷臣で、個人秘書でもあったマクシミリアン・トランシルヴァーノ(Maximilianus Transylvanus)(1485~90年~1538年)が帰国後のヴィクトリア号の生存者に航海の事、香料諸島の話、領海問題など聞き取り調査している。公式記録者なのに? ピガフェッタの日記では全く抜けている部分だ。トランシルヴァーノの調書「モルッカ諸島」初版 1523 年スペイン国として、今後どう扱って行くか。条約線をどちらかが越境していた場合は、解消しなければならない問題もある。彼はこの航海で得た情報と現実を王に報告し、国として早く世間に公表しなければならなかったらしい。彼の報告の手紙として、「モルッカ諸島(De Moluccis Insulis)」初版は 1523 年 1 月に出版された。※ ピガフェッタの著は1525年以降。※ この手紙が「トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書」らしい。これは現在ピガフェッタの「マゼラン最初の世界一周航海」(岩波文庫)に一緒に収められている。絶版本かもこの報告でピガフェッタが避けたサン・フリアン湾の反乱の事もはっきりスペインの将校と兵士の間での「恥ずべきで卑劣な陰謀」としている。また、香辛料の栽培なども詳しく紹介されているらしい。まだ完読していません因みに、トランシルヴァーノの妻は実は先に紹介した商人クリストファー・デ・ハロ(Christopher de Haro)(生没年不明)の姪であった。だからマゼランやバルボザとも親しかったのだろう。「トランシルヴァーノの調書」は埋もれた? ピガフェッタの本がマゼラン隊に関する唯一の記録? として長い事世間に知られていた。だからファン・セバスティアン・エルカーノは歴史から忘れさられ、最近になってその偉業がサルベージ(salvage)されたのである。サラゴサ条約線と教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)たった船一隻でもその財は大きかった。香料諸島の利権問題が勃発する。香料諸島はポルドガルのものか? スペインのものか?ポルトガル王とスペイン王の間で話し合いがもたれ、1529年4月、サラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)線が東経144度30分に敷かれた。ところでトルデシリャス条約線は西経46度37分。ポルトガルの方が広いようだが、実際には完全な線引きではなく、地域で部分部分の例外が決められていた。しかし、いずれにしてもこれはスペインとポルトガルが決めた事。確かに最初の教皇子午線はローマ教皇による裁定であったが、これから海洋に進出して来る欧州のほかの国が黙っているはずはない。また、植民地となり、奴隷とされた原住民の人権問題も考慮される時代になりローマ教皇庁も変化した?※ スブリミス・デウス(Sublimis Deu)では、アメリカ先住民は、たとえ異教徒であっても自由や私有財産の権利を持つ完全に理性的な人間であると述べている。1537年の教皇パウルス3世(Paulus III)(1468年~1549年)が公布した教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)によって、1493年の教皇アレクサンデル6世の教皇勅書インテル・カエテラは無効となった。つまり、スブリミス・デウス(Sublimis Deu)の公布をもって、かつての教皇子午線は無効となり、よって東方面がポルトガルの領地で、西方面がスペインの領地と言うかつての裁定も事実上消えたのである。これにより、ポルトガルとスペイン以外の国の海洋進出が始まり、世界各地に欧州の植民地の建設が開始されるのである。マゼラン隊のルート(Magellan Route) (By AuthaGraph)香辛料諸島を目指し、かつ地球を一周したコースをAuthaGraph World Map(オーサグラフ世界地図)上に載せてみてみた。フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)隊が成し遂げた世界周航のルート。1本で示してみた。そこにローマ教皇と取り決めしたポルトガルとスペインの権利分配のラインも書き込みました。西経46度に引かれたトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)のライン東経144度に引かれたサラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)のラインスペインのテリトリー(Territory of Spain)ポルトガルのテリトリー(Portuguese territory)上のルート図を見るに、やはり太平洋の距離があるのがわかる。マゼランは食料船を失い、ただでさえ、食糧不足の中、マゼラン海峡を出た後に食料補給もせずに太平洋に入った。すぐに陸地があると読んだのだが、それは大きな間違い。大西洋航路より、インド洋横断より、はるかに距離があった。アジアまで1万km以上。食糧不足は100日も続く。壊血病など死者も多数。船員がなくなると、マゼランはすみやかに海に流した。人肉を喰らう事を避けたからだ。モルッカ諸島の利権を手放した件ところで、モルッカ諸島では島にジョアン・カルヴァッジョ以下隊員50人が島に残留した。スペインが領有権を主張する為にも残留しなければならなかったのだろう。香料諸島はスペインとポルトガル、どちらの領域か?1529年のサラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)はポルトガルとスペインの話し合いで決まった。この時点で、香料諸島は線からはずれている。最終的にスペインは、マゼラン隊が苦労して得たモルッカ諸島を安い値段でポルトガルに売り払らったのだ。しかし、代わりにポルトガル領内ではあるが、スペインはフィリピンを手に入れた。スペインが太平洋航路を見つけると、フィリピンとアメリカ大陸間の交易が始まる。スペインは香料以外の交易品を多数見つけたのである。フィリピンからではなく、中国から・・。南米最南パタゴニア、マゼラン海峡1519年9月、セビリアを出港。マゼラン一行が最初に寄港した南米大陸はリオデジャネイロ?※ 座標 : 西経43度11分47秒南緯22度54分30秒 西経46度まではポルトガルのテリトリー(領域)だったから本来はここはポルトガル領だったはず。当時の座標が正確かはさておき、かつてアメリゴ・ベスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)が南米大陸東岸を南下し南緯50度まで到達している。※ 1501年~1502年、ポルトガル王の依頼で南米大陸を計測している。※ 実はアメリゴの計測結果でポルトガルはトルデシリャス条約をたてにブラジルの領土を主張した。だからアメリゴ・ベスプッチはブラジルの発見者として知られている。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)1494年6月に締結したトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)により西経46度を超えたらスペインのテリトリー。これはローマ教皇の裁定により決まった条約です。※ 後に撤回された。マゼランは密かに太平洋に抜ける航路を探していた。南緯50度まではかつてアメリゴ・ベスプッチが到達している。彼はデータを取っていたのでポルトガルには海図はあったはずだ。いずれにせよ南緯50度から先の海図は存在しなかったから、船員は海図の無い領域に進む船長に対する不信にあふれていただろう。マゼラン船団がスペインを出港したのは1519年9月。おそらく大西洋に吹く貿易風を待って横断したからかもしれない。しかし南米に到着するまでに2か月が経過していた。陸に上がらず、どんどん南下し寒さが増す中、サン・フリアン湾で反乱もおきた。逃亡する船もあらわれた。そんな中やっと抜けられる水道を発見する。それがマゼラン海峡(Strait of Magellan)と名付けられたパタゴニア(Patagonia)の海峡だ。パタゴニア(Patagonia)は現在の南アメリカ、アルゼンチンとチリの両国にまたがる南緯40度以南の地域。要するに南米大陸の最南端に位置する秘境である。上の地図はウィキメディアより借りました。諸島の中を抜けて太平洋につながる航路をマゼラン隊は見つけて欧州人としては初めて航海に成功。それは重大な発見であり、航海図に記される大発見であった。しかし、交易が盛んになってもマゼラン海峡を通過する航路は表に出ていない。マゼラン海峡を通過してアジアに行くのは非常に危険な航海となった事から、スペインは別のルートを模索し、太平洋航路を確立させた。次回、大西洋から太平洋を横断する、新たなルートの紹介です。最初に書きましたが、今回は「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回です。一往Back numberをいれます。Back numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal) マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン
2023年03月21日
閲覧総数 1512
-
18

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑
ラストに「ハプスブルグ家」関連のBack numberをいれました。けっこうあります。遅れてすみません。甲冑の写真がありすぎて厳選するのに大変で・・。ある程度は系統だてして仕分けしたかったし・・。以前、「西洋の甲冑」を紹介したシリーズがあります。西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)リンク 西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)リンク 西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)そもそも甲冑(かっちゅう)シリーズを始めたのは、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)、略して(V&A)の甲冑のテキスタイルと手先のグローブを紹介しようと思っただけだったのです。(当時は一週間サイクルだったから中身も薄い。)ところが、アクセスも少なかったので続きを保留にしていたのです。今回は、(V&A)の後に行ったウイーン新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からたくさん紹介します。当初予定のグローブも少し載せます。※ 「西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)」ではウイーン王宮のトーナメント用の武具のみ紹介してました。ウイーン王宮の品は完全な王室コレクションです。中世の騎士道、華やかなりし頃の名品の甲冑が量、質とも見ごたえバツグン。ハプスブルグ家のコレクションは、実際に誰が着用していたか解っている武具も残っているし、誰が造った鎧かわかっている物もあるのがすごい。また、その展示方法が素晴らしく、武具好きの方には特にお勧めの美術館です。※ 中世には王侯貴族の甲冑を請け負っていた有名な甲冑師一族もいたようです。西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑ウィーン王宮の甲冑コレクション皇帝のパレード双頭の鷲の紋章ローマ帝国以降の欧州と戦争西ローマ帝国解体後から始まるローマ帝国の危機ロリカ・スクマタ(lorica squamata)中世、暗黒時代を経ての復活十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会西洋の鎧のルーツと名称ホーバーク(Hauberk)メイル・アーマー(Mail Armour)兜 バルビュート(Barbute)とイタリアン サレット(Sallet)バルビュート(Barbute)コリント式ヘルメット(Corinthian helmet)イタリアン サレット(Sallet)アベンテイル(Aventail)アーメット(Armet)クローズヘルメット(Close helmet)マクシミリアン・タイプ奇妙なヘルメットイタリア ルネッサンス期の甲冑スペイン王フェリペ 2 世(Philip II)の騎馬戦闘用の鎧15世紀後半のヨーロッパの有名鎧鍛冶家イギリス サセックス伯の甲冑グローブ(glove)戦闘用の防具が甲冑(かっちゅう)です。日本にも鎧(よろい)、兜(かぶと)がありますが、使用の目的は同じです。見た目は違いますが、頭と体、また腕や足などを守る造りなのもほぼ一緒です。ただ、西洋の甲冑は時代による変遷もさることながら、用途で構造が全く違うのです。地上戦用殴り合い用?馬上用、トーナメント用騎馬の馬用欧州では甲冑造りの有名工房がイタリアとドイツにあったので、国による好みや造りの違いはあったのかもしれません。そもそも甲冑は高価故に着用できる人間は限られていました。多くは王の臣下達です。鋼鉄で造られているのですから、体にフィットさせる為にフル・オーダーです。それは構造上、日本の甲冑以上に体に忠実にフィットさせなければならなかったからです。ところで、西洋の甲冑(かっちゅう)は、古代ギリシャ、ローマ時代と、それ以降で分けて考えた方が良いようです。西ローマ帝国が解体され、ローマ兵がいなくなった欧州の西側は、過去の優れた文化が引き継げない自体にまで荒廃。東ローマ帝国側も病気の蔓延や地震などで弱体化。以降の欧州はイスラム勢に攻められ、暗黒時代を迎え、文明も一度リセットされているからです。古代の武具は青銅製。中世の欧州で使用されたのは鉄製と素材も変わっている。希少だった鉄が手に入りやすくなったこともある。何より機動力が上がる精巧な造りに加えて、軽量化は見てとれます。ウィーン王宮の甲冑コレクション皇帝のパレードウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から以下の写真は照明が暗かったのと、武具、細部の見やすさの為に色調調整してコントラストを下げつつ明るくしています。馬の甲冑もあるのですね。確かに馬がやられては大変ですが・・。腰に付いているのは神聖ローマ帝国の紋章、双頭の鷲(Doppeladler)のようです。つまり、これは皇帝の乗る馬の鎧らしい。考えたら、馬も自分の甲冑と主の甲冑で総重量が人間2人分くらいになっているはず。重いよね。双頭の鷲の紋章もともとローマ帝国の国章は単頭の鷲の紋章だったらしい。それに対して「双頭」は「西ローマ」と「東ローマ」の帝国の支配権を表しているとも・・。つまり双頭の鷲は二つの帝国の支配を示し、13世紀末から東ローマで使われるようになった紋章らしい。13世紀と言えばヴェネツィアが十字軍と共に東ローマ(ビザンツ)帝国に侵攻してコンスタンティノポリスを陥落。ラテン帝国を樹立したのが1204年である。以前書いたが、東ローマ(ビザンツ)帝国は完全にギリシャの帝国と化していた時代だが、実質西の支配に落ちた。だがそのラテン帝国も1261年に陥落。つまり双頭の鷲の紋章が使われ始めた時期は、西側のラテン帝国が滅んだ後の混沌とした時代に、帝国の支配権を主張する者たちが、こぞって付けたがった紋章らしい。神聖ローマ皇帝の紋章であり、ハプスブルグ家の紋章にもなった。騎士の防具、前と後をセットにしてみました。上の甲冑と一見似ているけど、比べてみると、前より後ろで違いが解りやすいですね。鎖帷子と鋼鉄のプレートの混合(Mail and plate armour)です。それにしても防具はパーツ毎に革ベルトで止められている。ベルトが切れたら外れてしまうわけで、戦場で切られたらかなり慌てますね。高級だから捨て置く事もできない。防具を抱えて撤収も在りだったかも・・。そう考えると、防具も毎日のメンテナンスが重要になる。オイルは絶対塗っていただろう・・と思われる。錆(さび)ちゃうし動きを良くする意味でも。やはり戦場には鍛冶屋も同行していたのかもしれない。補修もあるれけど場合によっては変形して脱げなくなる事もあるからね。後で歴史を振り返りますが、要所で言うと、暗黒の中世を経て、復活した欧州人の逆襲が始まる中世後半、騎士が増えたのです。特に十次軍の遠征では、農民も兵士となって聖地エルサレムに向かったから、何万と言う兵士が従軍している。欧州では中世期に十次軍遠征と言う一大イベントがあった。そこでの甲冑の需要は必須。First Crusade (1096年~1099年)Second Crusade (1145年〜1149年)3rd Crusade (1189年~1192年)4th Crusade (1202年~1204年)西欧側(ローマ教皇が中心に)は聖戦の参加者を大量に募集。もともと領主になれない次男以下の貴族の子弟が、こぞって騎士を目指した事もあり、騎士ブームが到来する。最も、その頃は騎士のトップとなる諸侯はフルで武具を着用してましたが、お金の無い騎士見習いなどは装備を整えるのに何年もかかった。それ故、使いまわしも多く、戦場で敵方から奪った甲冑や、古い時代の甲冑もリメイクしたりと割と長く汎用されていたと思われる。造形的にすごくきれいです。鍛冶屋の作と言うよりは、やはり甲冑造りには造形デザイナーがいたのでしょうね。欧州史のおさらいからです。何事も歴史的背景は考慮すべき重要点ですが、武具は特にそうです。ローマ帝国以降の欧州と戦争西ローマ帝国解体後から始まるローマ帝国の危機西ローマの皇帝制が解体され西ローマ帝国が消滅したのは476年。以降、帝都コンスタンティノポリスのあった東ローマ帝国の管理下にはあったが、かつての西ローマ帝国領は縮小の一途をたどって行く。※ 西ローマ帝国解体でローマ兵も居なくなったからだ。一方、東ローマ帝国側も大変な事態に追い込まれて行く。北アフリカやシリア・パレスティナの穀倉地をイスラムに奪われ、その奪還に奔走していたから西側の防衛どころではなかった。※ 穀倉地(属州)が無ければ市民に食料の供給もできないし、兵士に給料も支払えない。※ ローマ帝国の安泰は、高い給料を払う事で得られていた強いローマ軍兵士の存在だった。東ローマの皇帝ユスティニアヌス1世(在位527年~565年)もローマ帝国の再起をかけて奮闘はしたが、疫病のバンデミックと災害に阻まれ、実質のローマ帝国はユスティニアヌス1世の代でほぼ終わっている。ローマ帝国の公用語はラテン後。それは王政期以来、ローマのアイデンティティー(identity)であった。これが消えた時点でローマ帝国は終了したとみて良い。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)には、他国の、また他の時代の武具の展示もありました。ロリカ・スクマタ(lorica squamata)下はローマ帝国時代の武将と馬のモデルです。マネキンが着衣しているものは本物ではないと思われます。彼が着ているのはローマの共和制から帝政時代にローマの武将が身につけていたロリカ・スクマタ(lorica squamata)lを模していると思われます。※ 英語だと「スケールアーマー(Scale armour)」壁画などに見られるだけで、存在は知られているが、完品は現存していないらしい。ロリカ・スクマタ(lorica squamata)は鱗(うろこ)状の鎧(よろい)です。防御の為に、カバーしたい部分を青銅、鉄、鋼、革などの小片のパーツをシャツなどに重ねて、つなぎとめて仕立てられていた。構造がまさに魚のウロコや爬虫類のウロコ。制作には時間や技術がいるものの、皇帝だけでなく、百人隊長などの武将も身につけていた当時の武具です。それは革一枚のロリカより、当然、防御力はあった。いつから取り入れられたかは不明。主に1~2世紀の帝政期初期の主流? 8世紀間に渡って利用されていた武具のようです。下は、ウィキメディアから借りました。小さな金属片をつなげた品の一部です。上は、青銅を薄くして小さくしたプレートを縫い付けてあるようです。マネキンが身に付けて居るのは腰と肩に、おそらく上よりは大きめの厚手の革を縫い付けていたのでは? と想像できます。防御だけでなく、オシャレさもあったのかもしれない。ところが、現存も無い事を考えると、この技術はすたれてしまった。と考えられる。もともと細工が細かいし、時間もかかるし技術もいる。これよりはメイルの方が造りやすかった? 長い暗黒時代に、技術者もいなくなり、もっと楽で丈夫なMail Armour(メイル・アーマー)にとって代わられたのかもしれない。中世、暗黒時代を経ての復活つまり、西も東もイスラム勢を押さえるストッパーがほぼ居なくなり、荒らされ放題だったのが暗黒時代です。5世紀から9世紀頃。特に地中海域はひどかった。海賊による襲撃や拉致が横行。拉致されれば、奴隷として売り飛ばされ生涯が終わった。シチリア島も陥落し、ローマではヴァチカンさえ襲撃された。暗黒時代とは、「キリスト教徒にとっての悪夢の時代」を指しているワードです。フランク族のカール王(742年~814年)がローマ教皇に指名されて大帝(神聖ローマ皇帝在位:800年~814年)となると、彼はキリスト教国である西欧の国を守ると同時にかつての西ローマ領を奪還するべく戦いを開始。すぐに結果が出たわけではなかったが、強いフランク族の存在が、西欧を暗黒の中世から救ったのである。カール大帝以降に、領主に付随する騎士階級が誕生する。システムも装備も、かつてのローマ兵とは全くの別物です。王の兵士と言うよりは、騎士は王の臣下(しんか)と言う位置です。武具はまたそこから進化を始める。そこらへんを書いたリンク先以下です。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊また、9世紀、襲われてばかりいた沿岸国の中で海運に特化して海賊との戦闘に力を入れ自主防衛をしながら地中海交易を再開する国がイタリア半島とアドリア海岸から出現する。Marine Republics(海洋共和国)の台頭はローマ帝国以来の地中海交易を活発化させた。ヴェネツィア商人とか、ジェノバの商人はここから生まれている。少なくとも、地中海交易の復活はキリスト教社会の復活の足がかりになったのは間違いない。※ この当時はまだガレー船が主流の時代です。そこらへんを書いたリンク先以下です。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦十字軍の遠征と聖地奪還後に設立された騎士修道会先に少し触れた騎士階級の誕生が、結果的に十字軍の遠征に繋がる。ローマ教皇の命で聖地エルサレムをイスラムから奪還するべく、各国の王は臣下(騎士)を連れて隊を組み出動。第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年。※ First Crusadeではおよそ騎士4200人~4500人。歩兵3万人が参加と伝えられるが、実際の戦力は1/6程度? さらに実際聖地にたどり付けたのは数%。ところで、十字軍の出動をどうカウントしているか?First Crusade (1096年~1099年)Second Crusade (1145年〜1149年)3rd Crusade (1189年~1192年)4th Crusade (1202年~1204年)※ Crusadeは聖戦の意。十字軍はローマ教皇庁が公式にその出動を認めた時にカウントされている。だから勝手に自分たちで行ったのは十字軍とは言えない。また、ローマ教皇庁が認めていたのは大国の君主がそれなりの騎士を連れて出かけた隊を指すから個人レベルのは当然入らない。1~4回が数えられているが4回目は「暴挙」。そもそも聖地へも本当に行く気があったのか? 正当性を考えるなら、十字軍としてカウントできないと思う。※ 4回目が落としたのは同胞のキリスト教国。かつてのローマ帝国の首都である。それはCrusadeではない。内紛に乗じた、ただの略奪行為だった。話を最初に戻すと、最初の十字軍部隊が聖地エルサレムを奪還した後に主要部隊は帰国してしまった。つまり聖地を管理する者が一気に減ってしまったのだ。聖地はイスラム圏の中の孤島のような場所。いつ取り返されるかもわからない危険地帯。巡礼者が、せっかく近郊の港までたどり付いても、そこから神殿まで危険がいっぱい。これがきっかけで、テンプル騎士団やヨハネ騎士団などの騎士修道会(Knights of Christ)が誕生する事になる。聖地への巡礼者を守る為に自主的にできたボランティアの騎士らが昇格してテンプル騎士団となった。※ テンプルは聖地のソロモン神殿(エル・アクサ・モスク Mosque of El Aksa)内に本拠を置く事を許された事からネーミングされた。※ ヨハネ騎士団は後から軍事化。もとは巡礼者の病院だった。つまり、騎士修道会はどこかの王族に属している騎士では無かった。キリストの騎士を名乗のる慈善団体のような立場。彼らはローマ教皇庁には従った。※ 各国に窓口となる事務局など支部も持っていた。十字軍の騎士が着用していたのがMail (Armour)である。いわゆる鎖帷子(くさりかたびら)。特にテンプル騎士団は、Mail Armour(メイル・アーマー)の上にシトー会の白装束をつけて戦っていた。これら騎士修道会は中世あこがれの存在となる。信心深い者らは十字軍に参加する事を夢見ていた。一方、彼らの事務局のまわりには武具や武器の商人らが集まってきていた。十字軍時代は、武器も兵士も大量に必要であったからだ。要するに、十字軍が聖地を奪還してしばらくは、兵士の補充、バレスチナへの食糧、武器など物資の輸送。また大量に押し寄せる巡礼者の旅費など経済はものすごく回っていたわけです。騎士修道会を書いたリンク先以下です。リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)一時は聖地エルサレムを奪還し、周り(パレスチナ)に十字軍国家も複数建設していたキリスト教軍であったが、100年後には一変。エルサレムを奪われ、追われ、さらにアッコを奪われキプロス島、最後はロードス島に逃れて縮小されて行くのである。結局、エルサレムを奪ったのは最初だけで終わった。Second Crusadeに至っては、エルサレムにもたどり付けなかった。因みに、十字軍の活躍と共に海洋共和国(Marine Republics)は多大な恩恵を受けていた。先に触れたが、巡礼者や兵士、また武器や食料を運ぶ為の船や荷に特需があったから当時の海洋共和国は11世紀頃にどこも全盛期を迎えている。とは言え、直接エルサレム近郊の港に着岸できる権利を持った海洋共和国は3つくらい。逆に言えば、パレスチナの港に着岸許可を持つヴェネチアやジェノバしか、巡礼者を船でエルサレムまで(地中海を横断して)運べなかったのである。だから聖地行きの船はヴェネチアやジェノバから出航していた。西洋の鎧のルーツと名称話をタイトルの甲冑に戻します。西欧の中世の鎧は、およそ3つのタイプに分類できます。Mail (Armour)・・・・・連状の鎖で造られた俗に「鎖帷子(くさりかたびら)」の衣。Mail and plate armour・・鎖帷子と鋼鉄のプレートの混合。Plate armour・・・鋼鉄の鎧(よろい)ですが、これもまた呼び方が複数。Hauberk(ホーバーク)・・そもそもはMail で造られたシャツがHauberk (ホーバーク)です。 (Part2の時に説明)※ しかし、Mail hauberk(メイル・ホーバーク)、Chain hauberk(チェーン・ホーバーク)と素材を入れて表現する人もいる。この場合、鉄のプレートで造られたPlate armour(プレート・アーマー)の事をsteel hauberk(スチール・ホーバーク)と呼ぶ場合もある。つまり、Mail Armour、Armour Clothing Mail、Hauberkと呼び方もそれぞれ。だからややこしかったのです。ホーバーク(Hauberk)ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からこちらは西洋の甲冑 2」で一度紹介していますが・・。メイル(Mail)でできたシャツがホーバーク(Hauberk)「Mail (armour)の歴史」などはPart2で扱っています。リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)ゲント(Gent) フランドル伯居城からメイル(Mail)の編み方に厚みがあります。チェーンのつなげ方も特徴があるようですね。ベルギーのゲント(Gent)にあるフランドル伯の居城は、十字軍時代に建造された古い城です。マクシミリアン1世の代にハプスブルク家に受け継がれたフランドル。※ もともとブルゴーニュ公領だったフランドル。妻はそのブルゴーニュ公の1人娘。ゲントは孫のカール5世(Karl V)の生まれた街でもあります。武具の他に拷問器具の博物館でした。※ 城は写真だけ少し公開してました。リンク ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)メイル・アーマー(Mail Armour)ホーバーク(Hauberk)の説明を見て解るのは、やはり中世期の西洋の鎧(よろい)は、ギリシャやローマ時代の胸当(ロリカ・Lorica)ではなく、鎖帷子(くさりかたびら) Mail Armour から始まっているようです。その鎖帷子がいつ頃出たのかは定かでない。でも原型は古代青銅時代にあったらしい。当時、鉄はまだ希少品。古代ギリシャには青銅製の品があったらしいが、先に紹介した鱗(うろこ)の鎧(よろい)、ロリカ・スクマタ(lorica squamata)の方が人気があったのかもね。メイル(Mail)の素材は、中世の欧州で鉄(iron) or 鋼鉄(steel)となった。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)左のカブトは7世紀頃から? 十字軍の兵士もこのタイプを被っていたかも・・。※ 9世紀から13世紀にかけて最も一般的に着用されたメイル(Mail)防護服である。もしかしたら、古代の物とは、ルーツが違うかもしれない。なぜなら、中世のものは郵便輸送用の袋がルーツらしいから・・。中世の鎖帷子(くさりかたびら)が「メイル(Mail)」と呼ばれるのは、そうした理由かららしい。余談ですが、一般の郵便システムができるのは神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)の時代、1516年である。マクシミリアン1世の時代には、すでにPlate armour(プレート・アーマー)が出現している。※ マクシミリアン1世は中世最後の騎士と呼ばれている。※ 郵便事業のルーツについては以下に書いています。リンク 欧州のポスト 1 郵便事業のルーツと黄色いポストの由来リンク 欧州のポスト2 赤色-ポストの誕生と緑のポスト※ 神聖ローマ帝国圏の郵便輸送事業は一社独占で行われていた。馬車も制服も目立つ為に黄色であった。冒頭に触れたが、欧州では、古代に素晴らしい文明があり、それをローマ帝国が引き継いではいたが、ローマ帝国が衰退の道をたどった時に西ローマ側(現EU諸国)は一度文明がリセットされている。だから? 中世期の西洋の鎧(よろい)は、メイル アーマー(Mail Armour)から再度始まっている。とする説はあながち間違いではないと思う。そのメイル(Mail)は十字軍時代に活躍し、欧州ではプレートの鎧が出現する14世紀まで長く利用されていた。防護性も使い勝手も良かったのだろう。しかし、武器の変化に伴いメイル(Mail)だけでは使われなくなった。※ イスラムではオスマン帝国時代を通してずっと使用されていたが・・。兜 バルビュート(Barbute)とイタリアン サレット(Sallet)バルビュート(Barbute)ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から古そうに見えるけど、実は15世紀のイタリアで人気だったヘルメット。左 1460年 T字型 メトロポリタン美術館右 1470年~1480 年 Y 字型 メトロポリタン美術館※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。バルビュート(Barbute)は古代ギリシャのコリント式に似ている事から古代礼賛のルネッサンスの中で生まれたヘルメットと考えられている。知識人が多くいたイタリアならではの古代へのリスペクトと考えられる。実際、イタリア以外での人気は無かったらしいから・・。参考に以下に古代ギリシャのコリント式ヘルメット(Corinthian helmet)を紹介。左 BC500年 青銅製のコリント式ヘルメット(Corinthian helmet) ミュンヘン古遺物博物館右 BC430年頃 コリント式ヘルメットを付けたペリクレスの胸像 バチカン美術館Vatican Museumsこれ自体は後年のコピーらしい。※ 着用した時に首筋が守られる造りだった。※ 上の写真はいずれもウィキメディアからかりました。比べると解るイタリアン バルビュート(Barbute)より遙かに芸術性が高いコリント式。防御能力も高そうです。でも、重かったでしょうね。なぜペリクレスを載せたか? そもそもギリシャの重装歩兵は戦闘時以外ではペリクレスのようにヘルメットを上向きに着用していたらしい。ローマ帝国でも1世紀まではイタリア式コリント ヘルメットが使用されていたらしいが、ローマ兵も上向きに着用の慣行からスッポリかぶると言うより帽子のように着用していたらしいのだ。それが粋(いき)な着用の仕方だったのかもね。 ローマ帝国ではギリシャ文化を礼賛していたようだから・・。イタリアン サレット(Sallet)それ故? 無駄な部分ははずされ? 安全性は落ちるけど、最初から被るだけのサレット(Sallet)誕生につながったのかもしれない。ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)から頭頂部が尖っているのは、そうする事で強度が得られたから。サレット(Sallet)とバルビュート(Barbute)は、ほぼ同時期にイタリアに現れた関連したヘルメットだったらしい。アベンテイル(Aventail)ヘルメットと Mail が合体したもの。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)突起にメイル(Mail)をカーテンのようにつなげて利用していた? と思われる。1320年頃から着脱式が出てきたらしい。こうした表面がみががれていない鉄色の黒い甲冑も存在する。エドワード黒太子(Edward, the Black Prince)(1330年~1376年)と呼ばれるイングランドの王太子がそう呼ばれたのは、甲冑の色が黒だったから、という説もある。??ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)被るだけのタイプ?アーメット(Armet) 15世紀から17世紀半ばまで使用されたArmetはバイザーが横開き。Close helmetは縦開き。サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)写真がなくて、少しぼけてますが、横開きはこれくらいしかなくて・・。これがArmetかな?アーメット(Armet)はイタリア、フランス、イギリス、低地諸国、スペインで広く使用されたらしい。ベルギーは低地だしね。クローズヘルメット(Close helmet)ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から中世後期からルネッサンス時代1390年~1410年バイサーはとがっていたらしいが、1410年頃からバイザーは丸みを帯びてくる。サンカントネール美術館(musée du Cinquantenaire)から (ベルギー ブリュッセル)国により? それぞれ。タイプがいろいろあります。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から右のはどこから開くのかもわからない。マクシミリアン・タイプウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)マクシミリアン・タイプ? のドイツ式クローズヘルメット。ベローズバイザー付き。1520年。アーメット(Armet)と似ているが、バイザーが縦に開らく。またクローズ式でもニュールンベルク型とアウグスブルク型があったらしい。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から本家のマクシミリアン・タイプ?神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世 (Maximilian I)(1459年~1519年)はブルゴーニュ公女(一人娘)と結婚した事で金羊毛勲章(Toison d'or)をハプスブルグ家に継承した。マクシミリアンが中世最後の騎士と呼ばれるのは、彼がブルゴーニュ公の領土をフランスから守ったからなのである。フランスvsオーストリアの因縁はそこから始まったらしいが・・。因みに彼の孫がカール5世(Karl V)(1500年~1558年)である。※ 金羊毛勲章(Toison d'or)と公女との結婚の事など書いています。リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)ゲントのフランドル伯居城にもマクシミリアン・タイプがありました。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からトーナメント用の騎士の所に展示されていました。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から皇帝もしくはそれらに準じる人たちの甲冑かも金の象嵌細工がほどこされ、帽子も盾も非常におしゃれ。いずれにしてもキズもなさそうなので、実戦使用は無かったと思われる。1500 年頃から、甲冑やヘルメットにもファッション性が現れてくる。クローズヘルメットは多種多様なものが現れてくる。実践やトーナメントはもちろん、パレードやお祭りに特化したような物もあらわれる。状況でパーツの取り換えなどするタイプも出ていたらしい。トーナメント武具は前回紹介していますが、馬上から長い棒で付き合う試合なので防具は特殊な形に進化しています。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から戦場で目立つ為なのか? ゴージャスすぎる甲冑後ろの肖像画の方の甲冑ですが、誰か調べている時間も無いので・・。奇妙なヘルメット「グロテスクな」バイザーを備えたヘルメットも数多く残っているらしい。これらは、パレードやお祭りの際に着用される「衣装鎧」の一部として使用されたと考えられています。下のは肖像の人物に似ているかも。イタリア ルネッサンス期の甲冑メイルとプレートの混合写真を探していて、変な物を見つけた。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から右の騎馬のおじさんは細かいメイルとプレートの混合であるが、正面の甲冑は何か変。ヘルメットが螺髪(らほつ)柄だ甲冑もちょっと異色。甲冑の主はウルビーノ公フランチェスコ マリア 1 世(Francesco Maria I) (1490年~1538年)。ローマ風の鎧 。これはイタリアン、 ルネサンスの典型的なスタイルらしい。布地にたくさんのプレートを縫い付けてできているらしい。1532年頃にミラノの有名な甲冑師フィリッポ・ネグローリ(Filippo Negroli)によって制作。ウィーンに説明はなく、ネットで画像検索して見つけました。ところで、前回「ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日」の中、「ルネッサンスの中で掘り起こされた古代の舞台劇」でも書きましたが、この時代、15世紀、イタリアでは偶然も含めて多数の過去遺跡の発見や書物の発見(ローマ時代やギリシャ時代の)があったのです。知識人や人文学者、また芸術家らがこぞってそれら過去の遺物を掘り起こし、研究を行い、礼賛し、古代にあった文明を復興させようと活動。それがルネッサンス(Renaissance)です。※ Renaissanceはフランス語で「再生」の意。それにしてもエンボス加工で螺髪(らほつ)の造形って、笑うこれはリクエストなのか? 甲冑師の趣味なのか? 説明ではムーア人の・・となっていましたが、これはまさにヘレニズム期のペルシャの人々の頭です。ヘレニズム期にペルシャ帝国で、ギリシャ彫刻のスタイルを借りて初めて仏像が制作された。それら像は東洋に伝来。ブッダの頭髪はペルセポリスの壁画にいる人々と全く同じ螺髪(らほつ)のヘアスタイルです。下は象嵌細工がほどこされた鎧。黒く磨かれた鎧に金線を埋め込み模様を描く象嵌細工(ぞうがんざいく)の手法と、エンボス加工の技術で造られた鎧だそうです。金の絵付けかと思ってましたが象嵌細工だったのですね。金工象嵌は、元々シリアで生まれ、シルクロード経て飛鳥時代に日本にも伝来した技術です。シリアのダマスカスで生まれたからダマシン(Damascene)と呼ばれる。トレドの工芸品の土産として今も有名。トレドではダマスキナード(Damasquinado)と呼ばれている。6世紀~13世紀、イベリア半島はイスラムに支配されていた。キリスト教と反転するレコンキスタ後は、改宗して残留した元イスラムの職人らが、キリスト教文化と融合したムデハル(mudejar)様式なる建築などを残している。スペインが他の欧州と少し違うのはその為だ。また、シチリア島もイスラムに占領された時代があり、シチリアでもムデハルが見られる。金工象嵌は、イスラムの職人らが欧州人に伝えた技術だったのかもしれない。因みに、イベリア半島は1492年のイスラムのナスル朝(グラナダ王国)陥落で完全に一掃された。中世後期ヨーロッパで有名な甲冑師一族であるアウクスブルクのヘルムシュミート(Helmschmied)家の作品。スペイン王フェリペ 2 世(Philip II)の騎馬戦闘用の鎧甲冑師デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)(1513年~1579年)制作。1544 年頃。画像が暗すぎてかなり色調を明るくしてます。カラーが少し違うかもしれません。この鎧は神聖ローマ帝国皇帝カール5世(Karl V)(1500年~1558年)(神聖ローマ帝国皇帝在位:1519年 ~1556年)が息子フェリペ 2 世(Felipe II)(1527年~1598年)の為に発注した鎧。ウイーンにはボディ。スペインにヘルメットがあるらしい。若かりし頃のオラニエ公ウィレム1世(Willem I)(1533年~1584年)の肖像上の写真はウィキメディアからかりましたが、デルフトのプリンセンホフ博物館(Municipal Museum Het Prinsenhof)にあった肖像画で、若かりし頃のオラニエ公です。彼が身に着けている甲冑が、先に紹介したフェリペ2世の甲冑と同じ甲冑師、デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)の作品です。ヘルムシュミート家では、神聖ローマ帝国含む複数の王侯貴族を顧客としていた。ヘルムシュミート(Helmschmied)家の代表するメンバーローレンツ・ヘルムシュミート(Lorenz Helmschmied) (floruit 1467年~1515年)コルマン・ヘルムシュミート(Kolman Helmschmied)(1471年~1532年)デジデリウス・コルマン・ヘルムシュミート(Desiderius Kolman Helmschmied)(1513年~1579年)15世紀後半のヨーロッパの有名 鎧鍛冶家アウグスブルク(Augsburg)のヘルムシュミート(Helmschmied)家インスブルック(Innsbruck)(Austria) のゾウゼンホーファー(Seusenhofers)家ミラノ(Milan)のミサリア(Missaglias)家イギリス サセックス伯の甲冑ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)第5代サセックス伯ロバート・ラドクリフ(Robert Radclyffe, 5th Earl of Sussex)(1573年~1629年)の甲冑。先に黒大使の話を書きましたが、時代は違えど、イギリスでは黒が好まれたのかな?あるいは、霧の多い国だから、目立つ為かもしれない。ナポレオンはそこに彼が居るのが判る為に帽子をわざと横向きに被ったと言われている。戦いにおいて、大将がどこにいるか臣下らから判る。と言うのも必要だったのかな?グローブ(glove)グローブの試着見本がありました。ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)手の平側はなめし皮革。グローブもそれぞれなのか? 時代による変遷か? 使用目的別なのか? 役割別なのか?手のひら側はなめしの革です。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)から細かいメイル(Mail)で繋がれている。これは蒸れ防止なのか? より細やかに動かせる為なのか? 武器と一体化したグローブもありました。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)からガラスケースの中なので反射と写り混みで見ずらいのが難ですが・・。おまけ股間用の鎧メイル(Mail)だけでなく、こんなカバーもあったようですが、写真はコレのみでした。行方不明になりがちなのかな?武具に詳しいわけではないので、こんな程度の紹介しかできませんが、とにかく写真が大量にあったので写真公開をしておこうと思ったのです。これらは見本でなく、後世のレプリカでもなく、全て実戦用に当時造られた武具だからです。しかも、今まで、いろんな美術館、博物館などで、使い古しの汚いのや、兜だけとかいうのは見てきましたが、大量に、ここまで保存が良い武具を見たのは初めてです。例えば、フランス革命で解体されたフランスには、王家の物は何一つ残っていない。革命期に略奪されたり、革命政府に売り飛ばされ(競売がおこなわれたりしている)たりと紛失しているからです。でも、オーストリ帝国の場合、同じく王政は解体されはしたが、第一次大戦後にゆるやかに解体されたし、解体以前からハプスブルグ家のコレクションは美術史美術館で一般公開されていた。フランスのように散逸する事はなく、王家のものはそのまま残ったのだと思われます。※ 美術史美術館は1891年に開館。武具もその中の一つであろうが、武具は美術史美術館ではなく、新王宮の方の美術館で公開されています。ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien) 武器と鎧のコレクション)(Collection of Arms and Armour)にて展示。※ 新王宮美術館の方は以前紹介しています。リンク ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)新王宮は、外から外観の写真を撮る人はいるかと思いますが、中に入れると知らない人は多いはず。宮殿は、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世( Franz Joseph I)(1830年~1916年)(在位1848年~1916年)の為に1869年に計画され、1881年に建設開始、1913年に完成。つまり、ほぼオーストリア帝国解体後に完成したから結局ハプスブルグ家の人々は誰も住まなかったという曰くのある宮殿になっています。なかなか時間が無いと行けないと思うので、これだけでも誰かの参考になれば幸いです。「ハプスブルグ家」関連はいろいろ書いています。関連のBack numberリンク 西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)リンク 西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント) 西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 1 ハプスブルグ家納骨堂リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 2 マリアテレジアの柩リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降リンク ハプスブルグ家の三種の神器リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)リンク ウィーンの新王宮美術館(Neue Burg Museum Wien)リンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃ポンパドール夫人らとタッグを組んだオーストリア継承戦争の事を書いています。リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)昔のなのでショートです。リンク ベルヴェデーレ宮殿 1 (プリンツ・オイゲン)リンク ベルヴェデーレ宮殿 2 (美しい眺め)リンク ベルヴェデーレ宮殿 3 (オーストリア・ギャラリーと分離派とクリムト)リンク カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 1 (大聖堂の教会史)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 2 (内陣祭壇とフリードリッヒ3世の墓所)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 3 (北側塔のテラス)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 4 (南塔)他にもあるけどあまり昔のは見てほしくないのでのせません
2023年11月10日
閲覧総数 1219
-
19

ホテル・ザッハーのザッハ・トルテ +オペラ座
オペラ座(ウィーン国立歌劇場)について書いたリンク先をラストに追加しました。Break Time (一休み)以前(11月)デーメル(DEMEL) のザッハトルテ を紹介しましたが、今回ホテル・ザッハーの写真もあるので、紹介です。夜なのでちょっと見にくいですが、ショップのザッハ・トルテも紹介です。元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)フィルハーモニカー通りにある5つ星ホテルで、ザッハ・トルテで世界的に名がしれていますが、由緒あるホテルです。1876年、所謂家具付きの高級アパートメント(maison meublée)として建設。創始者、エドゥアルト・ザッハーの死後、未亡人のアンナ・ザッハーにより、ホテルは貴族や外交官が宿泊する格式あるホテルにしたそうです。ホテルは、2005年、部屋数を増やすために上層階を増築。オペラ座(ウィーン国立歌劇場)の裏に位置しています。このあたりは、オペラ座の舞台装置の搬入の為によくトラックが止まっているそうです。道は狭く、下がれないので、正面はとれません。1階にはカフェがありますが、ザッハトルテの販売は、このホテルの中ではしていません。ショップは、ウィーン一の目抜き通りであるケルントナー通り(オペラ座とシュテファン寺院を結ぶ)にあります。歩いて20mくらいの所ですが・・・。オリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)ショップ商品以前デーメルでも紹介したように、1814年、開催されたウィーン会議の時に、そこに集まる王侯貴族たちの為に、ウィーンの菓子職人が競いあった時に作られたのでは? との諸説もあるようです。(本家のホームページには1832年)デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)も木箱です。固めのチョコレートスポンジのケーキに、固いチョコレートがコーティングされているケーキです。水分は少なく・・・だから日持ちします。ここのオリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)は中が2層に分かれ、間にアンズのジャムが薄くのばされています。(デーメルとの違い。)ウキペディアの写真をかりました。小さいサイズは丸いチーズのような小箱です。お土産に人気ですが、見た目より比重があり、重いのでスーツケースの重量制限に注意です。クリスマス限定? と思われる木箱発見。アーティスト作品ぽいですが、不明。たぶん値段も高い。おまけ写真・・・国立オペラ座(Staatsoper) (ウィーン国立歌劇場)パリ、ミラノと並ぶ3大オペラ座フランツ・ヨーゼフ1世が行った都市整備で建設。1869年、モーツァルトの「ドン・ジョバンニ」でこけら落とし。第二次世界大戦で消失し、1955年に再建。座席数1642、立ち見570。※ ウィーンの歌劇場について後年詳しく解説ブログだしました。リンク先はラストにのせてます。暗闇拡大したのでボケてますが、奥のがオペラ座。前はトラムと駅ウイーンのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)については2015年05月07日「カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)」で紹介しています。リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)またデーメル(DEMEL) のザッハトルテについては2009年11月荷⒎紹介しています。リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)リンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)オペラ座内部の紹介をしています。リンク ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日
2009年12月10日
閲覧総数 686
-
20

新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情
マリーアントワネット関連back numberのリンク先をラストにさらに追加しました。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)の作品の中から衝撃の絵を発見しました。これで全ての説明が付きました。客人は持参のオマル? の下に写真追加。写真を入れ替え、増やして編集し直しました。全面改訂です。「マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情」初期も初期に書いた、つぶやきに近い物が、毎日一番多いアクセスをいただき恐縮です。長らく避けてきましたが、写真だけでも入れ替えをと見たら、中身もとてもはずかしい内容で。 (* v v)。ハズカシイ やはり直したくて仕方無くなりました。前作では、ベルサイユ宮殿は入場料を取る上にトイレも有料と言う事を書きました。トイレ代金はトイレ管理のおばさんへのチップとして徴収されていたのですが、おばさんがチップの金額をごまかすのを防止する為に領収書を発行していたのです。それが2018年くらいに新たな無料の大きなトイレが王の前庭の地下に造られ、渋滞の大幅改善がされたようです。入り口はガブリエル翼と旧翼の両方からアクセスできると言うので、個人入場口と団体入場口の両方から入れるトイレらしい。とにかくベルサイユのトイレは評判が悪かったのです。最も、このトイレも庭だけ見学の人は対象外らしく、城への入場料を支払った人のみと言う事らしい。新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情トイレ事情の悪いフランスベルサイユ宮殿のトイレ事情マリーアントワネットのトイレシオン城のトイレ客人は持参のオマル?ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王1778年マリーアントワネット22歳の肖像画マリーアントワネットが王妃になるのは1774年。18歳で王妃にこちらの写真はウイーンの美術史美術館から持ってきました。実家に送られたマリーアントワネットの肖像画で、ルイ16世と対になっています。ベルサイユにも同じ物があるようですが、こちらは大きい作品です。本物であるのは間違いないです。トイレ事情の悪いフランスそもそも、フランスと言う国自体、公共のトイレが今現在でも非常に少ない国です。地下鉄駅にトイレは存在しないし、フランス国鉄の大きな駅でさえ、個室が僅かの有料トイレが一つある程度です。※ ルーブル美術館の駅だけ外に個室の多い有料トイレがありました。デパートもそうです。各階にトイレは無く、1階おき。男性はさらに数が少なかったと記憶しています。また、必らずと言って良いほど壊れて使用できないトイレが複数存在するのでフランスでトイレはどこも行列です。そう言えば、シャルル・ドゴール空港でも、真ん中あたりの地下に一つとそこまで行くのに大変でした。※ 一つと言う事はないでしょうが、トイレまでの距離がありすぎるし、必ず待つ事になるので時間がね。パリの街は今でこそ下水道がしっかり完備されましたが昔は汚水を窓からバケツで投げ捨てていたらしい。2階の窓から棄てる輩もいたから汚物がはねてドレスが汚れる事も・・と読んだ記憶があります。近年まで下水道の整備が遅れていたのかもしれません。私が初めてパリに行った時、街は犬のフンの悪臭だらけでした。今はフンの清掃が年中来るし、下水溝の間口が広くされ、いっきに洗い流すようにされてパリの街においては、臭い事は無くなっています。が、問題は他にも。この国はトイレが少なく、しかも有料が基本の国なので必然的にトイレでしない人が多いのです。同じフランス語圏のベルギーもそうでした。街や特に地下鉄などの地下道が臭いのです。掃除が行き届いていない事もありますが・・。これではペストも流行るよね・・と思うわけです。そんな訳でフランス旅行はトイレ・ポイントを考えながらプランを作る事をお勧めします。因みに、団体旅行でトイレ付きのバスと言うのがありますが、これもあてにできません。運転手がトイレ掃除が嫌でトイレを使用させない事が多々あるそうです。王の前庭からの王宮この地下に2018年頃、大きなトイレができたらしい。入城者は無料。下の写真のみウィキメディアから借りてきました。ベルサイユ宮殿のトイレ事情「ベルサイユ宮殿にはトイレが無かったので臭くて汚かった。」と言うのは、大方の所では当っていると思います。王や妃の場合は自室の領域に便座トイレの個室があるのを私も見た記憶があります。だから全くなかったと言うわけではないのですが、汚水を処理する下水の観点から見ると、やはり無かったと言えると思います。そもそも近年でも来客用のトイレが宮殿内に設置できなかったのは、そう言う場所が無かったと言う事を意味しているのでは無いでしょうか?ルイ14世時代には、ルイ13世の小城館とル・ボーの新城館の中庭に面した場所に「キャビネ・ドゥ・シェーズ」(椅子の間?)と呼ばれる小さな小部屋があり、シューズ・ペルセ(便座椅子)が置かれていて、ルイ14世の専用トイレだったと言われています。ルイ15世の時は寝室の隣に上げ蓋式の便器を備えた部屋があったそうです。これは城見学に行くとよくあるパターンで、私も見た記憶があります。(捜したが写真が無い)ルイ16世の時は? 「水洗式のトイレを使用していた。」などと言う説もありますが、文献がないのでわかりません。本当に水洗であるなら、下水道が無ければならない。そのような施設がどこにあったのか? どこに汚物を流したのか? と考えると不自然な気がします。ベルサイユは庭の噴水の為に遠く川から水を引き上げていました。水道の方は説明できなくは無いですが・・。ローマ水道の時に紹介したように、水洗トイレは上下水道が完備された時に初めて機能するものだから。プチトリアノン(le Petit Trianon)にある王妃の部屋の中にマリーアントワネットも使用した木製便座のトイレがあります。ガラス張りで中までのぞけませんが、水洗には見えません。横の小さな穴の方が気になります。そこから水でもそそいだのでしょうか?トイレは王妃の部屋に付随している。ベッド類も再現物のようです。また。テキスタイルもちょっと現代風でいただけない貼り方です。ついでにプチトリアノン(le Petit Trianon)のロビー吹き抜けです。ルイ15世がポンバドゥール夫人の為に建設したものの、間に合わなかった建物です。でもロココでなく、新古典様式の建物です。最初に使用したのは次の公妾(こうしょう)デュ・バリー夫人(Madame du Barry)。ルイ15世が病気で倒れるとデュ・バリー夫人は宮廷から追い出された。その後、1774年から1789年までマリー・アントワネットが使用。シオン城のトイレさて、一般のトイレですが、何百人も集まるパーティーなどにおいて、客人が使用するトイレは下水の観点からも無かったと言えます。ただ、使用人達が使用していたであろうトイレはあったはずです。写真を捜しましたが、無くてしかた無く中世のスイスの城から持ってきました。木製になっているだけで古代の石のトイレと似てますね。ただ、あちらは水洗でしたが・・。スイスのモントルー(Montreux) のレマン湖畔にあるシヨン城(Château de Chillon)の兵隊達が使用したトイレです。トイレと言った個室ではなく、煖炉もある広い部屋の一画にあり穴の下は下界です。シオン城の写真はウィキメディアから借りてきました。自分の写真は全景が入っていなかったので・・。前の湖はレマン湖です。客人は持参のオマル?基本的にトイレは椅子型の場合も、オマル型、あるいはし尿ビン型にしても一時的に受けるもので、中身はどこかに棄てなければならないものでした。また、用を足す部屋があったか? 無かったか? と言うなら、客人用には無かったようです。「274の便座椅子がある」と書いてあった本がありましたが、全くもって確証がとれません。招待を受けた紳士淑女たちは、香をたいた携帯のMy便器を持参したと言われています。でも、その中身は従者が庭に捨てていたから、ある廊下のはずれは「汚物で沈んでいた。」とまで書かれていました。一晩のパーテイーに100人来たとして、その従者などいれたら400人以上。確かに一晩で汚物まみれになりそうです。故に、ベルサイユ宮殿が汚物にまみれて汚く悪臭を放っていたのは本当なのでしょう。だから宮殿南の翼にオレンジの果樹園を置いて空気を浄化しようとした。とも言われています。フランソワ・ブーシェ(François Boucher)(1703年~1770年) 写真はウィキメディアから英語版で見つけました。1760年頃の作品。今はプライベート・コレクションとなっています。載せて良い画像か少し悩みましたが、これは当時の風俗が解る貴重な資料と思い掲載しました。何より驚くのは、これをブーシェが描いていたと言う事実。ヽ(・_・;)ノ ドッヒャー 衝撃でした。何でこんな絵を描いたのか? また描かせたのか? この女性の羞恥心は? (;^_^Aそれにしても女性の場合はこんな感じだったのですね。取ってが付いたスープ皿のような受け皿ですね。 ドレスが汚れそうです。これの中身を従者が庭に棄てに行っていたと言う事なのでしょう。住居している人の汚水処理のタンクはあったのかもしれませんが、ベルサイユにそれらを棄てる場所が公式にはなかった。また、汚水はおそらく畑にまかれるとか、遠くセーヌ川まで運ばれて棄てられていたのではないかと結論できそうです。下は、ベルサイユ宮殿内にあるゴブラン織りの衝立です。フランス王立織物工場で宮殿用に制作されたもので、とても精巧な素晴らしい物ですが・・。こうした衝立(ついたて)の物影でスカートの中にオマル入れたのですかね。それくらいの羞恥心は欲しいところです。フランドル産に比べたらたいした事ないと思ってしまう。ルイ14世は「最高の香気を匂わす国王と呼ばれていた。それは、糞便の悪臭をごまかす為に大量の香水をつけていたからだと言われています。その理由は、下絶えず下痢状態で1日14~18回もトイレに行っていたかららしい。また、間に合わないこともしばしばで、便座トイレに座ったままで会議をした事もあったとか。ルイ14世は主治医によって抜歯されていた為に歯が無かった。咀嚼(そしゃく)ができないから消化を助ける為に下剤を飲まされていたからだと伝えられている。香水が最も発達したのはこの頃なのだと言うのも納得ですね。フランス人は昔からトイレに対して、前向きな取り組みをした事がないように思えます。「取り立てて考える必要の無いどうでも良い事象 ? 」当時のエピソードを聞くと、もよおした所がどこかにかまわず、そこをトイレとしていたようです。羞恥心の生まれた18世紀からは「しないような努力と我慢の歴史」となったらしいが・・。最後にマリーアントワネットが使用していたであろう食器を紹介しておきます。今後で使用する事もなさそうなので・・。セーブル焼きの磁器?ティーカップでなくてエッグスタンドにも見えますが・・。まだ完成されていないと言うか手作り感が凄く見えますね。ドイツやイタリアに比べると磁器造りもおくれているようです。磁器の元となるカオリンはベルサイユの近郊であるセーヴルで見つかったそうです。でも当初は技術が追いつかなかったとか・・。トイレ、あるいはオマルの写真がまた見つかりましたら追加しますが、城など行っても、なかなかトイレまで修復していないので無いのが現状です。おわりマリーアントワネット関連back numberリンク マリー・アントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃back numberリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 1
2009年06月19日
閲覧総数 97820
-
21

デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)
前回に引き続きハプスブルク家の紋章(双頭の鷲)がブランドマークのデーメル。今回はデーメルのザッハトルテの紹介です。ウイーンの名物菓子、ザッハトルテには商標権が存在します。その商標権を持って製造しているのは2社のみ。今回はその事情も・・。デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 2 (ザッハトルテの商標権争い)デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)オリジナル・ザッハトルテ(Original Sacher-Torte)オリジナル・ザッハトルテとデーメルのザッハトルテの戦い実は、「ザッハトルテ」はウィーンのホテル・ザッハーの名物菓子なのです。1832年、ホテル・ザッハーの菓子職人フランツ・ザッハー(en:Franz Sacher)が、時のウイーンの宰相クレメンス・メッテルニヒ(1773年~1859年)の為に創作したチョコレートを使ったケーキだったと言われています。1814年、開催されたウィーン会議の時に、そこに集まる王侯貴族たちの為に、ウィーンの菓子職人が競いあった時に作られたのでは? との諸説もあるようですが、本家のホームページには1832年となっていました。ホテル・ザッハーの名物菓子として、スペシャルなケーキ(保存のきくケーキなのです。)として販売されていたので、そのレシピは長らく門外不出だったそうです。現在それをデーメルが持っているのは、ホテル・ザッハーの経営危機の時に、(おそらく政略結婚)嫁いだデーメルの娘からレシピが流出したと言われていますが真相は?デーメルもザッハトルテを売り出し、7年に及ぶ、商標等をめぐる裁判になったそうです。判決は、デメルのものもデーメルのザッハトルテ(Demel's Sachertorte)として売ることが認められたと言う事で、本家のオリジナル・ザッハトルテに対して、デーメル・ザッハトルテが存在するのです。そういう事ですから、ウイーンの名物菓子ではあるけれど、ザッハトルテの商標を持って販売しているのはこの2社のみなのです。デーメル・ザッハトルテ(Demel's Sacher-Torte)のテイクアウト用店内のカフェではお一人様用に作られています。周りのチョコレート・コーティングは非常に硬く、ちょっとやそっとでは崩れない頑丈さです。中のチョコケーキも硬めで水分は少ないのです。そのかわりかなりの日持ちのするケーキです。因みに、ホテル・ザッハーのオリジナルザッハトルテ(Original Sacher-Torte)は2層に分かれ、間にアンズのジャムが薄くのばされています。当時としては、かなりの画期的なケーキであった事は間違いないですね。177年も変わらず売られ続けているのですから・・・。以前はオーストリア航空のマイレージをためて「ザッハトルテ」(オリジナルの方)がもらえました。(今は無い。)注文申し込みすると、オーストリアから空輸されて「ザッハトルテ」が届いたものです・・・。それをお歳暮にしてました下は、デーメルの他のチョコレート・ケーキです。私的には、こちらのシットリタイプのモダンなチョコレート・ケーキのが好きですが、たまにザッハトルテも食べたいけど・・・。下はモンブラン、ここではMaroni Frou Frouとか・・・。デーメルの今が旬のお土産。クリスマスツリー・オーナメント・クッキー。組み立てるとロウソクも飾れる優れもの。発想が素敵。クリスマスが終わったら食べてしまうのね・・ウイーン王宮御用達菓子店のデーメルでした。尚、本家オリジナルのザッハトルテについては2015年05月07日「カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)」で紹介しています。back numberリンク デーメル(DEMEL) のザッハトルテ 1 (ウイーン王宮御用達菓子店)リンク カフェ・ザッハー・ザルツブルグ(Cafe Sacher Salzburg)リンク 元祖ザッハ・トルテのホテル・ザッハー(Hotel Sacher)
2009年11月28日
閲覧総数 626
-
22

聖ペテロの魚(St. Peter's fish)と聖ペトロ
マタイによる福音書17章「神殿税を納める」の中で、キリストがペテロにこう言います。「湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると。銀貨が1枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。」聖ペテロの魚(St. Peter's fish)と聖ペトロ聖ペテロの魚(St. Peter's fish)聖ペトロ下の魚がその魚です。聖ペテロの魚と呼ばれるセント・ピーター・フィッシュ(St. Peter's fish)です。今やガリラヤ湖の名物だそうです。ガリラヤ湖は、イスラエル7北部に位置する国内最大の湖。周囲53km、南北に21km、東西に13km。面積166平方kmの。最大深度は43m。海抜マイナス213m。「ガリラヤの海」など「海」と呼ばれることもあったが、純粋な淡水湖である。だから魚も淡水魚で、ティラピアではないか? と思われる。ティラピア(Tilapia)はスズキ目シクリッド科に属す魚だそうだ。ナイルティラピアかも ? 日本では外来生物に入るカワスズメ(モザンビークティラピア)が近種。鯛類とは全くの別種で、生息環境も異なる。※ 2019年8月「アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ」の中「ガリラヤ湖、ゲネサレト湖畔と使徒ペトロ」でガリラ湖についてもっと詳しく書いています。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ聖ペトロペテロ(シモン・ペトロ)はキリストの最初の弟子の1人、12使徒のリーダーとなる存在である。彼はもともとガリラヤ湖で弟と漁師をしていた。マタイによる福音書4章「4人の漁師を弟子にする」でキリストがペテロ兄弟に言います。「私について来なさい。人間をとる漁師にしよう。」と言われた。2人はすぐに網を捨てて従った。下はバチカンのサンピエトロ大聖堂の中にある聖ペテロの座像です。13世紀アルノルフォ・ディ・カンビオ作皆がペテロの右足をキスしたり、なでて行くので摩滅しています。バチカンのサンピエトロ寺院はペテロの亡骸の上に建てられた教会です。64年、神聖ローマ皇帝の迫害の為に殉教したキリストの弟子ペテロはバチカンの丘に葬られます。349年になって、その後にペテロの墓と聖ピエトロ聖堂が建築されました。カトリックではペテロを初代のローマ教皇とみなしています。これは「天の国の鍵」をペテロがキリストから受け取った事で、その権威を与えられ、それをローマ司教としてのローマ教皇が継承したとみなすからだそうです。上のペテロが左手に握っている2本の鍵が天国の鍵です。ペテロを表す物として、天国の2本の鍵と逆さ十字(聖ペテロ十字)が用いられます。(ペテロは逆さ磔刑で殉教した。)聖名祝日はカトリックでは6月27日、正教会では7月12日です。
2009年05月17日
閲覧総数 3520
-
23

ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠
ウイーンの王宮にある宝物館の写真を見返していて、ナポレオンの子息(ナポレオン2世)の為に造られたベビーベットが目に留まった。あまりの豪華さに写真撮影していたのだ。よくよく見るとベットにはたくさんの蜂がデザインされている。どうもナポレオンが蜂を意匠に使用していたらしい。最初は紋章における蜂について調べて見たのだが、ナポレオン関連のあちらこちらから蜂の意匠が現れるので結局ナポレオンの歴史も追ってしまった。そして気付けばナポレオンの住まいであったフォンテーヌブロー宮殿にも案の定、ナポレオンの玉座に蜂がいっぱい。いろいろ迷走したが、初心に戻って今回はナポレオンの紋章に関する所にしぼって紹介する事にしました。ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠オーストリア皇女との間に生まれたナポレオンの息子象徴としての鷲と蜜蜂蜜蜂の紋章(Emblème de l'abeille)フォンテーヌブロー宮殿ナポレオンの玉座の蜜蜂ウイーンの宝物館に展示されているナポレオン2世のベビーベット鷲はナポレオンの紋章である。オーストリア皇女との間に生まれたナポレオンの息子1810年4月ルーブル宮殿の礼拝堂でナポレオンは2度目の結婚をした。相手は敗戦国オーストリアの皇女。マリー・ルイーズ(Maria Luisa)(1791年~1847年)ナポレオンはオーストリアの敵。彼女は泣く泣くナポレオンに嫁いだそうだ。マリー19歳。すでに皇帝となっていたナポレオンは41歳。しかしナポレオンはマリーにとても優しく彼女もいつしかナポレオンが好きになったらしい。そして1811年3月。ナポレオンとの間に第一子誕生。それが将来ナポレオン2世となるナポレオン・フランソワ・シャルル・ジョゼフ・ボナパルト(Napoléon François Charles Joseph Bonaparte)(1811年~1832年)である。※ 母の実家、オーストリアではライヒシュタット公フランツ(Franz,Herzog von Reichstadt)として知られる。敵であるナポレオンの名前が使用される事はなかった。難産で危険なお産だったそうだ。一時マリーとベビーの命が天秤にかけられ、ナポレオンは迷わず妻の命を優先しろ。・・と言ったそうだが、幸い二人とも助かり、特に息子誕生にナポレオンは非常に喜んだらしい。その喜びによりナポレオン・フランソワは生まれながらにしてローマ王に即位したのである。下のベビーベットの天蓋には女神が月桂冠を授けている。ベットのレリーフにはローマ建国の神話であるオオカミとロームルス (Romulus) とレムス (Remus) が描かれていて、それだけでこのベットがナポレオン・フランソワのものだと解るのだ。さらによく見るとベットには蜂がたくさん装飾されている。そもそも今回の謎はここから始まったのである。これは何の印?下の豪華な衣装箱? にもプリントや刺繍ではなく、金属の蜂がたくさん装飾されている。ウイーンの宝物館にあったマリー・ルイーズ(Maria Luisa)(1791年~1847年)の肖像画マリーのドレスにもローブにも蜂が刺繍されている。これはブルボン王家がアイリスの紋章をたくさんプリントしているのに似ている。フランス読みでマリー・ルイーズ(Maria Luisa)としましたが、オーストリアではマリア・ルイーザ(Marie Louise)。彼女の棺を2014年「カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降」で紹介しています。リンク カプツィーナ・グルフト(Kapuzinergruft) 3 マリア・テレジア以降ちょうどその中にシシイこと、エリーザベト(Elisabet)の柩も載っているのでよかったら見てねウイーンの宝物館にあったナポレオンの肖像画ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)ナポレオンの紋章の黄金の鷲(ワシ)が胸にたくさん付いている?いや、これは1802年にナポレオンが創設したレジオンドヌール勲章(L'ordre national de la légion d'honneur)のようだ。たぶん第一帝政スタイル。レジオンドヌール勲章は現在も存在するフランスで最も名誉ある勲章。形が時代で少しずつ変わっているようなのだ。※ 勲章には1~5等までのランクがあり、北野武さんがフランスから贈られた勲章がこれである。ところでナポレオンは地中海に浮かぶコルシカ島の出身であるが、フランス貴族と同等の権利を持つそこそこ裕福な家の子弟。家に家紋があってもおかしくないが、どうもその筋からではなさそう。因みに10歳の時にパリに留学。15歳で陸軍士官学校に入学して11ヶ月で卒業。非常に優秀だったそうだ。象徴としての鷲と蜜蜂鷲は強いので古来勇気や正義、また不死の象徴となるアイテムである。神話においては空の使者、神の使者や神が鷲に変身する事もあったので、古代ローマ帝国でも国章となっていたようだし他にも多くの帝国(オーストリア、ドイツ、スペイン、ハンガリーetc)や貴族が家紋に入れ、街や教会のシンボルにもされている。また福音所記者マルコのシンボルでもある。、強い信念をアピールしたい所が使用するアイテムかも・・。よく見れば騎士のローブに蜂が描かれている。では蜂の意味は? 蜂は間違いなく蜜蜂である。なぜなら蜂が採取してくる蜜が貴重な栄養源であり神の食べ物であるから。それ故、蜜蜂としての意匠だけでなく、蜂の巣や養蜂の巣箱なども同じく紋章の中に使われています。調べて見ると蜂や巣箱を家紋にしている所が結構ありました。ローマ教皇ウルバヌス8世の紋章ローマ教皇ウルバヌス8世(Urbanus VIII)(1568年~1644年)(在位:1623年~1644年)実家であるバルベリーニ(Barberini)家の蜂が由来らしい。おそらく3匹の蜂は三位一体にひっかけていると思われる。蜜蜂は集団で社会生活をするところから活発、勤勉。労働、また社会的結束や秩序のシンボルです。勤勉や秩序は修道士達の模範です。また蜂の巣を教会にみたて、蜂は熱心に共同体に変わらぬ忠誠(活発、労働、社会的結束)をつくす信徒とも解釈されます。甘い蜜をつくり出す事から甘美と言う意味あいもあり、言葉による誘惑なども含まれ弁のたった聖アンブロシウスやクレルヴォーの聖ベルナルドゥスのアトリビュート(attribute)にもなっているそうです。※ アトリビュート(attribute)は宗教画などの中で聖人を表すための象徴的なアイテムとなるもの。蜜蜂の紋章(Emblème de l'abeille) (加筆訂正の部分)王政においては絶対君主性に関連づけられ特に女王の巣箱の支配は強い王政の象徴でもあったようです。しかしナポレオンの場合ナポレオンは蜜蜂の帰属性や社会的結束を自分の統治する帝国の理想に求めたのか? と最初は思いましたが・・。真意はナポレオンの理想でなく、ナポレオン自身の意志の表明のようでした。国民の支持により選ばれた皇帝(ナポレオン)はもとの地位にこだわりなく能力のある者を積極的に登用し、きちんとした中央集権的な国造りに着手。先人には敬意を表しつつ、しかし革命直後のような恐怖政治は否定。革命の自由平等は失わず、しかし秩序ある国造りの実現。そして国の内外にフランスの栄光を実現させると言う強い目的と意志。第一帝政、第二帝政のシンボルとして、奉仕、自己犠牲、社会への忠誠などを象徴する蜜蜂(ミツバチ)がスローガンと言うよりはむしろナポレオン自身の強い意志として使われたらしいのだ。良い統治者になる。と言う志しを蜜蜂の意匠が示していたと言う事になる。ナポレオンの開いたフランス第一帝政の国章 (ウキメディアコモンズより借りてきました。)黄金の鷲と黄金の蜜蜂の意匠ブルボン王家の紋章フルール・ド・リス(fleur-de-lis)の意匠絶対君主であったブルボン王家ではアイリスをシンプルにデザインした意匠を使用している。フルール・ド・リス(fleur-de-lis)である。493年、キリスト教への改宗したフランス、メロヴィング朝の最初の君主。クロヴィス1世が王家の紋章に最初に採用して以降キリスト教徒のフランス王を象徴するものになったとか・・。フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)門の上にあるのはナポレオンの意匠、黄金の鷲足につかんでいるのは雷(いかづち)らしい。12世にはすでに居城があったと言われている。現在にいたる宮殿を造ったのはフランソワ1世(François Ier)(1494年~1547年)の治世らしい。宮殿は何度も改築されている。特にフランス革命においては調度品が売り払われ宮殿は荒廃。ナポレオンはそんなフォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)を自分の権威の象徴として修復してここに住んだのである。ナポレオンの玉座天蓋にも蜂が無数に刺繍されている。椅子にも蜂がいっぱい。やっぱりナポレオンの蜜蜂の使いかたはブルボン家のフルール・ド・リス(fleur-de-lis)のテキスタイル用デザインをかなり意識したか、真似た物であるのは間違いなさそう。フォンテーヌブロー宮殿には他にナポレオンの執務室や寝室。マリーアントワネットの寝室はジョセフィーヌの寝室にもなっていて公開されている。古い写真になるが部屋の中は変わらないだろうから近日紹介するかも・・。..追記 2017年2月「ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式」の中、フォンテーヌブロー宮殿内の「ナポレオンの居室」や「マリーアントワネットのベッド」を紹介していすます。よかったらリンク先を見てね。リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式リンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子リンク ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Greenリンク ロゼッタ・ストーンとナポレオン
2017年01月27日
閲覧総数 14112
-
24

ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー
前回の「ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)」で紹介したようにノイシュヴァンシュタイン城は、ドイツ、オーバーバイエルンの美術品や図書などの集積所としてナチス支配下で使われていた時代があった。確かに城塞型で近辺が一望できるこの城の存在はナチスにとっても好都合な場所だったのだろう。リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)ルードビッヒ2世の理想の城はニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg)のような平城(ひらじろ)の居城ではなくどちらかと言えば中世の防衛型城塞が意識された山岳の城なので・・。そこに父の影響もあったのかもしれない。ルードビッヒ2世が青年時代に過ごした彼の父(マクシミリアン2世)が建てたホーエンシュヴァンガウ(Hohenschwangau)城も城塞型であった※ どちらも古い城跡の上に再建されている。しかし、城の内部は城塞とは遠く、どちらも当事流行のロマン主義が色濃く出た装飾がされている。マクシミリアン2世のホーエンシュヴァンガウ城は中世の騎士や英雄伝説の絵画や壁画で飾られている。共に中世を意識する所は同じであるが、ルードビッヒ2世のノイシュヴァンシュタイン城は同じ中世でも、ほぼワーグナーのオペラの内容に特化している。つまり創作性が高いのだ。当然その装飾の仕様も今までの一般的な城のインテリアとは全く違う。どこにも無いタイプなのだ。各部屋にテーマもあるが、それら装飾は例えるなら舞台装置の様相である。実際、ノイシュヴァンシュタイン城内のデザインをしたのは城郭の専門家ではなく、舞台装置画家(クリスティアーン・ヤンク)だったというのだから納得だ。※ ホーエンシュヴァンガウ城とワーグナーについては、2018年2月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)」で少し紹介。リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー城の建築で受けた地元の恩恵未完の城歌人の広間とタンホイザーとパルジファルルードビッヒ2世の寝室、トリスタンとイゾルデルードビッヒ2世の執務室 タンホイザールードビッヒ2世の個人礼拝堂 聖王ルイ9世城の建築費城部門でも、観光全般でも上位に入るのがノイシュヴァンシュタイン城である。毎年約140万人が訪れると言う。(夏期は、1日平均6000人以上の訪問者があるらしい。)それ故、見学も一応予約制になっている。だいたい40~50人くらいのグループでまとめられて移動。城内をかってに見学する事はできない。初夏のノイシュバンシュタイン城城には常時30人が勤務して管理。王が城に滞在している時はその倍の職員が居て王に対応したらしい。写真中心部分のテラスがルードビッヒ2世の寝室のテラス1869年9月5日城の礎石が置かれる。※ 岩山を8m程 爆破して低くし、給水と道路を確保した上で礎石は置かれた。※ 設計は王室建築局の監督、エドゥアルド・リーデル(Eduard Riedel)(1812年~1885年)。1869年~1873年に城門館が建築。1873年~本丸の王館に着手1883年には1,2,4,5階が仕上る。1884年春には4階の王の住居部は完成。1884年5月27日~6月8日 ルートヴィヒ2世(Ludwig II))(1845年~1886年)城に初滞在。1886年6月13日に亡くなるまでのおよそ2年間に城に滞在したのは172日間であった。※ ルードビッヒ2世(Ludwig II)(1845年8月25日~1886年6月13日)城の正面、見えるのは城門館城の建築で受けた地元の恩恵ノイシュバンシュタイン城の建設には19世紀と言う時代の割にしっかりした建設計画や労働組合が存在していたと言うのだから驚く。前回、膨大な資材が投入された事に触れたが、例えば資材を運び上げる滑車は蒸気機関のクレーンを使用。資材はさらにトロッコで各所に運ばれていた。そんな建築機器の安全性と機能の検査を行う検査協会が当事すでにあり安全の確保が計られていたと言うのだ。前に紹介した琵琶湖疏水工事の環境を考えると日本とは比べものにならない文化レベルの高さである。※ 琵琶湖疎水は1885年(明治18年)~1890年(明治23年)(第1期)ほぼ同時期に建設されている。※ 2017年6月「琵琶湖疏水 2 (蹴上インクライン)」で書いています。リンク 琵琶湖疏水 2 (蹴上インクライン)また、この時代としては革新的だったのが1870年4月「ノイシュバンシュタイン城建設に従事する職人協会」と言う社会制度ができていた事だ。1ヶ月0.70マルクの会費に国王が多額の補助金を援助し、建設従事者が病気や傷害で休んでも最長15週間の資金支払いを保証すると言うもの。工事には何百人と言う職人を必要とし、多数の商人との取引が行われている。1880年には209人の石工、左官、大工、臨時工が直接建築に従事し、運送人、農民、商人、納入業者、さらに飲食業も建築に間接的に関わって来る。この地方全体の人が城建設に関わったと言って過言ではない。つまりこの地方全体が王が亡くなって工事が中断される1886年6月まで城から受けた恩恵は非常に大きかったと言う事だ。城門門に入ってすぐに見えるのは、後方の王の居室がある本丸。本当ならこの手前に礼拝室と巨大な塔ができるはずであった。入り口正面の突出したテラス部分は、塔ができる予定だった基礎の部分。本来は下のような90mの天守閣と下には宮殿礼拝堂が建築されるはずであった。建築はルードビッヒ2世の死と共に中断され未完となってしまったが、もしこれが完成されていたなら、もう少し城はカッコ良かったかもしれない。ちょっと中途半端なのはその為なのだ。城門館の内側城の見取り図上の二つがメインの王館となる部分ルードビッヒ2世の居室は中、ブルー系の所。メインの王館となる建物が正面テラスより上が「歌人の広間」と呼ばれるホール部分。その下の階がルードビッヒ2世の居室のある階。たぶん見える窓は左がクローゼット。壁画はニーベリングの指輪四部作の3つ目、ジークフリート(Siegfried)からジークフリートの大蛇退治。部屋の装飾はワーグナーのオペラからテーマが選ばれている。城内の撮影は禁止されているので直接の写真は無いが、参考までに城で買ったテキストから写真を拝借。そもそも印刷が悪いので写りも悪いですが・・。歌人の広間普通の城であるなら、ここは舞踏会場となる広間であるが、ノイシュバンシュタイン城では歌人の広間と呼ばれている。歌人の広間とは、文字通りここが歌合戦の会場を意味している。歌人の広間とタンホイザーとパルジファル欧州では10世紀頃より吟遊詩人らによる散文詩の歌が歌われ流行している。ドイツではヴァルトブルク城の歌合戦が有名で、ワーグナーはそれに着想してオペラ、タンホイザー(Tannhäuser)を書き上げている。※ タンホイザーの正式名称はタンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦(Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)である王はどうしても歌人の間が欲しくて、この広間を中心にノイシュバンシュタイン城を建てたと言われているほどこだわった場所だ。広間はヴァルトブルグ(Wartburg)城の祝祭会場と歌人の広間を参考にしていると言うが・・。とは言え、このアラブの意匠の入った不思議な装飾はワーグナーがルードビッヒ2世に捧げたとされるオペラ「パルジファル(Parsifal)」に由来している?※ 舞台装置画家クリスティアーン・ヤンクはエドゥアルド・リーデルの設計を書き換えて王の好むスタイルに変えていた。絵画はアンフォルタス王とパルジファル白いドレスの女性が持って要るのが聖杯。女性はもしかしたら妖女クンドリーか?パルジファル(Parsifal)聖杯と聖槍とそれらを守護する騎士団が登場。アラビアの異教徒クリングゾルは魔法と妖女クンドリーを使ってアルフォンタス王を誘惑。王は聖槍を奪われたばかりか重傷を負う。王を救えるのは清らかな愚者。そこに現れた青年パルジファル(Parsifal)。でも彼は事情が飲み込めていない。二幕ではクリングゾルはパルジファルを誘惑するが失敗して聖槍をパルジファルにとられてしまう。三幕ではパルジファルが聖槍を持ってアルフォンタス王の前に進み傷を治すと聖杯の騎士に列するる事を誓う。パルジファル(Parsifal)はルードビッヒ2世に求められて書かれたらしい。第一草稿は1865年に完成して国王に贈呈するが全草稿が完成するのは1877年。それから作曲が始まり初演は1882年、バイロイト祝祭歌劇場である。聖杯伝説も乗っかったいかにもルードビッヒ2世が好みそうなストーリーである。苦悩する新王はルードビッヒ2世の事なのか?あるいは聖杯の騎士こそが王なのか?残念ながら王の存命中にこの広間が使用される事はなかったと言う。1933年~1939年までワーグナー没後50年で祝祭コンサートが開かれたのが最初らしい。ルードビッヒ2世の寝室、トリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)後期ゴシック、樫の木がふんだんに使われた木彫のゴージャスベッドの天蓋、洗面台、読書椅子など、製作はミュンヘンのペッセンバッハー・エーレングート社製。既製品ではないだろうが、家具会社に発注したもののようですね王の身長は191cm。思ったより大きいベッドである。眠りと死は同一? キリストの復活が描かれていると言うが、このベット、祭壇とか廟(びょう)にしか見えませんね トリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)を読む婦人寝室のテーマはトリスタンとイゾルデ(Tristan und Isolde)。それはケルト伝承の散文が後に欧州に広まった物語。簡単に言えば悲恋の物語である。いかにも女性が食いつきそうなお話である。それを寝室のテーマに使った王は乙女か? ※ トリスタンはアーサー王伝説の円卓の騎士に連なる騎士。でも「トリスタンとイゾルデ」は別の話。ルードビッヒ2世の執務室 タンホイザーテーマは先ほど広間で触れたタンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦(Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg)である。壁絵はJ・アイグナー(J Aigner)ヴェーヌス山のタンホイザータンホイザー(Tannhäuser)舞台は13世紀吟遊詩人タンホイザーは恋人がいるにもかかわらず、ヴェーヌス山で愛欲に溺れる。やがてその生活に飽きると、その世界は消え現実に帰還。地上ではヴァルトブルク城で歌合戦が行われる。お題は「愛の本質」。そこで恋人エリザーベトとも再開。しかしここでタンホイザーは過ちをおかす。非現実の世界で愛欲に溺れていたタンホイザーの「愛の本質」は(精神的な)純潔な愛ではなく、(肉欲的な)快楽の向こうにある愛。皆の非難を受け、法王に許しを請う為にローマに巡礼する事になった。が、結局許してもらえず自暴自棄になったタンホイザーは再びヴェーヌス山に逃げようとしていた。一方、タンホイザーを想う恋人エリザーベトは自分の命を差し出して彼の贖罪を願っていた。エリザーベトの葬列を見て全てを理解したタンホイザーは狂気から覚めるが彼が真に贖罪されたと同時に彼も息絶える。あらすじはこんな所であるが、これをどう演出するかでオペラの内容も面白さも大きく変わる。ダンス音楽を奏でるタンホイザールードビッヒ2世の個人礼拝堂 聖王ルイ9世ルイ9世で飾ったこの祭壇はミュンヘンのJ・ホフマン設計。ルイ(Louis)は、ドイツ語でルードビッヒ(Ludwig)。ルードビッヒ2世の名は聖人となったフランス王、ルイ9世からもらっている。※ ルイ9世(Louis IX)(1214年~1270年)※ 聖王ルイ9世については2017年2月に以下書いています。「フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)」「フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)」リンク フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)公開されている部屋はまだあるが、実際写真は撮影できないので紹介はこんなところで・・。春のノイシュバンシュタイン城ワーグナー(Wagner)に捧げげたとも思える城ではあるが、この城が寝泊まりできるようになる1年前(1883年)にワーグナーは亡くなっている。※ ヴイルヘルム・リヒャルト・ワーグナー(Wilhelm Richard Wagner)(1813年~1883年)城の建築費ところで城の建築費であるが、王は国税を直接使ったわけではない。王の私財と王室費(国家君主の給料)から城の建設費を支出している。とは言え、その資金だけでは十分ではなく、ルードビッヒ2世は多額の借金をしてまかなっていた。※ 官僚が度々王に支出削減を進言していたのはこの借金の事らしい。ヴィッテルスバッハ家の古文書による王室会計の帳簿によれば、1886年の建築終了までに建築に要した費用は6,180,047金マルクだとか。(現在のお金で200億くらいらしい。)しかし、王の借金は、王の死後に家族から返済されているそうだ。だから王の贅沢で国を破綻させたと言うのは誤りらしい。若き王は政治に絶望し、人に裏切られ、個人攻撃され、すっかり人間嫌悪に陥って行ったようだ。なぜ城を造ったのか? と言う答えは明確になされていないが、王侯なら、城の一つや二つ造るのは自然な事だったらしい。そもそもドイツやオーストリア圏では冬の住まい(宮殿)と夏の住まい(宮殿)は別である。それぞれに立派な宮殿を持っているのが常識。ただ、ルードビッヒ2世が王位について、1866年、内戦が起き、バイエルンはボロ負け。バイエルンの被害はとても大きいものだった。その上、プロイセンに主権放棄と3000万グルデン(5400万金マルク)と言う賠償金を払わなければならなかった事なども国庫を苦しいものにしていたのだろう。王の造った城の中でもこのノイシュバンシュタイン城はまさしく彼が夢の中に逃避するのにピッタリの城であったのは間違いない。が、せっかく造った城なのに172日間しかいられなかったなんて気の毒過ぎもっと居て、城を完成したかったろうに・・。そう考えると、何だか今も王の魂はこの城にありそうな気がしてきたゾ さて、これでノイシュバンシュタイン城おわりますが、ルードビッヒ2世に関するバックナンバーがこれで一応完成しました。2018年02月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)」2018年03月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 2 ノイシュヴァンシュタイン城 1 冬」2018年03月「ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザー」2015年07月「ルードビッヒ2世(Ludwig II)の墓所 (聖ミヒャエル教会)」リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 1 リンダーホフ城(Schloss Linderhof)リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 2 ノイシュヴァンシュタイン城 1 冬リンク ルートヴィヒ2世(Ludwig II)の城 3 ノイシュヴァンシュタイン城 2 タンホイザーリンク ルードビッヒ2世(Ludwig II)の墓所 (聖ミヒャエル教会)ルードビッヒ2世が生まれた離宮と彼の乗り物2015年08月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 1 (宮殿と庭)」2015年08月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 2 (美人画ギャラリー)」2015年09月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 4 (馬車博物館 馬車)」2015年09月「ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 5 (馬車博物館 馬ソリ)」リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 1 (宮殿と庭)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 2 (美人画ギャラリー)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 4 (馬車博物館 馬車)リンク ニンフェンブルク宮殿(Schloss Nymphenburg) 5 (馬車博物館 馬ソリ)
2018年03月29日
閲覧総数 4957
-
25

新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)
写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました摂政フィリップ2世の所追記しました。写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。大陽王ルイ14世は1715年9月1日77才の誕生日まで後4日を残して亡くなった。壊疽(えそ)だったと伝えられているのでおそらく持病であった糖尿病によるものと思われる。※ルイ14世(Louis XIV)(1638年~1715年) (在位:1643年5月~1715年9月)ルイ14世の長い治世は(人口5/6が農民)度重なる重税と不況、凶作や疫病が絶えず民衆の生活を圧迫。「偉大なる世紀」は農民側から見れば危機と悲惨な時代でしかなかった。それ故、王が亡くなった時、民衆は神に感謝して歌い、踊り、過ぎる葬列をののしったとも伝えられる。ヴォルテールは評価したらしいが、後の歴史家達の評価は低い。戦争を好んだ事もあるが、当然ベルサイユ宮殿の莫大な建築費による浪費が大きい・・。また、ルイ14世は宮廷儀礼をたくさん造り複雑化させた。宮殿での礼拝のみならず起床着替え、飲食までことごとく儀式化。それら儀礼を回りの者に課す事により彼らの立ち居振る舞いをがんじがらめに縛ったのである。儀式ずくめの国王の宮廷生活をルイ14世自身が造りあげ、俳優のようにそれらを死の直前まで演じたらしい。 今回「メルキュールの間」を改め、「王のアパルトマン」としてそれら儀礼の部屋を一括紹介してしまいます。かつては写真4枚程度までしか載せられませんでしたが今回はその5倍以上のせました。 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)寝御の間閣議の間摂政フィリップ2世アポローンの間メルクリウスの間フルーリー枢機卿マルスの間ディアーナの間ヴィーナスの間少年王、ルイ15世の肖像 ウイキメディアから借りてきました。1723年、アレクシス・シモンベル作。ルイ15世13歳ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)1722年10月、ルイ15世はランス大聖堂で成聖式を終えた。これにより形式的には摂政政治が終わった。それにしても美少年です。彼は先王、ルイ14世のひ孫。父が天然痘で急死し、わずか5歳で即位している。ところで、亡くなる直前ルイ14世はひ孫を呼び出しこう諭したと言う。「私は戦争を大変好んだが、あなたは隣国と平和を保つ事を心がけなさい。人民の苦しみをできるだけ軽減するように。もはや私がしたような浪費はできないのだ。」火の車状態にしたのは誰のせいだ? 何をか言わんや・・である。また位置の確認で宮殿の写真です。ピンクの囲ったところが王の寝台がある所です。寝御の間 (No18)全体写真の撮影が難しいので。上はウィキメディアから借りた写真です。王の正式な盛儀寝台現在の寝所は鏡のギャラリーが造られてからなので1701年からここに存在する。上部の金箔の飾り物はクストゥの作品で、「王の眠りを見守るフランス」とタイトルされている。王は、医師と外科医により、朝の健康チェックを終えるまでこのカーテンは開かなかった。次に理髪師とかつら師が、髪を整え終えた時、初めてベッドから降りたと言う。それは王が小柄な事。また晩年の1648年には病気により毛髪の大部分を失っていたのでカツラをかぶっていたからだ。加えて言うと、小柄な王はハイヒールを好んだと言う。カツラ同様にかさ上げして身長を高く見せたかったらしい。また王に着替えのシャツを渡せる人は、入室順位一位の王族系の一番偉い人(皇太子)であり、皇太子がその場にいなければ、次の位の王族、というように、宮廷儀礼が、権力分布の象徴的な意味を持っていたと言う。先にふれた宮廷儀礼では、王の起床、就床に諸侯は参列せねばならず、最盛期で100人以上が並んだ。これはルイ14世が創始したが、ルイ15世もルイ16世もこの儀式を遵守したと言う。寝御の間の装飾の修復は1980年完成。夏の内装となっている。絢爛たる錦織が再現され、壁、扉、寝台のカーテンなどに使用されている。金糸が強くて撮影がちょっとぼやけ感があるのが難ですが・・。リュエル(ruelle)世話係やごく親しい者だけが入る事が許されたベッド脇のスペース閣議の間 (No19)寝御の間に隣接して閣議の間がある。ルイ14世はこの部屋を絵画と珍品の蒐集に使用していたそうだ。ルイ15世は居室用に改造。金箔青銅の振り子時計はルイ15世の為に1754年に造られた。シンメトリーに置かれたトミール青銅像をのせた2点のセーブル焼き。摂政フィリップ2世1715年、ルイ15世がブルボン朝第4代の王となったのは僅か5才の時。※ ルイ15世(Louis XV)(1710年~1774年) (在位:1715年9月~1774年5月)当然摂政がついた。それがルイ14世の甥オルレアン公フィリップ2世である。※ オルレアン公フィリップ2世(Philippe II)(1674年~1723年)摂政による政治(摂政時代)は9年。(1715年~1723年)その摂政の間、王の居城はベルサイユを離れ、パリのパレ・ロワイヤルに移っている。ルイ14世が亡くなり、自分の時代を感じたオルレアン公フィリップ2世は徴税を減らしたり貴族による集団政治を企画したり、25000人もの兵士を解雇。また高リスクの政策を認めて失敗。政治にも経済にも疎い人物であった。傍目(はため)には自由で、世俗的、享楽的、遊技的な、摂政時代が展開。141カラットのダイヤモンドをフランスの王冠につけるために購入したりしているが、ルイ14世の言葉通り、もはやフランス王家は公事にも私事にも破産状態の危機を加速させていた。ソルボンヌ大学の聴講を無料とし、王立図書館を公に開放。教育を奨励するなど評価点もある。自身はパレ・ロワイヤルでサロンを開き、絵画の膨大なコレクション(オルレアン・コレクション)有し且つ芸術を奨励していたようだが、それらコレクションはフランス革命後に多くがロンドンで競売にかけられたようだ。追記彼の政治評価は分かれるが、結果的に彼はフランス革命の大きな要因を造る大失態をした。1720年財務総監にスコットランドの経済学者で銀行家のジョン・ローを呼んだ。ジョン・ローの革新的経済政策は大失敗し、パリの株価が暴落する一大事件をおこしたのだ。リーマン・ショックならぬミシシッピー・ショックである。ジョン・ローはすぐに退任どころか暮れには国外逃亡している。アポローンの間戦争の間の隣である。こちら正殿は1673年~1682年.の間ルイ14世の住居であった。1682年、王は現在の寝所に移るので、以降諸室は宮廷レセプションに使用される。これから紹介する正殿の名前は全て天井に描かれた絵のモチーフに由来している。当然、この「アポローンの間」の名前も天空翔るアポローン(Apollōn)に由来する。アポローンは朝、東の宮殿で目覚め、黄金に輝く馬の引く大陽の戦車を御して天空を駆け西の地平に没するのが日課。大陽王であるルイ14世は、当然アポローンのイメージに重ねられる。この部屋は大陽神に捧げられた部屋であると同時に、大陽王ルイ14世はこの部屋で使節団と謁見。そこに意味があった。それ故、当時はここに銀の玉座が置かれていたと言う。天井画はル・ブランの門下シャルル・ドゥ・ラフォスの作品。四季を従えた早駆け馬車の上のアポローン。その下にいる婦人は「フランス」と、「王の偉大」を象徴した擬人である。タペストリーの前にはルイ15世様式の椅子。閣議の間の椅子のようです。ベルサイユ宮殿に納めている家具屋さんを知っているが、座椅子のクッションにはワラの他に馬の毛が使われている。ルイ16世、マリーアントワネットと子供達の肖像画が飾られている。もっとも、部屋の家具調度、絵画も度々変えられているようだ。メルクリウスの間1678年に開始された鏡の間の造営にあたり、王のと王妃のアパルトマンからそれぞれ二つの広間と新城館の角部屋が削られた。それによりアポローンの間にあった寝所(国王の盛儀寝台)は、今度はメルクリウスの間に移動。天井は全てジャン・パティスト・ドゥ・シャンバーニュの作品。中央の主題は「明の明星(みょうじょう)に先導され芸術と、学術に伴われ、二羽の雄鶏(おんどり)の引く戦車の上にいるメルクリウス」メルクリウスの間で、ルイ14世が崩御した時に遺体が安置されていた寝台らしい。もとは銀の境柵の奥にあったらしい。調度品も銀製であったが、1689年に熔解された。確か、王妃の間の銀の調度品も熔解されたと聞いた。財政難の為だったと思われる。この寝台についての説明が無いが、ゴブラン織りのカバーだと思う。しかし、意外にチープで驚いた。ゴブラン織りはもともとベルギーからぶんどった技術である。技術的には当時のベルギーの足下にも及んでいない気がする。土産物にしか見え無い。以前ベルギーのタペストリーを紹介した時にフランスのゴブラン政策にもふれた。ルイ14世の財務総監のジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert)(1619年~1683年)によってゴブラン織りは国策となり、ベルギーの市場を奪ったのに・・だ。リンク サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)1730年、イアサント・リゴー作 ルイ15世の肖像 ルイ15世20歳。より美青年になっています。フルーリー枢機卿1723年、フィリップ2世は12月にヴェルサイユ宮殿で突然逝去。14歳のルイ15世の親政が始まる。落ちたフランスであったが、優れた政治家であるフルーリー枢機卿の登場(執政)によりフランスは持ち直しを計る。元々フルーリー(Fleury)枢機卿 (1653年~1743年)は当初イエズス会系の聖職者としてルイ14世の妃に仕えていた。ルイ14世は幼いルイ15世の教育者に彼を任命し、フルーリーはルイ15世から全幅の信頼を受けていた彼は1726年から死去する1743年まで若いルイ15世の宰相を務め結果的に政治家になるが、アカデミー・フランセーズの一員でもあった。枢機卿任命 1726年9月11日彼の宰相時代(実際は宰相にはなっていない)、ルイ15世の治世下で最も平和で安定? ルイ14世期の戦争による人的物質的損失からの「回復」の時代(gouvernement "réparateur")となる。彼は宮廷で常に控え目であったと言う。その人柄は肖像画からもうかがえるが、何より彼を紹介するのは、逼迫した財政からフランスを救ったのが彼の経済政策なのである。フルーリー枢機卿は大蔵郷と連携して1726年に貨幣を安定化させ、1736年には収支の均衡に成功。国立土木学校が創立され、土木事業が進められて、フランス各地に近代的な道路が舗装。また1738年にはサン・カンタン運河を開通させてオワーズ川とソンム川をつなぎ、後にスヘルデ川とネーデルラントにまで拡張。海上交通も急成長して、フランスの貿易額は1716年から1748年までの間に8000万リーブルから3億800万リーブルに増加したと言う。マルスの間最初は衛士の間として造られたので天井には戦いの題材が使用されている。マルスは軍神である。続いて舞踏会や賭博場として利用されていた。ルイ15世と妃マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)(1703年~1768年)の肖像画ディアーナの間ガブリエル・ブランシャール作の天井画はアポローンと双子のディアーナを現している。ジャン・ロレンツォ・ベル二ーニ(Gian Lorenzo Bernini)(1598年~1680年) ルイ14世の胸像 イタリアの彫刻家であり、建築家。画家でもあるバロック芸術の巨匠。ルーヴル宮殿の改築計画では設計案を出している。ローマでは、サン・ピエトロ広場の設計にたずさわり、完成後1668年、ルイ14世に招かれパリに来た時、大理石の彫刻は彫られた。1685年、この部屋に彫像を置かせたのは王自身らしい。シャルル・ド・ラフォス作「イーピゲネイアの犠牲」まさに犠牲に捧げられようとするイーピゲネイアをデイアーナが連れ去ろうとする図。※ シャルル・ド・ラ・フォッス(Charles de La Fosse)(1636年~~1716年)シャルル・ルブランの弟子。ヴィーナスの間ルネ・アントワンヌ・ウアス作 戦車に乗ったヴィーナスが三美神から花冠を授けられている図。ヴィーナスの間と名がついていますが、天井画の全てはルイ14世治政下の出来事をオリンポスの神々に例えた寓意画となっている。ジャン・ヴァラン作ローマの皇帝に扮した青年王ルイ14世の彫像左手に持っているのはメドゥーサの付いたアテナイ女神の楯。正殿の夜会の時には軽食が用意される部屋であったらしい。ルイ14世の時代にあった大階段がルイ15世の時代にとり壊されたが、この部屋は大階段に隣接する部屋であった。大階段は内外からの使者らに王宮の素晴らしさを見せる為の素晴らしい物であったらしい。なぜ取り壊されたのか? つづく ベルサイユ宮殿 9 の前にベルサイユ宮殿番外、リアルタイムで載せています。こちら先にお願いします。リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とロココの意匠Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間)リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン) 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃
2009年06月14日
閲覧総数 1592
-
26

ボツワナの動物 3 ( ケープハゲワシ)
ある意味Break Timeです。ゾウの写真をPIC UPしていたら、あまりに紹介したい写真の量が多すぎて絞れません。ゾウは生態も紹介したいので、何部作かになると思います。で、編集中の為、今回は哺乳類ではなく鳥で行きたいと思います。ジャングルに欠かせない鳥と言えば・・・ハゲタカですハゲタカは、サバンナの掃除屋とも呼ばれている嫌われ者?・・・・な鳥です。でも、考えようによっては環境にやさしい鳥なのかも・・。所謂「エコ・鳥」か?ボツワナ共和国チョベ国立公園(Chobe Nationzl Park)とアフリカの動物ケープ・ハゲワシ(Cape griffon)シブリー・アールキスト鳥類分類鳥綱 Aves コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ亜目 Ciconii ハヤブサ下目 Falconides タカ小目 Accipitrida タカ科 Accipitridae タカ亜科 Accipitrinae シロエリハゲワシ属 Cape Griffon Vulture Gyps ケープハゲワシ種 Cape Griffon G. coprotheres分布 ジンバブエ南部、スワジランド、ナミビアの一部、ボツワナ南東部、南アフリカ共和国、モザンビーク南西部のサバンナやステップなどに生息。ケープハゲワシは、他のハゲワシより、案外カワイイ顔です。全長100~120cm。翼開張260cm。体重7~11kg。食性食性が腐肉食と言う事で、大型動物の死骸を食します。彼らはは生態的上位の者が摂食中の死体を狙い、隙を見て横取りしたり、残り物を得たりする習性があります。スカベンジャー・腐肉食動物(scavenger)動物の死体(動物遺体)を主に食する性質を持つ動物を腐肉食動物or屍肉食動物と言うそうです。環境中にある死体を探し当てて食物とする彼らは、ある意味生態系の食物連鎖に重要な役割をしているとてらえる事も出来ます。屍肉食いの代表のように考えられ代名詞化までしているハイエナは、実は自分で狩りをする事も多く、むしろ獲物を奪われる側なのだそうです。その獲物を横取りしたりするのがジャッカルやハゲワシのようです。肉は確かに腐りかけが(熟成した方が)美味しいのは確かです。案外グルメなのかな?高い木の上から360°獲物を探しているようです。不思議と枯れ木に止まっているような・・・よく見えるからか?倒れたら、死んだかと思われて、食われそうで怖い気がしますが・・・・。1回に1個の卵を産み、雌雄交代で抱卵。営巣場所が限られるため同じ営巣場所が数世代に渡って用いられることもあり、数百ペアからなる大規模な集団繁殖地(コロニー)を形成する事もあるのだそうです。 肉食動物の減少や家畜の死骸処分(焼却や埋葬)により獲物が減少。また、、薬用の捕獲、交通事故、送電線による感電死、人間の侵入による繁殖地の減少で生息数は減少しているようです。
2009年11月16日
閲覧総数 587
-
27

ツタンカーメン王の黄金のマスクと棺
Break Time (一休み?) じゃないな・・。私はだれでしょう? 「後ろの正面だーれだ? 」Aエジプト、カイロの考古学博物館所蔵Bツタンカーメン王 (Tutankhamun) トゥトアンクアメン(Tut-ankh-amen)古代エジプト第18王朝のファラオ(BC1333~BC1324頃)です。そして、もちろんこれはツタンカーメン王のミイラが着けていた黄金のマスクです。Aは後ろ側ですが、表だけでなくちゃんと後ろもあり、かぶるタイプのマスクですね。手抜かり無しのお金のかかったマスクです。ルクソールのナイル川西岸にある王家の谷にあるツタンカーメン王の墓は1922年11月26日考古学者ハワード・カーターが、(英のカーナヴィン卿がスポンサー)発見、発掘しました。ほとんど盗掘されていない王墓で、副葬品も王のミイラにかぶせられていた黄金のマスクもほぼ完全な形で見つかりました。ミイラと一番外側の人型棺と石棺はこの王家の谷で展示され、黄金のマスク他の副葬品はカイロの考古学博物館に展示されています。(考古学博物館の目玉となっていますが、これが100年前だったら絶対エジプトにはなかったと思います・・。)2005年にCTスキャン撮影によってミイラ調査がされ、死亡推定年齢が19歳、身長165cmで華奢な体格(当時の平均らしい)と判りましたが、事故死説か他殺説かの論争の決着はつかなかったそうです。保存状態はきわめて悪いと言う事で、プレクシグラス製ケース内で保存されています。下はカイロ考古学博物館にある第3人型棺です。墓は通路と四つの部屋からなり、王のミイラは玄室いっぱいに置かれた四重の木製金張りの逗子と珪岩製の石棺、三重の人型棺におさめられ、黄金のマスクを着けた状態で発見されたそうです。下がカイロ考古学博物館にある逗子の一つ。下がエジプト、ルクソールの王家の谷のツタンカーメン王墓の入り口です。王家の谷メイン・ビューです。ここは。新王国時代の王達の墓所です。王家のものがたくさん見つかっていますが、貴族や王族の墓もたくさんあります。18王朝から20王朝までのほとんどの王がここだそうです。今日は出かけていたので、Break Timeで短くと思ったらやはり長くなってしまいました。
2009年05月18日
閲覧総数 2105
-
28

古代ローマの下水道と水洗トイレ
写真など入れ替え改定しました皆さんが古代ローマの水道の話を忘れてしまう前にどうしても下水道に触れておきたいです。古代ローマの下水道と水洗トイレ古代ローマの下水道工事エフェソスの公共トイレ(水洗式)水洗トイレの起源古代ローマの下水道工事BC753年に初代ローマ王ロムルスが現イタリア、ローマのテレヴェ川域の七つの丘の上に街を築いた時、丘に囲まれた盆地は(後のフォロ・ロマーノ)排水性の悪い沼地でした。当時、人は丘の上に住み、丘の下は死者を葬る以外使えない土地。丘の上の居住が手狭になると、人々は沼地に降りて市場や集会所としてそこを使うようになる。そこで、この沼地の排水工事が必要になったようです。工事をしたのは、エトルリア出身の第5代王タルクィニウス・プリスクス(在位BC615年~BC579年)。異邦人にもかかわらず市民権を得、先王の死後立候補して王になった異色の王です。彼は、平和な時に兵士を使って王の故郷エトルリアから導入した技術で水道を建設したり下水工事をしたようです。湿地であった土地に水はけ用の水路を造り、集まった水を川に流す為の大下水溝クロアーカ・マクシマ(掘割式)を完成させ。(BC575年頃)排水機構を整備します。この排水溝はBC2世紀頃まで露天でしたがローマの富と力が増大すると、下水溝は石造りのアーチ(ヴォールト)で覆われBC33年クロアーカ・マクシマはリメイクされました。驚くべき事にクロアーカ・マクシマは2500年以上たった今でも立派に排水溝として使われているようです。パラティーノ橋近くのテヴェレ川に石造りアーチの直径4メートルくらいの排水溝が出ているのがそれらしいです。※ 一部、紅山雪夫さんの著を参考にさせてもらいました。下水に関しての詳しい資料が拾えないので、判っている事から推察すると、古代に栄えていたエトルリアから上下水道は伝わり、古代ローマではほぼ同時に上下水道が完備されたのではないかと考えられます。エフェソスの公共トイレ(水洗式)下は下水道あっての古代の水洗トイレです。写真は前に紹介したトルコのエフェソス遺跡(古代ローマ水道 4)からです。エフェソスの最初の起源はBC10世紀頃イオニア人の入植により始まったとされますが、ローマの属州時代がこの都の最盛期です。下のトイレはローマ時代のものかギリシャ時代からあったのかはちょっと解りませんが、見た所、ギリシャの古代遺跡で見たトイレと全く同じタイプだと思います。奥に見えるのが図書館です。公共のトイレは図書館の近くにあったのです。見てわかるように座るタイプです。便座前に貯水槽があり、そこに海綿が置かれ、それで拭いた? とか掃除した? とか?ガイドの説明がありましたが・・。ここはかなり広い(30畳以上?)スクエアになっていて。回りをぐるりとトイレが並んでいます。数えた人の話では40以上席があったとか・・。一枚石版に3人分。たいした道具も無い時代によくこんなに綺麗にできたものです。床に足を置いてへこんだ跡が見えるのがリアルです。下は水が常に流れる水洗式で、汚水は下水道で川まで運ばれたようです。水洗トイレの起源水洗トイレはローマが始まりではありません。今から4000年以上前のメソポタミアのシュメールのエシュヌンナ遺跡からアッカド王朝時代(BC2200年頃)の宮殿に残る世界最古のトイレが発見されているそうです。煉瓦で椅子形に積み上げた腰掛け式の水洗式トイレで、廃水は壁に沿って造られた地下管に流れ込んでいた。管は地下に掘って埋められ、その上にアーチの蓋が掛けられた。その中は上部に通路があって掃除のために歩けるようになっていたらしい。同じくオリエントではBC2100年頃、一般住宅にも同様のトイレがあったようです。下を水が流れ、汚水は焼き物で造られた配水管を通って下水道からティグリス川の支流へと流れる水洗式トイレであったとされています。(ウキペディアより)また地中海に浮かぶ島、クレタ島でもBC2000年頃から発祥したクレタの遺跡からも水洗トイレは見つかっているそうです。(こちらは木製の便座)近年まで水洗トイレを知らなかった日本人からしたら驚きのトイレ史ですね。水洗トイレの発祥元がどこだったのか? たまたま同じ原理にたどり着いたのか? まだ謎です。ところで、ローマの水洗トイレはギリシャ由来なのは間違いありません。なぜならローマの下水道及びこうしたトイレの文化はギリシャの文化を吸収したエトルリア人からもたらされたものだからです。
2009年06月05日
閲覧総数 8648
-
29

イタリア名門陶器 リチャード・ジノリ
代々使える食器シリーズ 1 (リチャード・ジノリ)イタリアの高級陶磁器の歴史は16世紀、メディチ家のアート・アカデミーがポルチェラーナ(白磁)の制作を始めたのが最初で、続いてフィレンツェの名門、トスカーナ大公のカルロ・ジノリ侯爵がドイツのマイセン窯に対抗して自領に窯を開いた(1735年)といわれています。侯爵は自ら原料を探し、生成や発色まで磁器の研究を行い、イタリア初の白磁を完成させたそうです。東洋からもたらされた白磁器は西洋ではあこがれの高級品でした。各国がこぞって製造開発に乗り出しましたが、マイセン窯やウィーン窯には遅れていました。1896年ミラノの陶器会社のジュリオ・リチャードと合併し、リチャード・ジノリ(Richard Ginori)は誕生します。開窯当初はマイセンのような豪華で精緻な芸術作品に力が注がれていましたが、 現在は中国磁器のマテリアルとドイツ製陶のテクニツクを取り入れイタリア的な絵付けの仕上げが特徴です。1956年にはさらにイタリアの陶磁器会社と合併して、イタリア最大の陶磁器メーカーとなっています。私が取り上げたのは、デザインが制作されてから一貫して継承されるので、壊れても買い足しや、修復がきく陶器だからです。これはジノリだけに限らず欧州に古くからある陶磁器会社の特徴でもあります。(日本のようにすぐにデザインを変えてしまわれると、揃っていた器がちぐはぐになり、みっともないですが・・)コーヒーカップのお皿(ソーサー)が一枚割れても買い換えができるようになっています。また、最初から全てそろえなくても買い足して行く事ができます。だから先祖代々同じ食器を使えるようになっているわけです。そんな欧州陶磁器の合理性は伝統を守る事につながります。とても大事な事だと思います。以前友人の結婚の時にフルセットの食器を注文し、私がティーカップセットを負担、残りを彼らの友人や従兄弟たちがそれぞれ負担して祝いの品に替えた事があります。(欧州ではそういった風習があるそうです。)彼らは将来娘に継がせたいと言って喜んでくれました。一人で高価なお祝いは無理ですが、何人かで分ければ財産となるような素敵なプレゼントとしても可能です。1758~1791年の二代目ロレンッオの時代には日本でもお馴染みの「イタリアン・フルー ツ」と「アンティックローズ」が誕生します。下の写真がイタリアン・フルーツのコーヒーポット゜とクリーマーとシュガーポット゜。波形皿はリチャードジノリの定番。「イタリアンフルーツ」は、1760年頃、ある貴族がトスカーナに持っていた別荘用のテーブルセットとしてデザインされたそうです。白地に散らされた花々とフルーツは、ボッティチェリの名作「春」のような春風に乗る花とフルーツです。アルカディア(理想郷)をイメージしたデザインなのでしょう。250年前のデザインなのにすがすがしく新鮮です。下は、ベッキオ・フルーツです。割と初期に制作されたベッキオ・ビヤンコ (白磁にバロック彫刻の浮き彫り)とイタリアンフルーツが合体したものです。イタリアン・フルーツより薄手で、金彩がほどこされています。他に美しいグリーンと金彩の縁取りに遺跡から発掘されたポッドがワンポイントでデザインされているベズビオは、ポンペイの遺跡が発掘された事を記念して誕生したモデルです。200年以上前のデザインなのに今見てもとてもモダンなものです。(納戸にあると思うが・・)デパートにあるかな? とにかく、長く続いているデザインは飽きの来ない良い物です。陶器は簡単に朽ちる事はないので、末永く大切にできるものを選び、惜しまず、毎日使う事が大事なのだと思います。下は私のリチャード・ジノリのコレクションの一部です。一番のお気に入りの天使たちです。高さ21センチくらいで、これに彩色したものもあるようです。天使コレクションのきっかけになりました。小ぶりの天使たちです。これもフィギュアに入りますかね・・。キャンドル立てです。少し彫りが浅いのが難ですが・・。キャンドル立ては実際に使わないのでもっぱら飾り用です。そのうちにマイセンとロイヤル・コペンハーゲンもやりますね。
2009年05月06日
閲覧総数 1118
-
30

ウイーンの高級食材店 ユリウス・マインル(Julius Meinl)
加筆しました シュテファン寺院のすぐ近くグラーベン(Graben)通りはブランドショップが立ち並ぶ高級品通りです。そのグラーベン通りがコールマルクト(Kohlemarkt)通りに突き当たった所に今回紹介するウイーン老舗高級食材店があります。そもそもはホテルの部屋で食べる美味しいフルーツやスイーツを探しに入ったのですが、実はコーヒーの焙煎で世界的に有名なお店だったそうですついでに店内にあるレストランも、オーストリアの中でもトップ5に入る有名店だったそうで、たまたま食事もしてきたので紹介します。ウイーンの高級食材店 ユリウス・マインル(Julius Meinl)ユリウス・マインル・アム・グラーベン(Julius Meinl Am Graben)Restaurant Julius Meinl Am Grabenユリウス・マインル(Julius Meinl)の創業は1862年に遡る。最初はスパイス店として店を開きスパイスの他に紅茶やココア、コーヒー豆、砂糖などを販売。その後息子のユリウス・マインル2世(Julius Meinl II)は、1877年にコーヒー豆を美味しくローストする技法を編み出したそうだ。そして、ユリウス・マインル(Julius Meinl)は世界初、コーヒー豆を焙煎して売り出す店となった。コーヒーのパイオニアであるユリウス・マインルは世界中から最高のコーヒーの生豆を入手する事が可能らしい。そして美味しい豆の焙煎技術。今でもユリウス・マインル(Julius Meinl)と言えば美味しいコーヒー・・と絶賛される理由はそこにあるのでしょう。入り口とその上のレストランの外壁が修復中でちょっとガッカリ入り口左には喫茶が併設。軽食もとれるようです。(前がコールマルクト(Kohlemarkt)通り)因みにコールマルクト通りの名は石炭市場の意だそうです。店内はさしずめ紀伊國屋と言った感じ。下は商標となっているマインル・ムーア(the Meinl Mohr)少年の人形。1924年にグラフィックデザイナーのJoseph Binderが手がけたらしい。1階は生鮮野菜にフルーツ、牛乳ヨーグルトやワインショップの他にチョコレートなどお茶や雑貨一般が置かれている。1階は単に高級スーパーと言った感じ。2階は主に高級デリカテッセンに紅茶やケーキやパン、生ハムやソーセージ、オリーブやピクルスなどを扱う専門店が入っている。ユリウス・マインル(Julius Meinl)が成功したのはコーヒーの焙煎だけではなかった。もともと食材店である。ユリウス・マインル2世は第一次世界大戦中に自社開発のビスケットを陸軍省に独占納入して成功。1913年にはオーストリア・ハンガリー帝国だけでなく、コーヒーの輸入と焙煎で世界最大手の会社に成長。ところで2代目ユリウス・マインル2世(Julius Meinl II)(Julius Meinl II)(1869年~1944年)は日本人の女優でオペラ歌手の田中路子と1931年頃に結婚し10年ほど暮らしている。2階にはMICHIKOの名を冠した紅茶が売られていた。年の差40歳。ユリウス・マインル2世は時の財政界の重鎮であり、財力もある。彼女のヨーロッパ・デビューを支えたが、彼女は恋多き女だったようだ。ハムやソーセージの種類はハンパないつい食べたくなり生ハムもスライスしてもらった。ここで買ったチェリーは一粒がこの上なく大きい。そしてケーキやパン、トマト、オリーブ、チーズも購入。今までいろいろ食材店には行ったが、確かに最高の品揃えのお店であった。(枠の関係で紹介できないのが残念)今でもユリウス・マインル(Julius Meinl)のコーヒーは世界に流通しているが、食材店は最盛期には欧州に1000店あったらしいが今はウイーンにあるこの店だけのようです。おそらく転機がきたのは第二次大戦後、そして1960年代、業務提携? あるいは買収されたか? 創業以来の店舗は縮小。2000年には食料品部門の撤退をして残り店舗はドイツ系の「Billa」や「SPAR」が買収。ユリウス・マインル(Julius Meinl)は立て直しの為にコーヒー部門のみに特化したようです。Restaurant Julius Meinl Am Graben2階にあるレストランはユリウス・マインル・アム・グラーベン(Julius Meinl Am Graben)の直営のレストランでした。1969年創刊のフランスで最も強い影響力を持つレストランガイドブック「ゴー・ミヨ(Gault et Millau)では高い評価をされているレストランだそうです入り口が割と地味な所にあり見落としやすい場所。オープンと同時に入ったのだが、空いていた。 窓から見えるのはグラーベン(Graben)通りとペスト記念柱何より美味しかったのだが、その飾り方に感激。アートでしたパンと一口前菜 一口サイズのクロケットです。モッツアレラ・チーズ(Mozzarella) 19ユーロ前菜にローストしたフォアグラとテリーヌ(Biogansei Eber) 25ユーロフィレ肉のパイ包み(Meinl's Wellington) 41ユーロウイーン風カツレツ(Wiener Schnitzel)とサラダ 26ユーロコーヒー・メーカー本来なら食後のコーヒーとデザートははずせない。でもこの日突然の胃痛で苦しくて食べられなかったのです 振り返ってみればレストランは当然ながらお店のお総菜や生ハム含めて今回の旅行で一番美味しい店だったかも・・
2014年10月14日
閲覧総数 2081
-
31

ここはどこ? シリーズ3作目 6 (ホウシャガメとコブウシ)
Break Time(正月休み)のタイトルは本日で「松の内」も終わったのでとりやめますね・・とりあえず、マダガスカルは後、2回くらい紹介してから途中になっていたローテンブルクに戻ります正月飾りと「松の内」「松の内」は本来、1日の大正月から15日までの小正月までのお正月の「松飾り」を飾っていた期間を指すそうです。門柱に飾る門松は歳神様を迎える為の道しるべや依代(よりしろ)で、鏡餅は歳神様への捧げ物だそうです。最近ではいつまでも正月気分に浸っていられないせいでしょうか、大正月から7日までを「松の内」として、鏡開きも昔は20日だったのが、前倒しで11日になってきたそうです。因みに、歳神様への捧げ物の鏡餅は、三種の神器(鏡・剣・玉)の一つ、昔の青銅製の鏡の形から来ているそうです。さて、マダガスカルに戻って・・今日は瘤牛(コブウシ)とホウシャガメを紹介。マダガスカル共和国(Republique Madagascar)バオバブの並木道で見かけた牛車のウシは普通見かけるウシとは違いました。Zebu・瘤牛(コブウシ)亜目 ウシ亜目(反芻亜目)亜科 ウシ亜科 Bovinae族 ウシ族 Bovini属 ウシ属 Bos種 オーロックス B. primigenius亜種 コブウシBos primigenius indicus背中のコブ、幅の狭い頭骨、首下に垂れ下がった胸垂が特徴。牛と思うと奇妙です。インド亜大陸での分布が確認されていると言う事です。古来、バビロニアのウル、インダス文明時代でも存在が確認され、特にインドで神聖視されているウシは本来このコブウシを指していたそうです。マダガスカルには最初からいたのか、後からボルネオ島からの移民が運んだのかは不明ですが・・・。実際、インド亜大陸とマダガスカルの動植物の類似はパンゲア大陸時代からの起源のようです。コブウシはラクダのコブと同じような原理でか、耐暑性があり、熱帯性の病気や害虫に対する抵抗力が強いため、家畜化された南アジアから、東南アジア・西アジア・アフリカなどの高温地域に広まったようです。白牛の顔の模様が非常に興味あります。他の白牛もこの顔。この牛は蹄も白い。さて、神秘のマダガスカルでも、やはり爬虫類の珍しさは格別です。ホウシャガメ(Radiated tortoise) 別名マダガスカルホウシャガメリクガメ亜科、ホウシャガメ属、ホウシャガメ種マダガスカル南部の固有種だそうです。有刺植物で前に紹介したディディエレア科の自生する乾燥地帯の林や岩場に本来は生息しているようです。雨が降ると甲羅の汚れを落とす為に踊るらしい・・・絶滅危惧種としてワシントン条約の附属 書1のリストに載っています。最大甲長40cm? 重さ16 kg近くなるらしい。背甲の色彩は黒や暗褐色で、甲板ごとに黄褐色の放射状の模様が入り、甲板は成長輪がわかりやすく盛り上がっています。(個体差もあるようです。)ホウシャガメは、基本的に草食で、花、果実、多肉植物を食べるようです。他のリクガメ同様に、タンパク質を与えすぎると、甲板がピラミッド状に盛り上がる傾向があるそうです。ここは保護された施設なので、栄養は管理されているのでしょう。綺麗な形の甲羅です。その違いは個体差か? 甲羅のテカリや、班の盛り上がり方が前者の亀よりも極端ですね。ホウシャガメ属は1種のみなので、別の種ではないはずです。日本では、ワシントン条約加盟前に流通した個体が登録書付きであれば流通することもあるそうです。リク亀好きにはたまらない種のようですよ。マダガスカル次回は簡単にカメレオンを紹介。
2010年01月07日
閲覧総数 537
-
32
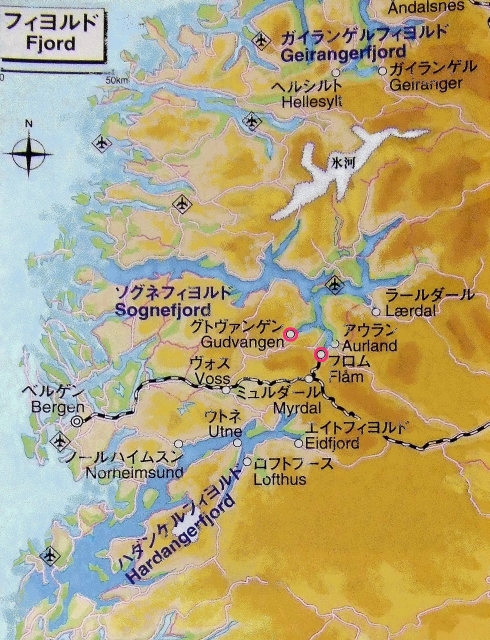
フィヨルド 2 (ゲイランゲル 2 )
ノルウェーの4大フィヨルドノルウェー海の沿岸はフィヨルドだらけです。数あるフィヨルドの中の代表的なフィヨルドが4つあげられます。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)ソグネ(Sogne)フィヨルド(Fjord)ハダンゲル(Hrdanger)フィヨルド(Fjord)リーセ(Lyse)フィヨルド(Fjord)今回は、上の2つのフィヨルドを紹介します。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)引き続き第2夜です。ゲイランゲル(Geiranger)フィヨルド(Fjord)海岸より深部にあるフィヨルドで、ゲイランゲルの街からヘルシルトへのフェリーの航路はゴールデンルートと呼ばれる人気のコースです。全長20km、最深部で200m。(フィヨルドとしては浅い方です。)春先(6月下旬)までは大量の雪解けの水が山肌を幾筋もの滝となってフィヨルドに注いでいます。オスロからゲイランゲルまで約500km。途中1000mを超す高原を通過しますが、高原は5月中旬まで雪と雪崩の為に閉鎖されているようです。(ルートは他にもあるようですが・・。)観光用のフェリーは春から夏場のシーズンには増便されているようですが、冬場でも地元の人達の足として、フェリーは運行活躍されています。不凍港(ふとうこう)前回軽く流しましたが、ノルウェーは冬季においても海面等が凍らない港です。地理学的言葉で言うと不凍港(ふとうこう)なのです。通常ならこれだけの高緯度地帯(北緯57度以上)に位置するため凍りつくはずなのですが、アメリカ大陸東岸から北大西洋を北東方向に北上して流れる北大西洋海流が分岐してノルウェー海流となってノルウェー海域に来るからなのだそうです。英語で「a warm-water port」とか「an ice-free port」と言うようです。水面が鏡面となってきれいです。下は、七姉妹の滝です。ダイナミツクな景観とアクセスの良さで夏場は世界各国から観光客が来ますが、夏場とはいえ寒くて冬の軽めの防寒着を身につけますが、冬場のフェリーは寒すぎてデッキには出られないそうです。2021年4月 このフィヨルドに住み付いていたバイキングについて書いています。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人
2009年08月10日
閲覧総数 384
-
33
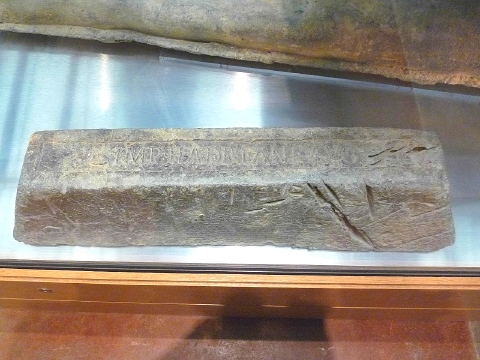
古代ローマ水道 9 (イングランド・バース編 2)
古代ローマ水道 9 (イングランド・バース編 2)ケルト人と温泉とローマ浴場(イングランド・バース)先住ケルト民族の移動。バース(Bath)の温泉の歴史は、伝承によれば、イングランドの建国神話の王様、フラダット王が泥の沼に浸かってライ病を治した事に始まると言わる。その後このバースの街を造ったとされる。つまりローマ人が侵略する前から温泉はすでに存在していたわけです。先住ケルト民族の移動。BC800年頃ケルト人と称される人々が大陸から渡来。鉄器文化を運んで来た。彼らは初期にやって来たゲール人と、後に来たブリトン人に代別される。ゲール人はブリトン人に追われる形でアイルランドに渡り、一部がさらに、スコットランドの西部に住み着く。一方、ブリトン人は現在のイングランドとウェールズに住み着いたとされている。また、ガリア人も同族のケルト人で、彼らはフランスに移住。因みに、「ブリテン」の地名は、ローマ人が「ブリトン人の地」と言う意味でブリタニアと呼んだのが最初です。バースは、イギリスの南西端、ウエスト・カントリーのサマーセット州にあるので前出のフラダット王はケルト人であることは間違いないでしょう。ブリトン人の時代になると、この泉は女神スリスの霊場とし、人々に畏怖の念を起こさせる特別な泉として祀られる。ドルイド(神官)が祭祀を司どり、泉の中に捧げものを投げ込む儀式が行われたらしい。それはローマ人がここに浴場を建設してもこの泉の神秘性は有効で神聖視された。女神スリスは、ローマ女神のミネルヴァに同一視され、スリス・ミネルヴァと呼ばれ神殿が建てられ、その横に浴場が建設された。※ ローマ人が浴場を建設する前は温泉とは言え、泥土の中、熱い湯が湧き出てる小川そのもの。湯気をたてながらエイヴォン川に流れるだけだったようです「神様にお参りして、温泉に入れば病も癒える。」をうたい文句として。霊場の隣にローマの温泉が建設されたわけです。下は、女神の泉に捧げられた品です。神聖な泉から、鉛職人達によって泉に投げ込まれた2つの鉛のインゴットが発見されました。A鉛は、ローマ水道や、温泉の導管や分配管の素材として、非常に大切なものでした。このインゴットには「ハドリア・アウグストス帝の所有」と刻印されています。ハドリアヌス帝時代の物であることが偲ばれます。バースの大浴場 長さ約25m 幅約12m。1世紀頃建築。今でも、バース中心部の3つの泉から1日46度以上の100万リットル以上湧き出ているそうです。B前回の写真とは反対から撮影。(浴槽の防水は、やはり鉛版が使われていたそうです。)ローマ人は日に一回は入浴したいほどの風呂好きだったようで、自分たちが快適に入浴し、余暇を楽しみ、同時にブリトン人の指導者達にもローマ式の生活を理解してもらいたかったのかもしれません。つづくリンク 古代ローマ水道 10 (イングランド・バース編 3) 終章
2009年06月04日
閲覧総数 960
-
34

レトロ写真館 (ザルツブルク)
Break Time (一休み)相変わらずマンションの工事中なので外の天気もわからず・・寒いし・・家にひきこもりの日々です。生活パターンも完全に逆転・・もっとも昔から夜の方が頭がさえる夜タイプなのですが・・今、それこそザルツブルク・タイムになっているのでかなり・・まずいです・・ところで時差ボケですが、ヨーロッパから戻る時は、飛行機に乗ったら映画など見ずにぐっすり眠ってしまう事です。(人によっては睡眠導入剤を飲む人もいます。)目が覚めたら日本タイムにあうように・・・。さて、前回紹介したザルツブルク(Salzburg)にあるホーエンザルツブルク城。そのケーブルカーの駅の近くにレトロな写真館があり、観光客にとても人気となっているようです。衣装を選んで、割と短時間でそれなりに撮影してくれるようです。しかもお値段は案外安い・・・こんな風に撮影してくれるのです。「私も、私も・・。」と思うのですが・・・中身が違うし・・・。撮影して帰る日本人は結構たくさんいるようです。こういう写真館て日本ではメチャクチャに高いですからね。(2~3万円はする。)フォトは20~30ユーロ。フレームが17ユーロ。だいたい併せて5000円~6500円くらい。セピアだから粗も見えず、化粧してなくてもわかりにくいし・・。実物より美しく撮れるはず・・。ナイスな発想。 旅の思い出に素敵
2009年12月16日
閲覧総数 244
-
35
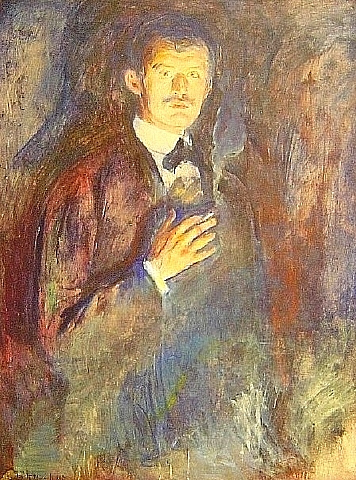
エドヴァルト・ムンク 1
ムンク美術館の写真があるので紹介しようかと思っていたのですが、ムンクは好みではないので、勉強不足でした。(資料を読んでいたら朝になってしまって・・。)しかも、彼の絵画の分析は難しいな・・。そんなわけ語る事はあまりないと思いますが、前半部、彼の画業をめざした初期印象派の影響の見える作品と自画像のみ先に公開する事にしました。エドヴァルト・ムンク(Edvard Munch)(1863年~ 1944年)ノルウェー出身の画家であり、版画家であり、装飾画家です。彼の作品で「叫び」は特に有名ですが(インパクトで・・)、おそらくそれ以外の彼の作品を知っている人はほとんどいないでしょう。81歳まで存命しているので、作品はとても多いはずなのですが、それはなぜか? 私が思うに、彼の作品は通常の絵画の分類に区分しにくく、テーマの中で扱われる事があまりないから見かけないのかもしれません。また、後半彼は自分の作品をまとめて飾りたがり手放すのを嫌ったと言います。その為、彼の死後にまとめて寄贈されたノルウェーのオスロにあるムンク美術館に作品が集中している事も原因でしょう。(ギュスターブ・モローもそうでした。)もう一つ原因は、彼の作品は「マドンナ」はともかく、コレクションして飾るには不気味さがありますし、ぶっちゃけ画家として腕があるかと言うと疑問符もあります。自分スタイルを確立した個性派と言う点で評価され、「叫び」で完結してしまっている感は否めないですね。1895年頃の32歳頃のエドヴァルト・ムンク自画像。1868年、エドヴァルド・ムンクが5歳の年に結核で母を失い、1877年には姉も結核で亡くなったそうです。幼少期に立て続けに起きた不幸はエドヴァルト少年の心に深い傷跡を残し、生涯消えることのなかった苦悩は、彼の作品の中に繰り返し現れる病室と死のイメージによって推し量られています。1885~1886年に制作された「病める子」ムンク美術館所蔵。同じテーマで何度も描かれているこの作品は、まさしく幼児期の思い出から生まれたようです。パリでゴーギャンの義弟と親交があり、後期印象派の作品にふれた直後の最初の作品のようです。普通の印象派の作品よりも精神性の込められた深い作品(重すぎる)だと思いますが、テーマが暗いので何ですが、良い絵である事は間違いありません。(奇抜な彼の作品にもこんな深い精神性が閉じ込められているのか? )彼自身も病気がちで、部屋に閉じ込められている事が多かったそうです。加えて、軍医だった父も妻の死以降、信仰にのめり込み、狂気手前だったようで、「病気と狂気と死が私のゆりかごの番をする黒い天使たちであり、生涯私に付きまとって離れなかった。」と後年語ったそうです。(彼自身も精神を病んだ時期があります。)故郷ノルウェーでは狭すぎ、1883年、パリに向かいます。そしてゴーギャンの、ファン・ゴッホなどのポスト印象派の画家たちに大きな影響を受けたそうです。上の2点は額縁付きで撮影したものをトリーミングして載せました。つづく
2009年08月17日
閲覧総数 314
-
36

サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)
サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)サグラダ・ファミリア(Sagrada Familia) Part 3生命の木・・・糸杉天からの使い(聖霊)としての白鳩果実今回は建物に表現されているキリスト教の象徴から紹介。その前に、前回降誕のファサードの3つの入り口について左の門がヨセフ、中の門がキリスト、右の門が母マリアを象徴する・・と紹介しましたが、門にはそれぞれ名前がついていました。左の門「信仰の門」中央の門「慈悲の門」右の門「希望の門」左の門「信仰の門」と中央の門「慈悲の門」入り口降誕のファサード、上部4本の鐘塔と中央「慈悲の門」の上部にある糸杉のオブジェ拡大してみると鐘楼となる塔の壁には「sanctus」と、文字が刻まれている。sanctus・・・意味は「聖なる」 という形容詞他にsanctusが示すのは1.三聖唱「聖なるかな,聖なるかな,聖なるかな・・・」で始まる賛美歌。2.ミサの最高潮の時にならす鈴または鐘。3.鐘楼そのもの。ガウディはこのサグラダ・ファミリアの外壁のあちらこちらにこうした文字も刻んでいます。生命の木・・・糸杉ヒノキ科イトスギ属、西洋檜(せいようひのき)サイプレス(Cypress)とも呼ばれます。糸杉は、ローマ時代には棺桶の素材でもあり、今も墓場に糸杉、あるいは死のイメージがつきまとった樹木です。聖書の各所には糸杉の記述があり、それによりいつしか「生命の木」の解釈がされるようになったようです。特に13世紀のビザンティン美術の中で十字架が生きた樹木として表現される時に糸杉が用いられるようになったと言われています。天に向かってまっすぐ伸びる事、常緑樹である事から墓場の糸杉は死後の生命の不滅・・と解釈され、キリストの復活と永遠の命のシンボルとなったようです。因みにキリスト磔刑(たっけい)の十字架はこの木から作られた・・との伝説もあるようです。白い鳩はアラバスターで彫られているらしい。天からの使い(聖霊)としての白鳩鳩は旧約聖書の「ノアの箱船」の中ですでに言伝の使者として登場しています。また「モーセの律法」の中でも「汚れていない物」として山羊や羊の代わりに神への捧げ物の動物とされていたようです。キリスト教では白鳩は三位一体、神の第三位格である聖霊としてのイメージで使われています。キリスト教美術において白鳩が現れた時、それは聖霊の啓示を受けた事を現しています。他にも外壁にはいろんな箇所に文字が刻まれている。ガウディは彫刻だけでなく、文字や石の壁の形にもこだわって、最高の聖堂を作ろうとしていたようです。聖堂そのものが、聖なるメッセージとなるように・・。告知する天使の像天使の頭の上の柱にも文様のような文字が浮かぶ。降誕のファサード左側身廊の側壁上部フルーツの盛り合わせらしい。果実は豊穣と知恵のシンボルそして、ここでは果実は聖霊の12の果実を暗示する為、愛、喜び、平和、忍耐、寛容、親切、誠実、善意、柔和、信仰、節制、純潔のシンボルになるようです。拡大してみるとモザイクになっているようです。Back numberリンク サグラダ・ファミリア 1 (未完の世界遺産)リンク サグラダ・ファミリア 2 (降誕のファサード)サグラダ・ファミリア 3 (生命の木)リンク サグラダ・ファミリア 4 (未完の理由 と主祭壇)リンク サグラダ・ファミリア 5 (天井と福音書記者の柱)リンク サグラダ・ファミリア 6 (天井の立体幾何学模様)リンク サグラダ・ファミリア 7 (ステンドグラス)リンク サグラダ・ファミリア 8 (受難のファサード)リンク サグラダ・ファミリア 9 (鐘楼のバルコニーから)リンク サグラダ・ファミリア 10 (教会建設)
2010年12月08日
閲覧総数 2085
-
37

イエローストーン国立公園 9 (グランド・ガイザー近辺)
イエローストーン国立公園の全リンク先をラストに追加しました。イエローストーンに戻ってきました。それにしてもあまりにカイザーが多いので、少し巻きでサクサク行きたいと思いますイエローストーン国立公園 9 (グランド・ガイザー近辺)イエローストーン国立公園(Yellowstone National Park)ガイザー・カントリー(Geyser Country)アッパー・ガイザー・ベイスン(Upper Geyser Basin) Part 4 トレイルガイザーの点在する丘をぬうようにファィアーホール川が右へ左へと流れています。今回はガイザー・ヒルを越えて少し歩いたグランド・ガイザーの近辺です。残念ながらグランド・ガイザーの噴出の写真はありませんが・・。Depressing Geyser丘の上に見えるのがキャッスル・ガイザー(Castle Geyser)イエローストーン最古と言われるキャッスル・ガイザー(Castle Geyser)の下にあるのがTortoiseshell Spring べっ甲池? とcrested pool 紋章の池? どっちだろ?スッポンの形なんだけどね地図にものらないような小さなスプリングもあちこちに・・。しかも不思議なのは緑の芝の中に突然湧いている事です。たぶん Spasmodic GeyserSpasmodic は「突発的な」を意味する。間欠泉としては一般的なかたちかも・・。ちょうど来ましたグランド・ガイザー(Grand Geyser)泥の穴の向側にグランド・ガイザー(Grand Geyser)があるのですが、噴出していないのでわかりにくいですがイエローストーンでは有名なガイザーの一つです。(ボードウォークは写真の後方左奥に続いています。)あまり水たまりもないし、盛り上がりもない・・しかも遠いので噴出口は見えません。グランド・ガイザーの噴出間隔は7~15時間で、噴出の高さは30mから60mなのでボードウォークから離れているのかもしれません。見れなくて残念。グランド・ガイザーの先の森林地帯にもまたまた幾つものスプリングです。つづくリンク イエローストーン国立公園 10 (ジャイアント・ガイザー)Back numberリンク イエローストーン国立公園 1 (分水嶺とアメリカバイソン)リンク イエローストーン国立公園 2 (5つのエリア)リンク イエローストーン国立公園 3 (ミッドウェイ・ガイザーベイスン)リンク イエローストーン国立公園 4 (グランド・プリズマティック・スプリング)リンク イエローストーン国立公園 5 (ミッドウェイ・ガイザーベイスン景観)リンク イエローストーン国立公園 6 (アッパー・ガイザー・ベイスン)リンク イエローストーン国立公園 7 (ガイザー・ヒル)リンク イエローストーン国立公園 8 (ビーハイブ・ガイザー) イエローストーン国立公園 9 (グランド・ガイザー近辺)リンク イエローストーン国立公園 10 (ジャイアント・ガイザー)リンク イエローストーン国立公園 11 (グロット・ガイザー)リンク イエローストーン国立公園 12 (モーニング・グローリー・ブール) リンク イエローストーン国立公園 13 (イエローストーン湖)リンク イエローストーン国立公園 14 (ヘイデンバレーとマッドボルケーノ)リンク イエローストーン国立公園 15 (キャニオンの眺め)リンク イエローストーン国立公園 16 (Lower FallsとUpper Falls)リンク イエローストーン国立公園 17 (マンモスホットスプリングス)リンク イエローストーン国立公園 18 (テラスマウンテン)リンク イエローストーン国立公園 19 (ミネルバテラス)リンク イエローストーン国立公園 20 (ウエストサム)リンク イエローストーン グリズリー・ベア(Grizzly bear)イエローストーンは間を開けながら最終的に20までです。
2010年07月12日
閲覧総数 270
-
38

ミケランジェロ作のメディチ家礼拝堂
彫刻大好きの私ですが、お気に入りの素晴らしい作品の多くは、意外に墓石に多く存在します。今回はイタリアのフィレンツェにあるミケランジェロ作のメディチ家礼拝堂を紹介します。メディチ家(Medici)とは、ルネッサンス期のイタリアのフィレンツェにおいて、銀行家、薬種問屋、政治家として、フィレンツェに君臨した一族です。その巨大な財力でミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ボッティチェリ等の後世に残る芸術家を支援し、育て、保護し、ルネサンスの文化を育てる上で大きな役割を果たした一族としても知られています。フィレンツェにあるこの墓は、メディチ家の歴代当主の墓で、新廟と旧廟からなっています。広大な八角堂である旧廟は財力と権力にものを言わせ、大理石や宝石によって床や壁が飾り立てられ、天井はフレスコ画で覆われています。新廟は1520年から1533年にかけてミケランジェロによって建てられました。新廟右手にロレンツォ豪華王の孫ウルビーノ公ロレンツォ2世(1492~1519)の墓があり、向かい側にロレンツォ豪華王の三男ネムール公ジュリアーノ(1478~1516)の墓があります。「曙と黄昏」(あけぼのとたそがれ)ミケランジェロは瞑想の姿勢をとるウルビーノ公ロレンツォ2世の像下に「曙光」を象徴する女性像と「黄昏」を象徴する男性像を配します。下の写真です。写真プリントを上からデジカメで撮影したので綺麗ではありません。あしからず、参考まで・・。「昼」と「夜」ジュリアーノの像には力と指導力を。彼の像下には「昼」の象徴として男性像、「夜」の眠りを象徴して女性像が置かれています。写真下私は数あるミケランジェロの作品の中でもこのテーマある作品がとても気に入っています。こんなお墓に入りたいものです。ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo di Lodovico Buonzrroti Simoni)(1475~1564)イタリアルネッサンス期の彫刻家、画家、建築家、詩人であり、ルネッサンスの三大巨匠の一人です。(他の二人はレオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ・サンティ)画家としては、バチカンのシスティーナ礼拝堂の天井フレスコ画の「天地創造図」と壁画の「最後の審判」が有名。建築家としては、バチカンの「サン・ピエトロ大聖堂」、「カンピドリオ広場」の設計が有名。彫刻家としては「ピエタ」、「ダビデ像」、「モーセ像」など多数あり、彫刻家としての面のほうが、クローズアップされているかもしれません。下はバチカン美術館にある「サン・ピエトロのピエタ」です。
2009年05月08日
閲覧総数 2214
-
39

スペイン・ミハス 2 (ミハスのロバ・タクシー)
今回は街のタクシーを紹介。と、言っても普通じゃない動物愛護団体からブーイングが出そうな予感が・・・。スペイン(Espana)アンダルシア(Andalucía)州マラガ(Málaga)県ミハス(Mijas)ミハス名物ロバ・タクシーミハスはとても小さな街である。せいぜい1時間もあれば回ってしまう。実は取り立ててみる所は白い町の景観くらいなのです。でもこれを見る為にグナダから2時間かけてここに立ち寄ったりもする。(もっともこの近くに空港があるせいもあるかも・・)逆コースもあるけれどアンダルシアのツアーではたいていミハスに数時間立ち寄るので、知る人ぞ知る街なのです。ここミハスでもう一つ名物なのが・・実はロバ・タクシーなのです。街の麓のバス乗り場の隣で、ロバがたくさん並んで待機している場所がある。何やら頭に札がついている。まるで売られていくロバの値札のようでもある。前回馬車の写真も紹介していますが、それは近年のことで、ロバは昔からスペインで荷物を運ぶ使役動物の定番でした。最もスペインだけでなく、ギリシャの島(サントリーニ島でも紹介)やイタリアでも沿岸の街や島がロバを未だ使っている所があるので、取り立ててめずらしい事ではないのだが・・。そして、たいていは地元民がささやかに使うか、観光用です。ここも確かに観光用が主なのだが、ちょっと他に類のない形態をとっている。この子にも札がついている。拡大・・な、な、なんと・・・・MIJAS BURRO TAXI 30 ミハス・ロバ・タクシー No 30タクシーの登録証の鑑札だったのだ・・・ナンバー・プレートか?驚くべし・・ミハス・・本当にタクシーとして使っていたこちらは2人まで乗れる椅子付きのタイプ。台車だけでも重そうなのに2人も乗ったら気の毒だ。馬車は一台30分で20ユーロ(2600円)。(最近の値段)ロバは聞いてないが馬車よりはるかに安いと思う。乗っている観光客はほとんど見かけない・・・・。山坂があるから確かに必要だが、フンが落ちるのでコースは決まっているのかも・・。道は綺麗だし・・。住民は歩いているようだ。つづく
2010年02月23日
閲覧総数 1315
-
40
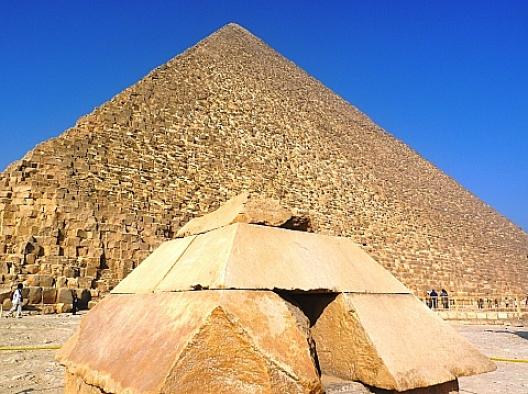
エジプト 2 (ギザのピラミッド)
まずは答えからエジプト 2 (ギザのピラミッド)言わずもがな・・・これはピラミッドです。ギザの3大ピラミッドの一つクフ王のピラミッドです。前に写り込んでいるのは、ピラミッドの最トップを飾っていた石の部分です。古代王朝が栄えたエジプトは、今は立憲共和制の国となっていますが、今も、古代王朝時代のロマンを感じる事のできる国です。でも、最近の人の多さと、観光為の開発にむしろロマンが破壊されているのを感じます。誰でもがリーズナブルに簡単に出かける事のできる国は、違う進化をせざる終えないのでしょう。エジプト・アラブ共和国(Arab Republic of Egypt)ギザ(Giza)全体を写していないのには訳があります。これが、今のエジプトの現実だからです。近距離からだと全部は入らないし・・。まあ、ピラミッドは四角錐なので後ろからもとれますが・・・。前にはつい近年発掘された「太陽の船の博物館」がけったいな姿をして鎮座しています。なぜあんな形にしたのかは不明ですが、私には一見プレハブトイレに見えたそれにしても駐車場も・・・「かんべんしてよ・・。」て感じですね。数千年のロマンが一気に引いてしまう光景ですまあ、気を取り直して・・。近くに寄ります。かなりくずれて大きな石が転がっています。外装の美しい石(化粧石)がはがされてむき出しの内部の石が見えているからです。ズームしてサイズを見てください。前回紹介したように下段の石は大きく、上に行くほど小さくなっています。今回はこんなところで・・つづく。リンク エジプト 3 (ピラミッドとピラミッド・ピュー)
2010年01月13日
閲覧総数 691
-
41

パンチボール(Punchbowl) 4
「2012年7月 ここはどこ? クイズ 1~4」で紹介したものにタイトルを付け替えました。他の人はほぼ行かない結構貴重な写真なので見てもらう為に。ただし形体はそのままクイズのままにしてあります。2012年7月 ここはどこ? クイズ 4 (解答編 2)パンチボール(Punchbowl) 42.パンチボール・クレーター(Punchbowl Crater) 国立太平洋記念墓地(The National Memorial Cemetery of the Pacific) リンカーンの手紙 エリソン・ショージ・オニズカ(Ellison Shoji Onizuka)氏のお墓前回に引き続き、今度は近年のパンチボール史です。1948年2月に、国立太平洋記念墓地(The National Memorial Cemetery of the Pacific)となり、名称もプオワイナからパンチボール・クレーター(Punchbowl Crater)と呼ばれるようになった・・と言うのは前回書きましたが、ここが墓地になる案は1890年代後半からあったそうです。当時は増えるホノルルの人口を収める為の墓地計画だったそうですが、場所が場所であった事などあり否決されたようです。米国政府の独立機関が1923年に議会によって設立した・・とモニュメントには書いてありましたが、実際1943年、Hawaiiの知事が国家墓地として土地を提供。しかしこの時も予算不足で先送りされたと言います。近年は場所がなく、こんなへりまで・・。おそらくミッションごとにお墓はかたまっていると思われる・・。パンチボール・クレーター(Punchbowl Crater)ここは1949年に 国立太平洋記念墓地(The National Memorial Cemetery of the Pacific)となり、1964年にはホノルル記念共同墓地が加えられ45,000人以上のアメリカ軍人が眠る共同墓地です。敷地112 1/2エーカー(455000m2)ここに本格的な墓地建設が始まったのは第二次世界大戦後の事。大戦で戦死した大量の兵士達の埋葬場所として必要に迫られたからだったようです。主に第二次世界大戦、ベトナム戦争、朝鮮戦争で亡くなった兵士の方。そして退役軍人の方もここに埋葬されています。とは言え、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の34000人の復員軍人全員の分はまかないきれないようで、今他にも軍人さん用の墓地ができています。女神像前の階段の両サイドには幾つかのブースがもうけられている。World War II(第二次世界大戦)のブースブースを囲む大理石には内壁外壁ともにぎっしり部署別、アルファベット順に名前が刻まれている。おそらく第2次世界大戦の間に戦没した行方不明者のリストのようです。「28778人はミッション中になくなり、海葬された者もいるが不明の者も多く、名前で個々に敬意を表している。」・・・旨が下の看板に書いてあったような気がします。リンカーンの手紙最初に女神像の足下の詞をのせましたが、意味がわかりましたそれはリンカーン大統領が南北戦争で5人の息子を亡くしたビクスビー夫人(Mrs Bixby)に宛てた追悼の手紙のラストの一文でした。(超訳)The solemn pride that must be yours☆To Have Laid☆so costly a sacrifice upon the altar of freedom自由の祭壇に捧げられた尊い犠牲、それを貴方の誇りとして下さい。以下に続きます。Yours very sincerely and respectfully,A. Lincoln心より敬意をこめてA. リンカーンリンカーンの言葉を借りてここに参拝に来る、家族や友や知人へのメッセージとしていたのでしょう。さて、ここには日本でもとても有名な方が眠っている。日系アメリカ人エリソン・ショージ・オニズカ氏のお墓は一等地にある。なぜなら彼はハワイ島コナの出身の英雄だからである。エリソン・ショージ・オニズカ(Ellison Shoji Onizuka)氏のお墓(1946年6月24 日~1986年1月28日)日本名 鬼塚 承次ハワイ州ハワイ島コナ出身アメリカ空軍の軍人であり、アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙飛行士。スペースシャトルには2回搭乗。1985年1月24日ディスカバリー号1986年1月28日チャレンジャー号2回目のスペースシャトル・チャレンジャー号打ち上げ直後にシャトルは爆発して墜落。その映像は世界中継されていたから私も含め全世界の人々が見守る中の事件であり、記憶に残るショッキングな映像だった。特に日系人として初の宇宙飛行士だったので日本人にはとてもなじみ深い宇宙飛行士の一人である。女神像の前からの撮影。遠くに見えるのはパンチボールの入り口ゲート。他に、ここには第二次世界大戦で戦った日系二世だけで編成された部隊の方も眠っている。ハワイと言えば特に日系の方が多く、日本とアメリカが開戦した為にその狭間で移民の方達はかなり苦労をしたそうです。アメリカの中で生きていく為に、アメリカ人として戦い、アメリカに最も貢献し戦果をあげた部隊だったそうですが、それだけに戦いは厳しく、戦死者が最も多かった部隊だったそうです。今となっては敵味方関係ありません。皆さんのご冥福を祈りたいと思います m(_ _)m 追記・・ここに観光でツアーが入れなくなったのは、お墓の中で用を足すバカ者がいたからだそうです。トイレは女神像のある廟(メモリアル教会と地図のギャラリー)の建物の両サイドにありますよ。Back numberリンク パンチボール(Punchbowl) 1リンク パンチボール(Punchbowl) 2リンク パンチボール(Punchbowl) 3 パンチボール(Punchbowl) 4
2012年07月14日
閲覧総数 295
-
42

フレデリクスボー城 3 (ノルマン人とヴァイキング)
フレデリクスボー城 3 (ノルマン人とヴァイキング)デンマーク王国(Kingdom of Denmark)フレデリクスボー城(Frederiksborg Slot) Part 3ヴァイキング達の国ヴァイキングと呼ばれたノルマン人消えたノルマン人フレデリクスボー城 謁見室デンマーク王室の歴史でも・・と思ったらもっとさかのぼってしまったヴァイキングと呼ばれたノルマン人BC12000年にはすでに人が居住していたと言われるスカンディナヴィア半島は、長い歴史の後に再び歴史の表に現れるのは8世紀頃です。9世紀から300年近く、中世ヨーロッパに侵略してその歴史に大きな影響を残したヴァイキングは、もとはその時代にスカンディナヴィア半島やバルト海沿岸に原住していた人々を指す呼び名のようです。(古ノルド語で「フィヨルド」とか「入江」を指す言葉。)私たちのイメージの中では略奪する海賊的なイメージがあるヴァイキングは、もともとそれが生業ではなく、文化の進んだ国の農民であり漁民だった彼らが域外へと進出したのは、人口増加、あるいは食糧の生産低下か・・いずれにせよ自国では暮らせなくなってきたからと考えられています。種族的にはインド・ヨーロッパ語族(ゲルマン語派)を祖先とするヨーロッパ中北部に広まり、そこを原郷としたゲルマン人であったようです。彼らは8世紀後半から9世紀にかけてヨーロッパ各地を侵略。フランク人は彼らをノルマン人と呼びました。消えたノルマン人一時はパリまで進軍した一部はフランス北西部のノルマンディーにノルマンディー公国を建国。グレートブリテン島、アイルランド島等のイングランドを侵略した一派は、デーン人、ノース人と、ノルマン人はどんどん分離し、土地に同化して中世以降ノルマン人と言う概念は消えてしまうようです。そのデーン人を包括して統一国家としてデンマーク王国は建国されます。(ノース人は主にノルウェー人です。)因みにヨーロッパ中部に広く分布したのがインド・ヨーロッパ語族(ケントゥム語派)のケルト人達です。彼らはローマ人やゲルマン人に追われて、現在はアイルランド、イギリス、フランスの一部に定住して同化。(ケルト人については6月に「古代ローマ水道 9 (イギリス バース編 2)」で紹介。)リンク 古代ローマ水道 9 (イギリス バース編 2)北欧の国家を建国したノルマン人たちはルーン文字を始め彼らの宗教を捨てキリスト教に改宗。13世紀頃には彼らの意識も薄れて欧州カトリックに同化していったようです。フレデリクスボー城 謁見室門入って左の西棟が礼拝堂で正面の北棟が王の棟、そして右の東棟が王女の棟です。写真は城の北西の角、王の棟に繋がるのが写真に見える湖を渡る廊下でその先、謁見室に続きます。写真左は馬上鑓試合の行われる場所。右にあるのが礼拝室のある西棟渡り廊下内部暖房もなくひんやり廊下です。博物館初期の大型絵画が飾られています。謁見の間入り口の飾り謁見室写真2枚です。天井は高く装飾が美しい。謁見の間は火災の焼失から免れ、建設当初1682~1688年の時のままです。フランス・バロック様式。シャンデリアは鹿ですよ部屋には歴代王の大型肖像画が飾られています。城は横に長く続いています。片側に廊下のある部屋と部屋の内部にしか出入り口のない場合とあります。いずれにせよ各隣の部屋と横に繋がっているのです。扉はもともとなかったのか最初からないのか・・・。暖房効率は悪そうです。歩いているとたまに暖かい部屋はありました。装飾はいろいろ 女神の描かれた美しい天井飾り北欧神話の女神フレイヤ(Freyja)? 太母また海の守護神つづく休んだので写真枠が今日は贅沢に使えるリンク フレデリクスボー城 4 (クリスチャン4世と海軍)
2010年02月02日
閲覧総数 938
-
43

ベネチアの仮面
謝肉祭(カルネヴァーレ)に行く前に私のコレクションを紹介。ところが納戸の奥深く眠る仮面を探す為に納戸の整理をするはめになりました。A一番のお気に入りのピーコックの仮面です。アート作家の作品でシリアルNo入りですが、誰だか読めません・・。下も同じ作家の作品です。BC上は作家物で実用ものです。下はリングがついていたので飾り用のようです。(少し面が狭い)Dもっともベネチアらしい仮面です。実用品。ELuciano Chinaglia ルチアーノ・キナリア (版画)ベネチア在住のベネチア画家でベネチアのカルネヴァーレをテーマにした作品を多く出しています。ベネチアの街をうろうろしている時に偶然見つけ10点程購入してきたものの中の1点です。彼の作品はどれも夢幻の中のベネチアを表現しています。これには「貴人と青年と月」のタイトルを付けました。共和国政府はカルネヴァーレを奨励しました。この時ばかりは万事おとがめなしで、普段はっきりしている階級の差(貴族も商人も・・)も一時取り払われ、皆、一緒になって踊り、はめを外したのです。その時特に身分の高い者は顔を隠して街の様子を見に出る。いつしか、町中で仮面は流行、仮面職人と言う身分規定もできるほどに・・。この祭りは共和国が終わるまで続いていました。現在のベネチアのカルネヴァーレは1980年以降に再び始まったものです。仮面を専門とする店も再び脚光を浴びはじめたようです。
2009年05月01日
閲覧総数 305
-
44

アラモアナ・ビーチ・パーク 1 (パークの歴史)
さて、またまた毎度写真選択に苦労するハワイのビーチ・シリーズです。アラモアナ・ビーチ・パーク(Ala Moana Beach Park) 1 (パークの歴史)アラモアナ・ビーチ(Ala Moana Beach)パークの歴史 1オアフ島、ワイキキ外れにあるアラモアナショッピングセンターは、ハワイ一の巨大モールなので、ハワイを訪れた人なら必ず立ち寄る場所です。その向かいにある敷地面積100-acre (0.40 km2)の緑地公園がアラモアナ・ビーチ・パーク(Ala Moana Beach Park)です。マジック・アイランドから撮影したアラモアナ・・ショッピングセンターアラモアナの中でも、セレブ御用達高級デパート、ニーマンマーカス(Neiman Marcus)のレストラン、マリポサ(Mariposa)のテラスが調度パークの正面にありパークが眺められます。まずは例によって位置確認の地図から赤いライン(マジックアイランド)とその左一帯がアラモアナ・ビーチ・パークです。写真中央にアラワイ運河の河口があり、そこにアラワイヨット・ハーバーが広がっています。さらに右隣はヒルトン・ハワイアン・ビレッジとなり、ワイキキ・ビーチの西端がそこで終わっているのです。つまりここはワイキキ・ビーチには入っていません。わずかの所でワイキキ・ビーチ・エリアから外れているのです。昨年カタマランで航海した時に海から撮影した写真から・・。写真真ん中までがアラワイ・ヨット・ハーバーで写真左半分がアラモアナ・ビーチ・パークです。中央に見えるビルはアラモアナ・ショッピング・センターの隣に建つアラモアナ・タワー、ナウル・タワー、ハワイキ・タワーなどです。ABCとつけたのは撮影場所の位置の為です。アラモアナ・ビーチ・パーク(Ala Moana Beach Park)は、ワード・センター前からアラモアナ・ショッピング・センター前の半マイル(800m)以上にわたるアラモアナ・ビーチとピクニックエリア、エクササイズエリア、テニスコート、ビーチバレーコートもある緑地。それに海に飛び出したマジック・アイランド(Magic island)から構成されています。アラモアナ・ビーチ(Ala Moana Beach)BとCの間あたりから撮影Cから撮影砂浜のすぐ近くまで芝が生えていて、地面はしっかり、泳がない人も芝の上で寝転びながらビーチを楽しめる素敵な公園です。ワイキキ・ビーチより地面は絶対良い感じです とは言え、ここは人工ビーチです。アラワイ運河の河口が隣にあるこの場所は、間違いなくかつては湿地帯だった場所です。パークの歴史 11931年ホノルル市と郡は、モアナ域をきれいにして公園を作る事を計画。フランクリン・D・ルーズベルト大統領のニューディール政策の資金を使用して1934年に76acre のパークが誕生。フランクリン・D・ルーズベルト大統領に捧げられたこの公園の開園には大統領自ら来たと言いわれ、東にあるパーク入り口の門はルーズベルト門と呼ばれています。残念ながらルーズベルト門の良い写真がありません 1947年には、モアナ公園からアラ・モアナ公園に名称変更。モアナ(moana)はハワイ語で「海」アラ・モアナ(ala moana)はハワイ語で「海への小道」の意翌、1948年にはアラモアナ・ショッピング・センターの構想ができ、1955年にこの人工ビーチが作られています。砂はオアフの西海岸から運ばれたとか・・。因みにアラモアナ・ショッピング・センターの完成は1959年。地元の人には人気のパークですが、近隣のホテルの人でなければ観光客はあまり来ない所です。来ないと言うより、知らないのだと思います。そう言う意味では日本人に会うこともなく、穴場かも・・。週末はバーベキューをする人で人気ですし、アメリカの独立記念日には花火を上げるなどさまざまなイベントの開催地となる場所でもあるそうです。(花火はマジックアイランドの方で・・)ワイキキとは違う意味で都会のパークです。それにしても海が綺麗です。このあたり海はいきなり深くなるそうです。だから小さい子供はここでは危険。マジックアイランドの突端に人工のビーチがあるので水遊びにはそちらのがいいかも・・です。(次回紹介)高級コンドミニアムのビルが海岸前に林立。ホテルばかりのワイキキと違い。一般向けの不動産ビルです。まさに一等地。つづくリンク アラモアナ・ビーチ・パーク(Ala Moana Beach Park) 2 (ハワイを造った会社)リンク アラモアナ・ビーチ・パーク(Ala Moana Beach Park) 3 (マジックアイランド先端)
2013年04月08日
閲覧総数 1221
-
45
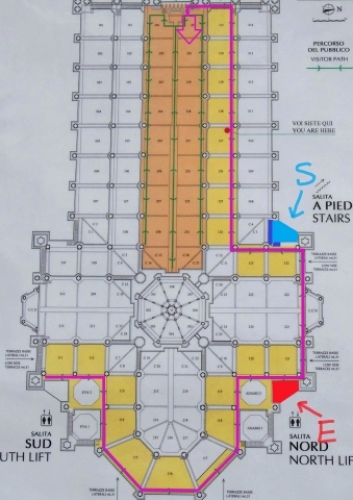
ミラノ(Milano) 5 (ミラノ大聖堂 3 外壁の装飾)
前回、飛び梁(フライング・バットレス・flying buttress)の装飾が、ミラノ大聖堂のものは非常に美しい・・と言う事を書いたが・・。いろいろ考えて見ると、もしかしたら昔は他でも美しい装飾があったのかもしれない。ただ、修復にかかる経費が倍増するので他のところではそこまで手を入れて修復していないからなのかも・・。この大聖堂はいつ行っても修復工事をしているそうだ。確かに直すところは果てしなく多い。外壁に設置されている彫像は取り外されてメンテされ、壊れた所は修復。そしてしっかり落ちないように固定される。ものによっては公害などにより石が溶けて修復出来ない物もあるようだ。そんな物は近くのドゥオモ博物館にオリジナルが保存されレプリカが飾られる。彫像だけで約3600体 怪物96体 ガーゴイル150体、この大聖堂の場合、修復とは永遠に終わる事のない仕事に違いない。ミラノ(Milano) 5 (ミラノ大聖堂 3 外壁の装飾)ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)ファサードは西、主祭壇は東の法則屋上テラスの図面E・・・エレベータ S・・・階段ピンクが屋上のルートでオレンジ部分が屋根のテラス部分。側廊のテラスから屋上の屋根に上る階段。この階段はファサードのガレリア側。ファサードの装飾の裏側に階段がある。このネオ・ゴシック様式のファサードの完成は1813年。ナポレオンが自分の戴冠式に間に合わせる為に短期間で、かつ少ない経費で建設出来るよう奔走したのである。ファサードは西、主祭壇は東の法則ところで聖堂の入り口であるファサードは西に向かって建っているのが一般的。それは欧州の場合、内陣の主祭壇が東に位置するからなのである。現在は土地の問題もあるだろうが、基本聖堂はエルサレムの方向を向いて建てられ、エルサレムの方向に祈るようにできているかららしい。それはイスラム教で言うミフラーブ(mihrāb)と同じ意味のようだ。最初からモスクとして建てられた所はミフラーブが必ず礼拝堂内部正面の壁に設置され、それが聖地メッカのカアバ神殿の方角を示している。(後からモスクになった所は正面に無い)それにしてもイスラム教徒は必ずカアバ神殿の方角に祈りを献げる。だから出先にモスクが無い時はカアバ神殿の方角を示しているキブラ (Qibla)に向かって祈るのだ。階段にも凝った装飾が付けられている。注意深く見ていると、けっこう笑える物もある。おそらく、法則はなく、石工の人がそれぞれ好きな物を掘ったのだろう・・と考えられる。珍しい事に、この大聖堂建築では、設計段階のやりとりや、職人とのやり取りまで細かく記載された記録資料が残っていると言う。1回目に紹介した建築プロジェクト「ヴェネランダ・ファッブリカ・デル・ドゥオーモ(Veneranda Fabbrica del Duomo)」が一貫して管理しているからなのだろう。身廊の屋根の上。(左が正面のファサードの天辺部分)非常に贅沢な石のスレート屋根。初期の大聖堂の屋根は木造だったそうだ。ファサード方面を撮影。(この写真は今回のものではありません。)今回は身廊の屋根の半分が修復工事だったので、ファサード方面は障害物.の無い昔の写真を採用。下は聖堂方面。これは今回撮影。なぜか屋根瓦(大理石のスレート)の上に被いがされている。ここで何かイベントでもするのでは? 尖塔の上には全てに聖人の像が据え付けられている。(これら聖人は全て教会の外に向いて立っている)そもそも尖塔は何の為にあるのか?当初は時計や鐘をつるす役目もあったそうだ。もちろんそびえる塔は天を指して神をイメージする・・と言う意味もあったろう。しかし、ここでは尖塔の数だけでも135本。これは非常識に多い。これはぶっちゃけ、世間に目立つ、驚くような大聖堂を造って自慢したい・・と言う司教や建築家や、当時の市民の気持ちの表れのようだ。立派な大聖堂は街に冨と名声をもたらすのだそうだ。大半の尖塔は1800年代のものらしい。飾り、ファルコナトゥーラ(スペル不明)ファルコナトゥーラのトップやフリルの部分はだいたい植物で葉か花。中にはひまわりの花も・・。中には人や人の頭部を彫った凝った彫り物もある。下はキリストと天使?雨樋・ガーゴイル( gargoyle)巨人が支えるガーゴイル(gargoyle)この大聖堂の雨樋であるガーゴイルのうち96体は巨人が支える形をしていると言う。ガーゴイルだけでなく、重い物を支える時、こうした使い方がされるようだ。背中の部分が割れていて、そこに樋(とい)が通されて口から雨水が排出される。ガーゴイル(gargoyle)と言えば、基本ゴブリン(小鬼)のようなグロテスクなものが魔除けとして好んで用いられるが、まれに変わり種がある。司教や職人に似せてからかったものもあるそうだ。昨年紹介したブリュッセル、グランプラスの市庁舎のガーゴイルは人間が多かった。※ 2013年10月「ブリュッセル(Brussels) 5 (グラン・プラス 5 市庁舎 ガーゴイル)」飛び梁・フライング・バットレス(flying buttress)の一部装飾葉の部分はアカンサス(Acanthus)にも見えるがアザミの蕾か?もし、アザミなら地の悲しみと罪のシンボルであるし、中世では薬草としても珍重された花である。フライングパットレスには裏表に彫像が据えられている。石像だけでなく、頭の上のテインパノや足下の装飾もセット。尖塔の上の聖人像に哀愁を感じる ミラノ大聖堂つづくリンク ミラノ(Milano) 6 (ミラノ大聖堂 4 聖堂身廊から)
2014年08月17日
閲覧総数 1116
-
46

古代ローマ水道 10 (イングランド・バース編 3) 終章
イングランド・バースの浴場と古代ローマの水道 ついに完結です。古代ローマ水道 10 (イングランド・バース編 3) 終章バースの温泉施設鉛管ローマ人の入浴ローマ帝国の滅亡と共に消えた大浴場施設バースの温泉施設バースの大温湯浴場はローマ時代に起源を持つ浴場ですが、この施設は19世紀に造られた新古典様式の建築です。19世紀、遺跡の発掘などブームがおき、古代へのリスペクトが新古典様式を産んだ。当時イングランドでも流行していた様式です古代ローマの様式にマッチしたので違和感なく、むしろロマンティックな雰囲気を醸し出したかもしれません。石像類は遠い昔にほとんど盗まれ、レプリカでしょう。ここは現在遺跡博物館として公開されていて、今はここの温泉を眺めるだけです。それでも、当時の優雅に入浴するローマ人の姿がここなら容易に想像できるというものです。C前にポンペイの遺跡で紹介したように、レンガで持ち上げられた床に熱風を送る熱気浴室(サウナ)も。もちろん備えられ、燃料は石炭が使われていたようです。鉛管下は床に埋め込まれた鉛管です。水道が流れていたと推察できます。(変色していない。)鉛の幅は15cmくらい? じゃまにならないよう埋めるという発想と技術もすごいてす。D下は温泉の接合部です。三路になっているみたいですね。イオウ分で変色しているのかさび付いているのか?E下は、LDAと刻印されています。制作会社? 制作者? の名の入った鉛のパイプです。Fローマの上水道でとにかく大切なのが、導水管or配管です。それらに鉛が使われていた事は「古代ローマ水道 3」で紹介しましたが、ポンペイの鉛管よりかなり進歩していますね。(合金かな? 製造会社? の刻印入りとは・・それもすごい・・。)鉛は、ここから15マイル離れたメンディップ丘から奴隷によって採掘された。「pigs」と呼ばれるインゴッドで運ばれ(「古代ローマ水道 9」 の写真A)、パイプ造りの会社で板状の鉛に変えられた後、鉛を木製の丸い棒に巻き付け接合部をハンダ付けしてパイプに仕上げるのだそうです。(ここの遺跡博物館で説明されている。)さて、これだけの温泉施設も、ローマ帝国が滅亡すると、浴場も神殿も荒廃していく。水道橋もそうですが、メンテナンスが重要だったからです。浴場は荒れ果て、維持管理どころか排水路はつまり、それでも温泉は吹き上げたので、再び一帯は泥土化し、再び土砂に埋もれてしまったらしい。近代に発掘された時には逆にこの事が幸いして水源地や浴槽が無傷のまま残っていたらしい。※ ポンペイも火山灰に埋もれたが故にそのまま残った。バースの温泉復活は、ノルマン人のイングランド征服まで途絶えます。1090年ノルマンの司教ジャン・ド・ドゥールがバースの修道院に赴任してくると、温泉浴場は医療目的で再興。1539年修道院が解散させられるとヘンリー8世の命で一般に開放され、痛風に良い温泉とバースの人気が上がったと言われている。ローマ浴場の本格的な発掘は1878年から。バース市の土木建築技監がたまたまキングス・バースの湯場の床下から発見。発掘を行なった。すでにあった民家も買収し、せっせと掘って浴場施設を発掘。素晴らしい古代のローマの浴場の姿が蘇ったのです。※ この浴場は1978年まで使われていたようですが、病原菌の繁殖で使用されなくなった。かなりヤバイ病気を引き起こしたらしい。ローマ人の入浴入浴はもともと古代ギリシャから伝わった慣習だったそうです。最初は金持ちだけが個人の邸宅内に設備した物で一般の民の入れるものではありませんでした。それを初代皇帝アウグストゥスの腹心アグリッパがローマ初の市民も入れる大浴場を建設した事から入浴とそれに付随する入浴施設はローマの人にとってなくてはならないものとなっていく。(もちろんそれ以前にも小さな浴場はあったが・・。)もともと大浴場の建設は皇帝の名を高める為の市民へのサービス事業です。料金もほとんどタダ同然で入れて、施設ではいろんな娯楽に興じられ、市民の見たこともない本を読む事もできた。市民に愛されたのは当然、1日1回浴場に行く人がいても全然不思議じゃなかったのだ。かくして歴代皇帝による浴場建設ラッシュとなり、ローマ市のみならず、ローマの属州(植民都市)にもたくさん大浴場は建設されるに至った。そうなると、何が起こるか? 水不足です。だから大がかりな浴場を建設する度に水道施設も増設しなければならなくなったのです。ローマ市では最大13本の水道があったとされています。ローマでの水の使用量は大変なものだったと推察します。ローマ帝国の滅亡と共に消えた大浴場施設山の泉や川の源泉から水を引くのは動力のない時代には大変な事です。全ては自然の摂理にのっとって「水は高い所から低い所へ流れる。」水を流す導水道には傾斜が付けられた。それには源泉の標高と水を供給する場所の標高を綿密に計算して、傾斜角度が計算される。※ 傾斜は1kmで最低7cm落ちないと水は流れないのだそうです。ローマの水道橋はただ建てられているのではなく、その場その場にあった橋の水路の位置が綿密に計算されて建てられているわけです。その技術たるやローマ帝国滅亡後1000年以上真似の出来ない技術であった。古代ローマ時代に建築された水道橋は、BC312年から3世紀にかけてローマの諸都市に水を供給するために建築された、古代ローマ帝国の最大にして最高の土木建設事業であった。帝国崩壊後、異民族により水道橋は破壊され、水の無くなった街は荒廃していった。水の来ない浴場は荒廃して朽ち、さらに同族人により水道橋や浴場の石材や鉛などが資源として掠奪され、ローマの残骸は中世の人から見たらもはや取るところの無くなったゴミ? 放置され風化され消えて行った。高い文明を誇った強大なローマ帝国の無残な姿です。皮肉な事に今ローマの面影を完璧に伝えてくれるのは、突然の天変地異で消滅したポンペイの街くらいです。これでローマ水道は終わりにさせてもらいます。本当に長々と・・。最後まで全部読んでくださった方、感謝です。Back number 古代ローマ水道 10 (イングランド・バース編 3) 終章リンク 古代ローマ水道 9 (イングランド・バース編 2)リンク 古代ローマ水道 8 (イングランド・バース編 1) リンク 古代ローマ水道 7 (スペイン・セゴビア)リンク 古代ローマ水道 6 (イスラエル・カイザリア)リンク 古代ローマ水道 5 (チュニジア・ザグーアン)リンク 古代ローマ水道橋 4 (水道管とエフェソス)リンク 古代ローマの水道橋 3 (フランス・ニーム 2)リンク 古代ローマ水道橋 2 (フランス・ニーム 1)リンク 古代ローマ水道橋 1 (こだわりの水道建築)その他リンク 古代ローマの下水道と水洗トイレリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 (帝政ローマの交易)
2009年06月05日
閲覧総数 2404
-
47

ケルト(Celt) のドラゴン
Break Time(一休み)ちょっと寄り道です (;^_^A前回シティの紋章であるドラゴンの話をしましたが、本当のドラゴンの出所はどこか? 気になって考えていました。ケルト(Celt) のドラゴンウェールズの赤い竜の伝説ケルトに伝わる魔除けのドラゴンヴァイキング船のドラゴンシティの紋章の柄についてはセント・ジョージ(聖ゲオルギウス)の退治したドラゴンと言う事に(公式発表)落ち着きましたが、実はもとはウェールズを出身とするテューダー家の流れをくんで造られた紋章だったと言われています。ウェールズの赤い竜の伝説ウェールズの国旗(ウィキメディア・コモンズより)白と緑の二色の旗の上にウェールズの象徴である赤い竜(竜の図に規定は無し)ウェールズではすでに9世紀にはドラゴンが象徴として使用されていたと言われ、彼らの赤い竜に対する思いはもはや民族のアイデンティティー(identity)になっています。ドラゴン伝説 1 (赤い竜と白い竜の戦いの伝説)赤い竜が侵略者からブリトンの土地を守る・・と言うあらすじです。ケルト系ブリトン人の守護神が赤い竜。対して侵略者は白い竜を守護とするゲルマン民族(サクソン人とアングル人)つまりこれは実話の戦いを竜伝説で比喩した話となっています。ローマ帝国の属州ブリタニア(ブリトン人の土地)はローマの撤退後に領土の取り合い合戦が始まります。ブリタニアを奪還して土地を守ろうとするブリトン人と新たな侵略者サクソン人のそれぞれの軍旗から「赤い竜と白い竜の戦い」と呼称された伝説ができたと考えられています。ドラゴン伝説 2 (ドラゴンの封印とドラゴンの再来)ローマ以前にブリトンを統治していた王とされるking Ludは、暴れる両者の竜を穴に埋めて封印し、戦いを止めた。が、その封印が解かれる時、再び戦いは始まる・・と言うあらすじです。封印はブリトン人とサクソン人の戦いが終わった事を意味します。それは実際ヴァイキングのブリトン進行に対処する為に彼らが連合し、一時停戦。しかし伝承通り封印は解かれ、戦いは再び起きる事になります。(史実)ドラゴン伝説 3 (マーリンとアーサー王)封印が解かれ、再び地上にドラゴンが現れる事を予言したのが、魔術師マーリンです。そして「アーサー王が白い竜を退治した時に戦いは終わる」と予言。伝説では予言通りに赤い竜の元でアーサー王は勝者となり、土地を守り、赤い竜はアーサー王の象徴となった。ウェールズでのドラゴンに対する特別な思いは、そんな幾多の伝説とアーサー王が同じケルト系ブリトン人である・・と言う誇りにより国旗になった・・と言うわけです。ケルトに伝わる魔除けのドラゴンアーサー王の伝説は世界的に有名な話ですが、実際の所実在人物かどうか定かではありません。これは各地の伝承が吟遊詩人によって語り継がれ、ロマンス性が加えられて著書となり、物語として完成した話なのです。もっとも誰かしらモデルがいたとも考えられます。それはローカルの名君だったかも・・。ところで物語の中でアーサー王は金色の竜(ドラゴン)の軍旗を掲げていた。・・気がします。実は考えているうちにドラゴンの出所に思い当たる所がありました。それは3年前に特集した「ヴァイキング」に出て来る竜頭です。もしかしたらドラゴンの発祥はヴァイキング船の船首につけていた守り神。竜頭から来ているのではないか? と思ったわけです。中世流行した時のアーサー王は中世の騎士の姿で挿絵されてしまったが、本当のアーサー王の時代は6世紀頃の話です。赤い竜と白い竜の戦いは軍旗ではなく、もとは船首についていたトラゴン・ヘッド由来だったのでは?島のケルト人たちが乗っていた船はいわゆるヴァイキング船だったかも・・と仮説してみた。インド・ヨーロッパ語族の民族移動実はブリトン人はローマ時代に土地に定住していた島のケルト人です。その祖はインド・ヨーロッパ語族ケルト語派の民族です。つまりアーサー王は、島のケルト人と考えられます。そしてまたゲルマン人もまたインド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派の民族です。つまりゲルマン民族であるサクソン人もアングル人も同じ先祖を持つ者。さらに別の侵略者ヴァイキグもまたインド・ヨーロッパ語族(ゲルマン語派)を祖先とする民族です。つまり祖先を辿ると出自がみんなインド・ヨーロッパ語族の同族だった事がわかります。(おそらく民族の伝統文化もそんなに変わりはなかったはず。)その違いはと言えば、民族の移動時期と移動のルート。長い時間の混血です。2010年02月のヴァイキング特集で詳しく書いています。「ヴァイキング 1 (民族移動) 」「ヴァイキング 15 (北方ゲルマン人の民族移動総括) 」リンク ヴァイキング 1 (民族移動)リンク ヴァイキング 15 (北方ゲルマン人の民族移動総括)アナトリア(現トルコ)あたりにいたインド・ヨーロッパ語族の先祖達は移動と分裂を繰り返し大陸を移動して行きます。BC6100年頃ケルト語と分離し、BC3400年頃ゲルマン語派やイタリック語派の民族が誕生。いったんヨーロッパ中北部に移住した彼らは後にまた分離していきます。そんな彼らの民族の大移動は数世紀毎に何度か確認。2世紀から5世紀のゲルマン民族の移動もその一つです。ヨーロッパ中北部に定住した民族。南に下りローマで傭兵になってローマ文化を吸収した民族もいる。ローマを相手に交易した者達もいる。ラテン王国を築いたゴート族もゲルマン民族です。スカンディナビア半島や北海沿岸に定住した彼らはノルマン人(Norman)「北方の人」になり、8世紀初めから11世紀初頭iに再び民族移動。ヴァイキングと呼ばれる者たちもその一部です。2度に渡るイングランドの征服でイングランド地方に定住した者もいる。それがいわゆるブリトン人です。北方から食べ物を求めてさらに西にルートをとった者は飢餓でほとんど滅んでしまった。アメリカ大陸に到達した民もわずかにいたが・・。歴史の中に悪く言われがちなヴァイキングの登場はほとんど無い。一つにはキリスト教化されて別の民族になってしまっている事もあります。逆にキリスト教に改宗しなかった者は異端として敵になりヴァイキングとして恐れられた。・・と言う事なのでしょう。実はアーサー王自体がキリスト教に改宗した王なのです。そう言う意味では、アーサー王はブリトンの王であるけれど、ケルトの王ではなく、キリスト教徒として王位についている。後世のアーサー王伝説は間違いなくキリスト教色を強める物語に変化していると言えます。ヴァイキング船のドラゴンヴァイキング船の船首に付けられている守り神、モンスタ-・ヘッドの別名は「竜頭柱」「ヴァイキング 3 (竜頭柱とヴァルハラ宮殿) 」以前紹介した写真を改めて載せました。船の船首にとりつけられる守り神のドラゴン精密なケルト文様の細工がほどこされた船首に取り付けるドラゴン・ヘッドはまさしくアーサー王の父の名前ユーサー・ペンドラゴン(Uther Pendragon)「竜の頭」と一緒。「竜頭柱」の首の部分上に紹介した「竜頭柱」は全てノルウェーのオスロにあるヴァイキング船博物館で撮影した写真です。ノルウェー、グドヴァンゲン(Gudvangen)にかつて復元されていたヴァイキング船写真左の船首には簡単だがドラゴンの彫刻が施されている。これこそがヴァイキング船の象徴。かつてイングランド含めてたくさん存在していたヴァィキング達の資料は今やノルウェーにしか無い。ところでグラストンベリー(Glastonbury)で発見されたと言うアーサー王のお墓ですが、(本物とは断定できないしウソかもしれない)その遺骸は船の聖棺に王妃と共に葬られていたと言います。この船に死者を葬る慣習もヴァイキングのものと一致します。やはりアーサー王がヴァイキングと同民族のケルト人である事は間違いなさそうです。。
2013年07月21日
閲覧総数 1654
-
48

新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)
ウイーンのマルタ教会の他、ロードスの写真も入れ変え中身も多少追加しました。書き換えたのでお約束。「新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)」にしました。今回はテンプル騎士団の紹介が目的だったので The First Crusade(第一次十字軍)から騎士修道会設立までのいきさつををメインに紹介しました。十字軍についてはその後も何度かの遠征があり、欧州の諸王達も利権をかけた隊を派遣しているので複雑な歴史がたくさん続きます。が、それはまたどこかで関連してきたら取り上げる事にしてとりあえず聖ヨハネ騎士修道会の最後を簡略に紹介して終わります。新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)アトリビュート(attribute)「キリストを現す獅子」流れ流れて・・聖ヨハネ騎士修道会は?ロードス島(Rhodes)ロードスの騎士(Knights of Rhodes)ロードスの騎士からマルタの騎士にウイーンのマルタ教会(Maltese Church)現在の聖ヨハネ騎士修道会正式名称アトリビュート(attribute)「キリストを現す獅子」マルタ教会の天井のクロッシングに付いていたライオンの彫物。これの意味がわかりました。通常ライオンと言えば福音書記者マルコのシンボルでありアトリビュートとなる物と連想してしまうが、ここでは全く別の意味で使われていた。ライオンは中世にはすでに百獣の王と認識されていた事から「全人の王キリスト」にもなぞられていたらしい。また、ライオンは眠っている間もまぶたを閉じ無い動物と考えられていた? 悪魔が「主の羊(人間)」を盗む事が無いよう常にキリストが見守っている。と言う考えからもキリスト自身になぞられる存在らしい。図は、子ライオンと共に描かれている。生まれて間もく目を開かない子ライオンに向い吠えて蘇(よみがえ)らそうとしている光景らしい。その行為もまたキリストが死して神の声に蘇った事が掛けられていると言う。因みに羊は人民一般を現すアイテムです。キリスト教におけるアトリビュート(attribute)とは、その物が何か別の意味を持って表現されている。と解釈される存在です。例えば聖人が何かを持っているとすると、その持ち物で誰かわかるような象徴的なアイテムがアトリビュートと言えます。以前紹介した使徒ペテロのアトリビュートは鍵(かぎ)。それは彼が天国の門の鍵をキリストから預かった人だからです。キリスト教では、いろんなアイテムがアトリビュートとして使われています。解説の本も出ているくらい数が多いし、一つのアイテムで幾つも意味を持つ場合もあるのでややこしいのです。おそらく時代の認識も違ったからかもしれません。さて、今回はロードス島へ渡ってロードスの騎士となった聖ヨハネ騎士団です。エルサレム(Jerusalem) → アッコ(Acre) → キプロス島(Cyprus) → ロードス島(Rhodes) → マルタ島(Malta) 流れ流れて・・聖ヨハネ騎士修道会は?一時は聖地を奪還したものの、やがで再び聖地はイスラムの手に落ちてしまう。エルサレムにいた十字軍の騎士修道士はエルサレムが陥落すると、王国の首都を北のアッコ(Acre)に移動。1291年、そのアッコ(Acre)も陥落。十字軍国家は中東の拠点を失い地中海の島に逃れてイスラム勢力と戦う事になる。テンプル騎士団もヨハネ騎士団もキプロス島(Cyprus)に待避。※ ルアド島に逃げて立てこもったテンプル騎士もいたが1312年テンプル騎士団は解散。キプロス(Cyprus)島はイングランドのリチャード1世がたまたま占領してエルサレム王が買い取った場所であり、一応十字軍国家の属州であった。が、キプロスに逃げた段階でテンプルは主要騎士を失っていたので(事務職ばかり?) ほとんど機能していなかったようだ。一方、聖ヨハネ騎士団はキプロス王国の内紛に巻き込まれ島を出る。そして当時東ローマ帝国(ビザンツ帝国)領であったロードス島(Rhodes)に渡るのである。1309年、聖ヨハネ騎士団はロードス島を占拠してそこに本拠を移すと名前もロードス騎士団(Knights of Rhodes)と呼ばれるようになる。ロードス島(Rhodes)現在はギリシャ共和国の所領となったロードス島は極めてアナトリア半島に近いドデカネス諸島にあり、ロードス・シティは島の北端に位置。ホメロースの詩にも謳われる古代都市だったロードス・シティはBC408年に建設された街。14世紀から15世紀にかけて聖ヨハネ騎士団が街を占領中に城塞を築き街そのものを要塞化した。城壁の上から撮影した市街同じく城壁の上から撮影。大型客船が多数寄港している。聖ヨハネ騎士修道会の遺構はどこよりもこのロードス島に多い。ロードス・シティの旧市街はそれ自体がこの島の一番の観光名所になっている。中世の城塞都市の特質が最も良く残された場所として1988年「Medieval City of Rhodes(ロードスの中世都市)」ユネスコの世界文化遺産に登録。11の門と何層にもかさなる厚い城壁まるで万里の長城のように延々続く城壁は、その上を歩いて回る事ができる。ロードスの騎士(Knights of Rhodes)聖ヨハネ騎士団がロードス島に本拠を移す(1309年)と1522年オスマン軍によりロードスを追われるまでの200年ちょっとの間に彼らはここにテンプル騎士団の財産を使って鉄壁な要塞を築くのである。もともと巡礼者の病院として発展した彼らは病院としての慈善事業を進めながら戦士として戦ってきたが、ここに来て海軍力も保持する事になる。ロドス・シティは高い城壁で囲われた街である。その城壁は区分毎に郷土別に部隊が守備していた。Langue(ラーング・舌)部隊フランス(仏北部)、オーヴェルニュ(仏中部)、プロヴァンス(後の仏)、アラゴン(後のスペイン)、カステーリャ(後のスペイン)、イタリア、ドイツ、イギリスもともと騎士団は寄り集まりの為、言語もバラバラ。その為に戦時は言語により部隊が分けられた。全体にはフランス出身者が多かったので第1公用語はフランス語。第2公用語はイタリア語。騎士団通りには、Langue(ラーング・言語?)部隊毎に館が建ち並んでいる。騎士団長の館1856年に火薬庫の爆発事故で崩壊。1937年にイタリア人によって再建されるも歴史的な正当性を欠いたリノベーションになったと言う。ロードスの騎士からマルタの騎士に1522年、オスマン帝国の第10代皇帝スレイマン1世の軍勢の前にロードスは陥落。ロードスを追われた聖ヨハネ騎士団(ロードス騎士団)はしばらく流浪の民となり、1530年に神聖ローマ皇帝カール5世よりマルタ島の賃貸契約が締結。賃貸料・・・鷹一羽マルタ島に渡ってさらなるイスラムからの攻撃を受ける。キリスト教徒側からするとイスラム勢力と一括りにしているが、実は十字軍が戦ったイスラムは一つではない。ルイ9世を捕虜として捕らえ十字軍を撃退したのはマムルーク朝であったが、騎士団が地中海に出てから戦うイスラムはオスマン帝国になる。オスマン朝(1299年建国?)はアナトリアの小国から発したイスラム王朝であるが、やがてバルカン半島のキリスト教圏や、同じイスラムのマムルークの所領など西アジア、北アフリカのイスラム教国を征服して地中海の過半を覆う大帝国に発展。そんな勢いのある軍隊の前にもはや島一つの騎士団はそれほど相手にされず、むしろ台頭してきたモンゴル帝国の方が驚異だったようだ。1565年の「マルタ包囲戦」はかろうじて撃退するも1798年6月13日敵はオスマン帝国でなく、ナポレオンの艦隊にあっさり降伏してマルタをあけ渡す。マルタ騎士団はここに終わる?しかし聖ヨハネ騎士修道会はなぜか今も生き残っている。居所を失った聖ヨハネ騎士団は、ロシアに助けを求める。1801年にロシア皇帝パーヴェル1世を騎士団総長にして生き延びるのだ。1834年に本拠はローマに移り慈善団体として、現在世界の約94か国と外交関係を持ち、在外公館を設置。国際連合にオブザーバーとして参加する国際組織になっているのである。(⌒▽⌒;) オッドロキー ウイーンのマルタ教会(Maltese Church)正式名は洗礼者ヨハネ教会(Church of Saint John the Baptist)聖ヨハネ騎士団をルーツとする教会です。教会は、カールスプラッツ駅からオペラ座の横を通りシュテファン大聖堂に至るケルントナー通り (Kärntner Straße) 沿いで偶然発見。最初は聖ヨハネ騎士団の後方支援の事務所として1217年頃に建てられた場所らしい。現在の建物は15世紀半ばに建立? さらに1806年に再建された。第一次世界大戦後、財政難で一度手放され、1960年に買い戻されたと言う。下は、エントランス上部とパイプオルガン1730年、祭壇画はJohann Georg Schmidtにより描かれた。現在の聖ヨハネ騎士修道会正式名称エルサレムの聖ヨハネ病院の騎士団 (Hospital of Saint John)はその過程からいろんな呼び方がされてきた。ロードス騎士団(Knights of Rhodes)マルタ騎士団(Knights of Malta)聖騎士団 ジョン(Saint John)現在の正式名称はKNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTAロードスおよびマルタにおけるエルサレムの聖ヨハネ病院独立騎士修道会騎士修道会おわり騎士修道会バックナンバーリンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre) 1リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)
2013年08月25日
閲覧総数 548
-
49
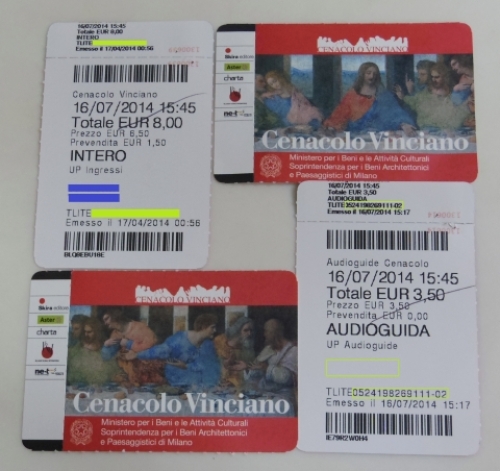
修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復
ウィキメディアからのきれいな写真に変更しました。やはりポスターでは色調が・・・。前は無かったのです。基本撮影ができない所なので、どこかが許可どりして撮影した写真なのでしょう。非常に助かります。今回トイレ事情が一番悪かったのがイタリア、ミラノでした。欧州の常識は、トイレが少なく、かつ有料が原則。トイレがタダなのは空港や美術館の中、レストランくらい。駅のトイレも有料です。だから逆にトイレでしない人がいるから街の衛生が悪くなる現状もあるわけです今回のサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院もトイレ事情が悪い所の一つです。教会にトイレが無いのはあたりまえ。カフェで飲食すればタダで借りられますが、トイレだけなら有料。近辺にこれといったカフェもあまり無いところです。チケットを持っていて「最後の晩餐」を見学した人は出口のお土産コーナーにあるトイレを借りる事ができますが清潔・・とは言えないトイレでした。(便座が無い洋式が一つと、汚れたアラブ式。しかも男女共用)因みに近所のカフェのトイレも便座がありませんでした。どうもイタリア人は女性でも便座に座らずにするようです。行く前にどこか比較的きれいな所ですませて行く事を勧めます (;^_^A修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復完成後から崩れ始めた壁画ナポレオンが発注した複製モザイク画事務所で受け付けしてもらったチケット。(2人分)予約した人の名前が入っている。2枚は当日借りたオーディオ・ガイドのチケット。オーディオ機器は、借りる時にIDを預け返却の時にIDを返してもらう。CENACOLO VINCIANO(最後の晩餐)事務所待合室わずかな座席しかないので次の回に入る人で一杯。(見学は15分で入れ替え)CENACOLO VINCIANO(最後の晩餐)の壁画はもちろん撮影禁止。(本から撮影)部屋の広さに呼応している遠近方、食堂の長さを1.5倍にしている。(実際はもっと薄暗い)当初質素な食堂は、ブラマンテか? あるいはダ・ヴィンチが絵画との調和を考えてルネッサンス風に改築。また、後世、戸口を付ける為にキリストの足が描かれていた部分が壊されている。さらにダ・ヴィンチは壁画を描く壁の裏を砂袋を入れた袋を並べて壁自体の保護補強をしている。そのおかげで1943年の爆撃で食堂の東の壁と天井が崩れ落ちたのにこの壁画のある壁は生き残った。まさにミラクル教会の方の売店で買ったポスターから撮影下はウィキメディァから前は無かったのです。近年の修復は1977年~1999年まで行われた。この修復はできるだけダ・ヴィンチのオリジナルに戻す事とされ、従来の修復の概念に反した為に物議を醸したようですが、保存と美的観点から、この修復計画は成功したようです。何しろ18世紀に行われた修復では顔、表情、物腰、色までゆがめた上にダ・ヴィンチが陰影によって表現した時間軸や使徒達の属性をも塗りつぶしてしまっていたようです。要するにダ・ヴインチの作品か? と言うほど変貌していたようだ。ダ・ヴィンチはこの絵画を科学的考察により描いている。多才なダ・ヴィンチはこの頃、力学や弾道学など物理学の研究もしている。解剖学の勉強はデッサンに生かされ、建築学、幾何学と彼の興味は枚挙(まいきょ)にいとまがなかった。彼はただの芸術家では無かったので、この絵の中には彼の実験がたくさん閉じ込められている。それが近年の新しい修復により、500年前の姿が取り戻されたのである。今、ダ・ヴインチが見る者に伝えたかった真実を見せてくれているのである。限りなく、オリジナルに戻すと言う修復方法は、絵画においては、今後の修復の基本になる事だろう。下もウィキメディアから色彩は飛び、壁もかなり剥落しかけているが、人物にダ・ヴィンチらしさが感じられる。完成後から崩れ始めた壁画しかし、実際オリジナルに戻す事はかなり難しい問題があった。普通のフレスコ画で描かれていないこの作品の元の壁がどこまで残っているか?上の加筆された壁を取り除いた時にどれだけオリジナルが残っているかは、やってみなければ解らない一つの賭けだったようだ。上の写真はもちろんポスターを写しとったものであるが、壁や色の剥落がこの写真からも解ると思う。おそらく、私達が今まで本などで見ていた修復前の色あざやかな作品とは別物になっている事だろう。壁の土台は石膏2層の壁。それにテンペラ画で描かれている事が科学的解析で判明。(数カ所油性)通常フレスコ画の場合、まだ湿った状態の漆喰層の上に絵の具を染みこませて色を付けるのが一般的。だが、彼は後から絵の具の上塗り(加筆)による効果を考えて普通のフレスコ画の技法では描かず、テンペラの絵の具を使用したようだ。その実験的趣向のせい? あるいは湿気のせいか? 「最後の晩餐」は完成後から20年目には早くも傷み始めたと言う。さらに50年すると壁画はもっと悲惨な状況になり、修復の仕方で大論争も起きている。1770年の修復ではユダ、ペテロ、ヨハネ、キリスト以外の使徒の元絵そのものを全て塗りつぶして書き換えられたと言うナポレオンが発注した複製モザイク画写真は、ウイーンのミノリーテン教会(Minoriten Kirche)に置かれている「最後の晩餐」のモザイク画である。これは本物の複製として造られたモザイク画らしい。制作年は1809年。製作者はGiacomo Raffaelli。依頼者はナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)このモザイクはナポレオンが皇帝時代に発注してパリに運ばれるはずだったものだそうだ。完成時にナポレオンが皇帝ではなくなっていたので、フランツ1世が買い取りウイーンに運ばれ、どう言う経緯か解らないがここに飾られる事になった。※ 確かにナポレオンはサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院に来ている。さすがに壁画は持ち去れなかったが、教会の聖母像前から銀の燭台(しょくだい)を持ち去ている。上のダ・ヴィンチの作品とは似て非なるもの。非常に細かなモザイクでカメラでアップしてもモザイクには思えない。モザイクの腕はすばらしいが・・。制作年から推察すると、この作品はひどい修復時代の作品がモデルになっている。構図だけが最後の晩餐を示しているもののダ・ヴィンチの作品としては見る影もない。もし、これが修復以前の最後の晩餐の姿であったのなら、やはり真実の姿に戻してくれてありがとう。・・と、言いたいです。m(_ _)m アリガトォ~★関連back numberリンク ミラノ(Milano) 1 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 1)リンク ミラノ(Milano) 2 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 2 聖堂内部)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2 (仮予約と支払い)
2014年08月03日
閲覧総数 2692
-
50

オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)
タイトル変更長期旅行では、よく利用していたアメリカン・エキスプレスのドル・トラベラーズ・チェック(T/C) が今年2014年3月31日に日本での販売が終了していましたトラベラーズ・チェックはそもそも海外渡航中の現金の盗難や亡失といったリスクを回避する為にできた旅行小切手でしたが、昨今は国際キャッシュカードやクレジットカードの普及に加えてデビットカードが現れ需用が一気に激減していたようです。これからはクレジットカードか? デビットカードか? あるいは電子マネーか?デビットカードは自分の口座にお金さえあれば即時決済です。だから買い物をする時点で口座にお金が無ければならないが、購入の時のレートで決済されるから納得が行くのが利点。一方クレジットカードでは、決済の時期が購入時と異なる為に為替のレートが変わってしまう問題があった。(ヴィトンなど高額の品物を買うとレートが高い時に決済されていた。)またクレジットカードはお金が無くても借金できる利点がある一方キャッシングすると実はものすごく高利。(気付いていない人が多い。)逆にデビットカードはクレジットカードの取得が困難な若者でも口座開設と共に発行されるが、即時決済のリスクが生じるし、クレジットカードと違って24時間利用できない場合があるそうだ。(即時決済のリスクとは、店員の入力ミスによって金額に重大な問題が生じた場合でも一度デビットカードで決済すると(海外の場合)現金の時のような返金は難しい・・と言う事。)実はデビットカードも微妙な展開。電子マネーもBitCashの問題があったから今後はわからない。さてさて、大金を移動する人はこれから銀行送金か、それができなげれば危険ではあるがキャッシュを持ち歩くしかないのかな?さて、今回はレールジェット(railjet)の座席予約について・・と、ダイニング・カーで提供される料理を紹介。オリエント急行はともかく列車内レストランとしてはかなりメニューも豊富で何より味が良かったのですオーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)座席予約の確認列車レストランのメニューDining Cabinちょっとした調理室を備えた厨房のあるキャビンにはテーブルが4人がけ4つと二人がけ1つある。従来の列車はテイクアウトが中心のビストロであったが、レールジェット(railjet)では完全な食堂車レストランになっている。またBusiness(ビジネス)やテーブルのあるFirst Class (1等客室)には座席までのサービスが付いている。Economy Class(2等客室) に関しては、新幹線のような車内ワゴンサービスが来ていた。座席予約の確認ちょっと見えにくいが、天井部に赤い〇と→でしるしをしました。このような表示がされている席は、予約席になっています。ウイーンからザルツブルクまでは誰かが指定している席・・と言うサインです。これ以外の区間であれば座れます。基本、こちらの座席予約は日本のような車両単位になっていません。(日本なら自由席車両、指定席車両と分かれている。)ですから指定席予約をしていない人は、First Class あるいはEconomy Class の中で空席のところを好き勝手に座る事が可能です。(始発駅なら早く入って座席をとれるが途中駅からの乗車なら予約しておいた方がよい。)First Class の指定料金は一人3ユーロで意外に安い。尚、チケットの値段は同じ区間でも取り方によりバラツキがありすぎでした。例 ウイーン~ザルツブルク (317km) 所要2時間40分から3時間 乗車運賃(特急料金含) First Class 1人、83.20ユーロ Economy Class 1人、47.50ユーロこれを3ヶ月近く前に予約するとFirst Class で1人34ユーロになりました。(早割がある。)どこの国でチケットを購入するか?その国にはどのような割引サービスがあるのか?当日や前日は定価になりますが、うまいことチケットを予約購入するとお得に旅ができるのです因みにドイツには土日割引があります。(オーストリアには無い)そのかわりオーストリアにはレールジェット(railjet)などの特急や急行は除外されますが2~5人のグループで、全員1日乗り放題(月~金am9:00~翌am3:00)で35ユーロと言う(Einfach Raus Ticket)格安チケットが発売されています。列車レストランのメニュー最初に座席にメニューが配られました。列車内レストランはHenry am Zugと言うウイーンの会社が運営。この会社は他の列車にも提供しているようですが、おそらくレールジェット(railjet)はここが一社独占のよう。※ Economy Class (2等客室)はもう少し小ぶりな冊子が椅子の前に挟まっていた。自分達は予約の段階で向きあわせの固定テーブル座席を指定していたので席でサーブしてもらえた。値段は割と安い。しかもパン付きで非常においしかった ほぼイメージ通りこのサンドイッチは感激。別の乗車時に再び注文して2度も食べた 朝食セットメニュースパークリングワイン付き朝食カレーやシチュー、スープなどもあるし、ホットサンドやサラダもある。キッズ・メニューカプチーノ 2.8ユーロ左のプレッツェルはよくわからないがサービスでもらった。注文した人だけなのかは不明。飲み物はソフトドリンク7種、ビール5種、ワイン&スパクリング8種、コーヒー&ティー9種など種類も豊富。値段もリーズナブルで列車内の割にはむしろ安いかも・・。尚、値段には20%~10%の付加価値税が含まれて表示されている。テーブルでのサービスだったので給仕さんにチップは1割ほどのせて渡したが、Dining Cabinで直接購入するならそれはいらない。また乗りたいな・・と思える列車でした。バックナンバーリンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)ザルツブルグの所でQBBの発券機を紹介しています。リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)
2014年08月25日
閲覧総数 4721
-
-

- 北海道の歩き方♪
- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…
- (2025-11-10 14:20:41)
-
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…
- (2025-11-14 00:00:17)
-
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 道の駅めぬまにあるバラ園に行きまし…
- (2025-11-15 11:08:11)
-







