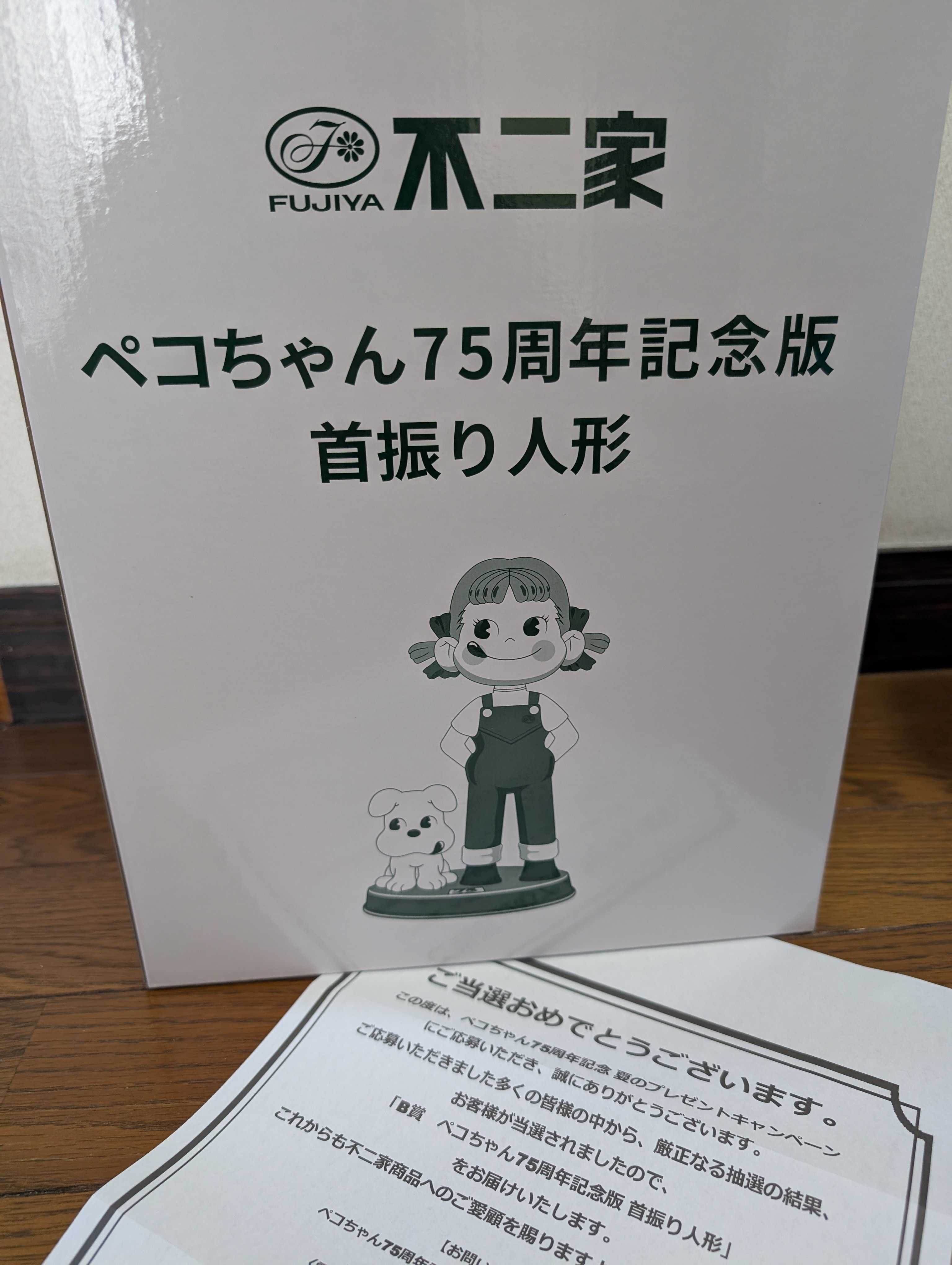2013年10月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
原理運動の放送を中止した山形放送
1976年7月3日の『ワイド山形』(12時から13時)で放送する予定の「わが子を返して!“原理運動被害者父母の会”の怒り」が突然中止になり、内容が差し替えられた。山形放送は中止の理由を、原理運動側の出演を申し入れたが断られたので、一方の意見だけを放送するわけにはいかなかった」と説明したが、出演拒否に備えて、原理運動に参加している若者たちに事前にインタビュー取材をしていた事実が確認されている。■メディア総合研究所編『放送中止事件50年 テレビは何を伝えることを拒んだか』花伝社(メディア総研ブックレット10)、2005年 による。■関連する過去の記事 みちのく銀融資問題を放送しなかった青森放送(2013年10月30日) 系列で唯一自衛隊番組を放送した青森テレビ(2013年10月30日) 昭和47年秋田放送の人気番組打ち切り事件(2013年10月29日)
2013.10.31
コメント(0)
-
みちのく銀融資問題を放送しなかった青森放送
1991年(平成3)12月4日。夕方6時30分からの『RABニュースレーダー』は、この日「みちのく銀行が暴力団組長に融資」をトップ項目で報道する予定だったが、社長の判断で放送を中止した。中止の理由について、坂井公介報道局長は「大事なスポンサーでもあり、社長と相談のうえ記事の報道を差し控えた」と述べたため、青森放送労組は6日、他の報道機関はこのニュースを扱ったことから、不信を招いた社長が自らを処分するよう抗議文を会社に提出。奈良和磨社長は、現場を尊重するのは当然で、諸会議等で十分な議論を深めていくようにしたいと答えた。■メディア総合研究所編『放送中止事件50年 テレビは何を伝えることを拒んだか』花伝社(メディア総研ブックレット10)、2005年 による。■関連する過去の記事 系列で唯一自衛隊番組を放送した青森テレビ(2013年10月30日) 昭和47年秋田放送の人気番組打ち切り事件(2013年10月29日)
2013.10.30
コメント(0)
-
系列で唯一自衛隊番組を放送した青森テレビ
1973(昭和48)年のこと。木原光知子氏をレポーターに仕立てて各地の自衛隊を探訪する自衛隊宣伝番組シリーズ『ミミの体当りレポート』が、各地の放送反対運動で予定していた放送局に拒否されて、ただ一局、青森放送のみが放送に応じた事件。放送開始は10月。第1回は、ニュージーランドに旅行したミミがウェリントンで海自の遠洋航海部隊に出会う『出会い』。日経映画社の手で順調に制作は進んだが、前年に祭の裏方としての自衛隊員を描いた『祭りをつくる人びと』を、スポンサーを覆面にして放送したフジテレビが、そのことで批判を受け、その時の反対運動に懲りて今回は放送を降りたため、フジ系列のローカル局も右ならえ。あわてた代理店の「大広」はU局を説得し、青森テレビからテレビ宮崎まで全国17のU局が一度はOKして、全国ネットが成るかに見えた。そこへ長沼ナイキ訴訟判決で、札幌地裁の福島裁判長は自衛隊違憲の明解な判断を下したことから、放送反対の運動が全国で高まり、U局も続々放送中止を決定。残るは青森テレビ一局になった。10月27日、青森テレビは市民の抗議を恐れてバリケードを築き、警官隊に守られて『ミミの体当りレポート』の放送を開始した。なお、同年末から74年にかけて秋田、山形、静岡、愛媛などのU局で同番組の放送計画が復活。提供防衛庁を堂々名乗って息を吹きかえした。■メディア総合研究所編『放送中止事件50年 テレビは何を伝えることを拒んだか』花伝社(メディア総研ブックレット10)、2005年 による。■関連する過去の記事 昭和47年秋田放送の人気番組打ち切り事件(2013年10月29日)
2013.10.30
コメント(0)
-
昭和47年秋田放送の人気番組打ち切り事件
秋田放送の人気番組『唄っこで勝ち抜きまショー』の公開録画が本荘市文化会館で開かれ、挑戦者が新チャンピオンに選ばれたところで、長い間お楽しみいただいたこの番組は都合により今回をもって終わる、と司会者が挨拶。突然の打ち切りに満場の来客は驚いた。前年4月の秋田市長選挙で保守系の萩原候補が、4選を目指す革新系の川口候補を破った。ところが選挙戦で萩原陣営が『週刊実話』を買収して川口市長の中傷記事を書かせ、それを大量に市内にばらまいたことが暴露され、地元の野党や労働組合を中心に、萩原市長リコール推進連盟が結成され、この年の暮れにリコール住民投票が行われる予定であった。推進連盟の代表委員が、民謡研究家として知られる大島清蔵氏。『唄っこ』の審査委員長でもあった。秋田市は秋田放送の三番目の大株主。萩原市長派が秋田放送に圧力をかけ、大島氏はこの日の録画を最後に委員長を降りることになっていた。これに対し、秋田放送労組や地元労組、市民団体が、リコール運動に対する介入、報復であるとして反対運動に立ち上がったために、秋田放送は人気番組そのものを打ち切ってしまったもの。■メディア総合研究所編『放送中止事件50年 テレビは何を伝えることを拒んだか』花伝社(メディア総研ブックレット10)、2005年 によるさて、上掲書には、秋田放送に関してもう1件が収載されている。1987年(昭和62)11月14日のこと。夕方のニュース番組『ABSニュースワイド』で、地元ローカル紙の秋田魁新報社の関連会社である岩城総合開発が経営するゴルフ場「岩城カントリークラブ」の改修工事に県費約7700が使われていた疑惑を取り上げて報道しようとしたところ、オンエア直前になって報道局長からストップがかかり、放送中止に追い込まれた。中止になったニュースの内容は、県議会の農林水産委員会に県側が工事計画の説明を行ったのを受けて、同委員会が30日にも現地視察を行うことになったことを伝えるもので、NHKのローカルニュース枠では、同じ問題をトップで報道しており、秋田放送報道部も当日朝に岩城カントリークラブのVTR取材を済ませ、昼には報道局長、報道部長と担当記者の間で夕方のニュース放送を確認して準備を調えていた。秋田放送労組の調べによると、放送直前になって秋田魁新報社より報道局長に電話が入り、魁新報社編集局次長の要請として、30日の現地調査まで放送を控えるようにとの内容が伝えられ、報道局長がこれに応じて中止命令を出したのだという。秋田魁新報社は秋田放送の筆頭株主で、秋田放送の歴代社長もすべて魁新報社の出身者で占めている。
2013.10.29
コメント(0)
-
風船爆弾放流の地 勿来関
秋から冬にかけて日本上空を強い偏西風が吹く。太平洋の上空8千メートルから1万2千メートルの亜成層圏に、最大秒速70メートルのジェット気流が北米大陸に向けて流れていく。大戦中の1944年秋から日本軍はアメリカ本土に向けて風船爆弾を放った。敗色強まる日本が、米国を撹乱する秘密兵器として、気球に爆弾をつり下げてジェット気流で運んだものである。約9000個が放流され300個前後が米本土に着いたとされる。この極秘の「ふ号作戦」を実行した風船放流地の一つが、いわき市勿来関麓だという。他には千葉県一の宮海岸と北茨城市大津町五浦(いづら)。勿来関にほど近い五浦には、大本営直属の風船爆弾の作戦部隊が置かれていた。丘に挟まれ現在は田圃に復元されている沢に、兵舎、倉庫、水素タンクなどが設置された。海岸沿いには放流地跡の碑文がある。精密な電気装置で爆弾と焼夷弾を投下した後、直径10メートルの気球部は自動的に燃焼する仕掛けであった。球皮は、こうぞの和紙をコンニャク糊で5層重ねて貼り合わせたもので、手間が掛かり、女子学生や女子挺身隊が動員された。気球を遠くに飛ばすには、夜をどう乗り切るかが課題。夜は上空の気温が低下し気球が縮み水素も漏れていく。そこで、風船爆弾には浮力が下がると自動的におもりを落とし、高度を維持する装置が付けられた。気圧計で変化を検知すると歯車一個分づつ回転盤が回り、一定以上の高度が下がる(気圧が上がる)と電気スイッチで砂のおもり(バラスト砂)のひもを焼き切って落とす仕組みだった。爆弾は50時間程度で米国に着く。米国側の被害は僅少だが、山火事を起こしたほか送電線を故障させて原子爆弾製造を3日間遅らせたとされる。オレゴン州では森にピクニックに出かけた牧師夫人と日曜学校の子ども達の計6人が、不発弾に触り爆発のため死亡。このことはずいぶん年数が経ってから日本に伝わった。戦時中に作業をしていた元女子学生たちが心を痛めて慰霊に渡米したという。ワシントンの博物館には不発の風船1個が展示されている。アメリカが最も恐れたのは伝染性の細菌などの生物兵器。そのため、報道管制を徹底する一方で、バラスト砂を分析し、砂の採取地を日本の5か所に絞り込んだ。偵察機でついに放流地を探り当て、このため末期には風船爆弾はほとんどが上昇中に米戦闘機に撃ち落とされた。下記文献を参考にした。■左巻健男『面白くて眠れなくなる地学』PHPエディターズ・グループ、2012年風船爆弾の話は知っていたが、東北に隣接する北茨城市が秘密基地で、勿来からも放流していたとは、知らなかった。ネットで見てみると、勿来駅から内陸側の南東方向に伸びる専用引き込み線が建設され、倉庫や兵舎、砲台や防空壕などが配置された。また、数カ所の放球台が設けられ、今なお跡も残っているという。また、勿来関文学歴史館で風船爆弾の展示をしていたこともあったという。
2013.10.27
コメント(0)
-
日シリ初戦則本は奇策か 行くぞ日本一!
いよいよ今夜が初戦。関東地方では朝から台風27号の風雨が報じられているが、仙台の夜の決戦には影響がないだろう。さて、監督会議で予告先発の導入が決まり、G内海に対して、わがイーグルスは則本。大方の予想は初戦で田中と内海、第2戦が則本と菅野だったから、則本の予告先発はさまざまな憶測を呼んでいる。田中を全戦でリリーフ待機させる、ということはまさかあり得ない。先発の枚数が多いわけでもなく、中継ぎや抑えに不安を抱えているから、リリーフで勝つ試合は多くない。節目の試合で先発完投させて必ず勝つために田中を使うしかなく、余裕をみて特に後半戦でブルペン待機くらいだろう。あまり考えたくないが、田中に何らかの事情がある可能性も、一応ありうる。各紙の報道を眺めてみると、球団側が田中の疲労を考慮した、本人が万全の登板を希望しているから、というのが大筋の報じ方のようだ。CSでは月曜日(21日)に最終回を投げているから、中5日にして日曜の第2戦の必勝を期するということで、「理由」としては成立する。しかし、それは嘘ではないとしても、さらに意味のある「作戦」のはずだ。第2戦と第6戦なら万全な田中で確実に勝てる。第1戦を則本で取れば、連覇でドームに乗り込むので、シリーズの主導権を握れる。このような発想が考えられる。ただし、第2戦必勝から逆算するこの考えは、初戦をとるかどうかで大きく分かれるいわばギャンブルと言える。それでも、星野監督が自ら監督会議で予告先発制度を提案したことも考え合わせれば、一定の合理的な考えに基づくのではないか。次のように。巨人は内海、菅野の順番で来る。菅野は打てるが内海はどうか。それならば、巨人打線にとって初モノの則本に相手が手こずるはずだから、そのうちに、AJとマギーの爆発を待つ。シリーズ開幕投手を任せれば則本は期待に応えるだろう。レギュラーシーズンの開幕こそ黒星だが、ここで勝てば本人にも大きな自信になり敵地での第5戦も投げ勝つ可能性が高まる。つまり、2連勝する可能性が高く、そうすれば短期決戦の流れをイーグルスが掌握するという訳だ。ドームでの3戦目と4戦目は、美馬と辛島が先発するだろうが、青山、斎藤、長谷部、宮川などで何とか試合を作って、3勝2敗で、最悪でも2勝3敗で仙台に帰ってくる。かりに敵地で連敗しても、或いはギャンブル性のある開幕戦を落としていても、第5戦で則本を再び送りこんで絶対に仙台に帰ってくる。そうすれば、ホーム第6戦は田中で必勝。ここで最終勝利が星野監督の描く最高のシナリオだ。もし、第6戦で通算3勝3敗のタイとなる場合には、第7戦は美馬の先発に則本も田中もブルペン待機で、歓喜の日本一を取る。ここには、ホームグラウンドに戻ってからの田中の役割を重視している「作戦」が読み取れる。東北のチームとしての「勝ち方」も考えているのだ。私は、星野監督はCS直後からこう考えていたと思う。ホームの第6戦を田中で勝つことを基軸にして、若武者則本への信頼と打線の可能性を見抜いた上で、こう考えたのではないか。仙台で2つ最初に取る。そのために、則本を送り出すのだ。闘将の胸の内では、奇策でも何でもない。日本一への、そしてチームが地元で最高の姿を見せてくれるための、合理的な「作戦」なのだと思う。今夜の東北は熱くなるだろう。
2013.10.26
コメント(0)
-
山形県立米沢栄養大学
本日(10月25日)の大学設置審答申で新設が認められた大学に、山形県立米沢栄養大学(健康栄養学部健康栄養学科定数40)の名がある。大学の新設認可というと、田中真紀子大臣の騒動があったためか、今では、審議会で可または不可の判定を出すことになっているようだ。ほかに、審査継続(保留)や取り下げの区分もある。米沢栄養大は「可」とされている。その内容は、設置者が公立大学法人山形県立米沢女子短期大学、留意事項として「設置計画を確実に履行すること、開設時から4年制大学にふさわしい活動を行い、その水準の一層の向上に努める」べき趣旨が記されているが、これはどの案件にも共通に付されるもののようで、米沢の場合はこの他に固有の課題は示されていない。なお、備考欄に、現行の米沢女子短期大学が来春募集停止すること、設置者の名称が公立大学法人山形県立米沢栄養短期大学に変更の予定であることが記されている。東北関係では、このほかに青森中央学院大学が看護学部(定員80)を新設。これは青森中央短期大学看護学科を4年制に改組するもののようだ。また、弘前医療福祉大学短期大学部に救命救急学科(3年制、定員35)を新設。さて、新設される米沢栄養大学についてだが、現在の県立米沢女子短大は、国語国文、英語英文、日本史、社会情報、健康栄養の5学科を有する。沿革は、昭和27年に家政や被服の課程を設ける米沢市立の短大としてスタート。栄養士、保母、教職の養成に対応するほか、昭和38年に県立移管となって国語国文学科、やがて英語英文学科も設けられた。平成に入ってから、社会情報学科、健康栄養学科を開設する一方で家政学科は廃止。平成21年に地方独立行政法人に。4年制大学の計画は、管理栄養士養成課程のための高等教育機関について山形県で検討を行い、現行の栄養士養成の実績を活かして改組(4年制)することとしたようだ。(山形県ホームページなどから。)取得可能な資格としては、管理栄養士国家試験受験資格、栄養士免許、栄養教諭一種免許。もともと米短は、5学科を有しており、各地の公立の短大の中でも充実した体制を誇っている。他県の例では、県立大学に再編したり、専門職養成部分をそのまま4年制に改組するなどの例はあるが、専門系を4年制に拡充しながら従来の人文系4科も含めて、独立の道を進んでいくのはかなりユニークのような気がする。おそらく、教育実績と卒業生の活躍が定着しており、また米沢という都市に欠かせない教育機関だと認知されているのだろう。私も何人か知人が居るが、東北を中心に県外から米短をめざす人が相当程度いると思う。イメージとしては、国公立大学に準じた選択。(言い方は悪いが)一部の短大入学層よりは、相当の本気度がある選択だと言えるのでないか。(現在の定員)国語国文学科(入学定員)100(収容定員)200英語英文学科 50 100日本史学科 50 100社会情報学科 50 100健康栄養学科 40 80合計 290 580一般入試倍率(平成25年度)1.64現実に米短の卒業生を見ると、4年制大学への編入者も80人以上と相当多い。
2013.10.25
コメント(1)
-
末の松山と東日本大震災の津波
多賀城にある歌枕「末の松山」は、貞観津波(869年)が襲った際にここまでは津波が届かなかったとされる。契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは(清原元輔)貞観の津波と関連してこの和歌に出てくる末の松山が多賀城だと、初めに知らしめたのは、『地名辞書』を著した吉田東伍であった。東日本大震災では末の松山は奇跡的に津波を免れている。すぐ下の守り役の家の塀には、津波の跡が線になって残っているが、少し上に立つ松までは届かなかった。ここから10メートル足らず〔おだずま注:100メートル足らずと言うべきか〕にある沖の石などが標高2メートル位なのに比較して数メートル程度小高い。波が越すことがあり得ないという和歌の伝説を知っていたことから、地震の後すぐこの高台に避難して助かった人もあった。太宰幸子『地名に込められた伝言 災害・崩壊・津波地名解』彩流社、2013年■関連する過去の記事 末の松山・沖の石(10年4月30日) かなり古い時代の岩 沖の石(2011年11月27日)
2013.10.19
コメント(1)
-
角館、増田を歩く
秋田デスティネーションキャンペーンのパンフレットを見ながら、バーチャルで散歩してみました。角館町平福記念美術館は、大江宏氏の設計。新潮社記念文学館は同社を創設した地元出身の佐藤義亮などを紹介。角館樺細工伝承館では製作実演もある。ちなみに、この3館の共通観覧券(720円。中学以下無料)がある。個別だと各300円。食べ物では、なると餅、西明寺栗のモンブランなども魅力的だが、佐竹北家の殿様が鷹狩りの獲物をその場で焼いたという、野趣豊かな「御狩場焼」も面白そうだ。また、武家屋敷の町角館から、明治の繁栄を伝える内蔵のまちなみの増田へ「角館~増田・蔵 直行便」(予約制のバス、片道1000円)があるそうです。角館1300発、横手市増田まんが美術館1420着。帰りは増田1540発、角館1700着。さらに、「こまち蔵しっく号」なるバスも。角館1015発で、旧池田氏庭園。秋田ふるさと村、増田、湯沢を経て大曲駅に1725着。周遊をサポートする便のようです。3000円。増田のまちなみは、かつて栄えた商人達の内蔵が40棟以上も残り、溜息が出るほどだそうです。日の丸醸造の文庫蔵は漆の輝き。また、横手市増田まんが美術館は、釣りキチ三平の矢口高雄など。
2013.10.17
コメント(0)
-
猿田という地名を何と読むか...
昨日に続き、宮城県内の災害を知らせる地名の話を。太宰先生の本を読みながら。(太宰幸子『地名に込められた伝言 災害・崩壊・津波地名解』彩流社、2013年)■昨日の記事 仙台・泉区の赤生津を考える(2013年10月14日)水害を知らせる地名としては、昨日記した赤生津や荒川などのほか、袋、郎丸が関連する。また、ウメ(梅田など)、カケ(欠、懸、柿など)、カメ(亀田など)、ヨネ(米川、米山など)、ツル(鶴巻、鶴巣など)も水害を受けやすい地を示している。崖崩れなどの災害を知らせる地名としては、クリ(栗生、栗木など)、アザブ・アオソ(麻布、青麻)、小豆、倉(大倉、沼倉)、サクラ(佐倉)、シロ、放れ、竹(竹谷など)、貫(平貫など)、萩(萩野など)が関連する。いずれも、崩れる、荒れる、取れるなどの言葉から生まれたものとされる。中でも興味を引いたのが、「猿」である。サルは、古語のザレ(礫)の転訛で、山の崩れて欠け落ちた所や岩の崩れることをいう。地名の例として挙げられているのが「猿田」で比較的多い地名とのことだ。同書に説明されているものでは、○ 猿田(石巻市北村)(平成15年宮城県北部地震で被災)○ 猿田(角田市)(地元ではサンダと呼ばれる。猿田溜池がある。昭和61年8.5豪雨で地滑り。○ 猿跳(さるぱね、丸森町)○ 猿鼻(さるはな、蔵王町)ハナは地形が出っ張っていること。住所表記は町尻。東に猿頭の地名があり、ザレの始まりの地だろう。もう一つある。この読み方が興味深い。○ 猿田(ねこた、蔵王町)地元では「去る」で縁起が悪いので猫にしたと伝わる。猿田と書いてネコタと読ませるのだから面白い。松川と薮川の合流地点で、猿が来て田植えを手伝ったという伝説があるが、川が崖を曲流していて、古くから崩れていたのではないかという。また、ネコは山の麓や山の根方を意味し、ここも山の際に位置している。私も地図を見てみた。蔵王町の宮地区の小字に猿田があり、読みはやっぱりネコのようだ。
2013.10.15
コメント(0)
-
仙台・泉区の赤生津を考える
泉区の七北田公園は地図では、その北半分が泉区七北田字赤生津とされている。また、泉中央から七北田公園西口を経て北環状道路方面に抜けようとすると、七北田川を越えるが、この橋は「赤生津大橋」である。宮城県の地名研究で高名な太宰幸子先生によれば、赤生津(あこうづ)は、阿久戸、阿久津などとともに、アクタ(川沿いの低湿地で水はけの悪い地)の転訛という。(太宰幸子『地名に込められた伝言 災害・崩壊・津波地名解』彩流社、2013年)雨や豪雨の水がなかなか抜けにくい地に多くある地名だが、その大雨や洪水で肥沃な土が運ばれることが多いので昔から稲作が行われ、決してその地を捨てるようなことはなかったようだ。栗原市志波姫の一迫川流域に「阿久戸」(あくと)があるが、アイオン台風で土手が切れた。大崎市鹿島台の「阿久戸」(あくど)は鳴瀬川が蛇行する氾濫原で古くから大雨などで水はけが悪い。「赤生津」の地名は、登米市豊里町(旧北上川)、奥州市前沢区(北上川)にある。前沢の赤生津は北上川が大きく蛇行し一関遊水地のすぐ上流。昭和30年には豪雨で赤生津橋が流失したほか、平成14年、19年にも浸水被害が発生した。泉区の赤生津は、古くから七北田川の氾濫原で、開発の際にもこれを認識して公園とした(上掲の太宰先生の書による)。仙台市建設局の資料(橋梁長寿命化修繕計画。平成23年)によると、赤生津(アコウヅ)大橋(112.2m)は経過年数22年。下流の「かむり大橋」28年に比べると意外と新しい。■関連する過去の記事 飛び地の多い上谷刈(2010年11月15日) 近世までの東山道と中山古街道、七北田街道(2011年10月23日) 七北田川を考える(07年10月3日)
2013.10.14
コメント(0)
-
山形と新潟の県境にある山 日本国の伝説
4世紀頃にできはじめた大和政権は、自国をヤマトと呼ぶようになったが、外交上は倭国を名乗ったようだ。「日本」の国号が使われるようになったのは、689年に飛鳥浄御原令で定められたとの説があるが、それより早い天武の時代とか、701年の大宝律令で明文化とする説もある。旧唐書東夷伝によると、702年に遣唐使が唐の則天武后に対して、それまで倭王の遣いと述べていたのを初めて日本の遣いと述べたと記されている。しかし、倭国がそのまま日本になったとも言えない。倭国と日本国は別々の地域を指しており、どちらかは蝦夷だったという考え方がある。浅井建爾『超雑学 読んだら話したくなる 日本の地名』(日本実業出版社、2010年)には、新潟と山形の県境にある555mの山「日本国」の名について、諸説あるも次のような由来を紹介している。------------6世紀後半、蘇我氏に暗殺された崇峻天皇の第一皇子の蜂子皇子が、聖徳太子に助けられて出羽国に落ち延びる。成人して出羽三山の開祖となった。後年、この山に登り、故郷のある未申(南西)を指して、これより彼方は日本国(やまとのくに)と言ったという。
2013.10.09
コメント(0)
-
3県境の八溝山
福島、栃木、茨城の3県の境をなし、また、頂上まで車で比較的容易に到達することが出来るのが、八溝山だ。八溝山地の主峰で、1022メートル。那須岳や奥日光の山並みを眺望できる。頂上の入口の階段から展望台までは茨城県、三角点を有する頂上は福島県、だという。(石井裕『県境マニア!日本全国びっくり珍スポットの旅』ランダムハウス講談社、2009年、による。)県境スポットを案内する上掲書では、栃木と茨城の県境にある有名な鷲子山上(とりのこさんしょう)神社とセットで日帰りトリップできる(首都圏から)と勧めている。
2013.10.06
コメント(0)
-

優勝セレモニー 歓喜のKスタ
優勝決定後初のホーム。凱旋試合に惜しくも敗れましたが、試合後のセレモニーにKスタは沸きました。専用の白いテープ(100円)の芯を抜いて、投げ入れました。スタジアムの外に出たとき、雑踏の中で、サンドウィッチマンと草野アンバサダーと握手。
2013.10.04
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1