2013年12月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
栗駒耕英の開拓史(後編)
(前編から続く) 栗駒耕英の開拓史(前編)(2013年12月7日)■朝日新聞仙台支局『宮城風土記1』宝文堂、1984年 から(おだずま註:内容は当時の時点のものです。また、実名で登場する人物はイニシャルにしました。)8 山草の販売栗駒山一帯は高山植物の宝庫。耕英開拓地には特別保護地区の世界谷地第一、第二湿原があり、山草ブームで貴重な植物が心ない盗掘者達に運び去れていく。耕英の人たちにはそれが残念でならない。開拓地の中心部、県道と開拓道路の交差点近くで高山植物の生産販売をする「雲海園」を営むIさん(51歳)は、迫町の出身で農家の三男。炭焼き、ナメコ栽培の傍ら、耕英森林保護組合長を務め、盗掘の臨時監視もした。高山植物が簡単に手に入れば乱獲も減ると考え、細々と高山植物の生産を始める。昭和45年火災で新住宅を建設するのを機に、農業を捨て植物園一本にかけた。実生の苗を丹精込めて育てた。園を開いて1年後にはどうにか販売できるようになった。初めはハイマツ。サラサドウダン、ハクサンシャクナゲ、ナナカマドなど。アツモリソウやクマガイソウなども。Iさんの敷地には150種を越える山草樹木があり、栗駒山の自然を凝縮するかのようだ。1979年には山麓で珍種イシヅチランの群生地を発見し、一部を採取して現在も育てている。子ども達は山を下りてしまったが、自然を愛しながら山で暮らすつもりで居る。9 二世の仕事耕英の主産業はダイコンとイチゴ。イチゴは露地のほか冬場のハウスイチゴがあるため、相当数の家族は冬期間だけ山を下りる。ハウス栽培をしていない人でも冬は里に建てた家や子ども達の家で過ごすため、耕英に残る人はごく僅かだ。雪に埋もれる冬の耕英でも仕事はないものか、と考える耕英二世も現れ始めた。裸一貫で原生林に入植した「耕英一世」にたいして、耕英で生まれ育ち現在の働き手になっている20台後半から30台の中堅層が「耕英二世」で、耕英小中学校で学び、ほとんどが一度耕英を離れて、約10年の後に本格的に農業をやろうと帰ってきた。一度外から耕英を見ている感覚で、一世には思いも寄らない発想がある。昭和22年の入植先遣隊の一員Sさんの長男(33歳)は、耕英中学校を出て川崎市の会社に勤めるが、耕英に戻ったあと、夏は農業、冬は鳴子スキー学校栗駒分校長をしている。もしスキー場ができれば耕英住民の暮らし向きも良くなるはず、と雪との融和を模索する。また、冬の仕事として生け花に使用する花木の販売に取り組む二世集団もある。昨年夏に耕英花木研究会が発足した。OさんSさんKさんOさんYさんの5人は耕英二世だ。代表のYさん(36歳)は、せっかく耕英に戻ってきたのに単に作物を売るだけでは意味がないと考え、栗駒町農協からの呼びかけに乗って、生け花の花木の栽培と出荷に挑戦。先進の名取市を視察したが、名取では採算がとれないとの理由でやっていない自然木の催芽を、耕英ならできると直感して、昨年11月に県補助金も得て開拓道路脇の原野に催芽室を建てた。苗木の枝を切って芽を出させ、冬場に出荷できれば、冬の仕事を確立させられると語る。10 脱サラで民宿観光客の宿泊施設として、古くからある駒の湯のほか、いこいの村栗駒、キャンプセンター、白樺荘、民宿四季美、高原荘、民宿秣森、がある。民宿秣森を経営するKさん(41歳)は脱サラ経営者。戦後の入植を経験もしくはその地を引く人々の中で、昭和56年から山で暮らし始めた耕英新入生だ。東京生まれで、戦後の食糧難時代に茨城県に。小名浜の高校を出て東京に就職したが、休日には登山やスキーばかりしていた。特に水上温泉の上ノ原高原に惹かれて、そこに住もうとさえ考えたが、耕英花木研究会代表のYさんが同じ勤め先にいた縁で耕英を訪れるようになった。48年にYさんの妹と結婚を機に耕英永住を決意。周囲を説得して御沢近くに264平米の民宿を建設。砂金を抱えての船出は苦しいが来客は伸びているという。民宿の名は建築許可申請の際に町の担当者が便宜的に付けたものだが、今では気に入っている。かつての開拓とは違い、平和の中での開拓。自分のように後から耕英に来たい人のためにも、魅力ある耕英づくりの先鞭を付けたい、と話す。
2013.12.31
コメント(0)
-
栗駒耕英の開拓史(前編)
耕英の開拓の歴史について。栗駒山の宮城側中腹、標高500から650メートル一帯に耕英開拓地がある。昭和22年に28人の開拓者が入植し、ブナの原生林を切り開き厳しい自然と格闘してきた。半数以上は大望むなしく山を下り、残った人たちは開拓地を高原ダイコン、イチゴ、イワナの産地に変えた。昭和57年4月には、それまでの沼倉栗駒の字名を耕英に変えた。栗駒の地番が山を下りた旧栗駒村の一部にもあり郵便物などに支障との理由だ。■朝日新聞仙台支局『宮城風土記1』宝文堂、1984年 から(おだずま註:内容は当時の時点のものです。)1 入植のはじまり一帯は、かつてはブナの原生林で人を寄せ付けなかった。栗駒山自体古くから修験者の山として知られ、今でも行者滝などに面影を残している。辛うじて湯治場「駒の湯」があり、里の人が、登山の行き帰りや秋の骨休めに、食糧を背負って細い山道を登ってくるだけだった。昭和22年3月31日、農林省が計画した県営委託開墾建設事業のため、この地に初めての入植者たちが辿り着いた。この日の午後、旧栗駒村役場には、12か13人の入植先遣隊のメンバーが集合。ほとんどが、伊具郡耕野村の出身者。先遣隊の一行は、駒の湯の主人菅原孝さんの案内で山に入る。旧役場前から耕英開拓地までは、現在の県道(築館栗駒公園線)舗装道路でも17キロ。当時は沢に沿って狭いけもの道だけ。3月末でも積雪は多いところで1.5メートル。役場から6、7キロはトラックに揺られ、降りると原生林が立ちはだかった。「出発は午後。行者滝から孕(ハラミ)坂を通り、駒の湯に着いたのは夕方だった」(菅原さん)。当座の食糧をぎっしり背負った先遣隊員が、菅原さんを追って岩盤と雪の上を追うのは大変だった。メンバーは農家の次男や三男。食べて行くためには戻ることは許されない。先遣隊を初めとしてこの年28人が入植した。当時の駒の湯は、わらぶき小屋4棟と湯舟だけだったが、その1棟で24年秋まで2年半の共同生活が始まった。2 開拓の背景(満州移民)伊具郡耕野村は、昭和15年、当時の八島考二村長の分村移民計画で、農家の二男三男対策を解決しようと、県経済部厚生課の菅原兵市氏に相談した。菅原氏は栗原分栗駒町文字出身。理想が合致した2人は、その年耕野村で谷津冬蔵氏を団長とする第一次移民団を組織し、満州の東満総省勃利県へ入植した。菅原氏も翌年、県庁を辞して出身地の人々で組織した第二次移民団団長として満州に乗り込む。菅原氏は、駒の湯の主人菅原さんの妻の父親である。しかし間もなく敗戦。菅原氏夫妻は満州で病死。人々も傷心のうちに帰国した。八島村長が兵市氏の焼香のため、栗駒町文字の菅原兵三郎氏(兵市氏の父)を訪ねた。八島村長に対して、当時駒の湯の主人であった兵三郎氏は、湯の周辺を切り開けば何とかなるだろうと答えた。農林省でも戦後の開墾事業を開始しようとした矢先で、22年3月31日の先遣隊結成の発端となった。耕英の名は、満州耕野開拓団よりも更に秀でた開拓地にしようとの発想から、秀=英の字と、耕野の耕の字を一文字ずつ取った。耕英には、その後、栗駒町文字や登米郡などからも入植が相次いだ。3 現状耕英開拓地の広さは11万平方キロ。7月末現在で54世帯、156人が住む。昭和29年のピーク時には92戸が開墾に従事し、昭和33年までに入植した戸数は、(山を下りた家族も含めて)延べ140戸を数える。これだけの世帯で広大な原野を切り開いた事実に驚かされる。4 開拓の苦労初めて耕英入りした先遣隊(12人か13人)のうち、今でも耕英に残るのは6世帯。その一人Sさん〔おだずま註:書中では実名です。〕は、耕英東に隅、子供4人と孫4人。長男が跡を継ぎ、高原ダイコンと露地イチゴで生計を立てる。24歳で入植したときはまだ独身。裸一貫の出発だった。駒の湯の共同生活の最中に結婚。開墾とはいってもまずはブナの原生林を切り、炭を焼く。その合間に食糧集め。炭を背負って7キロ下の連絡所に運ぶ。帰りには米や味噌を担いで山道を登る。炭焼きの後原木ナメコ栽培に入るが他産地のオガクズナメコに押されて、今ではダイコン、イチゴ主体に。仲間が去る時オレも辞めようと思ったが、その時の仲間が来て去らなければ良かった、という。今では本当に住みよいところだ、とSさんは語る。5 農業の歩み昭和22年から始まった耕英の農業は、駒の湯での共同生活の後、組経営、個人経営と移った。共同生活の頃は、国有林払い下げによる炭焼きと材木売りが主。24年秋に共同生活が終わり住宅が立ち始めると日雇いに出る人も多く、製炭とともに重要な資金源となった。このころの主食はごはんと塩汁だけ。里で味噌汁を出された人が、「中に何が入っているかわからず、飲むのが不安だった」との当時の逸話が残る。昭和29年に原木ナメコの試験植菌が始まる。32年からは耕英開拓農協(23年設立)を通じて共同出荷され、はじめて安定経営の見通しがついた。夏場はナメコ、冬は出稼ぎのパターンが定着しつつあった。ナメコと並行して、和牛、乳牛、稲作も始まったが、牛は餌の買い付けや乳を里に下ろす費用で赤字。稲作も高地のため不良で、結局見切り。それでも、ナメコの値が高いうちは良かった。44年に、栽培しやすく形の良いオガクズナメコが競合産地から出荷され、大暴落する。耕英では、すぐ活路を見いだした。高冷地を利用して天然抑制栽培の高原ダイコンを植え始める。また、イチゴは41年42年から本格生産に。ナメコ暴落の年は、大根とイチゴの本格栽培と重なり、暴落を賄うには至らずとも、ポストナメコの基幹作物の見通しがついた。6 先見ある農業経営農業産品は高原ダイコンと並んで、「夏は山、冬は里」で栽培するイチゴ。昭和42年組織の耕英地区野菜生産組合には、54戸中の49戸が加入。露地イチゴ4.5ha、半促成イチゴ21.5ha、ダイコン18.5haを耕作。出荷高は57年度実績でイチゴ96百万円余、ダイコン56百万円弱。イチゴは独特の栽培方式を確立。露地イチゴは収穫後に翌年のための苗を採り仮植させて11月頃に大型冷蔵庫に入れて強制休眠させる。この方法で、他産地より遅いお盆前までの出荷が可能となった(抑制栽培)。一方、47年から冬場の出稼ぎ対策として13戸が山を下りた鳥矢崎地区の2か所でハウスによるイチゴ栽培(半促成)を始め、一年を通して農業に従事できるシステムを確立した。この実績により、昭和57年度宮城県朝日農業賞が組合に贈られた。組合長のSさんは露地イチゴ栽培を成功させた功労者。登米郡中田町上沼の出身で、26年春に耕英に入る。最初は他の入植者と同様炭焼きが主な仕事。早々に耕英開拓農協の組合長になって生活道路や営農資金の獲得などに奔走。炭焼きから原木ナメコに移ったとき、一斉にナメコが顔を出し収穫に四苦八苦することを防ぐため、原木に水をかけて芽出しの時間を調整し収益を上げた。さらに、ナメコでの順調な生活は長く続かない、と昭和44年の大暴落を予想し、イチゴ栽培を早めに手掛けた。7 イワナ養殖栗駒山に降る雨は無数の沢から、三迫川となり、下流で一迫、二迫川と合流し、迫川となる。沢は耕英の人たちの命綱。ほとんどの家が沢からホースを引いて、飲料水や生活用水を確保している。滅菌の必要ないミネラルウォーター。沢の至る所に、イワナやヤマメが生息する。一度釣り竿を浸すと翌日は全く釣れない、というほど警戒心の強いイワナも、最近は乱獲で数が減少し幻の魚といわれる。このイワナ養殖に成功し、農業とは別の道を歩んでいるのがKさん一家だ。〔おだずま註:書中では実名です。〕Kさんの家の20数個の池には5万匹を越えるイワナ、ヤマメが泳いでいる。いまでは養殖は長男が受け継いでいる。イワナのKとして県内外に知れ渡っているKさんは、白石市越河の出身。農家の三男坊で、戦後4年間のシベリア抑留の後、たまたま同地区出身のOさんが耕英に来ていたこともあって、25年にやってきた。皆と同様に炭焼きや原木ナメコを作ったほか、アズサの木を利用してウス彫りもした。しかし作業中大木の下敷きとなり力仕事が出来なくなった。他の人たちが主幹作物をイチゴや大根に変えたとき、Kさんはイワナ養殖に懸けた。きっかけは、当時耕英小中学校校長の寺坂二男さん(現在鳴子町長)の提案。他県で成功しているので耕英でもできないかと、約10人が先発産地の山形県を視察。Kさんは参加しなかったが戻ってからの反省会に出席して、これならやれると思った。42年頃だ。Kさんはじめ5人ほどが挑戦。近くの沢からイワナを捕獲して、自宅の池で育てた。46年にようやく出荷の見通しが立つが、それまでに仲間は、思うようにエサを食べない、成功するかどうかわからない、と次々と養殖を離れていた。小さなイワナを採卵用の大型魚に育てるまで5年間、Kさんには現金収入が無く、それまでの貯えで細々と食いつないだ。初年度の売上げは34万円で、全部エサ代に消えた。成功のつかの間、47年には日照りで池が枯れてイワナが全滅。55年頃には不心得者に水を抜かれたり、バッテリーを使って親魚を殺されたりした。水管理も大変で、少しでも汚水が入るとイワナは死滅するため、雨が降ると寝ずに取水口の汚物処理にあたることもしばしば。努力のかいがあって、今では耕英地区内の宿泊施設に卸すほか、観光客も多く訪れてイワナを買い求めるようになった。(後編につづく)
2013.12.07
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「サッカー選手の夢」を諦め、たこ焼き…
- (2025-11-15 22:00:04)
-
-
-
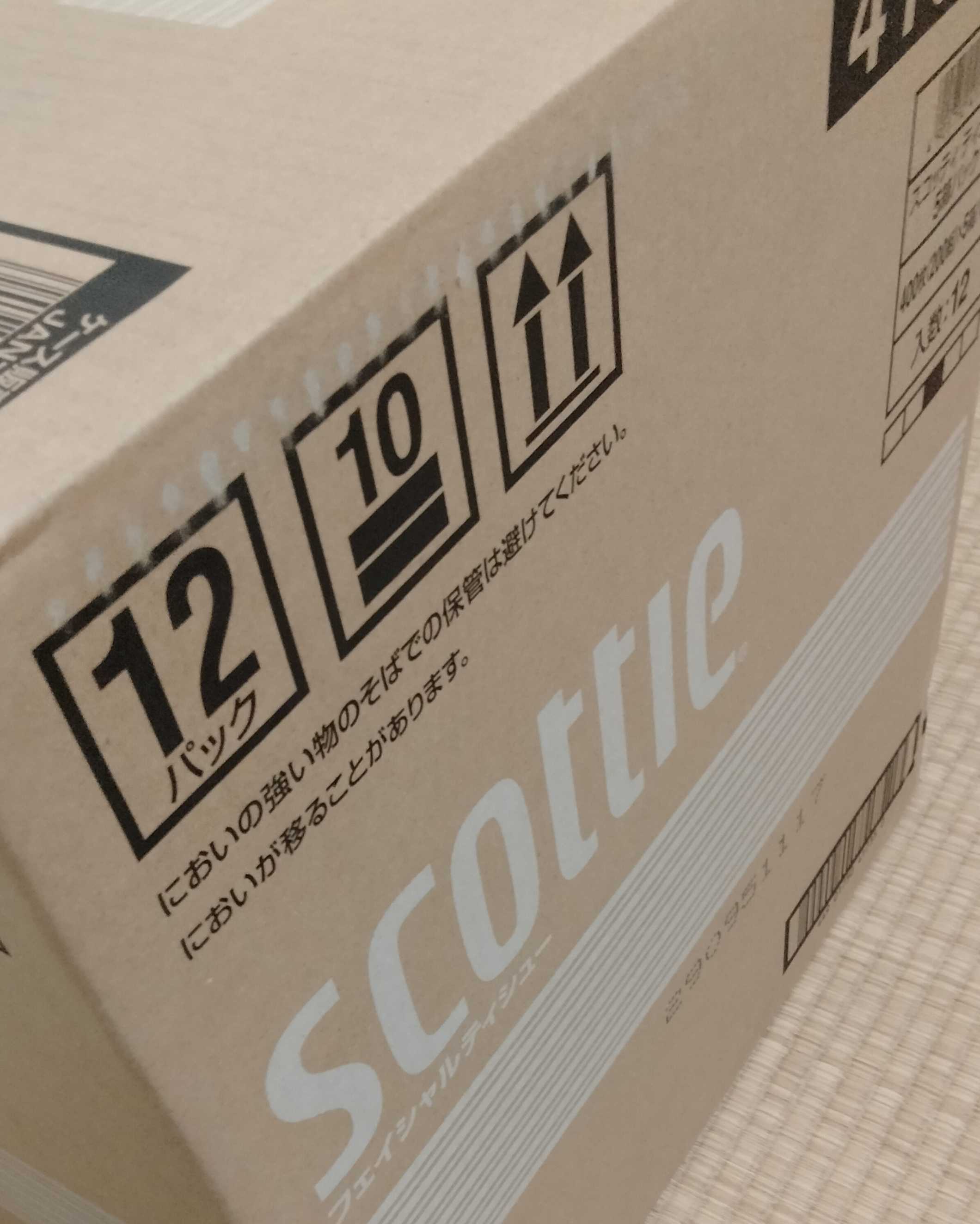
- 株主優待コレクション
- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…
- (2025-11-15 18:27:26)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 【北村晴男】話せる範囲でお話ししま…
- (2025-11-15 22:09:17)
-






