PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(106)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(24)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(30)読書案内「近・現代詩歌」
(50)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(130)徘徊日記 団地界隈
(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(12)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(29)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244
NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245
週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)
アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243
週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)
週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」(新潮社)
王兵(ワン・ビン)「青春」元町映画館no246
コメント新着
キーワードサーチ
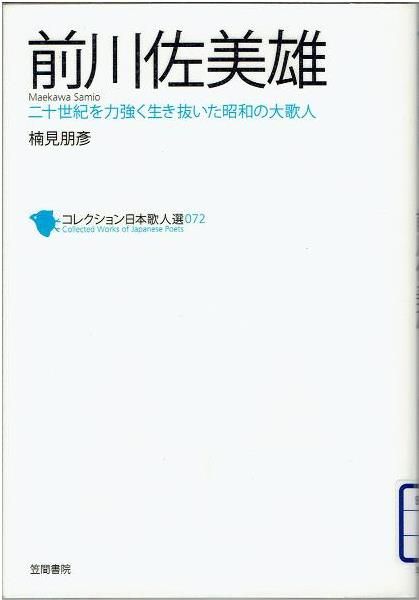
週に一度だけ女子大生の皆さんが、高校とかの授業の練習をやっているのをみています。そこで、二学期最後のテーマ「古典短歌』の授業をやってもらうことになりました。
なんといいますか、偶然ですね。ちょうど軌を一にしてというか、ほんとは何の関係もないというか、 笠間書院
が出し続けていた 「コレクション日本歌人選 全80巻」
が完結しました。
現代詩であれば 「現代詩人文庫」
という旧シリーズから 「新選 現代詩人文庫」
まで、300巻を越えようかという 思潮社
が出し続けている叢書があって、近代以降の詩人の主要作品を読むことができます。
短歌についても 「現代歌人文庫」
というシリーズを 国文社
が出版していますが、これは昭和以降(?)というべきか、戦後というべきか?、その時代の現代歌人に限られていました。
笠間書院
の 「コレクション日本歌人選」
は短歌と解説がセットという便利な本で、その上、万葉歌人から現代歌人まで網羅しているのですから、教科書でしか短歌などというものにはお目にかかったことはないが、それなりに興味はあるとか、教科書の短歌を高校生相手に解説しなければならないというような人にはうってつけのシリーズだと思います。
当然、学校の、せめて高等学校の図書館には並べてほしい本だと思います。
現代歌人の、いやもう昭和の歌人のというべきでしょうか、ここにあげた 「前川佐美雄」
がほぼ最終の出版らしくて、図書館の新刊の棚に見つけて読み始めました。
いわゆる、 アララギ
系というか、 正岡子規
から 斎藤茂吉
と連なる写実派の歌人グループとは異なる歌風の歌人で、 日本浪漫派
の人たちや、作家の 三島由紀夫
と親交があった人として知られている人なのですが、高校の教科書などにはあまり登場しません。
顔やからだに レモンの露を ぬたくって すっぱりとした 夏の朝なり
切り炭の 切りぐちきよく 美しく 火となりし時に 恍惚とせり
二階より 雨降る庭に 灯を差し向け 夜ひとり見をり 虚しさのはて
まあ、こんなふうな短歌の人です。ぼくの好みは次のような短歌ですね。
いますぐに 君はこの街に 放火せよ その焔の何んと うつくしからむ
運命は かくの如きか 夕ぐれを なほ歩む馬の 暗き尻を見て
「顔やからだにレモンの露を」
のような短歌
になると、ウへ、どんな男前やね、チャールズ・ブロンソンかとなってしまう程度の読み方しかできないのは、ぼくの問題でしょうが、
まあ、ここでは内容よりも本の作り方の工夫を案内したいと思います。
どの歌人についても同じ編集方針らしいのですが、それぞれの歌人の伝記的な経緯をなぞるように、およそ五十首の歌が鑑賞、解説されています。
前川佐美雄
の場合は 楠見朋彦
という歌人で小説家が書いていて、単なる素人向けの入門解説ではないところがよいところですね。読みごたえがあるというのだでしょうか、歌人 前川佐美雄
の短歌の肝に触れんとしている意欲を感じる解説です。
一冊読み終えて棚を探していると、面白いことに、この叢書には 「ユーカラ」
とか 「今様」
、 「おみくじの歌」
なんていうのもあることに気付きました。和歌とは縁がないと思っていた 夏目漱石
は 「漱石の俳句・漢詩」
と題して俳句二十句、漢詩二十編で一冊の本になっていました。
解説、鑑賞は漱石研究者で評論家の 神山睦美
です。早速、二冊目を借り出して読み始めましたが、解説が少々くどいところが好みではないのですが、漱石の漢詩を解説現代語訳付きで読めるので、便利な事この上ありません。出かけるときのお供にするのにかさばらないし、二ページから三ページで一首完結の体裁なのでばっちりです。
新古今の歌人 「式子内親王」
が、借り出した三冊目です。 丸谷才一
おススメの歌人で、 「のりこ」
と読むのが正しいそうですが、ぼくは、この人の和歌はかなリ好みなのです。
例えばこんな和歌があります。
わすれめや 葵を草に ひきむすび 仮寝の野辺の 露のあけぼの
この和歌に対しての 平井啓子さん 解説はこんな感じです。
葵祭の祭主をつとめる内親王は、祭の前日、潔斎のため、みあれ野に作られた仮屋に泊まる。葵を枕に結んで眠った夜が明け、いよいよ神事に臨む朝の情景》。
こういう調子からこうなります。
葵祭といえば、源氏物語の六条御息所と葵の上の車争いのくだりが有名だが、彼女は主催者としての、ういういしく清らかな「心の張り」を詠んだ。
と続けられて納得すると思いませんか。。
みなさまも、お出かけにご利用なさってはいかがでしょう。(S)
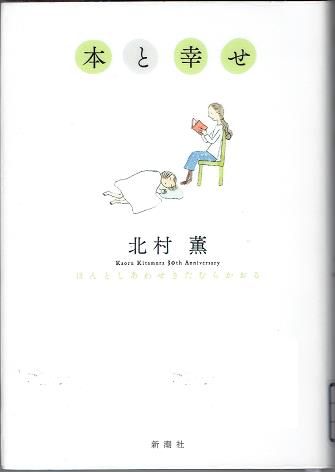
こんな紹介を書いて、二年以上たちましたが、最近読んでいた 北村薫 の 「本と幸せ」(新潮社) の中に「次代の子供たちにとって、前の世代からの大きな贈り物になる。これはそういう叢書だ。」という文章を見つけてわが意を得たりの気分になりましたが、2012年の「リポート笠間』の記事だったことに気付いて、ちょっとショックもありました。気付く人は遠の昔に気付いているのですね。

ボタン押してね!
ボタン押してね!


-
週刊 読書案内 吉野弘「母」 中村稔「… 2024.05.01
-
週刊 読書案内 安東次男「其句其人」(… 2024.04.29
-
週刊 読書案内 永田和宏「歌に私は泣く… 2024.03.09










