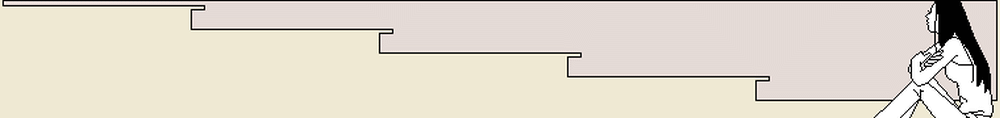2009年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
未だこゑの戻らぬままや寒波来る
朝9時頃昨日と同じところから野川を撮った。川の中洲は寒波の影響で水没していた。普段中洲にいるはずの家鴨は疾うに逃げてしまっている。どこにいるか探したが見つからなかった。午後雨が止み日がさしてきたので3時頃もう一度川に出てみると中洲は水面に現れ、家鴨が何もなかったかのように白い身体を休ませていた。思わぬ寒波で疲れたことであろう。 未だこゑの戻らぬままや寒波来る だんまりを通すのは難しいですよ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月31日
コメント(0)
-
横なぐりに寒の雨飛ぶ野川かな
冬の雨のうち特に寒中に降る雨のことを寒の雨という。耳鼻咽喉科の医者によると声帯の傷に瘡蓋ができたので、それが自然に取れるまで絶対に声を出してはいけないとのこと。万一声を出そうとすると治るのが遅れるそうだ。あと10日もみておけば良いらしい。 横なぐりに寒の雨飛ぶ野川かな 皆様にご心配頂きありがとうございました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月30日
コメント(0)
-
青木の実こころ通はすこともなく
木の実や草の実のほとんどが秋の季語とされている。そんな中で青木の実は冬の季語。一度覚えれば忘れ難い実。冬枯れの中に青木の赤い実が人目を誘う。雪が降りかかれば将に絵画の如き趣を呈する。青木の実は鳥が啄むのであろうか、何かに役に立つのであろうか。詮無いことを詮索している。兎に角青木の実は好き嫌いの範疇外にあることだけは否めない。 青木の実こころ通はすこともなく あと6日で立春ですね、春はどこから来るのでしょう クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月29日
コメント(0)
-
八方に青引き冬の曼珠沙華
あの赤い花なら曼珠沙華の曼珠沙華は冬に葉を茂らせる。色は青々として冬の野川沿いに彩りを添えている。多分冬の曼珠沙華に関心がない人には解らないだろう。近くに喜多見不動尊がある。1月28日は初不動なので何かやっているのではと思い、午後出かけてみたが・・・・・・トホホホ何もやっていなかった。なんという罰当たりな。喜多見不動尊の門前に2月3日午後4時から節分の豆撒きの予告が出ていた。興味のある方はどうぞ。以前行ったことがあるが、電車に乗ってわざわざ観に行くほどのこともないので、近くで歩いて行ける方にお勧めする。 八方に青引き冬の曼珠沙華 今日は髪を染めました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月28日
コメント(0)
-
喉赤きままの日数や寒椿
寒中に咲く紅椿は美しくもあり、もの哀しくもある。花は何も言わないがそれを見た人が何かを思う。 喉赤きままの日数や寒椿 羅府からのコメントありがとう御座いました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月27日
コメント(0)
-
八幡の寒紅梅に歩を寄せぬ
当地へ越してきて4年目に入った。郵便局の斜め向かいに八幡さんがある。神輿蔵のようなものがあるが、鳥居もなく御身体がどこにあるかも解らないが八幡さんらしい。どうやら此の宮が地元の祭りになるようだ。 八幡の寒紅梅に歩を寄せぬ 気分がすこし良くなってきたが未だ貝になったままでいます クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月26日
コメント(4)
-
下校児の岐れの道の寒菫
草花が寒の最中に可憐な花を咲かせている。本当は春の麗らかな日和にほころび、皆の注目を浴びたいところであろうが、菫はそんなことを考えたこともないように路傍に精一杯の笑みをたたえて咲いている。 下校児の岐れの道の寒菫 ロスより再び、昼間は17℃と クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月25日
コメント(0)
-
寒木瓜の彩とりどりの他郷かな
木瓜の花は春の季語であるが、私の近辺ではもう咲いている。寒木瓜という種類は特になく、寒中に咲く「寒木瓜」は色の少ないときの鮮やかな花として珍重される。生け花にも使ったことがある。吸入をしての帰り風花が舞った。「吸入」も「風花」もともに冬の季語。 寒木瓜の彩とりどりの他郷かな ロスへ行っている人からケイタイにメールが届き驚いた クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月24日
コメント(2)
-
雨しづく零れつぐなり寒の薔薇
声が一日も早く出るようになるには毎日吸入をした方が良いと医者に言われ、吸入をしに通うことにした。吸入だけだと予約なしにすぐにできる。その帰り道の雨上がりに寒の薔薇を見つけた。植物園ではなく、民家に咲いていた。この寒い雨の中けなげに咲いているのに心を動かされた。私のようだと云うには歳をとり過ぎた思いしきり。 雨しづく零れつぐなり寒の薔薇 あと12日で立春です、待ち遠しいですね クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月23日
コメント(2)
-
朝雨のかかりて冬の花わらび
朝から久々の雨が降っている。雨脚と云うほどでなくお湿りと云った感じである。私の町の降雨量50%、最高気温7度、最低気温5度。殿が谷戸庭園に冬の花蕨が咲いていた。これは蕨とは別の品種で夏に枯れ冬に花が咲くという珍しい植物である。歩いていて、この花に目を留める人はほとんどいない。 朝雨のかかりて冬の花わらび 喉は1週間分回復しましたあと2週間かかるようです クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月22日
コメント(2)
-
寒雀離れて一羽また一羽
極寒の頃に見かける雀。寒いので空気の層を厚くするために、全身の羽毛をふくらませて丸くなっている。これを「ふくら雀」という。雀は一羽でいることはない、いつも群れていて、行動をともにしている。雀は雀同士助け合って生きている。 寒雀離れて一羽また一羽 ふくら雀とはうまく名付けたものですね クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月21日
コメント(4)
-

大寒(だいかん)
文鳥のみみさん文鳥のみみさんは飼い主のMotoさんをママと思っているらしい。ちょっと籠から出してもらうとすぐにMotoさんにまとわりつく。今時であるから文鳥も携帯電話を使いたいらしい。使うようになれば真っ先に天国のトトさんと話をするつもりであろう。 大寒や文鳥なれどケイタイを 久々に文に登場してもらいました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月20日
コメント(4)
-
らふ梅や弱日の中の殿が谷戸
ろう月(陰暦12月の異称)、葉の出る前に香りの高い小さな黄色い花が、数個ずつ集まって咲く。梅とは別種である。庭園の受付付近で良い匂いがしたので、ふと見ると今を盛りにろう梅が地味な花を沢山咲かせていた。 らふ梅や弱日の中の殿が谷戸 ろう梅は弱日につつまれ輝いていた クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月19日
コメント(2)
-
寒牡丹こころほぐれてきたりけり
12がつごろから1月にかけて咲く牡丹のこと。本来は5月頃に咲くが花期を遅らせて冬牡丹として咲かせる。厳冬に咲くので藁づとをかけ根元も藁を敷いていたわってやる。手塩にかけてやっと咲いた牡丹には人の心を和ませる香気が漂っていた。 寒牡丹こころほぐれてきたりけり 寒牡丹惚れ惚れしますね クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月18日
コメント(2)
-
幼名は牛若丸や冬木の芽
この木は何の木か解らないが、樹の芽にしては大きい。生まれたての兜虫のようにネバネバしていて赤茶けた色をしている。芽の中は何かぎっしりと詰まっていて、空へ突き立てている様に力強ささえ感じる。冬木の芽は寒風に耐え暖かい日差しが当たるのを待っているかに覚えた。 幼名は牛若丸や冬木の芽 固く結んだ冬木の芽もやがて解れる クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月17日
コメント(2)
-
水仙の一輪といふ気高さよ
昨日の耳鼻咽喉科の医師の治療と処方箋のお陰で風邪はほぼ治ってきた。今回の風邪ではいろいろと考えさせられた。一時は痰と咳で布団の上で七転八倒し、死ぬかと思ったが、今は生きる力が湧いてきた。水仙が特に綺麗なのは爪木崎と越前岬である。このどちらへも私は2回ずつ訪れている。写真は野川沿いのサイクリング道路の脇に咲く水仙。2・3本ではあるが、気品があって好きな花である。ここから野川の中洲に眠る家鴨が見える。水仙に目をやり家鴨を見やりと穏やかな日常が戻ってきた。今日はたまっていたコメントの返事を一気に書きました。元気なときはこんなこと平気なんですね。この落差に驚いています。 水仙の一輪といふ気高さよ 明日明後日と句会だバンザイ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月16日
コメント(4)
-
唄ふなと云はれてをりぬ小正月
1月15日を小正月または女正月と呼んでいる。松の内の間、家事に追われた女性たちがほっと息をつく日。川沿いを散策して元気な家鴨の姿を久々に見た。声が出なくなって1週間がたつので、いかに暢気な私もこれは変だと思い始めた。内科クリニックの向かいにある耳鼻咽喉科へ飛び込んだ。医師は若手のバリバリで、パソコンを駆使して次々に喉や耳を診て即座に治療をテキパキとこなしていた。すぐ治りそうな予感を感じた。結果声帯が荒れていた。完治まで2・3週間はかかるとのこと。でも治るらしいのでひとまず安堵。鼻を通したり耳を通したりするのは初めてである。歯医者よりはまだましだがそう何回も受けたくない荒療治に驚くばかりであった。 唄ふなと云はれてをりぬ小正月 さあいよいよ活動開始だ~ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月15日
コメント(2)
-
寒梅やゆかしき人の住みをらん
読んで字の如く寒中に咲く梅を寒梅という。ハイタウンの1階は庭付きである金網の外の生け垣はほとんどが山茶花と椿である。庭には各家が思い思いの木を植えている。このように梅もある。我が家の下に梅の木があったが、居住者が替わったとき根こそぎの憂き目にあい、勿体ない気がした。 寒梅やゆかしき人の住みをらん なんとなくだらだら起きています クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月14日
コメント(4)
-
癒ゆる日のさう遠くなし布団干す
窓辺に行って気がついた。いつも置いているところにガラスの鉢がない。ガラスの鉢には色とりどりのビー玉やガラスの金魚、ガラスの蛙を入れている。何故そんなものをと思われる方もあろう。私は金魚鉢の代わりに置いている。風水では金魚鉢は寝る時胸より高いところに置いてはいけないということである。風邪がこじれて声が出ないのはその所為だとはたと気づいた。そういえばはー君が来た時その鉢を観葉植物のガラス棚に誰かが置いてそのままになっていたのである。素早く金魚鉢を洗い下に下ろしたのはいうまでもない。ついでに蒲団を干すことにした。蒲団干しは重労働であるがそれを誰の手も借りずやってのけた。何にせよこれで近々癒えることは間違いなし。万歳!! 癒ゆる日のさう遠くなし蒲団干す 前より喉の調子がひどくなったねと医者がいう クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月13日
コメント(4)
-
成人の日や振り袖を胸高に
成人の日に意識するのは女性の振り袖姿。実に一人一人が輝いて見える。例え見かけだけであっても美しい姿を惚れ惚れと眺めるのは私だけではあるまい。 成人の日や振り袖を胸高に 明日は病院へ行く日もっと効く薬ほしいよ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月12日
コメント(4)
-
寒晴や風切つてゆく一輪車
あまり写真がないと淋しいので、2階の階段から野川を撮っていると一輪車を駆った青年が二人野川に沿って成城方面へ急いでいるのが見えた。一輪車はバランスを取るのは難しいだろうと常に思っているが、今の子ども達は平気らしい。 寒晴や風切つてゆく一輪車 昼間の日がある内に今年三度目の入浴 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月11日
コメント(2)
-
隣室にをさな眠れり宝船
正月のよい初夢を見るため、宝船の絵を枕の下に敷いて寝る。元日の夜または二日の夜という説がある。 隣室にをさな眠れり宝船 明日の外出は咳がひどいのでやめました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月10日
コメント(2)
-
婆々の踏ん張りなどと初雪す
この冬初めて降る雪のことを初雪という。こんな事くらいで音を上げるなといわれているようである。 婆々(ばあばあ)の踏ん張りなどと初雪す 目下声がでないので電話には出られないんです クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月09日
コメント(4)
-
松過や仕舞ひ忘れし賽一つ
松の内の終わったあとのしばらくのことをいう。門松や注連縄などの飾りが外されると家々は普段の状態になり、町も普通の姿に立ち返る。しかしなんとなく正月気分が抜けきらずどこかに残っている。部屋の片隅に双六の賽子が転がっているのも松過ぎの光景である。 松過や仕舞ひ忘れし賽一つ 咳は相変わらず出るので薬が変わった クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月08日
コメント(4)
-
人日(じんじつ)・七種(ななくさ)
本当はこんなことをして寝ている訳にはいかないのだが・・・・。一日中上げ膳据え膳に甘えている手前、もう一つの仕事が滞ったままである。皆様にご心配頂いて申し訳ありません。38度9分あった熱も平熱にもどり、口内炎が同時進行していましたが、医者から貰った抗生物質のお陰でそれも消え、食欲が少しづつ戻ってきています。あとは喉がいがらっぽく咳が出始めるとたて続きに出、痰・鼻水に悩まされています。それに声が出ません。家の中で、家人に移らないようマスクをしています。マスクは案外つらいですよ。 人日や泡石けんを幾たびも 11日の句会までには治さねば クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月07日
コメント(2)
-
玄関に紅緒の下駄や松の内
もう参りました。去る12月インフルエンザの予防接種を受けたので、それは風邪とはちがうからと頭では解っていたが油断したが為苦しんでいる。初詣用にと用意した下駄も履くことなく、玄関に置いたままになっている。 玄関に紅緒の下駄や松の内 コメントの返事は気分がよくなってから書きます クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月06日
コメント(6)
-
小寒の富士見てすぐに返しけり
谷戸橋地区センターから崖線をあがったところに地元の人が建てた清稲荷神社がある。そこから富士山が見える。 小寒の富士見てすぐに返しけり
2009年01月05日
コメント(2)
-
稲積むや酒より旨き水を飲み
寝ることをめでたく言い替えた正月の忌み言葉。「寝る」といえば病臥の意味にも通じるため、その古語「寝ぬ」「寝ね」を稲にいいかえたのである。また、「積む」は楽しいことを積み重ねるというイメージがある。 寝積(いねつ)むや酒より旨き水を飲み きのうが風邪のピークでした クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月04日
コメント(4)
-
境界線律儀に敷きて寝正月
元旦も早起きするでもなく、正月休みの間じゅう家に籠もったきり、年始にも初詣にも出ずに過ごすこと。わざと横着を決め込む場合もあるが、病気で新年早々床に就いている場合もある。私の場合後者。先ほど迎えが来てはー君はやっと帰って行った。 境界線律儀に敷きて寝正月 明日からは平常に戻らなければ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月03日
コメント(4)
-
正月凧墜ちると見えて揚りけり
喜多見ふれあい広場では親子が凧揚げをしている。のどかな正月風景である。 正月凧墜ちると見えて揚りけり とうとう家中に風邪が蔓延してきました クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月02日
コメント(2)
-
元日の日の当りゐる川瀬かな
歳旦三物元日の日の当りゐる川瀬かな 藁青々と匂ふ輪飾花の下うす紅色の御召着て元日の野川は柔らかな日差しの中、緩やあかに流れている。家鴨は子ども達にパンを貰っていた。家鴨の白と子どもの服の赤が元日らしい色あいであった。 今年もどうぞ宜しくお願いします クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ
2009年01月01日
コメント(4)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 11/20 20時〜数量限定‼️もち吉『ブラ…
- (2025-11-20 21:59:07)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- “Jカップ超2次元ボディ”伊織いお、圧…
- (2025-11-21 00:30:10)
-