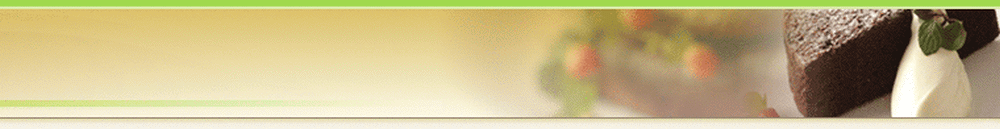2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年11月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
一言では言い切れませんが。。。
例のマンションの耐震強度審査の偽装問題。今日、国会審議があったようですが、たぶん皆さんは建築にかかわった人たちに対してムカついてるんじゃないかと思うんだけど、個人的には、この事件をとても複雑な思いで見てます。もちろん、ずさんな管理については間違いなくとんでもないことだし、マンションそのものの住民とか周辺住民は、お気の毒としかいいようがない。楽天会員さんの中にも、ローンの途中で退去の話がきてる人もいるかもしれないし、同じく賃貸ではあるけどマンションに住む者としては、自分の住居で、もし同じような瑕疵があるのにだまされてたとしたら、少なからず憤るでしょうね。同条件の物件紹介してくれて、なんらかの見返りがもらえるんなら我慢もできるかもしれないけど、ディベロッパーの代表者が、その場しのぎのいい加減なことを云ってるし。彼は、テレビに出すぎだな。目立ちたがり屋さんなんだろうな。ただ、彼らにしてみても、どうも賠償責任をとれる体力がなさそうに見えるし、その場合、自分がかわいいというか、第一優先にしたい気持ちも、わからなくもないんだよね。「本当に、マンションに住む人たちのほうを向いて仕事やってるのか!?」なんて云われたってさ、その前に自分が一番大事なわけだしさ。肩持つつもりは毛頭ないけどさ。鬼の首とったようにギャーギャーわめいてる、フルダチさんとかオグラさんとかミノさんとかタワラさんとか見てると、ちょっとムカつくんだよね。「てめえは当事者じゃないし、てめえん家は安全だから、いくらでも好きなこと云えていいよな」とか、ヒネた目線で見て思ったりなんかして。実際の住人の目から見ると、たぶんこいつらのテレビでの言動が、逆に頭にくるんじゃないかと思うよ。「カンケーねーだろ」って。ただ、今回のマンションにかかわった奴らは、苦りきってるだろうね。計画倒産して、賠償責任負わなくてもいいように海外へ逃げちゃおうとか、俺だって汗水たらして家族や従業員のために必死で働いてるのに、なんでこんな、本来は金の亡者の政治家ごときにつるし上げられなきゃいけないんだ、とか、腹の底で思ってるんじゃないか。でも、やっちゃったことはとんでもないことで、情状酌量の余地は、ほとんどないわけで。怖いなと思ったのが、今回の事件のきっかけっていうのが、たぶんほんのちょっとの気の緩みというか、手抜きの積み重ねだったんだと思うんだけど、ジャンルや業界こそ違え、ちょっとした気の緩みによるミスが積み重なって重大なミスに広がったり、あるいは自分のミスを認めるのが嫌で意地を張って、傷口を広げたりすることが、過去の自分の身の上に全くないといえばウソになるからね(注:私の場合、こんな大事になったわけじゃありませんよ、念のため)。今回の事件は、↑の後者のケースですね。これまでの各業界だとか官公庁などでの不正ってのも、だいたいそうなんじゃないかと思います。プライドが高すぎるんだよ。今回の場合、一級建築士だったり、国で認定された監査法人だったり、政治家と知り合いのゼネコンとかディベロッパーだったりしたわけでしょ。だから、これまでは、ミスったとしたって、ちゃんと届け出なくても「下のもの」がケツぬぐってくれたり、自分のせいじゃないと主張する権力があったり、自分は叱る側とか、見張る側だけでよかったりしたわけでしょ。だけど、そうやってはぐくまれた「悪事の温床」を取り除くための行政改革が進むにつれて、そういうのは許されない世の中になってきてるのは確かなんだよね。また彼らは、自分をかばうだけでなくて、ほかにかばいたいものが絶対あるはずなのだ。たとえば家族とか、部下だとか、今回のつながりだとか。そういったもの。そういうのがなくて、生身の自分のことだけ考えるのならば、彼らはもうちょっと本音で正直に話せるのかな。よくわからないけど。
November 29, 2005
-
明日はジャパンカップですね♪
なんだか海外からやってくる馬が強いらしいですね。予想はなんともつけにくいけど、ゼンノロブロイとこれら強豪との対決、というのがもっとも注目を集めるということのようではある。だけどデザーモ、ってのが、どうも昔から信頼できない。コタシャーンに跨って出場した年は、ゴール板100m手前で立ち上がってしまって、結果レガシーワールドを差せなかった。その上今年の宝塚でも、期待を大きく裏切ってくれたし(まあ、私もそうなるんじゃないかとは予想してたけどね)。このゼンノロブロイって馬も、秋の天皇賞では最後差されちゃったし。で、差したヘヴンリーロマンスも、JCの強敵相手でどこまでやれるのかは未知数。有力馬の一頭、ハーツクライも、なかなか勝ちきれない馬。鞍上のルメールも、日本のG1では2着、3着が続いてるし。とはいえ外国馬も、これまでの多くのレースで、「史上最強」とかいわれつつ、凱旋門賞馬があっさり着外に消えたり、ブリーダーズカップの馬がイマイチ直線伸びずに負けてしまったりしてるので、当てにならないっちゃあ、これほど当てにならないものもない。アウェイゲームというのは、特に馬にとってはことさら厳しいもののようですね。というわけで、まったく何がくるのか想像もつかないのだが、JCではすこぶる相性のいいデットーリ・アルカセットのコンビ対、明日負けたら「日本に来るな!」とファンに云われかねないデザーモと、明日負けたら「有馬記念をディープインパクトの独り舞台にしたA級戦犯」の烙印を押されかねないゼンノロブロイの、がけっぷちコンビの一騎打ちになるのではあるまいか。昨日、琴欧州が朝青龍を力相撲でガッチリと寄り切った。昨日負けると、当面彼は朝青龍には勝てないと思われただけに、がけっぷちで踏ん張り、大関をほぼ手中にした。なので明日のJCのほうも、がけっぷちゼンノロブロイが激走してアルカセットを破り、無敵の一人横綱ディープインパクトとの千秋楽(有馬)対決に持ち込むのではないかと予想する。ま、買わないからどっちでもいいんだけどね。◎ ゼンノロブロイ○ アルカセット▲ ハーツクライ
November 26, 2005
-
あまり取り上げられてないスポーツのネタなどを。。。
<ハスキーズ優勝!>社会人アメフトのX2リーグで、今期はぶっちぎりの負けなしで全勝優勝。おめでとう(^^)!!今さらたたえるまでもなかったかな。というか、ハスキーズのホームページにBBSが消えたので、こっちでひっそりとお祝いしているわけです。というわけで、12月11日に入れ替え戦が、川崎球場で行われるそうです。相手は、昨年苦杯を喫し、二部転落の憂き目を見せられたルネサス・ハリケーンズ。今年は借りを返す番だ!!とはいえ、近頃はアメフトが少年たちに人気だそうで。「アイシールド21」という漫画の影響らしいけど。この漫画、私はSFものかと思ってたら、アメフトだったのね。m(_ _)mなんとなく、「スクールウォーズ」っぽくブームになってるみたい。だがこれで競技人口が増えるかというと、ユニフォームとかテクターがバカ高いので、簡単にはいかない、日本ではまだお坊ちゃまスポーツなのでした。。。<成蹊高校>高校ラグビーの東京代表になったそうで。東京MXテレビで見てたら、終了のロスタイムで逆転サヨナラ勝ちみたいな感じで勝っていた。相手の高校がかわいそうだったね。31年ぶりというから、さすがに前回出場のときには見てなかった。というか、そもそもテレビでそのころ放送してたのかどうかも疑問。この高校って、松尾雄二さんがかつて高校生のころ、はじめに入学した高校だったよな。そのころの成蹊高校って、全国出場経験はあるけど、どっちかといえばお遊びラグビーっぽいチームで、松尾さんはチンタラやってたらしい。で、のちに入学する明治大学のラグビー練習場に、ときどき遊びに行っていたという。そんな折、明治大学のグラウンドに現れた目黒高校の、ぜんぜんレベルが違う練習風景と、明治大学との練習試合を見て、その迫力に惹きこまれ、目黒へ転校したことが、その後の松尾雄二の飛躍のきっかけになったんだそうで。今日とは勢力分布がまったく違ってたわけですね。近年久しく低迷している目黒高校は、今年も予選で早々に姿を消し、成蹊高校が全国の切符を手にした。盛者必衰って感じだね。
November 25, 2005
-
まずはチャレンジ
某文芸雑誌が毎月募集しているショートショートのコンテストに、とりあえず1本投稿してみました。ネタがなかなかひらめかないのが難点ですが、引き続き、ひらめきのつどこうしたチャレンジは続けていこうと思ってます。よい結果が出たら、またご報告します。あと、もうひとつチャレンジしてみたい賞があるんだけど、長編小説の募集なので、ちょっと書く暇があるかどうかが不安。あまりそっちに傾倒してしまうと、受験勉強の時間がなくなってしまう。。。
November 24, 2005
-
オフの日はスナフキンになってみる?
話題の本などを紹介する雑誌「ダヴィンチ」の今月号で、「スナフキン特集」なんてのをやってるのが目に留まったので、ちょっとナナメ読みしてみた。スナフキンってのは、ご存じの人も多いだろうけど、「ムーミン」に登場する、さすらいのギター弾き(ハーモニカだったっけ?)で、自由人。同じくムーミン谷に住むミムラ姉さんやミーとは、異父兄弟でもあるらしい。特集の内容っていうのはどってことはなくて、「ムーミン」の中でスナフキンが、友達のムーミンに語った語録だとか、『スナフキンって芸能人にたとえると誰?』みたいなアンケートだとかいうのが前面に出ていて、それ自体はさほど興味を覚えなかったんだが、懐かしいという思いと、自分はスナフキンの存在についてどんなふうに考えてたかなあ、なーんてことに、しばし考えをめぐらせつつ、この特集コラムを読んだ。スナフキンは、その印象をひとことで云えば「かっこいい」。自由に世の中を旅して回り、一人ギター(ハモニカ)を奏でたりしている。ただ、それに酔いしれたり悦に入ったりしているわけでもない。一つのことに耽溺することなく、常に世の中を客観的に見つめている。はたで見ると、それは世の中を「正しく見ている」ようにも見える。スナフキンは、「屈強の漢」ではない。むしろ弱っちそう。たぶん「体育会系」とは対極にいる人だから、部活なんて絶対無縁である筈だし(体制を嫌う彼は、「軽音楽研究会」にも入らないだろう。そもそも学校も中退とかしてるかも)、あまつさえ肉体を鍛える姿など想像もつかない。けれど、長らく放浪の旅や屋外生活をしても、病気ひとつしない(?)ところを見ると、雑菌に対する抵抗力が強いといった、身体の芯のところの強さみたいなものは、ほかの人より優れているのかもしれない。主人公のムーミンは、物事に迷うと、よく川辺で釣りなどをしてるスナフキンのところへ、相談にやってくる。スナフキンは、互いに害のない範囲で、相談に乗ってやる。ムーミンの問いに対するスナフキンの答えは常に客観的でドライで、ときに冷たく突き放すような言葉もあるのだが、彼は、友達であるムーミンへの尊重と思いやりを忘れない。ムーミンは、話すうちに自分で答えを見つけ、満足して帰っていき、以後もその良好な関係は続いていく。ある意味、スナフキンのような態度でカウンセリングできるようになるのが、今後の私にとっての目標でもあったりする。彼は常に反体制的な思考を持ち、公的な干渉には断固抵抗する。共同体を好まず、好んで孤独に生活しているにもかかわらず、周囲の人望は厚い。スナフキンが、若者ウケするタイプだというのははっきりしている。だから若い頃、「スナフキンみたいな生き方に憧れる」と云う人は、けっこういた筈。「理想の生き方」なんていう人もいたりする。でも、結局その憧れ、理想は、大半において実現できなかったりする。悪い云いかたをすれば、スナフキンは風来坊であり、生産性がないし、多分収入を得ようとしないから税金も納めてないだろうし、そのくせ役人を批判的な目で見てるだろうから、ホームレスみたいなもんで、公的に厄介な存在であるのは間違いない。役人にとって、スナフキンみたいな存在は、消えて欲しい悩みの種だ。ムーミン谷を管轄する、ヘルムという警察の署長さん(?)は、スナフキンのことを厄介者扱いしているし、逆にスナフキンもヘルムを毛嫌いしている。若者がスナフキンに憧れる理由の一つに、こんな反体制的な側面を漂わせている点も、含まれているに違いない。スナフキンは、完璧な人物では決してない。けれど、完璧でないところこそが、彼の魅力でもあったんじゃなかろうか。よくわからないけど。どうでもいいことながら、そんなふうに思ったりする。「ダヴィンチ」のスナフキン特集コラムの中に、「スナフキニズム」なんていう言葉が使われていた。あまり丁寧に読んでなかったので、ライターが意図する正確な意味は、よくは理解してなかったんだけど、改めて意味を想像するに、「スナフキンに憧れ、スナフキンのように物事に拘泥せず、不安定を恐れず自由奔放に生活し行動する主義」みたいな意味なんだろうか。それとも、「スナフキンの心を忘れず、適宜自然に帰り自分を解放する主義」という意味なんだろうか。もし後者が、このライターのいう「スナフキニズム」であるとするなら、たとえば週末や休日、あるいはオフタイムなどに「スナフキニスト」になることは、自分の使い分けをするような価値観がまかりとおる今の世の中、誰でもできるんじゃないか、なんてアホなことを、ふと考えた。まあ、なろうと思えばなれなくもないんじゃないの、ってことだけどね(笑)。昔あれほど憧れてたのに実際できなかった「スナフキンみたいな生き方」が、休みの日だけならできるよ、というわけ。とはいえ今の私は、「スナフキニスト」にはあんまりなりたくないかも。観念的には共感するけどね。物理的には、そんな真似をする元気やパワーは、今の自分にはない。スナフキンが嫌ってそうなものを好きだったりするし。不便や不安定を恐れずに生きていくことなどできない。たとえばスナフキンは、パソコンなんか絶対使わないだろうしね(笑)。
November 19, 2005
-
残されし企業は。。。
「近代経営論の父」ことピーター・ドラッカー氏が、去る今月11日に亡くなった。不思議と、ニュースや新聞ではこのビッグネームの訃報を目に留めることがなかった。たぶん日曜朝の、竹村健一さんとか田原総一郎さんの番組あたりで、話題に上るんじゃないですかねえ。ドラッカー氏は、つい最近まで、さまざまな場所とか紙面に顔を出していた。90歳を超える年齢で、すごいバイタリティだと思う。この人の足跡・功績について、詳しいことは恥ずかしながらあまりよく知らないのだが、常にいつもいろんなところで彼の名前は目にしたし、耳にもしてきた。名言をパクるのが大好きな、日本の有名企業経営者の著作やスピーチでも、よく「ドラッカーの本に・・・」だとか、「かつてドラッカーは、企業は******すべしと言っていた。私もそれに同感だ」などというように、非常に頻繁に引用されたりしていて、こっちは流すように見たり聞いたりしていただけだったけど。m(_ _)m彼の発言や著書はいわば、とりわけ日本の企業経営者にとってのバイブル的なものでもあったのじゃないかと想像する。なんとなく、最近のネット株式売買だとか企業買収、合併といった話を見たり聞いたりするだに、従来の企業モラルだとか常識といったものが、いま大きく変容しようとしている時期のような気がする。それがいい方向に向いているのか、悪い方向に向いているのかは、一言では断言しがたいのだけれど、未曾有の前進をしていることへの不安感があるのは事実で、旧来の日本企業経営者たちの当惑も見て取れる。ドラッカー氏は、どんな目で今の日米企業の現状を見ていたのだろうか。経済がこういう形になってしまうと、よかれと思ってやる経営者は多いだろうとは思う反面、うち何%かは悪に方向に手を染めようと考えるもんなんだと思う。いや、そういう輩は過去から必ず既にいるはずなのだが、悪事が実行しやすい環境になってしまっている、ということなんだろう。ネット社会の到来とともにウィルスが次から次へとばらまかれ、それを取り締まる情報セキュリティとのいたちごっこが続いてるように、不正な契約や取引なんてのも、極秘裏にあっという間に行わちゃったりしてるんじゃなかろうか。それが横行するにつれて、かつてのインサイダー取引とか談合みたく「常識」になってしまって、やがて企業のモラルハザードが起きる。ピーター・ドラッカー在りし日に、起業したり社長に就任したりして彼を奉ってきた現在の企業経営者たちは、彼のような「教祖」のいない今日、果たしてあるべき企業モラルを維持できるのだろうか。ミキタニさん、ムラカミさんよ、あんたたちも気をつけな(細木風)。最後に、ドラッカー氏のご冥福をお祈りします。
November 18, 2005
-
同じ日本人として恥ずかしい・・・
以下は、数日前に遭遇した出来事の再現です。見かけた人が、楽天広場にいたのかどうかは知りませんけど。ここ数日、関連したテーマの話を多くあげてる理由として、こんなことがあったというのも、なきにしもあらずかも。というか、たまたま同じ感想を抱くような出来事に出くわしたのかもしれないが。とある、割と若者が多く集まる繁華街のはずれにある資料館へ調べものがあり、その帰り道、もみ合いをしてる男たちを見かけました。「謝れこのやろう!」なんて怒号が聞こえる。すでに出来ていたヤジ馬の人だかりに近づいてみると、スタジャンを羽織った金髪の若い男が、太った体躯の中年男性につかみかかっている。中年男性は胸ぐらをつかまれて、苦しそうによたよたしながら、何か云おうとしているのだが、言葉が口をついて出ない。若造の怒りの前に圧倒されているのか。もみ合いしてる2人の脇に、1本の松葉杖が転がってました。中年男性のアンバランスな動きを見て、彼の杖だということが、パッと見てすぐにわかりました。この中年男性はどうやら脚が不自由で、松葉杖でなんとかバランスを保ちながら街を歩いていたところを、運悪くこの若造と衝突して、彼がぶつかったことにキレている、といったところか。正確ないきさつは見てないからよくわからないけど。若造は、はっきり云って弱そうだった。というかあどけない童顔だった。だがキレてるだけあって、弱っちさを補ってあまりある迫力。声はでかいし、その上相手は「弱者」だし。しかし彼の言葉の内容は、声がデカい反面支離滅裂。聞こえるのが「このヤロウ」「ムカつくんだよ」「とれえ(とろい)んだよ」などと云った単純な言葉だけ。これらを組み合わせ、マシンガンのようにまくし立ててる。殴ったりはしてないにせよ、なぜそこまで腹を立てるのか。それも人通りの多い街の真ん中で。やがて通報を受けたのか、警官が2人、もみ合いを止めにやってきた。警官に事情を聞かれて、若造が話している。こんどは、自分を含む周りのヤジ馬にも、その内容がかなりはっきりと聞き取れました。若造:「だっていきなりぶつかってきてさあ、ハンパねぇ(ほど)いてーのに、ぜんぜん謝らねえから頭きたんすよ」警官:「わかったから、事情はあっち(警察?)で聞くから来て」中年:「はいすいません、あの・・・」若造:「今頃謝ってるんじゃねぇよ!ぶっ殺すぞてめえー!」警官:「いーからはやく!」とても情けなくなっていたたまれず、私はその場を立ち去りました。他人事で、こんなに人をガッカリさせることのできる奴っているんだなと、逆に感心してしまいました(苦笑)。帰途で、ふと頭の中に、この若造のあどけないバカ面が、ぽっかりと浮かんできたので、心の中で、奴に向かってつぶやきました。「恥ずかしいね。俺も同じ日本人として、ホント恥ずかしいよ・・・」
November 16, 2005
-
「ごめんね」を「ありがとう」に言い換える
「1リットルの涙」ってドラマ、はじめ見るつもりはなかったんだけど、新聞で大きくPRしてるものだから、チラッと途中から見たら引きずりこまれてしまい、終わりまで見てしまって、気づくと涙をボロボロこぼしている。冷静に考えると、これ見よがしの話なんだけど、原作は実話をもとにしたもので、心に突き刺さるストーリーなんだよね。タイトルのとおり、これ見た人は日本中で泣いてるかもしれないね(泣かないか)。1人で1リットル涙を流すのは無理だけど、あるシーンで日本中の視聴者が同時に泣いてるとしたら、その瞬間の合計が1リットルに届いてるかもしれない。「瞬間視聴率」ならぬ「瞬間涙量」が1リットル、ってなとこかな(だから泣かないっての)。流した涙で心が洗われて、おまけに視野が清く鮮明になって、バリアフリーというか、ユニバーサルな目で社会を見ることができる人が増えるといいですね(^^)。皆が涙したかどうかなんて知ったことじゃないけどさ。どうも近頃、「世界の中心で愛を叫ぶ」、「いま、会いに行きます」、「あいくるしい」だのといった、難病などの病気に苦しんで死んじゃう人たちを主人公にした映画やドラマが多くて、なんとなく、ブームっぽくなってる。そういうブームに乗って流すように見ちゃうのがイヤで、つとめて見ないようにしてたんだが、あんまりそういうことにこだわるのも、バカバカしいと思ってたところでもあるのにゃ。それはそうと、私が泣けてしまったシーンのひとつ。------------------------------------ヒロインの少女が、普通の高校生のように歩いて学校に通いたい、家族に負担をかけたくないと思うのに、思ったようにいかなくて、結局回りの好意に甘えることになる。そして症状の進行とともに、だんだんと周りの負担が増えていく。そこで、仕事や学校を抜けて見舞いに来てくれる母や妹、荷物を持ったり歩行を支えてくれる友達、車で送り迎えに来てくれる父などに、元来素直で心優しい彼女は、「ごめんね」とつい謝ってしまうんですね。職人気質のお父さんは、「何あやまってんでい」なんてちょっとテレ気味に鼻をこすったり、ちょっとツッパリ気味の妹も「ごめんごめんって、もう、いちいちウザいんだよ」なんて云いながら荷物担いだりする。それ見た本人は、ますます申し訳なさそうに笑顔を作る。------------------------------------なんとなく、自分自身が少し以前に病気をして、忙しいときに仕事を滞らせてしまったときなんかにも、云わずにはいられなかったんだよね。この「ごめんね」って言葉。そのときの、なんともいえず心苦しい記憶を、このシーンにオーバーラップさせ、共感してしまったようなところがある。「わかるなぁーその気持ち、うぉーん」なんて、徳光さん風に嗚咽したりしてね(笑)。ちょっと他の人とはツボが違うだろう(笑)。なんかね。「ごめんね」って言葉は、云ってる本人と云われてる相手の、扱い方とか受け止め方がまるっきり違っちゃう言葉なんだけど、云ってる側は、なかなかそれに気づくのに時間がかかるんだよね。もどかしいことにね。本人は「云わにゃぁばちが当たる」という義務感で云ってるようなところがあるんだけど、謝られる側にとってはこの「ごめんね」が、「私があんたたちみたく元気じゃないせいで迷惑かけちゃって、このままだとあんまり情けないから、せめて謝っとくので、お願いだからお詫びの言葉聞いて」みたいなひがみっぽい意味に聞こえて、けっこう傷ついちゃう。そういう言葉を、できれば聞きたくないのに聞かされるから、案外苦しい。とはいっても、こういう気まずい気持ちも苦しくてウザい気持ちも、「いま生きてる」って実感しながら味わってると、味わい深い人生のプロセスなんだとは思いますけどね。その場じゃそんなふうに思えるはずもなく、とにかく当の本人たちは苦しいのだ。先週の話の最後で、ヒロインの少女は、この「ごめんね」が逆に相手を傷つけ、苦しめる言葉でもあることに気づいて、「ごめんね」をやめて「ありがとう」に言い換えようと心に決めるんですね。このことは、結構お互いの心の重荷を解くためのすばらしい前進で、たぶん有効に作用することなんだろうと思います。ほかにも、障害者の認定を受けることに対する抵抗とか、親しい人たち以外の、周辺の人々の視線に対する意識とか、いろんな葛藤とか悩みが、この物語の主人公一家にはあるみたいなんだよなあ。だけど、本人たちが前向きに生活しようと思える限り、彼らは決して「かわいそう」でも「気の毒」でもない。かといって、「大丈夫?」「大変だね」「辛いね」「頑張って」なんて、いちいち云ってみるのも、ときと場合によりけり。あんまり普通な態度というのも、ときにいたわりを欠く場合もあるし、かといって過剰に意識しすぎるのもよくなかったり。障害者と接するときって、どうしても「健常者とは別だな」って意識で見ざるを得ないから、苦しんでる人たちと接するときって、人間関係上でも、互いに辛い時期は必ずあるよね。これはしようがないのかもしれないけど、互いが互いを思いやる気持ちを持って接すれば、たぶん乗り切れるんじゃないか、なんて。なんだか、またまたとりとめなくなってきたな。こういう話は、書いてるうちに頭がぐしゃぐしゃになって、云いたいことが支離滅裂になっちまうんだ。こういう思考傾向って、自分にとってはいけないことだってわかってるんだけどね。
November 15, 2005
-
えなりくんの育て方
深い意味は全くないけど、けふはえなりくんをいじってみます。<ジジキャラ>えなりくんは、TVに出るたびにジジむさいとよく云われ続けているけれど、本当にジジむさい人なのかもしれない。というか、根っからそうなるように操作されているのかもしれない。「渡る世間は鬼ばかり」の橋田センセはかなりのご高齢だが、えなりくんは本当に小さい頃から子役として、橋田センセの脚本に従って、味噌ラーメンのオヤジとか泉ピン子とか、生活時間の多くの部分で、あのへんのジジババに囲まれ、接しつつ育ってきたんだろうと思われる。そうなると、ジジババ会話が身についてしまって、他のものには関心も奪われてしまっている可能性がある。たぶん、えなりくん自身の性格と、ジジババのトーンというのが、相性がよかったのかもしれない。それでそのまま「ワタオニ」に育てられて、気分のいい環境に身をゆだねているうちに、本当にジジババ的な性格のヒトに成長してしまったのかもしれない。<ワタオニチルドレン>これが、ある程度大人になってから「ワタオニ」出演が決まった、他の俳優さんたちなら話は別で、藤田朋子とか植草和秀などは、しっかりと若い人たちとの普通モードの会話にも対応できるんだろうと思う。だけど、えなりくんに限っては、橋田センセの世代の会話の枠に収まってしまわざるを得ないのである。云ってみれば、純粋培養された生粋の「ワタオニチルドレン」なんですね。他の番組やドラマなんかには滅多に抜擢されないし、出るとしても、彼の背中にはワタオニメンバーの顔が、背後霊のように憑いてるのが見えるので、おのずと彼の仕事はジジババ向け番組になってしまう。他の芸能人との交流の世界に入るのにも、たぶん彼は自分のワタオニモードとのギャップを克服するのに苦心しているだろうと思いますヨ。私自身は「ワタオニ」殆ど見ないのでよく知らないため、ときどき見てるらしい妹から聞いた話なんだけど、どうも「ワタオニ」に登場する若い人たちが携帯電話を使うシーンなどで、なんとなく今の時代からはピントが外れたようなことをしてる場面があるらしい。橋田センセが、リサーチを怠ってるせいで、登場人物の言動は、ドラマの中に限っては、皆ジジババ向けにさせられるのであるネ。他の役者さんはその場限り。えなりくんはドップリ(笑)。<では、えなりくんを育ててみよう>だが、もしえなりくんを子役の時代からずっと使ってきた脚本家が別の若手の作家だった場合を想像してみると、結構面白いかも。もしかしたら違ったキャラクターの人になっていたかもしれない(とはいってもそういう脚本家や監督って、あんまり知らないけど)。野島真司だとしたら、地味でおとなしい優等生みたいにするのかな。工藤官九郎だったら、逆に明るくひょうきんな、サザエさんちのカツオみたいな性格なんだけど、やや仲間からは浮いてるようなキャラに、えなりくんを育てるかもしれない。面白そうなのが三谷幸喜。彼ならば、なんでも出来て器用ビンボーっぽいえなりくんを、二枚目を除いたいろんなキャラに使いこなすかも。そんでもって、使いやすいからいろんな芝居やドラマや映画に登場させて、多忙な大根役者に育て上げるかもしれない。なんつーて、スゲー適当な想像でした(^^)。
November 13, 2005
-
心をのぞけなくとも・・・
やれやれ。近頃の殺人事件ときたら、少年が犯した信じられないようなものばかりが話題に上ってますね。事件の詳しい事情まで知らないからなんともいえないが、ニュースや新聞を見る限りだと、あまりに稚拙というか屈託のないような動機で、人の命を簡単に奪っちゃってる。「高校入学後彼女が冷たくなったから刺した」なんていう話だったけど、そんな、フッタ元カレに冷たくするなんていう当たり前のことに対して、当たり前に受け止められないっていう、社会性マイナス100みたいな事件だよな。その前の毒物オタクの少女による母親殺人みたいなのも、親子のつながりみたいな、ものすごく基本的なことに対する認知ができてない犯行だった。乱暴な云いかたをすれば、「こんな未熟なガキのくせして凶器とか毒物の使い方とか覚えようとするなよ」みたいな事件だったね。んで。これらの事件のことではないけど、近頃の稚拙な少年犯罪だとか学校の崩壊のような話題に対して、テレビのニュース解説をやったりする犯罪評論家や教育評論家みたいな人が、いろんなこといいますね。たとえば、「親が子どもをほったらかしにするせいだ」「昔と違って、社会の大人が子どもや若者をしつけないからだ」「学校が子どもを受験地獄に追いやったせいで、スポーツができなくなった子どもにストレスが溜まって非行に走る、スポーツやればOK牧場」「大人が悪い見本見せるから子どもが真似するんだ」などなど。云ってることは理解できなくもないというか、的を得てる部分も多いとは思います。ただ、なんとなく人に責任を押しつけるような意見が多い。子どもには責任を負える能力がないことから、それを守るのが大人社会や親であるという考え方。それだけでは前進というか根本的改善の道が見えないように見える。勝手な私の思い込みかもしれないですけど。今回の殺人事件2件を見てると、その加害者の周りに、身近な友達のような存在が、よく見えない。よくわからないまま想像の範囲で無責任な云いかたをするようで、申し訳ありませんが、彼らにも友達はいたのだろうけど、犯行動機におよぶ過程で、友達には何も相談したりしなかったんだろうな。また、犯行に及ぶ経過で、彼らに情報を与えたり動機を高める役割をしているのが、テレビだったりインターネットだったり、そういうものに限られていたのではないか。そんなふうに思えてならないんですけど、どうでしょうか。もしなんでも相談できる友達がいるならば、たとえば元彼女が冷たいから、ということを友達に相談したりできているかもしれないし、お母さんがムカつくとかそういうことを話すことができていたかもしれない。そうした会話を通じて、友達から適切な行動のヒントをもらえていたかもしれない。友達って、そういう拙い行為や発言を補う上で大事な役割を持ってるもんだと思うのですが。もし「大人が悪い」という意見が根強くて、大人の問題点に重きを置くのであれば、次のような点が問題点かなあ、などと思ったりしています。(1) その子のよき友達づくりを応援したり見守ったりする配慮が不足していたこと(2) 子どものテレビやインターネットからの情報の使いすぎに対してもっと注意すべきだったということ(3) 今回の被害者への「悪意」に関する話を親身に聞いてやり、尊重してあげられる余裕がなかったこと(3)は、あるいはスクールカウンセラーなどの役目かもしれませんが。そういう心のゆらぎに対し、耳を傾けてやるような存在が、彼等の周辺にはいなかったんでしょう。まあ、親にも先生にも相談できないようなことの相談相手を見つけるのは、なかなか難しいことなのかもしれない。相談に乗る役割の人が、通り一遍の存在だったらいけないのだろうなあ、などと思います。
November 12, 2005
-
まり~り~ん・・・(T T)
本田美奈子さんが死んだ。民放の日曜夕方のニュースを見ようとTVの電源を入れた直後、チラリと彼女の「ミス・サイゴン」の映像が映ったあと、すぐに別のニュースに切り替わってしまったので、「!?」と思ったまま、今朝の新聞を見るまで正確な情報がわからなかった。入院当初、「良性の白血病だから、必ず復帰するから応援してください」と、彼女の所属事務所などの話をスポーツ新聞で紹介していたので、てっきりそのうち直って、「徹子の部屋」なんかに笑って出演してくるものだと信じていたのだが。「良性」っていう情報は、なんだったのか。医師による励ましか、はたまた本人からファンへの心遣いだったのか。そう、考えてみれば、この人は我が同年代の人なんである。なので、この訃報は、他の芸能人の場合以上に、すごく心にズッシリくるニュースなのである。白血病なんて、もっと若い人も患ったり亡くなったりはしてると思うけど。けれど、割合最近、物心ついてから初めて「友達」と呼んだ人を、やっぱり突然の病気で失ったことがあるだけに、同年代の死ってのは、ショックがすごく大きい。で、数年前に別の病気で入院経験もある我が身としては、身体を大切にせねばならんのう、と改めてしみじみ思ったりするのでもある。古い話だが、ビートたけしが司会の「スーパージョッキー」に、本田美奈子がゲストで登場したとき、ファンから彼女に宛てたハガキを、たけし軍団のグレート義太夫が読み上げながら、義太夫 : 「『本田美奈子さんはお菓子が大好きで、いつもお菓子ばかり 食べてるから、ご飯が食べられなくてなかなか太れないそうですね』 というお便りですけど、僕もお菓子が大好きでよく食べるけど、同じこと やってるのに、僕だけどうしてこんなに太っちゃったんでしょう?」たけし : 「ばかやろう、お前は菓子も食うけど飯もたらふく食ってるじゃ ねえかよ! パシン(ハリセンで義太夫の頭を叩いた音)」美奈子 : 「アハハ・・・」てな感じのやりとりがあったのを、ぼんやりと記憶している。ピンクレディーが昔大変だったという話が最近よく出るけど、昔のアイドル歌手というのは、寝るヒマもないほど、一様にものすごい過密スケジュールをこなしていたという。今考えると、明らかに健康に悪いようなダイエットも沢山流行ってたし。成長期に多忙で、規則正しい食生活や健康管理ができないまま、さらに忙しい芸能生活を続けてしまったせいで、病気を克服するだけの抵抗力が弱まってしまったんじゃないだろうか、なんてつまらんことを考えたりする。天国で、やっぱり歌が上手かった岡田由希子と仲良く同年代ユニットでも組んでいて欲しいと祈るばかりだね。ってちょっと云ってることが変かなと思いつつ、冥福を祈るばかりだ。
November 7, 2005
-
雑感
ややお久しブリだいこん。ここのところ得た情報を見て感じてることとかとりとめもなく。<爆笑>最近テレビで2回ほど云ってたけど、「爆笑」ってのは、大勢で蜂の巣をつついたような笑いのことを云うんだってさ。つまり一人で爆笑する、ってのはありえない。だから、ホームページとかメールで、笑い話のあとに(爆)とか書いてたが、ありゃ間違いだったってこったね。ちと恥ずかすぃつーかなんつーか。まあ、当分私は、あんまりネットの書き込みもやらないだろうから、どうでもいい話ではあるけど。この話は以上!<和泉元弥>「モトヤ」の「ヤ」の字がでてこないのでご勘弁。それはともかくとして、この人は、なにやってんだか。東スポで、やたらと近頃、「狂言チョップ」のこととかセコンドにお母さんが陣取るとか、相手のアメリカで悪役レスラーやってる夫婦が「葬ってやる」とインタビューで云ったりとか、インリンさまと奥さんが下着脱がせ合戦をやるとか、そんなのが紙面を賑わしてるネ。「ハッスル」に出るという話はなんとなくわかったけど、具体的にどうするのか、またどうなったのかとか、そういうのが全くわからない。ワイドショーとか見てればわかるのか?わからないけど、想像を膨らませると面白いネ。この人、北条時宗だった、宮川一郎太に似てる人でしょう。あのか細い体で、プロレスラー相手にどうやって戦うのかとか、受身をちゃんと取れるのかとか、いろいろあらぬ想像をしてしまうネ。それとも、声だけフキカエで、実際は高田が出てきて、「かかってこいやぁ~!」って、あの通る声でオタケビを上げたりするのだろうか。まあ、わかんないままでいいや(笑)。<N’s(ナース)あおい>「週刊モーニング」で連載中のこの漫画が、年明けからドラマ化されることが決定したそうだす(^^)。個人的には大好きな漫画なので、いちおう応援してます。タイトルとは裏腹に、看護師のあたたかさに包まれた、医療現場の問題点を鋭くえぐるような内容の、けっこうシリアスな内容の作品。だから、患者のことを物扱いするような言動をとるドクターとか、医療の限界が垣間見えるようなシーンが、原作では結構出てきます。手塚先生の「ブラックジャック」や、フジテレビで過去にやってた「ナースのお仕事」などより、数段リアリティがあるだろうと思われます。実際どうなるかわからんけど。それにしても、コミックのドラマ化は、近頃本当に多い。実際に絵を見てしまってるだけに、ストーリーもスッと頭に入って来やすい点が、制作者としてはメリットにもデメリットにもなりうるところでやんす。「ドラゴン桜」みたいに、ドラマのほうが原作を追い越しちゃって、実際のストーリーと違う決着がついたこともあったしねえ。それはそれでいいと思うけど、ドラマウォッチャーに対して、ごまかしが効かないという点で、ハードルが高そうですね。<楽天と村上ファンド>金曜日はプロ野球オーナー会議でしたね。どうなったのか、よくわからないけど、またどうなったとしても、それを見てどうこういう気持ちも資格も、あんまりないけど云っちゃうけどね。村上さんと三木谷さんにお願いしたいのは、プロ野球を大切に思って欲しいってことだね。最低それだけは忘れないで欲しい。なんか報道を見る限りだと、2人は金儲けのために球団を使おうとしてて、それに反対する古くからの人材のクビをブッタ切ろうと考えているみたいな、そんな感じで報じられているけど。そりゃあダメだ。そんなことするなら、今回は手を引いたほうがいい。60年近くもかけて培われた、プロ野球の形が、いいのか悪いのかはよくわからないけど、たぶん悪い部分も多いんだろうと思うけど、いい部分もあるんだと思う。そんなことは、2人にはあまり興味ないんだろう。古き悪しきシステムだけを崩して改善する、ってのなら、大いに賛同する。けれど、そんなことまであんまり考えてなさそうに見えるもんなあ。稼げるだけ稼がせてもらって、あとはどこの馬の骨ともわからない投資家が現れて「売ってくれ」って云われれば、すぐ売っちゃったりするんだろう。経済の世界ではそんなの常識かもしれないけど、そういうやり方は、プロ野球の世界はじめ日本社会では、まだぜんぜん浸透してないんだよ。まずは目線を相手に合わせる気配りを、なぜできないのだろう。そのうえ、社長就任後、株式上場に反対してた前幹部を全員クビにするだのなんだの、云うことがいちいち乱暴すぎる。単に上場を反対したという理由だけで、球団の発展に本気で取り組もうとしてたかもしれない幹部のクビを、情け容赦なく斬ったりしたら、当然反発を受けて、やがて我が身をも斬ることになるんじゃないかと思ってしまう。投資会社って、云い方はよくないかもしれないが、わらしべ長者に見える。結局のところ、自力では何も社会に貢献しないで、他人のフンドシで相撲をとってるだけのような。というか、そういう目で見ちゃうのが、今の日本社会なんだよね。だけど、「日本むかし話」のわらしべ長者ってのは、もっと謙虚な人であったはずだと思うけど。「まんが日本むかし話」でやらないかなあ。<マチャアキ体操と新米コシヒカリ>「あるある大辞典」で紹介していた3分間のサーキット運動。毎朝3週間続けてたら、心なしか身体が軽くなってきた(ような気がする)。さらに、腹部の贅肉が心なしか落ちて、なんとなく腹筋も浮かび上がってきた(ような気がする)。今まで地道に走りこんだり腕立て腹筋などなどやってきたその積み重ねはいったいなんだったのかと、やや情けない気もする。さて、こうして油断していると、こういうささやかな喜びをぶち壊しにしかねないのが、食欲の秋でありますにゃ。つーても、自力でそれを満喫するにはたかが知れてますが。田舎の新潟から送られてきたコシヒカリの新米を、前日実家からもらった。前月、親族の法事に出かけたのだが、それを契機に送られてきたものであるらしい。私はふだん、混合無洗米に押し麦を混ぜて食うというテキトーな食生活を送っており、昼もこのご飯を弁当に詰めて外出するため、早い話が日がな麦飯生活なんであるが、この前新潟でこの新米のご飯の味を再確認してしまった私は、この新米に麦を混ぜてしまうのはあまりにももったいないと考え、久々に「米だけの飯」を炊いた。炊き上がった新米の、なんてツヤツヤで真っ白で美しいこと。それをかみ締めた瞬間に、ささやかな至福の瞬間が訪れた。(↑って、どうも池波正太郎とか、彦麻呂みたいな表現は恥ずかしくてできないけど、そんな感じだったのですね)このために拵えたなめこ汁を添えて、久しぶりに贅沢な朝食を食らうことができた。向こう2、3日は、新米を食うことができる♪農家の人たちに感謝したい気持ちになりましたね。家庭や学校での「食育」ってのは、いいものを食べさせながらやったほうが、絶対に上手くいくんだろうなあ。どうでもいいけど。
November 5, 2005
全12件 (12件中 1-12件目)
1