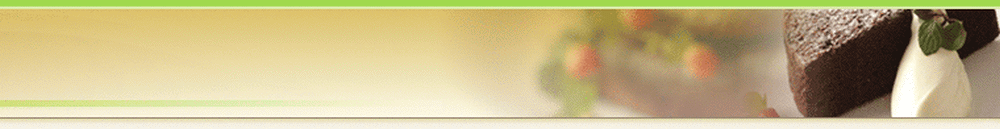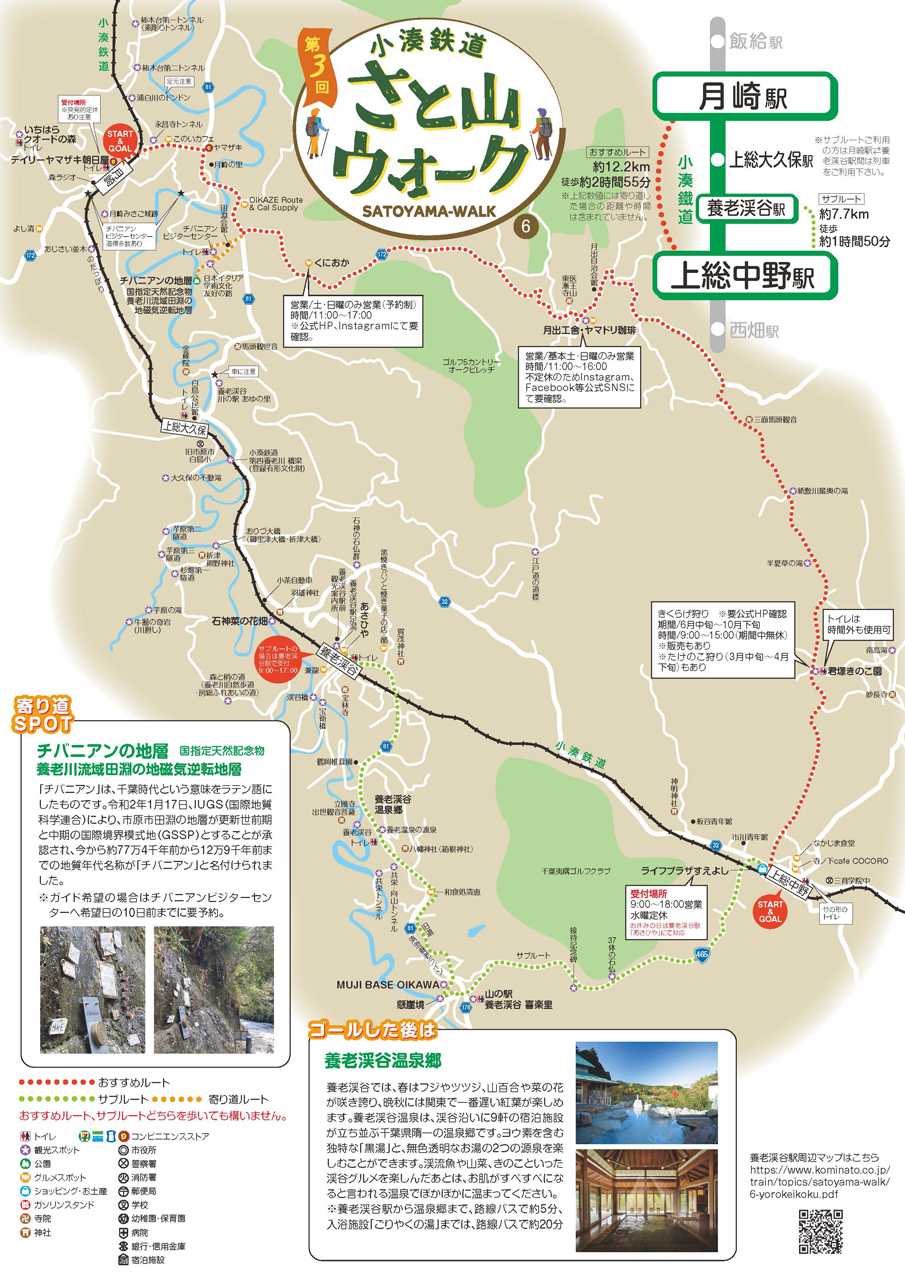2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年07月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
お前が打たねば誰が打つ!?
<おばちゃま週末はね・・・>土日は、大学院見学と図書館ごもりの受験追い込み勉強の日々であった。このところ、朝は9時から夕方まで図書館にこもりっきりの小森のおばちゃまでざ~すのよ(鶴太郎風)、ってな感じの日々である(ちと古いか・・・)。ちなみに今日はタイプー7号による大雨警報が出たため自宅で勉強中。まあ、自宅にこもりっきりの状態よりかはいくぶん気分転換になるし、テレビも漫画本もないぶん、10倍以上は勉強に集中できる。ためしに時間を計ってみたら、いつも3日がかりで和訳する5頁ほどの英文を、3時間程度で一気に訳し終ってしまった。このように毎日、本を読みにいくわけでもないのに図書館を独占してしまうのは本当はダメらしいのだが、まあこういう生活も今年だけですから、図書館の人たちにも、寛容な対応をお願いしたいものだ(←勝手な了見)。<ワセダ酔い?>そんなわけで(何がそんなわけなのかは不明)、土曜日はワセダ大学の隣にある、バカ田大学の大学院を訪問。「みやこのせいほーく ワセダーのとなりー バカダーバカダー♪」という校歌は聞くことができなかったが、なかなか面白い大学であった。目的地までの道筋がわかりにくく、ウロウロしてたらワセダ大学の敷地内まで潜入してしまっていた。ひとつの街のような大学だネ。周辺には、学生向けとおぼしき安い飯屋が軒を連ねてるし。だけど、はじめてきちんと歩くワセダは、私にとっては「行けば酔っ払う街」という印象であった(酒を呑んだわけでは全くない)。大学生だらけの街で、おしなべて、メガネの奥に鋭い眼光を光らすワセダの学生(その日見かけたのはそんな奴ばっかりだったのだ)を、横目に見ながら歩いていたら、なんだか頭がクラクラしてきた。あるいは熱中症だったのかもしれないけど。これはワセダに限ったことではなく、つくばとかタマ、ハチオージ、トコロザワといった学園都市等を訪れた場合も、俺はこんな感じになるのかな、とふと思った(←んなこたぁないだろう)。けれど、来年からそういうところに通おうと思う人間が、そんなことを云ってるバヤイではない。試験の日までに「ワセダ酔い」を克服せねば大変なことになる。<やきう禁断症状!?>日曜日はつるみのほうで、わが愛するベアーズが試合であったのにゃ。そっちへ行きたい気持ちを抑えつつ、図書館へ向かった。だが時間を追うにつれ、やきうが恋しい気持ちはだんだんとエスカレートして抑えきれなくなり、かといってやきうができるわけでもなく、しょうがないからその埋め合わせに(?)、午後日が暮れない時刻に帰宅すると、東京MXTVで放送していた、高校やきう・西東京地区の予選を見た。そのへんの思考の脈絡が全然ないのだけど、疲れで頭がボーッとしてきて、甘いものが欲しくなったような気分とでもいいましょうか。とにかくそういう気分になって、取った行動が「高校やきう見る」だったのだ。んー、やはりやきうはいいもんだ(←「やきう中毒」というのがあるなら、どうやらそれらしい)。ひところ、高校やきうに対してなにかしら反感を抱いていたが、だんだんそういう気持ちは薄れてきたネ。ヘタッピながら、自分でも草やきうをやるようになったからかもしれない。高校やきうをとりまく周りの環境には何かしらの問題があるのはわかってるけど、プレイヤーには関係ないというか、責任のない話だからね。そんなの全くおかまいなく、縦横無尽、楽しそうに走り回ってる選手たちを見ていると、妙な反感めいた気分はどこかへ吹っ飛んで、すがすがしい気分になれる。<ド根性じあい>以下、やきうの試合の話がムダに長くなるよん(笑)。TVで見たのは、ホリコシ学園対メイ大ナカノハチオージの試合であった。ちなみにメイ大ナカノハチオージは中大兄皇子とは関係ない(←当り前だ)。以下「メイナカ」と記す。ホリコシが先行して、メイナカが追いつくという競った展開が9回まで続く。メイナカのエース・ホリくんは再三ピンチを招くも、ときに力でねじ伏せ、ときに打たせてとるという巧みな投球で踏ん張る。ホリコシのエース・ヒジカタくんも抜群の制球力で、なかなか点を与えない。我輩、次第にメイナカを応援する気持ちになってきた。9回表ツーアウトまで、ホリコシが3-2とわずか1点のリード。同点ランナーが2塁にいる。あと1アウトとればホリコシはそのままベスト4進出。あきらめムードが漂いはじめた瞬間、メイナカの打者がライト前にタイムリーを放って同点。でその裏もピシャリと抑え、試合はついに延長戦へ。どっちもなかなか主導権を譲らない。ホリコシにあと1点でも入った瞬間にサヨナラ勝ちでゲームセットだし、メイナカのホリくんも疲弊して、はっきり肩で息をしてるし、ホリコシ圧倒的的有利かな、と思ったのだが、打線がこのホリくんをどうしても捕えることができない。そのまま放送は、試合結果を待たずに終了してしまった。翌朝新聞を見たら、メイナカが延長12回で勝利したという。こんな暑い中、どっちのチームも大した精神力だが、最後はメイナカが、ド根性でワシ掴みした、という感じの勝利である。ホリコシはさぞかし悔しかったことだろう。だけど、1、2年生中心のチームだけに、来年は優勝候補の一角を担いそうな予感がする。<乾坤一擲!>メイナカ・1番ライトのコマチくん。チーム内で最もバッティングの評価が高くて、監督からも全幅の信頼を得ていながら、放送の間は全く打てなかった、というか、いい当たりの打球を打つのに、全部野手の正面を突いて、6打席凡退していたが、勝負を決した延長12回表に回ってきた7打席目(!)に、値千金、決勝の3ランホームランを打ったらしい。残念ながら、TVカメラはこの瞬間をとらえることができなかった。この打席のコマチくん、対するホリコシのエース・ヒジカタくんとも、まさしく「乾坤一擲」の気持ちで勝負に挑んだであろう。いちかばちか、のるかそるかの勝負。勝利の女神は、この打席の瞬間、打者のほうに微笑んだ。なんとなく7年前のヨコハマ高校-PL学園の、延長17回に及ぶ激闘を彷彿とさせるネ。思えばあの試合以来、高校やきうの延長戦は15回までと制限されたのだったネ。ちかごろ、高校野球の応援で、なぜか山本リンダの「狙い撃ち」(古い!)が流行ってて、「ウララーウララーウラウララー この世は私のためにある♪」という歌詞を、「打てよー打てよーホームランー お前が打たねば誰が打つ♪」と替え歌して唄ってるのをよく耳にするが、これぞまさしく、「お前が打たねば誰が打つ!?」という感じであったネ。まあほかの選手も打ってはいたけど、最後にコマチくんが打った結果勝利をつかんだところを見ると、彼はどうやら打線のキーマンとして、チームメイトからも頼りにされている人材らしい。彼はたぶん準決勝でも、この打席で得た勢いに乗って、打撃を爆発させるであろう。このまま甲子園まで行けるほど、予選は簡単ではないと思うけど、最後まで頑張って欲しい。なんとなく「あきらめずに懸命に頑張って、最後に報われた」という例を見たようで、こっちも元気をもらったような気分であった。こちとらもあきらめずに必死で頑張るべし!!・・・って、なんとなくオチは決まったようでいて、全然脈絡ない話になってしまったけれど、こちとら別に文章書きのプロじゃないから、バカ田大学OBのバカボンパパにちなんで、「これでいいのだ」といいたいところだが、全然よくないのだ。
July 26, 2005
-
気になる気になる・・・
<気にならない>前回の日記のつづきは、書くのをやめました。くだらないし、例に挙げたゴシップ話は、どれも全く私には興味がないしね。唯一、キクちゃんは好きなアナウンサーだったので、早くほとぼりが冷めて、ブラウン管に復活して欲しいですね。なーに、そんなのすぐでしょうよ。口角泡を飛ばしてる奴に限って、若いミソラに酒で失敗してるんだろうから(笑)。ただ、このお嬢は、いろんな意味で「落ちる」のが好きらしいのがちょっと気になりますね。こういう人はAV界が放っておかないから言動に要注意。<気になる>ちなみに、こんな話題が最近の私のツボというか、興味深いというか、気になってたりします。ややヒネクレ気味で恐縮ですが。○スーダンの内戦知らなかった。200万人もの国民が犠牲になっているとは!アフリカの情勢に関しては、情報がないという理由だけで、我々はかくも無知でおれるものなのか。戦争の悲惨さ残虐さを、単純に死者の数で測ることはできないが、今問題になってるロンドンのテロより、単純な数字上の計算でははるかにひどい。内戦の原因は、やはり宗教が一枚噛んでいるらしい。イスラム教とキリスト教。この2つの宗教信者は、どこの世界においても断じて相容れないものらしい。日本では、こんな争いというのは、事実はわかるけれど、全然実感がわいてこない。だから、この内戦に対して、どうのこうの云う資格などないのかもしれない。云えるのは、内戦などすること自体全く希望していなかったであろう国民が殺された大半であろうことに対して、「悲しいだろうに」「つらいだろうに」という程度のことだ。○はちみつ二郎いきなり全然違うトーンの話で申し訳ございません。以下こんなようなのばっかりでございます。m(_ _)mいえね、どういう人物なのか、何者なのかも全然知らないんですよ。あるテレビ番組のテロップに、突然名前が出てきたのを見てギョッとしたね。苗字が「はちみつ」だからね(笑)。このネーミングセンスは、想像するに、たけし軍団の新人とか、そんな感じですかね。詳しい人はおせーてくださいまし。○「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」光文社新書電車の中吊り広告でタイトルを発見して、どうしても読みたくなって、衝動的に買ってしまった本。まだ読んでない。どうやら新書らしい。「バカの壁」と同じだね。年に何冊か、こういう買い物をしてしまう。前回は「へんないきもの」だった。「電車男」はそういう本には含まれなかったネ(爆)。ベストセラー本は、滅多に読まないんだけど、これは面白そうな予感。会計についてのわかりやすい本だというが、私は会計については全然興味がない(笑)。○常食茨城県大洗町で食されている、お好み焼きともんじゃの中間ような食べ物「たらし」というのを、この前ニュースのおしまいで紹介していた。こういう、地元ならではの、名物というほどの仰々しさのない食べ物のことを「常食」と呼んで、「駅前の歩き方」というどマイナー漫画で紹介してた。他にもそういうものは各地にあるネ。テレビで紹介されてもあんまり食べたいと思わない、地元の食べ物(笑)。柏で売ってる、もんじゃ焼きが挟まった巨大なギョーザみたいなのとか。さしずめ山形は以前「あじまん」であった。近頃はよく知らないけど。もんじゃ焼きは月島が有名だけど、これは最近、観光名物っぽくなってしまい個人的には、なんだかつまらないものになってしまったようだ。かわりに月島の常食としては「レバフライ」がある。下町は奥が深いのだ。たぶん、皆さんの地元とかふるさとにも、そういういろんな「常食」があるんだろうね。○次はつぶしてやる!ナベツネがライブドアに対して云った言葉ではない(爆)。朝青龍が、黒海に負けたあと、支度部屋で黒海を指してこう怒鳴ったらしい。おおコワイコワイ。けど、これだけ闘魂をアピールできる力士は、相撲界にはほかにいないようだね。日本人は、国民性として、こんなことを公言できる人はいないだろうからね。やはりモンゴル人ならではの過激発言なんだろうか。ちなみに相手の黒海はグルジア人(笑)。
July 21, 2005
-
犯人はナシモトなのだ(1)
<ゴシップ学級>二子高校の2年F組は、別名「ゴシップ学級」と呼ばれている。別に、とりわけ不良生徒が集まっているわけでもないのだが、どういうわけか、このクラスばかりに、なにやらよからぬ噂が、次から次へと湧き上がっては、その都度クラスの生徒が次から次へと槍玉に上がり、休み時間は学校中の生徒が話題の生徒のもとへと押しかける。もはやまともな学校の1教室の姿ではなかった。休憩時間ともなると、教室がさながら記者会見会場や事件現場、はたまた珍獣がいる動物園みたいに、1年生から3年生にいたるまで、学生服を着た、文字どおり「黒山の人だかり」ができる始末。F組の男子生徒はさしずめ警備員だ。ただしそれは、たまたまそのとき「ゴシップ」の張本人でないものに限るわけで、昨日警備員役を買って出た者が、今日矢面に立たない保障はないのである。昼休み、これらの噂話について、オータとタナカという男子生徒2人組が面白おかしく語り、イージマという女子生徒が混ぜっ返すもんだから、これらの話の盛り上がりはさらに増すのであった。とある日の放課後、2年F組担任のオグラ先生は頭を抱えつつひとりごちた。「うーん、キューちゃ~ん、帰ってきてくれよォ。お前がいなくなってから、私がホームルームで話す話題が、全部クラスの奴らのヘンてこな話題に奪われてなくなってしまったじゃないか・・・」「キューちゃん」というのは、陸上部に在籍していたタカハシという女子生徒で、1年の秋に長距離で県1位の好成績を上げ、期待されていた生徒であった。先生たちへの受け答えもよく、クラスの中でも人気者であった。担任のオグラは陸上はずぶの素人だったが、自分の担任するタカハシの出る大会ということもあり、彼女に同行して得意の写真の腕を振るったりしたものであった。ところが今年の春に突然、顧問のコイデ先生と練習方針の食い違いから大喧嘩をし、先生を殴って怪我をさせてしまうという、信じられないようなことをしでかしたという。その上、その帰宅途上に、学校の近所の回転寿司屋に立ち寄って、腹立ち紛れの無銭飲食をしたことが明るみになって、とうとう停学処分になってしまった。さらに、この話にいつしか尾ひれがついて学校中に広まり、「タカハシが無銭飲食した寿司屋の損害額は5万円」などというとんでもない噂が出回ったせいで、元来温厚なタカハシも腹を立て、「あんな学校、こっちから辞めてやる!」などと家で母親に向かって涙ながらに話しているという。だが、自宅に引きこもっているというタカハシを励まして学校に出てこさせようとするオグラが先日家庭訪問に行っても、母親が、「うちの娘はコイデ先生に暴力などふるってないし、無銭飲食などもしていないと申しております。誰がそんな根も葉もない噂を立てているのか存じませんが、私どもはもう、お宅の学校が信じられません。他校への転入を考えています」と、玄関先でオグラはムゲに追い返されてしまったのである。<噂の数々>「あの事件以来、すっかりウチのクラスはおかしくなってしまったもんなあ。なぜこんなことになったんだろう・・・??」オグラ先生は、今後予想される難題に、再び頭を抱えた。確かにタカハシの事件を発端に、クラスの生徒をめぐる妙な噂が、あとからあとから湯水のごとくあふれ出てきているのを、オグラもすでに、いくつも小耳にはさんでいた。そしてその噂ネタに対して、なぜか全校の生徒が聞き耳を立てて押しかけてくることも。数ある噂の中から主なものを抜粋すると・・・噂1.『空手使いのホリエが単身、市内にある空手の強豪・藤高校へ、道場破りに行ったが、なぜか同じ市内の相風高校番長のキタオが割り込んできて、2人がかりで袋叩きに遭って逃げ帰り、以来道場破りをやめている』噂2.『男に縁がなく「負け犬」と呼ばれていたスギタが、とある合コンパーティーで知り合ったどこかの御曹司と交際をはじめたが、早くも別れの噂が立っている。駅前のマクドナルドで、彼氏に殴る蹴るの暴力をふるうスギタの姿を見た者が多数いるという』噂3.『先日亡くなった、理事長の遠い親戚の息子ハナダは、父の死後、遺産をめぐり大学生の兄マサルと激しく対立している。父の愛車フェラーリは伯父が引き取ることをさっさと決めたため、現在父のハーレーをどちらが取るかでもめている。ハナダは、「兄マサル氏は、すでに父から“ローバー”を買ってもらっているので、バイクは俺のものと考えるのは当然だ」と公言しているが、兄は下宿先から全く実家へ戻らず連絡も絶ち、話し合いを避けているらしい』噂4.『放送部員のキクマは、通っているバレーボールクラブの中学生と練習のあと、帰り道に立ち寄った酒屋で、ビールを無理やり飲ませようと迫り、酒屋の店員に厳重注意を受けた。バレーボールの監督であるお父さんの七光りで、警察への通報は免除されたが、酒屋での光景を見た者がいる。世の中は壁に耳あり障子に目あり、である。ちなみにその中学生とキクマとの関係は現在調査中である』などなど。ほかにも数えて見ればもっといろいろあるのだが、いずれも年頃の高校生の好奇心を、そそらざるを得ない話題ばかりなのであった。なぜこのような噂が飛び交うのか?誰が、なんのつもりでこんな悪意に満ちた噂を流すのか?次回、オグラ先生とともに我々は、驚愕の真相を知り、愕然とすることになる。(といいつつ、タイトルですでにバレバレ 爆)
July 19, 2005
-
学校や担任があてにならずとも・・・
「ドラゴン桜」「女王の教室」という、たぶん賛否両論の物議をかもしそうなドラマが2本同時にはじまったネ。個人的には、これらの物語の内容には基本的に賛同する。「女王~」がちょっとホラーっぽい感じなのが少々気になるが。「学校の怪談」とは話のコンセプトが全く違うわけだから、学校にわざわざ恐怖を持ち込んでウケを狙う必要などないからね。今後変わってくるのだろうか。「学校はサービス業」「勉強やらなかった奴はやった奴に、社会の仕組みを利用して一生だまされ続ける、だまされたくなければ勉強やれ!」というメッセージは、一見斬新に見えるが、至極当り前の理屈だと思う。それが、教育界に対する世論や倫理が「教育者=聖職者」にしてしまい、こうした理屈はことごとく否定され、あるいは包み隠され続けてきた。それを今まかり通そうというのは、世相に乗じたアピールということなんだろうか。ちなみにそういう番組を配信する人たちもまた、現行の教育によって育ってるんだけどね(笑)。このお話に出てくる先生の人格とか、教育者としての資質には、今までの「常識」からかんがみるに、いささか問題があるようだ。「こういう学校の先生は望ましくない」と思う人も多分大勢いるだろうと思うのだが、テレビが単に面白半分でこんなドラマを視聴者に見せているのかというと、そうでもないような気もする。というか、そういうことにあまりにとらわれすぎるから、気に病んだり、ストレスを溜めたり、絶望してしまうような気がする。担任の先生が、「金八先生」や「ヤンクミ」のような「人格者」(?)であるのに越したことはないが、もしそうでなかったとしても、なおかつ、自分の担任が、全く「人格者」と呼べるような人じゃなかったとしても、そんなことは、子どもにとっては思ったほど、精神的な発達や学校生活に悪影響を及ぼさないのではないか?「先生に考えを変えてもらいたい」「他の、もっと人間味あふれる先生に担任をやってもらいたい」ということを、当然はじめは皆考えるでしょう。だけど、変わることなど短い学校生活の間に簡単にはできないし、そもそも他人を変えることは不可能なのである。そうなると、変える必要があるのは、自分たちの考え方やものの見方だ。「人格者」じゃない担任の先生には、気安くいろんな相談なんかには行けないし、授業中、教室に笑い声がこだますることなどまずない。が、クラス担任だけが学校での話し相手ではないわけだから、友達と助け合ったり協力しあうことを覚え、自力で問題解決する能力も育つかもしれないし、その答えだって、他の先生や周りの大人の協力が得られれば、おのずと出てくる。授業なんてそもそも遊びじゃないんだ、というふうに考えれば、云うこときいて素直に受けてれば、そんなに子どもにストレスは溜まらない。担任とのコミュニケーションがとれないことなど、決してマイナス材料ばかりとはいえないと思う。むしろ、担任抜きでの子供同士の結束は固まるんじゃないのだろうか。ちなみに私の小中学校時代、卒業時の担任なんて、そんなに好きじゃなかったし、先生を尊敬する気持ちなんて、クラスの皆の中ではそんなに強くはなかったと思ったけど。話は少し変わるのだが・・・高校を舞台にした学園ドラマには、私はあまりリアリティを感じないのだが、一般的にはどうなのだろうか。私の通った高校では、担任の先生や他の教師に対して、ドラマで見るようにベタベタとふれ合うことなどなかった(というふうに私には見えた)。不良っぽい奴もいたことはいたけど、教師に面と向かってはむかったり口答えする生徒など、見たことがなかったね。だからそういうのは中学で卒業なんだと思っていた。不良っぽい生徒が怒られれば、「犯人が刑事に叱られる」ような感じで大人しく教師の説教を聴いていた(私の知る限りでは)。あたかも大人社会のやり方の勉強という感じで。教師としては、随分やりやすい環境だったのではないかと思う。だから、こういうドラマを見るたび「俺たちの高校って特別だったのかな?」という思いに駆られざるを得なかったんですネ。同時に「これが一般的だとすると、普通の高校生ってのは幼稚だな」とも思った。別に無理に距離を詰めてベタベタふれ合わなくても、心の交流はできるし、友情だってちゃんと育まれるわけで。なぜなら、そうしてできた高校時代の友達とは、10数年を経た今でも交流はあるし、呑みに行ったりもしてるもんね。まあ、だからといって「東大に行こう」などという思考にはいたらなかったわけで、全然比較にはならないだろうけど(笑)。だからというわけじゃないけど、生徒たちと心が通わないことを、大人が過度に気に病む必要はないように思うし、学校にそういうことを求める必要がある、と考えすぎる必要など、あまりないだろうという気がしてますネ。ただ、子どもたちのストレスのはけ口が完全に塞がれるということは危険なので、どこが彼らのフォローをする役割を担うか、っていうことを、生徒一人一人に対して考えてやることが、最も必要なことなんじゃないかと思ったりしますネ。そのことが、逆に一番難しいのかもしれない・・・。
July 18, 2005
-
野球至上主義?
最近の野球マンガとかアニメで、「サッカーが人気出ちゃって日本で一番盛り上がってるみたいだけど、本当は野球のほうがエラいんだぜ!」という、原作者のメッセージが聞こえてきそうなのがあるね。あだち充の「H2」とか、土曜日の夕方、NHK教育でやってる「メジャー」がそう。作者は決してそんなつもりはないんだと思うけど、そういうことに敏感に反応する一部の読者や視聴者は、そういう目で見るんじゃなかろうか。「H2」は、木根くんという男がサッカー部で、はじめのうち、主人公のヒロに対するアンチヒーローを演じていたが、徐々にその軽薄な性格が露呈してしまい、最後は結局ヒロに屈して、野球部の一員になる。「メジャー」でも、アンチヒーローのいじめっ子はサッカー少年で、主人公の少年と対立した結果タイマン勝負に敗れ、結局は一緒に野球をやることになる。なんか、あまりに簡単でアンバランスな、勧善懲悪的ストーリーが展開されているので、「こんな話でいいのかなあー」と思いつつも、読んだり見たりしつつ、知らず知らず、年甲斐もなく口元がニヤけている自分がいるのに気づくとき、我ながら情けないよな罪悪感のような、変な気持ちになって落ち着かなくなったりして、後味の悪いことこの上ない。なぜニヤけるのかといえば、勧善懲悪のお話を見て読んで、気分良くなるという「時代劇ファン的心理」以外のなにものでもないのだが、その題材がこれだからねえ。「だったら読まなけりゃいいじゃん!」みたいな話だけど、この手のマンガは好きだから、どっちみちまた読むのである。これらを見る層はおそらく、その大半が少年たちだろうから、熱心に読んでる子の中には、知らず知らず物語に影響されちゃう子もいるに違いないだろうね。その影響というのが、物語の本質に対してズバリであればいいのだが、それがちょっと歪んで野球、サッカーそのものに向けられるものだと、ちょっと嫌だなあ。「野球やってる子→いい奴、正義」「サッカーやってる子→いじめっ子、悪」みたいなね。まあ、そこまで考えて見る子なんて実際はいないかもしれないし、原作者もそんな子はいないだろうという想定で書いているのだとは思うが。学校の先生は、これらの作品について、夏休みに感想文でも書かせてみるってのはどうだろうか。あるいは「総合的な学習の時間」かなにかの授業の一コマに加えて、クラスで話し合ってもらうというのも面白いかもしれない。もちろん先生が自分の考えを持って、それを伝えて締めくくらないと、おかしなことになるだろうけど。・・・などと考えては見たけど、女の子には関心がないことかもしれないので、やっぱり難しいかもねえ。それに、ぜんぜんそんなこと問題じゃない場合にひっこみがつかなくなるしね。ということで、この空しい企画は、野球オタクの熱血教師の中で空回りした挙句、ボツなのであった(爆)。
July 17, 2005
-
絶賛王国
今日、夜8時のテレビ朝日「ミュージックステーション」で、私の妹の旦那さんが、「D51」というグループのバックで演奏するそうです。最近は、そういう仕事がメインらしいです。たまーにテレビに出たりしてます。ピンぼけの場合が多いですけど(苦笑)。地味な野村ヨッちゃんといったところでしょうか。ちなみにベース担当です。どうぞ見てやってくださいまし。* * * * * * * * * * * * * * * * * *タモリつながりの別の話。今日の「笑っていいとも」を見てたら、「テレホンショッキング」のゲストが常盤貴子だったのだが、彼女の会話の巧さに感心した。こういうのはお手本にしたいなあ、と思った。まあもちろん、会話というのはいろんなTPOがつきまとうと思うので、全てにおいてそれが通用するものだとは思わないけれど。常盤が、自分の出演する映画の話をはじめたところ、撮影現地でのエピソードの話題から、虎にエサをやる話になって、「こわかったですうー」とかなんとかいう話をしていたのね。そこでタモリが、「やっぱり虎に直接エサをやるのは怖いだろう?」と相槌混じりに云ったら、常盤が、「そうなんです。虎って個人的には大好きな動物なんですけど、そのときは本当に怖くて怖くて・・・」とかなんとか、そんなことを云った。するとタモリが、「えっ!? 個人的には大好きって、どゆこと?」と、得意技の「話の腰折り術」という、ゲストにとってはやや不快だが、視聴者へは薬にも毒にもなりうる、一般人が使用するにはあまりにリスキーだが、汚れ芸人にとっては日常茶飯事的という、微妙な技を繰り出してきた。会場は「ええー?」などと云って少しざわめいた。「テレホンショッキング」は、最近ときどき見るのだが、当初と比べてかなり時間が短くなっていて、そういう本筋と外れた話をしてしまうと、しゃべりたい本来の話ができないまま終ってしまう場合が間々あるようだ。生収録なので、長時間の録画を編集されて放送するというわけにはいかないのであるネ。お笑い芸人、特に間寛平などの吉本新喜劇の芸人などは、出だしでタモリとのギャグの応酬でほとんど時間を費やしてしまうことが多いらしい。「テレホンショッキング」以外の、笑福亭鶴瓶とタモリとピーコのコーナーなどは、脱線のしすぎで、無間地獄というか、出口の見えないトンネルの趣すら漂う。本人たちはあれで皆が面白いと思ってるのかなあ。思ってるんだろうなあ。タモリは常にホスト役で毎日出る立場だから別にいいけど、ゲストにとっての「テレホンショッキング」はその日のその時間限りであるから、話したいことがある人は、それが話せなくて、ちょっと不満な顔をしたりするのである。けれど、常盤貴子はタモリの攻撃に対し、「まあ、その話は今日じゃなくても話せるので、追い追い別の機会に話しますから・・・」と云って、自分の話したい話をよどみなくペラペラペラッと話し、会場はその話題で再び盛り上がった。技をかけ損ねたタモリの表情が一瞬曇ったのだが、彼には来週もそのまた次もあるのだから、今日フラストレーションがあったとしても、別にいい。そのへんも常盤は心得ているように見えた。銀座あたりのキャバレーなどで、オヤジのセクハラをうまく手玉に取り、ちょっぴりいたずらを叱ることによって、オヤジのMっ気を引き出して満足されちゃう、手だれのホステスのようでもあった。さらに、月曜日に呼ぶゲスト選びで、同じ映画で共演している主人公役の少年を呼ぶ段になり、その紹介で、「映画『○○○○○○』で、先日のカンヌ国際映画祭で史上最年少で主演男優賞を受賞した、ナントカくんです!」と、しっかり仕事仲間を立てる紹介の仕方で締めくくった。完璧である。なかなかああいう、皆の視線が集まる場で、あーは出来んよ。月曜日ゲストのナントカくんは、常盤に足を向けて眠れないと思ったことだろう。常盤貴子は若く見えるけど、結構ベテラン女優であるし、若い頃から人気者であったから、いろんな人と話をしてきて、テレビでしゃべる機会も豊富にあっただろうから、かなり心得ているのだろうと思う。彼女のしゃべりが流暢で話題豊富なことに感心したわけでは決してなくて、状況と今日このときの目的にあわせた対応がきっちりできていたことに対して、なおかつギャラリーや視聴者のことも意識したしゃべりがきちんとできていたことに対して、「凄い」と思ったネ。
July 15, 2005
-
怪談というか・・・
もうすぐ暑ーい夏なんで、というかすでに暑いので、背筋が涼しくなるこわい話でもと思ったのですが、どうも私の周りには、どっちかというと笑える妖怪しかいないもので申し訳ない。以下、私や私の身内や知人の身の回りに出没してきた妖怪(?)たちです。大したことないんでそのへんは許してください。つーか、もうちょっと「怪談」らしい話を持ってる方は提供してください。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<白衣男>ウチの近所には子どもの頃、小高い山がいくつかあって、今はすっかり整備されてしまいましたが、今は首都高入り口になっている辺りに、切り立った崖がありました。その崖のほうに行くと、白衣を着た、痩せた中年男の姿をした妖怪がいる、と云われておりました。その男は、遊びにきて迷い込んだ子どもをかどわかしては、そのへんに当時生息していたマムシの毒が入った注射を打って、打たれた子どもは眠らされたまま生きて帰れなくなってしまうということで、その崖の方へは行ってはいかん!と小学校の担任の先生から厳しく禁じられ、私たちはそれまで一部で流行していた「ターザンごっこ」をやりに行くのをやめました。これは、この担任の先生が子どもたちを危険から遠ざけるために、このあたりの言い伝えとして、即興でこさえたお話で、いちおうクラスのお母さんたちの間では、割合まことしやかに広まり、「子どもにドリフは見せないこと」というのと同様、「子どもを崖のほうでは遊ばせないこと」という禁止事項が、お母さんたちの合言葉としてすっかり定着しました(笑)。ところが同級生の中に、勇敢というか、ただ単に目立ちたがり屋の少年がいて、好奇心も助けてか、「白衣の妖怪を退治しに行こうぜ」としきりに私たちを誘うのですが、誰一人として彼について行く者はいませんでした。その後、夏休みのある日の夕方、彼は無謀にも、たった一人で崖のほうへと出かけて行ったらしいのですが、白衣のおじさんは結局現れなかったようです。彼は「俺が退治したんだ」と言い張っていましたが、平素から彼はウソをつく癖があって、クラスの皆から嫌われていたため、誰も信用しませんでした。<峠の山婆>これは大学の先輩のバイト先での話。トラック運転助手をやっていた先輩は、ちょうど秋も深まっていこうとする季節、4tトラックに乗ってとある峠を通過しようとしてたのです。すると、左手に一人のおばあさんがいる。おばあさんと目が合った先輩は、会釈をした。トラックはそのまま時速60kmでその場を走り去っていったのです。トラックがやがて県境にさしかかる頃、その先輩、変わりゆく景色と山道の綺麗な紅葉にうっとりしていたわけアルネ。そうして再び左手に目をやると、また一人のおばあさんがいる。随分ババアとよく会う日だなと思ってたら、再び目が合ったのでよく見ると、先程と同じ顔、同じ身なりをしたおばあさんだ!そこで先輩、あわてて窓から頭を出して、トラックの左手で起こっている状況を、改めてよーく見た。そこには、素足で時速60kmで走るババアがいたという。・・・多分にウソくさい話なんだが、この手の目撃情報は、東北地方のあちこちで、一時期飛び交っていた、「ミミズハンバーガーの話」や「恐山のイタコが青森弁でジミヘンの口寄せをやった話」と並ぶ、20年ほど前の一世風靡ネタです。<ラジオ体操男>朝、近くの運動公園へラジオ体操をやりにいくと、必ずいて、ラジオ体操が終ったあとで、公園内のゲートボール場の地ならしをする初老の男がいる。ゲートボール場の維持に情熱を燃やし、そのゲートボール場が避難場や駐車場になることに猛烈に反対していたのだが、誰にも相手にされなかった。私の親父が昔、朝この公園でよく出合って仲良くしていたらしいのだが、素性も本名も不明。その後結局、ゲートボール場は駐車場の増設によってなくなってしまったため、それと同時に姿をあらわさなくなったらしいのだが、夜中などに公園を通り過ぎると、ときどき「7番、アウトボール!」という、この男の声が聞こえるという噂があるとかないとか。実は「ラジオ体操男」ではなく「ゲートボール男」だったらしい。<貧乏神>私が去年まで勤めていた会社は、魑魅魍魎の集まる場所であった。社長は「ゲゲゲの鬼太郎」に出てくる日照り神そっくりの暑苦しい顔だったし、彼の腰巾着としていつもひっついていた副社長は、猫娘ならぬ猫男であった。その他、ぬらりひょん、ぬりかべ、モリチャンといった妖怪が、次々と姿を現しては消えていった。彼らの発する妖気にあてられて辞めていった者も少なくなかった。今にして思えば。だが一番強力だった妖怪は、この会社の倒産の決定打となった「貧乏神」である。彼は、よりにもよって経理部長だった(笑)。しかも、この会社に中途入社するまでに勤めてきた会社は、最後にいつも倒産したという噂があったのだが、案の定この会社も倒産した。貧乏神は倒産の前に、皆が数ヶ月間にわたって給与をもらえない中、会社名義で勝手に自分用のクレジットカードを作り、大量に買い物をして生活をつないでいたことが、その後の調べにより判明したがあとのまつりであった。さすがである(爆)。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *申し訳ありません。m(_ _)m寒い話で涼んでくださいとしかいいようがないね(苦笑)。つーわけで、「もっと怪談っぽい話」を募集中~♪なんにも出ないけど気軽に書き込んでくださいませ。
July 12, 2005
-
部員90人!
全国高校野球選手権大会の予選大会が、そろそろ開幕するということで、朝日新聞にわしらの地域の予選出場校のプロフィールが紹介されていた。その中に、私の出身校も載ってたんだけど、その変わりようにぶったまげた。なんと、部員が90人もいる! ちょっとした甲子園常連校なみの人数じゃねえか。練習できるのだろうか、というか、どこかに専用野球場でも作ったのか?そんな予算が取れるのだろうか? などと、つい余計な心配をしてしまうね。だが、次のような奇跡的なめぐり合わせも、決してなきにしもあらず。高野連のワキムラ会長は、言動がかなりアホのように見えるので、「部員50人以上学校なのに専用野球場がない学校には補助金を10億円出す」などと無謀なことを、コイズミの郵政民営化のように、周囲の反対を押し切って強引に決定した頃、偶然にもウチの高校に大勢入部希望者がきたため、補助金を受けるために入部試験などせず全員残した結果、幸運にもカネが流れてきた、ということだったのかもしれない(←んー、ありえないね)。・・・とまあ、そんな邪推100%の話はここまでにして。監督だかキャプテンが云ったと思われるチームのPRコメントには、「やるべきことを確実にクリアして、都立高で初めて甲子園で校歌を歌うのだ!」などといったような、デカいことをぬかしている。頼もしいことに、甲子園での勝利が目標ときたもんだ。まあ、近頃は一回戦で全部の学校の校歌は流れるから、甲子園に出さえすれば目標クリアなわけだけど、勝って校歌を聞くほうが気分いいからね。俺らが在学中の野球部というのは、野球部員は20人強ぐらいで、いいとこ3回戦までは行くけど、そこでシード高とぶつかってコールド負けして夏が終わる、というのがパターンであったのだが、今じゃ掲げる目標も高く、大量の部員獲得で、意気も高まってるようだ。まあ確かにねえ。卒業してからこれまでのあいだには、南海が福岡ダイエーになってソフトバンクにまでなっちゃったり、巨人が金満アホ球団に変身しちゃったり、近鉄がオリックスに吸収合併されて楽天が仙台にチーム作ったり、日本人が大リーガーになったりといった、昔は信じられなかったようなことが、野球界全体でも起こってるわけだもんねえ。関係ないけど、俺だって会社を何社も移ったあげく、今は「セカンド・キャリア」を目指してるわけだし。ひと時代は確実に過ぎ去っているわけで、学校も野球部も変わってて当然だ。出身高校も校舎をリニューアルしたと聞いたけど、中身もだいぶ様変わりしてるんだろうね。それにしても、都立高校というのは、偏差値も低くて最近は大学進学にも不利ということで、近頃はあまり生徒が入らなくなってるものとばかり思っていたのに、部員90人確保というのは立派なものだ。「ドラゴン桜」の高校にも見習って欲しいぐらいだ(笑)。決して強豪じゃなかった筈なのだが、最近は、前年度優勝校から大金星を挙げたり、秋季大会のブロック戦で優勝したりといったふうに、進境著しい。何年か後には、ぜひ夢を実現して欲しいと願うのだが、それと同時に、母校の校歌が甲子園で流れることを、どうもにわかには受け入れがたい自分もいる。まだすぐには難しいと見てるので、さういふ心配は、取らぬ狸の皮算用だけど。校舎のリニューアルと同時に校歌もリニューアルされてるといった、不条理なことが起こっていないことを祈りたいね(爆)。甲子園に流れる校歌を聞いて、「えーこれ、どこの校歌だよ」みたいなの。鉄拳に、「こんな母校はいやだ。甲子園に出たのでテレビで見たら違う校歌だ」というネタにされてしまいそうな展開は、どうかカンベンして欲しいものだ。
July 9, 2005
-
人を殺していい日なんてあるわけない!
<まさか「殺すこと」が最終目標じゃあるまいに・・・>ロンドンの町が、この2日間にわたって喜びと悲しみをいっぺんに経験した。2012年のオリンピックのときには、昨日の爆弾テロからの復興といった話題がのぼることは間違いないだろう。アルカイダのアメリカへのテロ攻撃やイラク戦争の怒りや悲しみ、憎しみを、歳月をかけてようやく忘れようとしていた矢先の事件だけに、ことさら恐怖がつのる。いや、やはり我々は、あのときの出来事を忘れてはならないのだろう、と身の引き締まる思いである。若貴兄弟のあつれきがようやくおさまったと思っていた矢先のこと。人間は、爆弾を投げるのは決して好きではないのだろうけど、深層心理のどこかでそれを欲しているのに違いない。平和を何よりも望んでいるのに、平和が続くと面白くない。とりわけ、憎いアンチクショウが、バカ面さげてノホホンと生きてるのを見るにつれ、アンチクショウに向かって、爆弾投げたくて投げたくて仕方なくなるのかな。なんとなく、そのムズムズ感、イライラ感は全くわからなくもないんだけど、テロを決行しちゃうことの美学については、全く理解も共感もできないね。なんで爆弾投げたいかっていうのは、投げる本人にしか本当のことはわからない。あるいは本人にもよくわからないのかもしれない。わからない時点でやめるべきなのに。単純に「ムカつく」「ゆるせない」というだけのことではないと思うけど、何か理由を頭につけて「~だからムカつく」「~だからゆるせない」ということなのだろう。その理由を考えるのも当然必要なことだが、これにはおそろしく時間がかかる場合がある。とくに今回のテロの問題は、解明する人が一生かけても解明しない可能性が高い。それより一番大切なことは、「ムカつく」とか「ゆるせない」という思いを、爆弾投げて相手を殺すことで晴らす、という思考や行動のもっていき方を、問題行動として着目することじゃないかと思う。相手を殺してこの世からなくしちゃうのは、一見事務手続き的には一番簡単なことではある。面倒くさい折衝もしなくていいし、憎い相手の顔も声も、見たり聞いたりしなくて済むし、それでいて相手には確実にダメージを与えることができる、という意味では、一番楽な方法ではあるわな。でも、それで解決だと思っちゃって彼らはいいのだろうか?というか、敵を殺すことなど、本来の目的の副産物的成果にすぎないんじゃない?敵を殺すことを目的にしちゃう人生というのは、ある意味、その敵のために命をささげてるのと同じことだろ。同時に黒幕にも命をささげてることにもなるけど。本来は、彼らだって平和や幸せのために生きているはずであり、その延長がテロや戦争になってしまったはずだ。ところが、そのいさかいが終わっちゃえば、皆が平和とか幸せの回復を喜ぶ中、喜びを分かち合うことができない。というか、国際的には戦争犯罪人のレッテル貼られちゃうわけだ。たとえ国のためにあんなに頑張ったつもりでも。そんな人生、空しいだろうに。<「殺すこと」がテーマの最近気になった映像・出版作品>◆「シルミド」韓国映画。いわゆる「韓流」とは違った趣のシリアスな作品。最近、テレビの「日曜洋画劇場」でも放映した。死刑囚数名が、韓国の軍隊からの「金日成暗殺」という特命のもと、死刑を免がれて軍に入り、厳しい特殊訓練を受け、いよいよ作戦決行という日に、軍の総司令部から暗殺計画の中止を云いわたされる。金日成暗殺だけを目標に、それが終われば無罪釈放を約束されていた兵士達は、絶望のあまり暴走し、民間人を巻き込んでバスジャックを図った挙句、自分達を統率してきた軍隊に包囲され、最後は民間人を解放して自決する、という実話に基づいた悲劇。なんて空しくて悲しい話だろうと、見終わってから涙がボロボロこぼれた。イスラムの爆弾テロは、「シルミド」の哀れな兵士と考え方が同じのような気がする。なんでテロ行為やらなくちゃいけないのか、自分できちんと考えて判断することなど許されないことなのかも。違うのは、上に立つ責任者が、テロ決行を計画どおり発令したことだ。彼らの思いなど、平和な現代の日本で暮らす我々の感覚では、とても理解できないのかもしれない。◆「エグジスタンス」ちょっと例外的に、時節柄個人的にはオススメできない劇画。「ビッグコミックスペリオール」今週号(今日発売)に掲載。六本木で、快適な居場所を求め、ヤクザと抗争を展開中の若者たち。彼らのリーダー格で、ちょっとインテリヤクザ風の若者が、自分たちの仲間を殺した敵のチンピラヤクザを拘束して縛り上げ、「キリストの言葉に『目には目を』ってのがあるのを知ってっか?」と脅したあとで、ややためらいつつも、仲間が殺されたのと同じ形でなぶり殺しにしてしまうシーンがあったのだが、この若者は「目には目を」の出所について勘違いしている。知っている人も多いと思うけど、「目には目云々」はイエス・キリストの言葉ではなく、旧約聖書の「出エジプト記」で、モーセとの対話でエホバの神が云ったのだ。もっと有名なのは、さらに遡ってバビロニアの「ハムラビ法典」である。しかもそれは「仲間を殺されたからそのお返しに殺してもいい」ってこととは全く違う。そうじゃなくて、人との間でなんらかの害を与えてしまった場合の、自分も相手と同等の害をこうむることによって償いなさい、という意味である。人をあやめるかどうかという、非常に倫理的に重大な局面の話にも関わらず、人気の雑誌に、安易に読者にえせ知識を植えつけるようなことを書いてはダメだ(怒)!ましてこういう時期に、だ。若者が読んでなんらかの影響受けるんだから。「週刊プレイボーイ」のサッカーW杯最終予選の記事での「悪の枢軸」発言といい、雑誌編集者のチェックもいい加減なもんだなあ、と思ったものである。◆「この世に人を殺してもいい日はない」鈴木健二著。今朝の新聞の朝刊の広告で掲載されていた。これは、テロではなくて、昨今の、少年による両親、兄弟、友達の殺害、また大人による児童殺害、一家強盗殺人などの数々の殺人事件を憂い、改めて人の道を説いたものらしい。そんなに高い本じゃないみたいだし、こんな世の中だからこそ、浮き足立たずに、自分の足元をしっかり見つめなおす意味で、読んでみようかと思う。
July 8, 2005
-
「神の子」いじり
今日も勝手な個人的感想でし。たあいのない話題が、イメージ暴走機関車と化してる私の中で、膨らみすぎてたいへんな字余りになっております。読者の皆様には、どうかまたぞろ気を悪くなさいませぬよう。m(_ _)m* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<名前負け?>山本キッド徳郁選手って、「神の子」とか自分で云ってるけど、自分で考えたのか他人に云われて名乗ってるのか知らないけど、重い名前背負っちまってるなあ、とつくづく思うんだよねん。大晦日の試合のときはなんとなく、このキャッチフレーズがいい感じだったような気もするけど、あんまりにも浸透しすぎると違和感があるっつーかなんつーか。テレビ局も調子に乗って、ことあるごとに「神の子」を連発してるけど、試合が惨敗だったときとかにフォローできなくて、アナウンサーも解説者も必死で言葉を探してるし。少し前のK-1で、ギリシャの、化け物のように強い選手にKO負けしたとき、「でもこれはある意味当たり前ですよ。彼はK-1はじめて、わずか1年そこそこなんですから」っていう解説者のコメントがあってから、「キッドが負けるはずがない」と信じてる視聴者たちのフラストレーションは、ようやく少しだけ晴れたのだと思うのだが、わかってるならはじめから云っとけよ、そういうことは(笑)。サッカーじゃなくて、こっちがホントの「絶対に負けられない試合が、そこにはある」だよ(爆)。普通の選手なら、あそこで負けても許されるけど、「神の子」を名乗った瞬間から、彼は出る試合すべてに、絶対に負けてはいけなくなったのだ(と私は思う)。トレーニングや調整が大変なんだろうけど、なんてったって「神の子」なんだから。試合会場でお姉さんの美憂選手とか奥さんが、手に手をとって涙をこらえながら応援する姿というのは、ちょっと「神の子」というにはほど遠い感じであった。何にたとえればいいかな。そうだな、「下町の、自分ちの大家族や地元商店街の期待を背負って戦うけなげな長男」を見ている感じに近かったかも(笑)。「神の子」にはペーソスも不要なのだ。自分の家族よりも、世界を救うのが、神の称号を得た者の役目なのだ(と私は思う←しつこいけど)。<「王子様」に路線変更したほうが・・・>「神の子」なら、もっと勇猛果敢で無敵なイメージをファンに与える演出をし、実際ホントにそれだけ強くなきゃだめ。無敵のヒクソンを頂点にしたグレイシー一族のような強さというか。それで、もっと他の選手もマスコミも全て見下すぐらい、奢り高ぶって傲岸不遜に威張ってないとな。インタビューに対して、演出じゃなくマジに「うるせえ!当たり前のことを聞くな!」ぐらい云ってもいいぐらいの、かつての貴乃花や中田英など足元にも及ばぬほどの近寄りがたさ。そんでもって、それがまかり通ること。それが「神の子」だ(私の中では)。テレビでのしゃべくりを聞いててもヤサ男な感じで、ファンは男も女も、妙に親近感持ってる。「神の子」に馴れ馴れしくするんじゃねえ! と思うね。ギリシャの選手にKO負けしたとき、「ありゃりゃカワイソー」と思った。「神の子」と呼ばれる格闘家が「カワイソー」と思われたらおしまいだ。ただヒールでいくなら話は別だけど、ヒールにしちゃうには、家族だとか血筋が高級すぎる感じだし(笑)。そんなわけで、ベビーフェイス路線を進むのがどうやら正解っぽいから、マスコミは早めに、本人とともに練り直しをしたほうがいいね。「神の子」キャラには、向き不向きというのがある。山本はどっちかというと向いてないように、私には見える。そんなのやめて、エリートボクサーのオスカー・デラホーヤのようなイメージで、王子様というか貴公子というか、そういう路線で売っていくのも悪くない、と私は勝手に思うのだが、そういうのは日本の格闘技界ではダメなのだろうか。<こいつのほうがふさわしいような?>ちなみに「神の子」を名乗っていいキャラの人物は、私の中では他にちゃんといる。「誰にもいつでもタメ口ボクサー」こと亀田興毅(笑)。亀田が東洋・太平洋あたりのタイトルを取った瞬間、リングの上でインタビュアーのマイクを無理やり奪い取って、「俺サマが神の子や、せやから今日、こんなレベルのトコで楽勝できんかったんが悔しいんじゃあ!!」なんて、勝ったくせになおも不遜に吠えて、相手は反論もできずに尻尾を巻く、というのが、私の中での亀田のピッタンコイメージなんだけどね(笑)。こいつなら、負けても「神の子」でいていいような気がするし、負けた瞬間ボクシングやめそうな気もするから、それはそれで伝説になりそうだし。過剰な演出にも耐えそうなタフさが見える。オヤジさんも許しそうな気がするし(笑)。ということで、ワガママで、思いっきり誇り高くて強い「神の子」誕生って感じだけど、どうでしょう(却下かな・笑)。以上、すげえ勝手な云い分でした。m(_ _)m
July 7, 2005
-
友人のいた会社
今朝の某新聞・朝刊に掲載されてる求人コーナーのコラムに、高校時代からの友人が、以前勤めていたという会社の社長さんが、でっかい顔写真つきで載っていた。僕とほぼ同年代の、いってみれば今話題のITベンチャーの、やり手の女社長さんである。ホリエモンや三木谷さんとはちとジャンルは別だけどね。そのコラムを読む前から、友人を通じてこの会社のことはよく話を聞いていたし、HPを何度か見たこともあったので、「あーなるほどね」といった感じで、コラムの内容に代わり映えした感じはしなかったけど、時を経て、僕の勝手な想像の中でのこの会社へのイメージが、勝手な想像に応じて微妙に様変わりしていることを、自分でも面白く思っている。あらかじめお断りしておくけど、このあと書く内容で、この会社の悪口を書くつもりなどさらさらない。だいいちそんな権利があるわけもない。だから、読んでくださる方にも、どうか悪口だと思って欲しくない。ベンチャー創業時の会社にいれば、誰しも当たり前に経験するようなことだと思うし。客観的事実と、その事実の周辺の人の目から見て心で感じられたことというのは違うんだ、という話をしようとしているのだが、果たしてそういうオチになるかどうかはわからん。ならなかったらゴメンナサイ。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *実はこの友人とは、彼がこの女社長さんの会社に就職を決める少し前まで、電子出版系の会社を作って、自分たちで独立しようという、今でこそポンコツに見えるけど、当時の僕たちにしてみれば、それなりに「ワクワクするような夢の起業作戦」を練っていたのだ。彼はオヤジさんが経営する映像制作会社で企画営業をやっていて、片や僕は情報システム系のコンサル会社で企画・マーケティングをやっていたので、互いに計画の立案や情報収集、企画の立案はそこそこ経験豊富であった。かくして極秘裏に、起業の作戦はドンドコドコドンと進み、我々は夢中でベンチャーキャピタルに対するプレゼンの準備を続けていった。だが、会社設立のための資金を出してくれるという、いわゆるベンチャーキャピタルに対するコンペで提出した企画書が、最終審査の結果ボツになった、ちょうどその時を潮に、彼のオヤジさんが、自分の経営する会社を縮小するということになり、息子である彼を社員(役員?)という立場から外へ放出した。彼は職を失い、僕は本業での過労もつのって、うつ病を患うことになったのだった。余談になるけど(って以下の話の大半は余談なのだが)。別の話に関してあとのほうでも書くけど、創業当初の会社というのは、食うか食われるかで、とにかく大変である。だから、この程度の挫折で精神が参ってしまう、僕のようなやわな人間が、仮に出資を受けられて、独立できるような方向にことが運ばなくて、結果としてはよかったような気もする。そうして失業していた彼を採用したのが、このIT企業だったというわけなのだ。で、我々のこしらえた企画書は、そのうち余裕ができ、お互いまだその気があればまた考えてみようといいつつ、結局は宙ぶらりんのままになってしまい、その後似たようなビジネスモデルを掲げて事業家する企業が急激に増加してきたため、すっかり陳腐化してしまい、このポンコツ起業の話は事実上ボツになった。そして僕らは再び、それぞれ別の道を進んでいくことになった。その話の経緯の概略は、ディテールを掘り下げると多少事実にもとるかもしれないが、大体そんな感じである。実名を挙げていないので、そのへんの細かいことは大目に見て欲しいと思う。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *あまりほじくり返すのも友人に申し訳ないが、もう時効の話なのでもう少し書く(笑)。彼が転職した当時、このIT企業は、まだ創業の時期だった。したがって、営業に配属された彼は、会社が運営するサイトにコンテンツを掲載するクライアントを求めて、まさしく全国津々浦々を飛び回っていた。うつ病が快方に向かってきたあとも、すっかり本業に取り組む意欲が失せていた僕は、まだ少しだけ例のポンコツ起業に未練を残しつつ、それまでのワーカホリック的生活をやめた。そして進んで暇を作っては、起業話の再燃を胸に秘めて、ときどき会っていたのだが、そんな僕とは逆に、会うたび彼はますます忙しくなっていった。そして片時も耳元から携帯電話を離すことなく、遠方の取引先や自分の会社と連絡を取りつつ、飯を食ったり酒を飲んだりしていた。じっくり腰を落ち着けて会話を交わすような機会は、その後おのずと減っていった。それ以前は、もう少し、というか殆ど正反対に近いほど、彼には余裕があったので、僕のほうでも強引に暇を作っちゃあ、バカ話をするためだけに酒を飲みに行ったり、家に遊び云って奥さんの料理をゴチになったりしていた延長のつきあいだったのだが、そうもいってはおれなくなっていた。その時期の経験が、彼にとってよかったのか悪かったのかは、10年20年経った後、改めて彼に聞いてみないとおそらくわからないと思うけど、少なくともこの時期、彼が精神的に追い込まれ、磨り減っていったのは事実だろう。その精神的磨耗は、結局彼がその会社を辞める時まで続いた。、仕事があるのはいいことには違いないのだが、働いた分に対する十分な見返りが得られないのが、零細起業や、創業時のベンチャー企業の弱いところである。僕がいた会社にしても、経営がヤバくなってきた頃、給与が上がらないばかりか払えないような月が続いた頃、社長に同じような不満を漏らし、直訴する社員があとを絶たず、直訴した社員は皆一様に、ほぼ直訴した直後、遅くとも数ヵ月後には辞めてった。だから在職当時この友人に、この女社長さんのIT企業に対する評価を聞くたびに、聞こえてくる言葉というのは、だいたいネガティヴなことばかりであった。「経営者が自分の度量を越えたことばかり計画して目標立てるから、下にいる俺たちは毎日地獄のようだ」「休日なんて今月はまだ2日しかとってない。夜は終電ギリギリに帰れればいいほう」「これだけやってる割には、残業代も出ない」「火の車だー。このままだとつぶれるかもしれない」なーんていうことだね。ただ、こういう経験は、ちっぽけですぐ経営難に陥りそうな、脆弱な割に、経営者のプライドが妙に高くて、掲げる目標が身の丈よりも高すぎる会社ばかりわたり歩き、「俺の職場はロシアのバレーボールチームかよ!」などとボヤき続けてきた僕には、20代の間はごく当然の日常的な話だったので、「ウッソー、しんじられなーい」などと、ふた昔前のバブリーOLのようなことは決して云わなかった。けれど、あるいはその頃は少しずつ、「そんな会社、俺ならさっさとやめたくなっちゃうかもな・・・」と、うつ病の虫が胸のうちでささやいていたような気がするのでもある。かといって、「そんなのあったりまえだのクラッカーだぜ、おめーらその程度のことで今さら騒いでるなんて甘すぎるぜ、まるでハーシーの板チョコだぜ」などと不必要に威張って語尾に「ぜ」を連発して、場を台無しにしてしまうこともなく、うなづきトリオのように、比較的おとなしく「ウンウン、なるほどー」と共感していたのだ。まあそれはまた別の話なんでおいといてえ。( ̄  ̄)//そうはいっても、このIT企業さんは、今や業界でも有名な優良企業になってきているように、このコラムからは見えるのである。「愛・地球博」からも、仕事を受注しているらしいし(まあ、受注してりゃあいいってものでもないのだろうけど)。なんつーか、コラムを僕の目を通して見る限りでは、大変いいイメージなんであるネ。だから、今はこの会社も、おそらくはこの友人がいた頃よりかは、従業員をコキ使うことも、かなり少なくなってきてはいるのではないかと勝手に思うのである。けど、実態はそうではなくて、コラムは偽の姿で、ますます大変な、火の車になってるのかもしれないけど(笑)。今となっては僕からは積極的に知る由もない。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *えーと、話が知らず知らず長くなりすぎて、話をもとに戻すのも大変なのだが、実際この日記を書きあげるまでの所用時間は正味40分程度なので、大したことないと思って、ためしに推敲してみたら、ちゃんと話に筋道立ててオチに持っていくのが、「ありゃりゃ!?」と思うほど面倒くさい(苦笑)。だけど強引に、朝青龍の上手投げのように「オリャッ!」と話を元に戻す。つまり創業時というのは、経営者もつぶれないように必死に、半ば強引に物事を進めていかないと、本当につぶれてしまうのではないかという危機感のもと、しゃにむに動くため、下で働く人たちというのも、まだ比較的少ない従業員数で運営される職場では経営者のカリカリした姿を直接目の当たりにするため、職場は辛く苦しいオーラが漂ってるのだろう。経営者も実際、そういう自分を振り返るゆとりがあんまりないから、それでも自分を振り返る時間が作れるれるような、超人的な度量がない普通の経営者(それが悪いと云ってるわけじゃない。普通ねフツー)は、周囲には鬼のように映るのだろうと思う。事実、この社長さんは、母親としての、子育てと会社経営を両立しようとしていた、僕の友人とも同年代の人だったので、経営者としては大きなハンディキャップを背負っていたことになるだろうし、そのハンディを覆そうと出力されるパワーも、ハンパなものではなかったことだろう。だから、その時期に会社にいた、友人のような人間にとっては、この会社はおそらくとんでもなく地獄のようだったのではないかと勝手に想像する。まあ、それを云ったら、彼女の旦那さんやお子さんが一番地獄だったのかもしれないけどね。詳しい事情はよく知らないけど(爆笑)。そして、やがてそういう苦しい時期を脱して経営が安定してくると、職場にもゆとりの空気が漂いはじめ、経営者からも鬼気迫るオーラのようなものは影を潜めるのかもしれない。だから、今の段階でこの会社に入ろうと訪れる人にとっては、友人が見てきた会社のイメージとは違って、むしろ明るくのびのびした会社の雰囲気に、あるいはなっているのかもしれない。というか、そうであることを祈るけど、他人事だから、まあどっちでもいいや(笑)。
July 5, 2005
-
俺に喝!
けふのやきうの試合での俺は、サイアクであった。というか、今年に入ってからずっとサイアクなんだけどね。松岡修三的に見ると、なぜ全力で走らない!? なぜ飛びつこうとしない!? といった感じである。これから、秋にかけてやきうからは離れるが、自分の中で意識改革しないと、勉強のほうも中途半端に終わってしまうぞ。なんとかしようぜ、俺。不完全燃焼にもかかわらず、妙に疲れたから、けふはこれでおしまいなのだ。
July 3, 2005
-
ウォーターベアーズ
ちなみに「ウォーターボーイズ」と「三ツ沢ベアーズ」の話では全然ない。また、チーフベアハート産駒や熊沢重文騎手鞍上の馬が明日の競馬で激走する暗示というわけでも全くない。以前買った「へんないきもの」という本の中で紹介されていた、クマムシという生き物がいるんだけど、こいつがかなり変わっている。(註・この「へんないきもの」という本は、読み返せば読み返すほど面白い。買ってよかった、と思える一冊である。バジリコ出版刊)この本に載っていた生き物の中で争われる「輝け!へんないきもの大賞」というものがもしあるのならば、個人的には大賞をあげたいぐらいである。こんな生き物が世の中に存在していたことさえ、この本を読まなければ知らなかったというのも、衝撃を受けた理由かもね。しかもすごく身近にいるらしい。子どもの頃に読んだ「生き物図鑑」だの「なんでも百科事典」には、残念なことにクマムシというのは載ってなかったからね。事実、あまり研究する学者もいなかったのだろうから仕方ないが。クマムシというのは、主に土壌や水辺、コケの中などに生息する、1ミリにも満たないぐらいの虫で、「緩歩類」という仲間に含まれている節足動物である。このクマムシの凄いところは、周りの環境の変化に応じて、身体をその環境に順応できる状態に変化させ、環境に合わせた生き方でいくらでも生き延びることができるという点にある。たとえば、水分のない乾燥した状態の中では「乾眠」という仮死状態になって、かなりの高温の中でも、あまつさえ放射能の下ですら生き延びるのだという。だから、「イラク戦争」の後処理で、日本の自衛隊員を全員クマムシで固めとけば、たとえ無茶な指示を受けても平然と赴くことができるだろうし、暑さによる消耗もなく、爆弾直撃さえなければ、無事に帰ってこれることだけは確かであるが、いかんせん、身体が小さいので肉体労働は役に立たず、現地では「乾眠」しているので、「日本の自衛隊は何やってるんだ」と現地の評価が低くなるのは仕方あるまい。だがそれでいいのだ(何が?)。当然のことながら私はクマムシを飼育したことなどないから、詳しいことは知らないのだが、クマムシはふつう平気で100年近く生きるという。誰がクマムシの寿命について研究したのかは知らないが、その寿命の長さにはぶったまげである。で、微生物らしく、水中に浮遊する有機物を摂取したりとか、コケのエキスを吸ったりして生きるという。天敵もいるんだろうけど、あまりに取るに足らない存在ゆえに、大した敵はいないらしい。まあ、たまたま水の中に落っこちたとき、メダカかなんかに、ミジンコと間違われて飲み込まれる、といった不慮の事故みたいなのはあるかもしれないけど。目立たぬ生き方、大きさだから、互いに淘汰したり、足元をすくわれたりすることもない。だから絶滅の心配も当面はないらしい。そのルックスとは裏腹に、地味でつつましやかな生き物なのである。そう、クマムシというのは、直接見たことないけど、なかなか勇猛果敢な姿かたちをしているのである。「へんないきもの」に描かれているクマムシの絵を見ると、その名のとおり熊っぽくもあり、また未来モノのSFに出てくる装甲月面歩行マシーンみたいにも見える。人間が、自分と同じ大きさのクマムシに立ち向かったら、みるみるぶちかまされて吹っ飛ばされた上に踏み砕かれ、「グチャッ」と云って絶命するだろう。だけど実際は1ミリにも満たない、小さいおとなしいヤツだから、そんな心配は無用なのである。その生態や歩き方から、この生き物は、クマムシ、英語でwater bearと呼ばれるようになったという。水の熊、ってなわけだね。身近にいながら、存在を気にもかけられず、かといって自らをアピールすることもないんだけど、よく見ると存在感があって面白くてその上タフで、誰にも迷惑かけない、スッゲエいいヤツ、という印象。なんとなく、小学校時代に音楽の授業で教わった「手のひらを太陽に」という歌の歌詞にクマムシを付け足して口ずさみたくなるね。別に口ずさまなくてもいいけど。ミミズだって、オケラだって、クマムシだってえー♪みんなみんな生きているんだ、友達なんだあー♪みんなー、新しく発見されたお友達のクマムシくんです、仲良くしてあげてねー♪などと、さとうひろみちお兄さんに紹介されそうな感じ。だけどクマムシくんは、本当は昔から皆の周りにいたにもかかわらず、誰ひとりとして存在に気づかず、かといってそれに対する不平不満も云わず、雨の日も風の日も、カラッカラの渇水の日も、原爆が落ちた日でさえも、平気な顔して、ほかの皆が死に絶えた後も、のんびり100年も生きるのだった。ある意味尊敬に値する生き様だけど、人間である我々は、決してそうは生きられないのであるネ。
July 2, 2005
-
うちうせんそう
なにやら随分と話題になってるみたいなこの映画。「恋に落ちたら」に出てた、ピノキオ草薙の相手役の松島なんとかさんという背の高い女の子が「宇宙戦争って、なんなの!?」と叫んだからか?それともS.スピルバーグが監督で、トム・クルーズが主演だからかな?だけど、個人的には、当初「物凄く見たい!」というふうには思ってなかった。むしろ「逆境ナイン」のほうが、今の俺にとってはだんぜん面白そう(笑)。見たいと思わなかった理由は、別につまらなさそうだからとか、そういう理由ではない。たぶん、客観的に見てかなり面白いだろう。ウェルズが書いた原作は、世界的にも物凄く有名なSF界の名作だと思うし、子どもの頃読んで、イメージの中でハラハラドキドキした。なんかそれが、今のハリウッド映画のハイテクを駆使した映像に加工された姿というのが、昔のハラハラドキドキ感を台無しにしてしまうような気がするからだ。自分のヘンクツな性格を、我ながら残念に思う。デートのネタとしてはいいのかも、と思ったりとかね。でもデートで「宇宙戦争」見たとしても、こんなヘンクツな俺のことだから、映画見たあとで入った喫茶店かファミレスかどこかで、女の子を前にしながら、自分の「宇宙戦争」に対する思いのようなことだとか、原作本の内容との違いみたいなことを、うんちく王「くりいむしちゅー」の上田よろしく、とうとうと語ることだろう。それで、女の子はすっかり「シーン」となってしまい、話題が切れて、ふと我に返ったところで、ようやく失敗に気づくのだ。あーあ・・・。どの道ボクにとっては、心安らかには見られない映画っぽいのだが(苦笑)。まあ、それはともかくとして。そういうことが起きないように(起きてもいいけど)、ここで原作のことやらなんやら、気になることをチラチラ書いて、ここでゲロってしまうことにしよう。・・・と思って書いてるうちに、だんだん考えが変わってきたわけであるネ。この原作本は、小学校低学年の頃に、図書館から借りて読んだんだか、家で買ってもらったのだったか忘れたけど、とにかくそんな感じで読んだのだ。原作のストーリー。たぶん大勢の皆さんが読んで知ってるストーリーだとは思うけど。読んでない人にはゴミんなさい、つーか、日記読まないで、どうぞ別のページにジャンプしちゃってください。m(_ _)m火星人がUFOでいきなり地球に攻めてきて、各地の都市を次々に破壊し、地球人を次々にさらっていく。目的は、自分たちの食料がなくなってきたので、かわりに地球人や動物の体液を自分たちの栄養にするということ。火星人はいわゆるタコ型のヤツね。頭だけ異常にでかくて、ハイテク機械を操る頭脳と手足以外の部分は退化してそうなってしまったらしい。それでいよいよ地球が完全に征服されてしまう寸前に、タコ火星人たちがUFOを降りるやいなや、地球の細菌感染が原因で、たちまちのうちに死滅してしまうという、大どんでん返しの結末が待っているのである。かくして地球は守られる、ということで大団円。超めでたいハッピーエンドという訳では全くないんだけど、何はともあれ助かってよかったよかった、みたいな話。随分と昔(戦前じゃなかったか?)に書かれたストーリーだった筈だけど、SFのハシリの小説としては、イマジネーションとか話の構成、落としどころが秀逸で、だからこそ現代に映画化しても見れる映画として作れるのだろうと思ってしまう。どれほど映画が原作に忠実なのかはわからないけど。同時に、今日の教訓にもなりそうな、メッセージ性のある話でもあったんだなあと、今頃になって感じたりもする。地球の自然の力が、火星人の侵略を最後は食い止めるのである。だけど、地球温暖化だとか砂漠化が進んだりして、自然が破壊されてしまうと、火星人みたいな侵略者を追い払えなくなっちゃうぞ、てな感じなのであるネ。逆に、自然環境に対して人間がやってる科学技術の開発こそが「侵略」であるという考え方もできそうだし。また、火星人のいきなりの地球侵略は、戦争をしかけて相手国の征服とともにそこにある資源を略奪しようとする大国の横暴さだとか、企業の理不尽な買収などにも通ずるものを感じるのであるネ。ウェルズが、当時のナチスドイツあたりを揶揄していたのかどうかまでは、詳しくないからわからないけど、現代にたとえて云えば、自分たちの石油がまかなえないため、イラク悪の枢軸と決めつけた上に、「悪い国をやっつける」というのを大義名分にしてこれを殲滅し、周辺の石油をせしめようとする、アメリカのタコ大統領の発想になぞらえることはできそうだ。てな具合で、いろいろなことに注意を向けてみると、単なるスピルバーグのSFアクション映画、というわけでもない。あるいは一見の価値のある映画なのかもしれないし、原作本を探してもう一度読んでみようか、という気に少しなったりもしてくる。時代を経て見たり読んだりしたら、別の感想を抱く作品というのもあるものだ。特に、オイルショックから間もない時代に読んだ本を、今の時代に読み直す、という作業は、案外有意義なことなのかもしれない。そうだそうなのだ。残念っぽいのが、アメリカでこの映画が完成したというとき、この映画を教訓にして、この国の世論が反戦へと向いてる、という話が全く聞こえてこないこと。どうも、スピルバーグ監督の撮影技術が凄いだとか、主演のトム・クルーズがかっこいいとか、「バットマン・ビギンズ」「エピソード3」とともにアカデミー賞候補の大作だとか、そんなような話ばっかり出てくるものだから、軽薄すぎる日本のマスコミの取り上げ方に、少々ムカついてる。「華氏911」みたいなストレートな物語じゃないとそういうモンを嗅ぎ取る嗅覚はないのかねえ君たち~? てな感じ。それとも本当にそれだけが注目点なのか?アメリカでは、この映画はどんなふうに受け止められているのだろうか? とか、ウェルズが後世(現代)に残したメッセージは、この映画の中にも生きているのだろうか? などといったことが、ちょっと気になってたりもしている。そんなこんなで、一度見ておこうかなどうしようかな、と迷っちゃったりなんかしちゃったりしているわけなのであるけど、やっぱりただのSFのミサイルドッカンドッカンの、トム・クルーズが白い前歯キラリンでカッコいいだけの映画だったらガッカリだしなあ(泣)。といふわけで、誰か試写会だとか封切直後に劇場に足を運んだという方は、ご一報くださいませませ。m(_ _)m
July 1, 2005
全14件 (14件中 1-14件目)
1