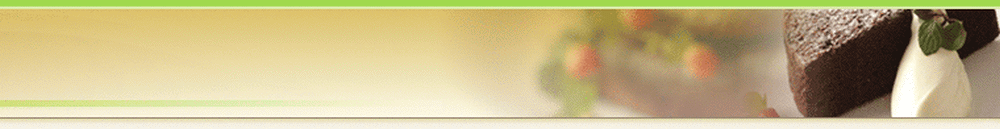2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年01月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
消え行く店、生き残る店
ここのところ、土日は仕事か競馬のことばかりアタマにあったことに気がついた。競馬のほうは、去年の「クリスエスショック」から抜け出せていないので、ここのところお休みしている。・・・というわけで、午後はジョギングがてら、街中を散策しつつ、楽器屋でギターの弦を買いに行こうと、フラリと外へ出たのだが。。。楽器屋はつぶれていた(T_T)。最近は、CDを置くスペースが増えて、端っこにチョコチョコと、キーボードとかギターを置いてたりしたんだけど、とうとうなくなってしまったね。もっとも、こういうインスツルメンタル関係の、たとえばギターの弦だとかピックなどを買いに来るわしらのようなショボ客に対する店員の態度が、CDを買いに来る客に対して冷淡だったのが気にかかってはいたのだ。以前は、「ヤマハとオーガスティンのどちらになさいますか?」などと、細かい配慮までしてくれてたのだが、潰れる前、最も最近買いに行ったときは、ヤマハ一本槍になっていた。しかも「チッ」みたいな態度で雑に袋に品物を放り込む態度を、オレは見逃さなかったね。あーいう、客を見て態度を変えるような店は長続きしないものだ。というか、「楽器屋さん」なんてものが街中に「全く」なくなってしまったらしいのが、なんだか物悲しい。その店のスペースは、ケイタイショップに変わっていた。うーむ(-_-)。同様に、消え行く街の小さい専門店みたいなものは結構少なくないような気がする。ニーズがないから店を維持するだけの売り上げを確保できないのだ。テーラーとか、スポーツ用品店とか、毛糸やさんとか。こういう店は、大手の直営店だとか量販店に売り上げを持っていかれてしまっているんだろうなあ。で、おのずとさびれてゆくため、店員の表情もさえず、「あ、もうすぐここも・・・」とかいう感じになるのだろうか。各町々にあった個人営業の小売店みたいなものは消えて、次第に、こういった大手のチェーンとか、専門店街みたいなところに淘汰されてしまうのだろうか。変わって、少し前から、古本屋というのがあちこちでチェーン展開をしてなかなか盛況らしい。ゲームソフトとかCD、DVDなんかも一緒に扱っているところがミソのようだ。そのあおりを食って、フツーの書店だとか、出版社などが困ってるらしい。新刊本の販売促進が阻害されてしまうから。雑誌は、よくゴミ箱あさりのおっちゃんがその日のうちに回収してキレイにして安売りしてるしねえ(笑)。電子書籍なんてのも出てきたりして。新聞にいたっては、Webで見れるから買わない人もいるでしょう。こうなると、何がなんだかわからなくなってしまうね。そんな中、すたれながらも、町の少年野球チームのユニフォームづくりを担って頑張ってるスポーツ用品店がある。ミズノショップと近いのだけれど、そこはSSKとかローリングスなどの安めのブランドも置いてあるので嬉しい。この店にはなんとか頑張って街に存在し続けて欲しいものだ。またまた話が右往左往してしまったけれど、はじめの話に戻すと、どうやらわしらの町には「インスツルメンタル」を自らかなでようというニーズが低いらしい。寂しいことである。
January 31, 2004
-
タッちゃんの話。
☆枕 「トリビアやらせ発覚!」って、東スポも相変わらずバカっぷりがいいです。そんなこた最初から知ってたっつーの。 大体あんな怪しい番組をたてまつらんでもよろし。 「ローラーゲーム」とか「スターボウリング」の世界を巨泉にもっていかれた、って感じでずっと見てるんだからね。☆本題 さて、タッちゃんというのは、小学校時代に、学芸会で人形劇「泣いた赤鬼」で共演した、僕の幼なじみです。 その後、中学校に入って、2年のクラスで、タッちゃんと僕は同じクラスになりました。 このクラスは、校内暴力こそなかったけれど、とにかくワルぶるのが流行っていて、何かというと教師につっかかるのが大好きな反抗期の生徒の吹き溜まり。 女の先生は毎日泣かされ続けておりました。 そして、新任のT先生という国語の先生は、年のころ27、8で、普通の先生だったんだけれど、いささかぽっちゃりしすぎていたのと、冗談が通じないマジメな先生だったということもあって、たちまち我がクラスの餌食にされてしまいまして。 ちょっと、とある生徒が授業前に黒板に豚の絵を書いたのね。 で、教室に入ってきたTセンセ、「これは何?」「えーと、先生の似顔絵です♪」なんてちょっぴりお茶目に誰かが答えたもんだからさあ大変!! T先生は半狂乱になって教室内を駆けずり回って怒鳴り散らした。「みんな私のことをそんな目で見てたのね!!」って、自分でも気にしてたらしい。 で、授業は中止。 担任のY先生というのは、生活指導の、丸太のような腕を持つ技術家庭の教師。 「全員、目をつぶれ!」「黒板に豚の絵を書いた奴、手をあげろ」(誰もあげなかったらしい) 「・・・じゃあ、今回のことで反省しているもの、手をあげろ」(こんどは大多数の者が手をあげたらしい) 「よし、全員目を開けろ」ってな具合で、よくある拷問タイムは終了。 結局、クラス全員でその日の反省文を書いて提出することになりました。 翌日、タッちゃんが私のところへやってきて、 「これ、オレの作文、読んでみな」っていうから読んだら、 「さあ、ここからあとの文章は、ジローズの『戦争を知らないこども達』の曲で唄おう」 って書いてあって、 「せんせいがーおこーったー ぶーたーのーえをみてー・・・(以下略)」 なんて書いてあるから、思わず吹きだした。これ、タッちゃんの反省文。 なんかそのまま提出しちゃったらしく、そのあとタッちゃんだけ呼び出されてセッキョーされていたらしいんだけど、ニコニコして受け答えしていたらしい。 タッちゃんは不良ぶってもいないんだけど、なんかその頃から反体制的な考えを持っていて、それでいて勉強もよくできた、面白い少年でした。 やがて3年生になって、受験シーズンになったとたん、タッちゃんはキャラが変わったかのように、マジメで大人しい生徒になってしまったんだけど、実は受験勉強にまい進していたのです。 果たして、K大学付属の物凄くアタマのいいヤツが入る高校に進学していきました。 そのあとのタッちゃんのことは、よく知りません。 何年かのちにクラス会があって、皆それぞれ大人になってたわけだけど、中学時代にタッちゃんと親友づきあいをしてた男の子から、学生の中の極左的な組織に入り、三里塚闘争に巻き込まれて命を落としたらしい、というようなことをチラッと聞きました。 信じられませんでしたけど、この世にタッちゃんはいなくなってしまったのです。知らない間に、タッちゃんは空のお星様になってしまったのでした。 「友達の死」というのを初めて知った瞬間でした。 僕はジョッキのビールをグイッと飲み干しました。でも気持ちを落ち着かせることはできませんでした。目から出る泪を懸命にこらえてました。そいつは鼻の穴からツイーと出てきました。 いつしか宴席は談笑に移り変わって、次第に気持ちが落ち着いてきました。それは永遠の、どうしたって再会できないお別れだったのでした。 その後、あの中学2年のときの担任のY先生も鬼籍に入りました。死因はガンでした。 中卒で働きながら定時制高校、大学を出て、最後はどこかの校長先生にまでなった苦労人。「大好きな先生」ってわけにはいかなかったけど、生きてもう一度あいたかった。 ときどき、空を見上げて考えます。 タッちゃんとY先生は、今でも天国にある学校の職員室でかけ漫才みたいなやりとりしてるんじゃないか、なんて。
January 30, 2004
-
あれやこれや。
☆豚丼 「とんどん」と呼ぶらしい。「すき家」の新メニュー。 確かこれ、「クッキングパパ」のメニューに載ってたぞ(笑)。 昔だったら「なんだそんなら自分で作って食うからいいや!」と云って断じて食わなかったりしていたはずだけど、今は「あーよかった、大盛りに玉子つけてね!!」とか云って喜々として買いに行ってしまう自分がなさけねー(泣)。☆6弦が・・・ ギターで、昨日の「うなぎの唄」を弾いて唄ってみようとしたら、6弦が切れてるじゃん(泣)!! 楽器屋閉店までに間に合わず、弾き語りはお預け状態でごじゃります。トホホ。☆来客攻撃 週末サシで勝負するため、ボスにアポとろうと懸命に隙をうかがっておったのだが、どうも昼間は来客に次ぐ来客で、そのあと素面のくせにミョーにハイテンションになっておったので、今日はつけ入る隙がなかった。 どーせ今頃は呑んだくれてさらにハイテンションになってるだろうから、果たし状を出すのは明日に延期。 いつもこの手で年度をまたがれ、矢継ぎ早の仕事攻めにやられているので、今回はスパッといかないとね。☆渡辺謙 ついにアカデミー賞受賞! かと思ったら、「受賞候補に名前が載った」というだけだった。 早く決めてくれー。でないとオレの「トリビア」が・・・(ってもうどーでもいいか・笑)。☆コジロウ 漫画「バガボンド」の佐々木小次郎は、生まれつき耳が聞こえない、という設定になっている。 そのぶん研ぎ澄まされた剣の腕を描く迫力は凄い。 さすがに「スラムダンク」の作者だけあって、そこらへんの描写は巧みだなあ。☆これとは話は別だけど 最近のドラマの原作って、小説よか漫画のほうが多いような気がする。それも圧倒的に。 負けるな、小説!!
January 29, 2004
-
うなぎの唄
作詞・作曲 : chang-weiうた : 未定(JASRAC未申請)→ヤバイ(^^;;)※( )はコードうなぎの身体は(G) ぬめるのね(Am7)ちょっとやそっとじゃ(C) つかめない(D7)あのコのハートと(G) おんなじに(Am7)スルリスルリと(C) 逃げられる(D7)うなぎはなんにも(Em) 知らないの(Bm7)日本や世界の(Am7) 混乱も(G7)やがて去り行く(Em) としつきの(Bm7)のちに我が身が(Am) 焼かれるのも(D7→G)うなぎの命は(G) はかないの(Am7)串を打たれて(C) 開かれて(D7)炭火で焼かれて(G) タレの中(Am7)泳いでゴハンに(C) 乗せられて(D7)真夏の日差しの(Em) 照りつける(Bm7)下で働く(Am7) おっちゃんも(G7)このときばかりは(Em) えびす顔(Bm7) 「あーしあわせ」(D7) ってみーんなをなごませる(D7→G)(coda)世界が平和を(G) 宣言し(Am7)核廃絶が(C) 決まった日(D7)うなぎが一匹(Em) 飛び跳ねた(Bm7)エサのトンボを(Am) 追いかけて(D7→G)何も知らずに(Am)・・・(D7)「ごちそうさま~!!」「ありがとう~あしたぁ(明日)!!」僕らに元気を(C→Bm7) くれるうなぎ~(Am7→D7→G)ジャンジャン(D7→G)------------------------------------------------------会社をサボって、ようやく少しずつ元気になりつつある日の午後でごじゃります。なまじ元気になったりすると、頭と身体を若干もてあまし気味、かといってマジに勉強したりこれから仕事にとりかかろう、っていうわけにもいかず。こういう日は「うた」でもしたためて遊びましょう!! ってことで。「鳥の唄」とか「りんごの唄」とか、いくつかそれなりに世をわかせた名曲がごじゃりましたね。また、巷ではもうすぐ聖バレンタインズデイ。ここに当て込んだ国生さゆりの「バレンタインデイ・キッス」っていう唄がありましたが、考えてみると、バレンタインデイの唄って、他にあんまりないですね。CMソングでもあんまり印象深いものは思い浮かばない。この唄、リリース時は対してヒットしなかったと思ったけど(だってヘタクソだったしね)、「他にない季節モノの曲」ってことで、毎年この頃になると必ずバレンタイン特集のBGMに使われる。おまけに、小林亜星氏が掌握するJASRACが、著作権使用料徴収制度を作っちゃったもんだから、この曲が番組で使われるたんびに、この曲を作詞作曲した秋元康氏と後藤次利氏、あと唄った国生さゆりさんの手元にこの「著作権使用料」なるものが支払われ、JASRACにピンハネされた残りが懐に飛び込んでくるわけです。いやー、こりゃあうまいことやったもんだ、なあんて某はなしゃんと掲示板でお話しておりました。では、こちらもバレンタインデイなどよりずっと歴史と伝統があり、かつあんまり歌い継がれていない、土用の丑の日の「うなぎ」に焦点を当てて、一曲作ってみようじゃあありませんか、つーことで、↑のような唄を作ってみた次第。・・・というのはあとづけの理由で、実は「スポナビ倶楽部」の掲示板で、ジュビロ磐田がファーストステージ優勝したとき、ちょうど土用の丑の日が近かったので、即興でこさえた唄なのね。僕的には、唄はなぎら健壱さんを推薦したい(「いっぽんでもにんじん」の仇をとって欲しい・爆)んだけど、「違うヒトのほうがいい」とか、どうやって売り込むか、とか、「ここはもっとこうしたほうがいいんじゃない?」などのご意見を、これから募集いたします。んで、この曲が本当に土用の丑の日の定番ソングとしてヒットした暁には、ご協力くださった皆さんにも何かあげちゃうのだ。もちろん発案者のオレが一番いっぱい貰うけどね(うっひっひ)。
January 28, 2004
-
有給王!!
会社の有給休暇って、勤続年数が長けりゃ長いほど増えていくから、今年度はさしずめ40日近くあったんだけど、今年度だけで34日ぐらい使ってしまった。まさに「有給王」であるね。逆に、今まで消化しなさ過ぎた、というのもある。その反動ではないけど、今になってこういう形で30日以上使ってしまうというのは、「もう、アカン」と会社に向けて発しているサインだと自覚してるけど、あんまり周りは勘付いていない感じだな。皆自分のことに精一杯だろうし。残って頑張っている人たちには申し訳ないけれど、こんな感じで会社に残ってやっていく気にはなれない。もしやるんだとすれば、「副業として」ですね。本意でない仕事で、いやいや休み休み仕事やって、正社員の給与をもらうのはおこがましいし、それで恩を着るのはもうおしまいにしたい。今まで、それでも現環境下でなんとかモチベーション高めようとしてやってきたのよ。心の風邪も完治しないままに。けど再びそれでフル稼働した結果、生死の間に立った経緯もあるし。以前は別の道で独立しようという作戦を立てたこともあって、そのときは楽しかったなあ。だけど結局それはお流れになって、再びチャレンジするヒマもなくなって、そのあと心の風邪をひいた。ボスの都合としては、ほかにこんな業界スパイじみた仕事を喜んでやる人がいないから、残って欲しいと思っているらしい。同時に、ボスはこの仕事のことをすごく大事に思ってるらしい。じゃあ自分でやればいいじゃん。オレは別にやりたいことがあって、アンタの描く、オレたちにとっては「絵空ごとに見えるようなこと」と違う、世の中に必要と考え、自分の意志でカウンセリングを一生の仕事にしようと、強く心に決めたことなのだ。そそぐ意識のレベルが違うのだ。・・・と、今週末には伝えようと思う。それで、向こうが妥協案を出してくるのか、「出て行け」といってくるのか、いずれにせよ、ここらへんで自分の意志を伝えるときがきた。いちおう、「辞表」もしくは「退職願」なるものが必要になるでしょう。結構、昨年末からペンディングしてきた件なんだけど、そろそろ、自分にもけじめをつけたいと思う。ちょっと「会社やめる話」ごときで日記1日分費やしてしまってごめんなさいね。でも自分の日記だし、どうか許してね。
January 27, 2004
-
ココロのクスリ。
我が身から手放せない、脳内の活性物質の分泌を助ける薬「トレドミン」が切れた。薬がないというだけで、今日1日は物凄く不安と強迫観念に取りつかれつつ、基本としてやっている仕事はこなせてはいたのだけれど、イレギュラーなことにたちまちつまづいてしまいました。内容は些細なことで、頼まれごとに対して細かい確認を怠ったために話が食い違ってしまい、「今大丈夫だから」っていう電話に対して、「了解」って返事したあと、「何が大丈夫で、どうすればいいのか」をよくわからないまま生返事をして、そのまま10分ほどほったらかしにしてしまいました。ややあって、電話の相手がアベジョウジさんのような顔でやってきて、「なんでさっさと来ないんだよ? ずっと待ってたんだぞ」「あれ、来いってことだったの!? 来なくていいってことかと思ってた、ごめんごめん」みたいな程度のことだったんだけど、(あれ、こんな程度の確認のコミュニケーションも満足にできないのか>オレ。薬飲んでないせいかな、頭が集中してないな)などと、振り返っているうちにますます気持ちが滅入ってきました。夕方だったので、そのあとの仕事は自主的に「放棄」して、薬をもらいに病院へ行くことにしてしまいました。で、薬をキープしてようやく一安心。帰宅したら、先週MSNとリンクしてた転職サイトで、「あなたの年収無料で査定します」っていうのがあったので、(どーせこのあと転職情報メルマガだのDMだの電話のアメアラレ攻撃は来るだろうけど断っちゃえばいいんだし)と思って試しに送った結果が届いておりました。結果は・・・、驚いたことに、自分の見積もっていた金額の1.5倍!!大雑把な査定だとは思うけど、こんなに高く出るなんて!! などと「ぬか喜び」して、とりあえずいい気分で眠りにつきたいと思います。こういう、文字情報とはいえ、プラスのストロークというのも、大事なココロのクスリではあります。ぬか喜びっていうのは、自分の目指す道ではどこかに仕える気持ちは消えているからです。だから、実際そんなにくれるモンじゃあない。それに自分は完全健康体ではないから、この査定年収分フル稼働したらパンクして死んじゃうだろうと思うので。それでも結果、そんなに皆様が下さるというなら喜んでいただきますけどね(笑)。まあありえないでしょう。6~7割で細々と、皆さんの幸せに何か役に立てる存在であれればそれでいいです。・・・って、読み返してたら支離滅裂じゃんか!!なんだ、今日の日記は!!
January 26, 2004
-
レフト線はあたかも府中の直線のように・・・
昨日の「大言壮語」は、海の藻屑と消えたのであったのでござりました。私たちのチーム「プレッツ」は、前半3回にエース・OTさんのランニングHRなのかレフトのエラーなのか、レフトを目がけた打球を相手チームのレフトが後逸する間に、一気に冬のダイヤモンドを駆け抜けた。久しぶり、というか私が参加したこのチームの試合では初めて先制点。レフトフライも無難に捕球し(今日の私は9番レフト)、内外野ともに守備も上々だったんだけど。。。5回の表にスクイズ(!)で同点にされたあと、ギャーワシの守るレフトの頭上を越えるレフト線際のライナーが、はるかかなたの「フェンス」まで転がって行った。このやきう場は、もともと陸上競技場を改造して野球場が2面取れる、いわゆるレフト線が長くてライト線が短いやきう場なのである。直線にして、170mはあっただろうね。ライナーのボールを追いかける私にとっては、ボールを拾い上げたフェンス際までは、府中競馬場のラストの直線ほどにも感じられたねえ。ボールを手に取って、振り向いたら打者は三塁直前まで来ていた。これで3点ビハインド。結果、その後相手打線が着実に点を重ね、1-7で最終回ウラ。一死後、今日当たりに当たっている8番のOS君がレフト前にクリーンヒットを放った。これに続こうと、最後の打席に立ったんだけど。これまでポップフライを繰り返し、情けないのでせめて一矢報いたいところ。相手の抑えピッチャーは体格は大きいのだけど、球はあんまり速くない。むしろ遅い。「中魔神」といったところか。2球目を思い切り叩いた。打球は、三塁線をライナーとなって飛んだんだけど、サードの真正面。三塁手はさすがに打球を弾いたりはしてくれなかった。そのまま帰塁できなかった一塁ランナーは併殺。で、ゲームセット(泣)。まあ、勝つことはできなかったのと、ヒットも打てなかったのは悔しいんだけれど、グラウンドとボールの感触を味わえたのと、風もなく、天気もよかったのでほどよく汗もかけて気分のよい一日であった。で、筋肉痛は、引越しも含めて明日からボチボチ出てくることでしょう。次は2月中旬に練習試合が組まれています。次こそは私の参加するプレッツの試合での「初勝利」と、自らの「初ヒット」を目指して頑張りたいと思います。
January 25, 2004
-
あしたはやきうなのねん♪
昨日今日と夜逃げ三昧の日々を送っておりましたが、ちょっと一休みしないとね。で、明日はやきうのれんしう試合をいたばしでやっております。たぶんカラダは動かざること山の如し、で、敵対する武田のような状況なのはいささか不満でごじゃるが、たぶん明日は「勝つ」と予想しておりマッスル。だってホームラン打つ予定だし(爆)。そのために筋肉いじめておるし、定期的に走りこみも続けておるからねー。ちょっと今年の私は違うでござるよ。タフィー・ローズも真っ青の「最強の7番打者」になったるよ(爆)。結果は明日の日記にて。それにしても朝青龍は強かった。千代大海に突き合いで勝ってしまうのだから。まだ若いので八百長のお世話になる必要もなく、マスコミの前評判を実力で覆したってことで、個人的には嬉しいですね。大きなケガでもしない限り、下手すると、千代の富士を超える大横綱になる可能性すら感じます。というのも、周りに彼に追随するものがいない、というのが最大の理由であり相撲協会の悩みの種だったりするんだろうけどね。
January 24, 2004
-
剣呑としちゃいました。
今週が過ぎ去ろうとしているんだけれど、明日、引越しが無事終わるのか、終わってからの、いろんな起こりうることを想像すると、少なからず不安ばっかりですね。なんだか、引越しの交渉を担当した先輩がピリピリカリカリして、パニクりながら皆に指示を出して、よくわからないからもたもたしてると余計イライライライラして、こっちもなんでこんなにキンチョーしなきゃいけないんだろう、と思いながらも、その先輩の気持ちもよくわかるし(いきなり引越し責任者にさせられて「一週間以内に引越し先決めて引越し準備せえ」なんていう無茶な引越し手配を命令されたら、パニックになるのは当たり前です)、辛さを分けてもらいつつ一週間を過ごしておりました。こんなに、年明けいきなり引っ越すことになった理由は、ボスが現実を受け入れようとせず、社員の前でカッコつけようとしすぎたことにあるように思います。ヤバいということを、はっきり云わない。なんか言葉をオブラートで包んで、ダメだった話も「ダメだった」っていわない。うまく行きそうな感触が、たとえそれが相手のリップサービスだとしても有頂天になる。社員にプレゼンしてどうする、って感じだね。でもプレゼンの参考にはなりますな。いかにリスクを隠して長所をアピールするかっていう。また、今まで彼と直接仕事をやってきたヤツラが、徹底したイエスマンだったり茶坊主だったり、逆にストレートに問題を指摘して逆ギレを誘うタイプだったり、のどちらかだったのが、ますます彼を頑なに、自分のスタイルを変えないようにしてしまったのかもしれません。あと私はどうだったかというと、直接仕事を一緒にやって、数ヶ月で心が風邪をひいたという「よわもの」だったため、どっちともいえないですね。ただ自分に自信がなくて、入社できるはずもないと思ったら入社を許されるといったことで、「衣食を得た」ことに対して恩義を感じてはおりましたが、それ以上の痛手も負っているので、プラマイゼロ、ってところでしょうか。やっぱり今が、転機・潮時みたいです。少々ストレスフルになりますけど、ぶつかってみないことには答えは出てこないものね。・・・というわけで、ここ数日、ギャグが少なめでゴメンナサイ。m(_ _)mすんごく今余裕がないんですよ。精神的にも金銭的にも。
January 23, 2004
-
タコは己の足を食って生きる
いやはや、にっちもさっちもどーにもブルドーッグ♪(ワン!)・・・みたいな展開になってしまいまして。業績が上がらず、危機感を覚えた社員は沈みかけた船の穴からチュウチュウと泣きながら出て行ってしまって、残った自分たちがこれまでやってきた仕事は先行き見通しが立たない。何か提案をしても、ボスのフィーリングにあわない仕事は前に進まず、それでも前に進めようと考えた提案のネタも底をつきかけている。これはこちらの問題でもあるが、モチベーションくれ、って感じでもあり。今こそ何かニッチの世界で手っ取りばやい商売を探して着手しようという考えでもあればいいのだけれど、ボスは「いっぺんに大もうけ」できない商売はやりたくないという。だったら宝くじ買うとかヒシミラクルの単勝買うとかする嗅覚でもあるのかと思いきや「ギャンブルは不潔じゃ」という。そのくせ酔っ払いのネタはキャバクラネタだの韓国パブのような話題ばかり。カネはないので、たぶんそーゆうところで豪遊してみたい「願望」らしい。彼は決して外では呑まない。会社に冷蔵庫があって、いつも冷たい缶ビールがストックしてある。これをボスは、夜8時を回る頃から夜中にかけ、毎晩10缶以上はひとりで飲んでいる。で、周りに誰か話し相手をはべらせ、自分の自慢話→今の愚痴話→説教を聞かせるのが通常の流れになっている。こんな環境なので、真面目にボスと話し合いをしようとしても、彼は現実と向き合ってくれない。だから皆ケツをまくって辞めてしまうか、心身の病気で辞めてしまうかのいずれかである。人手は足りないが、給与も出せない。経理の社員は板ばさみ状態で、つきあい酒の呑みすぎで身体をおかしくして、過去に1人亡くなってしまい、その後継者も同じ経緯で現在うつ状態。今までよくぞまあこんなんで生きてこれたものだと思う。自称・ITコンサル会社と銘打っているが、実態はIT業界大手をリストラされたあと、その会社の後輩を捕まえて昔の恩をエサに下請けマーケティングリサーチの仕事をもらって細々と収入を得て息をつないできたのだ。この担当はオレたちがやっている。だけど今それに裂く予算がクライエントサイドで縮小されてきているので、来年度はいよいよヤバい。けど、ボスはそれでもなお、何か新しい構想が脳みそに入っているらしい。この人はどうやら地球人ではないらしい(見た目から判断するにたぶんヨーダと同じ星の人だと思われる)ので、発想のスケールがでかい。だけど中身がカラッポに見えるため、フツーの地球人のクライエントには現実的に話が通用しない。それでどんどん顧客の心は離れていく。それでもボスは「いい感触だ」と思っているらしい。「話に乗ってこないのはあいつらがバカだからだ」という。ビールを毎晩大量に摂取しているため、脳がおそらく梅酒のようになっているのではないかと思われる。それどころか、おそろしいことに、今テナントで入っているオフィスビルの家賃を、これまで3年にわたって滞納し続けてきたのが判明した。フロアを縮小することで一度は難を逃れたかに見えたが、年明け早々、やはり追い出されることになった。ビルのオーナーが裁判所を通して催告書を出してきたのだ。というわけで、週明けからあるベテラン社員が大慌てで駆けずり回って、奇跡的に妥当な物件を探して契約してくれたので、このあとものすごいスピードで内装を見て間仕切りをして、荷物を箱づめして搬入して、今週中に出て行くことになった。新しいオフィスは家賃がかなり安く抑えられるらしい。少し狭いけど、社員数からいえば妥当なところではないか。立地的にはかなりぜいたくな場所ではあるし。だけど、それでもボスの夢物語は、彼の脳みその中で、現実とは裏腹にまだまだこれからも続くらしい。宇宙人はタコのような姿をしているといわれていたけれど、もしかしたらホントにこの人はタコかもしれない。ヤツらは自分の足を食っても生きるからね。あとラッキョが好きみたいだしね。ラッキョ食ってビール飲んで、夢物語を皆に聞かせてあげて、幸せに暮らせたら、こんなにいいことははないよね。まあ幸せで長生きしてくらはい、って感じだね。本人がそれでいいというのなら、これまでだ。缶ビールの宴会とともに、会社もお開きにするか、オレたちも、ビールの泡とともに消えてなくなるか。このままの状態で、下のモンの話を聞く耳持たないで独断で生きていくのなら、明日はたぶん永遠に見えてこない。せめて、新しいオフィス探して引越しの手配をしてくれた社員に、お金出せないのは仕方ないとしても、ねぎらいの一言ぐらい云ってあげて欲しいんだけど、最近は地球人の言葉も忘れかけているらしい。。。
January 22, 2004
-
時事爺次々ジジジjijiji...ジハード!!
☆ぎうどんよサヨウナラ? どうも「すき家」で「鳥そぼろ丼」ばかり進められるとミョーな感覚を憶えるものですな。 筋肉スグルくんもきっと悲しんでいることでしょう。 私も悲しいです。結構昼食の貴重なメニューだっただけに、これがいきなり消えてしまうというのは、鹿島から住友金属が撤退してしまうようなものです(ってそんな大げさでもないか)。 なので、牛丼が販売をやめるその日まで、私はできる限りお昼は牛丼を食べたいと思います(って勝手にしろって感じですけど・笑)。☆新撰組! なんだか去年の「武蔵」と比較して、面白いから許すけど時代考証がおかしい、との声が出ているらしいですね。 初回で、江戸のそば屋で近藤勇と土方歳三が、長州藩の桂小五郎と出くわし、何やかやと嫌味を云われた上にそばの代金を奢るといわれてキレそうになり、けんかになりかけたところで坂本竜馬がそれを仲介する、というシーンがあったんだけど、もし仮にそんな設定があり得るのなら面白いけど、どうやらそんなことは、当時の彼らの置かれていた立場とかいた場所等を突き詰めると、どうしてもあり得ないことらしい。 さらにあろうことか、近藤勇はその場で坂本竜馬と裸になって相撲までとってしまうんだからすごい。 かといって、それを見ていた人が生きてるわけでもないから、設定を作り変えちゃうことについては自由なんだけど、こだわり派の幕末ファンの間では「こんな大河ドラマあり?」みたいな感じも否めず、ってことらしい。 「ジャンクスポーツ」を見たい派の私にとっては、そんなことについての意識はプライオリティ低いほうなんだけど、時代劇は好きなので、今後どんなハチャメチャな展開になるのか、というのも期待感があるね。 できればハリスの役をデーブ・スペクターにして欲しいな(笑)。 たぶんこの脚本を書いた三谷好喜氏が好みで選んだキャスティングだと思うけど、中村獅童は月代にすると面白いように存在感が消えるなあ。☆そんな暢気な話じゃなくて・・・ イラクに日本の陸上自衛隊が到着した。 テロが日常茶飯事の状況で、死者が出なかったら奇跡である。 いくら特別手当もらっても、金では命は買えないのよ。 小泉総理大臣がいくら「我々も覚悟を決めて臨みたい」と云っても、アンタが覚悟を決めたって、死ぬのはアンタじゃないでしょ。 四国でうどん食ってるバヤイではない。国会はさっさと予算など決めること決めて、自分も早々に現地を訪れるべきである。 それがダメなら福田か安部が行け。大所高所からエラソーなことばっか云ってるんじゃないよ。 お前らが命懸けてるところを見せないと、ウワサになってるけど本当に、自衛隊の中から2.26事件並のクーデターが起きるよ。 「どっちみち死ぬんなら内閣つぶせ」ってチョイスする奴がいても、文句云う資格ないと、自衛隊員だけでなく一般国民の世論レベルでさえ思っちゃうよ。☆爺婆と現代の生き証人 それにしても、戦争での悲惨な経験を持つ人が爺婆だけになってしまった今、彼らの戦争に対しての肉声というのは大変貴重ではあるわけだけれど、こと今回の戦争の話になるとピントがずれがちになる。 幾時代かを経ると、記憶は鮮明さを失っていく。 そして今の戦争は、当時のそれとはスタイルもシステムも違うし、環境も違う。残忍さは同じかもしれないけれど。 彼らにとって、第二次大戦は今はセピア色化しているかもしれない。 そうなると、それを伝え聞く私たちにとっては、 「いく時代かがありまして 茶色い戦争ありました」 みたいな、中原中也の詩のような、空想的なものとしてしか、イメージできない。そのへんのギャップがもどかしい。 早く、第一陣でイラクに出向した自衛隊員に帰還してもらい、現地の悲惨さや恐ろしさを我々に伝えて欲しいものだ。 一番いいのは、何事もなく、当初政府が描いていた「人道復興支援」が実現されることなのだけれど。☆「ジハード」 一番怖いのは、「アメリカvs全イスラム勢力」という構図ができてしまうことだ。 今の段階では、アメリカ・イギリスとイスラム原理主義との対立に留まっているが、これがエスカレートする要素は沢山ある。 もしエスカレートし、イスラム全体との敵対関係が成立するとなれば、非常に複雑なことになる。 全米国内にもムスリムは大勢存在する。特にアフリカン・アメリカンの人たち。イスラムには人種差別はないから入信資格は誰にでもあるのだ。 かつアメリカは自由思想の許される国であるから。 彼らもまた、自らの住むアメリカで暴動を起こしたり、迫害を受けたりする可能性もあり、そうなると、ラスタファリアニズム(黒人回帰主義)を提唱する全世界のアフロ系民族とアメリカとの対立構造等も生まれる危険性もある。 アメリカ政府が国連やEU諸国と協力したとしても、このイデオロギーの対立に終止符が打たれる見通しは、全くといってよいほど立たなくなってしまう。 そうなる前に、可能であればアメリカを主体とした譲歩による歩み寄りを、ぜひ切望したいものだ。・・・なんだかいつもいつも話が飛躍しすぎてとりとめがなくなってしまいますね。申し訳ない。m(_ _)m
January 21, 2004
-
イラ立ちと平穏と。
なんとなく、ここ数日の日記などから、私の心の中がいら立ちに満ちて見える人もいらっしゃるのではないかなあ、と思うのですが、今の自分の精神状態はどうなんだろう、って、ふと考えてみたりしています。ここのところ頻繁にそんなことを繰り返して、「今の自分」を感じていたいと思います。・・・って、そういうことが大事だって、私たちに心理学とカウンセリングを教えてくれた講師の先生が、今受けている研修会(クリニカルスタディ)の場で何度も繰り返し云います。それに対して反感を抱いているのかどうかわからないけれど、好意的に受け止めようとしない元・クラスメイトがいます。この人は、本来とても思いやり深くて、勉強も人一倍熱心にやるタイプで、コミュニケーションも私より数段すぐれていると思う。だけど、今のこの人を見て思うのは、人の好き嫌いをはっきり云うことと、何かにとても焦っている、ということです。いわく「そんな当たり前のこと教えられても全然面白くない」「このまま話を聞いていても、それで自分がスキルアップできると思えない」また、講師にマイナスのストロークをもらって反感を抱いている、というところもあるらしい(個人的には、マイナスのストロークでは決してなくて、そのストロークをもらったことで見えたこともあった筈、と思うのですが)。さっき云った「好き嫌い」にこれがひっかかってくると、「嫌い=受け入れたくない」になっちゃう。それは、せっかくこういう勉強をしてきた者としては勿体ないことだなあ、と思うのですね。その人の発言に対して振り回されてるわけでは、決してないのですけれど、本人が穏やかでないところを赤裸々に見せて接してくるのを見て、それが転移しているのかな、という気もします。人間関係って、結構自分一人でコントロールできないものだな、って思います。とくにその人に対して好意的に思い、接するほど、そう思うのです。その焦りというのは、いろいろあると思いますけど、その一つは、カウンセリング実践の場が得られない、ゆえに自分のカウンセリング・スキルがアップしない、ということへの焦りなのかな、などとふと思います。多分、同期の元クラスメイトに、この人の気持ちに共感する人もいたりするのかなあ、と思うんだけれど、それで皆が皆、同様に、今受けている研修会(クリニカルスタディ)がスキルアップにつながらないと感じるかというと、それは違うのであって、今そう感じているのは、一プロセスなのであって、その先に何が見えてくるのか、というのが大切なことのように思っています。なので、今自分は、いろいろと周囲の波風を見て不安を感じつつも、研修は受け続けたいと思って、昨日その後どんな展開になるのか楽しみだったりしたのですが、突発やっつけ仕事と夜逃げ準備に終われ、出席できなかった、悔しい!!この悔しい気持ちをあと1週間抱き続けて、でも来週を楽しみにしているんだけど、共感して、と云っても皆ワケわからんだろね(笑)。基本的に、自分自身は風邪ひいた以外は、心の芯の部分は平穏なんだけど、周りがイライラドタバタしてたのを受けて一緒にドタバタしちゃったかな、っていうのがここ数日の自分の状態です。まだまだその程度の波風ごときで動揺してるようでは修行が足りないですよね(^^)。
January 20, 2004
-
週明けからカンベンしてくれ!!
☆モリちゃん2号、暴走す 風邪薬が切れたのだが、まだ完全復活とはいかず、医者で風邪薬をもらってから出社しようと思い会社へ電話したところ、目下WKP(私の周りの困った人)ランク1位にランキングされている、モリちゃん2号(注:モリちゃん1号もいたのだが、現在消息不明)が電話に出て、まくし立てた。「あのですね、週明け早々あれですが、実はあちらさんから大至急あれをナニして欲しいというオーダーを受けまして、シャチョーに相談したところ、chang-weiさんに頼むのが最適だろうということで、シャチョーの許可もいただきましたので、こうしてお電話で大変あれですがお願いしているわけなんですがね」と、モリちゃん2号は、ビールの大ジョッキを一気飲みするがごとくここまで一気にしゃべった。無論、何を云っているのかさっぱりわからない。モリちゃん2号は、さすがランキング1位の実力を遺憾なく発揮し、①指示代名詞を多用し、云ってることが全くわからない②でかい声で受話器に口をつけてしゃべるからうるさい③オレの都合など全く聞こうとしない④何かにつけ「シャチョーの許可」という言葉を口にする⑤オレより年上という、5拍子揃った、朝青龍も真っ青な理詰めの攻撃をしかけてきた。これでは付け入るスキがなく、風邪で弱りきったオレはマワシに全く手をかけることもできぬまま、あえなく土俵を割った。オレは、医者に行くのをやめて、おっとり刀で会社へ向かった。「シャチョー命令」を利用されてはなあ。風邪薬なんて貰ってる時間などなかった(クッ)。会社へたどりついて、モリちゃん2号に「何がどうしたんですか?」と聞いた。モリちゃん2号は、電話とほぼ一言一句違わぬ言葉を再びまくし立てた。そこで「『あれ』ってなんですか?」「『ナニ』ってどうすることでしょうか?」と個々に細かく質問したところ、ようやく話が見えてきた。非常に簡単に片付く問題であることが判明した(笑)。このモリちゃん2号は、50歳を越えた今まで会社組織に属したことのない、生粋の野生児に近い難民で、ゆえに一緒に仕事をする人間は悩む。マジメに正面から向き合えば向き合うほどストレスが溜まって、ノイローゼになる。ゆえに、真面目に向き合うことをモットーとしてきたオレは、彼との接触を極力避け続けてきたのだが、今回は、酒癖の悪さゆえにWKP第2位にランクされているウチのボスと最強タッグを組んで、オレに挑んできた。できればボスと組まないで欲しかったのだが、成り行き上仕方ない。でも実質マル1日で片づく仕事だったので、勿体つけて2日間かけてやることにした。☆結局追い出されるのじゃ 一時、追い出されずに済むはずのところだったのが、急にオフィスを引っ越すことが決定。 荷物の片付けをしながら調査をしながら、モリちゃん2号の仕事をこなしながら、というズボラな1日を過ごしているうちに、カウンセリングの研修に行く時間もなくなってしまうし、人に仕事を頼んできたモリちゃん2号はオレを置いて先に帰っちゃうし、荷造りを焦って、紐を切ろうとしてカッターナイフを手に刺してしまうし。 あまりにいろいろ続くので、笑ってしまったぜ。 疲れたのでもう寝よう。でもバタバタしてるうちに風邪は治ったみたいだね。
January 19, 2004
-
面白い!! RUMさんの本
「アメリカの弁護士は救急車を追いかける-アメリカの不思議なジョーシキ114」(ウォール真木・「よっこいしょういち」著/宝島社文庫)をようやく入手。現在、ナナメ読みしているところです。パラパラと読んでいるのだけど、面白いね。「よっこうしょういち」ことRUMさんは、ベアーズ・夜の部(ナイターのことではない)の中心的存在で、野球の試合以外の、フットサルとかテニスのときはいつも登場し、肝心の野球の試合も、昨年は4試合ほど出場。もともと話題豊富な人だと思ってはいたけれど、アメリカの大学に留学し、生活していたとは知りませんでした。共著のウォール真木さんは日本生まれでアメリカ在住の主婦ライターさんで、彼女の目を通じて感じるアメリカの「不思議なジョーシキ」を、淡々と書いているんだけど、その淡々としたところが面白いですね。アメリカの日常でのフシギなところとか、日本とあきらかに違うんだけど、向こうでは常識になってるところなんて、結構見落としがちなんですよね。で、わからないままアメリカに行ってワケわからなくなってしまうこともある。そういう意味で、ある意味実用的な本でもあるかな、とも思います。「トリビア」よりは役に立ちますね。トリビアはそもそも「役に立たない」のをウリにしているのだからそれでいいんだけどね。 RUMさんも、真木さんと協力して本の制作、販売を企画し、フツーに書店に並んでいるあたり、タダモノではない。まだ彼の素性は完全に明らかになってはいないのですが(笑)、とにかくもっともっと売れて、ベストセラーになることを祈りたいと思います。たぶん、まだ全部読んでない(さっき買ったばっかりだから当たり前だ)ので、これから読むうちに目からウロコの話題が出てくることでしょうね。また、アメリカは広いからもっともっとフシギなことはあるだろう。読み終えて、ちょっとアメリカにも行ってみたいかな、なんて思うかもしれません。あ、あとちなみに、この本は、短いコラムっぽいネタが2~3頁ずついくつも載ってる本なので、パラパラと移動電車の中で読むにはもってこいの本ですね。逆に「じっくり目を皿のようにして」読む本ではない感じ。何度も何度も、パラパラ読みできる、そんな感じの「スナック」的な本ですね。「料亭」的な本ではないようです(なんじゃそりゃ)。※ 午前中に書いた日記について 一時の感情から、そのときの自分の気持ちを書いたんだけど、冷静に考えてみると彼らはかけがえのない仲間であり、おめでたい話に水を差すような話題を文字でいつまでも残しておきたくないと思ったので、サシカエることにしました。 ご心配いただいた皆様、ありがとうございました。m(_ _)m
January 18, 2004
-
こんな同窓会は○○だ!!
同窓会あれやこれや。☆シメに校歌を歌う同窓会 ワセダとかケイオーとかだとカッコいいのだが、「ピーエルがくえん」とか「ちべんがくえん」のバヤイは、どうも具合が悪そうだな。 つーか、普通の呑み屋で卒業生が呑み会やって、ひと暴れしちゃったりしたあとでシメはやらないほうがいいですな。 そのせいで、なぜか関係ないやきう部が「大会出場停止」というワケわからん処分を受けるから。 あと、創立が古い学校とか極端に新しい学校だと、それぞれ恥ずかしい校歌だったりするから、これもちょっと辛い。☆仏教系の学校の同窓会 いつも学校の敷地の中にあるお堂でやる。 食事は、いつも一汁一菜と決められており、一同正座の上開宴。酒などもってのほか。ほうじ茶と白湯のみ。 皆、在学中に受けた修行の成果か、それぞれの間ではそれなりに楽しかったりするのだが、毎年参加者が減っていく傾向にある。☆30年以上ぶりの同窓会 当然のことながら、お互いの見た目の変化に驚くのがルール。 中には、最後まで誰にも思い出してもらえないヤツとか、最後まで別のヤツと間違えられていたヤツとか、逆に実はクラスメイトじゃなかったヤツとかもいたりする。☆60年以上、毎年行われ続けている同窓会 実際に、人数が同窓会名簿から、というよりも、この世から毎年減り続けている。 病気で出られないヤツが何人かいる。 話題が、オレオレ詐欺に遭った話とか、戦争中の思い出の話とか、年金の話、孫の話などに集中する。 それと、差別用語が飛び交う。 つづきは、また思いついたら書きます。
January 17, 2004
-
なぜか連日フォークダンスネタ
☆マイムマイム・補足 昨日の「マイムマイム」の話を書いてから、あてずっぽうとはいいながらもかなりテキトーだったと思い、いちおうインターネットをゴニョゴニョ覗いてみたところ、似たようなことを書いている人が20人ほどいらっしゃいました(笑)。 で、その中で、かなりマジモードで書いている方がいらっしゃったので、パクリならぬ補足の意味での引用をば・・・。 「マイムマイム」の掛け声は、正しくは、「マイム マイム マイム マイム マイム ベッサンソン♪」 だそうでございます。で、この「ベッサンソン」というのは、「嬉しい」とか「グッドだ」とか、そういう意味だそうです。 まあ、大筋としては、私めの昨日の解釈は当たらずとも遠からず、ってとこで、「大ウソ」にならなくてよかったのですが、さらに驚くべき新事実が発覚したのでございます!! この歌は、その前の「チャーラーラララーララララ チャーラーラーラララッチャッチャ♪」という演奏の部分にも歌詞があるそうなのですが、詳しい歌詞まで書くとホントにパクリになるので省略しますけど、その起源は、旧約聖書の「イザヤ書」に由来するものだそうなのです。 そんでもって、この「マイムマイム」という踊りは、聖なる水を寿ぐ神聖な儀式の踊りなんだそうなのです(ひぇー)。 詳しく知りたい方は、大学の宗教史の教科書もしくは「イザヤ書」そのものを読んでみてくだされ。なんか大変そうだけど。☆「クイカイマニマニ・・・」の踊り このほかにも、小学校ではいろんなダンスを習いましたな。もはや今となっては二度と踊らないようなヤツ。「オクラホマミキサー」とか「ジェンカ」とか。運動会が懐かしいです。あっ、親子フォークダンスなんてのはありえるかも。 その中で、タイトル忘れたんだけど、歌詞があるダンスで「クイカイマニマニマニマニダスキー クイカイコー クイカイコー♪」というのがあったの憶えてます? 忘れちゃった? そういうのがあったの!! ←青空球児風これ、ヘンな歌だと思って、でも大した疑問もなくサラリと流していたのですが、さて、これは何語の歌でしょう?・・・ってのを、TBSの朝のニュース番組の合間の「トリビアっぽいコーナー」でやってたのですねー。なのでこのネタはトリビアでは使えません。ザンネンでしたー。正解は、驚くなかれ、英語だったんですねー。歌詞は、正確にはこんな言葉を使っているそーです。“Quick I many many many many dusky,quick I go,quick I come,・・・”(急いで行くぞー、速く速く。外が真っ暗なうちに、行くぞー。さあ僕は来たよー・・・)これ、どういう状況かといいますと、アメリカ・インディアンのナントカ族の若者「レコデモ」君が、夜中だか早朝に、恋人の「○○」ちゃんに、人目を避けて会うために行くところを歌った歌なんだそうです。まあ、良く云えば「ランデヴー」、悪く云えば「夜這い」ですな。なんで人目を避けてたのかはよく憶えてません。あるいは禁じられた「ロミオとジュリエット」みたいな恋だったのか、それともインディアンの風習で婚前の男女の恋愛は禁じられていたのか。まあそれはおいといて、そんなロマンチックというかきわどいというか、そんな歌だったのでありますねー。そうとは知らなかったとはいえ、学校もよくぞ小学校のガキどもにそんな歌を歌わせた、偉い! といった感じでしょうか。で、歌詞の続きは「オー、レコデーモー、オー、○○(女の子の名前)」というのが出てきて、大人たちにつかまることもなく、コヨーテとかハイイログマみたいなのに襲われることもなく、2人のラブラブカップルは逢瀬を果たすことができた、という歓びのオチになってるようです。つーか、すっかり忘れたというか、そもそも歌詞なんて憶えようとも思わなかったので、ここで初めて「へぇー」って感じですわね。
January 15, 2004
-
なぜか「マイムマイム」の話
えーと、小学校の時分、体育の時間とか、お昼休みとかに、フォークダンスの時間とかがあったというおもひでを持つ人も多いと思いますが、いろんなダンスがあった中に「マイムマイム」というのがありましたな。ずっと前なんだけど、「マイムマイムについて考える」という企画を、「タモリ倶楽部」でやってたんだけど、その番組の中で、「なんだこの踊りは?」ってあちこち聞いて回って、結局よくわからぬまま「空耳アワー」の時間がやってきてしまったのね。で、その番組の中でわかったことというのが、・ この踊りは、イスラエルの踊りである・ 「マイム」というのは「水」のことである・ 皆が口ずさむ言葉は「マイムマイムマイムマイム マイムベッサッソン♪」という発音であるということでありました。で、もしかすると知ってる人は知ってるかもしれないし、でも私はそのへんの因果関係を知らぬまましゃべっている中で、以下のように推理してみました。イスラエルというのは、首都がエルサレムな筈なんだけど、そこをパレスチナと取り合いやってる国で、エジプトとかにも隣接してたりして、イエス・キリストも生まれたりとか、ヘドバとダビデの故郷だったりとか、サッカーが意外に強かったりとか、いろいろ話題豊富な国ではありますが、地域的には「中近東」というあたりにあるわけですね。で、あのへんの気候というのは、おそらく「乾燥帯」と呼ばれる、砂漠が結構いっぱいあって、日本なんかに比べると、はるかに水に乏しい国ではないかと思うのね。これが1のキーワード。次に、「マイムマイム」の踊りの動きを思い出してもらうと、輪になって、ステップ踏んで、「マイムマイムマイムマイム、マイムベッサッソン!」って叫んで、さらにステップ踏みながら、手を打って隣同士の人とも手と手を打ち合ったりしてますよね。これすなわち、喜びの意を表しているジェスチャーなのではないかと思ったりするのね。これが2のキーワード。さあこのへんで、答えが見えてきたでしょうか!?んー、「ベッサッソン」の意味はよくわからないんだけど、勘ぐるに「湧いてるぞ!」「あるぞ!」みたいな意味なのではないかと。砂漠に水、といえば、井戸もしくはオアシスですね。これらを総合して、考えるに、この「マイムマイム」という踊りは、砂漠地帯の生活の中で、井戸を掘り当てた、もしくはオアシスにたどり着いたことによって、潤沢な水を手に入れたことに対する、お祝いの踊りなのではないでしょうか?日本でいえば「豊穣の祭り」に匹敵するようなね。井戸で、湧き出る水を囲んで、「水、水、水、水、水が湧いたぞ♪」って、大はしゃぎしたりして。そんな、大昔のイスラエルの人たちの、無邪気に喜び踊る姿を思い描いたりします。どうです、ぴったりくると思いませんか?・・・って、オノレの推理に酔っているところに、体育の先生がツツッとやってきて、「そうです、そんなことは常識です」とか云われちゃうと、私のイマジネーションが全否定されてしまう。いやん(爆)。オレはお釈迦様の掌で暴れてる孫悟空かよ!!
January 14, 2004
-
IT化ですべてが解決するものか!
ここのところ、政府とか食品業界が「トレーサビリティシステム」というものを開発して、食品の生産・流通履歴を管理する体制を作ることによって、消費者の安心と信頼を取り戻すことに注力している。で、今話題になっている問題が、畜産物の病原菌に対する不安とかだったりして、一見「安全確保のために農林水産業や食品業界は頑張っているんだなあ」と思えたりもする一方、その背景を見てみると、Y印、Nハムといった大手食品メーカーなどの安全性管理不足による「不良品の流通」がその発端だったりするわけでしょう。現にこの前だって、半年前の鶏卵を新鮮な卵と偽って販売していた事業者がいたりとかさ。国内のIT化というのは、生活を豊かにし便利にするためのツールとして有効であり、我々もその恩恵を受けているのは確かです。けれど、ITによって安全管理をバッチリやっているから大丈夫、っていうのは、ちと云ってる話が違うような気がするんですね。感染症だとか、自然災害だとか、人の力ではどうしようもないものに対して、生活の安全を守るための措置としては、これは必要不可欠な話だと思うんだけど、それ以外に、人為的な原因により発生する「安心・安全の侵害」というのも物凄くいっぱいあるわけでしょう。それに対してのセキュリティだとか危機管理だとかいう話は、IT化以前にやることがあるだろうと思ったりするわけです。たとえばそれを発生させる人たちのモラルハザードをどうやって改善していくかとか。そうはいっても、大量生産・大量消費の時代にあって、ひとつひとつのモノや事象に対して関わってられない、っていう言い分もあるかもしれません。けれど、安全チェックをする人がもう少し真面目に管理に時間を費やして、よりよい商品を提供しよう、という意識が高ければ、あるいはこんな、高コストのシステム化なんてしなくてもよかったりする可能性もあった。あくまで主体は「人」であって、そのポテンシャルを補うのがハイテクノロジーだったりITだったりする、っていうのが原則なわけですよね。ともすればそっちの意識が、PCのシステム運用を覚えるのに必死なあまり、どっかに飛んじゃってたりしちゃうのなら、そんなムダなことはやめればいい。それで、アナログでいいから、人の手で責任持って管理すればいいのだ。なんかそのへんの優先順位がいつしかすりかわってて、おかしなことになってるような気がするんだけどねえ。食品安全に限った話ではありません。それ以外の商品の流通、交通安全、医療、教育、防犯、テロ、・・・。あと、今問題となってるコンピュータウィルスだとかハッカーにしたってさ、作ってる奴がいるから被害者もいるわけでしょ。自然発生したものではないでしょ。「アンチウィルス」などのワクチンソフトメーカーと、ウィルス作ってる奴らがつるんでるんじゃないだろうね、・・・なんていうのは下司の勘ぐりかもしれないが、仮にもしそうだったら許せないよね(笑)。ある漫画で、こんな話がありました。街で、ひったくりが横行していて、そのうち一人が現行犯逮捕された。彼は過去にも余罪がある「前科者」。ただ少年だったので軽い刑で出てきたらしい。で、再犯ということなのだが、動機について何か不自然な点がある。彼は検察に送られ、検事さんがかなり綿密にコミュニケーションを重ねた結果、真実を暴露した。初犯のとき、取り調べに当たった、結構ベテランの刑事にこう云われたという。「しばらくの間、お前らの仲間も集めて、もっと(ひったくりを)やっていいぞ、そのかわり、場所を○○地区に限定してやれ。つかまっても俺の権限で刑を受けなくてもいいように取り計らってやる」その検事がさらに調べてみると、とある警察関係の財団が、情報機器メーカーと組んで、○○地区に防犯モニターを設置する計画を進めていたという。その必要性を高めるための既成事実づくりに、少年たちは利用されていたのでした。・・・というオチでこのおはなしはおしまい。これはフィクションなんだけど、なんだか「病気がなくなると儲からないので、病原菌を医者がばらまく」みたいな話で、ぞっとしますよね。もし万が一、こんな本末転倒な理由でIT化を進めるのだったら、そんなのすぐにやめて欲しい。先に、もっと大事なこと、たとえばお互いを思いやる気持ちとか、迷惑をかけまいと努力する気持ちを養うとかね、そういうことを発想の原点において、ビジネスにせよ政策にせよ考えていかないと、その事業者は必ずや、どこからか、痛~いしっぺ返しを食らうことでしょう。ITに限らず、なんか今のビジネス社会は「自己中」な営業が多いような気がします。どことはいわないけど、とくに金融とか不動産を扱う会社さんたち。自分さえよければそれでいい、みたいな会社。トップのそういう意識が下々にまで浸透してしまっているんだろうなあ。。。・・・って、おっと、知らず知らずヤバい方向に話が展開してしまうところであった。これ以上しゃべるのはコワいので以下省略です(笑)。
January 13, 2004
-
「学歴」やら、あれやこれや・・・
この話、読む人によっては不快感を与えることもあると思うのですが、あくまで極私的・極主観的な思いを綴った話題です。最後まで読んでくださる方がいらっしゃれば幸いですが、嫌だったら駄文として読み捨てちゃってください。①「ヨソモノ感」 自分の話からしましょうか。 私は、都立高校を出たあと、地方の国立大学に入りました。 学校を選んだ理由は、大したことじゃあなかったような気がする。入試科目が小論文だけだったりとか、自分が好きだった世界史の教育実習生の先輩がそこを出ていたこととか、その人の恩師で面白い先生がいるというウワサを聞いていたりとか。 「大学」もしくは「大学生」というのは、あまり地域がどうだとか、そういうこだわりのないところ(ヤツら)だろう、と思っていたんだけど、実際は当初イメージどおりじゃなかった。しばらく「ヨソモノ」扱いは抜けなかったね。そういうのは覚悟してたつもりだったんだけど、思った以上にストレスはありましたね。 中には「お前が合格した分、オレの友達が浪人した」などと言ってきたヤツがいた。 バカなヤツだ、と思ったけど黙っていた。 ヤツらの地元意識は強くて、出身高校が同じだった者同士で徒党を組む連中が、どうしても多かった。初対面で「お前、どこの出身だ? 南高? 東高? 中央? 日大?(その地方ではメジャーな高校)」なんて聞かれることしばし。 だけど、ヨソから出てきている者も決して少なかったわけではなくて、仙台などの東北の他県をはじめ、新潟とか、北海道とか、いろんなところから来ている人も多くて、はじめはそういう「ヨソからきたもの同士」で友達が出来て行ったっけかなあ。 二十歳前の若造が仲間作りするときってのは、まだまだ「裸一貫」で飛び込むのには勇気が必要だったりして、土地のモン同士がくっつくのも自然な流れなのかなあ、なんて思いました。 高校時代の友達ってのも、ある意味人格形成の上で最も堅い友情で結ばれたりするってこともあるからね。地方の国立大学なんていったら、まさしくそういうヤツらがある意味「エスカレーター式」的に進路に選んだ、ってことなんでしょう。やがて時間の経過とともに、そういう壁はなくなっていき、それなりに楽しい大学生生活を送ることはできました。②社会に出て感じた「学閥」意識 就職した会社は、W大学出身の役員で固められた中小企業。 あとで聞いたところによると、その大学でボス格だった人が、仲間と語らって地主の息子だった社長を口説き落として会社を作ろうと持ちかけてスタートしたらしい。 で、営んでいた事業は、進学塾とスポーツクラブでした。 私は、スポーツクラブの新卒採用のためのリクルーターとして何年間か、毎年駆けずり回っていました。 ある意味、その時期は営業はどこもイケイケゴーゴーの時代。店舗はどんどん展開する。だけどそこで働く人手が足りない。だからとにかく優秀な人材を一人でも多く採って来い。けどなるべく予算は削れ。ローリスクハイリターンだ、・・・とかなんたらかんたら。 ・・・などなどと、上司であるW大卒の役員は私たちに云いました。 目標というものは、いつの時代もムリが伴なうもの。スポーツクラブで働きたいと思う「名門大学」の大学生というのも稀有な存在だった。 いたとしても、業界大手のEザスとか、Cトラルあたりに行ってしまう。 で、そうはいいつつ、「ウチは面白い会社だよー」「今入っておけば会社が大きくなったときに幹部になれるよー」などとおいしい言葉を並べつつ、ほうほうのていで何十人かの学生を集めてきた。 で、いざ面接に移って、選考をするにあたって、幹部がゴネり出した。 「なんだよ、こんなヘボ大学ばっかり集めやがって」 な、何をー!? W大学出身者の驕りか。大体こいつらは、学生一人一人と話をして、その内容をもとに云っているのだろうか。 私たちは必死に幹部を説得した。「彼らは私たちが会って話をして、こいつならやっていけると思って、他の会社を蹴ってもらって今日来てもらっているんです。」「でもK大学だからなあ・・・」この幹部は、K大学が嫌いらしく、さんざんゴネたあげく、OKを出した。ウッヒッヒ。 中小企業にしてこの体たらくだから、大企業だの、国家公務員Ⅰ種なんていう世界では、もっとさらにこういうこと「ばかり」に目を奪われている輩が多いんだろうねえ。中身なんて見もしないで。③「ちょっとした頑張り」をしないで・・・ 前に交際していた女の子と別れるきっかけになったやりとり。 「H(←オレ)はいいよねー、大学出てるしー」 彼女は専門学校卒業である。 「出てるったって大したことないよ」 「アタシなんてさー、専門出ただけで学歴ないしさー、バイトしかないしさー」 「でもさ、K子(←彼女)だってやりたいこととかあるんだろ?」 「できっこないよー」 「できるって! あきらめないで挑戦してみなよ」 「きれい事言わないでよ!! Hは自分が大学出だからそんなこと云えるんだよ。あたしなんてどーせ・・・」 何かと学歴を引き合いに出してひがみっぽく話す言い草に、オレはキレた。 「オマエなあ、そんなに大学に行きたかったんなら、行けばよかったじゃねーか!? 専門学校行く金があったんなら大学だって行けるだろうがよ」 「だって勉強嫌いだったしぃー・・・」 「あーあ、話になんねーよ。その考え方、頭悪すぎだと思わない? 今の世の中、大学なんて行こうと思ってちょっと頑張れば誰だって行けるんだぜ。お前の場合『行けない』んじゃなくて『行きたくない』んだろ、自分ごまかして周り見てひがんでんじゃないよ!! 迷惑なんだよ!!」 嗚呼、なんてひどいことを云ってしまったのだろう。云った直後に後悔した。 だが云ってしまったことばは引っ込められないような空気に、その場は包まれていた。「うう・・・(泣)、もう帰るうー。もうここには来ないから。サヨナラッ!!」 追いかけようと思ったけど、こっちも依怙地になっていたので、追わなかった。 正論ではあると、今でも思うことだけれど、K子をいたわる言葉ではなかった。 ちょっと日記の本筋からそれたけど、「そんなこともあったよん」という話。④学歴って、なんだ? 結局のところ、学歴って、何なのだろう? 誇り? アイデンティティ? 思い出? それとも、信用手形とかお墨付きみたいなもの? それを利用できる場というのは、一部のエリート社会を除いてごく少ないような気がする。今のボーダーレス社会では特に。 「私は東大出ました」って、卒業証書を自分の経営する会社の社長室に飾ってる社長は「タコ社長」のように見えるし。 そのくせハーバードでMBAなんか取ってたりして、それを飾ってると「おおっ! 只者じゃないな」なんて思っちゃったりするわけでもあって、どうも嫌らしい感じもするんだけどねえ。 云いたいのは、過去がどんなに優秀でも、私めの目で見て「アホ」な東大出だとかW大出なんてのは何人もいるのねん。要はハートの中身の問題なのだ! といいたいんだけど、わからんちんもまたいたりするんだよねえ。 大学って、今では社会人になってからでも入れるシステムが増えているから、学歴を取る、という意味だけじゃなくて、生きがいとか、生活を豊かにする、同じ道で学ぶ仲間と気持ちを共有する、といった意味でも、時間とお金の余裕がある人は入ってみるのもいいかもしれないね。 20歳前後当時とまた違った目で見るキャンパス、ってどんなものに映るんだろう(ワクワク)。 蛇足(つーか、ホントどーでもいい話)だけど、よくいる「同じ大学のOB・OG同士」の寄り集まりが、「同窓会」なら許してもいいけど、実のない「タテ関係」をミョーに意識している姿も、空しく見えたりするのは、そういうのを持たない我が身のひがみなのかな。いや、実があれば、そういうのどんどんひけらかして、使っちゃえばいいと思うのだけど、現実なかなか実を結ばないのは、やはり不景気のせいなのかねえ。はあ・・・。
January 12, 2004
-
メジャー番組になることの代償
☆枕・めでたいネタ熊仲間のよっこいしょういちが、共著で本を出したとの知らせが入ってきましたぞよ(すごい!! パチパチパチ)。ちょっと今まであまりになんでもかんでも話題に絡んでくるので、何者なのか、素性が不明だったのだが、ここで明らかになることでしょう。『アメリカの弁護士は救急車を追いかける-アメリカの不思議なジョーシキ114』宝島社 文庫本 600円ISBNコード 4-7966-3837-7(1月15日ごろ発売予定)という本ですって。皆さん、ぜひ読んでみましょう。なかなか面白そうです。著者名はあえてここではヒミツでございます。つーか、買えば書いてあるに決まってるので、そこに書いてあるヒトのどっちかがヤツです(笑)。☆本題ミニスカート 履いたまんまで またぐには ちと高すぎる 金の敷居は(解説 : 深夜番組で楽しみに見ていた番組が、深夜枠でなかなかの高視聴率をあげたので、テレビ局のはからいでその番組をゴールデンタイムに「昇格」させたのはよかったのだが、深夜ならではの醍醐味だった「バカ」「エロ」「毒」などの自重を強いられ、本来の面白さを失ってしまい、平凡な番組に成り下がってしまったことを嘆き詠みける歌・爆爆)・・・というわけで、話は飛ぶのですが、こんどは、テレビ番組がメジャーになることによって蒙る代償の話ね。以前、「トリビアの泉」というのは、もう少しアホらしさが加わってて、そのアホらしさが番組を面白くしていたと思うんですね(これに関しては深夜見てなかったので推測なんだけど)。その他「笑う犬」だとか「ボキャブラ天国」とか、ゴールデンタイムに移って腐っていった番組は少なくないですなー。ある意味、ゴールデンタイムに上がるっていうことは、番組制作者としてはすごく名誉あることに違いないんだろうけど、それだけ制約も増えてきて、のびのびできないのかもしれませんな。深夜、平気でエロネタやバカネタを出せてたのが、ゴールデンに進出することによって、PTAや教育委員会などの、「娯楽番組撲滅派・セイシュン喪失逆恨み民族」たちがギロ目を光らせて、ちょっとでもエロ・バカ・毒ネタを出したものなら、たちまち、「まあっ、なんてお下劣なおテレビ番組じゃござませんこと!?ウチのケンちゃんたちの健全育成の阻害要因ざます!!」と、怒鳴り込みをかけるために、モニタリングと称して「しっかり見ている(爆)」から、次第に自粛せざるを得ず、面白さのレベルも下がってしまってきているのでございます。最近、この「トリビア」のほかに「でぶや」が出てきて、さらに今度「ジャンクスポーツ」がゴールデンに移ってくる。「でぶや」の場合は、太った二人が食ってるだけで、やってることは対して変わってないけど、「ジャンクスポーツ」の場合は、けっこうヤバネタが売り物のハマちゃんが司会なので、おのずと話題のトーンが落ちてくるのは必然。ちょっと寂しい話ではありますな。まあある意味、資本主義社会の構図にも似たところがございます。ローカルで人気を得ていた地方の小さなお店が、やがて全国区で人気のお店になっていくにつれ、あまねく好評を得るには、その地方に限っては店の強みだったものが、「アク」になって伸び悩むことを怖れ、ニュートラルなものに変貌していく姿にさも似たり、ってところか。これに対して、しぶとくポリシーを変えず、20年以上深夜枠に止まっている「タモリ倶楽部」はあっぱれといいたいね。同じく「ミニスカポリス」あたりもエラい。でも最近見てないなー。そんな時間まで起きてられないもの。
January 11, 2004
-
今からねー・・・
「メダルが何個」とかって、アテネオリンピックのこと計算しているスポーツマスコミ界。別にいいけどさー。断言して国民をぬか喜びさせて、あとでそうならなかったときのことも考えてしゃべろうぜ。水泳とか陸上なんていう、体力勝負の種目の場合は特に、ピークをどう持っていけるかで、結果なんて予想とぜんぜん違ってくるんだしさ。日本がようやく復活の兆しを見せている柔道とか体操にしたってさ、審判の判定が狂うことだってあるし、たたみだとかマットがたまたまオリーブオイルで滑ったりとか(そんなことあるかどうかは不明)、何があるかなんてわかったもんじゃない。なんせ、開催地およびその周辺諸国が有利になるように運ぶのが、オリンピックの特徴なわけで、そんなこと、長野オリンピック見てたら一目瞭然だろ?それを乗り越えて勝った選手を心からリスペクトしてあげようじゃないの。日本のメダルだけに固執する今のオリンピック・ウォッチングの考え方は時代遅れだと思うよ。それなら、イギリスの「ブックメーカー」よろしく、各競技ごとの優勝選手予想でもして、ギャンブル的に楽しむほうがよほど健全だと思いますが、各スポーツ紙の皆さん、どんなもんでしょ?・・・なんていったら日本体育協会とかJOCから「このホームページは不適切発言が多すぎる」といって消されるかもしれないから、このへんでやめといてやるよ(笑)。ちなみに、今のところ「金メダル有力」と云われてるのは、・谷 亮子(女子柔道)・阿武教子(同)・井上孝生(男子柔道)・北島コースケ(男子平泳ぎ)・シンクロナイズドスイミングの各種目のうちどれか・野球・ソフトボール・男子体操・種目別のうち誰か・女子マラソンのうち誰かなんて云われてるけどね。日本選手が勝てば嬉しいけどさ、それぞれの種目の醍醐味が、日本がダメだとしても、ちゃんと伝わるような報道してくれよな。「日本ダメー」→「ドッチラケー」ってのはオリンピックの魅力を半減どころか、オリンピック種目への冒涜だとオレは思っているからね。
January 10, 2004
-
「病名」っぽいレッテル
「うつ状態」と「うつ病」は、同じじゃないんですよ。「過食」と「過食症」も同じじゃない。「症状」と「障害」または「疾患」の名前の違い。けっこう、そのへんが一緒くたになって、生活者に理解されがちだったりしそうなのがちょっと心配だったりします。最近ではテレビだとか新聞記事、書籍でも、「うつ病」「摂食障害(過食症・拒食症)」「多重人格障害」「統合失調症」「アルコール依存症」「パニック障害」などなどなどなど、いろんな、メンタルの疾患や神経症の名前が出てきて、そういう研究している人たちの本もものすごく一杯あって、書店にも並んでいるので、関心を高めることになるのはとてもよいことだけど、心配なのが、自分の心身に少し異常を感じた一般の人たちが、各種の情報を自分で読んで「理解」しちゃったようになって、お医者さんだとか心理臨床家をスルーして、たとえば自分で「私は『うつ病』だ!」とか思い込んじゃったりすることなのね。一般のウェブサイトなどでも、たとえば“goo”とかにも「おしえてドットコム」のようなところでメンタル相談をするコーナーを見ていると、冒頭で、「私はうつ病でしょうか?」「これって過食症?」って、ノッケのタイトルから「うつ病」「過食症」という名前が出てくる。「気力がわいてきません」とか、「眠れないんです」「食べたい欲求がおさまらない」とかいうのでなくて、「うつ病」「過食症」って、先回りして聞いてくる。しかもこれに答える人って、素人さんである場合が多いんだけど、「早めに専門家に相談することをお勧めします」「ここのURLでいろいろ参考になる情報が載ってるし相談にも乗ってもらえますよ」っていう答えならいいんだけど、とりわけ自分もうつ病だったりして、きっとそれは本人の親切心からだと思うが、「残念ながらそれはうつ病です」などと断定的に答えてたり、「こういう『治療法』があります。私はこれでよくなりました」なんて経験談を話し出す。背筋がゾクッとすることがままあります。本当は、本人の取り越し苦労であったり、思い違いである可能性もあるかもしれない。第一、文字のやりとりを見て、「こういう病気だ」断定されることによって、思い込みがますます激しくなって、本当に病気になる場合があります。そうなると、本来、ちょっと気分転換を図ればなんてことはなかったのかもしれなかったのが、薬を必要とすることになったり、治癒に時間がかかったりするんです。そういう人に出会った経験はまだないんだけど、コミカルに呼ぶと「なんちゃってうつ」、正式には「医原病」といいますね。そういうサイトで軽く「アンタうつ病だよ」って書いた人は、どうせサイト上でのやりとりだからちょっと軽い気持ちで書いてるかもしれないが、本当は物凄い責任問題になる可能性もあるんだからね。だから、ちょっと考えようなんだよねー。情報がたくさんあることはすごくいいことなんだけど、それをうまく生かして自分でなんとかできるレベルならいいんだけど、それがわからないようなことに遭遇したとき、専門家に聞く方向にシフトできるかどうか。クライエントが私に「うつ病なんです」って相談してきたら、どうしよう。「そうですか、あなたは『うつ病』なんですね」じゃなくて、「そうですか、あなたは『自分がうつ病だと思っている』んですね」と答えないと、質問が断定的なのに、その断定をさらに固めることになってしまう。もしかしたら「医原病」の決定打に、自分がなってしまう危険性もあるから。だから、「どうしてうつ病だと思うの?」と、その理由を聞こうと思います。「精神科のお医者さんに診断されたから」なのか。「歯医者さんに云われたから」なのか。「本で読んだから」なのか。で、「うつ病を治したい」なら、精神医学の力を借りなくてはいけない。そうではなくて、「うつ病かどうかはわからないけど、ゆううつな気持ちが続くから、それをなんとかしたい」なら、さらにそのことについて話し合う必要が出てくるでしょう。ものすごく選択肢がいっぱいあるでしょうね。私たちもさらに勉強が必要になりますね。ちょっとキリがなくなってきたので今日はこのへんで。
January 9, 2004
-
「バカの壁」のカベ
去年の出版界をにぎわせた養老猛さんの「バカの壁」。この本が売れたことに対するインタビューで、養老先生は、「あの本が売れること自体世の中がおかしくなってる証拠」だとか云ってたらしいね。本が売れて、アンタの考えが社会に評価されたんだから素直に喜べばいいのにね。彼が云っていた内容ってのは、これまでだって、言葉を変えていろんな人が書いてたことなんだよね。ビートたけしが書いてた「みんな自分がわからない」と、云ってる内容が殆ど変わらないもん。別に養老ちゃんがここで斬新なこと書いてるとは思わなかった。ただ面白かっただけ。ここでは、「みんな固定観念に縛られすぎていて、肝心な大事な部分を見落としてるぞ。大事なのはこういうことだぞ」って書いている。こういう本は大体社会にウケるね。問題はその先なんである。「このことは『バカの壁』に書いてあったから正しい」とかって、「バカの壁」をバイブルとかマニュアルにする奴が必ずいるだろう、ってこと。そこまでしなくとも、ウケウリをする奴はいるだろうね。「バイブルとかマニュアルにすがりついてたら視野が狭まるぞ」っていう話なのに、そういう奴は、「○○さん、それはこういうことではないでしょうか?」「ん? なんでそう思うの?」「だって、養老先生がこうおっしゃっていました・・・」なんて、さも得意げに云っちゃうのだろう。「養老教」が、かくして2003年に生まれる(笑)。だけど宗教法人申請しないから「バカの壁を支持する会」と、いつまでも「謎の集団」よばわりされ続けることだろう。だって本人が嫌がるから(爆)。みのもんたあたりは、そういうふうになりたげに見える。ブラウン管を通して「見える」だけで、ホントはどうだかわかりゃしないけどね。ウチのオフクロなんてもろに「バカの壁のカベ」にぶちあたる典型といってよいだろう。「8時だよ全員集合」とか「おれたちひょうきん族」は大嫌いだったのに、「徹子の部屋」に加藤茶とかたけしが出たとたんに「彼はなかなか素晴らしい人物だ」とか云うし。というわけで、「バカの壁」には、乗り越えてもさらにまた多くの人が超えられないカベがあったりして、そのカベをさらに頑丈に作ってしまう人もその中にはいるよ、というお話でした。おしまい~♪
January 8, 2004
-
横綱と 電子政府と 牛丼屋
とりあえず、川柳風タイトル(笑)。年始早々ピンチの三羽烏でございます。☆横綱 モンゴル人力士として初めての横綱・朝青龍。 若くして横綱になって、実際の相撲で好成績を収めている、というところまではよかったのだが、去年の九州場所を終えて、公式の「大相撲」の場所が終わってからトラブル続きで、最高位を占める立場が早くも危ういとの噂もチラホラ。 故郷モンゴル帰郷から日本へ戻る前後に先代の高砂親方が死去。その葬儀を欠席したといって騒がれ。 正月の初稽古を休んで、昨日だかの横綱審議委員総見のけいこで振るわなかったからといって騒がれ。 でも、12勝2敗だったらしいと聞いているんだけどなー。 その負けの中に、いつもけいこでこてんぱんにやっつけている高見盛に負けた、というのが騒ぎをまたまた大げさにしてたりして。 外国人力士が帰省して、旅の疲れを残してけいこが不十分なのは当たり前で、そんなことで騒ぐなよ、という気もするけどねえ。 いろいろ、モンゴルと日本の国民の気質だとか価値観の違いもあるはずだし、たかだか23歳ほどの若者である。やんちゃなところが出てもまだ許される年頃でもあると思うけど。 普通の、大学出のサラリーマンと同年代なわけで、まだまだ社会に出て、これから人間として成長していく年頃であるからして。 相撲という枠の中ではそれも許されないのかねー。相撲協会の人って、相撲取り出身だから、みんなでかい身体してる割に、了見狭いねー、なんて思っちゃうけど。 あー、審議委員の中にナ○ツネがいたんだっけ。じゃあしょうがないかな(爆)。 過去に、双羽黒(北尾)という、ちゃんこがまずいと言って部屋を飛び出して破門されたプッツン横綱がいたけど、それよりか随分マシかなあ、と思うよ。☆電子政府 2000年頃から、政府が「ミレニアムプロジェクト」を皮切りに、「日本を世界一のIT国家にする」というスローガンのもとで、まずは役所の事務手続きを次々と電子化し、PC等からも行政手続ができたりする世の中にしようとしてきている。いわゆる「電子政府」というヤツ。 これが、なかなか思うように進まない。というか、国が勝手にドンドコドンドコドンドコドンと進めているのだが、いわゆる「ひとり歩き状態」になってしまって、国民の信頼とか合意を十分に得られてない。 一昨年「住民基本台帳ネットワーク」のことでひと悶着あったのを覚えている方もいらっしゃると思うけど、個人情報を国に管理・監視されて、なおかつそれが漏洩しない保障がない、っていうのが一番の国民の合意を得られない理由。 だけどこれは引き続きドンドコドンドコさらに進もうとしていたりしたんだけど、去年あたりから、電子政府を進めるにあたって、古い行政情報システムを効率的なものに変えようという動きがあったんだ。 それで、旧来のシステムをいろいろ調べていくうちに、これらが物凄くムダな経費を裂いて、非効率な作業をやってきている、というのがわかったんだね。 これらのシステムを構築したりメンテナンスしたりするのを、完全に業者丸投げだったりして、そこでカネだけもらってテキトーに操ってミスっても責任とれない、みたいなのが多すぎた。 実は私がある情報システムについて本省の役人に話を聞きに行ったときに、「ああそんなの全部業者任せだよ、オレたちにできるわけないじゃん」って胸を張って云われたもの。 それで政府は慌てて、旧来のシステムを切り替えるための「精算」に追われている。 アウトソーシングするならするで、責任持って効率的に仕事ができる業者に、今後は切り替わっていくだろう。 今までの、「昔ながらのつきあい(癒着)」による契約の継続(随意契約)はやめて、一般競争入札で、本当に「信頼のおける業者」を選ぶ時代になってきたのだ。 なんか、ゼネコンの崩壊と同じで、そうなるとIT関係の大手各社は泡食ってるという有様。ヘタすると外資に食われるかもしれないし、そうなればなったで国内IT産業の伸び悩みなんてこともあるかもしれない。所詮は国から仕事もらって生き延びてきた輩なんだよなー。 で、そのカネの大元は、国民の税金によるもの以外の何者でもないのであります。 この話は、語りだすとキリがなくなるので、またの機会にこの続きをば。☆牛丼屋 BSEのことがあってから、いったん波風が収まった牛肉問題だが、またぞろ、今度は輸入牛肉、しかも輸入先の「最大手」アメリカの牛がBSEに感染しているのが発覚し、食肉業界に暗い影を落とし始めている。 今度は、アメリカ産の牛を使っている牛丼業界が大ピンチ。最大手で「牛丼一筋100年」のY野家は、来月にも牛丼やめるとまで云っております。 貴重な昼飯のアイテムがー(泣)、と嘆いているバヤイではございません。「豚丼」とか「ホルモン丼」「カレー」など、何か代替品の試作などにシフトして、当座をつなぐなどしないと、「一筋」というキレイ事では済まないのであります。 でもできることなら、再び安心して牛丼を安価で食えるようになって欲しい、と願う牛丼派。 すでに、ほかの丼モノではライバルたちに先を行かれてしまっているY野屋の、明日はどっちだ!?
January 7, 2004
-
「今ここにいる自分」を感じること
昨日受けた「クリニカルスタディ」は、研修用に録画した、カウンセリングのケースに関するビデオを見ながら、その場その場の文言や動作、聞く姿勢等、について、自分がセラピストの立場だったらどうするか、あるいはどうするのが最適か、というのを、かなり丁寧に考える、というのをやった。セラピストは、若くしてウチの協会のトップであるF先生。心理学博士号も取得している。クライエントがはじめに発した言葉、二言三言を見て「これを見て、何かおかしいと感じた点は?」という質問がきて、その都度頭をひねる我々受講者たち。「この時点で、クライエントのまず抱えている問題点を察知できなかったら駄目だ」とF先生は云ったそうだ(うひゃー厳しい)。考えるのに時間がかかる。やがて一人の受講者がおそるおそる挙手。「『本当のお母さん』という言葉が、もしかしたら・・・」「もしかしたら、何?」と、講師のI先生。このクラスでは、自分の意見を、根拠立てて言語化することがルール。それができないと発言は却下されてしまう。だからとても発言が慎重になる。笑ってごまかすことも厳禁。「もしかしたらおかしい言葉遣いなんじゃないかと私は思いました」「なるほど。他には?」といった具合で、何度も何度もビデオを巻き戻しては再生し、を繰り返した。わずか3分間の間に交わされたやりとりのビデオを見る中で、次々と、驚くほどいろんな問題が見えてくる。F先生は、その3分間の対話の中で、クライエントの言葉を巧みに引き出し、イメージを共有するための話の受容の姿勢がものすごくスムーズに、かつ的確に必要なところを押さえている。それを受講者のための「適切な対応の手本」として見せることができるのが凄い。たぶん、講師の先生方は皆それができてしまうのだろうから、昨日、またそれ以前のスクーリングでは、まさしく月を見上げるスッポン状態だったオレたち。昨日は、その3分間のやりとりを見たところでタイムオーバー。実際のセラピーで、自分がひとつひとつのやりとりをスムーズに、自然にできるまでには、相応の経験とフィードバック(スーパーヴィジョン)が必要だな、と感じた。それには、今のノホホンとした構えから、途方もなく意識を変えることになっていくのだろうな、と、昨日は思った。同じことをやろうとしても、昨日、今日の自分にはできない。模倣が正しい方法ともいえないから。先生のコピーになるわけにはいかないわけだから。それこそ一挙手一投足、言葉の抑揚から言葉遣いにいたるまで、自分の発言や相手の発言を振り返ってみるという努力を、何百回、何千回と繰り返すことが大事だなあと感じた。また、それに加えて重要なことがあるのに改めて気づく。これまで、「自己洞察」「自己一致」「今ここの自分を感じること」の重要性を再三指摘され、理屈では頭に入っていても、実践にどう生かせるのかがピンときてなかったところがあった。「今、自分はこういう感情を抱いて、こういう姿勢で、クライエントの話を聞いているな」というのが見えること、というのが、カウンセリングのその場で、感情などに流されず、ニュートラルに相手を受容でき、また話の運び方もスムーズにできることにつながるのだと、改めて感じ入ってしまった。日常の会話とカウンセリングの格差を感じると同時に、日常でカウンセリングの話し方を生かすことができたら、あるいはスムーズに話題が運ぶかもしれないし、実際のカウンセリングの場にも生かせるかもしれない。特定の問題ばかりに目をやっていてもらちは開かないだろうから、いろんな会話の場面を、カウンセリングに当てはめて考えてみたいものだ。それが実際にカウンセリングになったりすればメッケものではあるけど、今ここの自分は、宣言ばかりが先行してしまって、いざなかなかそれを試みようと気持ちをシフトできずにいる。だけど、これから必ずやるぞぉ、っていう気持ちになった。今はそんな段階です。これから先の道のりは長いです。
January 6, 2004
-
生きているって、楽しいさぁー
お正月、NHKのドラマアンコールでやった「ちゅらさん・総集編」の最終回(1月2日)で、ヒロインのえりぃ(国仲涼子)が云った一言。なんかすごく、今頃になって、胸を突く一言でした。たしか、この回は、何回も見た記憶があります。そのときは聞き流していたことば。だけど、今、というか一昨日のあの瞬間、心のツボに刺さりました。なんでかなー。涙が止まらなかったんだよねー。「そうだよねー」って、心の中でTV画面に向かってつぶやいていました。生きていて辛いこともある。煩わしくて疲れることもある。だけど、そういうことも含めて、生きていることっていうのは、本来、トータルで見て楽しいことである。あるいはそうでありたい。今年は、私も「生きているって、楽しい」と思いながら生きていきたい。目標なのかどうなのか。違うかもしれないけど、自己暗示かもしれないけど、楽しんで生きていたい。
January 4, 2004
-
うう。。。
今日は珍しく呑みすぎでちょとムカムカしておりまする。なので今日はうどんしか食ってない。正月だからいっか、ってことで。今日は「アブラ抜き」である。そればかりか、もうひとつムカつくことがあったのでありますのよ(ーーメ)。年賀状に混じって、一通の封書が届いており、開封すると、ヘンな督促状が入っておった。むかーし、若い頃(っておじいちゃんかオレは)、「資格商法」の人から電話がかかってきて、よく世の中の仕組みを知らない私は、うっかり話を聞いちゃったのですね。そしたらほどなくして教材と支払い手続きの書類みたいのが送られてきて、「これであなたも○○士になれます」みたいな話が書いてあって、愚かな私は「おお、こんな資格にチャレンジしてみるのもいいかもな!」などと思ったのだが、どーも怪しい。よくある通信教育と比べて値段が高すぎる。知人に聞いたら「それは悪徳業者だ」というので、「クーリングオフ」というのを教わって、返却した。すると、またほどなくして、別の業者が電話をしてきて、似たようなことをぬかすので、「お金がないのでできません」とか、なおもしつこく食い下がるヤツには、「すいません、実はヒトを車ではねてしまってその弁済をしているんですー」などといっては断り続けてきたのだ。まあ一回ひっかかっちゃうと、しつこいねーヤツらは。オレの名簿がたぶんヤツらの「悪徳ネットワーク」に流出しまくったことだろう。ヤツらがあまりに執拗なので、引越しなどもしてたらますますお金がなくなってきたりして、別の理由で会社もやめた。で、しばし安堵していたら、忘れた頃に来たね。今日。わけのわからん督促状作戦で、恐喝まがいのことが書いてあった。「資格を取るまでやめることができないシステムなのは知っているくせに、貴方は勝手に断った」「8日までに50万円支払わないと我々は法的手段に出ざるを得ない」「容赦なく取り立てに行くので待ってろ」「裁判所に申し出て物品や財産を差し押さえる」だってさ。普段だったら笑っちゃうところだが、二日酔いのムカつきがさらにムカついてきた。ヒトを一回だまして高額な教材を売りつけようとしておいて、こんどは「滞納者呼ばわり」である。正月気分も丸つぶれである。面倒くさいねー。正月早々消費者センターに行くのは。口で負けるだろうからね。向こうはヤクザの親分みたいな上司に鍛えられ、だますテクニックで日々研鑽に研鑽を重ねたプロだからねー。逆ギレ作戦に出ちゃおうかな。でもコワいヤツだったらどうしよう(^^;;)。警察に頼めばガードしてくれたりするのだろうか。
January 3, 2004
-
「ナンバ」は日本人たる証??
「身振りと仕草の人間学」とかいったタイトルの、中公新書(?)あたりの本に紹介されていた話なんですけどね。「ナンバ歩き」とか「ナンバ走り」というのが話題になっとりまして。これ、何かと申しますと、右手と右足を同時に出して歩いたり走ったりする動きを指して、日本の時代劇の脚本家さんだったか監督さんがいろいろお話されていたらしいんだけど、よく覚えてないのです。ちょっともう一度この本読み直す機会があったら確認してみようかと思うんですけど。そしたらね。去年の暮れあたりに、スポーツ新聞の広告で、去年の世界陸上200m銅メダルの末続選手の走法が、この「ナンバ走り」を生かした日本人独特の走法だとかなんとかいいたげな本(説明にそんなことが書いてあったんだよ)が紹介されとったので「おやや!?」と思った次第でして。よく、陸上に限らずスポーツ選手が走るとき、腕振りのことを重視しますよね。短距離の選手なんかとくに、ブオンブオン腕を振って、その勢いも使って加速するから、上半身の筋肉とかも物凄く盛り上がってる選手が多い。彼らは、一般的に一歩一歩腕と脚の動きが逆に出る。これは我々も基本的にそうだと思いますし、そのように指導も受けてきたのでおのずとそうなっているはず。末続が「ナンバ走法」なわけではないんだけど、彼の走りは、腕の振りがさほど他の選手ほど大きくない。小さく振ってはいるけれど、よく見ると、記憶が定かできないんだけど、肩の出方が脚と一緒に出ていたような気もしたなあそういえば、なんて、ふと思いました。「ナンバ」は、昔の武士が使っていた歩き方、走り方であるらしいんです。甲冑つけて、腰に刀挿して、移動するときに、現代の腕脚逆出し歩行&走行だと、すごく上下動が大きいような気がします。ガチャガチャウザいだろうし、振動で刀なんか抜けちゃって危なっかしいかもしれない。なので、ススッと、上下動少なく移動するための方法だったのかもしれませんが、よくわかりません。面白いことに、昔の日本では、馬にもそういう訓練を施していたらしく、ナンバ走りをする馬にまたがって武士は戦などを戦っていたらしい。確かに競馬とか乗馬の、サラブレッドの走りの上では武士は縦揺れが激しくて振り落とされるかもしれないですね。ナンバのほかに、摺り足なんかもそうかもしれません。今、それをやってるのは、相撲ですね。あれは一歩一歩、相手を押す力が直接前に加わるから、効果的なのですね。摺り足も含めて、それが土俵上でちゃんと出来てる力士は、身体は小さくとも強いです。最近の力士では、千代の富士、若貴、朝青龍はこの基本がきっちりできていたように思います。逆に強かったんだけど、意外にこれが出来てなかったのが、輪島、北の湖、武蔵丸、魁皇あたりですね。彼らは素質でそのへんをカバーしていたような気がする。機会があれば相撲のビデオ等ごらんになって見るとおわかりいただけると思います。最近、時代劇に若手の役者さんがたくさん増えてきて、世代交代しながらも時代劇が受け継がれていくのは嬉しいんだけど、ちょっと物足りないのが、殺陣とかの動きが現代風になってしまって見えること。時代劇の役者の動きに独特の魅力を感じていたのが、もしかしたらこのナンバの動きだったのかな、などとふと思ったりします。ナンバができる役者なんているのかなあ、たぶん殆どいないでしょう。最後に。よく、結婚式のスピーチを頼まれたりして、物凄く緊張して壇上に向かって歩いているのを見られて、「お前、手と脚が一緒に出てたぞ」なんていわれた経験はありませんか?これも不確かな話なんだけど、緊張すると、人間って、本来の動きを無意識にしてしまうことがよくあります。日本人の血によって受け継がれた、これは「先天的クセ」なのかもしれないな、なんてふと思ったりしていますが。。。
January 2, 2004
-
元旦が簡単に。。。
皆様あけましておめでとうございます。・・・って、トップページで書いてるので以下省略。いやはや、それにしてもあっけなく年が明けてしまい、大晦日も正月もあっという間に過ぎ去っていくにちがいないでしょうなあ。んでもって、余韻に浸っているいとまもなさそうです。それでもきちんと薮入りの里帰り、の方もいらっしゃることでしょうし、皆さん大変ですよねー。特に遠方の方は。昔(といってもそんなに昔でもないけど)、「渋滞」っていう映画があったけど、萩原健一と黒木瞳の夫婦がクルマで実家に帰ろうとするんだけど、渋滞で、しかも実家が中国地方のほうだったりして、子どもがグズったり、ケンカしたり、仲直りしながら、何日も何日もかかって、移動中に年が明けちゃって、正月三が日の最後の日の、ほんの10分だけ両親と、寒空の下で顔合わせして帰る、その道すがらを映画にした話で、結構味わい深くて面白かったなあ。今は、そこまでする人も少なくなったとは思いますね。逆にスキーに行ったりハワイに行ったり、バカンスとして年末年始の休みを楽しむとか、そこまでしなくても、ウチでゴロゴロしてれば楽しいテレビ番組もいっぱいあるし。簡単で楽なほうを選ぶタイプの私は、基本的に「ただただ休む」。スポーツの催しも結構あるので、それを見に行ったりはすることもあるけど、ゴチャゴチャしたところとか喧騒は苦手なので、空いてるところに行きますね。なんか、似たタイプの人たちが世の中には増えてきたみたいで、いいんだか悪いんだかよくわかりませんけど。そのおかげで忙しくなってるのがコンビニとかスーパーで働く人たち。どーも申し訳ないでございますが、皆様がガンバってくださるおかげで、何不自由なく年末年始を送れるわけでございます。それでも「アメ横」あたりがすたれてしまったか、というとそんなことはなくて、元気に押しくら饅頭してる人たちは去年もいたみたいですね。そういうのが失われちゃうと、ホントに寂しい時代になっちゃうんだろうなー、とは思います。お昼ごろ、寝起きで近所の神社に初詣に行ってきた(なんて簡単な)。いちおう、住んでるところの土地神様なので大事にしなければ、とか思って、それは欠かさず行ってるんだけど、プラスアルファでどっか行ったりすることもあるけどね。それはともかくとして、おみくじは「小吉」で、読んでみたら、「過去の積み重ねにこだわると凶/転居は早いほど吉/旅立ちは大吉/西の方角に吉あり」などなど、なにやら人のココロを見透かしたようなことを書いてあった。恐るべし、土地神。つまり、初心に返って、住まいも環境も変えて気分一新せよ、ってことのようですね。「西の方に何かいいことがある」って、なんかサン・クリシュナ教の啓示を受けたみたいでサイケな気持ちになってくるぜ(ワクワク)。でもオレは東が好きなんだけどね(爆)。ということで、今年は、転居&転職で、少し「西のほう」で暮らすことも一考の余地あり、という、よくわからんけど検討してみるでございます。つーことで(何が「つーこと」かは不明)、今年もよろしくお願いいたします。
January 1, 2004
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 639.開いてごらんよ その眼を 視えな…
- (2025-11-17 00:00:15)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 生きがいの見つけ方
- (2025-11-16 10:51:00)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「イマドキではない」19歳女優 ビキ…
- (2025-11-17 00:30:05)
-