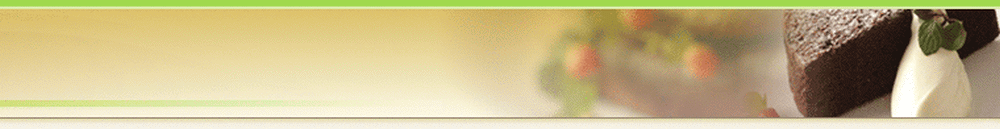2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年05月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
小兵の貴公子
以下、30日に亡くなった、元大関・貴ノ花の二子山親方の現役時代の思い出を中心にした話題です。私より上の年代の方で、彼の思い出を抱いてきた方も大勢いらっしゃることでしょう。相撲ファン以外の人にも、あまねく広く愛されるお相撲さんでした。これからも、相撲ファンをはじめ、彼を知る人たちからは、長く愛され続けることでしょう。ご冥福をお祈りします。----------------------------------------------ディープインパクトのことを「チビ馬」呼ばわりしたが、小柄の人を軽視したわけでは全くない。念のため。逆に「山椒は小粒だがピリリと辛い」という言葉は結構好きである。唯一、チビで嫌いだったのが、去年つぶれた自分の会社の社長なのだが(爆)、それはあんまり関係ないのでどうでもいい。けど、歴史上の偉大な人物って、こと日本では案外小柄な人が多いんだよね。豊臣秀吉なんて、本当にチビだったらしい。チビでなければ「猿」だの「ハゲネズミ」なんてあだ名はつかなかっただろう。源義経だって、戦の大将のくせに「八艘飛び」なんてやるぐらいだから、当然小柄だった筈だ。無論、偉い人が全部小さいというわけじゃあ全くないけど。幼い頃に、夕方になってから、テレビで家族が相撲を見ているのを脇のほうで見ていると、小さくてか細いお相撲さんが、彼に比べれば全然大柄なお相撲さんの突進を巧みに交わしつつ、ときに勝ってしまう姿が印象的だった。彼は、どう見ても相撲取りの顔には見えない、アイドル歌手のようなきれいな顔立ちをしているのに、裸にまわしを巻いて、頭にはちょんまげがついてる。「おすもうさんはからだがおっきくてふとっちょ」という固定観念みたいなものがたぶんその頃からあったのだと思うので、これには衝撃を受けた。今思えば、当時よく見ていた「ウルトラマン」でも、自分よりでかい怪獣を、力ずくで投げ飛ばしてやっつけるウルトラマンがいたから、抵抗はなかったんじゃないかと思うんだけど、なかなかそれと重ね合わせて見ることができなかった。見るからに弱々しいそのお相撲さんは、テレビで見る日はよく負けていた。それも、残酷なまでに土俵の外へ軽々と突き飛ばされたり、あるいは土俵の中央に倒されたりしていた。小さいんだから当たり前だと思った。自分もその頃はチビだったから、小さいがゆえに大きい子にねじ伏せられることも、しばしばあったから。「小兵」という言葉は、当時はまだ知らなかった。こんなに弱いのに、それでも辞めないでいつも出てくるのが不思議だった。で、やはり他のデブずもうたちに、吹っ飛ばされたり土俵にねじ伏せられたりしていた。男の幼児というのは、こういう、か弱いヒーローが悪役(?)にねじ伏せられているのを見ると、なぜか胸がドキドキして、股ぐらのあたりが熱くなる(笑)。フロイトの「性的欲動」のようなものか。ちなみにホモとは違う。この力士が負けたときの記憶に、なんとなくそういう生臭いようなのがある。だから覚えているのでもある。今、「角界の貴公子」こと、貴ノ花の記憶を頭の中でたどっている。「若貴ブーム」の横綱貴乃花じゃなく、その父親、初代の大関貴ノ花。現役時代の貴ノ花の成績は、自分がテレビで見ていたのよりも、ずっと凄いものだったということを知ったのは、もっと後のことである。つまり実際は自分が知っているよりももっともっと勝っていた、強い力士だったのだ。大関になるぐらいだから当たり前だけど。大横綱大鵬を引退に追い込んだのも貴ノ花だったという。天才・北の湖を寄り切って2度も優勝したことさえある。その相撲は、残念なことに生で見たことがない。その後テレビで見たときは、いつも北の湖に簡単につり出しで運び出されるか、数秒ではたきこまれて土俵を這っていた。相撲をよく見るようになってから貴ノ花が引退するまでに、北の湖に勝ったのを見た記憶は全くといっていいほどない。でも強い勝ち方で勝ったこともあったというのである。今もって残念である。北の湖は、そのまま大鵬を上回ろうかという勢いでどんどん強くなり、優勝回数を重ねていった。貴ノ花は、大関の座から上に上がることはついぞなく、そのかわり陥落もせず、必死に土俵の上で戦っていた。これが今の魁皇や千代大海ならば、「ふがいない」の一言で片づけられてしまっていたであろう。けれど、横綱昇格の目がなくなってからも、小兵大関貴ノ花の必死の土俵に対する声援は決して途絶えることはなく、負けた日には皆が残念がり、勝ち星には誰もが喜んだ。判官びいきの日本国民の好みにぴったり合った、不世出の人気大関だった。最後は、北の湖のあとを受けて一時代を築いていく、当時は頂点に上りつめる途上にあった千代の富士に、完璧な相撲で敗れたのを契機に、現役引退を決意した。ちなみに千代の富士は、それ以前の対貴ノ花初対戦当時は、貴ノ花よりも細い、100キロにも満たないガリガリで筋肉ムキムキの小兵力士で、あだ名の「ウルフ」が定着する前は「小型貴ノ花」と呼ばれていた。知らず知らず、世の中は貴ノ花中心に回っていたのだ(笑)。貴ノ花が、なぜか圧倒的に強い日がときどきあった。僕が応援する力士を相手にしたときだ。相性なのか僕の日ごろの行いが悪いせいなのか。おそらく両方だろう(笑)。輪島、魁傑、蔵間、豊山などの顔ぶれ。彼らとの対戦をテレビで見るときは、貴ノ花を応援しなかった。だけどそういうときは、大概貴ノ花が、寄り切りかつり出しで勝っていた。貴ノ花は意外に腕や足腰の強い力士で、自分より大きい力士を持ち上げてしまうことも、しばしばあった。それと、細くてか弱いにも関わらず、貴ノ花は簡単に立会いに変化したり、引き技を使ったりしなかった。押し相撲の一本やりの富士桜、麒麟児といった力士との対戦では、いつでも真っ向から立ち向かって果敢に突っ張り返し、激しい応酬になった。だからときには吹っ飛ばされるんだけど、ときには強靭な足腰がものをいうことがあるんだよね。テレビで取り上げる名勝負の中にはあまり数えられていないみたいだけど、個人的には、貴ノ花 vs 富士桜はベスト・オブ・マッチだと思うなあ。けれど、そう思う割には、この対戦で貴乃花が富士桜に勝ったシーンの記憶が殆どない。トータルでは、おそらく貴ノ花が勝ち越していたと思うのだが。勝負の決着よりも、バシバシ突っ張り合う取り口のインパクトに、記憶が集中してしまっているのかもしれない。貴ノ花は、兄の二子山部屋に入門してからも、なかなか大きくなれなかった。兄の二子山親方は、このことを案じて、現役時代からの信念「力士は酒で強くなる」という言葉をかたくなに信じており(なんで?)、実際に貴ノ花にもそれを試そうとしたという。それで、未成年の時分から、ちゃんこの前に、どんぶり1杯、清酒をなみなみと注ぎ、食前酒として一気に飲むことを義務づけたそうだ。胃が刺激されて食が進むように、という理屈だったらしい。だがそんな無茶が身体にいい筈もなく、間もなく貴ノ花は胃炎を起こし、食も細くなってますますやせ細ってしまい、そのことは彼の力士生命全般において、内臓疾患の持病となって、先々延々と影響したという。彼が太れないのは煙草のせいだと聞いていたのだが、もっと根本的なところに原因があったようである。いまどき、たけし軍団の若手だってそんなことはやらない(笑)。不謹慎な云い方だけど、未成年者にそんなことをすれば寿命も縮むわけである。力士は「神の使い」というけど、彼ら自身は神ではなくて人間なのだ。現役を退いてしばらくは、自らが興した藤島部屋での弟子の活躍もめざましく、ついには息子たちが2人とも、角界の頂点である横綱にまで上り詰めるまでにいたった。だが、二子山部屋を引き継いで以降、夫人との離婚や、兄弟横綱のいさかい、引退後の兄の出奔など、内紛の絶えぬ日々が続き、伝統を重んじる日本相撲協会との板ばさみで、夜も眠れないような日々が続いたことだろう。二子山部屋は、「ガチンコ相撲」で有名だ。要するに、常に手を抜かない、全力を傾けて相撲をとるという意味。八百長などもってのほか。稽古場だろうと巡業だろうと本場所の土俵だろうと、力士は常に、ガチンコを貫くことを課せられているという。相撲用語であったガチンコという言葉を、各界に広めたのも二子山部屋。で、当然現役時代の貴ノ花もまた、ガチンコスタイルであった。前に書いた富士桜戦などは、まさにガチンコの典型である。現役引退後の人生もまた、舞台が土俵上ではないにせよ、常にガチンコだったことだろう。けれど、その後の人生における幾多のトラブルの荒波は、現役時代の相撲と同様、いやそれ以上に、彼の細い体躯にのしかかってきたことであろう。それに真正面からぶつかって支えるには、彼の身体はやはりあまりに小さく、か細すぎたのかもしれない。鬼籍に入った今こそが、この小さな角界の貴公子の、これまでの人生の中で、身も心も、最も安らいだときなのではなかろうか。やれやれ、気がつけばすっかり長くなってしまった。書き出すとキリがないのだが、とりあえず話はここまでにして、合掌します(涙)。
May 31, 2005
-
神々の祝福
ディープインパクトの強さはなんなのだ。私は、はっきり云ってこの馬についてはあんまり高く評価していなかった。そもそも、あまりレースも見ていなかったしね。気に入らなかった一番の理由が、「チビ」だったこと。皐月賞時点で440キログラムだった。ダービーではいくぶん体重を増やして出てきたようだけど。こんなに小さい馬がダービーで上位入選した例は、最近だと1992年2着のライスシャワー、1993年3着のナリタタイシンぐらい。ライバルのグラスワンダーに比べかなり華奢と思っていたスペシャルウィークでさえ、470キロはあった。あとは最近は軒並み500キロ前後のデカ馬が主流、でもあったからね。数年前の年度代表馬のシンボリクリスエスは最高で540キロぐらいあったからね。だから、チビ馬が強いなどありえない、と勝手に思い込んでいたし、クラシックもどうせダメだろう、云うほど強くないよ、などと決めつけていた。だが、いざふたを開けてみたら!皐月賞では、スタートでつまづいて出遅れたのに圧勝。今日のダービーでも、スタート直前まで終始チャカチャカして、尻っぱねまでして、屋根の武豊を落とすんじゃなかろうかと思わせておきながら、スタートこそ出遅れたのだけど、そんなことは関係ないといわんばかりに、しかも最終直線で大外を回って、しかも走破タイムは堂々のダービーレコードタイであった。なんとなく、これまでの日本のサラブレッドとも規格違いの馬のようである。個人的に、近年では一番強いと思っていたナリタブライアン、トウカイテイオー、ミホノブルボンのトップスリーを、まとめて交わしてこいつをトップと云わざるを得ないね。悔しいけど(別に悔しくないか・笑)。はじめのほうでも書いたように、私は本来、ディープインパクトを「あんまり応援しない派」を自負していたので(自負する必要はないんだが・笑)、このところ競馬の神々(?)からは見放されており、今回ばかりは神々に祝福されているディープを外すわけにいかなくなってしまった(??)。なので、低配当ながらもちまちまと馬券を買って、1番人気が物凄く久しぶりに的中して、配当はともかくとして、なんとなくいい気分ではある。午前中の草野球でも、負けはしたけど久しぶりに接戦の好ゲームになり、割合いい気分。これはきっと、ディープインパクトの馬券を買った人間への、神々の祝福に違いない(???)。だが、秋の菊花賞は、期待のサジターリオが上がってくるので、そうは簡単に三冠馬を出すわけにはいかないのだウッシッシ(大橋巨泉風)。「反主流派」としては、つけいる隙さえあれば立ちどころに主流を支持しなくなる性なんだもんね。ひねくれものと笑うがいい(フンフン)。ちなみに、ディープインパクトを管理している池江厩舎って、現役時代のオグリキャップがいた厩舎で厩務員やってて、引退レースで「池江コール」受けてたおっちゃんが独立してやってる厩舎だよね。やはり時代はめぐるというか、凄い馬を生み出す運命の星の下にいる人なんだろうねえ。
May 29, 2005
-
リバプールのサポーターだったらなあ・・・と思った話
不眠で仕方ないから、眠くなるまでテレビでも見ようと思って電源入れて見たら、なんだかすごい結果になっていたようで、ジョン・カビラが夜中というのに大声張り上げ、ジローラモ氏がうなだれ、明石家さんまとウッチーが馬鹿笑いをしていた。いつも思うのだが、カビラが司会のサッカーの番組というのは、音量調節が難しい(笑)。うるさいから音を絞ると試合の実況が聞き取れないし、音を上げてうっかりしてると、再びご近所迷惑と思うほどの声を、突然腹から出すし。けど、んなことはどうでもいい。サッカーで3点差というのは、はっきりいって絶望的な点差だと思っていた。実際、殆どの試合ではそうなんだろうね。しかも、前半を終えて3点リードしているのは、この決勝に進むまでに殆ど失点をしていないACミランだったわけだから。リバプールに同点に追いつかれた後半の、その間わずか6分間だったとのことだが、その時間帯、リバプールサイドは押せ押せで、そんなこと考える余裕もなかったかもしれないけど、ミランサイドから見たら、悪夢というか、雷に3連続で打たれたような、信じられないような時間帯だったに違いないね。以下、私が勝手に想像しただけの話。あんまり大声でいうとミランにも、勝ったリバプールにも失礼になっちゃうからね。さんまが「神が宿ったんだ」としきりに連呼していたけれど、僕は、ミランDF陣に珍しく、ほんのわずかな心の隙が生まれたのが、この6分間だったんじゃないのかな、という気がしている。もちろんリバプールの攻撃力決定力もすばらしかったと思うけど、ミランにこのわずかな隙が生じたこと自体が、奇跡なんじゃあるまいか(笑)。世界中で最もハイレベルといっても過言ではない大会で、決勝での前半だけでの3点という点差は、勝ってる側の心の隙を生むのには、あまりに十分すぎる条件だよ。この大会では大本命とずっといわれ続け、ライバルのインテルを下してから士気も高まってきて、残る決勝はもう一方の本命、スター軍団のチェルシーかと思いきや、戦力的には明らかに格下と見られていたリバプールが勝ち上がってきた。案の定、試合開始直後に先制して、前半終わっただけで大量リード。あとは鉄壁のカテナチオを普通にきっちり固めれば、そのまま優勝はおのずと勝手に転がり込んでくる。ワハハ俺たち優勝だ。優勝だったら優勝だぁ!!・・・と、選手と陣営の誰もが思っちゃったのが、奇跡を呼んじゃったような気が「しなくもない」んだよねえ(ここんここ強調ね。断言してないから)。そのあとは引き締まって、延長に入ってからも全く点を許してないわけでもあるし。あの6分間だけ切り取って、なくなって欲しい! とミランサイドは思っていることだろうな。もうあとの祭りだけど。祭りといえば、カカの脳裏には、早くも故郷ブラジルの、歓喜のサンバのリズムがなり響いていたんじゃないだろうか。クレスポは頭の中でタンゴを踊っておねえちゃんの足引っ掛けてたりとかね。よく知らないけど(笑)。もし本当にそうだったなら、お祭りを始めるのがちと早すぎたのかもね。校長先生がいうとおり、修学旅行は、無事おうちに帰るまでは、まだ終わりではないのだ(爆)。リバプールにしてみれば、使い古された表現をすれば、3点先に取られた段階で、後半以降はいい意味で開き直れたんでしょう。さらに追い上げに入ったときというのは、映画のインディ・ジョーンズかなんかのクライマックスで、絶望の淵に立ってるインディ博士達が、敵の物凄くわずかな隙をついて鋼鉄の牙城に潜入し、宝物のありかに忍び込んで奪い取るように、UEFAの優勝カップを奪い去ってしまったような感じだったね。ああいうときに、集中力が最大限出せるところが、さすがに強豪ひしめくヨーロッパのクラブNo.1に輝くことが許される実力なんでしょう。ミランの話ばかり書いたけど、心情的には今回はリバプール派(?)だった。というか、基本的にチェルシーが好きなので、チェルシーに勝ったリバプールをなんとなく応援してたので、いちおう嬉しい(弱っ)。日本では滅多にないような試合だったから、いつかはこういう大きな試合で、スタジアムでどっちかを応援してみたいものだ。まあ選手もサポーターも、向こう数日はなんにもしないで、ギネスの黒ビールでもあびるほど飲んであびる優になっちゃえ(?)。んで、今日は日本が試合だね。W杯予選まであとわずか。まあ、そんなわけで、もし今日圧勝しちゃったとしても、あんまり喜ばないほうがいいですな(爆)。かといって引き分けだったり負けちゃうというのも、それはそれで日本中が不安で一杯になることは間違いないし、「ジーコクビにしろ」説が過激なサポーターから早くも再び再燃するだろうから、そのへんうまく調整して、1点差、2点差ぐらいで勝って欲しいですな(笑)。
May 27, 2005
-
フロイトとユング
この前のなぞなぞ。あまりにアホらしい日記につきほったらかしにされると思いきや、アホにつきあって解答してくださったみもざ花さん、つりえさん、ありがとうございました。m(_ _)mはい、僕が20年前に考えた正解は「ウガンダ」でした。みもざ花さん大正解!!つーより、あまりにもあっけなかったですな。ちなみにウガンダの独裁者といえば、アミン大統領ですな。ウガンダの小学校で「ア~ミン将軍ありがとう~♪」と、掃除をしながら子どもたちが歌っている映像を見た記憶がございます。独裁者が考えることというのは、国や時代を問わず、同じなんですにゃ。だが、「マリも浮く」ということで「マリ共和国」という、北朝鮮の同点ゴールのような、予想だにしない解答を出してくださったつりえさん。それは私もノーマークでございました。m(_ _)mひねり運動はウエストラインの引き締め効果あり、ということでこちらも大正解!!お二人には約束どおり、○○○をプレゼントいたしたく、詳細は改めて。------------------------------------------------近頃、「フロイトとユングの生涯」みたいな英文を読みました。つっても、本買って読んだのではなく、今通ってる予備校で配られたものを読んだだけなんですが(←なあんだ)。英文だけに、訳してから読むといった二重の作業をして読んだだけに、年々衰えを見せてきている我が脳みそとはいえ、その内容はしっかりとこの、黄土色の脳細胞にとどめましたな。彼らの伝記みたいなものは、子どもの頃、近所のお兄さんのおさがりで、学研の「がくしゅう」というざっしの中に、フロイトの少年時代の話が載ってるのをチラッと見かけた記憶があるだけ。無論当時はぜんぜん興味なし。ユングは、河合隼雄しゃんを通して知ったばかりなので、殆ど知らなかった。けど、たとえ手もとにあったところで、ろくに読みゃしなかったでしょう。感想。面白い。今読んだからだと思うけど、今さらになって読めるチャンスが与えられたことに感謝したい。好き嫌いを聞かれれば、2人とも「好きじゃない」けど、かといって、単に「嫌い」とも断言できない。我が目指す道の偉大なる先達であるとはいえ、心理学者になる人なんて、変わり者なんだろうな、とあらかじめ思ってはいたけど、案の定、2人とも予想を大きく上回って変わった人だったのが嬉しかったです(なんで?)。変わり者というだけで、人物そのものを批判したり揶揄したりするつもりはない。特にユングは凄い。子どもの頃に、従兄弟と一緒に超常現象に遭遇して、それを大学時代の論文にまでしたためている。医学生なのに。つわものだ。よほど衝撃的な出来事だったのだろうけど、普通、そこまで引きずらないよ。記憶にとどめてはいたとしても。もっとも、そういうものが発端となって、心理学者になったんでしょうけど。のちにユングは世界中に旅をして、アフリカ、アジア、中南米の寓話、シャーマン、民間伝承、占いなどを研究する。さらにUFOとか超能力といったオカルトの世界もあわせて研究し、自分の「分析心理学」に取り入れていく。結局、自分の生業というか、人生全般にまで、そういう「不思議系」を持ち込んだわけです。この姿勢は、「夢を追い続けること」という意味で、現代の若者たちにも見習って欲しい!! などと、教育界の偉いおとっつぁんとか武田鉄矢あたりが簡単に云いそうなことではあるけど(笑)。ある意味、そのとおりだともいえるかもしれないけど・・・・・・。あまりオススメできるものともいえないような気もする(爆)。なんともいえないが。はまりこむと、思いっきりオタクの世界でもあるしね。テーマ的にもどーもね(笑)。オカルトにはまり込んで、それで食って行くと宣言する息子や娘を見て、どうよ。支持したいと思う(笑)?「この子はあやしい宗教に引きずり込まれたんじゃないか?」と思うんじゃないかな?たぶん若い頃のユングって、そういう感じの人だったんじゃないかと思ったりもするわけね。結果出世したわけだからいいけどさ(爆)。フロイトとユングは20世紀初頭に初めて出会い、しばし活動をともにするんだが。フロイトもなかなかどうして変わってるんだけど、彼の場合はその理論自体から、当時変わり者呼ばわりされていたというわけなんだけどね。彼はなんでもかんでもセックスとか性欲に関連づけてしまうから、心理学者の間でも忌み嫌われていたらしい。しかもフロイトはユダヤ人だった。ナチスドイツが台頭してる時代、彼が表舞台に出ることはできなかった。だから、活動を通じてはじめて知り合った、それまで縁もゆかりもなかったユングを、自分が作った「国際精神分析学会」の初代会長に任命したというわけなんだね。だがやがて、フロイトとユングは対立し、決別することになった。「セックス一筋80年」のフロイトに対し、ユングは「オカルト一筋80年」の人。それぞれが、各々の独自の論拠をもとに活動を展開していく上で、どうしてもかみ合わなかった。“SM”と“SF”で「一文字違い」ということで妥協する、といった和風な考えは、彼らにはできなかったわけアルネ(←普通はできねーよ)。吉野家は「牛丼一筋80年」から、頑固一徹の経営方針を一時的に変えたけど、フロイトとユングは互いに妥協できなかった。フロイトと決別したユングは、やがて苦しみながらも、独自の思想と理論にもとづく「分析心理学」という新たな心理学の分野を開拓し、これはその後今日にいたるまで、アメリカをはじめ世界中に広まっていくのである。バンド活動なんかを見てても、個性の強いメンバーを揃えたバンドほど、互いの主張したい方針の食い違いが原因でさっさと解散するケースが多いというけど、フロイトとユングの対立は、すさまじい個性同士のぶつかり合いだったということが云えるかもしれない。静かな戦いではあるけどね。フロイトとユングに共通していた点として、二人とも語学に堪能で、各国の言葉を学ぶとともに、いろんな言語の、物凄く幅広い分野の本や書物を読んで学んでいたということ。それだけに、精神分析をはじめ、あらゆることを考える上で、幅広い視点から答えを導き出そうとしたんだろうな、などと思う。これはリスペクトしてよいことかな、と自分の中では単純に思ったりしています。------------------------------------------------だけど、フロイトとユングは、元マブダチだった時期もあったわけです。だから、一度対立しちゃうと「坊主憎けりゃ袈裟をも憎い」みたいになっちゃったんじゃないかとも思えたりするわけね。見ててなんとなくね。ある意味似たもの同士というか。決別する前のフロイトとユングは、頻繁に文通していたという。フロイトがオーストリア、ユングがスイスと、離れた土地にそれぞれ住んでいたということもありますが、二人はかなり親しくて、互いの手紙も大切に保管していたらしい。文字通り「メール交換」なわけですな。国際電話というのもなかったような時代だから、想像に難くないところではありますが。二人が友好関係が佳境にある頃、フロイトはユングに一通の手紙を送っています。フロイトが、自分をアレキサンダー大王の父フィリッポス5世に見立てて、ユングを自分の後継者として激励したというわけ。「親愛なる息子アレキサンダーよ、苦しうない。汝に、我がいまだなしえぬ世界の征服を任じよう。精神医学の世界すべて、そして、今日の文明社会の賛同を掌中に収むるべし。けだし我が目には、この文明社会はいまだ未開の地なれど。汝の情熱あらんことを!」みたいな感じ。これを読んだあと、予備校の人たち(若い女性が大半)は、「自分の息子でもなんでもない他人に、こんなワケわからん手紙を送るところが信じられない」「へんじんだ~」などと一様に云っていて、私も「そうだねえ」などと云っておりましたけど、内心では「クププププ」と笑っておった。こういうの、楽しいなあ(^^)。いい年こいて、ちょっとオタクっぽすぎるような気もするけどね。フロイトとユングが、少年のように時代劇ごっこやってるみたいで。男の子というのは、こういう会話が大好きなのです。女の子にはわかるまい(笑)。男の子の母親になればわかるかもねん。互いの人間関係は最終的にはうまくいかなかったけど、結果的にユングは、少々のれんの名前を変えたとはいえ、フロイトの思想を土台に、それを継承して立派に世界中に広めたと云っても過言ではないと思うから、当初フロイトがユングに抱いた思いは、はからずも今日成就されているんだと、私は思うけどね。
May 26, 2005
-
わきゃるきゃ~!
いやー、近頃はなぞなぞが大流行だしゅにゃー。ためしにこの前「サルヂエ」なんぞといふ番組をのぞいてみたが、なかなか出題の問題も凝っていて、こんなものに頭をひねってみるのも面白い。だが、ひねりすぎのなぞなぞもちとこまりまする。某雑誌に出てたなぞなぞ。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *問.したきりすずめのおばあさんの生まれ故郷の島はどこでしょう?→正解は次号○月○日発売号にて* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *なんてのがあった。「したきりすずめのおばあさん」って、島そだちだったの?などと、本題とは別の疑問に首をかしげている暇はないのじゃ。で、しよーがないから頭をひねってひねって、日曜日、春の部屋の中でひねもすのたりのたりと考えておったら、たちまち日が傾いてきたので、あきらめて、正解が載るといふその雑誌の次号を心待ちにしておった。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *正解.沖永良部島(おっきいのえらぶしま)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *だってよ(ビヨヨヨ~ン)。す、すごすぎる・・・。問題を解く以前に、「したきりすずめのおばあさん」が大きいつづらを選んだことさえ覚えていないのだった(笑)。「そんなのチョロイよお!」なんていう人の脳みその柔軟性がはかり知れん。おとぎ話も記憶も頭に残ってて、日本の地理を習ったばかり、という子どものほうが強いかもね。ところが、このなぞなぞは正解すると賞品がもらえたり、正解数をカウントしてもらえてランキングして、トータル上位の人にはなんかもらえたりするといふのじゃ。なんとなく、スポーツ新聞のクロスワードパズルとか間違い探しより面白そう!!と、食いつこうかと思ったのだが・・・・・・とてもとてもそんななぞなぞにすべてチャレンジできる頭の柔軟性とか精神力がないので、見かけたらやってみる、ぐらいにしておくのだ。こんななぞなぞばっかりやって、軽くポンポン答えられるようになってきたら、たぶん頭の回転とか機転が効くようになるんじゃろねー。けど今はとてもじゃないけどできそうもないね。くやしーので、私が20年以上も前に作ったこのなぞなぞを解いてみろ!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *問.アフリカ大陸が沈没しても、ひとつだけ沈まない国はどこでしょう?→正解は次の日記(たぶん今週中)にて* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *いやー、20年間でこの国は滅びたり名前が変わっちゃったりしなかったので答えを変えなくてすんだ。当時、ミャンマーは「ビルマ」だったし、ロシアは「ソ連」だったしね。ちなみに、このなぞなぞを考え出すちょっと前に、この国ではクーデターがあったような記憶があるね。なんか、今話題の将軍様みたいな独裁者が大統領で、この大統領に感謝する歌を、小学校などで歌わせている映像を見たのをおぼろげに覚えてるよ。・・・って、これヒントでもなんでもない。ただのノスタルジックなコメント(グフフ)。正解者から抽選で、○○○をプレゼント!!
May 24, 2005
-
セルフ・ハンディキャッピング
某大学院の「入学試験問題集」なるものを入手。早速目を通してみたものの、現時点では手も足も出ない感じ。英文を読解するのにやや不明の単語が多すぎるのと、日本語にせよ専門用語の理解が不十分で、見た瞬間、今解くのはやめとこう、としり込みしてしまいました。このあと、大学院の説明会や模試といった催しが順次あるので、入試に対してあまりのんびり構えてもおられぬ時期になってまいりました。今、今秋または来春に受ける大学院での研究計画のテーマを検討しているんですが、最初は何を研究したらよいのかもわからず、予備校の先生に相談したところ、いろんな心理学系の論文集を収めている図書館を紹介され、そこでひとしきりいろんな論文を斜め読みしてきました。興味深いと思った論文テーマの中から、セルフ・ハンディキャッピングというのを、研究テーマとして取り組んでみようかな、と今は考えています。セルフ・ハンディキャッピングって、今回初めて知った言葉だったんですが、よく読んでいると、自分の行動・思考パターンにもよく当てはまりそうな内容で、たいへん興味深い。どういうことかというと、たとえば、試験前などにはかなりのプレッシャーが精神的にかかったりするわけですが、えてして試験勉強をしない人というのがいますね。それで、彼が試験前に何をしていたかといえば、連夜遊び歩いていたと。その遊び歩いていた本人の中の根拠となる思考パターンというのがカギなんですね。理由は主に2通りあって、ひとつは、「どうせ今から準備をしても試験当日はできっこないんだから、やらないでおいて、結果が悪くても『準備してなかったからできなかったのは当たり前』と言い訳できちゃうもんね」という思考パターンで、もうひとつは、「準備しないで試験に臨んでいい点を取れれば、『俺は才能があるから努力しなくても高得点を取れる』と周囲に自慢できる」という思考パターン、ということのようなんですね。このへんまでの研究というのはすでにいろんな人が進めているようで、これにたとえば「自尊心」とか、「自己防衛」などといった心理傾向との関連性を検証しようとする研究が行われているようなんだけど、さらにもうひとつ、研究するに値するポイントを加えて自分の研究テーマにしようと考えているのだが、これがなかなか思い浮かばず、ここ数週間頭を悩ませているところです。セルフ・ハンディキャッピングって、前にも書きましたけど、よく内容を読んでいると、自分でもこれまで比較的よくやってきたことのような気がします。試験前、プレゼン前日、試合前、などという重要なときに、まああくせく頑張って徹夜したり直前まで自分を追い込むこともあったのだけれど、そうじゃなくて遊んじゃったり酒飲んじゃったり、熟睡しちゃったりして、当日後悔と開き直りの心境ないまぜに本番に臨むといったことが、過去何度あったことか。熟睡についてだけど、「眠らないでやらなきゃ」と思ったときに限って、よく眠れたりするんですね(笑)。これは困った性癖だなあと。だから、そういうときの自分の意識や心理状態みたいなものを思い起こして、テーマを考えるヒントを導き出そうとしているんだけど、なかなかうまい具合に考えがまとまりません。このまま時が流れてしまい、試験当日が近づいたりしちゃうと、そのまままさにセルフ・ハンディキャッピングしてしまうのではないかと内心オロオロしてしまう今日この頃です。つーか、このあと予備校主催の模擬試験があるのだった。だからこんなことを今うだうだ書いてる場合じゃないのだ。今宵はこのあともう少し頭をひねってみたいと思っております。では。
May 20, 2005
-
ゴジラーノの呪い(前編)
「魑魅魍魎の巻」「きょんちゅ」の滝ッパナオーナーは、頭を抱えていた。我が運営する「きょんちゅ」は現在目下のところ最下位。このままシーズンを終えてしまったら、かのナカシマさんがはじめて監督をつとめた昭和50年以来の不名誉なシーズンということになってしまう。自分がオーナーに就任したとたんそれでは、栄光の「きょんちゅ」の名前に傷をつけてしまうどころか、不名誉はすべて自分の肩にかぶさってきてしまうのである。「それにしても」と滝ッパナ氏はひとりごちた。「アツイがいなくなったとたん、ウチは優勝できなくなってしまったな。そのおかげで売り上げも落ちているし。チヨハラひとりの人気では、もう実際支えきれないよ」ひとりで悩んでいても仕方がないと考えたオーナーは、かねてから懇意にしている、占いアドバイザーのホソーキー数子氏に相談してみることにした。ホソーキー氏は、近頃ではタレント活動に忙しいが、本来はこうした会社経営者への助言というのが得意(というか好き)な人物でもあったのだ。彼女の、ズバリと確信したような断定口調は、会社経営という、明確な方針や判断を要求される世界では、貴重なものであるらしい。前会長のナベツーネ氏が認知症にかかって一線を退いてしまったあとで、強硬に物事の指図をしてくれる人物が、社内はおろか、フロ野球界にもいなくなってしまった今、滝ッパナオーナーにとって、ホソーキー氏は大変に心強い支えでもあるのだった。彼女は、平日の昼下がりだというのに、その巨体に色鮮やかな紫色のドレスをまとっていた。滝ッパナ氏は、「ホソーキー・オフィス」の扉を開けた瞬間、思わず一歩あとずさりをした。「あーらタッキー、珍しいわね」にこやかに云われて、滝ッパナ氏の背筋に粟肌が立った。「ご、ごぶさたしてます、先生」「およしなさいそんな他人行儀な。『かずちゃん』でいいわよ」他人じゃなきゃなんだというのだ!? 滝ッパナ氏は、思わずそう口走りそうになったが、ぐっとこらえた。「ぼさっと突っ立ってないで、すわんなさいよ。昨日虫干ししたから気持ちいいよう、ウチのソファ」どうも、仕事の相談でのこういうファミリーな会話は苦手なのだが、これが滝ッパナ氏も何度か相談に訪れるうちに知った「ホソーキー流」なのだ。滝ッパナ氏は、「じゃあ失礼します、かず・・・ちゃん」と蚊の鳴くような声で云いつつ、なぜか血糊のようなものの痕跡が、大きくベットリとついた巨大な獣の毛皮が背もたれにかかった来客用のソファに、こわごわ腰かけた。ホソーキーが自分で獣を狩って、毛皮を剥ぎ取りでもしたのか、真相はよくわからないのであるが、その毛皮は妙に脂っぽく、ソファからは動物園のライオンの檻のような臭いが、モワッと鼻をついた。これは余談だが、以前ホソーキーは、ムツゴロウと親交があり、動物王国にもよく赴いていたのだが、その頃ムツゴロウ飼っていた動物が相次いで姿を消してしまったことから、ホソーキーに動物泥棒の疑いがかかり、以後親交が途絶えたというウワサがあった。今まで深く考えたこともなかったが、そのウワサは、もしかすると本当だったのではあるまいか?滝ッパナ氏は、鼻の奥と尻の下が、むずがゆくなってくるような錯覚を感じた。「それで、今日はあんたどうしたの? なんか相談があるんでしょ?」「はい、それなんですけど」滝ッパナ氏は、目下自分が抱いている心配事と悩みを、ホソーキー氏に伝わるように、できる限り理路整然と説明した。ホソーキー氏は、滝ッパナ氏の話を聞き終えると、やおら口を開いた。「ふーん、あんたの悩みってのは、つまりこういうことね。今年『きょんちゅ』の負けが込んで、優勝をのがしてしまうと、あんたが不名誉の汚名を着せられて困るから、なにがなんでも手段を選ばず優勝して、自分が矢面に立たなくてもいい方法を教えて欲しい、ってこと?」「いえ先生、そんな身もフタもないことは何も僕はひとことも・・・」「かずちゃんって呼べって云ったでしょ!?」ホソーキー氏は強い口調で滝ッパナ氏の言葉を制した。「だってそういうことじゃないの、云ってることはおんなじでしょ!? 今私も真面目に考えているんだから、あんたも真面目になってもらわなきゃだめ」「はぁ・・・」滝ッパナ氏はたじたじとなって、うつむいた。「心配しなくてもいいのよ。トクちゃんから『きょんちゅ』が苦しんでいるってことは聞いてるから、そろそろ何か相談あると思ってたんだから」トクちゃんというのは、ホソーキー氏と番組の司会をやっているアナウンサーで、「きょんちゅ」系列のTV局の局アナだったこともあってか、退社後も熱烈に「きょんちゅ」を応援し続けてくれている、しつこいウソ泣きがややうざったいが、滝ッパナ氏にとっては、大切なお得意さんみたいな人だ。「すいません、恩に着ます」「そういえば、たしか3週間ぐらい前だったかな、ソンちゃんが遊びにきて、フロ野球の存続のことで相談してきたんだから」「えっ、ソンさんって、『そふとばんく』のソンさんですか!?」ソン氏と滝ッパナ氏は、ついこの前、フロ野球の国際化について対談をしたばかりだった。「ほかに誰がいるって云うのよ。だからあたしは、ちゃんと考えてアイディアを出してやったわよ」話し合いでは、ソン氏の意見は滝ッパナ氏の考えと真っ向から対立し、結局話が前に進まぬまま、予定時間を大幅にオーバーして終わったのだった。あのときのオレの対立意見のソースは、この先生だったのか・・・。食えねえ婆ァだぜ、と滝ッパナ氏は小さく舌打ちをした。「あんた今私に敵意を抱いたでしょ。ウソ云ったって全部お見通しだからね」心の中まで読まれている。この人にはかなわない、と滝ッパナ氏は観念し、この場をすべて相手に委ねることにした。「じゃあタッキー、ずはり云うわよ! 私の云うことをよーく聞きなさい」ホソーキーは、例のごとく大上段から切り下ろすようなしゃべり方に変わった。「はじめに、どうして今みたいな状態になってしまったか、理由を云うわね」「はい、かずちゃん」「先生でいいの! 今度ふざけた呼び方をしたら、あんた地獄へ送るわよ!」おお怖い。だけど、はじめにあんたが云ったことじゃねえかよ・・・。「じゃあ話すから聞きなさい」「日本のフロ野球は12球団あるから、ちょうど星にあてはめて、それぞれの運気を占うことができるのよ。それで『きょんちゅ』は木星にあたるんだけど、木星は1990年代半ばをピークにして、それから下り坂に来てしまっているのね。それで2001年から2010年にかけては大殺界に当たるんだよ」本当か? 滝ッパナ氏は首をかしげた。なぜ木星に当たるのかを聞きたいと思ったのだが、質問できる雰囲気ではなかったので黙っていた。ホソーキー氏は話を続けた。「だからその時期に、独断で何か周りが不利益になるようなことをすると、『きょんちゅ』の存続をおびやかすようなしっぺ返しが必ず起こるって、私は知ってたのよ。ほらね、案の定去年あんなことがあったでしょ」なんだか、つじつまが合いすぎている。そんなこと、知ってるならもっと早く教えろよ、と滝ッパナ氏は腹の底でつぶやいた。(前編・完。どーでもいい話なので、後半へつづくかどうかは気分次第)
May 16, 2005
-
あっぱれさんま総理大臣
テレビで見る小泉総理のコメントは、お笑いタレントみたくなってきているね。昔からそうだったのかもしれないが、ウケればそれでいいみたいなね。たとえば国会などでもそう。ウケ以外、何も望んでいないように見えたりとか。本当はそうじゃないことを祈りたいのだが。また逆に、「踊るさんま御殿」などを見ていると、なんとなく、さんまは小泉総理に似てるなあ、などとも思ってしまう。根本的に人の話をよく聞かないで、自分の都合のいい展開にもっていくところとか。それがまたツッコミの的になってしまうんだけど、内心そういう、ツッコまれる展開を「おいしい」などと云って喜んでしまうところとか。えーと、さんまが司会をやってる番組で「あっぱれさんま大教授」というのがありますね。はじめは「あっぱれさんま大先生」というタイトルだったのだが、最近は違う感じの、大人の役者さんなどを呼んでのトーク番組になっている。けれどこれは、似た番組がゴマンとあるだけに、すぐに頭打ちのような気もするね。そこで、提案というかアイディア。これに続く番組として、さんまを総理大臣に見立てて、政界の人たちと個別対談をしてもらおうというもの。タレント議員を革切りにして、現役の議員や話題の政治家、政界OB、政治評論家、政治家になりたいと思っているタレント、などなどを招き、さんま独特のナメた口調でまぜっかえしてもらう。第1回目はやはり、小泉総理本人に出てもらおう。以下、ハマコー氏、舛添議員、土井氏などなど、30分程度出てくれる人は沢山いるだろう。さんまが忙しい中、どの程度勉強して番組に臨んでくるかという課題はあるけど、もし続けるのがむずかしくなったとしても、最低1年ぐらいは回せるんじゃないか。人気番組になってくれば、出たいと思う政治家は増えると思うよ。裾野が地方政治にまで広がれば、結構いいかもしれない。「いじられキャラ」の政治家は、たくさんいるからねえ。おいしいところを小泉総理にさらわれて、悔しがってそうな奴もいることだろうし。「TVタックル」や「サンデープロジェクト」じゃ云えなかったことを、「あっぱれさんま総理大臣」で吐き出して笑いをとって、さんま総理に「毒消し」をしてもらえれば、多分政治家先生たちも、心の健康を取り戻せたり、票取りに結びついたり、と政治家側のメリットはあると思うし、お茶の間サイドでも、政治家のトーク番組は内容がカタくて抵抗がある人なんかにも、国政への関心づくりのきっかけになるだろう(?)。あと、この番組を、首相や国政の中心にいる人たちにも見てもらい、「さんまさんって、俺に似てるなあ」ということに気づいて欲しいという狙いもある(笑)。この程度のモンというふうに、お茶の間では見られてるのよ、アンタたちの器は。
May 13, 2005
-
天使の笑顔
とある昼下がり。街を歩いているうちに、養護学校の前を通り過ぎました。その校門を通り過ぎてしばらく行くと、後ろのほうで、笑い声が聞こえました。振り返ると、中学生ぐらいの背格好の女の子と目が合いました。次の瞬間、養護教諭とおぼしき人が、彼女の名前を呼んで振り向かせました。何やら一所懸命女の子に話している。「気をつけて帰るのよ」というようなことを云っているようです。変なおじさんには、絶対について行っちゃだめよ、か。僕はそのまま歩き去ろうとしました。駆け足の音が聞こえてきたので、ふと右手を見ると、その女の子が僕に並びかけてきました。「うああー!」と女の子は、僕を見て云いました。こんにちは、と云ってるようだ。僕は「こんにちは」と返事をして、口元をにこっとさせました。やれやれ、さっき先生に云われたばっかりじゃないか。「学校は、もう終わったのかい?」と、僕は当たり前の、どうでもいいようなことを彼女に聞きました。彼女は軽くうなづくと、「うきゃきゃ」と楽しそうに笑いました。心の底から湧き出るような笑いに、僕には見えました。女の子が「あい」と云って、手をさしのべました。手をつなごうとしているようだ。養護学校の先生には悪いが、まあいいか。僕は別に悪いおじさんじゃないし、気にすることはない。僕は女の子の手をそっと握りました。あたたかい手でした。目の前の交差点をわたるまで、そのまま手をつないで歩きました。なんだか僕も、心の底からうれしい気分になりました。こんな、親でも学校の先生でもない、ましてや友達でもない、見も知らないあやしげな男に、ただでさえ、社会への不信を胸の中にいっぱい抱えた子が、無条件に心を開いてくれたことが、無性に「有難かった」のです。こんな自分でも、生きている値打ちが、もしかしたらあるのかもしれないな、と思いました。ちょっとだけ、おセンチになった瞬間。平日の真昼間、近所の奥さんたちに見られて、ゆうかい犯か何かと間違われたら面倒だなあ、と一瞬だけ思ったけど、アホらしいので、すぐにそんな考えは頭の中で打ち消しました。本人がいいと云っているのだから、これでいいのだ。「君のおうちはどっち?」と、交差点をわたり終えてから、僕はたずねました。女の子は、道なりにまっすぐ前方を指さしました。僕の行き先とは別の方向。心配だったので、家まで送ってあげようかなと一瞬思ったのですが、この子にも、日々家と学校を往復するという、立派な日常がある。こっちはただの通りすがり。通りすがりの僕が、大切な日常を壊す必要もないな、と思い直しました。「じゃあ、おにいちゃんはこっちだから、ここでお別れだね」バイバイ、と僕は手を振りました。女の子は、天使のような笑顔で手を振り返すと、きびすを返し、そのまま家路を「ドドドドッ」とものすごい勢いで、走っていきました。ちょっとだけ幸せな気持ちになれた数分間。距離にしてわずか100メートル余り。
May 12, 2005
-
「終戦」という言葉に刻まれる感覚
小泉総理が、ロシアのナチスドイツに対する勝利から60周年を記念する記念日(戦勝記念日というのか?)にあたり、ロシアを訪問した、といったようなニュースが流れていた。一方、ドイツではナチスドイツの降伏記念日というのがあったらしい。それぞれの国民は、どんな思いでこの日を迎えているのか。詳しいことはわからないけど。どうでもいいことなのかもしれないが、日本では「終戦記念日」というね。「敗戦記念日」とはいわない。否定の意味は全然ないけど、うやむやに茶を濁すことを好む国民性なのかな。国を挙げて反戦を前面に掲げ、過去の軍国主義を徹底的に否定することができるのなら、「敗戦記念日」という呼び方が適切だろう。これを「どうでもいいこと」から「どうでもよくないこと」にするのは、思いのほか反響が大きく、危険なことでもあるような気がする。だから、とりあえずは「どうでもいいこと」にしておこうと思う。今まであまり考えたこともなかったのだが、日本人である我々は、とりわけ戦争を知らない世代の我々は、当然のことながら戦争に勝ったことがない。戦争したことがないのだから当たり前だ。ごくまれに、職業軍人として海外の紛争に兵士として参加し、その戦争に勝ったという人もいるかもしれないけれど、その人にしても、母国が勝ったわけではないから。「国の勝敗」という次元とは別の感覚を抱いているんじゃないかと想像する。また、実際の戦争を経験した世代で今も存命の方に、戦争に勝った経験を持つ人はいないのではないだろうか。日本軍として外国との戦争に勝ったのは、遠く日露戦争にまで遡らなければならないわけだからね。何が云いたいかというと、「戦勝国」の感覚がわからないのである。これは決して「わかりたい」と云っているわけではない。わかるためには戦争をしなければならないし、それは最も嫌なことだから。戦争は悲惨だ、残酷だ、という言葉は、これまで耳にタコができるほど、親たちをはじめとした先達から、教育者から、またはマスコミを通じて、聞かされてきたことである。そしてそのとおりだとは思う。けれど、その「悲惨だ、残酷だ」という言葉の中に込められた、戦争そのものに対する感覚というのは、戦争に勝った国と負けた国の国民の間には、乖離があるのではあるまいか。根本的には、戦争を通じて家族を失ったり犠牲を出したりしたときの悲しみ苦しみは、本来は戦争の勝ち負け関係なく同じだと、みんないう。でも本当にそうだろうか。そんなに単純に、純粋に等しい感情など持ち得ないように思うのだが。戦争に負けた国というのは、勝った国に対して服従し、本来国際的にも屈辱的な立場におかれ、勝った国の人々が、ずかずか土足で入り込んできて好き勝手なことをし、イデオロギーにいたるまで勝った国に左右されても、国民は我慢させられなくてはならない。そういう、屈辱的な経験は子孫の代にいたるまで反映される。どんなにその後国交が正常化して、戦勝国から恩恵を受けようと、消えない。日本人がアメリカ人に対して抱く感情の根底には、そういうものが今でもあるのかな? と疑問に思う。こればかりは、自分は抱いていないから、抱く人に聞いてみないとよくわからない。逆にアメリカ人が日本人に対して抱く感情に、「この敗戦国のイエローモンキーが」というのはあるのかな? これもわからないね。そしてはからずも今、日本は中国との国交において、同様のことで悩まされている。「悲惨だ、残酷だ」という国民の感情を背負っているのにも関わらず、国際情勢がややこしくなると、国策としてすぐに武力行使で片づけようと考えるアメリカ政府。日本人はそれを見て、短絡的すぎるとか、その国のおごりであると思う。けれど、アメリカ国民は、反対派を含みつつもトータルで戦争を支持してしまう。これは、戦勝国と敗戦国の感覚の違いのような気がするけど、どうなのだろうか。想像しているばかりでは何もわからないのだ。戦争をしたいと考える国の感覚を、もっと理解しないことには、いくら反戦を叫んでも、いざ戦争だという流れになったら食い止められないだろうな、という気がなんとなくしてしまうのだ。この議論は、ともすれば互いへの否定からスタートしてしまい、我先に自分の主張だけを矢継ぎ早に述べて、相手の主張に耳をふさぐ傾向にあるから、平行線の先を見ることができないように思う。互いの主張をもっと深く理解し、互いが満足いくまで受け止めたことなど、戦争についての議論をする人たちの大半は、きちんとやったことがないだろう。「やった」という人へ。自分と間逆の反対意見の者の意見を、相手が満足いくように受け止めただろうか。「そんなことは必要ない」と思っているのではないのか。私は、このことを意識して話し合うことが必要だと考える。もう一度、「きちんと」話し合いをやってみて欲しいと思うのだ。ちなみに、「朝まで討論」という番組は、不毛だと思う。というか、結論が出ないオチになるのが目に見えるから、見ていて安心感がある(笑)。だから見ない(爆)。たぶん取り上げるテーマについては、いつもいつも、テレビ局としても視聴者としても、結論を出されては困るような話だろうと思うのだ。桝添も三宅も森永も二宮も、難しい言葉を並べているのは、視聴者をけむに巻くためであって、下手に視聴者に介入されることを恐れているようにも見えなくもない。「文化人も政治家も真面目に話し合っている」ということをアピールしたいだけなのじゃないだろうかね。
May 9, 2005
-
バイバイ。
NHKの朝ドラ「ファイト」。あまり見るつもりもなかったのだが、まあ生活リズムを規則正しくする意味でテレビをつけているうちに、内容もしっかり注目しちゃっている。主人公のお父さんが経営するバネ工場は、取引先である先輩の勤める商社に楯突いたおかげで、この商社から報復を受け、受注が滞って経営できなくなってしまった。そのせいで、家を売り払ってその金で従業員に退職金を払い、無期限休職(事実上解雇)という形をとり、家族もバラバラに暮らすことになる。私の勤めた会社も、社長が同じように失敗しており、社長の人格的にはこの物語とは違うイメージがあるけれど、結果やってることは同じだと思うので、かなり自分たちとリアルに重ね合わせて見てしまった。プライドに拘泥して、「なんとかなる、絶対なんとかするから」と周囲を丸め込み、最後はにっちもさっちも行かなくなって、従業員と家族を路頭に迷わせる、というときの状況は、云うほどドラマチックじゃないし、「金の切れ目は縁の切れ目」という言葉がそのまま当てはまるような場面に、何度も遭遇したからねえ。またこのバネ工場の一人娘であるヒロインは、所属する高校のソフトボール部を、脚のケガによってやめざるを得なくなったり、クラスメイトと仲良くなれずに人間関係で苦しんだりしてしまう。・・・とまあ、ここのところの物語は、非常に逆境に直面しているのである。「逆境ナイン」の不屈闘志よりも、現実的に逆境なのである(なんのこっちゃ)。辛い物語なのであるが、その舞台にはいつも明るい雰囲気が漂っている。朝のドラマだから、明るい演出にしようとしているのもあるだろう。だけど、「辛いときにも常に笑顔を絶やさない」とか、そういう単純な、今までのNHKドラマのような教訓じみた理由ではない。そういう、リアルさを欠いた聖人君子のような人格の主人公というのは、見ているほうも肩が凝るし、共感できないことが多いのよね。適度に、お母さんと娘は明朗で、お父さんは誠実で真面目、幼い息子は無邪気である、という設定はあるけど、基本的にここの家の夫婦は、若いということもあって未熟者である。だから判断を誤って工場を潰すし、夫婦喧嘩はするし、実家の親に反抗もする。妻は就職経験がないままいきなり働きに出て育児と仕事の両立に苦労し、夫も一会社の社長から一介のアルバイト生活に転落して苦労し、やがてその苦労を見て生活している子どもたちにも影響を与える(だろう)。それらのもろもろの経過を経て、親も子もたくましく育っていく姿とか、やがて再び訪れる、一家の再会と会社復興の喜びを、感動的に見せようというドラマなんでしょうな。よくしらないけど(笑)。で、この一家は、別れのあいさつがいつも「バイバイ」なのである。夫婦の別居(旦那は娘と工場に住み、奥さんは、近郊の温泉で仲居をしながら弟を育てるということになった)にあたって、駅へ奥さんたちを見送りに行くシーンでも、互いに贈る別れの挨拶の言葉は「バイバイ」なのであった。若者や子どもじみた軽いノリの挨拶が、これが決して「今生の別れ」などでなく、近い将来、再び一緒に暮らせることを予感させ、またそうであると信じようとして、自分自身に暗示をかけているかのように、そゆことべんきょうちうの私には見えてしまう。ちなみに、アメリカのネイティブの会話でも、大人同士の仕事のあととかデートのあとに「バイバイ」って云って別れてるみたいだから、本来あながち特別なことでもないはずなんだけどね。ただ、NHKの朝ドラといえば、おっちゃんおばはんドラマが多いから、「バイバイ」を日常的に使う人たちは、あんまり登場しなかったので、「この世界」では新鮮なのである。物語の中で、ヒロインはいろんな理由が絡み合って、クラスメイトである親友と喧嘩中なんだけど、それにもかかわらず、この喧嘩中の2人は、気まずい別れ際にも、仏頂面をしながら「バイバイ」と云って手を振り合うのだ。基本的に、親しい仲でなければこんな言葉は口にしない。この挨拶の裏には、「今は喧嘩してるけど、あんたと私は友達だからね。本当はもう一度仲良くなりたいと私はいつでも思ってるんだからね」というメッセージが隠れていることを、2人は知っているのだ。と、思~う~よ。それが、辛い状況での、彼らの数少ない心の支えだと思うのである。話がなんだかよくわからなくなってきたので、これでおしまい。バイバイ。-----------------------------------<こんな話のあとになんで乗せるか・NHKマイルカップ・駄目予想>◎ 4・アイルラヴァゲイン○14・ビッグプラネット▲ 2・ペールギュント注11・マイネルハーティー☆ 8・バブルエスティーム△ 3・セイウンニムカウ 17・イヤダイヤダ 18・インプレッションとはいえ、軸未定。あまり書けたもんでもないが、予想の根拠はあるぞ。しようもない根拠だけど。------------------------------------どうも、相変わらずトラックバックというものの存在の意味がよくわからん。もう1年前近く前の日記に書いた言葉を拾い上げて自分のホームページにトラバさせて、それに対して、こっちの意図と全然関係ない考察を加えている。「ヘンな職業」の話だったかな。そんな前にふざけて書いたことは忘れた(笑)。「オレの云ってることとちと違うんだよな」みたいなことをそのHPでは書いてたが、そりゃ違うだろうなあ、同じことを書きたいとそもそも思ってないから。意図が謎だし、挨拶なしでそういうことする気持ちがわからないので、「トラバありがとう」みたいな挨拶には行かないよ。行くと思ったかあクルりんぱっ。こういう瑣末なことでイライラするし、解決したりスキっと解決する術も知らないので、インターネットやめちゃおうかな、などと思ったりしちゃうね。まあすぐ気が変わるとは思うけどね(注 : 本当はインターネットやめるより、競馬をやめたほうがいいという説が有力である・爆)。ということで、今日のところはバイバイ。
May 7, 2005
-
GW ひねもすのたり 松太郎
ようやく身体がふつうに動くようになってきたので、ジョギングを再開した。それにしても日中の外は暑い暑い。ちんたらちんたら走っているうち県境を越え、やがて武蔵野線の線路にぶつかったので、電車に乗ったり降りて走ったりを繰り返していたら、某公園で高校野球の埼玉県大会の決勝をやるというので、フラリと球場に潜入した。とくに高校野球を見たかったわけじゃないんだけど、なんでもいいから野球のゲームを見たかったのね。プロの試合ほど本格的でなくてもいいけど、草野球よりもしまったゲームとして、昨日の僕にはちょうどよかった。入場料も500円と安かったし。試合は、浦和学院と、栄東高校の試合だった。栄東高校というのは、初めて聞く名前の学校だったですね。ノックを見た時点で、浦和学院有利かな、という感じはしましたね。栄東の選手が、ポロリポロリが多すぎる。決勝で緊張していたのか。試合でもそれが大事な場面で出てしまった。もし、ちょくちょくポロリしても、連続しなければ最後は勝てることもあるのだが。ヒットは互角に出て、チャンスの数もそれなりに同じくらいあったのだが、要所で浦和学院はきっちり守り、栄東は、ピンチを背負ったところで、外野手が目測を誤ってのフライ後逸を繰り返し、点差がどんどん開いていった。なんとなく、自分たちの草野球チームでの、僕のプレーを栄東の外野手に重ね合わせて見てしまった。僕も外野手だし。しくじってる内容もフォームも、「たぶん自分もああなってるだろう」という感じになっていたし。いい反面教師になったね。たぶん栄東高校という学校も、準決勝までははつらつといいプレーを出していたのだろう。緊張や疲労もあっただろうけど、相手の浦和学院を見て、戦う前から手足がすくんでしまったのかもしれないね。気候が温かすぎて、集中して観戦するには眠くなってきたので、浦学勝利を勝手に確信したところで、途中で抜け出して帰ってしまった。どっちも応援しないで観戦するのも、たまにはいいもんである。思い入れが強くなると、あとの疲れがきつく感じることもあるからね。そのぶん、両チームのプレーを客観的に見て、勉強することができて、なかなか収穫があったよ。-------------------------------帰宅してニュースを見ると、JRの列車事故に対する報道が続いていた。思うに、この事故は現代のタイタニック号事件だよなあ。タイタニックの名前の由来は、最先端文明を駆使した最強の神「タイタン」。この文明に対する過信とおごり、さらに利益最優先という考えによる、常識を逸脱したスピード超過が、暗礁を避けることを不可能にしたのが、タイタニックの事故の原因と云われている。JRの事故も、聞けば企業の考え方のロジックが、タイタニックと同じなんだよね。僕は、警察のテロ対策室に、テロの関連について着目して欲しいと思ったりしたんだけどね。だってその後の鉄道トラブルの連発は普通じゃないよ。JR西日本の問題にみんなが気をとられている間に、テロの魔の手は着々と各地の鉄道に伸びているのかもしれない。実は事前に鉄道会社の幹部に向けてテロリストからの脅迫状が、電話かメールなどで送られ、口を封じられていて、そうとは知らない乗務員たちは、運転席に潜入してきたテロリストの催涙ガス攻撃に手も足も出なかった、としたらどうであろう。結構つじつまが合うんじゃあるまいか。不祥事の話が今日になって出てきたけど、日ハムのときも、三菱自動車のときも、新潟県警のときも、似たような感じの批判があったのを、みんな覚えていることでしょう。要するに、今回のJRにはじまった話ではないのだ。「まあまあまあ、もう一杯ぐらい飲んでからだっていいでしょう」みたいな、なあなあな、モラトリアム志向になるのは日本人の習性だからして。今そのことでJR社員だけをつるし上げるのはナンセンスでしょう。NHKがそういうことを報じるのを見ていて、「不祥事業界の先輩のくせに、どの口がそういうことを云うかあぁぁ!?」と思ってしまうのは、やはり自分が事件の被害をこうむっていないからかな。ボウリング大会の幹事がテロリストに脅迫されていたのかもしれないし(しつこいか)。-------------------------------K-1は、相変わらず盛り上がってるね。考えすぎだと思うけど、なんか、主催者たちが旧来のボクシングと、あえてかけ離れた演出をしているように見えてしまって仕方ない。無論そんなつもりはないと思うけど。個人的な感覚にすぎないんだが、なんか、ムエタイ系のK-1選手たちの、膝蹴りが気に入らない。拳のみを交えて勝負するボクシングを見慣れてしまっているせいだろうか。なんか簡単に、KOで勝負がつくのが見えるようだしね。観客が、戦術とかテクニックに醍醐味を見つけられず、派手なKO決着ばかりに面白さを追求してしまうのも、ちょっとね。まあ、こういうのは好き好きだから、別に批判するつもりは毛頭ないけどね。-------------------------------この前の、「がっちりマンデー」を見るまで気がつかなかったのだが、サッポロの「ドラフトワン」って、麦を使わずエンドウ豆を使っていたんだね。いやー、これはうかつであった。どうも、「ビールの味がしなさすぎるなあ」と思っていたんだが、実際ビールでも発泡酒でもなかったのだ。飲まなくなったとはいえ、そもそもビールの味が好きな私は、安いという理由だけで、たまーに飲むのは「ドラフトワン」ばかりで、「んー、ビールがうまくないなー、ついに酒が身体に合わなくなってきたのかなあ、ちと淋しいなあ」と思っていたのだが、安心したよ(笑)。というわけで、のどかでやる気のないGWの数日間、世間ものんびりムードにつき、ときどき昼間からドラフトワンを飲んだりしてしまった。このバチ当たりが!!
May 5, 2005
-
おうまちゃんぱかぱか・・・
はは、ノーマークのスズカマンボが勝っちゃった。春の天皇賞は毎年、予想しても外れるか、当たってもガチガチの決着で配当がつかないかのどっちかなので、今回もあまり真面目に予想してなかったんだけどなあ。そういえば土曜の朝、某テレビ番組に謎のマンボミュージシャンが出てきて、趣味の「まんぼん栽」というヘンテコな盆栽を紹介していたのを、ふと思い出した。こんなところにサインがあったとはねー(笑)。そんなの気づくかよ。つーか、そういう予想の仕方をして何度も失敗をしているので、今年からやめたとたんにこれだからね(くどくど)。2着に入ったビッグゴールドは、いちおう押さえで予想に入れていたので、とはいっても200円ずつしか買ってないからあんまし悔しくないけど、もし当たれば盛り上がったのになあ、という気はするね。ちなみに僕の本命はハーツクライでした(T T)。例年だと、天皇賞のあとというのはしばし間が空いたりするので、予想を外したGW後半は寂しい思いをしていたのであるが、来週はNHKマイルカップがあるようなので、まだ楽しみが残ってますな。つーか、今年は買うつもりもあんまりないのですが。日曜、府中に行われたスイートピーステークスは、ライラプスという馬が強い勝ち方をしたね。オークスは、たぶんこの馬が獲るのではないでしょうか。本番も屋根がケント・デサーモだったら、なお堅いような気もするが。今のところ、本命にライラプス、対抗にラインクラフト、シーザリオが3番手、という感じがしてます。オークスを革切りに、これから再び3歳クラシックシーズン到来。ダービーまでは、やはりディープインパクトで、相手探しという話になるのかな。ディープインパクトが、秋までもつかどうかはまだわからないね。ケガがない保証もないし。強い馬というのは、同時にケガもしやすい馬ということだからね。トウカイテイオーなどはその典型だからね。でも、今の感じだと、最低でも「2冠・最優秀3歳牡馬」にはなれることでしょう。それにしても、今年の競馬はさっぱりわからないね。
May 2, 2005
-
カメムシ車両
GWでガラ空きのJR山手線の車両に乗り込むと、前方の車内広告の紙の上を、一匹の虫がモゾモゾと這っていた。ハエか何かかと思って、眼鏡をかけてよく見たら、それはカメムシだった。ヒェ~。俺は昆虫の中でも、カメムシがハチの次に苦手なのである。昔、自分の部屋に飛び込んできて、追い払おうとして手で払ったら、そいつが手に当たってしまい、やつは自分の身を守るために、強烈な臭いを撒き散らした。それは「激烈」とも思えるヤツであった。地雷を踏んだようなものである。以後しばらくは、部屋の他人を通すことをあきらめた。そのことがあって以来、カメムシを見るたびに、俺は逃げたくなるのである。あまつさえ、カメムシのとんがったシルエットを見ただけで、背筋に寒気がするようになってしまった。以前は、虫を見るたびに気になって、手で払ったりしていたのであるが、それ以来、むやみやたらと虫を手で払うことをやめた。虫は基本的に、こちらがかまわなければ何も攻撃してはこないのだ。直接関係ないが、最近、電車の事故やトラブルが頻発している。今まで意識してなかったからかもしれないが、注意してニュースや新聞を見ていると、あの事故の翌日以降、別の線でも毎日のようにトラブっていた。なんだったのだろう。金曜日も、山手線の線路に異常な音がした影響とかで、京浜東北線が一時運転を抑制した。この日京浜東北線で移動していた俺は、ちょっと肝を冷やした。例の福知山線の事故では、死者が107人にも及んでしまったという。被害者の遺族はJRを憎んでいるという発言をしていたけれど、気持ちはすごく察するけれど、問題点はそれだけではないんじゃないか? とも思ったりする。電車移動という、今までごく安全で普通のことと思っていた日常行動の中にも、死の危険というのはひそんでいるんだなあ、と思いましたね。ちょっと、辛いし怖いし、複雑な思いにさせられる事件であった。これから、我々は生活の中で、ただボーッと生活するだけでなく、死のリスクも含んだいろんなことに意識を向けながら生活していく必要があるな、と思ったりした。別に、考えたところで死ぬときは死ぬわけではあるけれど。逆説的な話だが、危険に対する覚悟とか心の準備をするということは、精神的な安心を得るための、自己防衛手段でもあると思うのだ。その他、電車車両に対しては、ほかにも改善されたというか、変わったことがあるね。専用車両なんていうのも続々とできていること。ラッシュアワーの痴漢防止対策というが、女性にとってはありがたいことではあるだろうと思うけど、かたやすし詰めの車両の隣で、涼しい表情で女性たちが座っているのは、ちょっと不思議な光景でもある。専用車両が現れるよりずっと以前に、ラッシュの時間帯だというのに、たまに凄く空いてる車両があったりするね。まあ、細かく書くと差別的な言葉も書くことになるかもしれないから詳しく書かないけど、嗅覚が麻痺していれば普通に座って乗れる車両である。でもあの臭いというのは、目にもくるからねえ(笑)。同じ理由で、俺が昨日乗ったカメムシがいた車両というのは、ちょっと不用意に虫に危害を加え、やつが抵抗することによって、「カメムシ専用車両」になっていなかったという保障はない、実は抜き差しならぬ状況でもあったのである(?)。かといって、カメムシ一匹におびやかされて移動するのも、瑣末すぎてアホらしいことでもある。俺は、余裕があるGWの山手線の座席に腰掛ながら、カメムシが自分の方へ飛んでこないことを祈っていた。ヒマだったので、そったらつまらねえことばかり、乗車してる間、ずっと考えていた。だけど、このカメムシがそのあと、運転席に潜入し、運転手がやつの放つ激臭に、頭がクラクラして運転を誤り、大惨事を起こさないということは、誰も保障できない状況でもあったのだ(?)。ヒェ~。
May 1, 2005
全14件 (14件中 1-14件目)
1