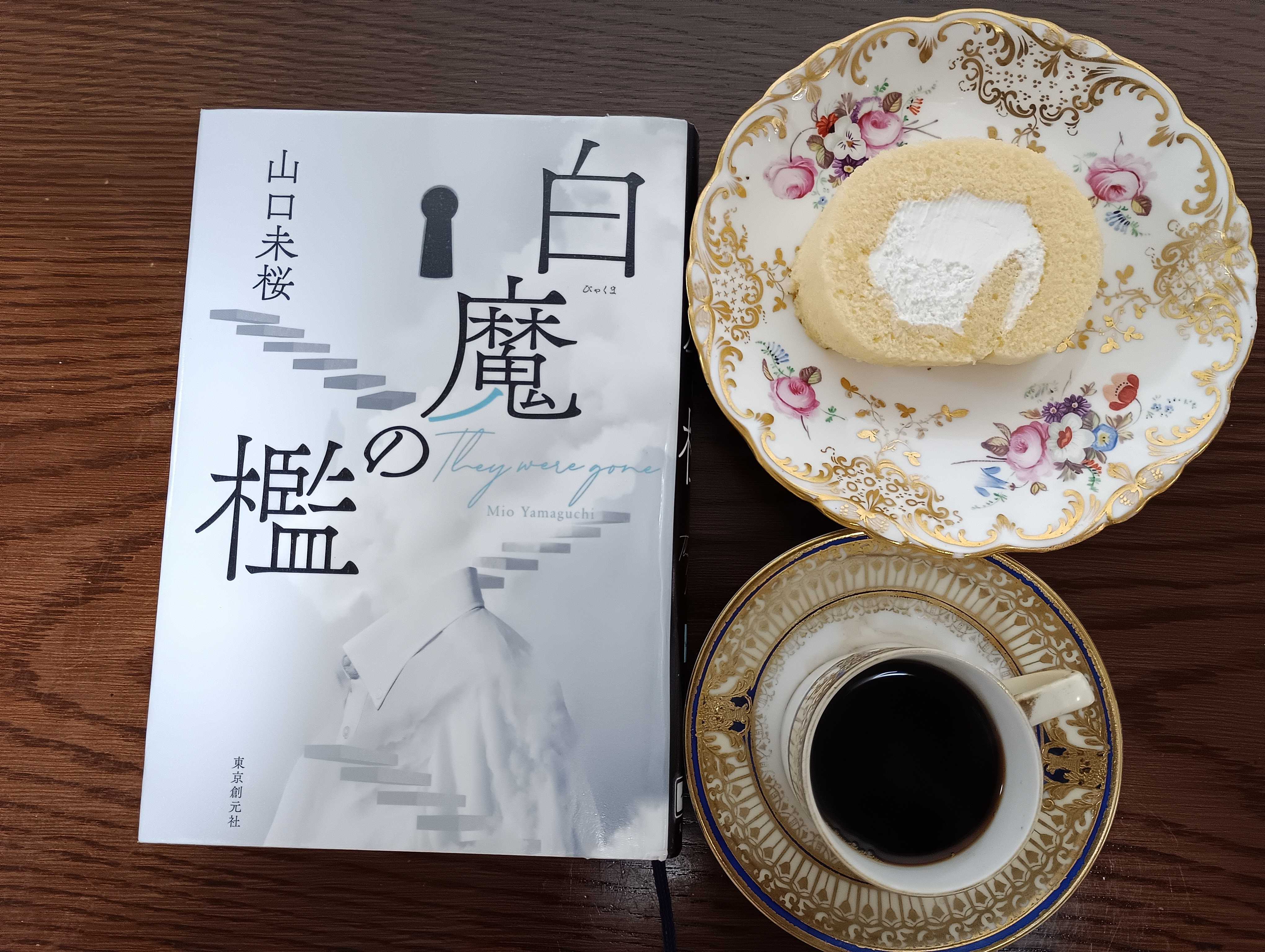2006年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
「My Town 泉」での連載エッセイ第1回 「奇妙な肩書き」
自宅と大学のある仙台の泉パークタウンの新しいマガジンにエッセイの連載をすることになった。そろそろ、出回る頃かな。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ひょんなことから犬を飼うことになった。それまで住んでいた高森の住居では犬を飼うことはできなかったので、結局半年後には紫山の家を買う羽目に陥った。12万円で買った犬のおかげで、人生で一番大きな買い物をしたことになる。この犬は、動物嫌いだった私にも遠慮容赦なく飛びついてくる。早朝には散歩に連れて行かねばならない。最初はいやだったが、そのうち手を舐められるのにも慣れるようになってきた。私をのぞく家族はこの犬(「ちょこら」という名前)とキスまでしているのだが、私はそこまではまだ踏み切れないでいる。よく見ると犬を連れて散歩をする人のいかに多いことか。いや、犬に連れられて、あるいは引きずられて散歩している人が多いといった方が実態かもしれない、、、、、。よく見ると犬の種類(犬種)とその名前も様々である。個々の犬の顔つき、表情、体形、文様、吠え方、そして犬の人格(犬格とでもいうのだろうか、、、)などの多彩さにいつのまにか目を凝らすようになった。犬のいる生活をすることになって、今までまったく知らなかった社交の世界が広がっていたことに驚いた。飼い主の職業や肩書きなどを気にしている人はいない。いつの間にか「ちょこらちゃんのパパ」と呼ばれて、私自身が犬の付属物のようになるという主客逆転の不思議な感覚を味わうことになった。今ではこの奇妙な肩書きも気に入っている。私が仕事から帰宅すると、家族より先に、最愛の人と久しぶりに会うかのように、甘えた声を出して鼻を鳴らしてものすごい勢いで毎回突進してくる。その後しばらくはちょこらとの熱いコミュニケーションの時間となるのが今や日常のリズムである。居間でテレビを観ながら横たわっていると私の腕枕で寝ることを要求する。散歩の時、糞をすくっていると何か懐かしい匂いがする、、、、、。飼い始めて2年ほどたった頃、娘から「お父さん、人間度がアップしたね!」と言われて苦笑したこともある。この調子で行くと私もいずれは、ちょこらとキスをするようになるかもしれないという悪い予感(?)もする。いや、新しい自分と出会う「楽しみ」とでも言おうか、、、、、、、、、、。犬のいる生活も、もう6年になった。
2006/08/31
コメント(0)
-
方言(専門用語)とどう向き合うか
今や標準語に押されて全国各地の方言は旗色が悪い。地方独特の文化の基盤である方言と全国共通の標準語との関係はどうなっていくのだろうか。さて、ビジネスマン時代、職場を変わるごとにその部門特有の専門用語が障壁となって仕事を覚えるスピードが鈍った経験がある。営業部門の用語、本社部門の用語、サービス部門の用語、技術部門の用語など、独特でそれが部門の文化を形成しているからやっかいだ。営業部門と技術部門が意思疎通できないことにいらだって、お互いに「あなたホントに会社の人?」という言葉を投げ合っている姿に何度も遭遇したことがある。本社の広報というセクションに異動になって、自分の仕事は独自の専門用語(これを方言と呼ぼう)を身につけた集団同士の翻訳機能を果たすのが役目であることを発見したこともある。その後、大学に移ると方言というより古語に近い言語を操る集団と向き合うことになる。そして大学教員として企業や官庁との付き合いも増えてくると、それぞれの会社や組織ごとの風土の違いが目につくようになった。まず、官庁と民間では言語の体系が違うこともあり互いに困っている。またメーカーとサービス業など業界ごとに言葉が違ってくるから異業種同士ではなかなかコミュニケーションがとれない。そして自動車会社と製薬企業など、それぞれの大国独特の言語が登場する。同じ業界であっても会社ごとに用語の意味が違う。2009年度までに始まる裁判員制度も、実は同じ問題を抱えている。裁判のメインプレイヤーである裁判官・検事・弁護士は同じ業界だから同一の言語を使う。しかし裁判員として指名を受ける民間人とは言語が違うから意思の疎通ができない。司法の側は自分たちの言葉が標準語だと固く信じているからやっかいだ。法律用語は実は特殊な人々だけに通用する方言に過ぎない。いっそ、それを司法方言とでも呼ぼうか。この裁判員制度成功への突破口は、司法側が自らの専門用語を方言として認識するかどうかにあると私は見ている。こういう言語環境の中で私たちは仕事やプロジェクトを遂行していかねばならない。専門化、分業化の流れの中で、違う言葉への言い換え、新しいキーワードの発明、重なりや違いの見分けなどの努力や、それを解きほぐそうという態度が大切になってきた。専門用語という方言と共通語としての標準語の使い分けがあらゆる業界に共通するテーマとなってきたのである。(「ビジネスデータ」9月号に執筆)
2006/08/30
コメント(0)
-
大崎市行政改革推進委員会の初会合に出席
午後行われた第1回会合に出席したが、私はこの委員会の会長に選出された。新たに就任した伊藤市長も2時間の会議にずっと出席されて、挨拶や発言もされた。今回は、まず、市側から基本方針や計画策定フロー、委員会の業務工程、補助金のあり方などの説明を受けた。今後、1市6町という大型合併の新市の舵取りの方向を議論することになるが、本日は、この委員会の位置づけと行政改革推進の基本方針について議論を行った。会長としての挨拶では、市民ニーズの見極め・最後のチャンス・破綻の先延ばしにならないように・市の他の計画に先行するのでいい計画を・形だけ整えるのはやめたい・足元を掘ろう・行政方言の禁止(市民にわかる標準語)・施策のプライオリティのしくみ構築・内外のコミュニケーションをキーワードに推進、、、といった私の行革にあたる考えを述べておいた。男性6人、女性4人で旧・古川市や6町から様々な分野の人が委員になっている。JA理事、合併協議会委員、会社社長、観光審議会委員、ボランティア団体代表、元会社社長、電気工事会社専務、公認会計士、元工場長、学識経験者などが委員の顔ぶれだ。皆さん、危機意識も高く論客が多いようで、最初から議論は活発だった。次回は10月。
2006/08/29
コメント(1)
-
タイムマネジメント
秋葉原にある大手旅行会社の本社で研修講師をつとめたので、東京日帰りだった。対象は20代の後半の若手第一線の支店社員だった。事務局からは、タイムマネジメントの重要性とその技術についても指導して欲しいとの注文もあったので、そちらよりに話をしてみた。若い人は時間管理がなかなか身についていないということなのだろう。思えば、自分自身も若い頃はタイムマネジメントができなくて、いきあたりばったりの仕事や生活をしていたことを思い出した。仕事に追いたてられて精神的な余裕はなかった気がする。組織のマネジメントができるためには自分自身をコントロールできなければならないし、セルフマネジメントの要諦は時間管理、つまりタイムマネジメントである。このことに早く気づくことがもっとも大切なことだと思う。そのことを理解してもらっただろうか。
2006/08/28
コメント(0)
-
東和町(「岩手県)の萬鉄五郎記念美術館、宮沢賢治のイギリス海岸
立ったまま入浴するという名物の「白猿の湯」(1.5mの深さ)など昨日から3度楽しんで、鉛温泉の藤三旅館を後にする。この歴史のある旅館は、田宮虎彦(1911-1988年)の小説「銀心中」(しろがねしんじゅう)の舞台となった旅館である。今日の目的地は花巻市と遠野市の間にある東和町土沢の「萬鉄五郎記念美術館」である。萬鉄五郎(1885年生まれで41歳で1927年に死去)は、東和が生んだ日本近代美術の先駆者の一人である前衛画家だ。萬の出た小学校が記念館になっている。また生家の土蔵を復元した隣の「八丁土蔵」の2階で、萬鉄五郎の作品や生涯をハイビジョン映像で楽しめる。8月27日の日曜日は、花巻の宮沢賢治の誕生日で、25日から3日間お祭りをやっていたが、時間の関係で今回は賢治が愛した「イギリス海岸」を訪ねることにした。北上川と瀬川の出会う所にできた豊かで明媚な川岸である。賢治が愛した風景が心を和ませてくれる。「なみはあおざめ支流はそそぎ たしかにここは修羅のなぎさ」と賢治自ら作詞・作曲した歌曲「イギリス海岸の歌」にある岸辺である。賢治は学生たちを連れてよくここに来たという。花巻市の地図を見ていると、37歳で逝った偉大な宮沢賢治の足跡を示す土地や建物などが実に多いことに気づく。花巻や遠野には何度も足を運ばねばならないと感じる。 (萬鉄五郎記念美術館の訪問記は別途書く予定)
2006/08/27
コメント(0)
-
「遠野」探訪-----柳田國男・佐々木喜善
仙台から車を飛ばして土曜日の昼前に、まず、「昔話語り部館」で、菊地玉さんの「カッパ淵」と「ザシキワラシ」の名人芸の語りを聴く。「とおの昔話村」には、佐藤忠良作の柳田國男の胸像が建っている。まず、「柳翁宿」という旧・高善旅館を見る。この旅館には「遠野物語」の柳田國男、折口信夫、ネフスキー、金田一京助、桑原武夫らが投宿している。遠野に3度訪れた柳田國男らが泊まった2階の部屋も見ることができた。館内から続いている「物語蔵」では、日本民俗学の父と称される柳田國男(1875-1962年)の一生とその業績が展示されている。柳翁宿を出て向い側にある「遠野昔話資料館」を見る。隣には「遠野物語研究所」もある。車で少し走り、「安部屋敷跡」の傍を流れる川の「カッパ淵」を歩く。先ほどの物語のあった場所だ。その近くにあるカッパ狛犬のある「常堅寺」でお参りをして、「伝承園」へ歩く。ここにある「佐々木喜善記念館」を見る。佐々木喜善は東京で柳田國男に遠野の昔話を語り、これが「遠野物語」に結実した。宿は、遠野から1時間半ほどの距離にある花巻温泉郷の鉛温泉の藤三旅館にとった。 (柳田國男と佐々木喜善については、別途訪問記を記す予定)
2006/08/26
コメント(2)
-
株式会社デュナミス 第1回定例株主総会に出席
宮城大学卒業生でつくる株式会社デュナミスの第1回株主総会が、21世紀プラザで行われ出席した。代表取締役、および各事業部長(取締役)からの説明を受けた。残念ながら前期は若干の赤字となった。今期は売り上げ高利益率10%を目指す。戦線が着実に拡大し、事業も充実してきているとの印象を持った。今期は、各事業部自体の改革はもちろんだが、経営としては内部統制の強化と、事業部同士の相乗効果の発顕が課題だろう。-------------------------------------------------------2005年度の概要Mr.PC事業部 訪問指導サービスから訪問型トラブル対応サービスへの転換を図るリサーチ&コンサルティング事業部 クライアント数・受注増も、目標の黒字化に届かずメディアデザイン事業部 図考スタジオ始動。下請的制作業からプロデュース業へキャリア開発支援事業部 新規事業部立ち上げ、初年度より順調に受注コーディネーターグループ 産学連携コーディネーター業がスタート-------2006年度事業計画 全事業部で黒字Mr.PC事業部 パソコントラブルサポート・パソコン講習会スタッフサービス・ インターネットマンションメンテナンスサポート・プロバイダサービスリサーチ&コンサルティング事業部 合意形成促進事業「ニーズ発掘業・課題解決力育成業・図解コミュニケーション研修業」メディアデザイン事業部 デザイン業からプロデュース業への移行と図解指導の自主運営が改革テーマキャリア開発支援事業部 起業教育「東北経済産業局・仙台市教育委員会の事業」 プロジェクト参画プログラム「NPO法人ETHIC・東北大学大学院・長期インターンシップ、、」コーディネーターグループ 留学生派遣事業・人材獲得支援・イノベーション研修&コンサルティング事業------------------------------------------------------------------
2006/08/25
コメント(0)
-
卒業生O君(人材ビジネス業界)が研究室に現われる
12時、人材ビジネス業界に就職した6期生のO君が研究室に現われた。私のゼミを卒業して1年半になるが、雰囲気はあまり変わっていない。今は、大学や専門学校のキャリア部門に対するアドバイスや情報提供を行う仕事をしているそうだ。もともとこういう分野に興味があり、卒論もこの分野をテーマとしていた。関心のある業界でもあり、仕事に対する取り組み姿勢はいいと感じた。人材に関する専門家に育って欲しい。東京などで活躍している卒業生やゼミのOBの情報もいくつかもらった。N君は他社に引っ張られて面白い仕事をやりそう、大手メーカーに入ったH君は採用関係で毎月仙台に現われている、S君は就職先を辞めてしまった、、、、、。----------------------13時、学部研究生の留学生から大学院受験の相談を受けアドバイス。14時、東京の出版社から3人見えて、本づくりの相談と取材を受ける。
2006/08/24
コメント(2)
-
くりこま高原若者自立塾
大学院に社会人院生として在籍していた佐々木豊志さんが主宰しているNPO法人くりこま高原・地球の暮らしと自然教育研究所が、平成18年度厚生労働省委託実施事業である「くりこま高原 若者自立塾」を開くことになった。引きこもり・ニートに悩む若者を応援するプロジェクトである。志の高い先進的なプログラムであり、私の関与しているNPOキャリア開発研究機構でも、キャリアカウンセリングの部分をお手伝いすることにした。以下、パンフから。---------------------------------------------------------- 生活を創造していく生活体験、自然に入り込んで人間関係を学ぶ自然学習体験活動、 自発的行為を引き出す冒険体験を通じて、就労へ一歩踏み出す力を育みます。 体験学習法をベースに、失敗や対立から学んだり、上手く行かない事を、 流さずに受け止めて振り返ることで新しい発見や気づきから学ぶように指導します。 くりこま高原自然学校「耕英寮」の実績を活かした、 塾生個々の課題の分析と対応、そしてその実践的体験からの学びを大切に、 失敗を恐れない一歩を踏み出す勇気を育む応援をします。 入塾-2週間 グループ作り・フォーミング 共同生活習慣づくりが中心 3-6週間 生活体験・労働体験 特別プログラム 第一期 トレッキング 川下り 第二期 スキー 雪上キャンプ 7-10週間 労働体験・特別プログラム 資格取得プログラム(GEMS・ネイチャーゲーム、、) キャリアカウンセリング 11-12週間 トランスフォーミング・キャリアカウンセリング-----------------------------------詳しくは下記。http://kurikoma.org/
2006/08/23
コメント(0)
-
旧友たちとの再会
ある雑誌のインタビューを受けた。担当の女性編集者とは2度目の仕事だが、この方のご主人とは小学校から高校までの友人である。今回は一緒に仙台の大学まで見えることになっていたので、楽しみにしていた。2時間ほどの受け応えのあと、歩いて仙台ロイヤルパークホテルのレストランで3人で夕食を摂った。この友人とは昨年、東京で高校卒業以来久しぶりに会った。最近、懐かしい友人たちとの再会が多くなってきているが、私自身はそういう機会を大事にしていきたいと思っている。9月には数日間帰省する予定だが、福岡での旧友(ビジネスマン時代)と久しぶりに飲む機会や、故郷・中津の友人たち(小学校から高校)と再会の予定もある。今から楽しみだ。
2006/08/22
コメント(0)
-
人間は習慣の束である
このブログ日記の連続記入も先週で700日を超えた。気がつかないうちに自然に超えたという感じだ。書き込むことがもはや習慣になってしまった感もある。「人間は習慣の束」だから、よい習慣を持つことは、よい生活、そしてその結果、よい人生につながっていくと思う。
2006/08/21
コメント(0)
-
近代日本には偉い人が多い。「人物記念館を訪ねる旅」の連載12回目は岡倉天心
早いもので、PHP「ほんとうの時代」でのこの連載も12回目の「岡倉天心」で、丸1年たったことになる。1. 後藤新平 (政治) 岩手2. 司馬遼太郎(小説) 大阪 3. 福沢諭吉 (学者) 大分4. 岡本太郎 (絵画) 東京5. 原 敬 (政治) 岩手 6. 樋口一葉 (小説) 東京7. 松本清張 (小説) 福岡8. 遠藤周作 (小説) 長崎9. 新渡戸稲造(学者) 岩手10 杉原千畝 (外交) 岐阜11 森鴎外 (小説) 東京12 岡倉天心 (美術) 茨城分野や場所などのバランスには気を配りながら書いてきたが、最近、ちらほらと読者の姿を垣間見ることもあり、それも書き続ける推力にもなっている。日本の近代には偉い人が多い、と改めて感じている。次回は、寺山修司を予定している。
2006/08/20
コメント(0)
-
母・子ども・孫・ひ孫で食事会
九州から母が上京してきた。九州に上陸した台風で飛行機が飛ばなくなったため、急遽自由席券で新幹線の小倉で飛び乗り、新横浜までやってきた。母は昭和2年生まれで79歳になるからこちらも驚いた。戦争を乗り切った世代は強い。広島からは席に座れたとのことだったが、いずれにしても長旅は間違いない。19日は、母の子ども3人と、その配偶者。孫たち4人とその配偶者、そしてひ孫2人が東京有楽町の「吉祥」で昼食会を催した。仙台からは、長男の私と妻、そしてまだ学生の長女と長男。横浜からは、自動車メーカー勤務の弟と妻。関西に住む孫(男の子)は仕事で欠席。千葉からは、妹と航空会社勤務の夫。そして都内に住む結婚した孫(女性)と外資勤務の夫、そして母にとってひ孫にあたる女の子と男の子。またもう一人の電力会社に勤める孫(女性)。2-3時間の宴会だったが、賑やかだった。一番元気だったのは母かもしれない。来週は、横浜の弟の家、土日は短歌の全国大会に出席、次週は千葉の妹の家というスケジュール。
2006/08/19
コメント(0)
-
「プライス 若沖と江戸絵画」(東京国立博物館)---蒐集家という人生
気になっていた東京国立博物館で開催中の「プライスクレクション 若沖と江戸絵画展」を観た。「近世絵画研究者でプライスコレクションを知らない人がいるとは考えられない」といわれる老舗コレクション(江戸絵画を600点ほど蒐集している)の創設者は同志である日本女性エツコを妻に持つ身で、現在76歳である。20代の若き技師であったプライスは父の友人であったフランク・ロイド・ライトと一緒にタワーを建設する。帝国ホテルの設計者として日本でも有名なライトは、「君はGodのGは大文字で綴るかい。私はNatureのNも大文字で綴るんだ」と語りかけた。ライトにとっての先生は自然の造形だったのだ。プライスは日本の美術の中に、ライトの自然観を超える自然観を見出した。「千年余にわたり、日本人は、人間が手を加えることで自然を一段と高めようとしてきた。荘厳な伊勢神宮から桂離宮、そして簡素この上ない茶室に至るまで、その創造する力は自然を凌駕しているように思われる。日本人は、松の木の枝葉を切ったり、曲げたり、つかんだりして、その本質だけを残す、その残されたものは、自然の造形より遙かに松の木らしくみえるのだ」(プライス)そして、日本人は江戸時代の文化を常に高く評価してきたが、絵画だけはそうではなかったというプライスは、自らのコレクションを3つのカテゴリーに分類している。一つは異彩を放つ独特の画風を切り開いた伊藤若沖(1716-1800年)の傑作である。二つ目は「江戸時代の町人」をテーマとした絵画で、丸山応挙とその弟子たちの作品である。三つ目は江戸琳派のグループで、鈴木其一、酒井抱一たちのコレクションである。若沖は絵画というよりグラフィックという印象を持つ人も多く、鈴木其一(1796-1858年)は絵画というよりパッケージのデザインと見紛うような作品が多いという。プライスは、水墨画や文人画といった形のはっきりしない作品は好まず、知的な造形をもった作品を選んでいる。オクラハマ出身の一介の技師であったプライスは、蒐集した絵画から受ける「目の喜び」からたんなる趣味として始めたコレクションは、彼の人生に新しい目的を与えるまでに成長していった。自分が得たこの喜びを多くの人にも同じように体験して欲しいとの考えから、プライスは公開のための様々な試みに協力を惜しまない。オクラハマのプライス邸「心遠館」(火災で焼失した)、ロサンゼルス・カウンティ美術館のジャパニーズ・パヴィリオン(日本美術館)もその一環である。プライスは技師としての「エンジニアの眼」と画面の中に生命を感知する「アニミストの眼」を持っている。今回の企画展の主役である伊藤若沖は、このプライスによって現代に蘇ったのである。若沖などの再評価は、日本人によってではなく、アメリカ人によってなされたものである。こういた蒐集家のおかげで今日の私たちは逆輸入の形ではあるが、先達の残した優れた芸術作品を眼にすることができる。そういえば、経営学の神様・ドラッカーも日本の浮世絵の蒐集家だった。画家の名前でなく、自らの感性を信じて好きな絵を蒐集し続けた結果、そのコレクションは世に知られていなかった画家を掘り出したり、当時の評判の画家をもう一度蘇らせたりすることができたのである。エツコ&ジョー・プライスコレクションという名前のコレクションでプライスの名前は妻とともにながく残ることになるだろう。プライスは日本の江戸絵画の蒐集家(コレクター)という素敵な人生を送っているように見える。
2006/08/18
コメント(4)
-
昭和30年代半ばの貧しい生活の断片と豊かな記憶--旧友との再会
お互い小学生だったから。40数年ぶりになるだろうか。新宿のサザンタワーホテルでゆういっちゃんと会った。一緒に遊んだ友達たちの当時の様子とその後の消息情報の交換。今まで消えていた記憶がにわかに蘇ってきたり、懐かしい顔が浮かんできたり、確かに我々は同じ時間を共有していたのだ。風呂屋の二階でみた、栃錦と若乃花の名勝負、空手チョップの力道山の雄姿、、、。家の横を流れていた農薬汚染された小さな川で泳いだり、たらいの乗って流れたりした記憶、、。少し遠かった深い山(ごすてんのう)で遊んだ記憶、、、。昭和30年代半ばの貧しい生活の断片、、、、。不思議なことに、あの狭い空間に30人ほどの子供達がひしめいていて、一つの世界を確かに構成していたのだ。記憶を引っ張り出しながら思い出した子どもの数は、ほとんどは男の子だったから、話題にのぼらなかった女の子も多数いただろう。まるで映画のシーンを見ているような感覚だった。
2006/08/17
コメント(0)
-
映画「狩人と犬、最後の旅」
1962年生まれのニコラス・ヴァニエ監督の映画を観た。カナディアンロッキーのユーコン準州の世界遺産のあるクルアネ国立公園のある北極圏原生林が舞台である。最後の狩人、ノーマン・ウィンターの物語。7頭の犬・夏はカヌー・冬は犬ぞり・トナカイ・熊・鮭・カヌー・マイナス40度・オーロラ・木々の葉音・テン・ビーバー・オオカミ・夕焼け・山小屋・大きく過酷な自然「私の幸福は自然との関係の中にある」「死ぬということは、命を受け渡していくということだ」「狩人の役目は、狩りを通じて生態系を調整し、自然界の調和を保つことだ」この映画はフィクションとなっているが、全て皆ドキュメントである。このフランス映画は、ハスキー犬ブームを巻き起こし、カナダへの旅行者の増という社会現象を引き起こしたそうだ。とても印象的な映画だった。
2006/08/16
コメント(0)
-
澤田美喜記念館
エリザベス・サンダース・ホームを創立した澤田美喜の記念館は、神奈川県大磯の駅前の深い緑の中にあった。1901年生れの美喜のことは、東京上野の旧・岩崎家住宅見学の時に知った。そのため、大磯にある記念館を訪ねた。駅前の道路を渡ると、ホームの敷地に直ぐに入れる。右がホームのあったところ、左側の石の階段を登り切ると記念館に着く。その直前に90歳にならんとする男性が草を刈っていた。この人がこの記念館を守っている鯛さんである。ノモンハン事変の生き残りだそうだ。ネクタイをして背筋がピンと伸びたかくしゃくとした人である。「ここにくると元気になる」という鯛さんは、ママちゃまと呼ぶ美喜のもとで長い間、働き、その人柄と使命感に深く影響を受け、一生尊敬の念を抱き続けている。最初は1時間強のつもりだったのだが、結局は3時間以上の滞在となった。三菱財閥の基礎を築いた岩崎弥太郎の息子・岩崎久弥の娘であった美喜はお転婆で家族を困らせ、令嬢にあるまじき行為で見合いを破綻させていたが、外交官で後に初代国連大使となる澤田廉三と結婚する。若い頃はアルゼンチン、中国、イギリス、フランス、アメリカと夫について世界をまわるが、イギリスのドクター・バーナーズ・ホームでのボランティアが、美喜の運命を変える。建物の2階が教会で、1階が澤田美喜が集めた隠れキリシタンの遺品を集めた記念館となっている。40年間にわたって激務の傍ら集めた1000点の品々。九州長崎の島々を巡って集めたものも多い。親交のあった遠藤周作は16・17世紀の資料が貴重だとのメッセージを寄せていたし、三浦朱門・曽野綾子夫妻は「今日をいかに生きるかに悩む人々、未来の原型を過去に見出す能力を持つ人々、殊に若い人々に、このコレクションを見て欲しいと思う」と記念館の入り口にメッセージを残していた。2階の教会は、三宅よしろうという人の建築で、日本初の免震構造の建物だそうだ。「ママちゃまは、昼はオニばば、夜はマリア様だった」「坂本九の上を向いて歩こう、が好きだった」「テレビの水戸黄門が好きだった」2005年11月2日につくったプレートには、104名の逝去者の名前が刻んであった。目についた名前を控えてみた。アブラハム:澤田廉三エリザベス:澤田美喜ピーター:澤田久雄エリザベス・サンダースステパノ:澤田晃パウロ:田実渉昭和30年には、天皇・皇后両陛下はみえている。その記念に大きな日の丸の旗が飾ってあった。一階の記念館。昭和11年から集めた隠れキリシタン関係の品々が並んでいるおごそかな空間である。阿弥陀仏に模したマリア像、大友宗麟の鉄地蔵、細川ガラシャ夫人の遺品、高山右近手製のマリア像、ド・ロ神父考案の天国と地獄図、綾部焼、白萩焼、日本最初の版木の踏絵、キリシタン大名ゆかりの品々、キリストの姿が映る魔鏡、、、、。鯛さんは特別にシーボルト作の母子像を抱かせてくれた。-----------------------------------------------------------記念館を訪問したのは7月だったが、鯛さんの予告にあったとおり、8月15日には、「女の一生シリーズ」の中で「2000人の孤児の母・澤田美喜」という番組が日本テレビで放映された。美喜を演じたのは松坂慶子、夫の廉三は江守徹、父の岩崎久弥は児玉清という配役である。「全身をぶつけて、生きていける何かが欲しい」と語っていた美喜は、ドクター・バーナーズ・ホームという孤児園で「捨てられた子を社会から引っ張りだこにする魔法」という言葉に感銘を受けて、「私も魔法使いになりたい」とホームの建設を決意する。併設する聖ステパノ学園は、戦争で亡くした息子・晃のクリスチャンネームから名づけたものだ。財閥解体で国に物納してしまった多い曽野別荘を買い戻した美喜は、日本人、アメリカ人双方の無理解、妨害の中、小さな善意に助けられながら事業を展開していく。口癖は「顔を上げよ」だった。米兵に強姦されてできた子どもを捨てた母親、そして妊娠したその子どもとの再会のシーン。誰が母親で、誰が父親だったのか、なぜ自分がいまここにいるのかに苦しむ子供たち、、なぜこのような事業をやってきたのかという問いには「啓示。天から使命感が降ってきたとしか」と美喜は答えている。昭和55年(1980年)、「海外に出した養子たちも落ち着いてきたし、子どもを置き去りにする人もいなくなったし、私の仕事は終わったのかも、、」と述懐した美喜は最後の海外旅行にでるが、スペインのマヨルカ島で亡くなる・享年78歳だった。この2時間の番組は涙が溢れてとまらなかった。
2006/08/15
コメント(0)
-
目についた記事からーーー人物の旅
和歌山県田辺市の南方熊楠顕彰館が5月にオープン(2月11日・日経)三好京三記念室が奥州市前沢に4月に設置(5月3日・河北)石坂洋次郎記念館は13年間の教員生活を送った秋田県横手市にある(5月4日・河北)秋田文学資料館が4月に開館(3月17日・河北)後藤新平・斉藤実生誕百五十年記念事業実行委員会:岩手県奥州市水沢区(6月8日・河北)柳翁宿と旧柳田国男隠居所は岩手県のとおの昔話村にある(6月11日・河北)渋沢栄一の顕彰を目的とした渋沢敬三の日本実業史博物館構想花巻タウンウオーキングモニターツアー(宮沢賢治めぐりと新渡戸稲造めぐり)(8月10日河北)茂吉の里にマイベンチのオーナー募集・山形県上山金瓶(7月14日・河北)
2006/08/14
コメント(0)
-
「シンドラーのリスト」
第二次大戦で4600人のユダヤ人にヴィザを出して救った外交官・杉原千畝は、日本のシンドラーと言われている。石巻文化センターに資料展示している弁護士・布施辰治は日帝時代の朝鮮人の弁護を無償で手がけ、韓国人から日本のシンドラーと呼ばれている。このシンドラーとは何者だろうか。本物がわからなければ駄目だということで、「シンドラーのリスト」というビデオ2巻を観る。ドイツ人経営者シンドラーがナチスに面従腹背しつつ、ユダヤ人を1100人救い出すという物語である。ゲットーでの生活ぶり、虫ケラのように安易に殺されるシーン、間違えてアウシュビッツで殺されかかったときの女性たちの様子、、、。シンドラーはやり手の経営者で深くナチス軍人に近づいていくが、心の中はユダヤ人に対する同情であふれている。それを隠しながら、商売と見せながら最後は故郷に1100人のユダヤ人を集め、工場をつくる。戦争に使う物資をつくる工場だが、製品はつくらないで済ます。金が尽きたそのとき、ドイツが降伏する。シンドラーが最後に工場の中で、ユダヤ人とナチス軍人の前で行う演説もよかった。シンドラーは一転して追われる立場になるが、ユダヤ人たちは感謝のために様々な手を尽くす。戦後シンドラーは結婚と事業に失敗するが、イスラエル政府は、シンドラーに「正義の人」賞を送る。この賞は杉原千畝がもらったものと同じである。最後、シンドラーの墓の上にお世話になった人びとが石を一人一個ずつ置いていくシーンだった。映画の中に登場した人物が後年の姿で本人が出ているのには驚いた。いい映画である。10年ほど前の作品でオスカーの多くの賞をとったのも当然だと感じる。この映画が、あのスピルバーグ監督の作品だったことにも驚いた。
2006/08/13
コメント(0)
-
「大地の咆哮」の著者・杉本信行氏逝く
外務省勤務33年のうち14年間近くを北京・瀋陽・台湾・北京・上海で過ごしてきた杉本信行は、2006年5月に「大地の咆哮」を書いたが、その数ヶ月後の8月3日、肺がんで亡くなった。杉本の中国観は、外務省での地道な情報の積み重ねと分析と現地での政治・経済両面での実体験によって形成された。中国認識で重要なことは、データや机上の空論を排し、現実に即して中国を理解することだという。なかでも中国共産党が支配する「中華人民共和国中国」の現体制と「中国人一般」を同一視しないことが肝要だとも述べている。中国共産党の支配する体制はゆるぎないものにみえるが、共産党指導部内部では自信のなさ、悩み、不安、悲観が渦巻いている。党指導者たちの師弟の多くは海外留学に出ているが、これも共産党の支配体制が崩れた場合に備えているともいえる。中国指導部の最大の懸念は国内政策である。いわゆる「三農問題」、農村の貧困、農民の苦難、農業の不振である。農民の不満と怒りが高まっており、政治体制を揺るがしかねないほど深刻である。国内の不安定さゆえに、政権の正当性・正統性を維持するために、対外強硬路線をとる以外にないといった脅迫観念にとらわれているようにみえる。中国は日本にとってやかいな国であるが、少なくとも中国の失政のつけが日本に回ってこないように賢明に立ち回ることが大事である。・中国では義務教育費用の7割以上は受益者負担・年金基金は日本以上に破綻しているため、国内消費は15%程度と庶民はお金を使わない・日本が中国に与えたODA総額3兆円のうち、贈与要素は65%。2兆円は中国に供与されている・中国発展の基礎をつくたtのは日本からの円借款である・中曽根首相靖国参拝を契機に失脚した胡耀邦によって胡錦濤は中央に引き上げられた。・援助することによって問題を提起していく。初等教育、環境保全、医療分野、貧困対策、、・3100余りのダムからの過剰取水による黄河の断流問題。・北京での地盤沈下。水供給の3分の2は地下水。・668都市のうち、400都市以上が水不足・北京から18キロにまで砂漠が迫っている・農民には、年金、医療保険、失業保険、最低生活保障などの社会保障が受けられない・都市と農村の所得格差は30倍・国・省・県・市・郷鎮などの行政単位で、役人が異常に多い構造・人口13億のうち5-6%の共産党員が統治していることの正当性・正統性のための反日教育(すなわち愛国教育つまり愛党教育)を行っている。・中国共産党はプロレタリア独裁を放棄。全国民を代表する党になった。資産階級も入党した・台湾統一は共産党の主要なレゾンデートルになっており、柔軟な対応をとるのが困難・学費が跳ね上がり、エリート金持ちでないと大学にいけない・対日批判を口実とした何らかの組織的な反政府運動が中国全体に広がりつつあるのかもしれない・共産党の制御力が急速に衰えている。3億台の携帯電話普及と1億人インターネット利用者・三重の格差--都市と農村、沿岸部と内陸部、都市内における貧富の格差・極端な格差社会は、富の再分配メカニズムが働いていないことが原因・エネルギー効率は日本の10倍悪く、世界の3.4倍悪い・エネルギー・資源多消費型成長は、持続可能ではない・底なし沼の不良債権・胡錦濤の外交政策と軍が平仄があっていない。軍を掌握しきれていないのではないか・上海の高層ビルは4000棟。メンテと需要が問題。上海は地盤が極めて弱い。数年後には不等沈下・真の情報が中南海には届いてない・中国の問題はすべてが地球規模の問題だ-------------------------------------------------最近中国に焦点をあてて訪問している私にとって、「腑に落ちる」ところの多い書物だった。外交官の情報収集力・分析力のレベルの高さと責任感の強さを感じた。この杉本氏の遺書でもある本書は、しばらくは中国に関心を持つ人の必読の書となるだろう。
2006/08/12
コメント(0)
-
幼馴染みの「ゆういっちゃん」は樋口裕一(ベストセラーの著者)さんだった
木曜日の夜に、小学校4-5年までの幼馴染みの「ゆういっちゃん」からメールで40数年ぶりに連絡があった。「樋口裕一と申します。『頭がいい人、悪い人の話し方』の著者といえば、お分りいただけますでしょうか。、、」から始まる文面で、次郎さん、三平君、ヨっちゃん、タカちゃん、ミチコさん、タダシさん、フサちゃんなど懐かしい友達たちの名前を挙げている。最後は、「もしかして、本当に久恒さんは、あの『ケイちゃん』でしょうか」との問いかけだ。ゆういっちゃんの母親が「本を何冊も出している久恒啓一というのは『ケイちゃん』ではないか」と連絡してきて気がついたとのことだ。小学校の時に中津市から大分市に移っていったあの「ゆういっちゃん」であることは間違いない。裕一という名前の漢字も知らずに、そして樋口という苗字も知らずに、毎日遊んでいたわけだ。2年ほどまえに、樋口裕一という人が書いた本がベストセラーになったときに本を買った。経歴をみて「大分県出身」とあったことは記憶にある。それと幼馴染のゆういっちゃんとは結びつかなかった。インターネットで写真を見つけたが、あの子どもの頃の顔が40数年経つと進化(?)してこういう顔になるのだなあと合点がいった。彼の方は、「あの時代は自分にとっては特別な時代だった。そとでよく遊びまくった」と述懐している。私の方も九州に帰省するたびに、ゆういっちゃんの家があったところを過ぎるときに、「どうしているのかなあ」とふと思い出すことがあった。本日(金曜日)、東京に居る彼と電話でしばらく話したが、懐かしい知己に会ったように話が弾んだ。来週、東京で食事をすることになった。
2006/08/11
コメント(4)
-
大崎市行政改革推進委員会
宮城県でも市町村合併の嵐が吹き荒れた。合併劇が繰り広げられ、新たに誕生した市は生き残りをかけて新たな出発を模索している。県内では、栗原市、気仙沼市、石巻市、加美町、そして大崎市などが誕生した。大崎市は人口約13万9千人。面積は79,676haというから広大である。古川市、松山町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町、田尻町、三本木の1市6町が合併してできた大崎市は、大崎地方、大崎平野、大崎耕道などと昔から表現されていて、新市の名前としてはおさまりがいい。古川市:交流と連携でつくるはつらつ家族都市田尻町:思いやりと健康の里松山町:花と歴史の香るまち鹿島台町:瑞・華・翠21プラン いきいき安心鹿島台三本木町:輝く緑、光る川、花薫る町岩出山町:自然と共生 心豊かにくらすまち鳴子町:ゆっくり・ゆったり・くつろぎの里先日、この大崎市の助役と行革課長らが見えて、大崎市行政改革推進委員への就任を要請された。大型合併自治体の運営には大変なエネルギーが要求されるだろうが、行政の仕事がスムーズに流れるように設計することが大切で、庁内の混乱と渦巻くエネルギーを未来のために結集するには絶好の時期であると考え、引き受けることにした。古川市時代、農業審議会や産業活性化関係の仕事をした経験から考えると、今度の仕事は、住民満足志向、政策プライオリティ、コミュニケーション戦略がキーワードになると思う。大崎市の事例を深堀りしながら、この国の未来を考えてみたい。
2006/08/10
コメント(2)
-
「希望のニート」
NPO法人知的生産の技術研究会の機関誌「知研フォーラム」8月号が届いた。170頁の大作だ。通巻290号というから気の遠くなるような年月発行し続けていることになる。今号は、「生き方特集」と「ロシア特集」である。テーマと書き手もバラエティに富んで読みごたえがある。生き方特集・「希望のニート」 二神能基・「心豊かに 私 を生きる」 井久保伊登子・「家庭教育---心の躾」小島典子・「ある女性の波乱の生涯」近藤節夫ロシア特集・「ソ連崩壊とロシア政治史のサイクル」鈴木博信・「覇権国家 ロシア の本質と民族性」近藤節夫・「ウクライナ、ダイナミックに暮らす人びと」小野元裕二神さん(NPO法人ニュースタート事務局代表)の講演録から・レンタルお姉さんは半年で9割くらいの若者を落とす・若衆宿での集団生活・潔癖症は競争生活で自然に治る・昼夜逆転は、四国お遍路を歩かせると3日で治る・行徳の新居浜通りで1週間3種類以上の仕事をさせる・一番好きな職業と聞かずに、一番いやな仕事は?と聞いていく・ニートの子どもは介護などに非常に向いている・人材派遣会社株式会社スローワークを設立・「べつに族」が欲しいのは「根性」・人の役に立ちたいという願望が非常に強い・格差社会ではなく、選択肢の多い社会・体罰はしない・韓国、ローマ、シドニー、マニラに拠点8月の知研のセミナー 夏も各地でセミナーがいくつもある。・東京:8月28日 「日本の方に伝えたい いろいろなこと---途上国に生まれてよかったと思うこと」 講師:金容善(韓国ビジネス評論家) 場所:商工会館6F大会議室(虎ノ門) 参加費:2000円・大阪:8月24日 「ビジネス脳を鍛える電車力トレーニング」 講師:野村正樹(作家) 場所:大阪産業大学・梅田サテライト教室 参加費:2000円・名古屋:8月24日 「起業を考えるとき」 講師:神田善郎 参加費:2000円・福岡:8月24日 「図解思考塾」 場所:NPOボランティア交流センター 参加費:1000円
2006/08/09
コメント(0)
-
教授たちの教育能力開発のための研修会
大学ではFaculty Development(FD)という教授たちを対象とした研修会がある。FDは教育についての能力開発という意味である。私の勤務する大学でも今年で3度目になる全学FDの真最中である。全体会と共通教育部会で丸一日。各学部と大学院で一日、3学部あるので計3日。全体部会では、第一部は大学評価・学位授与機構の荻上紘一教授による「これからの特色ある大学教育のあり方」というテーマの講演。荻上先生は、東京都立大学総長を経て公立大学協会会長を歴任された方。私は座長をつとめた。「公立大学は国立大学とくらべて文部行政に関する情報収集力とプレゼンテーション力が弱い。大学の目的の明確化を。認証機関評価は教育の視点からの評価で質の保証と改善とその公開が重要。現代GP・特色GPなどは申請することによる効果が大きい。組織としての教育力向上のための教員組織の変更(教授・准教授・助教)、役割分担・連絡体制・責任の所在。、、、。第二部は、東北大学大学院教育情報学研究科の三石助教授による「e-leraning」というテーマの講演。午後の共通教育部会は、「リメディアル教育」「導入科目」「外国語教育」「情報リテラシー教育」についてそれぞれの担当教員によりプレゼンテーションがあり、討論を行った。9日は事業構想学部部会と事業構想学研究科の部会がある。
2006/08/08
コメント(0)
-
話題の書二冊
話題になっている書を読んでいる。--------------------------------------「大地の咆哮---元上海総領事が見た中国」(杉本信行) 岡本行夫氏の解説 ・現在の中国を分析するものとして世界中で書かれた多くの著作のうちでも屈指のもの、、。 ・中国の特徴や、抱える問題の淵源が、スルスルと、こんがらがった糸がほどけていくように、 ・日本政府の担当者が、中国の反応を気にせずに叙述した初めてのものでもある。 目次から ・北京研修時代 ・瀋陽研修時代 ・中国課時代 ・在中国大使館勤務時代 ・台湾勤務時代 ・在中国大使館勤務時代 ・上海総領事時代 ---------------------------「終戦後日記--頑蘇夢物語」(徳富蘇峰) 明治・大正・昭和を通じて活躍した言論人で歴史家、 徳富蘇峰が終戦直後から綴った日記をを初公開。 無条件降伏への憤り、昭和天皇への苦言から 東條、近衛ら元首相への批判と 大戦の行動を見誤った悔悟の念を赤裸々に明かす。 主な内容 敗戦空気濃化と予・陛下の玉音放送を謹聴して・敗戦の原因・戦争犯罪者と戦争挑発者・ 日本は侵略国に非ず・陛下のマ元帥訪問に思う・驚くべき日本上下の急豹変・ 御退位問題の核心・対米従属の日本政府・日本精神の破壊・あきれた軍人の火事場泥棒・ 予の一大懺悔・近衛公に対する期待と失望・明治節に暗涙禁ぜず・日本人たるを恥じる・ 東條と予、、。 御厨貴(解説者) ・四百頁を優に超える蘇峰の日記を、一気に一晩で読み終えた。あたかも蘇峰百年の気迫に一 挙に寄り切られたの感がある。 ・「なぜ、 あの戦争 に負けたのか」を、日々追及する試みに他ならない
2006/08/07
コメント(2)
-
石ノ森漫画館
石巻市にある「石ノ森漫画館」への訪問は二度目である。もちろん、郷土が生んだ漫画家・石ノ森章太郎を記念した建物であるが、誕生の地に建つ記念館が石ノ森章太郎個人に焦点があたっているのに対し、こちらは個人はもちろんだが、漫画そのものに重点をおいてある。石巻市は漫画をキーワードとした街づくりを行っており、この漫画館はその中核施設である。まず、アニメ映画を観たのだが、そのホールの入り口の壁に、石ノ森漫画主人公曼荼羅図が掲げてあった。石ノ森章太郎が生み出した多くの漫画の主人公たちが一枚におさまっている珍しい絵である。曼荼羅では中心は大日如来であるが、その場所にはサーボーグ007がおさまっていた。企画展では、石ノ森章太郎の漫画物語とそれが映画になったポスターなどが並べてあった。「佐武と市捕物帳」は、佐武が三浦友和、市は梅宮辰夫である。名取裕子も出ていた。「HOTEL」はTBSで今でもテレビドラマをやっているが、これも彼の作品だった。ビッグコミックで1984年から1998年まで連載した漫画がテレビドラマになったのである。主人公の赤川一平は高嶋政伸、支配人東堂克生は松方弘樹、大原社主は丹波哲郎というあのドラマだ。「化粧師}(けわいし)では、菅野美穂、いしだあゆみ、田中邦衛、柴田理恵などが出演している。「化粧とは外見を装いつつ心を美しくすることなり」。漫画家の巨匠たちの石ノ森章太郎評が面白い。・さいとうたかお(1936年生まれ) 「お前(石ノ森)は天才、オレは職人」 「絶え間なく本を読んでいる。知識欲・探究心」 「一つ選ぶとすると、九頭竜」・ちばてつや(1939年生まれ) 「一つ選ぶとすると、ファンタジーワールド」・矢口高雄(1939年生まれ) 「類まれなる画質と美的センス、それが萬画を生んだ」・里中満智子(1948年生まれ) 「創作以外の面でもマンガ界のためにひたすら尽くした人生だった」 「あらゆる分野で、自分こそは石ノ森さんの一番の友人と思っているだろう人は数え切れないほ ど居る」文章では言葉を自由にたくさん使えるが、漫画というメディアは、少ない言葉でエキスを伝えなければならない。だから常に本質に迫るという知識の吸収の仕方をしなければならない。中途半端な理解のままでは恐くて描けないのではないだろうか。図解に似ているところがあると感じた。石ノ森章太郎は、宇宙、自然、時代物、科学、刑事ものなど、あらゆる分野を描いている。漫画という表現手段を用いて世界を征服しようとしたのではないだろうか。今回の発見は、「学習漫画」というジャンルがあることだった。そして各界の著名人たちが監修などの名目で力を貸しているのに感銘を受けた。入門は漫画でよいのではないか。・「学習漫画・日本の歴史」(責任編集・考証 前東大教授笠原一男) 「学習漫画・世界の歴史」{監修 木村尚三郎) 「学習漫画・宇宙の歴史」「学習漫画・中国の歴史」・マンガ・日本の歴史 マンガ・日本の古典 「奥の細道」(矢口高雄) 「徒然草」(バロン吉元) 「古事記」(石ノ森章太郎)・マンガ・世界の文学 「赤と黒」(里中満智子)・MANGAゼミナール古典入門 「奥の細道」(赤塚不二夫) 「平家物語」(赤塚不二夫) 「今昔物語」(赤塚不二夫)・学習まんが人物館シリーズ 「南方熊楠」(監修 荒俣宏) 「キュリー夫人」(監修 竹内均) 「日本の歴史・人物事典」(監修 笠原一男)・まんがで学習 ことわざ事典・学習漫画 スポーツ偏 「少年野球」投手編・守備編・ 「少年サッカー」 「アスケットボール」・学習漫画 「病院のしくみ」 「警察のしくみ」 「テレビ局のしくみ」・学習漫画 「素晴らしい世界遺産、、」(監修 吉村作治)一口に漫画といっても実に世界が広い。漫画界は、あらゆるものを漫画で表現し尽くそうという志を持っているとみた。
2006/08/06
コメント(2)
-
布施辰治(石巻文化センター)
2年ほど前に、河北新報で布施辰治という名前を見かけた。私にとっては懐かしい名前である。高校2年生のとき、岩波新書の「ある弁護士の生涯」という本を読んで、布施辰治という人物の生き方に感動した。私はこの時点で進路に決断を下した。法学部に行って弁護士になろうと決心したのである。このときの姿を母は「朝の厨に貧しき人のため弁護士になると吾子は告げに来」と短歌に詠んでくれている。私はその後法学部に進む。しかし、結果的には弁護士にはなれなかったが、この人物と書物が人生の進路に影響を与えたことは間違いない。河北新報の記事によると、布施辰治(1880--1953)は宮城県石巻市蛇田の出身の人権派弁護士で、韓国政府から日本人初の「韓国建国勲章」(平成16年)を受けたとのことで、その後たびたび紙面にとりあげられ、ようやく布施辰治の常設コーナーがある石巻文化センターを訪問した。センターの隅に布施辰治の小さな展示コーナーがあった。石巻市は布施辰治顕彰会と家族から5000点の資料を寄付され、このコーナーをつくった。明治法律学校を卒業した布施辰治は、農民、労働者、借家人、朝鮮人という弱者の側に立って生涯にわたって活動を行った。法律家・思想家・社会運動家として生きた布施辰治の座右の銘として次の言葉が紹介されている。 「生きべくんば民衆とともに、死すべくんば民衆のために」 「正しくして弱き者のために余を強からしめよ」また、「敬天愛人」の本人自筆の書もある。この言葉は、江戸時代の大儒佐藤一斎の言葉であり、西郷隆盛などが座右の銘としていたが、布施辰治もこういう心持で人生を生きていたのであろう。布施辰治の遺品は、朝鮮建国憲法草案私稿、表札・印鑑セット・硯箱セット・法衣・写真・法帽・弔辞・松川事件訴訟趣意書、、、。22歳:判事登用試験合格、宇都宮地裁、25歳:トルストイに傾倒、26歳:東京市電値上げ反対騒擾事件弁護、37歳:普選運動を始める、38歳:米騒動弁護、39歳:万歳事件、41歳:自由法曹団結成、42歳:借家人同盟結成、43歳:朝鮮に渡る、46歳:日本労働組合総連合会長、52歳:弁護士除名、60歳:プラカード事件、69歳:三鷹事件弁護団長、松川事件、71歳:公安条例廃止運動、72歳:血のメーデー事件、大阪吹田事件、73歳:内臓ガンにて死去。伝記によれば間引きされる運命にあったが、早産で産婆が間に合わず、生まれてしまった布施辰治は、人生を意義あらしめることに人一倍信念を注ぐことになったのである。布施辰治は、法廷の戦士から、社会運動の闘卒へと向かう。個人の救済から社会の改造へと、弁護士活動を拡大して行った。・朝鮮と中国のような第一級の文化を持つ国民を武力で鎮圧してはならない。・徳で統治すれば栄え、力で統治すれば滅びる。・彼らの法律で彼らを縛れ。・弁護士活動を前進させ、社会運動の一兵卒となる。・自由を奪われた者は自由を奪い返す為、食物を奪われた者は食物を奪い返す為、闘わざるを得ない布施辰治研究の第一人者である森正・名古屋市立大学名誉教授によれば、弁護士の使命は「人権の擁護と社会正義の実現にある」と明記されており、弁護士法第一条に一貫して忠実であろうと苦闘したと述べている。足跡の幅の広さ、重さ、権力との長きにわたる緊張関係、その密度の濃さ等から布施は弁護士群像のシンボル的存在としている。布施の人権思想は、自由民権思想(あらゆる思想に寛容であるべきとするヴォルテール的発想)、東洋思想(論語、陽明学)キリスト教(キリスト教的人道主義)、初期社会主義思想、トルストイ思想(人間の価値と尊厳性を重んじ、良心を信じる)の5つの思想によってなりたっている。石巻文化センター調査研究報告の「奥の入会紀行」を読む。・空想や妄想に放散することを戒める思索訓練法・今度の旅行は、そういう入会権事件の研究を徹底して、私の残生を捧ぐべく決心した・四時起床、、、、六時まで日記を書く、・昨晩はどうしたものか、大杉栄氏の夢を見た。・床上運動を一時間ばかりやってから起きた・私はどんな所にも、何時でも眠られる、、、関わった事件の概要・プラカード事件 1946年5月19日の食糧メーデー 「朕はタラフク食ってるぞ、ナンジ人民飢えて死ね」という プラカード文面が不敬罪起訴・三鷹事件 1949年7月15日 無人電車が暴走、駅前の民家に突入、通行人6人が即死、20余人が重軽傷 吉田茂首相は、共産党の行為と断定 国鉄労組9人逮捕・松川事件 1949年 脱線転覆で乗務員3人が即死 最高裁差し戻し判決で全員無罪・血のメーデー事件 1952年5月1日 死者2名、負傷者1500名。1232名が逮捕。 最高裁で全員無罪--------------------------------------------------------私が写真を撮ったり、メモをとったりしていると、受付の女性が詳しく知りたければ学芸員を呼びましょうかと提案してくれた。学芸員は資料を見せてくれて説明をしてくれた。布施辰治は、日本による植民地統治下の朝鮮で数多くの独立運動家の弁護活動を無償で引き受けている。第二次大戦中、ユダヤ人難民を多数救った外交官杉原千畝になぞらえて「日本人のシンドラー」とも呼ばれる。しかし母校の明治大学法学部の韓国「建国勲章」受章記念シンポジウムで、布施辰治先生人権平和記念事業会代表者は、ドイツ人・シンドラーには布施辰治のような深い哲学とこれを実践するだけの勇気がなかったと語って、シンドラーは布施の足元にも及ばないと述べている。また、日本人でありながら、日帝の監獄で闘い、弁護士資格まで剥奪され、三男・杜生(京都大学生)を獄中で失うという辛酸を舐めたと韓国側からの評価を述べてもいる。2003年7月に叙勲が決まったが、日韓関係の政治的配慮から、政府通商外交部の2度にわたる保留措置がとられた。関係者の努力により2004年10月15日にようやく、「韓国の自主独立と国家発展に資したところが大きいので」盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領から受賞した。この代表者は、大局的見地から日韓両国の教科書に布施辰治の偉業を載せるべきだとも提言している。東アジアの緊張緩和のためにも、この布施辰治という人物の行った業績をもっと多くの人に知ってもらうべきだと感じた。日韓関係が必ずしもよくない中、この布施辰治の功績はもっと輝かせるべきだろう。
2006/08/05
コメント(2)
-
劇団わらび座ミュージカル「棟方志功 炎じゃわめぐ」 仙台公演
秋田県の田沢湖芸術村に本拠を構える劇団わらび座のミュージカル公演を観るのは今回で3度目である。仙台のイズミティでの「アテルイ」、秋田のわらび座の劇場で見た「宮沢賢治」、そして今回の「棟方志功」だ。わらび座のテーマは常に東北を意識していて、ミュージカルとしての質の高さもあり、私はファンになった。棟方志功については、青森の記念館の2度の訪問、県美術館で行われた展覧会にも行っているが、毎回何かしら発見があり、志功像が膨らんでいくのが楽しみとなっている。因みに、73歳で逝った志功の墓碑はゴッホと同じ形に作られている。棟方志功を演じたのは安達和平。わらび座生まれのわらび座育ちの看板俳優。「アテルイ」でも主役を演じたのを観た。妻・チヤを演じたのは秋田県出身の阿部佐和子。達者な演技だったが、どこかで見た記憶があると思ったら、「一人芝居」で観たことがある女優だった。この作品は志功がチヤの愛情に支えられて世界のムナカタになる過程を描いた夫婦の物語である。舞台となった県民会館は、7割がた埋まっていた。劇団四季のあたりでは仙台でもロングラン公演も満席続きだが、わらび座ももっとファンがついてもいいと思う。ねぶたの囃子と、成功した志功のニューヨークで公演での挨拶のシーンから始まる。 腕や技術よりも、心や魂が大切だ 他力 神や仏が助けてくれる 魂が武者震いする 私は私ではない 命のある限り絵を描こう わだばゴッホになる ゴッホの作品の中に日本の浮世絵の影響があった。それは広重の版画だ。「大和美し」から始まった運命の出会いである柳宗悦との邂逅シーンも良かった。「人は人によって人となる」(斉藤実)という言葉を連想した。この柳宗悦という名前も日本近代の人物を訪ねているときによく出会う。白州正子の師でもある日本民芸の紹介者。この人物のことも調べる必要がありそうだ。「腕や技術よりも、心や魂が大切だ」は、日本画の横山大観、たたら製鉄村下(むらげ)の木原明さんと通じる考え方だ。
2006/08/04
コメント(2)
-
顧客の視点
どのような業態においても顧客は、表面上は神様扱いである。小売業においても、交通業においても、医療業界においても、そして行政においてすら「顧客」は建前上は大切にされていることは疑う余地はない。しかし、私たちが実際にレストラン、眼鏡店、タクシー、病院、役所などで所用を足そうとすると、顧客としての自分を大切に扱わないことに憤る毎日となる。レストランでは、他に客がいないのに、注文を取りに来ない、聞き違えが多い。眼鏡店では若い女性店員が専門用語を使うが、こちらは全く理解できない。タクシーに乗ると、他のライバル会社のサービスを知らないのでこちらが教えてあげる羽目になる。専門病院の集積で総合病院を名乗る病院では患部のみに関心のある医者がとんちんかんな薬をだす。一人ひとりに悪気はないのだが、全体としては腹立たしいことを経験することが多い。独占・寡占業界以外は、いつの間にかお客が減っていく、ますます顧客に関心が薄れてサービスが悪くなるという悪循環に陥っている企業が多い。いったいサービスの全体を見ているのは誰なのだろうか。病院を例に挙げてみよう。まず、大勢の患者がいる。見舞いの家族や職場の同僚がいる。そして医者がいる。看護師がいる。レントゲン技師、薬剤師、会計部門、掃除人、食堂従業員、ショップの販売員、、、、など様々な職種の人々が働いている。しかしどの仕事をしている人も、病院全体の動きを知っている人はいない。それぞれが部分的に病院に貢献しているのだ。患者はどうか。患者は医者の動き、看護師の応対、掃除の回数、食堂のメニュー、ショップの品揃え、患者相互の情報交換、家族から入ってくる病院の評判などを総合的に見ることができる立場にいる。患者は全てを体験している。だから一人でなく、全体の患者が見る姿は、働いている人たちより視界が広くかつ正確である。だから、顧客の視点は、組織にとっては本当に神の視点なのである。しかし顧客を大切にすることは、「言うは易く行うは難し」でもある。組織の中ではいつの間にか供給側の感覚が身についてしまって、「客を教育せよ」などという暴言が飛び交うことになる。顧客の視点を身につけると、確かに全体が見えるわけだから組織の内部でも人を納得させることが多くなる。心したい点である。
2006/08/03
コメント(0)
-
今日の訃報から--昭和2年生まれのそれぞれの人生
今日の新聞では、訃報が目についた。88歳の鶴見和子(政治家・後藤新平の孫、政治家・鶴見祐輔の娘、哲学者・鶴見俊輔の姉) と79歳の吉村昭。吉村昭は、「戦艦武蔵」「天狗争乱」「破獄」などで知られる歴史作家。大仏次郎賞、太宰治賞、菊地寛賞、読売文学賞などを受賞している。妻は作家の津村節子。「同世代で同じような経験をしていて、ひどい目にも遭っただろうけど、ついぞそういう話をしない人でした」(城山三郎)79歳というと昭和2年生まれである。「昭和2年生れの会」というのがあると、同じく現在79歳の野田一夫先生から時折聞くことがあり、西武百貨店の堤清二(作家としての辻井喬)、作家の城山三郎、タレントの植木等などとの交遊を面白く話してもらっていた。野田先生は生涯2度ホールインワンを経験している。2回目は70歳のときに宮城大学学歌の作詞作曲をした小椋圭さんが大学に講義に見えて一緒に回った時(泉パークタウンゴルフ倶楽部)であり、1回目が50歳の時に、城山三郎さんとまわった時だそうだ。野田先生は運が強い。植木等さんはゴルフ場では、人格者で気遣いの名人だそうで、顔が似ているので野田先生はゴルフ場では植木等の兄ということで通していて、キャディーは本気にしていて「植木さんより兄さんの方が面白い」と笑いころげていたそうだ。私の母も昭和2年生まれなので、この世代が過ごしてきた時代環境やものの見方がなんとなくわかる気もする。ということで、昭和2年生れにはどういう人がいるのか調べてみたのが下記のリストだ。それぞれの分野での重鎮が多い。藤沢周平などすでに鬼籍に入っている人もいる。 勅使河原宏 映画監督 織本順吉 俳優 ユーベル・ジバンシィ 服飾デザイナー 植木等 タレント 石牟礼道子 作家 北村和夫 俳優 関根潤三 プロ野球選手 宮城まり子 歌手 利根川裕 作家 無着成恭 教育者 神代辰巳 映画監督 吉村昭 作家 北杜夫 作家 飯干晃一 作家 島桂次 NHK会長 緒方貞子 国連難民高等弁務官 ピーター・フォーク 俳優 加山又造 画家 ロジャー・ムーア 俳優 童門冬二 作家 喜味こいし いとしこいし 漫才師 山内溥 実業家 江藤俊哉 ヴァイオリン奏者 長谷川慶太郎 経済評論家 藤沢周平 作家 堤清二 経営者 作家
2006/08/02
コメント(4)
-
夏の計画
梅雨が明けないまま、8月に入った。今、夏の計画を立てている。毎年、年始に年度の計画を立てるが、連休と夏は別途やるべきことを書き出しておくのが習慣となっている。何事も無計画では実現はしない。書き出すことによって、意識の中にやるべきことがイメージを結び、具体的な行動をうながすことになる。計画と考えると「実現しなければならない」と窮屈になるから、私は「希望を述べる」という風に考えることにしている。3割できたらもうけもの、である。気楽にいこう。今年は、下記項目で書き出してみた。・後期の講義準備・本の執筆・人物記念館の旅・スポーツ・旅行・読書・書斎の整理・機器購入
2006/08/01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1