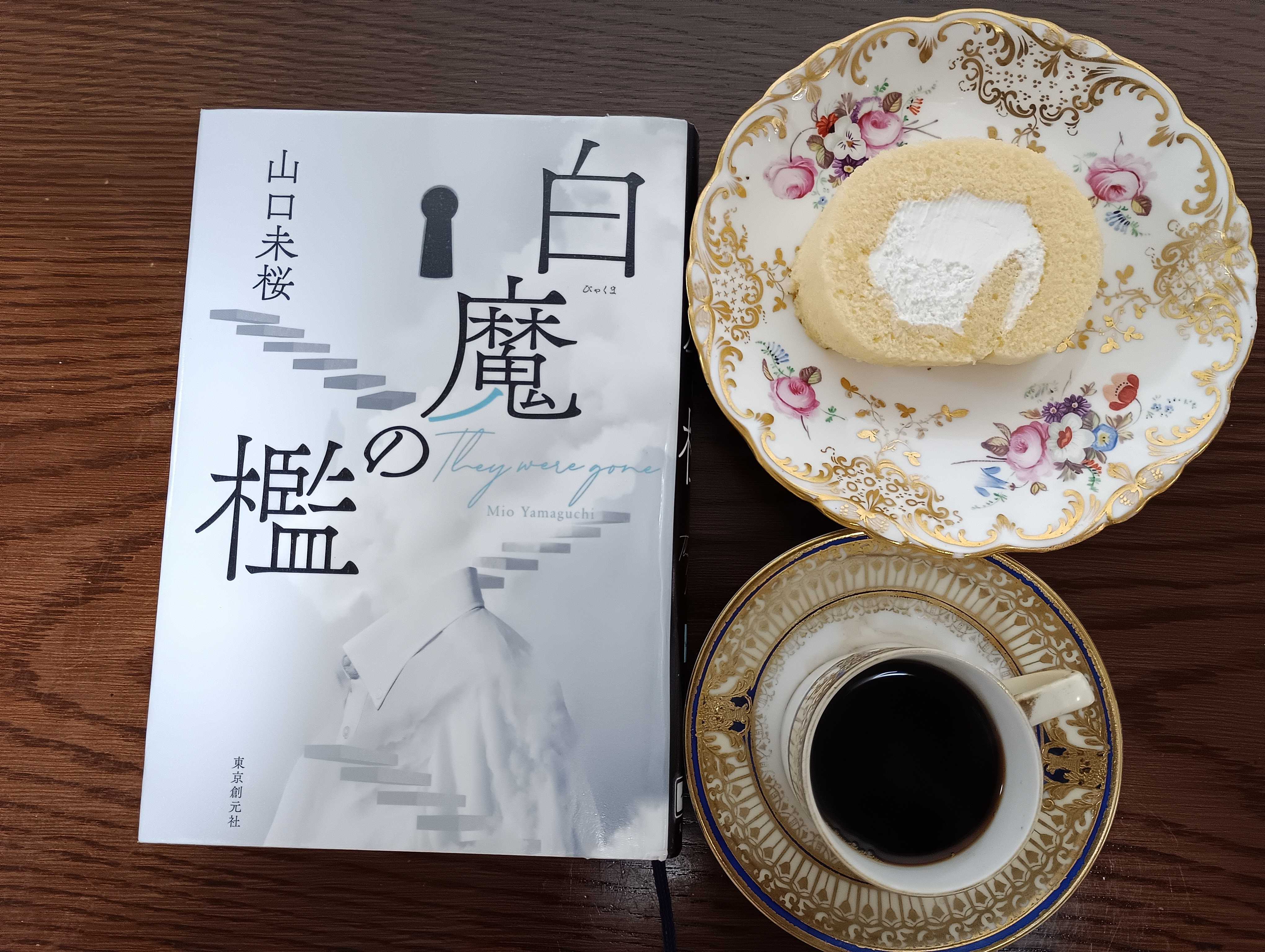2010年01月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
映画「おとうと」-山田洋二は市川崑が師匠、吉永小百合は女・笠智衆を目指す
昨日に引き続き映画を観る。今日は日本映画で「おとうと」。原作は、幸田文。http://www.ototo-movie.jp/日本の家族のあり方をずっとみせてきた山田洋次監督が描く可笑しくて哀しい物語。山田監督はパンフの挨拶に「家族という厄介な絆」というタイトルをつけている。「作り手と観客の間で、人々の暮らしのあり方が共有しにくくなった。だからこそ、現代の理想的なモデルを問うてみた」。主演の姉吟子役は吉永小百合、弟役は鶴瓶で、どちらも好演している。笑いと涙の物語である。山田監督が敬愛する、同じ「おとうと」という最高傑作を残している市川崑監督に捧げる作品である。吉永小百合は「母べえ」でも日本の母を上手に演じているが、役づくりへの取り組みについて次のように語っている。また、女・笠智衆を目指していることもわかった。「ロケ地を歩いたり、電車に乗ったりするのは、私の役作りでいちばんのかなめかもしれません。どんな場所で、どんな風に吹かれて、どんな暮らしをしているのか、それを肌で感じるためには。その人が暮らす場所を訪ねて、見学したり、調べたりします。ぱっと役になり切れるタイプではないものですから。」「笠智衆さんを目標にすることでした。、、男女の差はありますが、笠さんならどう演じられるだろうと考えました。、、いつもその微風のような立居振舞に、すごいなと感心していました。、、笠智衆さんを目標にしている自分がいるというのは、感慨深いものがあります。テレビでみる鶴瓶にはあまり感心はしていなかったが、今回のおとうと鉄郎の演技は見事だった。音楽は山田洋次監督作品の常連である富田勲さんだった。鉄平にはトロンボーン、吟子にはフルートを使っている。「吟子の清純さにはフルートを、鉄郎の憎めない滑稽さにはトロンボーンの音色を」と決めた事情を述べている。映画における音楽の役割もわかるインタビューである。富田先生と久しぶりに飲みたい。「つながった映像を観たときから、トロンボーンでいこうと決めていました。トロンボーンの持つおおらかさというのかな、優しくて滑稽な感じが鶴瓶さんのキャラクターに合う気がしたんです。しかも一部分の音じゃなく、最高音から最低音までの全部を使って、鉄郎の憎めないところを表現しようとしました。」「吉永さんの吟子にフルートを当てるというのも無理なく出たアイデアです。ヴァイオリンだと表情が豊か過ぎちゃうし、リコーダーだと少し色が付いちゃうでしょう。吟子の清純さにはやっぱりフルートかな。トロンボーンの音色もフルートがあったから際だったのかな。」「僕としては吟子と鉄郎の文字には書けない部分をある程度、音楽の側から表現できたかなって思っております。」
2010/01/31
コメント(1)
-
乱造が多いビジネス書の将来の方向性(手軽に作らない)を示す好書
「ビジネス書大賞BIz-Tai」(デュスカバー21)が送られてきた。新しく創設されたアワードで、ビジネス書を「ビジネスパーソンにとって学びや気づきがある本」と定義し、体裁やジャンルにはこだわらないとスタンスを広くとっている。書店、ブロガー、出版社、マスコミの70名が選考委員となっている。一次選考では、選考委員が5冊を選び、順位を決め、二次選考では、インターネットやTwitterによる一般投票で順位を決定するという選び方だ。「大賞」「出版社賞」は「ブラックスワン」(なシーム・・ニコラス・タレブ)、「書店賞」は「成功は一日で捨て去れ」(柳井正)、「読者賞」は「起きていることはすべて正しい」(勝間和代)、「マスコミ・ブロガー賞」は「不透明な時代を見抜く「統計思考力」(神永正博)、「新人賞」は「「20円」で世界をつなぐ仕事」(小暮真久)が結果だ。この選考に私の本もノミネートされていたことを初めて知った。全国紙書評担当という肩書きの人物が昨年7月に出した「KOKOROZASHI 志」(ディスカバー)を推薦してくれており、この本の価値をよく理解してくれている紹介だったので嬉しく思った。初版も多く刷り期待の一冊だったが、思ったほどは売れていないが、見ている人は見ていると心強く感じた。「著者が全国の偉人たちの資料館や博物館を巡る旅で見つけた名言を拾い上げる。偉人伝や名言集は多くあるが、この本は類似書とは根本的に違う。名言の元ネタがコピペではなく、偉人たちの地元で、学芸員たちが「郷土の英雄の業績を」と丹念に探し出したものだけに、偉人への思い入れが全く違うからだ。ありきたりな名言集に現地取材という手のかかる要素を盛り込むことで新しい書籍の魅力を切り開いた。乱造が多いビジネス書の将来の方向性(手軽に作らない)を示す好書。」今日は昼食を兼ねた大学院の教授会があり、それを終えて、夕方から、評判になっている映画{アバター」を観た。1997年の「タイタニック」で爆発的なヒットを記録したジェームズ・キャメロン監督の新作で、封切り後わずかな時間で、その記録を抜いたという作品である。キャメロンは、「ターミネーター」、「エイリアン」、「アビス」、「ランボー・怒りの脱出」、などの作品もつくったやり手である。1954年生まれ。ストーリー自体は、スリル、戦闘シーン、未開人と文明人の戦い、ハッピーエンドの結末、などで目新しい内容ではない。この映画を観るには、特殊なメガネをかける。そうすると画面が3Dの立体映像となってみえるという趣向だ。確かに大いなる自然や、戦闘シーンなどは迫力が全く違う。十数年前にフロリダのディズニーワールドで観た3D映画を思い出した。この作品が大ヒットを続けているのは、3D技術を活かせる内容であるからだろう。「子供の頃、ありとあらゆるSF小説を読み漁っていた。アバターは、その集約なんだ」というキャメロンは、もう3D以外の映画をつくることに興味を失っている。3D技術は、新しい世界を拓いたことは間違いない。
2010/01/30
コメント(0)
-
「山本冬彦コレクション展」--「多感のすすめ」が気に入った
10時半から九段サテライトで、朝日新聞出版の「大学ランキング」という本の寺島学長取材に立ち会う。「大学ランキング」は、毎年出る厚い本で、様々の観点から全国の大学をランキングする。一大学のトップという立場ではなく、大学業界や教育世界について詳しい識者としてのステイタスでのインタビューである。「日本の大学の問題点、課題」「教育環境」「教員の評価」「教養」「学力問題」「保護者対応」などがテーマだった。「グローバリズムに対応したMBAや法科大学院に対する反省期に入っている」「「時代の課題に向き合う」「教師が戦っている姿を見せる「「異質の交流」「気づきと誘発」「適切な規模感」「大学毎の共通テーマが大学を教員の教育力を鍛える」「大学自体の社会との関連性が問われている」「自立した大人へのプロセスを導く」などが学長の語ったキーワード。多摩大の取り組みなどを交えて一時間のインタビューとなった。インタビュアーの小林哲夫さんから「多摩大のホームページは凄いですね!」と言われた。「大学ランキング」の前任の清水さんは予定通り、バルセロナで豆腐屋を開いているとのことだった。2月に出る日経ビジネスの「大学特集」からも、教育界全体に対する見識を持っているということで、学長への取材も予定されている。今後、多摩大学長としての肩書きでのメディアへの登場が多くなってくるだろう。終了後、いくつかの報告と相談をする。12時からは昼食を食べながら今年最初の戦略会議。学長の「2010年年頭所感と方針」、「入試状況と就職状況」の報告がメイン。学長室長の私が司会。学長室からは「多摩大学ホームページリニュアルの前と後のアクセス等状況比較」という資料を説明した。昨年7月1日にリニュアルしたホームページ(学長室担当)の実績の分析を数字で報告。1-6月と7-12月の半年比較。「総閲覧ページ数は2.4倍に増加」「アクセス数は約1万人増加」「以前は一回のアクセスにつき2ページ弱しか見られていなかったが、4ページ近くに倍増」「直帰率は7割から4割に大きく下がり複数のページを見てもらえるようになった」「サイト滞在時間は二倍近く伸び、じっくり見てもらえるようになった」「新規訪問者は13%増加」。様々なページ(広く)を、じっくり(深く)見てもらえるようになったと報告。http://www.tama.ac.jp/14時に予定通り終了したので、新宿の佐藤美術館で開催されている「山本冬彦コレクション展」を見に行く。山本さんはサラリーマン勉強会業界では有名な人で、若いときからメディアにも多く登場する人であり、「知的生産の技術」研究会で活動する私とも接点があった人だ。大東京火災で長く勤務した後、あいおい損保の理事、国立大学事務・経営センター監事を経て、現在は放送大学の理事をしている。30年間に美術品コレクターとして1300点を集めたが、今回のコレクションはそのうち160点を展示するという企画である。最近出した「週末はギャラリーめぐり」(筑摩新書)はそういった軌跡と主張を述べたものだが、とてもいい本だった。「有名作家から現役の美大生の作品まで、70代から20代まで幅広い作家」の作品であること、「情報のない展覧会」であり作品のみで判断してもらいたいこと、これが山本さんの想いである。そして「鑑賞者の目」と「コレクターの眼」を通じてアートを体験して欲しいという趣旨だ。この企画展は、日経新聞でも紹介されていたし、今後NHKでも放映されるそうだ。小さい作品が多い、そして人物画が多い。ずっと見ていくと確かにコレクターである山本さんの「眼」を意識する。私が気にいったのは、阿部清子「多感のすすめ」、斉藤裕紀「植物が囲む既視の風景」、寒河江智果「春らんまん」、三島祥「蝶々」、石踊達哉「昼下がりの夢」などだ。特に「多感のすすめ」は、少女の揺らぐ心が透いてみえる強い目ぢからの表情がいいと思った。一点だけ自宅に飾るとしたら、この作品だ。一枚、一枚を長い時間をかけて集めた山本さんの眼を感じる。コレクションとは表現行為であるという感を深くした。偶然だが、すぐ近くに「野口英世記念会館」があった。前から一度訪問したかったところだった。野口英世記念会が運営する会館である。野口英世記念医学賞、野口英世記念奨学金、などの資料が展示されている。野口英世の銅像やモニュメントは、161点もある。ニューヨークなどの外国から、日本では小学校、中学校、大学などに多い。母シカの手紙が涙を誘う。「おまイの。しせ(出世)にわ。みなたまけました。、、、。ドかはやく。きてくだされ。、、かねを。もろた。こトたれにもきかせません。それをきかせるトみなのれて(飲まれて)しまいます。、、いっしょのたみて。ありまする。、、ねてもねむられません、、」。野口は達筆で、油絵もうまい。渡辺淳一の野口の伝記「遠き落日」を読みたい。野口の伝記の嚆矢と言われる奥村鶴吉編「復刻 野口英世」(財団法人野口英世記念会発行)を購入し、読み始めた。出生から手の大やけどあたりを少し読んだが、胸が熱くなる。夕食は、都内に勤める娘と、同居中の息子と、わたしたち夫婦の四人で待ち合わせて、新宿の京王プラザホテルで摂る。過去のエピソード、今後のことなどを話題に楽しい時間を過ごした。----今日の一首 手紙にて 添削終えた 歌届く 歌人の母は 厳しくもあり
2010/01/30
コメント(0)
-
「山本冬彦コレクション展」--「多感のすすめ」が気に入った
10時半から九段サテライトで、朝日新聞出版の「大学ランキング」という本の寺島学長取材に立ち会う。「大学ランキング」は、毎年出る厚い本で、様々の観点から全国の大学をランキングする。一大学のトップという立場ではなく、大学業界や教育世界について詳しい識者としてのステイタスでのインタビューである。「日本の大学の問題点、課題」「教育環境」「教員の評価」「教養」「学力問題」「保護者対応」などがテーマだった。「グローバリズムに対応したMBAや法科大学院に対する反省期に入っている」「「時代の課題に向き合う」「教師が戦っている姿を見せる「「異質の交流」「気づきと誘発」「適切な規模感」「大学毎の共通テーマが大学を教員の教育力を鍛える」「大学自体の社会との関連性が問われている」「自立した大人へのプロセスを導く」などが学長の語ったキーワード。多摩大の取り組みなどを交えて一時間のインタビューとなった。インタビュアーの小林哲夫さんから「多摩大のホームページは凄いですね!」と言われた。「大学ランキング」の前任の清水さんは予定通り、バルセロナで豆腐屋を開いているとのことだった。2月に出る日経ビジネスの「大学特集」からも、教育界全体に対する見識を持っているということで、学長への取材も予定されている。今後、多摩大学長としての肩書きでのメディアへの登場が多くなってくるだろう。終了後、いくつかの報告と相談をする。12時からは昼食を食べながら今年最初の戦略会議。学長の「2010年年頭所感と方針」、「入試状況と就職状況」の報告がメイン。学長室長の私が司会。学長室からは「多摩大学ホームページリニュアルの前と後のアクセス等状況比較」という資料を説明した。昨年7月1日にリニュアルしたホームページ(学長室担当)の実績の分析を数字で報告。1-6月と7-12月の半年比較。「総閲覧ページ数は2.4倍に増加」「アクセス数は約1万人増加」「以前は一回のアクセスにつき2ページ弱しか見られていなかったが、4ページ近くに倍増」「直帰率は7割から4割に大きく下がり複数のページを見てもらえるようになった」「サイト滞在時間は二倍近く伸び、じっくり見てもらえるようになった」「新規訪問者は13%増加」。様々なページ(広く)を、じっくり(深く)見てもらえるようになったと報告。http://www.tama.ac.jp/14時に予定通り終了したので、新宿の佐藤美術館で開催されている「山本冬彦コレクション展」を見に行く。山本さんはサラリーマン勉強会業界では有名な人で、若いときからメディアにも多く登場する人であり、「知的生産の技術」研究会で活動する私とも接点があった人だ。大東京火災で長く勤務した後、あいおい損保の理事、国立大学事務・経営センター監事を経て、現在は放送大学の理事をしている。30年間に美術品コレクターとして1300点を集めたが、今回のコレクションはそのうち160点を展示するという企画である。最近出した「週末はギャラリーめぐり」(筑摩新書)はそういった軌跡と主張を述べたものだが、とてもいい本だった。「有名作家から現役の美大生の作品まで、70代から20代まで幅広い作家」の作品であること、「情報のない展覧会」であり作品のみで判断してもらいたいこと、これが山本さんの想いである。そして「鑑賞者の目」と「コレクターの眼」を通じてアートを体験して欲しいという趣旨だ。この企画展は、日経新聞でも紹介されていたし、今後NHKでも放映されるそうだ。小さい作品が多い、そして人物画が多い。ずっと見ていくと確かにコレクターである山本さんの「眼」を意識する。私が気にいったのは、阿部清子「多感のすすめ」、斉藤裕紀「植物が囲む既視の風景」、寒河江智果「春らんまん」、三島祥「蝶々」、石踊達哉「昼下がりの夢」などだ。特に「多感のすすめ」は、少女の揺らぐ心が透いてみえる強い目ぢからの表情がいいと思った。一点だけ自宅に飾るとしたら、この作品だ。一枚、一枚を長い時間をかけて集めた山本さんの眼を感じる。コレクションとは表現行為であるという感を深くした。偶然だが、すぐ近くに「野口英世記念会館」があった。前から一度訪問したかったところだった。野口英世記念会が運営する会館である。野口英世記念医学賞、野口英世記念奨学金、などの資料が展示されている。野口英世の銅像やモニュメントは、161点もある。ニューヨークなどの外国から、日本では小学校、中学校、大学などに多い。母シカの手紙が涙を誘う。「おまイの。しせ(出世)にわ。みなたまけました。、、、。ドかはやく。きてくだされ。、、かねを。もろた。こトたれにもきかせません。それをきかせるトみなのれて(飲まれて)しまいます。、、いっしょのたみて。ありまする。、、ねてもねむられません、、」。野口は達筆で、油絵もうまい。渡辺淳一の野口の伝記「遠き落日」を読みたい。野口の伝記の嚆矢と言われる奥村鶴吉編「復刻 野口英世」(財団法人野口英世記念会発行)を購入し、読み始めた。出生から手の大やけどあたりを少し読んだが、胸が熱くなる。夕食は、都内に勤める娘と、同居中の息子と、わたしたち夫婦の四人で待ち合わせて、新宿の京王プラザホテルで摂る。過去のエピソード、今後のことなどを話題に楽しい時間を過ごした。----今日の一首 手紙にて 添削終えた 歌届く 歌人の母は 厳しくもあり
2010/01/29
コメント(0)
-
応援の 試験監督 自らは 解けそうもない 問題くばる(今日の一首)
後期試験が今日から始まった。私自身は試験をしないで、日常の出席と最終レポートで成績をつけるというスタイルだ。「マネジメントデザイン2」のレポートの課題は、「私のロールモデル○○○○(例えば岡本太郎)の人生鳥瞰図」と「○○○○から学んだこと」(A42枚)の提出である。こういうレポートが200枚ほど届く予定。さて、試験をしない教員は同僚教員の試験を手伝うことになっている。今日は二科目を手伝った。まず、「財務会計2」という科目である。この科目は2年前の一緒の時期に専任教員となった金子先生の科目だ。「引当金」「負債性引当金武」「金融資産」「財務耕晴要素アプローチ」「固定資産の減損損失」「ファイナンス・リース」「外債建て取引」「一取引基準」「のれん」といった財務会計のキーワードが並んでいる。全問記述式だ。ずいぶんと難しいことをやっている。次は、「社会心理」。担当教員は近藤隆雄先生。こちらは建学時からいらっしゃって今は定年で非常勤で教えている方だ。この近藤先生とは縁があって、「サービスマネジメント」や「サービスマーケティング」という本を書いている先生にある論文の査読をお願いしたこともある。また、顧客満足をテーマとした講義やゼミでは「サービスマーケティング」を教科書として使わせてもらっている。親しくお話をしたのは初めてだ。近藤先生によると、「サービスマネジメント」の方は、改定が時々なされているので新しいということだ。今後はこちらを使うことにしよう。「群衆」「好意の返報性」「ロミオとジュリエット効果」「援助における他者依存」「コミュニケーション」「不協和理論」といったキーワードだ並ぶ。こちらは選択式と記述式の混じった問題である。開始後20分たってすぐに出て行く人、最後まで粘る人、それぞれだ。こういった試験監督の手伝いは、普段あまり接する機会のない同僚とも話ができる機会でであり、また他の先生がどんな内容の講義をしているのかを垣間見ることができるので、私自身は嫌いではない。いいコミュニケーションの場として受け取っている。試験問題を全部もらって、その科目毎のキーワードを自分で調べてみると、ずいぶんと勉強になるはずだ。今日の一首 応援の 試験監督 自らは 解けそうもない 問題くばる----------------このブログを書いているのは29日の朝だが、朝日新聞に「知の現場」の広告が出ている。「話題沸騰!続々、重版出来!!」として三冊の本が出ているが、その最初にある。弾みがついてくれると嬉しい。「寺島実郎氏、小飼弾氏、小山龍介氏など知のスペシャリスト21名の、書斎、オフィスなどを訪ね「知の構想」現場を取材。仕事の進め方、情報の接し方、テーマの選び方、、、。あなたはどの型を採用してみる? 久恒啓一監修 NPO法人知的生産の技術研究会編」。同じ東洋経済の広告欄に、「知の現場」に登場いただいている野村正樹先生の「東京思い出電車旅」という新刊も載っている。----この「知の現場」のプロモーションということで、2月17日に丸の内丸善で、「丸の内本店~『知の現場』(東洋経済新報社)刊行記念~久恒啓一さん 山田真哉さん 樋口裕一さん トーク&サイン会」の開催が決まった。http://www.maruzen.co.jp/Blog/Blog/maruzen02/P/9473.aspx
2010/01/28
コメント(0)
-
動画特集--「知研」関係の動画です。出版パーティの様子も。
ユーチューブでのNPO法人知的生産の技術研究会(知研)関係の動画です。知研http://tiken.org/の歴史や活動がコンパクトにわかります。NPO知的生産の技術研究会(知研)東海支部の加藤さんがyoutubeに、1月26日の「知の現場」の出版記念パーティをアップしてくれました。「知的生産の技術研究会の40周年を機会に、「知の現場」の出版記念パーティーが東京・飯田橋のアグネスホテルで開催されました。 小中陽太郎氏始め、取材した先生方の出席を得て、久恒理事長(多摩大教授)、八木会長が40年の経緯を梅棹忠夫先生との出会いを 交えながら話されました。 」http://www.youtube.com/watch?v=qHrJTxTqgJ0--------------「NPO法人知的生産の技術研究会編「知の現場」(東洋経済新報社 )の取材で行われた久恒啓一氏インタビューの様子を収録した動画 ファイル。」2009年http://tiken.org/tinogenba/ 動画制作者はこちら。http://prompter.live door.biz/ 」http://www.youtube.com/watch?v=Ad-KyDJqK1A&feature=related--------------「apan 知的生産の技術研究会・本部の忘年会が東京 赤坂・永楽倶楽部で開催され、知的生産のエキスパート、本を出版 された方や編集者の方々のプレゼンテーション風景の映像です。」2008年http://www.youtube.com/watch?v=cOuvc46U6IQ&feature=related--------------「 9月5日、6日に愛地球博記念公園で行われる「愛フェス2009 」での当会紹介、1分間CMです。参加したイベント、活動記録と 図解で紹介。 」愛知万博。http://www.youtube.com/watch?v=pbxCf-Hq3kk&feature=related----------------------------佐々木俊直さんが、電子書籍に関する本を執筆中です。3月中に刊行予定。出版社はディスカバー21、干場社長は目ざとい!この本は楽しみです。Twitter空間で編集者としての仕事が磨かれていくという例。「佐々木俊直のネット未来地図レポート」から * 批判の多かったTwitter推薦ユーザーリストがついになくなり、ジャンル別推薦ユーザー選択式に変更。http://bit.ly/6Geugf * YouTubeのパンドラ風サービス登場。日本語も通る。好きなアーティストの名前で検索すれば、あとは音楽が流れっぱなし。仕事のBGMに最適!http://www.youtube.com/disco * これはレコーディングダイエットに最適。日本語化されていて驚く。「Wi-Fi Body Scale」での体重記録が、楽すぎる件についてhttp://bit.ly/8JBh32 * ハイチ地震で倒壊したホテルに閉じ込められたがiPhoneでダウンロードしていた医療アプリで助かった男性。Haiti Earthquake Survivor: "My iPhone Saved My Life"http://bit.ly/6akGpX--------------米アップルがタブレットPC「iPad」発表、499ドルからhttp://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT861379120100127
2010/01/27
コメント(0)
-
「知の現場」出版記念パーティは大盛況!(速報)
撮影が終わった一瞬に、別のカメラで摂った写真です。皆さんリラックスしていて、今回の会の雰囲気がよくでたいい写真となりました。前列左から、望月実先生、川上徹也先生、久米信行先生、久恒啓一(理事長)、八木哲郎(会長)、小中陽太郎先生、枡井一仁先生、原尻淳一先生、山田真哉先生、奥野宣之先生。2列目の徽章をつけているのは、左から樋口裕一先生、東洋経済の清末部長、編集の中村さん。19時から21時まで、スタッフの準備と努力もあって、なごやかに、そして順調に進み、皆さんにいい時間を過ごしていただいたと思います。出席された先生方、知研のスタッフの皆さん、ありがとうございました!知の現場終了後、バーで樋口裕一先生と山田真哉先生と三人で、2月17日に丸の内丸善で行う予定の「知の現場」のプロモーションのための鼎談の軽い打ち合わせ。その後、八木会長や知研のスタッフも交えて和やかに打ち上げ。
2010/01/26
コメント(2)
-
朝日歌壇より 「人みなに人格あるごと各村に村格あると村長語る」
月曜日の朝日新聞の「朝日歌壇」で紹介されている短歌から、気にいったものを選んでみた。選者によって選ぶ歌の味が違う。今回は4人の選者の中で二人の選んだものがいいと思った。感性があうのだろうか。日曜日には「日経歌壇」があり、二人の選者によって秀歌が選ばれているが、今回はいいと思ったものがなかった。高野公彦選 「生きてるよ」そのことだけを知らせんと出口をわずかに雪践みにけり(山形市・大沼武久) 刺身、ポトフ、フルーツサラダ、さつま汁、吾子の短い帰省は終わる(福岡市・東 深雪) ひたすらに六十万個作り来し財布職人の五十五年了る(香取市・嶋田武夫)馬場あき子選 「忽然と雨に見舞わるビル街に男は走る女は歩く(東京都・近藤しげを) 人みなに人格あるごと各村に村格あると村長語る(千曲市・五島光人)----------------------------------高野公彦宇宙的なひろがりを持った静謐かつ濃密な空間を、しっとりとした浪漫的情緒でうたう歌を作っている。1941年、愛媛県生まれ。所属結社「コスモス」。東京教育大学国文科在学中より短歌を始め、コスモス短歌会に入会。宮柊二氏に師事。現在は、選者も務めるコスモスの代表的歌人。同人誌「桟橋」編集人。代表作品少年のわが身熱(しんねつ)をかなしむにあんずの花は夜も咲(ひら)きをり (『汽車の光』昭和51)白き霧ながるる夜の草の園に自転車はほそきつばさ濡れたり (『汽車の光』昭和51)みどりごは泣きつつ目ざむひえびえと北半球にあさがほひらき (『汽車の光』昭和51)ことば、野にほろびてしづかなる秋を藁うつくしく陽に乾きたり (『汽車の光』昭和51)精霊ばつた草にのぼりて乾きたる乾坤(けんこん)を白き日がわたりをり (『汽車の光』昭和51)ふかぶかとあげひばり容れ淡青(たんじやう)の空は暗きまで光の器 (『淡青』昭和57)雨月の夜蜜の暗さとなりにけり野沢凡兆その妻羽紅(うこう) (『淡青』昭和57)青春はみづきの下をかよふ風あるいは遠い線路のかがやき (『水木』昭和59)風いでて波止(はと)の自転車倒れゆけりかなたまばゆき速吸(はやすひ)の海 (『水木』昭和59)夜の暗渠(あんきよ)みづおと涼しむらさきのあやめの記憶ある水の行く (『水行』平成3)-----馬場あき子古典文学や能への造詣が深く、女性の情念を形象化した、豊饒で香り豊かな歌を作っている。昭和22年まひるの会に入会し、窪田章一郎に師事。23年から中学高校の教員を務める。30年処女歌集「早笛」を刊行。古典、とりわけ能への造詣が深く独自な歌風を拓き、以後「地下にともる灯」「無限花序」「飛花抄」を刊行し、52年「桜花伝承」で現代短歌女流賞を受賞。代表作品楽章の絶えし刹那の明かるさよふるさとは春の雪解なるべし (『地下にともる灯』昭和34)草むらに毒だみは白き火をかかげ面箱に眠らざるわれと橋姫 (『無限花序』昭和44)母の齢(よわい)はるかに越えて結う髪や流離に向かう朝のごときか (『飛花抄』昭和47)忘れねば空の夢ともいいおかん風のゆくえに萩は打ち伏す (『桜花伝承』昭和52)さくら花幾春かけて老いゆかん身に水流の音ひびくなり (『桜花伝承』昭和52)ここ去りて漂いゆかん道もなし膝つきてひくき水飲みにけり (『桜花伝承』昭和52)夭死せし母のほほえみ空にみちわれに尾花の髪白みそむ (『桜花伝承』昭和52)夜半さめて見れば夜半さえしらじらと桜散りおりとどまらざらん (『雪鬼華麗』昭和54)捨て船と捨て船結ぶもがり縄この世ふぶけば荒寥の砂 (『ふぶき浜』昭和56)わたり来てひと夜を啼きし青葉木菟(あおばずく)二夜は遠く啼きて今日なし (『葡萄唐草』昭和60)
2010/01/25
コメント(0)
-
「神保町「二階世界」巡り 其ノ他」(坂崎重盛)
『神保町「二階世界」巡り 及其ノ他』という本を読んだ。平凡社刊の380ぺージの厚い本だ。オビの表には「夢か・うつつか・幻か あの町、あの人、あの文章 東京依存症的随文集成」、裏には「志ん生碑 昼酔う人の 浮き沈み(露骨)」という句がみえる。坂崎さんは、1942年生まれで、造園学と風景計画を学び、横浜市に勤務後、退職し編集者、随文家になった。「超隠居術」という書だったか、一時ビジネス本でも見かけたが、今は「東京下町」をテーマに「随文」を書いているらしい。神保町「二階世界」巡り及ビ其ノ他プロローグで、神保町の古本屋の本当の醍醐味は、異界としての二階の世界であるとして、有名な古本屋の例をいくつもあげている。其の一(第一章にあたる)は、「この人を巡りて」で、下町界隈の通人である半村良、正岡容、吉田健一、安藤鶴夫、池波正太郎、山田風太郎、植草甚一、草森紳一、野田宇太郎を論じている。其ノ二は、「この町を巡りて」で、浅草、向島、人形町、銀座、神保町、神田須田町、湯島、神楽坂、上野を巡る食の楽しみが描かれている。其の三は、「この本を巡りて」で、山口瞳、村松友視、石田千、伊藤桂司、山本容子、嵐山光三郎、、、、。そして本を巡る随文が書かれている。「エピローグにかえて」の「石版「東京名所絵」調べ事始め」は、蒐集家としての動きの深まりがわかる。20年ほど前に「九段坂ヨリニコライ堂遠望」、「吾妻橋月夜」などの石版の名所絵と邂逅し、蒐集本能が目覚める。その絵の蒐集を通じて、描かれた風景に関する知識を得たくなり、コレクションが始まる。学術的研究をする気はなく、石版周辺の雑情報と石版名所絵を気長に集めていくという宣言がされている。「初出掲載データリスト」を見る。「東京人」、「遊歩人」、「どうぶつと動物園」、「「うえの」、「波」、「すまいろん」、などの小さな雑誌と、本の解説を書いた文章が、この本の材料である。池波さんは江戸に長逗留された」と誰かが池波正太郎のことを書いていた記憶があるが、坂崎さんは東京下町の江戸から明治期に住んでいるという趣である。著者の収集癖と懐古趣味が溶け合った不思議な趣を持つ本である。子どもの頃からの懐古趣味、育った環境、、そして蒐集癖が、このような本を生んだ。この本も先日の神保町の古本屋で手に入れたのだが、2009年9月発刊だからまだ新しい本だ。古本屋に高く積まれていたから、古本屋としても読んで欲しい本なのだろう。この本に刺激を受けて、古本と下町の探訪にも興味がでてきた。
2010/01/24
コメント(0)
-
多摩学
1月の教授会。寺島学長が出席され、「2010年年頭所感と方針」をペーパーをもとに説明、解説があり、質疑応答があり、方針への理解が進んだ。「所感」では、均質性を超える知的刺激が課題であること、全員参加型経営を目指すこと、「現代の志塾」にふさわしい学風の確立が示された。「新年方針」では、「実学志向の大学」の実学を「今を生きる時代についての認識を深め、課題解決能力をたかめさせること」が実学と考えたいと再定義、、「現代の志塾」とは「学生一人ひとりが時代と向き合い、自らの能力・気質を踏まえた人生の目標を達成すること(自己実現)を促す高等教育環境を整えること」と、とされた。「多摩大学のアイデンティティの確立のための「多摩学」確立の決意」では、グローバリティの追求と足元を見つめるローカリティの追求が両輪であるとされた。「積極的経営企画(POSITIVE PLANNINNG)体制の構築。「学生サポトの充実」では、もう一段の工夫を加え、学生を支援すること。「一体経営管理志向」では、経営情報学部は「質的向上に専心」することがテーマとされた。「学力(特に物事を深く考える力)」の向上、創造的なカリキュラムの工夫、異質なバックグラウンドを持った存在との交流、新しい教育手法への挑戦、など。「目線を高く」、「求心力」、「学生に背中を見せる」、「前に進むエネルギー」、「コンテンツ、成果、実績」、「うねり」、、。-------------------終わって、そのまま業績評価検討委員会を開催。学長方針も年頭に置いた活発な議論が展開された。-----------「多摩学」に関係するが、多摩27市町村の郷土誌展示販売が、立川市のオリオン書房ノルテ店で行われていると、ミニコミや新聞で紹介されていたので、出かけてみた。22日から24日まで開催で、新刊書を含めて一千冊が展示されている。「多摩郷土誌フェア」という企画だった。今日は、八王子、青梅、日野、多摩の教育委員会などが編集した資料と、新刊本を含む単行本が並んでいた。観光、民話、開発史、など実に多彩な資料である。八王子市郷土資料館の販売図書では、「八王子空襲」「八王子の歴史と文化」「歴史と浪漫の散歩道」「石川日記」「尾崎日記」「千人同心関係資料」「八王子の歴史と文化」「埋蔵文化財年俸」「多摩の神道・垂迹美術」「織物の街に生きる」「夕焼けの里の文化」「北条氏氏照と八王子城」などがのリストがあった。私が購入したのは、以下。 * 「多摩川絵図」-今昔--源流から河口まで(今尾恵介解説・けやき出版) * 「三多摩に輝く」(原克孝・けやき出版) * 「多摩川と甲州道中」(新井勝紘・松本三喜夫)、吉川弘文館) * 「多摩の鉄道沿線 古今御案内」(今尾恵介・けやき出版) * 「鉄道計画にみる多摩市の移り変わり--旧富沢家展示会」(多摩市教育委員会) * 「富沢家と和歌・漢詩」(多摩市教育委員会)
2010/01/23
コメント(0)
-
「この授業を受けて、あなたはどう変わりましたか?」
秋学期の「マネジメントデザイン2」の最後の15回目の授業を終えた。この講義の目的は、「近代日本をつくった明治期を中心とするわが国の偉人の生涯(経営者・政治家・芸術家・作家・ジャーナリスト、、)を題材に、いくつかの切り口----仰ぎ見る師匠の存在、敵との切磋・友との琢磨、持続する志、怒涛の仕事量、修養・鍛錬・研鑽、飛翔する構想力、日本への回帰----を用いて今日のビジネス社会で生きる知恵について学び、自らのライフマネジメントについて深く考えてもらう。」ところにある。http://www.hisatune.net/html/01-kyouiku/tamadai/mana-des2/s_mana-des2.htmlこの講義では試験はなく、レポーとを出してもらう。「私のロールモデル○○○○の人生鳥瞰図」と「○○○から学んだこと」(A4を2枚)だ。レポートを見るのが楽しみ。岡本太郎・渋沢栄一・福沢諭吉・南方熊楠・樋口一葉・宮崎駿・松下幸之助・イチロー・与謝野晶子・宮崎駿、、、。多摩大生は、こういう人たちに関心が高い。最後の授業では、「この授業を受けて、あなたはどう変わりましたか?」という問いを書いたアンケート用紙を配って、自由に書いてもらった。 * 自分の生き方に対して自信を持たせてくれるような名言を聴いたとき、くじけそうだった私の心が救われました。岡本太郎というロールモデルに出会ったことが私を変えてくれました。 * 視野が広くなったと感じます。 * 世界観が変わった。 * 生き方を考えるようになり、一日一日を大切にして生きていきたいと思うようになりました。 * 自分と照らし合わせ、今後自分がどう生きていけばいいのかを考えるようになりました。 * 人生観が変わりました。 * これから努力を怠ることがないようにしてりきたいと思うようになりました。 * 様々な偉人の話を聞き、わたしの中にも新しい世界が開けました。 * 最後の「外的世界の拡大は内的世界を深化させる」という言葉にあてはまるような成長ができた。 * 自分の怠惰な生活を恥じた。 * タイムマネジメントの必要性に気づかされた。 * 自分のこれからの人生に対してしっかりと計画を立て、素晴らしい社会人になりたい * 優れた先人たちに興味を持ち、調べるようになりました。 * 尊敬する人が見つかりました。 * 自分の目標をつくりなおします。 * たくさん学んで知識をつけたいと思うようになりました。 * 計画を立て、有効に行動できるようになりました。 * 日記を書きます。偉人のようなすばらしい人生モデルを残したい。 * 一つ一つのことを重ねていくことができるようになりました。 * 目標を見つけたので、何をすればいいかがだんだんとみれるようになりました。 * 人生観が変わりました。 * 一日一日無駄にしないように生きて行きます。 * 色々な人の考えを自分に取り込んで、知識・教養をど増やし、幅の広い人間になり、日々成長していきたいと思うようになった * 自分の人生をもっと内容の濃いものにしたいと思うようになりました。いろいろ体験し、後悔のない人生を送りたい。 * 一日一日を大切に過ごしていきたい。 * 偉人の人生を知って、ものの見方や考え方が変わりました。 * 努力家が多かった。私もあきらめずに仕事をこなしていくようになりたい。 * 人生に対する考え方が変わりました。 * 他人の生き方を真剣に観察するようになりました。 * 一度の人生なので、偉人から教えてもらった強い言葉や意志を信じて、自分の道を歩んでいきます。 * 計画力が身につき、いろいろなことができるようになりました。 * 考え方が変わりました。 * 背景にあるものを意識できるようになりました。 * この授業を通じて、少し前向きになれた気がします。 * 視野が広がりました。 * ポジティブシンキングになりました。 * 心が大きくなりました。 * 心に響く言葉を聞いて、チャレンジ精神が強くなりました。 * 「もっと素晴らしい人間になろう!」という熱い気持ちを持つことができました。 * 自分の人生を見つめ直し、考えるようになりました。 * 偉人に近づけるように頑張りたい * 日記を書きはじめたら、毎日が充実してきました。 * 「私の最大の光栄は一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起きあがるところにある」(本田宗一郎)を座右の銘にする * 調べることの楽しさがわかってきた * これからの人生目標ができた。 * 自分の将来、今後の目標に、向き合えるようになりました。 * 自分をマネジメントしていきたい * 視野が広がった * 継続する人が多く、私も簡単に諦めないようになりました。 * 一日一日をもっと大切にしたいと考えるようになりました。 * よく本を読むようになりました。 * 調べることが多くなりました。 * 自分の意見を言えるようになりました。 * 目標が決まりました * 有名な人物の格言を調べてみたい。本をたくさん読もう。 * 毎日ブログを書くことによってその日を振り返り反省ができるようになった。一日一日を大切に考えるようになった。 * 人生計画を立てることの大切さを知りました。 * 人物についての本を読むようになりました。 * 視野を広げることが出来ました * 「勉強」としてではなく「楽しみ」としてレポート作成を終えました。もっと学んでいきます。 * 平凡に生きているわたしは時間を無駄遣いしているのではないかと感じるようになった。 * 偉人を人生を参考にして、オリジナルな人生を送りたい。 * わたしの人間としての幅が広がった * 人間に興味を持つようになりました * 歴史と文化が好きになりました。言葉の素晴らしさを知りました。-----------------------------------講義終了後、品川サテライトで会議。多摩に戻って、来年度のインターゼミ「社会工学研究会」の希望者たちとの面談。写真はその風景。
2010/01/22
コメント(0)
-
ゼミ生の春休みの計画-旅行・読書・スノボー・マラソン・SPI、、
秋学期最後のゼミの時間。ゼミ生(2年生)の春休みの計画を聞いた。 * バイト。本「世界を知る力」(寺島実郎)を読む。ブログを書く。 * スノーボード。テニスサークルの冬合宿。筋トレ、3年生からの就職に備える。 * スノーボードで新潟・長野・白馬。就活のためにSPIなど。地元の静岡の企業を調べる。 * バイト。関西と名古屋へのバイクの旅。 * イメチェン。知的に暮らす。勉強。 * バイト。遊び。本「世界を知る力」を読む。 * スノーボード。ユーキャンのボールペン講座。 * 日本三大名城の一つの熊本城を見物にいく * 3年生になる準備。同窓会。奈良で仏像をみる。 * 地元の長崎の五島列島のマラソン大会に参加する。 * 友人、先輩と会う。スノーボード。本「世界を知る力」 * ロンドン旅行 * 免許をとる。実家の広島に帰る。 * バスケットのサークル。本は3冊読む。「やりたいことがない人は起業しなさい」「カンブリア宮殿、、」 * 貯金中。バイト。勉強。TOEIC。読書は渡辺淳一の本を継続して読む。2月12日に地域をテーマとしたゼミ活動10本くらいの発表会があるので、その確認と、9日にリハーサルを行うことにした。わたしのゼミでは、多摩焼きチーム、公園マネジメントチーム、東京ヴェルディチーム、それからインターゼミの東鳴子温泉チームの発表が予定されている。
2010/01/21
コメント(0)
-
「外的世界の拡大は、内的世界の深化をもたらす」
朝、大学で仕事を処理した後は、ずっと新宿だった。昼食は、仙台時代にお付き合いの深かった富田さんが上京しているということで、私たち夫婦で新宿のサザンタワーで一緒に摂る。富田さんは宮城リコーなどの社長をながく勤めた方で、現在は定年後の日々を謳歌している。一昨日ロングステイの場所としてどうかということでマレーシアから戻ったばかりだそうで、今日は渋谷の野口式呼吸法の道場に来ているとのことだった。仙台時代は私のゴルフの師匠としてお付き合いいただき、野田先生とともに相当な数のラウンドをご一緒した。人生を楽しむ姿に接するたびにこちらも心が明るくなる。東京に出てきてゴルフから遠ざかっているので、今年は手合わせを願いたいものだ。参考:「富田秀夫のゴルフレッスン」「生涯スコア表」http://www.hisatune.net/html/05-career/private/private.htm午後は、今年度最後のJR東日本での研修講師。85人。冒頭に私の座右の銘の一つでもある「外的世界の拡大は、内的世界を深化させる」という言葉を紹介したのだが、アンケートの感想を読むとこの言葉が印象深かったと書いている受講生が多くいた。大学生時代に没頭した探検部で手にした、なぜ人類は探検するのかという問いに対する答えの一つだが、この考えは個人の生き方にも当てはまるということで、ずっと指針にしてきた。いい言葉は人を目覚めさせる。最後に、私の図解Webと多摩大ホームページを紹介しておいた。メルマガ希望者は20名ほど。研修終了後の懇親会では、「私、多摩大出身です」と若い社員が挨拶に来た。8期生の水漉晃さんで、アンケートには「自分は多摩大の卒業生だが、自分が学生の時には久恒教授がいらっしゃらなかったのは残念だった」と書いてあった。名刺には東京支社営業部業務課とあった。ほかにも卒業生がいるらしい。講演で多摩大の卒業生から声がかかったのは初めて。嬉しいことだ。次に、N出版社の本部長と担当編集者に、知研の秋田事務局長と一緒に会う。3月刊行を予定している知研の本についての打ち合わせ。終わって、秋田さんとお酒を飲みながら情報交換。---------------FMラジオ番組『ベストセラーズチャンネル』:1月23日放送 * 「あの久恒啓一氏が登場!『志 KOKOROZASHI』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『あなたの人生が上手くいく7つの「成功法則」』(三笠書房)を取り上げます。(企画・プロデュース:起業家大学、パーソナリティ:山口佐貴子、放送日:2010年1月23日(土)全国コミュニティFMにて)。「書籍執筆の動機や裏話、書籍には書くことができなかったさらに深い書籍の内容などを番組で語っていただきました」http://www.news2u.net/releases/63073」 * 「TOKYO FM(エフエム東京)傘下のMusic Birdより全国コミュニティFM45局ネットで放送(毎週土曜日 5:00~6:00)されています。※関連番組FMラジオ番組『ベストセラーズチャンネル』は、下記で放送されています。◆TJS【Team J Station】 アメリカ Los angeles 24時間日本語放送局で、毎週金曜日18:00~19:00に放送◆Love FM(ラブエフエム) http://www.lovefm.co.jp第4週目土曜日 21:00~22:00(Brand-new Focus!内で30分コーナーとして放送)◆.FM放送ラジオ番組『ベストセラーズチャンネル』URL:http://bestsellers.fm/」
2010/01/20
コメント(0)
-
匿名アカウントでもやってみるか-週刊ダイヤのツイッター特集から
週刊ダイヤモンドが「2010年ツイッターの旅」--「使えない」でjは済まされない!140字、1億人の「つぶやき」革命、と銘打ったツイッター特集。以下、参考になった情報。 * ユーザーは全世界で1億人。日本は昨年だけで10倍になって現在500万人。今年中に2倍になって1000万人。 * 20代、30代、40代が多く、平均年齢は35.7才。東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏で52.4%。今年はヒット商品番付の横綱か? * フォロワー数。アシュトン・カッチャー(俳優)430万。オバマ大統領300万。日本ではトップは55万、ホリエンモン31万、勝間和代25万、、、。 * 「いつも誰かとつながっているんだ」という充実感(広瀬香美) * 「実名アカウントと匿名アカウントを両方使ってみるのも、慣れてくると楽しいものです。(同) * 「つながる力倶楽部」の例会は、月曜日夜9時から1時間。ツイッター教室。#kohmitweet * hashtagsjp(人気タグ検索解析)、twitvideo(動画アップ・アイフォン動画も)、twitpic(静止画)、TweetLevel(影響度分析) * フォロワー数のアップ作戦。「@やRTで突っ込む」「ハッシュタグを活用」 * 「ゆるゆるとマイペースで続けていけば、フォロワー数も増えるし、友人もたくさんつくることができます」(「500人までフォロワーを増やした体験記」が話題になった「しゅうまい」さん) * 実際のアクティブユーザーは数十万人。50人のリストは必ず読む。検索しまくる。他人が読みたくなるようなネタは身近にある。(勝間和代) * 企業向けツイッター管理ツールあり(初期費用15万、月5万)・グルーヴィーメディア。 * ツイッター議員の数は、民主党が圧倒。(年齢と感度が違う!) * 「アメーバなう」「春までに一気に利用者を獲得する」(藤田晋) * 企業アカウント:ヤフー(24万)ソフトバンク(9千)、ユニクロ(2万3千)私のツイッター(http://twitter.com/hisatune)は、フォロワー数はもうすぐ700というレベルだが、コツコツと増やしていきたい。----------「時間主権」というキーワードに反応した取材申し込みがあった。「、、、著書などで展開していらっしゃる自分の能力を高めるための時間管理の考え方、および日経ビジネスアソシエで展開された「時間主権」の確立という概念が非常に参考になりました。それこそが、効率性の追求だけでなく、満足度を高める時間管理のために重要なことであると考えるためです。久恒先生に、時間主権の重要性と確立方法、残業の不毛性、朝時間や通勤時間の活用法などについてお話を伺わせていただき、、、、」-----朝は九段で学長、昼食はホテルニューオータニの「なだまん」で野田先生と沈先生と食事、午後は大学で秘書と打ち合わせ、夕刻は美容院。
2010/01/19
コメント(0)
-
古書店から、ツイッターとネット事業までのミニツアーの日
大学で仕事を終えて、九段へ。途中の駅の売店で、週刊ダイヤモンドの2010年ツイッターの旅」特集を購入する。「「使えない」では済まされない!140文字、1億人の「つぶやき」革命」という副題がついている。読んでまた感想を書くことにするが、現時点で31万人のフォローワー数がいるホリエモンが対談をしているのを読んだ。以下、ホリエモンの発言から。--自分のやっていることをプロモートする。Q&A。目利きを通したソーシャルフィルタリング。何が来るのか予測できないから、とにかくなんでもやってちく。新聞の存在意義がないことに誰もが気づく。、、、。神田神保町で少しの時間だが、古本屋街をぶらぶらする。最近は、九段サテライトに行くときは、神保町で降りて古本屋を冷やかしながら歩くことにしている。坂崎重盛「神保町「二階世界」巡り」(平凡社)と「加藤周一が書いた加藤周一」(鷲巣 力編・平凡社)を買ってみる。坂崎さんのこの本を読むといくつかの古本屋の名前が出てくる「三茶書房」「山田書店」「原書房」「大屋書房」「悠久道書店」「巌松堂図書」「湊川堂書店」「一誠堂」「玉英堂」、、、。この本を道案内に古書店の世界にも分け入ってみることにしよう。「加藤周一が書いた加藤周一」は、知の巨人・加藤周一が60年にわたる「売文業」の中で書いた170冊を超える本の中から、91の「あとがき」と11の「まえがき」を時代順に編集したものである。加藤はその著作が書かれたときの時代状況、なぜそういう主題の本を書いたか、そして私的なことがらを綴るという形式でほぼ一貫して「あとがき」を書いている。だから、それを集めただけでも歴史と個人の関わりをテーマとした一冊の本になるというわけである。私の場合は、梅棹忠夫先生が「まえがき」には、この本を書くに至った経緯を書く、という事をおっしゃっていたことを受けて、そういう書き方になっている場合が多い。いずれにしてもこういう知の巨人達は、どんな場合でもポリシーを持って仕事をしていることを痛感する。九段サテライトでは、大学院同窓会の幹事会をやっていて旧知のビジネスマンたちに久しぶりに会う。ギリークラブの渡辺さんに紹介してもらったネットプライスドットコムの小野田美香さんと会う。小野田さんはインキュベーション推進室長と経営戦略室長を兼ねているキャリアウーマンだ。エネルギー溢れる話を聴いていると容易ならざるビジネスが展開していることがわかる。(株)デファクトスタンダード、(株)ショップエアライン、(株)転送コム、(株)もしも、(株)オークション、、こういうネットを用いたビジネスの動きの話は実に面白い。こういう最先端の動きが時代を創っていくのだと感じた。大学とのコラボレーションのアイデアもいくつか出たので、形にしていきたい。なんだか、今日は、古書店から時代の最先端であるツイッターやネット事業まで、広い空間を旅した感じがする不思議な日になった。下記は、ユーチューブにアップされている最近の動画です。Interview of HISATSUNE Keiichi「知の現場」http://www.youtube.com/watch?v=Ad-KyDJqK1Aさよなら講義(ダイジェスト)宮城大学「これまでの10年 これからの10年」0803http://www.youtube.com/watch?v=FbzJDFMD9C4
2010/01/18
コメント(0)
-
美しい自然は人を表現者にする
天気がいいので、近所の素晴らしい公園(長池公園)をぶらぶらした。このところ気温が低かったこともあり、池に氷が張っている。ここ数日で氷の範囲が広がっているようだ。子ども達がその珍しい氷を割ったりしながら遊んでいる。この公園は里山の自然を活かした公園なのだからだろうか、珍しい鳥が多い。そのため、大きなレンズのカメラを抱えた人の姿をよく見かける。特に冬になると木々の緑が落ちて鳥の姿を捕まえやすくなるせいか、写真を撮影している人が多くなる。また、犬を連れて散歩している夫婦も多いが、小型のデジカメを手にしている人も多いようだ。この手の人は季節毎に咲く花を目標にしている。また、天気の良い日には、持参した小型の椅子に座って、池の風景やこの公園の名物である大きな橋や、スペイン風の建物である結婚式場などを、本格的なキャンバスに向かって描いている人も現れる。そしてその絵をのぞき込んでいる人もいる。この公園は、休日になるとキャッチボールやフリスビーを楽しむ親子連れも多くなる。広い空間と高低差のある環境が親子のコミュニケーションにいい。その風景を老夫婦が目を細めて眺めている。犬と散歩する人が多きので、あちこちで犬友たちの交歓が行われている。1年ほど私も散歩を続けていると、犬の特徴と名前も少し覚えてくる。今年から始めた短歌の題材となる景色も多く、五七五七七のフレーズを考えながら歩いている。そういう人も多いのではないだろうか。この公園には、絵描き、カメラマン、そして詩人などがいる。美しい自然は人を表現者にするようである。
2010/01/17
コメント(0)
-
大学入試センター試験の初日
本日は、大学入試センター試験の試験監督に一日中従事しました。朝は8時集合、9時半から始まって、英語のリスニングもあったので、19時までかかりました。100人教室で、駒沢女子大の二人の先生と多摩大は私を含めて3人の計5名のチームです。多摩キャンパスは二人、湘南キャンパスは一人。今日の私の役目は、主任監督者で、受験生に注意事項を読み上げる担当でした。一字一句読み間違えないようにと緊張します。アドリブは許されないので「ロボットのように」時間通りに進行することを心がけました。リスニングは受験生も監督側も緊張が走りますが、無事に終了。評論活動で忙しい神戸女学院大学の内田樹先生のブログでも「16 日 早起きして大学へ。これから二日間センター入試。入試業務と統括する立場なので、朝から晩まで大学にカンヅメ。なにもトラブルが起きませんようにと天に祈る。」と書いてありました。内田先生は今年度は入試部長だそうです。「15日 ゼミが一つのあと、会議が三つ。翌日からのセンター入試のためのミーティング。やれやれ。」ともあり、大変そう。「センター試験の試験監督について書いてあるブログ」という記事を見つけた。http://d.hatena.ne.jp/next49/20090119/p2-------------今日の一首 鬼気迫る静謐かもす若人の 鼓動も聴こゆ英語リスニング
2010/01/16
コメント(0)
-
思いがけない人達(神田敏晶さん、、)との遭遇が続いた珍しい日
八王子のエイビット社を学部長と一緒に訪問し、檜山社長、水谷さん、富永さんと地域活性化関係の連携の相談を行う。大きな、そして夢のあるプロジェクとに育っていくだろう。その後、品川の大学院の講義に向かう。山手線でビジネスマン時代の上司の市川さんに遭遇する。大学までの各種学校を傘下におさめる大きな学校法人の理事長をしているそうだ。品川サテライトで、授業の準備をしていると、カウボーイハットを被った派手な格好をした人が「カンダです」と言いながら入ってきた。それは、「Twitter革命」の著者の神田敏晶さんだということがすぐにわかった。今日は隣の部屋の授業でゲスト講義をするのだそうだ。アイフォンで二人で記念撮影。神田さんは拙著「通勤電車で寝てはいけない!」(三笠書房)を読んで、「できるだけ遠くに住んで通勤時間を有効活用すべし」という私の持論に影響を受けてすぐに湘南に引っ越したと言っていた。本日は、「社会的合意形成論」の最後の授業なので、講義をした後、鮨屋で食事とお酒で懇親をしながら意見交換を行う。皆さんリラックスして大いに場が盛り上がって、大きなプロジェクトの構想を語り合った。以下、受講生(全員が社会人)の書き込みより。f:id:k-hisatune:20100115200957j:image * 本日は秋学期の最終授業でしたので、全体の振返りと課題の話が中心でした。配布資料は、寺島学長のインターゼミのまとめと、同じく学長の新刊「世界を知る力」を久恒先生がまとめた資料の2本です。課題は2月10日締め切りです。テーマ1は「私の仕事」テーマ2は本日配布の「世界を知る力」のまとめ資料の2つを図解し、メールで提出します。(今回欠席の皆さんよろしくお願いします。)課題2は寺島学長に見ていただくことになるようです。授業終了後の懇親会(アフター授業)では「図解コミュニケーション学会」設立の話が盛り上がり、急遽「発起人委員会」第1回のブレストの様になりました。先生の授業を受けた院生を中心に学会設立のプロジェクトを起こすことになりましたので、皆様の積極的なご協力をお願いします。半年間のご指導にあらためて感謝いたします。また、今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。 * 先生の講義はもちろんのこと、一緒に受講した皆さんが描く図解が、私にとって大変勉強になりました。半年間、本当にありがとうございました。半年間での私自身の変化と言えば、図が少し柔らかくなったなぁと感じています。最初の頃は、四角ばった固い絵を描いていましたが、最近は何となく丸みを意識した絵になってきたように思います。柔らかい絵の方が、コミュニケーションを取るのもやりやすくなりますものね。「図解コミュニケーション学会」、とっても楽しみですね!Googleの言葉の知を超える、図解の知的資源を目指しましょう。私自身も貢献できるよう、図解能力をもっと磨いてまいりたいと思います。今日のお話の中で、「西洋の論理力というのはパターン化である。日本がもつ全体知こそ大切である」という言葉が大きな学びとなりました。全体を捉える構想力、養っていきたいです。 * 日本発の知力開発法として図解を世界に発信!西欧型論理は、二項対立を基本とする単純さを特長としていて誰にでも理解し易いため、世界中を席巻したかに見えます。しかしながら、現実の社会そのものも、また山積する社会の問題も、単純明解な西欧型論理をもって解決できるほど単純なものではないことに私たちは気づき始めています。そこで、図解の登場です。複雑な相関関係をもわかりやすく示すことができる図解。対立概念とはいえないが全く同じともいえない、といった微妙な相関関係でさえ、図解においては位置や大きさを工夫することによって見事に表現することができるのです。また、図解は複雑な現象や物事の本質を明示するための手法としてだけでなく、図解のプロセスにおいて本質を見抜く知力を開発する手段にもなります。図解教育を通じて、日本の現在を牽引するビジネスパーソン、将来を担う若い世代の知力開発に貢献し、さらにはアジアへ、そして西欧へと広げていきましょう。(と、飲んだ勢いもあり、昨晩は夢が果てしなく広がりました!)今学期最後だった昨日の講義の終盤は、もっぱら「図解学会」設立への意見交換となりました。残念ながら昨日出席できなかった方々も、ぜひぜひ一緒に推進していきましょう。 * 春学期に続き、秋学期も無事受講をすることが出来ました。図解をすることは全体の構成と個々のつながりや関係を示すと言うことを考え、皆に説明することも併せて考えてゆくこと。この作業を行っているときには体調さえ良ければ、頭が活性化されていることを感じていました。残念ながら、すべてフル回転とならなかった事を反省する材料としたいと思います。春学期に比べて、図解する速度は少し上がったように思えたことはちょっとだけ成長できたと自己満足しています。これから仕事と、レポートや論文へこの方法を活用して行こうと思います。最終回の課外活動の皆さんの提案の活動も楽しみにしています。講義は毎回楽しく色々な見方はとても参考となりました。まずは先生をはじめ受講生の皆様この場をお借りしてお礼申し上げます。-明けましておめでとうございます。 年末に駆け込みで買った大型テレビで、正月を過ごす事が出来、チャンネル数も増え、満喫していたら、放送大学のところで、ゴールデンタイムにも関わらず?!、久垣先生が講義をされてました。家族の冷ややかな視線も無視しついつい見てしまいました。授業で、聞き漏らした矢印や丸の使い方、意味会いをしっかり復習でき、全体を俯瞰し、課題を整理し考える最適な手法という事をあらためて理解しました。 今年の授業開始を楽しみにしてます。
2010/01/15
コメント(0)
-
「2009年の総括と2010年への基本的視座」--寺島実郎講義のまとめ
寺島実郎監修リレー講座の秋学期も今日で最終回。社会人受講生の全回出席者は67名を数えた。 * COP15の衝撃。何も決まらなかった。25%削減の鳩山演説にも無反応。途上国に雑言を浴びた。 * イラクにおける米軍兵士の死者は12月31日現在で4369人。アフガンは949人。合計5318人のアメリカの若者が芯だ。 * 正統性を失いつつあるアメリカ。 * 世界を回って、日本ほど暗い雰囲気の国はなり。 * 2009年の世界経済マイナス2.2%。(米国マイナス2.5%、日本マイナス5.3%、ロシアマイナス7.9%、中国+8.5%、インド+6.6%) * 2010年のコンセンサス(エコノミスト予測の平均)予測ではプラス2.9%。(米国+2.7%、EU+1.1%、日+1.5%、中国+9.6%、インド+7.7%、ロシア+4.1%) * 景気回復は、財政出動と金融緩和で、再びマネーゲームが始まっているのが理由。金の行き場を探している。石油価格の上昇(2008年夏147ドル・2008年末34ドル・2009年末75ドル。乱高下) * 09年1-11月の日本の貿易総額。米国13.6%、中国20.5%、大中華圏30.6%、アジア49.5%。 * 世界はネットワーク型で発展している。大中華圏とユニオンジャックの矢(ロンドン、ドバイ、バンガロール、シンガポール、シドニー) * シンガポールは、大中華圏の南端でASEANとのつなぎ、ユニオンジャックの矢に位置。バーチャル国家としての先行モデルだ。。システム、ソフト、技術、医療、バイオなど、、。 * 日本。20008年の雇用者5539万人のうち年収200万円以下(ワーキングプア)は1305万人(非正規雇用者の74%)。自営業で200万円以下と正規雇用者で200万円以下420万円。これらをあわせると、200万円以下で働く人は労働人口6376万人の34%にあたる2196万人。200万は時給1000円レベル。 * 生活保護を受けている人は159万人で、平均支給は173.9万円。失業保険を受けている人は61万人で、支給は152万円。200万円の層とそれほど違わない。 * 勤労者家計の可処分所得は減り続けている。2000年は月47.3万、2008年は月44.3万、2009年1-7月は41.2万。これは年収ベースで73.2万円の減少にあたる。また企業のフリンジベネフィット(寮・社宅・保養所、、)も減少。社会にフラストレーションがたまり、政治への期待がが増加。家計への直接給付への関心が高まり政権交代へつながった。 * 新政権でみえてきたこと。公共投資マイナス18%(コンクリート)、福祉・教育プラス10%(人)。子供を誰が育てるのか。社会が育てるという合意が形成されているのか疑問だ。これによって親子関係など社会の姿も変わってくる。官から政へというが、政治家のレベルの問題がある。 * 日本。民主党政権の弱点は産業政策がないことだ。項目が並んでいるだけ。政策論(プロジェクトエンジニアリング)が大事だ。 * 日本創生おシナリオ。次世代ICT。地上デジタルは南米は日本方式を採用したが、ハードは韓国勢が席巻している。光ファイバー網は基幹インフラとして9割敷設が終わっているが、家庭への接続でみると20%台。ラストワンマイル問題。ここを国家としてすみやかにやり高度情報化社会に立ち向かう・このためNTTを核とする国策特殊会社を設立し社債発行によって電撃的に行うプロジェクトが進行(税金を使わない)。 * 小中高生に電子教科書を配付し、高度ICT人材養成への本格的な布石を打つ。全ての教科書を採用すればよい。その教科書から百科事典、専門家の意見にもとべるようにする。ランドセル姿もなくなるだろう。 * 日本はエネルギーと食料を海外に依存してきた。技術によって食糧問題(カロリーベース自給率40%)を解決していく、腐らせない、移動できるようにする、バイオ技術の応用、、株式会社農業に人材と技術を投入。食料輸入は6兆円。輸出はいつのまにか5000億円に(ドバイでも日本の刺身が食べられる)。3-4年で1兆円を越すだろう。 * エネルギー。日本は国土面積は61位。しかし領海と排他的経済水域を合わせた海洋面積では6位。海洋基本法と宇宙開発基本法は超党派議員立法で成立している。09年10月に宇宙開発戦略本部がスタート。この二つは相関がある。日立の準天頂衛星の打ち上げで正確な資源探査が可能。11カ所の海底熱水鉱床の発見。各種資源のポテンシャルあり。 * 分配の議論から、自動車以降のプロダクトサイクルに向けて構想力を持って立ち向かわなければならない。
2010/01/14
コメント(0)
-
JR東日本、東洋経済新報社、KIQTAS
JR東日本の新宿の本社で今年度5回目の研修の講師。昨年受講した若手社員研修の応用編という位置づけ。東京、横浜、八王子、大宮、高崎、水戸、千葉、仙台、盛岡、秋田、新潟、長野の各支社から総勢75名が受講。題材は、中期経営計画。始まる前に、この研修の導入時の担当で、今はJR東日本パーソネルサービスの梅津取締役と久保田事業部長が挨拶にみえて懇談する。研修終了後、ビジネスマン時代からの長い付き合いのJR東日本の小がた副社長がみえて話をする。小がたさんとつきあっていた当時は彼は広報部長あたりだったが、今はJR東のキーマンとなっている。「7つの成功法則」を前回差し上げたので、今回は「知の現場」を贈呈する。終了後、赤坂のメゾン・ド・ユーロンに駆けつける。この店は2010年版のミシュランで一つ星を獲得した店だそうだ。さすがに料理も珍しいものが多く、パンもおいしい。昨年末に東洋経済新報社から発刊した「知の現場」を発案した清末部長(私の20年前に出した最初の単行本「図解の技術」の編集者!)と編集を担当した中村さんへの御礼の会である。知研からは、八木会長、秋田事務局長、わたし、田村さん等が出席。今回の写真を担当して下さったタツ・オザワさん(タツさんは東洋経済から出したChabo1メンバーの本のときのカメラマン。いい写真を撮るプロ)。また別件で食事を予定していたKIQTAS(キクタス)の早川さん(30才前)も一緒にはいってもらったので、賑やかな会となった。団塊世代論、団塊ジュニア論、山田真哉、勝間和代、山本冬彦、手帳論、知研らしさ、、、、と話題も発散し楽しい会となった。終わって、早川さんとコーヒーを飲みながら情報交換をする。いくつか企画が浮上。
2010/01/13
コメント(0)
-
『知の現場』の出版記念パーティ・サイン大会にどうぞ!
NPO法人知的生産の技術研究会はhttp://tiken.org/、『知の現場』(久恒啓一監修・NPO法人地的生産の技術研究会編)の出版記念パーティ&先生方大サイン大会・ご著書販売会を行います。http://tiken.org/tinogenba/ この機会に人脈を広げませんか。この度NPO法人知的生産の技術研究会(知研)では、21名の様々なジャンルの先生方に18名のプロジェクトメンバーで海外および国内を縦断して取材インタビューをおこなった本『知の現場』の出版記念パーティを2010年1月26日(火曜・大安)19時より開催いたします。昨年末に刊行した「知の現場」は、本日増刷の連絡が入りました。順調に売れているようです。東京・JR飯田橋駅から徒歩5分の、ミシュランガイドにも「快適なホテル」と紹介された、瀟洒な滞在型ホテル「アグネスホテル東京」にて、地下1階のアグネスホール(収容人員150名)を貸し切りで行います。21名の先生方は全てご招待となり、ご著書等の販売を希望される先生方全員の合同サイン会・ご著書販売会も、会場内にて同時に行いますので、皆様お誘い合わせのうえ、お越しくださいますようお願い申し上げます。ご著書販売&サイン会開催予定の先生がたは次のとおりです(順不同・参加確定分のみ)。奥野宣之先生・山田真哉先生・野村正樹先生・久保田達也先生・久米信行先生・小中陽太郎先生・小山龍介先生・望月実先生・舛井一仁先生。なお、販売は特にされませんが参加予定の先生方は次のとおりです(順不同・但し、持参した本にはサイン等はしていただけると思います)樋口裕一先生・武者陵司先生・望月照彦先生・松山真之助先生・原尻淳一先生・田中靖浩先生・久恒啓一。皆様ぜひ、先生方との交流を思う存分になさってください。ちなみに、「知の現場」の取材を受けられていない他の著者の方のご参加も大歓迎です。ブースは特にご用意いたしませんが、(空きがありましたらどうぞお使いください)お釣り・領収証をご持参いただけるのでしたら、ご著書の販売OKです。特に新刊を出された方は是非、ご参加いただき、この場で新しいファンを獲得していただければと存じます。 記『知の現場』の出版記念パーティ&先生方大サイン大会・ご著書販売会日 時: 2010年1月26日(火曜・大安)19時~21時場 所:「アグネスホテル東京」JR飯田橋駅から徒歩5分 http://www.agneshotel.com/access.html会 場:地下1階のアグネスホール(収容人員150名)参加費:7000円(事前振込制です)申 込:担当者秋田emirun@nifty.comまでメールにて申し込みのうえ、事前に下記口座までお振込みください。振込口座はつぎのとおりです。-----------------------------------------------------------みずほ銀行・府中支店・普通預金口座・口座番号1670383 口座名義:知的生産の技術研究会(みずほ銀行に略称のチケンで登録済みですので、「チケン」で早く簡単にお振り込みすることが可能です)。------------------------------------------------------------『知の現場』担当および連絡先:NPO法人 知的生産の技術研究会事務局長・『知の現場』プロジェクトリーダー 秋田英澪子 mail:emirun@nifty.com
2010/01/12
コメント(0)
-
安野光雅展(新宿紀伊国屋)--創造性と想像力
新宿紀伊国屋で開催中の安野光雅展をを観てきた。安野は叙情豊かな絵を描く画家で、多くの人が安野の描く風景に癒されている。私も好きな画家である。1926年生まれだから、もう80代の前半になるが、メディアでもよく見かけるから、今も健筆をふるっているのだろう。安野の絵は、島根県の津和野出身であることが影響しているという説が多い。「絵を志すようになったスタートラインは津和野だったと言うほかありません。」と本人もそのことを半ば認めてもいる。工業高校を出たあと、小学校の教員をしてあと、23才で上京し、三鷹市や武蔵野市で小学校教員をしながら勉強し、35才で画家として独立する。42才で「ふしぎなえ」(福音館書店)で絵本作家としてデビューする。芸術選奨文部大臣奨励賞、国際アンデルセン賞など多くの国際賞を受賞し、国内では紫綬褒章、菊池?賞も受けている。2001年には故郷津和野に安野光雅美術館も開館している。この画家の絵は、観る人の心を和ませてくれる。日本の原風景をおだやかに淡い色遣いで描いている。ファンが多いのはよく理解できる。笛吹川小景、富士川、身延山、大菩薩峠、桂川、山村初秋、笛吹川錦秋、笛吹川錦秋、笛吹川晩秋、、。イタリアの風景も展示されている。トスカーナの小さな村、バルベリーニ広場、ヴェネツイア、フィレンツエへの道、ローマ、、。「絵本 歌の旅」「絵のある人生」「絵の教室」などの本を購入して読んでみたが、この画家はエッセイが素晴らしくうまい。絵描きにとどまらず、文章を書かせてもいい。自然やものをみる目がいいと思う。「絵本 歌の旅」では、早春賦、朧月夜、荒城の月、牧場の朝、からたちの花、城ヶ島の雨、琵琶湖周航の歌、山小屋の灯、あかとんぼ、椰子の実、たき火、ふじの山、仰げば尊し、ふるさとなど実に懐かしい童謡、唱歌を題材に、ほのぼのとしたエッセイが並んでいる。映像作家・吉丸昌昭が安曇野の大町南高校に入学して渡された校歌の作詞者をみると吉丸一昌とあり、それが自分の祖父だといういことに驚く。この一昌は「早春賦」の作詞者だったが、確か大分の臼杵に記念館があった。この安曇野には、いわさきちひろ美術館、萩原守衛の碌山美術館もある。ぜひ出かけたい場所だ。「大人になってふりかえれば、その歌詞の意味を読み取ろうとするが、缶を開けて出てくる歌は、軍歌だろうと、恋歌だろうと、歌詞の意味はあまり問わない。」とある。そういえば、韓国旅行で知り合った高齢の紳士は、自分の青春の歌は日本の軍歌だったということを述べていたことも思い出す。「ただでくれるといわれたら、どれにする?」というふうに自分に問いかけてみると、自分なりの目が出来てくるのだそうだ。知り合いの人が、美術館では「自分の家にどれを飾ろうか」と考えて見るといいと教えてくれたが、同じような鑑賞の方法である。「絵の教室」という新書の「はじめに」の冒頭には、「自分で考える」という文章がある。どのような分野でもとにかく「受け売りでなかったらいい」ということを言っているのは共感を覚える。そして「絵が好き」という感性は、好奇心、注意力、想像力、そして創造力になり、枝分かれして物理学、生物学、医学というぐあいに変化しているのではなかろうか」「絵というものは、どうもイマジネーションというノウハウのない世界に力点がかかっているのではないかと思えてきたのです」この本にゴッホのことがでてくる。日本の浮世絵には線がある。縁取りなどの線がある。でもフランスの絵には線がないと、日本の絵に驚いている。私自身、美術館を訪問する機会が増えているが、日本は線で描くにに対し、西洋画は面で描くという言い方をよく聞くが、こちらから見ると未熟な手法だという自虐的な説が多いのだが、相手から見ると優れた手法に見えるということなのだ。「絵を描くとき、自分の意志というより、頭の中に誰かがいて、わたしの感性を左右するらしく、、、」(安野光雅)鴎外も「妄想」の中で「自分のしている事は、役者が舞台へ出て或る役を勤めているに過ぎないやうに感ぜられる。その勤めている役の背後に、別に何者かが存在していなくてrはならないように感ぜられる。」創造性は、想像すること、つまりイマジネーションからはじまります。そしてそれは疑う力とセットになっていると安野光雅は言う。そういう創造力は、子ども時代の豊かな時代にあったと深く思うようになった安野は、そういった日本の美しい自然を描く、残すことを使命と考えているように感じた。津和野と安曇野。私が訪れるべき場所が決まった。
2010/01/11
コメント(0)
-
馬驍水墨画芸術展(伊勢丹新宿店)--「借景生情」
馬驍水墨画芸術展(伊勢丹新宿店)中国伝統の水墨画と油絵を学んだ後、独自の技法で奥深い自然の姿を描き続け、日本のみならず、中国、フランス、アメリカ、イギリスなど海外の個展を開催。変幻自在の技法で大気、風、光が描かれた水墨画。30点が展示されている。馬驍(まぎょう:本名は大長 驍)は、1940年北京生まれ。中国人の父(東京工大建築家卒)と日本人の母を持つ。1979年に日本に帰国し馬驍水墨画会を設立、1982年から2007年にかけて伊勢丹新宿店で初公開をして、以後、全国各地で100回以上の個展を開催している。先日亡くなった平山郁夫さんは「描写力と水墨画を融合し、水墨の新境地を拓いた」と述べているし、加山又造さんは「具象絵画とシュールレアリスティックの、新しい水墨画」と評価している。溌彩画という独自の技法を開発。池袋には馬驍水墨画展示館もオープンしている。姓と名には馬という字がついているように、この画家の作品には「馬」が多い。溌墨画「唐代の王こうの溌墨法と英国水彩画の湿画法を用いて、私自身の溌墨の特殊技法を生みだした。」という馬驍は、大自然を師として、山水画でもっともむずかしい雲、すなわち空気の流動感と透明感を描こうとしている。目標と方法、そして人生の軌跡の三つが渾然一体となって、今日の私の創作活動を支えている。 * 創作の目標「自分の作品が、東洋人と西洋人、専門家でああるとないとを問わず、老若男女の皆さんに理解され、喜んでいただけることを目標にしています」そのため「先人や他人のも模倣ではない真実の自分を作品の中に表現するよう心がけています。 * 創作の方法「私は中国伝統の溌墨画の特徴に西洋画の立体感と空間表現を統合させ、伝統的でありながらも革新性に富んだ独特の溌墨山水画を世に問うてきました。」「日本人の心と禅の精神を作品に溶け込ませることを目指しています。」 * 創作と自分自身の人生とのかかわり「私の父は中国人、母は日本人です。、、、」文化大革命で建設省の最高技官の父はスパイ容疑により内モンゴルに追放される。四人組に迫害を受けて病死した父は、35才の馬驍に臨終時に子供達と一緒に日本に帰るように遺言する。39才で帰国。静岡で設立した馬驍水墨画会は、1996年現在で全国に16支部、400人の会員を数えている。この伊勢丹の展覧会では、30万-60万円が一番多かった。「画集の出版はマラソンの一里塚のような大切な意味を持っています。」創作の要諦鷹の剥製を写生し、形態と構造をよく知る。実物をよく観察して動作や飛翔の規則を把握する。鶴。取材では、美しい動作や形態をとらえることが大切。画面に組み合わせる時は、疎密の変化や動作の相違、相互の関係や遠近に注意。波。規則性を観察。実際よりも誇張して描くと、より一層生動感のある画面が表現出来る。富士山。高い所や低い所から、また、遠方や近くから、それぞれ観察と写生をしてみて、初めて富士山の本当の姿が認識できるのである。富士山の精神的な美しさを表現したい。「借景生情」という中国の言葉がある。写生は、創作の完了ではなく、絵画創作の素材となるものである。
2010/01/10
コメント(0)
-
インターゼミ(社会工学研究会)最終論文提出
インターゼミ(社会工学研究会)の最終論文提出日。5つのグループの最終論文に関するまとめの発表のあと、寺島学長と担当教員のコメントという進行となった。「いい展開」「「よくやった」「「よいフィールドワーク」という総括に加え、来年度以降のテーマ設定のヒントがいろいろあった。 * 多摩ニュータウンの再生多摩大学という名前・ローカリティとグローバリティ・多摩大総研・インターゼミ・多摩学・地歴・多摩の印刷史・羽村の中里介山・多摩の歴史・歴史・地理・文化・多摩大に集積・グローカルを思想の柱に・輪郭のしっかり * アジアとの交流プログラム多摩大は均質化(強み・弱み)・個性と輪郭(地方生・留学生・多摩学)・単位認定・環日本海連携・外との連携を深める・外との接点をじわりと広げる * グリーンユーディール外との相関・政治性のあるテーマ・COP15の年という総括・収斂 * ディズニーの研究サービスエンターテイメント産業・サービス産業に関する知見・まだ100分の1・次世代ICTにもかかわる(3Dなど) * 東鳴子温泉の活性化--「東鳴子温泉活性化に向けての都会の若者からの提言」観光庁・大崎市・宮城県などに報告・マイルストーン・食と農の方向・研究委託・地域学まとめ断片的でなく体系的に世の中を見る・ものの見方・切り口・ネトワーク型・相関性・シナジー・全体知・マージナル・ウチとソト・会社と社会・インター(間)・プロジェクトエンジニア・art of life(人生のアーチスト・鈴木大拙)・筆と絵の具・自分の絵を描く・貢献すること・最初の日(4月11日)に述べたアセットマップトヒューマンリレーションマップ・動いてくれる人間関係全論文(例えば東鳴子チームはA4・35枚)を学長が読んだ後、一度総括のゼミをもう一度行う方向になった。終了後、打ち上げ会。教員5人とほとんどのゼミ生が参加。--------10時40分:業績評価検討会12時10分:大学院教授会16時20分:インターゼミ
2010/01/09
コメント(0)
-
「日本政治の課題―組織・人材・政策」--佐々木毅(元東大総長)
7日の多摩大リレー講座は仕事で講義を聴けなかったところ、NPO法人知的生産の技術研究会http://tiken.org/の八木哲郎会長http://plaza.rakuten.co.jp/gendaiturezure/がまとめたものを送っていただいた。要旨を掲載します。---------------------多摩大リレー講座「佐々木毅」講演のまとめ日本政治の課題―組織・人材・政策1. 政治の主役としての政党の存在感。日本の政党は官僚制優位体制を前提にした国会議員の集まりである。与党という言葉はその残滓、イデオロギーを基盤とする組織政党ができていない。政党が政府・官僚制から独立した組織として発達することがなく、それへの寄生的な性格が強かった。明治維新以来日本を築いてきたのは官僚と軍人であり、政治家の存在は希薄であった。坂の上の雲というドラマにも軍人と官僚が主役であるが、政治家は出てこない。藩閥時代は政治家の存在感が大きかったが。アングロサクソン社会が政治家が大いに活躍し、政治のウエイトが大きい。アメリカでは官僚などは出てこない。ドイツは軍人と官僚が強い、フランスも官僚制と軍隊が強い。自民党は長期政権であることによって党員を増やした。その数は数百万とも呼ばれた。その多くは政府とそれに連なる利益・業界団体のメンバーが知らないうちに党員にさせられたり、義理で入ったりしていた。また個人後援会のメンバーは党員であった。味方になる人を増やすことが政権の維持安定につながり、いろいろな要求を聞いて受け入れ、ギブ アンド テイクの関係を築き、支持母体を増やした。自民党だから支持するのではなく政権与党であるから支持するという関係になり、政権交代が起こりにくい構造ができていた。与党であるから与党でいられるという構造(自己増殖型構造)、ここから一党優位体制が出現する。(野党の存在価値はどこに)しかし、一昨年のリーマンショック以来政府・官僚制の社会的・経済的権威が著しく失墜し、一党優位体制の仕組みは終わった。政治は中の中に属する人が7割くらいいる国家が最も反映し安定する。しかし中産階級中心型の社会は格差の拡大によって失われている。これからは政治の主導体制への漸進的移行が21世紀の日本政府の基本的な動向である。さらに政党間競争をおこし、、選挙制度の改革やマニフェストの約束によって政党間を対決可能にし、政権交代可能な政党システムへ移行しなければならない。ボトムアップ型からトップダウン型へ(政治のリーダーシップの可視化)、日本の政党は足腰の弱さが拡大し、支持率主導型政治への転落の可能性が増しているが、支持率さえ上げていれば政治の役割を果たしたとは言えない。少々の支持率が変動しても堪える政治が必要である。今、民主党はマニフェストにこだわりすぎてそれに縛られているという人も多いし、マニフェスト違反だと怒っている人も多い。政権を担当した以上、ぐらぐらしていたら訳がわからなくなる。政権交代は政党の組織問題の解決にただちにつながるものではない。対策と結び付いた組織化の可能性、いかに多くの人を支持者に組織するかが重要である。昔自民党は医師会、遺族会、宗教団体などを組織して支持団体にしていたが、小泉政権時代にそれらが失われてしまった。民主党はたくさんの人たちを支持者に組織することによって支持率主導型政治に対する政党の抵抗力を醸成することができる。これなしには長期的な視点に基く政策は困難である。2 政治と人材政治家には政党に所属して議員になるタイプもあれば知事とか首長のように直接選挙で選ばれることを求めるタイプもある。こういうタイプは権限が大きいが、個人が負担を背負いこむ。政党政治は集団で統治するので、多様な人材の有効活用を念頭においた政治のスタイルを作らねばならない。選挙に強いことは必要条件であっても、重要な役目を果たすためには十分条件ではない。党内がバラバラであっては困る。トップの指導力が強いのはイギリスで少数の幹部がすべて仕切り、あとはバックベンチャーである。人材はあまりにも同じタイプばかりだと硬直する。人材には得手不得手があって選挙に強い人、国会運営に長けた人、党内運営のうまい人、など様々な能力が必要である。トップは政党にとっていわば最大の商品である。それが全体ににじみ出てくる。人材育成にとって素質と訓練、経験の3つが不可欠である。政権党は政権を取っている長い間に党員をいろいろな役職につかせて訓練し経験を積ませる上で人材の育成と選抜の機会に恵まれている。自民党待っている人たちを当選回数に従って大臣に登用したりして経験をつませた。しかし素質が大事で素質を欠いた人はマイナスになる。政治家はなってみないとわからないことが多い。有権者にむかってよくしゃべることが政治家の能力のように思われるが、本当に有権者に信頼されるには相手の話をよく聞くことが政治家の評価になる。3割しゃべって7割聞く。こうしてはじめて有能な政治家が育つ。小泉政権時代は民間人の起用が多かったが、これが政治家の訓練の機会を逆に奪う。民主党はこのことを考えているらしい。組織運営と人材育成との連携について日本の政党はほとんど偶然任せ。足腰の弱さを自覚するならば議員間での組織運営と人材育成について継続的な努力がますます必要である。選挙ができることと政権を担い、統治することとの間には大きなギャップがある。政党はこれをうずめることに努力が必要である。自民党はかつて派閥に人材育成の機能を代行させていたが、派閥が消滅するにつれ、その機能が衰弱してしまい、それに変わる仕組みを実現できなかった。(統治ができるトップよりも選挙に勝てそうなトップへ)、民主党はすべてこれからであるが、膨大な数の新人議員をどう育成するか、議員の半分が若手新人である。これをどう指導し、選挙に勝てるメンバーにするかが大きな課題である。3 政治と政策 財政の無駄を省くとともに政策方向を転換するというのが目下の内政の課題である。「コンクリートから人間へ」「昔は良かった」「格差是正」という過去の是正も大事であるが、未来を見据えてどう未来を切り開くかが大事である。自民党は20世紀型経済・働き方だったが、それはリーマンショックで確実に終わった。21世紀型社会を目指して「しのぎ」から新たなモデル作りへ、未来志向なしには国民に負担増を求めることはできない、21世紀の経済構造、社会構造をどうするか民主党はそろそろそれをはっきり示さねばならない。今の社会は20世紀型で作られており、定年制とかいうのは若い人がたくさん供給できた時代の物である。ひとことでいえば量を拡大し、それで勝負する時代だった、軍事力しかり、経済力しかり、自民党の時代はそれだった。そういう時代は終わった。民主党の目玉は子供手当を優先的においている。それが一丁目一番地の売り物である。政治の歴史感覚が問われる時代、財政危機は政治の危機の象徴であり、それを乗り切るのが当面の課題である。国際環境の大変動への鋭い感覚と確かな目測能力が大事である。---------------------午前中は、講義。午後は、大学パンフレットの取材を受ける。マネジメントデザイン1・2とインターゼミ。夕刻は品川で研修会社の担当者と打ち合わせ。夜は、ビジネスマン時代の上司の中村さんと懇親。
2010/01/08
コメント(0)
-
Sankei News Channel
9時:出勤。9時半:学長室ミーティング11時:ホームページ打ち合わせ12時半:多摩大総研中庭先生と地域活性化マネジメントセンターの新しい部屋で打ち合わせ13時:産経新聞「祝賀版」と「産経動画ニュース」の取材で二人みえる。知研の八木哲郎会長も同席。「知の現場」パーティ上映&産経動画ニュース(YOUTUBE)は、下記のように活用。 * 1. 1/26の出版記念パーティの際に、10分の動画に編集して、会場で流すhttp://tiken.org/modules/news/article.php?storyid=55 * 2. おみやげとして、上記パーティの参加者にDVDの形で配る * 3. 産経新聞の動画ニュースとしてYOUTUBEで流すhttp://www.youtube.com/user/SankeiNews取材テーマ:図解思考と「現代の志塾」多摩大学 * 1.就活は難しくない!志のある企業を目指せ! * 2.まずは志のある大学に入ろう * 3.大学の4年間でどんな志を持つのかが重要! * 4.産・学・地元連携の多摩地区の試み(「志」での連携) * 5.「知の現場」のプロジェクトを総括する!産経新聞は、「特報版」や「祝賀版」と銘打って、本紙とは別の広告媒体をつくり新しいビジネスとして展開している。また、動画ニュースを配信してり、こちらは見ている人もずいぶんと多いという。新聞社もさまざまな業態を試みている。14時半:学長到着。いくつかの案件の説明と決済など。本日は、リレー講座があり、講師は佐々木毅先生。東大総長だった政治学者。この講義は聴けなかったが、講義の要約は八木哲郎さんのブログ「現代徒然草」でアップしていただけるとのこと。http://plaza.rakuten.co.jp/gendaiturezure/16時20分:ホームゼミ。年末年始の動きを全員から報告を受けた後、実習。インターゼミ東鳴子温泉活性化チームの最終論文の詰めを宮城君と行う。---------1月7日は、1989年に 昭和天皇崩御。明仁親王が即位し今上天皇となり、新元号を「平成」と決定。昭和64年最後の日。1月7日生まれの著名人。白洲正子。1910-1998年。昭和-平成時代の随筆家。明治43年1月7日生まれ。樺山(かばやま)愛輔の次女。白洲次郎の妻。女人禁制の能舞台に演者としてはじめてたつ。昭和18年「お能」を刊行し,「能面」「かくれ里」で読売文学賞を2度受賞。古美術,古典文学,紀行などはばひろい分野で活躍。平成10年12月26日死去。88歳。東京出身。アメリカのハートリッジ-スクール卒。http://d.hatena.ne.jp/k-hisatune/20080627
2010/01/07
コメント(0)
-
「川喜田半泥子のすべて」展--「大夢出門」という書は、Time is money
母親が九州から上京したのが12月24日、そのまま横浜の弟の新居で過ごす。30日には迎えに行き、我が家で正月を過ごす。母は40年来の歌人で、現在までに短歌集3冊(「風の偶然」「風あり今日は」)とを刊行し、70歳の時に「万葉集の庶民の歌」、80歳の時に「わたしの伊勢物語」という2冊の著書も刊行している。朝日新聞の大岡信の「折々の歌」(2004年12月19日)にも夫の看病を歌った歌も取り上げられたこともある。このときは最初に私が見つけて連絡した思い出がある。このときは本人は知らなかった。http://www.hisatune.net/html/05-career/private/05-1d.htm私の家にいた期間に、元旦にたまたま散歩しながら短歌のまねをしたところ、添削をしてくれて短歌らしくなった。これじ味をしめて数首つくってみた。実地の添削と解説なので、頭に入る。今年の正月の最大の収穫は、この短歌である。その母を直行バスで羽田まで送っていきながら、いろいろと話をする。多摩川の流れ、ビルの林立する赤坂、レインボーブリッジ、多摩川が海に注ぐあたり、そして羽田空港。今までは福岡空港だったが、今度は比較的新しい初めての北九州空港の往復である。---母を見送った後、銀座松屋で開催中の「川喜田半泥子のすべて」展に向かう。http://www.matsuya.com/ginza/topics/100118e_kawakita/index.html「東の魯山人、西の半泥子」と並に称された一流の風流人。伊勢の豪商の家に生まれ、百五銀行頭取、地方議員などの養殖をこなしつつ、書画、茶の湯、絵画、写真、建築、俳句と多芸ぶりを発揮する。とりわけ50才を過ぎて始めた陶芸では破格の才を示し、自由奔放ななかにも雅趣に富む世界を創造、「昭和の光悦」と声価をを高める。1878年生まれで、魯山人より5才上、加藤唐九郎より20才上という年齢感覚である。84才まで風流の道に生きた。書や俳句などではユーモアとウイットに富む作品が多い。「大夢出門」という書は、Time is moneyの邦訳。「波和遊」は、How are you?「愛夢倶倶楽通志友」は、I am glad to see you.36才から号として用いた「半泥子」は、「半ば泥(なず)みて、半ば泥まず」という意味である。「半泥子は、なににでも没頭し、泥んこになってしまう。泥んこになりながら、冷静におのれを見つめることを忘れない。大胆なふるまいをし、ハメをはずしているようでも、芯となる風雅の要諦は、けっして踏みはずさない。」(美術評論家・吉田耕三)無茶法師と名乗った連載随筆が本になっている。それが「泥仏堂日録」で、連載中から人気あった。日録の冒頭には、「此の無茶法師無茶苦茶が、是から記される日記である。読む人こそ災難である」とあり、単行本になるときのあいさつでは「、、それにしてもこれを読まされる方々こそお気の毒さまである」と書いている。人柄や処し方がわかる気がする。尾形乾山、仙涯、光悦、、などの名前が出てくる。資料を読んで、改めて半泥子についてまとめてみたい。
2010/01/06
コメント(0)
-
1月5日生まれの人々
思い立って、本日(1月5日)生まれの人を探す。バーナード・リーチ(イギリス人の陶芸家)は1887年生まれ。三木清(哲学者・兵庫県)は1897年生まれ。片岡球子(日本画家・北海道)は1905年生まれ。現在活躍中のところでは、宮崎駿、石川好、高橋三千綱、加藤秀樹、沢松和子、南部靖之、塚本慶一郎、などがいる。--これらの人の人生を追う。バーナード・リーチイギリスの陶芸家。イギリスで美術を学んだのち、明治四二年(一九〇九)来日。陶芸を学び、日本民芸運動に加わる。日本とイギリスの陶技を融合した作風をもち、両国の工芸の発展に尽くす。(一八八七~一九七九)三木清大正-昭和時代前期の哲学者。明治30年1月5日生まれ。西田幾多郎(きたろう),ハイデッガーらに師事。昭和2年法大教授となり,唯物史観の立場から哲学を論じて論壇にむかえられた。5年治安維持法違反で検挙,20年再検挙される。昭和20年9月26日獄死。49歳。兵庫県出身。京都帝大卒。著作に「パスカルに於(お)ける人間の研究」「唯物史観と現代の意識」「人生論ノート」など。【格言など】決して失われることのないものが本来の希望なのである(「人生論ノート」)片岡球子昭和-平成時代の日本画家。明治38年1月5日生まれ。吉村忠夫,安田靫彦(ゆきひこ)らに師事。昭和5年院展で「枇杷(びわ)」が初入選,27年日本美術院同人となる。母校女子美大の教授。歴史上の人物を主題にした「面構(つらがまえ)シリーズ」を迫力のある表現で連作し,50年「面構―鳥文斎栄之(ちょうぶんさい-えいし)」で芸術院恩賜賞。57年芸術院会員。平成元年文化勲章。平成20年1月16日死去。103歳。北海道出身。--三木清について、もっと詳しく調べる。哲学者。明治30年1月5日、兵庫県揖保(いぼ)郡平井(ひらい)村(現たつの市)の富裕な農家の長男として生まれる。1914年(大正3)第一高等学校に入学、西田幾多郎(きたろう)の『善の研究』を読んで感動し、17年京都帝国大学哲学科に入り西田に師事した。卒論は「批判哲学と歴史哲学」。新カント派の影響が強く示されているが、末尾で「普遍妥当的な価値は如何(いか)にして個性のうちに実現されるか、これが我々の根本課題である」と記し、早くもそれを超えていく姿勢がみられる。 1922年から25年までドイツ、フランスに留学、リッケルト、ハイデッガーに学んだ。留学中から発表していた論稿をまとめて『パスカルに於(お)ける人間の研究』(1926)を処女出版。「意識」に与えられた人間ではなく「絶対に具体的なる現実」としての人間を、「哲学の体系」としてではなく「生」そのものにおいて理解しようとしており、ハイデッガーの影響とともに、三木独自の人間学の出発点が示されている。 27年(昭和2)法政大学教授となるが、このころから「人間学のマルクス的形態」をはじめ多くのマルクス研究を発表、一躍論壇のスターとなった。これは、マルクス主義の理論家福本和夫(かずお)の華々しいデビューに刺激された面もあるが、自らの人間学に物質的な基礎を与えようとする意図を秘めていた。それらは、固定した公式として客観的な法則として理解されがちだったマルクスの思想を、「社会に於(おい)て生産しつつある人間」から出発して「発展の過程にある現実的なる理論」として主体化しようとする試みであった。しかし、正統派左翼からは「観念論の粉飾形態」として厳しく断罪された。 1930 年、日本共産党に資金を提供したかどで治安維持法違反に問われて検挙され、以後公職を退き、マルクス主義からもしだいに距離を置くようになった。『観念形態論』(1931)、『歴史哲学』(1932)、『人間学的文学論』(1934)などを公刊する一方、雑誌や講座の執筆、編集に精力的に活動した。また、ヒューマニズムの立場にたって、ナチスへの抗議、京大滝川事件への抗議、天皇機関説問題への警告など、社会的にも活発に動いた。37年「構想力の論理」第 1回「神話」を発表し、以後「制度」「技術」と書き継いで、『構想力の論理 第一』(1939)をまとめた。さらに「経験」を書き、「言語」を予告したが未完に終わった。これは、スタイルのうえでは体系的な叙述になっていないが、同時期に並行して発表した『哲学ノート』とともに、自らの思索に一定の形を与えようとする三木の試みであった。 三木の思想のもっともまとまった叙述は『哲学入門』(1940)にみられる。ここには、終生の師である西田の影響とともに、マルクス体験も刻印されている。現実を「対象」としてではなく、「そこで働き、そこで考え、そこに死ぬる」「基底」とし、「主観的・客観的なもの」としての人間に着目し、世界を創造することによって自己を形成する「技術」の哲学を展開している。この間、近衛(このえ)内閣の政策集団「昭和研究会」に参画、理論的主柱となる「新日本の思想原理」(1939)を書き、「東亜協同体論」を提起した。しかし、時代への抵抗は、しだいに絶望感から虚無感へと変化し、親鸞(しんらん)の末法思想へと傾いていく。1945年(昭和20)3月、友人タカクラ・テルをかくまったかどでふたたび治安維持法違反に問われ、戦後も釈放されないまま、同年9月26日東京の豊多摩拘置所で獄死した。64年故郷のたつの市白鷺山(しらさぎやま)公園内に三木清哲学碑が建立された。[渡辺和靖]ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー初泳ぎ。今日の一首。 プールよりジャグジー目当ての高齢者 色とりどりの水着で集う
2010/01/05
コメント(0)
-
「キャリアデザイン」よりも「ライフデザイン」という視点で
初出勤。学長からは、テーマをいくつかもらう。面白い展開になりそうだ。学部長、何人かの同僚達と会い新年の挨拶をした後、今年の方向や懸案についての意見交換をしながら歓談する。もう4日から授業も始まっている。日経新聞に日経ビジネスアソシエの本日発売号の広告が出ていたので、早速入手する。「大人の教養&マナー」特集と聞いていたが、私の記事は「休活で人生を変える!」」という特集の「提言」というコーナーだった。当初から予定されていた企画ではなく、昨年の「時間管理」に関する記事のインタビューの時に振られた企画で、時間がなく電話でのインタビューとなったので、どのような記事になるかなあと思っていた。「1年365日のうち休日は119日!」「肩書きをはずした休活で自分を鍛えれば、厳しい時代を乗り切るヒントが見えてくる」「休活で人生を変える!」というのが企画全体の趣旨である。「仕事術」「手帳術」「人脈術」など最近のビジネス雑誌は、切羽詰まって即役立つ特集記事が満載だが、「教養」や「休日」をテーマにしたのはいいと思う。本当は、細かな仕事の技術に特化するよりも平日と休日、仕事と趣味、などのバランスが大切だ。「キャリアデザイン」を含んだ「ライフデザイン」が大切なのだ。私の記事は三分の二ページで、「提言。「面白い」を続ければ、専門分野になる」というタイトル。ビジネスマン時代は、平日は本業、休日はビジネスマン勉強会である「知的生産の技術」研究会の活動という二本柱で動いた結果、休活でやっていた分野(図解コミュニケーション)が専門分野として認められ、大学教授に転身。そして今度は、平日は本業、休日は「人物記念館巡り」という二本柱で活動し、5年で300館に迫る頃から、休活で行っている活動が著作として表現できる段階になるなど専門分野に育ってきている。そういうストーリーだった。「目先の利益を求めると長続きせず、結局、ものにならない。一番いいのは、ほかの人はまだ中目していないけど、自分にとっては面白いという活動。好きで続けるうちに、誰も追いつけないレベルに達すれば、それは立派な専門分野。どんなジャンルでも、必ず自分の武器になります」。----------本日(4日)の日経新聞に「知の現場」(久恒啓一監修・NPO法人知的生産の技術研究会編・東洋経済新報社刊)の広告が出ている。珍しくこの本だけヨコ組になっている。目立つかもしれない。---------朝日新聞では月曜日に「朝日 歌壇・俳壇」というページがある。今までこのページに興味は無かったが、歌を詠むことにしたので、自然に関心がでてきた。気に入った歌と句を記録してみる。いい歌や句がある。ウェブ時代を彷彿とさせるものや時事ネタも意外に多い。こういう名首・名句を味わっていると、人生が豊かになる気がする。三万の兵を増やして六千を柩とともに帰す国なり(アメリカ在住者)乃木軍の旅順を攻めし展開をグーグルアースの地形に探るひたひたと死に近づくと言ひし母卒寿を前に万歩計つく相続の話ながなが聞きながら鍋の大根時どきいじる絵文字なきメールは友の訃報なり師走朔日享年五十こけし屋は木を見るだけで力湧く来年の原木買ふを決めたり道後にて見る真之の衣装櫃・子規のの褪せたる従軍鞄新幹線開通控える駅舎前馬が草食む「七戸十和田」声までも紅葉に染まり戻りけり(2009年朝日俳壇賞)まだ生きて年賀状など書いており今頃は京都あたりか毛糸編む手袋に五指の個性を納めたる
2010/01/04
コメント(0)
-
継続と記録の人--本居宣長に学ぶ
本居宣長(1730-1801年)は、35歳の時に着手した「古事記伝」全44巻を、35年の歳月をかけて70歳で完遂し、翌年亡くなっている。日記は、自分の生まれた日まで遡って書き、亡くなる二週間前まで書き続けていて、「遺言書」を書いて葬式のやり方から墓所の位置まで一切を支持している。宣長は記録魔だった。宣長は学問において、最も重要なことは「継続」であると考えていた。そのためには生活の安定が大事だと考えていた。彼の生活スタイルは、昼は町医者としての医術、夜は門人への講釈、そして深夜におよぶ書斎での学問だった。多忙な中で学問をするために、宣長は「時間管理」に傾注する。近所や親戚との付き合いをそつなくこなし、支出を省く。そうやって時間を捻出し、金をつくり書物を買い、そして学問の道に励んだ。学問する環境をいかに整えていったか、そして日常生活をいかに効率的に過ごすかというマニュアルが膨大に残っている。「されば才のともしきや、学ぶことの晩(おそ)きや、暇(いとま)のなきやによりて、思ひくづれて、止(や)むことなかれ。とてもかくても、つとめだにすれば、出来るものと心得べし。すべて思ひくずるるは、学問に大にきらふ事ずかし」(自分には才能がない、学問を始めたのが遅い、勉強する時間がないからといって、学ぶことを怠ってはいけない。如何なる場合も諦めず努力しさえすれば、目的は達し得るものであることを知るべきである。道半ばで挫折をしてしまうことが、学問の神様の最も嫌うところである)本居宣長は五百人の門弟を抱えていたが、彼の偉い点は、「学ぶことの喜びを多くの人に教えた」ことにある。養子の太平が描いた図が残っている。「恩頼図」といって、自分の学問にあたって恩を受けた人々と、自分を通してその学問に連なる人々の名前が記録されている。中央に宣長自身と、宣長が著した古事記伝を中心とする著書も配置されている。三重県の松坂には本居宣長記念館(吉田悦之館長)があり、そこには1万6千点に及ぶ宣長に関する資料が保存されている。今年はこの記念館にも訪れたい。今日は私にとって大切な日だったが、本居宣長のことを書くことになったのも何かの思し召しだろう。-------------------今日の一首。 犬友となりし夫婦の名前も知らず 今朝も笑顔をであいさつ交わす
2010/01/03
コメント(0)
-
初春の 冷気切り裂く 銀輪の 若者の足 鋼の如く
仙台にいたときは、泉区の加茂神社という地元の神社に毎年お参りをしてりた。この神社には10年以上通ったのだが、受験などのお願いなどすべて聞き届けてくれた気がする。やはり地元の神に祈るのが一番だ。今住んでいる多摩ニュータウンでは今年で二回目の正月となるが、小さくて、目立たない、そして人が少ない、近所の日枝神社へ初詣でをする。この神社は「国常立命(クニノトコタチノミコト)」を祭っているが、国常立命は、調べると、天地開闢の神で、国土形成の根源神、国土の守護神として信仰されている神であるとされている。なるほど、多摩ニュータウンの一角にある神社にふさわしい神である。新住宅市街地開発法に基づく多摩ニュータウンの建設に伴い、昭和50年12月に鎮守日枝神社を遷宮し、八坂神社合祀との記述が「区画整理記念」という石碑にある。毎年お神籤をひく。お神籤で思い出すのは、成田山だ。ある年にひくと「凶」がでた。他の場所でひき直すと「大凶」がでた。何度引いても「凶」がでる。だんだん気分が滅入ってきて、怖くなってくる。気を取り直して引きつづけると、とうとう5回目あたりに「末吉」が出てそれでやめにしたことがある。少し身構えて生活をしたのだが、この年には、いくつか良くないことはあったが、それほどではなかった記憶がある。さて、昨年は「小吉」だったが、今年は「中吉」と運勢は、少しよくなっている。和歌や運勢、具体的なテーマ毎のお告げをみると、実際には「大吉」のような気がしてくるから、今年はいい年であると思うことにしよう。同行した、娘も息子も、妻も、そして母も、私を除けば全員が「大吉」だった。昨年は、末吉と小吉と中吉だったから、我が家にはずいぶんと運が向いてきたのではないだろうか。さて、私の運勢を示す和歌は、次の一首だった。穏やかな年を連想させる。 いそしみし しるしは みえて ゆたかにも こがね なみよる おやまだのさと運勢は、以下。自重して励めばいいということだ。 する事なす事幸いの種となりて 心配事なくして嬉しき運なれば わき目ふらず一心に自分の仕事大事とはげむべし 些かも我儘勝手の気を起こして色や酒に溺れるな具他的なテーマ毎のお告げは、下記。自分と師匠を信じて進めばよいということだろう。 * 願事 のぞみのままなり 人の言葉に迷ふ忽れ * 待人 おとずれるなし来る * 失物 出づるも手間どる * 旅行 よし、連人に注意 * 商法 利益あり進んで吉 * 学業 師の教にしたがえ * 方角 何れにても可 * 争事 勝ちし後ぞくが利 * 抱人 人の世話あり吉 * 転居 差支えなし * お産 やすし安心すべし * 病気 早く本復すべし * 縁談 多くて困ることあり静かに心を定めてよしさて、今年は日本探検の一つとして短歌を試みてみようと元日に思った。日本文化の本質は和歌にあり、その伝統は短歌として生きている。私の母は、40年ほど短歌の世界にいる歌人なので、教えてもらいながら、歌をつくってみる。朝の散歩時に浮かんだ歌に、母に少し手を入れてもらった今日の一首。 初春の 冷気切り裂く 銀輪の 若者の足 鋼の如く
2010/01/02
コメント(0)
-
裸木に梢(うれ)に光の花が咲く 初日の出のスポットライト
新年、あけましておめでとうございます!2010年の元旦、いかがお過ごしですか?気がついたら、21世紀も10年経ってしまいましたね。今年は仙台から東京に移って3年目を迎えます。仕事や家庭のインフラもしだいに整ってきており、公人(仕事)、個人(ライフワーク)、私人(家庭)、それぞれの役割をバランスよく果たしながら、相乗効果をあげていこうと考えています。年末にかけて今年の計画の遂行状況をチェックし、大晦日に今年の総括を行いました。(「今年はどういう年だっただろうか?」--大晦日の今年の総括http://d.hatena.ne.jp/k-hisatune/20091231)その結果、今年やるべきこともはっきりと見えてきましたので、その道を着実に歩んでいこうと元日に改めて決意を新たにしています。初詣で、どのような「おみくじ」を引くか楽しみです。ウェブ時代を以下のメディアを駆使しながら乗り切っていきたいと思います。よろしくおつきあいください。・Twitter:http://twitter.com/hisatune 926ツイート フォロワー573・ブログ「今日も生涯の一日なり」http://d.hatena.ne.jp/k-hisatune/ 1952日連続記入・メルマガ「学びの軌跡」http://www.mag2.com/m/0000033275.html 707号・ホームページ「図解Web」http://www.hisatune.net/ 122万ヒット本年の皆様のご多幸をお祈りしております。----------------------------------------------元旦の早朝に詠んだ短歌です。今年は短歌に挑戦してみようか。さくさくと霜柱踏む里山の 初日の出みる妻と二人で裸木の先にまばゆい花が咲く 初日の出のスポットライトマンションの階段昇り元日の 初富士の姿こころあらたなり
2010/01/01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1