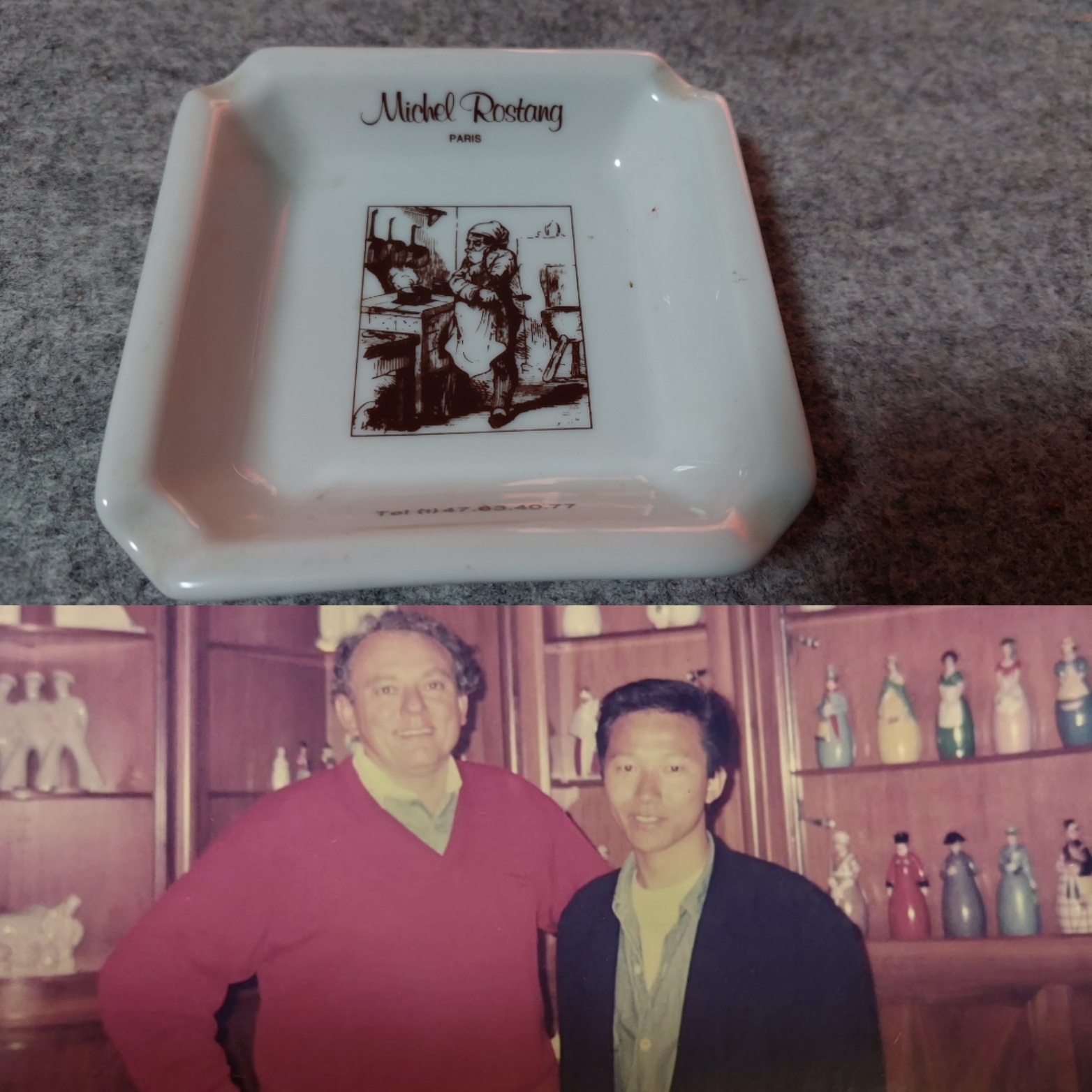2023年11月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

歩いて巡る隅田川河口の島々(その1)
この日は11月1日(水)、品川駅で現役時代にお世話になった協力会社の社長と17:00に待ち合わせの約束をしていた。先日の10月7日(土)に「隅田川屋形船の旅」を楽しんだが、屋形舟から見た隅田川そして運河沿いの様々な場所を歩いて訪ねて見たいと思い、この日は自宅を7:00に出て、小田急線、新宿駅から都営大江戸線を使って「勝どき」駅で下車する。地下道にあった、海に棲むギリシャ神話の神々を描いた壁画。ギリシャ神話風の人魚や妖精?たちが描かれていた。塙雅夫(Masao Hanawa)作フレスコ画・「海 ― Living Sea ―」。人魚が見上げているのは、勝どきの街の風景。近づいて。場所を移動して。そして「A4a」出口から地上に出ると正面にあったのが「勝どき駅前」交差点。中央区勝どき1丁目8-1。道路の反対側には勝どき駅「A1」出口。現在地の「勝どき」駅とこの日に巡った「隅田川河口の島々」の2島をGoogleマップから。高層マンション「勝どきビュータワー」。地上53階 地下3階建。中央区勝どき1丁目8−1。「晴海通り」にあった地図。右260m「勝鬨橋」、左280m「黎明橋」。そして「勝鬨橋」方向に歩く。右手にあったのが「中央区立子ども家庭支援センター」。18歳未満のお子さんや子育て家庭のあらゆる相談に応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在宅サービスの提供やケース援助、サークル支援やボランティア育成等を行っているとのこと。中央区勝どき1丁目4−1。「中央区立こども家庭支援センター きらら中央」。「中央区立 勝どき保育園」。センター内に入ると正面に、抽象的なモチーフの可愛らしいステンドグラスがあった。右。中央。左。その先にあったのが「月島警察署 勝どき橋交番」。中央区勝どき1丁目3番8号。近づいて。「中央区立月島第二小学校」の時計塔。時間は9:20。中央区勝どき1丁目12−2勝鬨橋の南詰にある「プラザ勝どき」の敷地内にあった「三五稲荷神社」。中央区勝どき1丁目1。正面から。奥へ進むと「さわやか保育園」があり、その校舎の手前に鎮座していた。乾汽船株式会社(旧・イヌイ倉庫)が奉斎する稲荷神社であると。木彫りの鳥居の扁額も「三五稲荷神社」。社殿。創建したのが明治37年の3月5日、祭礼は3月5日と会社の創立記念日の10月19日。とりわけ社名由来が創建日だと明記されているわけではないが、大筋で由来とみて間違いなさそう。よって「三五稲荷神社」。狛狐(右)。阿吽の表現はなされてなく、どちらも口を閉じている。右が子抱き、左が玉を抱える。抱かれている子供の懐き方がとてもかわいらしいが、顔はどうみてもヒゲを蓄えたおじさん。狛狐(左)。耳が大きくまっすぐ上に伸び、彫の深い個性的な狐像。四角い小顔に濃いあごヒゲ、奥目にしっかりした鼻筋。社殿に近づいて。「三五稲荷神社由来当稲荷神社は 明治三十七年(1904)三月五日に 京都伏見稲荷神社の分神として創建されたものであります 以来 勝どき河岸倉庫地区の守護神として 当地に鎮座されて居ります。祭神は倉稲魂命(うかのみたまのかみ)であります 『倉稲』(うか)は食物の意味で五穀を司り 農作物を護る神といわれています 初期の倉庫業においては 米穀を主とする農作物が主要な貨物であった為 稲荷神社を祭り倉庫の守護を祈るということが ごく自然な発想で行なわれたようであります毎年三月五日と当社創立記念日には 日頃の御加護に感謝し 社業の発展と 地域の平安を祈願して 三五稲荷祭を執り行って居ります平成三年十月十九日 執行施主 イヌイ建物株式会社」そしてその裏にあったのが「月島川水門」。・形式:鋼製単葉ローラーゲート・径間:11m×1連・門扉高さ:8.9m・竣工:昭和39年度・平成28年度に耐震化工事が完了し門扉等が新しくなった。中央区月島3丁目25−9。隅田川と月島川を隔てる水門で、1964(昭和39)年度に竣工。水門は、堤防の役割を果たす構造物。月島川は、1892(明治25)年に完成した埋立地である月島1号地(現・中央区月島)と、1894(明治27)年に完成した埋立地である月島2号地(現・中央区勝どき)の間で埋め残した水面。さらに南西側にある新月島川、月島・勝どき地区と晴海地区を隔てる朝潮運河とともに、月島川水門を含む4つの水門によって浸水被害から守られている。月島川に浮かぶ屋形舟を見る。「月島川水門テラス連絡橋」から「月島川水門」を見る。隅田川上流を見る。左手の高層ビルは「聖路加レジデンス」:地上38階/高さ146.1m/1994年竣工。「聖路加レジデンス」の32~38階には「ホテル 銀座クレストン」がある。上流側の「佃大橋」その先に隅田川にかかる斜張橋・「中央大橋」、更に先には「東京スカイツリー」が見えた。「中央大橋」、「東京スカイツリー」をズームして。「中央大橋」は隅田川で2番目の斜張橋で、1993年に完成。隅田川は、北区の荒川から分岐し東京湾に注ぐ全長約24キロメートルの1級河川で、数多くの橋が架けられている。中央大橋は、高層ビルが立ち並ぶ近代的な街並みとなった佃地区と都心を結んでおり、曲線桁を採用し、X字形のタワーで32本のケーブル形式が特徴の斜張橋形式の橋である。1989年に、隅田川とパリのセーヌ川の友好河川提携を記念して、パリ市長から贈られたメッセンジャー像(オシップ・ザッキン作)が、橋の中央、上流側の橋脚上に設置され、行き交う人々を見守っている。橋上からは、川上に永代橋、川下に佃大橋を望むことができる。「東京スカイツリー」の天望回廊(450m)と天望デッキ(350m)をズーム。そして隅田川の下流方向にあったのが「勝鬨橋(かちどきばし)」。以前に訪ねた「はとば公園」の井上 武吉作の「my sky hole 水の情景」を隅田川越しにズームして。「月島川水門テラス連絡橋」から「勝鬨橋」を見る。「勝鬨橋」は昭和15年に国家的イベントとして計画された万国博覧会のメインゲートとして計画された。昭和8年6月10日に工事を着手し、資材が不足する中、7年をかけ、昭和15年6月14日に完成。東京市(当時)、錢高組を主体とし、石川島造船所(現IHI)、横河橋梁製作所(現横河ブリッジ)、川崎車両(現川崎重工業)で工事を行った。当時は、隅田川を航行する船舶が多く、陸運よりも水運を優先させる可動橋として設計され、大型船舶の通航を可能とした。 午前9時、午前12時、午後3時の1日3回、1回につき20分程度開いていた。さらに昭和22年12月24日には都電が開通している。しかし、東京オリンピックが開催された昭和39年以降は、跳開回数は年間100回を下まわるようになり、昭和45年11月29日を最後に跳開されることはなくなった。跳開橋部分をズームして。ハの字に開いた勝鬨橋の姿をネットから。「隅田川テラス」を下流に向かって歩く。工事中の「勝鬨橋」。下流側は足場が組まれて、全体が板張りに。ズームして。「勝鬨橋塗装工事のお知らせこの度、勝鬨橋を塗り替えることになりました。工事期間中は、桁下が低くなりますので、ご通行の際は十分こ注意くたさい。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力を宜しくお願いいたします。」と。仮設足場に囲まれた「勝鬨橋」の下を通過。 ・・・つづく・・・
2023.11.30
コメント(0)
-

藤沢市民まつり湘南台ファンタジア2023へ(その3)
次に登場したのが「湘南みどりが丘幼稚園」。湘南台駅の先、小田急線沿いの高倉地区にある幼稚園であるようだ。全園児が鼓笛部に入らなくてはならないとネットには。学校法人冨田学園の幼稚園。イベントに力を入れており、家族参加型のイベントも多く、親としても楽しめるとの書き込みも。可愛い衣装に身を包み元気な演奏を披露してくれる鼓笛隊。友だちと力を合わせ、一生懸命演奏する姿は沿道の人たちを笑顔にしてくれるのであった。緊張した顔、しかし一生懸命に。「明治安田生命保険相互会社 一輪車内田姉弟」。「一輪車内田姉弟」👈リンク の演技披露。お姉さんと弟さんの息がぴったり。弟さんのジャンプ!!「一輪車内田姉弟」の後ろから「明治安田生命保険相互会社」の社員の方の行列が。再び姉の上をジャンプ。軽トラックに音響装置を載せて登場。「dk∞FREAKS(ディーケイフリークス)」👈リンク。地元湘南台誕生の「dk∞FREAKS(ディーケイフリークス)」がキッズとともに登場。よさこいを超える力強いダンスを披露。「大きな旗で祭りの風を吹かせ湘南台ファンタジアを盛り上げます」と。「アメリカ海軍第七艦隊音楽隊」👈リンク。横須賀に前方配備された旗艦ブルーリッジ艦上に司令部を置く、アメリカ最大の前方展開艦隊「アメリカ第7艦隊」。その担当区域には、常に70隻以上の艦船、200-300機の航空機、そして4万人以上の海軍兵や海兵隊員が展開していると。体に巻いているように見える、白くて大きい楽器の正式名称は「スーザフォン」。「Bravura March ブラヴューラ行進曲」👈リンク。そして次の曲は「星条旗よ永遠なれ(Stars and Stripes Forever)」👈リンク。そしてオオトリは圧巻の「神奈川県立湘南台高校吹奏楽部」。「県立湘南台高校 吹奏楽部 White Shooting Stars」👈リンク。「県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars」は、2021年12月17日開催の「2021JAPAN CUP全国高等学校マーチングバンド選抜大会」で優勝。16連覇という偉業を達成したのであったが、そして昨年度も金メダル獲得と。英語で「流星(流れ星)」は、“shooting star” 。マーチング日本一に輝いた演技。この日は全身黒の衣装で。白い羽付き帽子で。横浜市営地下鉄と相鉄いずみ野線の湘南台駅開業を記念して平成11年に始まったこのお祭りは、市民の皆さんの支持で今日まで続く、みんなの力で作り上げたお祭りなのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.11.29
コメント(0)
-

藤沢市民まつり湘南台ファンタジア2023へ(その2)
「開催ファンファーレ」👈リンク。神奈川県立湘南台高等学校 吹奏楽部WSS Shonandai Senior High School。「湘南台老人クラブ連合会 湘南台民生委員児童委員協議会」。「湘南台音頭」👈リンク の披露。我が地元の「六会ふるさと音頭保存会」。「六会ふるさと音頭」👈リンク の披露。白バイが先導。「神奈川県警察音楽隊」。「神奈川県警察第ニ交通機動隊 神奈川県警音楽隊」。ボーイスカウト&ガールスカウトのパレードが続いた。「ボーイスカウト 藤沢第12団」。「ガールスカウト 神奈川県第56団」。「藤沢市から交通事故を無くそう」と横断幕を掲げてのパレード。「湘南工科大学電動自転車」。「湘南工科大学」と書かれた幟。「電動アシスト4輪自転車」👈リンク であっただろうか?次に湘南台地区の「マスコットキャラクター」の登場。「ゆめみん」。デザインの生みの親はビッグ錠先生と、名付け親の堀内藍子さんとのこと。「湘南台のアイドル」と。「ゆめまる」。「ゆめまる」が私に挨拶してくれました!?。本格的な音楽隊!!「海上自衛隊 横須賀音楽隊」。「海上自衛隊 横須賀音楽隊」👈リンク の「宇宙戦艦ヤマト」の演奏。女性の姿も何人か。高校生と小学生のコラボ。「シャイニーダンストワラーズ 、鵠沼高校マーチング・バンド部 Albireo Nova」。チーム名「Albireo Nova」は、鵠沼の「鵠」が白島を意味することから、「私たちマーチングバンド部が白鳥座のニ連星Albireo (アルビレオ)のように光輝く新星Nova (ノヴァ)になる」という思いが込められているのだ と。2004年に男女共学になった「鵠沼高等学校」。同じく2004年に「鵠沼女子高等学校」から「鵠沼高等学校」に校名を変更。「湘南なぎさ連」。湘南藤沢地区に初めて誕生した阿波おどり連。2012年3月3日創連。本場徳島の正調阿波おどりを志し、着物は藤沢市のシンボルフラワー『藤の花』と湘南の海・徳島藍色を織り交ぜ繋がりを大切にしたい想いがあるとのこと。「湘南なぎさ連」👈リンク の阿波おどり。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.28
コメント(0)
-

藤沢市民まつり湘南台ファンタジア2023へ(その1)
この日は10月29日(日)、 10月28日(土)、10月29日(日) 両日ともに10:00~17:00の予定で、「藤沢市民まつり湘南台ファンタジア2023」が湘南台公園・原谷公園・駅地下アートスクエア・四ツ辻公園・湘南台駅周辺で行われており、この日・10月29日(日)は湘南台駅東西大通りにてパレードが行われるとのことで、自宅近くからバスにて湘南台駅東口に向かったのであった。湘南台駅東口でのパレードのスケジュールは下記のごとし。・オープニングセレモニー 11:05・パレード 11:40~15:00湘南台駅東口・終点でバスを下りて、湘南台公園方向に向かう。地球儀の形状の「湘南台文化センターこども館」の近くには既に神奈川県警の車そして警察官の姿が。「湘南台駅東口」交差点のT字路の先にあったのが「湘南台公園」。公園の前の道路は国道467号。「湘南台公園」の御祭案内図。ハンバーガーチェーン「モスバーガー」のキャラクターの姿が。創業から50年にあたる、今年4月1日から「モスバーガー」の新コーポレート「リルモス」であると。「リルモス(LilMos)」を正面から。モスバーガーという名称の由来は、Mountain(山:山のように気高く堂々と)Ocean(海:海のように深く広い心で)Sun(太陽:太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って)この3つの単語の頭文字をとっていて、これらが象徴する自然や人間への限りない愛情を込めてつけられているのだと。そして、ハットのデザインは頭文字である「M」をあしらったロゴマークは、丸みを帯びた食材であるパンをイメージしているのだとか。そして、メインカラーとして使用されている赤色は、力強さや真心を象徴しているのだとも。「リルモス(LilMos)」の案内をネットから。多くの食べ物や出店。テントの色は青と白。この祭りのシンボルカラーなのであろうか?銀杏の葉も色づいて。多くの家族連れの姿が。地元商店約30店舗・イベント組合約50店舗・キッチンカーが出店と。キャンピングカーの展示コーナー。そしてステージも設置されていて、子供たちのダンス披露が始まっていた。「LOICX☆チアダンススクール」と。ここ湘南台にスクールがあるようだ。元気いっぱいに笑顔で。地元の企業「いすゞ自動車」のバスも展示されていた。自衛隊の募集案内所も。出店が所狭しと。いかやき。お好み焼き。南米料理には長い列が。そして「湘南台公園」を後にして再び地球儀の形状の「湘南台文化センターこども館」を見る。「通行止めのお知らせ」。「円行東口大通り線」はこの日はパレードの為に11:00~14:00の間は通行止めと。地球儀の形状の「湘南台文化センターこども館」と左には帆船の如きモニュメントも。既に、来賓の方々も着席していた。一番右に藤沢市長 鈴木恒夫氏。我が大学の2年先輩。そして地元選出の衆議院議員の星野剛士氏、阿部知子氏。星野剛士氏は先日・10月28日(土)に白旗神社で行われた「湯立神楽」でも来賓としての姿を見たのであったが。パレードのオープニングは「遠藤谷太鼓保存会」👈リンクから。まずは、荷台に舞台をセットし、太鼓を叩く子供たちも準備万端にて、ウィングボディのトラックが道路中央に乗り込み、バンボディの両側が開く見事な演出!!「遠藤谷太鼓保存会」の「北原太鼓保存会」。そしてオープニングセレモニーが始まった。実行委員長・酒井一二氏の挨拶。藤沢市長・鈴木恒夫氏。衆議院議員・阿部知子氏。衆議院議員・星野剛士氏。その後も来賓の方々の挨拶が続いたのであった。そしてパレードの開始へ。下記写真の左側にはパレード・セレモニーの出演団体が記載されていた。パレードは午前中に東口、午後引き続き西口で行われるとのことであった。待ちに待ったパレードが開始された。最初に「湘南ユナイテッドBC チアリーダーズ」と。「湘南ユナイテッドBC」👈リンクは、日本のプロバスケットボールチーム。B3リーグ所属。ホームタウンは神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町。2020年創設。藤沢商工会議所メンバーと湘南地区で活動していた社会人チーム「湘南STATE」が団結し2020年に設立。2022-23シーズンからのB3リーグ参入。メインスポンサーは木下グループが務めている と。今秋開幕するプロバスケットボールB3リーグ2023―24年シーズンに参戦する「湘南ユナイテッドBC」の2代目チアリーダーが7月1日に決定したとのこと。今回メンバーとして選ばれたのは8人。5人が初代メンバーから続投する。そのうちの1人、岩崎美陽さんは「昨年は活動の中で湘南の人の温かさを感じた。今年もイベントを通じて湘南らしさを発揮しながら、地域の活性化に貢献したい」と意気込む とのネット情報。 ・・・つづく・・・
2023.11.27
コメント(0)
-

龍口寺・第13回 瀧の口竹灯籠へ(その3):江ノ電江の島駅への帰路
「龍口寺・第13回 瀧の口竹灯籠」を楽しんで帰路に。「日蓮大聖人滝ノ口龍口寺御法難之霊跡 日蓮宗霊跡本山龍口寺」と。龍口寺前の交差点に江ノ島駅から海岸方向に向かう江ノ電電車。こちらが進行方向、次の駅は腰越駅。ホームの藤沢方は併用軌道と踏切が重なり、踏切は、ちょうど併用軌道に乗り入れる場所にあるため、遮断機が山側1基しかない(警報機は道路側にもある)。また鎌倉方も踏切となっているため、この腰越駅では4両編成の列車は鎌倉方の1両がホームからはみ出て停車するためドアが開かないのだ。急な右カーブの江ノ電の線路。「電車接近」と。そして藤沢駅行きの江ノ電が交差点に入り、江ノ島駅に向かう。ズームして。国道467号を江ノ電・江ノ島駅に向かって進んで行くと右手にあったのが湘南モノレール・湘南江の島駅。大船駅からモノレールに乗り込み、住宅街の上空を快走すること14分。トンネルを抜けた先に待つ終着駅が、ここ湘南江の島駅。ビルの5階にあるホームの窓の向こうでは、相模湾がお出迎え。さらに改札を通ると、海と湘南の街並み、そして富士山を一望できる展望台があるのだ。1本の桁を挟んで、降車専用と乗車専用の2つのホームがある構造の湘南江の島駅の写真をネットから。そして「江の島駅入口」交差点を左折すると正面に、江ノ電・江の島駅の踏切が見えた。江ノ島駅方向を見る。江ノ電・江ノ島駅入口にあったのが小鳥付き車止め「ピコリーノ」。いつもお洒落な手編みのお洋服を着て地元の方々や観光客を出迎えているのだ。「江ノ電 江ノ島駅」。藤沢駅行きの電車が出発。藤沢方面のホームに設置されていたジオラマ。左手に「龍口寺」。撮影角度を変えて。「このジオラマは、平成10年11月11日に当社が当時闘病生活にあった新田朋宏くんの「江ノ電の運転士になりたい」という夢の実現をお手伝いしたご縁で、朋宏くんのお父さん新田和久さんのご友人でおられる石井彰英さんからご寄贈いただいたものです。寄贈先を探していた石井さんが当社への寄贈を決められたのは、「息子をジオラマの運転士にして欲しい」と熱望された新田さんの優しさに感動して、「ジオラマは朋宏くんが愛した江ノ電の利用者に見ていただくのが一番」とお考えになられたからです。なお、まことに残念ながら新田朋宏くんは平成10年11月15日に亡くなられましたが、ジオラマ上を走る江ノ電の運転士としてこれからもご活躍されることでしょう。」「ばくの小さなパラダイス昭和40年頃、両親・祖父母と何度も来た江の島。海で泳ぎ、あじさいの花を見た懐かしい情景をジオラマにしたくなり、当地を何度も取材しながら制作に費やした期間は約2年。静寂の中の極楽寺駅、明るい学生さんが乗り降りする鎌倉高校前駅、子ども達の笑顔がまぶしい江の島海岸、皆さんを乗せて元気に走る江ノ電。私の前に広がる風景は、当時の頃と何ら変化はありませんでした。皆様にこのジオラマを楽しんで頂けましたら、制作者としてはこれほど嬉しい事はございません。 2008年11月吉日 石井彰英氏より寄贈されました。」美しい、秋を感じさせる生花。「江の島」駅案内。鎌倉駅 - 藤沢駅 営業キロ10.0 km 駅数15 信号場1併用軌道区間だけでなく、わずか10kmほどの短い路線でありながら、多数の特徴的な鉄道風景があるのだ。「AQUA GARDEN LAB」。「江ノ島電鉄株式会社では、魚の陸上養殖と野菜の水耕栽培を掛け合わせたアクアポニックス事業の検証を行うため、今般、当社線江ノ島駅構内においてアクアポニックス施設を設置し、2023 年3月31日から「Aqua Garden Lab(アクアガーデンラボ)」として本稼働いたします。「Aqua Garden Lab」は、アクアポニックスを身近に感じていただくため、多くのお客様が利用される江ノ島駅の藤沢行きホームに面した場所に設置いたしました。現在、魚はティラピアを養殖し、野菜はレタスと小松菜を育てており、今後も随時様々な野菜を栽培していく予定です」 と。2009年3月31日(火)に江ノ島駅上りホームに冷暖房完備の待合室がオープン。室内には展示スペースを併設し、往年の303号車運転台カットモデル、プラレールのジオラマ、1001号車の模型、電車のヘッドマーク等を展示しています。また、モニターも完備しており、江ノ電沿線の地域情報を放映しているのだ。往年の303号車運転台カットモデル。近づいて。「303号車についてこの303号車は303+353号として走った連接車の藤沢方の車両です。この偏成は1929 (昭和4 )年製の江ノ電最初のボギー車101~104号車4両を改造して1957 (昭和32 )年につくられた2偏成の連接車のうちの1偏成です。もう1つの偏成である302+352号は1997(平成9)年、レトロ調電車10形偏成と入れ替えに廃車となりましたが、この303+353号は車体内外を改造・冷房化し、台車、機器を新造車両と同じものに更新するなどして新車と同様の性能になり活躍しました。しかし、惜しまれながら2007 (平成19)年ついに廃車となりまいた。」貴賓室の扉と1001号車の模型の展示ケース。1001号車の模型。貴賓室の扉。「「貴賓室の扉について」明治35年の開業(藤沢一片瀬間の3.42km )当時、全4両の車両のうち、半数の2両には、一般の3等席に加えて1等席が設けてありました。当時から、葉山の御用邸をはじめ鵠沼の秩父宮邸など、近隣には多くの高貴な方のお住まいがあったため、江ノ電(当時は江之島電気鉄道)は1等という特別列車を用意したのです。記録によると、1等と3等の合造車はこの扉を仕切りとして車内を3つに分け、個室を確保したようです。大正2年4月8日の『横浜貿易新報』によれば、大正2年4月6日に伏見宮博仁王ほか3殿下が、この特別仕立ての列車で片瀬(現江ノ島)ー長谷間を移動されたという記録が残っています。」待合室の壁には様々な写真等が展示されていた。「江ノ電 駅シリーズ乗車券全集」。「江ノ島」。「昭和49年(1974) 藤沢駅 江ノ電ビルへ乗入れ開始」左:「昭和54年(1979) 48年ぶりの完全新造車両 1000型(1001・1002) 就役」右:「昭和55年(1980) 最後のタンコロ 107号車・108号車引退」「昭和56年(1981) 社名変更 「江ノ島鎌倉観光」から「江ノ島電鉄」へ」。「江ノ島名所案内龍ロ寺 0.2KM 徒歩約3分江の島 1.1KM 徒歩約16分江島神社 1.2KM 徒歩約18分江の島展望灯台 1.4KM 徒歩約20分稚児ケ渕 2.0KM 徒歩約30分(岩屋) 」。亀の背中に江の島 のこのポスターは??そして江ノ島駅のホームを。藤沢駅が入線。そして藤沢駅から小田急線で帰宅の途へ。龍口寺で開催された滝の口・竹灯籠は、竹を使った灯籠が境内に並べられ、幻想的な世界を演出するイベントであった。このイベントは、毎年10月最後の週末に開催され、地元のボランティアの方々が集い、願い事が書かれた竹の灯籠を境内に並べていた。今年は約3000基の竹灯籠が並べられ、夕刻になるとロウソクに火が灯され、幻想的な世界が広がったのであったこのイベントは、静かで神秘的な雰囲気が漂い、参加者は心を落ち着かせ、自然と調和することができるのであった。竹灯籠の光が、境内に幻想的な世界を作り出し、参加者を魅了。また、竹灯籠に願い事を書くことで、自分自身の内面を見つめ直す機会にもなっていた。私も、このような幻想的な世界を演出するイベントに参加することができ、素晴らしい時間を楽しんだのであった。そして自宅への帰路での10月の満月。10月の満月は『ハンターズムーン』と呼ぶと。10月の満月は狩猟を始める頃である事に由来していると。そして月の右側には木星が急接近。『ハンターズムーン』。さらにズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.11.26
コメント(0)
-

龍口寺・第13回 瀧の口竹灯籠へ(その2)
さらに「龍口寺・第13回 瀧の口竹灯籠」の幻想的な世界を山門の先からデジカメで追う。竹灯籠は、その繊細な美しさ、和風の雰囲気、そして夜に灯る温かい光の融合によって、日本文化の深さと美意識を象徴する存在となっているのであった。周囲に優しい光を灯し出す「竹灯籠」。この光は穏やかでありながらも存在感があり、周囲の空間に静謐な雰囲気をもたらしているのであった。日本の伝統的な美しさを象徴する素晴らしいアートピース!!参道を進み、本堂への石段の上から山門方向を振り返って。ズームして。廻り込んで。そして前方に進む。天水桶の周囲にはキャンドルが並べられていた。近づいて。一つ一つの炎が、闇を照らし、希望を紡ぎ出す。キャンドルの美しさは、その独自の輝きと静寂の中に宿るのであった。炎の躍動感、灯りが作り出す幻想的な雰囲気、そして独自の温もりによって、この空間に深い感動と穏やかな魅力を与えていた。微風がやさしく触れ、炎は踊りながら語りかけ、キャンドルは秘められた物語を語り出すのだ。右手の竹灯籠の灯りは「2023」と。そして本堂内を。本堂を出て一方通行を進む。竹灯籠を上から。蝋の芯が心臓となり、その先に灯される炎は生命の息吹そのもの。反対側の天水桶にもキャンドルが。そして更に進むと、瀧口会館の横には消防自動車が待機していた。そして再び山門前に戻ると、石段上の竹灯籠は見事な輝きに変身していた。本金蒔絵の漆塗り大箱の如し。竹灯籠の作り方。①竹にデザイン紙をマスキングテープで仮止めする。 穴の径毎に色を変えると間違いが少ない。簡単なもののデザインはチョークなどで竹に直接描 いてもOK。②透明テープでデザイン紙を竹にしっかりと貼り付ける。③固定用の台に竹をセットし、竹用ドリルで穴をあける。 竹が動かないようしっかり固定して穴をあける。そしてこれが完成品と。龍口寺には龍は欠かせないのであった。しかしこちらは、円形の穴ではなく、長方形の穴の集合デザインであるため、作業量が莫大であることが容易に想像できたのであった。近づいて。そして再び仁王門の仁王像を。手前に金網があるため、焦点合わせがなかなか難しかったのであった。仁王像の影も美しかったのだ。玉眼入り。口の開け方も生々しく。山門も再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.25
コメント(0)
-

龍口寺・第13回 瀧の口竹灯籠へ(その1)
この日は10月29日(日)、藤沢市片瀬にある龍口寺は日蓮宗の寺院で、日蓮にまつわる4つの受難のひとつ、龍ノ口法難👈リンクに関わる地にある。境内には神奈川県では珍しい五重塔や白亜の仏舎利塔があり、また、大本堂には藤沢七福神のひとつである毘沙門天も祭られている。季節に応じたさまざまな行事も行われるが、今回はこの日に行われた「龍の口竹灯籠」に行ってきました。藤沢駅から江ノ電にて向かいました。日蓮の弟子日法が1337年(延元2年)に龍ノ口法難の霊場であるこの地に堂宇を建立し、日蓮の像を安置したのが始まりといわれています。その後信者であった島村采女が1601年(慶長6年)に土地を寄進し、本格的な寺院としての格式が整えられました。龍口寺は、江ノ電・江ノ島駅および湘南モノレール・湘南江の島駅近くにある日蓮宗の寺院。「江ノ島」駅で下車。龍口寺に向かって、国道467号を歩く。「瀧の口竹灯籠」と書かれた幟。「瀧の口竹灯籠」とは、龍口寺境内に並べられたおよそ3千基の竹灯籠に灯るろうそくの光の中、本堂前に施餓鬼壇を設けて、参詣者の先祖や亡くなった方の供養を行うのです。例年8月に行われていましたが、昨年・2022年からは10月下旬の開催となりました。時間は16:59。少しずつ暗くなって来ました。「瀧の口竹灯籠」と書かれた行灯が歩道横に。青海波(せいがいは)の模様。この柄の発祥は古代ペルシャとされています。シルクロードを経て日本に伝わったのは飛鳥時代、平安時代に書かれた源氏物語の中に『青海波』という雅楽を舞う若き光源氏の姿が描かれているとのこと。この神楽を舞う舞人の衣装の柄が青海波で、青海波の名はこの神楽に由来すると言われている と。そして左にあったのが「龍口明神社(元宮)」。龍口明神社の創建年代は、ここ片瀬・津・腰越の境界地(龍口明神社元宮地)に欽明天皇13年(641)創建、江島神女の霊感により降伏した五頭龍を祭神としています。明治維新後の社格制定に際して村社に指定されていた。昭和53年、鎌倉市腰越1548-4へ遷座しているのだ。社殿の姿は既に無く。そして「龍口寺」に到着。藤沢市片瀬3丁目13。「龍口寺」と彫られた竹灯籠には既に灯りが点っていた。「仁王門」横の「瀧口会館」に向かう石段にも一面に竹灯籠が。近づいて。まだ暗さが足りないので最後にもう一度訪ねることに。こちらの竹灯籠には「龍」の姿が。様々な紋様が輝き始めていた。今年の「第十三回瀧ノ口竹灯籠」のポスター。2023年10月29日(日)、龍口寺境内にて午後五時~午後八時まで開催と。「龍ロ寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参拝の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養またはお願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的なタベを大切な人とお楽しみください。」と。「瀧の口竹灯籠会場図会場内は一方通行です。矢印に沿ってお進みください。」と。「七面大明神例大祭」案内。七面大明神は法華経を信仰するものを守護し、苦しみを除き安らぎを与える神様です。例祭では加持祈祷を行い、七面大明神の御守護をお受け戴きます。どなたでもご奉拝下さい と。「竹灯籠 受付」、1基 1000円と。山門の手前右側に黄色いテントがありここが受付。灯籠代金(千円)を支払い申込用紙に必要事項(住所・氏名・電話番号)を記入し、「供養」または「祈願」の各項目のうちのいずれかひとつを選ぶのであった。その横では、和太鼓の演奏が。太鼓集団「ふじ」と。2009年8月に藤沢市で誕生した太鼓グループ。その名もズバリ藤沢の「ふじ」!!太鼓集団「ふじ」のプロデューサーは、FIFAサッカーW杯公式閉会式にて日本人初の2大会連続で演奏した、世界的な太鼓ドラマー“ヒダノ修一”。藤沢市のPRと活性化の目的のために発足した「ふじ」は、太鼓演奏を通じて多くの人々との交流を持ち、藤沢の更なる認知度アップを目指します。現在は藤沢市内外の各イベントに出演し、活動しています。太鼓集団名の「ふじ」は日本一の富士山と藤沢の「ふじ」。また「ふじ」は当て字だが「不二」という意味も含んでいて、「二つとない」団体という意味もある。「ふじ」の花言葉も「歓迎」「恋に酔う」など良い意味が多く、また「4月1日」の花でもあり、「4月1日」=始まりという意味もあって、今回新たに結成した団体が「始まる」という意味から「ふじ」と名づけているとのこと。太鼓集団「ふじ」が本堂内でライブ演奏と。藤沢市消防局の防水用水槽のマンホール蓋。そして仁王門の仁王像のお顔をズームして。阿形像。吽形像。石段の上に「山門」。扁額「龍口寺」。山門には、中国の故事に由来する素晴らしい木彫りの見応えある彫刻の美が。黄石公(こうせきこう)と張遼 張良(ちょうりょう)。黄石公の試練に耐え続けた張遼 張良がついに兵法の奥義を授かる話。羽目板彫刻では定番。???襄子(じょうし)の衣服を切る予譲(よじょう)。何度も襄子の暗殺を試みるが失敗し、とらわれの身となった予譲が最後に襄子の服を貰い受け、その衣服に三回切りつけて主君智伯の無念を晴らし自決する、という話。三国志演義の桃園結義かも知れません。左から長髭の関羽 長耳の劉備 虎髭(には見えないけど)の張飛ではないでしょうか。そして山門を潜ると、目の前には境内一面の竹灯籠の世界が広がっていた。約3000基の竹灯籠が所狭しと並べられ、本堂や五重塔と共に幻想的な空間を創り出していたのであった。竹灯籠一つ一つには、本物の蠟燭の火が灯されて。山門の先で留まり、しばし幻想的な竹灯籠を我がデジカメで追ったのであった。本堂を見る。本堂右奥には「五重塔」。「龍口寺 総受付」への建物への石段の上にも。正面から。 ・・・つづく・・・
2023.11.24
コメント(0)
-

白旗神社・湯立神楽へ(その5)
十、射祓(いはらい または弓祓と書く) 四隅に矢を放ち悪霊を退散させます。最後に正面(神前)に向かいますが、悪霊がいないため 矢を放たず鳴弦(めいげん)にとどめます。四方に放たれた矢を授かると開運招福・息災延命 になると伝えられています。舞の音を奏でる神職達。鈴と弓を持って舞う。邪気を射祓い、邪悪を射据えて、招福除災を祈念し天の下平らけく氏子安らけくあるべきを祈念する、静かな中にも力強い舞である。弓矢の威力で悪魔を調伏する神楽で、この矢を授かると開運の御神矢としての信仰がある。赤い面を被る神職。後ろで別の神職が手助けして。そして十一、剣舞(けんまい) 赤面の天狗(猿田彦)が剣を持ち邪悪を清め、悪しき大気を体内に吸い込み浄化され、二本の 指で空中に九字を切り、護身・除災・勝利のまじないをしながら豊年万作・大漁満足・ 天下泰平を祈念し、天地運行の乱れを正します。神楽の終段である。赤面の神は鉾を執って進み出て九字を切り、五風十雨、雨風時に順ひ、豊年万作・大漁満足・天下泰平を祈念して気息を整え、醜(邪悪)を踏み鎮め、天地運行の乱れを正し、邪霊を鎮めて散供する。赤い面を付けた天狗が空気を体に吐き入れそれを吐きだすことで空気が浄化されたりして天下泰平を舞う。護身、除災、勝利の舞をしながら豊年満作、大魚満足、天下泰平を祈念し天地運行の乱れを正すだと。十二、毛止幾(もどき) 剣舞の途中より黒面の山の神がしゃもじを持って現れ、天狗の真似をしたり滑稽な仕草を しながら、斎場にいるすべての人の心に平安と安らぎを取り戻させる『もどき』で神楽は 終了します。赤面の神の所作をまねたり、おどけたりして笑いを招きつつ座の雰囲気を和めながら散供する。そして参列者が心に平安と和らぎをとりもどし、平常心即ち普段の心の状態に戻り、新しく充実し、増進した生命力をもって、再び日常生活に励むようにさせるという「もどき」(真似をする意)の所作である と。斎場にいる全ての人の心に平安と安らぎ取り戻させる舞い、黒い面の山の神は神社での神事に参列され緊張された方が家の帰る前に普段の生活の戻す舞い、という神楽舞で構成されいると。黒面の山の神が近くまで来て。大きな叫び声をあげ、邪気を払ってくれた。そして再び神前に戻り舞う。そして十二座に亘る「湯立神楽」の終了を告げる宮司。神楽が終わると斎場に取り付けられた紙垂(しで)を持ち帰り、家の神棚に祀り、災い除けにする風習があるとのこと。櫃にぎっしりと入った紅白の「福餅」。「福餅」を一つ頂きました。5色の紙垂(しで)と竹で作られた天蓋(てんがい)を見上げてそして境内にあった今年の巨大な絵馬。「令和5年癸卯(みずのとう)歳 干支絵馬」この絵馬は藤沢市在住の漫画家 佐野絵里子先生による原画をもとに奉製した絵馬 と。牛若丸と今年の干支である兎が八艘飛びのように船上で戯れている様子が描かれている。そして「湯立神楽」のこの日に合わせて来年の絵馬が。「令和6年甲辰(きのえたつ)歳 干支絵馬」。旭日を背に舞う縁起の良い龍の姿が。原画は例年通り、藤沢市内在住の漫画家 佐野絵里子先生に依頼、絵馬作成は藤沢市長後の㈱グロリア工芸さんにお願いしたとのこと。今回の図案は、義経公が来年の干支である龍(辰)に乗って雲の上を駆けている様子が描かれている。架空の存在である龍が登場しているだけあって、幻想的な絵となっているのだ。そして順序が逆になってしまったが、「白旗神社」に参拝。「白旗神社御祭神 寒川比古命 源義経公配神 天照皇大神・大国主命・大山祇命・国狭槌命由緒古くは相模一の宮の寒川比古命の神社のを祀って、寒川神社と呼ばれていた。しかし、創立年代はくわしくはわからない。鎌倉幕府によって記録された『吾妻鏡』によると、源義経は兄頼朝 の勘気をうけ、文治5年(1189)閏4月30日奥州(岩手県)平泉の衣川館において自害された。その首は奥州より新田冠者高平を使いとして鎌倉に送られた。高平は、腰越の宿に着き、そこで和田義盛・梶原景時によって首実検が行われたという。伝承では、弁慶の首も同時におくられ、首実検がなされ、夜の間に二つの首は、此の神社に飛んできたという。このことを鎌倉(頼朝)に伝えると、白旗明神として此の神社に祀るようにとのことで、義経公を御祭神とし、のちに白旗神社とよばれるようになった。弁慶の首は八王子社として祀られた。」石段の上に拝殿。石段下左手に義経公に纏わる「鎮霊碑」が。白旗神社の御首と宮城県栗駒町半官森御葬札所の御骸、両地の魂土を合祀し、義経公の兜を象った鎮霊碑で1999年(平成11年)に建立された と。「源義経公鎮霊碑文冶五年(1189年)閏四月三十日、奥州平泉、衣川の高館で、藤原泰衝に襲撃された義経公は自害し悲壮な最期を遂げた。その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬礼所に葬られ、また一方の御薗は奥州箆を経て、同年六月十一二日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、潮に逆流し白旗神社の近くに流れつき。藤沢の里人により洗い清められて葬られたと語り伝えられる。本年、源義経公没後八百十年を記念し、両地有志の方々により「御骸」と「御首」の霊を合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊碑を建立する。」拝殿に参拝。現在の拝殿は、文政11年(1828)から7年をかけて、天保6年(1835)12月に完成した。本殿、弊殿、拝殿を連ねた典型的な流権現造り(ながれごんげんづくり)で、外壁部の彫刻は江戸時代の匠の技が光る貴重な文化財。昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置された と。そして、往路と同じくバスにて帰路についたのであった。藤沢・白旗神社の「湯立神楽」を鑑賞する貴重な機会に恵まれ、その神秘的な雰囲気に心が引き込まれたのであった。神社の広い境内に響く神楽の音と、神聖な舞台の上で繰り広げられる踊りが、まるで別世界にいるような感覚を呼び覚ましたのであった。神楽の舞台は厳かでありながらも美しく、神聖なエネルギーがその場に満ち溢れていた。独特の楽器の音色と共に舞われる踊りは、神秘的で迫力があり、見る者を引き込んで離さない。演じる神職たちの表情や仕草は、神話や伝統の中に息づく神々との交信の一端を感じさせ、自分も神聖な儀式に参加している気分に陥ったのであった。特に、神社の雰囲気と神楽が調和して、自然の中での演技が一層印象的。神聖な木々のそよ風や、境内に鳴り響く神楽の音が、訪れた者に心地よい穏やかさと神聖な感動を頂いたのであった。この貴重な経験から、日本の伝統や神聖な儀式に対する深い尊敬の念を抱きつつ、湯立神楽を通じて日本文化の美しさと豊かさに触れ、心に深く刻まれる一時になったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.11.23
コメント(0)
-

白旗神社・湯立神楽へ(その4)
そして「中入れ(なかいれ)」の短い休憩時間になり、狩衣(かりぎぬ)を脱いで白衣・袴の姿に。六、中入れ(なかいれ) 前半の清め・祓い・神招きが終了して短い休憩となります。神職は狩衣(かりぎぬ)を 脱いで白衣・袴の姿になり、後半の新人共楽の神楽に備えます。また神前にお供えされている お神酒とお赤飯を参列者に分かちます。前段は祓の所作が中心で、生れ出た尊いお湯を献ずるまでの経過であって、奉仕の神職も後段の「湯立神事」に備えて狩衣を脱しての所作に移るため心気を整える。又、神楽の場に集う参列者にも撤下の神酒など分かち、お下がりをお受けすることで神気を直接に自分の体にいただき確実に納めようとするのである。氏子代表の方々から赤飯を手のひらにいただきました。この後にお神酒も。後半の「座」について説明する「白旗神社」の宮司。七、掻湯(かきゆ) 御幣(ごへい)で四方を舞い鎮め、舞が終わると大釜の前に進み、煮えたぎった湯釜を 御幣の串で掻き回すと、渦巻きが生じて湯華(湯玉)が立ち昇ります。古くはこの湯立ちに よってその年の吉凶を占いました。湯立神楽を象徴する舞です御幣を手に大釜に向かう神職。御幣(ごへい、おんべい、おんべ)とは、神道の祭祀で、捧げられ、用いられる、幣帛(へいはく)の一種で、2本の紙垂(しで)を竹または木の幣串に挟んだもの。湯華神楽(湯立神楽)のクライマックスである。神招きの祈念をこめた御幣を持って、煮え立っているお湯を掻き、釜底から立ち上がる「湯の泡」の様子で今年の豊凶をトする。沸騰し、気化した気泡を「湯華」という。釜の湯を御幣でかき回す神職。移動して横から。釜底から立ち上がる今年の「湯華」は数も多く吉兆と。湯釜の「湯華」を覗き込む宮司。八、大散供(だいさんく) 初能(はのう)の二人舞で、祓い清めの舞です。このお祭りに招かない八百万神 (やおよろずのかみ)に洗米を散供し、四方を和め鎮めます。勇壮かつ優美な二人舞です。中入れ後の二座目の神楽で祓い清めの神楽である。羽織を着用し白扇の上に神饌の白米を捧持、二人で対角線上に舞いながら四方に散供をする神楽である。白扇の上に神饌の白米を載せて踊る2人の神職。「白旗神社」の宮司は横笛を吹く。二人で対角線上に舞いながら。四方に神饌の白米を散供する。正面にも。九、湯座(ゆぐら または笹の舞という) 二人の舞手が笹の葉で四方を舞鎮めた後、交互に大釜に向かい、熱湯を笹に浸して参列者の 頭上に散らし掛けます。このしぶきを浴びると災難病魔を祓い除けると言い伝えられて います。二人の舞手が笹の葉で四方を舞鎮める。そして湯釜に向かう。1人の神職のみ、もう1人は舞台に残る。大釜の前に立って。そして笹の葉を湯釜に入れて、それを外に出し、観客に向けて振り払うのであった。観客の前を移動して、様々な場所から。私も熱湯の飛沫を浴びさせていただきました。この飛沫を浴びると災難病魔を祓い除けると言い伝えられているのです。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.22
コメント(0)
-

白旗神社・湯立神楽へ(その3)
白旗神社の宮司が神前に詣でる。そして宮司がこれから行われる「湯立神楽」👈リンク の「十二座」について順次説明してくれたのであった。そしていよいよ「湯立神楽」の神事が始まったのであった。一、打囃子(うちはやし) はじめに笛・締太鼓・大胴の楽器によって音合わせをします。神職一同でこれからの奉仕に 備え祈念をし心意気を高め調子を揃えるのが打囃子です。この場において神楽を奏することを神々に祈念し、神楽の楽を調べ合わせる為に一通り楽曲を奏して奉仕者はもとより、参列者の心意を昂めるための所作であるのだと。二、初能(はのう) 宮司が左手に広げた扇に洗米をのせ、右手に鈴を持ち四方にお米を散供(さんく)して、 諸々の霊を和め清める舞です。左手に広げた扇に洗米をのせ、右手に鈴を持ち。神楽の聖域をととのえつくるため、白扇の上に神饌の白米を捧持し、これを四方に散供して稲霊の呪力によって、神楽の場に侵入しようとする邪霊や邪気(もの)を遠ざけて聖域に神霊の降臨を仰ぎ、神楽の滞りない進行を祈念する浄めの舞であると。四方にお米を散供。三、御祓(おはらい) お神酒とお祓いの道具を持ち、舞に使うすべての道具・斎場(さいじょう=神さまが 降臨される場所・釜場・火・水)を祓い清め、神様の降臨を待つ舞です。神楽の座及び神々の降臨を仰ぐ「ひもろぎ」となる山、お湯、釜をはじめ参列者を合わせて、ひろく「聖域」の清め祓いで、神々の降臨を仰ぐためのお祓いである。我々観客も清めていただく。そして神前を離れて。窯場に向かう神職。窯場を祓い清める。大釜の蓋を開け神様の降臨を待つ。大釜からは湯気が濛々と。大釜をズームして。四、御幣招(ごへいまねき) 神楽の対象となる産土神(うぶすなのかみ)・火の神・水の神をお招きする舞です。 舞が終わると参列者に恩頼(みたまのふゆ=神様の御霊魂)を授ける神事があります。邪霊や邪気(鬼・もの)を遠ざけ清め祓ひも終えて、斎庭・聖域の正面に設けられた山(やま)、ひもろぎに神々の来臨を仰ぎ祈る神招きの舞である。(神々は産土大神・火産皇霊神・水波能売神の三神である)。五、湯上(ゆあげ) 火の神と水の神が結びついてできた熱湯に湯たぶさ(笹)を浸し、熱湯を桶に汲み取り、 神前に捧げます。火の神と水の神が結びついてできた熱湯に湯たぶさ(笹)を浸す。介添人が装束の袖を支えて。用いる湯たぶさ(笹)は必ず生き生きした笹をもって作る。密生した笹むらが風も無いのに互いに触れ合ってサササ・・・とかすかに音を発する。この様子が神々の降臨を仰ぐ時の、依り来る神の出現の様子に似つかわしいとされることから用いられるとのこと。そして熱湯を桶に汲み取る。桶を手渡す。神前に向かって。神前に熱湯の入った桶と湯たぶさ(笹)を奉納。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.21
コメント(0)
-

白旗神社・湯立神楽へ(その2)
藤沢・鎌倉・葉山地区の神職がお供物を順次神事舞台へ奉納を始めた。神棚に奉納。次々と別の神職がお供物を神棚に。大きな木桶に入っていたのは「福餅」であった。そして「湯立神楽」で神事を務める、藤沢・鎌倉・葉山地区の各神社の神職・宮司が「義経藤」の下に整列を始めた。8名の神職・宮司が「笏」を持ち並ぶ。「笏」は礼服(らいふく)、束帯のとき威儀をととのえるため右手に持つ細長い板。元来は君命などを書きつけた備忘用の板であった。五位以上は牙(げ)、六位以下はイチイ、サクラなどの木製で、天皇の笏は上下の縁が方形、臣下のは丸みを帯び、すそすぼみである。明治以後は神官にも用いられている。そして「湯立神楽」の神事が始まろうとしたのであった。そしてここ白旗神社の宮司も列に加わり「湯立神楽」の神事が始まった。横笛を奏でる神職。宮司の列が舞台横の定位置に向かう。一番奥に「白旗神社 宮司」が。まずは「秋季大祭」の神事がスタートした。「湯立神楽」の司会進行の神職。湯立の大釜の下の火も確実に燃えて。②初能(はのう)の開始。 宮司が左手に広げた扇に洗米をのせ、右手に鈴を持ち四方にお米を散供(さんく)して、 諸々の霊を和め清める舞です。祝詞奉上。招待者の「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が始まった。まずは、白旗神社の別当寺である真言宗白王山荘厳寺(しょうごんじ)の住職による「玉串奉奠」。荘厳寺は、明治8年までの133年間、現在の白旗神社社務所辺りに本堂が建てられており、また、神仏分離後には、荘厳寺43世 原王照代徒弟英経師が近藤内記と名を改め白旗神社の宮司となったとのこと。氏子代表・総代の「玉串奉奠」。副総代。氏子一同も合わせて。関係団体長の玉串奉奠が続く。藤沢市長の「玉串奉奠」。地元の衆議院議員・星野つよし氏の「玉串奉奠」。藤沢市議会議長の「玉串奉奠」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.20
コメント(0)
-

白旗神社・湯立神楽へ(その1)
この日は10月28日(土)、「白旗神社」の「湯立神楽」神事が14時から執り行われるとのことで自宅近くから神奈中バスで向かう。「湯立神楽」は「白旗神社秋祭り」の特殊神事で、約800年前に京都の石清水八幡宮から鎌倉の鶴岡八幡宮に伝わった「神楽」と言われ、両社では一時期途絶えことで原型を残しておらず藤沢・「白旗神社」で行われている「神楽」が原型に一番近いとされている、と言われる神事とのこと。「白旗神社」には初詣、藤の花見物等で今まで何回も訪ねているが、「湯立神楽」神事に行くのは初めてなのであった。バス停「白旗神社前」で下車し、「白旗神社」に向かう。「白旗川」に架かる「御典橋」を渡る。社号標石「白旗神社」。平成8年8月に建立された。社名の「白旗」は平家の赤旗に対する源氏の旗。源平の戦いの時に敵味方を区別するものとして使われ、このとき以来、源氏の象徴として白旗が用いられることになったのだ と。正面に「大鳥居」。日本初のグラスファイバー製の大鳥居であると。高さ8m、幅6mの明神鳥居で、昭和59年12月に建立された。地震対策のために軽量で耐久性のあるグラスファイバーを取り入れ、建設時には新聞、テレビ、週刊誌等で報道されたのだと。「大御神灯」慶応元年(1865)6月に建立、高さ17尺(5.1m)、台座の底辺は7尺(2.1m)。石段の上に拝殿が見えた。参道左手に「手水舎」。この「手水舎」は平成5年7月に建てられた。手水石は真鶴の銘石、小松石で作られている。参拝の前に身を清める場所。唐破風下の見事な唐獅子の彫刻。小鳥、馬、猿。唐獅子、菊の花、亀、飛龍などの彫刻があり、江戸時代や明治なら通常ではあり得ない多様さであるのだ と。四隅にある木鼻は龍であり、懸魚は鶴であることから鶴亀をテーマにしていることは確かだ。亀の姿が。源義経は、文治5年(1189年)閏4月30日に奥州衣川館で自害した。首級は鎌倉に送られ首実検された。しかし、首級は腰越で曝されたあと江の島の対岸にある片瀬の浜に捨てられたが、泥にまみれたまま亀に背負われ境川をのぼり藤沢の里にたどり着いたとされる。また、社殿が建つ山は亀の形をしていることから亀尾山と呼ばれている。それで、亀が大切にされているのであろうとのこと。そして右手には「源義経公武蔵丸弁慶公之像」。この「源義経公武蔵丸弁慶公之像」は2019年(令和元年)10月竣工。源義経公没後830年の「記念事業」👈リンク の一つとして建てられたのだ。馬に乗る「源義経公」。平安武将の大鎧を再現した見事な源義経騎馬像。鎧だけでなく、馬具・轡(くつわ)なども忠実に再現したのだと。顔にズームして。そして「武蔵丸弁慶公」。武蔵坊弁慶が主君の義経を仰ぎ見る忠義の士の姿。ズームして。さらに顔をズームして。「義経公・弁慶公の御首は、文治5年(1189)6月13日に腰越の浜で首実検の後、金色の亀に乗り当地に辿り着いたと伝えられています。義経公の首塚は、現在の位置より北に40メートル、当社から南に150メートルの場所にあり、その御霊は当社に祀られました。一方、弁慶公の弁慶塚は藤沢宿 常光寺内にあり、その御霊は常光寺内の八王子社に祀られていましたが、現在は塚のみを残しています。一般的に神社は南向きか東向きに建てられていますが、この八王子社に限っては、主君 義経公が祀られている白旗神社の方を向いていたため北向きに建てられていたと謂います。此度、令和御大典の嘉年と主従役儀830年の佳節を吉年とし、ここに源義経公・武蔵丸弁慶公の銅像を建立し、御霊の平安と隆昌を永年に亘り祈り奉ります。」そして「湯立神楽」の見学席に座る。正面に神事の舞台の奉納品が。「湯立神楽」の説明書をいただく。「湯立神楽白旗神社に伝わる湯立神楽は江戸時代から承け継がれて来た神職が演じる格調高いお神楽です。大釜に熱湯をたぎらせ湯華(湯玉)の立ち昇りでその年の吉凶を占います。」神事の舞台を確認する宮司そして神職の皆様。「湯立神楽 十二座」の案内。「湯立神楽の解説(十二座)」。「湯立神楽の解説(十二座)一、打囃子(うちはやし) はじめに笛・締太鼓・大胴の楽器によって音合わせをします。神職一同でこれからの奉仕に 備え祈念をし心意気を高め調子を揃えるのが打囃子です。二、初能(はのう) 宮司が左手に広げた扇に洗米をのせ、右手に鈴を持ち四方にお米を散供(さんく)して、 諸々の霊を和め清める舞です。三、御祓(おはらい) お神酒とお祓いの道具を持ち、舞に使うすべての道具・斎場(さいじょう=神さまが 降臨される場所・釜場・火・水)を祓い清め、神様の降臨を待つ舞です。四、御幣招(ごへいまねき) 神楽の対象となる産土神(うぶすなのかみ)・火の神・水の神をお招きする舞です。 舞が終わると参列者に恩頼(みたまのふゆ=神様の御霊魂)を授ける神事があります。五、湯上(ゆあげ) 火の神と水の神が結びついてできた熱湯に湯たぶさ(笹)を浸し、熱湯を桶に汲み取り、 神前に捧げます。六、中入れ(なかいれ) 前半の清め・祓い・神招きが終了して短い休憩となります。神職は狩衣(かりぎぬ)を 脱いで白衣・袴の姿になり、後半の新人共楽の神楽に備えます。また神前にお供えされている お神酒とお赤飯を参列者に分かちます。七、掻湯(かきゆ) 御幣(ごへい)で四方を舞い鎮め、舞が終わると大釜の前に進み、煮えたぎった湯釜を 御幣の串で掻き回すと、渦巻きが生じて湯華(湯玉)が立ち昇ります。古くはこの湯立ちに よってその年の吉凶を占いました。湯立神楽を象徴する舞です。八、大散供(だいさんく) 初能(はのう)の二人舞で、祓い清めの舞です。このお祭りに招かない八百万神 (やおよろずのかみ)に洗米を散供し、四方を和め鎮めます。勇壮かつ優美な二人舞です。九、湯座(ゆぐら または笹の舞という) 二人の舞手が笹の葉で四方を舞鎮めた後、交互に大釜に向かい、熱湯を笹に浸して参列者の 頭上に散らし掛けます。このしぶきを浴びると災難病魔を祓い除けると言い伝えられて います。十、射祓(いはらい または弓祓と書く) 四隅に矢を放ち悪霊を退散させます。最後に正面(神前)に向かいますが、悪霊がいないため 矢を放たず鳴弦(めいげん)にとどめます。四方に放たれた矢を授かると開運招福・息災延命 になると伝えられています。十一、剣舞(けんまい) 赤面の天狗(猿田彦)が剣を持ち邪悪を清め、悪しき大気を体内に吸い込み浄化され、二本の 指で空中に九字を切り、護身・除災・勝利のまじないをしながら豊年万作・大漁満足・ 天下泰平を祈念し、天地運行の乱れを正します。十二、毛止幾(もどき) 剣舞の途中より黒面の山の神がしゃもじを持って現れ、天狗の真似をしたり滑稽な仕草を しながら、斎場にいるすべての人の心に平安と安らぎを取り戻させる『もどき』で神楽は 終了します神楽が終わると斎場に取り付けられた紙垂(しで)を持ち帰り、家の神棚に祀り、災い除けにする風習があります。我が座席の真ん前に「大釜」が。「大釜」、木材の確認をする宮司。「大釜」下に木材を差しいれ、火入れの準備を。神さまが宿るとされる榊(さかき)という木の枝に、紙垂(しで)や麻を結びつけた「玉串」の確認。そして「大釜」への火入れ。新聞紙を挿入して火起こし。神棚をズームして。左から塩、野菜、ご神酒、米、餅、榊。その下に赤、黒の鬼の面が。奉納品の神酒瓶、稲束、米袋。「藤沢市指定重要無形民俗文化財湯立神楽白旗神社を中心に神官により継承されている神事芸能。湯立てを伴う神楽で、湯花神楽、鎌倉神楽等の名称で、藤沢、鎌倉から三浦半島一円におよんでいる。古くは、関東一帯に分布したとされる神代神楽を源流とし、鎌倉の鶴ケ岡八幡宮の神楽男が伝承し、次第に近隣に定着したものとされる。「湯立て」という神事手法に組み込まれた神楽には品格があり、舞にも洗練されたものがある。演目は十一で打囃子、初能、御祓、御弊招、湯上、中入、掻湯、大散供、笹の舞、弓祓、最後の剣舞・毛止幾で神人共楽の内に終了する。 白旗神社神事 十月ニ八日 平成ハ年三月一日指定 藤沢市教育委員会」火がついた大釜。赤い炎が激しく。「湯立神楽」の神事舞台を再び。観客も増えて。準備完了。「大釜」の火の面倒を見る方も真剣に。再び鬼の面をズームして。剣舞を行う赤面の天狗(猿田彦)。黒面の山の神。準備された「玉串」をズームして。白旗神社の社紋・義経(源氏)の紋章「笹竜胆」。白の地下足袋を履いて、あくまでも白。笹竜胆紋は、笹に似た5枚の葉を下向きに広げて描き、その上に3つの花を描く。村上源氏、宇多源氏一門の代表家紋。また、清和源氏の一部でも使用されている。舞台を丸く半円で囲む観客。社のカメラマンも神事の舞台を写真撮影。 ・・・つづく・・・
2023.11.19
コメント(2)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その10)
「江の島・湘南キャンドル2023」を大いに楽しんで、会場の「江の島サムエル・コッキング苑」を出て、振り返る。江島神社の「美人守(ストラップ)」案内。美白・美肌・美笑・美形・美髪のお守りは、ストラップに掛けて・・・。「江の島で キレイ はじめる」と。帰路も「中津宮」前を通過。帰路も「展望台広場ウッドデッキ」から「江の島夜ヨットハーバー」そして「七里ヶ浜海岸」方向を見る。右手に石碑が2基。左は安岡 正篤(やすおか まさひろ)の感載碑。「明神降鑒衆生福智」安岡正篤撰竝書と刻まれていた。昭和の名宰相とされる佐藤栄作首相から、中曽根康弘首相に至るまで、昭和歴代首相の指南役を務め、さらには三菱グループ、東京電力、住友グループ、近鉄グループ等々、昭和を代表する多くの財界人に師と仰がれた人物とのこと。「江島神社、御鎮座千四百年祭」の石碑。左前方にあったのが「神事が行われる場所」であっただろうか。「洪鐘祭(おおかねまつり)御朱印」案内。「洪鐘祭(おおかねまつり)開催日 令和5年10月29日(日)小雨決行江島神社 60年に1度の大祭円覚寺江の島囃子 120年ぶりの大行列参加」と。円覚寺にある国宝「洪鐘(おおがね)」は北条時宗公の遺志を継ぎ、子の北条貞時公が鋳造させたもので「江島弁財天」への参籠、弁財天の啓示を受け、1301 (正安3 )年、鋳造に成功しました。洪鐘は720年の間、時を伝え、人を集めることのみならず、「円覚寺」の梵鐘として、鐘の音とともに功徳を広く伝えてきました。「江島弁財天」への鋳造成功のお礼として「円覚寺」と「江島神社」が共同で神事・仏事を行い、儀式に併せ、山ノ内の村人が「洪鐘弁財天」を奉載し盛大にパレードする「洪鐘祭(おおがねまつり)」は、1480 (文明12 )年に開催され、その後も60年毎の庚子(かのえね)年に続いてきました。「円覚寺」建立・開山の目的、梵鐘である洪鐘の歴史を再確認し、60年後、120年後の後世に繋げるべく、2023 (令和5)年の「洪鐘祭」として開催いたします。 主催:円覚寺洪鐘祭 実行委員会 連縮先: 2023ooganematsuri@gmail. com」「洪鐘弁財天大祭斎行記念 奉拝 江島神社」の御朱印も頂けると。「江島神社奉安殿」を左に見て進む。そして「辺津宮」。「江島神社 瑞心門」に向けて石段を降りる。「脚長爺さん」を自撮りする。さらに脚を長くして。前方に「江島神社 瑞心門」。前方に「江島神社 朱の鳥居(大鳥居)」。右手に「江の島エスカー乗り場」。崖の下の「無熱池(むねつち)」。インドに伝わる伝説の池を真似たもので、龍が住みつき、どんな干ばつのときでも水が涸れたことがないと伝わる池。 「江の島弁財天仲見世通り」沿い右側にあった「磯料理専門店 丸だい 仙水」。美味そうな海鮮料理が並ぶ。舟盛り「伊勢えび入活造り盛合せ 7000円」と。そして「江の島弁天橋」を歩く。人道橋の江ノ島弁天橋が架けられたのは明治24年だったが、台風でよく流されたため、昭和24年に橋脚をコンクリート杭とし、その後昭和28年、PC橋に改修された。横の車道橋の江ノ島大橋は、前回の東京オリンピックのヨット競技のため江ノ島港が建設されたことによって架けられた。目の前に対になった巨大な龍の灯籠が。江ノ島神社御鎮座千四百五十年記念事業を記念して奉納された、江の島の弁天橋出口の巨大な「大灯龍」。向かって右の龍は「阿形」。 向かって左の龍は「吽形」。国道134号「片瀬橋」入口から「江の島」を振り返る。国道134号「片瀬橋」を渡る。国道134号「片瀬橋」出口から「江の島」を振り返る。「片瀬橋」の下にはクルーザーが。そして「新江の島水族館」のイルミネーションを期待してここまで来たが・・・。「新江の島水族館」。国道134号を引き返して小田急線片瀬江ノ島に向かう。小田急線の片瀬江ノ島駅を正面から。駅舎は神社仏閣に用いられる「竜宮造り」と呼ばれる技法を採用。江の島の「五頭龍と天女の伝説」にちなんだ装飾も施されている。1929(昭和4)年の開業時から「竜宮城スタイル」の駅舎で知られた片瀬江ノ島駅。新駅舎は2018年2月に着工し、長年親しまれた旧駅舎のイメージを残しつつ、より「竜宮城らしい」駅に生まれ変わったのだ。楼門上層の窓ガラスには、江の島に伝わる「天女と五頭竜(ごずりゅう)」の伝説にちなんで天女の絵が描かれていた。向かって右。向かって左。屋根の上には鯱ならぬイルカが。向かって右。向かって左。波間から立ち上がる黄金の龍の姿が(右)。波間から立ち上がる黄金の龍の姿が(左)。向唐破風付け根の装飾。黄金に輝く竜の姿が。向かって右。向かって左。改札口横には、新江の島水族館の協力で、クラゲが漂う常設の水槽が。水槽は駅舎正面中央に置かれ、開口部が直径二メートルの円形で、二・六五トンの海水が入っており、ゆっくり回転するように流れている。二十匹ほどのミズクラゲがゆらゆら浮遊するしているのであった。新江ノ島水族館によると、館外に水槽を常設するのは初めて。少し離れた場所にろ過装置があり、地中を通した配水管でつなぎ、水温調節機能も備える。異常が生じれば、近くの同館に警報が伝わり、対応する仕組みになっていると。マリンブルーの神秘的な彩りの中をクラゲが回転しながらゆったりと浮遊しているのであった。片瀬江ノ島駅は。観光スポットの江島神社、江ノ島水族館やマリンレジャーで賑わう江ノ島海岸への最寄駅です。装飾類の内、龍と天女は江島神社に伝わる「江嶋縁起」に因んでいます。「江嶋縁起」の第二巻に「五頭龍は、江島に降り立った天女の美しさに目を奪われ一目惚れ。江の島に渡り結縁を求めるが、天女は五頭龍の所業を非難し諭すのである。そして五頭龍は悪行をやめ人々のため尽くす誓いを立て、天女と結縁する。(遊行寺宝物館発行、特別展江嶋縁起パンフレットより抜粋)」くだりがあります。この物語をテーマに、コンコースの天井には五頭龍を、竜宮門とその周辺に五頭龍と天女を配しました。コンコースの天井には、長さ15m×高さ90cm×厚さ18cmの巨大なケヤキの彫刻が。右側の彫刻を見上げて。左側の彫刻を見上げて。ズームして。左へと。出発を待つロマンスカー新宿行き。そして小田急線藤沢行きを利用して帰路に。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.11.18
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その9)
最後の展示エリアを、これでもかと歩き回りカメラでその美を追ったのであった。キャンドルの炎がゆらゆらと揺れ、周囲の影を舞い踊らせる光景は、まるで魔法の如し。その光と暖かさは、私を穏やかな気持ちに導いてくれたのであった。これ以上のキャプション(写真や挿絵に添えた説明文)は不要なのである。自ずと、キャンドルが語りかけてくれ、美しさを感じることが出来るのでは と。キャンドルの炎は、その小さな存在が持つ美しさを最大限に引き立て、暗闇を優しく照らし出してくれるのであった。「江の島シーキャンドル」と「昆明広場」の「春澤園」のコラボ。美しさに囲まれて、心が静まり、心地よい感触が心に残る瞬間の連続なのであった。そして、その美しさを言葉にすることが難しいことであることも、キャンドルの魅力の一部と言えること間違いなしであった。「江の島・湘南キャンドル2023」は、今年も素晴らしいイベントであった。幻想的なキャンドルアートが、江の島の美しい景色と調和し、訪れる人々の心を魅了。キャンドルの灯りが空を彩り、静寂に包まれた場所が一層神秘的に感じられのであった。多彩なデザインのキャンドルが、一つ一つ物語を語りかけるようで、心に深い印象を残した。また、イベントの雰囲気はとても穏やかでリラックスできる空間であり、家族や友人との素晴らしい時間を過ごすことができること間違いなしであった。「江の島・湘南キャンドル2023」は、美しい芸術と自然の融合が楽しめる素晴らしい体験であった。『江の島の 湘南の灯り 美しき 炎が踊り 海風に灯る』・・・詠み人知らずそして、「江の島・湘南キャンドル2023」の会場を後にして、往路と同じルートで「江の島」を下り、「江の島弁天橋」に向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.17
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その8)
「LONCAFE 湘南江の島本店」を後にして進むと「温室遺構」の炭にあった松の木も僅かにライトアップされて。そして「温室遺構エリア」内にはカップルの記念撮影ベンチが設置されて、係員がカメラマン役を請け負っていたのであった!!ベンチの周囲は、赤いキャンドル中心で白のキャンドルがアクセントに。オレンジ色の灯りはあたたかいだけでなく、アンティークな印象を醸し出していた。この下に記念撮影用ベンチが置かれていた。ズームして。江の島シーキャンドルを再び。そして赤、白、緑、紫・BEST MIXの「chaos」の世界へ。キャンドルの灯りはイルミネーションとは一味違うあたたかみが感じられるのであった。そして「昆明広場」の建物「騁碧亭(ていへきてい)」を見る。中国伝統様式の「四阿(あずまや)」。扁額「騁碧亭」。様々なアイデアが盛り込まれたキャンドル。キャンドルの台座も様々なアイデアを駆使。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.16
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その7)
入口から「江の島シーキャンドル」へのメインルートの出口。アーチ門の頂きには、漁師が海で使用するガラス浮き球に似たものが白く輝いていた。そしてここは地上、そして樹からぶら下がる白の世界。そしてガラス浮き球の世界へ。小さなSailorの姿も。ガラス浮き球の白の世界を追う。通路両脇にも。ススキもライトアップされて。ヤシの樹とシーキャンドルとのコラボ。ズームして。「UMIYAMA DO」前。この通路にはアーチ門が並ぶ。そしてここは「温室遺構」の上部。そして前方左手にあったのが「LONCAFE 湘南江の島本店」。通路脇の赤レンガの上にも。そしてここが「LONCAFE 湘南江の島本店」。「LONCAFE 湘南江の島本店」の横の庭から「江の島大橋」、「江の島弁天橋」を再び。月もますます輝いて。「LONCAFE 湘南江の島本店」の店内を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.15
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その6)
そして「江の島シーキャンドル」の展望台へのエレベーターの列に並ぶ。湘南のシンボルとして親しまれる「江の島シーキャンドル(タワー)」は、2002年の江ノ電開業100周年事業の一環として建設され、2003年4月29日にリニューアルオープンした。避雷針まで入れた高さは59.8m(海抜119.6m)あり、その斬新なスタイルは江の島の新しいシンボルとして親しまれている。高さ41.75m(海抜101.56m)のところにガラス張りの展望フロア、さらにその上には屋外展望台があり、富士山や丹沢などのワイドな眺望が楽しめるのであった。エレベーターを5台ほど待ち、高さ約42m(海抜約100m)のガラス張りの展望フロアに到着。ガラス越しに「江の島大橋」、「江の島弁天橋」そして左に境川河口、右に片瀬東浜海岸を見る。展望台に置かれていた案内板。左方向に目をやれば片瀬西浜海岸、鵠沼海岸。階段を上がり「屋外展望台」へ。「江の島サムエル・ コッキング苑」内の「湘南キャンドル2023」会場を見下ろす。写真左上には、なまこ壁の「UMIYAMA DO」。屋外展望台から、境川河口、片瀬漁港、片瀬西浜海岸を見る。再び屋外展望台から「江の島大橋」、「江の島弁天橋」そして左に境川河口、右に片瀬東浜海岸を見る。稲村ヶ崎、由比ヶ浜方面。渋滞する国道134号の車列のライトが点線状に続いていた。高さ約50mの屋外展望台から「湘南キャンドル2023」を楽しむ。後ほど訪ねた「ウインザー広場」の赤の輝きが美しかった。「江の島大橋」、「江の島弁天橋」の街路灯が水面に映りオレンジ色に輝いていた。そして帰路はエレベーターではなく屋外階段をゆっくりと一歩一歩下る。下部で輝く三角形の屋根の建物が「THE SUNSET TERRACE」。「THE SUNSET TERRACE」の屋外展望フロアのイルミネーション。「UMIYAMA DO」近くでライトアップされたヤシの樹。そして老木からぶら下がった優しい灯りが夜に浮かび幻想的!!ズームして。さらに。屋外展望フロアのウッドデッキに下りて。右は???幻想的な世界のようではあるが・・・。中央は「SEACANDLE」のシンボルマークか?左は???「江の島シーキャンドル」を見上げて。そして更に階段を下りて地上に。そして再び、老木からぶら下がった優しい灯りが夜に浮かび、幻想的なカオスの世界。全体を見渡す光景も美しいが、キャンドルに寄って見てみると、柔らかい色合いが魅力的なのであった。この展示場所は写真映えするキャンドルの演出が見事。幻想的な雰囲気のキャンドルに心を奪われいつまでも佇んでいたい空間なのであった。ファンタジックな世界に近づいて。そしてこちらが入口からのメインストリートの出口。近づいて。そして再び白色の世界に迷い込む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.14
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その5)
そして「江の島サムエル・コッキング苑」手前の広場に到着。「江の島Guide Map」。「湘南Candle 2023 入口」案内。「湘南Candle 2023」と「江の島シーキャンドル」のセット券を800円で購入。「江の島サムエル・コッキング苑」入苑門から入る。「湘南Candle 2023」のポスター。「穏やかに流れる時間 淡く広がるキャンドルの海」。開催:10/14(土)~11/5(日)開催期間中の行事一覧。キャンドル配置エリアマップ。エントランス右側のエリアには入れずに、最後の見学コースになっていた。「立ち止まらないで進んでください」と。右側奥にあったのがライトアップされた「昆明広場 (春澤園)」。中国風の四阿(あずまや)を中心に庭園のようになっている場所。四阿は色も鮮やかで美しい。しかしこの場所も近寄れず、帰りのコースになっていた。「江の島シーキャンドル」へのメイン通路を進む。蠟燭の灯が無色のグラスの中で輝く。所所にアクセントの如き色ガラスが。吊るされたランプの如き赤き輝き。近づいて。そしてライトアップされた「江の島シーキャンドル」を見上げる。こちらは赤き世界。テーブルの上で。月の姿を。ヤシの木もライトアップされて。再び白の世界に青のアクセントの輝きが。振り返って。そして老木から吊り下げられた、数えきれないほどのキャンドルが。大きな老木から吊り下げられたキャンドル。色とりどりのグラスに灯るキャンドル。観る場所、角度によってもいろいろな光景が楽しめるのであった。マヒナセイサクジョ・KENTA-ROHさんによるキャンドルツリーの作品 と一番奥にあったのが、子ども用遊具「ふわふわドーム」。青くライトアップされたヒョウタン形のこぶが二つ。トランポリンのように弾力があって上で跳ねたり滑ったり駆け回ったして遊ぶ子どもたちの姿が。ヤシの木の下には、オレンジ単色の輝きが一面に。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.13
コメント(0)
-
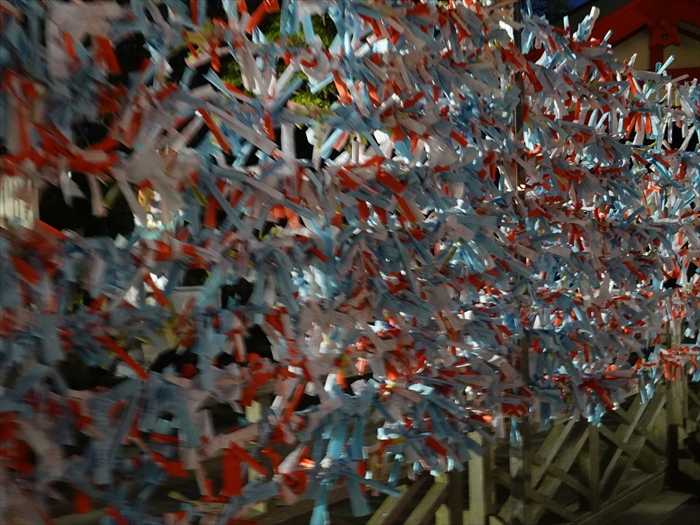
江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その4)
「辺津宮」を後にして、左手に進むと「辺津宮」の「おみくじ掛け」。右手にあったのが「江島神社」の「泰安殿」。「辺津宮」の南隣にある八角円堂。「裸弁財天」とも呼ばれる妙音弁財天像と八臂弁財天像を安置している。源頼朝は奥州の藤原秀衡調伏祈願のために文覚上人に命じてこの弁財天を勧請したと「日本三大弁財天 八臂 妙音 弁財天 拝観受付所」と。神奈川県の重要文化財に指定されている八臂弁財天(はっぴべんざいてん)。江島神社のHP(http://enoshimajinja.or.jp/gohoumotsu/)よりの転載です。同じく日本三大弁財天のひとつとして有名な妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)。 「裸弁財天」ともいわれ、琵琶を抱えた全裸体の意外に小さい座像。女性の象徴をすべて備えられた大変珍しい真っ白な姿で、鎌倉時代中期以降の傑作。 これも江島神社のHP(http://enoshimajinja.or.jp/gohoumotsu/)よりの転載です。 近づいて。見事な「蟇股」の美しい彫刻。「奉安殿江の島弁財天への参詣の歴史は古く、広島 の宮島、滋賀県の竹生島と並び「日本三 大弁財天」として篤く信仰されて来ました。 弁財天は当初、武人守護の神として信仰を 集めていましたが、時代が進み泰平の世に なることで、次第に“芸能・音楽・知恵 ・ 福徳の神”として信仰されるようになりました。奉安殿では勝運祈願の神として信仰される八臂弁財天(国重要文化財)や音楽芸能の上達を願う人々の信仰を集めている妙音弁財天(市重要文化財)の御尊像をお祀りする他、多くの宝物を収蔵しています。」その先右手にあったのが「八坂神社(やさかじんじゃ)」。 「八坂神社御祭神 建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。例祭日 七月十四日旧称 天王社御祭神の建速須佐之男命は八岐大蛇(やまたのおろち)退治で知られる日本神話の英雄で、神仏習合時は牛頭天王と呼ばれました。疫病を始めとするあらゆる災難からお守り下さる神様で、江島神社に祀られる三女神の父神でもあります。」「藤沢市指定重要無形文化財江の島天王祭令和ニ年(ニ〇ニ〇)四月一日指定八坂神社(江島神社境内社)の江戸時代以来の例祭。腰越で祀られていた神体(建速須佐之男命)が大波に流されたのを、江の島の大海士(素潜り漁師)が海中より、すくい上げて祀ったと伝わります。この伝承を再現したのが、今日では毎年七月第ニ日日に行われる神幸祭(神興の海上渡御・東浦祭典・小動神社渡御)です。その前後数日間の一連の祭礼が天王祭で、「かながわの祭り50選」に選ばれています。祭祀の始まりを再現する形態が、伝承通りに江の島島内の漁師を主体として伝えられていること、特殊神饌として調理した麦を供した後、参拝者に振る舞うことに特色があります。神興渡御の際に先導して奏でられる「江の島囃子」は、神奈川県の重要無形民俗文化財に指定されています。」江の島天王祭の写真。海に入る神輿の写真。「八坂神社」の先にあったのが「稲荷社・秋葉社」。「八坂神社」の隣にある小さな社。江島神社の末社だと。豊受気毘賣命(とようけひめのみこと)と火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)が祀られている。江の島随所にあった小祀(秋葉稲荷・与三郎稲荷・漁護稲荷など)を合祀した社とのこと。「稲荷社・秋葉社」。社殿に近づいて。石段の途中にあった「石鳥居」。「猿田彦大神」碑。「猿田彦大神」案内。「猿田彦大神この碑は庚申塔の一つで、天保3年(1832年)に建てられたものです。碑の執筆者である阿部石年は、藤沢宿の儒者として、また書家として知られ、天保6年(1835年)に没し、その墓碑は鵜沼の万福寺にあります。この碑に書かれている「猿田彦大神」とは、古事記・日本書記の神話に登場する神で、天孫「ににぎのみこと」降臨の際、高千穂までの道案内を務めた神といわれ、中世以降、「庚申信仰」や、「道祖神信仰」と習合しました。※庚申信仰とは人間の体内には、三戸という三匹の虫がいて、常に人間が犯す罪過を監視し、庚申の晩に体内から抜け天にのぼり天帝に罪過を報告し、人間を早死にさせるという。だから庚申の晩は、常に徹夜をしていれば体内から抜け出し報告できないので、早死にを免れ長生きできるという、中国道教の教えからはじまっています。猿田彦の名前から庚申の「申」と結びついたといわれています。」「展望台広場ウッドデッキ」から「江ノ島ヨットハーバー」が眼下に。上空には月の姿が。ズームして。対岸は逗子・葉山を走る国道134号。「江島神社・中津宮(なかつみや)」に到着。平成11年に江の島歌舞伎が行われた時の5代尾上菊五郎、7代菊之助の記念手形。近づいて。「平成十一年(一九九九)九月七代目尾上菊五郎、五代目尾上菊之助出演の「江の島大歌舞伎」が盛大に開催されました。当地ゆかりの「弁天娘女男白波」を演目とし、菊之助が演じた弁天小僧は大いに観衆をわかせました。開演に先立ちお錬りで弁財天に詣でた際、菊之助御自身の手植えにより献樹された「しだれ梅」であります。」「江島神社・中津宮(なかつみや)」の狛犬(阿形、右)。狛犬(吽形、左)。「中津宮中津宮には三女神の一柱である市寸島比賣命をお祀りしています。853年に慈覚大師によって創建され、明治時代までは辺津宮が「下之宮」と称されたのに対し、この「中津宮」は「上之宮」と呼ばれていました。現在の社殿は1 9 9 6年に全面的に改修されたもので、創建当時の朱色が鮮明な社殿を再現しています。境内には江戸時代に歌舞伎関係者によって奉納された石灯籠のほか、多くの奉納石造物があり、信仰の深さをうかがい知ることができます。」見事な朱の社殿。見事な彫刻。扉の紋様。扁額「中津宮」。「中津宮市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)をお祀りしています。創建は文徳天皇仁寿3年(853年)。その後、元禄2年(1689年)に改築され、朱色が鮮明な現在の御社殿は、平成8年の全面的な改修により、元禄2年改築当時の中津宮(権現造り)を再現したものです。幣殿・拝殿の天井には花鳥画や、彫刻が施され、境内に奉納された石燈籠等は、江戸時代における商人・芸人・庶民の信仰の深さを物語っています。美しい恋したい。「美しい弁財天さまにあやかり、綺麗になりたい!」と願う女の子たちの象徴として、弁財天様の羽衣をイメージした中津宮独自のマークです。三姉妹の女神様の中津宮の市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)が「もっと綺麗に、もっと美しく恋をしたい。」女神である女性達に贈る願いが込められております。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.12
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その3)
「江の島弁財天仲見世通り」を更に進むと、前方に「江島神社 瑞心門」が垣間見えて来た。社号標石「江島神社」。日露戦争・日本海海戦の名将・東郷平八郎元帥の揮毫により、大正十年(1921年)に建立されたもの。前方に「辺津宮 大鳥居(朱の鳥居)」。この朱塗りの大鳥居は、文化二年(1805年)に建立され、明治元年に再建された石の鳥居を、昭和11年(1936年)に鉄筋コンクリート造りで再建したもの。東京・山田流筝曲家元・林敏子さんの寄進とのこと。辺津宮(へつみや)の鳥居の左手前には、「日本三大弁財天 江島神社」と書かれた琵琶を模した案内板が。江島神社の妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)御尊像は「裸弁財天」ともいわれ、琵琶を抱えた全裸体の座像なのである。そして、正面を見上げると、白塗りの龍宮城をイメージした「瑞心門」が聳え、昭和12年(1937年)に整備された大石段には登り口に石灯篭、中段に朱塗りの春日灯籠が見えた。この大石段の近辺には由緒ある観光ポイントがたくさんあるのだ左手奥には「江の島エスカー乗り場」。「江の島エスカー乗り場」は、江の島2丁目3にある「江の島弁財天仲見世通り」を抜け、江島神社の鳥居の左手にある。屋外エスカレーターで、頂上まで石段を上っていくと20分かかるところを、わずか4分でアクセスできる。エスカー乗り場は1区、2区、3区の3か所がある。「瑞心門」そして朱塗りの春日灯籠を見る。昭和61年に建設された「瑞心門」は「瑞々しい心」でお詣り出来るようにと。今年も、7月15日(土)~8月31日(木)に開催された「江の島灯籠2023」のライトアップ。江の島に1000基の灯籠を設置してライトアップし、幻想的な世界を演出したのだ。以下の3枚の写真は友人から送られて来たものです。今年も「光の絵巻」が江島神社 瑞心門に登場。ベルベッタ・デザイン演出による「光の絵巻」がエリアを拡大して今年も登場!期間中、江の島エスカー1区で、江の島の伝説「天女と五頭龍」をイメージした映像を映しだしたのであった。昨年の江の島灯籠でも、夏の夜空に浮かぶ瑞心門を彩る光のインスタレーションは大変好評。2年目の今年はスケールアップ!瑞心門〜階段〜辺津宮まで広がったエリアで「天女と五頭龍の恋物語」をフィーチャーし、今年のモチーフ「花火」を加え、さらに華やかに“光の絵巻”を演出して江の島の夏の夜を彩ったものだと。 ここ瑞心門では「江ノ島誕生」 「五頭龍」 「天女降臨」 「天女と五頭龍の出会い」「五頭龍の御加護」加え、新たに「花火」のモチーフによって厄災を祓う気持ちと現代の美しい江の島の夜を表現したのだと。そしてこちらは、今年2023年に送られて来た写真です。朱塗りの春日灯籠に近づいて。瑞心門の両側には唐獅子画が。この唐獅子は神様を守るとともに、参拝者の災いを払うために描かれたものと。右側は青の唐獅子。左側は緑の唐獅子。「瑞心門唐獅子片岡華陽 筆中央アジアからもたらされたライオンが古代中国で幻想動物として描かれ、我国には密教曼荼羅の中の唐獅子が9世紀に渡来し、定着していきました。以後、仏法のみならず邪悪なものを退け、国家鎮護を祈念する形代として飾られるようになりました。この瑞心門唐獅子は御祭神の守護と合わせてご参拝の皆さまに厄災なきことを祈願して飾りました。平成7年4月初巳日 江島神社奉納 東京 中村明」「瑞心門」下から振り返って。石段を上ると正面にあったのが「弁財天童子石像」。近づいて。剣と宝珠を持つ弁財天。斜めから。優しいお顔の「弁財天 童子像」。「弁財天 童子像 建立之記平安時代中期に撰述せられた「江島縁起」は、天地開闢のことより説き起し、東海道相模国江ノ島が 天下の霊地たるを記述せられている。縁起に曰く、「欽明天皇13年卯月12日、戌刻より23日辰刻に至るまで、江野南海湖水湊口に雲霞暗く 蔽いて、天地震動すること十日に余れり。諸々の天衆龍神水火雷電山神類夜叉羅刹、雲上より 磐石をくだし海底より塊砂をふき出す。その後、竭雲収まり軽霞まきしりぞいて、海上に忽ちに 一つの嶋を成せり。即ち江野にまぞらえへて、これを江野嶋という。天女、雲上に顕れ、 白龍、十五童子を従へ、この嶋上に降居したまへり」とあり、弁財天が江ノ島に祀られることと なりしを伺い知ることが出来る。折りしも当神社御鎮座1450年を迎へ、記念事業としてこの縁起に基づき、弁財天顕現の一場面を、篤志者の御浄財を以て石像にて奉製いたし、弁財天の無量無辺不可思議の功徳を後の世永く称え奉るべく、祈念建立いたすものなり平成十四壬午歳十二月吉日 江島神社 宮司 相原圀彦」。「江島神社全景絵地図御祭神は、三人姉妹の女神様社殿によると、欽明天皇十三年(552)に、「欽明天皇の御宇、神宜により詔して宮を島南の竜穴に建てられ一歳二度の祭祀この時に始まる」とあります。これは、欽明天皇の勅命で、島の洞窟(岩屋)に神様を祀ったのが、江島神社の始まりであることが記されてます。欽明天皇は、聖徳太子よりも少し前の時代の天皇で、この頃、日本では仏教が公伝され、日本固有の神道と外来の仏教が共に大事にされていました」。「江島神社全景絵地図」「江島神社 三宮の御案内」。「江島神社 三宮の御案内 辺津宮・中津宮・奥津宮の三宮を総称して江島神社と称す。辺津宮(へつみや 下之宮)御祭神 ・・・・・ 田寸津比賣命(たぎつひめのみこと) 土御門天皇 建永元年(1206) 源實朝が創建。 弁天堂には日本三大弁財天の妙音・八臂弁財天御尊像を始め十五童子像・後宇多天皇の勅額 ・弘法大師の護摩修法による弁財天像が奉安されている。宋国伝来の古碑・福石・白龍銭洗池 ・御神木の結びの樹等があり八坂神社・秋葉稲荷社が境内社として鎮座する。中津宮(上之宮)御祭神 ・・・・・ 市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと) 文徳天皇 仁寿3年(853) 慈覚大師が創建。 現在の社殿は元禄2年(1689)の御造営で平成8年の御改修により、格天井には花鳥画が施され 彫刻等が復元された。境内には歌舞伎界より奉納された石灯籠等がある。奥津宮(御旅所・本宮)御祭神 ・・・・・ 多紀理比賣命(たぎりひめのみこと) 天保13年(1842)再建。源頼朝奉納石鳥居・酒井抱一画の八方睨みの亀・八十貫の力石・鎌倉 四名石の一つ亀甲石・御神木・山田流箏曲開祖 山田検校像等がある。龍 宮(わだつみのみや) ・・・・・ 龍神をまつる(例祭9月9日)岩 屋 波の浸食で出来たもので第一・第二霊窟からなり約150メートル深奥が当神社発祥の地であ る。欽明天皇13年(552)にこの地に鎮座された。 春季大祭 初巳例大祭 四月初の巳の日 秋季大祭 古式初亥祭 十月初の亥の日 一歳両度の祭祀として欽明天皇の御代より連綿と継承されている」さらに石段を上って行った。右側にあったのが「杉山和一の墓」。江戸時代に日本独自のはり技術である「管鍼法(かんしんほう)」を創案したとされる盲目の鍼医杉山和一検校(1610~1694)。「杉山和一総検校(すぎやまわいちそうけんぎょう)」像」台座には和一の歌「よばばゆけ 呼ばずば見舞へ 怠らず 折ふしごとに おとづれをせよ」が。銅像は生誕410年の記念に藤沢市鍼灸・マッサージ師会などが計画し、2020年9月に建立された。写真左側に、杉山検校和一の建てた江ノ島弁財天の道標とその後ろに『福石』と刻まれた比較的小さい石碑が。杉山検校は、江ノ島の弁財天で21日間の断食をし、祈願したところ、その満願の日、帰り道にこの石につまずいたと。その時、体を刺すものがあったので確かめてみると、松葉の入った竹の管だったいう。この出来事が、管鍼(かんしん)の技術を考案するきっかけとなったといわれていると。朱塗りの橋・「御幸橋(みゆきばし)」を下に見る。「御幸橋」は、江島神社と旧片瀬小学校江ノ島分校(今は「江ノ島市民の家」)を結ぶ橋で、下を奥宮に続く裏参道が通ります。 旧片瀬小学校江ノ島分校のあった場所には、かつて閻魔堂と杉山検校により元禄七年(1694年)建立された三重塔がありました。 なおアーチ形の現在の橋は、戦後架け替えられたものです。葛飾北斎 「富嶽三十六景 相州江の嶌」に描かれている「三重塔」。そして更に石段を上がると正面に「手水舎」が現れた。江島神社「十月 社頭歴」。江島神社の十月の祭礼・行事予定が書かれていた。手水舎でお清め。手水舎に龍の吐水口(とすいこう)。近づいて。日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められて来た。水はすべてのいきものにとって命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では穢れや邪気を祓う神聖なものとされた。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、心身を清めるために行うものですから、この水を「龍神から出ている水」と見せることで「神聖な水である」ことを表現しているのだ。そして更に石段を上ると「辺津宮」の屋根が現れた。石段を上り終わるとそこは辺津宮境内。弁財天を奉る江島神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を祀る「中津宮」、多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなっているのだ。辺津宮は本社。田寸津比売命(たぎつひめのみこと)が祀られている。右手にあったのが「茅の輪くぐり」。古歌を唱えながら茅の輪をくぐると罪などが清められるのだそうだ。 毎年、正月は中央に置かれてあったがこの日は脇に。正面から。正面には唐破風屋根が。唐破風はその名称から、中国由来と思われがちだが、日本特有の破風形式。その歴史は平安時代にさかのぼると。日本では中国の先進的な文物を「唐物(からもの)」と呼んで珍重し、何か目新しいものに「唐(から)」という名を付ける傾向があったので、「唐破風」と呼ばれるようになったものと。懸魚(げきょ)と扁額を見る。扁額「邊津宮」と。江島神社の社紋「向かい波三つ鱗」。鎌倉時代に崇敬された北条氏の家紋である「三枚の鱗」をモデルに、海の波で囲んだ「三つ鱗」を表現しているのだと。そして「辺津宮」に向かい合うのが、江島神社の辺津宮の「白龍王黄金浄水(銭洗白龍王)」江の島の弁財天は、かつては岩屋洞窟に安置され、その御霊水で金銭を洗うと金運向上・財宝福徳の御利益があるといわれてきた。水源には徳力製の純金の小判が秘められてあり、この御霊水で金銭を洗うと、金運向上、財宝福徳のご利益が授かると。 製作者は、相模彫の創始者・鏡碩吉(かがみけんきち)。辺津宮の賽銭箱も同人の作 と。弁財天の神使「白龍王」をズームして。「龍神と弁財天水辺に鎮まる龍神は古来より気象を司る国土安泰の神とされました。江ノ島では弁財天の夫神として財宝福徳の神として信仰を集めています。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.11
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その2)
この日の夕日の絶景を楽しんだ後は「江の島弁天橋」を「江の島」に向かって進む。「江の島サムエル・コッキング苑」内に建つ「江の島シーキャンドル」を見る。イギリスの貿易商、サムエル・コッキング氏が明治時代に造った洋風庭園を整備。高さ約60m、海抜約100mの展望灯台からは、南に大島、西に富士山、東に三浦半島を望むことができるのだ。「江の島シーキャンドル」の灯りは未だ。時間は16:50。未だ、箱根の山の端の上の雲は赤く染まっていた。「境川」の河口を見る。「境川」は、県北部の城山湖付近を源として都県境を南下し、藤沢市の江ノ島付近で相模湾に注ぐ、流域面積約211平方キロメートル、延長約52キロメートルの二級河川。「片瀬漁港」越しに「大山」の姿を。丹沢大山(たんざわおおやま)国定公園に位置する大山(おおやま)は、神奈川県伊勢原市を表玄関に、標高1252mのピラミッド型の美しい山容を誇る。大山が別名「雨降山」(あふりやま)と呼ばれるのは、相模湾の水蒸気をたたえた風を受け、雨が降りやすい(また上がりやすい)山容に由来し、別名「あめふりやま(雨降山)」転じて「あふりやま(阿夫利山)」となったため と。相模湾にも夕闇が迫りつつあった。片瀬漁港・西プロムナードの先端には「白灯台」、その先には丹沢の山々が。「江の島シーキャンドル」をズームして。最上階に灯室、その下に屋外展望台、さらにその下にガラス張りの展望室。屋外展望台には多くの観光客の姿が確認できた。夕日が沈んだ箱根・二子山をズームして。これぞ「残照」。そしてこの日の月も輝きを増して来た。波静かなこの日の相模湾。海鳥もネグラに戻るのか?「江の島弁天橋」その先に「江の島ヨットハーバー」の街路灯が。江の島唯一の天然温泉と絶景に癒される HOTEL & SPAで豊かな自然環境に恵まれた江の島入り口に位置する「江の島アイランドスパ」2020年4月より江の島ホテルが併設され、宿泊もできるホテル&スパへと生まれ変わった と。屋根から天に向かって突き出た金属製「相輪(そうりん)」を持つ「中華飯店 吉祥楼」が正面に。正面に「江島神社」の「青銅の鳥居」が見えて来た。「江の島アイランドスパ」の前庭のあるライトアップされたハート型のオブジェをズームして。江の島の玄関口にある「貝作」。湘南の海を眺めながら海の幸から洋食まで美味しい料理を楽しめる店。また新鮮な海産物をその場で焼き上げてくれる店。デッキで潮風を感じながら海鮮を楽しめる店。海産物を中心とした土産も豊富。「中華飯店 吉祥楼」、「江の島アイランドスパ」の入口。1Fエレベータホールの壁に描かれた花を中心にした和風絵画も見事。歩いて来た「江の島弁天橋」を振り返る。「江の島アイランドスパ」の前庭のあるライトアップされたハートのオブジェ。引き返して再び反対側を。牡丹、菊等が豪華に描かれていた。そして戻って「江島神社」の「青銅の鳥居」前に。江の島弁財天信仰の象徴である青銅の鳥居は延亨4年(1747)に創建された。現在のものは文政4年(1821)に再建されたもので、約200年の間、潮風をうけながらその姿をとどめているのだと。高さ5.52mと。「江島大明神」と書かれた鳥居の扁額と。この文字の書体は「鳥虫書」という中国の世帯であるとNHKのテレビでは。よく見ると、文字の一部が鳥の姿に見えるのであった。そして扁額の周囲の縁には龍の姿が。「青銅の鳥居江の島弁財天参拝の玄関口となる鳥居です。古くは木製の島居でしたが、1 8 2 1年に青銅製で再建されました。鳥居の柱には再建に尽力した大勢の人々の名前が刻まれており信存の篤さを物語っています。江戸・吉原の大旦那衆の名前や、人気の花魁・代ゝ山の名前もあると。正面の額には「江島大明神」と書かれていますが、特徴的な筆跡は弁財天のお使いである蛇をかたどっています。鎌倉時代、我が国にモンゴル軍が襲来した戦い(文永の役)で敵側が退散した事への神恩感謝として、第91の後宇多天皇が奉納したとされる勅額(天皇から賜った額)を写したものです。1997年に藤沢市の指定文化財に登録されました。」こちらの説明文には「蛇」、NHKの放送は「鳥」と、どちらが本当なのであろうか??この先の商店街の道「江の島弁財天仲見世通り」は神奈川県道305号江の島線なのである。右手にあったのが「しらす問屋とびっちょ 江の島弁財天仲見世通り店」。美味そうな丼が並ぶ。「しらすのかき揚げ丼」。「シェルランプ工房」。美しい貝殻の中で電球を光らせるシェルランプをガラスボトルや浮き球の中に組み込んだ、オリジナルのシェルランプとのこと。透き通ったガラスの向こうに広がる小さな海の世界をやわらかい光と共に楽しめたのであった「江の島弁財天仲見世通り」沿いに置かれていた行灯。伝統文様「青海波(せいがいは)」と鎌倉幕府執権北条氏が用いた家紋「三つ鱗」。「青海波」は三重の半円を連続して波を表した幾何学文様発祥はササン朝ペルシャとされる普及したのは江戸時代とされる未来永劫への願いが込められた吉祥文青海波は日本以外でもエジプトやペルシアなど各国で見る事ができる文様とのこと。古くは埴輪の着物に見られるが、水の意味として描かれるようになったのは鎌倉時代以降と。「青海波」という名前の由来は、雅楽の青海波という演目から来ている。江戸時代の舞人の袍にはこの文様が描かれている。平安時代にも源氏物語で青海波を舞う場面があるのだが、この時の装束はどのような文様か明確ではないのだ と。「創作ちりめん「布 遊舎」江ノ島店」の中には猫の面が並んでいた。江の島は猫が多い事でも有名とのことだが・・・。近づいて。洒落た和傘。その下には吊るし飾り玉? 「葛飾北斎 富嶽三十六景 相州江の島」。そしてその先右手にあったのが「岩本楼本館」入口。「旧岩本院(岩本楼)」案内。「旧岩本院(岩本楼)江の島の歴史の中て、置重な役割を担ってきたのが、この岩本院てす。中世、江の島には弁才天を本尊とした、「岩屋本宮」・「上之宮」(現中津宮)・「下之宮」(現辺津宮)の三宮があり、それそれ岩本坊・上之坊・下之坊の各別当寺が管理にあたっていました。この三坊の中で「岩本坊」は、「岩屋本宮」及び、弁才天の御旅所であった「奥津宮」の別当寺で、江戸時代に、院号の使用を許され「岩本院」と称し、江の島全体の別当でした。この岩本院の先祖は源氏一族の中の「宇多源氏」の流れをくむ、近江源氏として有名な「佐々木氏」です。江戸時代には、文字や芸能にもとりあげられ、中ても歌舞伎の「青砥稿花紅彩画(通称「白浪五人男」)に出てくる「弁天小僧菊之助」は、「岩本院の稚児」がモデルといわれています。」豊原国周「当世五人男」。右から桐野利秋/坂東彦三郎、篠原国幹/尾上菊五郎、西郷隆盛/中村芝翫、村田新八/市川左団次、田村啓二/市川団十郎詞書坂東彦三郎「遠からん者は鉄砲の音に、音羽の紋所九字ひしなりに曲んだる頑固士族の三隊長、 見かけて山鹿、木留口、数度戦場ゑくり出し、さつま造りの刀にて、多くの者を桐野利秋。」尾上菊五郎「さて其次に備へしは、名も梅幸と花の兄、まづ魁にすゝんだる、肥後熊本の城攻に、力も運も つき、弓も引て返さぬ武士の意地、暴徒が噂、高瀬へ行んと吉次峠の切所にて、重ね扇の 七重八重、取かこまれて閃きし、剣の雨の篠原国幹。」中村芝翫「事もおろかや大軍の、総大将と成駒屋、どふせ終はとふ丸の、かごしま県を出陣し、肥後川尻の 本営も、やぶれかぶれと日向路へ、引あげ方のともし火や、消る間近き西郷隆盛。」市川左団次「名のるもちつと嗚呼がましいが、うつ大砲の音もろとも、その名は早く高嶋屋、米といふ字の 兵粮奉行、横に東の我侭は、花に嵐が照る月に、むら雲ならぬ村田新八。」市川団十郎「さてどん尻の後陣は、暴徒の長と成田屋が、指揮の手配りかけ逐を、人も三升の三の嶽、 くま取りならで隈府の陣も、うち崩されて一名を、延岡辺の士族を煽動、こゝやかしこへ 集合なす、屯ろにあらで田村啓二。」「黄金水汲取記念碑」。【碑文】 昭和四年五月廿四日己巳歳巳月己巳日巳刻執行 江之嶋岩屋前海中に於て推古天皇以来我國最初行事也 隠遁術三十六法之内浪切法玄武之法則子孫永久末代開運基 神仙金龍一生一代之法術六十一年目黄金の潮汲黄金水汲取記念碑 江の嶋乃こかねの水や皐月晴昭和六年五月建設 東京市赤坂區青山/神理教 明徳教會 隠遁術三十六法極意神仙鈴木金龍【現代語訳】 昭和4年(1929年)5月24日午前10時執行。 江の島岩屋前の海中で、(これは)推古天皇以来、我が国最初の行事である。 隠遁術三十六法の内、浪切法と玄武之法は、すなわち子孫が末代まで永久に運が開ける 基盤となるものである。 神仙・(鈴木)金龍が一世一代の秘術を駆使して、61年目に黄金の海水を汲んだ。ちなみに黄金水というのは、修験者が精進潔斎の後、神通力をもって汲み取った水だと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.10
コメント(0)
-

江の島・湘南キャンドル2023:夜空に輝く10,000の灯りの魔法(その1):相模湾の夕日
この日は10月26日(木)、江の島サムエル・コッキング苑で行われている湘南の秋の夜を美しく彩る人気のイベント『湘南キャンドル2023』を楽しむために江の島に向かう。夕日の光景も楽しみたいので、自宅を16時過ぎに出発し。小田急線で「片瀬江ノ島駅」に向かった。2020年に完成した新駅舎は、先代の神殿調の駅舎デザインを引き継ぐとともに、社寺に用いられる「竜宮造り」の技法を取り入れて、江の島の「五頭龍と天女の伝説」にちなんだ天女と龍の装飾を施している一方、イルカの像をしゃちほこのように設置するなどの品格と遊び心を共存させたデザインとなっている。また、コンコースには新江ノ島水族館の協力を得てクラゲ水槽を設置しているのである。そして夕日を楽しむために「江の島弁天橋」に向かって急ぐ。「境川」に架かる「弁天橋」から国道134号の「片瀬橋」越しに江の島を見る。「弁天橋」の彫刻「雲の形」も夕陽を浴びて。「弁天橋」からの夕陽。そして「江の島弁天橋」を「江の島」に向かって進む。夕日が箱根・下二子山の左に沈みかかっていた。二子山(ふたごやま)は、神奈川県足柄下郡箱根町にある、標高1,099mの火山である。二子山は箱根火山のカルデラ内の南東側に位置し、約5,000年前の噴火で形成された溶岩ドームである。箱根駒ヶ岳、神山、台ヶ岳などとともに中央火口丘を構成する。その名のとおり、双生児のように二つの峰が並んでおり、北側が上二子山1,099m、南側が下二子山1,065mとなる。「江島神社御鎮座記念龍燈籠」が前方両側に。江の島は弁財天と五頭龍の伝説がある。この龍燈籠は「江島縁起」による江の島湧出の時から、数え1450年を記念に平成13年(2001年)に建てられたもの。片瀬漁港の「海釣りゾーン」の「東・西プロムナード」越しに夕日を見る。ズームして。夕陽をズームして。これぞ「真っ赤な太陽」。夕日が箱根の山の端に傾き、その真っ赤な太陽はまるで巨大な火の玉のようで、その鮮やかな赤はまるで天空に燃える炎を灯したかのようであった。太陽の周りには、深いオレンジ色と赤色の光線が広がり、空を美しく染めているのであった。しかし、箱根の山々の右側には富士山の勇姿が見えるのであったが、残念ながらこの日は・・・。「名勝及史蹟江ノ島」碑。オブジェ「潮音」。「円弧型日時計」といい、日時計作家 小原輝子の作、長洲一二元神奈川県知事の揮毫になる「潮音」という文字が黒御影石に彫られている。平成元年4月、藤沢のライオンズクラブが結成15年を記念して建てたものである。日時計の位置は、東経139度29分11秒、北緯35度18分秒。日時計にはこう刻まれている。「時は形がなく見えません。しかし、私達には確かに時が過ぎていくのが感じられます。人々は大昔、太陽の動きをつかまえて、とりとめもなく流れる時に区切りをつけました。それが日時計と時刻です」と。海面に映る朱の帯はまさに幻想的で美しい景色。移動して。太陽が西の地平線に沈みかかると、海面に広がる朱の帯が現れた。海は深い青から徐々に朱の色に変わり、太陽の余韻が海上に続いてたのであった。この朱の帯は、まるで大海が燃えるように美しく輝き、その美しさは心に焼き付くのであった。帯の輝きも刻々と変わって。朱の帯は、海の水面に広がり、太陽の色と海の静寂が絶妙な調和を奏でているかのように。それはまるで大自然が演じる壮大なシンフォニーであり、朱の色は海面に魔法の絨毯を敷いたかのようであった。波は穏やかに押し寄せ、太陽光の輝きが波間にキラキラと踊るのであった。夕日をズームして。海の上に広がる朱の帯は、美と静寂の共鳴を体現し、その光景は自然の贈り物として魅了し続けるのであった。太陽光の輝きが波間にキラキラと踊り、砂浜をも赤く染めるのであった。再び夕日をズームして追う。これぞ「落陽」。そしてこれぞ「落日」。夕日が西の山の端に沈みかかると、その温かな光が海の表面に触れる瞬間、海は魔法のように変身したのだ。海の帯は、まるで宝石のような輝きを放ち、その美しさは言葉では十分に表現できないほど圧倒的!!。雲の端も赤く染まり夕日との共演を。夕日が西の山の端に沈む瞬間、大地は神秘的な魔法に包まれるのであった。夕日は山の尾根にゆっくりと沈み、山々の輪郭を美しいオレンジ色で彩る。そのオレンジ色の光線は山の頂上に触れ、空を燃える炎のように染め上げていた。夕日は山々の間から徐々に消え、一日が静かに終わろうとしているのであった。デジカメ、ズームでその瞬間を追いかけたのであった。そして日没の瞬間。夕日は山の尾根にゆっくりと沈み、山々の輪郭を美しいオレンジ色で彩るのであった。そのオレンジ色の光線は山の頂上に触れ、空を燃える炎のように染め上げた。夕日は山々の間から徐々に消え、昼間の一日が静かに終わろうとしているのであった。時間は2023年10月26日、16:47:36。そして山の端は完全に黒く染まって。上空を飛行機が、海上自衛隊厚木航空基地から離陸したものか?この日の日没後の西の空の絶景。雲の姿はムンクの『叫び』を想い出したのであった。東の空には月の姿が。瞬く間に変わりゆく雲の色彩をしばし楽しむことができたのであった。そして「湘南港灯台(江ノ島白灯台)」も点灯して。1964年(昭和39年)9月26日 にこの灯台を設置。2002年(平成14年)4月1日 : 位置:北緯35度17分56秒 東経139度29分17秒、灯質:等明暗緑光 明2秒暗2秒、光度:700 カンデラ、光達距離:8.5 海里へ変更する。2010年(平成22年)3月15日 : 光度を820 カンデラへ変更する。とウィキペディアより。 ・・・つづく・・・
2023.11.09
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その17):
さらに「筑土八幡神社」の散策を続ける。参道右手に境内社の「宮比神社(みやびじんじゃ)」が鎮座。享和2年(1802)造立の「明神鳥居」風が立つ境内社「宮比神社」、技芸・芸能の御利益ある祭神・宮比神(大宮売命・おおみやのめのみこと、天鈿女命・あめのうずめのみこと)を安置。 古くは下宮比町(新宿区北東部、新宿区・千代田区・文京区の区境)の旗本屋敷の邸内社として祀られていたが、明治40年(1907)境内に遷座された と。扁額「宮比神社」。一木から彫り出したものであろうか。扉の隙間から内陣を。左手には神輿を格納する「神輿庫」。「神輿(みこし)について右側の黒い漆塗りの神輿は、延宝六年(西暦一六七八年)に、当時の氏子崇敬者が神徳に報謝して製作したもので、戦前から昭和四八年までの渡御に用いられました。左側の白木の神輿は、鉄製の飾り綱、支え棒のついた重厚で堅牢な造りで、慶応ニ年(西暦一八六六年)に製作されたものです。昭和五ニ年に修理されて、その後の渡御に用いられています。」正面の黒い漆塗りの神輿を格子の隙間から。その横の囲いは純米大吟醸「白鷹」の積み樽が。「白鷹」は灘の蔵元の清酒だが、明治19年、神楽坂の酒問屋・升本総本店の店主、升本喜兵衛に見出され、神楽坂の料亭などで広く販売したとのこと。「奉献 清酒「白鷹」菰冠積樽清酒「白鷹」は、全国の蔵元から唯一つ、伊勢神宮の御料酒として選定され、現在に至るまで日々神前に供えられている灘の銘酒であるが、当地牛込・神楽坂とも浅からぬ縁を持つ酒でもある。「白鷹」蔵は江戸末期、「超一流の酒のみを造る」という志で「白鹿」辰馬本家から分家した初代辰馬悦蔵によって興された。しかし超一流主義の造りは結果として高価なものとなり、酒質の評価は得たものの、市場ではなかなか受け入れられるに至らなかった。その中で、江戸・明治と、この白鷹を盛り立てたのが、神楽坂の料亭街と牛込揚場・神楽河岸に蔵を構えた酒問屋であった。神楽坂などの安定的な顧客を得た白鷹はその後着実に超一流の酒造りに取り組み、大正13(1924 )年には伊勢神宮の御料酒として選定されるに至ったのである。こうした経緯から、現在でも神楽坂では白鷹が愛されており、路地裏には白鷹の看板も散見される。また、江戸城外濠を隔てた飯田橋・東京大神宮でも、年間数万本の御神酒「白鷹」が参拝客にお頒(わ)けされている。そして、白鷹の関東一手捌元として名を馳せた酒問屋も牛込揚場・神楽河岸から津久戸町、そして筑土八幡町・御殿坂に移転し営みを続けている。斯くなる御縁に感謝し、この地の産土神たる筑土八幡神社に「白鷹」積樽を奉納する。」「社務所」。そして「筑土八幡神社」の「神殿」。狛犬(阿形・右)。狛犬(吽形・左)。神殿の向唐破風(むこうからはふ)、蟇股(かえるまた)を見上げて。神殿の正面。御祭神 應神天皇(おうじんてんのう) 神功皇后(じんぐうこうごう) 仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)。過去には、参拝の際に鳴らす大きな鈴があったようだが・・・。コロナ禍の名残それとも音の問題??扁額「築土八幡神社」はピンボケ。社殿内陣。ズームして。「本殿」を廻り込んで。「本殿」の裏にも各自治会の神輿庫?が並んでいた。引き返して参道を戻ると前方に見えたのが「JCHO 東京新宿メディカルセンター」。全国の社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院の3団体は、平成26年4月1日より「独立行政法人 地域医療機能推進機構・Japan Community Healthcare Organization(JCHO:ジェイコー)」が直接運営する公設・公営の病院へと移行することとなった。このことに伴い、昭和27年創設当時より長年親しまれてきました「東京厚生年金病院」は、「独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター」と名称変更して、新たにスタートしたとのこと。なお「JCHO 東京新宿メディカルセンター」を通称として用いているとのこと。石段を下る。石鳥居を潜り振り返って。「築土八幡町」交差点を渡り「三年坂」に入る。神楽坂善国寺から少し下ったところから筑土八幡神社に下るのがこの「三年坂」である。通常「三年坂」は寺や墓地があるものだが、ここの坂にはない。 この坂で転ぶと3年以内に死ぬという伝説から名付けられているとのこと。この坂の別名は「本多横丁」。 通りに坂名の標柱はないが、「本多横丁」の説明板がこの先にあった。右手に寿司屋「江戸前 福寿」。「ヤマト運輸 神楽坂営業所」の角に標柱があった。「本多横丁」。石畳の路地を歩く。「三年坂」はこの坂。そしてこの日の最後の目的地の「寒泉精舎跡」に向かって「大久保通り」まで戻る。右手の壁に案内板があった。「東京都指定旧跡寒泉精舎跡(かんせんしょうしゃのあと)所在地 新宿区揚場町二・下宮比町三指定 大正八年十月岡田寒泉は江戸時代後期の儒学者で政治家。名は恕(はかる)、字は子強、通称清助といい、寒泉と号した。元文五年(一七四〇)十一月四日江戸牛込に千二百石の旗本の子として生まれた。寛政元年(一七八九)松平定信 に抜擢されて幕府儒官となり昌平黌(後の昌平坂学問所)で経書を講じた。柴野栗山(彦輔)・尾藤ニ洲(良佐)とともに、「寛政の三博士」と呼ばれ、寛政の改革で学政や教育の改革に当たった三人の朱子学者のひとりである(寒泉が常陸の代官に転じた後は古賀精里が登用された)。寛政六年(一七九四)から文化五年(一八〇八)までの十四年間は、代官職として現在の茨城県内の七郡八十二村五万石余の地を治め、民政家としての功績は極めて大きなものがあった。寛政二年(一七九〇)八月十九日この地に幕府から三二八坪余の土地を与えられ、寒泉精舎と名付けた家塾を開いた。官職を辞した後も子弟のために授読講義を行い、「朝ごとに句読を授け、会日を定めて講筵を開き給えりしに、門人賓客にみちみちて、塾中いること能わざるになべり」とあって、活況を呈している様子を門弟間宮士信が『寒泉先生行状』に記している。文化十二年(一八一五)病気のため寒泉精舎を閉鎖し土地を返上した。文化十三年(一八一六)八月九日七十七歳で死去し、大塚先儒墓所(国指定史跡)に儒制により葬られた。著書に『幼学指要』『三礼図考』『寒泉精舎遺稿』などがある。 平成十三年三月三十一日 設置 東京都教育委員会」。全ての予定の散策を終え、JR飯田橋駅に向かって進む。「飯田橋」交差点の標識。水道橋から新宿方面の外堀通りと九段下から江戸川橋方面の目白通りが交差し、さらに大久保通りの起点になっている「飯田橋」交差点。「飯田橋」交差点には巨大な歩道橋が。「飯田橋」交差点の四角形の歩道橋は、JR飯田橋駅の東口前にある。目白通り、外堀通り、大久保通りが交わる都内有数の大型交差点を渡る歩道橋で、見た目もインパクトが大!!。南北に目白通り(都道8号)、東西に外堀通り(都道405号)、そして北西から大久保通り(都道25号)が交わる5差路だが、目白通りに沿って交差点東側を流れる神田川を挟んでもう1本、南行き一方通行の都道が外堀通りに交わっていた。飯田橋交差点からすぐ東側に、もうひとつ交差点が近接している形だが、信号は両方の交差点で連動しており、変形的な7差路と見ることもできるのだ。Googleマップより。交差点にあった案内地図。現在地はここ。そして「飯田橋」交差点を渡り、JR飯田橋駅(東口)へ。先日は、ここ「JR飯田橋駅(東口)」をスタートして「目白通り」の東側を散策し「飯田橋ウォーキングガイド・東京の歴史と文化を巡る」👈リンクと題してブログアップしたのであった。この日の帰路も新宿駅まで戻り小田急線で帰宅の途へ。JR飯田橋駅のホーム前、線路沿いの看板には東京国立博物館で開かれている「大和絵」👈リンクの展覧会のポスターが。これも興味深いのであった。神楽坂の坂道、そして周囲に広がる町・街を散策した。その美しい町並みと魅力的な雰囲気に心を奪われたのであった。石畳の坂道が風情を漂わせ、歴史的な建物や伝統的な日本の家屋、料亭、飲み屋が街を彩っていた。神楽坂の飲食店やカフェも見逃せないのであった。美味しい和食や洋食、スイーツなど、さまざまな料理を楽しむことができるようであった。また、古民家を改装したおしゃれなカフェで、ゆったりとしたひとときを過ごすことができそうであった。街の中には大小の神社や寺院も点在しており、歴史と宗教の要素が共存していた。神楽坂の独自の文化と雰囲気は、訪れる人々に深い感銘を与えること間違いなし。坂道の上からは、都心の景色を一望できる絶好のスポットもあり、日中はもちろん、夜にライトアップされた神楽坂の景色も素晴らしいものであろうと感じたのであった。神楽坂👈リンクの魅力は、日本の伝統と現代の融合から生まれる、独自の魅力に満ちていたのだ。是非また訪れ、この地で酒を飲みたいと思う魅力ある場所であった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.11.08
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その16):
「赤城神社」の境内社の「赤城出世稲荷神社・八耳神社・葵神社」の朱の鳥居の前の石段を下ると、下り坂のカーブの場所にあったのが標柱「赤城坂赤城神社のそばにあるのでこの名がある。『新撰東京名所図絵』によれば、『・・・俊悪にして車通ずべからず・・・』とあり、かなりきつい坂だった当時の様子がしのばれる。」「赤城神社」のすぐ西側に、北と西に向かって下る2つの坂道があるが,北に向う急な坂とそれにつながる南に上る坂が「赤城坂」。西に向かって下る坂道の名は?この奥にあったのが「貴乃花道場」。Googleマップから。再び「赤城坂」。再び「赤城神社」の境内に戻り、「赤城出世稲荷神社・八耳神社・葵神社」の横を歩き「赤城神社」の本殿の裏に廻るとあったのが「井戸・赤城幼稚園祉碑」。新宿区赤城元町4。「赤城幼稚園祉碑」と。さらに路地を東に向かって進む。築地塀に沿って進む。そして新宿区赤城元町の住宅街に出る。左手にあったのが「相生坂」。「相生坂『続江戸砂子』によると「相生坂,小日向馬場のうえ五軒町の坂なり。二つ並びたるゆえの名也という」とある。また『新撰江戸誌』では鼓坂とみえ「二つありてつづみのごとし」とある。一方、『御府内備考』『東京府志料』では仮名の由来は、神田上水の対岸の小日向新坂(現文京区)と南北に相対するためであると記されている。」次に坂も「相生坂」。「相生坂上記と同じ内容が記載されていた。」更に進むとT字路の正面に標柱が現れた。「御殿坂(ごてんざか)」。「江戸時代、筑土八幡神社の西側は御殿山と呼ばれ、寛永の頃(1624~1644)三代将軍家光が鷹狩りの際に仮御殿を設けたという。坂名は御殿山に因む。」「御殿坂」を下り振り返る。「大久保通り」に出て左折して進む。「築土八幡前」交差点の手前を左折する。正面に見えて来たのが「築土八幡神社」。右側にあったのが、「田村虎蔵先生顕彰碑 入口」碑。石段を上って行った。7段ほど上ったところに一の鳥居。石柱(注連柱(しめばしら))に横木を渡しただけの簡素なもの。「納」の彫り込みがあり、右の柱は「奉」であろう。石段の途中、右手に案内板が。「築土八幡神社由来嵯峨天皇の御代(今から約千二百年前)に武蔵国豊嶋郡(こおり)牛込の里に大変熱心に八幡神を信仰する翁がいた。ある時、翁の夢の中に神霊が現われて、「われ、汝が信心に感じ跡をたれん。」と言われたので、翁は不思議に思って、 目をさますとすぐに身を清めて拝もうと井戸のそばへ行ったところ、かたわらの一本の松の樹の上に細長い旗のような美しい雲がたなびいて、雲の中から白鳩が現れて松の梢にとまった。翁はこのことを里人に語り神霊の現れたもうたことを知り、すぐに注連縄(しめなわ)をゆいまわして、その松を祀った。その後、伝教大師(でんきょうだいし)がこの地を訪れた時、この由を聞いて、神像を彫刻して祠に祀った。その時に筑紫の宇佐の宮土をもとめて礎としたので、筑土八幡神社と名づけた。さらにその後、文政年間(今から約五百年前)に江戸の開拓にあたった上杉朝興が社壇を修飾して、この地を産土(うぶすな)神とし、また江戸鎮護の神と仰いだ。現在、境内地は約2200平方メートルあり、昭和二十年の戦災で焼失した社殿も、昭和三十八年氏子の人々が浄財を集めて、 熊谷組によって再建され、筑土八幡町・津久戸町・東五軒町・新小川町・下宮比町・揚場町・神楽可視・ 神楽坂四丁目・神楽坂五丁目・白銀町・袋町・岩戸町の産土神として人々の尊崇を集めている。御祭神 応神天皇 神功皇后 仲哀天皇大祭 九月十五日宮比神社由来御祭神は宮比神(みやびのかみ)て大宮売命(おおみやのめのみこと)・天鈿女命(あめのうずめのみこと)ともいわれる。古くから下官比町一番地の旗本屋敷にあったものて、明治四十年に現在地に遷座した。現在の社殿は戦災て失したものを飯田橋自治会が昭和三十七年に再建したものである。」「築土八幡宮同明神社」江戸名所図会より をネットから。石段途中の二の鳥居・「石造鳥居」が前方に。扁額は台座のみ。左手にあったのが「田村虎蔵先生をたたえる碑」。この碑には、「金太郎」👈リンクの音譜付きの歌詞と、「田村先生(1873-1943)は鳥取県に生まれ東京音楽学校卒業後高師付属に奉職言文一致の唱歌を創始し多くの名曲を残され、また東京市視学として日本の音楽教育にも貢献されました。」の説明文が刻まれていた。♫まさかりかついで きんたろうくまにまたがり おうまのけいこハイ シィ ドウ ドウ ハイ ドウ ドウハイ シィ ドウ ドウ ハイ ドウ ドウあしがらやまの やまおくでけだものあつめて すもうのけいこハッケヨイヨイ ノコッタハッケヨイヨイ ノコッタ♫「神楽のさくら」と。平成22年(2010)に東京神楽坂ライオンズクラブが植樹したもの と。右側に「手水舎」。「区指定有形民俗文化財 庚申塔」。寛文四年(1664)に奉納された舟型(光背型)の庚申塔である。高さ186センチ、黒褐色安山岩。最上部に日月、中央部に雌雄の猿と桃の木を配する。右側の牡猿は立ち上がって実の付いた桃の枝を手折っているのに対し、左側の牝猿はうずくまり桃の実一枝を持つ。牡猿の左手首及び牝猿の顔面の破損は昭和20年の戦災によるといわれている。二猿に桃を配した構図は全国的にも極めて珍しく、貴重である と。「百度石」明治十五年(1882)に置かれたもので、信仰篤い人々が百度参りした時に使用したもの と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.07
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その15):
「早稲田通り」を飯田橋駅方向に進み左手に折れると「赤城神社」案内柱・標柱があった。正面に「赤城神社」の「一の鳥居」が見えた。朱の鳥居。朱の「一の鳥居」を潜る。扁額「赤城神社」。「赤城大明神」と。「赤城神社 お祀りしている神様「磐筒雄命(いわつつおのみこと)」合殿「赤城姫命(あかぎひめのみこと」.後伏見帝の正安二年九月、上野国赤城山なる赤城神社の分霊を今の早稲田鶴巻町の森中に小祠を勧請。其後百六十余年を経て寛正元年大田道灌持資が牛込毫へ遷座。其後大胡宮内小輔重行が神威を尊び今の地に、始めて「赤城大明神」と称えるようになった。かくて天和三年幕府は命じて江戸大社の列に加え、牛込の総鎮守となる。」「螢雪天神 本宮ご祭神 菅原道真公かって横寺町に鎖座し朝日天満宮と称され、江戸二十五社の一つに列しておりました。その後信徒なき為、明治九年三月當境内にご遷座。先の戦災により焼失したものを、平成十七年十月現在横寺町にある旺文社の御寄進により「螢雪天神」として復興した。「螢雪」とは中国の故事で、苦労して勉学に励む事を意味します。「学問の神様」として全国の受験生の皆さんを応援しています。」「赤城出世稲荷神社ご祭神 宇迦御霊命(うかのみたまのみこと)/保食命(うけもちのみこと)赤城神社が当地にお遷りする以前(弘治元年1555年)から牛込の鎖守とされ、奉祀してきた産土神です。出世開運、五穀豊穣、商工業繁栄のご神徳があり、サラーマンの出世祈願、神楽坂商店街の商売繁盛で人気があります。」「八耳神社ご祭神 上宮之厩戸豊聰八耳命(別称・・聖徳太子)一般に八耳大神として親しまれている。聡明な知恵を授かるご利益があり、なにか悩み事がある時は「八耳様・八耳様・八耳様」と三回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶと伝えられる。また耳の神様として広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、全国各地から参拝に訪れている。」「葵神社ご祭神 徳川初代将軍徳川家康公牛込西五軒町の天台宗宝蔵院に鎖座していましたが、明治元年神仏混合を廃止された際に常境内へ遷座。かっての祠は明治十八年に御造営したが戦火にて焼失。平成二十二年秋に再建された。」「手水舎」はシンプル。更に表参道を進むと、道が二手に分かれます。まずは真っ直ぐ進んで本殿・拝殿方面へ。。背の高い石燈籠(右)。背の高い石燈籠(左)。「御神木」は楠であっただろうか。モグラのマスコット「モグハル」くんが宮司、巫女さんに変身して。神楽坂にオフィスを構えるクリエーティブ会社「モルスハルス」(新宿区神楽坂6)が制作したモグラのマスコット「モグハル」くん。「モルスハルス」の小原州開(くにはる)社長は「モグラは土に生息していることから、その土地に根付く縁の下の力持ちという意味を持たせた。土地にしっかりと根付き続けてほしいという願いに加え、由緒ある赤城神社で祈とうしてもらうことで、招き猫やだるまのように、このかいわいの商売繁盛の象徴となってほしい。新型コロナウイルスの影響で経済が不安定な今だからこそ、モグハルを通して神楽坂を応援したい。取材先の企業や店に温かく迎えていただき、少しでも明るくなってくれれば」と期待を込める とネットから。本殿・拝殿の手前左には境内社「蛍雪天神」。扁額「螢雪天神」。「螢雪天神 本宮繰り返しになるが、ご祭神 菅原道真公古来より天神様として広く民衆に崇め奉られております。ご祭神は『学問の神様』菅原道真公を祀ります。この神社はかつて横寺町に鎮座し朝日天満宮と称されておりました。江戸二十五社の一つに列しておりましたが、その後信徒なき為、明治9年(1876)3月當境内にご遷座。その後、戦災により焼失したものを、平成17年(2005)10月現在横寺町にある旺文社の御寄進により『螢雪天神』として復興しました。社名額には社長赤尾文夫奉納の銘がある。『螢雪』とは中国の故事で、苦労して勉学に励む事を意味します。全国の受験生の皆さん、螢雪天神はそんな皆さんを応援しています。」赤城神社の「拝殿」。国立競技場の設計を手掛けた隈研吾氏が監修したおしゃれな拝殿・本堂等。伝承によれば、正安2年(1300年)、後伏見天皇の御代に、群馬県赤城山麓の大胡の豪族であった大胡彦太郎重治が牛込に移住した時、本国の鎮守であった赤城神社の御分霊をお祀りしたのが始まりと伝えられています。その後、牛込早稲田の田島村(今の早稲田鶴巻町 元赤城神社の所在地)に鎮座していたお社を寛正元年(1460年)に太田道潅が神威を尊んで、牛込台(今の牛込見付附近)に遷し、さらに弘治元年(1555年)に、大胡宮内少輔(牛込氏)が現在の場所に遷したといわれています。この牛込氏は、大胡氏の後裔にあたります。天和3年(1683年)、徳川幕府は江戸大社の列に加え牛込の総鎮守と崇め、「日枝神社」「神田明神」と共に、「江戸の三社」と称されました。この三社による祭礼の際における山車、練物等は江戸城の竹橋から内堀に入り半蔵門に出ることを許されていました。その後、明治6年に郷社に列することになります。しかし、街の発展に伴い電柱や電燈などの障害物ができたので、盛観を極めた山車行列は明治32年の大祭が最後となりました とネットから。赤城神社の狛犬(右)。狛犬(左)。まるでスフィンクスを思わせる狛犬。「赤城神社の狛犬江戸時代、加賀白山犬とよばれて流行りましたが残っている物はわずかです。型や表情はシンプルでスフィンクスに似ていますが胸を張り力がみなぎっています。高天原からかみさまのお供をして来たような表情で澄まして座っていますが前肢は力強く全体に緊張感がみなぎっています。」赤城神社のガラス張りの「拝殿」に近づいて。御祭神「磐筒雄命」 ( いわつつおのみこと ) 「磐筒雄命」は伊邪那岐命が火の神、迦具土神を御刀で倒されたときにお生まれになった 神様で、智、仁、勇のすぐれたお力をお持ちになり、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又 特に火防の神として高い御神徳を発揚せられます。「赤城姫命」(あかぎひめのみこと) 一説に「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、旧別当は 天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺(江戸名所図会には東覚寺と記載)で同寺の 本地仏は乗馬姿の地蔵尊でありました。 かつての神仏混淆の頃、赤城大明神の御神影であると称して当覚寺から氏子中へ頒布した ことがあるので、今なお折々氏子中の旧家に散見されるため、 当社の祭神である「磐筒雄命」(いわつつおのみこと)とはかかわりはないが、合殿と されています。「赤城神社」。「赤城神社」の様々な種類の絵馬が。「赤城神社」の御神紋 「左三つ巴」。こちらは「狛犬」。こちらも。「螢雪天神」の絵馬。「社務所」。様々な御札、御守りが。近づいて。境内を引き返して、「拝殿」左の奥にあった境内社への参道を進む。前方、上に見えたのがさきほど訪ねた境内社「蛍雪天神」の横からの姿。よって「蛍雪天神」の下も参道になっていたのであった。「赤城山と大百足」。「赤城山」に巻きつくが如くに。手前に「赤城山」その奥に「大百足」。「お百度まいり赤城山と大百足 作 島 久幸昔、赤城山の神様は「ムカデ」👈リンクとなり中褝寺湖の領有をめぐり、ニ荒山の「マムシ」となった神様と戦いをされました。これが奥日光の「戦場ヶ原」の由来となりました。この百足を撫でご祭神のお力を頂き、ご本社や末社をお詣りください今回、氏子会長の飯島光幸氏がコロナウィルス感染症鎮静を願って寄進されたものです。 令和ニ年五月吉日」「大百足」をズームして。左手には石仏・石碑が。「観音菩薩立像」。病気平癒、厄除け、開運などのご利益があると。ふっくらしたやわらかい雰囲気の観音様。やさしいお顔に癒されたのであった。「観音菩薩立像赤城神社の北に位置した宝蔵院 (今の西五軒町にあたり、現在は 廃寺となっている)より移された。 舟形光背には「慶長18年丑年5月16日(1613年)」と刻まれています。ふっくらとした顔立ちで全体におおらかな雰囲気のある菩薩像である。俳人巻阿の碑巻阿は江戸期の俳人であり、幕府の家士でもあった人物。「梅か香や水は東より行くちがひ」「遠眼鏡には家もありかんこ鳥」「名月や何くらからぬ一とつ家」「あるうちはあるにませて落葉哉」の四句が刻まれている。」江戸時代中期の俳人加藤巻阿の句碑であり、4句が刻まれているのだと。「神楽の白梅」。「神楽の白梅」碑。そしてその先にあった「赤城出世稲荷神社・八耳神社・葵神社」鳥居に近づいて。手前にあったのが「手洗石」。「昭和五十年四月神楽坂商栄会通り歩道拡幅工事完成を記念し、合わせて赤城神社の隆盛と商栄会通りが門前町として、より発展する事を祈念して鉄製朱塗り灯篭六十基を、当社境内より参道を経て商栄会通り迄建立されました。幸に地元諸氏の熱意により、予定の奉納金額も集り更に橘田篤氏の奔走に依り、ここに記念水盤を奉納し、協賛者全員の芳名を不朽に記します。昭和五十六年九月吉日。 神楽坂商栄会灯篭及手洗石建立発起人篠原文吉 橋爪省三 橘田篤小松咲夫 橘雅茂 山本善夫」「赤城出世稲荷神社ご祭神 宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)/保食命(うけもちのみこと)創記は詳らかではありませんが、赤城神社が当地にお遷るする以前(弘治元年1555年)から地主の神と尊ばれ鎮座。出世開運のご利益があるとして大名・公家の崇敬を受けておりました。また穀物・食物を司る神様として、五穀豊穣、衣食住、商工業繁栄のご神徳を備えておいでです。現在は神楽坂商店街などの商売繁盛と近隣サラリーマンの崇敬を集めております。戦前まで5月5日の例祭日にはお神楽が奉納されていました。八耳神社ご祭神 上宮之厩戸豊聰八耳命(うえのみやのうまやどのとよとやつみみのみこと) (別称・・聖徳太子)戦火で焼失した昔の「太子堂」です。この八耳様(やつみみさま)は「あらゆる事を聞き分ける天の耳」を持つ聖徳太子であり、聡明な知恵を授かることができます。なにか悩み事のある時は「八耳様・八耳様・八耳様」と三回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶと伝えられる。また耳の神様として広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、全国各地から参拝に訪れている。合殿に大国主大神、丹生大神、を祀ります。葵神社ご祭神 徳川初代将軍徳川家康公牛込西五軒町の天台宗宝蔵院に鎮座していたが、明治元年、神仏混合を廃止された際に當境内へ遷座。徳川家初代将軍として江戸時代の政治、文化の礎を築き、近代日本の発展に多大な貢献をされました。かつては江戸市民の家康公への振興の対象でしたが、現在は神楽坂の「東照宮」として親しまれ、学問と産業の祈願成就を願って、参拝する方に心の安らぎを与えてくれます。」狛狐(右)。狛狐(左)。3社の拝殿。中央に「赤城出世稲荷神社」、右に「八耳神社」、左に「葵神社」。それぞれ3社の扁額。左の「葵神社」の扁額は「東照宮」と。中央に「赤城出世稲荷神社」の賽銭箱。右に「八耳神社」の賽銭箱。左に「葵神社・東照宮」の賽銭箱。「賽銭箱」は各社個別に!!。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.06
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その14):
「神楽坂通り」を北西方向に進みすぐ先を左折。右手にあったのが「正蔵院」。新宿区神楽坂6丁目54。「天台宗 正蔵院」。「草刈薬師如来 閻魔大王尊 安置」と。入口左にあった石碑は?民家の如き「正蔵院」。正蔵院は賑やかな繁華街神楽坂通り商店街の北側のはずれから、一歩脇に入ったところにあった。以前は通寺町と言い、隣の横寺町に続いて当寺の西側の通りには各宗の寺が並んでいたと。当寺は長禄年間(1458年頃)僧圓觀の創立。もと豊島郡千代田村にあった後、田安門に移り慶長5年(1600)取払いとなり、元和2年(1616)僧圓海が今の地に再興。明治44年7月には同町にあった養善院を合併した。江戸名所図会によると、当寺は東叡山に属し、開山圓觀律師。長禄年間(1458年頃)太田左金吾道灌が当寺を創建。前は梅林坂(御城内)にあり、後年田安の地に移され元和2年今の地に替えさせられたと。戦災で堂宇全焼失、その後小宇を再建、現在に至っている。本尊は薬師浄瑠璃如来、1寸8分の小さな御本尊。通称「草刈薬師」と言い、その由来は略縁起にると、太田左金吾道灌が今の宮城の基である江戸城を築こうとして、千代田の野辺に茂る草を刈らせている時、一人の僧が現れ一体の薬師如来を道灌に授け、「この尊像は後醍醐天皇に味方し奥州白河に流された北条高時が日夜護念していた伝教大師真作の薬師如来である。このご利益は国家の安泰のみならず庶民の現世災厄を除き未来得脱の果報が得られる有難き尊像である。今国家の乱れを鎮めようとして城を築こうとしているあなたに授けよう」と言ったと。そして尊像を授けられた道灌が城内の平川梅林坂に正蔵院を建て、圓觀上人を別当に補したと。又、脇本尊は合併した養善院の本尊であった閻魔大王尊。以前のお閻魔さまは坐像7尺、鎌倉期の大仏師運慶の作と伝えられていましたが、戦災で焼失。その後府中の在家の方が持仏としてお守りしていたお閻魔さまとお不動さまを寄進していただき安置。昨今のお寺巡りブームにより都内のお閻魔さま巡りも盛んになっているが、「草刈薬師」が何時の間にか「草刈閻魔」となって一部で知られるようになっていると ネットから。路沿いの境内にあった「稲荷祠」。祠内にはお狐様が2体。しかし、境内にはそれ以外の石碑や石仏等はなかった。更に進むと左手にあったのが「龍門禅寺」の表示。「曹洞宗桃嶽山 龍門禅寺」と。新宿区横寺町33。山門前から本堂を見る。右側に幟「南無身がわり地蔵尊」が並んでいた。「新宿区 横寺町 三三 竜門寺」と。「身がわり地蔵尊」。山門近くに祀られていて、千羽鶴が奉納されていた。祈りのときに唱える言葉は「オン・カー・カー・カ ビサンマーエイ・ソワカ」と。地蔵菩薩さまの真言(マントラ・お地蔵さんをたたえる短いお経)で7回繰り返すのだと。オン=お願いします。カーカーカ=お地蔵さまの笑い声ビサンマーエイ=ほめたたえることソワカ=そのようになる、成就すること。 という意味があるのだと。つまり、「地蔵菩薩様、地蔵菩薩様、地蔵菩薩様、あなたにすべてを投げ出して従い、讃え、願いを成就させます」という意味である と。ここにも奉納された幟が。ここにも小さな稲荷神社が。そして「本堂」。曹洞宗寺院の龍門寺は、桃嶽山菩提園と号す。龍門寺の創建年代等は不詳ながら、後に吉祥寺9世となった寰国龍鶯和尚(正保2年1645年寂)が創建、元和2年(1616)牛込門内田安から当地に移転したと。扁額「龍門禅寺」と。「竜門水子地蔵尊」。この場所にも何かあったのだろうか?そして「龍門寺」を後にして、さらに南西に進むと前方に標柱が。標柱「朝日坂」。『御府内備考』にはかつて泉蔵院という寺があり、その境内に朝日天満宮があったためこの名がついたとある。明治初年、このあたりは牛込朝日町と呼ばれていた(『東京府史料』)。正蔵院横から円福寺付近まで140mの緩やか(高低差6m,平均斜度2.5度)な登り坂。「朝日坂」の途中、右側の突き当りの路地に案内板が。「芸術倶楽部跡・島村抱月終焉の地」。「新宿区指定史跡芸術倶楽部跡・島村抱月終焉の地所在地 新宿区横寺町九・十・十一番地指定年月日 平成三年十二月六日この地は、評論家・劇作家・演出家・小説家など、多彩な活動を行った島村抱月(1871~1918)が、女優松井須磨子とともに、近代演劇や文学・音楽・芙術の普及.発表、交流のため大正2年(1913)7月に創設した芸術座の拠点「芸術倶楽部」の跡である.抱月は、幼名を瀧太郎といい、現在の島根県浜田市に生まれた。東京専門学校(現在の早稲田大学)に学び、卒業後は母校の講師となり、イギリスやドイツに留学、帰国後は創作活動に入った。明治39年(1906)には、坪内逍遙の文芸協会に参加し、西欧演劇移植に努めたが、大正2年(1913)内紛から同協会を脱会し、芸術座を結成した。その拠点芸術倶楽部は、木造二階建て、大正4年(1915)の建築であった。しかし、大正7年11月5日、スペイン風邪から肺炎を併発し、この倶楽部の一室で急死した。享年47歳であった。傷心の須磨子は翌年1月5日、この倶楽部の道具部屋で抱月のあとを追った。これにより芸術座は解散となった。 平成28年3月25日 新宿区教育委員会」島村抱月と松井須磨子。「芸術倶楽部(芸術座の専用封筒より)」。「朝日坂」を引き返し、新宿区横寺町32 TR神楽坂ビルの前の狭い路地へと左折して進む。左手にあったのが「鈴木家住宅主屋」。神楽坂地区の小路に北面する。木造平屋建、建築面積116㎡。切妻造妻入桟瓦葺で、正面に深い下屋を設ける。中廊下式で東から南にかけて居間や食堂、居室を配する。格子戸をたてるなど和風を基調としながら、煉瓦貼玄関や名栗仕上げの軸部などを散りばめる。そして「一水寮(いっすいりょう)」。一水寮は、1951年(昭和26年)、高橋博が開設した高橋建築事務所によって、現在地に大工寮として建られたものである。高橋は、山口県出身の建築家で、イギリスのロンドンで建築を学び、帰国後の昭和初期、神楽坂地区に高橋建築事務所を開設していた。一水寮は、数年後、隣家からのもらい火で、屋根、小屋裏を焼いたが、住込みの大工の手により復旧した。その後、数度にわたる改修工事が行われた後、大工寮から一般の貸出アパートへと使用目的が変更された。1990年(平成2年)、アパート経営をやめ、高橋博の娘婿である鈴木喜一の住宅兼建築設計事務所となり、1995年(平成7年)には、建築設計事務所のスタッフ、学生、芸術家、編集者などの住居となる。2016年(平成28年)には、耐震補強を含めた改修工事が行われ、現在は店舗・事務所として使用されている。なお、同じく高橋博の設計により1947年(昭和22年)に建築された鈴木家住宅主屋、及び、1954年(昭和29年)に建築された高橋建築事務所社屋も、登録有形文化財に登録されている。そして「日本調剤 神楽坂薬局」横の路地から「神楽坂通り・早稲田通り」に出る。「神楽坂通り」。神楽坂のAYUMI GALLERY前庭に「エルサレムの形のない図書館」と書かれたプレートが展示されていた。「エルサレムの形のない図書館」と書かれたプレートに近づいて。「工ルサレム形のない図書館Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.「もしあなたに庭と図書館があるなら、あなたは人生に必要なものを全て持っている」~キケロこの庭は、建第家であり旅人でもあった故鈴木喜ー氏かデサインしました。世界中を巡り歩き、場の瞬間を捉え共有することを追求した彼は、1 9 8 1年の復活祭の頃、エルサレムを訪れました。円屋根の連なる街の風景は、祝祭の雰囲気とあいまって彼に強い印象を与えました。数千年の歴史を持ち、世界で最も古い都市の一つであるエルサレムは、活気に満ち、想像カをかきたてると同時に、複雑な街でもあります。時間は独特な流れ方をしており、過去が未来に反響しています。街の石の一つ一つ、まにそれぞれの地層には、多くの物語や記憶が刻まれておりそれらはここで日々起こる特別な出会いの数々や色とりどりの情景に溶け込んでいます。このインスタレーションを図書館だと想像してみてください一それは場所の本質を捉えるえ試みです。知識を得るだけでなく、遠い地のさまざまな文化を体験する場所です。この類まれな街の、万華鏡のように変化する瞬間を垣間見る機会です。ここでは、時間と空間に固有の状況、瞬間、言語、伝統、音が、ギャラリーの庭の周囲や木の下に広がっています。QRコードをスキャンすると、都市の一部とその土地の空気(植物の匂いや、場所特有の音、語られる物語、儀式など)を体験することができます、エルサレムの地図が庭の大きさに縮図されており、それぞれのQRコードから実際の場所と瞬間にリンクされます。街の東側の瞬間は庭の東側にあり、西側の瞬間は庭の西側で見出すことができます。アユミギャラリーの庭は豊かな文化を内包する生きた円屋根に姿を変えています。ここでは、エルサレムに見られる典型的な円屋根(旧市街だけでも2048ヵ所もある)は、新たに解釈されています。頑強な円屋根ではなく、その特微的なシルエットを形作るポールで建てられた、架空の円屋根になっています。それぞれのポールは、街に刻まれた豊かな瞬間、色、状況、そして物語を表現しています。どうぞこ自由に歩き回り、木の下に座り、街の音で瞑想し、エルサレムの瞬間を集めてみてください。めぐりくる季節によって、様々なイベントが庭のインスタレーションのまわりで間催されます。ぜひご期待くだきい。2019年10月24日-2020年9月30日」文章を数回読み返したが、私には難解な内容なのであった。さらに「神楽坂通り・早稲田通り」を飯田橋駅方面に進む。「坂道、通り・路・道、横丁」 案内図をつくって見ました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.05
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その13):
次に訪ねたのが、「繁榮稲荷神社」の先にあった「法正寺」。新宿区岩戸町8。正面に本堂。榮松山念想院法正寺と号す。開山 雲蓮社昌譽上人助見和尚。寛永6年(1629年)7月23日示寂。創建年代は不詳ながらかつては清水門の外にあり、その後 田安屋形の近くに引っ越し、市谷本村(現防衛省)への移転を経て、元和元年(1615年)今の地に移転したといいいます。ここ本堂には本尊阿弥陀仏(立像)とその脇侍である観世音菩薩と大勢至菩薩の阿弥陀三尊を安置しています。寺号標石「浄土宗榮松山法正寺」。本堂に近づいて。本尊:阿弥陀如来。扁額「法正寺」。本堂の左側には墓地が。「まなざしの塔」有縁・無縁合同供養墓であるとネットから。墓地の入口左にあった「災害時協力井戸」。「法正寺遺跡」は、現在も岩戸町に所在する浄土宗法正寺の南側、江戸時代には同寺の境内であった範囲にあたる。1次調査では、甕棺を含む131基の埋葬施設と地下室、採土坑等が確認された。埋葬施設の多くは、法正寺がこの土地を手放す際に改葬されていたが、84号墓からは金蒔絵の漆箱が出土した。棺内に蓋石が落下していたため一部欠損するが、発見時には一面に描かれた鉄線唐草文が金色に輝いていた。中には鉄漿や白粉の道具、懐中鏡や琴爪、煙管そして一分判金が1枚納められていた とネットから。84号墓から発掘された金蒔絵の漆箱他様々な出土品の写真をネットから。そして「早稲田通り / 神楽坂通り」に出て、「寺内横丁」を目指す。ここが「寺内横丁」の入口。右側に「第一勧業信用組合 神楽坂支店」。「寺内横丁」を振り返る。左手に焼き鳥屋「酉玉 神楽坂」👈リンク。その先にあったのが「新宿区立寺内公園」。新宿区神楽坂5丁目7。「寺内公園の由来この寺内公園の一帯は、鎌倉時代の末から「行元寺」という寺が置かれていました。御本尊の「千手観音像」は、太田道灌、牛込氏はじめ多くの人々が信仰したと伝えられています。寺の門前には古くからの町屋「兵庫町」があり、3代将軍家光が鷹狩りに来られるたびに、 兵庫町の肴屋が肴を献上したことから肴町と呼ばれるようになりました。江戸中期の天明8年(1788)、境内の東側が武家の住まいとして 貸し出されるようになりました。この中に、貸地通行道(後の区道)という、人がやっとすれ違える細い路地がありました。安政4年(1857)頃、この一部が遊行の地となり神楽坂の花柳界が発祥したと伝えられています。明治4年(1871)には、行元寺と肴町を合わせて町名「牛込肴町」となりました。(昭和26年からは「神楽坂5丁目になっています。)行元寺は、明治40年(1907)の区画整理の際、品川区西五反田に移転し、大正元年(1912)に大久保通りができました。地元では、行元寺の跡地を「寺内」と呼び、味わい深い路地のある粋な花柳街として、毘沙門さまの縁日とともに多くの人々に親しまれ、山の手随一の繁華街として賑わっていました。文豪、夏目漱石の「硝子戸の中」大正4年作(1915)には、従兄の住む寺内でよく遊んでいた若き漱石の神楽坂での思い出話がでてきます。また、喜劇王・柳家金語楼と歌手・山下敬二郎の親子や、女優・花柳小菊、俳優・勝新太郎、芸者歌手・神楽坂はん子などが寺内に住んでいました。このように多くの芸能人や文士に愛された「寺内」でもありました。日本経済のバブル崩壊後、この一帯は地上げをうけましたが、その後の高層マンション建設に伴って、区道が付け替えられ、この公園ができることになりました。公園内には、地域の人たちのまちへの思いやアイデアが多く盛り込まれています。いつまでも忘れることのない歴史と由緒あるこの地の思い出をこの「寺内公園」に託し、末永く皆様の思い出の場、憩いの場として大切に護り育てましよう。 平成十五年三月吉日 新宿区」公園内の緑地には雑草が!?!?・??。そして「大久保通り」に出る。「牛込消防署」まで160mと。そして「大久保通り」の「神楽坂上」交差点を渡り、「牛込警察署 神楽坂上交番」方向に進むと手前にあったのが「安養寺」。「江戸三十三観音十六番札所厄除・疫病 大仏薬師如来開運・繁昌 大聖歓喜天」 と。「神楽坂上」交差点にある天台宗のお寺で、本尊薬師如来と大聖歓喜天王を安置する。「大聖歡喜天王 安養寺」と。「本尊薬師如来 天台宗」と。「聖天堂」。浄土宗寺院の安養寺は、清光山林泉院と号す。安養寺は、心蓮社深譽上人安阿貞公和尚が開山となり天正2年(1574)に創建、明暦2年(1656)市ヶ谷富士見から当地へ移転したと。通称:神楽坂聖天・江戸観音16番。「洗心寶生水」。銭洗いの水場。「洗心寶生水」と。安養寺の宝生弁財天は、銭洗い弁天。お堂の右手前にある「洗心宝生水」でお金を洗います。境内の「寶生觀世音像」。「子育地蔵尊」と「出世地蔵尊」。近づいて。境内には「洗心宝生水」、「宝生弁財天」、「宝生観世音」、「出世地蔵尊」、「子育地蔵尊」が安置されていたのであった。「洗心宝生水水は生命の源であり潤おいの徳は私共に施しの心を教えています。水天さまご真言 オンバロダヤソワカ」。「宝生弁財天(銭洗い)金融圓満芸能上達ご真言 オンソラソバテイエイソワカ」「宝生観世音私共のいろいろのお願いをおきヽ下さいますご真言 オンマカキャロニキャソワカ」「出世地蔵尊平成二年地中より出現された江戸期のお願いをもとにおまつりしました。出世開運の徳をお与え下さいます」「子育て地蔵尊除病延命学業増進等お子たちをお守り下さいますご真言 オンカーカーカービサマエイソワカ」「聖天堂」に近づいて。伝教大師最澄上人の高弟、天正十九年( 1591年)に徳川家康が江戸城築城の際、慈覚大師円仁(えんにん)和尚が開基といわれています。城内平河口より田安へ換地し天和三年( 1683年)に現在の神楽坂の地に移されました と。扁額「歡喜天」。この御堂に歡喜天=聖天がお祀りされているのだ。歡喜天(かんぎてん)とは、仏教の守護神である天部の一つで、頭は象、身体は人間の姿をした神様。インド神話の魔王が仏教にとり入れられたもので、ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)がルーツとされている。歡喜天は、仏法(ぶっぽう)を擁護し、衆生に利益を施して諸事の願いを成就させる善神として信仰されている。特に、密教において歡喜天信仰がさかんに重視されるようになり、造像もさかんとなった。歡喜天は、ヒマラヤ山脈のカイラス山(鶏羅山)で9千8百の諸眷属を率いて三千世界と仏法僧の三宝を守護するとされている とネットから。「聖天と身をあらわして福聚海 無量の誓いたのもしきかな(當山ご詠歌)十一面観音さまが聖天さまとなられて私共の願いをおきヽ入れの上、お救い下さることを詠ってあります。」「お願いやお悩みのある方はお気がねなく寺務所へお申出下さい。住職が心をこめてお祈りします。」本堂内陣。ズームして。最奥には聖天厨子がある。あの中に大黒様?が入っていた。「第十六番札所本尊 十一面観世音大聖歓喜天(聖天さま)三寳荒神愛染明王毘沙門天・大黒天」と。「大仏薬師如来ご奉安當寺本尊薬師如来は徳川家由来の霊仏で、太平洋戦争の空襲にあわれながらも、そのご生命である御顔薬壷・手首は無傷のまま殘られました。これをもとに復原申しあげ人々の難病をはじめ心身の病いを癒し、やすらぎの生活にと、お導き下さっています。ご真言 おん ころころ せんだりまとうぎそわかご祈祷のお申込は寺務所へおいで下さい。」内陣の扁額は山号「醫光山」。「醫光山」の山号は、本尊薬師如来に由来するとのこと。「本尊薬師瑠璃光如来 丈六尺像 総金箔 金銅仏」ズームして。低い位置から。「本尊薬師瑠璃光如来 丈六㘴像 総金箔 金銅仏三百有余年の歴史を有す霊仏で病気平癒・厄難消除の霊験あり毎月八日午後二時薬師供祈祷御祈祷のお申込みは寺務所へどうぞ。ご真言 おん・ころころ・せんだりまとうぎ・そわかとお唱え下さい。 醫光山 安養寺」そして「安養寺」を後にして、「牛込警察署 神楽坂上交番」手前の路地を入って行った。左手にあったこの階段が「駒坂」と。これもいわば「袖摺坂」といっていいサイズ感。道幅2mほどのタイル貼りの階段にクラシックな手すり。一応これでも新宿区の「区道」なのである と。石段の先の「駒坂」。ここまでとし、石段を下って引き返す。さらに北に進むとY字路に出会う。左手に進む坂が「瓢箪坂(ひょうたんざか)」。白銀公園の南端から南東に向かう狭い40mの、こちらからは登坂の道。「瓢箪坂坂の途中がくびれているため、その形から瓢箪坂と呼ばれるようになったのであろう。」前方の緑が「新宿区立白銀公園」。左折して早稲田通り方向に進むと「神楽坂マップ」があった。「早稲田通り・神楽坂通り」に合流し左折すると左手にあったのが「コボちゃん像」。4コマ漫画「コボちゃん」のブロンズ像。「コボちゃん」は、漫画家・植田まさしさんが描く、刈り上げ頭がトレードマークの少年・コボちゃんを主人公とする4コマ漫画。1982年(昭和57年)から30年以上にわたり連載され、1万4000回近くを数えるほか、1990年代にはアニメ化されるなど、長く幅広く愛されている。作者の植田さんは、神楽坂地域に35年以上居住しており、「コボちゃん」も連載初回の原稿が神楽坂で書き上げられた「神楽坂生まれ」。これらの縁から、東京メトロ・神楽坂駅出口に設置された商店街の案内板にコボちゃん一家が登場するなど、これまでも「地元」商店街のキャラクターとして活躍してきた。設置されている「コボちゃん像」は、台座約20センチ、像本体が約80センチのブロンズ像1基。神楽坂商店街振興組合が東京都や区の補助を受け、彫刻家・山田朝彦さんが制作したのだと。4コマ漫画「コボちゃん」。「神楽坂マップ」を再び。現在地はここ。「坂道、通り・路・道、横丁」 案内図をつくって見ました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.04
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その12):
「大信寺」を後にして「弁天坂」を進み突き当りを右折した場所右手にあったのが「正定院(しょうじょういん)」。「浄土宗 正定院」。新宿区横寺町40。浄土宗寺院の「正定院」は、不退山宝国寺と号す。正定院宝国寺は、然蓮社廓譽上人不退阿實和尚(ぜんれん しゃかくよじょうにん ふたい あじつおしょう)(寛永5年1628年寂)が開山となり、慶長7年(1602)麹町に創建、江戸城拡張に伴い当地へ移転したとのこと。参道を進む。お墓を継ぐ方がいなくても、お寺で、23回忌までお墓を維持・管理・供養を行う『永代供養制度』があるという寺。本堂はコンクリート製なので、歴史的な古さは感じられなかったが、本堂建物の上部に、二つの紋様が付けられていて、面白いデザインの寺。寺紋であっただろうか?本堂正面。本尊:阿弥陀如来立像。斜めから。特に石仏等はなかった。道路の向かいにあったのが「圓福寺」。新宿区横寺町15。「圓福寺」の山門の右側。文禄5年(1596年)9月3日、加藤清正公により創建された日蓮宗の寺。江戸時代には徳川家の祈願寺となり、大奥女中の信者が多くいた と。題目塔「南無妙法蓮華経」。日蓮宗では、法華経に帰依する意味で「南無妙法蓮華経」という題目を唱えると、その功徳によって成仏するといわれている。この題目を紙にして本尊としたり、石塔に刻んで寺や村々の辻などに立てていたと。右側面に「寛政十戊午歳(一七九八)十月日」と刻まれていた。山門の左側。「江戸三祖師 厄除開運祖師」「江戸三祖師 厄除開運祖師」は、日蓮聖人が49歳の時に自ら開眼した祖師像です。龍ノ口法難という迫害を奇跡的に免れたことから「厄除け開運祖師」と呼ばれ、堀ノ内妙法寺、赤坂圓通寺とともに「江戸三祖師」と言われているとのこと。「江戸城奉安 夜光鬼子母神」もともとは、江戸城紅葉山に祀られていたが、明治維新に際し、江戸城で徳川家および大奥の怨念、魔などを鎮めるために祀られていた夜光鬼子母神・七面大明神・妙見大菩薩が圓福寺に奉安されたとのこと。夜光鬼子母神は、真夜中に両眼が光り、暗いところで拝むことができる。鬼子母神は、子授け・安産・子育てなど子供の守護神として広く信仰されていた と。「文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩 六十日之問於牛込圓福寺境内開悵之砌諸講中朝詣之図」「文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩六十日之問於牛込圓福寺境内開悵之砌諸講中朝詣之図文久元年(一八六一年)三月、福寺において駿河国岩本實相寺の安国祖師像を六十日間開帳したときの賑わいを描いた版画です。このときの願主には牛込通寺町、牛込肴町など圓福寺近辺のニ十三町の講中が連名して参加していますが、日本橋、馬喰町、赤坂、東神田、麭町、品川、千住、内藤新宿などの幟や提灯もみられ、江戸と周辺の信者が多数参集している様子がみられます。信者の中には当時の歌舞伎役者の名もみられ、圓福寺が江戸の人々に熱心に信仰されていたことと、特にこの開悵がたいへんな評判であったことがうかがわれます。境内にはゆかりのある清正公の山車も入り、数々の出し物も演じられ、江戸庶民の信仰の熱意が伝わってきます。」文久元年(1861年)3月、駿河国岩本安国日蓮大菩薩が牛込圓福寺境内で60日間開帳された。この図は、開帳の際に諸講中が朝詣でをしている様子を表しているとのこと。「妙徳山圓福寺由緒当山は文禄五年(1596年)九月三日加藤清正 公により創建され、『妙法蓮華経』の功徳により福徳円満の御利益を授かるという意味が、山号、寺号の由来です。江戸時代の初期より祀られている祖師像は日蓮聖人 が四十九歳の時に彫られた御像で、聖人自ら開眼(魂入れ)なされ、その直後に龍ノ口法難(1271年)を免れたことから、生御影(生きるお姿)厄除開運の祖師と称され、古来より多くの参詣者を集めてきました。また、江戸時代末期に徳川家の祈願寺となり、大奥女中の熱心な信者も多く、明治維新には、江戸城紅葉山より夜光鬼子母神、七面大明神、妙見大菩薩が当山に奉安されました。」正面の「本堂」に向かって進む。左手に「妙徳稲荷大明神」。本堂に近づいて。本堂扁額は「廣布殿」。「廣布」の意味は『法華経の教えを広く宣(の)べて流布すること』と。御堂の手前には、「日蓮上人像」。「日蓮聖人像日蓮大聖人は、世の中の真の平和 人々の真の幸福とは何かと問い続け、法華経お題目によってそれが実現するとの確信に至り憂国の気持ちで立正安国論を鎌倉幕府に建白しました。その頃の気魂溢れるお姿を想い建立した御像です。平成十年十一月吉日妙徳山 ニ十五世 日達 記」「南無日蓮大菩薩」碑。「浄行堂」。手前に水桶と柄杓が置かれていた。扁額「浄行堂」。「浄行菩薩像」。「浄行菩薩法華経四菩薩の一人で率先して世の人々を哀れみ苦を除き楽を与える菩薩。病む人は正しく信仰し患部を洗い清めると平癒するという。別名洗い仏」。「南無妙法蓮華経 十方四生六道法界萬霊・・・」と刻まれた石碑。十方四生六道法界萬霊(じっぽうしせいろくどうほうかいばんれい)とは、迷いの中に生まれるすべての精霊を合祀して供養するために建てられた塔であると。法界とは、真理の世界、全宇宙のことで、万霊とはこの世の中の、一切の生きもののこととされているのだ。左に「宝篋印塔」。石碑、石塔が並ぶ。寺務所。「過去の罪、心からお詫びする。過去の行いにより今があり、今の行いにより未来が決まる。懺悔守りとは、心から懺悔(さんげ)することで過去の罪を消し、①健康運②仕事運③良縁、3つの運気に三化(さんげ)させ、朝日が昇るごとく、上向きに変化することを祈る御守りです。」私には、いまさら遅い「さんげまもり」!!「懺悔(サンゲ)守りの意味(サンゲが三化に、健康・仕事・人の緑が良い方向へ変化する)お釈迦様は、過去世の行いが原因となって、この世に結果として現われ、この世の行いが原因となり、来世結果として現われると言われています。私たちは大なり小なり罪を作ってきているのです。過去の罪があれば結果として悪い、不運なことが起きてくるという考えです。過去の罪はサンゲ(お詫び)によって消す事ができると信じて、自分の遠い過去世より今迄の罪、自分に係わる先祖の罪を心からサンゲすること、そして布施の気持(世の中が少しでも良くなるように見返りを求めずに奉仕すること)で努力することが大切です。・・・以下略・・・」日蓮宗の宗紋「井桁に橘」。「圓福寺」👈リンク の「当山 年中行事」。そして次に訪ねたのが「古今亭志ん朝旧宅」。Google mapに載っていたので来てみたが、説明板などは何も見当たらなかった。「古今亭志ん朝」は昭和から平成にかけて、名人の名をほしいままにした落語家だが、神楽坂の矢来町に住んでいたところから「矢来町の師匠」とも呼ばれていたと。東京都新宿区矢来町。在りし日の「古今亭志ん朝」👈リンク。今はどなたがお住まいなのか?次に訪ねたのが「尾崎紅葉旧居跡」。新宿区横寺町47。細い路地を進んで行った。尾崎紅葉がこの地に住んだのは、明治24年2月、二十五歳のときから。紅葉が当時盛んになってきた言文一致の文章を用いだしたのが、『二人女房』(同年8月―)からであるから、紅葉なりの新しい文体は牛込移住と並行してはじまったといえます。その後『心の闇』(明治26年)、『青葡萄』(同28年)などの代表作を生み、同29年2月からは、言文一致の労作『多情多恨』を執筆。翌年1月に書きはじめた『金色夜叉』の完結をみず、同36年10月30日この地に没した。紅葉の家は鳥居家となっているが、紅葉がふすまの下張りにした俳句が二枚残っています。それは「初冬やひげそりたてのをとこぶり十千万はしたもののいはひ過ぎたる雑煮かな十千万堂紅葉」というもの。十千万堂とは、緑山・半可通人などとともに紅葉が用いた号です とネットから。「新宿区指定史跡尾崎紅葉旧居跡所在地:新宿区横寺町四十七番地指定年月日:昭和六十年三月一日この地は、小説家の尾崎紅葉(一八六七~一九〇三)が、明治二十四年(一八九一)から明治三十六年(一九〇三)十月三十日に亡くなるまで十二年間暮らし、代表作「金色夜叉」など多くの作品を執筆した場所である。紅葉は、本名を徳太郎といい、江戸の芝中門前町(現在の港区浜松町)に生まれた。東京府第二中学 や三田英学校 で学び、明治十六年(一八八三)、大学予備門に入学、同十八年には山田美妙 らと硯友社 を結成、回覧雑誌『我楽多文庫』を発刊した。同二十一年には帝国大学法科大学(現在の東京大学)政治科に入学、翌年には文科大学国文科に移るが同二十三年に退学した。在学中から読売新聞社 に入社し、「伽羅枕」「三人妻」などを連載して人気作家となり、やがて明治文壇の重鎮として幸田露伴 とともに紅露時代をきずいた。紅葉は鳥居家の母屋を借りて居住したが、自らの号でもある「十千萬堂(とちまどう)」と称した。二階の八畳と六畳を書斎と応接間にし、一階には泉鏡花ら弟子が起居したこともあった。当時の家屋は戦災により焼失したが、鳥居家には今も紅葉が襖の下張りにした俳句の遺筆が保存されている。 平成二十八年三月二十五日 新宿区教育委員会」「尾崎一葉」。そして再び「袖摺坂」まで引き返し坂を振り返る。大久保通りを飯田橋駅方面に引き返し、次に訪ねたのが旧な坂を登る途中にあったのが「繁榮稲荷神社」。新宿区岩戸町14。朱の鳥居が社殿前に並ぶ。扁額「繁榮稲荷神社」。内陣。横から。「繁榮稲荷神社創立 明治二十三年十月二十五日所立 東京都新宿区岩戸町十四番地。崇敬 創立と同時に無格社に列格宍戸ま津の崇敬殊に厚く併せて明治ニ十三年十月ニ十五日当時 東京深川六間堀所立の分霊を勧請し奉斉す。昭和ニ十五年五月ニ十五日 戦災により社殿焼失し、仮社殿に奉斉す。昭和ニ十八年十ニ月三日 宗教法人として認知さる。昭和三十四年六月七日 官弊大社伏見稲荷大社の御分霊を更に勧請し仮社殿が 東京都新宿区岩戸町八番地に設立さるに際し仮還宮す。昭和四十一年三月ニ十四日 東京都新宿区岩戸町八番地に岩戸町々会設立の新築社殿に 奉斉す 以上 新宿区岩戸町々会 この年譜は、令和元年五月一日に新たに書き掲示す」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.03
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その11):
再び「地蔵坂」を引き返し、右に曲がり都営大江戸線「牛込神楽坂駅」方向に向かう。左、そして右に大きくカーブした坂道を下る。都道433号線・大久保通りに出て左折し進むと左側にあったのが「南蔵院」。新宿区箪笥町(たんすまち(たんすちょう))。たんすの町と書くのだから、文字通り、昔からたんすを作っている家具職人が多く住んでいた?と思いがちだが、実はそうではないのだと。東京都公文書館ホームページによると、箪笥町の「箪笥」は、”家具”ではなく、実は”武器”に関係するものなのだと。江戸時代、箪笥町のあたりには、幕府の武器をつかさどる具足奉行・弓矢鑓奉行組同心の拝領屋敷があった。幕府の武器を総称して、「箪笥」と呼んだことから、正徳3年(1713)年、町奉行支配となった際、町が起立し、牛込御箪笥町となった。その後、「御」と「牛込」がとれて、現在の箪笥町という名前になったのだと。たんすが武具のことだとは、びっくり。山門には「弘法大師 天谷山南蔵院」、「御府内八十八箇所之内 阿波國平等寺👈リンク模廿二番」と刻まれた石碑。『天谷山 (山号)南蔵院(院号) 竜福寺(寺号)』と号する真言宗豊山派の寺御府内八十八箇所(ごふないはちじゅうはちかしょ)は、東京都内にある弘法大師ゆかりの寺院で構成された八十八箇所の霊場。宝暦5年(1755年)頃に開創したと伝えられる。25番札所(長楽寺、日野市)および77番(仏乗院、神奈川県秦野市)以外すべて東京都23区内にある。25番および77番札所も元々23区内にあったが移転して現在地となっている。御府内八十八ヶ所 寺院マップ をネットから。「大聖歡喜天」石標。歓喜天は、仏教の守護神である天部の一つで、ヒンドゥー教のガネーシャに相当する尊格。頭は象、身体は人間の姿をしており、現世に福徳を授けるとされているがのちに仏教にとり入れられた。弘法大師空海が唐から日本に持ち帰った神様でもあるのだ。入口の壁には「神楽坂霊園」と。「南蔵院」内にある霊園で、宗旨宗派は不問で、神道、キリスト教、他宗教など宗教自由な霊園とのこと。「本堂」。真言宗豊山派寺院の南蔵院は、天谷山竜福寺と号す。南蔵院は、牛込城主の牛込勝重が正胤法印に請い、吉祥山福正院と称して、早稲田に創建、弁財天二体を上宮・下宮として祀っていたと。御用地となったため、延宝9年(1681)上宮と共に当地へ移転、天谷山竜福寺南蔵院と改号した。もう一体の下宮は弁天町の宗参寺に祀られ、弁天町の起源となったという。御府内八十八ヶ所霊場22番。創建:元和元年(1615年)。御本尊:千手観世音菩薩。扁額「南蔵院」。境内の石仏。比較的新しい地蔵さま。「南蔵院 案内」。内容は上記に同じ。本堂右には「歓喜天堂」。歓喜天の梵名(ぼんめい)はナンデイケーシユヴァラといい、仏教の守護神。狛犬(阿形)。狛犬(吽形)。扁額「歡喜天」。「南蔵院」の「本堂」、「歓喜天堂」を見る。ここが「神楽坂霊園」であっただろうか。アルファベットの墓標もあった。「南蔵院」を後にして都道433号を西に進む。横断歩道を渡った場所近くにあった案内板。「弁天坂 昭和五十九年三月 東京都」と。「坂名は、坂下の南蔵院境内に弁天堂があったことに由来する。明治後期の「新撰東京名所図会」には、南蔵院門前にあまざけやおでんを売る屋台が立ち,人通りも多い様子が描かれている。坂上近くの横寺町47番地には、尾崎紅葉が、明治二十四年から三十六年十月病没するまで住んでいた。門弟 泉鏡花、小栗風葉らが玄関番として住み、のちに弟子たちは 庭続きの箪笥町に家を借り、これを詩星堂または 紅葉塾と称した。」案内板の設置位置が大久保通り沿いにあり緩やかな坂になっているので、大久保通りのここを「弁天坂」と勘違いしそうになったのは私だけであろうか?「新撰東京名所図会」よりネットから。都道443号・大久保通りに平行に走る「弁天坂」を上る。地下鉄牛込神楽坂駅の上、南蔵院という寺の前から 大久保通りから分岐して、大久保通りと平行した後に、直角に曲がって北西に上る。途中で袖摺坂の階段が分岐している。坂上は 朝日坂の坂上につながる。約110mの緩やかな坂であった。左手、狭い路地の先にあったのが「常念寺」。吉孝山常念寺。大久保通り沿いですが、北側の高台を併走する小道・弁天坂に面し、目立ちません。民家のごとくに。宗派:単立(浄土真宗東本願寺派)。廃寺なのだろうか?直角のカーブの場所にあったのが「袖摺坂(そですりざか)」案内柱。「俗に袖摺坂と呼ばれ、両脇が高台と垣根の狭い坂道で、すれ違う人がお互いの袖を摺合わしたという(『御府内備考』)。」地下鉄大江戸線の 牛込神楽坂駅 東出口近く。大久保通りの‘箪笥町’交差点付近の北に上る 20段ほどの石段!!これが「袖振坂」。下まで降りて。途中から。ここは新宿区箪笥町一番地。「弁天坂」をさらに上って行った。左手にあったのが「大信寺」。新宿区横寺町43。「浄土宗 大信寺」。「大信寺」は、金剛山如来院と号す。大信寺の創建年代等は不詳ながら、室町時代に真言宗寺院として麹町に創建したと伝えられます。その後浄土宗に宗旨を改めて大蓮社超誉上人常然和尚(舟町西迎寺八世)が開山、番町への移転を経て当地へ移転したと。本尊:阿弥陀如来像近づいて。寺紋「抱き花杏葉(だきはなぎょうよう)」。この紋抱き花杏葉紋は、2枚の蔕(へた)の上に、半円の蘂(しべ)を置き、段々に毬花をつけた杏葉を2つ並べて左右から抱くように描く。境内の石仏。飛鳥時代の金銅仏風な石仏。寺務所。近づいて。ここにも石仏が。その先T字路に面した場所にあったのが「長源寺」。新宿区横寺町20。「曹洞宗 長源寺」。参道を進む。「本堂」。曹洞宗寺院の長源寺は、妙徳山と号す。長源寺は、徳翁寺三世在天智和尚(永徳12年1569年寂)が開山となり永禄元年(1558)麹町に創建、元和2年(1616)当地へ移転したと。扁額「長源寺」。「永代供養墓」。「有縁塔 永代供養墓です。」と。「石田鉄次郎翁之碑」。「石田鉄次郎翁之碑翁は安政五年江戸牛込揚場に生まれ資性朗膽侠氣に富み鳶方として三大区二番組に入り業務上異例なる手腕を認められ宮内省御用達を仰付れ亦他面数多の難工事を仕上げ其間子分身内を養成し業界に偉大なる足跡を遺せしは誠に斯界の亀鑑となす昭和十年九月廿二日病歿す榮名以て長に傳ふるに足る我等身内有志は敬慕の餘り記念碑建設を企つ幸に彫塑界の巨匠小倉右一郎先生は翁を知るあり之を賛助丹精に成り茲に此碑を建つ昭和十六年四月 親敬會」」「石田鉄次郎翁」。境内の石仏。墓地。「永代供養墓」。寺務所。「坂道、通り・路・道、横丁」 案内図をつくって見ました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.02
コメント(0)
-

神楽坂の坂道&横丁ウォーク・坂道の向こうに広がる古き良き東京の風情 (その10):光照寺(2/2)
「光照寺」の墓地を巡る。「忠烈無窮」と刻まれた石碑であると篆書体(てんしょたい)の師匠から。「忠烈無窮」と。忠義の心で困難に永遠に打ち勝った と。「故陸軍歩兵特務曹長勲六等功六級佐々木雄之助君碑記」と。「新宿区登録文化財 史跡便々館湖鯉鮒(べんべんかんこりふ)の墓」「新宿区登録文化財 史跡便々館湖鯉鮒(べんべんかんこりふ)の墓」所在地 新宿区袋町十五番地登録年月日 平成2年3月2日登録江戸時代中期の狂歌師便々館湖鯉鮒は、本名を大久保平兵衛正武といい、寛延2年(1749)に生れた。幕臣で小笠原若狭守支配、禄高150俵、牛込山伏町に居住した。はじめ、牛込二十騎町に住む幕臣で狂歌師の朱楽菅江(あけらかんこう)に狂歌を学び、その後、唐衣橘州の門下に転じ、世に知られるようになった。大田南畝(なんぽ・蜀山人)とも親交があり、代表作「三度たく 米さえこわし やわらかし おもうままには ならぬ世の中」を、南畝が揮毫した文政2年(1819)建立の狂歌碑が西新宿の常圓寺にあり、新宿区指定文化財に指定されている。文化15年(1818)4月5日、享年70歳で没した。 平成3年3月30日 東京都新宿区教育委員会」墓石は、高さ152センチである。隣にも石碑が。廻り込んで。墓地の奥から「本堂」を見る。◯◯家の墓 と。歴史を感じさせる古い墓であったが。「無縁墳墓地等改装公告墓所整備のために、無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、本墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告日より一年以内にお申し出ください。なお、期日までにお申し出のない場合は無縁墓地として改葬することとなりますので、ご承知ください。詳細は寺務所窓口へお問い合わせください。本墓地番号: E57 ◯◯家之墓公告年月日 令和5年7月3日墓地管理者」今後もこのような墓地が増えていくのであろう。少子高齢化が加速する現代において、社会問題化しているのがこの無縁墓の問題。自分の親や先祖のお墓の管理をこのまま継続していけるのか、あるいは、自分の死後、お墓の購入や維持管理の負担で子どもや孫に迷惑をかけたくないなどの心配をしている人がますます増えて行くのであろう。墓地の奥にも張り紙が。「お知らせとお願い墓石が古く、先の東日本大震災により一部転倒し、大変不安定で危険になっております。関係者以外立ち入りを禁止します 当山住職」と。無縁墓地とは別にこのような問題も発生していることを知ったのであった。「奥田抱生墓」と。墓碑には奥田抱生の一生を概略を漢文で書いたものです。 奥田は文政8(1825)年10月10日生まれ、儒学者奥田大観の子であり、儒大観に学び、文教家で金石学研究家。魚貝や書画骨董を収集し、漢詩漢文を教え、上京して牛込に住み読書・旅行・古器物の研究し、考古学の先駆者。 著書には「今瓦譜いまがわらふ」、「日本金石年表」、「明清書画名家年表」など。昭和9(1934)年没、享年75歳。『奥田抱生墓先君諱普、字弐齋、氏奥田、抱生・紫燕・飯沙・三山行者等號、大観先生長子、幼承家學從曽祖鶯谷先生、世為尾張徳川氏奥御儒者、明治元年藩命撰十少年、就清人金嘉穂學、先君年甫十一亦入其撰、弱冠任内閣屬、既而辭之不復仕、下帷教授、明治四十三年入都ト居牛籠、著有日本金石年表・金石私記・主客説・詩堂集』森敦(あつし)が眠る「森家之墓」。森敦は作家で、明治45年生まれ。昭和49(1974)年、61歳で芥川賞を「月山」で受賞。平成元年没。享年76歳。右側にある碑文は「われ浮雲の如く 放浪すれどこころざし 常に望洋にあり 森敦」と。そして境内の東側にあった「出羽松山藩主酒井家墓所」を訪ねた。「この墓域は出羽の国松山(松嶺)藩主酒井家一族の墓所である。松山藩は徳川の譜代大名であり、庄内藩初代藩主酒井忠勝の三男忠恒が分家として正保四年(一六四七)ニ万石で創設された。明治の廃藩置県に至るまで八代を数える。このうち、三代藩主忠休が寛延ニ年(一七四九)よりニ十六年間幕府の若年寄の要職を務めた功により、安永八年(一七七九)上野国に五十石が加増され、築城も許された。光照寺には初代忠恒以下代々の藩主及び妻子の墓があるが、一族のうち江戸で死去したものは光照寺に、国元で死去したものは、酒田市松山心光寺に葬られた。現在同寺には国元の有志により三代の廟所が設けられている。八代以降数代は、カトリックに改宗したため、墓所は台東区谷中に移された。江戸期における大名墓は、一般に国元ではよく保存されているが、府内のものは次々に消失している。新宿区内では当寺のものを含む数箇所のみである。」墓地の全体図。数字は造営順。主なものは①初代忠恒(1639ー1675)⑭三代忠休(1714ー1787)④四代忠崇(1751ー1824)④五代忠禮(1780ー1821)⑩六代忠方(1808ー1887)㊷七代忠良( 1831ー1884)㊻忠方第六子忠量(1856ー1913)及び開係者合葬手前から①初代忠恒 ③二代忠豫 ②同夫人? ④?初代酒井 忠恒(さかい ただつね)は、出羽松山藩の初代藩主。左衛門尉酒井家分家初代。庄内藩初代藩主・酒井忠勝の三男。寛永16年(1639年)8月8日生まれ。正保4年(1647年)12月11日、本家の庄内藩から2万石を分与されて、支藩である松山藩を立藩した。駿府加番や江戸城二の丸の石垣普請、酒井氏の菩提寺である心光寺の創建に努めた。延宝3年(1675年)8月6日(または1674年)に死去し、跡を長男・忠予が継いだ と。手前から㊴、㉚、⑯、・・・。⑭、㉓、⑧であっただろうか??上記墓石の案内図。全ての番号と名前のリストが欲しい!!??????右から㊷七代忠良(1831-1884年)、㉑五代忠禮(1780-1821年) ㉖??の墓上記案内図をズームして。㉖をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.11.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1