2014年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
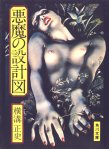
横溝正史『悪魔の設計図』
横溝正史『悪魔の設計図』~角川文庫、1976年~ 由利麟太郎&三津木俊助シリーズの3編の作品が収録されています。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。ーーー「悪魔の設計図」三津木俊助が休暇で訪れた信州で、旅芝居の芝居を見ているとき、その中で事件は起きた。役者の一人が、舞台の中で殺害されたのだった。座頭の珊瑚かと思いきや、それは全く別の役者だった。居合わせていた弁護士が、すぐに駆けつけるが…。 後日。東京に戻った俊助は、由利先生のもとで、あの弁護士と再会する。そこで聞かされたのは、珊瑚を含む3人の腹違いの姉妹が、遺産をめぐって、腹違いの男に狙われそうだという話だった。そして、さらに事件は展開し…。「石膏美人」三津木俊助を乗せた自動車とトラックがぶつかり、トラックの荷台から落ちた箱には、女の人形が入っていた。しかし、女の声が聞こえる気がし…。俊助を無視するトラックを追い、たどり着いた屋敷では、殺人が繰り広げられているように見えた。しかし、警察とともに入ったときには、現場と思われた部屋には何の形跡もなかった。その後、俊助の婚約者の家に遺体の入った箱が届けられ…。「獣人」女の生首が飾り窓に置かれていた…という衝撃的な事件が発生した。その頃、若かりし由利麟太郎は、甲冑をまとったゴリラのような姿を目にし、その生き物が向かった先の家を訪れた。しかし、家では、心当たりがないようで…。その後、その家をめぐってさらなる事件が起こる。ーーー 本書のなかでは、「石膏美人」が特に面白かったです。事件の背景の悲しさや、不遇な少年の思いなど、やりきれない思いにもなりました。本書の中では最も分量が多く、また、由利先生の初登場作品でもあるということで、気迫というか、勢いがあるように感じました。※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2014.01.25
コメント(0)
-
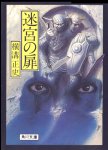
横溝正史『迷宮の扉』
横溝正史『迷宮の扉』~角川文庫、1979年~ 横溝さんによるジュヴナイルものの作品集です。表題作の他、2編の短編が収録されています。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。ーーー「迷宮の扉」燈台そばにたつ、通称竜神館を金田一耕助が訪れたとき、事件が起こった。15歳を迎える竜神館の主―日奈児を訪れた誕生日の使者が、何者かに殺害されたのだった。 日奈児の後見人と、日奈児と双子の月奈児の後見人―憎み合う夫婦たちが一堂に会したとき、双子の父親は衝撃的な遺言を残す。これが、さらなる惨劇への幕開けだった。 遺言書を管理することとなった金田一耕助のもとへ泥棒が入った夜、不可解な状況のなかでの殺人事件が起こる。「片耳の男」ほこらに近寄る少女にチンドン屋が襲いかかるのを目撃した宇佐見慎介は、あわてて少女を助けた。聞けば、少女と、研究にいそしんでいる兄には、一年に一度贈り物が届くという。チンドン屋はそれを狙っていると思われるのだが―。その後、贈り物の秘密を伝えるという手紙が少女に届き、慎介も手紙の指定する場所へ同行することとなる。「動かぬ時計」貧しい電話係の少女には、一年に一度、だれかから贈り物が届く。なかでも少女のお気に入りは、素敵な時計だった。ーーー 表題作は、ジュヴナイルものといっても、中学生向けに書かれたものということで、他のよくあるジュヴナイルもののような怪人が出てきません(あえていえば、青い髪の毛が不気味な雰囲気を醸し出していますが)。また、金田一耕助が登場する他のジュヴナイルでは、金田一さんがどちらかといえば脇役で、少年探偵が活躍するようなイメージもありますが、本作ではしっかり金田一さんが主役になっています。さらに、密室的な状況での事件があったりと、ジュヴナイルものという先入観を覆すような作品でした。 併録された2つの短編のなかでは、「動かぬ時計」が好みです。ミステリではありませんが、ラストの切ない感じなど、味わい深い物語です。※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。
2014.01.18
コメント(0)
-
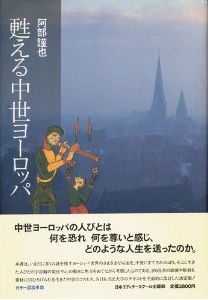
阿部謹也『甦える中世ヨーロッパ』
阿部謹也『甦える中世ヨーロッパ』~日本エディタースクール出版部、1987年~ 阿部謹也先生(1935-2006)が1986年にNHK市民大学「よみがえる中世ヨーロッパ」と題してテレビ放映した講座のテキストをもとにした一冊です。 もとが講座ということもあってか、ですます体ですし、読みやすい語り口となっています。 本書の構成は次のとおりです。ーーー序 ヨーロッパ中世史認識の二つの方法第1章 謎にみちた中世第2章 二つの宇宙第3章 中世建築の怪物たち第4章 中世都市の時間と空間第5章 死生観の転換第6章 富める者と貧しき者第7章 若き騎士の遍歴第8章 手仕事と学問第9章 子どもの発見第10章 二つの宇宙の狭間で第11章 中世の音の世界第12章 絵画にみる中世社会あとがきーーー 本書のなかで特に面白かったのは、序と第1章の問題意識です。森博嗣さんが、問題を解くことよりも問題をたてる方が難しいとしばしば指摘されていますが、あらためてそれを感じました。 たとえば、序では、このようにあります。「ヨーロッパ風の制度をとり入れてなりたっている会社や大学…などを現実に運営していく段になると、おもての顔ではうまく動きませんので、日本古来の伝統的な生活慣習、あるいは人間と人間とのつきあい方の原理がそこで働くことになるわけです。そこには血縁関係や、同族意識、同窓会あるいは派閥といったような、さまざまな関係があります。私たちの生活はいわば二つの層の上になりたっているのです」(3頁)。 背広やワンピースなど、ヨーロッパで生まれたもので囲まれて生活しながら、その背後にはきわめて日本人的な意識も残っている、ということですね。 一方、ヨーロッパも、当然ずっと今のようであったわけではありません。そこで、中世史を見るにあたって、(1)現在の制度が生まれるいきさつを見ていくこと、(2)現代とは異なる人間関係のあり方を見ていくこと、という手続きが必要になる、といいます。現代の日本のあり方とからめて、この問題意識をたてることが、とても面白かったです。 続く第1章では、大きく4つの問題をたてます。それは、怪物(教会の入り口などを彩る数多くの怪物たちの意味は?)、時間(意識)、空間(墓所、教会など、聖なる場所として公権力も介入することができない避難場所であるアジールはなぜ近代に消滅したのか?)、死生観(死を意識することは、生を意識することにもつながります)の4つです。 第2章は、これらの問題を解決するにあたってのキーワードである、「二つの宇宙」観を論じます。これは本書全体に通じるキーワードとなります。人間の理解の及ぶ範囲である小宇宙(ミクロコスモス。家、共同体…)と、人間の理解の及ばない大宇宙(森などの自然、天体…)の二つの観念があったと論じられます。ここで面白いのは、家のなかで使うかまどの火や、くんできた水と、山火事の火や大洪水の水は異なるものとして意識されていた、という指摘です。 第3章以下のメモは省略しますが、第1章までの問題関心と、第2章のキーワードでつらぬかれたその議論は、どれも非常に興味深いです。 ただ、少し気になったのは、ざっくり「中世では…」という議論がされている部分があること。中世といっても、西暦500年頃から1500年頃と1000年ほども続きますし、そのなかで変化もあります。一点、特に気になったのは、12世紀頃に都市共同体が成立し、時間意識が変化していくという議論のなかで、次のようにあります。「都市共同体の中で、機械時計が発明されているのです。商業は常に計算可能な仕事でなければなりませんから、必ず合理的な経営を営まなければならないのです。ちょうどその頃にキリスト教が入ってきますから、円環的な時間意識から直線的な時間意識へと時間意識の転換が始まってくるわけです」(106頁)。「ちょうどその頃にキリスト教が入って」きたわけではないですから、都市共同体のなかでの時間意識の変化には、また別の説明が求められると思います。 気になる点もありましたが、全体として知的興奮に満ちています。 10年ほど前に本書に出会ったときも、わくわくしながら読んだのを覚えています。アジールという概念や二つの宇宙など、当時非常に勉強になりました。ということで、個人的にも印象深い一冊です。
2014.01.11
コメント(0)
-
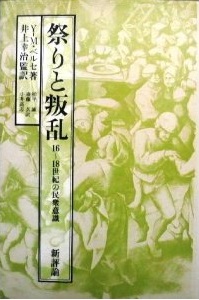
Y-M.ベルセ『祭りと叛乱―16~18世紀の民衆意識―』
Y-M.ベルセ(井上幸治監訳)『祭りと叛乱―16~18世紀の民衆意識―』(Yves-Marie Berce, Fete et revolte, Librairie Hachette, 1978)~新評論、1980年~ 学生時代から興味があったのですが、ようやくざっと通読しました。 著者のイヴ=マリ・ベルセ(1936-)は近代の農民反乱や民衆意識を専門とする歴史家です。ウィキペディア(http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves-Marie_Berc%C3%A9)によれば、リモージュ大学、ランス大学、パリ第4大学(ソルボンヌ)などの教授を歴任されているようです。 本書の構成は次のとおりです。ーーー日本語版への序文はじめに第一章 祭りの暴力第二章 反乱に変容する祭り第三章 市民の祝祭の終焉第四章 民衆宗教の迫害第五章 農業祭の終焉結論監訳者あとがきーーー 何ヶ月もかけて昼休みに少しずつ読んだこともあり、大した感想が書けません。なんとか目を通した程度です。 ですが、簡単にいくつかメモしておきます。・とにかく具体例が豊富。タラスコンという町で、行列の出し物として登場したといわれるタラスクという怪獣のエピソードなど、印象に残るエピソードが多いです。・行政などが祭りを禁止していこうという動きを見せますが、それでも民衆的な祭りというのは続いていくものだなぁ、という印象を受けました。・第一章では、若者たちによる振る舞い(暴力)に大きなウェイトが置かれています。新婚夫婦に、強制的に貢ぎ物を出させることなどが紹介されます(これも地域差があるそうです)。A村の女性とB村の男性が結婚すると、A村の若者にとってはそれだけ結婚の機会が失われるわけですし、A村の人口増加にも影響しますので、私的制裁が行われる―という背景もあります。・第二章では、女装した叛徒についての節が面白かったです。特に面白かったエピソードは、1840年代にウェールズ南部で起こった道路通行税反対の暴動のときの謎の首領、レベッカについてです(そこからレベッカ暴動と呼ばれたそうです)。「『レベッカに言いつけるよ』と脅せば、だだをこねる小娘も静かになるというほどかれは恐れられた」(139頁)というのですね。・第三章では、「竜と巨人の練り歩き」の節が面白かったです。上に書いたタラスクという怪獣も、この節で紹介されます。怪獣に限らず、巨人が祭りの行列に登場する町もあったそうで、このあたりのエピソードが興味深いです。 専門としている時代からかなり下った時代が対象となっていることもあり、あまり集中できなかったのが残念です(私のあり方がなってないだけですが…)。ただ、テーマや個々のエピソードはとても面白かったです。ーーーーあけましておめでとうございます。本年も細々と続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2014.01.04
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月15日分)
- (2025-11-29 01:10:07)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0943 キーエンス 最強の働き…
- (2025-11-29 00:00:12)
-







