2006年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

高田崇史『QED 神器封殺』
高田崇史『QED 神器封殺』~講談社ノベルス~ 『熊野の残照』事件の後、具合を悪くした神山禮子とともに、桑原崇と棚旗奈々は、和歌山での滞在を延長した。そこに、大規模な個人病院を設立した熱田光明殺害事件の取材にやってきた小松崎と、奈々の妹である沙織が合流した。光明は、首と右手を切断されていた。 光明は、和歌山で草薙剣を作らせようとしていたという。その関連もあり、三種の神器に関する崇の薀蓄が語られていく。 事件の取材に行く小松崎と沙織、神社参りに行く桑原と奈々と別れ、禮子は小さな古刹を訪れる。墓参りのために。そこで、幼馴染みである御名形史紋(みなかた・しもん)と偶然出会う。博識である史紋は、禮子から桑原の話を聞き、行動をともにすることになる。 その頃、また新しい事件が起こる。光明がつくった病院の事務局長が死亡した。容疑が濃厚である人物は自殺だと主張したが、毒殺との見方が有力だった。しかし、殺害方法がわからなかった。 二つの事件に加え、三種の神器にまつわる歴史について、桑原崇が解き明かしていく。 内容紹介の冒頭でも紹介したように、本書は前作『QED~ventus~熊野の残照』に続く物語です。 とにかく、面白かったです。えてしてQEDシリーズからは感銘を受けるのですが、今回もそうでした。私は日本史に詳しくないので、十分に理解できない部分もあったのですが(ある程度予備知識があったほうが面白く読めるでしょう)、自分が関心を持っている領域に言及があったのが嬉しかったです。 中世ヨーロッパには、三身分論という考え方がありました。その図式は一つだけではないのですが、定式化されたものとして有名なのは、祈る者-戦う者-働く者、という図式です。最近、この身分論もふまえた発表をしたので、少し復習をしたばかりで、その中でデュメジルの名前は聞いていたのですが、その説については知りませんでした。本書で簡単に知ることができ、デュメジルの論文もぜひ読んでおきたいと思いました。 ヨーロッパ関連で興味をもったといえば、ラスプーチンについての話もあります。帝政ロシア最後の皇帝、ニコライ2世のもとに仕えていた怪僧で、彼は青酸カリを飲んでも死ななかった、という話は読んだことがありました。それを説明する一つの説が紹介されていて、興味深かったです。文字色を変えましょう。青酸カリは、胃酸で分解されて、その効果があらわれるものだとか。ラスプーチンが青酸カリを飲んでも死ななかったのは、彼が無酸症だったからだ、という説です。 * 本書の最終章の後半は、袋とじになっています。開けにくかったです…。とまれ、その中は、本当に面白かったです。QEDシリーズを読むたびに、とくに日本神話や大和朝廷期の歴史について勉強したいと思い、『日本の歴史1 神話から歴史へ』などもぱらぱら読んでいるのですが、このたびその思いを強くしました。といって、自分のいまの勉強がありますから、なかなかじっくりとはいかないでしょうけれど。 殺人事件も起こりますが、本書の主題はそこにありません。とにかく面白かったです。 …本書のある説を読んでから表紙を見ると、不気味に感じてしまいました。
2006.01.31
コメント(2)
-

森博嗣『レタス・フライ』
森博嗣『レタス・フライ LETTUCE FRY』~講談社ノベルス~「ラジオの似合う夜 A radiogenic night」 ある小国に出張に訪れることになった私。以前、その国から日本にきていた知人の女性に、案内をしてもらう。私は、その国で過去に起こっていた二つの事件の話を聞く。一つ目は、強盗事件。犯人はまず一人に違いないのだが、金庫には犯人の指紋とは異なる、しかも新しい指紋がついいてという。二つ目は、蒸気機関車の殺人犯。乗客を殺しながらお金を巻き上げていった犯人が、消失したという。そして、私も新たな事件に立ち会うことになる。新しくできたばかりの美術館の、壁に穴があけられていたのだった。「檻とプリズム A prism in the cage」 幼い頃から、彼のことを尊敬していた僕。しかし、彼に興味をもつらしい彼女が、僕に近づいてきた。最近起こっている少女連続殺人事件と、彼を結びつけるように語る彼女にどう接すればよいか、僕は考える。<ショートショート5編> 「証明可能な煙突掃除人 Provable chimney sweeper」 煙突掃除人だった父が死に、彼も煙突掃除人になった。父が死ぬ間際に残した言葉、お化け煙突の謎にひかれて。 「皇帝の夢 The imperial dream」 不思議な夢を見て、ふらりと旅に出た男の話。 「私を失望させて Drive me to despair」 現代版桃太郎。 「麗しき黒髪に種を Seeds for her lovely tresses」 忘れられない子どもの頃の経験。 「コシジ君のこと My most unforgettable figure」 毎日夢で出会う、小学校の頃の友人コシジ君をめぐる思い出。「砂の街 The sandy town」 久々に故郷の街に戻ってきた僕。街の様子がおかしかった。街は砂に覆われていて。砂でできた車を運転する人々がいて。実家の裏の老夫婦が、僕と同じく大学院生の女性を紹介してきた。彼女は、この街の砂の謎について、調べているという。「刀之津診療所の怪 Mysteries of Katanotsu clinic」 山吹と海月の故郷、白刀島に遊びにきた、二人と加部谷。西之園とその叔母、佐々木も合流する。彼らの関心は、その島の怪談めいた噂話。診療所で幽霊を見て病気がちになった少年。着物服の女。診療所を訪れる、刀のようなものを持った男。こういった噂話が島に広まっていた。西之園たちは、その真相をつきとめようとする。 久々に森博嗣さんの作品を読みました。本書は短編集で、以上の九編が収録されています。目次には、特に<ショートショート集>ということを書いているわけではありませんが、便宜的につけておきました。 胸が痛んだ作品は、「麗しき黒髪に種を」「コシジ君のこと」の二編です。いずれも、子どもの頃の体験が話の主軸です。どちらもすごく生々しくて、繰り返しになりますが胸が痛みました。 「私を失望させて」はとても楽しく読みました。リアリズム志向ですね。「砂の街」も、冒頭のイメージとは逆に、途中は笑いながら読んだのですが、ラストがよく分かりませんでした…。 「刀之津診療所の怪」。解決(?)の方法が、当たり前すぎて気づきませんでした…。Gシリーズの登場人物が登場する初の短編ですが、海月さんは解決もしないのでほとんど話しません。わずかな発言で、笑わせてくれますが。「いたって」など、なかなか意味がわかりませんでした。ーーー 日記じみたことも。今日もセンター試験ということで、大学に立ち入り禁止ということで、近所の図書館で作業していたのですが、昨夜は薬を飲まずに寝たせいかあまり眠れず、疲れてしまったので、のんびりすることにしました。読了が先になるだろうと思っていた本書を読んだのも、そういう事情です。明日から平常モードでがんばるとします。
2006.01.22
コメント(4)
-
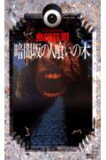
島田荘司『暗闇坂の人喰いの木』
島田荘司『暗闇坂の人喰いの木』~講談社ノベルス~ 1984年、石岡和己が、まだ『占星術殺人事件』と『斜め屋敷の犯罪』しか発表しておらず、御手洗潔の名前がそれほど有名ではなかった頃。石岡本人に、女性から電話があった。彼女は彼の収入などを聞いてきて、石岡にはその意図が分からなかったのだが、ともかく彼女の元恋人が藤並卓であり、今度の事件の第一の被害者となる。 台風が過ぎたある朝、暗闇坂の下にあるおもちゃ屋の主人が、暗闇坂の上の方にある藤並家の洋館の屋根の上に、人間が座っているのを発見する。卓の死体だった。 目立った外傷はなく、警察は心不全ということで片付けようとしていたが、御手洗は不審な点を指摘し、事件に注目する。被害者の死亡推定時刻に、彼の母親が、藤並家敷地内に生える巨大な楠の下で、頭部を強く打って倒れていたこともわかる。 この楠には、様々な噂があった。枝にぶらさがるずたずたになった少女の死体。洞に耳をあてると、楠が食べた人々の声が聞こえ、死体も見つかるという。 卓の弟、譲は、死刑の歴史に深い興味を持つ男だった。石岡は、彼から残酷な死刑の事例を聞かされることになる。 戦後しばらく、藤並の敷地には、外国人のための学校があった。創立者は卓たちの父親、ジェイムス・ペイン。卓の死体が座っていた屋根には、もともとにわとりの像があった。その像も、事件を境に行方がわからなくなっていたのだが、この像は、羽を動かし、またそれと同時に、音楽を奏でる仕組みになっていた。ペインは非常に規則正しい生活をしており、毎日正午にこれを鳴らしていた。しかし御手洗は、ここにも暗号を見出す。 事件はさらに深まっていき、ペインの故郷、スコットランドにまで御手洗たちは向かうことになる。 …やっぱり島田荘司さんはすごいです。読んでいて震えそうになるところもありました。読むとこれだけすごいと思うのに、再読なのです。ほとんど覚えていませんでした。 先日紹介した『ハリウッド・サーティフィケイト』など、松崎レオナさんが、このシリーズで重要な人物となるのですが、彼女の初登場作品が本書です。第一印象は高慢な女性なのですが、次第に御手洗さんに対する接し方が変わっていきます。以後の作品のレオナさんを理解するには、本書の前提があるとよいでしょう。 本書には、図版付きで様々な死刑の様子が紹介されています。最初に読んだのがたしか高校生の頃で、そうした死刑の歴史をいろいろ調べてみたいと思ったものですが、なにぶん露骨なタイトルの本を買うのはまだためらいがありましたから…。ある種、そちら方面のネタとして、本書を重宝しておりました。単に好奇心が強いのもありますが、どうしてこうも人間の醜い一面に興味をもってしまうのか。本書の中にもありますが、そうしたものは、一種独特の魅力を持っているのでしょうか。公開処刑に多くの人々が集まった事例が紹介されていますが、それはやはりその時代、その社会、その文化が影響しているのであって、現在ではなかなか受け入れがたい…といいたいところですが、アングラなサイトが多々あるということも聞きますし、やはり人間をとらえるところがあるのでしょう。目をそむけたい一面ですが。 いつものように話があちこちいってしまいますが、本書の冒頭では、スコットランドでの事件が紹介されています。少女を愛し、つかまえ、殺し、ばらばらにする男。彼は死体をコンクリートの壁に埋め込むのですが、 10年後にその建物が調べられたとき、死体が発見されなかったという、御伽噺めいた物語。御伽噺めいた物語といえば、内容紹介でもふれた、楠による人喰い。こうした謎も、きれいに明かされます。1984年、卓さんたちが被害者となる事件も、ミステリとして非常に魅力的ですが、こうした御伽噺のような事件も解決されるのが、嬉しいです。 良い読書体験でした。
2006.01.09
コメント(2)
-

アルベール・カミュ『異邦人』
アルベール・カミュ(窪田啓作訳)『異邦人』Albert Camus, L'Etranger~新潮文庫~ ずいぶん内容に立ち入ってます。特に文字色も変えていません。また、感想のところでは、いくつか引用もしています。 ある日、ムルソーのもとに電報が届く。養老院から、彼の母親の死を知らせるものだった。 暑い日だった。ムルソーは、バスに乗り養老院へ向かい、通夜と葬儀をすませる。彼は母親を見ようとせず、死に際して涙も見せず、母親の年齢も知らなかった。母親を養老院に入れたのは、看護をつけてあげるだけのお金がなかったからだが、そこで母親には仲の良い友人ができたようだった。「許婚」と呼ばれていたというトマ・ペレも、葬儀に立ち会った。 翌日、ムルソーは女友達のマリイ・カルドナと海水浴を楽しみ、映画を観にいく。その日、二人は関係を持った。 ムルソーが住むアパルトマンで、彼と話をする人物は二人。皮膚病を患った犬と暮らし、その犬をよく罵っているサラマノ老人。ある日犬がいなくなると、老人はあわてていた。 また、レエモンとも友人となる。レエモンは、囲っていた女性に裏切られたという話を聞かせてくれた。その兄とけんかをしたことも。彼は、ムルソーに、女性を「懲らしめる」手紙を書くように求めた。やがて、レエモンと女性は大喧嘩し、警察沙汰になるほどだった。 ある日、ムルソー、マリイ、レエモンは、レエモンの友人マソンの別荘へと遊びに行った。別荘は海辺にあり、彼らは海水浴を楽しむのだが、その道中、レエモンともめていた男-アラビア人-たちと出会う。アラビア人たちは海辺にまでやってきて、レエモンたちは彼らと争うことになる。いったん、レエモンが傷つけられた時点で事はすんだのだが、その際レエモンから拳銃を預かっていたムルソーが一人で散歩に出ると、再びアラビア人と出会った。陽の光が、肌を焼くようだった。ムルソーはアラビア人を撃ち、少し間をおいて、横になったアラビア人に4発銃弾を撃ち込んだ。 以上、第一部のあらすじを細かく書いてみました。第二部では、ムルソーの刑務所生活、裁判の様子が描かれています。背表紙にも書いてありますが、動機を聞かれたムルソーが、太陽のせいです、と答えるのもここです。 さて、物語はムルソーの一人称で語られます。数年前に本書を買い、読もうとしたときは、 20頁くらいで挫折していました。読ませない小説だ、と感じていたのですが、これが案外面白く読めました。やっぱり、月日が経つといろいろ変わるものですね。 面白かったのは、いろんなことに理由がつけられていること。その理由が、あってもなくてもよさそうなものだということ。たとえば、レエモンから手紙を代筆することを頼まれ、手紙を書くときに、「私は手紙を書いた。多少いい加減なところもあったが、それでも、レエモンに満足を与えるように努力した。というのは、彼に満足させないという理由は、別になかったからだ」 (36頁)とあります。以前に挫折したときは、多分ここまで読めなかった(母親の葬儀のあたりで挫折したように思います)とはいえ、こういう描写を以前は読みづらいと思い、いまは面白いと思えるようになっている、ということでしょう。それから面白かったのは、マリイから結婚してほしいと言われたとき、「それはどっちでもいいことだが、マリイの方でそう望むのなら、結婚してもいい」と答え、彼女から自分を愛しているかと尋ねられると、「それには何の意味もないが、恐らくは君を愛してはいないだろう」と答えている場面です(46頁)。(39頁にも同じような会話があります)マリイが、こういうムルソーの面白いところが好きだが、それと同じ理由で嫌いになるかも知れないと言うところが、印象深かったです。 刑務所に入ったムルソーは、自分の部屋の細部を思い出すという時間の過ごし方を実践します。家具、小物、その細部の様子など、それは細かく思い出すのです。また引用ですが、「そして、このとき私は、たった一日だけしか生活しなかった人間でも、優に百年は刑務所で生きてゆかれる、ということがわかった。そのひとは、退屈しないで済むだけ、たっぷり思い出をたくわえているだろう。ある意味では、それは一つの強みだった」 (85頁)というところも、印象に残っています。 有栖川有栖さんがその作中人物に言わしめているように、本書の書き出し「今日、ママンが死んだ」というのは、(ここは文字色を変えましょう)ある人は「痺れたわ」と言い、またある人は「その一文だけで、何やらぐらぐらと不安定な気持ちになりかける」というくらいの(ここまで)、それはネタになる一文だと思います。これはもう、訳者の業績でしょう。母親でもなく、お母さんでもなく、「ママン」という訳語を採用したのは。 さて、なかなか読まない古典なので、内容も感想も長めに書いてみました。なにより、挫折せずに読了できたことが嬉しいですし、さらに楽しめたので、本当によかったです。(追記)画像(アフィリエイト)は改版ですが、私が読んだのは旧版です。
2006.01.08
コメント(0)
-

フランツ・カフカ『変身』
フランツ・カフカ(高橋義孝訳)『変身』Franz Kafka, Die Verwandlung~新潮文庫~ *少し詳しく内容に立ち入っています。 ある朝起きると、グレーゴル・ザムザは、自分が一匹の大きな虫になっているのが分かった。外交販売をしているグレーゴルは、いままで無断遅刻をするようなことはなかったが、この朝ばかりはそうはいかない。ドア越しに声をかけてくる家族に、なんとか返事をしていたグレーゴル。しかし会社の上司がやってきて、ドア越しに声をかけられたあたりから、彼が発する言葉は誰にも理解されないものとなっていた。 妹グレーテが、グレーゴルに食事を与える役になった。なるべく彼を見ないように、事務的に仕事をこなすグレーテ。グレーゴルが、部屋を這いずり回ることに喜びを見出すと、妹はそれに気づき、部屋から家具を出してしまおうとした。そのとき、彼は唯一の抵抗として、自分が買っていた絵を覆い、まもったのだった。 家計が苦しくなり、両親も妹も仕事をさがした。家には、三人の下宿人を泊めるようになった。下宿人たちは特に問題なく暮らしていたが、グレーゴルに気づき、それに対応する家族の反応を見て、態度を変えるようになった。そして家族は、グレーゴルに対する態度を変えていく。 数年ぶりの再読です。古典を読んだ、という気分になれます。 グレーゴルは、最初のあたりでは(それが人間には聞き取れないにしても)台詞を口にするのですが、次第に一言もしゃべらなくなります(かっこつきの言葉がなくなっていきます)。地の文ではいろいろ考えているのですが。妹を音楽学校に行かせたかったなど、人間だったころに強く思っていたこと。自分に対する家族のあり方。最後には、グレーゴルは死んでしまいます。それまでグレーゴル中心の視点で物語が進んできたのですが、ここからは(当然といえば当然ですが)視点が変わっています。 どんどん人間らしさを失っていくグレーゴル。虫になった朝、「気がかりな夢」を見ていたということですが、彼が虫になる必然性は特にないだろうに、虫になり、家族から煙たがられ、そして死ぬのです。彼中心で見ると重たい物語なのですが、最後は、残された三人の家族にとっては救い(希望)のある終わり方となっています。そこにまた、どこか苦しいものを感じました。(追記)私が持っているのは旧版ですが、画像(アフィリエイト)は改版のものです。
2006.01.05
コメント(2)
-
映画「ポビーとディンガン」
昨日、楽しみにしていた映画「ポビーとディンガン」を観にいってきました。原作がとても面白かったので、映画化されると聞いたときには嬉しかったものです(原作の感想はこちらです)。あらすじはほとんど原作と同じなので、特にふれないことにします。以下、原作と映画の違った点について、多少ネタばれしますので文字色を変えます。まず、原作では裁判のシーンは映画版ほどなかったように思います(まったくなかったような…。原作にあたりなおしていません、すみません)。ですが、アシュモルの父、レックスの弁護士がずいぶんかっこよかったです。ケリーアンの空想の友達、ポビーとディンガンの存在を、少なくとも二人はケリーアンにとっては現実の存在だったことを認める町の人々。観るのも涙をこらえながらでした。それから、ケリーアンが亡くならなかったことです。あるいは、ポビーとディンガンのお葬式の後は、ケリーアンは登場しなかった(はずです)ので、暗に示されていたのかもしれませんが。ただ、原作で、ケリーアンが亡くなり、もともとポビーとディンガンという、目に見えない、空想の存在を否定していたアシュモルが、他人がなんと言おうとケリーアンはいるんだ、と言っているのが、とても良かったのです。ケリーアンにとっての二人、アシュモルにとってのケリーアンが、そのようにだぶっていく様子がとても感動的だったのですが、映画では、オパールを追い求めるという夢とだぶらせているだけで、ちょっと物足りない感じがしました。アシュモルやレックスへの町の人々のいやがらせには、胸が痛みました。レックスの家の近くに放火されたシーン、レックスの乱闘、アシュモルの自転車への悪意あるいたずら…。どれもショッキングなものでした(原作はもう少し優しい感じだったので)。反転ここまで。アシュモル役もケリーアン役もぴったり、と感じました。アシュモルはかっこいいし、ケリーアンはかわいいし。さらにお父さんはかっこいいしお母さんはセクシーだし。「姑獲鳥の夏」は役者さんにいろいろ違和感を感じながら観たのですが、この作品は役者さんにもすんなりはいることができて、よかったです。
2006.01.05
コメント(1)
-
ウンベルト・エーコ『薔薇の名前(下)』
ウンベルト・エーコ(中島英昭訳)『薔薇の名前(下)』Umbert Eco, Il Nome della Rosa~東京創元社~ 三人目の死者は、浴槽から見つかった。 修道院には、フランチェスコ会士の一団、そして彼らと対立する勢力、異端審問官ベルナール・ギーを中心とするドミニコ会の一団が到着した。教皇の権威、清貧をめぐり、両陣営の間に激しい論争が起こる。 ベルナール・ギーは、修道院内にいる元異端の人間に目をつける。その人物に、一連の修道院の事件の罪もなすりつける。 ところが、その後も事件は続く。ウィリアムは、なおも真相を追っていく。 昨日、頭痛のため大学に行くのを断念し、大方読み進め、今日は映画を観にいくのでもともと大学を休むつもりでいたので、まずは本書を読了しました。 上巻のところで長々と書いたので、こちらは短めに。 アドソが見る奇妙な夢。これが、単なるエピソードではなく、事件の解決に関係していくあたり、とても面白かったです。ある意味では、温泉旅館殺人事件で、他のお客さんや旅の人たちの何気ない会話を聞いて、事件の構造に気づく、というのと似ているかもしれませんが、アドソの夢自体とても興味深いので…。私はまた妙な例を挙げてしまいました…。 上巻の感想では、事件の方にはあまり言及しませんでしたが、「ヨハネの黙示録」の見立て殺人のような事件です。これ以上はあまり言わないことにしましょう。 2005年年末から読んだ本についてはたいてい書いているのですが、本書を読んだのも、とても良い読書体験でした。面白かったです。
2006.01.04
コメント(0)
-

ウンベルト・エーコ『薔薇の名前(上)』
ウンベルト・エーコ(中島英昭訳)『薔薇の名前(上)』Umbert Eco, Il Nome della Rosa~東京創元社~ 1327年、イタリアのとあるベネディクト会修道院に、ベネディクト会見習修道士アドソと、その師フランチェスコ会修道士バスカヴィルのウィリアムが訪れた。とき、教皇庁がアヴィニョンに移されており、皇帝と教皇は対立、フランチェスコ会内部の分裂、それをめぐる争いと、情勢は混乱していた。二人が訪れた修道院は、その混乱をおさえる役割を果たすと考えられていたのだが。 二人が訪れるすぐ前に、事件が起こっていた。修道士の一人が転落死したという。ウィリアムは、この事件を解決するよう、修道院長アッボーネに依頼された。 その修道院で、重要な役割を果たす建物。一階は厨房、二階は写字室(スクリプトーリウム)、三階は文書館になっていた。文書館には、館長以外は誰も立ち入ってはならないと命じられていた。 盲目の老修道士ホルヘ。彼とウィリアムは、「笑い」をめぐって論争する。 ウィリアムは、院長や知人ウベルティーノと、異端について議論する。 アドソは、どこの国の言葉でもありどこの国の言葉でもない言葉を話すサルヴァトーレの生い立ちを聞き、小兄弟派の様子を知る。また、小兄弟派、その代表とされるドルチーノについて、ウベルティーノらの話を聞く。 事件は、最初の修道士の転落死にとどまらなかった。二人が到着してから、また一人の修道士が死んだ。血のためられた甕の中に、逆さにつっこまれていた。 院長や館長らのかたくなな態度から、文書館に秘密がある、と考えるウィリアム。しかし、作業は順調には進まなかった。 いやはや、一日で下巻まで読む予定でしたが、読むのにずいぶん頭を使ったのもあり、時間がかかりました。それで、そもそもペースを落として休み休み読むことにしたわけですが。 時代は、私が専門に勉強している時代から1世紀近くくだった14世紀初頭。舞台はイタリアのベネディクト会修道院。 先日、『薔薇の名前』のビデオを観た感想として記事を書いたときに、ベネディクト会とフランチェスコ会については簡単に書いた…と思ったのですが、読み返すと、服の色だけですね。 ベネディクト会は、6世紀前半、イタリアのモンテ・カシノに修道院を開いたベネディクトゥスの戒律に基づいて生活する修道会で、その使命は「祈り、働」くことでした。また、修道士は、「清貧、貞潔、従順」の誓いをたてました。次第に典礼(祈り)の役割・時間が増し、また清貧の理想に反するように、修道院を華美な装飾で飾り立てたりするようになります。これに対しては、同じくベネディクト戒律に従うシトー会が反対していくようになるのですが、これはまた別の話。 フランシェスコ会について。12世紀末にアッシジのフランチェスコが、彼は富裕な商人層の生まれでしたが、その財を投げ捨て、清貧の生活を送るようになります。そして説教をして回るのですが、彼のまわりに集まった人々でもって、フランチェスコ会が作られていくことになります。こちらは、修道院の中で典礼に捧げることを主な職務とするのではなく、托鉢で生計をたて、民衆に説教することが主な職務でした。本書で勉強になった部分もあるのですが、ベネディクト会が「笑い」に否定的であるのに対して、フランチェスコ会は「笑い」に肯定的なようですね。映画の感想でも書きましたが、「笑い」をめぐる議論は興味深かったです。 本書は、アドソが、この事件の後、老いてから回想しながら書いた手記、という体裁です。ウィリアムらの台詞は、中世の文献(の和訳)を読んでいるような気分になりました。すらすらと先学の言葉をそらんじ、自分の見解を説明していく。私が主に勉強している12世紀末から13世紀半ばの人々は、まさに彼らの先学であるわけでして、知っているマイナーな人名が出てくるとちょっとテンションが上がりましたが、同時に自分の勉強不足を痛感します。明日からさっそく勉強をはじめますが、がんばらなきゃ…。 本書の最後の方で、異端についての議論が展開されます。非常に興味深いです。説教、異端、マイノリティ、大衆の信仰、利害関係。いろいろ、今後勉強をする際に心にとめておきたい問題関心ができ、本当に勉強になりました。下巻を読むのは少し先になりそうですが、楽しみです。
2006.01.01
コメント(0)
-
謹賀新年
本年もよろしくお願いします。*さて、元日には15時間読書、というのを、ここ2,3年間目標とし、また果たしてきたわけですが、今年は無理しまいと、昨夜寝る前に考えました。明日から大学に行くつもりもあるのと、昨日けっこう読書したこと、なによりたまには読書時間も少なくして、のんびりごろごろしようと思ったこと。以上の理由から、です。『薔薇の名前』上巻を、まだ読んでいる途中です。当初は上下巻読むつもりでしたが、ずいぶんお昼寝してしまったので、無理そうです。(明日から数日、下巻を読むために大学から早めに帰宅する可能性もありますが、おいおい考えます)とりあえず、今日は上巻の感想をアップできたらよいかと思っています。
2006.01.01
コメント(2)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










