2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年11月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
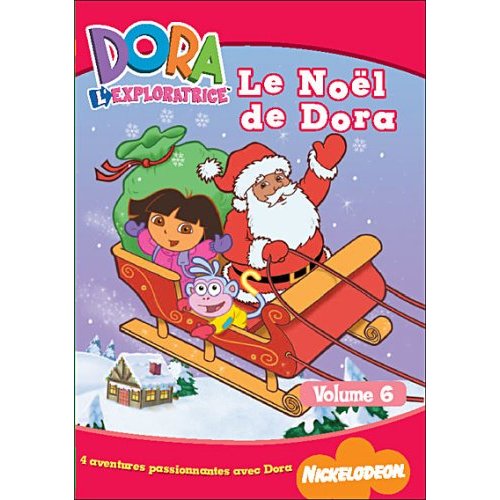
またやってしまった・・・
学習能力がない人間とは私のことです昨日は丸1日、胸がムカムカして体中が熱っぽく、痛だるくて使いものになりませんでした。風邪ではないし、つわりでもありません。その証拠に今日はスッキリしています。原因は・・・・・・というかこれしか考えられない!というかね、気づかなかったんですよ、それだっていうことを。というよりも他のものとすっかり勘違いしていました。ここまで引っ張ることもないのですが、食べちゃったんです。この時も痛い目にあった、あの食材を・・・でもさすがの私も生で食べるような無謀な真似はもう出来ません。しかも自分で調理することももう考えられません。たまたま、頂きもののお惣菜の中にちょこんと入っていたんですね~それをこれはムール貝だろうと自分に都合よいように思い込んで(よくみれば明らかに違うのに)口に入れてしまいました。すぐには反応が出なかったけれど(食べたのは夜)、夜中に眠りが浅くなって、翌朝にはしっかり上記のようなアレルギー反応が出ていました。これで生食のみならず、火を通したものも食べられなくなっていることを思い知らされてショック。牡蠣フライ、好きだったのになぁ・・・そして今週末は日本人の友人が手巻き寿司をご馳走してくれることになっています。鯛やマグロの他にホタテも用意してくれるそうですが、二枚貝がダメな体質になっていないことを祈るばかり・・・最近生で食べることはなかったけれど、ムール貝などはよく食べていたので大丈夫だと信じたい・・・季節的に二枚貝のノロウィルスが心配な時期でもありますが、手巻き寿司は大いに楽しんでこようと思います♪他にも今週はギャルドリーで保育士さんと私の間でひと悶着(という程のことではないのだけど)あってちょっと落ち込んだり、翌日にはマプッペと同じ年頃の子供を持つお母さん達と話す機会があって、前日のことで元気付けられたりといろいろありました。その度に親としての自分の未熟さを痛感させられる毎日です。明日から12月ですね。今日はこの後クリスマスツリーを買いに行ってきます。どんくまさんに続いて、マプッペが今夢中になっているのが、「ドーラといっしょに大冒険」のクリスマス編、その他のお話が入ったDVD。図書館で借りてきました。米国産ドーラはフランスですごい人気があるみたいでスーパーなんかにもキャラクターグッズが溢れているんですが、私は横目で見ていて正直、可愛くないな~と思っていたんです。でも実際DVDを見て人気な訳が納得できました。分かりやすいし、楽しい。↑このクリスマス編も、クリスマスソングがラテン調になっていて新鮮です^^日本ではうけるのかな?と思っていたけど、結構あるみたいですね、ドーラグッズ。↑この右のリープスターはこちらのクリスマス商戦でもすごい力を入れている商品です。DSとの違いがいまいちよく分からない年寄りな私ですが、こちらはテレビに繋げて画面を大きくすることができる・・・っていうことなのかな?!
2007.11.30
コメント(6)
-

エンダイブのポタージュスープ
先週の火曜から続いていた、年金改革に関わるフランスの交通及び各公務員ストライキ。私のいる街は市内の交通機関が半官半民なので影響は全くなかったのですが、パリの方達は大変だったと聞いています。特に今週前半は天気もあまり良くなくて、メトロやバスがまともに運行していないのは非常に不便だったのでは。そんな状況の中先週15日の木曜日に解禁された今年のボジョレー・ヌーボー。今年はこのストライキのせいか、あまり話題になっていなかった気が・・・元々このワイン自体が好きだという人は殆どいないというのが本国での印象ですが、輪をかけて影の薄い存在になっている(ような)今年。昨年も書きましたが、この解禁日を口実にカフェやバーで一杯♪という姿は結構見られ、通年はフランスの季節の風物詩になっていると思います。あと毎年日本のボジョレー風呂も取り上げられます、一応。今年はちょっと盛り上がりに欠けたかも・・・我が家では年行事のひとつなので1本だけ試しに飲んでみましたが、可もなく不可もない味でした(汗)ワイン好きの友達からは、美味しいワインが飲みたかったら最低でも1本5ユーロ、確実に選びたかったら7ユーロ以上は出すこと!とアドバイスされていますが、ボジョレーはそもそも価格設定が他の産地よりも低め。専門店はどうなのか知りませんが、スーパーで買えるのは4ユーロ台が主流で、良くても6ユーロくらいであまり参考にならず。(そもそもワイン好きはボジョレー・ヌーボーに関心がないのだけど・・・)ところでボジョレーと一緒に食した料理の話でも。昨年はクリーム系の食事を併せてあっさりしたボジョレーとのミスマッチ(?)を楽しみましたが、今年のメインは淡白な七面鳥の薄切り肉(エスカロップ)のステーキと野菜炒めでした。そしてもう一品作ったのがこちら、エンダイブのポタージュスープ(Velout? d'endive※)※仏語で野菜スープをPotageとも言いますが、より質感の濃厚なスープはビロードを意味する”Velout?”が使われることが多いです。発音は「ヴルーテ ド アンディーブ」。上にのせたパンがやや焦げているのはどうか気になさらずに・・・これです、エンダイブ(仏語読みでアンディーブ)。英語圏ではベルギーチコリです。日本でもチコリと呼ばれていますね。年中食べられますが、野菜不足になりがちな冬場に活躍する、低カロリー(100グラムにつき15カロリー)でビタミンB群が豊富な野菜。エンダイブは火を通しても苦味が残るのが特徴ですが、苦い味がダメな場合は真ん中の芯の部分を忘れずに取って下さい。(写真の”ici"と書かれた部分)参考にしたレシピはおなじみフランス版クッ〇パッドで見つけました。レシピを勝手に転載していいのか分からないので詳細は省きますが、これはエンダイブをバターでクタクタになるまで炒めて小麦粉をまぶし、牛乳でのばしてミキサーにかけ、パルメザンチーズを加えたもの。エンダイブを炒める際に、つぶしたにんにくをひとかけ入れる(のちに一緒にミキサーにかける)のが味のポイントのようです。小麦粉の代わりにじゃがいもを入れてもいいし、牛乳の代わりに生クリームにしたり、ハムやベーコンを一緒に炒めてミキサーにかけたりとアレンジは自由。仕上がりはほんのりと甘味があって、コーンスープに近いものがあります。フランスにはコーンスープが存在しないのでちょっと新鮮な味。エンダイブは生でブルーチーズや胡桃と一緒にサラダにしたり、グラタンにして食べることが多いですが、これは目新しくて家族にも好評でした。ボジョレーともよく合いましたよ☆(ちょっと無理やりこじつけ・・・^^;)
2007.11.22
コメント(2)
-

どんくまさんのくりすます
どんくまさんのくりすます ストにデモにと全国的に熱い今日この頃のフランスですが、クリスマスへ向けて街中のイルミネーションが徐々に始まる季節となりました。我が家のクリスマス準備は、まず↑上の絵本。8月にパリのブックオフで手に入れて以来マプッペのお気に入りになっていて、ここのところ1日最低1回は読み聞かせ中。最低1回・・・ということは読み聞かせが2回になることもあって、3回目からはマプッペが私に読んでくれます。まだ正しい文章にはなっていませんが(読めるひらがなもほんの少しだし)、キーワードや効果音なんかはちゃんと追っているので、各場面で何が起こっているのかはどうやら把握できているようです。これはフランス語の絵本でも同じで(読み聞かせは夫担当)、以前は私が仏語テキストを日本語に言い直して一緒に読んだりもしていたのですが、最近では「ママはフランス語が読めない」と判断したのか、私に読んで聞かせてくれるように。仏語は読めないふりをしたかいがありました。それでいてこちらのほうがなんとなく文章に近くなりつつあるような、、 話を絵本に戻しますと、この「どんくまさん」シリーズは1974年が初版とかで、私も子供のときに読んだ覚えがあります。体が大きくて力持ち、でもちょっとおっちょこちょいでいつも謝ってばかりの優しいどんくまさんは、いつも子供達の人気者。その彼のおっちょこちょいぶりがマプッペのツボにもはまったらしく、どんくまさんが転ぶシーンでは毎回読みながら大袈裟に転がってみせる母。娘がこれをいつまで喜んでくれるかは分かりません・・・ ところでうちにあるのは上にリンクしたものと同じ出版元ですが、日本カトリック幼稚園連盟が監修したバージョンです。よってクリスマスを、「きりすとさまがおうまれになったひ (どんくまさんのくりすますより抜粋)」と表現しているので、これが気になる方は要注意。もしかしたら普通のバージョンにはこう書かれていないかもしれません。私はカトリックの祝日が多い国にいるし、気にならないのでそのまま読んでいますが。(でもまだ娘にとってここは重要な個所ではないらしい→彼女の興味はあくまでもどんくまさん)この絵本は絵 も文も温かみがあって、それでいてこの時期特有のピリッとした空気を感じさせるもので、リズム感のいいところも気に入っています。しばらくはこれがクリスマス前の定番になりそうな予感。T・ハンクスが毎年11、12月になるとこの絵本を 子供達に読み聞かせていたというのを知って、すっかり感化されていた私です。それにしてもすっかり冬、そして年末モードですね。もう1年を振り返る時期。今年私は一体・・・(焦)
2007.11.15
コメント(8)
-
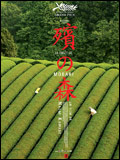
「殯の森(もがりのもり)」を観てきました
この日の日記で宣言した通り、こちらでは10月末に公開となった河瀬直美監督映画「殯の森」を観てきました。いざ公開!となると、単館ロードショーな上に1日の上映回数も少ないので「DVDが出るまで待つかな~」と消極的にもなったのですが、割引券も手に入れたことだし、せっかくだからと行くことに。 観終わった感想は、、 まぁ、特に映画館で観なくてもよかったかも?というのが正直なところ・・・(酷) でも今年のカンヌ映画祭グランプリという話題性のおかげか、1日2回しか上映がないせいか分かりませんが、土曜の夕方のこの回は100人未満収容の小さい上映室だったとはいえ、前3列を除いてほぼ満員になるくらい人が入っていました。パリではなく地方都市で、どういう人達がこの日本映画を観に来ているのか観察できただけでも、映画館まで足を運んだ甲斐があったという気もしています。 客層で多かったのは熟年カップル、次に熟年カップルと同じ世代のおじさま・おばさまグループ。この世代で日本文化やアジアに興味を持っているのは、そのこと(日本やアジア文化に造詣が深いこと)がステイタスになっている人達でもあり、皆何となく感じが似ています。映画の後は日本料理屋でSUSHI(この街は日本人経営でない店ばかりなので、あえて”寿司”とは書かない・・・)を食べに行ったりするんだろうな。 次は若い男女2-3人のグループ。中には友達に誘われて何気なく来た人もいたみたいで、上映前に「これってカンヌでグランプリ獲ったやつだったっけ?」なんて仲間に確かめている声も聞こえたり。でもこういう人も含めて独立系映画中心の映画館に来る人は「本当に映画を観たくて」来ているので、上映の最中に立ち上がって出て行くパターンが殆どありません。大手シネコンだと毎月決まった料金で何本でも鑑賞できるサービスを行っている故かこういうアクシデントに見舞われたりもしますが、今回は映画によく集中できました。 そんな理想の環境だったにも関わらず、「別に映画館で観なくても、、」と思ってしまったのは何故かと言いますと、手持ちカメラによるブレた映像が多くて、頭が痛くなってしまったから。大スクリーンである必要はなかったかなと、、 臨場感を出すための効果でもあるのかもしれないけれど、焦点の合わない映像が何度も出てくると、目が無理やり合わせようとするから疲れます・・・でも近親者の死から立ち直れない感情というのは、国や年齢を問わず誰にでも共感できるテーマで、話には非常に入りやすかったのだと思います。上映後に目をウルウルさせているフランス人を何人か見ましたよ(余談ですが上映室内に他に日本人はおらず)。あとは認知症の老人を介護する立場について。2歳児のパワーに圧倒されている私なんてまだまだ甘いと思わざるを得ないくらいの大変さが分かったような気がします。その場を治めるだけだったら子供は力ずくでやめさせることも出来るけれど、大人相手の場合はそうもいかないですからね。意思の通じ合いが大事なのは、どちらも同じなんだけど。 それから日本の森林とか山ってやっぱり青くていいなと思いました。大陸にはない青さですね。今住んでいる地域は山もないので余計に感じます。山育ちではないけれど、毎年夏休みは家族で長野の山に行っていたので、暑い季節になるとあの日本の山のしっとりした青さが恋しくなることがあります。 映画の感想はそんなところでしょうか。しかし今回思ったのは、カンヌのグランプリというのはこの映画祭の次点にあたるんですけど、最高賞(パルム・ドール)との格の違いというのを見てしまったようにも感じました。 例えば最近でいうと、2004年のグランプリ作「オールド・ボーイ」とか・・・韓国映画「オールドボーイ」ビデオCD(VCD)(直輸入 韓国版)↑これは日本語版DVDさえ出ていない・・・ それから2005年グランプリ受賞の「ブロークン・フラワーズ」ですね。 ブロークン・フラワーズ どれも題材なり映像なり面白い映画なのだけど、観終わった後に今ひとつ物足りなさが残るところが共通しているかな・・・(偉そうなこといえる立場じゃないんですが~)お時間のある方は歴代のパルム・ドール受賞作一覧→こちらと、審査員特別グランプリ受賞作一覧→こちらを見比べて、なるほど~♪ と頷いてくださいまし(もちろん反論もおありかと思いますが!)。 以上、オタク日記で失礼しました。続けて前回の日記のコメントへお返事するところでしたが、マプッペが昼寝から目覚めてしまったので、落ち着いてからゆっくりお返事書かせていただきます・・・すみません。
2007.11.10
コメント(4)
-
ダダこね2歳児とフランスの消防士
この年頃(2-3歳)の子供は誰もが通る道なのでしょうか。うちもこの頃のイヤイヤが発展して、2歳以降は別名自立期とも言われる「ダダこね」が盛んです。この「自立」は、まだ赤ちゃんでいたい!気持ちと、もう赤ちゃんじゃない!気持ちの両方が時に絡み合っていたりいなかったり、だそうです。子どもの自己主張やダダこねが始まるこの時期には、親子の関係が大きく変わらなくてはならない時期です。とここでも書かれているように、親も試行錯誤しながら子供との接し方を考えていく時期のよう。上に引用した一文はダダこね育ちのすすめという本の著者によるサイトからですが、ここを読んでおくだけでもかなりためになります→しつけとダダこねでもですね、これを実行するには親のほうが気力も体力もベストコンディションでないとかなりしんどい・・・この日も扁桃腺を腫らしていて体力に限界があった私と、いつもながら元気いっぱい!でもギャルドリーが1週間強の秋休み中でエネルギーを持て余している我が家の2歳児にこんなエピソードが・・・午前中天気が良かったので公園へ行ってきました。紅葉がとてもきれいだったので、しばし娘をモデルに親ばか撮影会を繰り広げていたところ、横をジョギングで通り過ぎる、揃いのジャージ+男ばかりの集団が。大学の体育会にしては年齢層もバラバラだし、平日の朝っぱらからジョギングしているのはどういう人達なんだろうと思いつつ、さほど気にとめずにマプッペはいつものごとく大好きな滑り台へと走っていったので後をついていくことに。でもこれ(滑り台)をやりだしたら止まらない。ここ(ダダこねの導き方-公園から帰りたがらない子供を連れて帰るとき)にも書かれていますが、うちも公園から家へ帰る際には毎回親子間の交渉が必要です。「じゃぁあともう1回だけ」「うん分かった」の意思のレベルでのやりとりが上手くいくときはスムーズにいくのだけど、この時は私が気力体力共に弱っていて子供に上手く伝えられなかったのでしょう。帰りたがらないマプッペを無理やり滑り台から剥がして連れて帰る結果に(汗)ダダこね中のうちの2歳児は放っておくとその場から動かないので、14キロもの重さを抱えて歩くことになります。私の腕の中で騒ぎ暴れるマプッペ、一刻でも早くこの場から離れようと私も小走りになっていました。すると背後から、「マダム!マダム!」と呼び止める声が。振り向くとさっきのジャージ集団のうちのひとりではありませんか。誘拐犯か、もしくは幼児虐待かと思われたのか?!道を聞かれるシチュエーションでもないし・・・と相手の言葉を待っていると、彼のほうもちょっと躊躇しながら、「いや、もしかしたら違うかもしれないんですけど・・・我々は消防士なんですが、もしかしたらお子さんが怪我をしたのかと思って・・・もしそうなら、救急用具をここに持ってきていますので・・・」と、意外な言葉が。彼の向こうには心配そうにこちらの様子を窺うジャージ集団^^あまりの騒ぎ振り+私の慌て振りに、消防士さんたちもただ事ではないと察したのでしょうか。丁寧にお礼を言ってその場を去りました。それにしても消防士まで出動(?)させるうちの2歳児、恐るべし。親子の修行はまだまだ続きます・・・
2007.11.05
コメント(9)
-
最近のスイミングの様子
久しぶりにスイミング日記。これは先月27日土曜日の日記に書くつもりがなんとなく書きそびれていたので、1週間後のここに記しておきます。先週の土曜日(27日)は、実にひと月ぶりに私も「子供(もうベビーではないし)スイミング」へ参加してきました。その間も夫とマプッペは参加していたんですけどね。平日は娘との接触の少ない夫が、親子で一緒に水遊びが出来るいい機会だろうと思って、私は行かれなくてもあまり気にしていなかったんです。実際この頃毎週末お客さんが夜来ていて、準備やらの関係上家族全員で行くのは無理だったんですが。それ以外にも、一定のプログラムに従ってプールの中で過ごす訳ではないので、決められた時間内(1時間)でどれだけこの場を活用できるかはそれぞれの親の力に掛かっています。こういう親子で参加する場では、母親が中心になって周りと上手くコミュニケーションをとりながら楽しむ役割になる気もして、参加者の中で唯一の外国人ママである私には正直ちょっと重荷になることもありました。単なる私の気にしすぎかもしれないですけど。因みに父親のみが参加している親子は、子供が直接コーチとコミュニケーションがとれる4歳以上の子ばかりで、この年頃になると子供同士で勝手に遊んでいますね。で、ひと月ぶりに顔を出して親子3人または周りの子とも存分に遊び、帰り際にコーチに言われた一言。「今日マプッペは非常に多くのことを学んでいたと思います。というのもお母さんが来ているときのほうが、危険にさらされる率が高いからです。」と、誉められているのか反対なのか一瞬迷う遠まわしな表現で、どうやら誉められていたようです。つまりは旦那とマプッペ2人だけの時、彼が娘可愛さに危険を回避しすぎるばかりに、あまり彼女のためになっていなかったということなのね・・・ここで、はじめてベビースイミングに参加した頃を思い出しました。最近はスイミングを「水の中での親子コミュニケーションの場」と捉えていたけれど、そもそも赤ちゃんに水泳をさせる目的は、子供を水難事故から守るためだったのではないかと。なんだかスイミングに通う目的がまたはっきりしてきて、さらに大袈裟だけどコーチから私(母親)の存在意義を肯定されたような気もして、また出来るだけ毎週行こうと思い直した母でした(単純なんです)。この日はまだ始めたばかりで知り合いのいない母親(&生後6ヶ月の赤ちゃん)がどうしていいのか分からずにプールの隅で赤ちゃんとポツンと佇んでいました。見かねた夫が話し掛けていたのですが、その横で赤ちゃんに向かってポン!とボールを投げたマプッペ。すかさず夫が「そうかマプッペ、この赤ちゃんとボール遊びがしたいんだね」というと、そのお母さんの嬉しそうだったこと・・・そうよね、フランス人女性だって自分から周りとコミュニケーションとっていくのが苦手な人もいるよね、外国人だからってハンデに思うことないよね!とも思い直したのでした(でも私の場合ますます態度がデカくなる危険性が?)。今年で3年目のスイミング、実りある1年にしたいです。
2007.11.03
コメント(2)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 令和7年 八朔祭 開口神社 ふとん…
- (2025-11-24 07:02:09)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- --< 南四日市駅から >--日本の車窓か…
- (2025-11-24 07:19:48)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-







