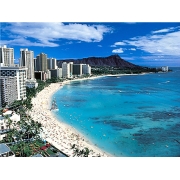PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
今日は7月7日、七夕について日本に伝わる諸々を紐解いてみました。
★------------★
天界を司る天帝の姫に機織りとしてつかえる織女はお年頃。天帝は、織女と天の川の西に住む牽牛とをお見合させるが、意気投合し機織りもせず昼夜くっついてばかりいる。天帝は大いに怒りて「七月七日の夜、天の川を渡って会うこと以外は許さぬ」と、二人に別居を厳しく申し付けた。その後二人は仕方なく、年に一度を待ちわびて七夕に逢瀬を楽しむことになった。
これが江戸時代の書『五節句雅童講釈』に記されている七夕の説明です。「たな」とは「たなびく」のたなで天のこと。「はた」とは「機織」のことで、「たなばた」とは「天で機を織ることである」とも記されています。
日本の七夕祭りの由来
日本の七夕は、この「タナバタツメ」と、中国の乞巧奠とが合体したものだという説が有力です。ちなみに乞巧奠は、平安時代の貴族たちが中国の風習を真似て導入していたようで、その後乞巧奠が民間に流れていき、次第に「タナバタツメ」と合わさっていったのだと言われています。
民俗調査などでは、七夕がお盆(旧7月15日)を迎えるための準備としての意味をもつ (七夕盆)場合や、農業の豊作を願う意味で行う場合など、様々な意味合いを持っている場合があります。これは後世になって民間のいろんな行事と混ざり合っていて、出来上がったものだと思われます。
おりひめと彦星は一年に一度デートができるか?
皆さんも短冊に願いを込めて今宵をお楽しみ下さい。
-
★「貴家ではどのように元旦を迎えましたか… 2023.01.07
-
高野山ろうそくまつり 2022.07.20
-
★Facebook開設7周年 2019.01.19