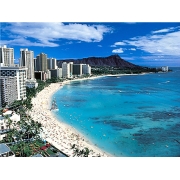PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
「電子書籍」は、出版業界もIT業界も熱い視線を送る成長分野
昨日4月2日出版物の電子化を進めるために、国内の出版業界が連携して「出版デジタル機構」を官民ファンドの産業革新機構からも、総額150億円の出資を仰いで発足させました。
新刊書のほとんどが電子化される時代、出版物の電子化を請け負う組織で、講談社、小学館、文藝春秋など大手出版社20社が共同で出資し、3月7日までに国内207の出版社等が設立に賛同しました。同機構は、紙に印刷されて発行される書籍や雑誌を、パソコンやタブレット端末、スマートフォンのような情報機器で読めるようにする「電子化」を推進します。
出版デジタル機構には、講談社、小学館、集英社の大手3社を中心とする複数の出版社と、大日本印刷、凸版印刷が、計約20億円の出資をしている。総額170億円の資本金(資本準備金を含む)のうち約90%を産業革新機構が出資して最大の株主となる。
日本政策投資銀行も3月28日、三井物産と東芝、NECとともに、電子書籍配信サービス会社「ブックライブ」と資本提携すると発表した。
産業革新機構は政府が9割を出資する国内最大級の投資ファンド。政投銀は政府が全額出資する政策金融機関。業界を横断する連携を国も後押しし、日本の電子書籍市場を拡大させる狙いがある。現在、国内の市場規模は年間600億円ほどだが、三井物産や東芝によると、スマートフォンやタブレット端末の普及で、2015年度には年間2千億~3千億円に急成長する見込みという。
政投銀も資本提携政投銀など4社は、トッパングループのブックライプが行う約29億円の第三者割当増資を引き受ける。ブックライブはネット上で、電子書籍ストアを運営。小説や雑誌、コミックなど約3万タイトル、約5万4千冊を持つ。提携後は電機2社が端末や配信システムの提供などで、三井物産が海外ネットワークをいかし、アジア展開などで協力しあうという。
設立準備会によると当面100万点が目標で、2010年の新刊発行点数は7万4714点(出版科学研究所調べ)でしたから、近い将来、新刊書のほとんどは電子化されると考えても差し支えないでしょう。
これまで日本の電子書籍はコミック中心だったが、文字で読めるコンテンツが一気に増えれば、ユーザー(読者)の選択肢も飛躍的に広がることになる。
「ベストセラーやメジャーな雑誌は紙に印刷されたものを買うしかない」と思われていました。それが今後は、有名な作家やマンガ家の最新作も、タレント写真集も、ハウツー本も、大学の先生が著した専門書も、みんな知つているあの雑誌も、出版デジタル機構で電子化され、本屋さんの棚に並んでいるのと同じものを電子書籍で読めるようになつていきます。ということは2012年こそ、本当の意味での「電子出版元年」と言えるのかもしれません。
雑誌の電子化と言つても大きく分けて2つの方法があり、一つは文章、写真、図表、イラストなどの「コンテンツ」を最初からデジタリレのデータとして制作し、それをコンピュータで編集して電子書籍をつくる方法で現在でも紙の雑誌の大部分はそうやつて作られています。もう一つは昔からあるアナログな本づくりの手法で印刷・製本まで行い、その1ページ、1ページを撮つたデジタル画像データを束ねて電子書籍をつくる方法です。紙の本をバラしてスキヤナーにかけ、自分だけの電子書籍に仕立てあげて読む「自炊」は、この方法です。
いずれにしても電子書籍は、従来の出版、印刷産業に加えて、ハ-ドウェア、デジタルコンテンツ制作、システムインテグレーターなどIT産業が深く関わつています。
野村総合研究所は2010年12月に出したレポートで、2010年度は850億円の電子書籍コンテンツの市場規模は、2015年度に約2.8倍の2400億円に成長すると推計しました。それまでに電子書籍を読める端末が1400万台普及するそうです。年間平均成長率は23.1%で、電子商取引(10.0%)、音楽配信(9.6%)、モバイルコンテンツ(3.0%)を大きく引き離す有望市場と位置づけています。
意外な異業種企業も見つかる電子書籍関連銘柄電子書籍関連銘柄としてまず思い浮かぶのは創作者人脈と出版の権利とブランドを持つ出版社ですが、講談社、小学館、文藝春秋のような最大手は非上場が多く、上場企業は角川グループホールディングス(9477)、学研ホールディングス(9470)ぐらいです。なお、出版デジタル機構にはIT関連の本を多く出版するインプレスホールディングス(9479)が出資しています。凸版印刷(7911)、大日本印刷(7912)、図書印刷(7913)、共同印刷(7914)のような印刷大手はどこも出版社とのコネクションを活かして電子書籍コンテンツ制作に参入しています。長年蓄積してきた本づくりのノウハウが強味です。
IT産業では固定、モバイルの通信キャリアを配信網に、数多くの企業が電子書籍の配信事業に参入しています。東芝(6502)、富士通フロンテック(6945)のような総合電機系から、インフォコム(4348)のような通信系、さらにパピレス(3641)、プライムワークス(3627)のようなベンチャーまで揃つています。イーブックイニシアティブジャパン(3658)、SmartEbook.com(2330)はその名の通り、電子書籍配信に特化しています。書店業の丸善CHIホールディングス(3159)は電子書籍ストアも運営しています。
電子書籍の制作、配信、閲覧をサポートするビジネスでは、制作支援のアクセルマーク(3624)、閲覧ソフトのACCESS(4813)、スターティア(3393)、インフォテリア(3853)の他、総合電機大手のソニー(6758)、シャープ(6753)、富士通(6702)なども各種のシステムを提供しています。
なお、流通のセブン&アイ・ホールディングス(3382)、資格教室の丁AC(4319)、楽器のヤマノヽ(7951)の電子書籍配信、商社の伊藤忠商事(8001)のコンテンツ制作、タイヤのプリヂストン(5108)の電子ペーパー、下着メーカーのグンゼ(3002)の端末タッチパネルなど、「えつ?」と思えるような異業種企業も電子書籍関連銘柄に数えられています。急成長が見込めるホットなビジネスは、異業種の参入も活発になるものです。
このように単に電子書籍そのもの動きのほか他業種・異業種の動きも連動し、惹いては株式市場をも動かす大きなうねりとなるかも知れません。
参考文献
朝日新聞 3月29日朝刊
日経デジタル
朝日デジタル